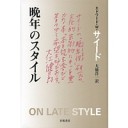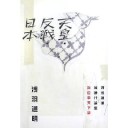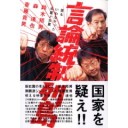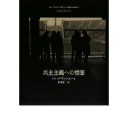日本人の精神と資本主義の倫理
2008年10月28日 読書
波頭亮と茂木健一郎による『日本人の精神と資本主義の倫理』を読んだ。
以下、目次
まえがき 自分の内なる鏡を磨くために
第1章 「大衆というバケモノ」が野に放たれた
プロフェッショナルな職業は使命と責任を負っている
自称プロフェッショナルが情報やスキルを悪用している
日本の富裕層はなぜ寄付しないのか
寄付を引き出す工夫をしているか
経済的繁栄を追求し、心の安寧を放棄した日本
「大衆というバケモノ」が放たれた醜悪な現代
平均値に引きずりおろす「ピアプレッシャー」の横行
見識者としての譲れない一線
ノーブレス・オブリージュが浸透しているイギリス
「世界には分からないことがたくさんある」が出発点
ハイレベルな文化に経緯を持てるか
「売れてなんぼ」に拮抗する価値軸がない日本
先人たちは自己反省を繰り返してきた
東京の景観が戦後の日本人の精神の荒廃を象徴している
ノーベル賞はもっとも成功したビジネスモデル
第2章 個性とテレビメディア
個性を無条件に肯定すべきではない
ポップカルチャーに対峙するハイカルチャーが消えた
変人が変人である自由を認められるか
日本人はなぜ突き抜けることができないのか
無個性な日本人のルーツを歴史に探す
テレビが決して伝えなかった篠沢秀夫の実像
「詠み人知らず」ジョークのブログを閉鎖
「腹を切れば許される」では正義が根付かない
世界で通用しない日本人の「当たり前」
欧米型を中途半端に取り入れてしまった日本
本当は日本を愛したい、でも愛せないのはなぜか
「トレンディ」のレッテルと小津安二郎
第3章 資本主義を生き抜くためのビジョンを総合知
平成を象徴するホリエモン的現象
ビジョンとフィロソフィーの欠如
強大な力を持つ者ほど自己規制が必要
金勘定だけで動く社会は死に絶える
カネのために仕事をしなくても飯は食える
信念を貫き通せば帳尻が合う
経済成長が「手段」から「目的」に変わってしまった
バブルの成金的風土から一転、不況へ
インテリの反撃が始まった
専門馬鹿でないことの大切さ
学習の効率をもっとも高めるには
「変化する」ことが「学習」である
複雑化する社会で働くことの意味を考える
多様で複雑な人間と社会をどう理解すべきか
第4章 格差を超えて
経済格差と豊かさの実感はリンクしない
ネット浸透の結果、生き延びるもの、淘汰されるもの
人間は地球の寿命を縮めている
秀吉がすべてなげうってでも得たかった千利休の世界
「日本人の忘れ物」に価値を見出す
世界最高の職人を生み出す日本が金儲けゲームに勝てない理由
教育システムが秀でた者を平均値に引きずりおろす
スティーブ・ジョブズ的価値が欠如している
アメリカを進歩させたのは怒りである
総合的なインテリジェンスと決断力
経済格差など気にするな
今や最高学府はインターネット上にあるが…
どう、薄っぺらい新書なのに、この目次の文字数の多さ。
目次の方が本文よりも充実している、と言ってもいいかもしれない。
内容については、目次ですべてが語られている。
いくつか文を引用してみるが、これらを読んで、どう感じなさる?
「サンダル突っかけているオバサンも、100億円稼いだ資産家も、その精神性において違いなどまるでないのが今の日本なのです」(茂木)
「僕は埼玉の田舎育ちで、両親にしても普通の人たちだから、僕自身はいわば大衆の側から生れてきた人間だと思っています。(中略)初めてオペラを鑑賞したのが高校3年のとき。それまで観たことがなかった。(中略)埼玉の田舎育ちで、少年期のクラシック音楽体験といえば、アルフレート・ブレンデルが弾いたベートーヴェンのピアノ・ソナタをレコードで聴いたことぐらいでしかなかった。有名なピアニスト、ウラディーミル・アシュケナージも知らなかったし、世界的な指揮者、クラウディオ・アバドの名前を知ったのも大学生になってからです。つまり、僕はそうした環境から出てきたわけです」(茂木)
「アイドルが出るドラマなど一瞬たりとも観たくない。そういうのがテレビに映るとすぐに消してしまうほど。もちろん、アイドルたちをアイコンにする世界は、イギリスにもあるけれど、それに対抗するハイカルチャーの軸がきちんと存在するわけです」(茂木)
「僕は東京大学理科Ⅰ類に進んだわけです。ところが、みんな勉強はできるけど、休み時間になると漫画ばかり読んでいる。それから理学部物理学科に進んだときも、学生控え室を覗くとやはり漫画が置いてあった。理学部物理学科は当時、東大の進学振り分けでテストの基準が一番高い学科。それでもこのざまです。自分はなんてくだらない世界に来てしまったのだろうと思いました」(茂木)
あと、小見出しにもなっていた「『売れてなんぼ』に拮抗する価値観がない日本」
これらの文章を読んでカチンときてしまうのは、単なる僕の僻み?
それと、この日記を読んで「アレ?」と思った人は、かなりの保山マニアである。
なぜなら、この本をタイトルにした日記が去年の11月にもあるからなのだ。
今回、僕はこの本を既に読んだことのある本だと気づかずに、読んでしまったのだ。
あいにくと日記書くのが面倒で、前回は本の感想をいっさい書いていなかった。
途中、「このエピソード、どこかで同じこと言ってたな」「こいつら、同じことばっかり書いているな。よっぽどネタに困っているにちがいない」「この対談、どこかに掲載されてたのを先に読んだんだろうか」「デジャブにしては激しすぎる」「僕はひょっとして予知無でも見たのか?」「僕って予言者?」と、ページをめくるたびに首をひねっていたのだが、読み終えてから自分の日記を検索してみたら、見つかったのだ。
まあ、1年近く前に読んだ本だから、これだけ間隔があいているのによくぞこれだけ覚えていたものだ、と逆に驚いたりもしたが、はっきり言って、2回も読む本じゃない。
日本の話芸で一龍斎貞心「朝顔日記」
すれちがいのメロドラマ、いいとこどり。
お年のわりにぴったりとしてまるで頭にのっけたような髪形が気になって、「その朝顔を取れ!」と言いたくなった。
「あの人にあいたい」は林忠彦。ルパンでの太宰の写真はトイレから撮ったとか。
永井荷風に会いに行ったら、本人が出て来て「永井は出かけております」と堂々と居留守使われたとか。愉快なエピソードが聞けた。
読んだ漫画はSABEの『ブルマー200X』わんだーらんどやアニメイト、信長書店などいろいろ探したあげく、とらのあなで買ったが2006年第1刷だった、ということは、あんまり売れていないのだろうか。カンフーとブルマに特化した内容。『世界の孫』は3巻まで読んだが、こんなに面白い漫画はまたとない、と思っているのに。
以下、目次
まえがき 自分の内なる鏡を磨くために
第1章 「大衆というバケモノ」が野に放たれた
プロフェッショナルな職業は使命と責任を負っている
自称プロフェッショナルが情報やスキルを悪用している
日本の富裕層はなぜ寄付しないのか
寄付を引き出す工夫をしているか
経済的繁栄を追求し、心の安寧を放棄した日本
「大衆というバケモノ」が放たれた醜悪な現代
平均値に引きずりおろす「ピアプレッシャー」の横行
見識者としての譲れない一線
ノーブレス・オブリージュが浸透しているイギリス
「世界には分からないことがたくさんある」が出発点
ハイレベルな文化に経緯を持てるか
「売れてなんぼ」に拮抗する価値軸がない日本
先人たちは自己反省を繰り返してきた
東京の景観が戦後の日本人の精神の荒廃を象徴している
ノーベル賞はもっとも成功したビジネスモデル
第2章 個性とテレビメディア
個性を無条件に肯定すべきではない
ポップカルチャーに対峙するハイカルチャーが消えた
変人が変人である自由を認められるか
日本人はなぜ突き抜けることができないのか
無個性な日本人のルーツを歴史に探す
テレビが決して伝えなかった篠沢秀夫の実像
「詠み人知らず」ジョークのブログを閉鎖
「腹を切れば許される」では正義が根付かない
世界で通用しない日本人の「当たり前」
欧米型を中途半端に取り入れてしまった日本
本当は日本を愛したい、でも愛せないのはなぜか
「トレンディ」のレッテルと小津安二郎
第3章 資本主義を生き抜くためのビジョンを総合知
平成を象徴するホリエモン的現象
ビジョンとフィロソフィーの欠如
強大な力を持つ者ほど自己規制が必要
金勘定だけで動く社会は死に絶える
カネのために仕事をしなくても飯は食える
信念を貫き通せば帳尻が合う
経済成長が「手段」から「目的」に変わってしまった
バブルの成金的風土から一転、不況へ
インテリの反撃が始まった
専門馬鹿でないことの大切さ
学習の効率をもっとも高めるには
「変化する」ことが「学習」である
複雑化する社会で働くことの意味を考える
多様で複雑な人間と社会をどう理解すべきか
第4章 格差を超えて
経済格差と豊かさの実感はリンクしない
ネット浸透の結果、生き延びるもの、淘汰されるもの
人間は地球の寿命を縮めている
秀吉がすべてなげうってでも得たかった千利休の世界
「日本人の忘れ物」に価値を見出す
世界最高の職人を生み出す日本が金儲けゲームに勝てない理由
教育システムが秀でた者を平均値に引きずりおろす
スティーブ・ジョブズ的価値が欠如している
アメリカを進歩させたのは怒りである
総合的なインテリジェンスと決断力
経済格差など気にするな
今や最高学府はインターネット上にあるが…
どう、薄っぺらい新書なのに、この目次の文字数の多さ。
目次の方が本文よりも充実している、と言ってもいいかもしれない。
内容については、目次ですべてが語られている。
いくつか文を引用してみるが、これらを読んで、どう感じなさる?
「サンダル突っかけているオバサンも、100億円稼いだ資産家も、その精神性において違いなどまるでないのが今の日本なのです」(茂木)
「僕は埼玉の田舎育ちで、両親にしても普通の人たちだから、僕自身はいわば大衆の側から生れてきた人間だと思っています。(中略)初めてオペラを鑑賞したのが高校3年のとき。それまで観たことがなかった。(中略)埼玉の田舎育ちで、少年期のクラシック音楽体験といえば、アルフレート・ブレンデルが弾いたベートーヴェンのピアノ・ソナタをレコードで聴いたことぐらいでしかなかった。有名なピアニスト、ウラディーミル・アシュケナージも知らなかったし、世界的な指揮者、クラウディオ・アバドの名前を知ったのも大学生になってからです。つまり、僕はそうした環境から出てきたわけです」(茂木)
「アイドルが出るドラマなど一瞬たりとも観たくない。そういうのがテレビに映るとすぐに消してしまうほど。もちろん、アイドルたちをアイコンにする世界は、イギリスにもあるけれど、それに対抗するハイカルチャーの軸がきちんと存在するわけです」(茂木)
「僕は東京大学理科Ⅰ類に進んだわけです。ところが、みんな勉強はできるけど、休み時間になると漫画ばかり読んでいる。それから理学部物理学科に進んだときも、学生控え室を覗くとやはり漫画が置いてあった。理学部物理学科は当時、東大の進学振り分けでテストの基準が一番高い学科。それでもこのざまです。自分はなんてくだらない世界に来てしまったのだろうと思いました」(茂木)
あと、小見出しにもなっていた「『売れてなんぼ』に拮抗する価値観がない日本」
これらの文章を読んでカチンときてしまうのは、単なる僕の僻み?
それと、この日記を読んで「アレ?」と思った人は、かなりの保山マニアである。
なぜなら、この本をタイトルにした日記が去年の11月にもあるからなのだ。
今回、僕はこの本を既に読んだことのある本だと気づかずに、読んでしまったのだ。
あいにくと日記書くのが面倒で、前回は本の感想をいっさい書いていなかった。
途中、「このエピソード、どこかで同じこと言ってたな」「こいつら、同じことばっかり書いているな。よっぽどネタに困っているにちがいない」「この対談、どこかに掲載されてたのを先に読んだんだろうか」「デジャブにしては激しすぎる」「僕はひょっとして予知無でも見たのか?」「僕って予言者?」と、ページをめくるたびに首をひねっていたのだが、読み終えてから自分の日記を検索してみたら、見つかったのだ。
まあ、1年近く前に読んだ本だから、これだけ間隔があいているのによくぞこれだけ覚えていたものだ、と逆に驚いたりもしたが、はっきり言って、2回も読む本じゃない。
日本の話芸で一龍斎貞心「朝顔日記」
すれちがいのメロドラマ、いいとこどり。
お年のわりにぴったりとしてまるで頭にのっけたような髪形が気になって、「その朝顔を取れ!」と言いたくなった。
「あの人にあいたい」は林忠彦。ルパンでの太宰の写真はトイレから撮ったとか。
永井荷風に会いに行ったら、本人が出て来て「永井は出かけております」と堂々と居留守使われたとか。愉快なエピソードが聞けた。
読んだ漫画はSABEの『ブルマー200X』わんだーらんどやアニメイト、信長書店などいろいろ探したあげく、とらのあなで買ったが2006年第1刷だった、ということは、あんまり売れていないのだろうか。カンフーとブルマに特化した内容。『世界の孫』は3巻まで読んだが、こんなに面白い漫画はまたとない、と思っているのに。
荒俣宏の『大東亜科学綺譚』
前口上 まぼろしの日本科学再訪
第1部 日本科学と少年科学
人造人間は微笑する
万能科学者・西村真琴
火星の土地を売った男
科学啓蒙家・原田三夫
冷凍を愛した熱血漢
発明事業家・星一
第2部 忘れられた科学の復活
江戸の幻獣事典
博物学者・高木春山
まぼろしの大東亜博物館
中井猛之進と”ある執念”
よみがえる徳川政治
徳川義親と昭南博物館
絶滅鳥を愛した探険家
蜂須賀正氏と冒険博物学
大和魂を科学した人
駿河湾の生物学者・中沢毅一
南洋の若き学徒たち
畑井新喜司とパラオ熱帯生物研究所
第3部 やんごとなき科学者たち
昭和天皇とアメフラシ
呪儀と科学のあいだ
ラストエンペラーの熱帯魚飼育
満州・中国のナチュラリスト
情熱と真面目さに打たれる。
紹介されているのが必ずしも奇人ではない、というのがちょっと物足りない。
つまりは、情熱と真面目さがちょっと鬱陶しい。
面白いんだけどね!
前口上 まぼろしの日本科学再訪
第1部 日本科学と少年科学
人造人間は微笑する
万能科学者・西村真琴
火星の土地を売った男
科学啓蒙家・原田三夫
冷凍を愛した熱血漢
発明事業家・星一
第2部 忘れられた科学の復活
江戸の幻獣事典
博物学者・高木春山
まぼろしの大東亜博物館
中井猛之進と”ある執念”
よみがえる徳川政治
徳川義親と昭南博物館
絶滅鳥を愛した探険家
蜂須賀正氏と冒険博物学
大和魂を科学した人
駿河湾の生物学者・中沢毅一
南洋の若き学徒たち
畑井新喜司とパラオ熱帯生物研究所
第3部 やんごとなき科学者たち
昭和天皇とアメフラシ
呪儀と科学のあいだ
ラストエンペラーの熱帯魚飼育
満州・中国のナチュラリスト
情熱と真面目さに打たれる。
紹介されているのが必ずしも奇人ではない、というのがちょっと物足りない。
つまりは、情熱と真面目さがちょっと鬱陶しい。
面白いんだけどね!
人生五十年、もうじゅうぶんであろう、という心の声にしたがって(誰?)、所蔵していた本などを次々と処分している。このまま死蔵のあげく捨てられてしまうよりは、とこまめに古本屋に行ってたが、今日はボナ・ド・マンディアルグの幻想小説『カファルド』を引き取ってもらえなかった。死蔵決定である。
せっかくなので再読したので、感想だけでも載せておこう。
ボナはアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグの奥さん。
「カファルド」の意味は巻頭に書いてある。
フランシスク=ミシェル著の『隠語辞典』によると「月」という意味。
間違いなく、これは月に憑かれた女性が人狼(ルー・ガルー)になりつつあることを描いた幻想文学なのだ。
月光に照らされた絵画を描写するがごとくに物語は進む。
いや、物語が進むのではなく、静的な絵画を描写しおえたときに物語が終わるかのような印象を受ける。ボナは自身、絵画作品をものしているので、文章も絵画的なのか。
夢というのは実際に見ているのは一瞬で、その後、脳は適当な長さのストーリーに仕立て上げる、とか聞いたことがある。それと同様、一瞬の強烈な印象がすべてで、そこから一編の小説が出来上がったようだ。
犬が怯えることで、自分が近い満月の日に人狼になるであろうことを察知するあたりが無気味で面白い。
なお、作中にアラゴンの『死刑執行』やブニュエルの「アンダルシアの犬」「黄金時代」などの名前が出てくるあたりがシュルレアリスムの時代を思わせて、なんだか微笑ましい。
まあ、カファルドはこの程度でいいだろう。
僕の持っているのはコーベブックスの初刷1500部の1冊だが、どこかに再録、あるいは翻訳がされているのだろうか。
今日は朝からまずABCラジオ「なみはや亭」で笑福亭三喬「次の御用日」(「あ!」の畳み掛けを、もっともっと、と望んでしまった。文枝の物真似もしてた)
続いて「米朝よもやま噺」で先週に引き続き、ゲストは暁照夫。宮川左近ショウの録音が聞けたり、また、河内音頭の出だしのおなじみの三味線は暁照夫が作ったものだとわかったりして、面白い。
午後2時からアリオ八尾でアリオダンスプロジェクト予選。
到着した時、既にみっくすじゅーすのダンスは終わっていて、審査員にアドバイスを受けているところだった。
出演チームは次の7組。
みっくすじゅーす
ポップコーンジュニア
リトルスパイダー
ビートクルー
ミリコレ
ピンキーズ
チョコ☆ドル
ダンスとダンスのあいだのアドバイスやらおしゃべりが長くてすごく退屈した。
10分もないダンスだから、7組連続でやると1時間もかからずに全部終わってしまう。それではイベントとして成立しないのだろう。でも、それは見ている観客や、準備しているキッズたちには関係のないことだ。もっと出場チーム増やすとか、ゲストのダンスをいくつも用意するとか、なんとかならなかったのだろうか。ダンスを終えて疲れている子供たちが審査員ひとりひとりの言葉を聞くためにずっと立ちん坊でいるのも早く解放してあげればいいのに、と思えた。
午後5時からいずみホールで「大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団定期演奏会 第18回現代音楽シリーズ〜日本人の古、その心の原泉へ〜」
柴田南雄/男声合唱と小鼓のための「美女打見れば」『梁塵秘抄』より(鼓:山内利一)
西村朗/無伴奏女声合唱組曲「浮舟」〜源氏物語の和歌による〜
20分の休憩後、委嘱初演作。
当間修一指揮、演出。千原英喜/舞台アート音楽作品「GAGAKU1、2」−折口信夫『死者の書』による
奏楽・弦楽のためのシンフォニア第3番「星乃音取」<1>Focus(焦点)
ひさかたの天二上に
奏楽・弦楽のためのシンフォニア第3番「星乃音取」<3>Earth(地)/畏き神々の御言葉
GAGAKU1(葬送歌)
機織り歌
奏楽・弦楽のためのシンフォニア第3番「星乃音取」<4>Orbit(軌道)/天球を統べる者
GAGAKU2(曼荼羅)
大津皇子・パントマイム:白木原一仁
耳面刀自・大伯皇女・藤原南家郎女:岩永亜希子
媼:神谷恵美子
箏:菊友仙三津野
今回の「GAGAKU1、2」では次の打楽器、笛を使っている。
バスドラム、魚板、ほら貝、鉦鼓、ツリー[メタル]チャイム、サヌカイト、キン、チューブラベル、銅板、締太鼓、磐笛、巡礼鈴、笏拍子、土笛、錫杖。
「GAGAKU」では、合唱のメンバーが仰向けになって発声したり、バルコニーにもメンバーがいたり、客席まで降りて来て歌ったり。上海太郎舞踏公司出身の白木原一仁のダンスに呼応するように合唱団員もそれらしい動きをしたり、みどころたっぷり。
なにより、初演であるので、次に何が起こるのかわからないワクワク感がたまらない。
と、いうわけで、ホールで現代音楽を聞いていたので、NHK-FM「現代の音楽」は聞き逃す。
帰宅して上方演芸ホールを見る。
御先祖様/桂春菜(マクラはお馴染みの家族ネタ、あとでトークもあり)
鋳掛け屋/桂春團治(桃太郎からいかけ屋へ)
「大阪ほんわかテレビ」見てたら、写真モデルとして、ポルテのこころちゃんが出てた。
コンビニ本で『おろち』読む。
映画化記念セレクトで「血」と「姉妹」、映画「おろち」の鶴田法男監督、脚本担当の高橋洋氏のインタビューも掲載されている。
「姉妹」は名作で何度も読んだ漫画、今回再読しても面白かった。当時、僕は長谷邦夫の「おそろち」を読んで、「おろち」をさらに深く味わっていたようだ。(長谷邦夫の『バカ式』と『アホ式』は十代の頃の僕の愛読書だった)
「血」の方はほとんど忘れていた。『おろち』のシリーズの中では他に傑作がひしめいているので、印象が薄れていたのだろう。今回再読しても、これはこれで面白いけど、他の話のインパクトには負けるかな、と感じた。ただ、前半、ページあたりの駒数が少ない絵画的展開にはシビレた。
せっかくなので再読したので、感想だけでも載せておこう。
ボナはアンドレ・ピエール・ド・マンディアルグの奥さん。
「カファルド」の意味は巻頭に書いてある。
フランシスク=ミシェル著の『隠語辞典』によると「月」という意味。
間違いなく、これは月に憑かれた女性が人狼(ルー・ガルー)になりつつあることを描いた幻想文学なのだ。
月光に照らされた絵画を描写するがごとくに物語は進む。
いや、物語が進むのではなく、静的な絵画を描写しおえたときに物語が終わるかのような印象を受ける。ボナは自身、絵画作品をものしているので、文章も絵画的なのか。
夢というのは実際に見ているのは一瞬で、その後、脳は適当な長さのストーリーに仕立て上げる、とか聞いたことがある。それと同様、一瞬の強烈な印象がすべてで、そこから一編の小説が出来上がったようだ。
犬が怯えることで、自分が近い満月の日に人狼になるであろうことを察知するあたりが無気味で面白い。
なお、作中にアラゴンの『死刑執行』やブニュエルの「アンダルシアの犬」「黄金時代」などの名前が出てくるあたりがシュルレアリスムの時代を思わせて、なんだか微笑ましい。
まあ、カファルドはこの程度でいいだろう。
僕の持っているのはコーベブックスの初刷1500部の1冊だが、どこかに再録、あるいは翻訳がされているのだろうか。
今日は朝からまずABCラジオ「なみはや亭」で笑福亭三喬「次の御用日」(「あ!」の畳み掛けを、もっともっと、と望んでしまった。文枝の物真似もしてた)
続いて「米朝よもやま噺」で先週に引き続き、ゲストは暁照夫。宮川左近ショウの録音が聞けたり、また、河内音頭の出だしのおなじみの三味線は暁照夫が作ったものだとわかったりして、面白い。
午後2時からアリオ八尾でアリオダンスプロジェクト予選。
到着した時、既にみっくすじゅーすのダンスは終わっていて、審査員にアドバイスを受けているところだった。
出演チームは次の7組。
みっくすじゅーす
ポップコーンジュニア
リトルスパイダー
ビートクルー
ミリコレ
ピンキーズ
チョコ☆ドル
ダンスとダンスのあいだのアドバイスやらおしゃべりが長くてすごく退屈した。
10分もないダンスだから、7組連続でやると1時間もかからずに全部終わってしまう。それではイベントとして成立しないのだろう。でも、それは見ている観客や、準備しているキッズたちには関係のないことだ。もっと出場チーム増やすとか、ゲストのダンスをいくつも用意するとか、なんとかならなかったのだろうか。ダンスを終えて疲れている子供たちが審査員ひとりひとりの言葉を聞くためにずっと立ちん坊でいるのも早く解放してあげればいいのに、と思えた。
午後5時からいずみホールで「大阪ハインリッヒ・シュッツ室内合唱団定期演奏会 第18回現代音楽シリーズ〜日本人の古、その心の原泉へ〜」
柴田南雄/男声合唱と小鼓のための「美女打見れば」『梁塵秘抄』より(鼓:山内利一)
西村朗/無伴奏女声合唱組曲「浮舟」〜源氏物語の和歌による〜
20分の休憩後、委嘱初演作。
当間修一指揮、演出。千原英喜/舞台アート音楽作品「GAGAKU1、2」−折口信夫『死者の書』による
奏楽・弦楽のためのシンフォニア第3番「星乃音取」<1>Focus(焦点)
ひさかたの天二上に
奏楽・弦楽のためのシンフォニア第3番「星乃音取」<3>Earth(地)/畏き神々の御言葉
GAGAKU1(葬送歌)
機織り歌
奏楽・弦楽のためのシンフォニア第3番「星乃音取」<4>Orbit(軌道)/天球を統べる者
GAGAKU2(曼荼羅)
大津皇子・パントマイム:白木原一仁
耳面刀自・大伯皇女・藤原南家郎女:岩永亜希子
媼:神谷恵美子
箏:菊友仙三津野
今回の「GAGAKU1、2」では次の打楽器、笛を使っている。
バスドラム、魚板、ほら貝、鉦鼓、ツリー[メタル]チャイム、サヌカイト、キン、チューブラベル、銅板、締太鼓、磐笛、巡礼鈴、笏拍子、土笛、錫杖。
「GAGAKU」では、合唱のメンバーが仰向けになって発声したり、バルコニーにもメンバーがいたり、客席まで降りて来て歌ったり。上海太郎舞踏公司出身の白木原一仁のダンスに呼応するように合唱団員もそれらしい動きをしたり、みどころたっぷり。
なにより、初演であるので、次に何が起こるのかわからないワクワク感がたまらない。
と、いうわけで、ホールで現代音楽を聞いていたので、NHK-FM「現代の音楽」は聞き逃す。
帰宅して上方演芸ホールを見る。
御先祖様/桂春菜(マクラはお馴染みの家族ネタ、あとでトークもあり)
鋳掛け屋/桂春團治(桃太郎からいかけ屋へ)
「大阪ほんわかテレビ」見てたら、写真モデルとして、ポルテのこころちゃんが出てた。
コンビニ本で『おろち』読む。
映画化記念セレクトで「血」と「姉妹」、映画「おろち」の鶴田法男監督、脚本担当の高橋洋氏のインタビューも掲載されている。
「姉妹」は名作で何度も読んだ漫画、今回再読しても面白かった。当時、僕は長谷邦夫の「おそろち」を読んで、「おろち」をさらに深く味わっていたようだ。(長谷邦夫の『バカ式』と『アホ式』は十代の頃の僕の愛読書だった)
「血」の方はほとんど忘れていた。『おろち』のシリーズの中では他に傑作がひしめいているので、印象が薄れていたのだろう。今回再読しても、これはこれで面白いけど、他の話のインパクトには負けるかな、と感じた。ただ、前半、ページあたりの駒数が少ない絵画的展開にはシビレた。
ケロッピー前田展☆身体改造藝術研究所@Subterraneans、佛蘭西短編飜譯集成第2巻
2008年10月24日 読書Subterraneansに行って「ケロッピー前田展☆身体改造藝術研究所」を見る。
ピアッシングやタトゥー、スプリットタンなど身体改造の写真展。
親指を紙でスーッと切っただけでヒエ〜となってしまう臆病な僕にとっては、自分でそういうのをしたいとは思わないが、ここに可能性を認めないわけにはいかない、という感じ。
26日には上海新天地の龍BARでレクチャーと上映もあるのだが、行くと決めたわけでもないくせに、ゾクゾクしてくる。
澁澤龍彦翻訳による『佛蘭西短編飜譯集成』第2巻を読んだ。
この巻にはアルフォンス・アレの「奇妙な死」が収録されているのだ。
「今世紀有数の大津波が、11月6日、先週の火曜日に勃発した。とにかく愉快な眺めなのだ。大砲の弾丸一発、いや、二発、いや三発とだって、わたしはこの眺めを交換しようとは思うまい」
アレの黒いユーモアぶりがいきなり炸裂している。
「医者たちはほくほくと揉み手をしながら、『しめしめ!チフス患者がたくさん出ることだろうて!』と独語を言っている」
いやー、たまらん。
先日読んだ山田稔訳では上の文章はだいたいこうなる。
「この世紀最大の大潮が去る11月6日の火曜日に生じた。みごとな眺めだった、こいつは大砲の弾1つ、いや2つ、いや3つとだって交換できない」
「医者は揉み手をして胸のうちでつぶやいた。『しめしめ、チフスがはやるぞ」
アレの話はどれも短いが、冒頭でひきつけるのが多い。
「諸君は発明家が好きですか?ぼくは大好きだ、かりに何も発明しなくても。たいていの発明家がそうだけど」(輝かしいアイデア)
「問題のひげというのは、パリでも五指に入るみごとなひげだったと仮定しよう。そしてもう、その話はよそう。いや、むしろその話をしよう」(ひげ)
「世の中には、ペルシャの詩人が語っている、バラのジャムを塗りたくった棒のごとき女がいるものだ。どこをつまんでいいかわからない」(結婚生活の悲惨)
「もし諸君が諺よりも愚かなものを見せてくれることができたら、季節がら贅沢な食料品というべきイギリスのサクランボを半キロ、ただちに進呈いたします。いや、間違っていた。一つの諺よりも愚かなものがある。それは二つの諺だ」(急がずに)
さて、『佛蘭西短編飜譯集成』第2巻に戻ろう。
以下、目次。
罪のなかの幸福/バルベー・ドールヴィリー
勇み肌の男/エルネスト・エロ
恋愛の科学/シャルル・クロス
奇妙な死/アルフォンス・アレ
仮面の孔/ジャン・ロラン
自転車の怪/アンリ・トロワイヤ
最初の舞踏会/レオノーラ・カリントン
『罪のなかの幸福』
「パリの動物園の豹の檻の前に立って、その紫色の手袋で猛獣の鼻づらをぴしりと打つ、全身黒ずくめの繻子の服をまとった驕慢な女人」(巻末の澁澤によるノートより)
うむ!つかみはオーケー!
彼女の名はオートクレール。彼女は剣術道場で男たちに稽古をつけるほどの腕前。ところが、突然彼女がいなくなった。入れ代わりに、サヴィニイ伯の屋敷に雇われた女中ユウラリイ。病床にあったサヴィニイ夫人が毒死する。さて。
この物語も冒頭の強烈なシーンでひきつけて、語り手によって物語が語られる形式をとっている。物語が死体と謎をつきつけるのは、おなじみのドールヴィリー節。
『勇み肌の男』
エドゥアールは最後の決闘以来、午後11時になると「ひとを殺した者は永いこと生きられませんよ!」という声を聞くようになった。(最後の決闘は風変わりなもので、コインの裏表で生死を決めたが、勝った相手側の申し出により、街に出て最初に出遭う人間に「耳をくれ」と要求し、拒否したらそいつを殺す。どっちが見事に相手を殺したかで勝負をつけようというのだ。エドゥアールは通りかかった青年を見事に殺して勝利を得る)
エドゥアールは声から逃げるため、ひとりきりになったり、大勢の中に行ったり、列車の騒音の中にいたりするが、逃げられない。遠い場所に逃げるが、まさにその言葉がかわされる場面にでくわし、エドゥアールは死ぬ。
怪談の定番のような話だが、随所に読ませどころがあって素晴らしい。
『恋愛の科学』
恋愛を科学的に研究しようとする男。
相手の女性の体温を秘かにはかったり、心拍をはかったり、ベッドで裸にした際に正確な体重をはかったり、衣服の裏にリトマス試験紙を差し込んでおいたり、口のなかに接吻計数器を仕込んでおいたり。
これは笑った。筒井康隆が書いたのかと思った。
『奇妙な死』
ありそうもない不思議な話を聞かされ、ラストで「嘘っぱちさ」と一笑に付す、見事な一本勝ち。
『仮面の孔』
仮面舞踏会の怪し気な雰囲気。
日常に戻る道標となるはずの警官は、蝋人形だった。
ますます非現実的な世界のなかでさまよう私。
舞踏会に集う人々の仮面の下には、何も存在していなかった。
ひょっとして、自分も、と思い鏡の前で仮面をはずしてみたら!
悪夢のようなムードがたまらない。
澁澤のノートには「なにやら悪徳の匂いのする仮面という小道具の秘密を、彼ほどよく知り抜いていた作家はいないであろう」と記されている。
『自転車の怪』
夫婦2人でいつも乗っていた二人乗り用自転車。
夫の死後、新しい恋人のもとに自転車を走らせる女。
うしろから、聞き慣れたためいきが聞こえ、体重すら感じるようになる。
それかあらぬか、ブレーキがきかず!
この物語、何よりこわいのは、ラストの部分。
この町の人々は、しとしと雨の降る晩に、自転車のベルの音が聞こえてきたら、戸をぴったりと閉め、鎧戸を固く閉ざす。こっそりと覗いてみれば、ものすごい速さで闇の中を疾走する二人乗り自転車が見える。
「うしろの座席は空っぽだ。だが前の座席には、真黒い着物を着た太った女が乗っていて、その頭上には、風に引きちぎられた長い喪のヴェールが、ひらひらひらひら舞っているのだそうである。」
これ!この「ひらひらひらひら」がめちゃくちゃ怖い!この「ひらひらひらひら」は志賀直哉を超えている!
『最初の舞踏会』
舞踏会に行くのがいやで、仲良しのハイエナに代わりに行ってもらうことにした少女。
このままではバレるというので、女中の顔を剥いで、人間のふりをするハイエナ。(残りの部分は食べてしまう)
でも、舞踏会で顔の部分も食べてしまって全部バレてしまう。
なにこれ!暗黒のメルヘン!
ピアッシングやタトゥー、スプリットタンなど身体改造の写真展。
親指を紙でスーッと切っただけでヒエ〜となってしまう臆病な僕にとっては、自分でそういうのをしたいとは思わないが、ここに可能性を認めないわけにはいかない、という感じ。
26日には上海新天地の龍BARでレクチャーと上映もあるのだが、行くと決めたわけでもないくせに、ゾクゾクしてくる。
澁澤龍彦翻訳による『佛蘭西短編飜譯集成』第2巻を読んだ。
この巻にはアルフォンス・アレの「奇妙な死」が収録されているのだ。
「今世紀有数の大津波が、11月6日、先週の火曜日に勃発した。とにかく愉快な眺めなのだ。大砲の弾丸一発、いや、二発、いや三発とだって、わたしはこの眺めを交換しようとは思うまい」
アレの黒いユーモアぶりがいきなり炸裂している。
「医者たちはほくほくと揉み手をしながら、『しめしめ!チフス患者がたくさん出ることだろうて!』と独語を言っている」
いやー、たまらん。
先日読んだ山田稔訳では上の文章はだいたいこうなる。
「この世紀最大の大潮が去る11月6日の火曜日に生じた。みごとな眺めだった、こいつは大砲の弾1つ、いや2つ、いや3つとだって交換できない」
「医者は揉み手をして胸のうちでつぶやいた。『しめしめ、チフスがはやるぞ」
アレの話はどれも短いが、冒頭でひきつけるのが多い。
「諸君は発明家が好きですか?ぼくは大好きだ、かりに何も発明しなくても。たいていの発明家がそうだけど」(輝かしいアイデア)
「問題のひげというのは、パリでも五指に入るみごとなひげだったと仮定しよう。そしてもう、その話はよそう。いや、むしろその話をしよう」(ひげ)
「世の中には、ペルシャの詩人が語っている、バラのジャムを塗りたくった棒のごとき女がいるものだ。どこをつまんでいいかわからない」(結婚生活の悲惨)
「もし諸君が諺よりも愚かなものを見せてくれることができたら、季節がら贅沢な食料品というべきイギリスのサクランボを半キロ、ただちに進呈いたします。いや、間違っていた。一つの諺よりも愚かなものがある。それは二つの諺だ」(急がずに)
さて、『佛蘭西短編飜譯集成』第2巻に戻ろう。
以下、目次。
罪のなかの幸福/バルベー・ドールヴィリー
勇み肌の男/エルネスト・エロ
恋愛の科学/シャルル・クロス
奇妙な死/アルフォンス・アレ
仮面の孔/ジャン・ロラン
自転車の怪/アンリ・トロワイヤ
最初の舞踏会/レオノーラ・カリントン
『罪のなかの幸福』
「パリの動物園の豹の檻の前に立って、その紫色の手袋で猛獣の鼻づらをぴしりと打つ、全身黒ずくめの繻子の服をまとった驕慢な女人」(巻末の澁澤によるノートより)
うむ!つかみはオーケー!
彼女の名はオートクレール。彼女は剣術道場で男たちに稽古をつけるほどの腕前。ところが、突然彼女がいなくなった。入れ代わりに、サヴィニイ伯の屋敷に雇われた女中ユウラリイ。病床にあったサヴィニイ夫人が毒死する。さて。
この物語も冒頭の強烈なシーンでひきつけて、語り手によって物語が語られる形式をとっている。物語が死体と謎をつきつけるのは、おなじみのドールヴィリー節。
『勇み肌の男』
エドゥアールは最後の決闘以来、午後11時になると「ひとを殺した者は永いこと生きられませんよ!」という声を聞くようになった。(最後の決闘は風変わりなもので、コインの裏表で生死を決めたが、勝った相手側の申し出により、街に出て最初に出遭う人間に「耳をくれ」と要求し、拒否したらそいつを殺す。どっちが見事に相手を殺したかで勝負をつけようというのだ。エドゥアールは通りかかった青年を見事に殺して勝利を得る)
エドゥアールは声から逃げるため、ひとりきりになったり、大勢の中に行ったり、列車の騒音の中にいたりするが、逃げられない。遠い場所に逃げるが、まさにその言葉がかわされる場面にでくわし、エドゥアールは死ぬ。
怪談の定番のような話だが、随所に読ませどころがあって素晴らしい。
『恋愛の科学』
恋愛を科学的に研究しようとする男。
相手の女性の体温を秘かにはかったり、心拍をはかったり、ベッドで裸にした際に正確な体重をはかったり、衣服の裏にリトマス試験紙を差し込んでおいたり、口のなかに接吻計数器を仕込んでおいたり。
これは笑った。筒井康隆が書いたのかと思った。
『奇妙な死』
ありそうもない不思議な話を聞かされ、ラストで「嘘っぱちさ」と一笑に付す、見事な一本勝ち。
『仮面の孔』
仮面舞踏会の怪し気な雰囲気。
日常に戻る道標となるはずの警官は、蝋人形だった。
ますます非現実的な世界のなかでさまよう私。
舞踏会に集う人々の仮面の下には、何も存在していなかった。
ひょっとして、自分も、と思い鏡の前で仮面をはずしてみたら!
悪夢のようなムードがたまらない。
澁澤のノートには「なにやら悪徳の匂いのする仮面という小道具の秘密を、彼ほどよく知り抜いていた作家はいないであろう」と記されている。
『自転車の怪』
夫婦2人でいつも乗っていた二人乗り用自転車。
夫の死後、新しい恋人のもとに自転車を走らせる女。
うしろから、聞き慣れたためいきが聞こえ、体重すら感じるようになる。
それかあらぬか、ブレーキがきかず!
この物語、何よりこわいのは、ラストの部分。
この町の人々は、しとしと雨の降る晩に、自転車のベルの音が聞こえてきたら、戸をぴったりと閉め、鎧戸を固く閉ざす。こっそりと覗いてみれば、ものすごい速さで闇の中を疾走する二人乗り自転車が見える。
「うしろの座席は空っぽだ。だが前の座席には、真黒い着物を着た太った女が乗っていて、その頭上には、風に引きちぎられた長い喪のヴェールが、ひらひらひらひら舞っているのだそうである。」
これ!この「ひらひらひらひら」がめちゃくちゃ怖い!この「ひらひらひらひら」は志賀直哉を超えている!
『最初の舞踏会』
舞踏会に行くのがいやで、仲良しのハイエナに代わりに行ってもらうことにした少女。
このままではバレるというので、女中の顔を剥いで、人間のふりをするハイエナ。(残りの部分は食べてしまう)
でも、舞踏会で顔の部分も食べてしまって全部バレてしまう。
なにこれ!暗黒のメルヘン!
佛蘭西短編飜譯集成第1巻
2008年10月23日 読書澁澤龍彦翻訳による『佛蘭西短編飜譯集成』第1巻を読んだ。
ロドリゴあるいは呪縛の塔/マルキ・ド・サド
(暴君の地獄めぐり。地獄などなんのその!)
ギスモンド城の幽霊/シャルル・ノディエ
(「来ましたわ!」「あたしよ!あたしよ!」「こんばんわ、ご機嫌よろしゅう、ギスモンド城のお客様!」こんな陽気な幽霊の登場シーンがあっていいものか!幽霊は晩餐に加わって飲み食いし、歌い踊る)
緑色の怪物/ジェラール・ド・ネルヴァル
(全身緑色のこどもが生れた。洒落てるのは、第4章「教訓」で話をしめくくっておいて、第5章「緑色の怪物はその後どうなったのか」で落すところ)
解剖学者ドン・ベサリウス/ベトリュス・ボレル
(間男を解剖して標本にする学者。ショック死した妻もまた彼のメスにかかる)
草叢のダイヤモンド/グザヴィエ・フォルヌレ
(螢は雪を予報するとき脚が黒くなる。寒気を予報するとき激しく光る。雨を予報するとき居場所を変える。嵐を予報するとき一度暗くなってまた燃え上がり消える。風を予報するとき地中にもぐりこむ。上天気を予報するとき青くなる。奇蹟を予報するときほとんどその姿が見えなくなる。子供の誕生を予報するとき白くなる。殺人を予報するとき赤味をおびる。奇怪な運命が遂げられたとき黄色くなる。ここに恋人たちがいた。男が死んで黄色くなっていた螢は、翌日もまた黄色くなった。女が後を追ったのだ)
こんな小説を毎日読めたら、さぞかし楽しかろう!
ロドリゴあるいは呪縛の塔/マルキ・ド・サド
(暴君の地獄めぐり。地獄などなんのその!)
ギスモンド城の幽霊/シャルル・ノディエ
(「来ましたわ!」「あたしよ!あたしよ!」「こんばんわ、ご機嫌よろしゅう、ギスモンド城のお客様!」こんな陽気な幽霊の登場シーンがあっていいものか!幽霊は晩餐に加わって飲み食いし、歌い踊る)
緑色の怪物/ジェラール・ド・ネルヴァル
(全身緑色のこどもが生れた。洒落てるのは、第4章「教訓」で話をしめくくっておいて、第5章「緑色の怪物はその後どうなったのか」で落すところ)
解剖学者ドン・ベサリウス/ベトリュス・ボレル
(間男を解剖して標本にする学者。ショック死した妻もまた彼のメスにかかる)
草叢のダイヤモンド/グザヴィエ・フォルヌレ
(螢は雪を予報するとき脚が黒くなる。寒気を予報するとき激しく光る。雨を予報するとき居場所を変える。嵐を予報するとき一度暗くなってまた燃え上がり消える。風を予報するとき地中にもぐりこむ。上天気を予報するとき青くなる。奇蹟を予報するときほとんどその姿が見えなくなる。子供の誕生を予報するとき白くなる。殺人を予報するとき赤味をおびる。奇怪な運命が遂げられたとき黄色くなる。ここに恋人たちがいた。男が死んで黄色くなっていた螢は、翌日もまた黄色くなった。女が後を追ったのだ)
こんな小説を毎日読めたら、さぞかし楽しかろう!
P・K・ディックの最後の聖訓 ラスト・テスタメント
2008年10月22日 読書グレッグ・リックマン編著の『P・K・ディックの最後の聖訓 ラスト・テスタメント』を読んだ。
以下目次
序文 フィリップ・K・ディック−時ならぬ回想録/ロバート・シルヴァーバーグ
アメリカ版初版の序/グレッグ・リックマン
1、本書成立の過程
2、本書の読み方
3、謝辞
日本版への序/グレッグ・リックマン
第1部 昔のヴィジョン
第1章 哲学の探究者
第2章 宗教への回心
第3章 空に浮かぶ顔/大戦の記憶
第4章 『易経』
第5章 大脳の右半球
第6章 声/アルキメデス/海ガメ/ポルトガル領アメリカ
第7章 傷ついた馬の夢
第8章 オー・ホー
第2部 ヴァリス1974
ヴァリス1974−序文メモ
第9章 黙示録/魚の印/ローマ人トマス
第10章 薔薇十字/クリストファー/聖エルモの火/情報プロセッサー/ユービック/時のさえぎり
第11章 帝国/我が究極の願い/哲学者たち
第12章 入眠時幻覚/筆記者
第13章 麻薬/エリヤの霊/探索
第14章 テッサ・ディック・インタビュー
第3部 タゴール1981
タゴール1981−序文メモ
[タゴール・レター]フィリップ・K・ディック筆
第15章 心霊治療師/入眠時幻覚/中庸
第16章 「曲に合わせて踊りたい」/カレン・シルクウッド/サダト/独裁者たち
第17章 「亡き妹を探して」
第18章 磔の救済者/死から生へ/「人生は自分の力で切り拓いてきた」
第19章 何ぞ我を?/「決定的ヴィジョン」/松明持ち/100万分の1の偶然
第20章 テープの寿命
第4部 弥勒1982
弥勒1982−序文メモ
第21章 ベンジャミン・クレーム/弥勒/「だれもぼくの言うことなんか信じない」/革命的手段
第22章 AIの声/宝瓶宮時代/白い魚の夢
第23章 政治活動/新たな総合/「スープを暖めてやりなさい」/幼な子たち/ロナルド・レーガンはデイジー・ダック/人類の意志に背くことなく
第24章 「わたしのことを思い出す人も少なくない」/芸術と文化/「人類至高の大望」/「これまでになく自分のことを深く思い知らされた」/「そのときはひとりで転覆させるさ」
第25章 自由企業体制/「この国の政府を葬り去る」/「もう指導者がいるんだ」
第26章 反救世主/聖なる書物/普遍言語/「見ゆれども見ず」
第27章 弥勒はどこにいたんでしょう?/スターリングラード/土壇場の介在/彼は裁かず/個人的にも社会的にも
第28章 アルジュナ/『易経』
第29章 「本当かもしれないよ」/ナンセンスか悪か/大量殺戮の中止
第30章 怒りと暴力/男と戦車
第31章 五旬節の奇跡/「自分自身の体験」/「過去は過去」/敵
第32章 社会的信念と宗教的信念/「ライト・ショー」/ぼくを納得させること/まっとうな証拠
第33章 流れよわが涙/夢の暗号/涙の王/『ハムレット』と『バッコスの信女』/聖ソフィア
第34章 手当たり次第に選ばれた/還元主義的心理学/「メシアを目指すことだってできた」/エリヤ/『仮面は剥がれている』/静かな細い声
あとがき
1、フィリップ・K・ディックの死
2、弥勒は何処?
付録
A、書誌
B、「釈義からの抜粋」/フィリップ・K・ディック著
C、註釈
これは1981年4月から1982年2月にかけて行われたディックとリックマンの対話を中心に編まれたもので、哲学、政治、宗教上の信念、幻視体験について主に語られている。
出だしは、哲学に興味を抱いたきっかけを問われて、マイモニデスやヒュームに触れた経緯を語る、など、ごく通常のインタビュー。
これが、ヴィジョンについて語り出すと、「オー・ホー」と呼ぶ壷を出してきてその壷に喋らせたりする。オー・ホーはヤーウェが壷の形になったものだと言う。それから親知らずを抜いた後、ペンタトール・ナトリウムが効いた状態で魚の形のペンダントを見た瞬間に世界が終末的な光景に変わったくだり(これは有名)を語ったり。
ここまでは非常にぶっとんではいるが、興味深いやりとりがなされていると言えよう。
すさまじいのが、第4部「弥勒」だ。
1982年2月になされた対話はインタビュー全体の約半分を占めているだけでなく、もはやインタビューや対話でもなく、ディックが怒涛のごとく語りたおすのである。
ベンジャミン・クレームに接して、「弥勒(マイトレーヤ)」を発見し、今までオカルトと無神論を行き来していたディックは、まるでマイトレーヤの広告塔に仕立て上げられたかのように、自信満々にまくしたてる。
僕は、早とちりにも、ああ、ディックよ、おまえもか、なんたるたわごとを、と嘆いてしまった。ノディエの『ギスモンド城の幽霊』の登場人物ブートレにならって「ヴォルテールとピロンの言葉を思い出してみたまえ!そいつは偏見さ!迷信さ!狂信さ!」とがなりたてたくもなる。ところが、後半に至るにつれ、ディックは加速して大暴走をはじめる。これは『黒死館殺人事件』のラストスパートにも匹敵する!愉快!愉快!
まさしく強力な電波の奔流に他ならない!
たとえば、『流れよわが涙、と警官は言った』には救済者復帰運動の情報が込められているといい、本を開く(本人も言うように「何とも不思議なことにオランダ語版」)。第27章の一段落の最後の単語がたまたま「王」になっており、次の段落の最初の単語「フェリックス」が、印刷上、「王」の真下に置かれている。これは、ディックによると、
「この記述は4つめの空間軸をさかのぼっているんだ。だってこいつは何かと言うと『ダニエル書』に由来するものだもの。『日の老いたる者』さ。ラテン語だよ。フェリックスは人名じゃなくて『幸福』を意味するラテン語なんだ」
「4つめの空間軸をどこまでさかのぼるかは、原文の書かれた時代による。そこで初めて四つの空間軸とひとつの時間軸とを認識するわけ。ぼくは随分長いこと見せてもらったから暗号に気づくことができたけど、意味は教えてもらえなかった」
それが、弥勒によるAIの声が「聖ソフィアは間もなく再生する。昔は受け入れられなかった」と口にしたのを聞いて、こう悟る。
「どう見ても最初の降臨と再臨のことを言っているんだな。だから、キング・フェリックスという暗号が再臨のことを示しているってわかったのさ」
このことに気づいたディックはこう言う。
「1974年の数カ月、自分が何をしたのか見せてもらったわけ。どうして厭になるほど災難に巻き込まれたのかもわかったよ。そんな情報を載せるってことは、命を失うのも同然だからなんだ」
ディックは「すべての救済者は実はひとつのものだという前代未聞の情報」を1974年にテレパシーの声で語り受け、「ぼくは救済者がこの世にいるという事実を天下に広めるために利用されたんだ」と語る。
さらに、こんなことも言う。
ディック「じゃあ、ちょっと考えてみて。『流れよわが涙』の目的は何だったのか?救済者がこの世にいるって語ることだ。『ヴァリス』の目的は?救済者が現世にいるって述べることだ。何が違うのか?『涙』では暗号になっているけど、『ヴァリス』ではあからさまに述べている。天と地ほどの違いだよ」
リックマン「『聖なる侵入』の目的は?」
ディック「何もないよ。エージェントとの契約を果たしただけさ」
キャー!『聖なる侵入』はもともと『ヴァリスふたたび』というタイトルだったというのに、この違い!
以下目次
序文 フィリップ・K・ディック−時ならぬ回想録/ロバート・シルヴァーバーグ
アメリカ版初版の序/グレッグ・リックマン
1、本書成立の過程
2、本書の読み方
3、謝辞
日本版への序/グレッグ・リックマン
第1部 昔のヴィジョン
第1章 哲学の探究者
第2章 宗教への回心
第3章 空に浮かぶ顔/大戦の記憶
第4章 『易経』
第5章 大脳の右半球
第6章 声/アルキメデス/海ガメ/ポルトガル領アメリカ
第7章 傷ついた馬の夢
第8章 オー・ホー
第2部 ヴァリス1974
ヴァリス1974−序文メモ
第9章 黙示録/魚の印/ローマ人トマス
第10章 薔薇十字/クリストファー/聖エルモの火/情報プロセッサー/ユービック/時のさえぎり
第11章 帝国/我が究極の願い/哲学者たち
第12章 入眠時幻覚/筆記者
第13章 麻薬/エリヤの霊/探索
第14章 テッサ・ディック・インタビュー
第3部 タゴール1981
タゴール1981−序文メモ
[タゴール・レター]フィリップ・K・ディック筆
第15章 心霊治療師/入眠時幻覚/中庸
第16章 「曲に合わせて踊りたい」/カレン・シルクウッド/サダト/独裁者たち
第17章 「亡き妹を探して」
第18章 磔の救済者/死から生へ/「人生は自分の力で切り拓いてきた」
第19章 何ぞ我を?/「決定的ヴィジョン」/松明持ち/100万分の1の偶然
第20章 テープの寿命
第4部 弥勒1982
弥勒1982−序文メモ
第21章 ベンジャミン・クレーム/弥勒/「だれもぼくの言うことなんか信じない」/革命的手段
第22章 AIの声/宝瓶宮時代/白い魚の夢
第23章 政治活動/新たな総合/「スープを暖めてやりなさい」/幼な子たち/ロナルド・レーガンはデイジー・ダック/人類の意志に背くことなく
第24章 「わたしのことを思い出す人も少なくない」/芸術と文化/「人類至高の大望」/「これまでになく自分のことを深く思い知らされた」/「そのときはひとりで転覆させるさ」
第25章 自由企業体制/「この国の政府を葬り去る」/「もう指導者がいるんだ」
第26章 反救世主/聖なる書物/普遍言語/「見ゆれども見ず」
第27章 弥勒はどこにいたんでしょう?/スターリングラード/土壇場の介在/彼は裁かず/個人的にも社会的にも
第28章 アルジュナ/『易経』
第29章 「本当かもしれないよ」/ナンセンスか悪か/大量殺戮の中止
第30章 怒りと暴力/男と戦車
第31章 五旬節の奇跡/「自分自身の体験」/「過去は過去」/敵
第32章 社会的信念と宗教的信念/「ライト・ショー」/ぼくを納得させること/まっとうな証拠
第33章 流れよわが涙/夢の暗号/涙の王/『ハムレット』と『バッコスの信女』/聖ソフィア
第34章 手当たり次第に選ばれた/還元主義的心理学/「メシアを目指すことだってできた」/エリヤ/『仮面は剥がれている』/静かな細い声
あとがき
1、フィリップ・K・ディックの死
2、弥勒は何処?
付録
A、書誌
B、「釈義からの抜粋」/フィリップ・K・ディック著
C、註釈
これは1981年4月から1982年2月にかけて行われたディックとリックマンの対話を中心に編まれたもので、哲学、政治、宗教上の信念、幻視体験について主に語られている。
出だしは、哲学に興味を抱いたきっかけを問われて、マイモニデスやヒュームに触れた経緯を語る、など、ごく通常のインタビュー。
これが、ヴィジョンについて語り出すと、「オー・ホー」と呼ぶ壷を出してきてその壷に喋らせたりする。オー・ホーはヤーウェが壷の形になったものだと言う。それから親知らずを抜いた後、ペンタトール・ナトリウムが効いた状態で魚の形のペンダントを見た瞬間に世界が終末的な光景に変わったくだり(これは有名)を語ったり。
ここまでは非常にぶっとんではいるが、興味深いやりとりがなされていると言えよう。
すさまじいのが、第4部「弥勒」だ。
1982年2月になされた対話はインタビュー全体の約半分を占めているだけでなく、もはやインタビューや対話でもなく、ディックが怒涛のごとく語りたおすのである。
ベンジャミン・クレームに接して、「弥勒(マイトレーヤ)」を発見し、今までオカルトと無神論を行き来していたディックは、まるでマイトレーヤの広告塔に仕立て上げられたかのように、自信満々にまくしたてる。
僕は、早とちりにも、ああ、ディックよ、おまえもか、なんたるたわごとを、と嘆いてしまった。ノディエの『ギスモンド城の幽霊』の登場人物ブートレにならって「ヴォルテールとピロンの言葉を思い出してみたまえ!そいつは偏見さ!迷信さ!狂信さ!」とがなりたてたくもなる。ところが、後半に至るにつれ、ディックは加速して大暴走をはじめる。これは『黒死館殺人事件』のラストスパートにも匹敵する!愉快!愉快!
まさしく強力な電波の奔流に他ならない!
たとえば、『流れよわが涙、と警官は言った』には救済者復帰運動の情報が込められているといい、本を開く(本人も言うように「何とも不思議なことにオランダ語版」)。第27章の一段落の最後の単語がたまたま「王」になっており、次の段落の最初の単語「フェリックス」が、印刷上、「王」の真下に置かれている。これは、ディックによると、
「この記述は4つめの空間軸をさかのぼっているんだ。だってこいつは何かと言うと『ダニエル書』に由来するものだもの。『日の老いたる者』さ。ラテン語だよ。フェリックスは人名じゃなくて『幸福』を意味するラテン語なんだ」
「4つめの空間軸をどこまでさかのぼるかは、原文の書かれた時代による。そこで初めて四つの空間軸とひとつの時間軸とを認識するわけ。ぼくは随分長いこと見せてもらったから暗号に気づくことができたけど、意味は教えてもらえなかった」
それが、弥勒によるAIの声が「聖ソフィアは間もなく再生する。昔は受け入れられなかった」と口にしたのを聞いて、こう悟る。
「どう見ても最初の降臨と再臨のことを言っているんだな。だから、キング・フェリックスという暗号が再臨のことを示しているってわかったのさ」
このことに気づいたディックはこう言う。
「1974年の数カ月、自分が何をしたのか見せてもらったわけ。どうして厭になるほど災難に巻き込まれたのかもわかったよ。そんな情報を載せるってことは、命を失うのも同然だからなんだ」
ディックは「すべての救済者は実はひとつのものだという前代未聞の情報」を1974年にテレパシーの声で語り受け、「ぼくは救済者がこの世にいるという事実を天下に広めるために利用されたんだ」と語る。
さらに、こんなことも言う。
ディック「じゃあ、ちょっと考えてみて。『流れよわが涙』の目的は何だったのか?救済者がこの世にいるって語ることだ。『ヴァリス』の目的は?救済者が現世にいるって述べることだ。何が違うのか?『涙』では暗号になっているけど、『ヴァリス』ではあからさまに述べている。天と地ほどの違いだよ」
リックマン「『聖なる侵入』の目的は?」
ディック「何もないよ。エージェントとの契約を果たしただけさ」
キャー!『聖なる侵入』はもともと『ヴァリスふたたび』というタイトルだったというのに、この違い!
『白頭の巨人』を読んだ。
博士の発明をめぐる争奪戦と、父の生命と事業を奪った仇探し。
こりゃまた大時代的な、と思ったら、昭和3年に書かれた小説だった。
耽綺社同人(土師清二、長谷川伸、国枝史郎、小酒井不木、江戸川乱歩、平山蘆江)によってサンデー毎日に連載された合作探偵小説。
博士の発明とは、こんなもの。
「いかなる砲弾でも、もしそれに触れたならばたちまち爆発力を失って、空しい鉄塊となって地上に落下してしまうという驚くべき作用を持つ」気流を発生させる装置で、これが「まったく簡単な機械で作り得られて、運搬にも、飛行機への取り付けにも容易」なのだ。
タイトルの「白頭の巨人」は主人公が若くして総白髪頭になっているところから来ている。
この本のみどころは、暗号にある。
「流賀多美無能比古保武無能武太無能九之呂八」
これが暗号。「無能」と何回も出てくるので僕のことかと思ったら、そうではないようだ。
これはある場所、住所をあらわしている。
ヒント1、2文字ずつ区切って読む。数字はそのまま。
「流賀 多美 無能 比古 保武 無能 武太 無能 九 之呂 八」
ヒント2、万葉仮名で読む。
「るが たみ なの ひこ ほん なの んだ なの 九 しろ 八」
最終ヒント、電報を打つときに使われた和文通話表(逓信省発行)を参照。
たとえば「あ」なら「明石のあ」なんて地名で全部書いてある。
答えは「月島西河岸9の8」
「無能」は万葉仮名で「なの」と読み、記号表の「信濃のし」(し、なの)を参照して、「し」と読むのだ。
あと面白かったのは、発明の設計図のありかを吐かせるために、奇妙な責め道具で拷問するシーン。
ガラスの筒に捉えてきた人間を入れ、その筒を高速回転させることで、空気を排除していき、窒息させる。
「あなた籠の鳥ね」
「硝子の人間だ」
なんて会話(硝子面に指で文字を書いて会話)もある。
博士の発明をめぐる争奪戦と、父の生命と事業を奪った仇探し。
こりゃまた大時代的な、と思ったら、昭和3年に書かれた小説だった。
耽綺社同人(土師清二、長谷川伸、国枝史郎、小酒井不木、江戸川乱歩、平山蘆江)によってサンデー毎日に連載された合作探偵小説。
博士の発明とは、こんなもの。
「いかなる砲弾でも、もしそれに触れたならばたちまち爆発力を失って、空しい鉄塊となって地上に落下してしまうという驚くべき作用を持つ」気流を発生させる装置で、これが「まったく簡単な機械で作り得られて、運搬にも、飛行機への取り付けにも容易」なのだ。
タイトルの「白頭の巨人」は主人公が若くして総白髪頭になっているところから来ている。
この本のみどころは、暗号にある。
「流賀多美無能比古保武無能武太無能九之呂八」
これが暗号。「無能」と何回も出てくるので僕のことかと思ったら、そうではないようだ。
これはある場所、住所をあらわしている。
ヒント1、2文字ずつ区切って読む。数字はそのまま。
「流賀 多美 無能 比古 保武 無能 武太 無能 九 之呂 八」
ヒント2、万葉仮名で読む。
「るが たみ なの ひこ ほん なの んだ なの 九 しろ 八」
最終ヒント、電報を打つときに使われた和文通話表(逓信省発行)を参照。
たとえば「あ」なら「明石のあ」なんて地名で全部書いてある。
答えは「月島西河岸9の8」
「無能」は万葉仮名で「なの」と読み、記号表の「信濃のし」(し、なの)を参照して、「し」と読むのだ。
あと面白かったのは、発明の設計図のありかを吐かせるために、奇妙な責め道具で拷問するシーン。
ガラスの筒に捉えてきた人間を入れ、その筒を高速回転させることで、空気を排除していき、窒息させる。
「あなた籠の鳥ね」
「硝子の人間だ」
なんて会話(硝子面に指で文字を書いて会話)もある。
歩武の駒〜ワイワイフェスティバル2001オータム
2008年10月17日 読書
今日は夜勤明けに図書館寄って、数冊借りてくる。
クルーグマンやテイラーが目当てだったのに、そんな今旬の人の本は既に借りられていた。
村川和宏の『歩武の駒』1〜4巻まで読んだ。最終巻の5巻がなかなか見つからないので未読。
将棋プロを目指す少年の物語。
敵としてあらわれるのは、龍使い、過去の全棋譜を記憶している男、早見えの男、2枚角使いなどなど。1本筋の通った1人のライバルがとくにいないため、読みきりの連続、といった感じ。
将棋のプロの息子がサラブレッド扱いで登場したりもした。僕は毎週駅の売店で週刊将棋という新聞を買って読んでいるのだが、そのなかで、囲碁とちがって将棋の場合、わが子を将棋のプロに育てようとする人が少ない、とするコラムを読んだばかりだった。鈴木宏彦氏の「いま、将棋界の話題」の「将棋の親子棋士はどうして少ないのか?」だ。その記事では、新聞の囲碁将棋担当記者やプロ棋士の発言から、挫折したときの過酷さ、プロになれる確率の低さをその要因にあげている。こういうことをネタにすれば、また違った展開もあったかもしれない。
監修は羽生キラーとして知られる深浦康市六段(2000年当時)。折にふれてあらわれる将棋の盤面が、面白い次の一手問題にもなっていて楽しかった。
5巻は読んでいないが、どうやらこの調子で話は進みそうだ。
見たビデオは「ワイワイフェスティバル2001オータム」
ガンで若死にしたミクの歌とダンスが堪能できる。
会場の子供たちも一緒に踊ったりするのだが、なによりもワイワイキッズのダンスの素晴らしさにあぜんとした。
後に「U15スキにさせて」に出演する子(南雲咲子)、ウルトラQに出る子(瓜田あすみ)、体操が得意でユニット「まゆのり」で活躍していた子(伊礼祈。現在は学業に専念)、松本唯(男子なのでよく知らない)の4人が踊る「チェッチェッコリ」は最高!
チェッチェッコリはジャドリストがネタにしていた印象が強かったが、これからはワイワイキッズの超絶技巧とともに思い出されることだろう。
「ワイワイキッズ」はサンテレビで放送されていたのだが、あんまり記憶に残っていない。
ミク(羽生未来)がamUのacoちゃんに似てるという話から興味を持って見てみたのだ。「ミクのワイワイダンス」のVTR見ているときはそんなに思わなかったが、確かに、このVTR「ワイワイフェスティバル2001オータム」のジャケット写真はちょっと面影がある。
ライブ見ているあいだは、ミクはまぎれもなくミクだし、acoはaco以外の何者でもないのだけれど。
クルーグマンやテイラーが目当てだったのに、そんな今旬の人の本は既に借りられていた。
村川和宏の『歩武の駒』1〜4巻まで読んだ。最終巻の5巻がなかなか見つからないので未読。
将棋プロを目指す少年の物語。
敵としてあらわれるのは、龍使い、過去の全棋譜を記憶している男、早見えの男、2枚角使いなどなど。1本筋の通った1人のライバルがとくにいないため、読みきりの連続、といった感じ。
将棋のプロの息子がサラブレッド扱いで登場したりもした。僕は毎週駅の売店で週刊将棋という新聞を買って読んでいるのだが、そのなかで、囲碁とちがって将棋の場合、わが子を将棋のプロに育てようとする人が少ない、とするコラムを読んだばかりだった。鈴木宏彦氏の「いま、将棋界の話題」の「将棋の親子棋士はどうして少ないのか?」だ。その記事では、新聞の囲碁将棋担当記者やプロ棋士の発言から、挫折したときの過酷さ、プロになれる確率の低さをその要因にあげている。こういうことをネタにすれば、また違った展開もあったかもしれない。
監修は羽生キラーとして知られる深浦康市六段(2000年当時)。折にふれてあらわれる将棋の盤面が、面白い次の一手問題にもなっていて楽しかった。
5巻は読んでいないが、どうやらこの調子で話は進みそうだ。
見たビデオは「ワイワイフェスティバル2001オータム」
ガンで若死にしたミクの歌とダンスが堪能できる。
会場の子供たちも一緒に踊ったりするのだが、なによりもワイワイキッズのダンスの素晴らしさにあぜんとした。
後に「U15スキにさせて」に出演する子(南雲咲子)、ウルトラQに出る子(瓜田あすみ)、体操が得意でユニット「まゆのり」で活躍していた子(伊礼祈。現在は学業に専念)、松本唯(男子なのでよく知らない)の4人が踊る「チェッチェッコリ」は最高!
チェッチェッコリはジャドリストがネタにしていた印象が強かったが、これからはワイワイキッズの超絶技巧とともに思い出されることだろう。
「ワイワイキッズ」はサンテレビで放送されていたのだが、あんまり記憶に残っていない。
ミク(羽生未来)がamUのacoちゃんに似てるという話から興味を持って見てみたのだ。「ミクのワイワイダンス」のVTR見ているときはそんなに思わなかったが、確かに、このVTR「ワイワイフェスティバル2001オータム」のジャケット写真はちょっと面影がある。
ライブ見ているあいだは、ミクはまぎれもなくミクだし、acoはaco以外の何者でもないのだけれど。
澁澤龍彦の『ねむり姫』を読んだ。
ねむり姫
狐媚記
ぼろんじ
夢ちがえ
画美人
きらら姫
古典を読んでいるかのような雰囲気がありながら、どこかでふっと肩の力が抜ける技が素晴らしい。
「ぼろんじ」のラストは、こうしめくくられる。
「ぼろんじ」という題には特別の意味はない。ただ音がおもしろく、むかしから私の気に入っていることばなので、これを採択したまでのことである。けだし「あんあん」「のんの」のたぐいか。
「画美人」にはこんな会話がある。
時代は安政のころ。女の汗が芳香を放っているのに気づき。
「伽羅の女とはめずらしい。特異体質だな」
「いやですよ。そんな近代のテクニカル・タームは存じませぬ」
「きらら姫」にもこんな描写が。
時代は嘉永のころ。星舟に乗り込もうとする音吉。
このままではE.Tみたいに置いてけぼりを食ってしまうぞと、必死の思いで音吉は杉の樹をよじのぼりはじめた。
なお、この話には結局きらら姫の顛末がほとんど触れられず、ツッコミがはいって終わりになっている。融通無礙とはこのこと?
なお、僕が読んだ単行本だと、著者の自装になっている。
ねむり姫
狐媚記
ぼろんじ
夢ちがえ
画美人
きらら姫
古典を読んでいるかのような雰囲気がありながら、どこかでふっと肩の力が抜ける技が素晴らしい。
「ぼろんじ」のラストは、こうしめくくられる。
「ぼろんじ」という題には特別の意味はない。ただ音がおもしろく、むかしから私の気に入っていることばなので、これを採択したまでのことである。けだし「あんあん」「のんの」のたぐいか。
「画美人」にはこんな会話がある。
時代は安政のころ。女の汗が芳香を放っているのに気づき。
「伽羅の女とはめずらしい。特異体質だな」
「いやですよ。そんな近代のテクニカル・タームは存じませぬ」
「きらら姫」にもこんな描写が。
時代は嘉永のころ。星舟に乗り込もうとする音吉。
このままではE.Tみたいに置いてけぼりを食ってしまうぞと、必死の思いで音吉は杉の樹をよじのぼりはじめた。
なお、この話には結局きらら姫の顛末がほとんど触れられず、ツッコミがはいって終わりになっている。融通無礙とはこのこと?
なお、僕が読んだ単行本だと、著者の自装になっている。
バルベ・ドルヴィイの『レア』を読んだ。
ドールヴィイの物語は死体と謎がつきものだ。
恋愛に苦しむ男女。
そして女性の死。
ラストの1行で全部ひっくりかえる大ドンデン返し!
叙述のトリックか!
素晴らしい!
ドールヴィイがもっと安価で読みやすい環境になればいいのに!
ドールヴィイの物語は死体と謎がつきものだ。
恋愛に苦しむ男女。
そして女性の死。
ラストの1行で全部ひっくりかえる大ドンデン返し!
叙述のトリックか!
素晴らしい!
ドールヴィイがもっと安価で読みやすい環境になればいいのに!
中井英夫の連作長編『人形たちの夜』を読んだ。
以下目次
1「春」
異形の列
真夜中の鶏
跛行
2「夏」
夢のパトロール
海辺の朝食
水妖(オンディーヌ)
3「秋」
笑う座敷ぼっこ
三途川を渡って
影人
4「冬」
憎悪の美酒
歪む木偶
貴腐(プリチュール・ノーブル)
あとがきによると、「1はプロローグと母娘二代の業を、2は反対に明るい夏の若い男女の愛と性を、3は推理小説めかして暗号解読を、4では”兄”の立場からする憎悪の哲学を語ってエピローグとした」とある。
おおむねその通りだが、今回久しぶりに中井英夫を読み返してみて、30年前の読後感とは違い、かなり女性っぽい印象を受けた。これは何なんだろう。
「跛行」の動機が面白い。
「これまでつき合った男は例外なく不具で、かりに健康だったとしてもわたくしと一緒になるが早いか片輪にならずにいない」と思いこむ女。非のうちどころのない男と結ばれた彼女は、「二度と夫を兵隊にとられぬようその脚に傷をつけ、戦争中の軍国主義者たちとは違った純粋な不具の男を傍らにおきたかった」
連作のため、1つ1つの短編で解決したはずの物語が、実は裏の真相があったのだ、と判明するのがたまらなく面白い。
「貴腐」では「人工の憎悪」という言葉が出てくる。
憎しみの足りなかったために相手を死なせてしまった人物が、「憎み得ないものを憎むことも私には必要だった」と打ち明ける。
なるほど、こういう感情は人生経験のない学生時代に読んでいてもピンと来なかったんだな、と知れる。
以下目次
1「春」
異形の列
真夜中の鶏
跛行
2「夏」
夢のパトロール
海辺の朝食
水妖(オンディーヌ)
3「秋」
笑う座敷ぼっこ
三途川を渡って
影人
4「冬」
憎悪の美酒
歪む木偶
貴腐(プリチュール・ノーブル)
あとがきによると、「1はプロローグと母娘二代の業を、2は反対に明るい夏の若い男女の愛と性を、3は推理小説めかして暗号解読を、4では”兄”の立場からする憎悪の哲学を語ってエピローグとした」とある。
おおむねその通りだが、今回久しぶりに中井英夫を読み返してみて、30年前の読後感とは違い、かなり女性っぽい印象を受けた。これは何なんだろう。
「跛行」の動機が面白い。
「これまでつき合った男は例外なく不具で、かりに健康だったとしてもわたくしと一緒になるが早いか片輪にならずにいない」と思いこむ女。非のうちどころのない男と結ばれた彼女は、「二度と夫を兵隊にとられぬようその脚に傷をつけ、戦争中の軍国主義者たちとは違った純粋な不具の男を傍らにおきたかった」
連作のため、1つ1つの短編で解決したはずの物語が、実は裏の真相があったのだ、と判明するのがたまらなく面白い。
「貴腐」では「人工の憎悪」という言葉が出てくる。
憎しみの足りなかったために相手を死なせてしまった人物が、「憎み得ないものを憎むことも私には必要だった」と打ち明ける。
なるほど、こういう感情は人生経験のない学生時代に読んでいてもピンと来なかったんだな、と知れる。
王位戦第6局大盤解説会〜『民主主義への憎悪』
2008年9月10日 読書
午後5時から関西将棋会館で49期王位戦第6局の大盤解説会。
羽生が追い上げてきている。
解説は小林健二九段。
小林九段の解説は、すっかり先生然としていた。こうしてみると、解説者によって、まるで漫談のような解説もあれば、客と一緒に将棋の流れを見守る解説もあり、バラエティに富んでいる。
勝負は、羽生の勝ち。負ける気がしない。
これで3対3のイーブンに持ち込んで、いよいよ最終局までもつれこんだ。
あいにくと、最終局の大盤解説には行けないが、結果が非常に気になるところ。
読んだ本はジャック・ランシエールの『民主主義への憎悪』
昨日読んだジジェクでも、ランシエールがよく引用されていた。
以下、目次。
序
勝利した民主主義から犯罪的な民主主義へ
政治あるいは失われた牧人
民主制、共和制、代表制
憎悪の理由
講演:デモクラシー、不合意、コミュニケーション
訳者解説:デモクラシーとは何か
原註/訳註
訳者あとがき
ジャック・ランシエール書誌
ランシエールの本は、つかみがうまい。
冒頭、フランスでの最近の事件を列挙し、それがどう解釈されているかを総括する。
事件というのは、公立学校で禁じられているイスラムのヒジャーブ(スカーフ)を取るのを拒否する女性たちや、破綻した社会保障、退職年金制度維持のためにデモする労働者、同性愛者の結婚、リアリティ番組が人気を博していること、列車内で襲われた嘘の話をでっちあげた女性などなど。
これらの原因は、すべて現代大衆社会における個人の際限なき欲望の支配から来るもので、つまり、民主主義に原因がある、と言っているのだ。民主主義が個人主義を促進し、伝統的価値を破壊する、と。
訳者解説の冒頭を引用すれば
「いまやデモクラシーは、行き過ぎた平等要求の別名でしかない」のである。
ランシエールは、そうした民主主義批判、いや、憎悪を批判している。
面白かったのは、民主主義の最大の特徴は「くじびき」だというところ。
プラトンによれば、統治者にとって必要な資格は7つある。親が子にふるう権力、年長者の年少者への権力、主人の奴隷への、貴族の平民への、強者が弱者への、学識ある者の無知な者への。そして、純粋な偶然の統治。つまり、くじびき。すなわち、デモクラシー。
これは、権謀術数によって権力を握ることに長けた人々によって統治される害毒を避けるのに役立つ。「よい統治とは、統治したいと思っていない人々の統治」だということなのだ。(プラトン)
分け前なき人々、数に数えられていない人々の異議申し立てでなりたつ運動こそが民主主義で、こうしてみると、多数決とか代議制が特徴だと思ってた民主主義観とは大きく違っている。むしろそれは革命に近い。
えっと、本文にも革命について書いてあったと思うが、どこだったか忘れた!
ランシエールの問題意識は、日本の今の状況にもあてはまるものだと思う。
行き過ぎた民主主義だの、個人主義の顛末だの、それらしい解説にごまかされてはならない。
この本読んでいるとき頭から離れなかったのは、コードギアス2でルルーシュが言い放つ「民主主義だ!」だった。ルルーシュのデモクラシー論を聞いてみたいものだ。
羽生が追い上げてきている。
解説は小林健二九段。
小林九段の解説は、すっかり先生然としていた。こうしてみると、解説者によって、まるで漫談のような解説もあれば、客と一緒に将棋の流れを見守る解説もあり、バラエティに富んでいる。
勝負は、羽生の勝ち。負ける気がしない。
これで3対3のイーブンに持ち込んで、いよいよ最終局までもつれこんだ。
あいにくと、最終局の大盤解説には行けないが、結果が非常に気になるところ。
読んだ本はジャック・ランシエールの『民主主義への憎悪』
昨日読んだジジェクでも、ランシエールがよく引用されていた。
以下、目次。
序
勝利した民主主義から犯罪的な民主主義へ
政治あるいは失われた牧人
民主制、共和制、代表制
憎悪の理由
講演:デモクラシー、不合意、コミュニケーション
訳者解説:デモクラシーとは何か
原註/訳註
訳者あとがき
ジャック・ランシエール書誌
ランシエールの本は、つかみがうまい。
冒頭、フランスでの最近の事件を列挙し、それがどう解釈されているかを総括する。
事件というのは、公立学校で禁じられているイスラムのヒジャーブ(スカーフ)を取るのを拒否する女性たちや、破綻した社会保障、退職年金制度維持のためにデモする労働者、同性愛者の結婚、リアリティ番組が人気を博していること、列車内で襲われた嘘の話をでっちあげた女性などなど。
これらの原因は、すべて現代大衆社会における個人の際限なき欲望の支配から来るもので、つまり、民主主義に原因がある、と言っているのだ。民主主義が個人主義を促進し、伝統的価値を破壊する、と。
訳者解説の冒頭を引用すれば
「いまやデモクラシーは、行き過ぎた平等要求の別名でしかない」のである。
ランシエールは、そうした民主主義批判、いや、憎悪を批判している。
面白かったのは、民主主義の最大の特徴は「くじびき」だというところ。
プラトンによれば、統治者にとって必要な資格は7つある。親が子にふるう権力、年長者の年少者への権力、主人の奴隷への、貴族の平民への、強者が弱者への、学識ある者の無知な者への。そして、純粋な偶然の統治。つまり、くじびき。すなわち、デモクラシー。
これは、権謀術数によって権力を握ることに長けた人々によって統治される害毒を避けるのに役立つ。「よい統治とは、統治したいと思っていない人々の統治」だということなのだ。(プラトン)
分け前なき人々、数に数えられていない人々の異議申し立てでなりたつ運動こそが民主主義で、こうしてみると、多数決とか代議制が特徴だと思ってた民主主義観とは大きく違っている。むしろそれは革命に近い。
えっと、本文にも革命について書いてあったと思うが、どこだったか忘れた!
ランシエールの問題意識は、日本の今の状況にもあてはまるものだと思う。
行き過ぎた民主主義だの、個人主義の顛末だの、それらしい解説にごまかされてはならない。
この本読んでいるとき頭から離れなかったのは、コードギアス2でルルーシュが言い放つ「民主主義だ!」だった。ルルーシュのデモクラシー論を聞いてみたいものだ。