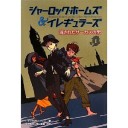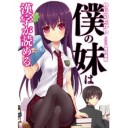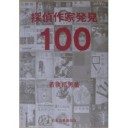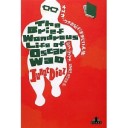日本におけるポール・クローデル
2018年7月12日 読書1922年
アインシュタイン講演会に際して。日本では相対性理論が流行して本も売れているが、それには滑稽な理由がある。日本では相対性という語句は男女関係を暗示するからである。
日本が満州の掌握に執着する理由は、国家の安全保障の問題で、経済的利益は二の次であること。アメリカよりも中国のほうが安全であること。
1923年
民衆の不満の主な理由は物価高にあるが、行政府が資本家階級だけの利益を追求しすぎるので一層深刻になっている。
プルーストの欠点は、意志、知性、道徳の欠如。にあり、その結果、彼の描く世界は平板で3次元でない。彼の作品は阿片吸引者に類する特徴がある。
正宗白鳥によるクローデル「女と影」の感想。
外国人の東洋趣味に過ぎず、詩とはいえない。
講演会を終えて。観客が自分の考えを受け入れるようになるのは自分の死後になるだろう。
吉野の桜見物に際して。吉野の美観は実に言語に絶するも、これを観賞するためには命懸けなり。雑踏に辟易する。
鼻は中国では人類生成の基である。日本では「私です」という時に自分の鼻をさす。
日本における軍国主義精神の減退。国民の間で職業軍人の人気は20年来低下し続けている。
N.R.F.誌リヴィエール宛書簡。日本での講演を掲載してもいいが、L.アラゴンなどの汚らわしい作家と並べないでほしい。
A.ジッドのドストエフスキー論は馬鹿げたもの。
関東大震災の翌日。フランス人の罹災者が多数出ていたと知り、逗子行を断念。停泊中のフランス郵船アンドレ・ルボン号を基地に、国籍を問わず罹災者救助の指揮にあたる。
アインシュタイン講演会に際して。日本では相対性理論が流行して本も売れているが、それには滑稽な理由がある。日本では相対性という語句は男女関係を暗示するからである。
日本が満州の掌握に執着する理由は、国家の安全保障の問題で、経済的利益は二の次であること。アメリカよりも中国のほうが安全であること。
1923年
民衆の不満の主な理由は物価高にあるが、行政府が資本家階級だけの利益を追求しすぎるので一層深刻になっている。
プルーストの欠点は、意志、知性、道徳の欠如。にあり、その結果、彼の描く世界は平板で3次元でない。彼の作品は阿片吸引者に類する特徴がある。
正宗白鳥によるクローデル「女と影」の感想。
外国人の東洋趣味に過ぎず、詩とはいえない。
講演会を終えて。観客が自分の考えを受け入れるようになるのは自分の死後になるだろう。
吉野の桜見物に際して。吉野の美観は実に言語に絶するも、これを観賞するためには命懸けなり。雑踏に辟易する。
鼻は中国では人類生成の基である。日本では「私です」という時に自分の鼻をさす。
日本における軍国主義精神の減退。国民の間で職業軍人の人気は20年来低下し続けている。
N.R.F.誌リヴィエール宛書簡。日本での講演を掲載してもいいが、L.アラゴンなどの汚らわしい作家と並べないでほしい。
A.ジッドのドストエフスキー論は馬鹿げたもの。
関東大震災の翌日。フランス人の罹災者が多数出ていたと知り、逗子行を断念。停泊中のフランス郵船アンドレ・ルボン号を基地に、国籍を問わず罹災者救助の指揮にあたる。
2017年4月の読書メーター
読んだ本の数:20冊
読んだページ数:3185ページ
ナイス数:81ナイス
http://bookmeter.com/u/479013/matome?invite_id=479013
■塔のなかの井戸~夢のかけら(全2冊)―ラドヴァン・イヴシック&トワイヤン詩画集
アニー・ル・ブランのパートナー、ラドヴァン・イヴシックの11の物語と1通の手紙、トワイヤンの絵。原文と、2パターンの絵も収録。シュルレアリスムの恋文か。
読了日:4月28日 著者:ラドヴァン・イヴシック,トワイヤン
http://bookmeter.com/cmt/63960714
■読む時間
本や新聞を読む人、あるいは本の写真が集められた写真集に、谷川俊太郎が詩を寄せている。街角や、書架の梯子の途中など、読む場所の多様さも面白かった。本が大量にある様を見たり、読書する人を見ただけで、半分本を読んだくらいの快楽が得られるのは何故なのか。
読了日:4月21日 著者:アンドレ・ケルテス
http://bookmeter.com/cmt/63781595
■ウラジーミル・イリーチ・レーニン―長篇叙事詩 (1965年) (現代の芸術双書)
この本が出たとき、既にマヤコフスキーのレーニンは小笠原豊樹訳(選集3巻)で出ていたが、階段式の表記でなく、誤訳が多いとして、ウサミ・ナオキが新訳したもの。小笠原訳のどこが誤訳かを一覧で示すなどしており、確かにわかりやすい翻訳になっていた。マヤコフスキーのレーニンへの思いが伝わる長編詩。
読了日:4月20日 著者:うさみなおき,ウラジーミル・V.マヤコーフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63767112
■少女達の野
1989年刊行の鈴木志郎康さんの詩集。詩のあいだに、散文体の「野ノ録録タル」がときおり挟み込まれる。沖縄の話や、まずいそば屋の話があるかと思えば、詩に使った単語が最後に五十音順に分類されていたり、「(動詞)って(動詞)(名詞)が(動詞)」みたいな実験的な表現、性欲やうんこの話も出てきて、生命力豊かな健在ぶりを見せていた。
読了日:4月20日 著者:鈴木志郎康
http://bookmeter.com/cmt/63766925
■雷雨をやりすごす
岩田宏のエッセイ集。ガラパゴスの紀行文、アーウィン・ショー、小熊秀雄、野村吉哉、鮎川信夫、澁澤龍彦も加わっていた「新人評論」、デ・カダンスのことなどが書かれているが、圧巻は巻末の「マヤコフスキーの愛人たち」。知人を集めての私的報告会の記録で、マヤコフスキーの魅力を存分に味わえた。
読了日:4月19日 著者:岩田宏
http://bookmeter.com/cmt/63764469
■ロシア革命 (「知の再発見」双書)
ロシア革命百年。写真、図版多数で目で見てわかりやすいロシア革命史。1905年の第1次革命から、1917年の2月革命、10月革命まで、それぞれのきっかけやモチベーション、主体の違いはあれ、権力側は一度や二度の打撃では潰れないのだな、と思わされた。
読了日:4月17日 著者:ニコラヴェルト
http://bookmeter.com/cmt/63749743
■大審問官―自由なき楽園の支配者
カラマーゾフの兄弟の大審問官の部分の新訳と、松岡正剛さんの解説(千夜千冊からの転載)。ロシア語原文も収録されていた(全く読めなかった)。自由と神、奇跡と神秘と権威、松岡正剛さんによると「いったいこの世界に他人を赦す権利をもっている者などいるのだろうか」というイワンの主張。大審問官や悪魔の態度、言動が現代ではむしろ正しく見えてしまっているだけに、考えさせられる。
読了日:4月16日 著者:フョードルドストエフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63707824
■アレハンドリア アリス狩りV
ユリイカに掲載された文章を中心に編まれた本で、何年も前から予告だけされている「アリスに驚け」とは別物らしい。テーブル、庭園、マニエリスム、英文学、源内、水族館劇場。もっと多くの本を読み、いろんなものを見に行きたくなる悪魔のような本だった。
読了日:4月15日 著者:高山宏
http://bookmeter.com/cmt/63707780
■死んでしまう系のぼくらに
最果タヒさんの詩には「死」がよく出てくるな、と思っていたら、この第三詩集では、タイトルもなかみも死の椀飯振舞いになっていた。「女の子の気持ちを代弁する音楽だなんて全部、死んでほしい」「恋に、最後の希望をかけるような、くだらない少女にならないで」など、ハッとさせられる言葉が随所に鏤められている。
読了日:4月12日 著者:最果タヒ
http://bookmeter.com/cmt/63707745
■換気口
アンドレ・ブルトン没後50年記念出版。ブルトン、サド、ランボー、アポリネール、ジャリ、ロートレアモン、スーポー、ピエール・ルイスなどの引用をまじえながら、殺されかけて息詰まる詩、シュルレアリスムの状況に風穴(換気口)をあけるポエジー爆弾。攻撃的な詩論はそのままポエジーに満ちていて、スピードがあるのに1ページごとに玩味させられた。「文化という概念が雑巾状態にまで貶められて、貧困極まりない日常の美学の垂れ流し的催し物の数々」の状況に、カツ!
読了日:4月9日 著者:アニール・ブラン
http://bookmeter.com/cmt/63707695
■空が分裂する
別冊少年マガジン掲載の、イラスト陣に萩尾望都、古屋兎丸、大槻香奈、志村貴子、西島大介、冬目景などなどを擁する詩などが収録されている。表紙は川島小鳥。「主犯はボアダムスだった」ではじまる詩もあり、86年神戸生まれのリアリティを感じる。若い感性に祝福された詩集。個人の思いが世界や人類や死などの大テーマに直結していた。
読了日:4月8日 著者:最果タヒ
http://bookmeter.com/cmt/63707562
■サトラップの息子
ロシアからフランスに家族で亡命してきた少年は、友人と二人で小説を書くことにした。少年は後にフランスに帰化し、フランス風にアンリ・トロワイヤと改名して作家になる。第二次世界大戦下のフランスも描かれて、自伝かと読めるのだが、自伝のふりをした小説なのだそうだ。これは面白い!
読了日:4月7日 著者:アンリ・トロワイヤ
http://bookmeter.com/cmt/63526826
■仮面の商人 (小学館文庫)
第一部は迎合出来ず不遇をかこつ小説家ヴァランタンの生涯。第二部は一転、五十数年後、作家の甥の視点で描かれる。彼は、死後評価されて名声を博すヴァランタンの伝記を書こうとする。第一部で出てきた人物たちによる自分勝手な歪曲された話で、実情とは程遠い伝記が織り成される。評伝の著作の多いトロワイヤにとって皮肉な物語だが、面白さは抜群。中心となる重要なことが抜け落ち、雑魚と枝葉がはびこるさまが爆笑もの。
読了日:4月5日 著者:アンリトロワイヤ
http://bookmeter.com/cmt/63466377
■いいってどんなこと?わるいってどんなこと?
マヤコフスキーの児童書、絵はキリロフ・ヴェ。物事の良し悪しをお父さんが子どもに教える。天候の良し悪しからはじまり、汚すことやいじめることを悪いとさとし、悪を追い払うことを勧める。最後、お父さんは「ちいさいときにぶたのこならば おおきくなってもぶたのまま」と言う。なるほど!これはキク!
読了日:4月5日 著者:マヤコフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63453895
■海と灯台の本
灯台と灯台守の役割を描き、最後に子どもたちに、このように生きなさい、と説く。ポクロフスキーの絵が極めてロシア的だし、社会主義への期待と信頼がマヤコフスキーを突き動かしていた時期だとあからさまにわかるのが、いい。
読了日:4月5日 著者:ウラジミール・ウラジーミロヴィチマヤコフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63448710
■夜明けあと (新潮文庫)
明治時代に起こった出来事を1年毎に新聞記事等で綴る。昔も今も変わらないなあ、ということや、今では考えられないことなど、面白い記事でいっぱい。狸囃子に狐憑き、犬神憑きに人面疽、ポルターガイスト。ウサギやカナリヤのブーム。セイフ餡やシュウセイ餡と名付けられた国会汁粉が売り出されたとか、輸出や三味線屋を当て込んだネコ会社の計画など。漢文を読めない大学生の話題など、昨日今日の記事を読むかのようだった。
読了日:4月4日 著者:星新一
http://bookmeter.com/cmt/63448529
■グッドモーニング
第13回中原中也賞。夜明け前から、グッドモーニングまで。その夜明けはおそらくは十代のイニシエーションなのだろうが、作者があとがきで言うように「十代は去ってなどおらず、わたしの血はその十代でできていた」のであり、「決してわたしは彼らを、遺物にはしない」との決意、つまり自らの十代を受け入れることで夜は明けたのだ。大人になる過程で忘れ、捨てられるものに着目する発想は、ともすれば、まだ大人になっていないことへの言い訳と居直りになってしまう。その罠を越えて朝を迎えた詩人に僕からも朝の挨拶を贈りたい。
読了日:4月3日 著者:最果タヒ
http://bookmeter.com/cmt/63429433
■日々涙滴 (1977年) (叢書・同時代の詩〈5〉)
鈴木志郎康さんの映画「草の影を刈る」を最近見る機会があり、そのなかで原稿が写っていたのが、この詩集の多分「投身の思い」だったんじゃないかと記憶している。「貯金通帳的詩集」になることを否定したい思い、「何んで自分はこんなことをしているのか」という問い、「居直りと浮き腰」の繰り返し。それはこの詩集だけのことではなく、自分の日々の過ごし方にも通ずるもので、考えさせられた。
読了日:4月3日 著者:鈴木志郎康
http://bookmeter.com/cmt/63429267
■朱日記
泉鏡花の小説を中川学が絵本化。無数の猿、懐から溢れるほどの茱萸、色白の嬢ちゃん坊ちゃん、赤合羽の坊主、読本の消火器、朱で記した日記の「火曜」、酷い風等々、火事の兆しに取り囲まれ、ざわざわとする。これで火災が起こらないと詐欺みたいなものだ。火事の原因もそれを語る女もこの世のものではなく、怖い。僕はうっかり、そうしてしまったが、これは、ひとりで夜読むな、の物語だ。絵の朱色が逃れられぬ宿命のような迫力だった。
読了日:4月2日 著者:泉鏡花,中川学
http://bookmeter.com/cmt/63429061
■渡り歩き
岩田宏(小笠原豊樹)のエッセイ集。エリオット・ポール、エルマー・ライス、エルンスト・トラー、ゲオルク・カイザー、ソフィ・トレッドウェルといった僕にとって未知の作家、劇作家や、デスノス、マヤコフスキー、トロワイヤ、セルジュ・レジアニについて、また、ユーディット、ピーター・イベットスン(そしてスヴェンガリ)について。本に関するエッセイが主だが演劇についての言及が多かった。
読了日:4月1日 著者:岩田宏
http://bookmeter.com/cmt/63428612
▼読書メーター
http://bookmeter.com/
読んだ本の数:20冊
読んだページ数:3185ページ
ナイス数:81ナイス
http://bookmeter.com/u/479013/matome?invite_id=479013
■塔のなかの井戸~夢のかけら(全2冊)―ラドヴァン・イヴシック&トワイヤン詩画集
アニー・ル・ブランのパートナー、ラドヴァン・イヴシックの11の物語と1通の手紙、トワイヤンの絵。原文と、2パターンの絵も収録。シュルレアリスムの恋文か。
読了日:4月28日 著者:ラドヴァン・イヴシック,トワイヤン
http://bookmeter.com/cmt/63960714
■読む時間
本や新聞を読む人、あるいは本の写真が集められた写真集に、谷川俊太郎が詩を寄せている。街角や、書架の梯子の途中など、読む場所の多様さも面白かった。本が大量にある様を見たり、読書する人を見ただけで、半分本を読んだくらいの快楽が得られるのは何故なのか。
読了日:4月21日 著者:アンドレ・ケルテス
http://bookmeter.com/cmt/63781595
■ウラジーミル・イリーチ・レーニン―長篇叙事詩 (1965年) (現代の芸術双書)
この本が出たとき、既にマヤコフスキーのレーニンは小笠原豊樹訳(選集3巻)で出ていたが、階段式の表記でなく、誤訳が多いとして、ウサミ・ナオキが新訳したもの。小笠原訳のどこが誤訳かを一覧で示すなどしており、確かにわかりやすい翻訳になっていた。マヤコフスキーのレーニンへの思いが伝わる長編詩。
読了日:4月20日 著者:うさみなおき,ウラジーミル・V.マヤコーフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63767112
■少女達の野
1989年刊行の鈴木志郎康さんの詩集。詩のあいだに、散文体の「野ノ録録タル」がときおり挟み込まれる。沖縄の話や、まずいそば屋の話があるかと思えば、詩に使った単語が最後に五十音順に分類されていたり、「(動詞)って(動詞)(名詞)が(動詞)」みたいな実験的な表現、性欲やうんこの話も出てきて、生命力豊かな健在ぶりを見せていた。
読了日:4月20日 著者:鈴木志郎康
http://bookmeter.com/cmt/63766925
■雷雨をやりすごす
岩田宏のエッセイ集。ガラパゴスの紀行文、アーウィン・ショー、小熊秀雄、野村吉哉、鮎川信夫、澁澤龍彦も加わっていた「新人評論」、デ・カダンスのことなどが書かれているが、圧巻は巻末の「マヤコフスキーの愛人たち」。知人を集めての私的報告会の記録で、マヤコフスキーの魅力を存分に味わえた。
読了日:4月19日 著者:岩田宏
http://bookmeter.com/cmt/63764469
■ロシア革命 (「知の再発見」双書)
ロシア革命百年。写真、図版多数で目で見てわかりやすいロシア革命史。1905年の第1次革命から、1917年の2月革命、10月革命まで、それぞれのきっかけやモチベーション、主体の違いはあれ、権力側は一度や二度の打撃では潰れないのだな、と思わされた。
読了日:4月17日 著者:ニコラヴェルト
http://bookmeter.com/cmt/63749743
■大審問官―自由なき楽園の支配者
カラマーゾフの兄弟の大審問官の部分の新訳と、松岡正剛さんの解説(千夜千冊からの転載)。ロシア語原文も収録されていた(全く読めなかった)。自由と神、奇跡と神秘と権威、松岡正剛さんによると「いったいこの世界に他人を赦す権利をもっている者などいるのだろうか」というイワンの主張。大審問官や悪魔の態度、言動が現代ではむしろ正しく見えてしまっているだけに、考えさせられる。
読了日:4月16日 著者:フョードルドストエフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63707824
■アレハンドリア アリス狩りV
ユリイカに掲載された文章を中心に編まれた本で、何年も前から予告だけされている「アリスに驚け」とは別物らしい。テーブル、庭園、マニエリスム、英文学、源内、水族館劇場。もっと多くの本を読み、いろんなものを見に行きたくなる悪魔のような本だった。
読了日:4月15日 著者:高山宏
http://bookmeter.com/cmt/63707780
■死んでしまう系のぼくらに
最果タヒさんの詩には「死」がよく出てくるな、と思っていたら、この第三詩集では、タイトルもなかみも死の椀飯振舞いになっていた。「女の子の気持ちを代弁する音楽だなんて全部、死んでほしい」「恋に、最後の希望をかけるような、くだらない少女にならないで」など、ハッとさせられる言葉が随所に鏤められている。
読了日:4月12日 著者:最果タヒ
http://bookmeter.com/cmt/63707745
■換気口
アンドレ・ブルトン没後50年記念出版。ブルトン、サド、ランボー、アポリネール、ジャリ、ロートレアモン、スーポー、ピエール・ルイスなどの引用をまじえながら、殺されかけて息詰まる詩、シュルレアリスムの状況に風穴(換気口)をあけるポエジー爆弾。攻撃的な詩論はそのままポエジーに満ちていて、スピードがあるのに1ページごとに玩味させられた。「文化という概念が雑巾状態にまで貶められて、貧困極まりない日常の美学の垂れ流し的催し物の数々」の状況に、カツ!
読了日:4月9日 著者:アニール・ブラン
http://bookmeter.com/cmt/63707695
■空が分裂する
別冊少年マガジン掲載の、イラスト陣に萩尾望都、古屋兎丸、大槻香奈、志村貴子、西島大介、冬目景などなどを擁する詩などが収録されている。表紙は川島小鳥。「主犯はボアダムスだった」ではじまる詩もあり、86年神戸生まれのリアリティを感じる。若い感性に祝福された詩集。個人の思いが世界や人類や死などの大テーマに直結していた。
読了日:4月8日 著者:最果タヒ
http://bookmeter.com/cmt/63707562
■サトラップの息子
ロシアからフランスに家族で亡命してきた少年は、友人と二人で小説を書くことにした。少年は後にフランスに帰化し、フランス風にアンリ・トロワイヤと改名して作家になる。第二次世界大戦下のフランスも描かれて、自伝かと読めるのだが、自伝のふりをした小説なのだそうだ。これは面白い!
読了日:4月7日 著者:アンリ・トロワイヤ
http://bookmeter.com/cmt/63526826
■仮面の商人 (小学館文庫)
第一部は迎合出来ず不遇をかこつ小説家ヴァランタンの生涯。第二部は一転、五十数年後、作家の甥の視点で描かれる。彼は、死後評価されて名声を博すヴァランタンの伝記を書こうとする。第一部で出てきた人物たちによる自分勝手な歪曲された話で、実情とは程遠い伝記が織り成される。評伝の著作の多いトロワイヤにとって皮肉な物語だが、面白さは抜群。中心となる重要なことが抜け落ち、雑魚と枝葉がはびこるさまが爆笑もの。
読了日:4月5日 著者:アンリトロワイヤ
http://bookmeter.com/cmt/63466377
■いいってどんなこと?わるいってどんなこと?
マヤコフスキーの児童書、絵はキリロフ・ヴェ。物事の良し悪しをお父さんが子どもに教える。天候の良し悪しからはじまり、汚すことやいじめることを悪いとさとし、悪を追い払うことを勧める。最後、お父さんは「ちいさいときにぶたのこならば おおきくなってもぶたのまま」と言う。なるほど!これはキク!
読了日:4月5日 著者:マヤコフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63453895
■海と灯台の本
灯台と灯台守の役割を描き、最後に子どもたちに、このように生きなさい、と説く。ポクロフスキーの絵が極めてロシア的だし、社会主義への期待と信頼がマヤコフスキーを突き動かしていた時期だとあからさまにわかるのが、いい。
読了日:4月5日 著者:ウラジミール・ウラジーミロヴィチマヤコフスキー
http://bookmeter.com/cmt/63448710
■夜明けあと (新潮文庫)
明治時代に起こった出来事を1年毎に新聞記事等で綴る。昔も今も変わらないなあ、ということや、今では考えられないことなど、面白い記事でいっぱい。狸囃子に狐憑き、犬神憑きに人面疽、ポルターガイスト。ウサギやカナリヤのブーム。セイフ餡やシュウセイ餡と名付けられた国会汁粉が売り出されたとか、輸出や三味線屋を当て込んだネコ会社の計画など。漢文を読めない大学生の話題など、昨日今日の記事を読むかのようだった。
読了日:4月4日 著者:星新一
http://bookmeter.com/cmt/63448529
■グッドモーニング
第13回中原中也賞。夜明け前から、グッドモーニングまで。その夜明けはおそらくは十代のイニシエーションなのだろうが、作者があとがきで言うように「十代は去ってなどおらず、わたしの血はその十代でできていた」のであり、「決してわたしは彼らを、遺物にはしない」との決意、つまり自らの十代を受け入れることで夜は明けたのだ。大人になる過程で忘れ、捨てられるものに着目する発想は、ともすれば、まだ大人になっていないことへの言い訳と居直りになってしまう。その罠を越えて朝を迎えた詩人に僕からも朝の挨拶を贈りたい。
読了日:4月3日 著者:最果タヒ
http://bookmeter.com/cmt/63429433
■日々涙滴 (1977年) (叢書・同時代の詩〈5〉)
鈴木志郎康さんの映画「草の影を刈る」を最近見る機会があり、そのなかで原稿が写っていたのが、この詩集の多分「投身の思い」だったんじゃないかと記憶している。「貯金通帳的詩集」になることを否定したい思い、「何んで自分はこんなことをしているのか」という問い、「居直りと浮き腰」の繰り返し。それはこの詩集だけのことではなく、自分の日々の過ごし方にも通ずるもので、考えさせられた。
読了日:4月3日 著者:鈴木志郎康
http://bookmeter.com/cmt/63429267
■朱日記
泉鏡花の小説を中川学が絵本化。無数の猿、懐から溢れるほどの茱萸、色白の嬢ちゃん坊ちゃん、赤合羽の坊主、読本の消火器、朱で記した日記の「火曜」、酷い風等々、火事の兆しに取り囲まれ、ざわざわとする。これで火災が起こらないと詐欺みたいなものだ。火事の原因もそれを語る女もこの世のものではなく、怖い。僕はうっかり、そうしてしまったが、これは、ひとりで夜読むな、の物語だ。絵の朱色が逃れられぬ宿命のような迫力だった。
読了日:4月2日 著者:泉鏡花,中川学
http://bookmeter.com/cmt/63429061
■渡り歩き
岩田宏(小笠原豊樹)のエッセイ集。エリオット・ポール、エルマー・ライス、エルンスト・トラー、ゲオルク・カイザー、ソフィ・トレッドウェルといった僕にとって未知の作家、劇作家や、デスノス、マヤコフスキー、トロワイヤ、セルジュ・レジアニについて、また、ユーディット、ピーター・イベットスン(そしてスヴェンガリ)について。本に関するエッセイが主だが演劇についての言及が多かった。
読了日:4月1日 著者:岩田宏
http://bookmeter.com/cmt/63428612
▼読書メーター
http://bookmeter.com/
2017年1月の読書メーター
読んだ本の数:12冊
読んだページ数:2927ページ
ナイス数:77ナイス
http://bookmeter.com/u/479013/matome?invite_id=479013
■みんなの怪盗ルパン
少年探偵団シリーズだけでなく、ルパンもシリーズに入った!この調子で、みんなの偕成社ジュニア探偵小説シリーズも出てほしい。このルパンの巻では、新たなルパンの活躍と言うより、ルパンをいかに活用するかに作家さんが頭をひねった感じ。
読了日:1月29日 著者:小林泰三,近藤史恵,藤野恵美,真山仁,湊かなえ
http://bookmeter.com/cmt/62056647
■ゴブリン・マーケット
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの妹、クリスティナが書いた物語に、ローセンス・ハウスマンが挿絵をつけた。アーサー・ラッカム、マーガレット・タラントによる挿絵も収録。あとのふたりのゴブリンが人間っぽいのに対して、ローレンス・ハウスマンのゴブリンは、さながら山のクトゥルフとでも言えそうな感じ。「G」と略したくなるおぞましさ。ストーリーは、食べてはいけないものを食べてしまい禁断症状で衰える妹をしっかりものの姉が救うというもの。自らゴブリンの中に飛び込んで、悪い果実は食べずに、体についた果汁を妹に届ける。自制心!
読了日:1月26日 著者:クリスティナ・ロセッティ
http://bookmeter.com/cmt/61938041
■ふしぎなエレベーター
佐々木マキの絵。エレベーターについていた見たことのない「Z」のボタンを押したら、ロボットの国に到着した!ロボットの国では電車乗るにもわれ先にと押し合いへしあいで、学校では1回答を間違えたら立ち直れないダメージを受けてしまう。人間の競争社会が極端になった世界なのだが、そんな世界にもう半分なっているんじゃないのか、とか思えた。ロボットなのにヒゲがはえている顔が面白い。
読了日:1月26日 著者:わたりむつこわたりむつこ
http://bookmeter.com/cmt/61937275
■菅野結以 (C)かんの
FMの「デヴィッド・ボウイ三昧」に出ていて気になった彼女の本を読んでみた。ファッション、スキンケア、メイク、ヘア、ネイル、映画、音楽、本、食べ物、趣味、Q&Aにインタビュー、それらに関連した彼女のブログ記事、写真など、2010年に出た本だが、彼女のことをひととおりおさらいできるように構成されていた。551のシュウマイが好きだとか、ダイエットのためにやってた岩盤浴やホットヨガ、ジムなどをやめてストレスなくしたらストンとやせられた、とか、親近感がわいたり、参考になることが詰まっていた。もっと知りたくなった。
読了日:1月21日 著者:菅野結以
http://bookmeter.com/cmt/61811829
■おちゃめな生活:あなたの魔法力を磨く法
『おちゃめな老後』と重複する内容もあるが、電車の中とかで読んでいると、まるで田村セツコさんとおしゃべりしながら乗っているような気分になれた。すごく気が楽になれて、ポジティブになれる本。グラフィック・デザイナー里見宗次氏の「簡単、簡単、3日でひと仕事」という言葉は見習いたい。
読了日:1月20日 著者:田村セツコ
http://bookmeter.com/cmt/61784160
■東京零年
徹底した警察国家になってしまった日本が舞台。事件の真相を追ううちに、敵の強大さと得体の知れなさが恐怖を呼ぶ。反権力の思想は監視のもとつぶされていく。最初は普通に今の日本のことか、と思って読んでいたけど、「石油の利権を守るために、国防軍が三千人も行ってる」の発言で、あ、違うのか、と気づいた。それだけ、今の日本は危ない、ということか。2年後くらいの近未来日本かもしれない。赤川作品だけに、後半になって救いのある展開にはなっていた。同日、映画「大願成就」を見たせいか、赤川次郎の源氏鶏太っぽさを強く感じた。
読了日:1月17日 著者:赤川次郎
http://bookmeter.com/cmt/61726953
■おちゃめな老後
明るく、可愛く、自分らしく。田村セツコさんは手塚治虫記念館での松本かつぢトークショーでお話を聞きしたことがある。それまでもイラストに魅力は感じていたものの、人間性にぞっこんほれてしまった。介護のことや、仕事のこと、だまされたことや、彼女が日々実践してきたことをあれこれと書いており、は~、友達になりたい!と願うまでになった。彼女は死んだら葬式も戒名もいらず、死体は献体したい、と思っているそうだ。さっぱりしてる!
読了日:1月14日 著者:田村セツコ
http://bookmeter.com/cmt/61656879
■AQUIRAX CONTACT ぼくが誘惑された表現者たち
桑原弘明、山本じん、恋月姫、櫻田宗久、金子國義、四谷シモン、はまぐちさくらこ、松井冬子、山田勇男、天野天街、やまだないと等など、宇野亞喜良が選びコンタクトした表現者を集めてある。ほとんどの作家との対話も収録されている。新しい現代美術の面白いところを見せてくれる愉しさが味わえた。
読了日:1月9日 著者:
http://bookmeter.com/cmt/61549955
■現代版 判じ絵本 ピースフル
表紙絵は、Pの形の古い椅子が描かれていて「P椅子古」=ピースフル。こういう前向きな言葉ばかりが、絵解きのために構成された突拍子もないイラストで表現される本。すぐに解けるものもあり、時間をかけても正解にたどりつかなかったものもあった。人間ピラミッドのおしりを登る絵では、正解は「団結」なのだが、てっきり「しりあがり」だと思ったり、駅で天狗とサイがいる絵は正解が「エキサイティング」で、僕は「天才」だと思ってしまい、もう一歩突っ込めばよかった、と思ったり。随分と楽しめた。
読了日:1月7日 著者:倉本美津留
http://bookmeter.com/cmt/61520274
■フラッシュ
「フラッシュ」は水洗トイレでジャーッと、日の入りの緑の光線(閃光)を意味している。カジノ船が汚水を垂れ流していて、魚やウミガメの生態、海水浴も妨げられていることについて、なんとか告発してやめさせようとする冒険譚。船を沈めて妨害しようとした父は逮捕され、その息子が妹や謎の老海賊などの助けを借りながら、「ロイヤルフラッシュ作戦」でとっちめようとする。魚釣り好きなハイアセンらしい作品で、またミステリー的要素もあった。
読了日:1月6日 著者:カールハイアセン
http://bookmeter.com/cmt/61520201
■ダ・ヴィンチ・コード ヴィジュアル愛蔵版
ルーブル美術館館長殺害容疑を受けたラングドン教授の逃亡劇をベースに、館長の残したダイイングメッセージと仕掛けた暗号の解読、聖杯伝説の謎、シオン修道会、テンプル騎士団のからむ事件の裏で糸をひく「導師」の正体、そして事件の全貌、と、えんえんと謎解きが繰り広げられる興奮の長編だった。クライマックスあたりのパスワード解読は肩すかしなほどにわかりやすく(僕でもわかったくらい)、そういうところが読みやすさにもつながっているのかな、と思った。この小説を映画化したくなる気持ちもよくわかる。
読了日:1月5日 著者:ダン・ブラウン
http://bookmeter.com/cmt/61449463
■おまえたちは狂人か (シュルレアリスムの本棚)
2017年最初の読了本はこれ。主人公ヴァガラム(もの悲しい気持ち、という意味)が、名を変え姿を変える女性と関わりをもちながらの日々を描く。万能薬がわりの苦行僧とか、左右で老若をあわせもつ女性とか蚤のサーカスとか占いとかいろいろあって、性研究所美術館に行ったり、服装倒錯のパーティに参加したりする。ジャック・スミスの「燃え上がる生物」を思い浮かべた。邦題の候補として「アホちゃうか?」というのもあったそうな。横山ホットブラザーズみたいな「おまえは↑ア↓ホ↑か↓」でもいいかな。
読了日:1月3日 著者:ルネ・クルヴェル
http://bookmeter.com/cmt/61403525
▼読書メーター
http://bookmeter.com/
読んだ本の数:12冊
読んだページ数:2927ページ
ナイス数:77ナイス
http://bookmeter.com/u/479013/matome?invite_id=479013
■みんなの怪盗ルパン
少年探偵団シリーズだけでなく、ルパンもシリーズに入った!この調子で、みんなの偕成社ジュニア探偵小説シリーズも出てほしい。このルパンの巻では、新たなルパンの活躍と言うより、ルパンをいかに活用するかに作家さんが頭をひねった感じ。
読了日:1月29日 著者:小林泰三,近藤史恵,藤野恵美,真山仁,湊かなえ
http://bookmeter.com/cmt/62056647
■ゴブリン・マーケット
ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの妹、クリスティナが書いた物語に、ローセンス・ハウスマンが挿絵をつけた。アーサー・ラッカム、マーガレット・タラントによる挿絵も収録。あとのふたりのゴブリンが人間っぽいのに対して、ローレンス・ハウスマンのゴブリンは、さながら山のクトゥルフとでも言えそうな感じ。「G」と略したくなるおぞましさ。ストーリーは、食べてはいけないものを食べてしまい禁断症状で衰える妹をしっかりものの姉が救うというもの。自らゴブリンの中に飛び込んで、悪い果実は食べずに、体についた果汁を妹に届ける。自制心!
読了日:1月26日 著者:クリスティナ・ロセッティ
http://bookmeter.com/cmt/61938041
■ふしぎなエレベーター
佐々木マキの絵。エレベーターについていた見たことのない「Z」のボタンを押したら、ロボットの国に到着した!ロボットの国では電車乗るにもわれ先にと押し合いへしあいで、学校では1回答を間違えたら立ち直れないダメージを受けてしまう。人間の競争社会が極端になった世界なのだが、そんな世界にもう半分なっているんじゃないのか、とか思えた。ロボットなのにヒゲがはえている顔が面白い。
読了日:1月26日 著者:わたりむつこわたりむつこ
http://bookmeter.com/cmt/61937275
■菅野結以 (C)かんの
FMの「デヴィッド・ボウイ三昧」に出ていて気になった彼女の本を読んでみた。ファッション、スキンケア、メイク、ヘア、ネイル、映画、音楽、本、食べ物、趣味、Q&Aにインタビュー、それらに関連した彼女のブログ記事、写真など、2010年に出た本だが、彼女のことをひととおりおさらいできるように構成されていた。551のシュウマイが好きだとか、ダイエットのためにやってた岩盤浴やホットヨガ、ジムなどをやめてストレスなくしたらストンとやせられた、とか、親近感がわいたり、参考になることが詰まっていた。もっと知りたくなった。
読了日:1月21日 著者:菅野結以
http://bookmeter.com/cmt/61811829
■おちゃめな生活:あなたの魔法力を磨く法
『おちゃめな老後』と重複する内容もあるが、電車の中とかで読んでいると、まるで田村セツコさんとおしゃべりしながら乗っているような気分になれた。すごく気が楽になれて、ポジティブになれる本。グラフィック・デザイナー里見宗次氏の「簡単、簡単、3日でひと仕事」という言葉は見習いたい。
読了日:1月20日 著者:田村セツコ
http://bookmeter.com/cmt/61784160
■東京零年
徹底した警察国家になってしまった日本が舞台。事件の真相を追ううちに、敵の強大さと得体の知れなさが恐怖を呼ぶ。反権力の思想は監視のもとつぶされていく。最初は普通に今の日本のことか、と思って読んでいたけど、「石油の利権を守るために、国防軍が三千人も行ってる」の発言で、あ、違うのか、と気づいた。それだけ、今の日本は危ない、ということか。2年後くらいの近未来日本かもしれない。赤川作品だけに、後半になって救いのある展開にはなっていた。同日、映画「大願成就」を見たせいか、赤川次郎の源氏鶏太っぽさを強く感じた。
読了日:1月17日 著者:赤川次郎
http://bookmeter.com/cmt/61726953
■おちゃめな老後
明るく、可愛く、自分らしく。田村セツコさんは手塚治虫記念館での松本かつぢトークショーでお話を聞きしたことがある。それまでもイラストに魅力は感じていたものの、人間性にぞっこんほれてしまった。介護のことや、仕事のこと、だまされたことや、彼女が日々実践してきたことをあれこれと書いており、は~、友達になりたい!と願うまでになった。彼女は死んだら葬式も戒名もいらず、死体は献体したい、と思っているそうだ。さっぱりしてる!
読了日:1月14日 著者:田村セツコ
http://bookmeter.com/cmt/61656879
■AQUIRAX CONTACT ぼくが誘惑された表現者たち
桑原弘明、山本じん、恋月姫、櫻田宗久、金子國義、四谷シモン、はまぐちさくらこ、松井冬子、山田勇男、天野天街、やまだないと等など、宇野亞喜良が選びコンタクトした表現者を集めてある。ほとんどの作家との対話も収録されている。新しい現代美術の面白いところを見せてくれる愉しさが味わえた。
読了日:1月9日 著者:
http://bookmeter.com/cmt/61549955
■現代版 判じ絵本 ピースフル
表紙絵は、Pの形の古い椅子が描かれていて「P椅子古」=ピースフル。こういう前向きな言葉ばかりが、絵解きのために構成された突拍子もないイラストで表現される本。すぐに解けるものもあり、時間をかけても正解にたどりつかなかったものもあった。人間ピラミッドのおしりを登る絵では、正解は「団結」なのだが、てっきり「しりあがり」だと思ったり、駅で天狗とサイがいる絵は正解が「エキサイティング」で、僕は「天才」だと思ってしまい、もう一歩突っ込めばよかった、と思ったり。随分と楽しめた。
読了日:1月7日 著者:倉本美津留
http://bookmeter.com/cmt/61520274
■フラッシュ
「フラッシュ」は水洗トイレでジャーッと、日の入りの緑の光線(閃光)を意味している。カジノ船が汚水を垂れ流していて、魚やウミガメの生態、海水浴も妨げられていることについて、なんとか告発してやめさせようとする冒険譚。船を沈めて妨害しようとした父は逮捕され、その息子が妹や謎の老海賊などの助けを借りながら、「ロイヤルフラッシュ作戦」でとっちめようとする。魚釣り好きなハイアセンらしい作品で、またミステリー的要素もあった。
読了日:1月6日 著者:カールハイアセン
http://bookmeter.com/cmt/61520201
■ダ・ヴィンチ・コード ヴィジュアル愛蔵版
ルーブル美術館館長殺害容疑を受けたラングドン教授の逃亡劇をベースに、館長の残したダイイングメッセージと仕掛けた暗号の解読、聖杯伝説の謎、シオン修道会、テンプル騎士団のからむ事件の裏で糸をひく「導師」の正体、そして事件の全貌、と、えんえんと謎解きが繰り広げられる興奮の長編だった。クライマックスあたりのパスワード解読は肩すかしなほどにわかりやすく(僕でもわかったくらい)、そういうところが読みやすさにもつながっているのかな、と思った。この小説を映画化したくなる気持ちもよくわかる。
読了日:1月5日 著者:ダン・ブラウン
http://bookmeter.com/cmt/61449463
■おまえたちは狂人か (シュルレアリスムの本棚)
2017年最初の読了本はこれ。主人公ヴァガラム(もの悲しい気持ち、という意味)が、名を変え姿を変える女性と関わりをもちながらの日々を描く。万能薬がわりの苦行僧とか、左右で老若をあわせもつ女性とか蚤のサーカスとか占いとかいろいろあって、性研究所美術館に行ったり、服装倒錯のパーティに参加したりする。ジャック・スミスの「燃え上がる生物」を思い浮かべた。邦題の候補として「アホちゃうか?」というのもあったそうな。横山ホットブラザーズみたいな「おまえは↑ア↓ホ↑か↓」でもいいかな。
読了日:1月3日 著者:ルネ・クルヴェル
http://bookmeter.com/cmt/61403525
▼読書メーター
http://bookmeter.com/
『シャーロック・ホームズ&イレギュラーズ1消されたサーカスの男』
2014年5月24日 読書
T・マック&M・シトリンの『シャーロック・ホームズ&イレギュラーズ1消されたサーカスの男』を読んだ。
ロバート・ニューマンのシリーズでウィギンズの妹「スクリーマー」がいい味出してるように、このシリーズでは、占い師の娘「パイラー」がいい味を出している。つまりは、コナン・ドイルの本家の作品には魅力的な少女は出てこなかったことの反動というか、どんな魅力的な少女を配することが出来るかが作家の腕の見せ所なのかもしれない。
とくに、この「イレギュラーズ」のシリーズは、ウィギンズがフェレットのシャーリーを飼っていたり、縫い物が得意な「スティッチ」がいたり、と、キャラクターに重きを置いているようだった。
以下、目次
第1章 ザリンダ・ブラザーズ、謎の転落死
第2章 重要な客、ホームズを訪ねる
第3章 キャッスルのパーティ
第4章 ベイカーストリートの話しあい
第5章 イレギュラーズ、バルボザ大サーカスに到着
第6章 サーカスでのききこみ
第7章 ウィギンズ、凶器を発見
第8章 暴かれた殺人
第9章 イレギュラーズ、パイラーにあう
第10章 パイラーVSカーロフ
第11章 オジーVSインディゴ・ジョーンズ
第12章 パイラーの活躍
第13章 イレギュラーズ、ベイカーストリートへもどる
第14章 スチュアート・クロニクル
第15章 代書屋のオジー
第16章 エリオット、手術をする
第17章 もどってきたパイラー
第18章 イレギュラーズ、埠頭に到着
第19章 埠頭での張りこみ
第20章 みしらぬ男
第21章 対決
第22章 ホームズと、イレギュラーズと、スコットランドヤード
第23章 イレギュラーズ、馬車で家にもどる
第24章 代書屋を訪ねてきた謎の男
第25章 ウィギンズとパイラー、ホームズを訪ねる
第26章 オジー救出作戦
第27章 オジーの証言
ロバート・ニューマンのシリーズでウィギンズの妹「スクリーマー」がいい味出してるように、このシリーズでは、占い師の娘「パイラー」がいい味を出している。つまりは、コナン・ドイルの本家の作品には魅力的な少女は出てこなかったことの反動というか、どんな魅力的な少女を配することが出来るかが作家の腕の見せ所なのかもしれない。
とくに、この「イレギュラーズ」のシリーズは、ウィギンズがフェレットのシャーリーを飼っていたり、縫い物が得意な「スティッチ」がいたり、と、キャラクターに重きを置いているようだった。
以下、目次
第1章 ザリンダ・ブラザーズ、謎の転落死
第2章 重要な客、ホームズを訪ねる
第3章 キャッスルのパーティ
第4章 ベイカーストリートの話しあい
第5章 イレギュラーズ、バルボザ大サーカスに到着
第6章 サーカスでのききこみ
第7章 ウィギンズ、凶器を発見
第8章 暴かれた殺人
第9章 イレギュラーズ、パイラーにあう
第10章 パイラーVSカーロフ
第11章 オジーVSインディゴ・ジョーンズ
第12章 パイラーの活躍
第13章 イレギュラーズ、ベイカーストリートへもどる
第14章 スチュアート・クロニクル
第15章 代書屋のオジー
第16章 エリオット、手術をする
第17章 もどってきたパイラー
第18章 イレギュラーズ、埠頭に到着
第19章 埠頭での張りこみ
第20章 みしらぬ男
第21章 対決
第22章 ホームズと、イレギュラーズと、スコットランドヤード
第23章 イレギュラーズ、馬車で家にもどる
第24章 代書屋を訪ねてきた謎の男
第25章 ウィギンズとパイラー、ホームズを訪ねる
第26章 オジー救出作戦
第27章 オジーの証言
『ホームズ少年探偵団』
2014年5月23日 読書
ロバート・ニューマンの『ホームズ少年探偵団』を読んだ。
ベイカー街イレギュラーズの活躍を描くシリーズ。他のシリーズでは、名探偵ホームズの手助けをする、というより、ホームズが役立たずの状態にあって、少年たちが事件を解決する、みたいな展開が多くて、「ほんとに、この作者、ホームズが好きなんだろうか」と疑問に思うケースが多い。しかし、このロバート・ニューマンの作品は、ちゃんとホームズの事件簿の1つのエピソードとして語るに足る、まっとうなパスティーシュになっていた。
コナン・ドイルのホームズものの雰囲気を壊していないのがいい。
主人公は、アンドリュー・クレイギーという少年。
イレギュラーズのなかで名前が明らかになっているウィギンズも出てくるが、このシリーズでは、ウィギンズよりも、その妹セーラが活躍する。セーラは「スクリーマー」とニックネームがついていて、彼女が叫ぶと、それはもう、少年ジェットのミラクルボイスみたいに、悪党どももダメージを受けてしまうのだ。
以下、目次。
1.ベーカー街を歩く
2.スクリーマー
3.エンパイアクラブの大騒動
4.ひとりぼっち、ロンドンに
5.また、スクリーマーと
6.貴族のあとつぎ
7.さらにふたつの事件が、ホームズに
8.盲目のベン
9.またあらわれた“ひしゃげ鼻”
10.聴診器
11.爆弾処理班
12.ホームズのふしぎな忠告と、おかしな行動
13.霧の中の追跡
14.闇の中の男
15.なぞとき
16.最後のつめ
ベイカー街イレギュラーズの活躍を描くシリーズ。他のシリーズでは、名探偵ホームズの手助けをする、というより、ホームズが役立たずの状態にあって、少年たちが事件を解決する、みたいな展開が多くて、「ほんとに、この作者、ホームズが好きなんだろうか」と疑問に思うケースが多い。しかし、このロバート・ニューマンの作品は、ちゃんとホームズの事件簿の1つのエピソードとして語るに足る、まっとうなパスティーシュになっていた。
コナン・ドイルのホームズものの雰囲気を壊していないのがいい。
主人公は、アンドリュー・クレイギーという少年。
イレギュラーズのなかで名前が明らかになっているウィギンズも出てくるが、このシリーズでは、ウィギンズよりも、その妹セーラが活躍する。セーラは「スクリーマー」とニックネームがついていて、彼女が叫ぶと、それはもう、少年ジェットのミラクルボイスみたいに、悪党どももダメージを受けてしまうのだ。
以下、目次。
1.ベーカー街を歩く
2.スクリーマー
3.エンパイアクラブの大騒動
4.ひとりぼっち、ロンドンに
5.また、スクリーマーと
6.貴族のあとつぎ
7.さらにふたつの事件が、ホームズに
8.盲目のベン
9.またあらわれた“ひしゃげ鼻”
10.聴診器
11.爆弾処理班
12.ホームズのふしぎな忠告と、おかしな行動
13.霧の中の追跡
14.闇の中の男
15.なぞとき
16.最後のつめ
『僕の妹は漢字が読める』
2014年5月22日 読書
かじいたかしの『僕の妹は漢字が読める』を読んだ。
大傑作!
23世紀の日本では、ほとんどの人が漢字を読めない世界になっていた。
主人公の少年も、もちろん漢字がまったく読めないが、妹はちょっと変わり者で漢字を勉強していて、普通に読めるのである。
また、この23世紀では、政治、教育、文学の世界などで、二次元と萌えが「普通」になっている。
そんな23世紀の兄妹が、21世紀にタイムスリップして巻き起こす騒動。
と、いうから、一応SFみたいなのだが、最後まで、「SF」を意識せずに読めた。
なかでも、作中引用される未来の正統派文学、オオダイラ・ガイの作品にはぶっとんだ。
これは、フィネガンズ・ウェイクもウリポも及ばない、最強の言語遊戯前衛文学ではないのか!?
以下、目次。
21世紀のみなさまへ
第1章 先生の文学
第2章 へいせいてん
第3章 きたいと現実
第4章 おにいちゃんのあかちゃんうみたい
第5章 物語は時代を超える
あとがき
大傑作!
23世紀の日本では、ほとんどの人が漢字を読めない世界になっていた。
主人公の少年も、もちろん漢字がまったく読めないが、妹はちょっと変わり者で漢字を勉強していて、普通に読めるのである。
また、この23世紀では、政治、教育、文学の世界などで、二次元と萌えが「普通」になっている。
そんな23世紀の兄妹が、21世紀にタイムスリップして巻き起こす騒動。
と、いうから、一応SFみたいなのだが、最後まで、「SF」を意識せずに読めた。
なかでも、作中引用される未来の正統派文学、オオダイラ・ガイの作品にはぶっとんだ。
これは、フィネガンズ・ウェイクもウリポも及ばない、最強の言語遊戯前衛文学ではないのか!?
以下、目次。
21世紀のみなさまへ
第1章 先生の文学
第2章 へいせいてん
第3章 きたいと現実
第4章 おにいちゃんのあかちゃんうみたい
第5章 物語は時代を超える
あとがき
小林雄次の『ウルトラマン妹』を読んだ。
円谷プロダクション監修で、著者はウルトラシリーズで脚本も書いている人、というわけで、公認バリバリ。
内容はというと、ウルトラシリーズの知識をときどきはさみながらの、わりとまっとうなライトノベルになっていた。妹がウルトラマン(妹なのに「マン」、というツッコミは作中、何度も行われる)になってしまう、というもので、当然、見習いウルトラマンのドジっこ展開が待っているのである。
ウルトラシリーズファン必読、とは、全く思わないけど、さらっと読むには面白かった。
以下、目次。
プロローグ
第1章 私、ウルトラマンになっちゃった!
第2章 光れ!ジャンヌ・スパーク!
第3章 新たなる女ウルトラ戦士
第4章 接吻遭遇
第5章 飛べ!ジャンヌ・スラッシュ!
第6章 月島翔太を抹殺せよ
第7章 変貌
第8章 ああ!隊長!
エピローグ
ウルトラマン妹の歌
あとがき
円谷プロダクション監修で、著者はウルトラシリーズで脚本も書いている人、というわけで、公認バリバリ。
内容はというと、ウルトラシリーズの知識をときどきはさみながらの、わりとまっとうなライトノベルになっていた。妹がウルトラマン(妹なのに「マン」、というツッコミは作中、何度も行われる)になってしまう、というもので、当然、見習いウルトラマンのドジっこ展開が待っているのである。
ウルトラシリーズファン必読、とは、全く思わないけど、さらっと読むには面白かった。
以下、目次。
プロローグ
第1章 私、ウルトラマンになっちゃった!
第2章 光れ!ジャンヌ・スパーク!
第3章 新たなる女ウルトラ戦士
第4章 接吻遭遇
第5章 飛べ!ジャンヌ・スラッシュ!
第6章 月島翔太を抹殺せよ
第7章 変貌
第8章 ああ!隊長!
エピローグ
ウルトラマン妹の歌
あとがき
『探偵作家発見100』
2014年5月15日 読書
若狭邦男の、知られざる探偵小説作家本、第3弾。
この本の目次をそのまま使った「探偵小説全集」みたいなものを読んでみたい。
ほとんどカタログで、雑感が加えられた、という体裁ではあるが、こういう本が他にないので、貴重。
今回、一番気になったのは、「蘭妖子」
僕はこの蘭妖子の作品は読んだことないのだが、天井桟敷に同名の女優がいるので、命名が本人なのか寺山修司なのか、ちょっと知らないけど、この探偵作家の「蘭妖子」と関連があったのかどうか、非常に気になるところ。
後に、時間があれば、目次も紹介。
この本の目次をそのまま使った「探偵小説全集」みたいなものを読んでみたい。
ほとんどカタログで、雑感が加えられた、という体裁ではあるが、こういう本が他にないので、貴重。
今回、一番気になったのは、「蘭妖子」
僕はこの蘭妖子の作品は読んだことないのだが、天井桟敷に同名の女優がいるので、命名が本人なのか寺山修司なのか、ちょっと知らないけど、この探偵作家の「蘭妖子」と関連があったのかどうか、非常に気になるところ。
後に、時間があれば、目次も紹介。
『ファンタジスタドール・イヴ』
2014年5月6日 読書なんというか、CGゲーム初期のような、ノスタルジーを感じさせる。
作風も、あえてノスタルジックなものを意識しているようで、海野十三とか、乱歩を思い出した。
作風も、あえてノスタルジックなものを意識しているようで、海野十三とか、乱歩を思い出した。
大念佛寺に行って、「万部おねり」を見てきた。
菩薩の面と衣装で、本堂のまわりの来迎橋を渡って、本堂に入る「入御(にゅうぎょ)」だけを見た。
二十五菩薩(僧侶が菩薩に扮装している)が、それぞれ持物をもって、歩く。
いわば、ブッキョリカル・パレードか。
おねりは午後1時からはじまり、菩薩の登場は午後2時頃。
僕がみた「入御」の後は、本堂内で法要があり、もとの橋を使って帰っていく還御(かんぎょ)が続く。
この法要は5月5日まで行われるが、明日3日には、午前10時30分から仏教讃歌奉納、11時から融通声明コンサートがあるので、それも気になるところ。
今日はゴールデンウィーク中の平日だったので、余裕で見ることができたけど、明日からは人がいっぱいになるかも。
http://www.dainenbutsuji.com/oneri/
なんばの高島屋7階グランドホールで、「円谷英二 特撮の軌跡展」を見てきた。
時代劇時代から、怪獣映画、ウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブン。
怪獣多数、映像多数、特撮技術あれこれ、ジオラマ多数、当時の玩具や文具、雑誌など資料多数、シナリオや原稿等資料多数。
音声ガイドで、スタッフやキャストの方々の思い出話、裏話も聞いた。
1/8計画で、石膏で作った受話器が本番で壊れたとか、ウルトラセブンの変身メガネ(ウルトラアイ)の素材が弱くてよく割れたとか。
そうそう。今さらな話、ウルトラセブンの額から出る光線、額に両手で「ちぃ~す」ってやって出すときと、胸に手をあてて「これがギリギリ」ってやるときとで、名称は違うんだろうか。ウルトラセブンは、僕には難しすぎて、子どものときにはリアルタイムで熱中しなかったので、後追いなのである。https://www.takashimaya.co.jp/store/special/event/tsuburaya.html
高島屋で、「Smile 浅田真央23年の軌跡」を開催してたので、見てきた。
幼い頃の写真から、大会での衣装、メダルを多数展示。
つい最近のあの涙のフリー演技の上映など。(実は、これ、ちゃんと見たの今日がはじめてだったので、もらい泣きしそうになって困った。冷静に見れば、これが最高の演技だと喜ぶよりも、浅田真央なら、もっと上を目指せるんじゃないか、と思ったけど)
ジュニアのときの衣装がリアルで小さいのは当たり前ながら、浅田真央もちゃんと成長しているんだな、と実感させられた。
会場出たところには、浅田真央がらみの商品を宣伝するブースが山ほど並んでいた。
円谷英二の展示見た直後だったので、まるで浅田真央もウルトラヒーローの一員であるかのような錯覚を覚えた。ウルトラマオ。http://www.takashimaya.co.jp/store/special/event/asada.html
菩薩の面と衣装で、本堂のまわりの来迎橋を渡って、本堂に入る「入御(にゅうぎょ)」だけを見た。
二十五菩薩(僧侶が菩薩に扮装している)が、それぞれ持物をもって、歩く。
いわば、ブッキョリカル・パレードか。
おねりは午後1時からはじまり、菩薩の登場は午後2時頃。
僕がみた「入御」の後は、本堂内で法要があり、もとの橋を使って帰っていく還御(かんぎょ)が続く。
この法要は5月5日まで行われるが、明日3日には、午前10時30分から仏教讃歌奉納、11時から融通声明コンサートがあるので、それも気になるところ。
今日はゴールデンウィーク中の平日だったので、余裕で見ることができたけど、明日からは人がいっぱいになるかも。
http://www.dainenbutsuji.com/oneri/
なんばの高島屋7階グランドホールで、「円谷英二 特撮の軌跡展」を見てきた。
時代劇時代から、怪獣映画、ウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブン。
怪獣多数、映像多数、特撮技術あれこれ、ジオラマ多数、当時の玩具や文具、雑誌など資料多数、シナリオや原稿等資料多数。
音声ガイドで、スタッフやキャストの方々の思い出話、裏話も聞いた。
1/8計画で、石膏で作った受話器が本番で壊れたとか、ウルトラセブンの変身メガネ(ウルトラアイ)の素材が弱くてよく割れたとか。
そうそう。今さらな話、ウルトラセブンの額から出る光線、額に両手で「ちぃ~す」ってやって出すときと、胸に手をあてて「これがギリギリ」ってやるときとで、名称は違うんだろうか。ウルトラセブンは、僕には難しすぎて、子どものときにはリアルタイムで熱中しなかったので、後追いなのである。https://www.takashimaya.co.jp/store/special/event/tsuburaya.html
高島屋で、「Smile 浅田真央23年の軌跡」を開催してたので、見てきた。
幼い頃の写真から、大会での衣装、メダルを多数展示。
つい最近のあの涙のフリー演技の上映など。(実は、これ、ちゃんと見たの今日がはじめてだったので、もらい泣きしそうになって困った。冷静に見れば、これが最高の演技だと喜ぶよりも、浅田真央なら、もっと上を目指せるんじゃないか、と思ったけど)
ジュニアのときの衣装がリアルで小さいのは当たり前ながら、浅田真央もちゃんと成長しているんだな、と実感させられた。
会場出たところには、浅田真央がらみの商品を宣伝するブースが山ほど並んでいた。
円谷英二の展示見た直後だったので、まるで浅田真央もウルトラヒーローの一員であるかのような錯覚を覚えた。ウルトラマオ。http://www.takashimaya.co.jp/store/special/event/asada.html
『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
2014年4月22日 読書村上春樹訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読んだ。
前回は野崎訳を読んで気になった箇所を村上訳とつきあわせてみたけど、今回は逆に、村上訳を読んでて気になったところを、野崎訳と比べてみた。
1
「クレイジーな大砲」(村上)
「イカレタ大砲」(野崎)
2
「僕はこの『風格ある』という言葉が何よりもきらいなんだ」(村上)
「『りっぱ』か!これこそ僕のきらいな言葉なんだ」(野崎)
2
「僕に向かってしょっちゅう『あーむ』と呼びかけるのはやめてくれないかなと真剣に思った」(村上)
「そう言いながら、僕は、さっきから僕を『坊や』といってるその呼び方をやめてもらいたくてたまんなかった」(野崎)
3
「『オーケー』と僕は言った。アックリーが自分の部屋に引きあげたからといって、君の胸が痛んだりするようなことはありえない」(村上)
「『ああ』と、僕は言った。べつに部屋へ帰られたからって、こっちががっかりするような相手じゃないからな、奴さん」(野崎)
6
「お前はとことん鈍くさい、蓮根なみの間抜けだ」(村上)
「おめえは全くきたねえ低能の間抜け野郎だ」(野崎)
10
「やれやれ。なんにもわかっちゃいないんだよな」(村上)
「それだけの頭しかないんだよ」(野崎)
10
「たとえば便所のことを『リトル・ガールズ・ルーム』と呼ぶとかね」(村上)
「でも、トイレのことを『おトイレ』なんて言ったりして、」(野崎)
12
「まっしぐらにすさまじいところだ」(村上)
「すごいんだ」(野崎)
12
「おそれいるじゃないか」(村上)
「たいしたもんさ」(野崎)
12
「グレイのフランネルのスーツに、例のおかまっぽい感じのタッターソールのベスト」(村上)
「グレーのフラノのスーツに、小意気なタタサルのヴェスト」(野崎)
12
「なんだか自分が間抜けの親玉になったような気がしてきた」(村上)
「次第にいらいらして落ちつかなくなってきた」(野崎)
13
「青天の霹靂というか」(村上)
「藪から棒に」(野崎)
13
「ちょいの間でいいよ」(村上)
「一回でいい」(野崎)
13
「ふつうの娼婦ならたぶん『よく言うよ』とか『冗談よしな』とか言うところだよね。『へへへだね』なんて言うもんか」(村上)
「売春婦やなんかだったらね、『笑わせないでよ』とか『でたらめはよしてよ』とか言いそうなもんじゃないか。それを『嘘ばっかし』って言うんだからな」(野崎)
え~っと、ここまでが前半で、後半もいろいろあったけど、メモがどこかに行ってしまったので、割愛。またメモが見つかったら追記します。
『サリンジャー戦記』読んだあとだったので、フィービーがホールデンを呼ぶ「あなた」についても注意して読んだ。
25
「あなたはあなたで好きなことをすればいいじゃない」(村上)
「兄さんはやりたいようにやったらいいわ」(野崎)
25
「あなたは乗らないの?」(村上)
「兄さんも乗らない?」(野崎)
25
「あなたのことをもうべつに怒ってないんだよ」(村上)
「あたし、もう兄さんのことおこってないのよ」(野崎)
あと、ホールデンの風貌を憶測する手掛かりとして、13章で娼婦がホールデンに向けて言う言葉がある。
「あんた、映画に出てた男にそっくりだわ」
「知らないはずないわ。メルヴィン・ダグラスといっしょにあの映画に出てた男よ。メルヴィン・ダグラスの弟になるの。ボートから落っこちるあの男よ」(野崎訳)
メルヴィン・ダグラスの出ている映画で、船から落ちるシーン、といえば、「我は海の子」のフレディー・バーソロミューかな、それだと、若造と見抜かれるホールデンっぽいな、と思ったけど、メルヴィン・ダグラスの弟役ではなかったと思うし、どうなのかな。
ただ、村上訳では「メルヴィン・ダグラス」が「メル=ヴァイン・ダグラス」表記だったと思う。娼婦のあいまいな記憶だから、とりあえずは、フレディー・バーソロミューを思い浮かべながらその後を読んだのだった。
本文は村上訳、野崎訳、どちらの方がいい、ということもなかったけど、タイトルは、断然「ライ麦畑でつかまえて」がいい、と思った。
前回は野崎訳を読んで気になった箇所を村上訳とつきあわせてみたけど、今回は逆に、村上訳を読んでて気になったところを、野崎訳と比べてみた。
1
「クレイジーな大砲」(村上)
「イカレタ大砲」(野崎)
2
「僕はこの『風格ある』という言葉が何よりもきらいなんだ」(村上)
「『りっぱ』か!これこそ僕のきらいな言葉なんだ」(野崎)
2
「僕に向かってしょっちゅう『あーむ』と呼びかけるのはやめてくれないかなと真剣に思った」(村上)
「そう言いながら、僕は、さっきから僕を『坊や』といってるその呼び方をやめてもらいたくてたまんなかった」(野崎)
3
「『オーケー』と僕は言った。アックリーが自分の部屋に引きあげたからといって、君の胸が痛んだりするようなことはありえない」(村上)
「『ああ』と、僕は言った。べつに部屋へ帰られたからって、こっちががっかりするような相手じゃないからな、奴さん」(野崎)
6
「お前はとことん鈍くさい、蓮根なみの間抜けだ」(村上)
「おめえは全くきたねえ低能の間抜け野郎だ」(野崎)
10
「やれやれ。なんにもわかっちゃいないんだよな」(村上)
「それだけの頭しかないんだよ」(野崎)
10
「たとえば便所のことを『リトル・ガールズ・ルーム』と呼ぶとかね」(村上)
「でも、トイレのことを『おトイレ』なんて言ったりして、」(野崎)
12
「まっしぐらにすさまじいところだ」(村上)
「すごいんだ」(野崎)
12
「おそれいるじゃないか」(村上)
「たいしたもんさ」(野崎)
12
「グレイのフランネルのスーツに、例のおかまっぽい感じのタッターソールのベスト」(村上)
「グレーのフラノのスーツに、小意気なタタサルのヴェスト」(野崎)
12
「なんだか自分が間抜けの親玉になったような気がしてきた」(村上)
「次第にいらいらして落ちつかなくなってきた」(野崎)
13
「青天の霹靂というか」(村上)
「藪から棒に」(野崎)
13
「ちょいの間でいいよ」(村上)
「一回でいい」(野崎)
13
「ふつうの娼婦ならたぶん『よく言うよ』とか『冗談よしな』とか言うところだよね。『へへへだね』なんて言うもんか」(村上)
「売春婦やなんかだったらね、『笑わせないでよ』とか『でたらめはよしてよ』とか言いそうなもんじゃないか。それを『嘘ばっかし』って言うんだからな」(野崎)
え~っと、ここまでが前半で、後半もいろいろあったけど、メモがどこかに行ってしまったので、割愛。またメモが見つかったら追記します。
『サリンジャー戦記』読んだあとだったので、フィービーがホールデンを呼ぶ「あなた」についても注意して読んだ。
25
「あなたはあなたで好きなことをすればいいじゃない」(村上)
「兄さんはやりたいようにやったらいいわ」(野崎)
25
「あなたは乗らないの?」(村上)
「兄さんも乗らない?」(野崎)
25
「あなたのことをもうべつに怒ってないんだよ」(村上)
「あたし、もう兄さんのことおこってないのよ」(野崎)
あと、ホールデンの風貌を憶測する手掛かりとして、13章で娼婦がホールデンに向けて言う言葉がある。
「あんた、映画に出てた男にそっくりだわ」
「知らないはずないわ。メルヴィン・ダグラスといっしょにあの映画に出てた男よ。メルヴィン・ダグラスの弟になるの。ボートから落っこちるあの男よ」(野崎訳)
メルヴィン・ダグラスの出ている映画で、船から落ちるシーン、といえば、「我は海の子」のフレディー・バーソロミューかな、それだと、若造と見抜かれるホールデンっぽいな、と思ったけど、メルヴィン・ダグラスの弟役ではなかったと思うし、どうなのかな。
ただ、村上訳では「メルヴィン・ダグラス」が「メル=ヴァイン・ダグラス」表記だったと思う。娼婦のあいまいな記憶だから、とりあえずは、フレディー・バーソロミューを思い浮かべながらその後を読んだのだった。
本文は村上訳、野崎訳、どちらの方がいい、ということもなかったけど、タイトルは、断然「ライ麦畑でつかまえて」がいい、と思った。