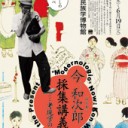毎年、コスプレとオタクでごったがえす日本橋ストリートフェスタ、今年も肌寒いなか、決行。
僕は、声優魂で松岡由貴ちゃん見たり、GMOステージで鈴木由佳ちゃん見たり、よくわからないコスプレで参加していたマック赤坂見たり、友人たちのコスプレ見たりして楽しんだ。
着想が面白かったり、質の高いコスプレ見る方がいいのは承知しながら、杜撰で、肌のケアも出来ていないコスプレ姿をついつい探してしまう。
そういう、やむにやまれぬ欲望の膿みたいなものにこそ病み付きになる悪い成分が多く含まれているような気がして。
http://nippombashi.jp/festa/2014/
ストリートフェスタの喧騒のピットインとして、大阪日本橋のアートスペース亜蛮人に行った。
キッズカンパニー 企画
特殊造形・特殊メイク展
「特殊藝術見世物小屋」
実演の1階。
2階には異形の展示。
絶対に、こいつら生きてるって思えて、展示物のすぐそばまで近寄るのに、すっごく勇気がいった。
日本橋ストリートフェスタのお祭りをいったん抜けて、人文地理学会の例会にもぐりこんできた。
テーマ:グローバル時代における「場所」―ドリーン・マッシーを迎えて―
1.グローバルな場所感覚
(グローバルな諸関係の産物として場所を考えなおす)
2.場所は意味を失うのか
(すべてはフローだという捉え方では場所の概念は意味を失う)
3.新しい場所へ
(「場所」を捨て去るのではなく、概念化しなおすべき。フローと場所は共に進んでいく)
4.自然や、人間にあらざるものの視点から場所を捉えることが有効。
ただし、人間だけでなく、自然もまた静止したものでなく、総てのものが動いている。
結論
1.場所(ローカル)はグローバルの産物/犠牲であるばかりでなく、グローバルのルーツである。
2.場所の役割に対する、応答責任の問題が生じる
3.場所に対する帰属は、応答責任との関係において展開しうる
ティーブレイクではドリーン・マッシーさんと身近に会話できる場を提供されていた。
ブレイク後の質疑応答では、日本の現状に絡めたやりとりなどがあったが、発表も含め、ほとんど全部、英語でのやりとりだったため、追いかけるのに必死だった。
とりあえず、研究者ばかりの集まりに、僕のような異質な存在をまぜてくれた人文地理学会に感謝。
http://hgsj.org/reikaibukai/reikai_no280/
ストリートフェスタの後は、なんば紅鶴で、
SOC2stROUND「コスプレ大喜利」に出演。
司会 / DJ急行、B・カシワギ
出演 / MyU☆、荻野アサミ、Bugって花井、河合カズキラングレー、藤本ぽやな、らみ、保山ひャン、不治ゲルゲ、そば2、津川まあこ、みうまっかーとにー、にしね・ザ・タイガー、七井コム斎、ともちん、ステファニー、他
http://benitsuru.net/archives/6065
イベントの趣旨からはずれるが、僕は普段着で参加した。
むちゃくちゃなこと書いて、あっさり1回戦で安定の脱落。
自分の頭ひねっていろいろ答え出すのも面白いけど、他の人の、なかなか自分では思いつかない回答見るのも面白い!
僕は、声優魂で松岡由貴ちゃん見たり、GMOステージで鈴木由佳ちゃん見たり、よくわからないコスプレで参加していたマック赤坂見たり、友人たちのコスプレ見たりして楽しんだ。
着想が面白かったり、質の高いコスプレ見る方がいいのは承知しながら、杜撰で、肌のケアも出来ていないコスプレ姿をついつい探してしまう。
そういう、やむにやまれぬ欲望の膿みたいなものにこそ病み付きになる悪い成分が多く含まれているような気がして。
http://nippombashi.jp/festa/2014/
ストリートフェスタの喧騒のピットインとして、大阪日本橋のアートスペース亜蛮人に行った。
キッズカンパニー 企画
特殊造形・特殊メイク展
「特殊藝術見世物小屋」
実演の1階。
2階には異形の展示。
絶対に、こいつら生きてるって思えて、展示物のすぐそばまで近寄るのに、すっごく勇気がいった。
日本橋ストリートフェスタのお祭りをいったん抜けて、人文地理学会の例会にもぐりこんできた。
テーマ:グローバル時代における「場所」―ドリーン・マッシーを迎えて―
1.グローバルな場所感覚
(グローバルな諸関係の産物として場所を考えなおす)
2.場所は意味を失うのか
(すべてはフローだという捉え方では場所の概念は意味を失う)
3.新しい場所へ
(「場所」を捨て去るのではなく、概念化しなおすべき。フローと場所は共に進んでいく)
4.自然や、人間にあらざるものの視点から場所を捉えることが有効。
ただし、人間だけでなく、自然もまた静止したものでなく、総てのものが動いている。
結論
1.場所(ローカル)はグローバルの産物/犠牲であるばかりでなく、グローバルのルーツである。
2.場所の役割に対する、応答責任の問題が生じる
3.場所に対する帰属は、応答責任との関係において展開しうる
ティーブレイクではドリーン・マッシーさんと身近に会話できる場を提供されていた。
ブレイク後の質疑応答では、日本の現状に絡めたやりとりなどがあったが、発表も含め、ほとんど全部、英語でのやりとりだったため、追いかけるのに必死だった。
とりあえず、研究者ばかりの集まりに、僕のような異質な存在をまぜてくれた人文地理学会に感謝。
http://hgsj.org/reikaibukai/reikai_no280/
ストリートフェスタの後は、なんば紅鶴で、
SOC2stROUND「コスプレ大喜利」に出演。
司会 / DJ急行、B・カシワギ
出演 / MyU☆、荻野アサミ、Bugって花井、河合カズキラングレー、藤本ぽやな、らみ、保山ひャン、不治ゲルゲ、そば2、津川まあこ、みうまっかーとにー、にしね・ザ・タイガー、七井コム斎、ともちん、ステファニー、他
http://benitsuru.net/archives/6065
イベントの趣旨からはずれるが、僕は普段着で参加した。
むちゃくちゃなこと書いて、あっさり1回戦で安定の脱落。
自分の頭ひねっていろいろ答え出すのも面白いけど、他の人の、なかなか自分では思いつかない回答見るのも面白い!
「南方熊楠とエコロジー」
2014年2月11日 学校・勉強関西大学で、シンポジウム「南方熊楠とエコロジー」を聞いてきた。
堺エコロジー大学の共催 。
内容としては、熊楠をエコロジーの先駆として安易に評価する最近の傾向を冷静に分析してみるものになった。
基調講演
「南方熊楠と二つのエコロジー」
講師:田村義也氏(南方熊楠顕彰会常任理事・成城大学非常勤講師)
エコロジー思想の先史として、ヘンリー・デヴィッド・ソロー、アルド・レオポルド、レイチェル・カーソンをとりあげる。
また、OED(オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー)から、19世紀から使われてきた生物学の一部門としての「エコロジー」と、近年使われるようになった、「エコ」「グリーン」としての「エコロジー」と2つあることを指摘されていた。
講演
「持続可能な南方熊楠論」
講師:安田忠典氏(関西大学人間健康学部准教授)
南方熊楠の業績をふりかえると共に、今世紀に入ってからの研究による評価を語られていた。比較説話学、文芸研究、国文学研究、欧米文学、植物病理学、それぞれの立場からの評価に共通してみられるのは、熊楠が資料を等価に扱う、いわば「読み」の不在であり、そこに問題点をみる人もあれば、また、永続的な資料収集という面から、援用可能な価値を見出す人もある。
聴講にきていた専門家の先生たちにもマイクをふって意見を聞くスタイルは新鮮だった。
実践報告
「堺市と関西大学との地域連携事業 熊野本宮子どもエコツアー」
報告者:関西大学人間健康学部 安田ゼミ3年生一同
最後に、田村氏によって、神社合祀反対運動にからめて、熊楠の時代に撮影された神社などの写真と、現在の写真を比較するスライド説明がされた。
このシンポジウムには、座席の後方に、関西大学の学生たちも聴講に多数きていたが、いかんせん、興味があって来た学生ばかりとは言えず、講演中もずっと私語がたえなかった。ゼミの取組を発表、アピールするせっかくの機会だったのに、そうした私語する女子学生によって、受けた印象といえば、「学生はダメだな」になってしまったのが、残念だ。http://www.minakata.org/cnts/news/index.cgi?c=o140123
堺エコロジー大学の共催 。
内容としては、熊楠をエコロジーの先駆として安易に評価する最近の傾向を冷静に分析してみるものになった。
基調講演
「南方熊楠と二つのエコロジー」
講師:田村義也氏(南方熊楠顕彰会常任理事・成城大学非常勤講師)
エコロジー思想の先史として、ヘンリー・デヴィッド・ソロー、アルド・レオポルド、レイチェル・カーソンをとりあげる。
また、OED(オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー)から、19世紀から使われてきた生物学の一部門としての「エコロジー」と、近年使われるようになった、「エコ」「グリーン」としての「エコロジー」と2つあることを指摘されていた。
講演
「持続可能な南方熊楠論」
講師:安田忠典氏(関西大学人間健康学部准教授)
南方熊楠の業績をふりかえると共に、今世紀に入ってからの研究による評価を語られていた。比較説話学、文芸研究、国文学研究、欧米文学、植物病理学、それぞれの立場からの評価に共通してみられるのは、熊楠が資料を等価に扱う、いわば「読み」の不在であり、そこに問題点をみる人もあれば、また、永続的な資料収集という面から、援用可能な価値を見出す人もある。
聴講にきていた専門家の先生たちにもマイクをふって意見を聞くスタイルは新鮮だった。
実践報告
「堺市と関西大学との地域連携事業 熊野本宮子どもエコツアー」
報告者:関西大学人間健康学部 安田ゼミ3年生一同
最後に、田村氏によって、神社合祀反対運動にからめて、熊楠の時代に撮影された神社などの写真と、現在の写真を比較するスライド説明がされた。
このシンポジウムには、座席の後方に、関西大学の学生たちも聴講に多数きていたが、いかんせん、興味があって来た学生ばかりとは言えず、講演中もずっと私語がたえなかった。ゼミの取組を発表、アピールするせっかくの機会だったのに、そうした私語する女子学生によって、受けた印象といえば、「学生はダメだな」になってしまったのが、残念だ。http://www.minakata.org/cnts/news/index.cgi?c=o140123
午前10時半から、I-siteなんばに行って、大阪府立大学21世紀科学研究所セミナー 森岡正博「関係の中で立ち現われてくる「いのち」ー ペルソナの哲学を構想する」を聞いてきた。
生命倫理学におけるパーソン論とはまた別のペルソナ論へのアプローチが語られた。
以下、ざっとした進行。
1、ペルソナ論の原風景
2、生命倫理学におけるパーソン概念
マイケル・トゥーリー
ピーター・シンガー
3、森岡のペルソナ論
4、ペルソナの思想史
プロソーポン=ペルソナ
ペルソナ=ヒュポスタシス
その後の展開(ボエティウス)
5、和辻哲郎のペルソナ論
6、ペルソナ論の今後
質疑応答では、普遍性と個別性の問題、非パーソン判定の問題、キリスト教の問題、ナチスの問題、などが論議された。
いのちの問題だけに、一筋縄ではいかないが、考えを深めると同時に、いろんな体験を通じてでないと見えてこないものもあるのかも、と思わされた。
http://www.osakafu-u.ac.jp/other_event/evt20131003.html
生命倫理学におけるパーソン論とはまた別のペルソナ論へのアプローチが語られた。
以下、ざっとした進行。
1、ペルソナ論の原風景
2、生命倫理学におけるパーソン概念
マイケル・トゥーリー
ピーター・シンガー
3、森岡のペルソナ論
4、ペルソナの思想史
プロソーポン=ペルソナ
ペルソナ=ヒュポスタシス
その後の展開(ボエティウス)
5、和辻哲郎のペルソナ論
6、ペルソナ論の今後
質疑応答では、普遍性と個別性の問題、非パーソン判定の問題、キリスト教の問題、ナチスの問題、などが論議された。
いのちの問題だけに、一筋縄ではいかないが、考えを深めると同時に、いろんな体験を通じてでないと見えてこないものもあるのかも、と思わされた。
http://www.osakafu-u.ac.jp/other_event/evt20131003.html
アートエリアb1で、カフェ・地域考「『さいごの色街 飛田』から考える~取材・フィールドワーク・通学・散歩~」
『さいごの色街 飛田』の著者、井上理津子さんと、フィリピン、カリンガ族のフィールドワークを行った平田隆行さんの報告を中心に行われた。飛田の面白さはよく知っていたせいか、平田さんの人食い人種(?)のフィールドワークがかなり興味深かった。
あと、大阪大学の菱田さんの大学と地域のつながりの話もあったが、飛田とフィリピンの話を聞いたあとでは、これといった感興もなかった。自分の学生時代、学校と地域は一体となっていたように思えたし。
また、建築家・浅見さんのホワイトボード芸が面白かった。
http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/2012/000351.php
今日はこのイベントに来る前に関西電力本店前に寄って、また、このイベント後は夜行バスで東京へ、というスケジュールで、疲れはそれほど感じないが、筋肉や関節がバキバキに痛かった。
『さいごの色街 飛田』の著者、井上理津子さんと、フィリピン、カリンガ族のフィールドワークを行った平田隆行さんの報告を中心に行われた。飛田の面白さはよく知っていたせいか、平田さんの人食い人種(?)のフィールドワークがかなり興味深かった。
あと、大阪大学の菱田さんの大学と地域のつながりの話もあったが、飛田とフィリピンの話を聞いたあとでは、これといった感興もなかった。自分の学生時代、学校と地域は一体となっていたように思えたし。
また、建築家・浅見さんのホワイトボード芸が面白かった。
http://www.cscd.osaka-u.ac.jp/2012/000351.php
今日はこのイベントに来る前に関西電力本店前に寄って、また、このイベント後は夜行バスで東京へ、というスケジュールで、疲れはそれほど感じないが、筋肉や関節がバキバキに痛かった。
国立民族学博物館で特別展「今和次郎 採集講義─考現学の今」を見てきた。
テーマ1 採集講義
セクション1 農村調査、民家研究の仕事
セクション2 関東大震災-都市の崩壊と再生そして考現学の誕生
セクション3 建築家、デザイナーとしての活動
セクション4 教育普及活動とドローイングのめざしたもの
テーマ2 衣装・ファッション・世相の今昔
セクション1 岡本信也・岡本靖子氏の「超日常観察記」
セクション2 「田中千代コレクション」と洋装史(テレビ番組「カーネーション」に登場した服装も展示)
テーマ3 住まいとその環境の記録・研究・再現
セクション1 「大村しげコレクション」から 町家ぐらし家財道具の一切しらべ
セクション2 世界のものしらべ(マダガスカルの家財道具一切しらべ 、ソウルスタイル・李さん一家の家財道具一切しらべ データベース)
セクション3 モンゴル・ゲルの家財道具一切しらべ
セクション4 縮尺1/10民家模型製作のための一切しらべ
中学生男子の制服のどこがすりきれているか、とか、蟻がどんな軌跡を描いて歩くか、とか、女学生の髪型とか、労働者が寝転ぶ姿とか、カフェーの女給の制服とか、一切を記録しつくそうという真剣なんだかネタなんだか疑ってしまいそうになる、情熱の記録がある。
午後5時から、立命館大学末川記念会館1階講義室で、マーティン・ジェイ講演会「“反”啓蒙の弁証法 ――過激派のスケープゴートにされたフランクフルト学派」
カストロ、エスチューリン、パトリック・ブキャナン、マイケル・ミンニチーノなどの事例から、過激派カルトの理論武装に利用されたフランクフルト学派について講演された。2011年7月にノルウェーの狂信的右翼ブレイビクが大量虐殺事件を起こした。そのブレイビクがアンドリュー・バーウィックのペンネームで記したマニフェスト「2083年ヨーロッパ独立宣言」のなかでもマーティン・ジェイの著作『弁証法的想像力』が歪んだ使われ方をしており、今回喫緊のテーマとして講演されたもののようだ。
通訳はつかず、またマーティン・ジェイの語り口は滑らか、また質疑応答も全部英語で行われたので、2時間の講演時間はみっちり中身の詰まったものになったが、いかんせん、僕自身の語学力がついていけず、とくに質疑応答でのマーティン・ジェイが回答で語らんとするニュアンスがうまく把握できたかどうかこころもとなく、それが残念。質問1つ1つに対して、膨大な回答を語ってくれていたのである。
テーマ1 採集講義
セクション1 農村調査、民家研究の仕事
セクション2 関東大震災-都市の崩壊と再生そして考現学の誕生
セクション3 建築家、デザイナーとしての活動
セクション4 教育普及活動とドローイングのめざしたもの
テーマ2 衣装・ファッション・世相の今昔
セクション1 岡本信也・岡本靖子氏の「超日常観察記」
セクション2 「田中千代コレクション」と洋装史(テレビ番組「カーネーション」に登場した服装も展示)
テーマ3 住まいとその環境の記録・研究・再現
セクション1 「大村しげコレクション」から 町家ぐらし家財道具の一切しらべ
セクション2 世界のものしらべ(マダガスカルの家財道具一切しらべ 、ソウルスタイル・李さん一家の家財道具一切しらべ データベース)
セクション3 モンゴル・ゲルの家財道具一切しらべ
セクション4 縮尺1/10民家模型製作のための一切しらべ
中学生男子の制服のどこがすりきれているか、とか、蟻がどんな軌跡を描いて歩くか、とか、女学生の髪型とか、労働者が寝転ぶ姿とか、カフェーの女給の制服とか、一切を記録しつくそうという真剣なんだかネタなんだか疑ってしまいそうになる、情熱の記録がある。
午後5時から、立命館大学末川記念会館1階講義室で、マーティン・ジェイ講演会「“反”啓蒙の弁証法 ――過激派のスケープゴートにされたフランクフルト学派」
カストロ、エスチューリン、パトリック・ブキャナン、マイケル・ミンニチーノなどの事例から、過激派カルトの理論武装に利用されたフランクフルト学派について講演された。2011年7月にノルウェーの狂信的右翼ブレイビクが大量虐殺事件を起こした。そのブレイビクがアンドリュー・バーウィックのペンネームで記したマニフェスト「2083年ヨーロッパ独立宣言」のなかでもマーティン・ジェイの著作『弁証法的想像力』が歪んだ使われ方をしており、今回喫緊のテーマとして講演されたもののようだ。
通訳はつかず、またマーティン・ジェイの語り口は滑らか、また質疑応答も全部英語で行われたので、2時間の講演時間はみっちり中身の詰まったものになったが、いかんせん、僕自身の語学力がついていけず、とくに質疑応答でのマーティン・ジェイが回答で語らんとするニュアンスがうまく把握できたかどうかこころもとなく、それが残念。質問1つ1つに対して、膨大な回答を語ってくれていたのである。
原発問題連続学習会@大阪弁護士会館
2012年4月28日 学校・勉強午後1時半から、大阪弁護士会館2階ホールで「原発問題連続学習会」最終回。
司会は康由美。
1.開会挨拶 山西美明
2.対談「マス・メディアが報道しない原発事故」
上杉隆、おしどり
3.質疑応答
4.閉会挨拶 和田重太
上杉隆(日本では元ジャーナリストの肩書き!)と、夫婦音曲漫才のおしどり、それぞれの発表と、対談。
時間が限られているせいか、駆け足でざっと報告、という感じだった。
この模様はユーストリームでも中継されていて、帰宅してから見たら、スクリーンにうつされた画像はユーストリームで見た方が見やすかった。ただ、こういうイベントは、家でインターネットで見ているのと、実際に足を運んで会場で話を聞くのとでは雲泥の差があるものだ。演劇でも演芸でもライブでも、インターネットで見るのと、会場で体験するのとでは、全然違う。こういう講演、発表の会では、インターネットで見ていると、なぜか何よりもツッコミどころを探したくなってしまう。それは、そのツッコミが正当かどうかにかかわらず、実に下品なのである。僕のような、上品が服を着て歩いているようなぼんぼんにはとうてい与することのできない境地だ。
案の定、インターネットでの反応は、批判的な書き込みが多かったように思う。批判ならまだいいが、悪口も多い。会場に集まっている人を、まるで洗脳されて詐欺にあっている狂信者たちのように書いているものもあり、そういう書き込みを見ると、インターネットで見ることの限界みたいなものを痛切に感じた。
たしかに、ツッコミたくなる気持ちがわからないではないのだが、おなじアホなら踊らにゃソンソン、なのである。
司会は康由美。
1.開会挨拶 山西美明
2.対談「マス・メディアが報道しない原発事故」
上杉隆、おしどり
3.質疑応答
4.閉会挨拶 和田重太
上杉隆(日本では元ジャーナリストの肩書き!)と、夫婦音曲漫才のおしどり、それぞれの発表と、対談。
時間が限られているせいか、駆け足でざっと報告、という感じだった。
この模様はユーストリームでも中継されていて、帰宅してから見たら、スクリーンにうつされた画像はユーストリームで見た方が見やすかった。ただ、こういうイベントは、家でインターネットで見ているのと、実際に足を運んで会場で話を聞くのとでは雲泥の差があるものだ。演劇でも演芸でもライブでも、インターネットで見るのと、会場で体験するのとでは、全然違う。こういう講演、発表の会では、インターネットで見ていると、なぜか何よりもツッコミどころを探したくなってしまう。それは、そのツッコミが正当かどうかにかかわらず、実に下品なのである。僕のような、上品が服を着て歩いているようなぼんぼんにはとうてい与することのできない境地だ。
案の定、インターネットでの反応は、批判的な書き込みが多かったように思う。批判ならまだいいが、悪口も多い。会場に集まっている人を、まるで洗脳されて詐欺にあっている狂信者たちのように書いているものもあり、そういう書き込みを見ると、インターネットで見ることの限界みたいなものを痛切に感じた。
たしかに、ツッコミたくなる気持ちがわからないではないのだが、おなじアホなら踊らにゃソンソン、なのである。
午前10時から、京都大学時計台百周年記念館ホールで、エマニュエル・トッドの特別講演会。
「ユーラシアにおける伝統家族システムと人口学的多様性-『近代』というものはあるのか?-」
トッド氏は英語で講演、希望者には同時通訳のイヤホンガイドの貸し出しもあった。もちろん、英語などチンプンカンプンの僕は借りて同時通訳で聴講した。
テーマのとおり、トッド氏は、家族システム、つまり人類学的データから得られる知見から社会や政治をみる。大きく、核家族、直系家族、共同体家族の3つのタイプにわけて、世界を説明しようとする。
(たとえば共産主義をこれら家族システムから説明してみる)
これはトッド氏の過去の著作でも展開されたおなじみの理論で、家族システムによって、多くの事柄がみごとに説明できる。
で、根本的な問題は、家族の形態が各国によっていろいろ違うのはなぜなのか。と、いうことだ。
これに対して、過去の著作『第三惑星』では、結論に「偶然」という章をたてて、こう論じていた。
「いかなる規則、いかなる論理とも関係なく地球上に散らばっているように見える諸家族構造の配置が示す地理的な一貫性の欠如は、それ自体ひとつの重要な結論なのである」
僕は、ここまではなんとか読んでいたが、次のトッド氏の論旨の展開は目からウロコだった。既に出た本のなかに、その展開があるのかもしれないが、未読。少なくとも、新しい著作には書いてあるというので、ちゃんと読んでみたい。
さっきも書いたように、トッド氏は、家族システムが世界にバラバラに存在している原因、理由を「偶然」と結論づけていたが、親しい言語学者に家族構造の分布地図を見せたところ、あっさりと、ひとつの説を言われたのだという。
その言語学者は、Laurent Sagart。
このあたりからが、テーマの後半、「近代化」に関わる問題になってくる。
ロシアや中国などにみられる古い共同体家族が、中央にどかっと存在していて、近代化を意味する核家族が、その周縁にバラバラに発生している。シルクロードならぬ「核家族ロード」でもあるならともかく、それぞれの国はバラバラだ。
共同体家族をシステムとしてもつのも、核家族をシステムとしてもつのも、すべてが偶然だとすれば、それは歴史の否定、つまりは近代化というものもなくなってしまう、という議論になる。
だが、Sagartは、言語学的知見から、伝播の法則、拡散の法則をあてはめてはどうか、と言ったのだ。
つまり、核家族を近代化のあかしと解釈するのではなく、実は逆で、古来核家族が存在していた世界に、共同体家族が近代化のプロセスとして出現したのではないか、というのだ。そして、共同体家族が近隣の地域に伝播していった結果として、核家族の地域が周縁にバラバラに残ったのである。
ふむ。僕みたいな学問に縁のない人間では何だかよくわからない説明しかできないな。これ、かなり衝撃だったけど、伝わらないどころか、僕が誤解している可能性もある。トッドの本を読もう。
ところで、京都大学に久々に行ったのだが、ユニオンエクスタシーが正門の横に、狭っ苦しく、まるで靴磨きの店みたいに片付けられていたのにはショックを受けた。確かに、正門入ったあたりはきれいに整備されていたが、くびくびカフェの存在が京都大学にもまだ可能性があるんじゃないか、と思わせる頼みの綱だっただけに、ガックリくるものがあった。恭平くんとしゃべっていないので、詳しいことはわからないし、無人だったから、片付けられているような印象を持っただけかもしれない。まあ、今後のなりゆきを注視しなくては。
http://extasy07.exblog.jp/
「ユーラシアにおける伝統家族システムと人口学的多様性-『近代』というものはあるのか?-」
トッド氏は英語で講演、希望者には同時通訳のイヤホンガイドの貸し出しもあった。もちろん、英語などチンプンカンプンの僕は借りて同時通訳で聴講した。
テーマのとおり、トッド氏は、家族システム、つまり人類学的データから得られる知見から社会や政治をみる。大きく、核家族、直系家族、共同体家族の3つのタイプにわけて、世界を説明しようとする。
(たとえば共産主義をこれら家族システムから説明してみる)
これはトッド氏の過去の著作でも展開されたおなじみの理論で、家族システムによって、多くの事柄がみごとに説明できる。
で、根本的な問題は、家族の形態が各国によっていろいろ違うのはなぜなのか。と、いうことだ。
これに対して、過去の著作『第三惑星』では、結論に「偶然」という章をたてて、こう論じていた。
「いかなる規則、いかなる論理とも関係なく地球上に散らばっているように見える諸家族構造の配置が示す地理的な一貫性の欠如は、それ自体ひとつの重要な結論なのである」
僕は、ここまではなんとか読んでいたが、次のトッド氏の論旨の展開は目からウロコだった。既に出た本のなかに、その展開があるのかもしれないが、未読。少なくとも、新しい著作には書いてあるというので、ちゃんと読んでみたい。
さっきも書いたように、トッド氏は、家族システムが世界にバラバラに存在している原因、理由を「偶然」と結論づけていたが、親しい言語学者に家族構造の分布地図を見せたところ、あっさりと、ひとつの説を言われたのだという。
その言語学者は、Laurent Sagart。
このあたりからが、テーマの後半、「近代化」に関わる問題になってくる。
ロシアや中国などにみられる古い共同体家族が、中央にどかっと存在していて、近代化を意味する核家族が、その周縁にバラバラに発生している。シルクロードならぬ「核家族ロード」でもあるならともかく、それぞれの国はバラバラだ。
共同体家族をシステムとしてもつのも、核家族をシステムとしてもつのも、すべてが偶然だとすれば、それは歴史の否定、つまりは近代化というものもなくなってしまう、という議論になる。
だが、Sagartは、言語学的知見から、伝播の法則、拡散の法則をあてはめてはどうか、と言ったのだ。
つまり、核家族を近代化のあかしと解釈するのではなく、実は逆で、古来核家族が存在していた世界に、共同体家族が近代化のプロセスとして出現したのではないか、というのだ。そして、共同体家族が近隣の地域に伝播していった結果として、核家族の地域が周縁にバラバラに残ったのである。
ふむ。僕みたいな学問に縁のない人間では何だかよくわからない説明しかできないな。これ、かなり衝撃だったけど、伝わらないどころか、僕が誤解している可能性もある。トッドの本を読もう。
ところで、京都大学に久々に行ったのだが、ユニオンエクスタシーが正門の横に、狭っ苦しく、まるで靴磨きの店みたいに片付けられていたのにはショックを受けた。確かに、正門入ったあたりはきれいに整備されていたが、くびくびカフェの存在が京都大学にもまだ可能性があるんじゃないか、と思わせる頼みの綱だっただけに、ガックリくるものがあった。恭平くんとしゃべっていないので、詳しいことはわからないし、無人だったから、片付けられているような印象を持っただけかもしれない。まあ、今後のなりゆきを注視しなくては。
http://extasy07.exblog.jp/
「アウシュヴィッツからの回復 プリーモ・レーヴィの場合」@立命館大学
2011年4月30日 学校・勉強 ◇立命館大学 末川記念会館講義室で、「アウシュヴィッツからの回復 プリーモ・レーヴィの場合」講師は竹山博英
竹山教授が今回の講義について書かれている。
立命館土曜講座エッセイより。
講義は、プリーモ・レーヴィの生い立ちから、人と作品の歴史を一通りたどったところで、タイムアップ。
意外とお年寄りの方の聴講が多くて驚いた。
プリーモ・レーヴィの写真や、ゆかりの地、そしてアウシュビッツの写真のスライドも見れた。
かえすがえすも、この日、国際平和ミュージアムが休館日だったのが惜しまれる。
講義中、ジャン・アメリーの名前が出てきた。アメリーの本は1冊しか読んでいなかったので、いずれ読んでみようと思った。
竹山教授が今回の講義について書かれている。
トリーノの町は碁盤の目のように、東西、南北の道が直角に交わり、整然とした町並みが形成されている。特に中心街がそうなっていて、由緒ある教会や歴史的建造物に並んで、優雅なカフェが建ち並び、独特の魅力を形成している。プリーモ・レーヴィはこうしたトリーノの町で生まれ、育ち、生涯同じ家に住み続け、その家で死んだ。それも自殺という劇的な形で。
プリーモ・レーヴィのことを考えると、彼の住んだトリーノの町を思い浮かべてしまう。彼はその町と同じように、端正で明快な文章で作品を書いた。その作品は、小説も評論も、物事の本質を見抜く理性的立場に支えられている。彼の世界には曇りがない。それがプリーモ・レーヴィが与える印象だった。そうした印象は彼の自死によって覆されてしまった。彼の世界は明快さと裏腹の影の部分を持っていた。そうした影の部分はさらに分析する価値があると思う。アウシュヴィッツから帰還したものが、いかに死の世界を克服し、現実社会に適応できるのか。彼の死はそうした難問を多くの人に投げかけているのである。
立命館土曜講座エッセイより。
講義は、プリーモ・レーヴィの生い立ちから、人と作品の歴史を一通りたどったところで、タイムアップ。
意外とお年寄りの方の聴講が多くて驚いた。
プリーモ・レーヴィの写真や、ゆかりの地、そしてアウシュビッツの写真のスライドも見れた。
かえすがえすも、この日、国際平和ミュージアムが休館日だったのが惜しまれる。
講義中、ジャン・アメリーの名前が出てきた。アメリーの本は1冊しか読んでいなかったので、いずれ読んでみようと思った。
変貌するジュネ@京都芸術劇場春秋座
2011年3月27日 学校・勉強京都芸術劇場春秋座で、ジャン・ジュネ生誕百周年記念シンポジウム「変貌するジュネ」
午前10時30分からはじまるというので、8時30分には家を出たのだが、微妙に間に合わなくて、パネラーの紹介中に会場に入れた。
駅からの道がわからなくて困ったが、方向音痴の僕にしては奇跡的にまったく道を引き返すことなく、ちゃんと行けた。40分くらいかかったけど、道を知っていても、それくらいはかかる、ていうことなのだ。
昨日は1部、2部で主に詩人、小説家としてのジュネが取り上げられたようだ。
今日はその続き。
第三部 「劇場のジュネI:ダンス・プロジェクト『恋する虜』をめぐって」
映像上映とディスカッション
10:30-12:15
ダンスプロジェクト『恋する虜』記録映像より
(企画・構成:山田せつ子、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター製作、2006/08年)
パネル・ディスカッション
パネリスト:鵜飼哲、宇野邦一、根岸徹郎、八角聡仁、山田せつ子、森山直人(司会)
第四部 「劇場のジュネII:ジュネを演出するということ」
13:40
講演「ジュネを演出するということ」 渡邊守章
パネル・ディスカッション
パネリスト:浅田彰、根岸徹郎、渡邊守章、森山直人(司会)
第五部 「ジュネにおける〈政治的なもの〉」
15:40
パネル・ディスカッション
鵜飼哲、宇野邦一、浅田彰(司会)
質疑応答
総括(渡邊守章も加わり)
終了したのは午後5時半頃だったかな。
「詩人、小説家、劇作家、エッセイスト、政治運動家としてのジャン・ジュネの、活動の多面性と受容の多様性を、時間軸と空間軸をあわせて検証し、作家ジャン・ジュネの言説の現代的意味を問い直す」とプログラムに書いてある。「変貌」はジュネ自身の変貌のみならず、受容の変貌も視野にいれている、ということだろう。
ジュネと言えば、ゲイで泥棒で云々、という決まり文句のような捉え方が、一面的に過ぎるものであることが、再三にわたって繰り返された。
第4部では「バルコン」のダイジェスト映像、第5部では「アンジェラ・デイヴィスはおまえたちの手中にある」の声明文を読み上げるジュネの映像が流れた。貴重。
渡邊守章がジュネに会ったときのエピソードが面白い。
どの写真を見てもいい顔で写っているのに、実際に見たときの表情は「ふにゃっ」としていて失望したとか。
渡邊守章のズバズバと断言する口調にユーモアがたっぷり含まれているのには感心した。「せりふは演技の譜面だ」という主張や、ジュネの演劇と複数の言語態の問題などなど。
あと、総括などに発揮された浅田彰の論点整理能力には舌を巻いた。
そして、宇野邦一の発言がひとつひとつ重い斧で振り下ろすような迫力があるのには驚いた。翻訳に際してのアルファベットの軽みと漢字の重みのこととか。
これらの経緯は、いずれ『舞台芸術』誌に収録されるそうなので、楽しみに待つことにしよう。
(こっそり追記)
浅田彰はコンパクトにまとめる達人で、そこまでわかりやすくしていいのか、と目からウロコが落ちる。おそらく、このシンポジウムは浅田彰の掌の上で開かれているようなもので、すべての経過は、先刻考慮済み、みたいな見通しのすごさを感じた。
鵜飼哲は明快な語り口だけど、その内容は難解なところを含んでいて、なにより、発言自体が予想の倍くらい長いので、論旨を追うのに疲れてしまうところがあった。これは僕の体力不足だ。
宇野邦一は、上記2人がズバズバ切ってしまって、漏らしてしまった部分にこだわり、なるほど、そう言われてみればそうだ、と振り返って考えなおす力を持っている。一番深いところを突いているんじゃないか、と思わせる。
渡邊守章は、ちょっと別格。好き嫌い、主観でものを言っていることを隠さないのだが、いちいちその断言が面白くて、鋭い。おそらくは正しいのだろう、と思わせる説得力がある。
な~んて、無責任に感想を書いてみました。
春秋座から出町柳駅までの徒歩(約30分)をゆっくりゆっくり歩きながら、午後6時からNHK-FM「現代の音楽」を聴いた。
猿谷紀郎
- “四人組とその仲間たち”室内楽コンサートから -(2)
「ソナタ チェロとピアノのために」 新実徳英・作曲
(27分50秒)
(チェロ)堤剛
(ピアノ)若林顕
「ストラータ8 バイオリンとチェロのために」池辺晋一郎・作曲
(9分10秒)
(バイオリン)亀井庸州
(チェロ)多井智紀
~東京・津田ホールで収録~
<2010/12/3>
「クインクバランス バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバスとピアノのために」池辺晋一郎・作曲
(7分50秒)
(バイオリン)久保田巧
(ビオラ)セルジュ・コロー
(チェロ)苅田雅冶
(コントラバス)永島義男
(ピアノ)向井山朋子
(指揮)池辺晋一郎
<カメラータ・トウキョウ 32CM-270>
先週は「今日は一日~三昧」だったし、その前は震災のため特別番組になっていたのだが、番組開口一番「今回は、前回に引き続き、四人組とその仲間たちの室内楽コンサートからお送りします」と言ったのにはずっこけた。
歩きながらラジオを聴いていたが、クリアにはあまり聞けず、雑音の彼方に不穏なムードの現代音楽が聞こえるのは非常に不気味だった。ほとんど見知らぬ古い都の町並みをそんな音楽をBGMにして彷徨うと、ミステリーゾーンに迷い込んだような気分になる。
と、いうわけで、時間が間に合えば日本橋ラブコンシアターでファンタピース見ようかと思っていたが、ぜんぜん間に合わなかった。
帰宅後、深夜のレコ部。
午前10時30分からはじまるというので、8時30分には家を出たのだが、微妙に間に合わなくて、パネラーの紹介中に会場に入れた。
駅からの道がわからなくて困ったが、方向音痴の僕にしては奇跡的にまったく道を引き返すことなく、ちゃんと行けた。40分くらいかかったけど、道を知っていても、それくらいはかかる、ていうことなのだ。
昨日は1部、2部で主に詩人、小説家としてのジュネが取り上げられたようだ。
今日はその続き。
第三部 「劇場のジュネI:ダンス・プロジェクト『恋する虜』をめぐって」
映像上映とディスカッション
10:30-12:15
ダンスプロジェクト『恋する虜』記録映像より
(企画・構成:山田せつ子、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター製作、2006/08年)
パネル・ディスカッション
パネリスト:鵜飼哲、宇野邦一、根岸徹郎、八角聡仁、山田せつ子、森山直人(司会)
第四部 「劇場のジュネII:ジュネを演出するということ」
13:40
講演「ジュネを演出するということ」 渡邊守章
パネル・ディスカッション
パネリスト:浅田彰、根岸徹郎、渡邊守章、森山直人(司会)
第五部 「ジュネにおける〈政治的なもの〉」
15:40
パネル・ディスカッション
鵜飼哲、宇野邦一、浅田彰(司会)
質疑応答
総括(渡邊守章も加わり)
終了したのは午後5時半頃だったかな。
「詩人、小説家、劇作家、エッセイスト、政治運動家としてのジャン・ジュネの、活動の多面性と受容の多様性を、時間軸と空間軸をあわせて検証し、作家ジャン・ジュネの言説の現代的意味を問い直す」とプログラムに書いてある。「変貌」はジュネ自身の変貌のみならず、受容の変貌も視野にいれている、ということだろう。
ジュネと言えば、ゲイで泥棒で云々、という決まり文句のような捉え方が、一面的に過ぎるものであることが、再三にわたって繰り返された。
第4部では「バルコン」のダイジェスト映像、第5部では「アンジェラ・デイヴィスはおまえたちの手中にある」の声明文を読み上げるジュネの映像が流れた。貴重。
渡邊守章がジュネに会ったときのエピソードが面白い。
どの写真を見てもいい顔で写っているのに、実際に見たときの表情は「ふにゃっ」としていて失望したとか。
渡邊守章のズバズバと断言する口調にユーモアがたっぷり含まれているのには感心した。「せりふは演技の譜面だ」という主張や、ジュネの演劇と複数の言語態の問題などなど。
あと、総括などに発揮された浅田彰の論点整理能力には舌を巻いた。
そして、宇野邦一の発言がひとつひとつ重い斧で振り下ろすような迫力があるのには驚いた。翻訳に際してのアルファベットの軽みと漢字の重みのこととか。
これらの経緯は、いずれ『舞台芸術』誌に収録されるそうなので、楽しみに待つことにしよう。
(こっそり追記)
浅田彰はコンパクトにまとめる達人で、そこまでわかりやすくしていいのか、と目からウロコが落ちる。おそらく、このシンポジウムは浅田彰の掌の上で開かれているようなもので、すべての経過は、先刻考慮済み、みたいな見通しのすごさを感じた。
鵜飼哲は明快な語り口だけど、その内容は難解なところを含んでいて、なにより、発言自体が予想の倍くらい長いので、論旨を追うのに疲れてしまうところがあった。これは僕の体力不足だ。
宇野邦一は、上記2人がズバズバ切ってしまって、漏らしてしまった部分にこだわり、なるほど、そう言われてみればそうだ、と振り返って考えなおす力を持っている。一番深いところを突いているんじゃないか、と思わせる。
渡邊守章は、ちょっと別格。好き嫌い、主観でものを言っていることを隠さないのだが、いちいちその断言が面白くて、鋭い。おそらくは正しいのだろう、と思わせる説得力がある。
な~んて、無責任に感想を書いてみました。
春秋座から出町柳駅までの徒歩(約30分)をゆっくりゆっくり歩きながら、午後6時からNHK-FM「現代の音楽」を聴いた。
猿谷紀郎
- “四人組とその仲間たち”室内楽コンサートから -(2)
「ソナタ チェロとピアノのために」 新実徳英・作曲
(27分50秒)
(チェロ)堤剛
(ピアノ)若林顕
「ストラータ8 バイオリンとチェロのために」池辺晋一郎・作曲
(9分10秒)
(バイオリン)亀井庸州
(チェロ)多井智紀
~東京・津田ホールで収録~
<2010/12/3>
「クインクバランス バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバスとピアノのために」池辺晋一郎・作曲
(7分50秒)
(バイオリン)久保田巧
(ビオラ)セルジュ・コロー
(チェロ)苅田雅冶
(コントラバス)永島義男
(ピアノ)向井山朋子
(指揮)池辺晋一郎
<カメラータ・トウキョウ 32CM-270>
先週は「今日は一日~三昧」だったし、その前は震災のため特別番組になっていたのだが、番組開口一番「今回は、前回に引き続き、四人組とその仲間たちの室内楽コンサートからお送りします」と言ったのにはずっこけた。
歩きながらラジオを聴いていたが、クリアにはあまり聞けず、雑音の彼方に不穏なムードの現代音楽が聞こえるのは非常に不気味だった。ほとんど見知らぬ古い都の町並みをそんな音楽をBGMにして彷徨うと、ミステリーゾーンに迷い込んだような気分になる。
と、いうわけで、時間が間に合えば日本橋ラブコンシアターでファンタピース見ようかと思っていたが、ぜんぜん間に合わなかった。
帰宅後、深夜のレコ部。
ロベルト・エスポジト講演「装置」としてのペルソナ@大阪大学
2011年3月7日 学校・勉強午後3時から、大阪大学吹田キャンパスで、ロベルト・エスポジト講演。
「装置」としてのペルソナ――人格の脱構築と三人称の哲学
講師:ロベルト・エスポジト(イタリア国立人文科学研究所副所長)
コメンテーター:フェデリコ・ルイゼッティ(ノース・キャロライナ大学准教授)
場所:大阪大学(吹田キャンパス)人間科学研究科・ユメンヌホール
内容後日
「装置」としてのペルソナ――人格の脱構築と三人称の哲学
講師:ロベルト・エスポジト(イタリア国立人文科学研究所副所長)
コメンテーター:フェデリコ・ルイゼッティ(ノース・キャロライナ大学准教授)
場所:大阪大学(吹田キャンパス)人間科学研究科・ユメンヌホール
内容後日
トークセッション「快楽の効用―肉の共同体へ向けて―」@ジュンク堂難波店
2011年3月5日 学校・勉強午後3時からジュンク堂難波店でトークセッション
『快楽の効用』(ちくま新書)
『哲学的なものと政治的なもの』(青土社)刊行記念
快楽の効用―肉の共同体へ向けて―
雑賀恵子(社会思想史)×松葉祥一(哲学)
【パネラー紹介】
★雑賀恵子(さいが・けいこ)
現在、大阪産業大学ほか非常勤講師。著書に、『快楽の効用 嗜好品をめぐるあれこれ』(ちくま新書)、『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食について』(人文書院)。
★松葉祥一(まつば・しょういち)
現在、神戸市看護大学教授。著書に、『哲学的なものと政治的なもの』(青土社)、『ナースのための実践論文講座』(人文書院)。訳書に、ランシエール『民主主義への憎悪』(インスクリプト)、バリバール『ヨーロッパ市民とは誰か』(共訳、平凡社)など。
☆ 会 場 … 難波店3階カウンター前特設会場。入場無料。
人食いや嘔吐について。
内容については後日。
『快楽の効用』(ちくま新書)
『哲学的なものと政治的なもの』(青土社)刊行記念
快楽の効用―肉の共同体へ向けて―
雑賀恵子(社会思想史)×松葉祥一(哲学)
【パネラー紹介】
★雑賀恵子(さいが・けいこ)
現在、大阪産業大学ほか非常勤講師。著書に、『快楽の効用 嗜好品をめぐるあれこれ』(ちくま新書)、『空腹について』(青土社)、『エコ・ロゴス 存在と食について』(人文書院)。
★松葉祥一(まつば・しょういち)
現在、神戸市看護大学教授。著書に、『哲学的なものと政治的なもの』(青土社)、『ナースのための実践論文講座』(人文書院)。訳書に、ランシエール『民主主義への憎悪』(インスクリプト)、バリバール『ヨーロッパ市民とは誰か』(共訳、平凡社)など。
☆ 会 場 … 難波店3階カウンター前特設会場。入場無料。
人食いや嘔吐について。
内容については後日。
午後1時30分から京都大学でロベルト・エスポジト特別講義「イタリア哲学の回帰-その起源とアクチュアリティ」
講師はイタリア国立人文科学研究所副所長のロベルト・エスポジト、通訳と解説はノース・キャロライナ大学准教授のフェデリコ・ルイゼッティ。エスポジトの本を翻訳し思想の紹介を各所で行っている岡田温司教授が司会、サポートをされていた。
紹介文は次のとおり。
つねに世俗経験の葛藤とトラウマにさらされているイタリア哲学は、主体理論、認識論、言語分析、解釈学的脱構築などとは別のものを目指している。イタリア哲学の中核には「生」というカテゴリーがあり、そこには「政治」および「歴史」というカテゴリーが緊密に――かつ問題含みの仕方で――結びついているのである。濃密で不透明なこのマテリア――生――は、表象のフォルマ的秩序には還元しえない。そのためにこそイタリアの思想は、今日のわたしたちの時代を特徴づける兆候と深く共鳴しあうのである。
内容については後日。
この日、くびくびカフェの強制撤去、抗議、再建があったそうだが、知らずに、寒さと空腹に負けて、寄らずに帰ってしまった。しまった!
講師はイタリア国立人文科学研究所副所長のロベルト・エスポジト、通訳と解説はノース・キャロライナ大学准教授のフェデリコ・ルイゼッティ。エスポジトの本を翻訳し思想の紹介を各所で行っている岡田温司教授が司会、サポートをされていた。
紹介文は次のとおり。
つねに世俗経験の葛藤とトラウマにさらされているイタリア哲学は、主体理論、認識論、言語分析、解釈学的脱構築などとは別のものを目指している。イタリア哲学の中核には「生」というカテゴリーがあり、そこには「政治」および「歴史」というカテゴリーが緊密に――かつ問題含みの仕方で――結びついているのである。濃密で不透明なこのマテリア――生――は、表象のフォルマ的秩序には還元しえない。そのためにこそイタリアの思想は、今日のわたしたちの時代を特徴づける兆候と深く共鳴しあうのである。
内容については後日。
この日、くびくびカフェの強制撤去、抗議、再建があったそうだが、知らずに、寒さと空腹に負けて、寄らずに帰ってしまった。しまった!