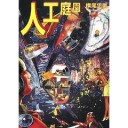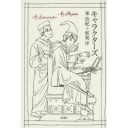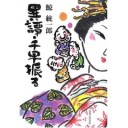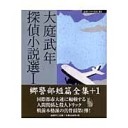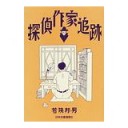『月光果樹園』、ツインズ・エフェクト、ドナウエッシンゲン現代音楽祭2007
2008年12月9日 読書高原英理の『月光果樹園』を読んだ。
以下、目次。
月光果樹園園丁から
第1章 山査子
ロマンティシズムの継承権
遠い記憶として−幻影の性、幻影の同盟
第2章 葡萄
形而上憧憬症候群−女性幻想文学者たち
第3章 檸檬
生涯一憧憬者−岩井俊二の小説
「バガージマヌパナス」ヌパナス−池上永一・栗原まもる
アンドロギュヌス・ロマンティック仕様−松村栄子『紫の砂漠』について
小川洋子の記憶
第4章 巴旦杏
未来基準−稲垣足穂の懐かしさ
足穂と童話
六月の夜の都会の空
第5章 橄欖樹
澁澤=サドの遊戯作法
澁澤龍彦と世紀末
奇獣たちの静かないざない−澁澤龍彦と『高丘親王航海記』
第6章 桜桃
過つ権利−矢川澄子
「父の娘」たちを語ること−『「父の娘」たち』解説
第7章 柘榴
困難な智−中井英夫の幻想小説について
文人と幻想文学者の間
第8章 無花果
横光運命説−横光利一
第9章 棗
無垢を排除せよ−坂口安吾
第10章 茘枝
もの見えず執深く−赤江瀑
攫われてゆくことの歴史とその継承−須永朝彦
半分嬉しく半分悲しく−日影丈吉
憧憬によって書かれたラブレターの数々。
横光利一や坂口安吾についての章は、しっかりと書いているけど、なんだか学生のレポートみたいだな、と思ったら、「早稲田文学」のために書いた文章だった。
この本読んでいると、いろいろと読みたい本が増えて困った。
試しに横光利一の作品をいくつか読んでみたら、「機械」の主人公の人間もどきぶりに今さらながら気づき、これは僕だ、と感じた。
ダンテ・ラム監督の「ツインズ・エフェクト」を見た。2003年。
香港の国民的アイドル、ツインズ主演の映画。
吸血鬼との恋、そして、悪の吸血鬼退治。
イーキン・チェンの他、特別出演のジャッキー・チェンもけっこう長い時間出ている。
いい方の血筋のいい吸血鬼はエディソン・チャンが演じており、今年エッチ写真流出した2人、エディソン・チャンとジリアン・チョン(ツインズのきりっとした方)が共演しているわけだ。
アクションはそりゃ面白いが、役柄のせいか、いまいちツインズの人気の理由がこの映画からは見えなかった。ツインズ出てきてわがまま言ったりドジふんだりするたんびにキーッ、イライライライラ!となってたくらい。容貌が田舎者くさくて、神秘性に欠けるのが僕の好みにあわないだけなんだろうけど。映画の中で、ツインズが「香港の女の子はみんなこうよ!」と開き直るシーンがある。と、いうことは、あえてそういう風に役柄を作っていたのかもしれないが、どうにも納得できない。
ツインズは日本でいうと、クワバタオハラ的人気なんだろうか。少なくとも、かっすんのいるチェリーパイの方が遥かにいいな。
NHK-FMで三夜連続で現代音楽の番組が組まれていた。
近藤 譲
− 海外の現代音楽 −(1)
〜ドナウエッシンゲン現代音楽祭2007から〜
「叫び」 ハンス・トマッラ作曲
(17分20秒)
「“211007”」 ジェームズ・ソーンダーズ作曲
(24分40秒)
「奇妙な儀式」 フィリップ・マヌーリ作曲
(12分30秒)
(演奏)アンサンブル・モデルン
(指揮)ヨハネス・カリツケ
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン ドナウハレBで収録〜
<2007/10/21>
(南西ドイツ放送協会提供)
「曲がりくねった小道」 ミヒャエル・ペルツェル作曲
(24分20秒)
(演奏)アンサンブル・ルシェルシュ
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン ドナウハレAで収録〜
<2007/10/20>
(南西ドイツ放送協会提供)
*トマッラは1975年ドイツ生まれで渡米。ただし、音楽の発表はヨーロッパでの方が多い。
「叫び」についてのトマッラのプログラムノートにはこんな内容のことが書いてある。「最近の現代音楽というのはいろいろ音の決まり文句が多くて、作曲家はそうした決まり文句を並べて言いたいことを言おうとしているようだが、私はむしろ、1つ1つの音が何を意味するかを考えるということから真剣な作曲がはじまるんじゃないかと思う。叫び(感嘆文)をどういうふうに音楽のなかであらわすことができるか、歴史的にそういう強い感情をあらわすときはどういう音型が使われてきたか、現代ではそれがいかに可能か、驚き、叫びという強い感情をあらわす音楽の開発に関心があって、この曲をつくった。また同時に、叫びは自分自身の内の叫びでもある」
*ソーンダーズは生年が秘密で公表されていないが、おそらくは70年代生まれと近藤譲は推測している。イギリスの作曲家。
「211007」は1回の演奏会ごとに曲が作り直されるプロジェクトの作品で、「不定のもの」と仮にタイトルがつけられている。この演奏会でのタイトルは、2007年10月21
日に演奏されたという日付をあらわしている。
*マヌーリは1952年生まれ、現代フランスを代表する作曲家だが、現在はアメリカで教鞭をとっている。
「奇妙な儀式」は、マヌーリによると、定常的なもの(儀式)が新しいものの侵入によって崩されていき、最後にはアナーキーな状態になることを描いている。
*「曲りくねった小道」は2台のピアノを1/6ずつ調律をずらしてあり、しかもプリペアドピアノ使用。
日本の話芸は桂米丸の「若き日の思い出」
落語ではなく、思い出話をしているのだが、米丸師匠の人が出ていて、面白い。
戦争のときの話もされていた(空襲警報が急に鳴ったため、いつも隠れる防空壕に入れなかったが、なんと爆撃でその防空壕が跡形もなくなった、とか)が、こういう話なら、子供も戦争体験の貴重な話を興味をもって聞くことができるだろう。
つい最近、誰だったか、落語の襲名のご挨拶で米丸師匠のところに行ったとき、お茶でもいかが、と引き止められたので、じゃあ、とお茶をよばれた話をラジオで聞いたばかりだった。お茶を飲みながらも、手持ち無沙汰で何も話すことがない。米丸師匠に「普通は、引き止めても、これから行くところがまだあるから、と断るもんだ」と教えてもらった、とか。米丸師匠が飄々と語っているのが目に浮かぶようだ。
以下、目次。
月光果樹園園丁から
第1章 山査子
ロマンティシズムの継承権
遠い記憶として−幻影の性、幻影の同盟
第2章 葡萄
形而上憧憬症候群−女性幻想文学者たち
第3章 檸檬
生涯一憧憬者−岩井俊二の小説
「バガージマヌパナス」ヌパナス−池上永一・栗原まもる
アンドロギュヌス・ロマンティック仕様−松村栄子『紫の砂漠』について
小川洋子の記憶
第4章 巴旦杏
未来基準−稲垣足穂の懐かしさ
足穂と童話
六月の夜の都会の空
第5章 橄欖樹
澁澤=サドの遊戯作法
澁澤龍彦と世紀末
奇獣たちの静かないざない−澁澤龍彦と『高丘親王航海記』
第6章 桜桃
過つ権利−矢川澄子
「父の娘」たちを語ること−『「父の娘」たち』解説
第7章 柘榴
困難な智−中井英夫の幻想小説について
文人と幻想文学者の間
第8章 無花果
横光運命説−横光利一
第9章 棗
無垢を排除せよ−坂口安吾
第10章 茘枝
もの見えず執深く−赤江瀑
攫われてゆくことの歴史とその継承−須永朝彦
半分嬉しく半分悲しく−日影丈吉
憧憬によって書かれたラブレターの数々。
横光利一や坂口安吾についての章は、しっかりと書いているけど、なんだか学生のレポートみたいだな、と思ったら、「早稲田文学」のために書いた文章だった。
この本読んでいると、いろいろと読みたい本が増えて困った。
試しに横光利一の作品をいくつか読んでみたら、「機械」の主人公の人間もどきぶりに今さらながら気づき、これは僕だ、と感じた。
ダンテ・ラム監督の「ツインズ・エフェクト」を見た。2003年。
香港の国民的アイドル、ツインズ主演の映画。
吸血鬼との恋、そして、悪の吸血鬼退治。
イーキン・チェンの他、特別出演のジャッキー・チェンもけっこう長い時間出ている。
いい方の血筋のいい吸血鬼はエディソン・チャンが演じており、今年エッチ写真流出した2人、エディソン・チャンとジリアン・チョン(ツインズのきりっとした方)が共演しているわけだ。
アクションはそりゃ面白いが、役柄のせいか、いまいちツインズの人気の理由がこの映画からは見えなかった。ツインズ出てきてわがまま言ったりドジふんだりするたんびにキーッ、イライライライラ!となってたくらい。容貌が田舎者くさくて、神秘性に欠けるのが僕の好みにあわないだけなんだろうけど。映画の中で、ツインズが「香港の女の子はみんなこうよ!」と開き直るシーンがある。と、いうことは、あえてそういう風に役柄を作っていたのかもしれないが、どうにも納得できない。
ツインズは日本でいうと、クワバタオハラ的人気なんだろうか。少なくとも、かっすんのいるチェリーパイの方が遥かにいいな。
NHK-FMで三夜連続で現代音楽の番組が組まれていた。
近藤 譲
− 海外の現代音楽 −(1)
〜ドナウエッシンゲン現代音楽祭2007から〜
「叫び」 ハンス・トマッラ作曲
(17分20秒)
「“211007”」 ジェームズ・ソーンダーズ作曲
(24分40秒)
「奇妙な儀式」 フィリップ・マヌーリ作曲
(12分30秒)
(演奏)アンサンブル・モデルン
(指揮)ヨハネス・カリツケ
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン ドナウハレBで収録〜
<2007/10/21>
(南西ドイツ放送協会提供)
「曲がりくねった小道」 ミヒャエル・ペルツェル作曲
(24分20秒)
(演奏)アンサンブル・ルシェルシュ
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン ドナウハレAで収録〜
<2007/10/20>
(南西ドイツ放送協会提供)
*トマッラは1975年ドイツ生まれで渡米。ただし、音楽の発表はヨーロッパでの方が多い。
「叫び」についてのトマッラのプログラムノートにはこんな内容のことが書いてある。「最近の現代音楽というのはいろいろ音の決まり文句が多くて、作曲家はそうした決まり文句を並べて言いたいことを言おうとしているようだが、私はむしろ、1つ1つの音が何を意味するかを考えるということから真剣な作曲がはじまるんじゃないかと思う。叫び(感嘆文)をどういうふうに音楽のなかであらわすことができるか、歴史的にそういう強い感情をあらわすときはどういう音型が使われてきたか、現代ではそれがいかに可能か、驚き、叫びという強い感情をあらわす音楽の開発に関心があって、この曲をつくった。また同時に、叫びは自分自身の内の叫びでもある」
*ソーンダーズは生年が秘密で公表されていないが、おそらくは70年代生まれと近藤譲は推測している。イギリスの作曲家。
「211007」は1回の演奏会ごとに曲が作り直されるプロジェクトの作品で、「不定のもの」と仮にタイトルがつけられている。この演奏会でのタイトルは、2007年10月21
日に演奏されたという日付をあらわしている。
*マヌーリは1952年生まれ、現代フランスを代表する作曲家だが、現在はアメリカで教鞭をとっている。
「奇妙な儀式」は、マヌーリによると、定常的なもの(儀式)が新しいものの侵入によって崩されていき、最後にはアナーキーな状態になることを描いている。
*「曲りくねった小道」は2台のピアノを1/6ずつ調律をずらしてあり、しかもプリペアドピアノ使用。
日本の話芸は桂米丸の「若き日の思い出」
落語ではなく、思い出話をしているのだが、米丸師匠の人が出ていて、面白い。
戦争のときの話もされていた(空襲警報が急に鳴ったため、いつも隠れる防空壕に入れなかったが、なんと爆撃でその防空壕が跡形もなくなった、とか)が、こういう話なら、子供も戦争体験の貴重な話を興味をもって聞くことができるだろう。
つい最近、誰だったか、落語の襲名のご挨拶で米丸師匠のところに行ったとき、お茶でもいかが、と引き止められたので、じゃあ、とお茶をよばれた話をラジオで聞いたばかりだった。お茶を飲みながらも、手持ち無沙汰で何も話すことがない。米丸師匠に「普通は、引き止めても、これから行くところがまだあるから、と断るもんだ」と教えてもらった、とか。米丸師匠が飄々と語っているのが目に浮かぶようだ。
らくご道@上方亭、『澁澤龍彦との日々』、琴の爪
2008年12月8日 読書詰将棋パラダイスモバイルが7日からスタートした。
携帯電話と縁のない僕にはちょっとどうかな、と思うが、いつでも詰将棋を携帯できるってのはいいかも。毎週読んでる「週刊将棋」だって、詰将棋以外は流し読みしてること多いしね。
http://www.katsuraba.mydns.jp/tumeparamobile/manual.html
午後7時から上方亭で「第45回らくご道」
池田の猪買い/笑福亭生寿
兵庫船/桂こごろう
蛸芝居/笑福亭生喬
対談:夕焼け日記
桂こごろうはwiiのマリオカートwi-fiで世界とつながることなどをマクラに。
笑福亭生喬は披露宴の話など。
中入り後の対談では、着物のことや、筋肉痛のことなど、まるで打ち上げに参加させてもらったかのような親近感の湧くやりとりがなされた。
衛星劇場で放送されてた落語は春風亭ぽっぽの「子ほめ」
若手の落語オンエアもいいが、名人の映像などを本当なら見たいところ。
澁澤龍子の『澁澤龍彦との日々』を読んだ。
以下、目次。
出会いと結婚
執筆の日々
北鎌倉のわが家
パイプ
わが家のオブジェ
宗達の犬と兎のウチャ
澁澤家の食卓
お酒
散歩
喧嘩とお叱り帖
旅と交友
初の外国旅行
三島由紀夫さん
吉行淳之介さん
石川淳さん
埴谷雄高さん
稲垣足穂さん
林達夫さん、大岡昇平さん
吉岡実さん
種村季弘さん
土方巽さん
多田智満子さん
池田満寿夫さん
堀内誠一さん
お正月
発病
全集刊行と没後の日々
澁澤龍子は29歳のとき、1969年に澁澤龍彦(当時41歳)と結婚した。以来、澁澤龍彦が1987年8月5日に亡くなるまで、彼を支え、死後も支えていると言っていいだろう。
本書の冒頭あたりと巻末の言葉をそれぞれ引用すると。
結婚してからわたしを裏切ったり、約束を守らなかったことは一度もありませんでした。おかげで彼との生活のなかで、嫉妬心とか猜疑心という言葉はわたしの辞書からなくなりました。
降り注ぐような愛で、生涯わたしを抱きしめてくれた人。
わたしの思う理想の結婚をプレゼントしてくれた人。
ですから亡くなったことは悲しいし、寂しいことですが、今でもずっとわたしは幸せです。
ワーオ!
こんなことを言われてみたいものだ。
面白かったのは、澁澤龍彦がメモ帳に書いた「お叱り帖」。これは「門徒もの知らず帖」とか「龍子バカ帖」と名付けられたもので、内容はたとえばこんなもの。
「ウサギウマはロバのことだよ。何度言っても忘れる」
「柿食えば鐘が鳴る鳴るという(大楠山でまた言った)」
要するに、龍子に対するツッコミが同じ内容で度重なったときに、いちいちツッコムのが面倒になってきて、メモに書いたもの。
これを一冊の本にしてもいいんじゃないか、とも思えた。
本書では、澁澤龍彦の方向音痴ぶりや、最後に見た映画が「ミツバチのささやき」だったことなど、澁澤の日常的な一面が書き記されていて、興味深い。酔っぱらったら手がつけられないこととか。40歳過ぎてから、学生に間違われたことも書いてあったな。好きな童謡は「チュウリップ兵隊」だとか。チョロギが好きとか。甘鯛、おこぜの唐揚げが大好物とか。
また、龍子に向けての澁澤語録とでも言うべきものも、面白い。
独身時代、展覧会に行く約束をしていて、澁澤が寝ていてすっぽかしたときの言葉は
「だって、この宇宙はぼくを中心に回っているから、これからもずっとそうだよ。そんなことで怒るのはおかしいよ」
また、
「おまえと俺の知識の差って1万対1ぐらいじゃないの」とか
「おまえがもっと白痴ならいい」
なんてしゃあしゃあと言ってのけるところが面白い!
堀川弘通監督の「琴の爪」を見た。1957年。
真山青果の『元禄忠臣蔵』「大石最後の一日」より。
討ち入り50日後からの義士たちを描く。
世間では仇討ちが流行していたりする。
沙汰があるまでの揺れる心情と、武士としての矜持がせめぎあう義士たちの葛藤。
「ひょっとしたら命は助かるのでは?」という希望もわくなかで、若き磯貝十郎左衛門(中村扇雀)は、武士としての潔い死を覚悟していた。彼には祝言を控えた、おみの(扇千景。可憐!)という女性がいた。「計略のために偽りの縁を結んだ」と言う磯貝。「一目会って気持ちを知りたい」と男装して磯貝に接触をはかる、おみの。おみのの男装を見抜いて、いったんは磯貝とのコンタクトを拒否した大石だったが、一転、おみのを磯貝に会わせる。
そこでも磯貝は態度を変えない。しかし、実は、というお馴染みのお話。
戦争に参加しておいて、裁かれる段になってまさか死罪にはならないだろう、なんて楽観している「貝になりたい」男などとは大違いだ。
携帯電話と縁のない僕にはちょっとどうかな、と思うが、いつでも詰将棋を携帯できるってのはいいかも。毎週読んでる「週刊将棋」だって、詰将棋以外は流し読みしてること多いしね。
http://www.katsuraba.mydns.jp/tumeparamobile/manual.html
午後7時から上方亭で「第45回らくご道」
池田の猪買い/笑福亭生寿
兵庫船/桂こごろう
蛸芝居/笑福亭生喬
対談:夕焼け日記
桂こごろうはwiiのマリオカートwi-fiで世界とつながることなどをマクラに。
笑福亭生喬は披露宴の話など。
中入り後の対談では、着物のことや、筋肉痛のことなど、まるで打ち上げに参加させてもらったかのような親近感の湧くやりとりがなされた。
衛星劇場で放送されてた落語は春風亭ぽっぽの「子ほめ」
若手の落語オンエアもいいが、名人の映像などを本当なら見たいところ。
澁澤龍子の『澁澤龍彦との日々』を読んだ。
以下、目次。
出会いと結婚
執筆の日々
北鎌倉のわが家
パイプ
わが家のオブジェ
宗達の犬と兎のウチャ
澁澤家の食卓
お酒
散歩
喧嘩とお叱り帖
旅と交友
初の外国旅行
三島由紀夫さん
吉行淳之介さん
石川淳さん
埴谷雄高さん
稲垣足穂さん
林達夫さん、大岡昇平さん
吉岡実さん
種村季弘さん
土方巽さん
多田智満子さん
池田満寿夫さん
堀内誠一さん
お正月
発病
全集刊行と没後の日々
澁澤龍子は29歳のとき、1969年に澁澤龍彦(当時41歳)と結婚した。以来、澁澤龍彦が1987年8月5日に亡くなるまで、彼を支え、死後も支えていると言っていいだろう。
本書の冒頭あたりと巻末の言葉をそれぞれ引用すると。
結婚してからわたしを裏切ったり、約束を守らなかったことは一度もありませんでした。おかげで彼との生活のなかで、嫉妬心とか猜疑心という言葉はわたしの辞書からなくなりました。
降り注ぐような愛で、生涯わたしを抱きしめてくれた人。
わたしの思う理想の結婚をプレゼントしてくれた人。
ですから亡くなったことは悲しいし、寂しいことですが、今でもずっとわたしは幸せです。
ワーオ!
こんなことを言われてみたいものだ。
面白かったのは、澁澤龍彦がメモ帳に書いた「お叱り帖」。これは「門徒もの知らず帖」とか「龍子バカ帖」と名付けられたもので、内容はたとえばこんなもの。
「ウサギウマはロバのことだよ。何度言っても忘れる」
「柿食えば鐘が鳴る鳴るという(大楠山でまた言った)」
要するに、龍子に対するツッコミが同じ内容で度重なったときに、いちいちツッコムのが面倒になってきて、メモに書いたもの。
これを一冊の本にしてもいいんじゃないか、とも思えた。
本書では、澁澤龍彦の方向音痴ぶりや、最後に見た映画が「ミツバチのささやき」だったことなど、澁澤の日常的な一面が書き記されていて、興味深い。酔っぱらったら手がつけられないこととか。40歳過ぎてから、学生に間違われたことも書いてあったな。好きな童謡は「チュウリップ兵隊」だとか。チョロギが好きとか。甘鯛、おこぜの唐揚げが大好物とか。
また、龍子に向けての澁澤語録とでも言うべきものも、面白い。
独身時代、展覧会に行く約束をしていて、澁澤が寝ていてすっぽかしたときの言葉は
「だって、この宇宙はぼくを中心に回っているから、これからもずっとそうだよ。そんなことで怒るのはおかしいよ」
また、
「おまえと俺の知識の差って1万対1ぐらいじゃないの」とか
「おまえがもっと白痴ならいい」
なんてしゃあしゃあと言ってのけるところが面白い!
堀川弘通監督の「琴の爪」を見た。1957年。
真山青果の『元禄忠臣蔵』「大石最後の一日」より。
討ち入り50日後からの義士たちを描く。
世間では仇討ちが流行していたりする。
沙汰があるまでの揺れる心情と、武士としての矜持がせめぎあう義士たちの葛藤。
「ひょっとしたら命は助かるのでは?」という希望もわくなかで、若き磯貝十郎左衛門(中村扇雀)は、武士としての潔い死を覚悟していた。彼には祝言を控えた、おみの(扇千景。可憐!)という女性がいた。「計略のために偽りの縁を結んだ」と言う磯貝。「一目会って気持ちを知りたい」と男装して磯貝に接触をはかる、おみの。おみのの男装を見抜いて、いったんは磯貝とのコンタクトを拒否した大石だったが、一転、おみのを磯貝に会わせる。
そこでも磯貝は態度を変えない。しかし、実は、というお馴染みのお話。
戦争に参加しておいて、裁かれる段になってまさか死罪にはならないだろう、なんて楽観している「貝になりたい」男などとは大違いだ。
『不気味で素朴な囲われた世界』、「善良な兵士シュヴェイク」
2008年12月4日 読書西尾維新の『不気味で素朴な囲われた世界』を読んだ。
先日読んだ『きみとぼくの壊れた世界』のシリーズ、と言っても、登場人物はほとんど重なっていない。探偵役の苗字が「病院坂」なのが共通で、前作の探偵役の親戚、という設定。
時計塔で起こった殺人。
やはり、トリックは単純で、コナン以下。主眼はそこにないのだから、なんとも批判しようがないが、これは作者の逃げなのかもしれないな、と感じた。
前作では話題だけだった「操り」が本作では導入されている。
前作からの引用で説明すると、
「犯罪に手を染めた実行犯の背後に、彼らを操り、犯行を実行せしめた『真の』犯人がいた」と、いう真相のこと。
これも作者の悪意がガンガン感じられる。なぜなら、操りの部分は「そんなこと言い出したら、何でも言えるじゃないか」と、言いたくなるようなもので、唐突なこじつけとも、蛇足ともとれる内容だったからだ。多くのミステリで操りを導入しているが、それらを嘲笑うかのごとき内容なのだ。
なぜそんな殺人トリックを用いたのか、という説明も人をくっている。それを言い出したら、何でもできるじゃないか、という裏技。かつて高木彬光の長編推理小説で、犯人が明かされ、さて、その殺人の動機は何かという段になって、「犯人は実は殺人狂だったのです」で説明が終わっている作品があった。そのときのガッカリを思い出した。脳みその構造が違うことを根拠に持ち出して説明されるのは、最初から納得させるつもりがない態度だからだ。人間はそう簡単には殺しなどしない、というのがミステリの前提である。たとえば、つまさきを角にぶつけてムシャクシャしてたから人でも殺してスッキリしようとした、なんてことを殺人の動機にされたって、実際にはありえても、ミステリという人間の知性と理性に信頼をおく小説では説明になっていない。本作では、あくまでも本格推理に対するアンチを提示しているので、本格推理の構造を借りて、決して納得できるはずのない解決を示して、本格推理のファンを嘲笑っているのである。
それと、前作も本作も、将棋が作中で象徴的に使われているが、将棋ファンが見たら、首をかしげる場面がある。将棋を会話にからめるやり方があまりにも稚拙で、将棋好きなら絶対にしない間違いもしているのだ。作者は将棋の初心者なのかな、とも思ったが、将棋をちょっと知っている程度で小説に使うほど、作家というのは安易な職業ではないはずだ。作者は将棋を小説内にとりこみながら、その実、将棋のことを嫌い、憎みぬいているにちがいない。やはり、悪意に満ちている。
本格推理と将棋が好きな僕にとっては、大切なものをけなされているような作品なのだが、読んでいて面白いのは否定できないなあ。悪意に満ちている、ということは、本格推理なり将棋なりに対して、無知ではありえない立場だから、まだ自虐の楽しさが残されているのだ。
イジー・トルンカの「善良な兵士シュヴェイク」コニャックの巻、列車騒動の巻、堂々めぐりの巻を見た。
兵隊の動きは人形アニメにはもってこいで、人形アニメにする理由もよくわかる。
一番面白かったのは、方向音痴で道に迷ったシュヴェイクをスパイだと思い込んで厳しい訊問をする「堂々めぐりの巻」で、これは原作を読めばもっと楽しめそうだな、と感じた。中学生の頃から、何度も読むチャンスがあったのに、ぜんぜん読んでいない怠慢がツケとして今めぐってきた。
先日読んだ『きみとぼくの壊れた世界』のシリーズ、と言っても、登場人物はほとんど重なっていない。探偵役の苗字が「病院坂」なのが共通で、前作の探偵役の親戚、という設定。
時計塔で起こった殺人。
やはり、トリックは単純で、コナン以下。主眼はそこにないのだから、なんとも批判しようがないが、これは作者の逃げなのかもしれないな、と感じた。
前作では話題だけだった「操り」が本作では導入されている。
前作からの引用で説明すると、
「犯罪に手を染めた実行犯の背後に、彼らを操り、犯行を実行せしめた『真の』犯人がいた」と、いう真相のこと。
これも作者の悪意がガンガン感じられる。なぜなら、操りの部分は「そんなこと言い出したら、何でも言えるじゃないか」と、言いたくなるようなもので、唐突なこじつけとも、蛇足ともとれる内容だったからだ。多くのミステリで操りを導入しているが、それらを嘲笑うかのごとき内容なのだ。
なぜそんな殺人トリックを用いたのか、という説明も人をくっている。それを言い出したら、何でもできるじゃないか、という裏技。かつて高木彬光の長編推理小説で、犯人が明かされ、さて、その殺人の動機は何かという段になって、「犯人は実は殺人狂だったのです」で説明が終わっている作品があった。そのときのガッカリを思い出した。脳みその構造が違うことを根拠に持ち出して説明されるのは、最初から納得させるつもりがない態度だからだ。人間はそう簡単には殺しなどしない、というのがミステリの前提である。たとえば、つまさきを角にぶつけてムシャクシャしてたから人でも殺してスッキリしようとした、なんてことを殺人の動機にされたって、実際にはありえても、ミステリという人間の知性と理性に信頼をおく小説では説明になっていない。本作では、あくまでも本格推理に対するアンチを提示しているので、本格推理の構造を借りて、決して納得できるはずのない解決を示して、本格推理のファンを嘲笑っているのである。
それと、前作も本作も、将棋が作中で象徴的に使われているが、将棋ファンが見たら、首をかしげる場面がある。将棋を会話にからめるやり方があまりにも稚拙で、将棋好きなら絶対にしない間違いもしているのだ。作者は将棋の初心者なのかな、とも思ったが、将棋をちょっと知っている程度で小説に使うほど、作家というのは安易な職業ではないはずだ。作者は将棋を小説内にとりこみながら、その実、将棋のことを嫌い、憎みぬいているにちがいない。やはり、悪意に満ちている。
本格推理と将棋が好きな僕にとっては、大切なものをけなされているような作品なのだが、読んでいて面白いのは否定できないなあ。悪意に満ちている、ということは、本格推理なり将棋なりに対して、無知ではありえない立場だから、まだ自虐の楽しさが残されているのだ。
イジー・トルンカの「善良な兵士シュヴェイク」コニャックの巻、列車騒動の巻、堂々めぐりの巻を見た。
兵隊の動きは人形アニメにはもってこいで、人形アニメにする理由もよくわかる。
一番面白かったのは、方向音痴で道に迷ったシュヴェイクをスパイだと思い込んで厳しい訊問をする「堂々めぐりの巻」で、これは原作を読めばもっと楽しめそうだな、と感じた。中学生の頃から、何度も読むチャンスがあったのに、ぜんぜん読んでいない怠慢がツケとして今めぐってきた。
北村薫の『野球の国のアリス』を読んだ。
鏡を通って、向こうの世界に入ってしまったアリスが、少年野球に参加する。
向こうの世界では、優勝をめざすトーナメントでなく、負け続けることで次に進出して行く逆の大会が人気だった。エラーや珍プレイばかりに注目が行き、バラエティのようにとらえられているのだ。アリスはそんな弱っちいチームに加入し、強い野球チームと互角に戦えることを証明しようとする。「野球の試合」になるんだ、ということを証明したかったのだ。
アリスをもじった部分もあるけど、トリッキーではなく、ストレートな青春物語になっている。
鏡を通って、向こうの世界に入ってしまったアリスが、少年野球に参加する。
向こうの世界では、優勝をめざすトーナメントでなく、負け続けることで次に進出して行く逆の大会が人気だった。エラーや珍プレイばかりに注目が行き、バラエティのようにとらえられているのだ。アリスはそんな弱っちいチームに加入し、強い野球チームと互角に戦えることを証明しようとする。「野球の試合」になるんだ、ということを証明したかったのだ。
アリスをもじった部分もあるけど、トリッキーではなく、ストレートな青春物語になっている。
薔薇合戦、『きみとぼくの壊れた世界』、『烈剣五郎』
2008年12月2日 読書健康診断。80才くらいの老婆による採血がまさしく恐怖。採血のあと、いつまでも針を抜かずにグリグリするので失神するほど痛かった。1週間たっても内出血のあとは消えない。2度と堺筋本町のあそこでは健康診断を受けない。
成瀬巳喜男監督の「薔薇合戦」を見た。1950年
丹羽文雄原作。
化粧品会社を経営する姉と、2人の妹の話。
化粧品会社が百合化粧品とニゲラ化粧品、と両方が花の名前なのが面白い。それで薔薇合戦なのか。出演しているのが桂木洋子、ときわめて植物的。
ブロバリンを宣伝するアドバルーンがあがっていたりするのが時代を感じさせる。
映画に関する言及も多く、「マイルストン物語」の試写会デートとか、「好きは好きでもシジャン・マレーやシャルル・ボワイエが好きなのと同じ」と言ったり。
クライマックスで、今まで姉のいいなりになっていた妹がこんなことを言う。
「以前の私は姉さんの言い付けどおり、右を向けと言われたら1日中でも右を向いていました。でも今では、どうせ向くとしても自分というものをかわいそうと思うだけ欲がでてきた」
ふむふむ。これとほぼ同じ文句をどこかで聞いたことがあるのだが、思い出せなくて、もどかしい。
西尾維新の『きみとぼくの壊れた世界』加筆修正したというハードカバー版を読んだ。
兄と妹のニア近親相姦。級友殺人。
ミステリ部分で言えば、あまりにも作者が本格推理に興味がないことを露わにしすぎで、困った。殺人らしきものが起こるのだが、死因すらはっきり書いていないのである。また、誰でもが真っ先に考えるトリックがそのまんまトリックとして使われていて逆に驚いた。死んだとたんに、死者は彼らのステージからは退場させられてしまう。かつては死はメッセージであったり、抗議であったり、あてつけだったりすることが出来たが、彼らにとって死は退場でしかないのだ。
こんな文章がある。
世界は問題だらけで、しかも、僕らの周囲にある問題は、消えることも絶えることもないその問題は、いつだって、卑近で、わずらわしいものばかりだ。もっと高尚な問題で悩みたいと思っても、近いところには、卑近で身近な、最近の問題しかないのだった。家族のこと、友達のこと、恋愛のこと、友情のこと、学校のこと。なんて、狭い、世界だろう。そして、そんな狭い世界でも、僕の思いのままにはならない。そこは僕の世界のはずなのに、でもその世界でも、僕は全然神様なんかにはなれないのだ。
どう?
若い人たちは、こんなうだうだとした言い訳を読んで共感しているのかと思うと、情けなくなる。作者の狙いはそこにある。上に引用したような、作者が「ほら、ほら、ここですよ、ここ読まなくちゃ。試験に出ますよ」的注意の喚起で、読者に「きみとぼく」の「世界」の情けなさを提示してみせるのだ。
小沢さとるの『烈剣五郎』全4巻を読んだ。
「冒険王」昭和37年4月〜38年8月号
少年烈風隊の活躍を描く漫画。隊員は、
吹雪五郎(烈剣白吹雪)
草間一平
かげろう藤太
鳥さしの三次
つぶての小源太
かえで(源氏久郎の孫)
三吉
の面々。
話は三部にわかれている。
1部:大砲の図面争奪戦
2部:豊臣家の血筋をひく盲目剣士、烏丸信秀
3部:軍用金のありかを書いた絵図面争奪戦
第1部途中のあらすじをそのまんま引用すると、こんな具合。
吹雪五郎を隊長とする少年烈風隊の5人は、白覆面の忍者の一団「白柄組」のたすけがあって、少年烈風隊の敵、海坊主の源造一味を、やっつけることができた。
だが、味方と思った白柄組は、隊員草間一平の父のつくった大砲の図面をねらう、忍者の一団だったのだ。
江戸にいく少年烈風隊には、白柄組の者がつけていた。隊員の忍者藤太は、尾行者をつぎつぎとたおしていくのだが。
結局、1部では、落雷で絵図面もろとも敵が全滅して終わり。
2部はめくら剣士が死んでしまう。
3部はあっさりと終わり。
「日本の話芸」で藁人形/桂歌丸
江戸落語。鍋の中を見ちゃいけない、と釘をさされるシーンにはぞくっときた。釘はさせない、という噺なんだが。
成瀬巳喜男監督の「薔薇合戦」を見た。1950年
丹羽文雄原作。
化粧品会社を経営する姉と、2人の妹の話。
化粧品会社が百合化粧品とニゲラ化粧品、と両方が花の名前なのが面白い。それで薔薇合戦なのか。出演しているのが桂木洋子、ときわめて植物的。
ブロバリンを宣伝するアドバルーンがあがっていたりするのが時代を感じさせる。
映画に関する言及も多く、「マイルストン物語」の試写会デートとか、「好きは好きでもシジャン・マレーやシャルル・ボワイエが好きなのと同じ」と言ったり。
クライマックスで、今まで姉のいいなりになっていた妹がこんなことを言う。
「以前の私は姉さんの言い付けどおり、右を向けと言われたら1日中でも右を向いていました。でも今では、どうせ向くとしても自分というものをかわいそうと思うだけ欲がでてきた」
ふむふむ。これとほぼ同じ文句をどこかで聞いたことがあるのだが、思い出せなくて、もどかしい。
西尾維新の『きみとぼくの壊れた世界』加筆修正したというハードカバー版を読んだ。
兄と妹のニア近親相姦。級友殺人。
ミステリ部分で言えば、あまりにも作者が本格推理に興味がないことを露わにしすぎで、困った。殺人らしきものが起こるのだが、死因すらはっきり書いていないのである。また、誰でもが真っ先に考えるトリックがそのまんまトリックとして使われていて逆に驚いた。死んだとたんに、死者は彼らのステージからは退場させられてしまう。かつては死はメッセージであったり、抗議であったり、あてつけだったりすることが出来たが、彼らにとって死は退場でしかないのだ。
こんな文章がある。
世界は問題だらけで、しかも、僕らの周囲にある問題は、消えることも絶えることもないその問題は、いつだって、卑近で、わずらわしいものばかりだ。もっと高尚な問題で悩みたいと思っても、近いところには、卑近で身近な、最近の問題しかないのだった。家族のこと、友達のこと、恋愛のこと、友情のこと、学校のこと。なんて、狭い、世界だろう。そして、そんな狭い世界でも、僕の思いのままにはならない。そこは僕の世界のはずなのに、でもその世界でも、僕は全然神様なんかにはなれないのだ。
どう?
若い人たちは、こんなうだうだとした言い訳を読んで共感しているのかと思うと、情けなくなる。作者の狙いはそこにある。上に引用したような、作者が「ほら、ほら、ここですよ、ここ読まなくちゃ。試験に出ますよ」的注意の喚起で、読者に「きみとぼく」の「世界」の情けなさを提示してみせるのだ。
小沢さとるの『烈剣五郎』全4巻を読んだ。
「冒険王」昭和37年4月〜38年8月号
少年烈風隊の活躍を描く漫画。隊員は、
吹雪五郎(烈剣白吹雪)
草間一平
かげろう藤太
鳥さしの三次
つぶての小源太
かえで(源氏久郎の孫)
三吉
の面々。
話は三部にわかれている。
1部:大砲の図面争奪戦
2部:豊臣家の血筋をひく盲目剣士、烏丸信秀
3部:軍用金のありかを書いた絵図面争奪戦
第1部途中のあらすじをそのまんま引用すると、こんな具合。
吹雪五郎を隊長とする少年烈風隊の5人は、白覆面の忍者の一団「白柄組」のたすけがあって、少年烈風隊の敵、海坊主の源造一味を、やっつけることができた。
だが、味方と思った白柄組は、隊員草間一平の父のつくった大砲の図面をねらう、忍者の一団だったのだ。
江戸にいく少年烈風隊には、白柄組の者がつけていた。隊員の忍者藤太は、尾行者をつぎつぎとたおしていくのだが。
結局、1部では、落雷で絵図面もろとも敵が全滅して終わり。
2部はめくら剣士が死んでしまう。
3部はあっさりと終わり。
「日本の話芸」で藁人形/桂歌丸
江戸落語。鍋の中を見ちゃいけない、と釘をさされるシーンにはぞくっときた。釘はさせない、という噺なんだが。
PONBASHI DAYS Vol.13@ディスクピア日本橋〜上方亭講談ライブ〜Saori@destiny@ディスクピア日本橋、スティル・クレイジー、ソウ2、シティ・オブ・ゴッド、「め〜てるの気持ち」
2008年11月29日 読書午後1時からディスクピア日本橋でPONBASHI DAYS Vol.13。
宝城里音
1.MIRAI
2.愛の奇跡
りおん公爵、もっと痛々しいキャラかと思ってたけど、えらくまっとうだった。
M/W
1.ひとさしゆびロマンス
2.ミッドナイトワンダーランド
3.落書き帖
4.最強ヒロイン瞬殺スマイル
「らんらんムー」ってのがいつ見ても面白いな。
MaryDoll
1.渚のシンドバッド
2.tell me
3.baby star
4.ハニーチューン
白の衣装バッチリ。
アイドルは衣装が半分だから、カジュアルな格好だと興趣が殺がれること夥しいのである。
午後2時30分から上方亭で講談。
山内一豊と千代/旭堂南海
妻・千代が手鏡の中に隠しておいた十両で名馬を購入、夫・一豊は流鏑馬の腕前で織田信長に認められる、というお馴染みのエピソード。馬の「あお」が大阪弁でしゃべるのも愉快。
かつては「見てきたような嘘」で本当と嘘の割合が4:6だったのが、歴史の研究が一般にも普及し、師匠の南陵から「史実に忠実に」と言われ、6:4の割合で本当のことを言うようになった、とか。
情け相撲/旭堂南鱗
横綱・谷風の物語。今なら八百長相撲だと騒がれるような内容だが、昔の人は見るところ、感じるところが違っていたんだなあ、と思わせる。僕は横綱審議会とか、八百長を弾劾する立場には、非常に違和感を覚えており、こういう講談の世界での感じ方に近い。ギャーギャーわめきたてる人を見ると、この人たちは本当に相撲が好きなんだろうか、と疑ってしまう。なお、マクラは横綱輪島の伝説について。(ガッツ伝説みたいなもの)
ワッハ上方ライブラリーで桂枝雀のDVD見る。
舟弁慶
かぜうどん
たまに見ると、その面白さに唖然とする。
このときの枝雀を越える落語家が今、いるのかと言われると、首をひねってしまうわけだ。
午後5時30分からディスクピア日本橋でSaori@destinyのインストアライブ。
アルバム「JAPANESE CHAOS」から。10曲入りのアルバムの半分を聞いたことになる。
セットリストはちょっとわからなかったが、こんな感じだったか
シャングリラ、パーフェクトワンダーガール、sakura、ヒカリシンドローム、あと1曲くらい。
エレクトロポップはボーカルの声を変えているため、多くが口パクになる。ならば、歌は本人が歌っていなくても成立するんじゃないか、と思われる。表舞台に立つ人間はステージや雑誌のインタビューなどをこなし、歌担当の人間はえんえんとレコーディングすることも可能なのだ。こういう2人1役って、実際にありそうだ。最近読んだ『キャラクターズ』みたい。
夜からいくつか見に行きたいイベントもあったが、ちょっと節約。
テレビで映画「スティルクレイジー」ブライアン・ギブソン監督。1998年
70年代ロックバンドの再結成ストーリー。70年代ロックが好きな僕にはツボ。
パンクファッションの観客から嘲笑されるグラムなステージが面白い。こういうのは笑おうと思えば笑えるし、すごいと賞賛しようと思えば賞賛できる。きわめて恣意的なものなのだ。
無茶してた全盛時にくらべ、年をとり、時代もかわって、健康志向になり、また、保守的になっていたメンバーたち。そんな彼らにハッパをかける言葉が、タイトルになっている「今でもハジケてるか?」だ。
ボーカルが50才の誕生日を祝うケーキを壁に投げ付けるシーンには考えさせられた。年老いることに苛ついているのだが、実年齢など早く60にでも70にでもなって、想像上の老人を裏切ればいいのに、と僕なら思うな。もうすぐ50才の誕生日を迎える僕は、早く来い来い誕生日、なのだ。
「ソウ2」ダーレン・リン・バウズマン監督。2005年
死を前にしたジグソウが生を粗末に生きている輩に生命の尊さを教えるために死のゲームをしかける「ソウ」。こういう設定は、あってもなくてもいいようなもので、真面目にこの設定を考えると、余計なお世話でしかなく、殺人ゲームの仕掛人が単なるおせっかい野郎に堕してしまう。と、思いつつも、やっぱりジグソウのやってることには違和感ばかりが先立つ。そんな「ソウ」シリーズの第2弾。面白くてグイグイ引き込まれた。
このシリーズの面白さは後ろで糸をひいているのは誰なのか、ということだ。それはジグソウだ、と答えは最初から出ているようなものだが、彼がどこにいるのか、というのが第1弾の眼目で、この第2弾でも、ジグソウの後継者が実は潜んでいた、という真相が明かされる。と、いうことはミステリーで言う「フーダニット」になるわけだが、もちろん、そういう目で見ると、あまりにも穴が多過ぎて、話にならない。単なる謎を解くための殺しあいのゲームだと思ってたら、こいつが犯人だったのか、という意外性がすべてだ。ホラーだと思ってたら、推理小説的結末が用意されていた、という。これが第3弾、第4弾になると、見る方もこの中に映像に示された以外の行動をとっている人間がいるはずだ、という先入観をもって見ることになる。近いうちに「ソウ3」も見る予定だが、そうした期待を上回ることができるかどうかが今から楽しみだ。
「ソウ2」に関して言えば、あまりにも死んでもかまわない登場人物ばかりで、恐怖感が味わえなかった。助かってほしい人物が存在しない。謎を解いて脱出するゲームのはずなのに、みんなバカすぎるのだ。おまけに、謎解きも不十分だ。次の作品で積み残された謎が解明される、ってのが僕の一番嫌いなタイプなのだ。どうせ自分で作った謎を自分で解ききれなかっただけなのだろう、と思ってしまう。
「シティ・オブ・ゴッド」フェルナンド・メイレレス監督。2002年、ブラジル映画。
金と暴力が支配する町。1960年代からのスラムの年代記。
町を牛耳るのが若者と子供だ、というのが悲しい。教育をきちんと受けていなくて文盲が多く、考え方の幼稚さと言ったらない。そんな人間たちばかりだからこそ、金と暴力が蔓延するのだ。
視点のさだまらないカメラに、すぐに命のやりとりをして、コロコロと登場人物が入れ替わる過激さが反映する。
なんとこれが事実に基づいた話だと言うから驚きだ。
金と暴力と薬と煙草と酒。子供と大人の差は、これをおおっぴらにするか隠れてするか、という程の違いなんだろう。
強烈な映画で、これは見てよかった!
奥浩哉の『め〜てるの気持ち』を読んだ。全3巻。
ひきこもりの男が若い義母とセックスして立ち直る物語で、このあらすじだけではまったくの幻想ファンタジーである。こんなバカな話があってたまるか、と思う。義母とセックスするときだけ、情けないひきこもり男がキリッとした好男子になるとか、完全にギャグ漫画なんじゃないだろうか。今夏のコミケで販売された同人誌『ソシオクリティーク/ナツカレ!2008』の記事「ひきこもり作品メッタ斬り!」で斎藤環が「ホントにやったら2度と立ち直れそうにない仕打ち(笑)」とか「はるかアフターケアなさすぎ」と一応発言しているが、それほど辛口では批評していない。やっぱりギャグ漫画だったのか。
宝城里音
1.MIRAI
2.愛の奇跡
りおん公爵、もっと痛々しいキャラかと思ってたけど、えらくまっとうだった。
M/W
1.ひとさしゆびロマンス
2.ミッドナイトワンダーランド
3.落書き帖
4.最強ヒロイン瞬殺スマイル
「らんらんムー」ってのがいつ見ても面白いな。
MaryDoll
1.渚のシンドバッド
2.tell me
3.baby star
4.ハニーチューン
白の衣装バッチリ。
アイドルは衣装が半分だから、カジュアルな格好だと興趣が殺がれること夥しいのである。
午後2時30分から上方亭で講談。
山内一豊と千代/旭堂南海
妻・千代が手鏡の中に隠しておいた十両で名馬を購入、夫・一豊は流鏑馬の腕前で織田信長に認められる、というお馴染みのエピソード。馬の「あお」が大阪弁でしゃべるのも愉快。
かつては「見てきたような嘘」で本当と嘘の割合が4:6だったのが、歴史の研究が一般にも普及し、師匠の南陵から「史実に忠実に」と言われ、6:4の割合で本当のことを言うようになった、とか。
情け相撲/旭堂南鱗
横綱・谷風の物語。今なら八百長相撲だと騒がれるような内容だが、昔の人は見るところ、感じるところが違っていたんだなあ、と思わせる。僕は横綱審議会とか、八百長を弾劾する立場には、非常に違和感を覚えており、こういう講談の世界での感じ方に近い。ギャーギャーわめきたてる人を見ると、この人たちは本当に相撲が好きなんだろうか、と疑ってしまう。なお、マクラは横綱輪島の伝説について。(ガッツ伝説みたいなもの)
ワッハ上方ライブラリーで桂枝雀のDVD見る。
舟弁慶
かぜうどん
たまに見ると、その面白さに唖然とする。
このときの枝雀を越える落語家が今、いるのかと言われると、首をひねってしまうわけだ。
午後5時30分からディスクピア日本橋でSaori@destinyのインストアライブ。
アルバム「JAPANESE CHAOS」から。10曲入りのアルバムの半分を聞いたことになる。
セットリストはちょっとわからなかったが、こんな感じだったか
シャングリラ、パーフェクトワンダーガール、sakura、ヒカリシンドローム、あと1曲くらい。
エレクトロポップはボーカルの声を変えているため、多くが口パクになる。ならば、歌は本人が歌っていなくても成立するんじゃないか、と思われる。表舞台に立つ人間はステージや雑誌のインタビューなどをこなし、歌担当の人間はえんえんとレコーディングすることも可能なのだ。こういう2人1役って、実際にありそうだ。最近読んだ『キャラクターズ』みたい。
夜からいくつか見に行きたいイベントもあったが、ちょっと節約。
テレビで映画「スティルクレイジー」ブライアン・ギブソン監督。1998年
70年代ロックバンドの再結成ストーリー。70年代ロックが好きな僕にはツボ。
パンクファッションの観客から嘲笑されるグラムなステージが面白い。こういうのは笑おうと思えば笑えるし、すごいと賞賛しようと思えば賞賛できる。きわめて恣意的なものなのだ。
無茶してた全盛時にくらべ、年をとり、時代もかわって、健康志向になり、また、保守的になっていたメンバーたち。そんな彼らにハッパをかける言葉が、タイトルになっている「今でもハジケてるか?」だ。
ボーカルが50才の誕生日を祝うケーキを壁に投げ付けるシーンには考えさせられた。年老いることに苛ついているのだが、実年齢など早く60にでも70にでもなって、想像上の老人を裏切ればいいのに、と僕なら思うな。もうすぐ50才の誕生日を迎える僕は、早く来い来い誕生日、なのだ。
「ソウ2」ダーレン・リン・バウズマン監督。2005年
死を前にしたジグソウが生を粗末に生きている輩に生命の尊さを教えるために死のゲームをしかける「ソウ」。こういう設定は、あってもなくてもいいようなもので、真面目にこの設定を考えると、余計なお世話でしかなく、殺人ゲームの仕掛人が単なるおせっかい野郎に堕してしまう。と、思いつつも、やっぱりジグソウのやってることには違和感ばかりが先立つ。そんな「ソウ」シリーズの第2弾。面白くてグイグイ引き込まれた。
このシリーズの面白さは後ろで糸をひいているのは誰なのか、ということだ。それはジグソウだ、と答えは最初から出ているようなものだが、彼がどこにいるのか、というのが第1弾の眼目で、この第2弾でも、ジグソウの後継者が実は潜んでいた、という真相が明かされる。と、いうことはミステリーで言う「フーダニット」になるわけだが、もちろん、そういう目で見ると、あまりにも穴が多過ぎて、話にならない。単なる謎を解くための殺しあいのゲームだと思ってたら、こいつが犯人だったのか、という意外性がすべてだ。ホラーだと思ってたら、推理小説的結末が用意されていた、という。これが第3弾、第4弾になると、見る方もこの中に映像に示された以外の行動をとっている人間がいるはずだ、という先入観をもって見ることになる。近いうちに「ソウ3」も見る予定だが、そうした期待を上回ることができるかどうかが今から楽しみだ。
「ソウ2」に関して言えば、あまりにも死んでもかまわない登場人物ばかりで、恐怖感が味わえなかった。助かってほしい人物が存在しない。謎を解いて脱出するゲームのはずなのに、みんなバカすぎるのだ。おまけに、謎解きも不十分だ。次の作品で積み残された謎が解明される、ってのが僕の一番嫌いなタイプなのだ。どうせ自分で作った謎を自分で解ききれなかっただけなのだろう、と思ってしまう。
「シティ・オブ・ゴッド」フェルナンド・メイレレス監督。2002年、ブラジル映画。
金と暴力が支配する町。1960年代からのスラムの年代記。
町を牛耳るのが若者と子供だ、というのが悲しい。教育をきちんと受けていなくて文盲が多く、考え方の幼稚さと言ったらない。そんな人間たちばかりだからこそ、金と暴力が蔓延するのだ。
視点のさだまらないカメラに、すぐに命のやりとりをして、コロコロと登場人物が入れ替わる過激さが反映する。
なんとこれが事実に基づいた話だと言うから驚きだ。
金と暴力と薬と煙草と酒。子供と大人の差は、これをおおっぴらにするか隠れてするか、という程の違いなんだろう。
強烈な映画で、これは見てよかった!
奥浩哉の『め〜てるの気持ち』を読んだ。全3巻。
ひきこもりの男が若い義母とセックスして立ち直る物語で、このあらすじだけではまったくの幻想ファンタジーである。こんなバカな話があってたまるか、と思う。義母とセックスするときだけ、情けないひきこもり男がキリッとした好男子になるとか、完全にギャグ漫画なんじゃないだろうか。今夏のコミケで販売された同人誌『ソシオクリティーク/ナツカレ!2008』の記事「ひきこもり作品メッタ斬り!」で斎藤環が「ホントにやったら2度と立ち直れそうにない仕打ち(笑)」とか「はるかアフターケアなさすぎ」と一応発言しているが、それほど辛口では批評していない。やっぱりギャグ漫画だったのか。
東西狂言会@東大阪市民会館、『人工庭園』
2008年11月28日 読書
午後6時から東大阪市民会館で東西狂言会。
その前に、ワッハ上方のライブラリーで桂雀々のDVDを見る。
田楽喰い
不動坊
さくらんぼ
「さくらんぼ」は「頭山」面白くない、と言うけれど、面白いよ!
で、東西狂言会。
主催はわが母校(?)、大阪樟蔭女子大学。
以下、番組。
解説「東西狂言会20年の足跡」木村要客員教授
大蔵流狂言「末広かり」茂山千之丞、茂山あきら、木村正雄
和泉流狂言「清水」野村萬、野村万蔵
大蔵流狂言「貰婿」茂山千五郎、茂山千作、茂山千三郎
満員!入場無料とは言え、東大阪市民中心に、狂言を見ようと足を運び、場内が笑いで包まれるというのが素晴らしい。文化力を感じた。
茂山千作(1919年生まれ)、野村萬(1930年生まれ)、両名は人間国宝である。千作の方は立ち上がる際に後見の助けを借りねばならない身体ではあったが、声も通り、衰えは見せない。
なお、今回の番組は、第5回と同じ演目であり、あえて5回めと同じ演目、同じ演者でやってみようという目論みがあったらしい。(演者は同じにならなかった)
読んだ本は横尾忠則の『人工庭園』
横尾の絵画、イラストレーション等作品と、エッセイ。新聞連載のもので、1つ1つが短いので、非常に読みやすい。
以下、目次。
弥勒モーツァルト
宝塚ミューズ神
猫と弥勒菩薩
死の世から生を
米同時多発テロ
突然やってきた雌猫
赤いパワーに興奮
マグリットの謎
自作の複製
死者と蛾
三島由紀夫へ
Y字路
銀幕のスター
画家宣言取り消し宣言
模写こそ絵画創造の原点
富士山は美の化身
描き忘れた「弓張月」
想像の現実化
駅伝と解放感
肯定VS否定
文楽は生命の表現
悪夢とおさらば
魂むしばむ戦争
既成狂言を破った挑戦
不眠解消と意識
限界のない世界
本からの自由
憧れの職業
社会的礼節
京都にひかれる
魂の輝き
心が作った病気
甘党の悦楽
アウトサイダー・アーティスト
「目垢」がついたもの
「複数」の自己
肉体中心の時代
芸術と散歩
能鑑賞は創造行為
源内はバサラ的人間
愛情のこもった装丁
嘘も方便
夏目漱石と偽り
うれしい名作連載
日記の目的は?
創作は真夏に限る
大リーグ開幕戦
歴史的行為の延長戦
60年代の空気
模倣すなわち歴史の継承
死の見えない日常
絵の極意
こころと芸術作品
ぼくの「レジャー」
盆の墓参り
アテネ五輪二題
誠意か義理立てか
出会いを待つ
結婚は天国と地獄
芸術は難しい
あと三日
内なる少年と再会
病気は自己超克の機会
シンドイ世の中
宝塚の舞台芸術
「休養」は難しい
眠りっぱなしのわが家の猫
熊本ブエノスアイレス化計画
こだわりの今昔物語
走るアート
時代に逆行恐れるな
ミスジャッジ
禁を破って制作再開
未完成品
ほとんどが未完成
無常の眼
美とは何か
死を想う習性
ストイックになるな
美術館「冬の時代」
老境からが勝負
子供に帰る
顔音痴
美術の知識
恐怖の爆笑
ミステリーサークル
年を取ること
常識からの脱却
非文明人
旅をするなら
パリにて
久世光彦さん
温泉の効果絶大
自分を信じる
絵葉書供養
持病と向き合う
ピサロとセザンヌ
作品の思想
職業と道楽
自然の中で
読書の記憶
古希を迎えて
大きなテーマ
終わり
全部で105。
石田えりに、何度会っても誰だかわからない(顔音痴)とか、鯛焼きは尻尾まであんこが入っているのはいやだ(甘党の悦楽)とか、鼻毛が気になる(社会的礼節)とか、いろいろ面白い記述があるが、ニューオリンズで開いた個展のときに講演を行い大爆笑をとった話(恐怖の爆笑)はオチも決まって、なかなかうまい。
その前に、ワッハ上方のライブラリーで桂雀々のDVDを見る。
田楽喰い
不動坊
さくらんぼ
「さくらんぼ」は「頭山」面白くない、と言うけれど、面白いよ!
で、東西狂言会。
主催はわが母校(?)、大阪樟蔭女子大学。
以下、番組。
解説「東西狂言会20年の足跡」木村要客員教授
大蔵流狂言「末広かり」茂山千之丞、茂山あきら、木村正雄
和泉流狂言「清水」野村萬、野村万蔵
大蔵流狂言「貰婿」茂山千五郎、茂山千作、茂山千三郎
満員!入場無料とは言え、東大阪市民中心に、狂言を見ようと足を運び、場内が笑いで包まれるというのが素晴らしい。文化力を感じた。
茂山千作(1919年生まれ)、野村萬(1930年生まれ)、両名は人間国宝である。千作の方は立ち上がる際に後見の助けを借りねばならない身体ではあったが、声も通り、衰えは見せない。
なお、今回の番組は、第5回と同じ演目であり、あえて5回めと同じ演目、同じ演者でやってみようという目論みがあったらしい。(演者は同じにならなかった)
読んだ本は横尾忠則の『人工庭園』
横尾の絵画、イラストレーション等作品と、エッセイ。新聞連載のもので、1つ1つが短いので、非常に読みやすい。
以下、目次。
弥勒モーツァルト
宝塚ミューズ神
猫と弥勒菩薩
死の世から生を
米同時多発テロ
突然やってきた雌猫
赤いパワーに興奮
マグリットの謎
自作の複製
死者と蛾
三島由紀夫へ
Y字路
銀幕のスター
画家宣言取り消し宣言
模写こそ絵画創造の原点
富士山は美の化身
描き忘れた「弓張月」
想像の現実化
駅伝と解放感
肯定VS否定
文楽は生命の表現
悪夢とおさらば
魂むしばむ戦争
既成狂言を破った挑戦
不眠解消と意識
限界のない世界
本からの自由
憧れの職業
社会的礼節
京都にひかれる
魂の輝き
心が作った病気
甘党の悦楽
アウトサイダー・アーティスト
「目垢」がついたもの
「複数」の自己
肉体中心の時代
芸術と散歩
能鑑賞は創造行為
源内はバサラ的人間
愛情のこもった装丁
嘘も方便
夏目漱石と偽り
うれしい名作連載
日記の目的は?
創作は真夏に限る
大リーグ開幕戦
歴史的行為の延長戦
60年代の空気
模倣すなわち歴史の継承
死の見えない日常
絵の極意
こころと芸術作品
ぼくの「レジャー」
盆の墓参り
アテネ五輪二題
誠意か義理立てか
出会いを待つ
結婚は天国と地獄
芸術は難しい
あと三日
内なる少年と再会
病気は自己超克の機会
シンドイ世の中
宝塚の舞台芸術
「休養」は難しい
眠りっぱなしのわが家の猫
熊本ブエノスアイレス化計画
こだわりの今昔物語
走るアート
時代に逆行恐れるな
ミスジャッジ
禁を破って制作再開
未完成品
ほとんどが未完成
無常の眼
美とは何か
死を想う習性
ストイックになるな
美術館「冬の時代」
老境からが勝負
子供に帰る
顔音痴
美術の知識
恐怖の爆笑
ミステリーサークル
年を取ること
常識からの脱却
非文明人
旅をするなら
パリにて
久世光彦さん
温泉の効果絶大
自分を信じる
絵葉書供養
持病と向き合う
ピサロとセザンヌ
作品の思想
職業と道楽
自然の中で
読書の記憶
古希を迎えて
大きなテーマ
終わり
全部で105。
石田えりに、何度会っても誰だかわからない(顔音痴)とか、鯛焼きは尻尾まであんこが入っているのはいやだ(甘党の悦楽)とか、鼻毛が気になる(社会的礼節)とか、いろいろ面白い記述があるが、ニューオリンズで開いた個展のときに講演を行い大爆笑をとった話(恐怖の爆笑)はオチも決まって、なかなかうまい。
将棋竜王戦第4局。三連勝している羽生名人がこのままストレートで決めれば、羽生の永世竜王が決定する。なんとしても将棋会館の大盤解説会に行かねば、と思っていたが、NHK衛星の番組で深浦王位が「あと1時間以内に決着がつくでしょう」なんて午後6時前に言ったので、到着時にはもう終わってるか、と判断して、行かず。午後5時から解説会は行われているのだが、番組が4時からの2時間番組だったので、ついついそっちを見てしまったのだ。
実際には形勢が混沌としていたため、見に行っていてもきっと面白かっただろう。
ただ、番組での深浦VS山崎の解説が滅法面白かったので、見逃す手はなかった。
結果は、渡辺竜王が一矢を報いた。
次の解説会には足を運ぶか。
読んだ本は東浩紀と桜坂洋の合作『キャラクターズ』
東浩紀が主人公の小説で、もともとは桜坂が小説を書き、東が評論、という分担だった(という設定)がどんどん崩れて、お互いが主導権をとろうとして話は混沌とし、東のキャラクターはラカン的に3人に分裂する。
結局、なぜか朝日新聞社を焼き、2ちゃんねるのひろゆきを殺しに行くことになる。
むちゃくちゃである。
ラスト近く、東は思う。
「ぼくには同志もいなければ、味方もいない。この身からあふれる言葉たちがあるだけだ」
それは最初からわかっている出発点のはずなのに、ラスト近くにいたって念をおすようなこの述懐。同志や仲間や味方や敵、なんてものが存在している、という夢をみた、というのがこの小説の中身だから、これってつまるところ、夢オチ?
実際には形勢が混沌としていたため、見に行っていてもきっと面白かっただろう。
ただ、番組での深浦VS山崎の解説が滅法面白かったので、見逃す手はなかった。
結果は、渡辺竜王が一矢を報いた。
次の解説会には足を運ぶか。
読んだ本は東浩紀と桜坂洋の合作『キャラクターズ』
東浩紀が主人公の小説で、もともとは桜坂が小説を書き、東が評論、という分担だった(という設定)がどんどん崩れて、お互いが主導権をとろうとして話は混沌とし、東のキャラクターはラカン的に3人に分裂する。
結局、なぜか朝日新聞社を焼き、2ちゃんねるのひろゆきを殺しに行くことになる。
むちゃくちゃである。
ラスト近く、東は思う。
「ぼくには同志もいなければ、味方もいない。この身からあふれる言葉たちがあるだけだ」
それは最初からわかっている出発点のはずなのに、ラスト近くにいたって念をおすようなこの述懐。同志や仲間や味方や敵、なんてものが存在している、という夢をみた、というのがこの小説の中身だから、これってつまるところ、夢オチ?
鯨統一郎の『異譚・千早振る』を読んだ。
落語のネタにカデンツァつけたような作品群。
以下、目次。
第1部 殿の熊
異譚・粗忽長屋
異譚・千早振る
異譚・湯屋番
第2部 陰の符合
異譚・長屋の花見
異譚・まんじゅう怖い
異譚・道具屋
異譚・目黒のさんま
異譚・時そば
落語の部分はほとんどが落語通り。だが、その裏には徳川幕府が倒壊し、明治維新への道を歩むきっかけが隠されていたのだ。
たとえば。
井伊直弼を大老に推すかどうかの判断で、推さないとの決断を告げる伝言が「酒に茶柱が立っていたら推すことにする」つまり、そんなことはまずないから、推さない、というメッセージになるはずだったのが、「長屋の花見」をしたがために、酒に茶柱が立つ、異常事態が実現してしまったのだ。そのせいで井伊は大老になり、結果として徳川幕府に対する反感を煽ってしまった。
また、平将門の呪いを解く呪文「お茶がこわい」は、そんなことを言う状況などありえない、と思って考えられたはずなのに、「まんじゅう怖い」のおかげで、呪いが解かれてしまう。
皇女和宮の降嫁をきめるメッセージを「窓の値をきく者がおれば、降嫁」と決め、そんな取り決めを知らない人間によって「道具屋」で窓の値をきくことになる。
などなど。
落語のサゲの部分を、歴史の転換のきっかけとなった隠密への伝言間違いとする趣向。
小手先の技術で書かれた作品としか言い様がないのだが、こういうのが、けっこう好きなのだ。
落語のネタにカデンツァつけたような作品群。
以下、目次。
第1部 殿の熊
異譚・粗忽長屋
異譚・千早振る
異譚・湯屋番
第2部 陰の符合
異譚・長屋の花見
異譚・まんじゅう怖い
異譚・道具屋
異譚・目黒のさんま
異譚・時そば
落語の部分はほとんどが落語通り。だが、その裏には徳川幕府が倒壊し、明治維新への道を歩むきっかけが隠されていたのだ。
たとえば。
井伊直弼を大老に推すかどうかの判断で、推さないとの決断を告げる伝言が「酒に茶柱が立っていたら推すことにする」つまり、そんなことはまずないから、推さない、というメッセージになるはずだったのが、「長屋の花見」をしたがために、酒に茶柱が立つ、異常事態が実現してしまったのだ。そのせいで井伊は大老になり、結果として徳川幕府に対する反感を煽ってしまった。
また、平将門の呪いを解く呪文「お茶がこわい」は、そんなことを言う状況などありえない、と思って考えられたはずなのに、「まんじゅう怖い」のおかげで、呪いが解かれてしまう。
皇女和宮の降嫁をきめるメッセージを「窓の値をきく者がおれば、降嫁」と決め、そんな取り決めを知らない人間によって「道具屋」で窓の値をきくことになる。
などなど。
落語のサゲの部分を、歴史の転換のきっかけとなった隠密への伝言間違いとする趣向。
小手先の技術で書かれた作品としか言い様がないのだが、こういうのが、けっこう好きなのだ。
大庭武年探偵小説選1
2008年11月20日 読書
『大庭武年探偵小説選1』を読んだ。
大庭武年は1904年生まれ。
本書に収められた小説は1930年から1933年にかけて発表されたものだ。郷警部が事件を推理する本格推理を中心に選んである。
本格推理を書いているが、解説によると、作者は推理小説を余技として書いており、本当は純文学の書き手なのだそうだ。
そう言えば、と思い当たるふしもある。
推理があくまでも推理でしかないことを探偵役の郷警部は言う。
「牧師服の男」のラストはこんな風。
郷警部は語り終えると、自信の籠った朗らかな笑い声をたててから言った。
「しかしみなさん、もう少したてば、いずれこの僕の杜撰な推理を是正する、真実の自白が聞かれるでしょう。まァお互いにそれをたのしみましょう」
自信のなせるわざか、いやみか、謙遜か。
いずれにしても、自分の推理こそ正解だとあえて言い切らない名探偵は珍しい。
以下、目次順に簡単な覚え書き。未読の人はまず、読んでから。
「十三号室の殺人」
第1章 二人の客
第2章 ジョン・ウィリアム
第3章 第十三号室
第4章 二重人格
第5章 惨劇
第6章 フリッツの検挙
第7章 訊問
第8章 ピストルと非常梯子
第9章 郷警部
第10章 論争
第11章 調査
第12章 物置と灰皿
第13章 蜘蛛の糸
第14章 参考人の審問
第15章 フリッツの告白書
第16章 第三十六号室
第17章 蜘蛛の糸の謎
第18章 背広の釦
第19章 事件の解決(1)
第20章 事件の解決(2)
第21章 警部の推理
第22章 キレアージ
第23章 デリケエトな問題
二重人格のマリヤと精神錯乱のフリッツのカップル。
マリヤは密室内で銃で撃たれ、死の直前に20メートル以上移動していた!
犯人の特定は、廊下に張られた蜘蛛の糸が決め手になった。事件に無関係な従業員が、衣服に蜘蛛の糸をつけたままなのがわかる。逃走する犯人が切るはずの蜘蛛の糸テープを、別人が切ったということは、犯人は現場から蜘蛛の糸がはってあった場所までの部屋に宿泊している人間なのだ。
二重人格は実は双子だった。
「競馬会前夜ー郷警部手記の探偵記録」
厩舎の馬を殺害し、自殺した犯人。
と、思いきや。
自殺死体を発見した馬主が、賭け金損失をのがれ、保険金を手にいれるため、馬を射殺したのだ。
「ポプラ荘の事件」
蓄音機の回転によって凶器を引っ張って隠す。
「牧師服の男」
牧師になりすました犯人。牧師は見えない人になって顔を記憶されなかった。
「海浜荘の惨劇」
第1章 惨劇
第2章 廃港市R
第3章 事件現場へ
第4章 屍体検案
第5章 家族
第6章 養女の幼名
第7章 可能犯人
第8章 訊問
第9章 靴跡
第10章 ハミルトン家の暗流
第11章 電話の中の会話
第12章 ブロウニング・三号型
第13章 その時の事情
第14章 発動機の爆音
第15章 町の古記録
第16章 告白
第17章 最後の鍮
第18章 一人の拘除
第19章 精神分析
第20章 大団円
潮の干満によって機械的殺害。
ダイイングメッセージ「Lil」は犯人の名前ではなく、殺害方法に関するものだった。
「リル」がダイイングメッセージだなんて、宍戸留美ちゃんはどう思うか。(愛犬の名前)
「旅客機事件」
飛行機内に撲殺死体、凶器見つからず。
いたはずのもう一人の客は墜落死していた。
犯人は副操縦士なのか?
さて、真相は。
部品が飛んで事故で死んだ客。
その客の金を盗んで、パラシュートで逃げようとした男。パラシュート開かず死亡。
墜落死体を見つけ、金を盗んだ農民。
大庭武年は1904年生まれ。
本書に収められた小説は1930年から1933年にかけて発表されたものだ。郷警部が事件を推理する本格推理を中心に選んである。
本格推理を書いているが、解説によると、作者は推理小説を余技として書いており、本当は純文学の書き手なのだそうだ。
そう言えば、と思い当たるふしもある。
推理があくまでも推理でしかないことを探偵役の郷警部は言う。
「牧師服の男」のラストはこんな風。
郷警部は語り終えると、自信の籠った朗らかな笑い声をたててから言った。
「しかしみなさん、もう少したてば、いずれこの僕の杜撰な推理を是正する、真実の自白が聞かれるでしょう。まァお互いにそれをたのしみましょう」
自信のなせるわざか、いやみか、謙遜か。
いずれにしても、自分の推理こそ正解だとあえて言い切らない名探偵は珍しい。
以下、目次順に簡単な覚え書き。未読の人はまず、読んでから。
「十三号室の殺人」
第1章 二人の客
第2章 ジョン・ウィリアム
第3章 第十三号室
第4章 二重人格
第5章 惨劇
第6章 フリッツの検挙
第7章 訊問
第8章 ピストルと非常梯子
第9章 郷警部
第10章 論争
第11章 調査
第12章 物置と灰皿
第13章 蜘蛛の糸
第14章 参考人の審問
第15章 フリッツの告白書
第16章 第三十六号室
第17章 蜘蛛の糸の謎
第18章 背広の釦
第19章 事件の解決(1)
第20章 事件の解決(2)
第21章 警部の推理
第22章 キレアージ
第23章 デリケエトな問題
二重人格のマリヤと精神錯乱のフリッツのカップル。
マリヤは密室内で銃で撃たれ、死の直前に20メートル以上移動していた!
犯人の特定は、廊下に張られた蜘蛛の糸が決め手になった。事件に無関係な従業員が、衣服に蜘蛛の糸をつけたままなのがわかる。逃走する犯人が切るはずの蜘蛛の糸テープを、別人が切ったということは、犯人は現場から蜘蛛の糸がはってあった場所までの部屋に宿泊している人間なのだ。
二重人格は実は双子だった。
「競馬会前夜ー郷警部手記の探偵記録」
厩舎の馬を殺害し、自殺した犯人。
と、思いきや。
自殺死体を発見した馬主が、賭け金損失をのがれ、保険金を手にいれるため、馬を射殺したのだ。
「ポプラ荘の事件」
蓄音機の回転によって凶器を引っ張って隠す。
「牧師服の男」
牧師になりすました犯人。牧師は見えない人になって顔を記憶されなかった。
「海浜荘の惨劇」
第1章 惨劇
第2章 廃港市R
第3章 事件現場へ
第4章 屍体検案
第5章 家族
第6章 養女の幼名
第7章 可能犯人
第8章 訊問
第9章 靴跡
第10章 ハミルトン家の暗流
第11章 電話の中の会話
第12章 ブロウニング・三号型
第13章 その時の事情
第14章 発動機の爆音
第15章 町の古記録
第16章 告白
第17章 最後の鍮
第18章 一人の拘除
第19章 精神分析
第20章 大団円
潮の干満によって機械的殺害。
ダイイングメッセージ「Lil」は犯人の名前ではなく、殺害方法に関するものだった。
「リル」がダイイングメッセージだなんて、宍戸留美ちゃんはどう思うか。(愛犬の名前)
「旅客機事件」
飛行機内に撲殺死体、凶器見つからず。
いたはずのもう一人の客は墜落死していた。
犯人は副操縦士なのか?
さて、真相は。
部品が飛んで事故で死んだ客。
その客の金を盗んで、パラシュートで逃げようとした男。パラシュート開かず死亡。
墜落死体を見つけ、金を盗んだ農民。
『変transcape』
2008年11月19日 読書
米澤敬の『変 transcape』を読んだ。
以下、目次。
1、変
01、蒐集の魔
02、夢の途中
03、乱神の貌
04、空の絡繰
05、畸人の徽
06、身中の蟲
07、砦の残照
08、愛の暴走
2、甲蟲事物
01、雨と森
02、鬱金香
03、潜水艇
04、海象
05、貯古齢糖
06、銀の鎚
07、猿
08、虫と名前
09、書物
10、数
11、金剛石
12、道
13、林檎
14、屍体
3、月次帖
00、花札事件
01、睦月 鶴になった鸚鵡
02、如月 春告鳥と異国の香り
03、弥生 枯れ木に花を
04、卯月 時の鳥と不時の花
05、皐月 いずれ菖蒲か杜若
06、水無月 胡蝶の夢、牡丹の幻
07、文月 七尽くし
08、葉月 別世界の使者たち
09、長月 不老長寿の花の宴
10、神無月 紅葉の山で占う
11、霜月 真冬の五月雨
12、極月 終わり良ければ
仕舞の記
牛若丸発行の本書は、何よりも造本装丁で遊んでいて楽しい。不思議な素材、本文と図版が半々の構成、さらにページのノンブルが素数のときだけアホになる芸などなど。
巻末に牛若丸の本の言葉が書いてある。最初にあげられたのは、こんな文。
「楽しく明るい玩具としての本」
本は暗いおもちゃだ、とでも言いたくなりそうなところ、逆をついてきたか、と思った。
さて、本書の内容。
「1、変」では変態、永久機関、畸人、寄生虫、革命、恋などのコレクション。
「2、甲蟲事物」はザ・ビートルズにまつわる随想。
「3、月次帖」は花札考。
内容は、たとえば
「(小乗仏教の経量部が説いた)『過未無体説』が唯識経由で輸入されたとき、あらためてリダンダンシーの高い日本語の構造によって規定されて『うつろい』や『はかなさ』といった概念に変質していったのかもしれない」
とか、
「『みち』の『ち』はまた、『おろち』や『いのち』の『ち』と同様に魂魄をあらわす。そんな『道』に出ることが、すなわち漂泊や巡礼である」
など、工作舎っぽさ全開である。
本文と同じだけの分量をもつ図版にはそれぞれキャプションがついているが、これがキャプションアートというかキャプション文学になっていて面白い。
たとえば、式亭三馬『阿古義物語』の欧文組みを真似た扉ページが載った箇所では、
「欧米人が、でたらめな漢字を使ったTシャツを着る感覚にも通じる」とある。
また、バーネットによる北極点の穴の図版には
「極北・極南幻想は一方でエドガー・アラン・ポーとなり、他方でナチスになった」とある。
作者が楽しみながら考えて書いている様子が感じとれて、すごくうらやましくなってくる。
読んだ漫画はSABEの『阿佐谷腐れ酢学園エマニエル編』
ブルマだウンコだおふろだペンギンだ鹿だでもやっぱりブルマだ。
SABEに駄作なし!何を読んでも面白い!
だって、ブルマが描かれているから!
以下、目次。
1、変
01、蒐集の魔
02、夢の途中
03、乱神の貌
04、空の絡繰
05、畸人の徽
06、身中の蟲
07、砦の残照
08、愛の暴走
2、甲蟲事物
01、雨と森
02、鬱金香
03、潜水艇
04、海象
05、貯古齢糖
06、銀の鎚
07、猿
08、虫と名前
09、書物
10、数
11、金剛石
12、道
13、林檎
14、屍体
3、月次帖
00、花札事件
01、睦月 鶴になった鸚鵡
02、如月 春告鳥と異国の香り
03、弥生 枯れ木に花を
04、卯月 時の鳥と不時の花
05、皐月 いずれ菖蒲か杜若
06、水無月 胡蝶の夢、牡丹の幻
07、文月 七尽くし
08、葉月 別世界の使者たち
09、長月 不老長寿の花の宴
10、神無月 紅葉の山で占う
11、霜月 真冬の五月雨
12、極月 終わり良ければ
仕舞の記
牛若丸発行の本書は、何よりも造本装丁で遊んでいて楽しい。不思議な素材、本文と図版が半々の構成、さらにページのノンブルが素数のときだけアホになる芸などなど。
巻末に牛若丸の本の言葉が書いてある。最初にあげられたのは、こんな文。
「楽しく明るい玩具としての本」
本は暗いおもちゃだ、とでも言いたくなりそうなところ、逆をついてきたか、と思った。
さて、本書の内容。
「1、変」では変態、永久機関、畸人、寄生虫、革命、恋などのコレクション。
「2、甲蟲事物」はザ・ビートルズにまつわる随想。
「3、月次帖」は花札考。
内容は、たとえば
「(小乗仏教の経量部が説いた)『過未無体説』が唯識経由で輸入されたとき、あらためてリダンダンシーの高い日本語の構造によって規定されて『うつろい』や『はかなさ』といった概念に変質していったのかもしれない」
とか、
「『みち』の『ち』はまた、『おろち』や『いのち』の『ち』と同様に魂魄をあらわす。そんな『道』に出ることが、すなわち漂泊や巡礼である」
など、工作舎っぽさ全開である。
本文と同じだけの分量をもつ図版にはそれぞれキャプションがついているが、これがキャプションアートというかキャプション文学になっていて面白い。
たとえば、式亭三馬『阿古義物語』の欧文組みを真似た扉ページが載った箇所では、
「欧米人が、でたらめな漢字を使ったTシャツを着る感覚にも通じる」とある。
また、バーネットによる北極点の穴の図版には
「極北・極南幻想は一方でエドガー・アラン・ポーとなり、他方でナチスになった」とある。
作者が楽しみながら考えて書いている様子が感じとれて、すごくうらやましくなってくる。
読んだ漫画はSABEの『阿佐谷腐れ酢学園エマニエル編』
ブルマだウンコだおふろだペンギンだ鹿だでもやっぱりブルマだ。
SABEに駄作なし!何を読んでも面白い!
だって、ブルマが描かれているから!
文学の断層〜セカイ震災キャラクター〜
2008年11月13日 読書斎藤環の『文学の断層〜セカイ震災キャラクター〜』を読んだ。
以下目次
序
#0「虚構」と「現実」の相互隠蔽
はじめに
レピッシュなサブカルチャー
虚構スタイルの構造的変遷
メタリアル・フィクションの時代
匿名性と虚構性
第1章 キャラクター
#1キャラクターと作家の自意識
清涼院流水から西尾維新へ
流水大説
ミステリーとシニシズム
西尾維新の小説システム
#2メタ・キャラクター・メタボリズム
ありえないリアル
キャラクターから物語へ
キャラクターにおける「隠喩」と「換喩」
メタ・リアリズムの不可能性
名前が支配する「世界」
第2章 棲み分ける「小説」
#3オンライン小説、あるいは文化的誤受信による三幅対
ベストセラーが象徴する「文化」
『Deep Love』とヤンキー文化
『いま、会いにゆきます』とサブカル文化
『電車男』と「おたく文化」
棲みわける三つの「文化」
投瓶通信から振り込め詐欺へ
想像的誤配、象徴的誤配
「誤受信可能性」の問題
第3章 家族
#4カーネーションよりも紅いバラを
家族=母親の疎外
「物語の欠如」への苛立ち
「母の呪縛」からの逃走
母性のしくみ
若者は「母なき世界」を浮遊する
第4章 戦争とニート
#5「中景」を喪くした「セカイ」
『宇宙戦争』と「セカイ系」
『バトル・ロワイヤル』の多重人格性
視点としての「となり町」、あるいは軍用犬
微生物とフリークス
#6なぜ「戦争」は「成長」を描き得ないのか
『君の友だち』における他者
セカイ系の歴史的端緒
舞城のセカイ、西尾のセカイ
他者としての「ニート」
カーニヴァル化とデータベース
『りはめ』のセカイと真理の審級
第5章 震災と文学
#7阪神・淡路大震災と文学
最初の一撃
震災と戦争
トラウマからの風景
「リアル病」
文学の急性的反応
#8遠隔地のトラウマ
災害サブカルチャー
カントとリスボン地震
震災と「転向」
震災と書くこと
#9言葉・空間・祈り
関東大震災と文学
リアリティの位相
清涼院流水
井上廣子の転向
「心理学化」の水位
村上春樹における「空間」
多重化する世界と解離のモチーフ
空間と祈り
第2章でのヤンキー文化、サブカル文化、おたく文化の話が興味深かったが、どれもこれも「文化」に安住してそれを享受しようとしているうちは、みんな同じ穴のムジナなのである。
また、ケータイ小説にみられる振り込め詐欺的「誤配の余地の無さ」、本文中で言う「送り手の意図いかんにかかわらず、想像的に正しい宛先に届いてしまう手紙」すなわち語受信可能性という新しい不確実性についての下りが興味深い。ちなみに、2008年7月30日第一刷では、このあたりの目次の小見出しが「想像的誤配、象徴的誤記」(正しくは「誤記」でなく「誤配」)とまさしく誤記されて誤配されているのが何かの陰謀のようである。
また、本書で端緒についたと思われる「震災」の考察は今後の展開が楽しみだ。
明らかに、僕は阪神大震災を境に変わってしまったし、勝手にいろんな啓示を受け取り、生き方が変わった。かつて「戦後」という言葉が意味をもっていたように、僕にははっきりと「震後」が生きている。「もはや震後ではない」と言うことができるのはいったいいつの日になることやら。
NHK-FMで第77回日本音楽コンクール − 作曲部門オーケストラ作品・本選会 −
入選「天と光と」 森川陽子・作曲
(16分07秒)
(フルート)木ノ脇道元
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
第3位「アルベルト・ジャコメッティの“鼻”による変奏曲」
大胡 恵・作曲
(8分13秒)
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
第2位「“ルーン”オーケストラのための」 江原大介・作曲
(11分39秒)
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
第1位「レ・フレオ」 江原 修・作曲
(11分28秒)
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
〜東京オペラシティ・コンサートホールで収録〜
<2008/10/21>
以下、76回日本音楽コンクール − 作曲部門室内楽作品・本選会 −
「パレットの上で奏でるグラデーション」 前田恵実・作曲
(9分57秒)
(オーボエ)浅間 信慶
(クラリネット)中村 克己
(サクソフォン)大城 正司
(ユーフォニウム)斉藤 充
(チェロ)高田 剛志
(コントラバス)長谷川信久
(指揮)夏田 昌和
「ウェル・クレイドル」 山口恭子・作曲
(11分15秒)
(リコーダー)鈴木 俊哉
(ビオラ)桑田 穣
(パーカッション)伊藤 映子
(バリトン)大久保光哉
(ピアノ)小坂 圭太
(指揮)安良岡章夫
「南国の魚、極彩色の夜」 小出稚子・作曲
(6分56秒)
(バイオリン)梅沢 和人
(クラリネット)重松希巳江
(ピアノ)小坂 圭太
「ピエドラ」 稲森安太己・作曲
(11分16秒)
(ソプラノ)佐竹 由美
(ハープ)井上栄利加
(バイオリン)川口 静華
(ビオラ)甲斐 史子
(チェロ)高田 剛志
(笙)石川 高
(指揮)安良岡章夫
以下目次
序
#0「虚構」と「現実」の相互隠蔽
はじめに
レピッシュなサブカルチャー
虚構スタイルの構造的変遷
メタリアル・フィクションの時代
匿名性と虚構性
第1章 キャラクター
#1キャラクターと作家の自意識
清涼院流水から西尾維新へ
流水大説
ミステリーとシニシズム
西尾維新の小説システム
#2メタ・キャラクター・メタボリズム
ありえないリアル
キャラクターから物語へ
キャラクターにおける「隠喩」と「換喩」
メタ・リアリズムの不可能性
名前が支配する「世界」
第2章 棲み分ける「小説」
#3オンライン小説、あるいは文化的誤受信による三幅対
ベストセラーが象徴する「文化」
『Deep Love』とヤンキー文化
『いま、会いにゆきます』とサブカル文化
『電車男』と「おたく文化」
棲みわける三つの「文化」
投瓶通信から振り込め詐欺へ
想像的誤配、象徴的誤配
「誤受信可能性」の問題
第3章 家族
#4カーネーションよりも紅いバラを
家族=母親の疎外
「物語の欠如」への苛立ち
「母の呪縛」からの逃走
母性のしくみ
若者は「母なき世界」を浮遊する
第4章 戦争とニート
#5「中景」を喪くした「セカイ」
『宇宙戦争』と「セカイ系」
『バトル・ロワイヤル』の多重人格性
視点としての「となり町」、あるいは軍用犬
微生物とフリークス
#6なぜ「戦争」は「成長」を描き得ないのか
『君の友だち』における他者
セカイ系の歴史的端緒
舞城のセカイ、西尾のセカイ
他者としての「ニート」
カーニヴァル化とデータベース
『りはめ』のセカイと真理の審級
第5章 震災と文学
#7阪神・淡路大震災と文学
最初の一撃
震災と戦争
トラウマからの風景
「リアル病」
文学の急性的反応
#8遠隔地のトラウマ
災害サブカルチャー
カントとリスボン地震
震災と「転向」
震災と書くこと
#9言葉・空間・祈り
関東大震災と文学
リアリティの位相
清涼院流水
井上廣子の転向
「心理学化」の水位
村上春樹における「空間」
多重化する世界と解離のモチーフ
空間と祈り
第2章でのヤンキー文化、サブカル文化、おたく文化の話が興味深かったが、どれもこれも「文化」に安住してそれを享受しようとしているうちは、みんな同じ穴のムジナなのである。
また、ケータイ小説にみられる振り込め詐欺的「誤配の余地の無さ」、本文中で言う「送り手の意図いかんにかかわらず、想像的に正しい宛先に届いてしまう手紙」すなわち語受信可能性という新しい不確実性についての下りが興味深い。ちなみに、2008年7月30日第一刷では、このあたりの目次の小見出しが「想像的誤配、象徴的誤記」(正しくは「誤記」でなく「誤配」)とまさしく誤記されて誤配されているのが何かの陰謀のようである。
また、本書で端緒についたと思われる「震災」の考察は今後の展開が楽しみだ。
明らかに、僕は阪神大震災を境に変わってしまったし、勝手にいろんな啓示を受け取り、生き方が変わった。かつて「戦後」という言葉が意味をもっていたように、僕にははっきりと「震後」が生きている。「もはや震後ではない」と言うことができるのはいったいいつの日になることやら。
NHK-FMで第77回日本音楽コンクール − 作曲部門オーケストラ作品・本選会 −
入選「天と光と」 森川陽子・作曲
(16分07秒)
(フルート)木ノ脇道元
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
第3位「アルベルト・ジャコメッティの“鼻”による変奏曲」
大胡 恵・作曲
(8分13秒)
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
第2位「“ルーン”オーケストラのための」 江原大介・作曲
(11分39秒)
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
第1位「レ・フレオ」 江原 修・作曲
(11分28秒)
(管弦楽)東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団
(指揮)小松 一彦
〜東京オペラシティ・コンサートホールで収録〜
<2008/10/21>
以下、76回日本音楽コンクール − 作曲部門室内楽作品・本選会 −
「パレットの上で奏でるグラデーション」 前田恵実・作曲
(9分57秒)
(オーボエ)浅間 信慶
(クラリネット)中村 克己
(サクソフォン)大城 正司
(ユーフォニウム)斉藤 充
(チェロ)高田 剛志
(コントラバス)長谷川信久
(指揮)夏田 昌和
「ウェル・クレイドル」 山口恭子・作曲
(11分15秒)
(リコーダー)鈴木 俊哉
(ビオラ)桑田 穣
(パーカッション)伊藤 映子
(バリトン)大久保光哉
(ピアノ)小坂 圭太
(指揮)安良岡章夫
「南国の魚、極彩色の夜」 小出稚子・作曲
(6分56秒)
(バイオリン)梅沢 和人
(クラリネット)重松希巳江
(ピアノ)小坂 圭太
「ピエドラ」 稲森安太己・作曲
(11分16秒)
(ソプラノ)佐竹 由美
(ハープ)井上栄利加
(バイオリン)川口 静華
(ビオラ)甲斐 史子
(チェロ)高田 剛志
(笙)石川 高
(指揮)安良岡章夫
山田正紀の『私を猫と呼ばないで』を読んだ。
月刊「遊歩人」に連載された20枚の短編群の中からよりすぐられた作品に加筆したものが収められている。
以下、それぞれの作品の覚え書き。
ミステリとしての結構を備えているものがほとんどだが、ポイントはそこになく、女性の心情などを描こうとしているようだ。
いちいち書くのも面倒だが、例によってネタバレするので、未読の人はUターン。
「消えた花嫁」
衆人監視の婚礼舟から花嫁が消えた。昔の田舎であるがゆえの消失劇。
「親孝行にはわけがある」
シングルマザーが息子に親孝行について語る。よく聞いてみれば、息子がシングルマザーにする親孝行ではなく、シングルマザーがその父親にする親孝行の話だった。
「猫と女は会議する」
会議のための会議に疲れるサラリーマン。猫は猫で集まって会議をしている。女は猫を相手に会議する。
「津軽海峡、冬景色」
離婚届を出す日に回想する、二人の出逢いの日の思い出。初々しい恋愛の話が展開されるが、結局その二人は結ばれず、別の女性と出逢ったのが今の離婚相手。
「つけあわせ」
スーパーのベンチで毎日きざみキャベツを食べている女性。彼女を追い払おうとあれこれ口実を設けるが、全部対応されてしまう。
「女はハードボイルド」
ATM強盗相手に反撃する女。バイオレンスアクション!
表紙の宇野亜喜良のイラストレーションは、この話からきている。ガラスの破片を持つ女の子。
「窓の見える天窓」
その女性の語る「窓の見える天窓」の話は、入院患者を安らかな気持で死にのぞませる。
評判だけを聞き、その話の内容がどうしても知ることができない。だが、近いうちに彼女に「窓の見える天窓」がどこなのか、教えてもらえる日が来そうである。
「恋の筑前煮」
商品開発で筑前煮にうちこみ、上司のデートの誘いを断わり続けてしまう女性。
「カゴを抜ける女」
カゴ抜けの知恵比べ。
「スイサイド・ホテル」
誰かに、それとも何かにさよならを言った人たちが集まるスイサイドホテル。
「恋のコンビニ愛のチップス」
コンビニ店員に告白してふられた女。そのときヤケ食いしたポテトチップスに違和感を覚え、失恋したときに食べるポテトチップスの味を探しはじめる。毎日ポテトチップスを買うためにコンビニに通ううち、コンビニ店員好みのぽっちゃりタイプになっていた。
「足りないものは何ですか?」
理想的な家具のレイアウトの部屋。別れるにあたって、家具がどっちのものになるかでもめて、ふたり仲良く家具を探しまわる。
「壁の花にも耳がある」
会社の派閥争いで盗聴まで仕掛けられていた。ある社員は派閥と無関係な派遣社員にスパイを頼むが、ふだん派遣の要望を無視してきたツケが彼にふりかかる。
「私を猫と呼ばないで」
ホテルの8階。情事がバレて逃げる女。逃げる際にいろんな部屋の中で起こっていることを目撃する。危険な恋をする若い男女、自殺を決意する老人、盗聴器を仕掛ける闇金の大物、宝石泥棒、裏切り者。女の機転でそれぞれバラバラな部屋の状況が1つに収斂する。
連載された作品の約半分を捨てて単行本にした、ということである。そう言えば、山田正紀の短編集ではそんな言葉を以前にも聞いたことがある。意外と捨ててしまった作品でも拾う神はいるものである。捨てた分を同人誌とか私家版にでもして出してくれれば、僕なんかはむしろそっちを喜んで読みそうだ。
月刊「遊歩人」に連載された20枚の短編群の中からよりすぐられた作品に加筆したものが収められている。
以下、それぞれの作品の覚え書き。
ミステリとしての結構を備えているものがほとんどだが、ポイントはそこになく、女性の心情などを描こうとしているようだ。
いちいち書くのも面倒だが、例によってネタバレするので、未読の人はUターン。
「消えた花嫁」
衆人監視の婚礼舟から花嫁が消えた。昔の田舎であるがゆえの消失劇。
「親孝行にはわけがある」
シングルマザーが息子に親孝行について語る。よく聞いてみれば、息子がシングルマザーにする親孝行ではなく、シングルマザーがその父親にする親孝行の話だった。
「猫と女は会議する」
会議のための会議に疲れるサラリーマン。猫は猫で集まって会議をしている。女は猫を相手に会議する。
「津軽海峡、冬景色」
離婚届を出す日に回想する、二人の出逢いの日の思い出。初々しい恋愛の話が展開されるが、結局その二人は結ばれず、別の女性と出逢ったのが今の離婚相手。
「つけあわせ」
スーパーのベンチで毎日きざみキャベツを食べている女性。彼女を追い払おうとあれこれ口実を設けるが、全部対応されてしまう。
「女はハードボイルド」
ATM強盗相手に反撃する女。バイオレンスアクション!
表紙の宇野亜喜良のイラストレーションは、この話からきている。ガラスの破片を持つ女の子。
「窓の見える天窓」
その女性の語る「窓の見える天窓」の話は、入院患者を安らかな気持で死にのぞませる。
評判だけを聞き、その話の内容がどうしても知ることができない。だが、近いうちに彼女に「窓の見える天窓」がどこなのか、教えてもらえる日が来そうである。
「恋の筑前煮」
商品開発で筑前煮にうちこみ、上司のデートの誘いを断わり続けてしまう女性。
「カゴを抜ける女」
カゴ抜けの知恵比べ。
「スイサイド・ホテル」
誰かに、それとも何かにさよならを言った人たちが集まるスイサイドホテル。
「恋のコンビニ愛のチップス」
コンビニ店員に告白してふられた女。そのときヤケ食いしたポテトチップスに違和感を覚え、失恋したときに食べるポテトチップスの味を探しはじめる。毎日ポテトチップスを買うためにコンビニに通ううち、コンビニ店員好みのぽっちゃりタイプになっていた。
「足りないものは何ですか?」
理想的な家具のレイアウトの部屋。別れるにあたって、家具がどっちのものになるかでもめて、ふたり仲良く家具を探しまわる。
「壁の花にも耳がある」
会社の派閥争いで盗聴まで仕掛けられていた。ある社員は派閥と無関係な派遣社員にスパイを頼むが、ふだん派遣の要望を無視してきたツケが彼にふりかかる。
「私を猫と呼ばないで」
ホテルの8階。情事がバレて逃げる女。逃げる際にいろんな部屋の中で起こっていることを目撃する。危険な恋をする若い男女、自殺を決意する老人、盗聴器を仕掛ける闇金の大物、宝石泥棒、裏切り者。女の機転でそれぞれバラバラな部屋の状況が1つに収斂する。
連載された作品の約半分を捨てて単行本にした、ということである。そう言えば、山田正紀の短編集ではそんな言葉を以前にも聞いたことがある。意外と捨ててしまった作品でも拾う神はいるものである。捨てた分を同人誌とか私家版にでもして出してくれれば、僕なんかはむしろそっちを喜んで読みそうだ。
山田正紀の『オフェーリアの物語』を読んだ。
以下、目次
序 人形流しの夏
第1話 顔なし人形の謎
第2話 落ちた人形の謎
第3話 消えた人形の謎
オフェーリア言の葉事典
ハイライトをまず。
「顔なし人形の謎」より
「さきほど男女ふたりの遺体が見つかったーと言ったが、代官所の役人が見つけたときには、虫の息ではあったが、まだ男のほうはどうにか息があったらしい。妙なことにな、この者は下帯ひとつの素裸だったという」
「下帯ひとつの素裸、でございますか」
「うむ、なにしろ男女ともに顔がズタズタに切り裂かれていて、誰なのだか見分けがつかぬ、それで代官所の役人は真っ先に、その男に『誰だ』と訊いたそうな。それに男はうなずいて、与吉、と言った。さらに代官所の役人は、誰にやられたのか、とその男に訊いたよ。するとなー」
「はい」
「人形にやられたとそう答えたのだという」
なぬ?
オフェーリアの物語、というタイトルからは思いもよらぬ、この時代劇、捕物帳風の展開は何?時代はどうなっちょる?と翻弄される。これは「銀魂」や「あまつき」みたいな、時代を超越した物語だととらえた方がわかりやすい。
主人公はリアという少女で、オフェーリアという名のビスクドールをもっている。
リアは人形使(にんぎょうし)で、人形のオフェーリアに入り込んで、照座御代(かみおますみよ)と影歩異界(かげあゆむいかい)の両方の世界を視ることができるのだ。巻末に「事典」ができるくらい、多くの造語による幻想的な世界が広がるわけだが、こういうのは山田正紀の十八番だ。おまけに、この物語は、多くの造語に加えて、時代劇風の言葉使いに、薩摩弁、江戸弁のたんかが入り交じり、多様な言葉が縦横無尽に駆け巡る。
(例)
「軍務をてげてげにしたとは許せんこっじゃっどん、村を思う気持ちに免じて、情状を酌量してやろう。ありがたく受けっがよか」
「ご維新を迎えて赤貧にしんにゅうがかかった」
啖呵をきるのは影華という登場人物で、こんな言い回しをする。
「先祖の助六が聞いてあきれるよ。そんなんじゃ、とてものことに花魁たちのキセルの雨は降りませんのさ」
「てめーみてーな薩摩芋のじゅうさんり、三歳の子供でも齧ってらあ。薩摩芋が怖くて往来が歩けるかってんだ」
そのたびにリアは「影華さん、何を言ってんのかさっぱりわかんないよ」
「顔なし人形の謎」では、顔をズタズタに切り裂かれた死体事件が起き、御所人形の顔が切り裂かれていた。
「落ちた人形の謎」では山車の上から落ちた外国人が、地面に落ちたのを見るとなんとそれは人間ではなく、人形に変わっていた、という事件。山車の上には兵士が立哨に立っており、下の者は上で外国人が叫んだのを聞いているのだ。からくり人形を扱っている。(からくりで動いていたので人間だと勘違いした、というような単純なトリックではない)
モルグ街からのアイディアを使っている。
「消えた人形の謎」は、村から人が消えてしまう事件を扱っている。湯が沸いており、硯の墨が濡れている。つい先程まで人がいたはずなのに、数十人の巡査が村を取り囲むなか、全員消えてしまうのだ。例のあの船の応用ですよ。文楽の浄瑠璃人形が扱われている。
どの話も幻想と推理の物語としてよく出来ているが、さらっと描いているので、作者の仕掛けや趣向を流してしまいそうになる。
どうやら、この連作は続編が用意されているらしいが、早く発表してくれないと、もろもろ忘却の彼方である。
以下、目次
序 人形流しの夏
第1話 顔なし人形の謎
第2話 落ちた人形の謎
第3話 消えた人形の謎
オフェーリア言の葉事典
ハイライトをまず。
「顔なし人形の謎」より
「さきほど男女ふたりの遺体が見つかったーと言ったが、代官所の役人が見つけたときには、虫の息ではあったが、まだ男のほうはどうにか息があったらしい。妙なことにな、この者は下帯ひとつの素裸だったという」
「下帯ひとつの素裸、でございますか」
「うむ、なにしろ男女ともに顔がズタズタに切り裂かれていて、誰なのだか見分けがつかぬ、それで代官所の役人は真っ先に、その男に『誰だ』と訊いたそうな。それに男はうなずいて、与吉、と言った。さらに代官所の役人は、誰にやられたのか、とその男に訊いたよ。するとなー」
「はい」
「人形にやられたとそう答えたのだという」
なぬ?
オフェーリアの物語、というタイトルからは思いもよらぬ、この時代劇、捕物帳風の展開は何?時代はどうなっちょる?と翻弄される。これは「銀魂」や「あまつき」みたいな、時代を超越した物語だととらえた方がわかりやすい。
主人公はリアという少女で、オフェーリアという名のビスクドールをもっている。
リアは人形使(にんぎょうし)で、人形のオフェーリアに入り込んで、照座御代(かみおますみよ)と影歩異界(かげあゆむいかい)の両方の世界を視ることができるのだ。巻末に「事典」ができるくらい、多くの造語による幻想的な世界が広がるわけだが、こういうのは山田正紀の十八番だ。おまけに、この物語は、多くの造語に加えて、時代劇風の言葉使いに、薩摩弁、江戸弁のたんかが入り交じり、多様な言葉が縦横無尽に駆け巡る。
(例)
「軍務をてげてげにしたとは許せんこっじゃっどん、村を思う気持ちに免じて、情状を酌量してやろう。ありがたく受けっがよか」
「ご維新を迎えて赤貧にしんにゅうがかかった」
啖呵をきるのは影華という登場人物で、こんな言い回しをする。
「先祖の助六が聞いてあきれるよ。そんなんじゃ、とてものことに花魁たちのキセルの雨は降りませんのさ」
「てめーみてーな薩摩芋のじゅうさんり、三歳の子供でも齧ってらあ。薩摩芋が怖くて往来が歩けるかってんだ」
そのたびにリアは「影華さん、何を言ってんのかさっぱりわかんないよ」
「顔なし人形の謎」では、顔をズタズタに切り裂かれた死体事件が起き、御所人形の顔が切り裂かれていた。
「落ちた人形の謎」では山車の上から落ちた外国人が、地面に落ちたのを見るとなんとそれは人間ではなく、人形に変わっていた、という事件。山車の上には兵士が立哨に立っており、下の者は上で外国人が叫んだのを聞いているのだ。からくり人形を扱っている。(からくりで動いていたので人間だと勘違いした、というような単純なトリックではない)
モルグ街からのアイディアを使っている。
「消えた人形の謎」は、村から人が消えてしまう事件を扱っている。湯が沸いており、硯の墨が濡れている。つい先程まで人がいたはずなのに、数十人の巡査が村を取り囲むなか、全員消えてしまうのだ。例のあの船の応用ですよ。文楽の浄瑠璃人形が扱われている。
どの話も幻想と推理の物語としてよく出来ているが、さらっと描いているので、作者の仕掛けや趣向を流してしまいそうになる。
どうやら、この連作は続編が用意されているらしいが、早く発表してくれないと、もろもろ忘却の彼方である。
AKB48@WTC〜BUG@vijon、『赤い雪』
2008年11月8日 読書午前11時からWTCでAKB48「大声ダイヤモンド」キャンペーンイベント。
若干遅れてはじまったが、出てくるなり「大声ダイヤモンド」を1曲歌ったあとは、とくにトークもなく握手会に入った。
その後、ツリーの点灯式などいろいろあるらしいのだが、握手会の終了まで待っていられないので、歌を聞いたあとは、すぐに四ツ橋まで帰る。
「大声ダイヤモンド」に関しては、CDで聞くのと変わらぬ歌唱力でびっくりした。まるで口パクのような、安定した歌唱。
12時半からclub vijonで「BUG- bring up girls-」
9月のBUGで見逃した前半戦の出演者が今回も出演しているので、やっとのことで補完できるか。
新希咲愛
とは言え、到着時、この子のラストの歌の真っ最中だった。たぶん2曲歌ったと思うが、そんなわけで全貌を知るにいたらず。次回に期待。
宮崎亜美
ドラゴンボールの歌など歌っていた。
いきなり「スーパーサイヤ人です!」など叫んでいて面白い。
この子が出ているというので、帰宅後、NHKの「一期一会」を見た。
大きな夢(アイドル志望)の彼女と、万古焼陶芸の職人で足元の夢をこつこつ叶えようとする女性との出逢い。なのだが、どうも2人の夢が両方の極として対比できるものには思えなかった。陶芸職人は、亜美ちゃんの夢は「それは夢じゃなくて単なるあこがれなんじゃないか」とか「人に夢を与える、と言っているが、今は人に夢を見させてもらっている」とか言ってた。それぞれ、まったくもってその通り、なのだが、それは否定したり改善したりする必要のないことだと思う。あこがれの何が悪い。「人に夢を見させてもらってる」そんな女の子を見ているだけでも、僕は夢を与えてもらっているのだ。個人的に言えば、亜美ちゃんが職人の道を選ばずに、アイドルとしてステージに立ってくれていることに、僕は感謝しているのである。
ただ、アイドルとして付加価値をつけるためには、もうちょっと演出が必要だと思う。衣装や選曲や歌い方など。こんなことを思ったのは、ステージで見た彼女もいいが、テレビで見たメイド姿の彼女にまた違う大きな魅力を感じたからだ。
仲村コニー
1.桃色片想い
2.ラムのラブソング
9月のBUG見に行ったときに、客席にお人形さんのように可愛い子がいるなあ、と感心していたのが、彼女だ。9月のときにステージを見れなくて、ステージはどうなんだろう、とワクワクして見た。
緊張していたようだが、彼女の場合は緊張もまた魅力に転換するマジックがそなわっているようだ。変にスレることなく、まっすぐ育っていってほしいと思う。
雪菜
オリジナルの「ウィル」など歌う。
M/W
1.うしろ指さされ組
2.ひとさし指ロマンス
3.リレーションズ
4.最強○×計画
5.最強ヒロイン瞬殺スマイル
お笑いネタのオタ芸の開拓が課題だとか!
ゲスト枠で出演だが、ゲストの出る前に流れるはずの映像がなかなか準備できなくて、かなり間があいた。この時間のロスが、ラストにいたってアンコールなしの事態を招いた。よかれと思って企画したことがアダになってしまったケース。おまけに、そのとき流れた映像も、このために撮った映像ではなく、今までのライブやテレビ映像のダイジェストで、まだまだ改良の余地がありそうだ。
シャンティ
夏水ericoと春菜ありさの2人組。
「ゼロの使い魔」と「ロザリオとバンパイア」からのアニメソングを歌った。
女子高生2人組といった風情で、かつての「マミホ」をほうふつとさせた。
夏雪
1.浮気なハニーパイ
2.ハレ晴れユカイ
「うどんもいいけど、わたしゃあんたのソバがいい」
「差し歯もいけど、わたしゃあんたが入れ歯いい」
謎かけも。「BUGのお客さんとかけて、クリームシチューととく。その心はあたたかい!」
夏輝ちゃんが水戸黄門に出たこともあわせて、なんだか和風&古風な味付けが面白い。
にゃんパラ
「にゃんパラ」という名前なのに、それには触れず、自分のことをずっと「ゆえ様」(優恵)と呼び続けていた。
キャラ作りがアニメ的で、二次元の世界から降臨した雰囲気。
「恋カナ」では歌詞とびまくり。
Mari7
この前のプラッツのライブで愛梨のステージにゲストで出て来たのが彼女だ。
フェミニンなそのときとは違って、今回はボーイッシュなロッカーのイメージ。
CDに入っているオリジナル「インスピレーション」歌ってるのを聞いて、「あっ、この歌知ってる!プラッツに出てた子だ!」とわかったのだから、女の子は衣装で大きく印象が変わるものだと思い知らされる。
ステージ度胸は満点。
4 leaf clover
1.ダンス
2.ヌーワールド
3.シャイニーロード
4.エンプティワールド
5.カラーオブシーズン
6.恋の魔法
衣装はスリットが深く入ったチャイナ服を脱ぐと、へそ出しルック。
衣装に対する感覚が他の出演者とは違うなあ、と思って出演者リスト見てみたら、ダンスできるのは彼女たちだけなのであった。
ましゅまろチェリーBURGER
1.ペッパー警部
2.恋ing
3.大声ダイヤモンド
DDネタや、「恋ましゅチェリing」とタイトルを言ってみたり、歌詞を替えて歌うのがましゅチェリで流行中。
「大声ダイヤモンド」は途中で音が途切れて、最初から。WTCで待機中に流れた分もあわせると、今日は「大声ダイヤモンド」のヘビーローテーションである。
みりん☆
魔法少女〜おジャ魔女、とマジカルな選曲のあと、
オリジナルのちゅーんラブ。
ちゅーんラブでの顔の横でスタン・ハンセン的猛牛振付けもおなじみ。
前回のプラッツでその兆候はあったが、今回のライブで、僕はすっかりこの「みりん☆」の大ファンになってしまった。
とにかく、何を歌っても、みりん節になるのだ。こんなに個性の突出したアイドルも珍しいのではないか。破壊的な魅力だ。お茶じゃなく水を飲む、というなんだかわからない出来事までもが立派なパフォーマンスになる。
不思議とアーティスト写真に見られるような上目使いの顔よりも、客席からステージ上の彼女を見たときのアングルが、より可愛い。また、客席で他の出演者のライブに乗っている彼女の姿(後ろ姿含む)もめっちゃくちゃ可愛いのだ。
とても気に入ったので、CDや写真でも買えばいいようなものだが、物販で人を押しのけたり、並んだりするのは苦手なのだ。おしゃべりするのも緊張する。シャイなので。また機会があれば、みりん☆グッズを買おう。
日記にヴィヴィアンのオーブが載っていて、野ばら君経由で知った、とか、おジャ魔女(宍戸留美)歌うとか、僕の友達とリンクしているのが、より親しみを覚えさせるのかもしれない。
アズ&咲
1.さくらんぼ
2.笑っちゃおうよボーイフレンド
3.ナイトでないと
おなじみのラインナップでお送りいたしました!
ピヨラビ
1.ゴッドノウズ
2.空色デイズ
3.光のキャンベル
男装の2人組。from東京。
オタ芸に特化しており、ステージ上からmixを発動したり、秋葉原ではやっている「イエローパンチョス」を紹介したり。
ドリームパーティでオタ芸が禁止になるなど、オタ芸粛正のムーブメントに対する、まさに反逆のオタ芸伝道師である。
MarryDoll
1.ラブ&ジョイ
2.ベイビースター
3.テルミー
4.さあ恋人になろう
5.ひまわり〜ハニーチューン
6.ホントのじぶん
これは、ここまで長丁場のライブを見て来たお客さんへの御褒美のようなもの。
でも、1組の持ち時間が30分以内、というのが疲れなくて僕にはちょうどいい。
ライブ終了後の物販はなんだか込み合っていて、回避。
帰りにまんだらけに寄って、安い漫画買う。
読んだ漫画は勝又進作品集『赤い雪』
以下、目次。
桑いちご
木魂
鈴虫坂
袋の草紙
子消し
夢の精
まぼろし
虎次郎河童
雁供養
赤い雪
エッセイ
鯨捕り
雪女
冬の夜遊び
寒造り
解説 呉智英
勝又進自筆年譜
「村(むーらー)の時間(じーかん)の時間(じーかん)がやってまいりました」という感じ。こういう民俗学で扱われるような話は、こういう書き手の存在によって伝わりやすく届くんじゃないか、と思った。
若干遅れてはじまったが、出てくるなり「大声ダイヤモンド」を1曲歌ったあとは、とくにトークもなく握手会に入った。
その後、ツリーの点灯式などいろいろあるらしいのだが、握手会の終了まで待っていられないので、歌を聞いたあとは、すぐに四ツ橋まで帰る。
「大声ダイヤモンド」に関しては、CDで聞くのと変わらぬ歌唱力でびっくりした。まるで口パクのような、安定した歌唱。
12時半からclub vijonで「BUG- bring up girls-」
9月のBUGで見逃した前半戦の出演者が今回も出演しているので、やっとのことで補完できるか。
新希咲愛
とは言え、到着時、この子のラストの歌の真っ最中だった。たぶん2曲歌ったと思うが、そんなわけで全貌を知るにいたらず。次回に期待。
宮崎亜美
ドラゴンボールの歌など歌っていた。
いきなり「スーパーサイヤ人です!」など叫んでいて面白い。
この子が出ているというので、帰宅後、NHKの「一期一会」を見た。
大きな夢(アイドル志望)の彼女と、万古焼陶芸の職人で足元の夢をこつこつ叶えようとする女性との出逢い。なのだが、どうも2人の夢が両方の極として対比できるものには思えなかった。陶芸職人は、亜美ちゃんの夢は「それは夢じゃなくて単なるあこがれなんじゃないか」とか「人に夢を与える、と言っているが、今は人に夢を見させてもらっている」とか言ってた。それぞれ、まったくもってその通り、なのだが、それは否定したり改善したりする必要のないことだと思う。あこがれの何が悪い。「人に夢を見させてもらってる」そんな女の子を見ているだけでも、僕は夢を与えてもらっているのだ。個人的に言えば、亜美ちゃんが職人の道を選ばずに、アイドルとしてステージに立ってくれていることに、僕は感謝しているのである。
ただ、アイドルとして付加価値をつけるためには、もうちょっと演出が必要だと思う。衣装や選曲や歌い方など。こんなことを思ったのは、ステージで見た彼女もいいが、テレビで見たメイド姿の彼女にまた違う大きな魅力を感じたからだ。
仲村コニー
1.桃色片想い
2.ラムのラブソング
9月のBUG見に行ったときに、客席にお人形さんのように可愛い子がいるなあ、と感心していたのが、彼女だ。9月のときにステージを見れなくて、ステージはどうなんだろう、とワクワクして見た。
緊張していたようだが、彼女の場合は緊張もまた魅力に転換するマジックがそなわっているようだ。変にスレることなく、まっすぐ育っていってほしいと思う。
雪菜
オリジナルの「ウィル」など歌う。
M/W
1.うしろ指さされ組
2.ひとさし指ロマンス
3.リレーションズ
4.最強○×計画
5.最強ヒロイン瞬殺スマイル
お笑いネタのオタ芸の開拓が課題だとか!
ゲスト枠で出演だが、ゲストの出る前に流れるはずの映像がなかなか準備できなくて、かなり間があいた。この時間のロスが、ラストにいたってアンコールなしの事態を招いた。よかれと思って企画したことがアダになってしまったケース。おまけに、そのとき流れた映像も、このために撮った映像ではなく、今までのライブやテレビ映像のダイジェストで、まだまだ改良の余地がありそうだ。
シャンティ
夏水ericoと春菜ありさの2人組。
「ゼロの使い魔」と「ロザリオとバンパイア」からのアニメソングを歌った。
女子高生2人組といった風情で、かつての「マミホ」をほうふつとさせた。
夏雪
1.浮気なハニーパイ
2.ハレ晴れユカイ
「うどんもいいけど、わたしゃあんたのソバがいい」
「差し歯もいけど、わたしゃあんたが入れ歯いい」
謎かけも。「BUGのお客さんとかけて、クリームシチューととく。その心はあたたかい!」
夏輝ちゃんが水戸黄門に出たこともあわせて、なんだか和風&古風な味付けが面白い。
にゃんパラ
「にゃんパラ」という名前なのに、それには触れず、自分のことをずっと「ゆえ様」(優恵)と呼び続けていた。
キャラ作りがアニメ的で、二次元の世界から降臨した雰囲気。
「恋カナ」では歌詞とびまくり。
Mari7
この前のプラッツのライブで愛梨のステージにゲストで出て来たのが彼女だ。
フェミニンなそのときとは違って、今回はボーイッシュなロッカーのイメージ。
CDに入っているオリジナル「インスピレーション」歌ってるのを聞いて、「あっ、この歌知ってる!プラッツに出てた子だ!」とわかったのだから、女の子は衣装で大きく印象が変わるものだと思い知らされる。
ステージ度胸は満点。
4 leaf clover
1.ダンス
2.ヌーワールド
3.シャイニーロード
4.エンプティワールド
5.カラーオブシーズン
6.恋の魔法
衣装はスリットが深く入ったチャイナ服を脱ぐと、へそ出しルック。
衣装に対する感覚が他の出演者とは違うなあ、と思って出演者リスト見てみたら、ダンスできるのは彼女たちだけなのであった。
ましゅまろチェリーBURGER
1.ペッパー警部
2.恋ing
3.大声ダイヤモンド
DDネタや、「恋ましゅチェリing」とタイトルを言ってみたり、歌詞を替えて歌うのがましゅチェリで流行中。
「大声ダイヤモンド」は途中で音が途切れて、最初から。WTCで待機中に流れた分もあわせると、今日は「大声ダイヤモンド」のヘビーローテーションである。
みりん☆
魔法少女〜おジャ魔女、とマジカルな選曲のあと、
オリジナルのちゅーんラブ。
ちゅーんラブでの顔の横でスタン・ハンセン的猛牛振付けもおなじみ。
前回のプラッツでその兆候はあったが、今回のライブで、僕はすっかりこの「みりん☆」の大ファンになってしまった。
とにかく、何を歌っても、みりん節になるのだ。こんなに個性の突出したアイドルも珍しいのではないか。破壊的な魅力だ。お茶じゃなく水を飲む、というなんだかわからない出来事までもが立派なパフォーマンスになる。
不思議とアーティスト写真に見られるような上目使いの顔よりも、客席からステージ上の彼女を見たときのアングルが、より可愛い。また、客席で他の出演者のライブに乗っている彼女の姿(後ろ姿含む)もめっちゃくちゃ可愛いのだ。
とても気に入ったので、CDや写真でも買えばいいようなものだが、物販で人を押しのけたり、並んだりするのは苦手なのだ。おしゃべりするのも緊張する。シャイなので。また機会があれば、みりん☆グッズを買おう。
日記にヴィヴィアンのオーブが載っていて、野ばら君経由で知った、とか、おジャ魔女(宍戸留美)歌うとか、僕の友達とリンクしているのが、より親しみを覚えさせるのかもしれない。
アズ&咲
1.さくらんぼ
2.笑っちゃおうよボーイフレンド
3.ナイトでないと
おなじみのラインナップでお送りいたしました!
ピヨラビ
1.ゴッドノウズ
2.空色デイズ
3.光のキャンベル
男装の2人組。from東京。
オタ芸に特化しており、ステージ上からmixを発動したり、秋葉原ではやっている「イエローパンチョス」を紹介したり。
ドリームパーティでオタ芸が禁止になるなど、オタ芸粛正のムーブメントに対する、まさに反逆のオタ芸伝道師である。
MarryDoll
1.ラブ&ジョイ
2.ベイビースター
3.テルミー
4.さあ恋人になろう
5.ひまわり〜ハニーチューン
6.ホントのじぶん
これは、ここまで長丁場のライブを見て来たお客さんへの御褒美のようなもの。
でも、1組の持ち時間が30分以内、というのが疲れなくて僕にはちょうどいい。
ライブ終了後の物販はなんだか込み合っていて、回避。
帰りにまんだらけに寄って、安い漫画買う。
読んだ漫画は勝又進作品集『赤い雪』
以下、目次。
桑いちご
木魂
鈴虫坂
袋の草紙
子消し
夢の精
まぼろし
虎次郎河童
雁供養
赤い雪
エッセイ
鯨捕り
雪女
冬の夜遊び
寒造り
解説 呉智英
勝又進自筆年譜
「村(むーらー)の時間(じーかん)の時間(じーかん)がやってまいりました」という感じ。こういう民俗学で扱われるような話は、こういう書き手の存在によって伝わりやすく届くんじゃないか、と思った。
『「謎」の解像度(レゾリューション)〜ウェブ時代の本格ミステリ』
2008年11月6日 読書円堂都司昭の『「謎」の解像度(レゾリューション)〜ウェブ時代の本格ミステリ』を読んだ。
以下、目次
プロローグ 基本感情
現実への抗いとしてのミステリ 有栖川有栖
1、場所
シングルルームとテーマパーク 綾辻行人
プライバシーの壊れた場所 折原一
楽園であり牢獄である都市 芦辺拓
2、人・アイデンティティ
「私」と「わたし」のギャラリー 北村薫
個人性の回復と分身 法月綸太郎
交換可能な人、あてレコ的な世界 麻耶雄嵩
編集・加工される記憶 島田荘司
「人間」を描くための「眼」 道尾秀介
3、システム・世界
POSシステム上に出現した「J」−90年代ミステリに与えた清涼院流水のインパクト
人と世界の多重イメージ 歌野晶午
現実感の裂け目の不条理 貫井徳郎
検索が無効な空間 我孫子武丸
相対化される推理 竹本健治
4、人とシステム
ファストフード的世界と疎外感 西澤保彦
器としての人形・館 綾辻行人2
モノ化するコトと「環境」の多面性 京極夏彦
ゼロ年代の解像度(レゾリューション)−本格ミステリをめぐる現在
エピローグ 「青春」「紙の本」以後
青春以前小説/青春以後小説 米澤穂信
「本の終焉」以後の小説−北山猛邦『少年検閲官』と山田正紀『ミステリ・オペラ』
一番面白かったのは、「1、場所」の各論。
そのなかで、駄目押しの推測がツボに入った。
たとえば、綾辻80年代のシングルルームから清涼院90年代のストリートへのうつりかわりを示す、次のような表記。
「だが、80年代的なシングル・ルーム感覚は、やがて携帯電話に代表される90年代のストリート感覚によって蝕まれ変質していった。このことは『黒猫館の殺人』(92年)以後、<館シリーズ>が長期にわたって中断したことと微妙に関係しているようにもみえた」
これぞ、『成吉思汗の秘密』でラストに明かされる「なるよしもがな」的駄目押しの締めくくりだ。
冷静に考えると、「ほんまにそうかいな?」と言うような粗い推理だが、傾いている体勢に加えられる最後のひと押しとして機能している。
同じ論考で、こんな文章も。
「『コズミック』(96年)で進行する1200個の密室殺人計画が、まず平安神宮の路上の密室でスタートしたことは暗示的だ」
著者は控えめに「〜ようにもみえた」とか「暗示的だ」と濁しているが、ここは断言してもらって、快哉を叫ばせてもらいたいところだ。
以下、目次
プロローグ 基本感情
現実への抗いとしてのミステリ 有栖川有栖
1、場所
シングルルームとテーマパーク 綾辻行人
プライバシーの壊れた場所 折原一
楽園であり牢獄である都市 芦辺拓
2、人・アイデンティティ
「私」と「わたし」のギャラリー 北村薫
個人性の回復と分身 法月綸太郎
交換可能な人、あてレコ的な世界 麻耶雄嵩
編集・加工される記憶 島田荘司
「人間」を描くための「眼」 道尾秀介
3、システム・世界
POSシステム上に出現した「J」−90年代ミステリに与えた清涼院流水のインパクト
人と世界の多重イメージ 歌野晶午
現実感の裂け目の不条理 貫井徳郎
検索が無効な空間 我孫子武丸
相対化される推理 竹本健治
4、人とシステム
ファストフード的世界と疎外感 西澤保彦
器としての人形・館 綾辻行人2
モノ化するコトと「環境」の多面性 京極夏彦
ゼロ年代の解像度(レゾリューション)−本格ミステリをめぐる現在
エピローグ 「青春」「紙の本」以後
青春以前小説/青春以後小説 米澤穂信
「本の終焉」以後の小説−北山猛邦『少年検閲官』と山田正紀『ミステリ・オペラ』
一番面白かったのは、「1、場所」の各論。
そのなかで、駄目押しの推測がツボに入った。
たとえば、綾辻80年代のシングルルームから清涼院90年代のストリートへのうつりかわりを示す、次のような表記。
「だが、80年代的なシングル・ルーム感覚は、やがて携帯電話に代表される90年代のストリート感覚によって蝕まれ変質していった。このことは『黒猫館の殺人』(92年)以後、<館シリーズ>が長期にわたって中断したことと微妙に関係しているようにもみえた」
これぞ、『成吉思汗の秘密』でラストに明かされる「なるよしもがな」的駄目押しの締めくくりだ。
冷静に考えると、「ほんまにそうかいな?」と言うような粗い推理だが、傾いている体勢に加えられる最後のひと押しとして機能している。
同じ論考で、こんな文章も。
「『コズミック』(96年)で進行する1200個の密室殺人計画が、まず平安神宮の路上の密室でスタートしたことは暗示的だ」
著者は控えめに「〜ようにもみえた」とか「暗示的だ」と濁しているが、ここは断言してもらって、快哉を叫ばせてもらいたいところだ。
林忠彦の『カストリ時代』を読んだ。
先日テレビで林忠彦の映像見たり、カストリ雑誌の小説関連の本読んだりして、僕のなかではちょっとしたカストリブームだったのだ。
以下、目次
誰か故郷を想わざる
占領の時代
焼け跡・闇市
戦災孤児の街
甦った青春
ニコヨンの哀歓
戦後の象徴・上野駅
空手チョップと赤バット
スター誕生
最後の文士
帰らざる日々
スルメと焼酎/吉行淳之介
僕が生まれるちょっと前の時代の写真だというのに、なんだか懐かしく思える。
文章は著者への聞き書きをもとに編集されている。
MPと殴り合いして血みどろになった秋山庄太郎の武勇伝とか、泥酔した女性のパンツを肴に飲んだ話とか、いちいち面白い。
カストリに関しては、こんな文章が。
「辞典に書いてあるような本物(のカストリ焼酎)はそれほど悪い酒じゃない。酒の粕を蒸留した、非常に香りの高い、いや味のない、いい酒といっていい。
戦後、カストリと称した酒は、まったく鼻つまんで飲まなきゃ飲めないような、何でできたかわからないような、ただアルコール度が強いだけの酒だった。だから、本当の意味のカストリ焼酎を作っていた醸造元は大変な迷惑を被ったんじゃないかと思う」
「朝になっても、目やにがこびりついて目があかない。それで、自分の手で瞼をひろげて、ああ、見える見えるって、やっと安心したような時代だった。そして、いつしかひどくなっていって、おしっこに血が混じりはじめた。これはいかんと深刻になったころには、やがてビールが出回り、ウィスキーも何となく出てくるような時代に変わってきて助かった。当時、ヒロポンの錠剤を頬張って、それで徹夜つづきの仕事をやったこともあった。あのまま続いていたら、おそらく盲目になったが、早くもあの世行きだったろう」
ひどい時代のはずなのに、なんともエネルギッシュ!
先日テレビで林忠彦の映像見たり、カストリ雑誌の小説関連の本読んだりして、僕のなかではちょっとしたカストリブームだったのだ。
以下、目次
誰か故郷を想わざる
占領の時代
焼け跡・闇市
戦災孤児の街
甦った青春
ニコヨンの哀歓
戦後の象徴・上野駅
空手チョップと赤バット
スター誕生
最後の文士
帰らざる日々
スルメと焼酎/吉行淳之介
僕が生まれるちょっと前の時代の写真だというのに、なんだか懐かしく思える。
文章は著者への聞き書きをもとに編集されている。
MPと殴り合いして血みどろになった秋山庄太郎の武勇伝とか、泥酔した女性のパンツを肴に飲んだ話とか、いちいち面白い。
カストリに関しては、こんな文章が。
「辞典に書いてあるような本物(のカストリ焼酎)はそれほど悪い酒じゃない。酒の粕を蒸留した、非常に香りの高い、いや味のない、いい酒といっていい。
戦後、カストリと称した酒は、まったく鼻つまんで飲まなきゃ飲めないような、何でできたかわからないような、ただアルコール度が強いだけの酒だった。だから、本当の意味のカストリ焼酎を作っていた醸造元は大変な迷惑を被ったんじゃないかと思う」
「朝になっても、目やにがこびりついて目があかない。それで、自分の手で瞼をひろげて、ああ、見える見えるって、やっと安心したような時代だった。そして、いつしかひどくなっていって、おしっこに血が混じりはじめた。これはいかんと深刻になったころには、やがてビールが出回り、ウィスキーも何となく出てくるような時代に変わってきて助かった。当時、ヒロポンの錠剤を頬張って、それで徹夜つづきの仕事をやったこともあった。あのまま続いていたら、おそらく盲目になったが、早くもあの世行きだったろう」
ひどい時代のはずなのに、なんともエネルギッシュ!
「日本の話芸」で三遊亭圓歌「電報違い」
マクラで、この新作落語を面白くないと思ってたのであまりしなかった、と圓歌。
よく出来た噺で面白い。
「ドキュメント挑戦」で旭堂南青の武者修行講談会の模様が。
カラオケボックスで練習してた。なるほど。
稲葉振一郎と立岩真也の『所有と国家のゆくえ』を読んだ。
2005年から2006年にかけて行われた対談をもとに構成されている。
以下、目次。
第1章 所有の自明性のワナから抜け出す
1、社会の基礎に所有がある
福祉国家の概念を壊す
所有という根本問題
いまある仕組みを批判する
他者から始まる所有論
政治・経済の基本要素
私有に対する別の私有
「みんな」を起点にした議論の限界
批判・否定のしかた
分けてしまえばよいもの/分けられないもの
2、どこまでが自分のものか
人とものの区別
所有される対象とは何か
身体の捉え方
切離できないものが分配されない
もっと繊細な決まりがある
左翼はどれだけこっか悪いか
「分配する最小国家」について/立岩
第2章 市場万能論のウソを見抜く
1、市場のロジックを検証する
人が必ずもつべきもの
人的資産の二重性
「売る」と「貸す」の区別
譲渡できるもの/できないもの
区別をどのようにつけるか
平等主義・保守主義
市場のダイナミズム
経済学が想定する初期条件
取引の自由は選べない
現状は現状維持なのか
二つのタイプの社会モデル
市場から所有へのフィードバック
市場社会の不幸な事故
2、分配の根拠を示す
結果の平等はなぜ評判が悪いのか
歴史原理と状態原理
嫉妬感情の正当性
再分配という発想
市場原理主義の矛盾
社会のダイナミズムと安定性
「物価」は安定していた方がいい
市場に対する制限
国家がやるべき三つのこと
第3章 なぜ不平等はいけないのか
1、平等をどのように規定するか
分配のために、まず国家は要る
分配的正義と搾取論
ローマーの「機会の平等」論
機会の平等と結果の平等
効用の個人間比較
フェアネスとは何か
ゲームのルールにみるフェアネス
労働を分割する
能力の差をどう組み込むか
アソシエーショニズムとは何か
統制経済の失敗から学ぶ
「国家が」でも、「自分たちで」でも、うまくいかない
国境を超えた分配
2、マルクス主義からの教訓
マルクス主義の二枚舌構造
分析的マルクス主義者の青写真主義
何をするか、しないかを考える
乱暴に考えないこと
実行可能性について
合意は大切だが合意でしかない
体制変革論の気分的な根拠
搾取理論の問題点
不平等こそ問題である
人間改造思想への危惧
マルキシズムおよびマルクス
変革のもとについて
世界主義
3、権利は合意を超越する
ノージックの権利論
規約主義と規範主義
思いを超えてあってほしいという思い
ノージック、ロールズ、立岩理論の違い
経済学の世代間取引モデル
次世代の問題をきちんと取り込む
第4章 国家論の禁じ手を破る
1、批判理論はなぜ行き詰まったのか
国家論の歴史
「国家道具説」から「相対的自律性」へ
批判理論への閉塞感
フーコー権力論の衝撃
悪者探しの無効化
フーコーの隘路から抜け出す
国家は単一の実体ではない
仮想から始める国家論
2、国家の存在理由
なぜ国家があるのか
ルーマンの憲法学的な構想
権利の基底性
実定法の外側にはみ出すもの
不平等批判の正しいかたち
肉体レベルに根ざす不平等感
ドゥウォーキンの補償理論
本当に国家に責任はないのか
責任を問うことの不毛さ
法的に呼び出される国家
国際秩序について
経済成長の必要性について/稲葉
分配>成長?−稲葉「経済成長の必要性について」の後に/立岩
これもまた目次だけでかなりの分量だ。
目次の中から註釈的メモ。
「経済学が想定する初期条件」
[稲葉]「厚生経済学の基本定理」が考えてるような初期条件っていうのは(中略)取引に参加しなくたって生き延びていける、ある種自給自足に近いような条件が想定されている。
「国家がやるべき三つのこと」
[立岩]具体的に、生産財の分配が要ると思う、労働の分配が要ると思う、そして所得保障も要る、最低三つは要る。
「フェアネスとは何か」
[稲葉]ロールズの正義論っていうのは、正義というのもを「フェアネス」を中軸に考えようという話ですね。このフェアネス、日本語で言うと「公正」とか「公平」とかいろんな訳され方をしますけど、これをどうつかまえるのかというのはけっこう厄介な問題だと思うんですね。(中略)中西洋さんがずっと言ってたことなんですが、フェアネスって何かというと、彼は「友愛主義」ってことばを使うんです。彼は「国家は竹馬である」と言うんです。ゴルフのハンディキャップだって言うんですね。
「アソシエーショニズムとは何か」
[稲葉]協同組合主義ですね。協同組合というのは、自発的な結社であるし、市場という環境の中で動き回るものですけれども、現在の企業において支配的な形態である株式会社、公開型の組織とはちょっと違って、わりと大事なところで強い閉鎖性をもっている。(中略)公開型の株式会社を主役とするんじゃなくて、そういう協同組合を主体とするような市場経済のことを考えてる人たちがいるわけです。
「ノージック、ロールズ、立岩理論の違い」
[稲葉]ノージックの原点における人っていうのは要するに他人とかかわっていてもかかわっていなくてもよい。むしろ他人とかかわらずに、一人でなんとかやっている人間をモデルとして考えていると言った方がどうもよさそうだ。立岩さんの場合はそうじゃなくて、最初から他人と取引だか喧嘩だかしているというシチュエーションから議論を組み立てようと考えている。そこが違いです。この違いはきわめて重要な違いです。
対談を読んだ分には、「ここからはじまる」って感じだった。
ただ、目次などにはあらわれないけど、面白かったのは、二人の個性があまりにも違っているところ。
華麗で饒舌な稲葉と身も蓋もなく朴訥な立岩(読んだ印象ですよ!)
読んでないけど、「アストロ球団」と「キャプテン」が戦っている感じ。どっちも読んでないけど!
鋭く難解で頭をキリキリと刺激する稲葉の発言が、立岩によって言い換えられると、「えっ、そんな普通のことだったの?」ととたんにわかりやすくなる。表現はわかりやすくなるけど、内容が難問であることにかわりがない。
立岩表現の一例。
「人が権利をもつということがどの水準で言えるのかという問いがあります。事実問題というか、実際には、人に権利があると言ったって、その権利をその権利として周囲の者たちが承認しないことにはなんら実効性をもたないものにしかならない。これは事実問題として言える。(中略)しかし、いま言った通りでありながら、人がいいって言わなきゃ人に権利はないのか。そうだって言いたくない。つまり、人がなんと言おうと、自分のことをどう思っていようと、あるいはその人がどうであろうと、その人には権利なら権利があるよって考えたいというか、あるいは考えるべきだって思っているということがある。それはぼくはとても大切なことであるように思います」
うむ。立岩氏の本をますます読みたくなってきた!
マクラで、この新作落語を面白くないと思ってたのであまりしなかった、と圓歌。
よく出来た噺で面白い。
「ドキュメント挑戦」で旭堂南青の武者修行講談会の模様が。
カラオケボックスで練習してた。なるほど。
稲葉振一郎と立岩真也の『所有と国家のゆくえ』を読んだ。
2005年から2006年にかけて行われた対談をもとに構成されている。
以下、目次。
第1章 所有の自明性のワナから抜け出す
1、社会の基礎に所有がある
福祉国家の概念を壊す
所有という根本問題
いまある仕組みを批判する
他者から始まる所有論
政治・経済の基本要素
私有に対する別の私有
「みんな」を起点にした議論の限界
批判・否定のしかた
分けてしまえばよいもの/分けられないもの
2、どこまでが自分のものか
人とものの区別
所有される対象とは何か
身体の捉え方
切離できないものが分配されない
もっと繊細な決まりがある
左翼はどれだけこっか悪いか
「分配する最小国家」について/立岩
第2章 市場万能論のウソを見抜く
1、市場のロジックを検証する
人が必ずもつべきもの
人的資産の二重性
「売る」と「貸す」の区別
譲渡できるもの/できないもの
区別をどのようにつけるか
平等主義・保守主義
市場のダイナミズム
経済学が想定する初期条件
取引の自由は選べない
現状は現状維持なのか
二つのタイプの社会モデル
市場から所有へのフィードバック
市場社会の不幸な事故
2、分配の根拠を示す
結果の平等はなぜ評判が悪いのか
歴史原理と状態原理
嫉妬感情の正当性
再分配という発想
市場原理主義の矛盾
社会のダイナミズムと安定性
「物価」は安定していた方がいい
市場に対する制限
国家がやるべき三つのこと
第3章 なぜ不平等はいけないのか
1、平等をどのように規定するか
分配のために、まず国家は要る
分配的正義と搾取論
ローマーの「機会の平等」論
機会の平等と結果の平等
効用の個人間比較
フェアネスとは何か
ゲームのルールにみるフェアネス
労働を分割する
能力の差をどう組み込むか
アソシエーショニズムとは何か
統制経済の失敗から学ぶ
「国家が」でも、「自分たちで」でも、うまくいかない
国境を超えた分配
2、マルクス主義からの教訓
マルクス主義の二枚舌構造
分析的マルクス主義者の青写真主義
何をするか、しないかを考える
乱暴に考えないこと
実行可能性について
合意は大切だが合意でしかない
体制変革論の気分的な根拠
搾取理論の問題点
不平等こそ問題である
人間改造思想への危惧
マルキシズムおよびマルクス
変革のもとについて
世界主義
3、権利は合意を超越する
ノージックの権利論
規約主義と規範主義
思いを超えてあってほしいという思い
ノージック、ロールズ、立岩理論の違い
経済学の世代間取引モデル
次世代の問題をきちんと取り込む
第4章 国家論の禁じ手を破る
1、批判理論はなぜ行き詰まったのか
国家論の歴史
「国家道具説」から「相対的自律性」へ
批判理論への閉塞感
フーコー権力論の衝撃
悪者探しの無効化
フーコーの隘路から抜け出す
国家は単一の実体ではない
仮想から始める国家論
2、国家の存在理由
なぜ国家があるのか
ルーマンの憲法学的な構想
権利の基底性
実定法の外側にはみ出すもの
不平等批判の正しいかたち
肉体レベルに根ざす不平等感
ドゥウォーキンの補償理論
本当に国家に責任はないのか
責任を問うことの不毛さ
法的に呼び出される国家
国際秩序について
経済成長の必要性について/稲葉
分配>成長?−稲葉「経済成長の必要性について」の後に/立岩
これもまた目次だけでかなりの分量だ。
目次の中から註釈的メモ。
「経済学が想定する初期条件」
[稲葉]「厚生経済学の基本定理」が考えてるような初期条件っていうのは(中略)取引に参加しなくたって生き延びていける、ある種自給自足に近いような条件が想定されている。
「国家がやるべき三つのこと」
[立岩]具体的に、生産財の分配が要ると思う、労働の分配が要ると思う、そして所得保障も要る、最低三つは要る。
「フェアネスとは何か」
[稲葉]ロールズの正義論っていうのは、正義というのもを「フェアネス」を中軸に考えようという話ですね。このフェアネス、日本語で言うと「公正」とか「公平」とかいろんな訳され方をしますけど、これをどうつかまえるのかというのはけっこう厄介な問題だと思うんですね。(中略)中西洋さんがずっと言ってたことなんですが、フェアネスって何かというと、彼は「友愛主義」ってことばを使うんです。彼は「国家は竹馬である」と言うんです。ゴルフのハンディキャップだって言うんですね。
「アソシエーショニズムとは何か」
[稲葉]協同組合主義ですね。協同組合というのは、自発的な結社であるし、市場という環境の中で動き回るものですけれども、現在の企業において支配的な形態である株式会社、公開型の組織とはちょっと違って、わりと大事なところで強い閉鎖性をもっている。(中略)公開型の株式会社を主役とするんじゃなくて、そういう協同組合を主体とするような市場経済のことを考えてる人たちがいるわけです。
「ノージック、ロールズ、立岩理論の違い」
[稲葉]ノージックの原点における人っていうのは要するに他人とかかわっていてもかかわっていなくてもよい。むしろ他人とかかわらずに、一人でなんとかやっている人間をモデルとして考えていると言った方がどうもよさそうだ。立岩さんの場合はそうじゃなくて、最初から他人と取引だか喧嘩だかしているというシチュエーションから議論を組み立てようと考えている。そこが違いです。この違いはきわめて重要な違いです。
対談を読んだ分には、「ここからはじまる」って感じだった。
ただ、目次などにはあらわれないけど、面白かったのは、二人の個性があまりにも違っているところ。
華麗で饒舌な稲葉と身も蓋もなく朴訥な立岩(読んだ印象ですよ!)
読んでないけど、「アストロ球団」と「キャプテン」が戦っている感じ。どっちも読んでないけど!
鋭く難解で頭をキリキリと刺激する稲葉の発言が、立岩によって言い換えられると、「えっ、そんな普通のことだったの?」ととたんにわかりやすくなる。表現はわかりやすくなるけど、内容が難問であることにかわりがない。
立岩表現の一例。
「人が権利をもつということがどの水準で言えるのかという問いがあります。事実問題というか、実際には、人に権利があると言ったって、その権利をその権利として周囲の者たちが承認しないことにはなんら実効性をもたないものにしかならない。これは事実問題として言える。(中略)しかし、いま言った通りでありながら、人がいいって言わなきゃ人に権利はないのか。そうだって言いたくない。つまり、人がなんと言おうと、自分のことをどう思っていようと、あるいはその人がどうであろうと、その人には権利なら権利があるよって考えたいというか、あるいは考えるべきだって思っているということがある。それはぼくはとても大切なことであるように思います」
うむ。立岩氏の本をますます読みたくなってきた!
若狭邦男の『探偵作家追跡』を読んだ。
第1章 探偵作家追跡
1、鮎川哲也「月魄」
2、江戸川乱歩「偉大なる夢」
3、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』
4、大下宇陀児『天狗の面』
5、耶止説夫「南進兄弟」
6、覆面作家「幽霊を抱いていた男」
7、香山風太郎「悪魔の貞操帯」
8、魔子鬼一『女のミステリー』
9、大阪圭吉『ほがらか夫人』
10、吉良運平『遺書の誓ひ』
11、大月恒志『流れ流れて』
12、水上幻一郎「火山観測所殺人事件」
13、守友恒『幻想殺人事件』
14、九鬼澹「死はかくして美しい」
15、華村タマ子「渦紋」
16、矢留節夫「悲恋の情」
17、岡戸武平『全力投球』
18、「新探偵小説」の三人「暗黒の殺人」
19、狩久『不必要な犯罪』
20、薄風之介『黒いカーテン』
21、川口直樹『悪魔の乱舞』
22、角田喜久雄『高木家の惨劇』
23、赤沼三郎『悪魔の黙示録』
24、都筑道夫「殺した女が腫れ物になった話」
25、杉山清詩『爆弾娘』
26、土屋光司『世界名作探偵小説集』
27、妹尾アキ夫『決闘』
第2章 「探偵雑誌」閲覧室
1、雑誌「ロック」
2、雑誌「さんるうむ」
3、雑誌「宝石」
4、雑誌「ぷろふいる」「仮面」
5、雑誌「トップ」
6、雑誌「黒猫」
7、雑誌「真珠」
8、雑誌「妖奇」
9、雑誌「オール・ロマンス」
10、雑誌「ネオ・リベラル(新自由)」
11、雑誌「実話講談の泉」
12、雑誌「怪奇探偵クラブ」
13、雑誌「探偵実話」
14、雑誌「オール猟奇」「綺談」「ベーゼ」
15、雑誌「探偵趣味」
一読、時間を忘れて読みふけった。
ここにあげられた多くの作品はカストリ雑誌に掲載されたもので、あいにくと、僕はそっち方面はほとんど守備範囲に入っていなくて、未読のものが多かった。
作品名を見ているだけでクラクラしてくる。
「覆面作家」が杉山清詩であることを明らかにするくだりや、赤沼三郎には偽者がおり、その正体は御手洗辰雄であったとする記述など、この著者がいなければ真相は闇に葬られていたんじゃないか、と思われる。都筑道夫が自伝エッセイで記憶が曖昧になっていたくだりを検証して特定もしている。
最近、昔の探偵小説が次々と復刻されたりして、嬉しいかぎりだが、これはたいへんな労力が必要なのだろう、と推察される。
探偵作家自身が高齢で故人となっていたり、雑誌が入手できなかったり、さらに、妹尾アキ夫の項で書かれているように、原稿が風呂の焚き付けに使われて現存しなかったり。
個人の情熱によって成し遂げられたこうした成果は賞賛してもしきれるものではない。
多くの作品は今や読むにあたいしないクオリティなのかもしれないが、とりあえず、大下宇陀児あたりはもっと復刻されてしかるべきなんじゃないかな。それに、クオリティが低くても、作家が無名でも、僕は読みたいぞ。
第1章 探偵作家追跡
1、鮎川哲也「月魄」
2、江戸川乱歩「偉大なる夢」
3、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』
4、大下宇陀児『天狗の面』
5、耶止説夫「南進兄弟」
6、覆面作家「幽霊を抱いていた男」
7、香山風太郎「悪魔の貞操帯」
8、魔子鬼一『女のミステリー』
9、大阪圭吉『ほがらか夫人』
10、吉良運平『遺書の誓ひ』
11、大月恒志『流れ流れて』
12、水上幻一郎「火山観測所殺人事件」
13、守友恒『幻想殺人事件』
14、九鬼澹「死はかくして美しい」
15、華村タマ子「渦紋」
16、矢留節夫「悲恋の情」
17、岡戸武平『全力投球』
18、「新探偵小説」の三人「暗黒の殺人」
19、狩久『不必要な犯罪』
20、薄風之介『黒いカーテン』
21、川口直樹『悪魔の乱舞』
22、角田喜久雄『高木家の惨劇』
23、赤沼三郎『悪魔の黙示録』
24、都筑道夫「殺した女が腫れ物になった話」
25、杉山清詩『爆弾娘』
26、土屋光司『世界名作探偵小説集』
27、妹尾アキ夫『決闘』
第2章 「探偵雑誌」閲覧室
1、雑誌「ロック」
2、雑誌「さんるうむ」
3、雑誌「宝石」
4、雑誌「ぷろふいる」「仮面」
5、雑誌「トップ」
6、雑誌「黒猫」
7、雑誌「真珠」
8、雑誌「妖奇」
9、雑誌「オール・ロマンス」
10、雑誌「ネオ・リベラル(新自由)」
11、雑誌「実話講談の泉」
12、雑誌「怪奇探偵クラブ」
13、雑誌「探偵実話」
14、雑誌「オール猟奇」「綺談」「ベーゼ」
15、雑誌「探偵趣味」
一読、時間を忘れて読みふけった。
ここにあげられた多くの作品はカストリ雑誌に掲載されたもので、あいにくと、僕はそっち方面はほとんど守備範囲に入っていなくて、未読のものが多かった。
作品名を見ているだけでクラクラしてくる。
「覆面作家」が杉山清詩であることを明らかにするくだりや、赤沼三郎には偽者がおり、その正体は御手洗辰雄であったとする記述など、この著者がいなければ真相は闇に葬られていたんじゃないか、と思われる。都筑道夫が自伝エッセイで記憶が曖昧になっていたくだりを検証して特定もしている。
最近、昔の探偵小説が次々と復刻されたりして、嬉しいかぎりだが、これはたいへんな労力が必要なのだろう、と推察される。
探偵作家自身が高齢で故人となっていたり、雑誌が入手できなかったり、さらに、妹尾アキ夫の項で書かれているように、原稿が風呂の焚き付けに使われて現存しなかったり。
個人の情熱によって成し遂げられたこうした成果は賞賛してもしきれるものではない。
多くの作品は今や読むにあたいしないクオリティなのかもしれないが、とりあえず、大下宇陀児あたりはもっと復刻されてしかるべきなんじゃないかな。それに、クオリティが低くても、作家が無名でも、僕は読みたいぞ。
<ほんもの>という倫理−近代とその不安
2008年10月29日 読書
チャールズ・テイラーの『「ほんもの」という倫理−近代とその不安』を読んだ。
第1章 三つの不安
第2章 かみ合わない論争
第3章 ほんものという理想の源泉
第4章 逃れられない地平
第5章 承認のニード
第6章 主観主義へのすべり坂
第7章 闘争は続く
第8章 もっと微妙な言語
第9章 鉄の檻?
第10章 断片化に抗して
本書でチャールズ・テイラーは、個人主義の発達と道具的理性の優位からくる近代特有の不安について述べている。
テイラーは「ほんもの」(authenticity)の回復を説くのだが。
僕にはこの本は難しすぎたようだ。
テイラーは、現代文化を心酔するのも誤りだし、痛罵するのも間違い、2つをすりあわせてみるのもおかしい、と言う。両者の戦いの中に答えがある、というのだが、どうもよくわからない。どうすればいいのかが見えてこない。
「ほんもの」の鍵は美意識にあり、とするのも特徴的で、うなずきかけるのだが、どうも違和感がある。テイラーの美意識と僕の美意識が違うような気がするのだ。
本書のもとになった講義をしたとき、テイラーが60才だったせいか、読んでいてなんだか年寄りの説教を聞いているような気分がしてくるのだ。
たとえば、こんなくだり。
「さきに第2章で、ほんものという(理想の息づく)現代文化が穏やかな相対主義へとすべり落ちてゆくさまを見ました。その穏やかな相対主義が、価値についての主観主義というひろくゆきわたった思い込みに、ますます拍車をかけることになります。ものごとが重要性をもつのは、ものごと自体に重要性があるからではなく、重要性があると思うからだ、というわけです。ものごとに重要性があるかどうかは、あると決めればあることになるし、知らず知らずにしても不承不承にしても、とにかく重要性があると感じさえすれば、あることにできるのだと言わんばかり。なんとも無茶な話です」
僕は、その「無茶な話」こそ面白くて、支持してしまう。
テイラーは「無茶な話」の例として、本書の最大の読みどころともなる表現をしてみせる。
「生温かいぬかるみに足を突っ込んでつま先をぴくぴく動かすこと、それをもっとも重要な行為と決める−わたしだったらとてもそんなことはできません」
テイラーにはできないかもしれないけど、僕ならできる。
テイラーは感じるだけではなにが重要かを決めることはできない、とするが、結局は感じるところに着地するのではないか。
「やれやれ、こんなこと、できませんよね、みなさん」と言いたげなテイラーには、なんだかワイドショーのコメンテーターなみの保守性を感じてしまう。
ナルシシズム、ニヒリズム、ひきこもり、ニーチェ、バタイユ、デリダなどなどを否定するテイラーは保守的なお年寄りと変わるところがないように思えるのだが、きっと、それは、僕がちゃんとこの本を読めていないせいなのだろう。
テイラーが当然あるものとして述べる「近代とその不安」も、僕にはちっとも不安じゃないのである。
ともあれ、「ぬかるみで足指をぴくぴくさせる」という至高の行為を教えてくれたテイラーに、今は感謝している。
第1章 三つの不安
第2章 かみ合わない論争
第3章 ほんものという理想の源泉
第4章 逃れられない地平
第5章 承認のニード
第6章 主観主義へのすべり坂
第7章 闘争は続く
第8章 もっと微妙な言語
第9章 鉄の檻?
第10章 断片化に抗して
本書でチャールズ・テイラーは、個人主義の発達と道具的理性の優位からくる近代特有の不安について述べている。
テイラーは「ほんもの」(authenticity)の回復を説くのだが。
僕にはこの本は難しすぎたようだ。
テイラーは、現代文化を心酔するのも誤りだし、痛罵するのも間違い、2つをすりあわせてみるのもおかしい、と言う。両者の戦いの中に答えがある、というのだが、どうもよくわからない。どうすればいいのかが見えてこない。
「ほんもの」の鍵は美意識にあり、とするのも特徴的で、うなずきかけるのだが、どうも違和感がある。テイラーの美意識と僕の美意識が違うような気がするのだ。
本書のもとになった講義をしたとき、テイラーが60才だったせいか、読んでいてなんだか年寄りの説教を聞いているような気分がしてくるのだ。
たとえば、こんなくだり。
「さきに第2章で、ほんものという(理想の息づく)現代文化が穏やかな相対主義へとすべり落ちてゆくさまを見ました。その穏やかな相対主義が、価値についての主観主義というひろくゆきわたった思い込みに、ますます拍車をかけることになります。ものごとが重要性をもつのは、ものごと自体に重要性があるからではなく、重要性があると思うからだ、というわけです。ものごとに重要性があるかどうかは、あると決めればあることになるし、知らず知らずにしても不承不承にしても、とにかく重要性があると感じさえすれば、あることにできるのだと言わんばかり。なんとも無茶な話です」
僕は、その「無茶な話」こそ面白くて、支持してしまう。
テイラーは「無茶な話」の例として、本書の最大の読みどころともなる表現をしてみせる。
「生温かいぬかるみに足を突っ込んでつま先をぴくぴく動かすこと、それをもっとも重要な行為と決める−わたしだったらとてもそんなことはできません」
テイラーにはできないかもしれないけど、僕ならできる。
テイラーは感じるだけではなにが重要かを決めることはできない、とするが、結局は感じるところに着地するのではないか。
「やれやれ、こんなこと、できませんよね、みなさん」と言いたげなテイラーには、なんだかワイドショーのコメンテーターなみの保守性を感じてしまう。
ナルシシズム、ニヒリズム、ひきこもり、ニーチェ、バタイユ、デリダなどなどを否定するテイラーは保守的なお年寄りと変わるところがないように思えるのだが、きっと、それは、僕がちゃんとこの本を読めていないせいなのだろう。
テイラーが当然あるものとして述べる「近代とその不安」も、僕にはちっとも不安じゃないのである。
ともあれ、「ぬかるみで足指をぴくぴくさせる」という至高の行為を教えてくれたテイラーに、今は感謝している。