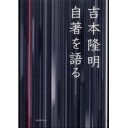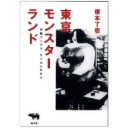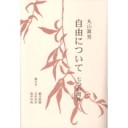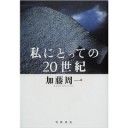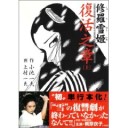『吉本隆明 自著を語る』
2009年4月22日 読書
『吉本隆明 自著を語る』を読んだ。
第1章 『固有時との対話』『転位のための十篇』
詩作の始まり/詩的衝動との対峙/転換点としての終戦/独自のスタイルへの到達/詩人と批評家の葛藤/現在の立場
第2章 『マチウ書試論』
新約聖書との出会い/マルクス主義への失望/宗教との向き合い方/絶対的なものへの憧れ
第3章 『高村光太郎』
戦犯者探しへの違和感/シンパシーの理由/敗戦の受け止め方/軍国少年であった自己との対峙/未発表の手紙/評論家としての出発点/批評とエモーションの間で
第4章 『芸術的抵抗と挫折』
アリバイ論への不満/新たな批評機軸/「吉本思想」の萌芽/「愛国」をどう捉えるか
第5章 『擬制の終焉』
闘争の最前線で/「マルクス主義」と「マルクス者」/連帯と決別/安保闘争後の”戦後処理”/避けられない”破局感”
第6章 『言語にとって美とは何か』
小林秀雄と江藤淳/『資本論』から得た着想/言語論から言語表現論へ/批評家個人としての水準/”還相”からの文芸批評
第7章 『共同幻想論』
”国家”という共同幻想/”死”という共同幻想/天皇制との決着/呪縛からの解放/対幻想の独創性/新たな問題意識
第8章 『花田清輝との論争』
不意打ち的な論争の始まり/花田清輝の評価/吉本隆明の「花田清輝論」/論争の落とし穴/よりエモーショナルな糾弾へ/”遠慮”の文化
第9章 『心的現象論』
吉本思想の根幹を成す三部作の位置づけ/揺るがない文芸批評としての立ち位置/精神医学との距離感/『心的現象論』が目指した広大な地平/「詩作」としての三部作
控えめにも吉本隆明の名前しか見えないが、インタビュアーは渋谷陽一がつとめている。吉本の各著作について、渋谷がわかりやすくまとめながらインタビューが進めているのが丁寧で面白い。それは吉本に言わせれば「ほめ過ぎ」であろうとも、吉本の各著作の勘所がこんなに明瞭に出された本は稀ではないか。実にみごとなまとめ方だ、て、渋谷陽一を何回もほめたくなる本だった。
第1章 『固有時との対話』『転位のための十篇』
詩作の始まり/詩的衝動との対峙/転換点としての終戦/独自のスタイルへの到達/詩人と批評家の葛藤/現在の立場
第2章 『マチウ書試論』
新約聖書との出会い/マルクス主義への失望/宗教との向き合い方/絶対的なものへの憧れ
第3章 『高村光太郎』
戦犯者探しへの違和感/シンパシーの理由/敗戦の受け止め方/軍国少年であった自己との対峙/未発表の手紙/評論家としての出発点/批評とエモーションの間で
第4章 『芸術的抵抗と挫折』
アリバイ論への不満/新たな批評機軸/「吉本思想」の萌芽/「愛国」をどう捉えるか
第5章 『擬制の終焉』
闘争の最前線で/「マルクス主義」と「マルクス者」/連帯と決別/安保闘争後の”戦後処理”/避けられない”破局感”
第6章 『言語にとって美とは何か』
小林秀雄と江藤淳/『資本論』から得た着想/言語論から言語表現論へ/批評家個人としての水準/”還相”からの文芸批評
第7章 『共同幻想論』
”国家”という共同幻想/”死”という共同幻想/天皇制との決着/呪縛からの解放/対幻想の独創性/新たな問題意識
第8章 『花田清輝との論争』
不意打ち的な論争の始まり/花田清輝の評価/吉本隆明の「花田清輝論」/論争の落とし穴/よりエモーショナルな糾弾へ/”遠慮”の文化
第9章 『心的現象論』
吉本思想の根幹を成す三部作の位置づけ/揺るがない文芸批評としての立ち位置/精神医学との距離感/『心的現象論』が目指した広大な地平/「詩作」としての三部作
控えめにも吉本隆明の名前しか見えないが、インタビュアーは渋谷陽一がつとめている。吉本の各著作について、渋谷がわかりやすくまとめながらインタビューが進めているのが丁寧で面白い。それは吉本に言わせれば「ほめ過ぎ」であろうとも、吉本の各著作の勘所がこんなに明瞭に出された本は稀ではないか。実にみごとなまとめ方だ、て、渋谷陽一を何回もほめたくなる本だった。
『東京モンスターランド 実験アングラ・サブカルの日々』
2009年4月21日 読書
榎本了壱の『東京モンスターランド 実験アングラ・サブカルの日々』を読んだ。
パビリオン1 少年詩人群像館/二科展と同人誌『かいぶつ』
転身ゲームの始まりは熊本先生の一言だった
パビリオン2 デザイン黎明館/粟津潔と『いちご白書』の季節
憧れのデザイナーとの遭遇 そして世界中の大学が燃えた
パビリオン3 絶世女流詩人館/吉原幸子と『粘液質王国』
原宿隠田に住む絶世の女流詩人に会いに行った
パビリオン4 草月前衛芸術館/草月会館半地下の五月革命
前衛の拠点草月アートセンターと鎌倉純情小曲集
パビリオン5 渋谷天井桟敷館/寺山修司と演劇実験室
怪人テラヤマの逆襲 あるいは母親ハツさんの肖像画
パビリオン6 鬼六緊縛館/団鬼六と芳賀書店社長
緊縛写真集の変態生写真に思わず生唾を呑み込んだ
パビリオン7 ダンスダンス館/『蛞蝓姫物語』とモワティエ舞踏会
ダンスはエロスの隣国 不思議な国でありす
パビリオン8 1970年回顧館/もうひとつのそれぞれの70年
自死する三島 療養する寺山 漂泊する萩原
パビリオン9 欧州アヴァンギャルド館/ヨーロッパ・アングラ奇行
小雨のナンシーの夜、突然に
パビリオン10 ウメスタ実験映画館/萩原朔美と家族商会活動所
代官山の眠れない夜々 あるいは恋の片路切符
パビリオン11 パリ青春逍遥館/シャローン通りの350日
パリの恍惚と不安 ヒロ・ヤマガタもいた青春の日々
パビリオン12 ビックリハウス館/100万円の『ビックリハウス』
アートのメディア誌計画がなんとパロディ雑誌作りに
パビリオン13 パルコ文化館/パルコのマスダ学校
増田通二専務の恐怖決裁にサバイバルすること
パビリオン14 パロディ編集館/「アンアン」が「ワンワン」になった日
アイディアの源泉は徹底した自己満足
パビリオン15 トラジコメディ館/28年目の悲喜劇
永すぎた少年期の終わりの物語
パビリオン16 テレビメディア館/『11PM』というメディアモンスター
『美の世界』『ザ・テレビ演芸』『マルチスコープ』に出る
パビリオン17 ヘンタイよいこ館/糸井重里と『ヘンタイよいこ新聞』
御教訓カレンダーから弐千円札が生まれるまで
パビリオン18 日グラコンペ館/「日本グラフィック展」と日比野克彦
天才ダンボールアート少年はにこやかに登場する
パビリオン19 デザイン会議館/黒川紀章と「日本文化デザイン会議」
日本の文化をデザインするモンスター達
パビリオン20 トークスクラップ館/20世紀モンスターサミット
そのときあの人とこんな話をした
●ネオパロディ時代始まる(1977)
粟津潔 中原佑介 福田繁雄 寺山修司 マッド・アマノ
●一番ひとに見せたいこと(1982)
糸井重里
●全肯定的アドトリアル・マガジンの氾濫(1982)
椎名誠 増田通二
●ヘタうまの時代とダサイズム(1982)
谷川晃一 横澤彪
●神田八丁堀は、ブラックホールだよ(1984)
梅原猛 糸井重里
●アルバイトに、プロレスをちょっと(1984)
C・W・ニコル 糸井重里
●反時代的感情のない時代(1985)
高橋源一郎
●模造人間の危機(1985)
島田雅彦
●無共闘時代の新人類(1985)
泉麻人
●脱建築とニューグロテスク(1985)
粟津潔 吉田光邦 ジェイムズ・ワインズ
●情報化社会に水を売る(1985)
細川護煕 粟津潔
●CIデザイン世界戦争(1986)
亀倉雄策 糸井重里
●チベットの女形(1986)
糸井重里 中沢新一 黒川紀章
●放置プレイの法則(1987)
糸井重里 中沢新一
●牛もうもうもうと霧を出たりけり(1987)
糸井重里 原田泰治 ビル・レイシー 芳賀徹
●奇々怪々 講談「百物語」(1987)
神田陽子 杉浦日向子 萩原朔美
●境界線上の劇場論(1989)
朝倉摂 池辺晋一郎
●混浴のアナキズム(1990)
田中優子
●自然発生した雨後の竹の子族
加藤正一 三枝成彰 杉浦日向子
●神亡き後のアート(1990)
伊東順二
●メディアサバイバル宣言(1991)
三宅理一 田中優子 黒川紀章 河原敏文 高松伸 竹山聖
●ダジャレの文化人類学(1993)
杉浦日向子 山口昌男 荻野アンナ
●広告表現の局地化(1995)
田中一光 中島信也
●変態少女ダンスの世界(1996)
黒川紀章 香山リカ
●欲望の鉱脈(1998)
西川りゅうじん
●大阪の若草物語(1998)
コシノアヤコ コシノヒロコ
●ウソも方便(1998)
伊奈かっぺい 山上進 つボイノリオ
●スカートの中の少女論(1998)
荒木経惟 サエキけんぞう 俵万智
●色白美人とガングロ少女(1999)
鈴木その子 中尊寺ゆつこ 原島博
●世紀末遊びの王国(2000)
香山リカ 森村泰昌
あとがき 東京モンスターランド/かいぶつ達は吼えたか
20世紀カルチャーのメガロポリスで
アングラサブカルの時代の面白かったこと、また懐かしいこと!
時代と自伝。
現代に近づくにつれ、著者のステータスや、やりたい仕事をやりたいように実現するだけの力はアップしているのだが、昔の話の方が、断然生き生きしていて、面白い。
著者の年齢のせいなのか、時代がそうなのか。
途中、恋愛のことなども語られる。言葉遊びの好きな人だとは思っていたが、予想以上のダジャリストのようだ。
榎本氏は、寺山の本の装幀や、ビックリハウスなどで、馴染み深い人だったが、今は京都造形芸術大学の教授なんだ!会いに行こうと思えば手の届くところ(足の届く?)にいらっしゃったとは!
パビリオン1 少年詩人群像館/二科展と同人誌『かいぶつ』
転身ゲームの始まりは熊本先生の一言だった
パビリオン2 デザイン黎明館/粟津潔と『いちご白書』の季節
憧れのデザイナーとの遭遇 そして世界中の大学が燃えた
パビリオン3 絶世女流詩人館/吉原幸子と『粘液質王国』
原宿隠田に住む絶世の女流詩人に会いに行った
パビリオン4 草月前衛芸術館/草月会館半地下の五月革命
前衛の拠点草月アートセンターと鎌倉純情小曲集
パビリオン5 渋谷天井桟敷館/寺山修司と演劇実験室
怪人テラヤマの逆襲 あるいは母親ハツさんの肖像画
パビリオン6 鬼六緊縛館/団鬼六と芳賀書店社長
緊縛写真集の変態生写真に思わず生唾を呑み込んだ
パビリオン7 ダンスダンス館/『蛞蝓姫物語』とモワティエ舞踏会
ダンスはエロスの隣国 不思議な国でありす
パビリオン8 1970年回顧館/もうひとつのそれぞれの70年
自死する三島 療養する寺山 漂泊する萩原
パビリオン9 欧州アヴァンギャルド館/ヨーロッパ・アングラ奇行
小雨のナンシーの夜、突然に
パビリオン10 ウメスタ実験映画館/萩原朔美と家族商会活動所
代官山の眠れない夜々 あるいは恋の片路切符
パビリオン11 パリ青春逍遥館/シャローン通りの350日
パリの恍惚と不安 ヒロ・ヤマガタもいた青春の日々
パビリオン12 ビックリハウス館/100万円の『ビックリハウス』
アートのメディア誌計画がなんとパロディ雑誌作りに
パビリオン13 パルコ文化館/パルコのマスダ学校
増田通二専務の恐怖決裁にサバイバルすること
パビリオン14 パロディ編集館/「アンアン」が「ワンワン」になった日
アイディアの源泉は徹底した自己満足
パビリオン15 トラジコメディ館/28年目の悲喜劇
永すぎた少年期の終わりの物語
パビリオン16 テレビメディア館/『11PM』というメディアモンスター
『美の世界』『ザ・テレビ演芸』『マルチスコープ』に出る
パビリオン17 ヘンタイよいこ館/糸井重里と『ヘンタイよいこ新聞』
御教訓カレンダーから弐千円札が生まれるまで
パビリオン18 日グラコンペ館/「日本グラフィック展」と日比野克彦
天才ダンボールアート少年はにこやかに登場する
パビリオン19 デザイン会議館/黒川紀章と「日本文化デザイン会議」
日本の文化をデザインするモンスター達
パビリオン20 トークスクラップ館/20世紀モンスターサミット
そのときあの人とこんな話をした
●ネオパロディ時代始まる(1977)
粟津潔 中原佑介 福田繁雄 寺山修司 マッド・アマノ
●一番ひとに見せたいこと(1982)
糸井重里
●全肯定的アドトリアル・マガジンの氾濫(1982)
椎名誠 増田通二
●ヘタうまの時代とダサイズム(1982)
谷川晃一 横澤彪
●神田八丁堀は、ブラックホールだよ(1984)
梅原猛 糸井重里
●アルバイトに、プロレスをちょっと(1984)
C・W・ニコル 糸井重里
●反時代的感情のない時代(1985)
高橋源一郎
●模造人間の危機(1985)
島田雅彦
●無共闘時代の新人類(1985)
泉麻人
●脱建築とニューグロテスク(1985)
粟津潔 吉田光邦 ジェイムズ・ワインズ
●情報化社会に水を売る(1985)
細川護煕 粟津潔
●CIデザイン世界戦争(1986)
亀倉雄策 糸井重里
●チベットの女形(1986)
糸井重里 中沢新一 黒川紀章
●放置プレイの法則(1987)
糸井重里 中沢新一
●牛もうもうもうと霧を出たりけり(1987)
糸井重里 原田泰治 ビル・レイシー 芳賀徹
●奇々怪々 講談「百物語」(1987)
神田陽子 杉浦日向子 萩原朔美
●境界線上の劇場論(1989)
朝倉摂 池辺晋一郎
●混浴のアナキズム(1990)
田中優子
●自然発生した雨後の竹の子族
加藤正一 三枝成彰 杉浦日向子
●神亡き後のアート(1990)
伊東順二
●メディアサバイバル宣言(1991)
三宅理一 田中優子 黒川紀章 河原敏文 高松伸 竹山聖
●ダジャレの文化人類学(1993)
杉浦日向子 山口昌男 荻野アンナ
●広告表現の局地化(1995)
田中一光 中島信也
●変態少女ダンスの世界(1996)
黒川紀章 香山リカ
●欲望の鉱脈(1998)
西川りゅうじん
●大阪の若草物語(1998)
コシノアヤコ コシノヒロコ
●ウソも方便(1998)
伊奈かっぺい 山上進 つボイノリオ
●スカートの中の少女論(1998)
荒木経惟 サエキけんぞう 俵万智
●色白美人とガングロ少女(1999)
鈴木その子 中尊寺ゆつこ 原島博
●世紀末遊びの王国(2000)
香山リカ 森村泰昌
あとがき 東京モンスターランド/かいぶつ達は吼えたか
20世紀カルチャーのメガロポリスで
アングラサブカルの時代の面白かったこと、また懐かしいこと!
時代と自伝。
現代に近づくにつれ、著者のステータスや、やりたい仕事をやりたいように実現するだけの力はアップしているのだが、昔の話の方が、断然生き生きしていて、面白い。
著者の年齢のせいなのか、時代がそうなのか。
途中、恋愛のことなども語られる。言葉遊びの好きな人だとは思っていたが、予想以上のダジャリストのようだ。
榎本氏は、寺山の本の装幀や、ビックリハウスなどで、馴染み深い人だったが、今は京都造形芸術大学の教授なんだ!会いに行こうと思えば手の届くところ(足の届く?)にいらっしゃったとは!
『なぜケータイ小説は売れるのか』
2009年4月20日 読書本田透の『なぜケータイ小説は売れるのか』を読んだ。
以下、目次
序章 ケータイ小説七つの大罪
大罪が刻印されたケータイ小説!?
第1の罪 売春
第2の罪 レイプ
第3の罪 妊娠
第4の罪 薬物
第5の罪 不治の病
第6の罪 自殺
第7の罪 真実の愛
第1章 ケータイ小説のあらまし
ケータイ小説ブームとその背景
PCとは異なるケータイ文化
ケータイ小説市場の特徴は何か
Yoshiが築いたジャンル「ケータイ小説」
『Deep Love』は他の文芸作品と大きく異なる
ケータイ小説市場の広がり
乱立・分裂するケータイ小説市場
第2章 ケータイ小説市場の最前線
ケータイ小説の現場の声
ケータイ小説で再スタートを切った版元
ケータイ小説を出版する版元
ケータイ小説に対して沸き上がった、盗作疑惑
ケータイ小説界の「プロ作家」からの視点
第3章 ケータイ小説の内容
ケータイ小説のヒット作を読む
全ての始まり〜『Deep Love』Yoshi(スターツ出版)〜
ケータイ小説のターニングポイントとなったシリーズ『天使がくれたもの』Chaco(スタ−ツ出版)〜
ケータイ小説の名を天下に知らしめた〜『恋空 切ナイ恋物語』美嘉(スターツ出版)〜
恋愛説話の完成形〜『赤い糸』メイ(ゴマブックス)〜
ケータイ小説の人気作品を読んでみて
第4章 ケータイ小説を巡る言説
「ケータイ小説女を口説く」から始まる
ケータイ小説は「小説」じゃない
ケータイ小説を読む男が出世できる!?
ケータイ小説は文学を殺すか
ケータイ小説が売れることに耐えられない人々
ケータイ小説は結局、「文学」なのか
第5章 なぜケータイ小説は売れるのか
すべての人間が「物語」を発信できる、新しい時代
活版印刷、ネット、そしてケータイへ
ケータイ小説の文体は、デバイスに規定されている
ニヒリズムの時代と、物語のパーソナル化
ケータイ小説の必要性、文学の必要性
ニヒリズムの果てに希望はあるか
「あとがき」で打ち明けているように、本書は「ライトノベル作家が、ケータイ小説を読んでみた」企画である。「はじめに」で本書の流れがコンパクトにまとめてあり、「あとがき」ではケータイ小説が売れる理由が簡潔にまとめてあり、また、ライトノベルとケータイ小説の違い(著者によると、水と油)も書いてある。
以前読んだ『1995未了の問題圏』で杉田俊介がケータイ小説を、地方の女性のプロレタリア文学と評しているのが面白くて、本書も興味深く読んだが、本書でも「ケータイ小説の主な読者は地方都市の女子中高生だ」とあり、なぜ読まれるのかの分析で「現状維持」と「保守回帰」という言葉が使われていた。本書全体で、そこはかとなくケータイ小説の読者のレベルの低さを面白がるところがあって、その扱い方はまるでオリエンタリズムである。なぜ売れるのか、なぜ読まれるのかの分析も、ほとんど人食い人種がなぜ人肉を食べるのかを分析する手つきと同じなのだ。いや、それが滅法面白いんですけど。なぜ地方の女子中高生はケータイ小説を読むのか、という問題は、なぜ猫はマタタビが好きなのか、という問題にも似ている。要するに、自分は絶対にケータイ小説なんかいいとは思わないけど、ケータイ小説を好む人種も存在する、そしてそのわけは、という分析。
とにかく、読んでいて痛快このうえない本である。
『Deep Love』はバブル時代に蘇った『銭ゲバ』だ、という面白い指摘も随所に仕掛けられているのだ。
以下、目次
序章 ケータイ小説七つの大罪
大罪が刻印されたケータイ小説!?
第1の罪 売春
第2の罪 レイプ
第3の罪 妊娠
第4の罪 薬物
第5の罪 不治の病
第6の罪 自殺
第7の罪 真実の愛
第1章 ケータイ小説のあらまし
ケータイ小説ブームとその背景
PCとは異なるケータイ文化
ケータイ小説市場の特徴は何か
Yoshiが築いたジャンル「ケータイ小説」
『Deep Love』は他の文芸作品と大きく異なる
ケータイ小説市場の広がり
乱立・分裂するケータイ小説市場
第2章 ケータイ小説市場の最前線
ケータイ小説の現場の声
ケータイ小説で再スタートを切った版元
ケータイ小説を出版する版元
ケータイ小説に対して沸き上がった、盗作疑惑
ケータイ小説界の「プロ作家」からの視点
第3章 ケータイ小説の内容
ケータイ小説のヒット作を読む
全ての始まり〜『Deep Love』Yoshi(スターツ出版)〜
ケータイ小説のターニングポイントとなったシリーズ『天使がくれたもの』Chaco(スタ−ツ出版)〜
ケータイ小説の名を天下に知らしめた〜『恋空 切ナイ恋物語』美嘉(スターツ出版)〜
恋愛説話の完成形〜『赤い糸』メイ(ゴマブックス)〜
ケータイ小説の人気作品を読んでみて
第4章 ケータイ小説を巡る言説
「ケータイ小説女を口説く」から始まる
ケータイ小説は「小説」じゃない
ケータイ小説を読む男が出世できる!?
ケータイ小説は文学を殺すか
ケータイ小説が売れることに耐えられない人々
ケータイ小説は結局、「文学」なのか
第5章 なぜケータイ小説は売れるのか
すべての人間が「物語」を発信できる、新しい時代
活版印刷、ネット、そしてケータイへ
ケータイ小説の文体は、デバイスに規定されている
ニヒリズムの時代と、物語のパーソナル化
ケータイ小説の必要性、文学の必要性
ニヒリズムの果てに希望はあるか
「あとがき」で打ち明けているように、本書は「ライトノベル作家が、ケータイ小説を読んでみた」企画である。「はじめに」で本書の流れがコンパクトにまとめてあり、「あとがき」ではケータイ小説が売れる理由が簡潔にまとめてあり、また、ライトノベルとケータイ小説の違い(著者によると、水と油)も書いてある。
以前読んだ『1995未了の問題圏』で杉田俊介がケータイ小説を、地方の女性のプロレタリア文学と評しているのが面白くて、本書も興味深く読んだが、本書でも「ケータイ小説の主な読者は地方都市の女子中高生だ」とあり、なぜ読まれるのかの分析で「現状維持」と「保守回帰」という言葉が使われていた。本書全体で、そこはかとなくケータイ小説の読者のレベルの低さを面白がるところがあって、その扱い方はまるでオリエンタリズムである。なぜ売れるのか、なぜ読まれるのかの分析も、ほとんど人食い人種がなぜ人肉を食べるのかを分析する手つきと同じなのだ。いや、それが滅法面白いんですけど。なぜ地方の女子中高生はケータイ小説を読むのか、という問題は、なぜ猫はマタタビが好きなのか、という問題にも似ている。要するに、自分は絶対にケータイ小説なんかいいとは思わないけど、ケータイ小説を好む人種も存在する、そしてそのわけは、という分析。
とにかく、読んでいて痛快このうえない本である。
『Deep Love』はバブル時代に蘇った『銭ゲバ』だ、という面白い指摘も随所に仕掛けられているのだ。
『自由について 七つの問答』
2009年4月16日 読書
丸山眞男の『自由について 七つの問答』を読んだ。
聞き手は鶴見俊輔、北沢恒彦、塩沢由典。
僕にとっての「丸山以後の丸山プロジェクト」の一環として読んだもの。なに?そんなプロジェクト、いつ思い立ったのか!今。
以下、目次。
第1部 戦争の記憶の底から
第1の問答
日本の思想史をとらえるにあたって、丸山さんは「思想が本格的な『正統』の条件を充たさない」ことを、その特徴として挙げておられます。だとすれば、ヨーロッパ、中国などでは「正統」は揺るがぬものとしてあるということですか?
戦後初めての広島
初めに「異端」ありき
軍隊の中で
二つの「正統」−”レジティマシー”と”オーソドクシー”
教典の背後に
第2の問答
仏教が日本思想史にもたらした影響について、お考えを聞かせてください。
宗教改革としての鎌倉仏教
個人の行動パターンに影響をもたらすもの
聖と俗、四つの類型
戦争の下の仏教
政治と仏教
キリスト教の背後に
第3の問答
志願して軍隊に入った若い兵士も、塹壕の中では「この戦争は間違っている」という信念を抱くことがあると思います。丸山さんのお仕事の中にも、そういう<服従−不服従>への観点がはらまれているのではないですか?
宣長論の視野
「神武創業の古」の逆説
「高度成長」への予測を誤る
アメリカの政治学
第4の問答
マルクス主義は、丸山さんの学問にどんな影響をもたらしましたか?また、そうした思想の再生の可能性について、お考えがあれば聞かせてください。
「疎外」観の深まり
南原繁と長谷川如是閑
京大事件以後
新カント派とスペイン内乱とのあいだで
第2の『資本論』へ
第2部 私があなたと考えを異にする自由
第5の問答
敗北者、たとえば西郷隆盛をどう評価されますか?また、「政治家」の政治責任と「政治思想家」の政治責任について、その違いをどのようにお考えになりますか?
マッカーシズムのことなど
「シンデモラッパヲハナシマセンデシタ」
結果責任とプライオリティ
西郷とトクヴイル
価値の多元性を掘りおこす
自由の次元
ワイマール再考
幕臣意識と自由民権
形式的自由のディレンマ
第6の問答
支配者ではない人びとが、対立を暴力的なものにしないように互いの付き合いを工夫することも、政治思想的なものではないでしょうか?
「国家学」から「政治学」にまたがって
ファシズムのレジティメーション
「賢明さ」をめぐって
政治嫌いの政治行動
種痘も政治?
第7の問答
現在の国際社会の中で、日本の「国民的統合」をどうお考えになりますか?未来にむけて、天皇制についての考えもお聞かせください。
多数少数決原理
『御成敗式目』−「道理」の精神
下から定義される政治
承認、協賛、翼賛
古代からの「過密情報社会」
ポリスが壊れて、コスモポリスが生まれる
「政事」の構造
平田派国学の「裏切られた革命」
絶対者がいない世界
女性の太陽神、複数的な天皇
電波の中の『枕草子』
解説
丸山さんを囲む会と文体研究会/塩沢由典
丸山眞男おぼえがき/鶴見俊輔
タイトルに関連する第2部の「私があなたと考えを異にする自由」はローザ・ルクセンブルクの言葉から。
この会そのものが、丸山先生にお聞きする、というスタンスのせいか、この対談を読むと、丸山眞男の対話におけるイニシアティブのとりかたのすさまじさがよくわかる。
相手を飲んでかかる、とでもいうのか。
「丸山眞男」のレッテルで語られることと、本人とのずれも感じた。これこそ、丸山以後の丸山プロジェクトの意味!って、さっき思いついただけなのに。
聞き手は鶴見俊輔、北沢恒彦、塩沢由典。
僕にとっての「丸山以後の丸山プロジェクト」の一環として読んだもの。なに?そんなプロジェクト、いつ思い立ったのか!今。
以下、目次。
第1部 戦争の記憶の底から
第1の問答
日本の思想史をとらえるにあたって、丸山さんは「思想が本格的な『正統』の条件を充たさない」ことを、その特徴として挙げておられます。だとすれば、ヨーロッパ、中国などでは「正統」は揺るがぬものとしてあるということですか?
戦後初めての広島
初めに「異端」ありき
軍隊の中で
二つの「正統」−”レジティマシー”と”オーソドクシー”
教典の背後に
第2の問答
仏教が日本思想史にもたらした影響について、お考えを聞かせてください。
宗教改革としての鎌倉仏教
個人の行動パターンに影響をもたらすもの
聖と俗、四つの類型
戦争の下の仏教
政治と仏教
キリスト教の背後に
第3の問答
志願して軍隊に入った若い兵士も、塹壕の中では「この戦争は間違っている」という信念を抱くことがあると思います。丸山さんのお仕事の中にも、そういう<服従−不服従>への観点がはらまれているのではないですか?
宣長論の視野
「神武創業の古」の逆説
「高度成長」への予測を誤る
アメリカの政治学
第4の問答
マルクス主義は、丸山さんの学問にどんな影響をもたらしましたか?また、そうした思想の再生の可能性について、お考えがあれば聞かせてください。
「疎外」観の深まり
南原繁と長谷川如是閑
京大事件以後
新カント派とスペイン内乱とのあいだで
第2の『資本論』へ
第2部 私があなたと考えを異にする自由
第5の問答
敗北者、たとえば西郷隆盛をどう評価されますか?また、「政治家」の政治責任と「政治思想家」の政治責任について、その違いをどのようにお考えになりますか?
マッカーシズムのことなど
「シンデモラッパヲハナシマセンデシタ」
結果責任とプライオリティ
西郷とトクヴイル
価値の多元性を掘りおこす
自由の次元
ワイマール再考
幕臣意識と自由民権
形式的自由のディレンマ
第6の問答
支配者ではない人びとが、対立を暴力的なものにしないように互いの付き合いを工夫することも、政治思想的なものではないでしょうか?
「国家学」から「政治学」にまたがって
ファシズムのレジティメーション
「賢明さ」をめぐって
政治嫌いの政治行動
種痘も政治?
第7の問答
現在の国際社会の中で、日本の「国民的統合」をどうお考えになりますか?未来にむけて、天皇制についての考えもお聞かせください。
多数少数決原理
『御成敗式目』−「道理」の精神
下から定義される政治
承認、協賛、翼賛
古代からの「過密情報社会」
ポリスが壊れて、コスモポリスが生まれる
「政事」の構造
平田派国学の「裏切られた革命」
絶対者がいない世界
女性の太陽神、複数的な天皇
電波の中の『枕草子』
解説
丸山さんを囲む会と文体研究会/塩沢由典
丸山眞男おぼえがき/鶴見俊輔
タイトルに関連する第2部の「私があなたと考えを異にする自由」はローザ・ルクセンブルクの言葉から。
この会そのものが、丸山先生にお聞きする、というスタンスのせいか、この対談を読むと、丸山眞男の対話におけるイニシアティブのとりかたのすさまじさがよくわかる。
相手を飲んでかかる、とでもいうのか。
「丸山眞男」のレッテルで語られることと、本人とのずれも感じた。これこそ、丸山以後の丸山プロジェクトの意味!って、さっき思いついただけなのに。
『私にとっての20世紀』
2009年4月14日 読書
加藤周一の『私にとっての20世紀』を読んだ。
以下、目次。
第1部 いま、ここにある危機
未知のものへの関心
私にとっての20世紀
1999年に起きたこと
対米従属しかし反米感情
この10年の危機
国連決議なき空爆
日本の大勢順応主義
日本人は本当に変わったのか
情報の不均等性
第2部 戦前・戦後その連続と断絶
人間は本性において悪魔なのではない
死刑廃止と戦争反対
人格を破壊された旧友
知的好奇心について
なし崩し的権力掌握の歴史
「近代の超克」座談会について
「国体」という言葉について
サルトルと自由について
死の切迫する状況のなかで読む
戦争中の芸術活動について
「雑種文化論」について
憲法問題を考える
はじめての南京訪問
第3部 社会主義冷戦のかなたへ
ソ連邦の崩壊
19世紀の社会主義思想
ソ連型官僚主義的社会主義
プラハの春
冷戦下における社会主義圏訪問
クロアチア紀行
サルトルのソヴィエト観
ペレストロイカについて
中国問題は冷戦史観では理解できない
第4部 言葉・ナショナリズム
20世紀の負の遺産
歴史的文化的ナショナリズム
日本人は「国」という言葉を使いたがる
大和心について
本居宣長の古事記解釈
富永仲基の『翁の文』
言葉に対する誇り
文学の仕事
テレビ番組を書籍化したもので、語り口はきわめてわかりやすい。
ところで、僕だって20世紀に生をうけて、相当の年数を過ごしてきたはずなのだが、社会や歴史といったものにほとんど関わっていないのを痛感した。時代風俗、流行にも乗ってこなかったのだ。僕にとっての20世紀は、これからなのかもしれない。
以下、目次。
第1部 いま、ここにある危機
未知のものへの関心
私にとっての20世紀
1999年に起きたこと
対米従属しかし反米感情
この10年の危機
国連決議なき空爆
日本の大勢順応主義
日本人は本当に変わったのか
情報の不均等性
第2部 戦前・戦後その連続と断絶
人間は本性において悪魔なのではない
死刑廃止と戦争反対
人格を破壊された旧友
知的好奇心について
なし崩し的権力掌握の歴史
「近代の超克」座談会について
「国体」という言葉について
サルトルと自由について
死の切迫する状況のなかで読む
戦争中の芸術活動について
「雑種文化論」について
憲法問題を考える
はじめての南京訪問
第3部 社会主義冷戦のかなたへ
ソ連邦の崩壊
19世紀の社会主義思想
ソ連型官僚主義的社会主義
プラハの春
冷戦下における社会主義圏訪問
クロアチア紀行
サルトルのソヴィエト観
ペレストロイカについて
中国問題は冷戦史観では理解できない
第4部 言葉・ナショナリズム
20世紀の負の遺産
歴史的文化的ナショナリズム
日本人は「国」という言葉を使いたがる
大和心について
本居宣長の古事記解釈
富永仲基の『翁の文』
言葉に対する誇り
文学の仕事
テレビ番組を書籍化したもので、語り口はきわめてわかりやすい。
ところで、僕だって20世紀に生をうけて、相当の年数を過ごしてきたはずなのだが、社会や歴史といったものにほとんど関わっていないのを痛感した。時代風俗、流行にも乗ってこなかったのだ。僕にとっての20世紀は、これからなのかもしれない。
『1995年 未了の問題圏』
2009年4月13日 読書中西新太郎編による『1995年 未了の問題圏』を読んだ。
はじめに ようこそ!「バブル崩壊後の焼け野原」へ/雨宮処凛
序論 1995年から始まる/中西新太郎
1、ふたつの厄災の年
2、格差・貧困化の時代
3、戦後スペクトラム像を超える
4、ポスト95年−どこからどこへ
5、格差・貧困化の文化形象
6、結びにかえて
対論1 生きづらさと1995年/雨宮処凛×中西新太郎
「平坦な戦場」という言葉が本当にしっくり来ました。
現実にみんなが気づくまでの時差に、自分たちは落ち込んでいたんだなと思います。
フリーターは外国人労働者と露骨に競わされていると、気づかざるをえないんです。
生き延びるために、『ゴーマニズム宣言』を読んだ。
自分たちの将来はホームレスだろうって予感していました。
経済状況ひとつでひっくり返ったりしない、絶対的な価値観が欲しかった。
みんなが「終わりなき日常」を生きられるわけではないんです。
バブル崩壊後の焼け野原で、女子高生を見習えと言われても。
『完全自殺マニュアル』を心の支えに生きていました。
働かせるシステムの精緻さは、30年前の比ではない。
フリーター時代は、社会から5センチくらい浮いている感覚がありました。
「生きさせろ」に思想は関係ないじゃないですか。
ヘイワでユタカだと勘違いされていた90年代と、「生きてる実感」問題/雨宮処凛
対論2 戦後・宗教・ナショナリズム/中島岳志×中西新太郎
宗教が一見肥大化しているようで、実はどんどん痩せ細っている。
「ゆるくてアツい」ぼくらの志向性は、団塊とつながっているところがある。
現代の「ジモト」志向を、新しいパトリと考えることができるか。
上からのナショナリズムは、幻想の平等性を付与できる。
上からのナショナリズムも、より洗練された形を獲得している。
ポストモダンとの出会いはフリッパーズ・ギターでした。
ゴーマニズムに頼る限り、公共性からどこまでも離れていく。
「祭り」が政治を動かす現状は、非常にあぶなっかしいですね。
人間の生きた軌跡を描くことで、左右の二分法を崩したいんです。
ゆるくて熱いーよしもとよしとも『青い車』/中島岳志
対論3 「構造改革」と貧困/湯浅誠×中西新太郎
日本社会全体をおおう貧困の広がりが、90年代後半を通じて見えてきた。
人間の定義がどこかで変わってしまった。
大学自治が潰されたことは、決定的に大きかったのではないか。
個人だけでなく、社会の「溜め」が縮小している。
行政が撤退した後の領域で、地域やボランティアの「支え合い」が強いられている。
人間の定義を変えない限り、この貧困を放置するなんてできないはず。
新自由主義でも土建国家でもない形で、社会と個人の関係をどうイメージするべきか。
勝てない闘いはしちゃいけないと思わされているんじゃないですかね。
95年ホームレス襲撃事件と08年無差別通り魔事件/湯浅誠
対論4 家族・不登校・女性労働/栗田隆子×中西新太郎
女性が生きるうえでの選択肢のなさとして、「生きづらさ」にぶつからざるをえないんです。
マイナーな人がマイナーなりに生きていくことの意味を、考えざるをえないんです。
家族に求めていたのは、ある種の親密さとか、拠りどころ。
女性の行き場のなさの出口として、オウムが求められたのではないか。
「希望は結婚」なのか?
弱さと性の関係を考えないと、女性が関係をもつ可能性の幅が広がらない。
それぞれの場所を少しでも生きやすくしようとしている人たちが、力の出る言葉をつくりたい。
不登校の不気味さは結局、家族の問題に落とし込まれてしまった。
わけのわからない薄気味悪さと、つきあっていきたいんです。
95年の「窓」/栗田隆子
対論5 サブカルチャーと批評/杉田俊介×中西新太郎
95年前後のサブカルには、他者への恐怖と寛容の模索が同居していた。
加害者にも被害者にもなりうる者どうしが共に生きる可能性を、『寄生獣』は問うていた。
他者との闘争を通じた対話の可能性を問うてきたのが少年マンガの歴史だと思います。
『ナウシカ』は設計されたユートピアではない未来の可能性に賭けた。
日本のマンガやアニメがなぜあれだけ性的な徴候に満ちているのか、精神分析的に見ていく必要があると思います。
性や暴力表現の空気のような蔓延は、真の暴力を隠蔽しているのではないか。
無限に強さをめざす『ジャンプ』の エートスは資本制の基本原理にマッチしている。
少年/少女文化のボーダーレス化は、ジェンダー装置の内的変動を背景としている。
虚構なら他人に何をしても構わない、という暴力の自己消去こそがトラップなんじゃないか。
同期=シンクロへの欲望は、他者と向き合うことを回避してしまう。
サブカルの想像力に根付いた、庶民的な共存の知恵を信頼しています。
「あちこちがただれてくるよな平和」と爆裂弾/杉田俊介
対論を終えて/中西新太郎
みな、一様にゴーマニズムに魅かれたことを告白し、一方、宮台への違和感を表明している。また、完全自殺マニュアルとか。僕の世代になると、これらベストセラーの思想なり傾向なりは、オプションでしかないのだが、当時の若い世代にとっては大きな存在だったのかもしれない。
はじめに ようこそ!「バブル崩壊後の焼け野原」へ/雨宮処凛
序論 1995年から始まる/中西新太郎
1、ふたつの厄災の年
2、格差・貧困化の時代
3、戦後スペクトラム像を超える
4、ポスト95年−どこからどこへ
5、格差・貧困化の文化形象
6、結びにかえて
対論1 生きづらさと1995年/雨宮処凛×中西新太郎
「平坦な戦場」という言葉が本当にしっくり来ました。
現実にみんなが気づくまでの時差に、自分たちは落ち込んでいたんだなと思います。
フリーターは外国人労働者と露骨に競わされていると、気づかざるをえないんです。
生き延びるために、『ゴーマニズム宣言』を読んだ。
自分たちの将来はホームレスだろうって予感していました。
経済状況ひとつでひっくり返ったりしない、絶対的な価値観が欲しかった。
みんなが「終わりなき日常」を生きられるわけではないんです。
バブル崩壊後の焼け野原で、女子高生を見習えと言われても。
『完全自殺マニュアル』を心の支えに生きていました。
働かせるシステムの精緻さは、30年前の比ではない。
フリーター時代は、社会から5センチくらい浮いている感覚がありました。
「生きさせろ」に思想は関係ないじゃないですか。
ヘイワでユタカだと勘違いされていた90年代と、「生きてる実感」問題/雨宮処凛
対論2 戦後・宗教・ナショナリズム/中島岳志×中西新太郎
宗教が一見肥大化しているようで、実はどんどん痩せ細っている。
「ゆるくてアツい」ぼくらの志向性は、団塊とつながっているところがある。
現代の「ジモト」志向を、新しいパトリと考えることができるか。
上からのナショナリズムは、幻想の平等性を付与できる。
上からのナショナリズムも、より洗練された形を獲得している。
ポストモダンとの出会いはフリッパーズ・ギターでした。
ゴーマニズムに頼る限り、公共性からどこまでも離れていく。
「祭り」が政治を動かす現状は、非常にあぶなっかしいですね。
人間の生きた軌跡を描くことで、左右の二分法を崩したいんです。
ゆるくて熱いーよしもとよしとも『青い車』/中島岳志
対論3 「構造改革」と貧困/湯浅誠×中西新太郎
日本社会全体をおおう貧困の広がりが、90年代後半を通じて見えてきた。
人間の定義がどこかで変わってしまった。
大学自治が潰されたことは、決定的に大きかったのではないか。
個人だけでなく、社会の「溜め」が縮小している。
行政が撤退した後の領域で、地域やボランティアの「支え合い」が強いられている。
人間の定義を変えない限り、この貧困を放置するなんてできないはず。
新自由主義でも土建国家でもない形で、社会と個人の関係をどうイメージするべきか。
勝てない闘いはしちゃいけないと思わされているんじゃないですかね。
95年ホームレス襲撃事件と08年無差別通り魔事件/湯浅誠
対論4 家族・不登校・女性労働/栗田隆子×中西新太郎
女性が生きるうえでの選択肢のなさとして、「生きづらさ」にぶつからざるをえないんです。
マイナーな人がマイナーなりに生きていくことの意味を、考えざるをえないんです。
家族に求めていたのは、ある種の親密さとか、拠りどころ。
女性の行き場のなさの出口として、オウムが求められたのではないか。
「希望は結婚」なのか?
弱さと性の関係を考えないと、女性が関係をもつ可能性の幅が広がらない。
それぞれの場所を少しでも生きやすくしようとしている人たちが、力の出る言葉をつくりたい。
不登校の不気味さは結局、家族の問題に落とし込まれてしまった。
わけのわからない薄気味悪さと、つきあっていきたいんです。
95年の「窓」/栗田隆子
対論5 サブカルチャーと批評/杉田俊介×中西新太郎
95年前後のサブカルには、他者への恐怖と寛容の模索が同居していた。
加害者にも被害者にもなりうる者どうしが共に生きる可能性を、『寄生獣』は問うていた。
他者との闘争を通じた対話の可能性を問うてきたのが少年マンガの歴史だと思います。
『ナウシカ』は設計されたユートピアではない未来の可能性に賭けた。
日本のマンガやアニメがなぜあれだけ性的な徴候に満ちているのか、精神分析的に見ていく必要があると思います。
性や暴力表現の空気のような蔓延は、真の暴力を隠蔽しているのではないか。
無限に強さをめざす『ジャンプ』の エートスは資本制の基本原理にマッチしている。
少年/少女文化のボーダーレス化は、ジェンダー装置の内的変動を背景としている。
虚構なら他人に何をしても構わない、という暴力の自己消去こそがトラップなんじゃないか。
同期=シンクロへの欲望は、他者と向き合うことを回避してしまう。
サブカルの想像力に根付いた、庶民的な共存の知恵を信頼しています。
「あちこちがただれてくるよな平和」と爆裂弾/杉田俊介
対論を終えて/中西新太郎
みな、一様にゴーマニズムに魅かれたことを告白し、一方、宮台への違和感を表明している。また、完全自殺マニュアルとか。僕の世代になると、これらベストセラーの思想なり傾向なりは、オプションでしかないのだが、当時の若い世代にとっては大きな存在だったのかもしれない。
谷町月いち古書即売会@大阪古書会館、宇宙戦争
2009年4月10日 読書今日は大阪古書会館で「谷町月いち古書即売会」
『宝石』を3冊買う。
昔の探偵小説雑誌はほとんど買っていなかったが、最近はなんだか面白くてよく手を出すようになった。大下宇陀児の書いたものを読もうと思ったら、こういう雑誌に手を出さざるをえないからだ。大下宇陀児関連で書いてみると。
『宝石』昭和26年7月号
『石の下の記録』で探偵作家クラブ賞長編賞をとり、グラビヤに「大いに自作を語る」として、写真とコメントが載っている。
そのコメントで「特筆すべきことが二つほどあるが、その一つは、木々君がこの小説をたいそうほめてくれたことであり、他の一つは、乱歩さんが、この小説を賞としたくなかった、ということである」とある。
その内容については、この号にある「探偵作家クラブ賞を繞って 探偵小説のあり方を語る座談会」に詳しく書かれている。タイトルには「本格か?文学か?」と書いてあるので、おおよそのところは察しがつくだろう。
座談会の出席者は大下宇陀児(長編賞受賞)、島田一男(短編賞受賞)、江戸川乱歩、木々高太郎、水谷準。司会は城昌幸。
この座談会で大下は「探偵小説は読んでみていかにも中学生、子供の読み物が多すぎると思うんだ」とぶちあげる。「本格探偵小説と称するものでも、狙いはその思想の段階においては非常に低いものが多いと思うんです。殺人の動機なんて実際なっちゃおらんと思うんだな。これがね、殺人の動機などがもっと大人が納得できるものでなければ駄目ですよ」こういう論は、僕が推理小説ばっかり読んでいた中学時代には、まさしくいらぬ忠告だったものだ。中学生だからねえ。
この座談会では大下の小説の書き方とかいろいろ興味深いことが語られている。
『宝石』昭和29年4月号
大下は「クラブ賞の将来」という感想が掲載されている。28年度探偵作家クラブ賞が2年連続で該当者なしになったことについて書いている。また、「美しい久作の夢」と題する『瓶詰地獄』解説も書いている。
『増刊 宝石』昭和33年5月エロティックミステリー16集。
大下宇陀児の「悪夢のアラビア」掲載。
以上3冊。いずれも僕が生まれる前に出た雑誌だ。
テレビで「宇宙戦争」
せっかくのダコタ・ファニングが台なしだ、と思った。
家族の再生は、もういい。
なお、宇宙人の乗るドゴラみたいな乗り物、アメリカ軍が兵器で攻めてもビクともしなかったが、なんと大阪では撃沈した、という。アメリカ人は「日本にできてアメリカにできないはずがない!」と勇気をふりしぼるのだ。
しかし、市民が銃も持たず、軍隊もない日本の大阪で、いかにしてあのドラゴを退治したのか、それが見たかった。結局、宇宙人は微生物にやられて勝手に死んでしまうわけだが、その手の生物兵器的なものが、大阪にはそなわっていたのかもしれない。
『宝石』を3冊買う。
昔の探偵小説雑誌はほとんど買っていなかったが、最近はなんだか面白くてよく手を出すようになった。大下宇陀児の書いたものを読もうと思ったら、こういう雑誌に手を出さざるをえないからだ。大下宇陀児関連で書いてみると。
『宝石』昭和26年7月号
『石の下の記録』で探偵作家クラブ賞長編賞をとり、グラビヤに「大いに自作を語る」として、写真とコメントが載っている。
そのコメントで「特筆すべきことが二つほどあるが、その一つは、木々君がこの小説をたいそうほめてくれたことであり、他の一つは、乱歩さんが、この小説を賞としたくなかった、ということである」とある。
その内容については、この号にある「探偵作家クラブ賞を繞って 探偵小説のあり方を語る座談会」に詳しく書かれている。タイトルには「本格か?文学か?」と書いてあるので、おおよそのところは察しがつくだろう。
座談会の出席者は大下宇陀児(長編賞受賞)、島田一男(短編賞受賞)、江戸川乱歩、木々高太郎、水谷準。司会は城昌幸。
この座談会で大下は「探偵小説は読んでみていかにも中学生、子供の読み物が多すぎると思うんだ」とぶちあげる。「本格探偵小説と称するものでも、狙いはその思想の段階においては非常に低いものが多いと思うんです。殺人の動機なんて実際なっちゃおらんと思うんだな。これがね、殺人の動機などがもっと大人が納得できるものでなければ駄目ですよ」こういう論は、僕が推理小説ばっかり読んでいた中学時代には、まさしくいらぬ忠告だったものだ。中学生だからねえ。
この座談会では大下の小説の書き方とかいろいろ興味深いことが語られている。
『宝石』昭和29年4月号
大下は「クラブ賞の将来」という感想が掲載されている。28年度探偵作家クラブ賞が2年連続で該当者なしになったことについて書いている。また、「美しい久作の夢」と題する『瓶詰地獄』解説も書いている。
『増刊 宝石』昭和33年5月エロティックミステリー16集。
大下宇陀児の「悪夢のアラビア」掲載。
以上3冊。いずれも僕が生まれる前に出た雑誌だ。
テレビで「宇宙戦争」
せっかくのダコタ・ファニングが台なしだ、と思った。
家族の再生は、もういい。
なお、宇宙人の乗るドゴラみたいな乗り物、アメリカ軍が兵器で攻めてもビクともしなかったが、なんと大阪では撃沈した、という。アメリカ人は「日本にできてアメリカにできないはずがない!」と勇気をふりしぼるのだ。
しかし、市民が銃も持たず、軍隊もない日本の大阪で、いかにしてあのドラゴを退治したのか、それが見たかった。結局、宇宙人は微生物にやられて勝手に死んでしまうわけだが、その手の生物兵器的なものが、大阪にはそなわっていたのかもしれない。
『自己内対話−3冊のノートから』
2009年4月9日 読書丸山眞男の『自己内対話−3冊のノートから』を読んだ。
1、折たく柴の記
2、日記
3、春曙帖
本書は丸山眞男没後に発見されたノートを復刻したもので、発表を意識されて書かれたものではない。「凡例」にあるとおり、「これは、読書、抄録、談話要約、発想、告白、体験、社会批判、感想、省察、その他などを含む覚書メモで多岐にわたっている」
後半には東大紛争で丸山がつるしあげられたことの顛末とか書いてあって、ぐいぐい読まされた。それ以外にもいろいろ面白いところがあったので、いくつか引用しておこう。
結果として非常に大きくなった出来事を、あたかも何人によっても狂瀾を既倒にくつがえしえない「必然的」な歴史的事件のように説明したくなるのは、われわれに共通した知的誘惑である。東大紛争もその一つである。それがエスカレートした過程を微細にみるならば、まだボヤのうちに、大火にならぬうちに消火しえたであろう無数のチャンスを見出すであろうし、また、そこでたまたまリーダーシップをとった人々が、もし他の人だったら、というような無数の「もし」を考えうるであろう。
しかし東京帝大の助教授という「地位」は大したものだった。
(中略)
それまで定期的につづいていた、特高ないしは憲兵隊の「御訪問」はバッタリと途絶えた。それにかわって(!)殺到して私をなやませたのは縁談だった。
生きざま死にざまに人間の深淵をかいま見ることにだけ感動し、そこにだけ「ほんもの」「にせもの」という−実は単純な−人間の分類法を見出す、ほとんど処置なしのロマン的思考の氾濫!
民衆は偉大だとか、民衆の力を評価せよ、とかいう日本のインテリのポピュリズムほど、滑稽なものはない。自分は民衆の一人だということを一時も考えたことがないのだろうか。自分は偉大だとか、自分のエネルギーを尊重せよとか書きたてる無神経さ!
1、折たく柴の記
2、日記
3、春曙帖
本書は丸山眞男没後に発見されたノートを復刻したもので、発表を意識されて書かれたものではない。「凡例」にあるとおり、「これは、読書、抄録、談話要約、発想、告白、体験、社会批判、感想、省察、その他などを含む覚書メモで多岐にわたっている」
後半には東大紛争で丸山がつるしあげられたことの顛末とか書いてあって、ぐいぐい読まされた。それ以外にもいろいろ面白いところがあったので、いくつか引用しておこう。
結果として非常に大きくなった出来事を、あたかも何人によっても狂瀾を既倒にくつがえしえない「必然的」な歴史的事件のように説明したくなるのは、われわれに共通した知的誘惑である。東大紛争もその一つである。それがエスカレートした過程を微細にみるならば、まだボヤのうちに、大火にならぬうちに消火しえたであろう無数のチャンスを見出すであろうし、また、そこでたまたまリーダーシップをとった人々が、もし他の人だったら、というような無数の「もし」を考えうるであろう。
しかし東京帝大の助教授という「地位」は大したものだった。
(中略)
それまで定期的につづいていた、特高ないしは憲兵隊の「御訪問」はバッタリと途絶えた。それにかわって(!)殺到して私をなやませたのは縁談だった。
生きざま死にざまに人間の深淵をかいま見ることにだけ感動し、そこにだけ「ほんもの」「にせもの」という−実は単純な−人間の分類法を見出す、ほとんど処置なしのロマン的思考の氾濫!
民衆は偉大だとか、民衆の力を評価せよ、とかいう日本のインテリのポピュリズムほど、滑稽なものはない。自分は民衆の一人だということを一時も考えたことがないのだろうか。自分は偉大だとか、自分のエネルギーを尊重せよとか書きたてる無神経さ!
『9・11以後 丸山真男をどう読むか』
2009年4月8日 読書菅孝行の『9・11以後 丸山真男をどう読むか』を読んだ。
以下、目次。
1、9・11以後 丸山真男をどう論じるか
この60年のさまざまな言及
丸山真男をいま読む意味
9・11以後ということの意味
ブッシュの戦争と<西欧の没落>
近代政治の規範と丸山の仕事
反「西欧近代」「戦後民主主義」論としての丸山批判
公共性の再構成のために
不可解な情熱−ポスト・コロニアル派の「国民主義」批判
虫唾が走る批判スタイル
作為の優位・契約国家・天皇制問題
ナショナリズムとの密通
いま丸山の思想を論じる意味
論じる側の自覚・自己内対話を
2、「時代の子」丸山真男の宿命−作為という価値の呪縛を生きる
丸山真男は「進歩的文化人」であったか
軍国主義批判=自然に対する「作為」の優位
「ファシズム」批判と主体性論争への視座
科学と価値・自由と歴史的拘束
機械的合理主義への距離
大衆が正義?
「別の時代」の子である我々と丸山
3、擁護しなければ葬送もできない−丸山真男の追悼のされ方
運動家!丸山真男
後から出てくる対丸山ケチツケの知恵
河上の鈍い「倫理主義」と西部・佐伯の秩序の思想
判断を誤ったのは誰?
「虚妄としての戦後」への賭け方
丸山をどう超えるのか
4、戦後思想は検証されたか−書評・小熊英二『民主と愛国』
本書の概観
民主・愛国・公共性の通底−戦中・戦後の連続
近代主義・「国民主義」批判の通念からの自由
公共性・ナショナリズムの定義の不在
女性と無名者−マージナルなものをめぐって
主体性論争への誤認
看板の一部に偽り!
あとがき
初出一覧
解説 先人の仕事を検証することの意味/太田昌国
いろいろ考えて、自分なりにも意見を書いてみたが、バッサリと消した。
どうしても、タイトルにあるように、この現代に丸山をどう読むのか、という問題意識に戻ってきてしまうのだ。
それで、これは僕なりの「丸山以後」を考えるためのヒントにしたくて読んだもので、ますます面白くなってきた。
以下、目次。
1、9・11以後 丸山真男をどう論じるか
この60年のさまざまな言及
丸山真男をいま読む意味
9・11以後ということの意味
ブッシュの戦争と<西欧の没落>
近代政治の規範と丸山の仕事
反「西欧近代」「戦後民主主義」論としての丸山批判
公共性の再構成のために
不可解な情熱−ポスト・コロニアル派の「国民主義」批判
虫唾が走る批判スタイル
作為の優位・契約国家・天皇制問題
ナショナリズムとの密通
いま丸山の思想を論じる意味
論じる側の自覚・自己内対話を
2、「時代の子」丸山真男の宿命−作為という価値の呪縛を生きる
丸山真男は「進歩的文化人」であったか
軍国主義批判=自然に対する「作為」の優位
「ファシズム」批判と主体性論争への視座
科学と価値・自由と歴史的拘束
機械的合理主義への距離
大衆が正義?
「別の時代」の子である我々と丸山
3、擁護しなければ葬送もできない−丸山真男の追悼のされ方
運動家!丸山真男
後から出てくる対丸山ケチツケの知恵
河上の鈍い「倫理主義」と西部・佐伯の秩序の思想
判断を誤ったのは誰?
「虚妄としての戦後」への賭け方
丸山をどう超えるのか
4、戦後思想は検証されたか−書評・小熊英二『民主と愛国』
本書の概観
民主・愛国・公共性の通底−戦中・戦後の連続
近代主義・「国民主義」批判の通念からの自由
公共性・ナショナリズムの定義の不在
女性と無名者−マージナルなものをめぐって
主体性論争への誤認
看板の一部に偽り!
あとがき
初出一覧
解説 先人の仕事を検証することの意味/太田昌国
いろいろ考えて、自分なりにも意見を書いてみたが、バッサリと消した。
どうしても、タイトルにあるように、この現代に丸山をどう読むのか、という問題意識に戻ってきてしまうのだ。
それで、これは僕なりの「丸山以後」を考えるためのヒントにしたくて読んだもので、ますます面白くなってきた。
松岡正剛と茂木健一郎による対話『脳と日本人』を読んだ。
第1章 世界知を引き受ける
第2章 異質性礼賛
第3章 科学はなぜあきらめないか
第4章 普遍性をめぐって
第5章 日本という方法
第6章 毒と闇
第7章 国家とは何ものか
第8章 ダーウィニズムと伊勢神宮
第9章 新しい関係の発見へ
第1章 世界知を引き受ける
第2章 異質性礼賛
第3章 科学はなぜあきらめないか
第4章 普遍性をめぐって
第5章 日本という方法
第6章 毒と闇
第7章 国家とは何ものか
第8章 ダーウィニズムと伊勢神宮
第9章 新しい関係の発見へ
『丸山眞男−リベラリストの肖像』
2009年3月25日 読書苅部直の『丸山眞男−リベラリストの肖像』を読んだ。
以下、目次。
序章 思想の運命
第1章 「大正ッ子」のおいたち
第2章 「政治化」の時代に
1、遅れて来た青年
2、「近代」への遡行
第3章 戦中と戦後の間
1、明治は遠くになりにけり
2、大いなる助走
3、八月十五日−終わりと始まり
第4章 「戦後民主主義」の構想
1、焼跡からの出発
2、「天皇制」との訣別
第5章 人間と政治、そして伝統
1、ニヒリズムの影
2、「恐怖の時代」をこえるもの
3、もうひとつの伝統
終章 封印は花やかに
著者は巻頭に、丸山眞男を語る者が帯びる「熱」を指摘する。
批判であれ、擁護であれ、異様な熱をもって語られる。
本書は、そういった熱を極力おさえて書かれているので、丸山眞男を知るには格好の入門書になっている。
本書では、丸山の思想史研究の多くが「伝統」の再解釈の営みであったとして、こう書いている。
「丸山は(中略)『伝統の解釈自身が多義的なんです』と述べている」
「丸山は、過去の思想の中から何を『われわれの伝統』として定着させるべきかは、『現在におけるチョイスの問題』だとする」
テレビで「爆問学問」のスペシャル見てたら、歴史について同じような発言があった。
伝統は、本書でも書いているように、「よく調べてみると、ある時代以後に初めて『支配的』になった、創られた伝統にすぎないことも多い」のは、あえてもう語る必要のないことなんじゃないか、とも思っていたが、そうではないようだ。
そう言われてみると、いろいろ思い当たるふしもある。詳しくは書かないけど。
以下、目次。
序章 思想の運命
第1章 「大正ッ子」のおいたち
第2章 「政治化」の時代に
1、遅れて来た青年
2、「近代」への遡行
第3章 戦中と戦後の間
1、明治は遠くになりにけり
2、大いなる助走
3、八月十五日−終わりと始まり
第4章 「戦後民主主義」の構想
1、焼跡からの出発
2、「天皇制」との訣別
第5章 人間と政治、そして伝統
1、ニヒリズムの影
2、「恐怖の時代」をこえるもの
3、もうひとつの伝統
終章 封印は花やかに
著者は巻頭に、丸山眞男を語る者が帯びる「熱」を指摘する。
批判であれ、擁護であれ、異様な熱をもって語られる。
本書は、そういった熱を極力おさえて書かれているので、丸山眞男を知るには格好の入門書になっている。
本書では、丸山の思想史研究の多くが「伝統」の再解釈の営みであったとして、こう書いている。
「丸山は(中略)『伝統の解釈自身が多義的なんです』と述べている」
「丸山は、過去の思想の中から何を『われわれの伝統』として定着させるべきかは、『現在におけるチョイスの問題』だとする」
テレビで「爆問学問」のスペシャル見てたら、歴史について同じような発言があった。
伝統は、本書でも書いているように、「よく調べてみると、ある時代以後に初めて『支配的』になった、創られた伝統にすぎないことも多い」のは、あえてもう語る必要のないことなんじゃないか、とも思っていたが、そうではないようだ。
そう言われてみると、いろいろ思い当たるふしもある。詳しくは書かないけど。
『時代を読む 「民族」「人権」再考』
2009年3月24日 読書加藤周一と樋口陽一による『時代を読む 「民族」「人権」再考』を読んだ。
1996年に行われた対話。
以下、目次
プロローグ
『美女と野獣』とGI
解放感と敗北感−敗戦
戦後改革の意味するもの
日本の「伝統」と天皇制
「憲法」という文化
「近代知」は終わったのか
「解釈改憲」をめぐって
第1章 自由と平等か/自由か平等か
戦前と戦後−西洋と日本
「同じだから平等」か「違うから平等」か
異論の自由
民主主義的傾向の「復活強化」?
「古典」の意味は
被害感情の欠落
知の虚栄がなくなった
「建て前社会」なのか?
キリスト教とマルクス主義のインパクト
第2章 戦後50年の変容
なぜ憲法を「押しつけられた」のか
「国体」の護持
「ヨーロッパ中心主義」か?
日米安保−その建て前と本音
全面講和論をふり返る
米中と日中の関係
「国際紛争」とは
核−政策の問題か、倫理の問題か
持ってる国が核を減らすこと
第3章 ネイション・ステート<国民国家>
ネイション−デモスかエトノスか
政教分離の意味すること
ネイション・ステートの動揺
「脱亜論」再考
文化の発生地と内容の区別
戦争と民主主義
「主権」の問題
あらためて第九条を考える
理想に近づくための有利な現実的条件
軍の論理と民主主義−徴兵制をめぐって
ナショナリズムをめぐる「右」と「左」
第4章 日本人のアイデンティティ
「普通の国」をめぐって
「雑種文化としての憲法」の可能性
時代錯誤としての「近代の超克」
「共同体」の正と負
ヨーロッパの「悲観主義」をめぐって
多数の専制に抗して
「空気」の圧力
ほんとうの「近代の超克」にむけて
いちおう、対話にはなっているが、衝突する意見があるわけではないので、リベラルなものの考え方のお手本として読める。
目次中で、いくつか注釈をいれておこう。
「ネイション−デモスかエトノスか」
デモスは人民、エトノスは民族ないしエスニシティの単位。
「なぜ憲法を『押しつけられた』のか」
日本政府のもとで作られた「憲法問題調査委員会」では天皇主権を前提にした明治憲法の微温的な改正案しか作れなかった。そのツケがその後繰り返し反動側から「押しつけられた憲法だから改憲だ」という形で出てきている。
なお、この章では樋口氏による「日付の社会学」が語られていて興味深い。
憲法のGHQ案を日本政府に示した日や、閣議決定した日が、リンカーンとワシントンの誕生日を意識して決められており、「リンカーンやワシントンの誕生日でアメリカンデモクラシーを日本に教えるという総指令部の教育者的感覚が期せずして出ているのです」
一方、吉田首相は憲法施行日を2月11日(帝国憲法の公布日と同じ紀元節)にしようとしたが、審議の進行が進まず、次は11月3日(明治節)に公布したいと主張する。「紀元節か明治節か、要するにアンシャン・レジームのシンボルを新憲法にセットしたいという非常にはっきりした方向が出ている」
11月3日公布で6ヶ月後の施行日、5月3日は極東軍事裁判の開廷1周年にあたっていた。その起訴状の公表伝達は4月29日の天長節だった。云々。
巻末には日本国憲法、大日本帝国憲法、マグナカルタ、アメリカ独立宣言、人権宣言、国連憲章、英訳日本国憲法のおまけもついていた。
しかし、「時代を読む」って、もうちょっとタイトルのつけようがあったんじゃないか、と思う。
1996年に行われた対話。
以下、目次
プロローグ
『美女と野獣』とGI
解放感と敗北感−敗戦
戦後改革の意味するもの
日本の「伝統」と天皇制
「憲法」という文化
「近代知」は終わったのか
「解釈改憲」をめぐって
第1章 自由と平等か/自由か平等か
戦前と戦後−西洋と日本
「同じだから平等」か「違うから平等」か
異論の自由
民主主義的傾向の「復活強化」?
「古典」の意味は
被害感情の欠落
知の虚栄がなくなった
「建て前社会」なのか?
キリスト教とマルクス主義のインパクト
第2章 戦後50年の変容
なぜ憲法を「押しつけられた」のか
「国体」の護持
「ヨーロッパ中心主義」か?
日米安保−その建て前と本音
全面講和論をふり返る
米中と日中の関係
「国際紛争」とは
核−政策の問題か、倫理の問題か
持ってる国が核を減らすこと
第3章 ネイション・ステート<国民国家>
ネイション−デモスかエトノスか
政教分離の意味すること
ネイション・ステートの動揺
「脱亜論」再考
文化の発生地と内容の区別
戦争と民主主義
「主権」の問題
あらためて第九条を考える
理想に近づくための有利な現実的条件
軍の論理と民主主義−徴兵制をめぐって
ナショナリズムをめぐる「右」と「左」
第4章 日本人のアイデンティティ
「普通の国」をめぐって
「雑種文化としての憲法」の可能性
時代錯誤としての「近代の超克」
「共同体」の正と負
ヨーロッパの「悲観主義」をめぐって
多数の専制に抗して
「空気」の圧力
ほんとうの「近代の超克」にむけて
いちおう、対話にはなっているが、衝突する意見があるわけではないので、リベラルなものの考え方のお手本として読める。
目次中で、いくつか注釈をいれておこう。
「ネイション−デモスかエトノスか」
デモスは人民、エトノスは民族ないしエスニシティの単位。
「なぜ憲法を『押しつけられた』のか」
日本政府のもとで作られた「憲法問題調査委員会」では天皇主権を前提にした明治憲法の微温的な改正案しか作れなかった。そのツケがその後繰り返し反動側から「押しつけられた憲法だから改憲だ」という形で出てきている。
なお、この章では樋口氏による「日付の社会学」が語られていて興味深い。
憲法のGHQ案を日本政府に示した日や、閣議決定した日が、リンカーンとワシントンの誕生日を意識して決められており、「リンカーンやワシントンの誕生日でアメリカンデモクラシーを日本に教えるという総指令部の教育者的感覚が期せずして出ているのです」
一方、吉田首相は憲法施行日を2月11日(帝国憲法の公布日と同じ紀元節)にしようとしたが、審議の進行が進まず、次は11月3日(明治節)に公布したいと主張する。「紀元節か明治節か、要するにアンシャン・レジームのシンボルを新憲法にセットしたいという非常にはっきりした方向が出ている」
11月3日公布で6ヶ月後の施行日、5月3日は極東軍事裁判の開廷1周年にあたっていた。その起訴状の公表伝達は4月29日の天長節だった。云々。
巻末には日本国憲法、大日本帝国憲法、マグナカルタ、アメリカ独立宣言、人権宣言、国連憲章、英訳日本国憲法のおまけもついていた。
しかし、「時代を読む」って、もうちょっとタイトルのつけようがあったんじゃないか、と思う。
『トリマルキオの饗宴』、スペイン狂想曲
2009年3月19日 読書青柳正規の『トリマルキオの饗宴〜逸楽と飽食のローマ文化』を読んだ。
『サテュリコン』の解読と、ローマ時代の饗宴を堪能。
こういう饗宴をやってみたい。
お金があれば。
作者のペトロニウスもまた面白い。
時間があればくわしく。
見た映画は「スペイン狂想曲」ディートリッヒ。ピエール・ルイスの『女と人形』が原作で、ドスパソスが脚本。
『サテュリコン』の解読と、ローマ時代の饗宴を堪能。
こういう饗宴をやってみたい。
お金があれば。
作者のペトロニウスもまた面白い。
時間があればくわしく。
見た映画は「スペイン狂想曲」ディートリッヒ。ピエール・ルイスの『女と人形』が原作で、ドスパソスが脚本。
第58期王将戦第6局大盤解説会@関西将棋会館、『埴谷雄高 語る』
2009年3月12日 読書関西将棋会館で第58期王将戦七番勝負第6局の大盤解説会。
挑戦者深浦康一王位が3勝、羽生王将2勝で迎えた一戦。
解説者は脇謙二八段。
羽生が深浦をコテンパンにのした。
こんな将棋指されたら、トラウマ必至だ。
角が、角が泣いとる〜!
読んだ本は『埴谷雄高 語る』
埴谷雄高と栗原幸夫の対談をおさめたもの。
以下、目次。
社会と存在の革命
*植民地・台湾での少年時代*文学の内的原点*『唯一者とその所有』を読む*ミューテーション*コンミューン*根源的な不快*一生を通じる妄念*主辞と賓辞*存在と関係*なぜ内面にこだわるのか*自己死滅する「党」*旋回としての革命*ロシア文学の主人公たち*レーニンのミイラ*ソ連とマルクス主義*運動のなかのスパイ*秘密のない運動*『死霊』九章の壁
自由と夢と想像力
*大審問官伝説の現代性*ドストエフスキイの革命性*革命的な党の本質*教育とコンミューン人間*差別に耐えられぬ気分*自由をめぐって*自由を支える倫理*無限者の見る夢*無いものを創ってみせるのが文学*首猛夫はどこにでもいる*吉本隆明との論争*世紀末は不毛か*経験とフィクションと表現*なぜ文庫本に入れないか
二つの転換期を生きて
*社会主義体制崩壊の意味*死者を出発点とした戦後文学*大状況の文学の後に*「形式のリレー」としてのパロディー*文学アクチュアリティー説*花田清輝の前衛性*世の中は進歩する*進歩は首猛夫をひきつれて進む
対談のあとの期待−あとがきにかえて
あとがき(栗原幸夫)
埴谷雄高自身が「あとがきにかえて」で自分自身を「古陋」と評しているが、それが現代を撃つ視点になっていて目を開かせられる。
「現実を超えるなにかが文学だという考えがなくなって、いままであった文学のパロディーで二流三流のものでもとにかく作ればいいというのは、やはり先行き日本文学はちょっと駄目なんじゃないかと思いますがね」とか。
埴谷雄高が井上光晴の『輸送』を批判して
「それはただ現実に起こっていることを未来的に書いただけだ」
「それじゃあ君が朝起きて飯を食って出かけるのと同じじゃないか」
「問題は人の心の無限性であって」
なんて言うのに対して、井上光晴が「埴谷さん『闇のなかの黒い馬』もいいけれど、マーケットへ行って買い物してください」
と応酬するくだりとか。
「あとがきにかえて」の最後は、こうしめくくっている。
「2012年は、ボナパルト敗退200年である」
カッチョイー!
挑戦者深浦康一王位が3勝、羽生王将2勝で迎えた一戦。
解説者は脇謙二八段。
羽生が深浦をコテンパンにのした。
こんな将棋指されたら、トラウマ必至だ。
角が、角が泣いとる〜!
読んだ本は『埴谷雄高 語る』
埴谷雄高と栗原幸夫の対談をおさめたもの。
以下、目次。
社会と存在の革命
*植民地・台湾での少年時代*文学の内的原点*『唯一者とその所有』を読む*ミューテーション*コンミューン*根源的な不快*一生を通じる妄念*主辞と賓辞*存在と関係*なぜ内面にこだわるのか*自己死滅する「党」*旋回としての革命*ロシア文学の主人公たち*レーニンのミイラ*ソ連とマルクス主義*運動のなかのスパイ*秘密のない運動*『死霊』九章の壁
自由と夢と想像力
*大審問官伝説の現代性*ドストエフスキイの革命性*革命的な党の本質*教育とコンミューン人間*差別に耐えられぬ気分*自由をめぐって*自由を支える倫理*無限者の見る夢*無いものを創ってみせるのが文学*首猛夫はどこにでもいる*吉本隆明との論争*世紀末は不毛か*経験とフィクションと表現*なぜ文庫本に入れないか
二つの転換期を生きて
*社会主義体制崩壊の意味*死者を出発点とした戦後文学*大状況の文学の後に*「形式のリレー」としてのパロディー*文学アクチュアリティー説*花田清輝の前衛性*世の中は進歩する*進歩は首猛夫をひきつれて進む
対談のあとの期待−あとがきにかえて
あとがき(栗原幸夫)
埴谷雄高自身が「あとがきにかえて」で自分自身を「古陋」と評しているが、それが現代を撃つ視点になっていて目を開かせられる。
「現実を超えるなにかが文学だという考えがなくなって、いままであった文学のパロディーで二流三流のものでもとにかく作ればいいというのは、やはり先行き日本文学はちょっと駄目なんじゃないかと思いますがね」とか。
埴谷雄高が井上光晴の『輸送』を批判して
「それはただ現実に起こっていることを未来的に書いただけだ」
「それじゃあ君が朝起きて飯を食って出かけるのと同じじゃないか」
「問題は人の心の無限性であって」
なんて言うのに対して、井上光晴が「埴谷さん『闇のなかの黒い馬』もいいけれど、マーケットへ行って買い物してください」
と応酬するくだりとか。
「あとがきにかえて」の最後は、こうしめくくっている。
「2012年は、ボナパルト敗退200年である」
カッチョイー!
『獄の息子は発狂寸前』
2009年3月11日 読書
昨日は『狂人三歩手前』を読んだが、今日読んだのは見沢知廉の『獄の息子は発狂寸前』だ。かなり接近してきた。
以下、目次。
序章 母と子
*12年が詰まっている段ボール
第1章 あの、蒼い日々
*母からの最初の手紙*息子が殺人犯…それを知って母は*懐柔*攪乱*間諜*違法接見*暗闇*面会*瓢箪のお守り*設楽からの手紙
第2章 檻の中
*旭川か関東か*品評会*人の弱みに付け込む輩*行き先は、ええと…*千葉刑*千葉での原点*母のノスタルジー*弟からの手紙
第3章 「小説禁止」の死角
*俺にとって小説を書くこととは*特製パンフレット*母の冒険心*わが心の伊藤蘭*健全な生活は健全な水着に宿る?*バーター取引き*転落*あっけない幕切れ*小説禁止令*暗号*”やや”わかったか*炙り出し
第4章 母の災難
*ツキに見放された母*歯がゆい日々*失業*御殿場*帰京*B型肝炎
第5章 「発狂寸前」
*「恩赦なし!」*八王子医療刑務所*設楽からのメッセージ*野村秋介と母*母の言葉*「武蔵になれ!」*どん底*「千葉大女医殺し」の藤田正の自殺*千葉刑で出会った藤田の母のこと*出さねえとまた請願やるぞ!*死ぬなら死になさい!*ピアスで開運
第6章 獄中の新人賞
*希望、一つ*切り刻まれた手紙*ハンスト*病舎で取った相撲*最終選考*野村秋介、果つ*母の重さを教えてくれた野村秋介*母と子の絆で耐えるしぐれ獄*虹の道
獄の息子への手紙
*母がはじめて野村秋介に会った日のこと*M夫が見せてくれたビデオ*お正月*お墓参り*千葉は大変!?*おばあちゃんが養老院に*「オヤヤメタイヨ」*恩赦*おばあちゃんの入院*カッコーの巣は嫌*おばあちゃんの涙*おばあちゃんからの最後の手紙*ゆっくり行けば遠くに行ける*出所した設楽と会った日のこと*出所する貴方へ
愚かな母の物語かと思いきや、官をだしぬくあの手この手に手に汗にぎり、快哉を叫んだ読後感は、母と子の関係にややうんざりさせられる。
めちゃくちゃ面白い本だったが、読んだあとで、いろいろと手をつくして生きようとする主人公と、簡単に人の命を奪った主人公の命に対するギャップに思いをはせざるをえない。身内に対する愛情を臆面もなく綴る主人公ならではの思想か。
以下、目次。
序章 母と子
*12年が詰まっている段ボール
第1章 あの、蒼い日々
*母からの最初の手紙*息子が殺人犯…それを知って母は*懐柔*攪乱*間諜*違法接見*暗闇*面会*瓢箪のお守り*設楽からの手紙
第2章 檻の中
*旭川か関東か*品評会*人の弱みに付け込む輩*行き先は、ええと…*千葉刑*千葉での原点*母のノスタルジー*弟からの手紙
第3章 「小説禁止」の死角
*俺にとって小説を書くこととは*特製パンフレット*母の冒険心*わが心の伊藤蘭*健全な生活は健全な水着に宿る?*バーター取引き*転落*あっけない幕切れ*小説禁止令*暗号*”やや”わかったか*炙り出し
第4章 母の災難
*ツキに見放された母*歯がゆい日々*失業*御殿場*帰京*B型肝炎
第5章 「発狂寸前」
*「恩赦なし!」*八王子医療刑務所*設楽からのメッセージ*野村秋介と母*母の言葉*「武蔵になれ!」*どん底*「千葉大女医殺し」の藤田正の自殺*千葉刑で出会った藤田の母のこと*出さねえとまた請願やるぞ!*死ぬなら死になさい!*ピアスで開運
第6章 獄中の新人賞
*希望、一つ*切り刻まれた手紙*ハンスト*病舎で取った相撲*最終選考*野村秋介、果つ*母の重さを教えてくれた野村秋介*母と子の絆で耐えるしぐれ獄*虹の道
獄の息子への手紙
*母がはじめて野村秋介に会った日のこと*M夫が見せてくれたビデオ*お正月*お墓参り*千葉は大変!?*おばあちゃんが養老院に*「オヤヤメタイヨ」*恩赦*おばあちゃんの入院*カッコーの巣は嫌*おばあちゃんの涙*おばあちゃんからの最後の手紙*ゆっくり行けば遠くに行ける*出所した設楽と会った日のこと*出所する貴方へ
愚かな母の物語かと思いきや、官をだしぬくあの手この手に手に汗にぎり、快哉を叫んだ読後感は、母と子の関係にややうんざりさせられる。
めちゃくちゃ面白い本だったが、読んだあとで、いろいろと手をつくして生きようとする主人公と、簡単に人の命を奪った主人公の命に対するギャップに思いをはせざるをえない。身内に対する愛情を臆面もなく綴る主人公ならではの思想か。
中島義道の『狂人三歩手前』を読んだ。
以下、目次。
生きていく理由
どうせ死んでしまう
妻と壮絶なバトル、くたびれ果てた
窓から空を眺めていた
テロはなかったのかもしれない
不覚にも涙が出てきた
みんな私から顔を背ける
悪の研究会
つまらない、つまらない
夏には哲学がよく似合う
愛される恐怖
「ぼくは死ぬ、ぼくは死ぬ…」
一億二千万分の二十
あの時私が拉致されていたら
私が嫌いな「私のことを好きな人」
愛したくも愛されたくもない?
「私」が無になるということ
たまにはセンセーらしく
怒る私
どうでもいいこと
共感しない心
向いているのかいないのか
なんで電気を点けるの
わが家の卒業式
私に近づくな
私は人を救えない
「共感する」ことができない
虚しさ以外の何も感じない
暗い一年だった
哲学という病
ちょっと親バカ
したたかになれない彼
みなさま、ありがとう
「ある」ことと「あった」こと
だから私は「ぐれる」のです
哲学などしないように!
『新潮45』2002年1月号から2004年9月号に連載されたコラムを集めたもの。
哲学者の条件としてあげている項目が面白い。
メルロ=ポンティの『眼と精神』から「哲学者とは、目覚めそして話す人間のことである」をひいた後で、こうつけ加えている。
「いや、もう一つの条件を加えておこう。どんな場合でも、周囲世界に埋没していないこと。われを忘れていないこと。いかなる事件が起ころうが、適度な距離をもって冷静に世界を眺めていること。つまり『冷たい』厭な人間であること」
これはさかさまに言えば、「世間」のことをあらわしているのだろう。
事の理非にかかわらず、「世間をお騒がせした」という理由で謝罪している姿を目にするたびに、哲学の道の険しさを感得するのである。
以下、目次。
生きていく理由
どうせ死んでしまう
妻と壮絶なバトル、くたびれ果てた
窓から空を眺めていた
テロはなかったのかもしれない
不覚にも涙が出てきた
みんな私から顔を背ける
悪の研究会
つまらない、つまらない
夏には哲学がよく似合う
愛される恐怖
「ぼくは死ぬ、ぼくは死ぬ…」
一億二千万分の二十
あの時私が拉致されていたら
私が嫌いな「私のことを好きな人」
愛したくも愛されたくもない?
「私」が無になるということ
たまにはセンセーらしく
怒る私
どうでもいいこと
共感しない心
向いているのかいないのか
なんで電気を点けるの
わが家の卒業式
私に近づくな
私は人を救えない
「共感する」ことができない
虚しさ以外の何も感じない
暗い一年だった
哲学という病
ちょっと親バカ
したたかになれない彼
みなさま、ありがとう
「ある」ことと「あった」こと
だから私は「ぐれる」のです
哲学などしないように!
『新潮45』2002年1月号から2004年9月号に連載されたコラムを集めたもの。
哲学者の条件としてあげている項目が面白い。
メルロ=ポンティの『眼と精神』から「哲学者とは、目覚めそして話す人間のことである」をひいた後で、こうつけ加えている。
「いや、もう一つの条件を加えておこう。どんな場合でも、周囲世界に埋没していないこと。われを忘れていないこと。いかなる事件が起ころうが、適度な距離をもって冷静に世界を眺めていること。つまり『冷たい』厭な人間であること」
これはさかさまに言えば、「世間」のことをあらわしているのだろう。
事の理非にかかわらず、「世間をお騒がせした」という理由で謝罪している姿を目にするたびに、哲学の道の険しさを感得するのである。
『絵解きヨーロッパ中世の夢』
2009年3月5日 読書
ル・ゴフの『絵解きヨーロッパ中世の夢』を読んだ。
中世の英雄と驚異を取り上げた書物。
想像力のよい部分を中心に編んであるので、悪魔などは出て来ない。
以下、目次。
日本語版序文
序文
アーサー
カテドラル(大聖堂、司教座聖堂)
シャルルマーニュ(カール大帝)
城塞
騎士と騎士道
エル・シド
クロイスター(修道院、あるいはその庭を囲む回廊)
コカーニュの国(桃源郷)
ジョングルール(大道芸人)
一角獣(ユニコーン)
メリュジーヌ
マーリン(メルラン)
エルカンの一党
女教皇ヨハンナ
狐のルナール
ロビン・フッド
ロラン
トリスタンとイズー
トゥルバドゥール、トゥルヴェール
ワルキューレ
図版も多く、中世に浸ってさながらルードヴィッヒのように1日を過ごすことが出来た。
狐物語のルナールがゾロの元ネタだったとか、面白い知識も満載。
こりゃしばらく中世に遊んでみるかな。
中世の英雄と驚異を取り上げた書物。
想像力のよい部分を中心に編んであるので、悪魔などは出て来ない。
以下、目次。
日本語版序文
序文
アーサー
カテドラル(大聖堂、司教座聖堂)
シャルルマーニュ(カール大帝)
城塞
騎士と騎士道
エル・シド
クロイスター(修道院、あるいはその庭を囲む回廊)
コカーニュの国(桃源郷)
ジョングルール(大道芸人)
一角獣(ユニコーン)
メリュジーヌ
マーリン(メルラン)
エルカンの一党
女教皇ヨハンナ
狐のルナール
ロビン・フッド
ロラン
トリスタンとイズー
トゥルバドゥール、トゥルヴェール
ワルキューレ
図版も多く、中世に浸ってさながらルードヴィッヒのように1日を過ごすことが出来た。
狐物語のルナールがゾロの元ネタだったとか、面白い知識も満載。
こりゃしばらく中世に遊んでみるかな。
『ことばをめぐる哲学の冒険』
2009年3月4日 読書
ライブの後は、なぜか、からだのあちこちが痛む。
あんなに体を動かさずに済むパフォーマンス考えたはずなのに、これはいったい。
筋肉痛ならまだしも、あっちこっちに傷ができていて、血が出ていたりする。打ち上げのときにさんざん話した、何か悪いものにでも憑かれているんだろうか。
近々、インテックス大阪で「癒しフェア」という催しがあって、スピリチュアルのふきだまりがそこに形成されるのだが、あいにくと無料入場券の受付に間に合わなかった。ライブ後は財布がすっからかんになるので(これも悪い病気か何かかも)、癒しに行けない。
と、いうわけで、今日も仕事と読書。
長谷川宏の『ことばをめぐる哲学の冒険』を読んだ。
著者は、ヘーゲルの翻訳でずいぶんとお世話になった(読みやすい!)が、今回の著作は中村雄二郎の本を読んだときにも似た読後感だった。やわらかくて正しい。
1つのキーワードをもとに、多くの文献などを散策する試み。
以下、目次と、主な渉猟文献。
第1章 愛
『古事記』、『万葉集』、『山の背くらべ』(木下順二)、『恋愛論』(スタンダール)、『定義集』(アラン)
第2章 誕生
『火山灰地』(久保栄)、『笛吹川』(深沢七郎)、『ルカによる福音書』、「I was born」(吉野弘)、『仮面の告白』(三島由紀夫)、『全体主義の起源』『人間の条件』(アーレント)
第3章 亡霊
『東海道四谷怪談』(鶴屋南北)、『妖怪談義』(柳田国男)、「北野天神縁起」、『ハムレット』(シェイクスピア)
第4章 平和
『歴史』(ヘロドトス)、『イーリアス』(ホメーロス)、『平和』『女の平和』(アリストパネス)、『永遠平和のために』(カント)、『「難死」の思想』(小田実)、『雪の中の軍曹』(リゴーニ・ステルン)、『老子』
第5章 旅
『伊勢物語』、『奥の細道』、『菅江真澄遊覧記』、『イタリア紀行』(ゲーテ)
ライブが終わって、しばらく何もせずに旅にでも出たい思いがつのっていたので、この本は助けになった。仕事があったので、どこにも行けなかったのだが、この本ですっかり旅気分だ。
あんなに体を動かさずに済むパフォーマンス考えたはずなのに、これはいったい。
筋肉痛ならまだしも、あっちこっちに傷ができていて、血が出ていたりする。打ち上げのときにさんざん話した、何か悪いものにでも憑かれているんだろうか。
近々、インテックス大阪で「癒しフェア」という催しがあって、スピリチュアルのふきだまりがそこに形成されるのだが、あいにくと無料入場券の受付に間に合わなかった。ライブ後は財布がすっからかんになるので(これも悪い病気か何かかも)、癒しに行けない。
と、いうわけで、今日も仕事と読書。
長谷川宏の『ことばをめぐる哲学の冒険』を読んだ。
著者は、ヘーゲルの翻訳でずいぶんとお世話になった(読みやすい!)が、今回の著作は中村雄二郎の本を読んだときにも似た読後感だった。やわらかくて正しい。
1つのキーワードをもとに、多くの文献などを散策する試み。
以下、目次と、主な渉猟文献。
第1章 愛
『古事記』、『万葉集』、『山の背くらべ』(木下順二)、『恋愛論』(スタンダール)、『定義集』(アラン)
第2章 誕生
『火山灰地』(久保栄)、『笛吹川』(深沢七郎)、『ルカによる福音書』、「I was born」(吉野弘)、『仮面の告白』(三島由紀夫)、『全体主義の起源』『人間の条件』(アーレント)
第3章 亡霊
『東海道四谷怪談』(鶴屋南北)、『妖怪談義』(柳田国男)、「北野天神縁起」、『ハムレット』(シェイクスピア)
第4章 平和
『歴史』(ヘロドトス)、『イーリアス』(ホメーロス)、『平和』『女の平和』(アリストパネス)、『永遠平和のために』(カント)、『「難死」の思想』(小田実)、『雪の中の軍曹』(リゴーニ・ステルン)、『老子』
第5章 旅
『伊勢物語』、『奥の細道』、『菅江真澄遊覧記』、『イタリア紀行』(ゲーテ)
ライブが終わって、しばらく何もせずに旅にでも出たい思いがつのっていたので、この本は助けになった。仕事があったので、どこにも行けなかったのだが、この本ですっかり旅気分だ。
『修羅雪姫復活之章』『西洋中世の愛と人格』
2009年3月3日 読書 コメント (1)
昨日はライブ「耽美城」で、打ち上げ後に「銭ゲバ」で朝まで。
むりやり誕生日を祝ってもらうイベントだったが、野中ひゆちゃんの活けた花は殺風景な僕の部屋をいろどるし、秋葉原紫音さんにもらったペロペロキャンディにはまったり、やっぱり何かをすれば何かが変わる。
当たり前だけど、面白い。
銭ゲバでは、上村一夫の『修羅雪姫 復活之章』(上下)を読んだ。
スウェーデン体操の普及と撲滅の争い。
ブルマ普及に名を残す井口あぐりも登場してた、かな。
阿部謹也の『西洋中世の愛と人格』を読んだ。サブタイトルは『世間論序説』
以下、目次。
1、世間と社会
世間の中の一人として
どのような世間に立脚しているのか
「社会」という言葉
島崎藤村の『破戒』では
世間との闘い−金子光晴にみる
2、個人と人格の成立について
個人と人格のありかた
人格を求めてーアーロン・グレーヴィッチの問題提起
初期キリスト教の時代−ピーター・ブラウンの問題提起
サガの世界−ステブリン・カーメンスキーの問題提起
十二世紀ルネサンスと告解
男女の性的関係は中世では罪であった
3、神判の世界とケガレ
公と私の逆転
いまも呪術的世界が−日常生活の次元で
参籠起請と神判−日本人の「罪」意識の原型
西欧における個人とは−神判との関連で
4、西欧における愛のかたち
「愛」、その真実
プラトンと初期キリスト教における愛
十二世紀以前−愛が発見されるまで
花開く トゥルバドゥール
宮廷風恋愛とは?−「トリスタンとイズー」の物語など
聖職者における愛のかたち−その変貌
宮廷における愛の作法
愛の理想化−「神への愛」から離れて
愛と禁欲
神判が拷問に移行する話は考えてもいなかったのでハッとしたな。
また、騎士の理想的な恋愛が、裸になって同衾してても最後の一線は越えない、てのは、最近はやりの草食系男子に通じるかな。騎士はやってることは肉体派なのにね。
むりやり誕生日を祝ってもらうイベントだったが、野中ひゆちゃんの活けた花は殺風景な僕の部屋をいろどるし、秋葉原紫音さんにもらったペロペロキャンディにはまったり、やっぱり何かをすれば何かが変わる。
当たり前だけど、面白い。
銭ゲバでは、上村一夫の『修羅雪姫 復活之章』(上下)を読んだ。
スウェーデン体操の普及と撲滅の争い。
ブルマ普及に名を残す井口あぐりも登場してた、かな。
阿部謹也の『西洋中世の愛と人格』を読んだ。サブタイトルは『世間論序説』
以下、目次。
1、世間と社会
世間の中の一人として
どのような世間に立脚しているのか
「社会」という言葉
島崎藤村の『破戒』では
世間との闘い−金子光晴にみる
2、個人と人格の成立について
個人と人格のありかた
人格を求めてーアーロン・グレーヴィッチの問題提起
初期キリスト教の時代−ピーター・ブラウンの問題提起
サガの世界−ステブリン・カーメンスキーの問題提起
十二世紀ルネサンスと告解
男女の性的関係は中世では罪であった
3、神判の世界とケガレ
公と私の逆転
いまも呪術的世界が−日常生活の次元で
参籠起請と神判−日本人の「罪」意識の原型
西欧における個人とは−神判との関連で
4、西欧における愛のかたち
「愛」、その真実
プラトンと初期キリスト教における愛
十二世紀以前−愛が発見されるまで
花開く トゥルバドゥール
宮廷風恋愛とは?−「トリスタンとイズー」の物語など
聖職者における愛のかたち−その変貌
宮廷における愛の作法
愛の理想化−「神への愛」から離れて
愛と禁欲
神判が拷問に移行する話は考えてもいなかったのでハッとしたな。
また、騎士の理想的な恋愛が、裸になって同衾してても最後の一線は越えない、てのは、最近はやりの草食系男子に通じるかな。騎士はやってることは肉体派なのにね。
『スピヴァクみずからを語る−家・サバルタン・知識人』、スリーピーホロウ、戦場のアリア
2009年2月27日 読書ガヤトリ・スピヴァクの『スピヴァクみずからを語る−家・サバルタン・知識人』を読んだ。
以下、目次。
家/聞き手:ショポン・チョクロボルティ
抵抗として認識され得ない抵抗/聞き手:スザーナ・ミレフスカ
知識人としてきちんと答えたとは言いがたい回答/聞き手:タニ・E・バーロウ
付録 家−私的な会話
付録は最初の「家」の数日前にかわされた会話で、内容はほとんどメイキング。
先日、バトラーとの対談本で、スピヴァクの「格」みたいなことを感じた旨、書いたが、本書を読んでみて、ちょっと印象が変わった。
「他人が私の論考を正しく読んでいるかどうか判断することには、関わりたくありません。(中略)くわえて、私が読んでいないものはとにかくたくさんあって、私について他の人が書いたものを読んで、それが間違っていると言うのは、、、そんなことはいかにも時間の無駄だと思いませんか」
「私はいつも、書きたくない物を書いています。わかってください。依頼をされて、いろいろと引き受けるんです。ほんとうは社会主義の倫理の可能性について書きたいのです。これについて15年か20年、書きたいと思いつづけてきました。まあでも、おそらくこの本を書かずに死んでしまうでしょうね」
「私の関心はもはや『グローバルな社会運動に携わる知識人』について考察することにはありません。それはかならずしも重要なことではありません。(中略)それをやる人にとってはほんとうに、とても良いことです。やっている人が思うほど効果があるわけでもないのですが。しかも、いまやそれは、無責任な道徳の革新者気取りの人たちのいいようになっています」
「だからこそ私は言うんです。国家の構造を変えたり、あるいは新しい国際的な市民社会のために働いたりといった仕事は、もうしませんと」
以上のように、スピヴァクに抱く近寄りがたさは、彼女の身も蓋もなさにあるんじゃないのか、と感じたのだ。
ちなみに、最後に引用した発言は、自分の仕事がいかに遅くて不確かでも、これ(主体の構造に影響を与える)がなされなければ長続きしない、として、こんなふうに続く。
「私が心から信じ、強く思うのは、国際的な共産主義が失敗した最大の理由の一つは、サバルタンの主体性に関わらなかったからだということです。共産主義がしたのは、サバルタンの動員でした。それは急ぎすぎました」
また、付録でのざっくらばんなスピヴァクは、思わずポロリのこんな発言もする。
「あとそれから、私が答えたら、私が傲慢に聞こえるような質問はしないでください」
これには相手のチョクロボルティも「これは保証できません」と一蹴している。チョクロボルティとはかなり打ち解けて話しているようで、スピヴァクの可愛さ(こんなこと言ったらスピヴァク怒るかもしれんが)も引き出せている。
スピヴァクが「お会いする前、私のことをどう思っていましたか」なんて質問し、チョクロボルティはこう答えている。
「あなたがいつも息せききっている人だということ。あなたの書くものは素晴らしいけれど、あまりに息せききっている。(中略)ときには立ち止まって息をついてほしいな、ということでした」
チョクロボルティはコルカタ(カルカッタ)のジャドプル大学、文化テキスト記録学部、共同学部長兼英文学教授で、日本でもその文章が読める、らしいのだが、探してみるか。
なお、後の聞き手については、ミレフスカはスコピエの「ヨーロッパ−バルカン」ジェンダー研究センターの視覚文化講師。バーロウはフェミニズム、ポストコロニアリティ、アジア史、とくに中国史の研究者、ワシントン大学の歴史学と女性学の教授。
見た映画は2本。
ティム・バートン監督の「スリーピーホロウ」はジョニー・デップ主演のミステリー。
首刈り騎士のホラー要素もあるが、それに隠れて、首なし死体につきもののトリックをうまくカモフラージュしている。
また、誰が魔女なのか、という推理のどんでん返しも面白い。
さらに、なぜジョニー・デップが迷信にとらわれずに科学的捜査法をとろうとしているのか、という説明も素晴らしい。素晴らしい、というのは、きわめてミステリー的だ、という意味だ。
とくに「おおっ」と思ったのは、ジョニー・デップと少年が森を歩いているときに、少年が異変に気づくシーン。こんな会話が交わされる。
「聞いて!」
「何も」
「僕もだ。鳥や虫の声ひとつない。静かすぎる」
これって、ホームズ的推理そのもの!
ジョニー・デップは科学的思考をしているようで、実は臆病だったりして、まあ魅力的に描かれているが、クリスティーナ・リッチがぜんぜん魅力的に描かれておらず、誰でもよかったんじゃないのか、という役割だったのが惜しい。
クリスチャン・カリオン監督の「戦場のアリア」は、決してだじゃれではない。
実話にもとづいているそうだが、クリスマスイブにそれぞれ塹壕でにらみあっている敵軍兵士たちが一時休戦して親交をもつ話。
この物語を甘い、と見るのは悲しい。
パレスチナ人の通行を無慈悲にさえぎり、発砲するイスラエル兵をドキュメンタリーでさんざん見た後なので、今のこの時代でも、この映画にあるような、「大義に反してでも人間として行動する」ようなエピソードが存在する余地があればいいのに、と思った。
以下、目次。
家/聞き手:ショポン・チョクロボルティ
抵抗として認識され得ない抵抗/聞き手:スザーナ・ミレフスカ
知識人としてきちんと答えたとは言いがたい回答/聞き手:タニ・E・バーロウ
付録 家−私的な会話
付録は最初の「家」の数日前にかわされた会話で、内容はほとんどメイキング。
先日、バトラーとの対談本で、スピヴァクの「格」みたいなことを感じた旨、書いたが、本書を読んでみて、ちょっと印象が変わった。
「他人が私の論考を正しく読んでいるかどうか判断することには、関わりたくありません。(中略)くわえて、私が読んでいないものはとにかくたくさんあって、私について他の人が書いたものを読んで、それが間違っていると言うのは、、、そんなことはいかにも時間の無駄だと思いませんか」
「私はいつも、書きたくない物を書いています。わかってください。依頼をされて、いろいろと引き受けるんです。ほんとうは社会主義の倫理の可能性について書きたいのです。これについて15年か20年、書きたいと思いつづけてきました。まあでも、おそらくこの本を書かずに死んでしまうでしょうね」
「私の関心はもはや『グローバルな社会運動に携わる知識人』について考察することにはありません。それはかならずしも重要なことではありません。(中略)それをやる人にとってはほんとうに、とても良いことです。やっている人が思うほど効果があるわけでもないのですが。しかも、いまやそれは、無責任な道徳の革新者気取りの人たちのいいようになっています」
「だからこそ私は言うんです。国家の構造を変えたり、あるいは新しい国際的な市民社会のために働いたりといった仕事は、もうしませんと」
以上のように、スピヴァクに抱く近寄りがたさは、彼女の身も蓋もなさにあるんじゃないのか、と感じたのだ。
ちなみに、最後に引用した発言は、自分の仕事がいかに遅くて不確かでも、これ(主体の構造に影響を与える)がなされなければ長続きしない、として、こんなふうに続く。
「私が心から信じ、強く思うのは、国際的な共産主義が失敗した最大の理由の一つは、サバルタンの主体性に関わらなかったからだということです。共産主義がしたのは、サバルタンの動員でした。それは急ぎすぎました」
また、付録でのざっくらばんなスピヴァクは、思わずポロリのこんな発言もする。
「あとそれから、私が答えたら、私が傲慢に聞こえるような質問はしないでください」
これには相手のチョクロボルティも「これは保証できません」と一蹴している。チョクロボルティとはかなり打ち解けて話しているようで、スピヴァクの可愛さ(こんなこと言ったらスピヴァク怒るかもしれんが)も引き出せている。
スピヴァクが「お会いする前、私のことをどう思っていましたか」なんて質問し、チョクロボルティはこう答えている。
「あなたがいつも息せききっている人だということ。あなたの書くものは素晴らしいけれど、あまりに息せききっている。(中略)ときには立ち止まって息をついてほしいな、ということでした」
チョクロボルティはコルカタ(カルカッタ)のジャドプル大学、文化テキスト記録学部、共同学部長兼英文学教授で、日本でもその文章が読める、らしいのだが、探してみるか。
なお、後の聞き手については、ミレフスカはスコピエの「ヨーロッパ−バルカン」ジェンダー研究センターの視覚文化講師。バーロウはフェミニズム、ポストコロニアリティ、アジア史、とくに中国史の研究者、ワシントン大学の歴史学と女性学の教授。
見た映画は2本。
ティム・バートン監督の「スリーピーホロウ」はジョニー・デップ主演のミステリー。
首刈り騎士のホラー要素もあるが、それに隠れて、首なし死体につきもののトリックをうまくカモフラージュしている。
また、誰が魔女なのか、という推理のどんでん返しも面白い。
さらに、なぜジョニー・デップが迷信にとらわれずに科学的捜査法をとろうとしているのか、という説明も素晴らしい。素晴らしい、というのは、きわめてミステリー的だ、という意味だ。
とくに「おおっ」と思ったのは、ジョニー・デップと少年が森を歩いているときに、少年が異変に気づくシーン。こんな会話が交わされる。
「聞いて!」
「何も」
「僕もだ。鳥や虫の声ひとつない。静かすぎる」
これって、ホームズ的推理そのもの!
ジョニー・デップは科学的思考をしているようで、実は臆病だったりして、まあ魅力的に描かれているが、クリスティーナ・リッチがぜんぜん魅力的に描かれておらず、誰でもよかったんじゃないのか、という役割だったのが惜しい。
クリスチャン・カリオン監督の「戦場のアリア」は、決してだじゃれではない。
実話にもとづいているそうだが、クリスマスイブにそれぞれ塹壕でにらみあっている敵軍兵士たちが一時休戦して親交をもつ話。
この物語を甘い、と見るのは悲しい。
パレスチナ人の通行を無慈悲にさえぎり、発砲するイスラエル兵をドキュメンタリーでさんざん見た後なので、今のこの時代でも、この映画にあるような、「大義に反してでも人間として行動する」ようなエピソードが存在する余地があればいいのに、と思った。