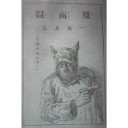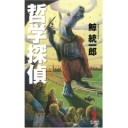パレスチナ1948 NAKUBA(ナクバ)、『ラカンはこう読め!』
2009年2月26日 読書広河隆一監督のドキュメンタリー「パレスチナ1948 NAKUBA(ナクバ)」を見た。
イスラエル建国によって発生したパレスチナ難民。着の身着のままで村を追い出されたパレスチナ人だが、その村のあとは、ただ破壊だけがなされており、すっかり荒れ地になっている。使い道ないんだったら、住まわせてやれよ!地上げ後の廃墟か!村には当然、墓地もあったわけだが、無残にも墓石も破壊している。
インティファーダの映像もあり、イスラエル側が発射したガス弾で広河監督がゲホゲホいうのが生々しい。石を投げるパレスチナ人、戦車と銃とガスで殺戮するイスラエル兵。死体があっちこっちで見つかるが、死がすぐ隣にある環境であることがひしひしと伝わる。
世界はちょっとずつでもよくなっているものと信じたい(チョムスキーなんかはそれを強調する)。でも、なんと遅々としか進まないものか。
読んだ本はスラヴォイ・ジジェクの『ラカンはこう読め!』
以下、目次。
死の前に生はあるか−日本語版への序文
1、空疎な身ぶりと遂行文/CIAの陰謀に立ち向かうラカン
2、相互受動的な主体/マニ車を回すラカン
3、<汝何を欲するか>から幻想へ/『アイズ・ワイド・シャット』を観るラカン
4、<現実界>をめぐる厄介な問題/『エイリアン』を観るラカン
5、自我理想と超自我/『カサブランカ』を観るラカン
6、「神は死んだが、死んだことを知らない」/ボボークと遊ぶラカン
7、政治のひねくれた主体/モハンマド・ボウェイリを読むラカン
「マニ車」は経文を書いた車で、これを回せば、経を読んだことになる。寺にもよくあるし、千日前アムザの近くにもあって、通りかかるたびによく回す。
「ボボーク」はドストエフスキーの短編からとった言葉で、肉体が滅びることをさしている。
「モハンマド・ボウェイリ」はドキュメンタリー映画作家テオ・ヴァン・ゴッホを殺したイスラム過激派の名前。
さて、本書はタイトルこそラカンの入門書っぽいが、内容はあいかわらずのジジェク節だった。目次見ていて思ったけど、このセンスは、物真似芸と似ているかもしれない。
たとえば、誰かが「寿司屋になったアントニオ猪木」という芸を考えたとしよう。そこで演じられるのは、芸人による猪木の応用である。同様に、ジジェクは「つづきましては、カサブランカを観るラカン」と演目を言って、面白く演じるのだ。
それぞれの章で引用される映画、文学の解釈の面白さ、論の進め方の楽しさは訳文の読みやすさも手伝って、これこそジジェクの面白さを誰にでも伝えることのできる1冊になったかもしれない。
ひとつ、共感しきりの部分があったので、引用しておこう。
「双方向性の裏返しが相互受動性である。(たんに受動的にショーを観ている代わりに)能動的に対象に働きかけるという状況を裏返せば、次のような状況が生まれる。すなわち、対象そのものが私から私自身の受動性を奪い取り、その結果、対象そのものが私の代わりにショーを楽しみ、楽しむという義務を肩代わりしてくれる。強迫的に映画を録画しまくるビデオ・マニア(私もそのひとりだ)ならほとんど誰もが知っているはずだ−ビデオデッキを買うと、テレビしかなかった古き良き時代よりも観る映画の本数が減るということを。われわれは忙しくてテレビなど観ている暇がないので、夜の貴重な時間を無駄にしないために、ビデオに録画しておく。後で観るためだ(実際にはほとんど観る治巻はない)。実際には映画を観なくても、大好きな映画が自分のビデオ・ライブラリに入っていると考えるだけで、深い満足感が得られ、時には深くリラックスし、無為という極上の時を過ごすことができる。まるで、ビデオデッキが私のために、私の代わりに、映画を観てくれているかのようだ」
引用が長い!でも、本1冊全部書き写したくなるほど、面白かったんだも〜ん。
イスラエル建国によって発生したパレスチナ難民。着の身着のままで村を追い出されたパレスチナ人だが、その村のあとは、ただ破壊だけがなされており、すっかり荒れ地になっている。使い道ないんだったら、住まわせてやれよ!地上げ後の廃墟か!村には当然、墓地もあったわけだが、無残にも墓石も破壊している。
インティファーダの映像もあり、イスラエル側が発射したガス弾で広河監督がゲホゲホいうのが生々しい。石を投げるパレスチナ人、戦車と銃とガスで殺戮するイスラエル兵。死体があっちこっちで見つかるが、死がすぐ隣にある環境であることがひしひしと伝わる。
世界はちょっとずつでもよくなっているものと信じたい(チョムスキーなんかはそれを強調する)。でも、なんと遅々としか進まないものか。
読んだ本はスラヴォイ・ジジェクの『ラカンはこう読め!』
以下、目次。
死の前に生はあるか−日本語版への序文
1、空疎な身ぶりと遂行文/CIAの陰謀に立ち向かうラカン
2、相互受動的な主体/マニ車を回すラカン
3、<汝何を欲するか>から幻想へ/『アイズ・ワイド・シャット』を観るラカン
4、<現実界>をめぐる厄介な問題/『エイリアン』を観るラカン
5、自我理想と超自我/『カサブランカ』を観るラカン
6、「神は死んだが、死んだことを知らない」/ボボークと遊ぶラカン
7、政治のひねくれた主体/モハンマド・ボウェイリを読むラカン
「マニ車」は経文を書いた車で、これを回せば、経を読んだことになる。寺にもよくあるし、千日前アムザの近くにもあって、通りかかるたびによく回す。
「ボボーク」はドストエフスキーの短編からとった言葉で、肉体が滅びることをさしている。
「モハンマド・ボウェイリ」はドキュメンタリー映画作家テオ・ヴァン・ゴッホを殺したイスラム過激派の名前。
さて、本書はタイトルこそラカンの入門書っぽいが、内容はあいかわらずのジジェク節だった。目次見ていて思ったけど、このセンスは、物真似芸と似ているかもしれない。
たとえば、誰かが「寿司屋になったアントニオ猪木」という芸を考えたとしよう。そこで演じられるのは、芸人による猪木の応用である。同様に、ジジェクは「つづきましては、カサブランカを観るラカン」と演目を言って、面白く演じるのだ。
それぞれの章で引用される映画、文学の解釈の面白さ、論の進め方の楽しさは訳文の読みやすさも手伝って、これこそジジェクの面白さを誰にでも伝えることのできる1冊になったかもしれない。
ひとつ、共感しきりの部分があったので、引用しておこう。
「双方向性の裏返しが相互受動性である。(たんに受動的にショーを観ている代わりに)能動的に対象に働きかけるという状況を裏返せば、次のような状況が生まれる。すなわち、対象そのものが私から私自身の受動性を奪い取り、その結果、対象そのものが私の代わりにショーを楽しみ、楽しむという義務を肩代わりしてくれる。強迫的に映画を録画しまくるビデオ・マニア(私もそのひとりだ)ならほとんど誰もが知っているはずだ−ビデオデッキを買うと、テレビしかなかった古き良き時代よりも観る映画の本数が減るということを。われわれは忙しくてテレビなど観ている暇がないので、夜の貴重な時間を無駄にしないために、ビデオに録画しておく。後で観るためだ(実際にはほとんど観る治巻はない)。実際には映画を観なくても、大好きな映画が自分のビデオ・ライブラリに入っていると考えるだけで、深い満足感が得られ、時には深くリラックスし、無為という極上の時を過ごすことができる。まるで、ビデオデッキが私のために、私の代わりに、映画を観てくれているかのようだ」
引用が長い!でも、本1冊全部書き写したくなるほど、面白かったんだも〜ん。
帝国的ナショナリズム
2009年2月24日 読書大澤真幸の『帝国的ナショナリズム』を読んだ。
以下、目次。
1、日本の変容
なぜオウムの存在はかくも耐えがたいのか?
少年の殺人と電子メディア
家族の還元
国民への現代的信従
マルチストーリー・マルチエンディング
2、アメリカの変容
司法的精神の逆説−大統領の不倫
寛容と不寛容−コロンバイン高校銃撃事件
集団的否認−チャレンジャー事故
「人種なき人種主義」の回帰
3、現代社会の変容
加速資本主義論−ディズニーランドと世界の内外
エアポート論−「都市」以後の「ネーション」/多木浩二、大澤真幸
4、日本とアメリカの現在
帝国的ナショナリズム
4章の「帝国的ナショナリズム」は先般刊行された大著の露払い的書き下ろし。
最初のオウム論は興味深く読んだ。
「オウムがわれわれにとって脅威なのは、オウムがわれわれと大きく異なるからではなく、逆にわれわれと同じだから、われわれ自身だからである」と書いている。
「オウムをこの社会において完全に乗り越えるためには、オウムを排斥して撲滅するのではなく、オウムと共存してみせなくてはならないのだ」と。
以下、目次。
1、日本の変容
なぜオウムの存在はかくも耐えがたいのか?
少年の殺人と電子メディア
家族の還元
国民への現代的信従
マルチストーリー・マルチエンディング
2、アメリカの変容
司法的精神の逆説−大統領の不倫
寛容と不寛容−コロンバイン高校銃撃事件
集団的否認−チャレンジャー事故
「人種なき人種主義」の回帰
3、現代社会の変容
加速資本主義論−ディズニーランドと世界の内外
エアポート論−「都市」以後の「ネーション」/多木浩二、大澤真幸
4、日本とアメリカの現在
帝国的ナショナリズム
4章の「帝国的ナショナリズム」は先般刊行された大著の露払い的書き下ろし。
最初のオウム論は興味深く読んだ。
「オウムがわれわれにとって脅威なのは、オウムがわれわれと大きく異なるからではなく、逆にわれわれと同じだから、われわれ自身だからである」と書いている。
「オウムをこの社会において完全に乗り越えるためには、オウムを排斥して撲滅するのではなく、オウムと共存してみせなくてはならないのだ」と。
人形がたり〜たまさか人形堂より〜@珈琲舎アラビク、『哲学者、怒りに炎上す。』
2009年2月23日 読書珈琲舎アラビクで「人形がたり〜たまさか人形堂より〜」。
「人と人形(ヒトガタ)/混乱する主従関係」と題されている。
最終日にやっと覗く事が出来た。入ってすぐの所に並ぶ古書は昨日来たときにひととおり見ていた。ラインナップは素晴らしいが、あいにくと僕の探している本はなかった。
靴を脱いであがり、鞄をあずけて展示を見る。
山吉由利子、きんすなご、トサカネコ舎、佐藤珠子、山田恵子、てらなおみ、田沼佐和子、山本じん、相場るい児、井桁裕子、四谷シモンらによる作品を堪能する。
相場るい児さんの「人形愛」の根付シリーズが興味をひいた。
夜、銭ゲバに行ってみると、カナリヤちゃんが焼いた赤子クッキーがあった。
赤子の人形をクッキーの中に一緒に焼きこんだ菓子で、昼間に見た「人形がたり」の続きがここでも催されているかのようだった。
読んだ本はミシェル・オンフレの『哲学者、怒りに炎上す。』
以下、目次。
長椅子の下に憲兵がいたら?
ありえない共同体
生きた矛盾形容詞
第三の性道徳革命−同性愛の婚姻
アッラーは(あまりに)偉大なり
たくさんのお仲間たちと物書きたち−マガリ・コモー=ドニに捧げる
食人種を飼い慣らす方法
聖水を身に振りまいて
反ユダヤ主義が来たぞと叫ぶ!
狼話の後日談…
ありそうにないアメリカの理性
病人とロクデナシたち
ユダの原理
牛の鼻先でバカ騒ぎ
通信の衛生学
バカモノどものヨーロッパ
テレビ宗教の篤信家たち
ワラジムシの生
友情にともなう義務
不埒な裏切り者世代−ピエール・オルソニへ
ペダルをこぐジャン=ポール・サルトル
近所のパン屋を襲撃する
ケルヒャー掃除機の不毛な議論
哲学的脳天気
ネズミの権利
フランス人は死者がお好き
これは戯画ではない
アンネ(フランク)とヨーゼフ(ラッツィンガー)
メディア受けする哲学のつくり方
娘に語るジャーナリズム
情報誌『コルシカ』に掲載された時評をまとめたもの。
これが面白い!
例えば、アガンベンが「強制収容所」の類推でなんでも考えようとしているのを指して、こう言う。
「たとえば列車だって潜在的には殺人兵器だと決めつけることになる」と。
また、同じ種族のフェロモンによってのみ動かされているような人を「ワラジムシ」と呼ぶ。
リュック・フェリーのベストセラーが、今まで目のかたきにしてきたデリダとヴァネジェイムの本のタイトルを流用して付けられていることを暴露したり。
カトリックやイスラムにも歯に衣着せぬ言い方で挑発する。
欧州憲法条約の国民投票で反対票を投じようとする連中をこう評する。
「それは、バカモノどもだ。何も考えず、愚かしく、無教養な輩。乏しい購買力、乏しい頭脳、乏しい思考力、乏しい感性。学業の修了証もなく、自宅に本もなく、教養もなく、知性もない。彼らは田舎に、地方に暮らしている。農民、それもどん百姓、ヤボったい田舎っぺ。歴史というものの意味もわからず、政治的なグランドデザインがどんなものなのか想像もつかない。進歩の大きな息吹にもとんと無縁で、心は恐れで張り裂けんばかり」
さらに続く。
「反対派の連中は ポピュリスト、デマゴーグ、過激派、不満うずまく反動主義者。恨みを抱く人の典型だ」
反対が過半数をしめそうだという予測のもとでの記事にちがいないが、ここまで言うとすっきりする。
逆に賛成派をどう賛美しているかは、本書でのお楽しみ。
K1ワールドマックス。
自演乙とひなたの試合が見たかった。
今回はこの2人に尽きるでしょう。
「人と人形(ヒトガタ)/混乱する主従関係」と題されている。
最終日にやっと覗く事が出来た。入ってすぐの所に並ぶ古書は昨日来たときにひととおり見ていた。ラインナップは素晴らしいが、あいにくと僕の探している本はなかった。
靴を脱いであがり、鞄をあずけて展示を見る。
山吉由利子、きんすなご、トサカネコ舎、佐藤珠子、山田恵子、てらなおみ、田沼佐和子、山本じん、相場るい児、井桁裕子、四谷シモンらによる作品を堪能する。
相場るい児さんの「人形愛」の根付シリーズが興味をひいた。
夜、銭ゲバに行ってみると、カナリヤちゃんが焼いた赤子クッキーがあった。
赤子の人形をクッキーの中に一緒に焼きこんだ菓子で、昼間に見た「人形がたり」の続きがここでも催されているかのようだった。
読んだ本はミシェル・オンフレの『哲学者、怒りに炎上す。』
以下、目次。
長椅子の下に憲兵がいたら?
ありえない共同体
生きた矛盾形容詞
第三の性道徳革命−同性愛の婚姻
アッラーは(あまりに)偉大なり
たくさんのお仲間たちと物書きたち−マガリ・コモー=ドニに捧げる
食人種を飼い慣らす方法
聖水を身に振りまいて
反ユダヤ主義が来たぞと叫ぶ!
狼話の後日談…
ありそうにないアメリカの理性
病人とロクデナシたち
ユダの原理
牛の鼻先でバカ騒ぎ
通信の衛生学
バカモノどものヨーロッパ
テレビ宗教の篤信家たち
ワラジムシの生
友情にともなう義務
不埒な裏切り者世代−ピエール・オルソニへ
ペダルをこぐジャン=ポール・サルトル
近所のパン屋を襲撃する
ケルヒャー掃除機の不毛な議論
哲学的脳天気
ネズミの権利
フランス人は死者がお好き
これは戯画ではない
アンネ(フランク)とヨーゼフ(ラッツィンガー)
メディア受けする哲学のつくり方
娘に語るジャーナリズム
情報誌『コルシカ』に掲載された時評をまとめたもの。
これが面白い!
例えば、アガンベンが「強制収容所」の類推でなんでも考えようとしているのを指して、こう言う。
「たとえば列車だって潜在的には殺人兵器だと決めつけることになる」と。
また、同じ種族のフェロモンによってのみ動かされているような人を「ワラジムシ」と呼ぶ。
リュック・フェリーのベストセラーが、今まで目のかたきにしてきたデリダとヴァネジェイムの本のタイトルを流用して付けられていることを暴露したり。
カトリックやイスラムにも歯に衣着せぬ言い方で挑発する。
欧州憲法条約の国民投票で反対票を投じようとする連中をこう評する。
「それは、バカモノどもだ。何も考えず、愚かしく、無教養な輩。乏しい購買力、乏しい頭脳、乏しい思考力、乏しい感性。学業の修了証もなく、自宅に本もなく、教養もなく、知性もない。彼らは田舎に、地方に暮らしている。農民、それもどん百姓、ヤボったい田舎っぺ。歴史というものの意味もわからず、政治的なグランドデザインがどんなものなのか想像もつかない。進歩の大きな息吹にもとんと無縁で、心は恐れで張り裂けんばかり」
さらに続く。
「反対派の連中は ポピュリスト、デマゴーグ、過激派、不満うずまく反動主義者。恨みを抱く人の典型だ」
反対が過半数をしめそうだという予測のもとでの記事にちがいないが、ここまで言うとすっきりする。
逆に賛成派をどう賛美しているかは、本書でのお楽しみ。
K1ワールドマックス。
自演乙とひなたの試合が見たかった。
今回はこの2人に尽きるでしょう。
『図説「最悪」の仕事の歴史』
2009年2月17日 読書トニー・ロビンソン&デイヴィッド・ウィルコック著の『図説「最悪」の仕事の歴史』を読んだ。
ローマ時代から中世、チューダー王朝時代、スチュアート王朝時代、ジョージ王朝時代、ヴィクトリア時代へとイングランドの歴史を追うなかで登場した最悪な仕事の数々。
「最悪」というのは、「きつい」「きたない」「危険」「低収入」「退屈」の5つの基準から選ばれている。
たしかに、最悪の仕事が並べられているが、実際に働きはじめると、マヒして毎日働いてしまうんだろうな、と思った。
きついに違いないと思って読んだ『原発ジプシー』では、きつさよりも、鈍い痛みのようなものを感じたが、この本で紹介されている仕事の多くも、そんな印象だった。
さて、内容については、また後日。
とにかく、この本も面白かった。
ローマ時代から中世、チューダー王朝時代、スチュアート王朝時代、ジョージ王朝時代、ヴィクトリア時代へとイングランドの歴史を追うなかで登場した最悪な仕事の数々。
「最悪」というのは、「きつい」「きたない」「危険」「低収入」「退屈」の5つの基準から選ばれている。
たしかに、最悪の仕事が並べられているが、実際に働きはじめると、マヒして毎日働いてしまうんだろうな、と思った。
きついに違いないと思って読んだ『原発ジプシー』では、きつさよりも、鈍い痛みのようなものを感じたが、この本で紹介されている仕事の多くも、そんな印象だった。
さて、内容については、また後日。
とにかく、この本も面白かった。
おちまさとの『鉄板病』を読んだ。
社会批評の本を続けて読めば読むほど、現代に住む一般大衆は愚民以外のなにものでもない、と感想を抱かざるをえない。
現代を嘆くだけでは、なんにもならないのに。
これも詳しくはまた後日。
社会批評の本を続けて読めば読むほど、現代に住む一般大衆は愚民以外のなにものでもない、と感想を抱かざるをえない。
現代を嘆くだけでは、なんにもならないのに。
これも詳しくはまた後日。
『オタクはすでに死んでいる』
2009年2月12日 読書岡田斗司夫の『オタクはすでに死んでいる』を読んだ。
慎重な書きようはしているが、どうしても世代論のアプローチが必要になり、読後はその印象が強く残る。
「オタク」にしろ、「デブ」にしろ、自意識過剰なネーミングについては、ピンとこないところがある。所与の部分が違うのだろう。
でも、腐女子みたいに、差異に拘泥しているつもりもないのだが。
とか、内容詳しくはまた後日。
天才てれび君MAXにPerfume出てた。
しかし、みどころはそこにはなく、ことりとメロディのデュエットにあった。
慎重な書きようはしているが、どうしても世代論のアプローチが必要になり、読後はその印象が強く残る。
「オタク」にしろ、「デブ」にしろ、自意識過剰なネーミングについては、ピンとこないところがある。所与の部分が違うのだろう。
でも、腐女子みたいに、差異に拘泥しているつもりもないのだが。
とか、内容詳しくはまた後日。
天才てれび君MAXにPerfume出てた。
しかし、みどころはそこにはなく、ことりとメロディのデュエットにあった。
『「心の傷」は言ったもん勝ち』
2009年2月11日 読書中嶋聡の『「心の傷」は言ったもん勝ち』を読んだ。
昨日読んだ『ブルマーはなぜ消えたのか』の延長線上にある論旨だが、編集との話し合いがあたのか、前作よりは言いたい放題ではなく、逆の立場への配慮もした記述になったいた。
以下、目次。
第1章 朝青龍問題と「心の病」
朝青龍はサボったのか/疾病利得とヒステリー/解離する意識/「心の病」の大膨張/新顔の「PTSD」/世の中のものさし/「心の傷」は大問題なのか/朝青龍の責任能力
第2章 軽症ヒステリーの時代
病名が患者を増やす?/「しっかりしろ」は禁句か/軽症ヒステリー患者たち/「適応障害」は後づけ/「心療内科」への誤解/「ギャンブル依存症」は存在しない/自助を助ける
第3章 セクハラは犯罪だろうか
セクハラに関する疑問/息苦しい論理/増殖する「ハラ」/相手が嫌なら「セクハラ」か/被害者がすべてを決める/ふざけてはいけないのか/単純化する思考
第4章 理不尽な医療訴訟
医療訴訟の問題/医師の説明責任をめぐって/治療の押し売りはできない/医師の裁量が認められない/患者と司法が医師を殺す
第5章 被害者帝国主義
「でっちあげ」の恐怖/「傷ついた」の万能性/「被害者帝国主義」の誕生/被害者の圧倒的有利
第6章 「辺縁」を生かす
ナースキャップが消えた/消された理由/本当に不要だったのか/消え行く名称/賭け麻雀は違法か/「辺縁」を考える/「お」が付くか/裁量を許す社会/患者様
第7章 精神力を鍛えよう
強い個人になるために/西本育夫君の話/「にもかかかわらず」の能力/精神力を鍛える七つのポイント
最後の「精神力を鍛える七つのポイント」は、
1、何事も人のせいにしない
2、おおざっぱでよいとする
3、忘れる」能力を身につける
4、辛いときでも相手の立場に立つ
5、不可能と決めつけない
6、自分を超える価値のために生きる
7、時にあって、全力を尽くす
前作では「ブルマー」本書では「ナースキャップ」
いやしかし、「被害者帝国主義」をここでも展開するとは。
僕自身は「加害者の人権ばかりが守られている」なんていう発言にはまったく賛成できないのだが、「被害者帝国主義」もちょっとどうか。
本書も懲りないおやじたちが「そう、そうだ、まったくだ」と同意するために書かれたもののようだ。
ただ、こういう意見が根強いことも認識しておかねばバランスを欠く、というものだ。
昨日読んだ『ブルマーはなぜ消えたのか』の延長線上にある論旨だが、編集との話し合いがあたのか、前作よりは言いたい放題ではなく、逆の立場への配慮もした記述になったいた。
以下、目次。
第1章 朝青龍問題と「心の病」
朝青龍はサボったのか/疾病利得とヒステリー/解離する意識/「心の病」の大膨張/新顔の「PTSD」/世の中のものさし/「心の傷」は大問題なのか/朝青龍の責任能力
第2章 軽症ヒステリーの時代
病名が患者を増やす?/「しっかりしろ」は禁句か/軽症ヒステリー患者たち/「適応障害」は後づけ/「心療内科」への誤解/「ギャンブル依存症」は存在しない/自助を助ける
第3章 セクハラは犯罪だろうか
セクハラに関する疑問/息苦しい論理/増殖する「ハラ」/相手が嫌なら「セクハラ」か/被害者がすべてを決める/ふざけてはいけないのか/単純化する思考
第4章 理不尽な医療訴訟
医療訴訟の問題/医師の説明責任をめぐって/治療の押し売りはできない/医師の裁量が認められない/患者と司法が医師を殺す
第5章 被害者帝国主義
「でっちあげ」の恐怖/「傷ついた」の万能性/「被害者帝国主義」の誕生/被害者の圧倒的有利
第6章 「辺縁」を生かす
ナースキャップが消えた/消された理由/本当に不要だったのか/消え行く名称/賭け麻雀は違法か/「辺縁」を考える/「お」が付くか/裁量を許す社会/患者様
第7章 精神力を鍛えよう
強い個人になるために/西本育夫君の話/「にもかかかわらず」の能力/精神力を鍛える七つのポイント
最後の「精神力を鍛える七つのポイント」は、
1、何事も人のせいにしない
2、おおざっぱでよいとする
3、忘れる」能力を身につける
4、辛いときでも相手の立場に立つ
5、不可能と決めつけない
6、自分を超える価値のために生きる
7、時にあって、全力を尽くす
前作では「ブルマー」本書では「ナースキャップ」
いやしかし、「被害者帝国主義」をここでも展開するとは。
僕自身は「加害者の人権ばかりが守られている」なんていう発言にはまったく賛成できないのだが、「被害者帝国主義」もちょっとどうか。
本書も懲りないおやじたちが「そう、そうだ、まったくだ」と同意するために書かれたもののようだ。
ただ、こういう意見が根強いことも認識しておかねばバランスを欠く、というものだ。
『ブルマーはなぜ消えたのか〜セクハラと心の傷の文化を問う〜』
2009年2月10日 読書中嶋聡の『ブルマーはなぜ消えたのか〜セクハラと心の傷の文化を問う〜』を読んだ。
中嶋氏は1955年京都生まれの精神科医。
以下、目次。
第1部 ブルマーの消滅という出来事
1、なぜブルマーなのか
ときめきの青春時代
ブルマーがある風景/幸せと喜びの源/消滅の兆し/全国を訪ねまわって絶望にいたる/清純派ブルマーファンは「アダルト」が嫌い
その後の私−絶望から開き直りまで
失われる健康なエロス/避けられる苦しさと危険/のっぺらぼうになる名称/構想への踏みだし
本書のプログラム
2、ブルマーの消滅
まえおき
ブルマーはいかがわしいのか?
ブルマーの歴史ー誕生から消滅まで
セーラー服とセットだった/日本のブルマー発展史/ちょうちんからぴったり化繊へ/ブルマー消滅の過程
ブルマーを滅ぼしたものーその力学の分析
形を変えていった要因は?/ブルマーをとりまく二つの力/規範と教育/人権とジェンダー/規範VS人権・ジェンダー
第2部 人権・ジェンダーから辺縁へ
3、人権と偏見について
急浮上する人権
ある違和感/信念はそんなに急に変わるのか?
本性としての偏見
分裂病者とは?/普通の人でなければいけない?/克服への道
4、性同一性障害をめぐって
それは突然現われた
ジェンダーについて
なにも言えなくなる社会
性同一性障害は本当に疾患か
性と感覚、どちらを信ずべき?
聖書的考察
性とは神から与えられた限界である/違和感へのすりかえ
「性同一性障害」の患者にどう向き合えばよいか
外科的手術は是か否か?
5、「辺縁」という概念
消えていった多くの事柄
ブルマーが醸し出してくれた甘酸っぱさ/市電と蒸気機関車のある風景/「さん」づけの不自然さ/ジェンダー・フリーはここがおかしい/体罰か、指導か?/体育会系の伝統/伝統がつくりあげた緩衝地帯
「辺縁」について
中心から外れたところに味わいがある/場としての辺縁と意味としての辺縁/さまざまな辺縁/類縁概念との関係
第3部 辺縁の社会精神病理
6、セクハラ
三つの問題点
嫌がらせは犯罪か
相手がセクハラと感じたらセクハラなのか
傷ついた人のためにみんな犠牲になれ/接待・宴会・社員旅行がもつ力/パブリックとプライベートのあいだにある遊びの空間/セクハラがもたらす味気なさ/自分自身で決断する
なぜ「セク」ハラなのか
セクハラと辺縁の倫理
7、タバコと禁煙運動
ヒステリックな状況
なんのために吸うのか
健康第一という強迫/この瞬間を味わうために/アイ・マスト・スモーク!!/志高性⊂辺縁
タバコの社会的効果
唯一の楽しみとしての喫煙/タバコは交流をひろげてくれる/病棟禁煙化という逆風/大部屋なしの病院ドラマなどありえない
8、インフォームド・コンセント
決めるのはだれか
説明しないのにはわけがある/パイロットと乗客のような関係
責任の所在をめぐって
患者の構えを見てとる/重大な副作用から説明するわけではない/自己決定の問題点/選択できない患者
お任せという考え方
第4部 辺縁とこれからの社会
9、「傷つく」現代人と被害者帝国主義
嫌な思いをしたではなく、傷ついた
少女よりおじさんの方が感じやすい/ストレスはあるのが当然である/強靱な精神をもつ
被害者帝国主義の台頭
肉体の傷と精神の傷の違い/加害者と被害者の立場の違い/解決の方法は?/泣く子と地頭にはやはり勝てない/被害者が審判になる/配慮を求めるのでなく、乗り越える
10、辺縁を楽しむ社会へ 「生」の復権のために
個人的な楽しみ・意味を削ぎ落とす社会
被害者帝国の出現/安全・安心のなかにひきこもる/ほどほどのエロスがなければ生きていけない/生の現実が遠ざかる/プロレスラーがその妻に負ける世の中/大人と子ども・専門家と素人のあいだに生まれる馬鹿馬鹿しさ
それぞれの欲望と楽しみを生かす社会
辺縁と「タテ社会」との関係/辺縁がもたらすもの/だれもが嫌がらない楽しみなどない/禁止の法ではなく、認め合うマナーや節度を/一人でも喜ぶ人がいるならやろう/独自性を尊重する社会に向けて
目次を見てわかるように、ブルマーの消滅を足がかりにして、社会の話にひろがっていくが、読んでいる側としては、「いつになったら話がブルマーに戻ってくるんだろう」と待ち遠しくてならなかった。
著者の言う「辺縁」は難しそうな言い回しだが、まあ「風情」とか「趣き」みたいなものと考えていいだろう。主張はかなり本音を語ったもので、読んでいて痛快な部分もあるが、総じて保守的な意見が多くて、反論したいことが多かった。これが読書の醍醐味でもある。
中嶋氏は1955年京都生まれの精神科医。
以下、目次。
第1部 ブルマーの消滅という出来事
1、なぜブルマーなのか
ときめきの青春時代
ブルマーがある風景/幸せと喜びの源/消滅の兆し/全国を訪ねまわって絶望にいたる/清純派ブルマーファンは「アダルト」が嫌い
その後の私−絶望から開き直りまで
失われる健康なエロス/避けられる苦しさと危険/のっぺらぼうになる名称/構想への踏みだし
本書のプログラム
2、ブルマーの消滅
まえおき
ブルマーはいかがわしいのか?
ブルマーの歴史ー誕生から消滅まで
セーラー服とセットだった/日本のブルマー発展史/ちょうちんからぴったり化繊へ/ブルマー消滅の過程
ブルマーを滅ぼしたものーその力学の分析
形を変えていった要因は?/ブルマーをとりまく二つの力/規範と教育/人権とジェンダー/規範VS人権・ジェンダー
第2部 人権・ジェンダーから辺縁へ
3、人権と偏見について
急浮上する人権
ある違和感/信念はそんなに急に変わるのか?
本性としての偏見
分裂病者とは?/普通の人でなければいけない?/克服への道
4、性同一性障害をめぐって
それは突然現われた
ジェンダーについて
なにも言えなくなる社会
性同一性障害は本当に疾患か
性と感覚、どちらを信ずべき?
聖書的考察
性とは神から与えられた限界である/違和感へのすりかえ
「性同一性障害」の患者にどう向き合えばよいか
外科的手術は是か否か?
5、「辺縁」という概念
消えていった多くの事柄
ブルマーが醸し出してくれた甘酸っぱさ/市電と蒸気機関車のある風景/「さん」づけの不自然さ/ジェンダー・フリーはここがおかしい/体罰か、指導か?/体育会系の伝統/伝統がつくりあげた緩衝地帯
「辺縁」について
中心から外れたところに味わいがある/場としての辺縁と意味としての辺縁/さまざまな辺縁/類縁概念との関係
第3部 辺縁の社会精神病理
6、セクハラ
三つの問題点
嫌がらせは犯罪か
相手がセクハラと感じたらセクハラなのか
傷ついた人のためにみんな犠牲になれ/接待・宴会・社員旅行がもつ力/パブリックとプライベートのあいだにある遊びの空間/セクハラがもたらす味気なさ/自分自身で決断する
なぜ「セク」ハラなのか
セクハラと辺縁の倫理
7、タバコと禁煙運動
ヒステリックな状況
なんのために吸うのか
健康第一という強迫/この瞬間を味わうために/アイ・マスト・スモーク!!/志高性⊂辺縁
タバコの社会的効果
唯一の楽しみとしての喫煙/タバコは交流をひろげてくれる/病棟禁煙化という逆風/大部屋なしの病院ドラマなどありえない
8、インフォームド・コンセント
決めるのはだれか
説明しないのにはわけがある/パイロットと乗客のような関係
責任の所在をめぐって
患者の構えを見てとる/重大な副作用から説明するわけではない/自己決定の問題点/選択できない患者
お任せという考え方
第4部 辺縁とこれからの社会
9、「傷つく」現代人と被害者帝国主義
嫌な思いをしたではなく、傷ついた
少女よりおじさんの方が感じやすい/ストレスはあるのが当然である/強靱な精神をもつ
被害者帝国主義の台頭
肉体の傷と精神の傷の違い/加害者と被害者の立場の違い/解決の方法は?/泣く子と地頭にはやはり勝てない/被害者が審判になる/配慮を求めるのでなく、乗り越える
10、辺縁を楽しむ社会へ 「生」の復権のために
個人的な楽しみ・意味を削ぎ落とす社会
被害者帝国の出現/安全・安心のなかにひきこもる/ほどほどのエロスがなければ生きていけない/生の現実が遠ざかる/プロレスラーがその妻に負ける世の中/大人と子ども・専門家と素人のあいだに生まれる馬鹿馬鹿しさ
それぞれの欲望と楽しみを生かす社会
辺縁と「タテ社会」との関係/辺縁がもたらすもの/だれもが嫌がらない楽しみなどない/禁止の法ではなく、認め合うマナーや節度を/一人でも喜ぶ人がいるならやろう/独自性を尊重する社会に向けて
目次を見てわかるように、ブルマーの消滅を足がかりにして、社会の話にひろがっていくが、読んでいる側としては、「いつになったら話がブルマーに戻ってくるんだろう」と待ち遠しくてならなかった。
著者の言う「辺縁」は難しそうな言い回しだが、まあ「風情」とか「趣き」みたいなものと考えていいだろう。主張はかなり本音を語ったもので、読んでいて痛快な部分もあるが、総じて保守的な意見が多くて、反論したいことが多かった。これが読書の醍醐味でもある。
書店では既に2号が並んで久しいが、『思想地図』vol.1をやっと読んだ。
以下、目次。
創刊に寄せて/東浩紀+北田暁大
[共同討議]「国家・暴力・ナショナリズム」/東浩紀+萱野稔人+北田暁大+白井聡+中島岳志
〜特集・日本〜
1、歴史のなかの「ナショナリズム」
日本右翼再考ーその思想と系譜をめぐって/中島岳志
日韓のナショナリズムとラディカリズムの交錯ー韓国の進歩イデオロギーと日本のアジア観を事例として/高原基彰
2、ニッポンのイマーゴポリティクス
マンガのグローバリゼーションー日本マンガ「浸透」後の世界/伊藤剛
データベース、パクリ、初音ミク/増田聡
物語の見る夢ー華文世界の文化資本/福嶋亮大
中国における日本のサブカルチャーとジェンダーー「80後」世代中国人若者の日本観/呉咏梅
[鼎談]日本論とナショナリズム/東浩紀+萱野稔人+北田暁大
ブックガイド「日本論」斎藤哲也
3、問題としての日本社会
「まつろわぬもの」としての宗教ー現代日本の「宗教」の位相/川瀬貴也
<生への配慮>が枯渇した社会/芹沢一也
社会的関係と身体的コミュニケーションー朝鮮学校のケンカ文化から/韓東賢
4、共和主義の再発明
共和制は可能か?/白田秀彰
死者への気づき/黒宮一太
[公募論文]キャラクターが、見ているーアニメ表現論序説/黒瀬陽平
予想以上に、現状報告というか、情報、知識をまとめた箇所が多かった。
知らないことだらけだったので、それはそれで楽しかったのだが、「へ〜、そうなんだ」といろいろ知るよりは、手持ちの情報からどんな思想を編み出してくれるか、という方に期待していただけに、ちょっと意外だった。
と、いうわけで、この一冊のなかで一番面白かったのは、公募論文の「キャラクターが、見ている」だった。各章前に、編集者からのガイダンスが書かれており、この「キャラクターが見てる」ではアニメ「あずまんが大王」「らきすた」「ぱにぽにだっしゅ」などを、『思想地図』の読者はあまり見ていないんじゃないか、と想定している文章が載っていた。逆な気がする。
以下、目次。
創刊に寄せて/東浩紀+北田暁大
[共同討議]「国家・暴力・ナショナリズム」/東浩紀+萱野稔人+北田暁大+白井聡+中島岳志
〜特集・日本〜
1、歴史のなかの「ナショナリズム」
日本右翼再考ーその思想と系譜をめぐって/中島岳志
日韓のナショナリズムとラディカリズムの交錯ー韓国の進歩イデオロギーと日本のアジア観を事例として/高原基彰
2、ニッポンのイマーゴポリティクス
マンガのグローバリゼーションー日本マンガ「浸透」後の世界/伊藤剛
データベース、パクリ、初音ミク/増田聡
物語の見る夢ー華文世界の文化資本/福嶋亮大
中国における日本のサブカルチャーとジェンダーー「80後」世代中国人若者の日本観/呉咏梅
[鼎談]日本論とナショナリズム/東浩紀+萱野稔人+北田暁大
ブックガイド「日本論」斎藤哲也
3、問題としての日本社会
「まつろわぬもの」としての宗教ー現代日本の「宗教」の位相/川瀬貴也
<生への配慮>が枯渇した社会/芹沢一也
社会的関係と身体的コミュニケーションー朝鮮学校のケンカ文化から/韓東賢
4、共和主義の再発明
共和制は可能か?/白田秀彰
死者への気づき/黒宮一太
[公募論文]キャラクターが、見ているーアニメ表現論序説/黒瀬陽平
予想以上に、現状報告というか、情報、知識をまとめた箇所が多かった。
知らないことだらけだったので、それはそれで楽しかったのだが、「へ〜、そうなんだ」といろいろ知るよりは、手持ちの情報からどんな思想を編み出してくれるか、という方に期待していただけに、ちょっと意外だった。
と、いうわけで、この一冊のなかで一番面白かったのは、公募論文の「キャラクターが、見ている」だった。各章前に、編集者からのガイダンスが書かれており、この「キャラクターが見てる」ではアニメ「あずまんが大王」「らきすた」「ぱにぽにだっしゅ」などを、『思想地図』の読者はあまり見ていないんじゃないか、と想定している文章が載っていた。逆な気がする。
君らの魂を悪魔に売りつけよ
2009年2月8日 読書新青年傑作選『君らの魂を悪魔に売りつけよ』
永遠の女囚/木々高太郎
家常茶飯/佐藤春夫
変化する陳述/石浜金作
月世界の女/高木彬光
彼が殺したか/浜尾四郎
印度林檎/角田喜久雄
蔵の中/横溝正史
烙印/大下宇陀児
お嬢キャラがいたり、妻の妹を愛したり、衆道、SMなど、変態性欲がちりばめられていた。
タイトルは浜尾四郎の『彼が殺したか』からの引用。
前後を加えて引用すると、こんな文章。
生命のいらぬ人々よ
君らの魂を悪魔に売りつけよ。
生命をもって価とせよ。
しからば君らには不可能ということはなくなるであろう。
正義よ、いくたび汝の名によりて血が流されたことであろう。
浜尾四郎ここにあり、といった文章。
永遠の女囚/木々高太郎
家常茶飯/佐藤春夫
変化する陳述/石浜金作
月世界の女/高木彬光
彼が殺したか/浜尾四郎
印度林檎/角田喜久雄
蔵の中/横溝正史
烙印/大下宇陀児
お嬢キャラがいたり、妻の妹を愛したり、衆道、SMなど、変態性欲がちりばめられていた。
タイトルは浜尾四郎の『彼が殺したか』からの引用。
前後を加えて引用すると、こんな文章。
生命のいらぬ人々よ
君らの魂を悪魔に売りつけよ。
生命をもって価とせよ。
しからば君らには不可能ということはなくなるであろう。
正義よ、いくたび汝の名によりて血が流されたことであろう。
浜尾四郎ここにあり、といった文章。
久米元一の『仮面魔』を読んだ。サブタイトルは「謎のランプ」
以下、目次。
石なげのめいじん
あやしい人かげ
われないホヤ
五郎の発見
あらわれた文字
壁に耳あり
美しい青年
あや子の妙案
ごくろうさま
白か?黒か?
湖のぬし
いよいよ宝さがし
ふしぎな音
ふきだす水
しまった!
五郎の活躍
外人屋敷
悪魔はどこに?
あぶない いのち
猛犬タイガー
ガスピストル
むらさき覆面の団長
黒い帽子
僕が知っているぞ
身をすててこそ
行きがけのだちん
じいやのゆくえ
兄さんきたる
おや!へんだぞ
ふしぎな暗号
忠作じいや
鬼の洞穴
糸を切るな
だれが来たか?
鍾乳洞
とびこめ!
穴ぐらの中
さあ今だ!
消えた団長
まだランプをねらっている
じいやが団長だ!
無気味な足音
じいやの逆襲
二つの指紋
ランプの謎
一郎の大失敗
とどろく銃声
釜の中のラジオ
早いもの勝ち
湖底のたから
鉄の箱
五郎の潜水
水中の格闘
無念!
もうだめか!
消えた、たから
一郎の計略
仮面をぬぐ
五郎の大発見
勝つか?負けるか?
悪魔の最期
巨万の財宝
表紙絵:伊勢良夫、さし絵:阿部和助
少年冒険ものの定番、宝さがしだ。
ランプのホヤに財宝のありかが記してあった!
その文句は、こんなふうに書いてあった。
「満月の夜、舟を湖水にうかべて、もっとも深きところへいたれ。月が中天にかかる頃、月のかげのやどれるところへ、イカリをおろせ」
ところが、この文句は、舟に穴あけて湖で邪魔者を抹殺するため、悪人たちがでっちあげた文面だった!
この悪人たちがどんな奴らかというと。
合言葉は「悪魔はどこだ?」「悪魔は、おまえの胸に!」
団長は、黒いガウンにむらさき色のビロードの覆面をつけ、目だけのぞかせた男。ナゾーみたいな感じかな?
手下には、だるまに似たダル公などがいる。はしっこい少年に対して「まるでねずみ小僧、児雷也小僧みたいだな」なんて言う。
ガスピストルを発明している。
電殺装置を持っている。黒い鉄かぶとに長い電線がついたもので、「ちょっと見ると、女が髪をちぢらせるときにつかう、パーマネントの帽子のように見えた」
などなど。
さすが久米元一、と何度もうなった。
モールス信号の暗号を使ってみたりする推理興味、ピンチに次ぐピンチ、展開の面白さ。
悪漢たちが少年の使う空手のあてみや石なげでいとも簡単にのされてしまうのも痛快。
以下、目次。
石なげのめいじん
あやしい人かげ
われないホヤ
五郎の発見
あらわれた文字
壁に耳あり
美しい青年
あや子の妙案
ごくろうさま
白か?黒か?
湖のぬし
いよいよ宝さがし
ふしぎな音
ふきだす水
しまった!
五郎の活躍
外人屋敷
悪魔はどこに?
あぶない いのち
猛犬タイガー
ガスピストル
むらさき覆面の団長
黒い帽子
僕が知っているぞ
身をすててこそ
行きがけのだちん
じいやのゆくえ
兄さんきたる
おや!へんだぞ
ふしぎな暗号
忠作じいや
鬼の洞穴
糸を切るな
だれが来たか?
鍾乳洞
とびこめ!
穴ぐらの中
さあ今だ!
消えた団長
まだランプをねらっている
じいやが団長だ!
無気味な足音
じいやの逆襲
二つの指紋
ランプの謎
一郎の大失敗
とどろく銃声
釜の中のラジオ
早いもの勝ち
湖底のたから
鉄の箱
五郎の潜水
水中の格闘
無念!
もうだめか!
消えた、たから
一郎の計略
仮面をぬぐ
五郎の大発見
勝つか?負けるか?
悪魔の最期
巨万の財宝
表紙絵:伊勢良夫、さし絵:阿部和助
少年冒険ものの定番、宝さがしだ。
ランプのホヤに財宝のありかが記してあった!
その文句は、こんなふうに書いてあった。
「満月の夜、舟を湖水にうかべて、もっとも深きところへいたれ。月が中天にかかる頃、月のかげのやどれるところへ、イカリをおろせ」
ところが、この文句は、舟に穴あけて湖で邪魔者を抹殺するため、悪人たちがでっちあげた文面だった!
この悪人たちがどんな奴らかというと。
合言葉は「悪魔はどこだ?」「悪魔は、おまえの胸に!」
団長は、黒いガウンにむらさき色のビロードの覆面をつけ、目だけのぞかせた男。ナゾーみたいな感じかな?
手下には、だるまに似たダル公などがいる。はしっこい少年に対して「まるでねずみ小僧、児雷也小僧みたいだな」なんて言う。
ガスピストルを発明している。
電殺装置を持っている。黒い鉄かぶとに長い電線がついたもので、「ちょっと見ると、女が髪をちぢらせるときにつかう、パーマネントの帽子のように見えた」
などなど。
さすが久米元一、と何度もうなった。
モールス信号の暗号を使ってみたりする推理興味、ピンチに次ぐピンチ、展開の面白さ。
悪漢たちが少年の使う空手のあてみや石なげでいとも簡単にのされてしまうのも痛快。
鯨統一郎の『哲学探偵』を読んだ。
事件を解決するのは、競馬場にいる哲学好きで短歌が趣味の男。
4話までは『小説新潮』に掲載され、残りの4話は書き下ろし。
例によって、哲学と短歌の話題でページを稼いでいるが、それほど謎やその解明に関連しているわけではない。鯨統一郎のミステリは、多くの場合、雑学本として読めばいいんじゃないか、とも思えてくる。
ネタバレしかしていないので、要注意。
第1話 世界は水からできている(タレス)
第2話 汝自身を知れ(ソクラテス)
第3話 われ思う、ゆえにわれ在り(デカルト)
第4話 人間は考える葦である(パスカル)
第5話 純粋理性を求めて(カント)
第6話 厭世主義の暴走(ショーペンハウアー)
第7話 神は死んだ(ニーチェ)
第8話 存在と時間の果てに(ハイデッガー)
1、「何もかも 世界は水からできている 哲学の始祖 タレスの主張」
グラスを置いた水滴から、興奮剤入りグラスのすりかえを見破る。
2、「誰よりも 汝自身を知った人 本を書かない 智者ソクラテス」
死人には切断したはずの指がはえていた!
双生児
3、「われ思う ゆえにわれ在りデカルトの 『方法序説』は平易な著作」
人にバッグをあずけてトイレに入って行った男が個室で殺されていた!凶器はなんとあずけたバッグの中から発見される。
被害者に変装した犯人。
4、「人間は 弱い葦だがパスカルは 考える葦だと『パンセ』で看破」
死体を341ものパーツに切り刻んだ理由は?
指つめをカモフラージュ
5、「純粋な 理性をカントは批判した 二律背反にたどりつくまで」
事故死や病死とみられていたものに、犯行声明を出す宗教家。
本当に殺した人間を目立たなくするための行動。
6、「凶暴な 意志が見果てぬ夢を追う ショーペンハウアー 厭世主義なり」
密室で撲殺されていた男。
窓の外から気功で投げ飛ばした。
7、「ニーチェ説く ルサンチマンが生み出した キリスト教は死んでいるなり」
20年ぶりにあけたタイムカプセルには生首が入っていた。今まさに殺されたばかりの生首が。
粘土。
8、「死を自覚 しても間違うときがある ハイデッガーはナチス入党」
電話アリバイ。
子機。
事件を解決するのは、競馬場にいる哲学好きで短歌が趣味の男。
4話までは『小説新潮』に掲載され、残りの4話は書き下ろし。
例によって、哲学と短歌の話題でページを稼いでいるが、それほど謎やその解明に関連しているわけではない。鯨統一郎のミステリは、多くの場合、雑学本として読めばいいんじゃないか、とも思えてくる。
ネタバレしかしていないので、要注意。
第1話 世界は水からできている(タレス)
第2話 汝自身を知れ(ソクラテス)
第3話 われ思う、ゆえにわれ在り(デカルト)
第4話 人間は考える葦である(パスカル)
第5話 純粋理性を求めて(カント)
第6話 厭世主義の暴走(ショーペンハウアー)
第7話 神は死んだ(ニーチェ)
第8話 存在と時間の果てに(ハイデッガー)
1、「何もかも 世界は水からできている 哲学の始祖 タレスの主張」
グラスを置いた水滴から、興奮剤入りグラスのすりかえを見破る。
2、「誰よりも 汝自身を知った人 本を書かない 智者ソクラテス」
死人には切断したはずの指がはえていた!
双生児
3、「われ思う ゆえにわれ在りデカルトの 『方法序説』は平易な著作」
人にバッグをあずけてトイレに入って行った男が個室で殺されていた!凶器はなんとあずけたバッグの中から発見される。
被害者に変装した犯人。
4、「人間は 弱い葦だがパスカルは 考える葦だと『パンセ』で看破」
死体を341ものパーツに切り刻んだ理由は?
指つめをカモフラージュ
5、「純粋な 理性をカントは批判した 二律背反にたどりつくまで」
事故死や病死とみられていたものに、犯行声明を出す宗教家。
本当に殺した人間を目立たなくするための行動。
6、「凶暴な 意志が見果てぬ夢を追う ショーペンハウアー 厭世主義なり」
密室で撲殺されていた男。
窓の外から気功で投げ飛ばした。
7、「ニーチェ説く ルサンチマンが生み出した キリスト教は死んでいるなり」
20年ぶりにあけたタイムカプセルには生首が入っていた。今まさに殺されたばかりの生首が。
粘土。
8、「死を自覚 しても間違うときがある ハイデッガーはナチス入党」
電話アリバイ。
子機。
杉作J太郎の『恋と股間』を読んだ。
若い世代に送る恋愛指南。
以下、目次。
恋愛は断られたところからすべてがはじまる。
1章 どうしたら、彼女ができますか?
本当に彼女をつくるための、はじめの第一歩
「生涯初彼女」を得るために
困ったら、まわりの人を仲人にする
「出会いがない」なんて寝言です
人前で弱みを見せるスキルを磨け!
いけしゃあしゃあとした人たち
早めに誰かのそばへ行き、「もうおしまいだ」とつぶやいておくこと
弱みをカミングアウトする方法
喜びも悲しみも、抱え込むのは危険です
ヘコむことを「恥」にしないために
セックスの極意は「思いやり」にこそある
どうして、専門学校がないんだろう
みっちりと、畏怖の念を叩き込む
お互いの存在が「異界」である
無理をしてこそ広がる世界
命がけのリラックス、過激なスローライフ
四十を過ぎてからのウルトラC
「お金」には名前を書く欄はない
ローテーションでお醤油を
彼氏になれなければ不幸なのか
2章 それは童貞の悪い癖です
見た目に自信がない場合、恋愛は何で勝負をすればいいですか?
まず、年上の女性に可能性を見出してみる
戦いに参加できない悔しさ
巨人的な視野を手に入れるために
生まれた瞬間からタイタニック号の上
「沈む」と「出会う」、どちらが早いか
「童貞」とは、いつ捨てるべきものですか?
それはね、一軍にあがってからです!
調子にのってると、「悲願」は達成できません
誰かの軒下を借りて生きているということ
童貞に「捨て場所」はあるのか
片思いの人への、ドラマティックなアクションの起こし方
それは、童貞の悪い癖です
告白されて怒り出す人
彼女のメアドを聞き出す「魔法のセリフ」とは?
アクティヴな働きかけは無意味です
「おカネがすべて」という価値観
意外とビッグ・チャンスな時代
「つづきはメールで」の極意
女性に対する「メールのNG」を教えてください。
教えましょう、「文芸メルマガ」はよしておいたほうがいい、ということを!
さらに、「ジョーク・メール」も禁止です
必要なことを、過不足なく
メールでは、恋愛の階段は上がれない
「覚悟」と「リラックス」のダブル・プレー
理想は「おもしろくて、やさしい人」。女性がそう言うたび、イラッとします。
「さんまさん」になる勇気を持てない人間
ネタの豊富な寿司屋をめざして
「オナニーのときに誰が思い浮かぶか」というジレンマ
二番手、三番手が登場するわけ
のぞみ号か、こだま号か?
いざというときにも平常心でいるために
世間ではみんな、AVのようなセックスを謳歌しているのでしょうか?
最低でも七割は割り引いて考えよう
「想像力」が開拓する、秘境へのルート
解答の出ていない参考書を片手に
オナニーは我と我が身を救う
告白したら「友だちでいましょう」と言われた
「友だちって何かね?」と言い返しましょう
「友だちからはじめましょう」もナシです
プレゼント、彼氏じゃなくても受け取ってもらえるものですか?
高価でなければ、いいんじゃないですか
3章 彼女ができても日々是修行
「コイツは小さい」と思われてしまう男の行動とは?
彼女の携帯を見る男は、小さい
彼女の手編みのセーターを着られない男は、小さい
ありったけの誠実さをこめたサービス
化粧を取ったら別人でした。だまされた気分です。
それはね、偽装工作じゃありません!
何がレギュラーで、イレギュラーなのか
トラブルは、起きてあたりまえです。
「何をしてもいい」と言われた場合、本当にしてもいいのはどこまでですか?
相手はかなりなことを望んでいます
「わからない」から必死になれること
恋愛に「職務質問」は許されない
一緒に寝るとき、彼女に背中を向けるのは失礼?
セックスに、小笠原流はありません
ハードボイルド・イン・ベッド
彼女が「昔のこと」を忘れてくれません。なぜ?
死んだはずの怪人がよみがえっている
動物界に反旗をひるがえした営み
彼女から別れを告げられました。男が発するべき第一声とは?
「それはないだろう!」と食い下がります
「歯ごたえがない男」という最低の評価
「カッコわるい」はストレスにならない
彼女の浮気を知ってしまった
「どうしてだ!?」と、パニック感あふれる取材をしてはいけません
画期的に困っている人を助けるシステム
浮気する人・しない人
「ストーカー」にならないための心得とは?
正直に、率直に伝えること
気持ちを表現するのは怖いことではない
自分をメインにしない、ということ
好きだったら本当に「しかたない」のか
心の殺傷罪を適用されますよ、もう
おわりに 女性のみなさん、ご静聴願います。
「いい男」のイメージについて、再考を促したい。
女性の話に、かたっぱしからうなずく男
「わかってたまるか」の大切さ
穴があることに気がつかない
男らしさ、女らしさという「演技」
何ということもなく、あったりするのかもしれない
笑いながら読みすすめられるが、意外とまっとうなことを語っているのには感心した。
これなら、ちゃんと迷える若き人々を間違った道に行かないように導けるんじゃなかろうか。
僕もかなりタメになった。
若い世代に送る恋愛指南。
以下、目次。
恋愛は断られたところからすべてがはじまる。
1章 どうしたら、彼女ができますか?
本当に彼女をつくるための、はじめの第一歩
「生涯初彼女」を得るために
困ったら、まわりの人を仲人にする
「出会いがない」なんて寝言です
人前で弱みを見せるスキルを磨け!
いけしゃあしゃあとした人たち
早めに誰かのそばへ行き、「もうおしまいだ」とつぶやいておくこと
弱みをカミングアウトする方法
喜びも悲しみも、抱え込むのは危険です
ヘコむことを「恥」にしないために
セックスの極意は「思いやり」にこそある
どうして、専門学校がないんだろう
みっちりと、畏怖の念を叩き込む
お互いの存在が「異界」である
無理をしてこそ広がる世界
命がけのリラックス、過激なスローライフ
四十を過ぎてからのウルトラC
「お金」には名前を書く欄はない
ローテーションでお醤油を
彼氏になれなければ不幸なのか
2章 それは童貞の悪い癖です
見た目に自信がない場合、恋愛は何で勝負をすればいいですか?
まず、年上の女性に可能性を見出してみる
戦いに参加できない悔しさ
巨人的な視野を手に入れるために
生まれた瞬間からタイタニック号の上
「沈む」と「出会う」、どちらが早いか
「童貞」とは、いつ捨てるべきものですか?
それはね、一軍にあがってからです!
調子にのってると、「悲願」は達成できません
誰かの軒下を借りて生きているということ
童貞に「捨て場所」はあるのか
片思いの人への、ドラマティックなアクションの起こし方
それは、童貞の悪い癖です
告白されて怒り出す人
彼女のメアドを聞き出す「魔法のセリフ」とは?
アクティヴな働きかけは無意味です
「おカネがすべて」という価値観
意外とビッグ・チャンスな時代
「つづきはメールで」の極意
女性に対する「メールのNG」を教えてください。
教えましょう、「文芸メルマガ」はよしておいたほうがいい、ということを!
さらに、「ジョーク・メール」も禁止です
必要なことを、過不足なく
メールでは、恋愛の階段は上がれない
「覚悟」と「リラックス」のダブル・プレー
理想は「おもしろくて、やさしい人」。女性がそう言うたび、イラッとします。
「さんまさん」になる勇気を持てない人間
ネタの豊富な寿司屋をめざして
「オナニーのときに誰が思い浮かぶか」というジレンマ
二番手、三番手が登場するわけ
のぞみ号か、こだま号か?
いざというときにも平常心でいるために
世間ではみんな、AVのようなセックスを謳歌しているのでしょうか?
最低でも七割は割り引いて考えよう
「想像力」が開拓する、秘境へのルート
解答の出ていない参考書を片手に
オナニーは我と我が身を救う
告白したら「友だちでいましょう」と言われた
「友だちって何かね?」と言い返しましょう
「友だちからはじめましょう」もナシです
プレゼント、彼氏じゃなくても受け取ってもらえるものですか?
高価でなければ、いいんじゃないですか
3章 彼女ができても日々是修行
「コイツは小さい」と思われてしまう男の行動とは?
彼女の携帯を見る男は、小さい
彼女の手編みのセーターを着られない男は、小さい
ありったけの誠実さをこめたサービス
化粧を取ったら別人でした。だまされた気分です。
それはね、偽装工作じゃありません!
何がレギュラーで、イレギュラーなのか
トラブルは、起きてあたりまえです。
「何をしてもいい」と言われた場合、本当にしてもいいのはどこまでですか?
相手はかなりなことを望んでいます
「わからない」から必死になれること
恋愛に「職務質問」は許されない
一緒に寝るとき、彼女に背中を向けるのは失礼?
セックスに、小笠原流はありません
ハードボイルド・イン・ベッド
彼女が「昔のこと」を忘れてくれません。なぜ?
死んだはずの怪人がよみがえっている
動物界に反旗をひるがえした営み
彼女から別れを告げられました。男が発するべき第一声とは?
「それはないだろう!」と食い下がります
「歯ごたえがない男」という最低の評価
「カッコわるい」はストレスにならない
彼女の浮気を知ってしまった
「どうしてだ!?」と、パニック感あふれる取材をしてはいけません
画期的に困っている人を助けるシステム
浮気する人・しない人
「ストーカー」にならないための心得とは?
正直に、率直に伝えること
気持ちを表現するのは怖いことではない
自分をメインにしない、ということ
好きだったら本当に「しかたない」のか
心の殺傷罪を適用されますよ、もう
おわりに 女性のみなさん、ご静聴願います。
「いい男」のイメージについて、再考を促したい。
女性の話に、かたっぱしからうなずく男
「わかってたまるか」の大切さ
穴があることに気がつかない
男らしさ、女らしさという「演技」
何ということもなく、あったりするのかもしれない
笑いながら読みすすめられるが、意外とまっとうなことを語っているのには感心した。
これなら、ちゃんと迷える若き人々を間違った道に行かないように導けるんじゃなかろうか。
僕もかなりタメになった。
『太宰治の正直ノオト』、クレージーの大爆発
2008年12月15日 読書「苦悩を売り物にするな」
NHKスペシャルでの派遣切り番組見て先行きが見えなくなり、心を鼓舞するため、クレージー見る。
上方演芸ホール、紅雀、鶴志
NHKスペシャルでの派遣切り番組見て先行きが見えなくなり、心を鼓舞するため、クレージー見る。
上方演芸ホール、紅雀、鶴志
メシアン、『タイマ』
2008年12月12日 読書NHK-FMで「鳥」の音楽特集を放送してて、メシアンとか流れてた。
「“鳥たちの深淵”〜“世の終わりのための四重奏曲”から」
メシアン作曲
(7分33秒)
(クラリネット)ポール・メイエ
<DENON COCO−78917>
「鳥の目覚め」 メシアン作曲
(21分40秒)
(ピアノ)イヴォンヌ・ロリオ
(管弦楽)チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
(指揮)ヴァーツラ・ノイマン
<SUPRAPHON CO−4498>
「ステンドグラスと鳥たち」 メシアン作曲
(8分28秒)
「異国の鳥たち」 メシアン作曲
(15分26秒)
(ピアノ)イヴォンヌ・ロリオ
(管弦楽)アンサンブル・アンテルコンタンポラン
(指揮)ピエール・ブーレーズ
<DISQUES〜MONTAIGNE NSC 1>
これ、再放送とで2回聞いたのだが、1回目は「メシアンだから何でもいいってわけではないんだな」と軽く失望していたが、2回目聞いたときは、「さすがメシアンは違う」と絶賛したくなった。1日経っただけなのに、この違い!聞く側の体調とか、環境とかで、こうも印象が違ってくるのか、とわれながらあきれた。
嶽本野ばら君の『タイマ』を読んだ。
大麻所持で逮捕されてからの復帰作。
あいかわらずの妄想小説で、健在ぶりを発揮していた。
「妄想小説」っていうのは、「幻想小説」とは意味合いが違っていて、作者の妄想によって小説のアクセルを踏んでいる作品のことで、今、僕が考えた。以前からきっと妄想を主食にして野ばら君は小説書いていたんだと思うけど、この本読んで急に僕がこう思った、っていうのは、本当なら隠しておくべきところを、手の内見せているというわけだ。これを、脇があまくなった、ととるか、新境地を開いた、ととるか。
野ばら君は書きたいものを書いているんだろうが、本当に書きたいものはまだ書いていないような気がしてならない。あるいは、もう本当に書きたいものは書いてしまっていて、次に書きたいものを手探りでさがしているのか。
「“鳥たちの深淵”〜“世の終わりのための四重奏曲”から」
メシアン作曲
(7分33秒)
(クラリネット)ポール・メイエ
<DENON COCO−78917>
「鳥の目覚め」 メシアン作曲
(21分40秒)
(ピアノ)イヴォンヌ・ロリオ
(管弦楽)チェコ・フィルハーモニー管弦楽団
(指揮)ヴァーツラ・ノイマン
<SUPRAPHON CO−4498>
「ステンドグラスと鳥たち」 メシアン作曲
(8分28秒)
「異国の鳥たち」 メシアン作曲
(15分26秒)
(ピアノ)イヴォンヌ・ロリオ
(管弦楽)アンサンブル・アンテルコンタンポラン
(指揮)ピエール・ブーレーズ
<DISQUES〜MONTAIGNE NSC 1>
これ、再放送とで2回聞いたのだが、1回目は「メシアンだから何でもいいってわけではないんだな」と軽く失望していたが、2回目聞いたときは、「さすがメシアンは違う」と絶賛したくなった。1日経っただけなのに、この違い!聞く側の体調とか、環境とかで、こうも印象が違ってくるのか、とわれながらあきれた。
嶽本野ばら君の『タイマ』を読んだ。
大麻所持で逮捕されてからの復帰作。
あいかわらずの妄想小説で、健在ぶりを発揮していた。
「妄想小説」っていうのは、「幻想小説」とは意味合いが違っていて、作者の妄想によって小説のアクセルを踏んでいる作品のことで、今、僕が考えた。以前からきっと妄想を主食にして野ばら君は小説書いていたんだと思うけど、この本読んで急に僕がこう思った、っていうのは、本当なら隠しておくべきところを、手の内見せているというわけだ。これを、脇があまくなった、ととるか、新境地を開いた、ととるか。
野ばら君は書きたいものを書いているんだろうが、本当に書きたいものはまだ書いていないような気がしてならない。あるいは、もう本当に書きたいものは書いてしまっていて、次に書きたいものを手探りでさがしているのか。
『1000の小説とバックベアード』、ウィッテン現代室内音楽祭2008ほか
2008年12月11日 読書将棋竜王戦第6局、今日こそは大盤解説会へ、と思ってたのに、BSの放送見てたら、午後4時過ぎに決着がついてしまった。(解説会は5時から)
これで3勝3敗になった。羽生乱調なのが気になるが、ドラマチックな7番勝負になった!
佐藤友哉の『1000の小説とバックベアード』を読んだ。
以下、目次
第1章 約1万4千冊の本たちから遠く離れて
第2章 ジャポニカ学習帳とトーカイグラフィック学習帳の交換
第3章 バックベアード
第4章 山の上ホテルでの『陵辱作業』(1)
第5章 山の上ホテルでの『陵辱作業』(2)
第6章 90年後の石川啄木
第7章 遅れてきた思春期・テスト・1000の小説・これよりはじまる
第8章 物語追放
第9章 地下
第10章 三つ巴
第1000章 死者たち
主人公の「僕」は片説家。片説家とは「簡単にいうと小説家みたいなものだが、本質はひどく違っている」どう違うかと言えば、片説家は依頼人に向けて物語を制作する職業なのだ。
また、「やみ」と呼ばれる、才能があるのに小説家にならず、執筆依頼を受けて書いた物語を金銭と交換する「犯罪集団」が暗躍。
依頼人がいて物語を書く、という構造は、その依頼の目的とあいまって、ストーリーはハードボイルドめいた展開をみせる。「女をさがせ」だ。
失踪した女性から自分は「日本文学」の秘密基地でくらしている、というメッセージが届いたり、「やみ」が「1000の小説」という計画を立ち上げて毒のある文章を世に流そうとしていると言ってみたり。
実際は、「1000の小説」の正体は、この世に存在する本物の小説1000冊のことであり、この1作は作者が小説を書く上での決意表明みたいなもので、「小説の国のアリス」なのだ。クライマックスはまるで「ニューシネマパラダイス」
NHK-FM今日の現代音楽はウィッテン。声を使った作品が多く、印象に残った。
− 海外の現代音楽 −(3)
〜ウィッテン現代室内音楽祭2008ほか〜
「始まり−エリオット・カーターの100歳の誕生日をたたえて」
ブライアン・ファーニホー作曲
(9分00秒)
(演奏)アルデッティ弦楽四重奏団
「6人の声のための音楽3」 ジェイ・シュワルツ作曲
(11分50秒)
(演奏)スコラ・ハイデルベルク
(指揮)ワルター・ヌスバウム
〜ドイツ・ウィッテン
ルドルフ・シュタイナー・シューレで収録〜
<2008/4/27>
(西部ドイツ放送協会提供)
▽タイム・オブ・ミュージック2007から
「ペトロール」 ジョルジュ・アペルギス作曲
(10分30秒)
「フアン・ゴイティソロの4つの引用」 マヌエル・イダルゴ作曲
(7分40秒)
(演奏)ノイエ・ヴォカリステン
〜フィンランド・ヴィッタサーリ教会で収録〜
<2007/7/7>
(フィンランド放送協会提供)
「彼女はといえば…、彼女は芸術」アディナ・ドゥミトレスク作曲
(8分40秒)
(演奏)アンサンブル・アレフ
〜フィンランド・ヴィッタサーリ パリスホールで収録〜
<2007/7/5>
(フィンランド放送協会提供)
▽アート・オブ・ザ・ステイツ No.121から
「コンポジション304(+91、151、164)」
アンソニー・ブラクストン
(11分20秒)
(サクソフォーン)アンソニー・ブラクストン
(コルネット、トロンボーン)テイラー・ホー・バイナム
(ラジオ・ボストン提供)
▽ユネスコ国際作曲家会議から
「交響曲 第2番」 パヴェウ・ミキエティン作曲
(24分10秒)
(管弦楽)ポーランド放送交響楽団
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
〜ポーランド・ワルシャワ
ナショナル・フィルハーモニック・コンサートホールで収録〜
<2007/9/21>
(ポーランド・ラジオ提供)
*ファーニホーはイギリス生まれ。「始まり」は40の断片からなる作品。
*シュワルツは1965年アメリカ生まれで90年代にドイツに移って活動。
「6人の声のための音楽3」は2008年の作品、エンマ・ハウクがハイデルベルクの精神病院から夫にあてて出した手紙をテクストにしている。(解読不能)
http://www.psychiatrie-erfahrene.de/eigensinn/museumneu/seiteemmahauck.htm
*アペルギスはギリシア生まれ、フランスで活動。本人は画家でもあり、音楽に演劇的要素を盛り込む作風。
「ペトロール」はアールブリュットのアドルフ・ベルフリの作品タイトル。ベルフリの作品の精神分裂的イメージ、その奇妙さ、多様さを作品化している。「ペトロール」も造語で、何を意味しているのやら。
*イダルゴは1953年スペイン生まれ、ドイツでヘルムート・ラッヘンマンの影響を強く受ける。
「フアン・ゴイティソロの4つの引用」は1990年の作品。スペインの実験小説作家ゴイティソロの作品から、作中に引用されたテクストを歌詞にしている。その4つの引用はそれぞれ、イブンハヅムの『鳩の首飾り』(10世紀)、アルフォンゾ・ジュッセの『日記』(13世紀)、ルソーの『孤独な散歩者の夢想』(18世紀)、フローベールの『ブバールとペキシェ』(19世紀)
*ドゥミトレスクは40歳くらいの女性作曲家、詳細不明。
*ブラクストンは1945年生まれ。ジャズと現代音楽の融合に特徴がある。
「コンポジション304(+91、151、164)」は過去の作品と即興のコラージュ作品。
*ミキエティンは第3世代の1人で、過去の音楽様式を自由に使う、典型的なポストモダン作曲家と評されている。
「交響曲 第2番」は2007年作品。ミキエティンによると、本作には2つのクライマックスがあり、黄金比率で全体の中に割り振られている。お互いに関係のない素材が独立で発展していくが、メビウスの環の裏表のように全体として1つの音楽になっている、と。
これで3勝3敗になった。羽生乱調なのが気になるが、ドラマチックな7番勝負になった!
佐藤友哉の『1000の小説とバックベアード』を読んだ。
以下、目次
第1章 約1万4千冊の本たちから遠く離れて
第2章 ジャポニカ学習帳とトーカイグラフィック学習帳の交換
第3章 バックベアード
第4章 山の上ホテルでの『陵辱作業』(1)
第5章 山の上ホテルでの『陵辱作業』(2)
第6章 90年後の石川啄木
第7章 遅れてきた思春期・テスト・1000の小説・これよりはじまる
第8章 物語追放
第9章 地下
第10章 三つ巴
第1000章 死者たち
主人公の「僕」は片説家。片説家とは「簡単にいうと小説家みたいなものだが、本質はひどく違っている」どう違うかと言えば、片説家は依頼人に向けて物語を制作する職業なのだ。
また、「やみ」と呼ばれる、才能があるのに小説家にならず、執筆依頼を受けて書いた物語を金銭と交換する「犯罪集団」が暗躍。
依頼人がいて物語を書く、という構造は、その依頼の目的とあいまって、ストーリーはハードボイルドめいた展開をみせる。「女をさがせ」だ。
失踪した女性から自分は「日本文学」の秘密基地でくらしている、というメッセージが届いたり、「やみ」が「1000の小説」という計画を立ち上げて毒のある文章を世に流そうとしていると言ってみたり。
実際は、「1000の小説」の正体は、この世に存在する本物の小説1000冊のことであり、この1作は作者が小説を書く上での決意表明みたいなもので、「小説の国のアリス」なのだ。クライマックスはまるで「ニューシネマパラダイス」
NHK-FM今日の現代音楽はウィッテン。声を使った作品が多く、印象に残った。
− 海外の現代音楽 −(3)
〜ウィッテン現代室内音楽祭2008ほか〜
「始まり−エリオット・カーターの100歳の誕生日をたたえて」
ブライアン・ファーニホー作曲
(9分00秒)
(演奏)アルデッティ弦楽四重奏団
「6人の声のための音楽3」 ジェイ・シュワルツ作曲
(11分50秒)
(演奏)スコラ・ハイデルベルク
(指揮)ワルター・ヌスバウム
〜ドイツ・ウィッテン
ルドルフ・シュタイナー・シューレで収録〜
<2008/4/27>
(西部ドイツ放送協会提供)
▽タイム・オブ・ミュージック2007から
「ペトロール」 ジョルジュ・アペルギス作曲
(10分30秒)
「フアン・ゴイティソロの4つの引用」 マヌエル・イダルゴ作曲
(7分40秒)
(演奏)ノイエ・ヴォカリステン
〜フィンランド・ヴィッタサーリ教会で収録〜
<2007/7/7>
(フィンランド放送協会提供)
「彼女はといえば…、彼女は芸術」アディナ・ドゥミトレスク作曲
(8分40秒)
(演奏)アンサンブル・アレフ
〜フィンランド・ヴィッタサーリ パリスホールで収録〜
<2007/7/5>
(フィンランド放送協会提供)
▽アート・オブ・ザ・ステイツ No.121から
「コンポジション304(+91、151、164)」
アンソニー・ブラクストン
(11分20秒)
(サクソフォーン)アンソニー・ブラクストン
(コルネット、トロンボーン)テイラー・ホー・バイナム
(ラジオ・ボストン提供)
▽ユネスコ国際作曲家会議から
「交響曲 第2番」 パヴェウ・ミキエティン作曲
(24分10秒)
(管弦楽)ポーランド放送交響楽団
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
〜ポーランド・ワルシャワ
ナショナル・フィルハーモニック・コンサートホールで収録〜
<2007/9/21>
(ポーランド・ラジオ提供)
*ファーニホーはイギリス生まれ。「始まり」は40の断片からなる作品。
*シュワルツは1965年アメリカ生まれで90年代にドイツに移って活動。
「6人の声のための音楽3」は2008年の作品、エンマ・ハウクがハイデルベルクの精神病院から夫にあてて出した手紙をテクストにしている。(解読不能)
http://www.psychiatrie-erfahrene.de/eigensinn/museumneu/seiteemmahauck.htm
*アペルギスはギリシア生まれ、フランスで活動。本人は画家でもあり、音楽に演劇的要素を盛り込む作風。
「ペトロール」はアールブリュットのアドルフ・ベルフリの作品タイトル。ベルフリの作品の精神分裂的イメージ、その奇妙さ、多様さを作品化している。「ペトロール」も造語で、何を意味しているのやら。
*イダルゴは1953年スペイン生まれ、ドイツでヘルムート・ラッヘンマンの影響を強く受ける。
「フアン・ゴイティソロの4つの引用」は1990年の作品。スペインの実験小説作家ゴイティソロの作品から、作中に引用されたテクストを歌詞にしている。その4つの引用はそれぞれ、イブンハヅムの『鳩の首飾り』(10世紀)、アルフォンゾ・ジュッセの『日記』(13世紀)、ルソーの『孤独な散歩者の夢想』(18世紀)、フローベールの『ブバールとペキシェ』(19世紀)
*ドゥミトレスクは40歳くらいの女性作曲家、詳細不明。
*ブラクストンは1945年生まれ。ジャズと現代音楽の融合に特徴がある。
「コンポジション304(+91、151、164)」は過去の作品と即興のコラージュ作品。
*ミキエティンは第3世代の1人で、過去の音楽様式を自由に使う、典型的なポストモダン作曲家と評されている。
「交響曲 第2番」は2007年作品。ミキエティンによると、本作には2つのクライマックスがあり、黄金比率で全体の中に割り振られている。お互いに関係のない素材が独立で発展していくが、メビウスの環の裏表のように全体として1つの音楽になっている、と。
『リアルのゆくえ』、東京行進曲、ドナウエッシンゲン現代音楽祭2007
2008年12月10日 読書大塚英志+東浩紀の『リアルのゆくえ おたく/オタクはどう生きるか』を読んだ。
以下、目次。
はじめにー世代間闘争について
第1章 2001年−消費の変容
なぜ物語に耐えられないのか
見えない権力システム
誰が作り手か分からない
権力とマーケティングの境界が曖昧に
決定的な世代の違い
「主人と奴隷」の問題
戦後まんが史に見る記号と身体
サブカルチャーの歴史化
第2章 2002年−言論の変容
雑誌は誰でも作れる
論壇誌でいかに語るか
暴走するセキュリティ化
自由のツケをどう考えるのか
非人称化する「権力」を批判する言葉はあるのか
工学化する社会
『ほしのこえ』と「ブロッコリー」
作家性はデータベースを超えるのか
すべてがバーコードなわけじゃない
動物化する言語環境
新しいリアルと新現実
データベース式物語の果てに
第3章 2007年ーおたく/オタクは公的になれるか
メタ化するか、空気を読むか
啓蒙か、ガス抜きか
富の再配分の方法
批評家に責任はあるか
公共性について
富の再配分と教育
国歌とGoogleの公共性
公共性か、システムか
批評家であることとネットの関係
イデオロギー切断と新しい座標軸
変化する知識人の役割
次の社会には何が残るか
言葉は希望か、それとも無力か
終章 2008年−秋葉原事件のあとで
同時代の事件に責任を持つ
彼らは何に怒っているか
サブカルチャーの実存的機能
あとがき 東浩紀
タイトルにある「おたく」と「オタク」の表記の違いは、次のとおり。
大塚「ぼくにとって『おたく』は、ひらがなです。宮崎勤を含むからね。岡田が東大で『オタク』って言葉を使った時点で、『宮崎の問題は置いといて』とされてしまった」
これは世代の問題としてとらえられ、多くの場面で世代の差を中心軸にして討論が開始する。
たとえば、東のこんな発言。
東「大塚さんにとってネットはオプションかもしれないけど、ぼくにとってはそうではないですから。そのダメージが身体的に感覚できるかどうかは、やっぱり世代的なものがあると思います」
さて、この本は後半がほとんど口げんかになっている。
東がたまらず「この議論は続けても仕方ないんじゃないかな。今、大塚さんはぼくの人格を批判しているので、それはやめたほうがよろしいんじゃないかと」なんて言いはじめる。これがまた何回か繰り返される。
ルールあってこそ格闘技は面白いので、喧嘩はあんまり面白くない。気持ちも荒むし。
秋葉原事件後の語り下ろしで、東は同時代の事件に責任を持つ、という表明をしている。
秋葉原事件は正社員と派遣といったレベルの問題でなく、世代間闘争だったのだ、というスタンスは、たしか超左翼マガジン『ロスジェネ』別冊2008「秋葉原無差別テロ事件『敵』は誰だったのか?」でも言ってたかな。
溝口健二監督の「東京行進曲」を見た。1929年、無声映画。
原作は雑誌「キング」連載。
「トテシャンだね」なんて言い方は、近代的ななかにも和風調がある。
NHK-FMの現代音楽番組、第二夜。
近藤 譲
− 海外の現代音楽 −(2)
〜ドナウエッシンゲン現代音楽祭2007ほか〜
「ゴヤ1−私は見た」 ヘルムート・エーリング作曲
(22分40秒)
「平和とは何か?−心の理由に向かって」クラウス・フーバー作曲
(22分50秒)
(ソプラノ)アンヌ・マリー・ジャカン
(メゾ・ソプラノ)ルシー・ラコスト
(カウンター・テノール)セバスティアン・アマデュー
(テノール)フベルト・マイア
(バス)アラン・リエ
(パーカッション)ノラ・ティーレ
(管弦楽)バーデンバーデン・フライブルクSWR交響楽団
(指揮)ルパート・フーバー
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン
バール・シュポルトハレで収録〜
<2007/10/19>
(東西ドイツ放送協会提供)
「ロゴス−断片」 ハンス・ツェンダー作曲
(33分20秒)
(合唱)シュツットガルトSWR声楽アンサンブル
(管弦楽)バーデンバーデン・フライブルクSWR交響楽団
(指揮)シルヴァン・カンブルラン
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン
バール・シュポルトハレで収録〜
<2007/10/21>
(東西ドイツ放送協会提供)
▽ユネスコ国際作曲家会議から
「すてきなチョコレート店」 マイケ・ナス作曲
(4分40秒)
(演奏)ニェーウ・アンサンブル
(指揮)ルーカス・フィス
〜オランダ・スヘルト・ヘンボス
フェルカーデファブリクで収録〜
<2007/11/7>
(オランダ公共放送提供)
*エーリングは1961年生まれ、東ベルリンで音楽を独学。
ゴヤのエッチング集『戦争の惨禍』44枚目の「私は見た」を音楽化したのが本作。ゴヤの「私は見た」はナポレオン戦争下でのスペインの市民の悲劇が描かれている。音楽的には、ゴヤの同時代人であるベートーベンからの引用もある。
*フーバーは1924年スイスの生まれ。キリスト教神秘主義に基づいたメッセージ色強い作品を作っている。
「心の理由に向かって」は2007年の作品で、タイトルはデリダのレクチャーから取ったそうだ。歌詞はオクタビオ・パスとジャック・デリダのテクストを使用している。
*ツェンダーは1936年生まれ、ドイツの作曲家で、指揮者としても有名。
「ロゴス−断片」では古代グノーシス主義のテクストが使われている。今回演奏されたものは「1、ヨハネの福音書」「6、トマスの福音書(ナグハマディ文書)」「5、ヴァレンチヌスのテクスト」
以下、目次。
はじめにー世代間闘争について
第1章 2001年−消費の変容
なぜ物語に耐えられないのか
見えない権力システム
誰が作り手か分からない
権力とマーケティングの境界が曖昧に
決定的な世代の違い
「主人と奴隷」の問題
戦後まんが史に見る記号と身体
サブカルチャーの歴史化
第2章 2002年−言論の変容
雑誌は誰でも作れる
論壇誌でいかに語るか
暴走するセキュリティ化
自由のツケをどう考えるのか
非人称化する「権力」を批判する言葉はあるのか
工学化する社会
『ほしのこえ』と「ブロッコリー」
作家性はデータベースを超えるのか
すべてがバーコードなわけじゃない
動物化する言語環境
新しいリアルと新現実
データベース式物語の果てに
第3章 2007年ーおたく/オタクは公的になれるか
メタ化するか、空気を読むか
啓蒙か、ガス抜きか
富の再配分の方法
批評家に責任はあるか
公共性について
富の再配分と教育
国歌とGoogleの公共性
公共性か、システムか
批評家であることとネットの関係
イデオロギー切断と新しい座標軸
変化する知識人の役割
次の社会には何が残るか
言葉は希望か、それとも無力か
終章 2008年−秋葉原事件のあとで
同時代の事件に責任を持つ
彼らは何に怒っているか
サブカルチャーの実存的機能
あとがき 東浩紀
タイトルにある「おたく」と「オタク」の表記の違いは、次のとおり。
大塚「ぼくにとって『おたく』は、ひらがなです。宮崎勤を含むからね。岡田が東大で『オタク』って言葉を使った時点で、『宮崎の問題は置いといて』とされてしまった」
これは世代の問題としてとらえられ、多くの場面で世代の差を中心軸にして討論が開始する。
たとえば、東のこんな発言。
東「大塚さんにとってネットはオプションかもしれないけど、ぼくにとってはそうではないですから。そのダメージが身体的に感覚できるかどうかは、やっぱり世代的なものがあると思います」
さて、この本は後半がほとんど口げんかになっている。
東がたまらず「この議論は続けても仕方ないんじゃないかな。今、大塚さんはぼくの人格を批判しているので、それはやめたほうがよろしいんじゃないかと」なんて言いはじめる。これがまた何回か繰り返される。
ルールあってこそ格闘技は面白いので、喧嘩はあんまり面白くない。気持ちも荒むし。
秋葉原事件後の語り下ろしで、東は同時代の事件に責任を持つ、という表明をしている。
秋葉原事件は正社員と派遣といったレベルの問題でなく、世代間闘争だったのだ、というスタンスは、たしか超左翼マガジン『ロスジェネ』別冊2008「秋葉原無差別テロ事件『敵』は誰だったのか?」でも言ってたかな。
溝口健二監督の「東京行進曲」を見た。1929年、無声映画。
原作は雑誌「キング」連載。
「トテシャンだね」なんて言い方は、近代的ななかにも和風調がある。
NHK-FMの現代音楽番組、第二夜。
近藤 譲
− 海外の現代音楽 −(2)
〜ドナウエッシンゲン現代音楽祭2007ほか〜
「ゴヤ1−私は見た」 ヘルムート・エーリング作曲
(22分40秒)
「平和とは何か?−心の理由に向かって」クラウス・フーバー作曲
(22分50秒)
(ソプラノ)アンヌ・マリー・ジャカン
(メゾ・ソプラノ)ルシー・ラコスト
(カウンター・テノール)セバスティアン・アマデュー
(テノール)フベルト・マイア
(バス)アラン・リエ
(パーカッション)ノラ・ティーレ
(管弦楽)バーデンバーデン・フライブルクSWR交響楽団
(指揮)ルパート・フーバー
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン
バール・シュポルトハレで収録〜
<2007/10/19>
(東西ドイツ放送協会提供)
「ロゴス−断片」 ハンス・ツェンダー作曲
(33分20秒)
(合唱)シュツットガルトSWR声楽アンサンブル
(管弦楽)バーデンバーデン・フライブルクSWR交響楽団
(指揮)シルヴァン・カンブルラン
〜ドイツ・ドナウエッシンゲン
バール・シュポルトハレで収録〜
<2007/10/21>
(東西ドイツ放送協会提供)
▽ユネスコ国際作曲家会議から
「すてきなチョコレート店」 マイケ・ナス作曲
(4分40秒)
(演奏)ニェーウ・アンサンブル
(指揮)ルーカス・フィス
〜オランダ・スヘルト・ヘンボス
フェルカーデファブリクで収録〜
<2007/11/7>
(オランダ公共放送提供)
*エーリングは1961年生まれ、東ベルリンで音楽を独学。
ゴヤのエッチング集『戦争の惨禍』44枚目の「私は見た」を音楽化したのが本作。ゴヤの「私は見た」はナポレオン戦争下でのスペインの市民の悲劇が描かれている。音楽的には、ゴヤの同時代人であるベートーベンからの引用もある。
*フーバーは1924年スイスの生まれ。キリスト教神秘主義に基づいたメッセージ色強い作品を作っている。
「心の理由に向かって」は2007年の作品で、タイトルはデリダのレクチャーから取ったそうだ。歌詞はオクタビオ・パスとジャック・デリダのテクストを使用している。
*ツェンダーは1936年生まれ、ドイツの作曲家で、指揮者としても有名。
「ロゴス−断片」では古代グノーシス主義のテクストが使われている。今回演奏されたものは「1、ヨハネの福音書」「6、トマスの福音書(ナグハマディ文書)」「5、ヴァレンチヌスのテクスト」