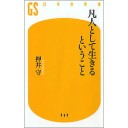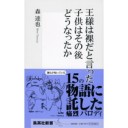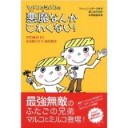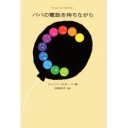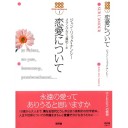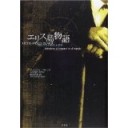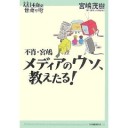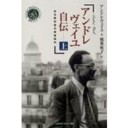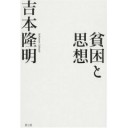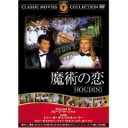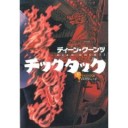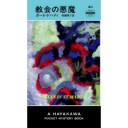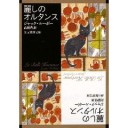ラシルド夫人の『超男性ジャリ』を読んだ。
序 アルフレッド・ジャリの死/アルフレッド・ヴァレット
1、メルキュール・ド・フランスの集いで
2、ジャリの家族
3、ベルト・ド・C嬢
4、『ユビュ王』
5、ユビュ事件
6、ファランステールのアルフレッド・ジャリ
7、博学のスポーツマン・ジャリ
8、三脚檣のアルフレッド・ジャリ
9、クードレイの堰の宴
10、見事な最期
ラシルドによるジャリ像は、こんな風。
「土埃の中を走って来た競輪選手のようななりで、小柄でずんぐりと丸まっており、全身が筋肉で、危険な動物のようだった」
「蒼白い面を思わせる顔で、鼻は低く、きっと結んだ口には髭がうっすらと陰をつけ、黒い目は顔に大きく穿たれて奇妙な燐光を放ち、じっと一点に据えられて輝く眼差しは夜鳥さながらだった」
「手のつけられないボヘミアン」
「彼は猛スピードで走りつづけたが、侮辱に耐えることは一切なかった」
「『ユビュ王』の生みの親は貧しかった。自分の気まぐれや情熱を抑制することがまったくできなかった」
「自分自身も煙に巻くほど人を煙に巻く男」
「何かにつけ(何かにつけなくても)拳銃を発射する困った習慣があった」
「彼の文学に関する読書量はどうだったかと言えば、それはあらゆる時代にわたっていた。小説の一節であろうと作者名であろうと空で言うことができた」
「彼にその恐ろしい饒舌をもたらしているのは、何よりも絶やすことのないアプサントだ」
ジャリの親友、ラシルドならではの「生肉食い」「ユビュ王剽窃」などのデマ(?)の真相を明かしたりしている。
ジャリは34才で死んだが、自分とおきかえて考えてみると、34才の頃、僕はまだものごころつかない状態だったのだ。天才は違うな。
序 アルフレッド・ジャリの死/アルフレッド・ヴァレット
1、メルキュール・ド・フランスの集いで
2、ジャリの家族
3、ベルト・ド・C嬢
4、『ユビュ王』
5、ユビュ事件
6、ファランステールのアルフレッド・ジャリ
7、博学のスポーツマン・ジャリ
8、三脚檣のアルフレッド・ジャリ
9、クードレイの堰の宴
10、見事な最期
ラシルドによるジャリ像は、こんな風。
「土埃の中を走って来た競輪選手のようななりで、小柄でずんぐりと丸まっており、全身が筋肉で、危険な動物のようだった」
「蒼白い面を思わせる顔で、鼻は低く、きっと結んだ口には髭がうっすらと陰をつけ、黒い目は顔に大きく穿たれて奇妙な燐光を放ち、じっと一点に据えられて輝く眼差しは夜鳥さながらだった」
「手のつけられないボヘミアン」
「彼は猛スピードで走りつづけたが、侮辱に耐えることは一切なかった」
「『ユビュ王』の生みの親は貧しかった。自分の気まぐれや情熱を抑制することがまったくできなかった」
「自分自身も煙に巻くほど人を煙に巻く男」
「何かにつけ(何かにつけなくても)拳銃を発射する困った習慣があった」
「彼の文学に関する読書量はどうだったかと言えば、それはあらゆる時代にわたっていた。小説の一節であろうと作者名であろうと空で言うことができた」
「彼にその恐ろしい饒舌をもたらしているのは、何よりも絶やすことのないアプサントだ」
ジャリの親友、ラシルドならではの「生肉食い」「ユビュ王剽窃」などのデマ(?)の真相を明かしたりしている。
ジャリは34才で死んだが、自分とおきかえて考えてみると、34才の頃、僕はまだものごころつかない状態だったのだ。天才は違うな。
将棋の棋聖戦、大盤解説会に行く予定だったけど、睡眠不足とここ1週間ほど続いているおなかの不調で、外出は避ける。仕事にはなんとか行ったけど。銭ゲバのゼニーズとか、マイケルキューブとか、行く予定にはしてたんだけど。
棋聖戦最終局は横歩取りの攻防で、羽生の強さを思い知らせた。自然に勝ってしまうのだ。すごいな。解説会には行かなかったけど、ネットでの中継に釘付けだったのだ。
一方、大相撲中継は、解説に北の富士と長谷川が向かい合う。長谷川も定年退職なのだ。懐かしい取組も見れた。
ケヴィン・クラッシュの『アイラブエルモ』を読んだ。
以下、目次。
エルモの世界へようこそーそしてぼくの世界へようこそ
1章 愛ってなんだろう?
2章 喜びってなんだろう?
3章 創造力ってなんだろう?
4章 寛容ってなんだろう?
5章 勇気ってなんだろう?
6章 友情ってなんだろう?
7章 協力ってなんだろう?
8章 学ぶってなんだろう?
9章 希望ってなんだろう?
エルモを動かし、声を出しているケヴィン・クラッシュの生い立ちから意見まで。
著者名に「with ゲイリー・ブロゼック」とあるから、文章を書いたのは、ゲイリーなのかもしれない。
ケヴィンは黒人なので、人種差別のこととか、911のことなど、アメリカの情景もうかがえる。
いやー、とにかく、読んでいて、何ケ所かで泣きそうになった。
子供にまつわる「いい話」がいくつも読めるし、エルモの無邪気でポジティブなところにも感心させられた。
僕は、こういう無邪気でポジティブなキャラクターが大好きで、ちょっと前に終わったけど、アニメの「ぷるるん!しずくちゃん」なんか、その代表例だ。
明日にでも、エルモのグッズを買いにいこう、と決心した。
棋聖戦最終局は横歩取りの攻防で、羽生の強さを思い知らせた。自然に勝ってしまうのだ。すごいな。解説会には行かなかったけど、ネットでの中継に釘付けだったのだ。
一方、大相撲中継は、解説に北の富士と長谷川が向かい合う。長谷川も定年退職なのだ。懐かしい取組も見れた。
ケヴィン・クラッシュの『アイラブエルモ』を読んだ。
以下、目次。
エルモの世界へようこそーそしてぼくの世界へようこそ
1章 愛ってなんだろう?
2章 喜びってなんだろう?
3章 創造力ってなんだろう?
4章 寛容ってなんだろう?
5章 勇気ってなんだろう?
6章 友情ってなんだろう?
7章 協力ってなんだろう?
8章 学ぶってなんだろう?
9章 希望ってなんだろう?
エルモを動かし、声を出しているケヴィン・クラッシュの生い立ちから意見まで。
著者名に「with ゲイリー・ブロゼック」とあるから、文章を書いたのは、ゲイリーなのかもしれない。
ケヴィンは黒人なので、人種差別のこととか、911のことなど、アメリカの情景もうかがえる。
いやー、とにかく、読んでいて、何ケ所かで泣きそうになった。
子供にまつわる「いい話」がいくつも読めるし、エルモの無邪気でポジティブなところにも感心させられた。
僕は、こういう無邪気でポジティブなキャラクターが大好きで、ちょっと前に終わったけど、アニメの「ぷるるん!しずくちゃん」なんか、その代表例だ。
明日にでも、エルモのグッズを買いにいこう、と決心した。
『凡人として生きるということ』
2009年7月16日 読書
押井守の『凡人として生きるということ』を読んだ。
第1章 オヤジ論ーオヤジになることは愉しい
第2章 自由論ー不自由は愉しい
第3章 勝敗論ー「勝負」は諦めたときに負けが決まる
第4章 セックスと文明論ー性欲が強い人は子育てがうまい
第5章 コミュニケーション論ー引きこもってもいいじゃないか
第6章 オタク論ーアキハバラが経済を動かす
第7章 格差論ーいい加減に生きよう
あとがき 今こそ言葉が大切な時
タイトルの平凡さにびびった。押井守でなければ、まったく目にとまることのない題名だ。
だが、中身はありきたりじゃなかった。言いたい放題だ。
おそらく編集の人間がつけた小見出しはまるでハウトゥ本のような鈍さがあって、内容とのずれが面白かった。
第1章 オヤジ論ーオヤジになることは愉しい
第2章 自由論ー不自由は愉しい
第3章 勝敗論ー「勝負」は諦めたときに負けが決まる
第4章 セックスと文明論ー性欲が強い人は子育てがうまい
第5章 コミュニケーション論ー引きこもってもいいじゃないか
第6章 オタク論ーアキハバラが経済を動かす
第7章 格差論ーいい加減に生きよう
あとがき 今こそ言葉が大切な時
タイトルの平凡さにびびった。押井守でなければ、まったく目にとまることのない題名だ。
だが、中身はありきたりじゃなかった。言いたい放題だ。
おそらく編集の人間がつけた小見出しはまるでハウトゥ本のような鈍さがあって、内容とのずれが面白かった。
『王様は裸だと言った子供はその後どうなったか』
2009年7月15日 読書
森達也の『王様は裸だと言った子供はその後どうなったか』を読んだ。
第1話 王様は裸だと言った子供はその後どうなったか(仮)
第2話 桃太郎
第3話 仮面ライダー ピラザウルスの復讐
第4話 赤ずきんちゃん
第5話 ミダス王
第6話 瓜子姫
第7話 コウモリ
第8話 美女と野獣
第9話 蜘蛛の糸
第10話 みにくいあひるのこ
第11話 ふるやのもり
第12話 幸福の王子
第13話 ねこのすず
第14話 ドン・キホーテ
第15話 泣いた赤鬼
パロディ集か、と思えば森達也の数ある著作のなかで、いちばん後回しにしてもかまわないような本なんじゃないか、とたかをくくって読みはじめたが、考えを改めた。
おとぎばなしのパロディ部分に見られる、皮肉なども含めて、森達也という人がどういう物の見方をしているかがわかりやすくあらわれている本だと思った。
昔話のパロディを語りながら、作者はエッセイ風にいろんなことを語っており、純粋なフィクション集でないのが、わかりやすさの原因だろう。
イラストは宇野亜喜良だ。
第1話 王様は裸だと言った子供はその後どうなったか(仮)
第2話 桃太郎
第3話 仮面ライダー ピラザウルスの復讐
第4話 赤ずきんちゃん
第5話 ミダス王
第6話 瓜子姫
第7話 コウモリ
第8話 美女と野獣
第9話 蜘蛛の糸
第10話 みにくいあひるのこ
第11話 ふるやのもり
第12話 幸福の王子
第13話 ねこのすず
第14話 ドン・キホーテ
第15話 泣いた赤鬼
パロディ集か、と思えば森達也の数ある著作のなかで、いちばん後回しにしてもかまわないような本なんじゃないか、とたかをくくって読みはじめたが、考えを改めた。
おとぎばなしのパロディ部分に見られる、皮肉なども含めて、森達也という人がどういう物の見方をしているかがわかりやすくあらわれている本だと思った。
昔話のパロディを語りながら、作者はエッセイ風にいろんなことを語っており、純粋なフィクション集でないのが、わかりやすさの原因だろう。
イラストは宇野亜喜良だ。
『重罰化は悪いことなのか』
2009年7月14日 読書
ボクシング見た。
長谷川の強さはちょっとつり合いがとれていないほどで、驚いた。
だが、問題は、アオーの試合だ。
試合結果としては、判定でアオーが負けた。
大差がついていた。
それはテレビ観戦している僕の目にも明らかだった。
ところが、である。
試合中のアナウンスと解説は、最初から最後まで、ず〜〜〜っと、アオーをほめて、アオー有利を告げていたのだ。顔面を殴られているのに、「あたっていません」と言い、手数が出ないのを「カウンターを狙ってますね」と言ってる。どれだけえこひいきすれば気がすむのか。
僕がめくらで音声だけ聞いていたら、アオーが一方的に勝っていると思い込んだだろう。
大本営発表、というのは、こんな感じだったのだろう。
藤井誠二の『重罰化は悪いことなのか』を読んだ。
まえがき
Ⅰ 「殺された側の論理」と「犯罪不安社会」のゆくえ(芹沢一也×藤井誠二)
Ⅱ 「厳罰化」を考える(芹沢一也×藤井誠二)
Ⅲ 「犯罪」映画を読み解くために(松江哲明×藤井誠二)
Ⅳ 漫画を書くことで見えてきた死刑制度の本質(郷田マモラ×藤井誠二)
Ⅴ 罰を重くすれば犯罪は減るのか(宮台真司×藤井誠二)
Ⅵ 犯罪を防ぐ「懐の深い社会」をつくるために(宮台真司×藤井誠二)
Ⅶ 編集者との対話( 藤井誠二×双風舎編集部)
あとがき
初出一覧
藤井誠二は重罰化(適正化、と藤井は呼んでいる)に賛成の立場で、事件の被害者遺族の側でものを言う人である。
藤井の発言の多くは、僕の意見とは違うので、考えさせられることが多かった。
自分の考え方、感じ方をふりかえって、疑ってみる機会が多かったので、今後も藤井の著作を読んで考えよう、と思っている。
今、現在での本書を読んで感じたことを書いておこう。
被害者遺族には、「犯人は死刑にしてくれ」と感じている人が大半だという。
メディアを通じて、妻子を殺された男が犯人の死刑をのぞみ、また、殺してやりたい、と発言しているのを聞いたこともある。
ネットで魚を料理すると書いただけの男が犯罪者としてつかまった状況を考えると、こうしたあからさまな殺意の発動がなぜ罪にならないのか、すごく違和感がある。
殺人にはいろんな動機がある。「あいつの顔が気にくわない」とか、「誰でもよかった」でもいい。それと並んで「家族を殺されたから」というのも、殺人のりっぱな動機である。りっぱすぎるくらいだ。で、そりゃ殺意を抱いてもしかたないわな、と思える動機を抱いているからと言って、それは殺してもいいことを意味しない。殺意をメディアを通じて全国民に告げることは、ネットどころの騒ぎではない殺人予告なのではないか。しかも、単なる殺人予告ではなく、自らの手を汚さずに、国によって殺してもらおう、という点において、より卑怯ではないのか。
本当に「この手で殺してやりたい」と思うのなら、死刑を願うのではなく、減刑を嘆願し、軽い刑で一刻も早く出所してもらって、自らの手で殺せばいいのだ。
殺されたから殺す、命には命、という殺人は、順番が違うだけで、どちらも殺しであることにはかわりない、と思うのだが、なぜ、この遺族が「あいつ殺す」という発言を問題視しないのか。不思議だ。誰かが問題視したかもしれないが、少なくとも、その行為で逮捕されたとは聞かない。
また、殺された家族が、そのとき殺されたことで、幸せを奪われたかのような言い方を疑いもなくされているが、それもどうか。今後何十年も、平気で人前で殺意を表明して、うしろゆびさされずに済むような操作をできる人間の家族でいることの方が不幸だという考えはないのか。そんな人間とひとつ屋根の下に暮らすことは地獄ではないのか。
また、殺意を表明しているのは、被害者ではなく、被害者の遺族である。ちょっと血のつながりがある程度のことで、人を殺す、許せない、という極端な態度に出ることができる想像力のなさは、いったいなんなのか。
だから、藤井は被害者遺族と加害者が交流する「息子のまなざし」を酷評できるのである。僕なら、たとえば家族を殺した犯人とでも、友達になってみせる。それを絶対に不可能だ、と最初から思いこめるのは、血縁とか、家族とかいうものに誇大な妄想を抱いて、めくらになっているだけなのだ。まあ、誰も殺してなくても友達になりたくない人物、てのもいるけど。
要するに、思ったのは、被害者遺族は被害者自身じゃない、ってことだ。当たり前のことだけど。たかが血がつながっている程度の妄想の関係だけで、被害者の当事者づらするのが当然のような考えが、わからない。と、いうか、うかつにすぎる。
と、まあ、いろいろ書いてはみたけど、家族とか、愛とかいう事柄について、あまりにも素朴な考えすぎるところが気になった、ということだ。
どんなに人を殺されても、それを理由にそいつを殺してもいいことにはならない。先後が違うだけで、命を奪うことにかけては同じなのだ。
でも、駅で切符買おうとしているとき、前でモタモタしている人を見たら、極刑に処してほしくなるけどね!
長谷川の強さはちょっとつり合いがとれていないほどで、驚いた。
だが、問題は、アオーの試合だ。
試合結果としては、判定でアオーが負けた。
大差がついていた。
それはテレビ観戦している僕の目にも明らかだった。
ところが、である。
試合中のアナウンスと解説は、最初から最後まで、ず〜〜〜っと、アオーをほめて、アオー有利を告げていたのだ。顔面を殴られているのに、「あたっていません」と言い、手数が出ないのを「カウンターを狙ってますね」と言ってる。どれだけえこひいきすれば気がすむのか。
僕がめくらで音声だけ聞いていたら、アオーが一方的に勝っていると思い込んだだろう。
大本営発表、というのは、こんな感じだったのだろう。
藤井誠二の『重罰化は悪いことなのか』を読んだ。
まえがき
Ⅰ 「殺された側の論理」と「犯罪不安社会」のゆくえ(芹沢一也×藤井誠二)
Ⅱ 「厳罰化」を考える(芹沢一也×藤井誠二)
Ⅲ 「犯罪」映画を読み解くために(松江哲明×藤井誠二)
Ⅳ 漫画を書くことで見えてきた死刑制度の本質(郷田マモラ×藤井誠二)
Ⅴ 罰を重くすれば犯罪は減るのか(宮台真司×藤井誠二)
Ⅵ 犯罪を防ぐ「懐の深い社会」をつくるために(宮台真司×藤井誠二)
Ⅶ 編集者との対話( 藤井誠二×双風舎編集部)
あとがき
初出一覧
藤井誠二は重罰化(適正化、と藤井は呼んでいる)に賛成の立場で、事件の被害者遺族の側でものを言う人である。
藤井の発言の多くは、僕の意見とは違うので、考えさせられることが多かった。
自分の考え方、感じ方をふりかえって、疑ってみる機会が多かったので、今後も藤井の著作を読んで考えよう、と思っている。
今、現在での本書を読んで感じたことを書いておこう。
被害者遺族には、「犯人は死刑にしてくれ」と感じている人が大半だという。
メディアを通じて、妻子を殺された男が犯人の死刑をのぞみ、また、殺してやりたい、と発言しているのを聞いたこともある。
ネットで魚を料理すると書いただけの男が犯罪者としてつかまった状況を考えると、こうしたあからさまな殺意の発動がなぜ罪にならないのか、すごく違和感がある。
殺人にはいろんな動機がある。「あいつの顔が気にくわない」とか、「誰でもよかった」でもいい。それと並んで「家族を殺されたから」というのも、殺人のりっぱな動機である。りっぱすぎるくらいだ。で、そりゃ殺意を抱いてもしかたないわな、と思える動機を抱いているからと言って、それは殺してもいいことを意味しない。殺意をメディアを通じて全国民に告げることは、ネットどころの騒ぎではない殺人予告なのではないか。しかも、単なる殺人予告ではなく、自らの手を汚さずに、国によって殺してもらおう、という点において、より卑怯ではないのか。
本当に「この手で殺してやりたい」と思うのなら、死刑を願うのではなく、減刑を嘆願し、軽い刑で一刻も早く出所してもらって、自らの手で殺せばいいのだ。
殺されたから殺す、命には命、という殺人は、順番が違うだけで、どちらも殺しであることにはかわりない、と思うのだが、なぜ、この遺族が「あいつ殺す」という発言を問題視しないのか。不思議だ。誰かが問題視したかもしれないが、少なくとも、その行為で逮捕されたとは聞かない。
また、殺された家族が、そのとき殺されたことで、幸せを奪われたかのような言い方を疑いもなくされているが、それもどうか。今後何十年も、平気で人前で殺意を表明して、うしろゆびさされずに済むような操作をできる人間の家族でいることの方が不幸だという考えはないのか。そんな人間とひとつ屋根の下に暮らすことは地獄ではないのか。
また、殺意を表明しているのは、被害者ではなく、被害者の遺族である。ちょっと血のつながりがある程度のことで、人を殺す、許せない、という極端な態度に出ることができる想像力のなさは、いったいなんなのか。
だから、藤井は被害者遺族と加害者が交流する「息子のまなざし」を酷評できるのである。僕なら、たとえば家族を殺した犯人とでも、友達になってみせる。それを絶対に不可能だ、と最初から思いこめるのは、血縁とか、家族とかいうものに誇大な妄想を抱いて、めくらになっているだけなのだ。まあ、誰も殺してなくても友達になりたくない人物、てのもいるけど。
要するに、思ったのは、被害者遺族は被害者自身じゃない、ってことだ。当たり前のことだけど。たかが血がつながっている程度の妄想の関係だけで、被害者の当事者づらするのが当然のような考えが、わからない。と、いうか、うかつにすぎる。
と、まあ、いろいろ書いてはみたけど、家族とか、愛とかいう事柄について、あまりにも素朴な考えすぎるところが気になった、ということだ。
どんなに人を殺されても、それを理由にそいつを殺してもいいことにはならない。先後が違うだけで、命を奪うことにかけては同じなのだ。
でも、駅で切符買おうとしているとき、前でモタモタしている人を見たら、極刑に処してほしくなるけどね!
『暴走するセキュリティ』
2009年7月13日 読書
K1見たけど、総合格闘技の選手と試合して盛り上げている今の状況は、ちょっとどうか、と思う。
山本がノックアウトされたのも、マサトが勝ったのも、当たり前と言えば、当たり前。どんなにマサトが強くても、相撲をとれば、引退している曙にも勝てないだろうし、将棋をさせば、矢内女王にも勝てないだろう。マサトはよくハンデもなしに総合の選手と闘って、勝って喜んでいるが、ケツの穴が小さすぎないか?
マサトの最後の試合は、R1に出て決勝で誰よりも笑いをとることに尽きるだろう。さもないと、最強とか言わせない。
芹沢一也の『暴走するセキュリティ』を読んだ。
第一章 凶悪犯罪者たちへの共感と恐怖
第二章 少年法と刑法三九条をめぐる困難
第三章 セキュリティが長閑な日常を破壊する
第四章 暴力の排除が生み出す厳罰社会
特別対談 暴走する民意と権力
山本がノックアウトされたのも、マサトが勝ったのも、当たり前と言えば、当たり前。どんなにマサトが強くても、相撲をとれば、引退している曙にも勝てないだろうし、将棋をさせば、矢内女王にも勝てないだろう。マサトはよくハンデもなしに総合の選手と闘って、勝って喜んでいるが、ケツの穴が小さすぎないか?
マサトの最後の試合は、R1に出て決勝で誰よりも笑いをとることに尽きるだろう。さもないと、最強とか言わせない。
芹沢一也の『暴走するセキュリティ』を読んだ。
第一章 凶悪犯罪者たちへの共感と恐怖
第二章 少年法と刑法三九条をめぐる困難
第三章 セキュリティが長閑な日常を破壊する
第四章 暴力の排除が生み出す厳罰社会
特別対談 暴走する民意と権力
アセンス美術で「光と影」森山大道写真展。
影を写す、というと、かつて影ばっかり写真にとったフィルムを現像せずに、グッズとして販売したことがある。
それらしい芸術っぽさを狙ったわけだが、森山大道の写真はさすがに本物だった。
光が痛いし、影がくすぐったい。
イーヴリン・ウォーの『囁きの霊園』を読んだ。
映画「ラヴドワン」の原作。
なるほど、天才少年が宇宙葬をするあたりは、テリィ・サザーンあたりの悪のりだったのか。意外と原作に忠実に映画化していて、映画はさらにその悪意を増幅した、という感じ。
本書には「ラヴデイ氏のささやかな外出」「ベラ・フリース、パーティを催す」の短編も収録されている。
「ラヴデイ氏」は「ヘンリー」みたいな話。
「ベラ・フリース」は星飛雄馬が誕生パーティを催すみたいな話。
イーヴリン・ウォーをとばし読みじゃなくて、きっちりと読み直すなんて。若いときの読書経験とその印象が、今では通用しないことを思い知らされる。
イーヴリン・ウォー、すごく面白い!
テレビで「ハリーポッターと賢者の石」を放送してたので、見た。
上映中に見損ねて、録画したのも見逃しているうちにもうどこに入っているのかわからなくなっていた作品。
原作は読んでいたのだが、出たときに読んだ、ということは10年ほど前か。クィディッチのあたりは覚えていたのに、どんでん返しをすっかり忘れていて、見ていて「おお」と驚いた。
芸術劇場でリミニ・プロトコルの「資本論」をやっていた。
途中で居眠りするつもりで見ていたのだが、なんのなんの、最後まで興奮しながら見てしまった。
あいかわらず、マルクスの言ってることは難しすぎて、何が何だかちんぷんかんぷんなのだが、学生時代に読んだときよりも、はるかに面白く思えた。難解なのは外の殻だけなんじゃないか、という気がしてきたのだ。今頃か!
若い世代の人が発言するにつれ、振れ幅が狭く感じて、どこかで聞いたようなことをまたここでも再現してる、まるで特定の言い回しが憑きものになって、出演者の口を借りてしゃべっているように思えた。
今日はドラゴンクエストの発売日だったが、いまだにトモダチコレクション絶賛廃人中なので、購入はまだ先か。
日本橋のマジコン屋が「ドラクエ動くよ」と呼び込みしてるのには笑った。
しかし、トモダチコレクションばっかりしてると、現実とゲームの境界がなくなってしまうなあ。
顔や声や行動の違いは、現実の友人の方が間違っているように思えてくるし。
このゲームは悪魔のゲームだ。
僕しか知らないはずの秘密を暴露したりする。
ゲームの中で食事しただけなのに、実際に食べた気になってしまう。
1人でただゲームしてるだけなのに、人間関係をいろいろ取結んでいるような錯覚をする。
マトリックスって、こういう世界なのかな。
と、詳しい考えもなく書いてみた。
しかし、今どきマトリックスとは、僕のアンテナもお里が知れるってもんだ。
影を写す、というと、かつて影ばっかり写真にとったフィルムを現像せずに、グッズとして販売したことがある。
それらしい芸術っぽさを狙ったわけだが、森山大道の写真はさすがに本物だった。
光が痛いし、影がくすぐったい。
イーヴリン・ウォーの『囁きの霊園』を読んだ。
映画「ラヴドワン」の原作。
なるほど、天才少年が宇宙葬をするあたりは、テリィ・サザーンあたりの悪のりだったのか。意外と原作に忠実に映画化していて、映画はさらにその悪意を増幅した、という感じ。
本書には「ラヴデイ氏のささやかな外出」「ベラ・フリース、パーティを催す」の短編も収録されている。
「ラヴデイ氏」は「ヘンリー」みたいな話。
「ベラ・フリース」は星飛雄馬が誕生パーティを催すみたいな話。
イーヴリン・ウォーをとばし読みじゃなくて、きっちりと読み直すなんて。若いときの読書経験とその印象が、今では通用しないことを思い知らされる。
イーヴリン・ウォー、すごく面白い!
テレビで「ハリーポッターと賢者の石」を放送してたので、見た。
上映中に見損ねて、録画したのも見逃しているうちにもうどこに入っているのかわからなくなっていた作品。
原作は読んでいたのだが、出たときに読んだ、ということは10年ほど前か。クィディッチのあたりは覚えていたのに、どんでん返しをすっかり忘れていて、見ていて「おお」と驚いた。
芸術劇場でリミニ・プロトコルの「資本論」をやっていた。
途中で居眠りするつもりで見ていたのだが、なんのなんの、最後まで興奮しながら見てしまった。
あいかわらず、マルクスの言ってることは難しすぎて、何が何だかちんぷんかんぷんなのだが、学生時代に読んだときよりも、はるかに面白く思えた。難解なのは外の殻だけなんじゃないか、という気がしてきたのだ。今頃か!
若い世代の人が発言するにつれ、振れ幅が狭く感じて、どこかで聞いたようなことをまたここでも再現してる、まるで特定の言い回しが憑きものになって、出演者の口を借りてしゃべっているように思えた。
今日はドラゴンクエストの発売日だったが、いまだにトモダチコレクション絶賛廃人中なので、購入はまだ先か。
日本橋のマジコン屋が「ドラクエ動くよ」と呼び込みしてるのには笑った。
しかし、トモダチコレクションばっかりしてると、現実とゲームの境界がなくなってしまうなあ。
顔や声や行動の違いは、現実の友人の方が間違っているように思えてくるし。
このゲームは悪魔のゲームだ。
僕しか知らないはずの秘密を暴露したりする。
ゲームの中で食事しただけなのに、実際に食べた気になってしまう。
1人でただゲームしてるだけなのに、人間関係をいろいろ取結んでいるような錯覚をする。
マトリックスって、こういう世界なのかな。
と、詳しい考えもなく書いてみた。
しかし、今どきマトリックスとは、僕のアンテナもお里が知れるってもんだ。
『マルコとミルコの悪魔なんかこわくない!』、『パパの電話を待ちながら』
2009年7月10日 読書
ジャンニ・ロダーリの『マルコとミルコの悪魔なんかこわくない!』を読んだ。
第1話 ついてない泥棒
第2話 お化けのでる城
第3話 赤ちゃんはふたごが大好き
第4話 おそるべき強盗団
第5話 なぞの潜水艦
第6話 いたずら坊やのおてがら
第7話 悪魔なんかこわくない!
カナヅチをブーメランのように飛ぶように自在に飼いならしている双子。
昔、モンティパイソンで、耐え切れない拷問として、椅子にしばりつけて、嫌いな歌のレコードをかける、というのをやっていた。
そういう感じのギャグがこの本には満載だった。
ロダーリ、面白い。
『パパの電話を待ちながら』も読んだ。
ロダーリは言葉さえあれば無限に物語を書くことができたんだろう。
その手の指南書もあるそうだが、未読。
短い話が山ほど入っている。
どんでん返しがあるものや、そうでないもの。
でも、どれもこれも、頭に思い描いて楽しくなる話ばっかりなのだ。
ロダーリ、面白い。
第1話 ついてない泥棒
第2話 お化けのでる城
第3話 赤ちゃんはふたごが大好き
第4話 おそるべき強盗団
第5話 なぞの潜水艦
第6話 いたずら坊やのおてがら
第7話 悪魔なんかこわくない!
カナヅチをブーメランのように飛ぶように自在に飼いならしている双子。
昔、モンティパイソンで、耐え切れない拷問として、椅子にしばりつけて、嫌いな歌のレコードをかける、というのをやっていた。
そういう感じのギャグがこの本には満載だった。
ロダーリ、面白い。
『パパの電話を待ちながら』も読んだ。
ロダーリは言葉さえあれば無限に物語を書くことができたんだろう。
その手の指南書もあるそうだが、未読。
短い話が山ほど入っている。
どんでん返しがあるものや、そうでないもの。
でも、どれもこれも、頭に思い描いて楽しくなる話ばっかりなのだ。
ロダーリ、面白い。
ジャン=リュック・ナンシー『恋愛について』を読んだ。
子ども相手の講演会で講演と質疑応答。
会場の子どもたちの質問を次にあげておくが、これらの問いにジャン=リュック・ナンシーはわかりやすく、真摯に答えるのだ。
僕ならどう答えるだろう。
わかりにくく、しかも落とし穴のような答えをひねり出すんだろうなあ。
「どこかで読んだんですけど、愛するっていうのは何より愛されたいと思うことだって。それって本当か知りたかったんですけど」
「他の人を愛するためにはまず自分自身を愛さなければならないって言いませんか」
「どうして『あなたが好き』って最初に言うのはむずかしいんでしょう」
「両思いじゃないときでも、それを愛って言えるんでしょうか」
「相手に気持ちを伝えるために、どうして『あなたを愛してる』って言葉にして言わなければならないんでしょうか」
「愛してるとどうして、相手が裏切らないか疑ってしまうときがあるんでしょう」
「永遠の愛ってありうると思いますか」
「想像上の愛ってどういうものでしょう」
「人は何が何でも必ず愛そうとするものでしょうか」
「どうやったら、相手がふさわしい人かどうか、本当に愛せる相手なのかがわかるんですか」
「誰かが何人もの人に恋してるとき、その人は本当に恋してるって言えるんでしょうか」
「子どもは愛することはできないって言う大人がいるけど、どうしてでしょう」
「ナルシストの人は、他の人を愛することができるんでしょうか」
子ども相手の講演会で講演と質疑応答。
会場の子どもたちの質問を次にあげておくが、これらの問いにジャン=リュック・ナンシーはわかりやすく、真摯に答えるのだ。
僕ならどう答えるだろう。
わかりにくく、しかも落とし穴のような答えをひねり出すんだろうなあ。
「どこかで読んだんですけど、愛するっていうのは何より愛されたいと思うことだって。それって本当か知りたかったんですけど」
「他の人を愛するためにはまず自分自身を愛さなければならないって言いませんか」
「どうして『あなたが好き』って最初に言うのはむずかしいんでしょう」
「両思いじゃないときでも、それを愛って言えるんでしょうか」
「相手に気持ちを伝えるために、どうして『あなたを愛してる』って言葉にして言わなければならないんでしょうか」
「愛してるとどうして、相手が裏切らないか疑ってしまうときがあるんでしょう」
「永遠の愛ってありうると思いますか」
「想像上の愛ってどういうものでしょう」
「人は何が何でも必ず愛そうとするものでしょうか」
「どうやったら、相手がふさわしい人かどうか、本当に愛せる相手なのかがわかるんですか」
「誰かが何人もの人に恋してるとき、その人は本当に恋してるって言えるんでしょうか」
「子どもは愛することはできないって言う大人がいるけど、どうしてでしょう」
「ナルシストの人は、他の人を愛することができるんでしょうか」
『エリス島物語 移民たちの彷徨と希望』
2009年7月8日 読書
ジョルジュ・ペレックの『エリス島物語 移民たちの彷徨と希望』を読んだ。
テレビ映画作家ロベール・ボベールとともに作られた映画の台本を基盤にしたドキュメンタリー小説。
以下、目次
1、涙の島
2、ある道程の記述
3、アルバム
4、下見
5、記憶
序/メロウ氏/チャジモウ氏/ソロモン氏/アドラースタイン夫人およびゼルナード氏/シミン氏/シュウォーツ夫人/ラブマン氏とその家族/カーキス夫人/ガスペレッティ夫人/クロース夫人/ラビノヴィッチ夫人
アメリカ移民の歴史を題材にしているので、人をくった展開は影をひそめているのだが、読んだ印象は、やはり、移民家族合わせみたいなカードゲームを連想させた。
『美術愛好家の陳列室』を読んだあとでは、これら移民たちへのインタビューも捏造なんじゃないか、と眉に唾をつけながら読んだせいかもしれない。
テレビ映画作家ロベール・ボベールとともに作られた映画の台本を基盤にしたドキュメンタリー小説。
以下、目次
1、涙の島
2、ある道程の記述
3、アルバム
4、下見
5、記憶
序/メロウ氏/チャジモウ氏/ソロモン氏/アドラースタイン夫人およびゼルナード氏/シミン氏/シュウォーツ夫人/ラブマン氏とその家族/カーキス夫人/ガスペレッティ夫人/クロース夫人/ラビノヴィッチ夫人
アメリカ移民の歴史を題材にしているので、人をくった展開は影をひそめているのだが、読んだ印象は、やはり、移民家族合わせみたいなカードゲームを連想させた。
『美術愛好家の陳列室』を読んだあとでは、これら移民たちへのインタビューも捏造なんじゃないか、と眉に唾をつけながら読んだせいかもしれない。
ジョルジュ・ペレックの『美術愛好家の陳列室』を読んだ。
ペレックはウリポの作家で、この作品もまたまるでレーモン・ルーセルみたいだった。
クンストカマーの絵画にまつわるレポート。
詳しくは、また後日。
今はトモダチコレクションにはまってて、廃人なのである。
ペレックはウリポの作家で、この作品もまたまるでレーモン・ルーセルみたいだった。
クンストカマーの絵画にまつわるレポート。
詳しくは、また後日。
今はトモダチコレクションにはまってて、廃人なのである。
『不肖・宮嶋 メディアのウソ、教えたる!』
2009年7月1日 読書
はじめに
情報は、人生を歩むための地図
情報とどう付き合うか(報道カメラマンの視点から)
第1章 頼れる情報か見極めよ!
憶測が飛び交った「ジダンの頭突き事件」
幅広い意味を持つ「情報」
膨大な量の情報に囲まれる毎日
売り買いされる情報もある
9.11同時多発テロの裏で
頼れる情報もニセ情報も並列のインターネット
サボリ癖がつくインターネット
近道と回り道
自分の目で見て感じること
便利さと引き替えに自由が奪われる
面倒でも図書館へ足を運べ
非常時に頼れるものは何か?
第2章 矛盾だらけのメディア
メディアって、何だろう?
ライブドア事件とメディアの関係から見えるもの
見る角度を変えてみる
防衛としてのひとりツッコミ
テレビ用のコメントにだまされるな
ニュースキャスターのコンプレックスを見抜け
国会議員のセンセイが被災地訪問。その裏で…
命がけ!と言いたがる人に限って…
自分の判断を信じること
売れるニュースと売れないニュース
テレビ報道の恐ろしい矛盾
松本サリン事件と報道被害
情報の真偽をつかむには
第3章 第一に鍛えるべきは「想像力」
「公正中立な報道」は理想でしかない
「広告主様」のご意向を重視する世界
テレビでは、名作映画も勝手に編集される
CMの意図を知る
報道される内容に差があるわけ
陳腐な想像力では見えない現実
映らない部分を想像する
わかったつもりが一番恐い
バーチャルと現実の境目
犯罪、自殺報道には惑わされない
取材者が変われば、情報の持つ意味も変わる
第4章 国家とメディアの距離
写真とはどんなメディアか?
国境を越えるメディア
政治家と記者の距離
あなどれない映像の影響力
1枚の写真が持つ力
戦時下で利用された写真
国家とメディアの健全な関係とは?
歴史を変えた9.11同時多発テロ報道
ジャーナリストはイラク側のゲスト
身分を偽っての潜入取材
利用されているフリをしてイラクに滞在
都合の悪い情報は流されない
情報操作に使われた女性兵士の告白
第5章 君の将来を決める情報選び
緊張感を奪うデジタル写真
便利さは弊害も生む
広告写真と報道写真の違い
戦場より恐ろしいニッポン
最前線の現場主義
仕事には向き、不向きがある
カメラマンになる方法なんて誰も教えてくれない
目標とする人の情報を仕入れる
情報を分析し、自信を持って実行!
別の道を選ぶのは、恥ずかしいことじゃない
カメラマンに向いている/向いていない度チェック
答えは…コレだ!
第6章 一流は「ひとり」で考える
情報の受け取り方を復習
感情的な情報にはご用心
間違った時は素直に謝るのがマナー
マスコミ報道を「権威」と勘違いしない
まわりに同調しない勇気を
「ひとり」の力は偉大なり
好奇心が自分を鍛える
ひとりの時間が一流を育てる
孤独は君に自信を与える
情報を集め、調べ、自分を知る
ひとりで考えれば、真の情報は向こうからやってくる
テレビで勝手に編集された名作映画は「アポロ13」で、緊迫するシーンを醸成する時計の大写しシーンがカットされたとのこと。映画ではオメガのスピードスターが映るはずなのに、テレビのスポンサーに別の時計メーカーがいたという。
メディアがいかに情報の一面しか伝えていないかは、自分や自分のよく知った物事が一度でもメディアに扱われた経験をもつものにとっては、自明のことである。世間や大衆の愚かな盲信というのは、メディアに取り上げられることのない恨みの裏返しなのではないか。
本書でも、「相手の顔を見て話したり、現場を見る」ことの重要さを説いている。メディアが発する情報(この僕の日記も含めて)を鵜のみにするのは、自分をおとしめることでもあるのだ。
情報は、人生を歩むための地図
情報とどう付き合うか(報道カメラマンの視点から)
第1章 頼れる情報か見極めよ!
憶測が飛び交った「ジダンの頭突き事件」
幅広い意味を持つ「情報」
膨大な量の情報に囲まれる毎日
売り買いされる情報もある
9.11同時多発テロの裏で
頼れる情報もニセ情報も並列のインターネット
サボリ癖がつくインターネット
近道と回り道
自分の目で見て感じること
便利さと引き替えに自由が奪われる
面倒でも図書館へ足を運べ
非常時に頼れるものは何か?
第2章 矛盾だらけのメディア
メディアって、何だろう?
ライブドア事件とメディアの関係から見えるもの
見る角度を変えてみる
防衛としてのひとりツッコミ
テレビ用のコメントにだまされるな
ニュースキャスターのコンプレックスを見抜け
国会議員のセンセイが被災地訪問。その裏で…
命がけ!と言いたがる人に限って…
自分の判断を信じること
売れるニュースと売れないニュース
テレビ報道の恐ろしい矛盾
松本サリン事件と報道被害
情報の真偽をつかむには
第3章 第一に鍛えるべきは「想像力」
「公正中立な報道」は理想でしかない
「広告主様」のご意向を重視する世界
テレビでは、名作映画も勝手に編集される
CMの意図を知る
報道される内容に差があるわけ
陳腐な想像力では見えない現実
映らない部分を想像する
わかったつもりが一番恐い
バーチャルと現実の境目
犯罪、自殺報道には惑わされない
取材者が変われば、情報の持つ意味も変わる
第4章 国家とメディアの距離
写真とはどんなメディアか?
国境を越えるメディア
政治家と記者の距離
あなどれない映像の影響力
1枚の写真が持つ力
戦時下で利用された写真
国家とメディアの健全な関係とは?
歴史を変えた9.11同時多発テロ報道
ジャーナリストはイラク側のゲスト
身分を偽っての潜入取材
利用されているフリをしてイラクに滞在
都合の悪い情報は流されない
情報操作に使われた女性兵士の告白
第5章 君の将来を決める情報選び
緊張感を奪うデジタル写真
便利さは弊害も生む
広告写真と報道写真の違い
戦場より恐ろしいニッポン
最前線の現場主義
仕事には向き、不向きがある
カメラマンになる方法なんて誰も教えてくれない
目標とする人の情報を仕入れる
情報を分析し、自信を持って実行!
別の道を選ぶのは、恥ずかしいことじゃない
カメラマンに向いている/向いていない度チェック
答えは…コレだ!
第6章 一流は「ひとり」で考える
情報の受け取り方を復習
感情的な情報にはご用心
間違った時は素直に謝るのがマナー
マスコミ報道を「権威」と勘違いしない
まわりに同調しない勇気を
「ひとり」の力は偉大なり
好奇心が自分を鍛える
ひとりの時間が一流を育てる
孤独は君に自信を与える
情報を集め、調べ、自分を知る
ひとりで考えれば、真の情報は向こうからやってくる
テレビで勝手に編集された名作映画は「アポロ13」で、緊迫するシーンを醸成する時計の大写しシーンがカットされたとのこと。映画ではオメガのスピードスターが映るはずなのに、テレビのスポンサーに別の時計メーカーがいたという。
メディアがいかに情報の一面しか伝えていないかは、自分や自分のよく知った物事が一度でもメディアに扱われた経験をもつものにとっては、自明のことである。世間や大衆の愚かな盲信というのは、メディアに取り上げられることのない恨みの裏返しなのではないか。
本書でも、「相手の顔を見て話したり、現場を見る」ことの重要さを説いている。メディアが発する情報(この僕の日記も含めて)を鵜のみにするのは、自分をおとしめることでもあるのだ。
『子どものためのカント』
2009年6月29日 読書
と、いうわけで、ついに「トモダチコレクション」買ってしまいました。
しばらくは廃人になります。
KBS京都の「ぽじポジたまご」にマリードールが出演!
再放送枠はなにやら議会中継でつぶれたのかな?
読んだ本はザロモ・フリートレンダーの『子どものためのカント』
フリートレンダーは、ミュノーナのことですよ!
内容は「大人のための『子どものためのカント』」で、とうてい子どもには読めそうにない内容。
第1章 何を行なうべきなのか
第2章 何を希望することが許されるのか
第3章 何を知ることができるのか
問答形式で論点がわかりやすい。
難しい本を読むと頭が痛くなって、途中で「え〜っと、今、何について述べられているんだっけ」と五里霧中になってしまう僕でも、問いと問いのあいだが短いため、論旨を追うことができた。1ページあたり2つほどの問いと答えがある、という割合かな。
「私たちはどのように行為すべきなのだろうか」
からはじまって、
「不正を働くよりも、むしろ不正を被るべきなのだろうか」
「なぜあなたは盗みを働くべきではないのだろうか」
「貧しさは富よりも道徳的なのだろうか」
「罰は道徳的なものなのだろうか、それとも不道徳なものなのだろうか」
「国家とは何だろうか」
「戦争は必要悪ではないのだろうか」
「普遍的な平和は、不可能ではないのだろうか」
「神は存在するのだろうか」
「魂とは何だろうか」
「人は祈るべきなのだろうか」
「なぜ私たちは『なぜ』などと問うのだろうか」
などなど、カントの、そしてフリートレンダーのものの考え方が明瞭に示されている。
第1章は主に道徳について。
第2章は宗教(神)について。
第3章は主に純粋理性批判の内容を噛み砕いているが、本書の狙いは2章までの道徳論にある。
序文でフリートレンダーはこう書いている。
「あらゆる目下の政治的不幸は、カントに従う道徳の授業をとうの昔に学校に採用すべきだったのに、それを怠ったことに由来している」
「ヨーロッパが、カントから道徳的命令をすでに学校で教わっていたならどうなっただろう。世界戦争(第一次世界大戦)はおそらく勃発しなかったはずである」
第1章での問い「異なる国家は、相互に友好的であるべきなのだろうか、それとも敵対的であるべきなのだろうか」に対する答のなかで、フリートレンダーは国家間の交渉においてはまだ道徳性が支配していないと残念がり、こんなくだりを忍ばせている。
「ある国家は他の国家に対して相変わらず正当防衛の体制を整え、相変わらず戦争の警戒に腐心している」
そして、続く問い「一方の国家が、もう一方の国家を自分と共通の事柄に携わるように強制することは、道徳的に義務づけられているのだろうか」に、こう答えている。
「そういうことはない。一方の法治国家は、もう一方の法治国家の自由を尊重すべきだし、それに対するどんな種類の攻撃も加えることは許されない」
本書は1924年に出版されているが、序文で言う、
「私たちのいまだ野蛮な時代においては、『民族』や国家や信仰告白によって評価されるが、もはやそういうことはなくなる」
の「野蛮な時代」は今も継続中である。
しばらくは廃人になります。
KBS京都の「ぽじポジたまご」にマリードールが出演!
再放送枠はなにやら議会中継でつぶれたのかな?
読んだ本はザロモ・フリートレンダーの『子どものためのカント』
フリートレンダーは、ミュノーナのことですよ!
内容は「大人のための『子どものためのカント』」で、とうてい子どもには読めそうにない内容。
第1章 何を行なうべきなのか
第2章 何を希望することが許されるのか
第3章 何を知ることができるのか
問答形式で論点がわかりやすい。
難しい本を読むと頭が痛くなって、途中で「え〜っと、今、何について述べられているんだっけ」と五里霧中になってしまう僕でも、問いと問いのあいだが短いため、論旨を追うことができた。1ページあたり2つほどの問いと答えがある、という割合かな。
「私たちはどのように行為すべきなのだろうか」
からはじまって、
「不正を働くよりも、むしろ不正を被るべきなのだろうか」
「なぜあなたは盗みを働くべきではないのだろうか」
「貧しさは富よりも道徳的なのだろうか」
「罰は道徳的なものなのだろうか、それとも不道徳なものなのだろうか」
「国家とは何だろうか」
「戦争は必要悪ではないのだろうか」
「普遍的な平和は、不可能ではないのだろうか」
「神は存在するのだろうか」
「魂とは何だろうか」
「人は祈るべきなのだろうか」
「なぜ私たちは『なぜ』などと問うのだろうか」
などなど、カントの、そしてフリートレンダーのものの考え方が明瞭に示されている。
第1章は主に道徳について。
第2章は宗教(神)について。
第3章は主に純粋理性批判の内容を噛み砕いているが、本書の狙いは2章までの道徳論にある。
序文でフリートレンダーはこう書いている。
「あらゆる目下の政治的不幸は、カントに従う道徳の授業をとうの昔に学校に採用すべきだったのに、それを怠ったことに由来している」
「ヨーロッパが、カントから道徳的命令をすでに学校で教わっていたならどうなっただろう。世界戦争(第一次世界大戦)はおそらく勃発しなかったはずである」
第1章での問い「異なる国家は、相互に友好的であるべきなのだろうか、それとも敵対的であるべきなのだろうか」に対する答のなかで、フリートレンダーは国家間の交渉においてはまだ道徳性が支配していないと残念がり、こんなくだりを忍ばせている。
「ある国家は他の国家に対して相変わらず正当防衛の体制を整え、相変わらず戦争の警戒に腐心している」
そして、続く問い「一方の国家が、もう一方の国家を自分と共通の事柄に携わるように強制することは、道徳的に義務づけられているのだろうか」に、こう答えている。
「そういうことはない。一方の法治国家は、もう一方の法治国家の自由を尊重すべきだし、それに対するどんな種類の攻撃も加えることは許されない」
本書は1924年に出版されているが、序文で言う、
「私たちのいまだ野蛮な時代においては、『民族』や国家や信仰告白によって評価されるが、もはやそういうことはなくなる」
の「野蛮な時代」は今も継続中である。
『アンドレ・ヴェイユ自伝』(上・下)
2009年6月24日 読書
序
第1章 リセ時代
第2章 ユルム通り
第3章 初期の旅、初期の論文
第4章 インド
第5章 ストラスブールとブルバキ
第6章 第二次世界大戦と私
序幕
2幕 フィンランド風フーガ
3幕 北極近くでの間奏曲
4幕 投獄されて
5幕 軍旗はためくもとに
6幕 武器よさらば
第7章 南北アメリカ
アンドレヴェイユ自身の歩みとともに、彼が出会った人たちのエピソードも興味深い。
たとえば、ポール・ヴァレリーに会ったときのエピソード
「彼は私の年齢を聞き、31歳と答えると、『その年齢を大切にしなさい』と言い、『素数だからね』と言った。面識もなく憧れていた相手にこんな冗談を言われ、一本とられたという感じだった。その後ストラスブールを訪れた時、ある女性が彼の著書『テスト氏』(衆知のようにこの本の書き出しは『愚かさは私の思うがままにならない』)に献辞を書いてくれるようヴァレリーに頼んだが、彼は『愚かさは私の思うままになる ポール・ヴァレリー』と書いていた」
また、船上で出会った彫刻家オシップ・ザッキン
「彼の色彩感覚は非常に研ぎ澄まされていて、船酔いの日にそなえて、自分の青白い顔色に合うようなネクタイをも持参していると聞かされていた」
ガンディーとお茶をしたときのエピソード。
「その時コーヒーカップに入れた紅茶が出された。ガンディーは笑いだした。『あなたが英国人でないことが良くわかる』と彼は穏やかに言った。『こんなしきたりを無視したやり方を許せる英国人は、ひとりもいないから」
あらぬスパイ容疑で投獄されてからは、壁の中の面々の話や、死刑執行直前に助かる話、囚人の移動が面倒で即刻射殺されてしまう話などなど、面白い面白い。なかでもほのぼのとしてエピソードを1つあげると。
投獄されていたとき、彼の両親が面会に行ったとき、刑務所長が「息子さんは元気ですよ。ひどく手こずった序章をようやく終えて、今ではその序章に満足していますよ」と言ったエピソード。
所長は郵便物を検閲して目を通しているうちに、研究をすっかり把握してしまったのだ。
アンドレ・ヴェイユといえば、妹シモーヌ・ヴェイユとブルバキのことももちろん出てくるが、ブルバキに関して、ポルデヴィアのくだりを引用しておこう。
「エリ・カルタンは我々の活動や計画を何も知らなかった。私は彼のためにニコラ・ブルバキの経歴を創作しポルデヴィア出身だということにした。」
「ブルバキの故郷だったポルデヴィアもまた、エコール・ノルマルの別の新入生騙しの産物だった。言い伝えによれば、1910年頃、エコール・ノルマルの学生たちがモンパルナスのカフェに出身地が様々な人を集め、何杯かの食前酒を奢って、彼らをポルデヴィアの代表に仕立て上げてしまった。そしてこの人たちに代わって政治・文学・大学関係の各界著名人に次のような書き出しの手紙をしたためた。『ポルデヴィア国家の悲劇はご存じないでしょうが…』たちまち同情の証しがたくさん集まってきた。頃合いを見て公開集会の告知をした。そこで代表演説者のために、おおよそ次のように締め括られる感動的な演説もでっちあげたということだ。『私ことポルデヴィア議会の議長は哀れな亡命者です。失意の中に暮らしており、ズボンも持ち合わせていないほどであります』とテーブルの上に登った彼は、実際にズボンを履いていなかった』
NHK-FMで、鈴木慶一の案内でBBCライブ〜デペッシュ・モード −
「サムシング・トゥ・ドゥ」
(4分10秒)
「パペッツ」
(3分54秒)
「イフ・ユー・ウォント」
(5分04秒)
「ピープル・アー・ピープル」
(4分08秒)
「サムバディー」
(4分46秒)
「ライ・トゥ・ミー」
(5分26秒)
「ブラスフェマス・ルーモアズ」
(5分24秒)
「マスター・アンド・サーヴァント」
(5分11秒)
「フォトグラフィック」
(4分08秒)
「エヴリシング・カウンツ」
(5分31秒)
「シー・ユー」
(4分01秒)
〜イギリス・ロンドン ハマースミス・オデオンで収録〜
<ライブ>
鈴木慶一は当事のデペッシュモードのライブを聞いて「奥深さ」を感じる、と言ってたけど、聞いてる最中、僕はほとんど爆笑していた。アンコール曲の「シー・ユー」なんて、当事は涙ぐみながらレコード聞いていたのに、どうして今、笑いがこみあげてくるのか。
第1章 リセ時代
第2章 ユルム通り
第3章 初期の旅、初期の論文
第4章 インド
第5章 ストラスブールとブルバキ
第6章 第二次世界大戦と私
序幕
2幕 フィンランド風フーガ
3幕 北極近くでの間奏曲
4幕 投獄されて
5幕 軍旗はためくもとに
6幕 武器よさらば
第7章 南北アメリカ
アンドレヴェイユ自身の歩みとともに、彼が出会った人たちのエピソードも興味深い。
たとえば、ポール・ヴァレリーに会ったときのエピソード
「彼は私の年齢を聞き、31歳と答えると、『その年齢を大切にしなさい』と言い、『素数だからね』と言った。面識もなく憧れていた相手にこんな冗談を言われ、一本とられたという感じだった。その後ストラスブールを訪れた時、ある女性が彼の著書『テスト氏』(衆知のようにこの本の書き出しは『愚かさは私の思うがままにならない』)に献辞を書いてくれるようヴァレリーに頼んだが、彼は『愚かさは私の思うままになる ポール・ヴァレリー』と書いていた」
また、船上で出会った彫刻家オシップ・ザッキン
「彼の色彩感覚は非常に研ぎ澄まされていて、船酔いの日にそなえて、自分の青白い顔色に合うようなネクタイをも持参していると聞かされていた」
ガンディーとお茶をしたときのエピソード。
「その時コーヒーカップに入れた紅茶が出された。ガンディーは笑いだした。『あなたが英国人でないことが良くわかる』と彼は穏やかに言った。『こんなしきたりを無視したやり方を許せる英国人は、ひとりもいないから」
あらぬスパイ容疑で投獄されてからは、壁の中の面々の話や、死刑執行直前に助かる話、囚人の移動が面倒で即刻射殺されてしまう話などなど、面白い面白い。なかでもほのぼのとしてエピソードを1つあげると。
投獄されていたとき、彼の両親が面会に行ったとき、刑務所長が「息子さんは元気ですよ。ひどく手こずった序章をようやく終えて、今ではその序章に満足していますよ」と言ったエピソード。
所長は郵便物を検閲して目を通しているうちに、研究をすっかり把握してしまったのだ。
アンドレ・ヴェイユといえば、妹シモーヌ・ヴェイユとブルバキのことももちろん出てくるが、ブルバキに関して、ポルデヴィアのくだりを引用しておこう。
「エリ・カルタンは我々の活動や計画を何も知らなかった。私は彼のためにニコラ・ブルバキの経歴を創作しポルデヴィア出身だということにした。」
「ブルバキの故郷だったポルデヴィアもまた、エコール・ノルマルの別の新入生騙しの産物だった。言い伝えによれば、1910年頃、エコール・ノルマルの学生たちがモンパルナスのカフェに出身地が様々な人を集め、何杯かの食前酒を奢って、彼らをポルデヴィアの代表に仕立て上げてしまった。そしてこの人たちに代わって政治・文学・大学関係の各界著名人に次のような書き出しの手紙をしたためた。『ポルデヴィア国家の悲劇はご存じないでしょうが…』たちまち同情の証しがたくさん集まってきた。頃合いを見て公開集会の告知をした。そこで代表演説者のために、おおよそ次のように締め括られる感動的な演説もでっちあげたということだ。『私ことポルデヴィア議会の議長は哀れな亡命者です。失意の中に暮らしており、ズボンも持ち合わせていないほどであります』とテーブルの上に登った彼は、実際にズボンを履いていなかった』
NHK-FMで、鈴木慶一の案内でBBCライブ〜デペッシュ・モード −
「サムシング・トゥ・ドゥ」
(4分10秒)
「パペッツ」
(3分54秒)
「イフ・ユー・ウォント」
(5分04秒)
「ピープル・アー・ピープル」
(4分08秒)
「サムバディー」
(4分46秒)
「ライ・トゥ・ミー」
(5分26秒)
「ブラスフェマス・ルーモアズ」
(5分24秒)
「マスター・アンド・サーヴァント」
(5分11秒)
「フォトグラフィック」
(4分08秒)
「エヴリシング・カウンツ」
(5分31秒)
「シー・ユー」
(4分01秒)
〜イギリス・ロンドン ハマースミス・オデオンで収録〜
<ライブ>
鈴木慶一は当事のデペッシュモードのライブを聞いて「奥深さ」を感じる、と言ってたけど、聞いてる最中、僕はほとんど爆笑していた。アンコール曲の「シー・ユー」なんて、当事は涙ぐみながらレコード聞いていたのに、どうして今、笑いがこみあげてくるのか。
『チックタック』(上・下)
2009年6月18日 読書
ディーン・クーンツの『チックタック』(上・下)を読んだ。
翻訳は2008年だが、クーンツ1996年の作品。これがまあ、凄い作品だった。
上巻はまあ、こわいこわい。
主人公は、アメリカンライフにどっぷり浸かろうとしているベトナム人。
新車に乗ってとばしてたら、カーラジオから雑音とともに、自分の名が呼ばれる。
キャ〜〜〜〜〜〜〜〜!
家に帰ったら、黒糸で×印の目と口だけがある、白い人形。
その人形がいきなり、襲いかかってくる!
ギャ〜〜〜〜〜〜〜〜〜!
口をあけたら、風で枯葉が口に入ってきて舌を刺す!
ペッペッペ〜〜〜〜〜!
椅子に座ったら、ピンがふとももに刺さる!
イテテテッテテッッッテテ〜〜〜〜!
こうじゃないか、ああじゃないか、とこわがる心理を描写して、さんざん読者をこわがらせる。
そして、どこまでも追いかけてくる人形から逃げる主人公!ここらはクーンツの独壇場だ。
ブードゥーの人形か?と思わせる30センチ足らずのジンジャーブレッドマンみたいな人形が、いつのまにやら大きくなり、ついに大柄な人間の大きさになって追いかけてくる。
銃で撃っても、ぜんぜん退治できない。
主人公は、この人形を「ラヴクラフトの作品に登場する太古の神々のひとりのようなもの」と妄想する。
さて、下巻に入ってからの展開は凄すぎる。上巻でのホラー、スリルがなければ、スラップスティックじゃないか、と勘違いさせるようなオフビートぶり。
主人公を助ける女性があらわれるのだが、この女性のスーパーウーマンぶりが、常識を超えているのだ。御都合主義を100回積み重ねてもまだ足りないくらい。作中で、主人公自身が「マンガ本」と評するほどのありえない超人ぶり。しかも単なるマンガ本じゃない。殺人鬼ジェフリー・ダーマーが作者のマンガ本みたいだ、とたとえているのだ。主人公はもう頭の中がハテナの嵐だ。
スーパーなのは、この女性だけじゃない。
作中人物が「Xファイル」と言ってしまうほどのスーパーナチュラルな世界が洪水になってあふれだす。
これが夢オチでなかったとしたら、まったく狂った電波小説にちがいない、と思えたほどだ。夢オチ以外、収拾のつけようがないむちゃくちゃな展開なのだ。
こんなムチャクチャ電波支離滅裂キチガイ世界の前では、上巻であんなに恐ろしかった人形も影が薄くなってしまう。そして、実際、気がぬけるほど簡単に脅威がおさまってしまうのだ。人形が退治されるシーンでは、居並ぶ登場人物たちのなかで、いちばんまともなのが、この人形だと言い切れるほどだ。
しかも、人形の脅威がなくなったあとに、思わぬ魔法合戦があり、ラストにいたっては、ついにみんな狂ってしまったのか、と思えるような、ハッピーエンドを迎える。
どこかおかしい、と思わせるこの世界では、言葉づかいも少し変になる。
主人公も他の登場人物も、こんな言葉使いをする。
「教えてくダサい」
おかしな世界の一端を知っていただくために、主人公の母と、くだんのマンガ本女との会話を引用しておこう。
「しゃべっていては聞くことはできないわよ」とトミーの母親。
「たわごとです」
「不愉快な娘だね」
「わたしは天気です」とデル。
「なんですって?」
「不快でも快適でもない。わたしは、いまたんにここにいるだけです」
「竜巻もそう。でも、不快で危険」
「わたしは地質学的というより気象学的なんです」とデル。
「どういう意味?」
「岩山より竜巻でいるほうがまし」
「竜巻は去来し、山は常に不動だわね」
「山がいつも同じ場所にあるとはかぎりません」
「常に同じ場所にある」トミーの母親は断言した。
デルは首を横に振った。
「とはかぎりません」
「どこに移動する?」
「太陽は爆発し、新星となり、地球は吹き飛ばされる」デルは勢いづいて答えた。
「あんた、いかれてるね」
「十億年ほど待って、その目で確かめればわかります」
なに?この会話。
この会話はまだまだ続き、こんなくだりも。
「それは大規模なジャンケンのようなものなんです」とデル。「竜巻は岩を負かします。なぜなら、竜巻は情熱だから」
「竜巻はただの熱気だね」
「冷気です」
「どちらにしろ、大気だよ」
「あんた、おかあさんがいるの?」トミーの母親がたずねた。
「実を言うと」とデル。「昆虫のタマゴから孵化したんです。わたしはただの虫けらですから。幼虫です」
ううむ。狂ってる。この会話では主に、マンガ本女のデルがむちゃくちゃだが、この会話は、悪魔人形に追い掛けられている真っ最中の会話で、よくぞこれだけ電波会話する余裕があったものだ、と思わせるが、彼らがこれからどこに行くのかと言えば、トミー(主人公)の母親の強いすすめで無理矢理、知り合いのヘアドレッサーのところに向かっているのだ。どういう状況で散髪にでかけてるんだ!(のちに、その意図とか判明するけど)
翻訳は2008年だが、クーンツ1996年の作品。これがまあ、凄い作品だった。
上巻はまあ、こわいこわい。
主人公は、アメリカンライフにどっぷり浸かろうとしているベトナム人。
新車に乗ってとばしてたら、カーラジオから雑音とともに、自分の名が呼ばれる。
キャ〜〜〜〜〜〜〜〜!
家に帰ったら、黒糸で×印の目と口だけがある、白い人形。
その人形がいきなり、襲いかかってくる!
ギャ〜〜〜〜〜〜〜〜〜!
口をあけたら、風で枯葉が口に入ってきて舌を刺す!
ペッペッペ〜〜〜〜〜!
椅子に座ったら、ピンがふとももに刺さる!
イテテテッテテッッッテテ〜〜〜〜!
こうじゃないか、ああじゃないか、とこわがる心理を描写して、さんざん読者をこわがらせる。
そして、どこまでも追いかけてくる人形から逃げる主人公!ここらはクーンツの独壇場だ。
ブードゥーの人形か?と思わせる30センチ足らずのジンジャーブレッドマンみたいな人形が、いつのまにやら大きくなり、ついに大柄な人間の大きさになって追いかけてくる。
銃で撃っても、ぜんぜん退治できない。
主人公は、この人形を「ラヴクラフトの作品に登場する太古の神々のひとりのようなもの」と妄想する。
さて、下巻に入ってからの展開は凄すぎる。上巻でのホラー、スリルがなければ、スラップスティックじゃないか、と勘違いさせるようなオフビートぶり。
主人公を助ける女性があらわれるのだが、この女性のスーパーウーマンぶりが、常識を超えているのだ。御都合主義を100回積み重ねてもまだ足りないくらい。作中で、主人公自身が「マンガ本」と評するほどのありえない超人ぶり。しかも単なるマンガ本じゃない。殺人鬼ジェフリー・ダーマーが作者のマンガ本みたいだ、とたとえているのだ。主人公はもう頭の中がハテナの嵐だ。
スーパーなのは、この女性だけじゃない。
作中人物が「Xファイル」と言ってしまうほどのスーパーナチュラルな世界が洪水になってあふれだす。
これが夢オチでなかったとしたら、まったく狂った電波小説にちがいない、と思えたほどだ。夢オチ以外、収拾のつけようがないむちゃくちゃな展開なのだ。
こんなムチャクチャ電波支離滅裂キチガイ世界の前では、上巻であんなに恐ろしかった人形も影が薄くなってしまう。そして、実際、気がぬけるほど簡単に脅威がおさまってしまうのだ。人形が退治されるシーンでは、居並ぶ登場人物たちのなかで、いちばんまともなのが、この人形だと言い切れるほどだ。
しかも、人形の脅威がなくなったあとに、思わぬ魔法合戦があり、ラストにいたっては、ついにみんな狂ってしまったのか、と思えるような、ハッピーエンドを迎える。
どこかおかしい、と思わせるこの世界では、言葉づかいも少し変になる。
主人公も他の登場人物も、こんな言葉使いをする。
「教えてくダサい」
おかしな世界の一端を知っていただくために、主人公の母と、くだんのマンガ本女との会話を引用しておこう。
「しゃべっていては聞くことはできないわよ」とトミーの母親。
「たわごとです」
「不愉快な娘だね」
「わたしは天気です」とデル。
「なんですって?」
「不快でも快適でもない。わたしは、いまたんにここにいるだけです」
「竜巻もそう。でも、不快で危険」
「わたしは地質学的というより気象学的なんです」とデル。
「どういう意味?」
「岩山より竜巻でいるほうがまし」
「竜巻は去来し、山は常に不動だわね」
「山がいつも同じ場所にあるとはかぎりません」
「常に同じ場所にある」トミーの母親は断言した。
デルは首を横に振った。
「とはかぎりません」
「どこに移動する?」
「太陽は爆発し、新星となり、地球は吹き飛ばされる」デルは勢いづいて答えた。
「あんた、いかれてるね」
「十億年ほど待って、その目で確かめればわかります」
なに?この会話。
この会話はまだまだ続き、こんなくだりも。
「それは大規模なジャンケンのようなものなんです」とデル。「竜巻は岩を負かします。なぜなら、竜巻は情熱だから」
「竜巻はただの熱気だね」
「冷気です」
「どちらにしろ、大気だよ」
「あんた、おかあさんがいるの?」トミーの母親がたずねた。
「実を言うと」とデル。「昆虫のタマゴから孵化したんです。わたしはただの虫けらですから。幼虫です」
ううむ。狂ってる。この会話では主に、マンガ本女のデルがむちゃくちゃだが、この会話は、悪魔人形に追い掛けられている真っ最中の会話で、よくぞこれだけ電波会話する余裕があったものだ、と思わせるが、彼らがこれからどこに行くのかと言えば、トミー(主人公)の母親の強いすすめで無理矢理、知り合いのヘアドレッサーのところに向かっているのだ。どういう状況で散髪にでかけてるんだ!(のちに、その意図とか判明するけど)
『私たちの希望はどこにあるのか 今、なすべきこと』
2009年6月17日 読書加藤周一の『私たちの希望はどこにあるのか 今、なすべきこと』を読んだ。
講演と質疑応答の記録。
以下、目次。
第1部 講演
1、戦争について考える
良心的徴兵拒否
戦争は英雄的か
戦争宣伝の嘘
目的はどこに
目的は達成されたか
2、希望はどこにあるのか
小さなグループの活動
空前の反戦運動
米国の変化の可能性
3、今、なすべきこと
何ができるのか
暴力と非合法
まだできることはある
第2部 会場からの質問に答えて
メディアの状況について
戦争は人間の本性ではないか
宗教に戦争を止める力があるか
正義の戦争はあるか
徴兵制の話は飛躍があるのでは
北朝鮮問題の現状と打開の方向は
知識人の定義は
若い人へのメッセージを
第1部の「何ができるのか」で、加藤周一は、市民が社会的責任をまっとうするためにある行動に出ようとする際に3つの段階がある、と言っている。そのひとつめにあげているのが、次のとおり。
「反対すべきか賛成すべきか考え、迷います。迷えば迷うほどいいのです。(中略)複雑な問題についてはただちに断言しないで、迷うほうがいい」
と、いうわけで、第1部の講演内容については要約せずにおく。
第2部の質疑応答での加藤周一の回答から、部分的に引用だけしておこう。
「メディアの状況について」
マスメディアが何に沈黙するかが決定的に重要なことがあります。
マスメディアが伝えないことに注意する必要がある。
「戦争は人間の本性ではないか」
そもそも人間の本性なるものはよくわからないでしょう。
タナトスとエロスはたいへんおもしろい。
おもしろいけれど、どこまで信用できるのかわからない。
宗教戦争についてはデマが多い。
私は戦争の原因としての宗教戦争というものは、あまり大きな要素ではないと思います。
「宗教に戦争を止める力があるか」
クエーカー教徒は武器を持たない、たとえ自分が殺されても人は殺さないという思想で、典型的な良心的兵役拒否として認められています。
ローマ法王のヨハネ・パウロ2世はイラク戦争では素晴らしかった。
彼はたえず戦争反対をカトリック教徒に呼びかけ、ホワイトハウスにも直接手紙を送り、徹底的な反戦の立場を貫きました。
「正義の戦争はあるか」
私は絶対平和主義じゃないので、ある場合には正義の戦争を認めなければならないと思います。
1つはいわゆる正当防衛。
しかし、将来攻撃されるかもしれないからあらかじめ相手を攻撃しようという話ではない。
2つ目は、誰が判断するのか非常にむつかしいのですが、いわゆる人道的な見地で、人権の蹂躙があまりにも巨大で、残酷で、疑問の余地のないほど現実に目の前で進行しているという場合。
どちらかといえば、私は心理的にはナチに対する戦争は正当化したいと思う。そしてナチの同盟国は日本ですから、そうすると日本に対する戦争も正当化されることになります。
「徴兵制の話は飛躍があるのでは」
第9条に関していえば、国際紛争に関して武器を使用しないで解決しようというのが、一つの建前としての対外政策の根本的な方向を決めています。
『日本周辺』では自衛隊が行動できるか、周辺とはどこまでか、北緯何度、東経何度までかということが問題じゃなくて、国際問題に軍事力を使うか使わないかということが問題です。
「北朝鮮問題の現状と打開の方向は」
どうして北朝鮮問題の場合には、相手が対外的に合理的な行動をするだろうという賭けに出ないのか。それは納得できません。
初めからけんか腰でやっていたのではますます危険は増大します。できるだけ危険を小さくしようという話で、ゼロにはできない。そのためにどうしたらいいかといえば、朝から晩まで北朝鮮の悪口を言っていてもはじまらないのです。
「知識人の定義は」
知識人の定義は、自分が知識人だと思っている人のことです。
「若い人へのメッセージを」
これがいいことだというのが1つあって、それにみんなが賛同すべきだという考え方をやめるように努力することが、集団としても個人としても大切だと思います。
2つめはヒューモア。
たまたまこの日、録画してあった「よろセン」で中島が偉人の1人としてヒトラーおじさんを解説する回を見直したところだった。
この回は、ヒトラーを親しみある人物として語るとはなにごとだ、と苦情が殺到したらしい。
かつては同盟していて、ヒトラーを礼賛していた日本人が、今では問答無用で拒絶反応を起こしているのだ。ヒトラーを悪者として毛嫌いするのなら、それと同じ程度に、日本の軍人たちも毛嫌いされてしかるべきだと思うのだが、実態はどうなんだろう。
講演と質疑応答の記録。
以下、目次。
第1部 講演
1、戦争について考える
良心的徴兵拒否
戦争は英雄的か
戦争宣伝の嘘
目的はどこに
目的は達成されたか
2、希望はどこにあるのか
小さなグループの活動
空前の反戦運動
米国の変化の可能性
3、今、なすべきこと
何ができるのか
暴力と非合法
まだできることはある
第2部 会場からの質問に答えて
メディアの状況について
戦争は人間の本性ではないか
宗教に戦争を止める力があるか
正義の戦争はあるか
徴兵制の話は飛躍があるのでは
北朝鮮問題の現状と打開の方向は
知識人の定義は
若い人へのメッセージを
第1部の「何ができるのか」で、加藤周一は、市民が社会的責任をまっとうするためにある行動に出ようとする際に3つの段階がある、と言っている。そのひとつめにあげているのが、次のとおり。
「反対すべきか賛成すべきか考え、迷います。迷えば迷うほどいいのです。(中略)複雑な問題についてはただちに断言しないで、迷うほうがいい」
と、いうわけで、第1部の講演内容については要約せずにおく。
第2部の質疑応答での加藤周一の回答から、部分的に引用だけしておこう。
「メディアの状況について」
マスメディアが何に沈黙するかが決定的に重要なことがあります。
マスメディアが伝えないことに注意する必要がある。
「戦争は人間の本性ではないか」
そもそも人間の本性なるものはよくわからないでしょう。
タナトスとエロスはたいへんおもしろい。
おもしろいけれど、どこまで信用できるのかわからない。
宗教戦争についてはデマが多い。
私は戦争の原因としての宗教戦争というものは、あまり大きな要素ではないと思います。
「宗教に戦争を止める力があるか」
クエーカー教徒は武器を持たない、たとえ自分が殺されても人は殺さないという思想で、典型的な良心的兵役拒否として認められています。
ローマ法王のヨハネ・パウロ2世はイラク戦争では素晴らしかった。
彼はたえず戦争反対をカトリック教徒に呼びかけ、ホワイトハウスにも直接手紙を送り、徹底的な反戦の立場を貫きました。
「正義の戦争はあるか」
私は絶対平和主義じゃないので、ある場合には正義の戦争を認めなければならないと思います。
1つはいわゆる正当防衛。
しかし、将来攻撃されるかもしれないからあらかじめ相手を攻撃しようという話ではない。
2つ目は、誰が判断するのか非常にむつかしいのですが、いわゆる人道的な見地で、人権の蹂躙があまりにも巨大で、残酷で、疑問の余地のないほど現実に目の前で進行しているという場合。
どちらかといえば、私は心理的にはナチに対する戦争は正当化したいと思う。そしてナチの同盟国は日本ですから、そうすると日本に対する戦争も正当化されることになります。
「徴兵制の話は飛躍があるのでは」
第9条に関していえば、国際紛争に関して武器を使用しないで解決しようというのが、一つの建前としての対外政策の根本的な方向を決めています。
『日本周辺』では自衛隊が行動できるか、周辺とはどこまでか、北緯何度、東経何度までかということが問題じゃなくて、国際問題に軍事力を使うか使わないかということが問題です。
「北朝鮮問題の現状と打開の方向は」
どうして北朝鮮問題の場合には、相手が対外的に合理的な行動をするだろうという賭けに出ないのか。それは納得できません。
初めからけんか腰でやっていたのではますます危険は増大します。できるだけ危険を小さくしようという話で、ゼロにはできない。そのためにどうしたらいいかといえば、朝から晩まで北朝鮮の悪口を言っていてもはじまらないのです。
「知識人の定義は」
知識人の定義は、自分が知識人だと思っている人のことです。
「若い人へのメッセージを」
これがいいことだというのが1つあって、それにみんなが賛同すべきだという考え方をやめるように努力することが、集団としても個人としても大切だと思います。
2つめはヒューモア。
たまたまこの日、録画してあった「よろセン」で中島が偉人の1人としてヒトラーおじさんを解説する回を見直したところだった。
この回は、ヒトラーを親しみある人物として語るとはなにごとだ、と苦情が殺到したらしい。
かつては同盟していて、ヒトラーを礼賛していた日本人が、今では問答無用で拒絶反応を起こしているのだ。ヒトラーを悪者として毛嫌いするのなら、それと同じ程度に、日本の軍人たちも毛嫌いされてしかるべきだと思うのだが、実態はどうなんだろう。
ポール・ドハティの『教会の悪魔』を読んだ。
13世紀のイングランドを舞台にしたミステリ。
密室の教会内で首吊り死体が発見された。国王の密偵ヒュー・コーベットが謎をとく。
中世のロンドンは汚くて臭い。当時の風俗、情景は臭いをともなって迫ってくる。
自殺と思われていたため、埋葬されず溝に捨てられた死体を探すシーン。
「形容できないほどの臭気にコーベットはすぐさまマントの端で鼻と口をかばった。坑にあふれんばかりのごみが寒さで凍りつき、冬でこれなら盛夏はどんなざまか、想像するのがやっとだ」
「そこは犬猫や間引いた赤ん坊の死骸ばかりか刑死者や自殺者の死体捨て場でもある」
主人公の妻子はペストで死んでいる。
「あのころは妻もわが子もほがらかに健やかで、清潔な四肢に恵まれていた。それがわずか数日のうちに、どちらも腫瘍(よこね)だらけの全身に膿を吹き出し、おぞましく臭気ふんぷんたる生きた屍に変わり果てた」
さらし刑の描写。
「両手をさらし台に固定されて腐った魚を首にぶらさげた男がぽつねんと座っていた」
19世紀まであったという熊いじめの見世物。
「動くのがやっとの巨大なけものが血走った目を怒りにたぎらせてけしかけられた犬を睨み、爪を立て、吼え、とびかかるたびに毛皮や血が飛び散る」
コーベットの推理により自殺ではなく殺人事件であることが判明し、悪魔崇拝の邪教の存在が浮かび上がる。徳川の時代に豊臣の残党が幕府転覆を狙う、みたいなイメージが湧いた。
読んだ感じは、まるで捕物帳である。当時の時代を感じさせる描写を楽しみ、複雑でない謎を楽しむ。時代小説が大好きな僕としては、非常に面白い。この和爾桃子という訳者は、ヒューリックのディー判事シリーズも翻訳しており、そっちも時代劇だった。
密室トリックは、手塚治虫のケン一探偵長のバリエーション。
犯人探しについては、これも捕物帳的。
昔、週刊誌に「遠山の金さん」の犯人当て懸賞小説が連載されていたことがある。40年くらい前?
それを読んで思ったのは、いかにも悪そうなやつが、真犯人なのだ。
意外性はまったくないが、悪いやつ、いやなやつがやっぱり犯人として裁かれるところに、大衆小説の王道を感じたのだ。そのときはまだ存在しなかったが、まるで2時間ドラマ、と今なら思うだろう。
この『教会の悪魔』もそれに似て、読んでいて「ああ、きっとこいつが犯人にちがいない」とはっきりとわかるようになっている。意外性はないが、物語としては、それが最も自然で、物語が成立する設定になっている。
安心して読めるミステリ、と思って読み終えたのだが、著者あとがきに、とんでもないどんでん返しが待っていた。
「どひゃー!」とひっくり返った。
このシリーズ、次も同様の趣向が待っているんだろうか。
13世紀のイングランドを舞台にしたミステリ。
密室の教会内で首吊り死体が発見された。国王の密偵ヒュー・コーベットが謎をとく。
中世のロンドンは汚くて臭い。当時の風俗、情景は臭いをともなって迫ってくる。
自殺と思われていたため、埋葬されず溝に捨てられた死体を探すシーン。
「形容できないほどの臭気にコーベットはすぐさまマントの端で鼻と口をかばった。坑にあふれんばかりのごみが寒さで凍りつき、冬でこれなら盛夏はどんなざまか、想像するのがやっとだ」
「そこは犬猫や間引いた赤ん坊の死骸ばかりか刑死者や自殺者の死体捨て場でもある」
主人公の妻子はペストで死んでいる。
「あのころは妻もわが子もほがらかに健やかで、清潔な四肢に恵まれていた。それがわずか数日のうちに、どちらも腫瘍(よこね)だらけの全身に膿を吹き出し、おぞましく臭気ふんぷんたる生きた屍に変わり果てた」
さらし刑の描写。
「両手をさらし台に固定されて腐った魚を首にぶらさげた男がぽつねんと座っていた」
19世紀まであったという熊いじめの見世物。
「動くのがやっとの巨大なけものが血走った目を怒りにたぎらせてけしかけられた犬を睨み、爪を立て、吼え、とびかかるたびに毛皮や血が飛び散る」
コーベットの推理により自殺ではなく殺人事件であることが判明し、悪魔崇拝の邪教の存在が浮かび上がる。徳川の時代に豊臣の残党が幕府転覆を狙う、みたいなイメージが湧いた。
読んだ感じは、まるで捕物帳である。当時の時代を感じさせる描写を楽しみ、複雑でない謎を楽しむ。時代小説が大好きな僕としては、非常に面白い。この和爾桃子という訳者は、ヒューリックのディー判事シリーズも翻訳しており、そっちも時代劇だった。
密室トリックは、手塚治虫のケン一探偵長のバリエーション。
犯人探しについては、これも捕物帳的。
昔、週刊誌に「遠山の金さん」の犯人当て懸賞小説が連載されていたことがある。40年くらい前?
それを読んで思ったのは、いかにも悪そうなやつが、真犯人なのだ。
意外性はまったくないが、悪いやつ、いやなやつがやっぱり犯人として裁かれるところに、大衆小説の王道を感じたのだ。そのときはまだ存在しなかったが、まるで2時間ドラマ、と今なら思うだろう。
この『教会の悪魔』もそれに似て、読んでいて「ああ、きっとこいつが犯人にちがいない」とはっきりとわかるようになっている。意外性はないが、物語としては、それが最も自然で、物語が成立する設定になっている。
安心して読めるミステリ、と思って読み終えたのだが、著者あとがきに、とんでもないどんでん返しが待っていた。
「どひゃー!」とひっくり返った。
このシリーズ、次も同様の趣向が待っているんだろうか。
サミュエル・ウェーバーの『破壊と拡散』を読んだ。月曜社の暴力論叢書第1巻にあたる。
以下、目次順に簡単なコメント。
*日本語版序文 自己−保存から自己−免役化へ
デリダを援用しつつ、グローバリゼーションとテロとの戦いなど今日の西洋的政策を分析する。
作者は、非−西洋的伝統と文化に属する読者(つまり、日本人)からの応答に関心を寄せている。
でも、僕から見ると、日本がはたして「非−西洋」の役割をになうに足るのかどうか、よくわからない。
*「戦争」・「テロリズム」・「スペクタクル」−タワーと洞窟について−
1、戦争・テロリズム・スペクタクル
戦争の劇場化について。タイトルのタワーは9月11日のツインタワー、洞窟はアフガニスタンのトラボラの洞窟。
テロリズムに対する戦争、というときの「戦争」はグローバリゼーションの擁護であり肯定である、と説く。地球規模で単一の秩序を課すこと、秩序を生き延びることへと関連づける役割はテレビなどのメディアによってなされる。その一例が、愉快。
「それはたとえば『チャンネルはそのままで。すぐ戻ってきます』という『コマーシャルによる中断』に関する儀式的告知においてあらわれている。そのままでいてください−そして生き延びてください。つまりは、わたしたちのもとを離れたら死んでしまいますよ、ということである」
2、信念・罪・テロ−ある古い物語の新たな章
トクヴィルの『アメリカの民主主義』では、「アメリカ人の哲学的方法」を特徴づけるのは自分自身の知性を用いようとする個々人の努力への信念だという。これは、自分自身の知性以外何事も信用しなくなる、つまり、他者をまったく信用しなくなることを意味している。
作者はホーソーンの『ヤング・グッドマン・ブラウン』をひきながら、「邪悪なもの」には「我慢できない」今日のアメリカを分析する。「我慢できない」ので、それについて議論したり解釈することはできず、排除だけがなされる。
破壊と拡散−権力の2様相−
テロは、もはや決まった立場をとることはなく、前線に姿を現すこともなく、戦闘において戦うのではなく、むしろ至るところで起こりうる断続的な攻撃を通じて戦う。テロは軍事的、警察的報復措置により逆に助長される。
目に見えない敵の非直線的な危険を、直線的(軍事的)に処理しようとしているのが、今のアメリカだ。軍事的措置で敵を特定の領土から排除すれば、敵は拡散するが、それは同時に敵を増大させ、強大化させる。パックス・アメリカーナは無限の正義の時代になるのではなく、無限の不正という破壊的な螺旋になるだろう、と作者は述べる。
戦時
1、(無題)
プラトン以来の、所有権の侵害としての暴力という考え方。
外からの侵害という概念の英語での「暴力(バイオレンス)」と、規則の保持、強制力を意味するドイツ語での「暴力(ゲバルト)」(ベンヤミン)
2、戦時 分割の動員結集
フロイトの『戦争と死に関する現代的見解』を読み解く。
フロイトの「幻滅」はヨーロッパ中心主義、帝国主義的偏向の失敗、コミュニケーションの手段が増加したのに、「文明化された諸民族が互いにほとんど知り合うことも理解しあうこともないため、一方が憎しみと嫌悪をもって他方と敵対するなどというほとんど把握しがたい現象」が続いていることにある。
フロイトは、「知性が確実に働くことができるのは、強い感情の動きの影響から引き離されている場合のみ」だと述べ、また2つの対立する感情が同時に同居する「感情の両価性」を指摘する。
3、Tuer son Mandarin(彼の高官を殺す)
現代における死への関係について、フロイトの論文から読み解く。
自分の死は想像不可能で非現実的。他者の死は敵の死として寄せつけない。
ただ愛する者の死において、それを悲しむと同時に喜ぶ両価性があらわれる。
メディアによる、死と戦争のスペクタクル化(スポーツ観戦化)
タイトルの「彼の高官を殺す」はバルザックの『ゴリオ爺さん』から。
「自分の大きな利益になるという理由で、北京の老いた高官をたんなる意志の作用によって−パリを離れることなく、またもちろん発覚することなく−殺すことができるならば、それをするかどうか」
(フロイトの論文では、このあと、「ルソーはその高官の命があまり重視されないであろうことをほのめかしている」と続く。ただ、ルソーの著作からそのエピソードは発見されていない)
戦争と死に関する同時代的なもの/フロイト(1915年)
ウェーバーの「戦時」で読みといた論文の翻訳。ウェーバーが使用したのは主に英訳版だが、ここで訳出されたのは、ドイツ語版から。ウェーバー自身も文中で触れているように、必ずしも一致しない。
1、戦争の幻滅
2、われわれの死への関係
「生に耐えることを望むなら、死に備えよ」というフロイト製格言でしめくくられる。
訳者解説 戦時 開かれた時間/野内聡
回想シーンのような解説。
以下、目次順に簡単なコメント。
*日本語版序文 自己−保存から自己−免役化へ
デリダを援用しつつ、グローバリゼーションとテロとの戦いなど今日の西洋的政策を分析する。
作者は、非−西洋的伝統と文化に属する読者(つまり、日本人)からの応答に関心を寄せている。
でも、僕から見ると、日本がはたして「非−西洋」の役割をになうに足るのかどうか、よくわからない。
*「戦争」・「テロリズム」・「スペクタクル」−タワーと洞窟について−
1、戦争・テロリズム・スペクタクル
戦争の劇場化について。タイトルのタワーは9月11日のツインタワー、洞窟はアフガニスタンのトラボラの洞窟。
テロリズムに対する戦争、というときの「戦争」はグローバリゼーションの擁護であり肯定である、と説く。地球規模で単一の秩序を課すこと、秩序を生き延びることへと関連づける役割はテレビなどのメディアによってなされる。その一例が、愉快。
「それはたとえば『チャンネルはそのままで。すぐ戻ってきます』という『コマーシャルによる中断』に関する儀式的告知においてあらわれている。そのままでいてください−そして生き延びてください。つまりは、わたしたちのもとを離れたら死んでしまいますよ、ということである」
2、信念・罪・テロ−ある古い物語の新たな章
トクヴィルの『アメリカの民主主義』では、「アメリカ人の哲学的方法」を特徴づけるのは自分自身の知性を用いようとする個々人の努力への信念だという。これは、自分自身の知性以外何事も信用しなくなる、つまり、他者をまったく信用しなくなることを意味している。
作者はホーソーンの『ヤング・グッドマン・ブラウン』をひきながら、「邪悪なもの」には「我慢できない」今日のアメリカを分析する。「我慢できない」ので、それについて議論したり解釈することはできず、排除だけがなされる。
破壊と拡散−権力の2様相−
テロは、もはや決まった立場をとることはなく、前線に姿を現すこともなく、戦闘において戦うのではなく、むしろ至るところで起こりうる断続的な攻撃を通じて戦う。テロは軍事的、警察的報復措置により逆に助長される。
目に見えない敵の非直線的な危険を、直線的(軍事的)に処理しようとしているのが、今のアメリカだ。軍事的措置で敵を特定の領土から排除すれば、敵は拡散するが、それは同時に敵を増大させ、強大化させる。パックス・アメリカーナは無限の正義の時代になるのではなく、無限の不正という破壊的な螺旋になるだろう、と作者は述べる。
戦時
1、(無題)
プラトン以来の、所有権の侵害としての暴力という考え方。
外からの侵害という概念の英語での「暴力(バイオレンス)」と、規則の保持、強制力を意味するドイツ語での「暴力(ゲバルト)」(ベンヤミン)
2、戦時 分割の動員結集
フロイトの『戦争と死に関する現代的見解』を読み解く。
フロイトの「幻滅」はヨーロッパ中心主義、帝国主義的偏向の失敗、コミュニケーションの手段が増加したのに、「文明化された諸民族が互いにほとんど知り合うことも理解しあうこともないため、一方が憎しみと嫌悪をもって他方と敵対するなどというほとんど把握しがたい現象」が続いていることにある。
フロイトは、「知性が確実に働くことができるのは、強い感情の動きの影響から引き離されている場合のみ」だと述べ、また2つの対立する感情が同時に同居する「感情の両価性」を指摘する。
3、Tuer son Mandarin(彼の高官を殺す)
現代における死への関係について、フロイトの論文から読み解く。
自分の死は想像不可能で非現実的。他者の死は敵の死として寄せつけない。
ただ愛する者の死において、それを悲しむと同時に喜ぶ両価性があらわれる。
メディアによる、死と戦争のスペクタクル化(スポーツ観戦化)
タイトルの「彼の高官を殺す」はバルザックの『ゴリオ爺さん』から。
「自分の大きな利益になるという理由で、北京の老いた高官をたんなる意志の作用によって−パリを離れることなく、またもちろん発覚することなく−殺すことができるならば、それをするかどうか」
(フロイトの論文では、このあと、「ルソーはその高官の命があまり重視されないであろうことをほのめかしている」と続く。ただ、ルソーの著作からそのエピソードは発見されていない)
戦争と死に関する同時代的なもの/フロイト(1915年)
ウェーバーの「戦時」で読みといた論文の翻訳。ウェーバーが使用したのは主に英訳版だが、ここで訳出されたのは、ドイツ語版から。ウェーバー自身も文中で触れているように、必ずしも一致しない。
1、戦争の幻滅
2、われわれの死への関係
「生に耐えることを望むなら、死に備えよ」というフロイト製格言でしめくくられる。
訳者解説 戦時 開かれた時間/野内聡
回想シーンのような解説。
『麗しのオルタンス』
2009年6月9日 読書
ジャック・ルーボーの『麗しのオルタンス』を読んだ。
未読の人がいるのなら、今すぐ読むべき本だ。素晴らしすぎる。
ルーボーはウリポ(潜在的文学工房)の人なのだが、これが創元推理文庫から出たことが快挙だ!
たしかにミステリらしい趣向は多分にある。
事件は金物屋連続鍋散乱事件で、ポルデヴィアの小像が盗まれる古典的な謎もある。
ラストあたりにはいっぱしに真相をあばくシーンもある。
しかし、そういう、何か事件があって、推理によって真相を導き出す、というような普通の話ではないのだ、この1冊は。
途中、こんな章がはさまれる。「幕間その1 いったい何がどうなっているのか?われわれはどこまで進んでいるのか?」こういった章は、まるでカーみたいでうれしくなってしまう。
この章では、筆者から14と1つの謎が列挙されている。
それは「犯行が市街図上で金物屋の螺旋を描いているのはどうしてか?」「彼はなぜ小像を盗むのか?」と、いった事件の謎もあるし、「語り手が剽窃したブロニャール警部との最初の場面はどの小説にあったものか?」というようなものもある。これは説明抜きでは何のことだかわからないだろう。この小説は、なにかというと、語り手と作者がしゃしゃりでてくるのである。第6章「ブロニャール警部が自分と『語り手』との関係をようやく釈明できる機会が与えられたことにまんざら腹を立てているわけではないことについて」では、それまで語り手(私)だったモルナシエ(訳者あとがきによると、この名前は小説家romancierのアナグラム)にかわって、ブロニャール警部が「私」として語りだす。で、途中で、モルナシエからつっこみが入るのだ。
「待った!待った!待った!」と言って、語り手の座を奪回し、ブロニャール警部が語り手であった部分が他の小説の一場面をそっくり剽窃している、と告発するのだ。
こうした脱線は山ほどあるが、別の場面で挙げておくと、クライマックス直前、語り手につっこみが入る。
「とりわけ私の気持ちを知らないイヴェットがこれでもかというほどこと細かく報告するので、もし、大詰めに近づいている捜査の興奮と気晴らしがなければ、とても耐えられなかっただろうと思う。(だったらどうだと言うんだ、このイモ野郎!−筆者の註)(苛立ってやがる−語り手の註)(いいかげんにしないか。おまえさんたちの喧嘩につきあわされる読者の身にもなってみろ−校正部長の註)」
また、ついには読者までもが口を出す。
「『しかし』と、ここで読者の声があがった。『話の腰を折るようで恐縮ですが、私の記憶が確かであれば、まずは第16章で、次にはつい最近、23章でも、アラペード刑事が立ち会ったマダム・イヴォンヌとシヌール神父の会話において、そのベンチはまさにブロニャール警部が捜査に使っている以上、ふさがっていると言っているではありませんか』」
と、さらにこうしてはどうか、と提案したりする。
また、語り手が現場に立ち会えなかった部分の描写について、その場にいた猫から話を聞いて、書いているのだが、猫の検閲によって、膨大な伏せ字でその場面は語られるのだ。
そうそう、幕間で14と1つの謎と書いたが、なぜ1つだけわけたかというと、1つの謎だけは、即明かされるのだ。その謎というのが、猫に関することで、本編自体が脱線しまくっているうえに、猫の恋の話が併行して語られることになる。
ただ、これはびっくりしたのだが、この猫の恋物語が、本編の事件の謎ときに大いにかかわってくるのだ。まあ、仲を裂かれた猫が仕返しに、証拠品を移動させて、仲を裂いた人物を犯人として逮捕されるように仕組むのだが。
また、ミステリ的事件と関係ないが、図書館での顛末には笑った。
図書館があの手この手を使って、蔵書を閲覧者から遠ざけようとしていることについての攻防を描いているのだ。
とにかく、描写ひとつひとつがひとくせもふたくせもあり、訳者も言うように「破天荒な小説」で「抱腹絶倒の悪ふざけ」になっている。(筆者、語り手、校正部長、読者が小説にツッコミいれてる、と書いたが、訳者も出てくる場面がある)
事件の謎をいよいよ解こうとする際の、ブロニャール警部とアラペード刑事の会話が凄い。
「最初からすべてをおさらいしてみよう」
「お願いです、警部どの」とアラペード。「読者のことも考えてください。最初からすべてをおさらいするとしたら、ただでさえ長い話をさらに長く話さなければならなくなりますよ。なぜならば、物語に含まれる出来事のひとつひとつについて、それが捜査の全体に占める位置を明らかにするために、かなり詳しい説明を付け加える必要があるからです。そんな危ないことを受け入れようとする小説家などこの世にはあり得ないし、はたしてあなたがそこで留まることができるかどうかも疑わしい。仮に現時点でわれわれのいる場所にふたたびたどり着いたとしても、またそこで最初に逆戻りして、(中略)この小説は、今われわれがいる時点に最初に戻ってきたときには、当初の分量の3倍になり、2回目に戻ってきたときには、さらに厳密を期そうとして7倍の長さになることだって十分あり得るわけで、そうなるとそこで留まることができるとは到底思えず、1より大きい等差級数は収束を見ないわけですから、この小説を終えることができなくなる」
このくだりはさらにすごいことになるが、長くなるので割愛。
今年読んだミステリの中でも最高に面白かったかな。
未読の人がいるのなら、今すぐ読むべき本だ。素晴らしすぎる。
ルーボーはウリポ(潜在的文学工房)の人なのだが、これが創元推理文庫から出たことが快挙だ!
たしかにミステリらしい趣向は多分にある。
事件は金物屋連続鍋散乱事件で、ポルデヴィアの小像が盗まれる古典的な謎もある。
ラストあたりにはいっぱしに真相をあばくシーンもある。
しかし、そういう、何か事件があって、推理によって真相を導き出す、というような普通の話ではないのだ、この1冊は。
途中、こんな章がはさまれる。「幕間その1 いったい何がどうなっているのか?われわれはどこまで進んでいるのか?」こういった章は、まるでカーみたいでうれしくなってしまう。
この章では、筆者から14と1つの謎が列挙されている。
それは「犯行が市街図上で金物屋の螺旋を描いているのはどうしてか?」「彼はなぜ小像を盗むのか?」と、いった事件の謎もあるし、「語り手が剽窃したブロニャール警部との最初の場面はどの小説にあったものか?」というようなものもある。これは説明抜きでは何のことだかわからないだろう。この小説は、なにかというと、語り手と作者がしゃしゃりでてくるのである。第6章「ブロニャール警部が自分と『語り手』との関係をようやく釈明できる機会が与えられたことにまんざら腹を立てているわけではないことについて」では、それまで語り手(私)だったモルナシエ(訳者あとがきによると、この名前は小説家romancierのアナグラム)にかわって、ブロニャール警部が「私」として語りだす。で、途中で、モルナシエからつっこみが入るのだ。
「待った!待った!待った!」と言って、語り手の座を奪回し、ブロニャール警部が語り手であった部分が他の小説の一場面をそっくり剽窃している、と告発するのだ。
こうした脱線は山ほどあるが、別の場面で挙げておくと、クライマックス直前、語り手につっこみが入る。
「とりわけ私の気持ちを知らないイヴェットがこれでもかというほどこと細かく報告するので、もし、大詰めに近づいている捜査の興奮と気晴らしがなければ、とても耐えられなかっただろうと思う。(だったらどうだと言うんだ、このイモ野郎!−筆者の註)(苛立ってやがる−語り手の註)(いいかげんにしないか。おまえさんたちの喧嘩につきあわされる読者の身にもなってみろ−校正部長の註)」
また、ついには読者までもが口を出す。
「『しかし』と、ここで読者の声があがった。『話の腰を折るようで恐縮ですが、私の記憶が確かであれば、まずは第16章で、次にはつい最近、23章でも、アラペード刑事が立ち会ったマダム・イヴォンヌとシヌール神父の会話において、そのベンチはまさにブロニャール警部が捜査に使っている以上、ふさがっていると言っているではありませんか』」
と、さらにこうしてはどうか、と提案したりする。
また、語り手が現場に立ち会えなかった部分の描写について、その場にいた猫から話を聞いて、書いているのだが、猫の検閲によって、膨大な伏せ字でその場面は語られるのだ。
そうそう、幕間で14と1つの謎と書いたが、なぜ1つだけわけたかというと、1つの謎だけは、即明かされるのだ。その謎というのが、猫に関することで、本編自体が脱線しまくっているうえに、猫の恋の話が併行して語られることになる。
ただ、これはびっくりしたのだが、この猫の恋物語が、本編の事件の謎ときに大いにかかわってくるのだ。まあ、仲を裂かれた猫が仕返しに、証拠品を移動させて、仲を裂いた人物を犯人として逮捕されるように仕組むのだが。
また、ミステリ的事件と関係ないが、図書館での顛末には笑った。
図書館があの手この手を使って、蔵書を閲覧者から遠ざけようとしていることについての攻防を描いているのだ。
とにかく、描写ひとつひとつがひとくせもふたくせもあり、訳者も言うように「破天荒な小説」で「抱腹絶倒の悪ふざけ」になっている。(筆者、語り手、校正部長、読者が小説にツッコミいれてる、と書いたが、訳者も出てくる場面がある)
事件の謎をいよいよ解こうとする際の、ブロニャール警部とアラペード刑事の会話が凄い。
「最初からすべてをおさらいしてみよう」
「お願いです、警部どの」とアラペード。「読者のことも考えてください。最初からすべてをおさらいするとしたら、ただでさえ長い話をさらに長く話さなければならなくなりますよ。なぜならば、物語に含まれる出来事のひとつひとつについて、それが捜査の全体に占める位置を明らかにするために、かなり詳しい説明を付け加える必要があるからです。そんな危ないことを受け入れようとする小説家などこの世にはあり得ないし、はたしてあなたがそこで留まることができるかどうかも疑わしい。仮に現時点でわれわれのいる場所にふたたびたどり着いたとしても、またそこで最初に逆戻りして、(中略)この小説は、今われわれがいる時点に最初に戻ってきたときには、当初の分量の3倍になり、2回目に戻ってきたときには、さらに厳密を期そうとして7倍の長さになることだって十分あり得るわけで、そうなるとそこで留まることができるとは到底思えず、1より大きい等差級数は収束を見ないわけですから、この小説を終えることができなくなる」
このくだりはさらにすごいことになるが、長くなるので割愛。
今年読んだミステリの中でも最高に面白かったかな。