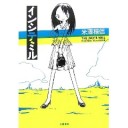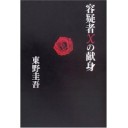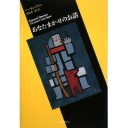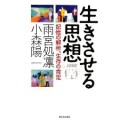勇嶺薫の『赤い夢の迷宮』を読んだ。
作者は「はやみねかおる」名義でジュブナイルを多数書いており、僕も「名探偵夢水清志郎事件ノート」シリーズを中心に数冊読んでいる。今回は成人向けの小説とあって、人殺しの暗く狂った感情や、死骸に群がる虫などのえぐいシーン、出口のないバッドエンディングで後味の悪さを演出したりしている。
はやみねかおるの『そして五人がいなくなる』のあとがきでは、「とくに好きな」推理小説の条件の1つとして、「HAPPY ENDでおわること」と書いてあるけど、さて、本作のラストはハッピーエンドなのか?
タイトルに関するヒントは、今まで出した本の中にちりばめられていた。はやみねかおるの『機巧館のかぞえ唄』の巻頭には、勇嶺薫の『夢迷宮』からの抜粋として文章が掲げられている。
「この現実が、だれかのみている赤い夢にすぎないのなら、それは、だれのみている夢なんですか?云々」
また、同じく『踊る夜光怪人』の冒頭には勇嶺薫の『赤い夢』からの抜粋が載せてある。
「だから、犯人も探偵も、一生覚めることのない、赤い夢の中に住んでいるんです。云々」
『赤い夢』『夢迷宮』が『赤い夢の迷宮』と無関係だとは思えない。
さて、本作は同窓会っぽい再会とともにはじまる惨劇を描いている。一種のタイムカプセル物語かな、と思いきや、そこはあんまりつっこまれず、閉ざされた場所での殺人ゲームがはじまるのである。いかにも新本格でござい、というトリックが使われているが、これはジュブナイルでもおなじみの、楽しく大がかりなトリックになっており、そのわかりやすさは明快で素晴らしい。
犯人の意外性は、もとよりクローズドサークルでの出来事で犯人候補者もかぎられているため、とくにびっくりはしなかったが、悪く言えば、別にだれが犯人でもよかったんじゃないのか、と思ってしまった。乱歩の二十面相シリーズみたいに、誰が犯人なのか、という興味が最小限な小説のような気がした。
登場人物の肉付けにちょっと感心してしまった。身の回りにいそうな、すごく嫌なやつをみごとに描いているのだ。このあたり、単なる駒として殺人ゲームを動かしているのではなく、じゅうぶん小説として読ませてくれる。
作者はあとがきで、主戦場はジュブナイルであることを書いている。それは、非常に正しい選択だ、と感じた。「はやみねかおる」の作品の方が好感をもてるような気がしたのだ。
作者は「はやみねかおる」名義でジュブナイルを多数書いており、僕も「名探偵夢水清志郎事件ノート」シリーズを中心に数冊読んでいる。今回は成人向けの小説とあって、人殺しの暗く狂った感情や、死骸に群がる虫などのえぐいシーン、出口のないバッドエンディングで後味の悪さを演出したりしている。
はやみねかおるの『そして五人がいなくなる』のあとがきでは、「とくに好きな」推理小説の条件の1つとして、「HAPPY ENDでおわること」と書いてあるけど、さて、本作のラストはハッピーエンドなのか?
タイトルに関するヒントは、今まで出した本の中にちりばめられていた。はやみねかおるの『機巧館のかぞえ唄』の巻頭には、勇嶺薫の『夢迷宮』からの抜粋として文章が掲げられている。
「この現実が、だれかのみている赤い夢にすぎないのなら、それは、だれのみている夢なんですか?云々」
また、同じく『踊る夜光怪人』の冒頭には勇嶺薫の『赤い夢』からの抜粋が載せてある。
「だから、犯人も探偵も、一生覚めることのない、赤い夢の中に住んでいるんです。云々」
『赤い夢』『夢迷宮』が『赤い夢の迷宮』と無関係だとは思えない。
さて、本作は同窓会っぽい再会とともにはじまる惨劇を描いている。一種のタイムカプセル物語かな、と思いきや、そこはあんまりつっこまれず、閉ざされた場所での殺人ゲームがはじまるのである。いかにも新本格でござい、というトリックが使われているが、これはジュブナイルでもおなじみの、楽しく大がかりなトリックになっており、そのわかりやすさは明快で素晴らしい。
犯人の意外性は、もとよりクローズドサークルでの出来事で犯人候補者もかぎられているため、とくにびっくりはしなかったが、悪く言えば、別にだれが犯人でもよかったんじゃないのか、と思ってしまった。乱歩の二十面相シリーズみたいに、誰が犯人なのか、という興味が最小限な小説のような気がした。
登場人物の肉付けにちょっと感心してしまった。身の回りにいそうな、すごく嫌なやつをみごとに描いているのだ。このあたり、単なる駒として殺人ゲームを動かしているのではなく、じゅうぶん小説として読ませてくれる。
作者はあとがきで、主戦場はジュブナイルであることを書いている。それは、非常に正しい選択だ、と感じた。「はやみねかおる」の作品の方が好感をもてるような気がしたのだ。
米澤穂信の『インシテミル』を読んだ。
クローズドサークルでの殺人&探偵ゲーム。
この手の作品は、学生たちを中心とした新本格と、マンガでよく見かけた。ちょっと前に大流行して定着した感のあるものだ。人を殺したり、探偵役になったりして、その報酬を最大にしようとする計算ゲームと、本来の探偵ゲームの面白さがミックスされている。
こういうのは、僕は「ルール小説」と勝手に呼んでいる。
で、この作品、どうだったか、というと、えらく面白かった。
しかし、推理小説の趣向はたんまりとあるが、醍醐味には欠けると思った。
それは、この作品のラストで明かされるように、この「暗鬼館」での殺人もまだ完成形ではなかった、というもどかしさによるものなのだろう。ひとことで言って、この小説の最大のびっくりポイントは何かというと、ちょっと思いだせないのである。
面白く読みすすめているうちに、ルールをうまく利用した者がうまくあがって終わった、という印象だけが強く、それはたとえば、しりとりで相手を「る」攻めにすることを世界で最初に思いついたケースみたいなもので、「そうか、なるほど、その手があるか」と膝を叩くが、2度目はないのである。これがルール小説、ってものなのだ。たとえば、なぜ犯人はいっぺんにみんなを皆殺しにしなかったのか、といえば、そうしないほうが報酬が高いからである。ただし、そのルールは作者が勝手に考えたもので、小説を面白く成立させるために恣意的に決められたものなのだ。これが、いつも、僕にはひっかかるのだ。
クライマックスで、残りの弾丸は1発しかない。これをはずすと失敗だ!これはサスペンスを盛り上げるが、1発しか弾丸がないのは、作者が盛り上げるために恣意的に設定したものだ、と思うと、ちょっとしらけてしまう。
実は、わたし、あと3日しか地球にいられないんです。ええっ、じゃあ、その3日間で僕と世界を楽しもう。これは作者が勝手に設えたものだ。物語を盛り上げるためだけにそんなことを勝手に決めたのだ。これはしらける。
「ソウ」シリーズがとても面白いと思いながら、ひっかかってしまうのも、これだ。
僕は、ルールというものが好きでないのかもしれない。
それと、違和感があったのは、この主人公、あまりにも推理小説の古典を読んでいなさすぎるんじゃないか?普通、推理小説の古典もちゃんと読んでいない人間に対して、この手の探偵ゲームを仕掛けたって、空回りに終わるんじゃないか?たとえば、推理小説は綾辻以後しか読んでないとか。そんな人間がどうやって綾辻を楽しめるのか。
タイトルの「インシテミル」は「淫してみる」だろう。新本格に淫してみれば、私にだってこれくらいのレベルのものは書けますよ、という作者のメッセージと受け取った!
クローズドサークルでの殺人&探偵ゲーム。
この手の作品は、学生たちを中心とした新本格と、マンガでよく見かけた。ちょっと前に大流行して定着した感のあるものだ。人を殺したり、探偵役になったりして、その報酬を最大にしようとする計算ゲームと、本来の探偵ゲームの面白さがミックスされている。
こういうのは、僕は「ルール小説」と勝手に呼んでいる。
で、この作品、どうだったか、というと、えらく面白かった。
しかし、推理小説の趣向はたんまりとあるが、醍醐味には欠けると思った。
それは、この作品のラストで明かされるように、この「暗鬼館」での殺人もまだ完成形ではなかった、というもどかしさによるものなのだろう。ひとことで言って、この小説の最大のびっくりポイントは何かというと、ちょっと思いだせないのである。
面白く読みすすめているうちに、ルールをうまく利用した者がうまくあがって終わった、という印象だけが強く、それはたとえば、しりとりで相手を「る」攻めにすることを世界で最初に思いついたケースみたいなもので、「そうか、なるほど、その手があるか」と膝を叩くが、2度目はないのである。これがルール小説、ってものなのだ。たとえば、なぜ犯人はいっぺんにみんなを皆殺しにしなかったのか、といえば、そうしないほうが報酬が高いからである。ただし、そのルールは作者が勝手に考えたもので、小説を面白く成立させるために恣意的に決められたものなのだ。これが、いつも、僕にはひっかかるのだ。
クライマックスで、残りの弾丸は1発しかない。これをはずすと失敗だ!これはサスペンスを盛り上げるが、1発しか弾丸がないのは、作者が盛り上げるために恣意的に設定したものだ、と思うと、ちょっとしらけてしまう。
実は、わたし、あと3日しか地球にいられないんです。ええっ、じゃあ、その3日間で僕と世界を楽しもう。これは作者が勝手に設えたものだ。物語を盛り上げるためだけにそんなことを勝手に決めたのだ。これはしらける。
「ソウ」シリーズがとても面白いと思いながら、ひっかかってしまうのも、これだ。
僕は、ルールというものが好きでないのかもしれない。
それと、違和感があったのは、この主人公、あまりにも推理小説の古典を読んでいなさすぎるんじゃないか?普通、推理小説の古典もちゃんと読んでいない人間に対して、この手の探偵ゲームを仕掛けたって、空回りに終わるんじゃないか?たとえば、推理小説は綾辻以後しか読んでないとか。そんな人間がどうやって綾辻を楽しめるのか。
タイトルの「インシテミル」は「淫してみる」だろう。新本格に淫してみれば、私にだってこれくらいのレベルのものは書けますよ、という作者のメッセージと受け取った!
東野圭吾の『容疑者Xの献身』を読んだ。
いつもは理系の謎を解くガリレオだったが、今回はちょっと違った。
数学の天才が、隣の母娘の犯行をかばうため、策略をめぐらす。
わかりやすく、しかも大きなトリックが用意されており、今でもこの規模のトリックで小説が成立するんだ、とちょっと驚いた。
これだけの大きく明瞭なトリックであれば、類似の前例もあるし、読者も解決以前に察しがついてしまうのだが、どうだ、この堂々たる傑作は!
アリバイトリックに関する一種の叙述のトリックがあり、それだけで本格ファンはふむふむ。な〜るほど、と納得してしまうのである。
また、タイトルの「献身」にまつわるエトセトラは、小説としての面白さをぐんと増した。
それと、この本読んで思ったのは、本格推理によくある「読者への挑戦」である。
あれはいったい、何についての戦いなのだろう、と。
作者が用意した真相をいちはやく読者が見抜いた場合、それは読者の勝ちなのか?
いや、読者がその「作者が用意した真相」に到達した、ということは、作者の勝ちなのだ。それは作中で事件の推理と解決がなされる以前と以後に関わりなし。
読者が勝つためには、作者が用意した以上の真相を論理の齟齬なく編み上げ、しかもそれがじゅうぶんに意外性をともなっていて、面白ければ、勝ちなのだ。つまり、名探偵が作中で明かす真相と読者の読みが結局一致するようでは、作者の勝ちになる。「こんな推理あるか!」とケチをつけている段階では作者に勝ったことにはならない。
よく「途中で真相がわかった」とか「トリックばればれ」などとうそぶく読者がいるが、それはまんまと作者の術中にはまった読者のうかつさをあらわしていることになる。
そしてまた、推理のためのデータが作者によって全部出されていない、などというのもお門違いな注文だ。小説は、答えの決まった試験問題を解くことではないのだ。
いつもは理系の謎を解くガリレオだったが、今回はちょっと違った。
数学の天才が、隣の母娘の犯行をかばうため、策略をめぐらす。
わかりやすく、しかも大きなトリックが用意されており、今でもこの規模のトリックで小説が成立するんだ、とちょっと驚いた。
これだけの大きく明瞭なトリックであれば、類似の前例もあるし、読者も解決以前に察しがついてしまうのだが、どうだ、この堂々たる傑作は!
アリバイトリックに関する一種の叙述のトリックがあり、それだけで本格ファンはふむふむ。な〜るほど、と納得してしまうのである。
また、タイトルの「献身」にまつわるエトセトラは、小説としての面白さをぐんと増した。
それと、この本読んで思ったのは、本格推理によくある「読者への挑戦」である。
あれはいったい、何についての戦いなのだろう、と。
作者が用意した真相をいちはやく読者が見抜いた場合、それは読者の勝ちなのか?
いや、読者がその「作者が用意した真相」に到達した、ということは、作者の勝ちなのだ。それは作中で事件の推理と解決がなされる以前と以後に関わりなし。
読者が勝つためには、作者が用意した以上の真相を論理の齟齬なく編み上げ、しかもそれがじゅうぶんに意外性をともなっていて、面白ければ、勝ちなのだ。つまり、名探偵が作中で明かす真相と読者の読みが結局一致するようでは、作者の勝ちになる。「こんな推理あるか!」とケチをつけている段階では作者に勝ったことにはならない。
よく「途中で真相がわかった」とか「トリックばればれ」などとうそぶく読者がいるが、それはまんまと作者の術中にはまった読者のうかつさをあらわしていることになる。
そしてまた、推理のためのデータが作者によって全部出されていない、などというのもお門違いな注文だ。小説は、答えの決まった試験問題を解くことではないのだ。
『りはめより100倍恐ろしい』
2009年5月29日 読書
木堂椎の『りはめより100倍恐ろしい』を読んだ。
タイトルの意味を本文から引用してみると。
「いじめなんかよりいじりのほうが全然怖いと思う。一文字違うだけだが、りはめより100倍恐ろしい。どちらも地獄なのだが、両者には決定的な差異がある」
で、その差異とは、
「いじめには被害者に絶対原因がある」が、「いじりは原因がこれといってない」
「いじめなら証拠もあるし先生も敏感に気づく。親も考えてくれる。必要とあれば登校拒否だってできる」一方、「いじりには逃げ道がない」「先生は誰も助けてくれない」
「いじめはふと止まる可能性がある。いじりは終わらない」
「さらに加害者の罪の意識もない。それが一番のいじりの残酷さだ」
この本は17才の現役高校生が書いた比較的リアルな小説なのだ。
いじりの典型例として、描かれるのが、一発芸の強要だ。
物語は、中学時代地獄のいじられキャラだった主人公が、部活や学級の場でいじりにあわないように、戦々兢々と日々を送るさまを描いている。
自分がいじられキャラにならないようにするため、別のスケープゴートをしたてて陥れたりする。
一応、青春小説らしく、後半は、主人公はひどいいじりを繰り返す奴に立ち向かい、謝罪をさせる。しかし、現実の高校生活ではそんな逆転劇はまず起こらずに、いじりは続行されるのだろう。
とにかく、いじられないようにするために、いろいろ考えて行動する主人公がリアルもリアル。思い出してみれば、自分の10代でも、この小説ほどじゃないとしても、毎日が戦争だった。2度と学生生活を繰り返したくない1つの理由がそこにある。クラスの中の、あいつとは仲良くしておこう、あいつとは接触をもたないように目立たなくしよう、的な策略が常に渦巻いていた。常にぼ〜〜〜っとしていて、考えていることの99%が探偵小説だった僕でもそうなのだ。一般の人間の受けたプレッシャーはどんなにすごかったのか。
タイトルの意味を本文から引用してみると。
「いじめなんかよりいじりのほうが全然怖いと思う。一文字違うだけだが、りはめより100倍恐ろしい。どちらも地獄なのだが、両者には決定的な差異がある」
で、その差異とは、
「いじめには被害者に絶対原因がある」が、「いじりは原因がこれといってない」
「いじめなら証拠もあるし先生も敏感に気づく。親も考えてくれる。必要とあれば登校拒否だってできる」一方、「いじりには逃げ道がない」「先生は誰も助けてくれない」
「いじめはふと止まる可能性がある。いじりは終わらない」
「さらに加害者の罪の意識もない。それが一番のいじりの残酷さだ」
この本は17才の現役高校生が書いた比較的リアルな小説なのだ。
いじりの典型例として、描かれるのが、一発芸の強要だ。
物語は、中学時代地獄のいじられキャラだった主人公が、部活や学級の場でいじりにあわないように、戦々兢々と日々を送るさまを描いている。
自分がいじられキャラにならないようにするため、別のスケープゴートをしたてて陥れたりする。
一応、青春小説らしく、後半は、主人公はひどいいじりを繰り返す奴に立ち向かい、謝罪をさせる。しかし、現実の高校生活ではそんな逆転劇はまず起こらずに、いじりは続行されるのだろう。
とにかく、いじられないようにするために、いろいろ考えて行動する主人公がリアルもリアル。思い出してみれば、自分の10代でも、この小説ほどじゃないとしても、毎日が戦争だった。2度と学生生活を繰り返したくない1つの理由がそこにある。クラスの中の、あいつとは仲良くしておこう、あいつとは接触をもたないように目立たなくしよう、的な策略が常に渦巻いていた。常にぼ〜〜〜っとしていて、考えていることの99%が探偵小説だった僕でもそうなのだ。一般の人間の受けたプレッシャーはどんなにすごかったのか。
内藤のボクシングは、まぶたが痛そう!
サップはもともと肉体が大きいだけの男だったのが、本来の姿に戻りきったか、という感じ。
山本KIDは親族まとめて、まるで下手な劇画だ。
カンセコも相手がクリス・ジェリコだったら、某映画スターを相手にしたときみたいに花を持たせてくれたろうに。
ペケーニョはなぜ所と再戦しなかったんだろう。
ルイ・アラゴンの『ダダ追想』を読んだ。
ダダの時代の随想がまとめられているが、「追想」とタイトルにあるが、執筆されたのは1923年頃のことになる。したがって、当時の熱気やいざこざが新鮮に描かれている。
本書の巻頭に載せられた『現代文学史計画』という「目次」は、『リテラチュール』4号(1922年9月)に掲載されたもので、ダダの歴史の見取り図として興味深い。
それは、「序論」「1913年から大戦まで」「1914年8月1日からアポリネールの死(1918年11月10日)まで」「休戦からダダまで(1918年11月から1920年1月)」「ダダ(1920年1月から1921年10月)」「ダダ以後(1921年10月から現在まで」「結論」と、区分けされている。
その項目を眺めているだけで、いろんな思いを馳せることもできるし、もしもこの計画が実現したならどれだけ大部の書物になったか、と想像してワクワクすることも可能だ。
以下、目次。
凡例
序文−草稿の経緯について−
テクストについての注記
現代文学史計画
アガディール
『吸血鬼』
『ペレアス』再演
ポール・ヴァレリーの『若きパルク』出版
ピエール・アルベール=ビロ
アンドレ・ジッド
アンドレ・ジッド(その2)
『リテラチュール』誌の創刊
レオンス・ローザンベール画廊でのルヴェルディのマチネー
トリスタン・ツァラのパリ到着
最初の『リテラチュール』の金曜日(その1)
最初の『リテラチュール』の金曜日(その2)
フォーブールのマニフェスタシオン
ミス・バーネイ邸におけるポール・ヴァレリー
クレマン・パンサール(1885−1922)
1921年、大いなるダダの季節
ポヴォロツキー画廊におけるピカビア展のヴェルニサージュ
「髭の生えた心臓」の夕べ(1923年7月6日)
幻像の画家マックス・エルンスト
さまざまな小説の1年(1922年7月−1923年8月)
「アガディール」は「現代文学史計画」の「序論」の筆頭にあげられている項目で、本書はアラゴンが書こうとしていた「現代文学史計画」の書けた部分を年代順に並べたものだと言えよう。
僕にとっては偉大な作家や有名人たちが、アラゴンの筆によって歯に衣着せぬ表現をなされているところもあって、面白い。
たとえばアンドレ・ジッドについて、こんなふうに書いている。
「彼はいつでも時流に精通していたいと願ったが、実際には何も理解できないので、時流に暗いことに死ぬほど不安を感じていた」
ツァラについては、
「以前の彼は、恐れおののきながら自分の部屋に閉じ籠っていて、そこから外出することもできず、またその元気もなかった。暗闇のなかで着替えをし、自分が生きなければならないこの恐ろしい場所を見ないようにした」
、と、ひきこもりだったことを暴露している。
なかでもけなされまくるのは、コクトーで、折にふれてコクトーの悪口が書いてある。
「スーポーとエリュアールが、いつもコクトーのことを話題にするときに、どんなに侮蔑の思いを込めて話していたか、いつも2人がコクトーをどんなに避けていたかはよく知られている」
「サティが『雄鶏とアルルカン』(コクトーの1918年の作品)を読んでどれだけ憤激し、アドリエンヌ・モリニエの店へねじ込んで行ったか、サティの支持者たちが2度とコクトーのことを口にしないように求めたか」
「ルヴェルディとスーポーとブルトンは、ほとんど評判にならなかった『喜望峰』(コクトーの1919年の作品)について抱いていた批判を隠そうともしなかった」
などなど。
あと、こりゃ面白いな、と思ったものをひとつ。
ディアギレフ劇団の公演で黒貂の襟巻きの盗難騒ぎがあったとき、奇矯な格好をしていたツァラが支配人から「怪しいやつ」と目をつけられており、嫌疑がかけられた。ツァラの疑いが晴れたときの、エリュアールとブルトンの言葉をアラゴンがひいている。
エリュアールは「思ってもみたまえ、もしこのような珍事の噂が広まって、2、3回こんな風に評判が落ちてしまったら、われわれの書くものもおしまいだ。すっかり台なしだぜ」
ブルトンは「ぼくは詩人よりも泥棒と見なされた方がいいよ」
アラゴンはこう言う。
「この2つの台詞は、ダダ運動の歴史におけるさまざまな波乱の芽を含んでいる」
たしかに!
「現代文学史計画」の項目の極端に少ない「序論」と「結論」のみ、ここに引いておこう。
この内、実際に書かれて、読めるのは序論の「アガディール」だけだ。
「序論」
アガディール
ルーヴルでの盗難
未来主義
ロシアバレー
ニック・カーター
ダンカン兄弟
「結論」
1922年初夏における精神の状態
ダダはなぜ世界を救済できなかったか
新しい鉄道文学の前兆、シャトーブリアンとマックス・ジャコブがその典型となるだろう
反動の波
まだ首つり自殺をしなかった何人かの人たち
すべてが分類される
普遍的な凡庸さ
いかにして歴史が書かれるか
ウ〜ん、書いててほしかった!
サップはもともと肉体が大きいだけの男だったのが、本来の姿に戻りきったか、という感じ。
山本KIDは親族まとめて、まるで下手な劇画だ。
カンセコも相手がクリス・ジェリコだったら、某映画スターを相手にしたときみたいに花を持たせてくれたろうに。
ペケーニョはなぜ所と再戦しなかったんだろう。
ルイ・アラゴンの『ダダ追想』を読んだ。
ダダの時代の随想がまとめられているが、「追想」とタイトルにあるが、執筆されたのは1923年頃のことになる。したがって、当時の熱気やいざこざが新鮮に描かれている。
本書の巻頭に載せられた『現代文学史計画』という「目次」は、『リテラチュール』4号(1922年9月)に掲載されたもので、ダダの歴史の見取り図として興味深い。
それは、「序論」「1913年から大戦まで」「1914年8月1日からアポリネールの死(1918年11月10日)まで」「休戦からダダまで(1918年11月から1920年1月)」「ダダ(1920年1月から1921年10月)」「ダダ以後(1921年10月から現在まで」「結論」と、区分けされている。
その項目を眺めているだけで、いろんな思いを馳せることもできるし、もしもこの計画が実現したならどれだけ大部の書物になったか、と想像してワクワクすることも可能だ。
以下、目次。
凡例
序文−草稿の経緯について−
テクストについての注記
現代文学史計画
アガディール
『吸血鬼』
『ペレアス』再演
ポール・ヴァレリーの『若きパルク』出版
ピエール・アルベール=ビロ
アンドレ・ジッド
アンドレ・ジッド(その2)
『リテラチュール』誌の創刊
レオンス・ローザンベール画廊でのルヴェルディのマチネー
トリスタン・ツァラのパリ到着
最初の『リテラチュール』の金曜日(その1)
最初の『リテラチュール』の金曜日(その2)
フォーブールのマニフェスタシオン
ミス・バーネイ邸におけるポール・ヴァレリー
クレマン・パンサール(1885−1922)
1921年、大いなるダダの季節
ポヴォロツキー画廊におけるピカビア展のヴェルニサージュ
「髭の生えた心臓」の夕べ(1923年7月6日)
幻像の画家マックス・エルンスト
さまざまな小説の1年(1922年7月−1923年8月)
「アガディール」は「現代文学史計画」の「序論」の筆頭にあげられている項目で、本書はアラゴンが書こうとしていた「現代文学史計画」の書けた部分を年代順に並べたものだと言えよう。
僕にとっては偉大な作家や有名人たちが、アラゴンの筆によって歯に衣着せぬ表現をなされているところもあって、面白い。
たとえばアンドレ・ジッドについて、こんなふうに書いている。
「彼はいつでも時流に精通していたいと願ったが、実際には何も理解できないので、時流に暗いことに死ぬほど不安を感じていた」
ツァラについては、
「以前の彼は、恐れおののきながら自分の部屋に閉じ籠っていて、そこから外出することもできず、またその元気もなかった。暗闇のなかで着替えをし、自分が生きなければならないこの恐ろしい場所を見ないようにした」
、と、ひきこもりだったことを暴露している。
なかでもけなされまくるのは、コクトーで、折にふれてコクトーの悪口が書いてある。
「スーポーとエリュアールが、いつもコクトーのことを話題にするときに、どんなに侮蔑の思いを込めて話していたか、いつも2人がコクトーをどんなに避けていたかはよく知られている」
「サティが『雄鶏とアルルカン』(コクトーの1918年の作品)を読んでどれだけ憤激し、アドリエンヌ・モリニエの店へねじ込んで行ったか、サティの支持者たちが2度とコクトーのことを口にしないように求めたか」
「ルヴェルディとスーポーとブルトンは、ほとんど評判にならなかった『喜望峰』(コクトーの1919年の作品)について抱いていた批判を隠そうともしなかった」
などなど。
あと、こりゃ面白いな、と思ったものをひとつ。
ディアギレフ劇団の公演で黒貂の襟巻きの盗難騒ぎがあったとき、奇矯な格好をしていたツァラが支配人から「怪しいやつ」と目をつけられており、嫌疑がかけられた。ツァラの疑いが晴れたときの、エリュアールとブルトンの言葉をアラゴンがひいている。
エリュアールは「思ってもみたまえ、もしこのような珍事の噂が広まって、2、3回こんな風に評判が落ちてしまったら、われわれの書くものもおしまいだ。すっかり台なしだぜ」
ブルトンは「ぼくは詩人よりも泥棒と見なされた方がいいよ」
アラゴンはこう言う。
「この2つの台詞は、ダダ運動の歴史におけるさまざまな波乱の芽を含んでいる」
たしかに!
「現代文学史計画」の項目の極端に少ない「序論」と「結論」のみ、ここに引いておこう。
この内、実際に書かれて、読めるのは序論の「アガディール」だけだ。
「序論」
アガディール
ルーヴルでの盗難
未来主義
ロシアバレー
ニック・カーター
ダンカン兄弟
「結論」
1922年初夏における精神の状態
ダダはなぜ世界を救済できなかったか
新しい鉄道文学の前兆、シャトーブリアンとマックス・ジャコブがその典型となるだろう
反動の波
まだ首つり自殺をしなかった何人かの人たち
すべてが分類される
普遍的な凡庸さ
いかにして歴史が書かれるか
ウ〜ん、書いててほしかった!
『あなたまかせのお話』
2009年5月27日 読書
レーモン・クノーの『あなたまかせのお話』を読んだ。
クノーの短編はここにほとんど収録されているらしい。
前半は、短編集。後半は、対談。
以下、目次。
「運命」
ラストはこんなふうにしめくくられる。
『そもそもこの話はちっとも面白くない。幸いこれでおしまいだ。お気に召したかどうかなんてどうでもいい』
「その時精神は...」
パタフィジック天文学。
ほとんどの物体は落下しない、として、大気中のほこり、鳥、雲、風船、飛行機、惑星、星、始祖鳥などを挙げ、行の中間に浮かせて書かれたりしてる。
また、月という概念は洋梨型の概念だとして、他に洋梨型概念として国際連盟とか旗などを例示する。一方、太陽という概念は卵型で、同じく卵型をしているものにキリスト、無名戦士などを挙げる。
物事を適当な二分法で示しているのかな、と思った矢先に、「戦争はシガーカッター型の概念である」「夜明けはどくろ型である」「雨傘はタイプライター型である」などとたたみかける。こりゃ面白い。
「ささやかな名声」
反ニュートン主義者の亡霊が、死後も自分の名声を気にして、自分のことを宣伝する。
ロダーリの『二度生きたランベルト』を思い出した。クノーのほうは既に死んでいるんだけど。
「パニック」
神経質に怯えて逃げ出す泊まり客と、何のことだか気にもしない支配人と下女。
「何某という名の若きフランス人1、2」
1、金ほしさに強盗に入るはずなのに、なぜか123456789の平方根を頭のなかで計算する何某。
2、タクシーに財布を置き忘れたかも、という男。自らすすんで身体検査してくれと申し出た何某のポケットから盗んだ財布が見つかった。
逃げ出して、かねてから用意してあった車に乗り込み、これで逃げられたかと思ったら、なぜか何某は車中で自殺。
「ディノ」
色も品種も思い出せない、そして、目に見えない犬、ディノとの冒険の旅。
犬に去られて、はっと気づくと、私は急行列車の指定席にいた。
「森のはずれで」
しゃべる犬、しゃべる猿
「通りすがりに ある悲劇に先立つ一幕、さらに一幕」
単なる通行人が物語の中心人物になりかけるが、終電にまけるシチュエーション。
ほとんど同じ筋立てで、男女がかわって反復。
「アリス、フランスに行く」
小麦粉で走る機関車の中でアリスがちょっとした冒険。
(インクなしのペンでひとこと書く、という冒険。うっかりふたこと書いて怒られる)
「フランスのカフェ」
25年ぶりに帰ってきたル・アーヴルのスケッチ。
『廃墟、売春、愚行、これらはいつでも詩人の心を慰めてくれる』
「血も凍る恐怖」
極端な「こわがり」が夜中にトイレにいく冒険。
「実在する気配のない虚無の存在」とか「存在感ある実在の虚無」だとか「存在なき虚無なき実在の気配」だとか「実在の気配のような虚無なき存在物」だとか「実在する虚無の気配のような存在」に怯えまくる。
「トロイの馬」
場末の酒場でのなにげない情景。
ただ、ひとつ違っていたのは、客のひとりは馬だったのです。
「エミール・ボーウェン著『カクテルの本』の序文」
「尾を切った馬」という意味をもつ「カクテル」。
そのことについて、バーで馬にからまれた思い出。
「(鎮静剤の正しい使い方について)1、2、」
鎮静剤が必要です、と言われるケースを2パターン。
「加法の空気力学的特性に関する若干の簡潔なる考察」
2+2=4の証明時に風速が考慮されてこなかったことを指摘する論文。
もしも風速が強ければ、数字が倒れたり、+が吹き飛んだりして、2=4になる可能性があるのだ。
「パリ近郊のよもやまばなし」
カフェや路上での辻占のようなエピソード
「言葉のあや」
英語でぜんぜん別の意味になるフランス語の表現についての憶測理論。
「あなたまかせのお話」
ゲームブック的ストーリー。
豆スープの悪夢をみる豆のはなし。
「夢の話をたっぷりと」
夢日記の記述かと思ったら、めざめているときのエピソードを夢らしく表現しただけの数々。
「附録 レーモン・クノーとの対話」
12回にわけて文芸ジャーナリスト、ジョルジュ・シャルボニエと対談したラジオの記録。
前半は言語についてが中心、後半は文学、ウリポの紹介など。
文学は「イリアス」型と「オデュッセイア」型に二分される(歴史と関わるか、個人の物語か)とか、フランス語は外国語に頼らない話とか、はさみで切って一生読み切れないバリエーションをもつ『百兆の詩篇』とか、興味深い話題がたっぷり。
今回の翻訳では、版権の関係で2編が訳出されなかった。
ミシェル・レリスの序文とともに、いずれ読める日が来るのを待とう。
クノーの短編はここにほとんど収録されているらしい。
前半は、短編集。後半は、対談。
以下、目次。
「運命」
ラストはこんなふうにしめくくられる。
『そもそもこの話はちっとも面白くない。幸いこれでおしまいだ。お気に召したかどうかなんてどうでもいい』
「その時精神は...」
パタフィジック天文学。
ほとんどの物体は落下しない、として、大気中のほこり、鳥、雲、風船、飛行機、惑星、星、始祖鳥などを挙げ、行の中間に浮かせて書かれたりしてる。
また、月という概念は洋梨型の概念だとして、他に洋梨型概念として国際連盟とか旗などを例示する。一方、太陽という概念は卵型で、同じく卵型をしているものにキリスト、無名戦士などを挙げる。
物事を適当な二分法で示しているのかな、と思った矢先に、「戦争はシガーカッター型の概念である」「夜明けはどくろ型である」「雨傘はタイプライター型である」などとたたみかける。こりゃ面白い。
「ささやかな名声」
反ニュートン主義者の亡霊が、死後も自分の名声を気にして、自分のことを宣伝する。
ロダーリの『二度生きたランベルト』を思い出した。クノーのほうは既に死んでいるんだけど。
「パニック」
神経質に怯えて逃げ出す泊まり客と、何のことだか気にもしない支配人と下女。
「何某という名の若きフランス人1、2」
1、金ほしさに強盗に入るはずなのに、なぜか123456789の平方根を頭のなかで計算する何某。
2、タクシーに財布を置き忘れたかも、という男。自らすすんで身体検査してくれと申し出た何某のポケットから盗んだ財布が見つかった。
逃げ出して、かねてから用意してあった車に乗り込み、これで逃げられたかと思ったら、なぜか何某は車中で自殺。
「ディノ」
色も品種も思い出せない、そして、目に見えない犬、ディノとの冒険の旅。
犬に去られて、はっと気づくと、私は急行列車の指定席にいた。
「森のはずれで」
しゃべる犬、しゃべる猿
「通りすがりに ある悲劇に先立つ一幕、さらに一幕」
単なる通行人が物語の中心人物になりかけるが、終電にまけるシチュエーション。
ほとんど同じ筋立てで、男女がかわって反復。
「アリス、フランスに行く」
小麦粉で走る機関車の中でアリスがちょっとした冒険。
(インクなしのペンでひとこと書く、という冒険。うっかりふたこと書いて怒られる)
「フランスのカフェ」
25年ぶりに帰ってきたル・アーヴルのスケッチ。
『廃墟、売春、愚行、これらはいつでも詩人の心を慰めてくれる』
「血も凍る恐怖」
極端な「こわがり」が夜中にトイレにいく冒険。
「実在する気配のない虚無の存在」とか「存在感ある実在の虚無」だとか「存在なき虚無なき実在の気配」だとか「実在の気配のような虚無なき存在物」だとか「実在する虚無の気配のような存在」に怯えまくる。
「トロイの馬」
場末の酒場でのなにげない情景。
ただ、ひとつ違っていたのは、客のひとりは馬だったのです。
「エミール・ボーウェン著『カクテルの本』の序文」
「尾を切った馬」という意味をもつ「カクテル」。
そのことについて、バーで馬にからまれた思い出。
「(鎮静剤の正しい使い方について)1、2、」
鎮静剤が必要です、と言われるケースを2パターン。
「加法の空気力学的特性に関する若干の簡潔なる考察」
2+2=4の証明時に風速が考慮されてこなかったことを指摘する論文。
もしも風速が強ければ、数字が倒れたり、+が吹き飛んだりして、2=4になる可能性があるのだ。
「パリ近郊のよもやまばなし」
カフェや路上での辻占のようなエピソード
「言葉のあや」
英語でぜんぜん別の意味になるフランス語の表現についての憶測理論。
「あなたまかせのお話」
ゲームブック的ストーリー。
豆スープの悪夢をみる豆のはなし。
「夢の話をたっぷりと」
夢日記の記述かと思ったら、めざめているときのエピソードを夢らしく表現しただけの数々。
「附録 レーモン・クノーとの対話」
12回にわけて文芸ジャーナリスト、ジョルジュ・シャルボニエと対談したラジオの記録。
前半は言語についてが中心、後半は文学、ウリポの紹介など。
文学は「イリアス」型と「オデュッセイア」型に二分される(歴史と関わるか、個人の物語か)とか、フランス語は外国語に頼らない話とか、はさみで切って一生読み切れないバリエーションをもつ『百兆の詩篇』とか、興味深い話題がたっぷり。
今回の翻訳では、版権の関係で2編が訳出されなかった。
ミシェル・レリスの序文とともに、いずれ読める日が来るのを待とう。
『生きさせる思想 記憶の解析、生存の肯定』
2009年5月26日 読書
小森陽一と雨宮処凛による対談『生きさせる思想 記憶の解析、生存の肯定』を読んだ。
以下、目次
はじめに/雨宮処凛
1、「90年代」から今が見えてくる
「ちびまる子ちゃん」と競争
「人生ごと人質に」とられて
「受験勉強なんか意味ない」
リストカットとバンギャル生活
フリーターの「自由」と現実
雇用の「規制緩和」ということ
脅かされる人間の尊厳と九条
政治の右傾化と「格差」、貧困
「豊かさ」とか「平和」とかいわれても
サブカル、右翼、「大きな物語」
2、暴力と思考停止の世界で
「それをお前らが言うなよ」と
書くことで自分をすくい上げて
言葉を失った経験とバッシング社会
「恐怖と怒りは紙一重」がここでも
思考停止の背後にある欲望
新たな変革が求められる時代
3、貧困の蔓延と人々が精神を病む国
教育課程からの排除と背景
「不登校その後」と「氷河期」と
リクルート事件とフリーター
ニートやフリーターと親子対立
新自由主義は家族を利用する
メンヘラーたちとデモで再会した
自傷の競い合い、ネット心中
「今を楽しむ」作法とその行方
自分でなく社会に怒りを向ける
4、無条件に生存を肯定する運動
根本的にひっくり返す言葉
自分を肯定できないと怒れない
競争原理と「自己責任」論の土壌
くすぶる罪障感と「免責共同体」
「人は一人で生きていける」のか
恋人、友達ではなく「同志」
役立たずでものっさばっていい
「幸せのハードル」を下げるとは
贈与の原理の具体化のために
おわりに/小森陽一
一見、なまぬるいことで苦しんでいるように見えても、そのなまぬるさを指摘したって苦しさが減るわけではなく、さらに苦しみを吐露することも連帯することもできなくなってしまう。これは逃げ場のない悪い流れだ。
厳しかった体験や過去を例に出して、今の苦しみを緩和することはできないのだ。
この本読んでいて思い出したことがある。
モダンチョキチョキズのファンクラブの会報の編集長にむりやりなって、好き勝手に作らせてもらっていた時期がある。
会報にのせるために、ボーカルのマリちゃんと、林茂助さんの対談に立ち会っていたときのことだ。
そのとき、マリちゃんは友達よりも、同じ目標をもって進む同志や、仕事を一緒にする同僚の大切さを力説したのだ。かなり強い口調だったので、「おや?」と驚いたほどだった。
本書で雨宮処凛が「同志」について語っているときの「恋人、友達ではなく同志」というのと二重写しになって甦った。
そして、今さらながら、あのとき、マリちゃんはたたかっていたんだな、とわかったのだ。
もちろん、僕はそのとき、そんなことを察するだけの人間の深さも度量もなく、マリちゃんと共闘するだけの準備も何もなかったのだ。
はやく人間になりたい。
以下、目次
はじめに/雨宮処凛
1、「90年代」から今が見えてくる
「ちびまる子ちゃん」と競争
「人生ごと人質に」とられて
「受験勉強なんか意味ない」
リストカットとバンギャル生活
フリーターの「自由」と現実
雇用の「規制緩和」ということ
脅かされる人間の尊厳と九条
政治の右傾化と「格差」、貧困
「豊かさ」とか「平和」とかいわれても
サブカル、右翼、「大きな物語」
2、暴力と思考停止の世界で
「それをお前らが言うなよ」と
書くことで自分をすくい上げて
言葉を失った経験とバッシング社会
「恐怖と怒りは紙一重」がここでも
思考停止の背後にある欲望
新たな変革が求められる時代
3、貧困の蔓延と人々が精神を病む国
教育課程からの排除と背景
「不登校その後」と「氷河期」と
リクルート事件とフリーター
ニートやフリーターと親子対立
新自由主義は家族を利用する
メンヘラーたちとデモで再会した
自傷の競い合い、ネット心中
「今を楽しむ」作法とその行方
自分でなく社会に怒りを向ける
4、無条件に生存を肯定する運動
根本的にひっくり返す言葉
自分を肯定できないと怒れない
競争原理と「自己責任」論の土壌
くすぶる罪障感と「免責共同体」
「人は一人で生きていける」のか
恋人、友達ではなく「同志」
役立たずでものっさばっていい
「幸せのハードル」を下げるとは
贈与の原理の具体化のために
おわりに/小森陽一
一見、なまぬるいことで苦しんでいるように見えても、そのなまぬるさを指摘したって苦しさが減るわけではなく、さらに苦しみを吐露することも連帯することもできなくなってしまう。これは逃げ場のない悪い流れだ。
厳しかった体験や過去を例に出して、今の苦しみを緩和することはできないのだ。
この本読んでいて思い出したことがある。
モダンチョキチョキズのファンクラブの会報の編集長にむりやりなって、好き勝手に作らせてもらっていた時期がある。
会報にのせるために、ボーカルのマリちゃんと、林茂助さんの対談に立ち会っていたときのことだ。
そのとき、マリちゃんは友達よりも、同じ目標をもって進む同志や、仕事を一緒にする同僚の大切さを力説したのだ。かなり強い口調だったので、「おや?」と驚いたほどだった。
本書で雨宮処凛が「同志」について語っているときの「恋人、友達ではなく同志」というのと二重写しになって甦った。
そして、今さらながら、あのとき、マリちゃんはたたかっていたんだな、とわかったのだ。
もちろん、僕はそのとき、そんなことを察するだけの人間の深さも度量もなく、マリちゃんと共闘するだけの準備も何もなかったのだ。
はやく人間になりたい。
『向上心について 人間の大きくなりたいという欲望』
2009年5月25日 読書
今日はだらだらと書いてみる。(いつもはあんな下手な文章でも、一応推敲したり、書き過ぎたかな、と思うところを削ったりしているのだ)
ベルナール・スティグレールの『向上心について 人間の大きくなりたいという欲望』を読んだ。スティグレールの本に関しては、今のところ、はずれ無しだ。本書も、まあまあ。「小さな講演会」シリーズの1冊。前半は講演、後半は質疑応答をおさめている。
タイトルだけ見れば、自己啓発のビジネス書みたいだが、タイトルの本来の意味は、後半の「人間の大きくなりたいという欲望」の方にある。直立二足歩行だって「大きくなりたいという欲望」だ、というところから説明しているのだから、見据えるところは大きい。
適当な日本語訳がないから、とつけられた「向上心」には、その対極として「怠惰」が設定されている。
この講演会は、若い世代に向けたものであるが、メッセージはむしろその親、大人の世代に発せられている。大人ならば怠惰に陥ってしまう傾向を自ら修正して、「向上心」に向けることができるが、若い世代は、大人の手助けが必要だ、と説いている。
また、テレビの弊害について説くところも、スティグレールらしい。
本来、親が教えねばならないことを、テレビにまかせてしまっている、とか。
僕みたいな、毎日テレビ漬けの生活を送っている人間にとっては耳の痛い話だ。そういえば、僕のものの考え方はいかにも浅いし、軽いし、一面的だ。とおりいっぺんの知識しかないし、雑学があれば物知りだと思い込んでいるふしもある。テレビのニュース解説で誰かが言ってたことを鵜のみにすることなど日常茶飯事だし、テレビで伝えられる事柄をはなから疑いもしていない。僕がワイドショーやネットで顕著な嫌韓、嫌中、右傾化などに反発しているのは、単なる天の邪鬼であって、深い思索があってのことではないのだ。第一、韓国にも北朝鮮にも中国にも、ましてや中東にも行ったことがないくせに、テレビで伝えられる映像やコメントをもとにして、意見らしきものをこさえる反応をしているだけなのだ。
20日付けの「ハアレツ」にあったニュース。ガザからロケット砲がイスラエルに打ち込まれ、1人が軽傷を負った。2ヶ月ぶりの攻撃だった。すぐさまイスラエルはガザを空爆し、物資を搬入するためのトンネル4つと、工場2つを破壊したそうだ。ガザは現在もイスラエルによって占領、封鎖されており、食糧や医薬品、建築資材などの物資を搬入するルートがない。世界の各国はガザ復興のために金を出しているが、イスラエルがルートを封鎖しているため、何も届いていない、とは、先日ETV特集「ガザ なぜ悲劇は繰り返されるのか」で報告されていたところだ。
と、まあこんなニュースをだらだらと書いたのは、こうしたニュースと、テレビから得た情報をつきあわせてみても、僕には、それについての意見が何もまとまらないってのを言いたかったのだ。まさしく、スティグレールが懸念するような、「怠惰」から脱却できない脳みそを抱え込んでしまっているのだ。
何とかしなくちゃ、と思うのは一見「向上心」のあらわれかとみえるが、そのとき思うだけで、これといって中東問題に関わろうとはしないのだから、「怠惰」なままだ。「今、起きる」と宣言して二度寝してるようなものか。
「人間の大きくなりたいという欲望」ということだけをとってみれば、僕はずっと「ちび」で、クラスでも屈指の背の低さを誇っていたが、そのことに関するコンプレックスはいっさい無かった。コンプレックスをもつだけの自意識にも欠けた、ぼーっとした児童だったのだ。現在では、「ちび」に加えて「でぶ」「はげ」「でっぱ」「色黒」「じじい」「めがね」と称号は増えたが、あんまり悩まない(めがねは全然かけていないので、事実と違うなあ、と思うが)。大きくなりたいという欲望どころか、怠惰の極地を驀進しているのである。
そういえば、「短小」「早漏」などといった下ネタ関連の栄誉ある称号も僕は獲得しているが、これもまた悩んでいない。毎日届く、膨大な数の親切なメールで、「ペニスが大きくなる」とか「逆援助交際」など、見知らぬ方々からありがたいアドバイスや申し出をいただいているが、怠惰な僕には届かない。むしろ、成長期にもっと悩んでおけば、巨根で遅漏な夜の帝王になれたかもしれず、多くの女性に捨てられずにすんだのかもしれない。「人間の大きくなりたいという欲望」とは、まさしくこういうことなのか、と思いいたれば、僕にはその手の欲望が欠けていたことに愕然とするのである。
今日はこれと言ってイベントはどこにも行かず、家で本読んで、録画しておいた番組見て、あと、書店に行ったくらい。怠惰だ。
書店では、コンビニ本によくある「サイコ画像」の本をぱらぱらと立ち読み。
ネットの住人であれば、たぶん見なれたネタばかりなのか。
僕も首のない少女を実際に見たことがあるが、それに似た画像もあった。
こういうのは、好奇心にまかせてついついのぞいてみるけど、心がすさむ。
また、今出ている「DAYS JAPAN」という写真誌には、処分されたばかりの死んだ犬たちの写真が載っていた。猫ばっかり飼っている女性の住む「猫屋敷」はよくあるが、犬ばかり飼っている家って、あんまりないんじゃないだろうか。
犬といえば、主従関係とか、支配とか、あるいは流行とか、そういうつまらない面がつきまとうような気がする。ペットショップってまあ、ほとんどが犬の店を意味しているし。でも、そういう愛玩犬ならまだましなのだ。番犬とか、猟犬とか、ああいう人間のいいなりになっている奴隷のような生物や、家畜はつまらない。猫はこれといって役にたたなくて、日がな1日ゴロゴロと寝てばかりいるのが、まるで自分を見ているようで、親近感がわくのだ。
ベルナール・スティグレールの『向上心について 人間の大きくなりたいという欲望』を読んだ。スティグレールの本に関しては、今のところ、はずれ無しだ。本書も、まあまあ。「小さな講演会」シリーズの1冊。前半は講演、後半は質疑応答をおさめている。
タイトルだけ見れば、自己啓発のビジネス書みたいだが、タイトルの本来の意味は、後半の「人間の大きくなりたいという欲望」の方にある。直立二足歩行だって「大きくなりたいという欲望」だ、というところから説明しているのだから、見据えるところは大きい。
適当な日本語訳がないから、とつけられた「向上心」には、その対極として「怠惰」が設定されている。
この講演会は、若い世代に向けたものであるが、メッセージはむしろその親、大人の世代に発せられている。大人ならば怠惰に陥ってしまう傾向を自ら修正して、「向上心」に向けることができるが、若い世代は、大人の手助けが必要だ、と説いている。
また、テレビの弊害について説くところも、スティグレールらしい。
本来、親が教えねばならないことを、テレビにまかせてしまっている、とか。
僕みたいな、毎日テレビ漬けの生活を送っている人間にとっては耳の痛い話だ。そういえば、僕のものの考え方はいかにも浅いし、軽いし、一面的だ。とおりいっぺんの知識しかないし、雑学があれば物知りだと思い込んでいるふしもある。テレビのニュース解説で誰かが言ってたことを鵜のみにすることなど日常茶飯事だし、テレビで伝えられる事柄をはなから疑いもしていない。僕がワイドショーやネットで顕著な嫌韓、嫌中、右傾化などに反発しているのは、単なる天の邪鬼であって、深い思索があってのことではないのだ。第一、韓国にも北朝鮮にも中国にも、ましてや中東にも行ったことがないくせに、テレビで伝えられる映像やコメントをもとにして、意見らしきものをこさえる反応をしているだけなのだ。
20日付けの「ハアレツ」にあったニュース。ガザからロケット砲がイスラエルに打ち込まれ、1人が軽傷を負った。2ヶ月ぶりの攻撃だった。すぐさまイスラエルはガザを空爆し、物資を搬入するためのトンネル4つと、工場2つを破壊したそうだ。ガザは現在もイスラエルによって占領、封鎖されており、食糧や医薬品、建築資材などの物資を搬入するルートがない。世界の各国はガザ復興のために金を出しているが、イスラエルがルートを封鎖しているため、何も届いていない、とは、先日ETV特集「ガザ なぜ悲劇は繰り返されるのか」で報告されていたところだ。
と、まあこんなニュースをだらだらと書いたのは、こうしたニュースと、テレビから得た情報をつきあわせてみても、僕には、それについての意見が何もまとまらないってのを言いたかったのだ。まさしく、スティグレールが懸念するような、「怠惰」から脱却できない脳みそを抱え込んでしまっているのだ。
何とかしなくちゃ、と思うのは一見「向上心」のあらわれかとみえるが、そのとき思うだけで、これといって中東問題に関わろうとはしないのだから、「怠惰」なままだ。「今、起きる」と宣言して二度寝してるようなものか。
「人間の大きくなりたいという欲望」ということだけをとってみれば、僕はずっと「ちび」で、クラスでも屈指の背の低さを誇っていたが、そのことに関するコンプレックスはいっさい無かった。コンプレックスをもつだけの自意識にも欠けた、ぼーっとした児童だったのだ。現在では、「ちび」に加えて「でぶ」「はげ」「でっぱ」「色黒」「じじい」「めがね」と称号は増えたが、あんまり悩まない(めがねは全然かけていないので、事実と違うなあ、と思うが)。大きくなりたいという欲望どころか、怠惰の極地を驀進しているのである。
そういえば、「短小」「早漏」などといった下ネタ関連の栄誉ある称号も僕は獲得しているが、これもまた悩んでいない。毎日届く、膨大な数の親切なメールで、「ペニスが大きくなる」とか「逆援助交際」など、見知らぬ方々からありがたいアドバイスや申し出をいただいているが、怠惰な僕には届かない。むしろ、成長期にもっと悩んでおけば、巨根で遅漏な夜の帝王になれたかもしれず、多くの女性に捨てられずにすんだのかもしれない。「人間の大きくなりたいという欲望」とは、まさしくこういうことなのか、と思いいたれば、僕にはその手の欲望が欠けていたことに愕然とするのである。
今日はこれと言ってイベントはどこにも行かず、家で本読んで、録画しておいた番組見て、あと、書店に行ったくらい。怠惰だ。
書店では、コンビニ本によくある「サイコ画像」の本をぱらぱらと立ち読み。
ネットの住人であれば、たぶん見なれたネタばかりなのか。
僕も首のない少女を実際に見たことがあるが、それに似た画像もあった。
こういうのは、好奇心にまかせてついついのぞいてみるけど、心がすさむ。
また、今出ている「DAYS JAPAN」という写真誌には、処分されたばかりの死んだ犬たちの写真が載っていた。猫ばっかり飼っている女性の住む「猫屋敷」はよくあるが、犬ばかり飼っている家って、あんまりないんじゃないだろうか。
犬といえば、主従関係とか、支配とか、あるいは流行とか、そういうつまらない面がつきまとうような気がする。ペットショップってまあ、ほとんどが犬の店を意味しているし。でも、そういう愛玩犬ならまだましなのだ。番犬とか、猟犬とか、ああいう人間のいいなりになっている奴隷のような生物や、家畜はつまらない。猫はこれといって役にたたなくて、日がな1日ゴロゴロと寝てばかりいるのが、まるで自分を見ているようで、親近感がわくのだ。
『大人のいない国 成熟社会の未熟なあなた』、ナショナル・トレジャー
2009年5月22日 読書鷲田清一と内田樹による『大人のいない国 成熟社会の未熟なあなた』を読んだ。
以下、目次。
プロローグ 成熟と未熟−もう一つの大事なものを護るために/鷲田清一
第1章 対談「大人学」のすすめ/鷲田清一&内田樹
クレーマー天国「失われた責任者を求めて」
「妥協しない生き方」の落とし穴
本物と偽物を見分ける能力をつけましょう
人は年をとるほど「多重人格化」していく
第2章 大人の「愛国論」/内田樹
「惨状と堕落」を嘆く人々
「自分好き」に終わる同胞愛
現代国家は「均質的集団」になり得ない
「不快な隣人たち」を受け容れられるか
第3章 「弱い者」に従う自由/鷲田清一
相互に依存しなければ何もできない人間
「可愛い」ができなければ「がんばれ」
誰もが「じぶんを担いきれない」状況にある
弱いものに従うということ
第4章 呪いと言論/内田樹
「匿名」で発信する理由
ネット上を行き交う「呪」の言葉
ネットへの書き込みで人が死ぬ社会
「言論の自由」はどのように誤解されているか
私の言葉を吟味し査定するのは「他者」である
「受信者への敬意」あるいは「ディセンシー」
第5章 大人の作法/鷲田清一
「席」というフィクション
3というポジション
陽水さんの「あいまいな」メッセージ
第6章 もっと矛盾と無秩序を/内田樹
大人たちの発する「矛盾した」メッセージ
子供が子供のままでいるという「災厄」
「価値観が同じ人との結婚」に潜むリスク
「子供を成熟させないシステム」を突き崩すには
内田樹が「未成熟な人間でも経営できる、操縦しやすく安定した社会システム」と揶揄して言うのが痛快。
ニコラス・ケイジ主演の「ナショナル・トレジャー」を見た。
アメリカ史を使ったゲーム的エンタテインメント作品。
やっぱり、これ、ゲームだなあ。
どうして今まで解けなかったのかが不思議なくらいにわかりやすく簡単な謎ばかりで、そこはほれ、アメリカの歴史の浅さを露呈してしまった感すら覚える。見つけた宝だって、大半はよその国から奪ってきたものだし。
以下、目次。
プロローグ 成熟と未熟−もう一つの大事なものを護るために/鷲田清一
第1章 対談「大人学」のすすめ/鷲田清一&内田樹
クレーマー天国「失われた責任者を求めて」
「妥協しない生き方」の落とし穴
本物と偽物を見分ける能力をつけましょう
人は年をとるほど「多重人格化」していく
第2章 大人の「愛国論」/内田樹
「惨状と堕落」を嘆く人々
「自分好き」に終わる同胞愛
現代国家は「均質的集団」になり得ない
「不快な隣人たち」を受け容れられるか
第3章 「弱い者」に従う自由/鷲田清一
相互に依存しなければ何もできない人間
「可愛い」ができなければ「がんばれ」
誰もが「じぶんを担いきれない」状況にある
弱いものに従うということ
第4章 呪いと言論/内田樹
「匿名」で発信する理由
ネット上を行き交う「呪」の言葉
ネットへの書き込みで人が死ぬ社会
「言論の自由」はどのように誤解されているか
私の言葉を吟味し査定するのは「他者」である
「受信者への敬意」あるいは「ディセンシー」
第5章 大人の作法/鷲田清一
「席」というフィクション
3というポジション
陽水さんの「あいまいな」メッセージ
第6章 もっと矛盾と無秩序を/内田樹
大人たちの発する「矛盾した」メッセージ
子供が子供のままでいるという「災厄」
「価値観が同じ人との結婚」に潜むリスク
「子供を成熟させないシステム」を突き崩すには
内田樹が「未成熟な人間でも経営できる、操縦しやすく安定した社会システム」と揶揄して言うのが痛快。
ニコラス・ケイジ主演の「ナショナル・トレジャー」を見た。
アメリカ史を使ったゲーム的エンタテインメント作品。
やっぱり、これ、ゲームだなあ。
どうして今まで解けなかったのかが不思議なくらいにわかりやすく簡単な謎ばかりで、そこはほれ、アメリカの歴史の浅さを露呈してしまった感すら覚える。見つけた宝だって、大半はよその国から奪ってきたものだし。
『古代から来た未来人 折口信夫』
2009年5月21日 読書中沢新一の『古代から来た未来人 折口信夫』を読んだ。
以下、目次
序文 奇跡のような学問
第1章 「古代人」の心を知る
「いま」を生きられない人/「古代」の広がりと深さ/文字の奥を見通す眼/姿を変化する「タマ」/精霊ふゆる「ふゆ」/文学も宗教も突き抜けた思考
第2章 「まれびと」の発見
折口と柳田−「神」をめぐる視点/「まれびと」論の原点/「南洋」へのノスタルジー/「あの世=生命の根源」への憧れ
第3章 芸能史という宝物庫
芸能史を再構成した2人/芸能史への奇妙な共感/苛酷な旅からつかんだもの/芸能とは「不穏」なものである/不穏だからこそ「芸能」を愛す
<コラム>大阪人折口信夫
第4章 未来で待つ人
とびきりの新しさ/死霊は踊る/「あの世」への扉が開かれるとき/高野山と二上山とを結ぶ線/「日本」を超え「人類」を見る眼
第5章 大いなる転回
キリスト教との対話/未成立の宗教/「神道の宗教化」という主題/超宗教としての神道へ
第6章 心の未来のための設計図
神道の新しい方向/ムスビの神/三位一体の構造/折口のヴィジョン
コラムにもあるように、折口信夫は難波、日本橋、四天王寺にゆかりがある。僕の住んでいるところや、活動範囲そのまま。3つあわせて「何してん?」である。
先日のトークショーでも中沢新一は折口信夫の『死者の書』を話題にのぼらせていた。
生と死、という対比で言うと、「ししゃのしょ」と「せいしょ」が対比できるような気がするから不思議である。不思議なのは、僕の頭ですか?
古代の思想を特徴づける類化性能に着目し、いまだ実現せぬ理念としての神道を考えた折口信夫を、中沢新一は「古代から来た未来人」と言ってみたのである。
中沢新一は本書でこう言っている。
「能にしても歌舞伎にしても、今日わたしたちが日本の古典芸能とよんでいるものの多くは、とてつもなく古いルーツをもっている」
古事記、日本書紀どころか、人類の表現活動のはじまりにまでつながっている、としている。
なるほど。
そういう視点があるのなら、トークショーのときの質疑応答のときに、質問者が遠くまで足を運んで見に行ったものに対して「そういうのは意外と歴史が新しいんですよ」などと意地悪なコメントしなくてもよかったのにな、と思った。
まあ、本書でも、表現の仕方にハッタリに近いようなものがあったりして、そういうものいいが面白いからこそ、僕は中沢新一を楽しく読めるわけだが。
以下、目次
序文 奇跡のような学問
第1章 「古代人」の心を知る
「いま」を生きられない人/「古代」の広がりと深さ/文字の奥を見通す眼/姿を変化する「タマ」/精霊ふゆる「ふゆ」/文学も宗教も突き抜けた思考
第2章 「まれびと」の発見
折口と柳田−「神」をめぐる視点/「まれびと」論の原点/「南洋」へのノスタルジー/「あの世=生命の根源」への憧れ
第3章 芸能史という宝物庫
芸能史を再構成した2人/芸能史への奇妙な共感/苛酷な旅からつかんだもの/芸能とは「不穏」なものである/不穏だからこそ「芸能」を愛す
<コラム>大阪人折口信夫
第4章 未来で待つ人
とびきりの新しさ/死霊は踊る/「あの世」への扉が開かれるとき/高野山と二上山とを結ぶ線/「日本」を超え「人類」を見る眼
第5章 大いなる転回
キリスト教との対話/未成立の宗教/「神道の宗教化」という主題/超宗教としての神道へ
第6章 心の未来のための設計図
神道の新しい方向/ムスビの神/三位一体の構造/折口のヴィジョン
コラムにもあるように、折口信夫は難波、日本橋、四天王寺にゆかりがある。僕の住んでいるところや、活動範囲そのまま。3つあわせて「何してん?」である。
先日のトークショーでも中沢新一は折口信夫の『死者の書』を話題にのぼらせていた。
生と死、という対比で言うと、「ししゃのしょ」と「せいしょ」が対比できるような気がするから不思議である。不思議なのは、僕の頭ですか?
古代の思想を特徴づける類化性能に着目し、いまだ実現せぬ理念としての神道を考えた折口信夫を、中沢新一は「古代から来た未来人」と言ってみたのである。
中沢新一は本書でこう言っている。
「能にしても歌舞伎にしても、今日わたしたちが日本の古典芸能とよんでいるものの多くは、とてつもなく古いルーツをもっている」
古事記、日本書紀どころか、人類の表現活動のはじまりにまでつながっている、としている。
なるほど。
そういう視点があるのなら、トークショーのときの質疑応答のときに、質問者が遠くまで足を運んで見に行ったものに対して「そういうのは意外と歴史が新しいんですよ」などと意地悪なコメントしなくてもよかったのにな、と思った。
まあ、本書でも、表現の仕方にハッタリに近いようなものがあったりして、そういうものいいが面白いからこそ、僕は中沢新一を楽しく読めるわけだが。
先日来、親戚のおばさんが入院して危篤状態だったが、どうやらしゃべれる程度には持ち直しているようだ。
何はともあれ、よかった。
新型インフルエンザも、パニック起こすまでもなく沈静しつつある。
マスク購入にあわてたり、イベント中止とか、つまらない方向で騒ぎがあったが、某国の空爆などには平気なくせに、インフルエンザ程度であわてる輩の気がしれない。命を何だと思っているのか。市民が軍に殺されることよりも、命に別状ない発熱の方がおおごとなのか?
ロバート・ファン・ヒューリックの『東方の黄金』を読んだ。
狄(ディー)知事シリーズの時系列第1作。
狄知事が平来(ポンライ)知事に任命されるところから物語ははじまる。
平来では前任の知事が毒殺されており、その知事の亡霊が目撃されているだけでなく、嵐の夜には墓地の屍が起き出し、妖怪変化が海霧に乗って徘徊すると言い伝えがある。おまけに、森には人喰い虎がいるという。
狄知事は、前知事殺害、消えた新妻、僧侶殺害などの事件の数々を解明していく。
おまえらは、ブレーキのきかない助さん格さんか、と思わせる助手、馬栄(マーロン)、喬泰(チャオタイ)との出会いもある。2人は狄知事を襲う賊(本人たちは義賊と言ってる)だったのだ。2人を相手にわたりあう狄知事の強さって、はかりしれない!
クライマックス、大法要で悪事をあばくスペクタクルは、まるで、痛快娯楽時代劇のようだった。そうか。唐の時代が舞台だから、時代劇にはちがいない。
ラストの謎解きでは、「えっ」と本の冒頭部分を読み返したりした。油断ならない。
じつは、このシリーズ、中国の名前とか地名とか文化とか馴染みがないし、そんなに面白くないんじゃないか、とたかをくくっていたのだが、謎ときもアクションもスペクタクルも、めちゃくちゃ面白いじゃないか!
以下、章立てと、ネタバレ。
1.友3名はたもとを分かち
街道の2人と剣を交える
2.勝負つかずに白刃を引き
燕州の宿舎で杯を交わす
3.殺しの現場で説明を受け
無人の部屋で怪異に遭う
4.犯行現場をつぶさに調べ
銅の茶炉から秘密を窺う
5.好漢2名はめしを奢られ
船着場の異変を目撃する
6.酔眼もうろう月をうたい
水上娼家で敵娼に出会う
7.判事は漆箱の報告を受け
深更いとわず寺を訪ねる
8.富豪は新妻失踪を申立て
判事は道行をなぞりゆく
9.部下をひきいて農家捜索
桑下に見出す異なるもの
10.儒者は超俗ぶりを披瀝し
判事は難事件を説明する
11.白雲寺まで管長を表敬し
河岸で望外の美味を知る
12.あてが外れた情事の告白
漆工人はゆきがた知れず
13.連れだって舟でひと遊び
思わぬ首尾に転ぶ逢引き
14.判事は未遂2件を吟味し
未知の女がお裁きの場に
15.若い女が数奇ないきさつを物語り
老人は怪しき罪の数々を告白する
16.酒楼にあがって麺を頼み
古人の名裁きに感じ入る
17.老管長は大法要を厳修し
儒者は化けの皮を剥がれ
18.邪な陰謀が白日のもとに
黒幕の身元ついに割れる
人喰い虎の正体は人虎!
天井に塗った毒が蒸気で剥がれ落ちて毒混入!
朝鮮への武器輸出かと思いきや、逆に黄金を運び入れていた!
杖の中身は黄金!仏像の中身は黄金!
前知事の亡霊は、双子で、真相へ導くために姿を見せていた!
悪漢のなさけない付けひげ!
ラストは火刑法廷!大東京四谷怪談!
何はともあれ、よかった。
新型インフルエンザも、パニック起こすまでもなく沈静しつつある。
マスク購入にあわてたり、イベント中止とか、つまらない方向で騒ぎがあったが、某国の空爆などには平気なくせに、インフルエンザ程度であわてる輩の気がしれない。命を何だと思っているのか。市民が軍に殺されることよりも、命に別状ない発熱の方がおおごとなのか?
ロバート・ファン・ヒューリックの『東方の黄金』を読んだ。
狄(ディー)知事シリーズの時系列第1作。
狄知事が平来(ポンライ)知事に任命されるところから物語ははじまる。
平来では前任の知事が毒殺されており、その知事の亡霊が目撃されているだけでなく、嵐の夜には墓地の屍が起き出し、妖怪変化が海霧に乗って徘徊すると言い伝えがある。おまけに、森には人喰い虎がいるという。
狄知事は、前知事殺害、消えた新妻、僧侶殺害などの事件の数々を解明していく。
おまえらは、ブレーキのきかない助さん格さんか、と思わせる助手、馬栄(マーロン)、喬泰(チャオタイ)との出会いもある。2人は狄知事を襲う賊(本人たちは義賊と言ってる)だったのだ。2人を相手にわたりあう狄知事の強さって、はかりしれない!
クライマックス、大法要で悪事をあばくスペクタクルは、まるで、痛快娯楽時代劇のようだった。そうか。唐の時代が舞台だから、時代劇にはちがいない。
ラストの謎解きでは、「えっ」と本の冒頭部分を読み返したりした。油断ならない。
じつは、このシリーズ、中国の名前とか地名とか文化とか馴染みがないし、そんなに面白くないんじゃないか、とたかをくくっていたのだが、謎ときもアクションもスペクタクルも、めちゃくちゃ面白いじゃないか!
以下、章立てと、ネタバレ。
1.友3名はたもとを分かち
街道の2人と剣を交える
2.勝負つかずに白刃を引き
燕州の宿舎で杯を交わす
3.殺しの現場で説明を受け
無人の部屋で怪異に遭う
4.犯行現場をつぶさに調べ
銅の茶炉から秘密を窺う
5.好漢2名はめしを奢られ
船着場の異変を目撃する
6.酔眼もうろう月をうたい
水上娼家で敵娼に出会う
7.判事は漆箱の報告を受け
深更いとわず寺を訪ねる
8.富豪は新妻失踪を申立て
判事は道行をなぞりゆく
9.部下をひきいて農家捜索
桑下に見出す異なるもの
10.儒者は超俗ぶりを披瀝し
判事は難事件を説明する
11.白雲寺まで管長を表敬し
河岸で望外の美味を知る
12.あてが外れた情事の告白
漆工人はゆきがた知れず
13.連れだって舟でひと遊び
思わぬ首尾に転ぶ逢引き
14.判事は未遂2件を吟味し
未知の女がお裁きの場に
15.若い女が数奇ないきさつを物語り
老人は怪しき罪の数々を告白する
16.酒楼にあがって麺を頼み
古人の名裁きに感じ入る
17.老管長は大法要を厳修し
儒者は化けの皮を剥がれ
18.邪な陰謀が白日のもとに
黒幕の身元ついに割れる
人喰い虎の正体は人虎!
天井に塗った毒が蒸気で剥がれ落ちて毒混入!
朝鮮への武器輸出かと思いきや、逆に黄金を運び入れていた!
杖の中身は黄金!仏像の中身は黄金!
前知事の亡霊は、双子で、真相へ導くために姿を見せていた!
悪漢のなさけない付けひげ!
ラストは火刑法廷!大東京四谷怪談!
『ダンシング・ヴァニティ』
2009年5月19日 読書筒井康隆の『ダンシング・ヴァニティ』を読んだ。
巻末の参考資料に、東浩紀の『ゲーム的リアリズムの誕生』が挙げられており、その影響下に書かれた小説だと考えられるが、いや〜、こんなに凄い小説書いてくれるんなら、筒井康隆を刺激する本をみんなもっと書いてくれないものか、と願った。
同じシーンがバリエーション違いで繰り返される不思議な世界。
こういうシチュエーションは、テレビでは「ゲバゲバ90分」とか、「ドリフの大爆笑」でおなじみだし、漫才のパターンでもあり、また美少女ゲームでも繰り返される。
タイムスリップで同じシチュエーションを繰り返す映画や小説なども今まで山のように存在している。
ならば、見なれた手法なのか、というと、それがそうは思えない強烈さである。
何の説明も了解もないままにずれた反復を繰り返しているのが、その強烈さのもとの一部なのだろう。
こういう実験的な作品を、筒井康隆にまかせるのではなく、若い世代の作品として読んでみたい、とも思うのだが、若い世代が同じような発想で作品を書いても、それを出版しようという勇気ある出版社が不在だ、ということなのだろうか。逆にいえば、文章も練れていない若い書き手が前例として作品を出すよりも、こうして筒井康隆の作品として読んだ方が、読者としては、凄い作品に出会えるわけだから、よしとするべきか。
そういえば、埴谷雄高に、同じような読後感の本があったように思うが、どうも最近、脳がスカスカで、忘れっぽくて、覚えられなく、思い出せない。年をとると、こういう微妙にずれた反復世界を自然に生きてしまうのかもしれない。
巻末の参考資料に、東浩紀の『ゲーム的リアリズムの誕生』が挙げられており、その影響下に書かれた小説だと考えられるが、いや〜、こんなに凄い小説書いてくれるんなら、筒井康隆を刺激する本をみんなもっと書いてくれないものか、と願った。
同じシーンがバリエーション違いで繰り返される不思議な世界。
こういうシチュエーションは、テレビでは「ゲバゲバ90分」とか、「ドリフの大爆笑」でおなじみだし、漫才のパターンでもあり、また美少女ゲームでも繰り返される。
タイムスリップで同じシチュエーションを繰り返す映画や小説なども今まで山のように存在している。
ならば、見なれた手法なのか、というと、それがそうは思えない強烈さである。
何の説明も了解もないままにずれた反復を繰り返しているのが、その強烈さのもとの一部なのだろう。
こういう実験的な作品を、筒井康隆にまかせるのではなく、若い世代の作品として読んでみたい、とも思うのだが、若い世代が同じような発想で作品を書いても、それを出版しようという勇気ある出版社が不在だ、ということなのだろうか。逆にいえば、文章も練れていない若い書き手が前例として作品を出すよりも、こうして筒井康隆の作品として読んだ方が、読者としては、凄い作品に出会えるわけだから、よしとするべきか。
そういえば、埴谷雄高に、同じような読後感の本があったように思うが、どうも最近、脳がスカスカで、忘れっぽくて、覚えられなく、思い出せない。年をとると、こういう微妙にずれた反復世界を自然に生きてしまうのかもしれない。
石持浅海の『賢者の贈り物』を読んだ。
推理のあーでもないこーでもないを楽しむ短編集。
「金の携帯 銀の携帯」
ショップで出された代替機には電子マネーがチャージされていた。
さあ、5万円チャージされた携帯、5千円チャージされた携帯、何もチャージされていない携帯、どれを取る?
そして、その根拠は?
「ガラスの靴」
鍋パーティーのあと、残された女ものの靴1足。
誰かが間違えてサンダルをはいて帰ったようだ。
しかし、誰もそのことを申告してこない。
なぜ?そして、なぜ靴を忘れたのか?
「最も大きな掌」
創業者の1人で、経営能力はないが開発能力にたけている男。
修羅場をくぐり、対外的業務をこなす能力があるが、ハイテクに疎い男。
名門大学院で経営学を修めたが、まだ若い男。
時期社長の条件、もっとも大きな掌の持ち主はだれのこと?
「可食性手紙」
オブラートで作ったカンニングペーパーにオブラート製の手紙がまじっていた。
教師に見つかりそうになったのでとっさに口に入れてとかしてしまったが、さて、その手紙には何が書いてあったのか。
「賢者の贈り物」
最近デジカメに持ち替えた写真好きの男に、妻はフィルムをプレゼントした。
何を思って、彼女は夫にフィルムを贈ったのか。
「玉手箱」
人妻は、別れの際に箱を渡した。
「これを差し上げます。でも、この箱をあけてしまったら、もう2度とあえなくなるでしょう」
さて、箱の中身は何じゃいな?
「泡となって消える前に」
正体を隠してつきあっている彼女。
彼女はなぜ正体を隠すのか。
「経文を書く」
味オンチの男が高価なワイン蒐集にはまった。
彼を救うにはどうすればいい?
「最後のひと目盛り」
やけになって過食に走るわたしを飲み食いに誘う友人。
それは何故?
「木に登る」
株価暴落の可能性をつかんだ男。
その株を全財産はたいて買った友人は連絡のつかないジャングルの奥地にいる。
さて、どうする?
作品の大半は推理にあてられていて、ケメルマンとかアシモフなどの系列かと思わせる。
それぞれなるほど、それが最も適当なおさまるべき推理だな、と思わせるが、リドルストーリーで終わっている作品もあって、残念。
リドルストーリーそのものは大好きだが、このシリーズでは、なんらかの解答がほしかった。
推理のあーでもないこーでもないを楽しむ短編集。
「金の携帯 銀の携帯」
ショップで出された代替機には電子マネーがチャージされていた。
さあ、5万円チャージされた携帯、5千円チャージされた携帯、何もチャージされていない携帯、どれを取る?
そして、その根拠は?
「ガラスの靴」
鍋パーティーのあと、残された女ものの靴1足。
誰かが間違えてサンダルをはいて帰ったようだ。
しかし、誰もそのことを申告してこない。
なぜ?そして、なぜ靴を忘れたのか?
「最も大きな掌」
創業者の1人で、経営能力はないが開発能力にたけている男。
修羅場をくぐり、対外的業務をこなす能力があるが、ハイテクに疎い男。
名門大学院で経営学を修めたが、まだ若い男。
時期社長の条件、もっとも大きな掌の持ち主はだれのこと?
「可食性手紙」
オブラートで作ったカンニングペーパーにオブラート製の手紙がまじっていた。
教師に見つかりそうになったのでとっさに口に入れてとかしてしまったが、さて、その手紙には何が書いてあったのか。
「賢者の贈り物」
最近デジカメに持ち替えた写真好きの男に、妻はフィルムをプレゼントした。
何を思って、彼女は夫にフィルムを贈ったのか。
「玉手箱」
人妻は、別れの際に箱を渡した。
「これを差し上げます。でも、この箱をあけてしまったら、もう2度とあえなくなるでしょう」
さて、箱の中身は何じゃいな?
「泡となって消える前に」
正体を隠してつきあっている彼女。
彼女はなぜ正体を隠すのか。
「経文を書く」
味オンチの男が高価なワイン蒐集にはまった。
彼を救うにはどうすればいい?
「最後のひと目盛り」
やけになって過食に走るわたしを飲み食いに誘う友人。
それは何故?
「木に登る」
株価暴落の可能性をつかんだ男。
その株を全財産はたいて買った友人は連絡のつかないジャングルの奥地にいる。
さて、どうする?
作品の大半は推理にあてられていて、ケメルマンとかアシモフなどの系列かと思わせる。
それぞれなるほど、それが最も適当なおさまるべき推理だな、と思わせるが、リドルストーリーで終わっている作品もあって、残念。
リドルストーリーそのものは大好きだが、このシリーズでは、なんらかの解答がほしかった。
『自殺するなら、引きこもれ 問題だらけの学校から身を守る法』
2009年5月13日 読書本田透と堀田純司による『自殺するなら、引きこもれ 問題だらけの学校から身を守る法』を読んだ。
以下、目次
プロローグ−学校から身を守るという、選択肢/本田
第1章 学校の正体/本田
学校とは何か/学校制度の誕生/時代とともに揺れ動く教育内容/学校は真理や真実を教える場ではない/国家にとって都合のいい人間を育てる/レジャーランド化する学校/「出家」というシステム/脱学校の社会/「いじめられる側」に問題はあるのか
第2章 流動化した社会/堀田
「学校を出て、就職すればそこそこ幸福に暮らせる」の終焉/流動化した価値観/ストレスフルな「自由」/規制か?自由か?/学校における自己責任原則/「伝統の崩壊」と「伝統への回帰」の二極化/『クラッシュ』と『ブロークバック・マウンテン』/癒し、自分探し、武士道/伝統の取扱いは要注意/意外に新しい伝統/公というものを頼りにしない
第3章 フリーターの人でも安心して暮らせる社会を/堀田
国の起源/子役の就労時間も延びた規制緩和/規制緩和を振り返る/日本にも誕生した民営刑務所/かつての規制のすさまじさ/多様な生活を肯定する制度を/多様化に対応した教育制度を/私も学校をやめて大検を受けました/「大検」から「高認」へ/引きこもる生活へ/引きこもりは快適/引きこもる意味/格差?いや多様性/今の時代には可能性もある/ジャパニーズドリーム
第4章 孤独力、妄想力がコンテンツ立国を支える/本田
「おちこぼれ」がつくる歴史/ADHD、LDだったエジソン/「LD」「ADHD」というレッテル/脳が小さかったアインシュタイン/「おちこぼれ」からしか天才は生まれない/スティーブ・ジョブズの人生/「今日が人生最後の日だと思って生きる」/孤独、挫折がエネルギーに/大人になってからの引きこもり/丘の上の愚者/学校に行かないほうが勉強がはかどるタイプ/あのまま学校に行っていたら…/引きこもり期のノートが本に/自我の崩壊/学校がイヤでイヤで仕方ない/物書きの仕事が天職/引きこもりが日本を支える/第四次産業/「妄想」が市場を形成する
あとがきに代えて/「生協の白石さん」こと白石昌則
学校信仰の呪縛を解いてくれる1冊。
学生時代から学校が好きな模範生で、卒業後も学校に職を求めた僕などは、すっかりこうした学校教に囚われていた。
皮肉にも、学校に勤務して、学校の実体を知るにつれて、学校教の呪縛は解けたのだが、本書はそんな学校批判の本というわけではない。学校批判も学校教の同じ穴のむじなだからだ。
以下、目次
プロローグ−学校から身を守るという、選択肢/本田
第1章 学校の正体/本田
学校とは何か/学校制度の誕生/時代とともに揺れ動く教育内容/学校は真理や真実を教える場ではない/国家にとって都合のいい人間を育てる/レジャーランド化する学校/「出家」というシステム/脱学校の社会/「いじめられる側」に問題はあるのか
第2章 流動化した社会/堀田
「学校を出て、就職すればそこそこ幸福に暮らせる」の終焉/流動化した価値観/ストレスフルな「自由」/規制か?自由か?/学校における自己責任原則/「伝統の崩壊」と「伝統への回帰」の二極化/『クラッシュ』と『ブロークバック・マウンテン』/癒し、自分探し、武士道/伝統の取扱いは要注意/意外に新しい伝統/公というものを頼りにしない
第3章 フリーターの人でも安心して暮らせる社会を/堀田
国の起源/子役の就労時間も延びた規制緩和/規制緩和を振り返る/日本にも誕生した民営刑務所/かつての規制のすさまじさ/多様な生活を肯定する制度を/多様化に対応した教育制度を/私も学校をやめて大検を受けました/「大検」から「高認」へ/引きこもる生活へ/引きこもりは快適/引きこもる意味/格差?いや多様性/今の時代には可能性もある/ジャパニーズドリーム
第4章 孤独力、妄想力がコンテンツ立国を支える/本田
「おちこぼれ」がつくる歴史/ADHD、LDだったエジソン/「LD」「ADHD」というレッテル/脳が小さかったアインシュタイン/「おちこぼれ」からしか天才は生まれない/スティーブ・ジョブズの人生/「今日が人生最後の日だと思って生きる」/孤独、挫折がエネルギーに/大人になってからの引きこもり/丘の上の愚者/学校に行かないほうが勉強がはかどるタイプ/あのまま学校に行っていたら…/引きこもり期のノートが本に/自我の崩壊/学校がイヤでイヤで仕方ない/物書きの仕事が天職/引きこもりが日本を支える/第四次産業/「妄想」が市場を形成する
あとがきに代えて/「生協の白石さん」こと白石昌則
学校信仰の呪縛を解いてくれる1冊。
学生時代から学校が好きな模範生で、卒業後も学校に職を求めた僕などは、すっかりこうした学校教に囚われていた。
皮肉にも、学校に勤務して、学校の実体を知るにつれて、学校教の呪縛は解けたのだが、本書はそんな学校批判の本というわけではない。学校批判も学校教の同じ穴のむじなだからだ。
『ハル、ハル、ハル』
2009年5月12日 読書古川日出男の『ハル、ハル、ハル』を読んだ。
「ハル、ハル、ハル」「スローモーション」「8ドッグズ」の3編。
この物語はきみが読んできた全部の物語の続編だ。(ハル、ハル、ハル)
全体にすっとばす物語で、「スローモーション」なんて、奥歯の加速装置を噛んで執筆したがために、世界がスローモーションに見えるのをタイトルにしたんじゃないか、と思えるほどのぶっとばし作だった。著者が巻末で言うように「僕は完全に新しい階梯に入った」のだとすると、ちょっと寂しい気もする。たとえば、本書よりも『アラビアの夜の種族』の方が数倍面白かったと思うのは、僕の老いによるものなのだろうか。と、いうより、同じ作者とは思えない作品なので、確かに、完全に新しい階梯に入ったのだろう。
こういうスピード感あふれる作品もいい。でも、これなら他の書き手にまかせてもいいんじゃないか、と思ったりする。
そうそう、それと「8ドッグズ」冒頭の文章には笑った。
犬の話はもうじゅうぶんだろ。おれだって聞き飽きた。
確かに!古川日出男の作品にはなぜ犬がよく出てくるが、それは大きな欠点だ、と断言していい!
「ハル、ハル、ハル」「スローモーション」「8ドッグズ」の3編。
この物語はきみが読んできた全部の物語の続編だ。(ハル、ハル、ハル)
全体にすっとばす物語で、「スローモーション」なんて、奥歯の加速装置を噛んで執筆したがために、世界がスローモーションに見えるのをタイトルにしたんじゃないか、と思えるほどのぶっとばし作だった。著者が巻末で言うように「僕は完全に新しい階梯に入った」のだとすると、ちょっと寂しい気もする。たとえば、本書よりも『アラビアの夜の種族』の方が数倍面白かったと思うのは、僕の老いによるものなのだろうか。と、いうより、同じ作者とは思えない作品なので、確かに、完全に新しい階梯に入ったのだろう。
こういうスピード感あふれる作品もいい。でも、これなら他の書き手にまかせてもいいんじゃないか、と思ったりする。
そうそう、それと「8ドッグズ」冒頭の文章には笑った。
犬の話はもうじゅうぶんだろ。おれだって聞き飽きた。
確かに!古川日出男の作品にはなぜ犬がよく出てくるが、それは大きな欠点だ、と断言していい!
『フォトドキュメント ゲバラ 赤いキリスト伝説』
2009年5月7日 読書アラン・アマーの『フォトドキュメント ゲバラ 赤いキリスト伝説』を読んだ。
アマーはフランスのジャーナリストで、キューバに長年滞在し、多くの証言と未公開写真をもとに、ゲバラの実像を描き出した。
ゲバラブームにあやかった後追いのにわか作りの本も多々あって、そういうのも面白くて大好きなのだが、本書はそういう類書とはひとあじ違った。
キリスト伝説、と銘打つだけあって、ゲバラの死体写真がこれでもか、と数種類載っていたのが面白い。
以下、目次。
赤いキリスト
革命家の誕生
キューバ市民、エルネスト・ゲバラ
世界市民、エルネスト・ゲバラ
イゲラの聖エルネスト
アマーはフランスのジャーナリストで、キューバに長年滞在し、多くの証言と未公開写真をもとに、ゲバラの実像を描き出した。
ゲバラブームにあやかった後追いのにわか作りの本も多々あって、そういうのも面白くて大好きなのだが、本書はそういう類書とはひとあじ違った。
キリスト伝説、と銘打つだけあって、ゲバラの死体写真がこれでもか、と数種類載っていたのが面白い。
以下、目次。
赤いキリスト
革命家の誕生
キューバ市民、エルネスト・ゲバラ
世界市民、エルネスト・ゲバラ
イゲラの聖エルネスト
谷町月いち古書市、『創造性の宇宙−創世記から情報空間へ』、春の新作アニメ
2009年5月2日 読書谷町月いち古書市に行く。
足繁く通ってみるものだ。
探していた本が1冊見つかった!
あんまり待望してたので、すぐに読む気にもなれない。
いずれまたゆっくりと読んで、まとめてみよう。
港千尋・永原康史監修による『創造性の宇宙−創世記から情報空間へ』を読んだ。
宇宙アートなど面白い試みが紹介もされている。
しかし、昔の人が創造したもののスケールの大きさにはかなわない。
こりゃいったい、どうしたわけだ。
創造は既に終わったのか?そんなことを考えているときに、ちょうどこの本がヒントになった。
以下、目次
ヴィジュアルステージ/港千尋・永原康史
第2のビッグバンにむけて/港千尋
1、コスモロジーの冒険
創世記に見られる天地創造とその創造主/秦剛平
ムカルナスー空虚の装飾/高橋士郎
ディープコスモロジー−宇宙からのイメージ/伊藤俊治
2、関係性の力
インタラクションに関する考察−「自己座標系」をデザインすること/須永剛司
インタラクティヴな遠近法/ジャン=ルイ・ボワシェ
計算する多宇宙の囲碁/久保田晃弘
3、メディアを超えて
オープン・クリエーション−PAZ(分散的テンポラリー・ゾーン)の実践/四方幸子
観測される現在地−存在のリアリティ/平川紀道
柔らかなデジタル/前田ジョン・永原康史
情報宇宙の作図法−インタラクション・ユニヴァースのための制作ノート/永原康史
5月になったので、そろそろ春の新作アニメがふるいにかけられたきた。
野球中継などで録画しそこねたのをきっかけにして、見なくなったもの。(これが多い)
登場する何人もの人が外国人の名前で覚えにくい。
アニメオタクあるいはゲームオタクに特化している作品。(僕はそのどちらでもないので、一般ピープルは退散した、という形)
既に3話で何のことなのかストーリーを追えなくなった。(僕のような年寄りには記憶力がないのだ)
などが消えていった。
曜日別に、今の段階で継続して見ているのを書いておこう。
来月あたりになると、これがまた減っている可能性も大だ。
日:ジュエルペット
クロスロード
鋼の錬金術師
花咲ける青少年
グイン・サーガ
ドラゴンボール改
月:アスラクライン
シャングリラ
火:夏のあらし
東のエデン
水:スポンジボブ
木:けいおん
バスカッシュ
タイタニア
金:咲
ファントム
土:ハヤテのごとく2
戦国BASARA
亡念のザムド
戦場のヴァルキュリア
真マジンガーZ
アラド戦記
神曲奏界ポリフォニカS
月〜金:クッキンアイドルあいまいまいん
アニメ三国志
キャラディ
あと、ケーブルテレビではじまったアキカン!
話の順番が整ったハルヒ
あたりを見ている。
一番面白いのはなんと言っても「クッキンアイドルアイマイまいん」(僕の表記もあいまいマイン)
つづいて、「スポンジボブ」「東のエデン」「けいおん」「鋼の錬金術師」が2番手グループ。「スポンジボブ」を新作の仲間にいれるのはちょっと雰囲気が違うけど、面白さではダントツ。これら新作よりも、継続して見ている「銀魂」が一番面白い。戦記ものは苦手だったけど、「タイタニア」や「アラド戦記」はそこそこ面白いし、1話め見て「こりゃないな」と思った「戦場のヴァルキュリア」も、監督の「3話めからが面白い」の言葉を信じて見続けていたら、本当に面白くなってきた。テンションにつられて見ている「真マジンガーZ」と「戦国BASARA」、ひょっとして原作読んだ方が面白いのかも、と思わせる「アスラクライン」と「シャングリラ」、などいろいろ。
足繁く通ってみるものだ。
探していた本が1冊見つかった!
あんまり待望してたので、すぐに読む気にもなれない。
いずれまたゆっくりと読んで、まとめてみよう。
港千尋・永原康史監修による『創造性の宇宙−創世記から情報空間へ』を読んだ。
宇宙アートなど面白い試みが紹介もされている。
しかし、昔の人が創造したもののスケールの大きさにはかなわない。
こりゃいったい、どうしたわけだ。
創造は既に終わったのか?そんなことを考えているときに、ちょうどこの本がヒントになった。
以下、目次
ヴィジュアルステージ/港千尋・永原康史
第2のビッグバンにむけて/港千尋
1、コスモロジーの冒険
創世記に見られる天地創造とその創造主/秦剛平
ムカルナスー空虚の装飾/高橋士郎
ディープコスモロジー−宇宙からのイメージ/伊藤俊治
2、関係性の力
インタラクションに関する考察−「自己座標系」をデザインすること/須永剛司
インタラクティヴな遠近法/ジャン=ルイ・ボワシェ
計算する多宇宙の囲碁/久保田晃弘
3、メディアを超えて
オープン・クリエーション−PAZ(分散的テンポラリー・ゾーン)の実践/四方幸子
観測される現在地−存在のリアリティ/平川紀道
柔らかなデジタル/前田ジョン・永原康史
情報宇宙の作図法−インタラクション・ユニヴァースのための制作ノート/永原康史
5月になったので、そろそろ春の新作アニメがふるいにかけられたきた。
野球中継などで録画しそこねたのをきっかけにして、見なくなったもの。(これが多い)
登場する何人もの人が外国人の名前で覚えにくい。
アニメオタクあるいはゲームオタクに特化している作品。(僕はそのどちらでもないので、一般ピープルは退散した、という形)
既に3話で何のことなのかストーリーを追えなくなった。(僕のような年寄りには記憶力がないのだ)
などが消えていった。
曜日別に、今の段階で継続して見ているのを書いておこう。
来月あたりになると、これがまた減っている可能性も大だ。
日:ジュエルペット
クロスロード
鋼の錬金術師
花咲ける青少年
グイン・サーガ
ドラゴンボール改
月:アスラクライン
シャングリラ
火:夏のあらし
東のエデン
水:スポンジボブ
木:けいおん
バスカッシュ
タイタニア
金:咲
ファントム
土:ハヤテのごとく2
戦国BASARA
亡念のザムド
戦場のヴァルキュリア
真マジンガーZ
アラド戦記
神曲奏界ポリフォニカS
月〜金:クッキンアイドルあいまいまいん
アニメ三国志
キャラディ
あと、ケーブルテレビではじまったアキカン!
話の順番が整ったハルヒ
あたりを見ている。
一番面白いのはなんと言っても「クッキンアイドルアイマイまいん」(僕の表記もあいまいマイン)
つづいて、「スポンジボブ」「東のエデン」「けいおん」「鋼の錬金術師」が2番手グループ。「スポンジボブ」を新作の仲間にいれるのはちょっと雰囲気が違うけど、面白さではダントツ。これら新作よりも、継続して見ている「銀魂」が一番面白い。戦記ものは苦手だったけど、「タイタニア」や「アラド戦記」はそこそこ面白いし、1話め見て「こりゃないな」と思った「戦場のヴァルキュリア」も、監督の「3話めからが面白い」の言葉を信じて見続けていたら、本当に面白くなってきた。テンションにつられて見ている「真マジンガーZ」と「戦国BASARA」、ひょっとして原作読んだ方が面白いのかも、と思わせる「アスラクライン」と「シャングリラ」、などいろいろ。
『ボードリヤール再入門』
2009年4月30日 読書塚原史の『ボードリヤール再入門』を読んだ。
サブタイトルに「消費社会論から悪の知性へ」とある。
この前読んだ吉本隆明の『自著を語る』で渋谷陽一が吉本隆明の堅めの本にも詩を感じる、みたいなことを言っていた。(そういえば、渋谷は吉本隆明の「パッション」をしきりに言っており、その論調は坂本龍一を迎えての「サウンドミュージアム」でも坂本龍一を相手に再現されていた)
それと同様、ボードリヤールの本も『透き通った悪』あたりから、文学になっていることを塚原氏は書いている。僕がボードリヤールを面白く読めるのは、文学になってからのボードリヤールであることは言うまでもない。難しい理屈はよくわからないのだ。
本書はボードリヤールの歩みをたどり、また巻末には各著作のレジュメまであって、ボードリヤールを読み直してみる手助けになる。
サブタイトルに「消費社会論から悪の知性へ」とある。
この前読んだ吉本隆明の『自著を語る』で渋谷陽一が吉本隆明の堅めの本にも詩を感じる、みたいなことを言っていた。(そういえば、渋谷は吉本隆明の「パッション」をしきりに言っており、その論調は坂本龍一を迎えての「サウンドミュージアム」でも坂本龍一を相手に再現されていた)
それと同様、ボードリヤールの本も『透き通った悪』あたりから、文学になっていることを塚原氏は書いている。僕がボードリヤールを面白く読めるのは、文学になってからのボードリヤールであることは言うまでもない。難しい理屈はよくわからないのだ。
本書はボードリヤールの歩みをたどり、また巻末には各著作のレジュメまであって、ボードリヤールを読み直してみる手助けになる。
『POST NO FUTURE』
2009年4月28日 読書工藤キキの『ポストノーフューチャー』を読んだ。サブタイトルは「未分化のアートピア」
東京でのアートシーンを主に綴った文章が並んでいる。
著者はコンセプト好きだと告白しているが、この本を読むと、実際には見に行っていないアートのエッセンスを面白く感じ取ることができた。
この本を読んでいると、いろんなアイディアが湧いてきた。
こういったアートシーンに目をやったり、渦中にいる、ということでアートは発生するのだ。もっとアンテナ磨いて、フットワークを駆使したい。
東京でのアートシーンを主に綴った文章が並んでいる。
著者はコンセプト好きだと告白しているが、この本を読むと、実際には見に行っていないアートのエッセンスを面白く感じ取ることができた。
この本を読んでいると、いろんなアイディアが湧いてきた。
こういったアートシーンに目をやったり、渦中にいる、ということでアートは発生するのだ。もっとアンテナ磨いて、フットワークを駆使したい。