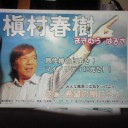伊丹市立美術館に行って、「ベン・シャーン展 線の魔術師」を見た。
主に1930年代から60年代にかけて活躍したアメリカの画家。
ドレフュス事件を扱ったり、第五福竜丸を扱った「ラッキー・ドラゴン」シリーズなど、社会派の面も強い。後期は社会から、より深く個人に着目した作品が多く、「マルテの手記」など題材にしていた。
http://artmuseum-itami.jp/exhibition/current_exhibition/5805/
伊丹アイホールに行って、現代演劇レトロスペクティブシリーズ、劇団太陽族の「血は立ったまま眠っている」を見てきた。
1960年の寺山修司の作品を、岩崎正裕が演出した。
上演後には岩崎正裕の司会進行で、九條今日子(寺山修司元夫人、テラヤマ・ワールド共同代表)と、笹目浩之(寺山修司記念館館長、ポスターハリス・カンパニー代表)のトークもあった。今回の演劇の感想から、寺山修司にまつわるエピソードなど、かなり貴重なトークで、これを活字化して本にしてほしい、と思ったほどだ。
寺山の作品が三幕ものだったのを、一幕ものにして、現代演劇らしくスピーディに事が運ぶことなどに、九條今日子はしきりに感心していた。また、トークのなかで、「血は立ったまま流れている」が最初に発表されたものと、後に角川から出たものとでは、随分内容が違っていることが取り上げられていた。今回の上演に関しては、最初に出た形を採用したとのこと。また、八尾西武ホールでの「レミング」のモチーフが、「血は立ったまま眠っている」にも、今回の演出にも顔を出していることが、語られたりした。
僕は幸いなことに八尾西武ホールでの「レミング」は、席の位置をいろいろ変えて、全部の回を見たのだが、扉に釘を打ち付けて観客を閉じ込めてしまい、一切の明かりを消してしまう完全暗転は、前のほうで見たときには感動したが、うしろのほうで見たときは、外の声がかすかに聞こえたりして興ざめだったのを思い出した。
また、トーク終了後、寺山グッズの抽選会もあったが、あいにくと、僕には何も当らなかった。かなり貴重なものだったのだが、それぞれファンの人の手に渡って、なにより。
主に1930年代から60年代にかけて活躍したアメリカの画家。
ドレフュス事件を扱ったり、第五福竜丸を扱った「ラッキー・ドラゴン」シリーズなど、社会派の面も強い。後期は社会から、より深く個人に着目した作品が多く、「マルテの手記」など題材にしていた。
http://artmuseum-itami.jp/exhibition/current_exhibition/5805/
伊丹アイホールに行って、現代演劇レトロスペクティブシリーズ、劇団太陽族の「血は立ったまま眠っている」を見てきた。
1960年の寺山修司の作品を、岩崎正裕が演出した。
上演後には岩崎正裕の司会進行で、九條今日子(寺山修司元夫人、テラヤマ・ワールド共同代表)と、笹目浩之(寺山修司記念館館長、ポスターハリス・カンパニー代表)のトークもあった。今回の演劇の感想から、寺山修司にまつわるエピソードなど、かなり貴重なトークで、これを活字化して本にしてほしい、と思ったほどだ。
寺山の作品が三幕ものだったのを、一幕ものにして、現代演劇らしくスピーディに事が運ぶことなどに、九條今日子はしきりに感心していた。また、トークのなかで、「血は立ったまま流れている」が最初に発表されたものと、後に角川から出たものとでは、随分内容が違っていることが取り上げられていた。今回の上演に関しては、最初に出た形を採用したとのこと。また、八尾西武ホールでの「レミング」のモチーフが、「血は立ったまま眠っている」にも、今回の演出にも顔を出していることが、語られたりした。
僕は幸いなことに八尾西武ホールでの「レミング」は、席の位置をいろいろ変えて、全部の回を見たのだが、扉に釘を打ち付けて観客を閉じ込めてしまい、一切の明かりを消してしまう完全暗転は、前のほうで見たときには感動したが、うしろのほうで見たときは、外の声がかすかに聞こえたりして興ざめだったのを思い出した。
また、トーク終了後、寺山グッズの抽選会もあったが、あいにくと、僕には何も当らなかった。かなり貴重なものだったのだが、それぞれファンの人の手に渡って、なにより。
椅子@studio21
2013年3月31日 演劇京都芸術劇場studio21で、杉原邦生演出のイヨネスコ劇「椅子」を見てきた。
もとのイヨネスコでは、次々と出てくる登場人物が、椅子であらわされ、不在の人物との会話がかわされ、舞台上が椅子でいっぱいになるのだが、今回の演出では、椅子だけでなく、実際の観客に役を振って、セリフのない役者として椅子にすわらせていた。
面白い!
さらに、最後の最後には、イヨネスコが残した自由演技の部分で、とんでもないあつくるしさを見せてくれて、すごかった。開演前に場内にかかっていた音楽のセンスの悪さが、伏線になってたのか、と感心しきり。
もとのイヨネスコでは、次々と出てくる登場人物が、椅子であらわされ、不在の人物との会話がかわされ、舞台上が椅子でいっぱいになるのだが、今回の演出では、椅子だけでなく、実際の観客に役を振って、セリフのない役者として椅子にすわらせていた。
面白い!
さらに、最後の最後には、イヨネスコが残した自由演技の部分で、とんでもないあつくるしさを見せてくれて、すごかった。開演前に場内にかかっていた音楽のセンスの悪さが、伏線になってたのか、と感心しきり。
マリィヴォロン@AI・HALL
2012年10月29日 演劇伊丹のAI・HALLホールロビーで、Plant-M「マリィヴォロン」。
北村想作品の連続リーディングの最終日。他の作品も見に来たかったが、仕事とかで来れず。
演出は樋口ミユ、出演は出口弥生。
以前、戸川純がひとり芝居で上演したときに見たはずなのだが、内容はすっかり忘れていた。演出が違うので、違う印象だったのかもしれない。
500円の安い値段だし、演じられるのがロビーだったので、油断していたが、しっかりと演劇になっていて、得した気分。
北村想作品の連続リーディングの最終日。他の作品も見に来たかったが、仕事とかで来れず。
演出は樋口ミユ、出演は出口弥生。
以前、戸川純がひとり芝居で上演したときに見たはずなのだが、内容はすっかり忘れていた。演出が違うので、違う印象だったのかもしれない。
500円の安い値段だし、演じられるのがロビーだったので、油断していたが、しっかりと演劇になっていて、得した気分。
東京2日め。と、言っても、今晩帰る。
弥生美術館で「奇っ怪紳士!怪獣博士!大伴昌司の大図解 展」を見る。
こどもの頃に持っていてよく読んでいた怪獣の本や、少年マンガ雑誌の特集ページなど。僕が一番記憶に残っているのは、江戸川乱歩の世界を描いたもので、内容は鏡地獄で発狂した男とか、あと、地獄風景とか、鬼とかが取り上げられていたと思う。大時計の文字盤で長針に首を切られそうになっている表紙は、復刻版でも見れたと思うが、中身までは紹介してくれていないのが残念(しかも、表紙は小説の中身と違って、体が切られそうになっている)。
あと、青銅の大魔神のソノシートもあって、青銅の大魔神を退治するために日本古来の化け物(守護する妖怪?)が出てきて戦うのだが、全体に音楽の鬱屈したムードとあわせて、夏のけだるさを思い出させる。
隣接している竹久夢二美術館では「夢二と大正時代Ⅲ 夢二の恋と関東大震災をめぐって―大正9~12年を中心に―」
震災時のスケッチと文章もまとめて読むことができて、これはよかった。
http://www.yayoi-yumeji-museum.jp/
高円寺に移動して、座・高円寺で演劇実験室・万有引力の「紙芝居活劇オペラ 怪人フー・マンチュー」を見た。
映画のシーンもまじえて、現実と虚構が交錯する音楽劇。
ストーリーは、ぼけ~っと見ていたせいか、あってないような感じだった。
やっつけた!と思ったら、復活した!またやっつけた!あ、復活した!みたいな感じ。
音楽は伊福部のくすぐりからはじまって、JAシーザー全開。寺山修司らしさはあったが、ライトな感じだったかな。
http://www.banyu-inryoku.net/main/main.htm
弥生美術館で「奇っ怪紳士!怪獣博士!大伴昌司の大図解 展」を見る。
こどもの頃に持っていてよく読んでいた怪獣の本や、少年マンガ雑誌の特集ページなど。僕が一番記憶に残っているのは、江戸川乱歩の世界を描いたもので、内容は鏡地獄で発狂した男とか、あと、地獄風景とか、鬼とかが取り上げられていたと思う。大時計の文字盤で長針に首を切られそうになっている表紙は、復刻版でも見れたと思うが、中身までは紹介してくれていないのが残念(しかも、表紙は小説の中身と違って、体が切られそうになっている)。
あと、青銅の大魔神のソノシートもあって、青銅の大魔神を退治するために日本古来の化け物(守護する妖怪?)が出てきて戦うのだが、全体に音楽の鬱屈したムードとあわせて、夏のけだるさを思い出させる。
隣接している竹久夢二美術館では「夢二と大正時代Ⅲ 夢二の恋と関東大震災をめぐって―大正9~12年を中心に―」
震災時のスケッチと文章もまとめて読むことができて、これはよかった。
http://www.yayoi-yumeji-museum.jp/
高円寺に移動して、座・高円寺で演劇実験室・万有引力の「紙芝居活劇オペラ 怪人フー・マンチュー」を見た。
映画のシーンもまじえて、現実と虚構が交錯する音楽劇。
ストーリーは、ぼけ~っと見ていたせいか、あってないような感じだった。
やっつけた!と思ったら、復活した!またやっつけた!あ、復活した!みたいな感じ。
音楽は伊福部のくすぐりからはじまって、JAシーザー全開。寺山修司らしさはあったが、ライトな感じだったかな。
http://www.banyu-inryoku.net/main/main.htm
東京女子流の石丸イベントをUstreamで見たりして、午前中をすごし、
昼からは、観劇。
森ノ宮ピロティホールで、、真心一座身も心も ザ・ファイナル「流れ姉妹たつことかつこ エンド・オブ・バイオレンス」を見に行った。
アイドル、声優、写真家の宍戸留美ちゃんは、この演劇を東京で2回見て、あまりの面白さに大阪でも見よう、とわざわざ来阪しての観劇。僕もコマーシャルなどで見て気になってた演劇だったので、せっかくだから、と一緒に見に行った。
このシリーズは、この最終章だけを見たのだが、事前にサイトであらすじを頭にたたきこんでいたし、本番はじまる前に、前回までのあらすじをちゃんと見せてくれた。
目つぶしの突き技上等の姉たつこ(バスタオル姿が戦闘服!)と、陵辱の人生を送る妹かつこの人生模様を描く。
キャストは、千葉雅子(たつこ)、村岡希美(かつこ)、坂田聡(谷村)、河原雅彦(末次)、たつこの相手をつとめるゲストラバーは池田成志(松川金水)、かつこの相手をつとめるゲストレイパーは古田新太(槇村春樹)、がや四人衆に小林顕作、政岡泰志、伊達暁、信川清順。
いや~、面白かった。
毎回出てくる、ほぼ等身大の動物たちは、今回、カニに鯉に竜、そして河童???(竜は、たつこ。河童は、かつこ。と韻を踏んで暗示されている)
架空の動物に等身大もへったくれもないのだが、そうした、「想像上」のいきもの、金のメタファーであろう「カニ」、恋のメタファーであろう「鯉」を配置して、全体の物語の行き着く先を予感させて、まとめあげるあたりは、手がこんでいる。空想の河童は川流れするが、実在の鯉は滝のぼりしちゃうんである。
途中、古田新太演ずるゲイのクリーニング屋が、町長選に立候補して、選挙活動で客席におりてきて、選挙用のちらしを通路ぎわに座った人にランダムに配ってまわるサービスもあった。僕は、通路ぎわでもなかったのに、チラシくれた。なんとも言えず、ラッキー!
観劇後、留美ちゃんチェックイン、僕は「現代の音楽」エアチェックのため、いったん帰宅。
- 芥川作曲賞創設20周年記念
ガラ・コンサートから -(2)
「マイザレーム 独奏チェロのための」 伊佐治直・作曲
(10分00秒)
(チェロ)多井智紀
「ピアノのための“無常の鐘”」 権代敦彦・作曲
(7分50秒)
(ピアノ)有森直樹
「尺八のためのエチュード」 川島素晴・作曲
(9分50秒)
(尺八)藤原道山
「ソプラノ・リコーダーのための“サラマンダー2”」
伊藤弘之・作曲
(6分50秒)
(リコーダー)鈴木俊哉
「満月の夜に3 for piano solo」菱沼尚子・作曲
(11分00秒)
(ピアノ)山田武彦
~東京・サントリーホールで収録~
<2010/8/28>
しかし、ちょうど午後6時からあべのHOOPで東京女子流のステージがあり、じゅうぶん間に合いそうだったので、歩いて天王寺へGO!
石丸でのステージは、
1.ヒマワリと星屑
2.Love like candy floss
3.鼓動の秘密
の3曲だったが、大阪での本番直前のリハーサルでは、4曲やってくれて、期待が募る。大阪のセットリストは。
1.ヒマワリと星屑
2.おんなじキモチ
3.Love like candy floss
4.鼓動の秘密
重大発表として、4月13日にアルバムが発売されることと、5月にツアーがあることのアナウンスがあった。
大阪は5月1日(日)心斎橋クアトロ。
さて、東京女子流も満喫したところで、録音したばかりの「現代の音楽」を聞きながら中崎町の天劇キネマトロンで、留美ちゃんと合流して、食事。
そこに、集まる、集まる、楽しい表現者たちの輪。
その模様が部分的にツイキャスされたりとかして、楽しい。
春以降のいろんな人たちの展開なども聞けて、面白かった。
僕にこれといった新展開はないのだが、こういう場に参加しているだけで、自分の前にも何か道が開けているような気分になるのがうれしい。そういう気分になっちゃうと、もう、道は開けたも同然なのだから。まあ、別に僕の場合はちっとも行き詰ってなかったんだけどね!
まあ、とにかく、楽しい宴でした!
東京女子流イベントから流れてきてくれた友人もおり、ほとんど相手できなかったけど、ありがたかった。
昼からは、観劇。
森ノ宮ピロティホールで、、真心一座身も心も ザ・ファイナル「流れ姉妹たつことかつこ エンド・オブ・バイオレンス」を見に行った。
アイドル、声優、写真家の宍戸留美ちゃんは、この演劇を東京で2回見て、あまりの面白さに大阪でも見よう、とわざわざ来阪しての観劇。僕もコマーシャルなどで見て気になってた演劇だったので、せっかくだから、と一緒に見に行った。
このシリーズは、この最終章だけを見たのだが、事前にサイトであらすじを頭にたたきこんでいたし、本番はじまる前に、前回までのあらすじをちゃんと見せてくれた。
目つぶしの突き技上等の姉たつこ(バスタオル姿が戦闘服!)と、陵辱の人生を送る妹かつこの人生模様を描く。
キャストは、千葉雅子(たつこ)、村岡希美(かつこ)、坂田聡(谷村)、河原雅彦(末次)、たつこの相手をつとめるゲストラバーは池田成志(松川金水)、かつこの相手をつとめるゲストレイパーは古田新太(槇村春樹)、がや四人衆に小林顕作、政岡泰志、伊達暁、信川清順。
いや~、面白かった。
毎回出てくる、ほぼ等身大の動物たちは、今回、カニに鯉に竜、そして河童???(竜は、たつこ。河童は、かつこ。と韻を踏んで暗示されている)
架空の動物に等身大もへったくれもないのだが、そうした、「想像上」のいきもの、金のメタファーであろう「カニ」、恋のメタファーであろう「鯉」を配置して、全体の物語の行き着く先を予感させて、まとめあげるあたりは、手がこんでいる。空想の河童は川流れするが、実在の鯉は滝のぼりしちゃうんである。
途中、古田新太演ずるゲイのクリーニング屋が、町長選に立候補して、選挙活動で客席におりてきて、選挙用のちらしを通路ぎわに座った人にランダムに配ってまわるサービスもあった。僕は、通路ぎわでもなかったのに、チラシくれた。なんとも言えず、ラッキー!
観劇後、留美ちゃんチェックイン、僕は「現代の音楽」エアチェックのため、いったん帰宅。
- 芥川作曲賞創設20周年記念
ガラ・コンサートから -(2)
「マイザレーム 独奏チェロのための」 伊佐治直・作曲
(10分00秒)
(チェロ)多井智紀
「ピアノのための“無常の鐘”」 権代敦彦・作曲
(7分50秒)
(ピアノ)有森直樹
「尺八のためのエチュード」 川島素晴・作曲
(9分50秒)
(尺八)藤原道山
「ソプラノ・リコーダーのための“サラマンダー2”」
伊藤弘之・作曲
(6分50秒)
(リコーダー)鈴木俊哉
「満月の夜に3 for piano solo」菱沼尚子・作曲
(11分00秒)
(ピアノ)山田武彦
~東京・サントリーホールで収録~
<2010/8/28>
しかし、ちょうど午後6時からあべのHOOPで東京女子流のステージがあり、じゅうぶん間に合いそうだったので、歩いて天王寺へGO!
石丸でのステージは、
1.ヒマワリと星屑
2.Love like candy floss
3.鼓動の秘密
の3曲だったが、大阪での本番直前のリハーサルでは、4曲やってくれて、期待が募る。大阪のセットリストは。
1.ヒマワリと星屑
2.おんなじキモチ
3.Love like candy floss
4.鼓動の秘密
重大発表として、4月13日にアルバムが発売されることと、5月にツアーがあることのアナウンスがあった。
大阪は5月1日(日)心斎橋クアトロ。
さて、東京女子流も満喫したところで、録音したばかりの「現代の音楽」を聞きながら中崎町の天劇キネマトロンで、留美ちゃんと合流して、食事。
そこに、集まる、集まる、楽しい表現者たちの輪。
その模様が部分的にツイキャスされたりとかして、楽しい。
春以降のいろんな人たちの展開なども聞けて、面白かった。
僕にこれといった新展開はないのだが、こういう場に参加しているだけで、自分の前にも何か道が開けているような気分になるのがうれしい。そういう気分になっちゃうと、もう、道は開けたも同然なのだから。まあ、別に僕の場合はちっとも行き詰ってなかったんだけどね!
まあ、とにかく、楽しい宴でした!
東京女子流イベントから流れてきてくれた友人もおり、ほとんど相手できなかったけど、ありがたかった。
激富10’ RINDOUMARU 〜鬼の瞳に涙〜
2010年6月4日 演劇激富2010年度公演『激富10’ RINDOUMARU 〜鬼の瞳に涙〜』を見に行った。
当日券なしの満員御礼。
歴史の裏にひそむ暗闘を描いた作品。
石田アキラさん、染谷有香さんの達者な演技にほれぼれとする。
JK21の須田琴子ちゃの殺陣や演技も、堂に入ったもので、りっぱにヒロインを演じていた。JK21のメンバーも観覧に来ていた。
久しぶりに演劇見たけど、これは面白い。でも、おしりが割れそうだった。
当日券なしの満員御礼。
歴史の裏にひそむ暗闘を描いた作品。
石田アキラさん、染谷有香さんの達者な演技にほれぼれとする。
JK21の須田琴子ちゃの殺陣や演技も、堂に入ったもので、りっぱにヒロインを演じていた。JK21のメンバーも観覧に来ていた。
久しぶりに演劇見たけど、これは面白い。でも、おしりが割れそうだった。
花札伝綺@テラヤマ博、ぐるぐる猿と歌う鳥 (ミステリーランド)
2008年3月7日 演劇
ISBN:4062705834 単行本 加納 朋子 講談社 2007/07/26 ¥2,100
-IST零番館プロデューステラヤマ博「花札伝綺」を見に行った。
末満健一(ピースピット)演出。
天井桟敷の初期の上演作品で、寺山曰く「唯一の不入り作品」。僕もこの「花札伝綺」についてはあまり強い印象はなくて、今回の上演は新鮮な気持で見ることができた。
「生と死の転倒を喜劇にした、ニヒリスティックなユーモア」(寺山)は1967年当時の若者には不評でも、2008年の若者には受け入れられた、ということか。
登場するのは(戒名)、墓場の鬼太郎(男装の麗人)、葬儀屋団十郎(ボリス・カーロフ氏)、その妻おはか(刺青姐御)、その娘歌留多(琵琶語り付)、髭の男爵(新興成金)、無産党員(アナキストの墓)、卒塔婆おぎん(仁義一代)、獄門次(ルパンの百姓)、肉天女(ああ肉体美!)、仏蘭西刑事(「近代」の小児麻痺)、手毬童女(オカッパ)、ひきがえるの庖丁(墓掘人夫)、蟹潰し(死歯抜き)、棺桶の死美男(ダンシングチーム)、幽霊ジョニー(棺の中のドラマー)、あんまの笛(好色盲)などなど、寺山ここにあり、というラインナップ。
上演後に、戯曲を読み直してみたのだが、大きく変更したところはなく、わりと忠実に再現しているように思えた。
見ていてうれしくなるシーンが多々あった。
ただ、寺山の持つおどろおどろしさはこの「花札伝綺」からはあまり感じとれなかった。それは、演出者の狙いだったのかもしれない。
ショッキング、恐怖、暗黒、いかがわしさ、裏、闇、病、さらには死でさえもあまり感じられず、きわめて明るい印象をもった。
その大きな原因は、音楽に大槻ケンヂを使っていたところや、アドリブのパートがあまりにも最近の劇団っぽかったところにある。ひとくちで言うと、この「花札伝綺」は寺山演劇ではなく、「大槻ケンヂ演劇」だったのかもしれない。とてもライトな感じ。男装の麗人たる墓場の鬼太郎に「コードギアス」と呼びかけて観客をくすぐる感性にすべてがあらわれている。いっそのこと、寺山的などろどろしたものを、全部アニメ的感覚で処理してくれた方が、刺激的だったように思うが、それではまったく寺山演劇でもなんでもない、ということになろう。難しいな。「花札伝綺」じゃなくて「大貧民伝綺」にしちゃうとか。こりゃ、まったく違う演劇になっちゃうな。
読んだ本は加納朋子の『ぐるぐる猿と歌う鳥』
ネタバレしかしていないので、要注意。
プロローグ−あるいは、物語の前のひとりごと
第1話 ぐるぐる猿と歌う鳥
第2話 図書室の暗号
第3話 社宅のユーレイ
体育館の屋根から町を見おろしたら、町中の屋根を使って、猿が描かれていた。ナスカの地上絵みたいに。
ところが、町全体を見おろせる場所から同じ町を見下ろしたら、そんな猿はちっとも見えない。これいかに?(真相はチェンジングシール)
幼いときの記憶。家に軟禁されている「あや」と遊んでいると、男がいきなり拉致しようとした。この事件の意味は?(我が子を間違えてひきとろうとした)
本書はかなり面白かった。
わるい大人をこらしめるために、住所表示のナンバープレートを偽造して、空家に誘導し、そこでお化け屋敷的おどかしをする話。血だまりは、赤いスライムを使って、あとかたづけをしやすくする。なるほど、アイディアだ!
また、「あや」の正体とか、伏線がいっぱいはってあるのが快感。(ピンクのレンジャーになりたがらない、とか、特撮ヒーローものに詳しいとか)
また、友達になろうと手紙を出した同級生に、突然敬遠される理由とか。(手紙の差出人を勘違い)
ミステリーを読む際は、あからさまに挑戦でもされないかぎり、あんまり眉にツバつけながら読んだりしないことにしている。真相を見抜いた快感よりも、だまされることの方が気持ちいいからだ。
なんでもなさそうな事柄の理由や真相が明らかになっていく過程はとても面白くて、久々にミステリーを読んだ、という実感を得ることができた。
-IST零番館プロデューステラヤマ博「花札伝綺」を見に行った。
末満健一(ピースピット)演出。
天井桟敷の初期の上演作品で、寺山曰く「唯一の不入り作品」。僕もこの「花札伝綺」についてはあまり強い印象はなくて、今回の上演は新鮮な気持で見ることができた。
「生と死の転倒を喜劇にした、ニヒリスティックなユーモア」(寺山)は1967年当時の若者には不評でも、2008年の若者には受け入れられた、ということか。
登場するのは(戒名)、墓場の鬼太郎(男装の麗人)、葬儀屋団十郎(ボリス・カーロフ氏)、その妻おはか(刺青姐御)、その娘歌留多(琵琶語り付)、髭の男爵(新興成金)、無産党員(アナキストの墓)、卒塔婆おぎん(仁義一代)、獄門次(ルパンの百姓)、肉天女(ああ肉体美!)、仏蘭西刑事(「近代」の小児麻痺)、手毬童女(オカッパ)、ひきがえるの庖丁(墓掘人夫)、蟹潰し(死歯抜き)、棺桶の死美男(ダンシングチーム)、幽霊ジョニー(棺の中のドラマー)、あんまの笛(好色盲)などなど、寺山ここにあり、というラインナップ。
上演後に、戯曲を読み直してみたのだが、大きく変更したところはなく、わりと忠実に再現しているように思えた。
見ていてうれしくなるシーンが多々あった。
ただ、寺山の持つおどろおどろしさはこの「花札伝綺」からはあまり感じとれなかった。それは、演出者の狙いだったのかもしれない。
ショッキング、恐怖、暗黒、いかがわしさ、裏、闇、病、さらには死でさえもあまり感じられず、きわめて明るい印象をもった。
その大きな原因は、音楽に大槻ケンヂを使っていたところや、アドリブのパートがあまりにも最近の劇団っぽかったところにある。ひとくちで言うと、この「花札伝綺」は寺山演劇ではなく、「大槻ケンヂ演劇」だったのかもしれない。とてもライトな感じ。男装の麗人たる墓場の鬼太郎に「コードギアス」と呼びかけて観客をくすぐる感性にすべてがあらわれている。いっそのこと、寺山的などろどろしたものを、全部アニメ的感覚で処理してくれた方が、刺激的だったように思うが、それではまったく寺山演劇でもなんでもない、ということになろう。難しいな。「花札伝綺」じゃなくて「大貧民伝綺」にしちゃうとか。こりゃ、まったく違う演劇になっちゃうな。
読んだ本は加納朋子の『ぐるぐる猿と歌う鳥』
ネタバレしかしていないので、要注意。
プロローグ−あるいは、物語の前のひとりごと
第1話 ぐるぐる猿と歌う鳥
第2話 図書室の暗号
第3話 社宅のユーレイ
体育館の屋根から町を見おろしたら、町中の屋根を使って、猿が描かれていた。ナスカの地上絵みたいに。
ところが、町全体を見おろせる場所から同じ町を見下ろしたら、そんな猿はちっとも見えない。これいかに?(真相はチェンジングシール)
幼いときの記憶。家に軟禁されている「あや」と遊んでいると、男がいきなり拉致しようとした。この事件の意味は?(我が子を間違えてひきとろうとした)
本書はかなり面白かった。
わるい大人をこらしめるために、住所表示のナンバープレートを偽造して、空家に誘導し、そこでお化け屋敷的おどかしをする話。血だまりは、赤いスライムを使って、あとかたづけをしやすくする。なるほど、アイディアだ!
また、「あや」の正体とか、伏線がいっぱいはってあるのが快感。(ピンクのレンジャーになりたがらない、とか、特撮ヒーローものに詳しいとか)
また、友達になろうと手紙を出した同級生に、突然敬遠される理由とか。(手紙の差出人を勘違い)
ミステリーを読む際は、あからさまに挑戦でもされないかぎり、あんまり眉にツバつけながら読んだりしないことにしている。真相を見抜いた快感よりも、だまされることの方が気持ちいいからだ。
なんでもなさそうな事柄の理由や真相が明らかになっていく過程はとても面白くて、久々にミステリーを読んだ、という実感を得ることができた。
月蝕歌劇団詩劇ライブ「凍りつくアドレス」
2006年9月16日 演劇
月蝕歌劇団詩劇ライブ「凍りつくアドレス」〜『プレイメイト戦士登場』〜を見に行った。
一心寺シアター倶楽で午後5時15分から。
大阪で月蝕歌劇団が公演するなんて、いったい何年ぶりなんだろう。
そしてなんと、来年にも月蝕歌劇団大阪公演があるという。
今回は「静かなるドン・魔界天翔篇」をひっさげての公演だったが、1回こっきりの詩劇ライブの方を選んだ。
寸劇なども交えながら、歌と踊りと朗読で綴る月蝕歌劇団の世界が堪能できる。
作・演出は高取英、音楽はJ・A・シーザー。
以下、演目。演者はソロのみ記載。
1.人里離れた
2.魔の知る夜明け
3.ベリアル、バフォメット/有村深羽
4.人魚姫/美弥乃静
5.さよならみんな/美弥乃静
6.新宿ダダ
7.紫のバラ/姫宮みちり
8.恋のバッキン
9.紅つばめ/木塚咲
10.勇者よ眠れ/三坂知絵子
11.東京がなんぼのもんや
12.魔女の鏡/合沢萌
13.ひとつぶの麦〜新宿ダダ
14.赤い糸車/藤田実加
15.月よりの使者/笹生愛美
16.夏のクリスマス/一ノ瀬めぐみ
17.孤独の叫び(朗読)/スギウラユカ
18.哀しみの向こうに
芝居の内容は、「ベリアル、バフォメット」を歌う有村深羽(ありむら・みう)と、「人魚姫・さよならみんな」を歌う美弥乃静(みやの・しず)が誘拐される。少女探偵団が修学旅行で不在のため、プレイメイト戦士が彼女たちを奪還するといったもの。
「東京がなんぼのもんや」でも保鳴美凛(ほなみ・りん)が東京からの爽やかな転校生を演じる寸劇になっていた。
スギウラユカの朗読は寺山修司の「書を捨てよ、町に出よう」から、「コカコーラの壜の中のトカゲ」っていう例のやつで、「おまえに壜を割って出てくる力なんかあるまい、そうだろう、日本!」のくだりは何度聞いてもしびれる。
なお、公演前に劇団員手書きのおみくじを売り歩くのが恒例になっており、僕が買ったのは、プレイメイト戦士のひとり、小嶋小鳥の書いたもので、「凶」だった。これはうれしい。
芝居で誘拐された2人は「萌え燃え隊」というユニットでも活動しているようで、東京におれば見に行っているだろう。
このライブを見ると、本編の演劇ではどうなのかわからないが、主役は完全に美弥乃静が握っていた。彼女が今の月蝕歌劇団のエースなのだろうか。一ノ瀬めぐみが歌では活躍できないゆえの僕の勘違いかもしれないけど。
一心寺シアター倶楽で午後5時15分から。
大阪で月蝕歌劇団が公演するなんて、いったい何年ぶりなんだろう。
そしてなんと、来年にも月蝕歌劇団大阪公演があるという。
今回は「静かなるドン・魔界天翔篇」をひっさげての公演だったが、1回こっきりの詩劇ライブの方を選んだ。
寸劇なども交えながら、歌と踊りと朗読で綴る月蝕歌劇団の世界が堪能できる。
作・演出は高取英、音楽はJ・A・シーザー。
以下、演目。演者はソロのみ記載。
1.人里離れた
2.魔の知る夜明け
3.ベリアル、バフォメット/有村深羽
4.人魚姫/美弥乃静
5.さよならみんな/美弥乃静
6.新宿ダダ
7.紫のバラ/姫宮みちり
8.恋のバッキン
9.紅つばめ/木塚咲
10.勇者よ眠れ/三坂知絵子
11.東京がなんぼのもんや
12.魔女の鏡/合沢萌
13.ひとつぶの麦〜新宿ダダ
14.赤い糸車/藤田実加
15.月よりの使者/笹生愛美
16.夏のクリスマス/一ノ瀬めぐみ
17.孤独の叫び(朗読)/スギウラユカ
18.哀しみの向こうに
芝居の内容は、「ベリアル、バフォメット」を歌う有村深羽(ありむら・みう)と、「人魚姫・さよならみんな」を歌う美弥乃静(みやの・しず)が誘拐される。少女探偵団が修学旅行で不在のため、プレイメイト戦士が彼女たちを奪還するといったもの。
「東京がなんぼのもんや」でも保鳴美凛(ほなみ・りん)が東京からの爽やかな転校生を演じる寸劇になっていた。
スギウラユカの朗読は寺山修司の「書を捨てよ、町に出よう」から、「コカコーラの壜の中のトカゲ」っていう例のやつで、「おまえに壜を割って出てくる力なんかあるまい、そうだろう、日本!」のくだりは何度聞いてもしびれる。
なお、公演前に劇団員手書きのおみくじを売り歩くのが恒例になっており、僕が買ったのは、プレイメイト戦士のひとり、小嶋小鳥の書いたもので、「凶」だった。これはうれしい。
芝居で誘拐された2人は「萌え燃え隊」というユニットでも活動しているようで、東京におれば見に行っているだろう。
このライブを見ると、本編の演劇ではどうなのかわからないが、主役は完全に美弥乃静が握っていた。彼女が今の月蝕歌劇団のエースなのだろうか。一ノ瀬めぐみが歌では活躍できないゆえの僕の勘違いかもしれないけど。
あたしは天使じゃない、ラスト・デイト
2006年3月31日 演劇
鈴木いづみコレクション第2巻『あたしは天使じゃない』を読んだ。
「あたしは天使じゃない」という作品があるのかと思ったが、なかった。天使じゃない、ってあえて言わなくても、鈴木いづみのことを天使だなんて思ってないよ!
収録されているのは、SFを除く短編が中心。
「夜の終わりに」
「声のない日々」
「悲しき願い」
「渇きの海」
「血いろの太陽」
「九月の子供たち」
「歩く人」
「郷愁の60年代グラフィティ 勝手にしやがれ!」
「なつ子」
の9編。
「悲しき願い」のように、ミステリーとしての結構をそなえている作品もあるが、だいたいにおいて男女のことが書かれており、セックス&ドラッグ&アルコール&バイオレンスにどっぷり漬かって抜けだせない話が多い。
と、いうか、誰も抜け出そうとしてないし。
鈴木いづみ描くところの不良たちは、まったく「勝手にしやがれ」と突き放してしかるべきだし、言われなくても、既に勝手にしやがっている。
暴力とクスリ、アルコールなんていう、精神の弱い人間の三種の神器を手放せない男女。。
相手が熱くなるととたんに冷めてしまうとか、幼稚園レベルの感情をそのまま恋愛だとぬかす奴らが大挙して出て来る。
男女のこととか、恋愛のことが中心にない僕のような男性にしてみれば、恋愛ごときで命のやりとりするような無鉄砲さは、憧れでもある。
でも、これは恋愛の相手が誰であるか、によって大きく変わってくるものなのかもしれない。
以前、恋愛をすべての中心にすえたつきあい方をしようと決心したことがある。でも、そのときの相手が「そりゃ困る」みたいな反応で、尻すぼみになってしまった。
これは相撲で立ち会いの呼吸があわなくて「待った」をかけられるようなものだ。相撲と違って、恋愛は「仕切りなおし」というのがなかなか難しそうだ。こっちは、いくらでも仕切りなおすつもりがあるのに、相手の座右の銘は「覆水、盆にかえらず」だったりするのだ。ちぇっ。
鈴木いづみ描く男女の恋愛は、決して幸せなものではない。でも、安全地帯に身をおいて常に傷付かない傍観者でいようとする一般的恋愛よりは、その強烈さに魅かれるところが多い。
僕は、感情なんてコントロールしてなんぼ、的な考えの持ち主だが、感情に身をまかせるドラッグ的快感もまたこれまた捨てがたい。
僕も「感情のなせるわざだから、どうしようもない」なんて言いわけしてみたいものだ。感情ほど、自分の思いどおりになるものはないっていうのに。
と、いうわけで、京都アートコンプレックスに行って、戸川純と奇異保の2人芝居「ラスト・デイト」を見て来た。
ヘルプアイドルの野中ひゆちゃんのお誘い。プロデュースの西尾友里さんのご厚意により、招待いただいたのだ。フィネガンズウェイクつながり。
戸川純は鈴木いづみを演じ、奇異保はその夫、阿部薫。
不可聴の音を聞く阿部薫と、不在の阿部薫を顕然せしめる鈴木いづみ。
音楽=時間=速度の世界で、そこにない音を聞き取る阿部薫と、エクリチュール=空間=場所の世界から、そこにいない阿部薫を召喚する鈴木いづみ。
2人の住む世界はもともと違う。
70年代を生きる希望のアナーキストと、80年代まで生きてしまった絶望の作家。
阿部薫は80年代を体験せずにいなくなる、引き際を知った者だ。
鈴木いづみは、常に敗北する人で、それゆえに80年代まで生き延びねばならなかった。
2人の出会いは、その最初からラストデイトであったに違いない。
鈴木いづみは、長い長いデイトを首吊りによって終わらせたのだ。
戸川純が鈴木いづみを演じるのは、ちょっと面白いなあ、と思った。戸川純はきっと鈴木いづみが好きなんだろうが、2人は大きく違っている。
一生のうち、鈴木いづみが生きた女の時間を差し引いた部分が、戸川純の生きている領分だと思うのだ。
つまり、戸川純はデビューの頃から、少女であると同時に老女だったのだ。少女と老女のあいだを埋める形で、鈴木いづみの時間は流れている。
しかも、少女と老女はともに永遠を約束されているが、鈴木いづみときたら、死者なのだ。
作、演出の岩崎正裕の描く鈴木いづみは、僕が考えていた鈴木いづみよりも、随分と俗っぽい。いや、俗っぽいというより、他の誰かと代替可能なありきたりな感じがする。俗っぽいのも、ありきたりなのも、鈴木いづみの特徴なのだが、どこか違う。
女の生きざまを描くのに、それをストレートに出しすぎているような気がした。
だからと言って、演劇がつまらなかったわけではない。
書いた日記をいつも半分くらいの分量に削ってから送信している僕が、このぐだぐだと長ったらしい駄文(しかも的を射ていない)をこのまま送ろうとするほどに、刺激され、興奮しているのだ。
さあ、今、送るぞ。
「あたしは天使じゃない」という作品があるのかと思ったが、なかった。天使じゃない、ってあえて言わなくても、鈴木いづみのことを天使だなんて思ってないよ!
収録されているのは、SFを除く短編が中心。
「夜の終わりに」
「声のない日々」
「悲しき願い」
「渇きの海」
「血いろの太陽」
「九月の子供たち」
「歩く人」
「郷愁の60年代グラフィティ 勝手にしやがれ!」
「なつ子」
の9編。
「悲しき願い」のように、ミステリーとしての結構をそなえている作品もあるが、だいたいにおいて男女のことが書かれており、セックス&ドラッグ&アルコール&バイオレンスにどっぷり漬かって抜けだせない話が多い。
と、いうか、誰も抜け出そうとしてないし。
鈴木いづみ描くところの不良たちは、まったく「勝手にしやがれ」と突き放してしかるべきだし、言われなくても、既に勝手にしやがっている。
暴力とクスリ、アルコールなんていう、精神の弱い人間の三種の神器を手放せない男女。。
相手が熱くなるととたんに冷めてしまうとか、幼稚園レベルの感情をそのまま恋愛だとぬかす奴らが大挙して出て来る。
男女のこととか、恋愛のことが中心にない僕のような男性にしてみれば、恋愛ごときで命のやりとりするような無鉄砲さは、憧れでもある。
でも、これは恋愛の相手が誰であるか、によって大きく変わってくるものなのかもしれない。
以前、恋愛をすべての中心にすえたつきあい方をしようと決心したことがある。でも、そのときの相手が「そりゃ困る」みたいな反応で、尻すぼみになってしまった。
これは相撲で立ち会いの呼吸があわなくて「待った」をかけられるようなものだ。相撲と違って、恋愛は「仕切りなおし」というのがなかなか難しそうだ。こっちは、いくらでも仕切りなおすつもりがあるのに、相手の座右の銘は「覆水、盆にかえらず」だったりするのだ。ちぇっ。
鈴木いづみ描く男女の恋愛は、決して幸せなものではない。でも、安全地帯に身をおいて常に傷付かない傍観者でいようとする一般的恋愛よりは、その強烈さに魅かれるところが多い。
僕は、感情なんてコントロールしてなんぼ、的な考えの持ち主だが、感情に身をまかせるドラッグ的快感もまたこれまた捨てがたい。
僕も「感情のなせるわざだから、どうしようもない」なんて言いわけしてみたいものだ。感情ほど、自分の思いどおりになるものはないっていうのに。
と、いうわけで、京都アートコンプレックスに行って、戸川純と奇異保の2人芝居「ラスト・デイト」を見て来た。
ヘルプアイドルの野中ひゆちゃんのお誘い。プロデュースの西尾友里さんのご厚意により、招待いただいたのだ。フィネガンズウェイクつながり。
戸川純は鈴木いづみを演じ、奇異保はその夫、阿部薫。
不可聴の音を聞く阿部薫と、不在の阿部薫を顕然せしめる鈴木いづみ。
音楽=時間=速度の世界で、そこにない音を聞き取る阿部薫と、エクリチュール=空間=場所の世界から、そこにいない阿部薫を召喚する鈴木いづみ。
2人の住む世界はもともと違う。
70年代を生きる希望のアナーキストと、80年代まで生きてしまった絶望の作家。
阿部薫は80年代を体験せずにいなくなる、引き際を知った者だ。
鈴木いづみは、常に敗北する人で、それゆえに80年代まで生き延びねばならなかった。
2人の出会いは、その最初からラストデイトであったに違いない。
鈴木いづみは、長い長いデイトを首吊りによって終わらせたのだ。
戸川純が鈴木いづみを演じるのは、ちょっと面白いなあ、と思った。戸川純はきっと鈴木いづみが好きなんだろうが、2人は大きく違っている。
一生のうち、鈴木いづみが生きた女の時間を差し引いた部分が、戸川純の生きている領分だと思うのだ。
つまり、戸川純はデビューの頃から、少女であると同時に老女だったのだ。少女と老女のあいだを埋める形で、鈴木いづみの時間は流れている。
しかも、少女と老女はともに永遠を約束されているが、鈴木いづみときたら、死者なのだ。
作、演出の岩崎正裕の描く鈴木いづみは、僕が考えていた鈴木いづみよりも、随分と俗っぽい。いや、俗っぽいというより、他の誰かと代替可能なありきたりな感じがする。俗っぽいのも、ありきたりなのも、鈴木いづみの特徴なのだが、どこか違う。
女の生きざまを描くのに、それをストレートに出しすぎているような気がした。
だからと言って、演劇がつまらなかったわけではない。
書いた日記をいつも半分くらいの分量に削ってから送信している僕が、このぐだぐだと長ったらしい駄文(しかも的を射ていない)をこのまま送ろうとするほどに、刺激され、興奮しているのだ。
さあ、今、送るぞ。
東京3日め。大阪から持って来た本を読み終えた。
岩波文庫の『バガヴァッド・ギータ−』
かなり前に、違うバージョンで読んだことがあったが、本書の内容を死神ちゃんに教えてあげようとしたら、おおざっぱなあらすじしか伝えられなかった。ほとんど読んでいないも同然だな、と思ったので、新しい翻訳のものを読んでみた。
表紙には「ひとは社会人たることを放棄することなく現世の義務を果たしつつも窮極の境地に達することが可能である、と説く」と書いてある。僕が以前読んだときもほぼ同様の理解だった。
アルジュナは戦争に際して、なぜ同族同士が命を奪いあわねばならないのか、と悩み、敵の命を奪うくらいなら、むしろ自分の命を奪われる方がいい、と思う。
そのとき、クリシュナがヨーガの秘説を説いて、アルジュナの迷いを断つのだ。
「いったい何のために戦うのだ」と迷い悩む主人公、という図式は後年、ロボットアニメなどでさんざん使われる。
で、ここにそのヨーガの秘説について覚え書きを残しておくべきなのだが、どうも僕にはまだまだ要約が困難なようだ。
人には生まれながらなすべき行為が決まっており、それを見返りなしに行為することが大切なのだ、という教えはわかる。俗世を捨てずに、「窮極の境地」に達する事ができるのだ。
でも、バガヴァッド・ギーターには知識の最高の帰結として、「自己を制御し、音声などの感官の対象を捨て、また愛憎を捨て、人里離れた場所に住み、節食し」「常に瞑想のヨーガに専念し」等々で、ブラフマン(最高の存在)と一体化する、と書いてある。こんなことしようと思ったら、俗世を捨てねばならないんじゃないか。
ヨーガの奥義はわからぬまでも、本書には面白い記述が多々ある。
「純質(サットヴァ)」「激質(ラジャス)」「暗質(タマス)」を三要素という。
純質が増大したときは知識の光明が得られ、純質的な者は油質で腹持ちがいい食べ物を好む。
激質が増大したときは活動、躁状態、切望が生ずる。激質的な者が好むのは、苦く、酸っぱく、塩辛く、刺激性の食べ物だ。
暗質が増大したときは怠慢、迷妄、無知が生ずる。暗質的なものの好物は、前日調理された、悪臭をはなつ、食べ残し。
食べ物の好みで、どの要素(グナ)が多いのかが逆算できるってことだ。
インドの話だから、カレーでたとえると、激辛なんかが好きな人はラジャス的な貪欲で偽善的に尊敬されたがる人物。3日めのカレーが一番旨いなんて言う人はタマス的で、無活動、睡眠がもっとも快楽と思える人物なのだ。
そうか?でも、この本にしたがえば、そうなのだ。
世田谷美術館に「瀧口修造 夢の漂流物」を見に行った。ちょうど『バガヴァッド・ギーター』読了後で、ヨーガの真髄について考えていたときだったので、世田谷美術館に行くのはタイムリーだった。最寄り駅は「用賀(ヨウガ)」なのだ。瀧口修造は詩人であり、現代美術の評論家である。本展では、瀧口自身の作品と、1950年代から70年代にかけて、前衛美術家たちが瀧口修造に贈った作品が大量に展示してある。
大量に展示してある、とわかったのは、見れども見れども出口にたどりつかないからだ。膨大な数の漂流物があったものだ。これは一大現代美術展の様相を呈している。デュシャンにミロに合田佐和子に野中ユリに。
また、瀧口の詩や評論文が展示してあれば、読んでしまう。いくら時間があっても足りない。
だがしかし、よく考えてみると、これら作品は瀧口修造個人に贈られたものが大半のはずだ。美術館サイズの倉庫があるなら別だが、これら漂着物はごちゃごちゃのまま、鑑賞する術もなく堆積していたのではないか。もったいない。ひるがえって自分の部屋の中で堆積したまま冬眠している本の数々を思い出すと胸が痛む。
早稲田に出て、流山児祥原作、高取英脚本、天野天街演出の「テロルのオペレッタ 夢の肉弾三勇士」を見に行った。爆弾三勇士に朝鮮人虐殺に、タイムスリップしてきた真田十勇士が絡む。お客さんの鞄を奪い取って穴の中に投げ込む役者たち、お客さんを拉致して穴に放り込む役者。前日の「邪宗門」で拉致されたお客さんは、客のふりをした役者だったが、今回は、本当に客を無理矢理穴に放り込むのだ。途中で這い出してくる客もまた芝居の一部になってしまう。アングラ演劇ここにあり、という王道だった。これを見ると、寺山の「邪宗門」は綺麗すぎる。泥くさくないというか。でも、それは寺山の特異性を示すものなのだろう。
銀座に出て、資生堂ギャラリーで「ローラ・オーエンズ展」
フェルトや紙など、平面を重ねることで不思議な立体感を持たせた可愛い絵画。
平面プラス平面でアンチ立体を実現している、という感じ。
続けて、プラスマイナスギャラリーで「以心伝心 原倫太郎展」
ポンプをスイッチがわりに押すことで液体を動かし、それがさらに何かのスイッチを入れる、連動型の作品が並んでいる。あるスイッチでは色水がチューブの中を走り、スニーカーの靴ひも(チューブ)に色をつける。あるスイッチでは洗濯機のスイッチを入れて、中のものの様子をカメラで見せる。またあるものはシーソーを動かし、その上をボールが転がることで、別のものをまた動かす等々。何が何のスイッチになっているやら。それは因果関係とかブラックボックスとか、いろんな意味づけが可能だろう。でも、これは芸術を鑑賞するというよりも、おもちゃで遊ぶ感覚に近い。
渋谷に出て、中島らも追悼写真展「彼の世でアンコール!」を見た。
若い頃の写真から、原稿、部屋の再現模型など、中島らもは死んでからも人気がある。
僕は追悼ライブに参加できなかったので、焼香でもするような気分で、記帳してきた。
ポータブルラジオで「現代の音楽」を聞こうと思ったが、渋谷は毒電波が飛び交っており、まともに聞くことができなかった。ブツブツと切れる。
ライズXで「アラキメンタリ」を見た。
トラヴィス・クローゼ監督のドキュメンタリー映画。(2004年)
荒木経惟を追った作品。アラーキーの精力的な活動や、妻との死別、その愛については、周知の事実であろう。だからそういう面を描かれても、「へえ、そんな一面があったんだ」もないし、「おお、こんな人が存在しているのか」も、もちろん無い。つまらなかったわけではない。でも、アラーキーを追い掛ければ面白いに決まっているので、その予定調和がいかがなものかと思ったのだ。アメリカ人にとってはものめずらしいのかもしれない。
今日は先日ワークルームでピープショーの展示などされた吉田稔美さんのところに泊めていただいた。彼女は学生時代からの友人で、今は国際的にも優れた仕事をされているが、僕の中ではいつまでもその頃の印象が強い。僕の中で彼女は年をとるのを忘れている人なのだ。
吉田邸にて、サラ・ムーンの映画「サーカス」を見せてもらった。途中からマッチ売りの少女の話になってしまう物語。愛しの女性がいなくなり、ピエロが背中に「Fin」と書いて両手に花火を持って去っていくシーンは印象的。情けないけどね。その他、山田勇男のビデオとか、辻直之のアニメとか貴重な秘蔵映像上映会みたいになった。
その他、彼女の秘蔵の人形だの作品だの、ざっと見せてもらった。まだまだありそうだ。ここでも僕は夢の漂流物をかいま見せてもらったことになる。
岩波文庫の『バガヴァッド・ギータ−』
かなり前に、違うバージョンで読んだことがあったが、本書の内容を死神ちゃんに教えてあげようとしたら、おおざっぱなあらすじしか伝えられなかった。ほとんど読んでいないも同然だな、と思ったので、新しい翻訳のものを読んでみた。
表紙には「ひとは社会人たることを放棄することなく現世の義務を果たしつつも窮極の境地に達することが可能である、と説く」と書いてある。僕が以前読んだときもほぼ同様の理解だった。
アルジュナは戦争に際して、なぜ同族同士が命を奪いあわねばならないのか、と悩み、敵の命を奪うくらいなら、むしろ自分の命を奪われる方がいい、と思う。
そのとき、クリシュナがヨーガの秘説を説いて、アルジュナの迷いを断つのだ。
「いったい何のために戦うのだ」と迷い悩む主人公、という図式は後年、ロボットアニメなどでさんざん使われる。
で、ここにそのヨーガの秘説について覚え書きを残しておくべきなのだが、どうも僕にはまだまだ要約が困難なようだ。
人には生まれながらなすべき行為が決まっており、それを見返りなしに行為することが大切なのだ、という教えはわかる。俗世を捨てずに、「窮極の境地」に達する事ができるのだ。
でも、バガヴァッド・ギーターには知識の最高の帰結として、「自己を制御し、音声などの感官の対象を捨て、また愛憎を捨て、人里離れた場所に住み、節食し」「常に瞑想のヨーガに専念し」等々で、ブラフマン(最高の存在)と一体化する、と書いてある。こんなことしようと思ったら、俗世を捨てねばならないんじゃないか。
ヨーガの奥義はわからぬまでも、本書には面白い記述が多々ある。
「純質(サットヴァ)」「激質(ラジャス)」「暗質(タマス)」を三要素という。
純質が増大したときは知識の光明が得られ、純質的な者は油質で腹持ちがいい食べ物を好む。
激質が増大したときは活動、躁状態、切望が生ずる。激質的な者が好むのは、苦く、酸っぱく、塩辛く、刺激性の食べ物だ。
暗質が増大したときは怠慢、迷妄、無知が生ずる。暗質的なものの好物は、前日調理された、悪臭をはなつ、食べ残し。
食べ物の好みで、どの要素(グナ)が多いのかが逆算できるってことだ。
インドの話だから、カレーでたとえると、激辛なんかが好きな人はラジャス的な貪欲で偽善的に尊敬されたがる人物。3日めのカレーが一番旨いなんて言う人はタマス的で、無活動、睡眠がもっとも快楽と思える人物なのだ。
そうか?でも、この本にしたがえば、そうなのだ。
世田谷美術館に「瀧口修造 夢の漂流物」を見に行った。ちょうど『バガヴァッド・ギーター』読了後で、ヨーガの真髄について考えていたときだったので、世田谷美術館に行くのはタイムリーだった。最寄り駅は「用賀(ヨウガ)」なのだ。瀧口修造は詩人であり、現代美術の評論家である。本展では、瀧口自身の作品と、1950年代から70年代にかけて、前衛美術家たちが瀧口修造に贈った作品が大量に展示してある。
大量に展示してある、とわかったのは、見れども見れども出口にたどりつかないからだ。膨大な数の漂流物があったものだ。これは一大現代美術展の様相を呈している。デュシャンにミロに合田佐和子に野中ユリに。
また、瀧口の詩や評論文が展示してあれば、読んでしまう。いくら時間があっても足りない。
だがしかし、よく考えてみると、これら作品は瀧口修造個人に贈られたものが大半のはずだ。美術館サイズの倉庫があるなら別だが、これら漂着物はごちゃごちゃのまま、鑑賞する術もなく堆積していたのではないか。もったいない。ひるがえって自分の部屋の中で堆積したまま冬眠している本の数々を思い出すと胸が痛む。
早稲田に出て、流山児祥原作、高取英脚本、天野天街演出の「テロルのオペレッタ 夢の肉弾三勇士」を見に行った。爆弾三勇士に朝鮮人虐殺に、タイムスリップしてきた真田十勇士が絡む。お客さんの鞄を奪い取って穴の中に投げ込む役者たち、お客さんを拉致して穴に放り込む役者。前日の「邪宗門」で拉致されたお客さんは、客のふりをした役者だったが、今回は、本当に客を無理矢理穴に放り込むのだ。途中で這い出してくる客もまた芝居の一部になってしまう。アングラ演劇ここにあり、という王道だった。これを見ると、寺山の「邪宗門」は綺麗すぎる。泥くさくないというか。でも、それは寺山の特異性を示すものなのだろう。
銀座に出て、資生堂ギャラリーで「ローラ・オーエンズ展」
フェルトや紙など、平面を重ねることで不思議な立体感を持たせた可愛い絵画。
平面プラス平面でアンチ立体を実現している、という感じ。
続けて、プラスマイナスギャラリーで「以心伝心 原倫太郎展」
ポンプをスイッチがわりに押すことで液体を動かし、それがさらに何かのスイッチを入れる、連動型の作品が並んでいる。あるスイッチでは色水がチューブの中を走り、スニーカーの靴ひも(チューブ)に色をつける。あるスイッチでは洗濯機のスイッチを入れて、中のものの様子をカメラで見せる。またあるものはシーソーを動かし、その上をボールが転がることで、別のものをまた動かす等々。何が何のスイッチになっているやら。それは因果関係とかブラックボックスとか、いろんな意味づけが可能だろう。でも、これは芸術を鑑賞するというよりも、おもちゃで遊ぶ感覚に近い。
渋谷に出て、中島らも追悼写真展「彼の世でアンコール!」を見た。
若い頃の写真から、原稿、部屋の再現模型など、中島らもは死んでからも人気がある。
僕は追悼ライブに参加できなかったので、焼香でもするような気分で、記帳してきた。
ポータブルラジオで「現代の音楽」を聞こうと思ったが、渋谷は毒電波が飛び交っており、まともに聞くことができなかった。ブツブツと切れる。
ライズXで「アラキメンタリ」を見た。
トラヴィス・クローゼ監督のドキュメンタリー映画。(2004年)
荒木経惟を追った作品。アラーキーの精力的な活動や、妻との死別、その愛については、周知の事実であろう。だからそういう面を描かれても、「へえ、そんな一面があったんだ」もないし、「おお、こんな人が存在しているのか」も、もちろん無い。つまらなかったわけではない。でも、アラーキーを追い掛ければ面白いに決まっているので、その予定調和がいかがなものかと思ったのだ。アメリカ人にとってはものめずらしいのかもしれない。
今日は先日ワークルームでピープショーの展示などされた吉田稔美さんのところに泊めていただいた。彼女は学生時代からの友人で、今は国際的にも優れた仕事をされているが、僕の中ではいつまでもその頃の印象が強い。僕の中で彼女は年をとるのを忘れている人なのだ。
吉田邸にて、サラ・ムーンの映画「サーカス」を見せてもらった。途中からマッチ売りの少女の話になってしまう物語。愛しの女性がいなくなり、ピエロが背中に「Fin」と書いて両手に花火を持って去っていくシーンは印象的。情けないけどね。その他、山田勇男のビデオとか、辻直之のアニメとか貴重な秘蔵映像上映会みたいになった。
その他、彼女の秘蔵の人形だの作品だの、ざっと見せてもらった。まだまだありそうだ。ここでも僕は夢の漂流物をかいま見せてもらったことになる。
ミュージカルギャラクシーエンジェル、邪宗門
2005年3月19日 演劇東京2日目はまず、新宿サザンシアターで「ミュージカル ギャラクシーエンジェル」を見た。昨日のWのミュージカルとは微妙に色合いの違うファンたちが大勢グッズ売り場に並んでいる。ギャラクシーエンジェルはアニメを見ていて、そのストーリーは大きく評価していたので、今回もミュージカルを見ることに決めたのだ。
伝説のロストテクノロジー「アワーズ」を使って、銀河ケーキコンテスト用にケーキを作ろうとするミルフィーユ。アワーズはまるで泡立て器そっくりなのだ。
ステージは途中でアイキャッチャーが入ったり、リアクションがまるでアニメ調だったり、かつらと衣装がそのままコスプレとしてキャラクターをあらわしていたり、アニメを見ているみたいだった。
キャストに「ウゴウゴルーガ」の小出由華がおり、蘭花・フランボワーズの役をしている。
帰阪後、「ルーガちゃんが出ていたんでしょう?どうなってた」といろんな人から聞かれたが、あんまり印象に残っていない。普通に綺麗なお姉さんに成長しているのだ。それ以上に、大阪在住の僕にとって「ウゴウゴルーガ」がほとんど見たことのない番組で、なじみが薄いということもあるのだろう。
今回のミュージカルで好感を抱いたのは、明坂聡美演ずるヴァニラ・Hだった。
役も役者もどっちも良い。
いずれ写真などを購入したりするんじゃないか、と自分の行動を予測して、おそろしい。
新宿の紀伊国屋書店でかなり長時間にわたって立ち読みなどしていた。いつも行く本屋と並び方が違うので、欲しくなる本も違ってくる。これは刺激的な読書体験だった。
夜からは池の下プロジェクト公演「邪宗門」を見る。
新宿スペース107に行くまでに、「ダメ、ゼッタイ」のムチャチータの看板を見て、以前このあたりを死神ちゃんとうろうろ歩いていたことを思い出してしまった。僕にとって東京は非日常のイベントだ。なのに、大阪にいるときと同じようなことばかり頭に浮かぶのは、何故だ。
「邪宗門」は寺山修司の作品で、黒子が役者を操り、最後には芝居であることを解体してしまう演劇だ。
客席のお客さんがつかまって、無理矢理役を与えられる。悲鳴をあげるお客さん。
客席を走り回る黒子。
桜吹雪が最後の舞台解体で客席に強風とともに吹き付けられ、客は全員桜まみれになる。
僕は最前列で見ていたので、全身桜になった。
僕はこのまま桜に埋もれていたかった。
マルタ君宅に戻る際、夜景の綺麗な長い橋を渡る。一人の移動時には僕はポータブルラジオでFM聞きながら歩くのだが、橋にさしかかったとき、まるで主題歌のようにデヴィッド・ボウイの「スターマン」がかかった。それはまさに天の配剤。長い長い橋を渡りきるまで、僕は涙を流しっぱなしだった。
伝説のロストテクノロジー「アワーズ」を使って、銀河ケーキコンテスト用にケーキを作ろうとするミルフィーユ。アワーズはまるで泡立て器そっくりなのだ。
ステージは途中でアイキャッチャーが入ったり、リアクションがまるでアニメ調だったり、かつらと衣装がそのままコスプレとしてキャラクターをあらわしていたり、アニメを見ているみたいだった。
キャストに「ウゴウゴルーガ」の小出由華がおり、蘭花・フランボワーズの役をしている。
帰阪後、「ルーガちゃんが出ていたんでしょう?どうなってた」といろんな人から聞かれたが、あんまり印象に残っていない。普通に綺麗なお姉さんに成長しているのだ。それ以上に、大阪在住の僕にとって「ウゴウゴルーガ」がほとんど見たことのない番組で、なじみが薄いということもあるのだろう。
今回のミュージカルで好感を抱いたのは、明坂聡美演ずるヴァニラ・Hだった。
役も役者もどっちも良い。
いずれ写真などを購入したりするんじゃないか、と自分の行動を予測して、おそろしい。
新宿の紀伊国屋書店でかなり長時間にわたって立ち読みなどしていた。いつも行く本屋と並び方が違うので、欲しくなる本も違ってくる。これは刺激的な読書体験だった。
夜からは池の下プロジェクト公演「邪宗門」を見る。
新宿スペース107に行くまでに、「ダメ、ゼッタイ」のムチャチータの看板を見て、以前このあたりを死神ちゃんとうろうろ歩いていたことを思い出してしまった。僕にとって東京は非日常のイベントだ。なのに、大阪にいるときと同じようなことばかり頭に浮かぶのは、何故だ。
「邪宗門」は寺山修司の作品で、黒子が役者を操り、最後には芝居であることを解体してしまう演劇だ。
客席のお客さんがつかまって、無理矢理役を与えられる。悲鳴をあげるお客さん。
客席を走り回る黒子。
桜吹雪が最後の舞台解体で客席に強風とともに吹き付けられ、客は全員桜まみれになる。
僕は最前列で見ていたので、全身桜になった。
僕はこのまま桜に埋もれていたかった。
マルタ君宅に戻る際、夜景の綺麗な長い橋を渡る。一人の移動時には僕はポータブルラジオでFM聞きながら歩くのだが、橋にさしかかったとき、まるで主題歌のようにデヴィッド・ボウイの「スターマン」がかかった。それはまさに天の配剤。長い長い橋を渡りきるまで、僕は涙を流しっぱなしだった。