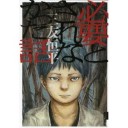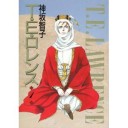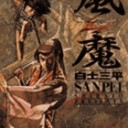Salon the Art Room~一番星
2013年12月1日 アニメ・マンガユーストリーム番組「Salon the Art Room」に進行役で出演してきた。
今回は「魔法少女まどか☆マギカ」の特集で、安斎レオさんが5つの注目点をあげて、解説してくださる、ということだった。
出演は、僕、安斎レオ、杉下淳生、仲村コニー、大阪ひとみ。
ブックレビューでは、安斎さんが『謎の円盤UFO大全』、杉下さんが『ガチ!』僕が『時間ループ物語論』を紹介。
川柳モンパルナスのお題は「魔法」「リボン」「契約」で、当日の出題は「天使」「悪魔」だった。
最初のほうで、なぜかマシントラブルが発生して、再起動しなくてはならなかった。きっと、何かの力が働いていたものと思われる。
番組終了後、日本橋に移動して、出来立てのメイド喫茶「一番星」に行った。
ライブも行われており、店の雰囲気は、まるで学園祭のような楽しさがあった。
竜宮城ではなく、雀のお宿、という感じの店だった。
今回は「魔法少女まどか☆マギカ」の特集で、安斎レオさんが5つの注目点をあげて、解説してくださる、ということだった。
出演は、僕、安斎レオ、杉下淳生、仲村コニー、大阪ひとみ。
ブックレビューでは、安斎さんが『謎の円盤UFO大全』、杉下さんが『ガチ!』僕が『時間ループ物語論』を紹介。
川柳モンパルナスのお題は「魔法」「リボン」「契約」で、当日の出題は「天使」「悪魔」だった。
最初のほうで、なぜかマシントラブルが発生して、再起動しなくてはならなかった。きっと、何かの力が働いていたものと思われる。
番組終了後、日本橋に移動して、出来立てのメイド喫茶「一番星」に行った。
ライブも行われており、店の雰囲気は、まるで学園祭のような楽しさがあった。
竜宮城ではなく、雀のお宿、という感じの店だった。
アートスペース亜蛮人で「ブツケルモノタチ」第2週。
木岡英敏、史群アル仙の作品。
あふれでてる感じがいい。
夜、アメリカ村三角公園近くで、ライブペインティング&ノイズをゲリラ的にやっている人たちがいた。あれは誰だったんだろう。交番もすぐ近くにあるのに、やり逃げできたのはすごい。
堀江のART HOUSEでPEASアニメーション上映会。
「汚点」中村武
「骨」橋本誠史
「ただいま」村上直子
「歩行」村上裕
「長猫」K.Kotani
「いつも、そう」中村伊久映
「バートルビー」服部拓磨
「やみうた」安居佳吾
「When I was young…」オオニシカオリ
「瞬きフィルム」出雲絵里菜
自由な発想の作品が面白かった。
木岡英敏、史群アル仙の作品。
あふれでてる感じがいい。
夜、アメリカ村三角公園近くで、ライブペインティング&ノイズをゲリラ的にやっている人たちがいた。あれは誰だったんだろう。交番もすぐ近くにあるのに、やり逃げできたのはすごい。
堀江のART HOUSEでPEASアニメーション上映会。
「汚点」中村武
「骨」橋本誠史
「ただいま」村上直子
「歩行」村上裕
「長猫」K.Kotani
「いつも、そう」中村伊久映
「バートルビー」服部拓磨
「やみうた」安居佳吾
「When I was young…」オオニシカオリ
「瞬きフィルム」出雲絵里菜
自由な発想の作品が面白かった。
ツイン21の古書市に行って来た。
なんだか寒くて天候もよくないので、外に出るのがためらわれたが、家にいるのが一番寒くて、だらだらしてしまうので、外出。
古書市では、昔の探偵小説を中心に探してみたが、今回のラインナップは、あまり探偵小説を置いていない感じだった。
探している大下宇陀児や、ファントメットが見つからなかったのは、予想済みとして、探し方が悪かったのか、『宝石』の1冊も見当たらなかったように思う。
と、いうことで、3時間ほどかけて念入りに本を見たあげく、何も買わずに帰宅。
ただし、帰宅途中に、自宅近くの古本屋に行って、特価本を10冊ほど買った。
手ぶらで帰るのが何とも面白くなかったせいもある。
で、これと言って何もしなかった1日だったが、漫画は1冊読んだ。
三友恒平の『必要とされなかった話』
村の食糧庫が火事で焼けてしまったため、口べらしのために、長老は村民全員にこう尋ねる。
「村の全員がはやり病で死にかけているとき、1人分の特効薬を持っていたら、それを誰に使うか」
主人公の少年は迷わずに姉と答える。
この質問は、誰からも名指しされずにいた人物を「必要とされなかった人物」として、森に捨ててしまおう、という選択の質問だったのだ。
少年は誰からも名指しされずに、森に捨てられる。
少年の姉は、迷った末に、配偶者を選んでいた。
森で少年が出会ったのは、片足をなくした狼。
いわばこの狼も仲間から捨てられて死の宣告を受けた存在も同然だった。
少年と狼は、協力して獲物をとらえることによって、共生するようになる。
さて、と、いう物語。
誰かを選ばねばならないときに、誰を選べばいいのか、という「ソフィーの選択」みたいな状況は、たまに夢で見ることがある。
たいていはアイドルユニットがいて、断崖絶壁で、僕が1人だけ助けることができれば誰を助けるのか、という状況だ。
アイドルという存在自体が好きな僕(それをDDと呼ぶ場合もあろう)にとっては、非常に難しい選択だ。
まあ、それはそれとして、この漫画の結論は、さしあたっては共生が必要でも、最終的には一人で生きていく力を持たねばならない。そのためには別れも必要、というものだった。
やたらと承認欲求だけが取り沙汰される今に対するメッセージと受け取れる。
たとえば、ツイッターなどでフォロワーの数が多いことを誇る、みたいな風潮。
必要とされる人材を第一に目指すための資格やスキルばかりを取り沙汰する社会の風潮。
そういうのは、中に入ってしまうと、それが当たり前になってしまって、考えなおすこともしなくなってしまうのが、こわい。
なんだか寒くて天候もよくないので、外に出るのがためらわれたが、家にいるのが一番寒くて、だらだらしてしまうので、外出。
古書市では、昔の探偵小説を中心に探してみたが、今回のラインナップは、あまり探偵小説を置いていない感じだった。
探している大下宇陀児や、ファントメットが見つからなかったのは、予想済みとして、探し方が悪かったのか、『宝石』の1冊も見当たらなかったように思う。
と、いうことで、3時間ほどかけて念入りに本を見たあげく、何も買わずに帰宅。
ただし、帰宅途中に、自宅近くの古本屋に行って、特価本を10冊ほど買った。
手ぶらで帰るのが何とも面白くなかったせいもある。
で、これと言って何もしなかった1日だったが、漫画は1冊読んだ。
三友恒平の『必要とされなかった話』
村の食糧庫が火事で焼けてしまったため、口べらしのために、長老は村民全員にこう尋ねる。
「村の全員がはやり病で死にかけているとき、1人分の特効薬を持っていたら、それを誰に使うか」
主人公の少年は迷わずに姉と答える。
この質問は、誰からも名指しされずにいた人物を「必要とされなかった人物」として、森に捨ててしまおう、という選択の質問だったのだ。
少年は誰からも名指しされずに、森に捨てられる。
少年の姉は、迷った末に、配偶者を選んでいた。
森で少年が出会ったのは、片足をなくした狼。
いわばこの狼も仲間から捨てられて死の宣告を受けた存在も同然だった。
少年と狼は、協力して獲物をとらえることによって、共生するようになる。
さて、と、いう物語。
誰かを選ばねばならないときに、誰を選べばいいのか、という「ソフィーの選択」みたいな状況は、たまに夢で見ることがある。
たいていはアイドルユニットがいて、断崖絶壁で、僕が1人だけ助けることができれば誰を助けるのか、という状況だ。
アイドルという存在自体が好きな僕(それをDDと呼ぶ場合もあろう)にとっては、非常に難しい選択だ。
まあ、それはそれとして、この漫画の結論は、さしあたっては共生が必要でも、最終的には一人で生きていく力を持たねばならない。そのためには別れも必要、というものだった。
やたらと承認欲求だけが取り沙汰される今に対するメッセージと受け取れる。
たとえば、ツイッターなどでフォロワーの数が多いことを誇る、みたいな風潮。
必要とされる人材を第一に目指すための資格やスキルばかりを取り沙汰する社会の風潮。
そういうのは、中に入ってしまうと、それが当たり前になってしまって、考えなおすこともしなくなってしまうのが、こわい。
白土三平の『消え行く少女』を読んだ。
とことん不幸な話。
原爆で家族を失い、原子病(!)になった少女は、どこに行っても厄介者扱いされ、たまに優しい人に出会っても、自分の存在がそのひとに迷惑をかけていると思って、その場所を去る。
少女はこどもたちには「乞食だ」、と石を投げられ、犬は襲い掛かって衣服や荷物をズタズタにされ、厄介になった居候先では泥棒扱いされ、原爆の病気は何の治療も施されないままに悪化し、そもそも現代の医学ではどうしようもない不治の病。
彼女を守ろうとする少年とはすれ違い、おばあさんには宮城参賀の事故で死なれ、朝鮮人は強制送還され、結局、孤独のままに死亡、解剖に付されて、文字通り「消え行く」のである。
後編にある「前号までのあらすじ」から引用すると。
時事的な社会派、という以上に、いつの時代にも通じる悲劇であるように思えた。
梅田のビッグマン前で、バンプレストの造形天下一武道会の作品展示。
寒河江さんのクリリンを応援!
孫悟空少年期(松浦健)VSランチ(中澤博之)
孫悟空青年期(浩貴)VS牛魔王(山下マナブ)
クリリン(寒河江弘)VS桃白白(大西孝治)
クリリンの相手は桃白白か!
これを「桃白白」(タオパイパイ)にちなんで、「TPP問題」と呼ぶ。
とことん不幸な話。
原爆で家族を失い、原子病(!)になった少女は、どこに行っても厄介者扱いされ、たまに優しい人に出会っても、自分の存在がそのひとに迷惑をかけていると思って、その場所を去る。
少女はこどもたちには「乞食だ」、と石を投げられ、犬は襲い掛かって衣服や荷物をズタズタにされ、厄介になった居候先では泥棒扱いされ、原爆の病気は何の治療も施されないままに悪化し、そもそも現代の医学ではどうしようもない不治の病。
彼女を守ろうとする少年とはすれ違い、おばあさんには宮城参賀の事故で死なれ、朝鮮人は強制送還され、結局、孤独のままに死亡、解剖に付されて、文字通り「消え行く」のである。
後編にある「前号までのあらすじ」から引用すると。
たった、14才の少女が・・・しかも原子病というおそろしい病気をもった・・・たった一人でこの世にとびだしていって・・・一体生きて行くことが出来るのだろうか?それほど世の中の人々は親切なのだろうか?いやたとえ親切であったとしても自分自身がくうかくわれるかの世の中である・・・
今はまったくこじきのようになってしまった雪子・・・しかし誰も一目で病気とわかるみよりのない少女にやさしい手をさしのべるものはなかった・・・もしあったとしても、自分や自分の家族をやしなうのにせいいっぱいな世の中ではただ同情とあわれみのまなざしを投げるだけであったろう。
時事的な社会派、という以上に、いつの時代にも通じる悲劇であるように思えた。
梅田のビッグマン前で、バンプレストの造形天下一武道会の作品展示。
寒河江さんのクリリンを応援!
孫悟空少年期(松浦健)VSランチ(中澤博之)
孫悟空青年期(浩貴)VS牛魔王(山下マナブ)
クリリン(寒河江弘)VS桃白白(大西孝治)
クリリンの相手は桃白白か!
これを「桃白白」(タオパイパイ)にちなんで、「TPP問題」と呼ぶ。
『T・E・ロレンス』
2011年10月18日 アニメ・マンガ
『T・E・ロレンス』を読んだ。
力作だし、めちゃくちゃ面白かった。
アラビアのロレンスで名を知られる実在の男性の生涯を追ったフィクション。
アラブの戦争とか、国際情勢とか、けっこう硬い内容なのに、どうして人気あるのか、と読む前には思っていたが、読んでみて、ちょっと納得した。
僕の印象では、ロレンスの世界は男の世界そのものなのだが、この漫画では、ロレンスが同性愛者で、マゾヒストである、という描写をときおりまぜることで、女性読者のハートをつかんだのだろう。
どういうわけか、その手の性愛描写になると、(ヘテロであっても)、時間のむだみたいに思えて、とばし読みしてしまうのだが、この漫画の程度なら、なんとか大丈夫。それでも、ときどきロレンスが男同士の性愛場面に至ると、これって必要なのか、と思ってしまった。
最近の少年漫画にみられる、頭の中が性愛しかないような内容に比べると、断然いいけど!
たぶん、僕は、性愛は自分が体験するときにこそ楽しいのであって、他人や虚構の性愛などつまらない、と思っているのだ。
力作だし、めちゃくちゃ面白かった。
アラビアのロレンスで名を知られる実在の男性の生涯を追ったフィクション。
アラブの戦争とか、国際情勢とか、けっこう硬い内容なのに、どうして人気あるのか、と読む前には思っていたが、読んでみて、ちょっと納得した。
僕の印象では、ロレンスの世界は男の世界そのものなのだが、この漫画では、ロレンスが同性愛者で、マゾヒストである、という描写をときおりまぜることで、女性読者のハートをつかんだのだろう。
どういうわけか、その手の性愛描写になると、(ヘテロであっても)、時間のむだみたいに思えて、とばし読みしてしまうのだが、この漫画の程度なら、なんとか大丈夫。それでも、ときどきロレンスが男同士の性愛場面に至ると、これって必要なのか、と思ってしまった。
最近の少年漫画にみられる、頭の中が性愛しかないような内容に比べると、断然いいけど!
たぶん、僕は、性愛は自分が体験するときにこそ楽しいのであって、他人や虚構の性愛などつまらない、と思っているのだ。
今日は、自然に恵まれた某場所を散策&探索。
いずれ、その詳細については、報告することもあるだろう。
白土三平の『風魔』を読んだ。小学館文庫の二分冊本。(写真は別バージョン)
忍者の権利を守る風魔のシリーズ。
今までの作品に出てきた登場人物が出てきたりもするが、その都度説明があって、シリーズものによくあるような、さっぱり話が見えない、てなことはない。
以下、目次。
1
二階堂乱舞の巻
プロローグ
第1章・神かくし
第2章・亡霊復活
第3章・多面武蔵
第4章・異変二階堂流
第5章・二階堂乱舞
2
シジマ無情の巻
第6章・猿風
第7章・月影
第8章・螢火狂乱
第9章・竜煙
第10章・飢牙作戦
第11章・シジマ無情
身体を瞬間的に視界から消す「一本ヤグラ」
空を駆ける「天足通」
など、忍術がそのからくりとともにストーリーの要となるのが面白い。
からくり、といえば、二階堂流秘術「心の一方」は、まるでジョジョに出てくるディオのスタンド「ザ・ワールド」を思わせた。
とじこめたはずの者が、いつのまにやら抜け出ていて、背後から襲う、みたいな技。きっと、この「心の一方」を読んでいて、「ザ・ワールド」を思いついたんじゃないか、と思えるほど。
いずれ、その詳細については、報告することもあるだろう。
白土三平の『風魔』を読んだ。小学館文庫の二分冊本。(写真は別バージョン)
忍者の権利を守る風魔のシリーズ。
今までの作品に出てきた登場人物が出てきたりもするが、その都度説明があって、シリーズものによくあるような、さっぱり話が見えない、てなことはない。
以下、目次。
1
二階堂乱舞の巻
プロローグ
第1章・神かくし
第2章・亡霊復活
第3章・多面武蔵
第4章・異変二階堂流
第5章・二階堂乱舞
2
シジマ無情の巻
第6章・猿風
第7章・月影
第8章・螢火狂乱
第9章・竜煙
第10章・飢牙作戦
第11章・シジマ無情
身体を瞬間的に視界から消す「一本ヤグラ」
空を駆ける「天足通」
など、忍術がそのからくりとともにストーリーの要となるのが面白い。
からくり、といえば、二階堂流秘術「心の一方」は、まるでジョジョに出てくるディオのスタンド「ザ・ワールド」を思わせた。
とじこめたはずの者が、いつのまにやら抜け出ていて、背後から襲う、みたいな技。きっと、この「心の一方」を読んでいて、「ザ・ワールド」を思いついたんじゃないか、と思えるほど。
ジョージ秋山の『アシュラ』を読んだ。
最近、タイガーマスクとか、あしたのジョーとか、古めの漫画がリバイバルしているので、次はきっとこれだろう、と踏んで、ぱらぱらと頁めくってたら、最初の数ページの迫力に巻き込まれて、最後まで読み通してしまった。
日本の中世についても、もう1回読み直してみたくなった。
ラストの銭ゲバそっくりなやつ(スター・システム?)が出てきたあたりから、話が急展開というか、絶対これ、ページ抜けてるな、と思えるようなバタバタ感があった。完結編や番外編も今では読めるようなので、近いうちに読もう。
最近、タイガーマスクとか、あしたのジョーとか、古めの漫画がリバイバルしているので、次はきっとこれだろう、と踏んで、ぱらぱらと頁めくってたら、最初の数ページの迫力に巻き込まれて、最後まで読み通してしまった。
日本の中世についても、もう1回読み直してみたくなった。
ラストの銭ゲバそっくりなやつ(スター・システム?)が出てきたあたりから、話が急展開というか、絶対これ、ページ抜けてるな、と思えるようなバタバタ感があった。完結編や番外編も今では読めるようなので、近いうちに読もう。
「フランダースの犬」放送35周年記念 世界名作劇場展
2010年8月13日 アニメ・マンガ
高島屋のグランドホールで「世界名作劇場展」
ハイジは「世界名作劇場」じゃないんだな。
あと、マルコの話じゃない「クオレ」もあったように思ったけど、これも別なのか。
名作劇場、と銘打っているが、人気の度合いは、動物が握っており、なんといっても一番の人気は「あらいぐまラスカル」だった。グッズの数も展示物の数も半端じゃない。もっとも「名作」度が低いのに!(失礼!)
あとは、フランダースの犬のパトラッシュとか。
人間の主人公でこの2匹をこえる人気ものはいないようだ。
会場内では、アニメの総集編や最終回などを複数の場所で上映していた。
その大画面で「ロミオの青い空」の最終回を見た。人身売買の話だったのか。
ジオラマ再現のコーナーで、「フランダースの犬」と「ラスカル」の最終回も見た。
ハイジは「世界名作劇場」じゃないんだな。
あと、マルコの話じゃない「クオレ」もあったように思ったけど、これも別なのか。
名作劇場、と銘打っているが、人気の度合いは、動物が握っており、なんといっても一番の人気は「あらいぐまラスカル」だった。グッズの数も展示物の数も半端じゃない。もっとも「名作」度が低いのに!(失礼!)
あとは、フランダースの犬のパトラッシュとか。
人間の主人公でこの2匹をこえる人気ものはいないようだ。
会場内では、アニメの総集編や最終回などを複数の場所で上映していた。
その大画面で「ロミオの青い空」の最終回を見た。人身売買の話だったのか。
ジオラマ再現のコーナーで、「フランダースの犬」と「ラスカル」の最終回も見た。
漂流教室(サンデーコミックス版)
2009年2月7日 アニメ・マンガ楳図かずおの『漂流教室』サンデーコミックス版全11巻を読んだ。
読んだのは実に30年ぶりか。
完全版はさらに約180ページ増量らしい。
コミックスにすると1冊分くらい。
その日の朝/ゆれた教室/おびえる目/とざされた世界/狂気をよぶパン/6年3組の挑戦/862人の墓標/死の遠出/母の願い/壁の中からの叫び/いけにえ/一枚の木の葉/新リーダー・女番長/大和小学校国の門出/せまりくる大怪虫/捨て身の挑戦/小さな強敵/勇気ある一撃/死を呼ぶ渇き/黒い斑点/狂気のペスト禍/果てしなき暴走/しのびよる死の影/時をへだてて/失われた光明/未来植物の試食/のろいの教団/巨大な目/つめたい目/暗黒の世界/滅亡の記録/母の贈り物/闇からの脱出/恐怖の糸/失われた友情/危険な執刀/女番長の遺言/死の行進/危険な天国/飢餓集団/いつわりの告白/よみがえった友情/漂流の果てに
印象深かったのは「のろいの教団」の章で、一つ目教をつくり、へび女的変貌を遂げつつある美川(よしかわ)さんが、目をあけたまま眠っていたり、音楽室でピアノ弾きながら「ヒュ〜ッ」と歌っているシーン。
それと、「危険な天国」の章で、富士大レジャーランド・天国の案内用ロボット(マリリンモンローを模している)が「どうぞ…こちらへ…」と言いながら追いかけてくるシーン。このシーンは怖くて、はじめて読んだときからずっと悪夢のように記憶にこびりついていた。
今回再読してみて、「蠅の王」とか「皆殺しの天使」とか「火星年代記」などをちらっと想起してしまい、年をくって要らぬ知識が増えた弊害を感じた。
読んだのは実に30年ぶりか。
完全版はさらに約180ページ増量らしい。
コミックスにすると1冊分くらい。
その日の朝/ゆれた教室/おびえる目/とざされた世界/狂気をよぶパン/6年3組の挑戦/862人の墓標/死の遠出/母の願い/壁の中からの叫び/いけにえ/一枚の木の葉/新リーダー・女番長/大和小学校国の門出/せまりくる大怪虫/捨て身の挑戦/小さな強敵/勇気ある一撃/死を呼ぶ渇き/黒い斑点/狂気のペスト禍/果てしなき暴走/しのびよる死の影/時をへだてて/失われた光明/未来植物の試食/のろいの教団/巨大な目/つめたい目/暗黒の世界/滅亡の記録/母の贈り物/闇からの脱出/恐怖の糸/失われた友情/危険な執刀/女番長の遺言/死の行進/危険な天国/飢餓集団/いつわりの告白/よみがえった友情/漂流の果てに
印象深かったのは「のろいの教団」の章で、一つ目教をつくり、へび女的変貌を遂げつつある美川(よしかわ)さんが、目をあけたまま眠っていたり、音楽室でピアノ弾きながら「ヒュ〜ッ」と歌っているシーン。
それと、「危険な天国」の章で、富士大レジャーランド・天国の案内用ロボット(マリリンモンローを模している)が「どうぞ…こちらへ…」と言いながら追いかけてくるシーン。このシーンは怖くて、はじめて読んだときからずっと悪夢のように記憶にこびりついていた。
今回再読してみて、「蠅の王」とか「皆殺しの天使」とか「火星年代記」などをちらっと想起してしまい、年をくって要らぬ知識が増えた弊害を感じた。
まぼろし城(完全版)
2008年7月31日 アニメ・マンガ桑田次郎の『まぼろし城』完全版上中下を読んだ。
隠密、木暮月之介の活躍を描く。
上巻は、どくろ仮面のまぼろし武士たちとまぼろし城主が敵。
将軍に献上する名馬を盗んで、その身代金をせしめようとする陰謀。
隠密の木暮月之介は、白天狗の変装をして、まぼろし武士に立ち向かう。
白天狗の着想は、まんま月光仮面で、高垣眸の原作にはない設定だ。(と、思う。『少年倶楽部』昭和11年の連載分では、こういう設定はなかった。長編バージョンは未読で不明。ただ、これも高垣の漫画用原作としてのアイディアだったかもしれず、さだかでない)
中巻は、KKKを思わせるトンガリ頭巾の一つ目鮫のひとつめ党が敵。
まぼろし城の秘宝のありかを記したあぶりだしの絵図面をめぐる争奪戦。
ここでは白天狗は登場しない。
中巻後半からは、幽霊船の物語。御用船の金銀を奪う海賊。
死んだはずのまぼろし城主があらわれる。
高垣原作の『荒海の虹』のストーリーも組み合わせながら、月之介の忍術とまぼろし城主の幻術一騎討ち。
下巻は、脱獄したまぼろし城主(クーター・バランと名乗った!)が悪の般若党を乗っ取って党首におさまり、月之介に報復を企てる。
最後は再び、クーター・バランと月之介の一騎討ち。ネーミングのセンスは桑田次郎丸出しなんだけどなあ。
隠密、木暮月之介の活躍を描く。
上巻は、どくろ仮面のまぼろし武士たちとまぼろし城主が敵。
将軍に献上する名馬を盗んで、その身代金をせしめようとする陰謀。
隠密の木暮月之介は、白天狗の変装をして、まぼろし武士に立ち向かう。
白天狗の着想は、まんま月光仮面で、高垣眸の原作にはない設定だ。(と、思う。『少年倶楽部』昭和11年の連載分では、こういう設定はなかった。長編バージョンは未読で不明。ただ、これも高垣の漫画用原作としてのアイディアだったかもしれず、さだかでない)
中巻は、KKKを思わせるトンガリ頭巾の一つ目鮫のひとつめ党が敵。
まぼろし城の秘宝のありかを記したあぶりだしの絵図面をめぐる争奪戦。
ここでは白天狗は登場しない。
中巻後半からは、幽霊船の物語。御用船の金銀を奪う海賊。
死んだはずのまぼろし城主があらわれる。
高垣原作の『荒海の虹』のストーリーも組み合わせながら、月之介の忍術とまぼろし城主の幻術一騎討ち。
下巻は、脱獄したまぼろし城主(クーター・バランと名乗った!)が悪の般若党を乗っ取って党首におさまり、月之介に報復を企てる。
最後は再び、クーター・バランと月之介の一騎討ち。ネーミングのセンスは桑田次郎丸出しなんだけどなあ。
ジュンク堂大阪本店でアントニオ・ネグリとマイケル・ハート著『ディオニュソスの労働〜国家形態批判』出版記念トークセッション「労働の拒否と生きた労働〜資本の支配を生き抜くために〜」が開かれた。
翻訳者のうちから酒井隆史(社会思想史)と崎山政毅(ラテンアメリカ研究)の2人がパネラーとなってトークを行った。
トークセッションの広告には、こんなふうに書いてある。
「ネオリベラリズムに抗する主体としてのマルチチュードの可能性はどこから発するのか。アウトノミアの思想家、アントニオ・ネグリの思考の源泉から『帝国』『マルチチュード』の意味をあらためて問い直す」
さあ、困った。
この『ディオニュソスの労働』は『帝国』『マルチチュード』に先立つ本である。
『ディオニュソスの労働』の構成を第1章「批判としてのコミュニズム」の「道程−経路」から抜粋してみると、
本書の第1部の第2章(ケインズと国家の資本主義的理論)および第3章(憲法における労働)は、1960年代にアントニオ・ネグリによって書かれた。ネグリは、著名な資本主義的な経済学や法理論の理論家たちの読解をとおして、近代的な国家−形態の主たる諸要素と、そのうえに国家がそびえたつ資本と労働の弁証法的な関係性を規定しようとする。
第2部の諸章は、1970年代にアントニオ・ネグリによって書かれたものである。そこで彼は、とくに公的支出という立論構制に関わる正当性と蓄積を担う国家のメカニズムという視点から、近代国家の危機の本質に接近している。これらの論文は、さまざまなマルクス主義者やコミュニストにおける国家解釈と、国家に対する実践的批判を提出する社会運動に焦点を当てている。
第3部は、過去3年間にわたって二人の著者によって協働的に書かれた。これら最後の諸章はそれらが描く道筋総体によって本書に概観を与えるという作業に当てられる。その内容は、第一にポストモダンな資本主義国家を規定する論理と構造について詳述し、第二にこの新たな領野に立ち現れる国家の枠組の外部における社会的表現を担う潜勢力のオルタナティヴな諸形態について分析を加える、という二つの作業から成り立っている。
よし、これで本書の見取り図は入手できた。ところが、あいにくとまだ読了できていなくて、それどころか、なんだかよくわからなくなってきて、一から読み直しだ、と思っていた矢先のトークセッションだった。ちなみに、僕は第1部途中で迷宮に入り、すっとばして第3部から読んだりしていた。
さて、トークセッション。
酒井氏は「序」から「本書の狙いは悦びの実践の提起にある」という一文をひき、崎山氏は、本書のわかりにくさは、結論が書かれていないところにある、と説明する(本書のあとがきでも崎山氏は同様のことを書かれている)。配られたコピーで山崎カヲルの書評を読むと、「これは議論に向かって開かれた本なのだ」としめくくってある。
つまり、これは自分の日常や労働にひきつけて読むべき本なのだ、ということだった。トークはざっくりとしたものだったが、細かいことに囚われて滞留していた読みの詰まりが取れたような気がした。停滞しているのが馬鹿らしくなってきた、というか。とは言え、読み終わるのはまだまだ先のことになりそうだ。
読書中より、このトークセッションの方が面白い、と思えてしまうあたりに、僕の読解力の限界があるようにも感じた。
と、言うわけで、今日読んだのは上村一夫の『一葉裏日誌』
一葉裏日誌
「たけくらべの頃」
「花ごもりの頃」
「にごりえの頃」
うたまる
帯の男(全6話)
最近、日本の文化に興味が湧いている。
それは、パトレイバー見て急に再燃した落語のマイブームがもとになっているんだろうけど、こういう「和」への傾倒はひょっとしてナショナリズムなんじゃないか、と思う節もあって、注意しておかねばならない。オリンピックが近づいていることともあいまって、まんまとマスコミの術中にはまっているのかもしれないからだ。あと、マルチニーク島在住の孫(小6)が夏休みを利用して日本に帰ってきていることも関係しているのかもしれない。フランス語をしゃべる孫は伝統的な日本文化からポケモン、ガンダムまで、日本を味わいつくしてやろう、と毎日飛び歩いているのである。
この『一葉裏日誌』では、置屋、おはぐろ溝、鉄道馬車、白熱ガス灯、絵師、間男結び、手鎖り結び、竹人形、稲穂のかんざし、顔師、荒縄結び、といった日本的なものがふんだんに出てくる。
どの話もよく出来たミステリになっていて、そっちの興味からも、たいへん面白い1冊だった。
翻訳者のうちから酒井隆史(社会思想史)と崎山政毅(ラテンアメリカ研究)の2人がパネラーとなってトークを行った。
トークセッションの広告には、こんなふうに書いてある。
「ネオリベラリズムに抗する主体としてのマルチチュードの可能性はどこから発するのか。アウトノミアの思想家、アントニオ・ネグリの思考の源泉から『帝国』『マルチチュード』の意味をあらためて問い直す」
さあ、困った。
この『ディオニュソスの労働』は『帝国』『マルチチュード』に先立つ本である。
『ディオニュソスの労働』の構成を第1章「批判としてのコミュニズム」の「道程−経路」から抜粋してみると、
本書の第1部の第2章(ケインズと国家の資本主義的理論)および第3章(憲法における労働)は、1960年代にアントニオ・ネグリによって書かれた。ネグリは、著名な資本主義的な経済学や法理論の理論家たちの読解をとおして、近代的な国家−形態の主たる諸要素と、そのうえに国家がそびえたつ資本と労働の弁証法的な関係性を規定しようとする。
第2部の諸章は、1970年代にアントニオ・ネグリによって書かれたものである。そこで彼は、とくに公的支出という立論構制に関わる正当性と蓄積を担う国家のメカニズムという視点から、近代国家の危機の本質に接近している。これらの論文は、さまざまなマルクス主義者やコミュニストにおける国家解釈と、国家に対する実践的批判を提出する社会運動に焦点を当てている。
第3部は、過去3年間にわたって二人の著者によって協働的に書かれた。これら最後の諸章はそれらが描く道筋総体によって本書に概観を与えるという作業に当てられる。その内容は、第一にポストモダンな資本主義国家を規定する論理と構造について詳述し、第二にこの新たな領野に立ち現れる国家の枠組の外部における社会的表現を担う潜勢力のオルタナティヴな諸形態について分析を加える、という二つの作業から成り立っている。
よし、これで本書の見取り図は入手できた。ところが、あいにくとまだ読了できていなくて、それどころか、なんだかよくわからなくなってきて、一から読み直しだ、と思っていた矢先のトークセッションだった。ちなみに、僕は第1部途中で迷宮に入り、すっとばして第3部から読んだりしていた。
さて、トークセッション。
酒井氏は「序」から「本書の狙いは悦びの実践の提起にある」という一文をひき、崎山氏は、本書のわかりにくさは、結論が書かれていないところにある、と説明する(本書のあとがきでも崎山氏は同様のことを書かれている)。配られたコピーで山崎カヲルの書評を読むと、「これは議論に向かって開かれた本なのだ」としめくくってある。
つまり、これは自分の日常や労働にひきつけて読むべき本なのだ、ということだった。トークはざっくりとしたものだったが、細かいことに囚われて滞留していた読みの詰まりが取れたような気がした。停滞しているのが馬鹿らしくなってきた、というか。とは言え、読み終わるのはまだまだ先のことになりそうだ。
読書中より、このトークセッションの方が面白い、と思えてしまうあたりに、僕の読解力の限界があるようにも感じた。
と、言うわけで、今日読んだのは上村一夫の『一葉裏日誌』
一葉裏日誌
「たけくらべの頃」
「花ごもりの頃」
「にごりえの頃」
うたまる
帯の男(全6話)
最近、日本の文化に興味が湧いている。
それは、パトレイバー見て急に再燃した落語のマイブームがもとになっているんだろうけど、こういう「和」への傾倒はひょっとしてナショナリズムなんじゃないか、と思う節もあって、注意しておかねばならない。オリンピックが近づいていることともあいまって、まんまとマスコミの術中にはまっているのかもしれないからだ。あと、マルチニーク島在住の孫(小6)が夏休みを利用して日本に帰ってきていることも関係しているのかもしれない。フランス語をしゃべる孫は伝統的な日本文化からポケモン、ガンダムまで、日本を味わいつくしてやろう、と毎日飛び歩いているのである。
この『一葉裏日誌』では、置屋、おはぐろ溝、鉄道馬車、白熱ガス灯、絵師、間男結び、手鎖り結び、竹人形、稲穂のかんざし、顔師、荒縄結び、といった日本的なものがふんだんに出てくる。
どの話もよく出来たミステリになっていて、そっちの興味からも、たいへん面白い1冊だった。
落語:上方演芸ホール(録画)
笑福亭瓶太「田楽喰い」
ん廻しで「医療保険年金天引きちんぷんかんぷん、じーちゃんばーちゃんカンカン」で「ん」の数だけおでんもらう。
桂文華「はてなの茶碗」
漫画:桑田次郎の『エスパー3』
連載当時(1964)の扉によるあらすじ。「ものしずかな、めくらの青年ジョージ秋月。だが、この青年こそ、ひともしらぬふしぎな能力をもつエスパー(超能力者)だったのだ!」
座頭市のエスパー版か。「3」はジョージ秋月のもつ3つの能力「観念動力」「透視能力」「精神感応」を指す。エスパーのペスター編と、めちゃくちゃ短くて尻切れとんぼのカーマイン首相編。
収録作品「悪魔博士」地球の危機と思わせて人類をロケットで宇宙に向かわせるザダン星人。ザダン星人は人類を食糧にする計画を秘めていた。
収録作品「般若」邪教般若教のアジトは火山の上。火山活動で自滅。
笑福亭瓶太「田楽喰い」
ん廻しで「医療保険年金天引きちんぷんかんぷん、じーちゃんばーちゃんカンカン」で「ん」の数だけおでんもらう。
桂文華「はてなの茶碗」
漫画:桑田次郎の『エスパー3』
連載当時(1964)の扉によるあらすじ。「ものしずかな、めくらの青年ジョージ秋月。だが、この青年こそ、ひともしらぬふしぎな能力をもつエスパー(超能力者)だったのだ!」
座頭市のエスパー版か。「3」はジョージ秋月のもつ3つの能力「観念動力」「透視能力」「精神感応」を指す。エスパーのペスター編と、めちゃくちゃ短くて尻切れとんぼのカーマイン首相編。
収録作品「悪魔博士」地球の危機と思わせて人類をロケットで宇宙に向かわせるザダン星人。ザダン星人は人類を食糧にする計画を秘めていた。
収録作品「般若」邪教般若教のアジトは火山の上。火山活動で自滅。
石井いさみの漫画『アッパーセブン神出鬼没』を読んだ。
雑誌「まんが王」昭和42年11月号別冊付録。
この漫画、リアルタイムで読んでいて、アッパーセブンが鉄の手袋をはめて敵にチョップを見舞うシーンとか、強烈に印象に残っていた。ただ、タイトルや作者はほとんど忘れており、「なんとかセブン」くらいが手がかりだった。今回、古本屋で見つけて買い、まさにドンピシャリの漫画だったので興奮した。40年ぶりの再会だ。
「アッパーセブン神出鬼没」はイタリア映画「L’UOMO DE UCCIDERE」を漫画化したもの。
目次は以下のとおり。
1、ライセンスJ7
2、コブラスとチェンとサントス
3、テムズ川は赤信号
4、10億ドルへの脱出
5、銀行は正面からはいれ
6、すてきな相棒
7、風がないている
8、神出鬼没
アッパーセブンことポール・フィニーは西側諜報部員。
南アフリカとアメリカ間でとりかわされる10億ドルの取引に関して冒険がはじまる。
東側の秘密組織が取引を妨害しようとしているとの情報を受けて、アッパー7は組織の黒幕を調査する。
黒幕のコブラスの計画は、アメリカから出る10億ドルを贋札にすりかえて、アメリカの信用を失墜させ、さらに南アフリカが用意したダイヤモンドも奪い、その資金をもとにアフリカ連合国をつくり、世界を支配しようというのだ。
このコブラス一味は地下にミサイル基地まで作っているのだ。
コブラス一味(アフリカ連合を作る、と言っていたが、後半ではアラブ連合になっている)は、絶海の孤島の国立刑務所を襲ってデュークを脱獄させ、南アフリカに送り、ダイヤを奪わせる。
一方、アッパー7は美人のCIA局員ヘレンの助けを借りて、コブラス一味の陰謀を砕く。
アッパー7は変装の名人で、爆弾ベルトや鉄の手袋などを使って大活躍する。
映画を見ていないので何とも言えないのだが、いきあたりばったりなストーリーだ。
「まんが王」本誌では、アッパー7のプロフィールが紹介されていて、1日に珈琲を7杯飲む、というくだりが忘れられなくて、つい最近まで1日にコーヒーを何杯も飲んだときなど、「まるでナントカ7だな」と思ったりしていた。
この漫画も、最近石井いさみの昔の作品を復刻しているマンガショップあたりで復活するのだろうか。
仕事などで1日に使える自由時間が限られている。1つのことに熱中すると、他のことがおろそかになり、後回しになってしまう。しばらくは学生時代のように、時間割を意識して過ごしてみることにした。
落語:NHKラジオで笑福亭由瓶「手水回し」
長い頭を回しているところとか、ラジオでは見れなくて残念。
30分の尺のうち、半分はインタビュー。
最近落語が自分の中では旬なので、1日に1落語は継続していきたい。
音楽:BON JOVI特集(スペースシャワー)
昨日「comp.」で見たオフスプリングとくらべると、客層の違いがあまりにも違っていてあらためて驚かされた。パンクはナーズと切っても切れないのかもね。
続けて見たキュアーのライブは、なんだか今の僕にはあっていなくて、最後まで見ていることができなかった。音楽だけならまだしも、あの体型とメイクが気になって、音楽どころの騒ぎではない。
FMでは、ワールドロックナウ(ウィーザー、アラニス・モリセット新譜)
歌詞の朗読があってアラニス・モリセットの歌が見違えて聞こえた。やっぱり、歌は歌詞もちゃんとわかってないとね。ポール・ウェラーの曲もかかる。
将棋:将棋チャンネルで、19期竜王戦題局、渡辺竜王VS佐藤棋聖の解説。
腰掛け銀から渡辺竜王入玉。入玉の対局って、見ているだけで息が詰まって、疲れてしまうな。竜王が入玉か。語呂合わせのようだ。
同じく、37期新人王戦U26から、番組解説の戸辺誠3段(当時)と松尾歩5段(当時)の対局解説。飛車の上に玉が乗る「チョコレート囲い」が実現しそうな一戦で、ちょっと期待してしまった。
アニメ:いずれ1週間分、まとめて書こうかな、と思ってたけど。
「ドラえもん」の「大ベンと小ベン」には笑った。
「RD」の「ラブレター」は理想的な本が登場していた。最後のページが白紙になっていて、読者が完成させる本。前回の「スーマラン」が電脳どっぷり依存の話で、今回が紙媒体の話なのが興味深い。
「クレヨンしんちゃん」は犬(シロ)がヘレンケラーの「ウォーター」なみに「ショーガ」と吠える感動巨編?
「狂乱家族日記」は、鬼畜戦争遊園地の後編。前回は全知全能の神と死神が戦ったが、今回は2人は力をあわせて妹と戦う!凶華の正体が明かされる。
「きらりんレボリューション」はジャージ娘のファッション改革。あいにくとビデオの残りがなくて、前半しか録画できなかった。
今日はノーマイカーフリーチケット使って、駒川商店街や天神橋筋商店街、岸里〜玉出あたりを散策。
昔からの面白い店はほとんどなくなっていた。
雑誌「まんが王」昭和42年11月号別冊付録。
この漫画、リアルタイムで読んでいて、アッパーセブンが鉄の手袋をはめて敵にチョップを見舞うシーンとか、強烈に印象に残っていた。ただ、タイトルや作者はほとんど忘れており、「なんとかセブン」くらいが手がかりだった。今回、古本屋で見つけて買い、まさにドンピシャリの漫画だったので興奮した。40年ぶりの再会だ。
「アッパーセブン神出鬼没」はイタリア映画「L’UOMO DE UCCIDERE」を漫画化したもの。
目次は以下のとおり。
1、ライセンスJ7
2、コブラスとチェンとサントス
3、テムズ川は赤信号
4、10億ドルへの脱出
5、銀行は正面からはいれ
6、すてきな相棒
7、風がないている
8、神出鬼没
アッパーセブンことポール・フィニーは西側諜報部員。
南アフリカとアメリカ間でとりかわされる10億ドルの取引に関して冒険がはじまる。
東側の秘密組織が取引を妨害しようとしているとの情報を受けて、アッパー7は組織の黒幕を調査する。
黒幕のコブラスの計画は、アメリカから出る10億ドルを贋札にすりかえて、アメリカの信用を失墜させ、さらに南アフリカが用意したダイヤモンドも奪い、その資金をもとにアフリカ連合国をつくり、世界を支配しようというのだ。
このコブラス一味は地下にミサイル基地まで作っているのだ。
コブラス一味(アフリカ連合を作る、と言っていたが、後半ではアラブ連合になっている)は、絶海の孤島の国立刑務所を襲ってデュークを脱獄させ、南アフリカに送り、ダイヤを奪わせる。
一方、アッパー7は美人のCIA局員ヘレンの助けを借りて、コブラス一味の陰謀を砕く。
アッパー7は変装の名人で、爆弾ベルトや鉄の手袋などを使って大活躍する。
映画を見ていないので何とも言えないのだが、いきあたりばったりなストーリーだ。
「まんが王」本誌では、アッパー7のプロフィールが紹介されていて、1日に珈琲を7杯飲む、というくだりが忘れられなくて、つい最近まで1日にコーヒーを何杯も飲んだときなど、「まるでナントカ7だな」と思ったりしていた。
この漫画も、最近石井いさみの昔の作品を復刻しているマンガショップあたりで復活するのだろうか。
仕事などで1日に使える自由時間が限られている。1つのことに熱中すると、他のことがおろそかになり、後回しになってしまう。しばらくは学生時代のように、時間割を意識して過ごしてみることにした。
落語:NHKラジオで笑福亭由瓶「手水回し」
長い頭を回しているところとか、ラジオでは見れなくて残念。
30分の尺のうち、半分はインタビュー。
最近落語が自分の中では旬なので、1日に1落語は継続していきたい。
音楽:BON JOVI特集(スペースシャワー)
昨日「comp.」で見たオフスプリングとくらべると、客層の違いがあまりにも違っていてあらためて驚かされた。パンクはナーズと切っても切れないのかもね。
続けて見たキュアーのライブは、なんだか今の僕にはあっていなくて、最後まで見ていることができなかった。音楽だけならまだしも、あの体型とメイクが気になって、音楽どころの騒ぎではない。
FMでは、ワールドロックナウ(ウィーザー、アラニス・モリセット新譜)
歌詞の朗読があってアラニス・モリセットの歌が見違えて聞こえた。やっぱり、歌は歌詞もちゃんとわかってないとね。ポール・ウェラーの曲もかかる。
将棋:将棋チャンネルで、19期竜王戦題局、渡辺竜王VS佐藤棋聖の解説。
腰掛け銀から渡辺竜王入玉。入玉の対局って、見ているだけで息が詰まって、疲れてしまうな。竜王が入玉か。語呂合わせのようだ。
同じく、37期新人王戦U26から、番組解説の戸辺誠3段(当時)と松尾歩5段(当時)の対局解説。飛車の上に玉が乗る「チョコレート囲い」が実現しそうな一戦で、ちょっと期待してしまった。
アニメ:いずれ1週間分、まとめて書こうかな、と思ってたけど。
「ドラえもん」の「大ベンと小ベン」には笑った。
「RD」の「ラブレター」は理想的な本が登場していた。最後のページが白紙になっていて、読者が完成させる本。前回の「スーマラン」が電脳どっぷり依存の話で、今回が紙媒体の話なのが興味深い。
「クレヨンしんちゃん」は犬(シロ)がヘレンケラーの「ウォーター」なみに「ショーガ」と吠える感動巨編?
「狂乱家族日記」は、鬼畜戦争遊園地の後編。前回は全知全能の神と死神が戦ったが、今回は2人は力をあわせて妹と戦う!凶華の正体が明かされる。
「きらりんレボリューション」はジャージ娘のファッション改革。あいにくとビデオの残りがなくて、前半しか録画できなかった。
今日はノーマイカーフリーチケット使って、駒川商店街や天神橋筋商店街、岸里〜玉出あたりを散策。
昔からの面白い店はほとんどなくなっていた。
2週ほど前のアニメ「魔人探偵脳噛ネウロ」を録画しそこねて、電人HALのパスワードが何なのかわからないままだった。
スラッシュ含みで、最大文字数21。
それが動機をあらわしている、という。
気になってしかたないので、コミックスを読んだ。
HALの物語は8巻〜11巻にかけて。
で、パスワードわかったけど。
これ、一応手がかりは明らかになってたけど、視聴者なり読者が推理して唯一の正解にたどりつくのは無理だった。
まあ、なんとかして解明しようと悩んだのは自分の勝手だから、文句はないけど。
でも、漫画も面白かった。ふんぱつして買ってよかった。
スラッシュ含みで、最大文字数21。
それが動機をあらわしている、という。
気になってしかたないので、コミックスを読んだ。
HALの物語は8巻〜11巻にかけて。
で、パスワードわかったけど。
これ、一応手がかりは明らかになってたけど、視聴者なり読者が推理して唯一の正解にたどりつくのは無理だった。
まあ、なんとかして解明しようと悩んだのは自分の勝手だから、文句はないけど。
でも、漫画も面白かった。ふんぱつして買ってよかった。
8マン(扶桑社文庫版)
2008年5月22日 アニメ・マンガ8マン全6巻を読んだ。
コズマの最終回を桑田二郎になってから描いた完全版。
桑田二郎版じゃない方も読みたいな。
三つ巴の戦いが新鮮な漫画だった。
コズマの最終回を桑田二郎になってから描いた完全版。
桑田二郎版じゃない方も読みたいな。
三つ巴の戦いが新鮮な漫画だった。
藤子・F・不二雄の『キテレツ大百科』を読んだ。
昨日読んだ『毒ガス帯』、とくに「分解機」がきっかけになった。本箱に入っていたFFランド版全4巻を引っぱりだしてきた。
第1巻
ワガハイはコロ助ナリ
脱時機でのんびり
しん気ろうでやっつけろ
キッコー船の冒険
聞き耳ずきん
片道タイムマシン
モグラ・マンション
江戸時代の月面図
公園の恐竜
キテレツの団体(「こどもの光」昭和49年4月号〜50年1月号)
第2巻
冥府刀
一寸ガードマン
チョーチンおばけ捕物帖
地震の作り方
サイボーグキンちゃん
潜地球
水ねん土で子どもビル
うらみキャンデー
失恋はラブミ膏
らくらくハイキング
念力帽子(「こどもの光」昭和50年2月号〜12月号)
第3巻
如意光で引っこし
植物人間リリー
わすれん帽
物置でアフリカへ
宇宙怪魔人
動物芝居を作るナリ
地獄へいらっしゃい
海底の五億円
ネパール・オパール
ボール紙の町(こどもの光昭和51年1月号〜10月号)
巻末読切:ぼくのオキちゃん(小学四年生昭和50年11月号)
第4巻
枢破天狗
おもい出カメラ
空地の銀世界
ままごとハウス
遊魂帽
超鈍速ジェット機
仙鏡水
唐倶利武者
さらば大百科(こどもの光昭和51年11月号〜52年7月号)
巻末読切:ボクラ共和国(小学五年生昭和50年7月号)
キテレツでのジャイアン役は「ブタゴリラ」なのだが、読切の「ボクラ共和国」に出てくるガキ大将は「フトマムシ」だった。五文字の名前が多いな。「ボクラ共和国」では主人公(その正体は!)は花田マサルだった!
キテレツ読んでると、小学生の頃に学研の「科学」と「学習」を読んでいた頃の、こども目線でのSF興味が甦ってきて楽しかった。特別な能力や、未来からの輸入によらない秘密道具の存在には、ワクワクして、自分でもひょっとしたら作れるんじゃないか、と思わせてくれた。
それと、各巻にはA先生の「ウルトラB」が連載されていて、これがもう、怖いのなんのって。
なお、写真はテレビ版で、コロ助の頭部(まり)の色は薄く、ガチャ目になっていない。原作バージョンの方が、はるかにいいな!
昨日読んだ『毒ガス帯』、とくに「分解機」がきっかけになった。本箱に入っていたFFランド版全4巻を引っぱりだしてきた。
第1巻
ワガハイはコロ助ナリ
脱時機でのんびり
しん気ろうでやっつけろ
キッコー船の冒険
聞き耳ずきん
片道タイムマシン
モグラ・マンション
江戸時代の月面図
公園の恐竜
キテレツの団体(「こどもの光」昭和49年4月号〜50年1月号)
第2巻
冥府刀
一寸ガードマン
チョーチンおばけ捕物帖
地震の作り方
サイボーグキンちゃん
潜地球
水ねん土で子どもビル
うらみキャンデー
失恋はラブミ膏
らくらくハイキング
念力帽子(「こどもの光」昭和50年2月号〜12月号)
第3巻
如意光で引っこし
植物人間リリー
わすれん帽
物置でアフリカへ
宇宙怪魔人
動物芝居を作るナリ
地獄へいらっしゃい
海底の五億円
ネパール・オパール
ボール紙の町(こどもの光昭和51年1月号〜10月号)
巻末読切:ぼくのオキちゃん(小学四年生昭和50年11月号)
第4巻
枢破天狗
おもい出カメラ
空地の銀世界
ままごとハウス
遊魂帽
超鈍速ジェット機
仙鏡水
唐倶利武者
さらば大百科(こどもの光昭和51年11月号〜52年7月号)
巻末読切:ボクラ共和国(小学五年生昭和50年7月号)
キテレツでのジャイアン役は「ブタゴリラ」なのだが、読切の「ボクラ共和国」に出てくるガキ大将は「フトマムシ」だった。五文字の名前が多いな。「ボクラ共和国」では主人公(その正体は!)は花田マサルだった!
キテレツ読んでると、小学生の頃に学研の「科学」と「学習」を読んでいた頃の、こども目線でのSF興味が甦ってきて楽しかった。特別な能力や、未来からの輸入によらない秘密道具の存在には、ワクワクして、自分でもひょっとしたら作れるんじゃないか、と思わせてくれた。
それと、各巻にはA先生の「ウルトラB」が連載されていて、これがもう、怖いのなんのって。
なお、写真はテレビ版で、コロ助の頭部(まり)の色は薄く、ガチャ目になっていない。原作バージョンの方が、はるかにいいな!
月館の殺人 IKKI COMICS
2007年12月10日 アニメ・マンガ
ISBN:4091885810 コミック 綾辻 行人 小学館 2005/08/10 ¥1,050
『月館の殺人』上下巻を読んだ。
テツオタネタと、最初の方に大胆に手がかりが出ているところが面白かった。
あまりにも世間知らずな主人公の無知っぷりを使ったトリックなのか、と思っていたが、それは列車「幻夜」の正体部分で使われていた。列車に乗ったことがない人物!
『月館の殺人』上下巻を読んだ。
テツオタネタと、最初の方に大胆に手がかりが出ているところが面白かった。
あまりにも世間知らずな主人公の無知っぷりを使ったトリックなのか、と思っていたが、それは列車「幻夜」の正体部分で使われていた。列車に乗ったことがない人物!