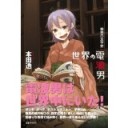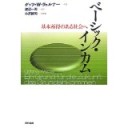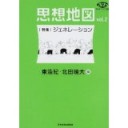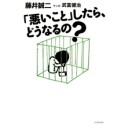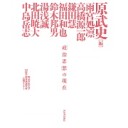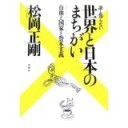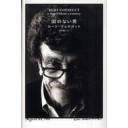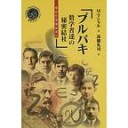『CODE Version 2.0』
2009年9月8日 読書
ローレンス・レッシグ教授の『CODE Version 2.0』を読んだ。
以下、目次。
第二版への序文
序文
第1章 コードは法である
第2章 サイバー空間からのパズル4つ
境界線/統治者たち/ジェイクのコミュニティ/かぎまわるワーム/主題
規制可能性
第3章 現状主義:現状は変わらないのか?
サイバー場所:ハーバード大学vsシカゴ大学
第4章 コントロールのアーキテクチャ
「誰が」どこで何をした?/誰がどこで「何をした」?/誰が「どこで」何をした?/結果
第5章 コードを規制する
アーキテクチャを規制する:規制の2段階方式/コードを規制して規制のしやすさを高める/東海岸コードと西海岸コード/Z理論
コードによる規制
第6章 各種のサイバー場所
空間の価値観/サイバー場所/なぜアーキテクチャが問題になって空間に差が出るのか/コードを規制してよりよい規制を
第7章 なにがなにを規制するか
点の暮らし/政府と規制する方法について/間接的な手法の問題点/その先にあるもの
第8章 オ−プンコードに見る限界
かぎまわるバイト/数える機械/ネット上のコード/ネット上のコード小史/オープンソースの規制/いきつくところ
隠れたあいまいさ
第9章 翻訳
第10章 知的財産
著作権の終焉を告げる各種の報告について/法が救いに/サイバー空間における知的財産の未来/財産・所有物保護の限界/公法を私法で置き換える/不完全性からくる匿名性/許認可文化vsフリー文化/完成がもたらす問題/選択
第11章 プライバシー
私的状況でのプライバシー/公共の場でのプライバシー:監視/公共の場でのプライバシー:データ/解決策/捜索/プライバシーの比較
第12章 言論の自由
言論を規制するもの:出版/言論の規制:迷惑メールとポルノ/言論の規制:フリー文化/言論を規制するもの:流通・配付/言論の教訓
第13章 間奏
競合する主権
第14章 独立主権
空間の主権:規制/空間の主権:規制の選択
第15章 競合する主権
対立/互恵的な盲目性/サイバー空間の「中に」いることについて/考えられる解決策
対応
第16章 われわれが直面している問題
法廷の問題/立法の問題/コードの困ったところ
第17章 対応
司法の対応/コードに対する反応/民主主義の対応
第18章 デクランは何を見落としているのか
第19章 補遺
訳者あとがき
バージョン2について/本書の概要/「規制」とインターネット/民主主義の将来/本書の意義(個人的に)/レッシグその後/謝辞など
注
索引
この前読んだ『FREE CULTURE』と主張は変わらないが、同じことを言っているわけではないので、最後まで面白く読み通せた。
規制の4つのパターン「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」については、何度もくり返されるので、記憶が80分しか持たない僕でも覚えてしまった。また、随所に著者による見取り図やまとめがさしはさまれるので、全体の流れもわかりやすい。
第5部にあたる「対応」で示されたまとめを例として引用しておこう。
第1部の教訓は、もとのインターネットの規制不可能性はやがて終わる、ということだった。そこでのふるまいを再び規制できるようにするアーキテクチャが登場するだろう。第2部は、その規制可能性の一面を描いた−技術だ。その規制の一部として「コード」の重要性はますます高まり、通常の法律が脅しを通じて実現するようなコントロールを直接強制するようになる。そして第3部は、技術的な変化が根本的な価値観に対するわれわれのコミットメントをあいまいにしてしまう状況を3つ検討した。これをわたしは隠れたあいまいさと呼んだ。知的財産やプライバシー、言論の自由をどう保護するかは、憲法起草者たちが行なわなかった根本的な選択に左右される。第4部は、この対立を行政区域に適用した。ここでも教訓は第1部に戻ってくる。政府としてはますます規制しやすいネットを目指したがるし、今後は国境なきインターネットに地理的な領域を復活させようとするだろう。
この4部にわたり、わたしの中心的な目的は、一度述べれば言うまでもないような認識を強いることだった。それは、このネットワークがどう発展するかについては、なんらかの選択をしなくてはならない、ということだ。こうした選択は、ネットワークにどんな価値観が組み込まれるかに根本的に影響してくる。
この第5部における質問とは、われわれにその選択をするだけの能力があるかということだ。わたしの意見では、ない。われわれは実に完璧なほどに、原理原則の問題で司法府を縛ってしまったし、また立法プロセスも、利益誘導の裏返しによって徹底的に腐敗しているので、このきわめてだいじな瞬間に直面している今この時に、われわれはなんら有効な決断ができないでいる。(後略)
翻訳者の山形浩生も巻末に「本書の概要」を書いている。それだけレッシグの主張はまだ新しいということなのだろう。
読んでいて、本文に書いてあるわけではないが、「なるほど」とわかったことがある。
たとえば、悪質な少年犯罪は昔に比べて減っているのに、マスコミの誘導で、その逆のイメージをわれわれは持っている。それによって、少年法改正をあとおしすることが可能になった。同じように、迷惑メールが大量に来ることで、ネット規制を歓迎する世論を作り出すことができる。スパムメールで得するのは、業者だけではないのだ。国民を管理し、支配したい者にとって、スパムは歓迎すべきものだ。と、すると、毎日届く大量のスパムのうしろに、彼らが関わっていないのか、と考えるのがスジだ。
携帯電話の爆発的普及で、通話はすべて簡単に盗聴可能になったいきさつと似ている。
レッシグは第4章「コントロールのアーキテクチャ」でこんな一文を書いている。
「本当に匿名性がほしければ公衆電話を使いなさい!」
町から公衆電話が消えつつあるのは、そういうわけだったのか。
公衆電話が撤去され、かわりに監視カメラが置かれる町。コストとセキュリティーの裏で、それを操って国民を管理しようとする一連の流れがあるのだ。
この手の議論が古臭く思えるのもまた、何らかの力が働いているせいかもしれない。
なお、本書は膨大な正誤表がサイトにあるほど、誤字脱字が多い。さきほどの引用部分でも、途中「この4部にわたり」は「ここまでの4部にわたり」と訂正されているが、それ以外に、僕が訂正した箇所もある。そんな誤字のなかで、本書を読んでいて思わずにんまりと笑ってしまったのは、「著作権」を「著作嫌」と誤って変換している箇所。これって、わざとじゃないんだろうか。
以下、目次。
第二版への序文
序文
第1章 コードは法である
第2章 サイバー空間からのパズル4つ
境界線/統治者たち/ジェイクのコミュニティ/かぎまわるワーム/主題
規制可能性
第3章 現状主義:現状は変わらないのか?
サイバー場所:ハーバード大学vsシカゴ大学
第4章 コントロールのアーキテクチャ
「誰が」どこで何をした?/誰がどこで「何をした」?/誰が「どこで」何をした?/結果
第5章 コードを規制する
アーキテクチャを規制する:規制の2段階方式/コードを規制して規制のしやすさを高める/東海岸コードと西海岸コード/Z理論
コードによる規制
第6章 各種のサイバー場所
空間の価値観/サイバー場所/なぜアーキテクチャが問題になって空間に差が出るのか/コードを規制してよりよい規制を
第7章 なにがなにを規制するか
点の暮らし/政府と規制する方法について/間接的な手法の問題点/その先にあるもの
第8章 オ−プンコードに見る限界
かぎまわるバイト/数える機械/ネット上のコード/ネット上のコード小史/オープンソースの規制/いきつくところ
隠れたあいまいさ
第9章 翻訳
第10章 知的財産
著作権の終焉を告げる各種の報告について/法が救いに/サイバー空間における知的財産の未来/財産・所有物保護の限界/公法を私法で置き換える/不完全性からくる匿名性/許認可文化vsフリー文化/完成がもたらす問題/選択
第11章 プライバシー
私的状況でのプライバシー/公共の場でのプライバシー:監視/公共の場でのプライバシー:データ/解決策/捜索/プライバシーの比較
第12章 言論の自由
言論を規制するもの:出版/言論の規制:迷惑メールとポルノ/言論の規制:フリー文化/言論を規制するもの:流通・配付/言論の教訓
第13章 間奏
競合する主権
第14章 独立主権
空間の主権:規制/空間の主権:規制の選択
第15章 競合する主権
対立/互恵的な盲目性/サイバー空間の「中に」いることについて/考えられる解決策
対応
第16章 われわれが直面している問題
法廷の問題/立法の問題/コードの困ったところ
第17章 対応
司法の対応/コードに対する反応/民主主義の対応
第18章 デクランは何を見落としているのか
第19章 補遺
訳者あとがき
バージョン2について/本書の概要/「規制」とインターネット/民主主義の将来/本書の意義(個人的に)/レッシグその後/謝辞など
注
索引
この前読んだ『FREE CULTURE』と主張は変わらないが、同じことを言っているわけではないので、最後まで面白く読み通せた。
規制の4つのパターン「法」「規範」「市場」「アーキテクチャ」については、何度もくり返されるので、記憶が80分しか持たない僕でも覚えてしまった。また、随所に著者による見取り図やまとめがさしはさまれるので、全体の流れもわかりやすい。
第5部にあたる「対応」で示されたまとめを例として引用しておこう。
第1部の教訓は、もとのインターネットの規制不可能性はやがて終わる、ということだった。そこでのふるまいを再び規制できるようにするアーキテクチャが登場するだろう。第2部は、その規制可能性の一面を描いた−技術だ。その規制の一部として「コード」の重要性はますます高まり、通常の法律が脅しを通じて実現するようなコントロールを直接強制するようになる。そして第3部は、技術的な変化が根本的な価値観に対するわれわれのコミットメントをあいまいにしてしまう状況を3つ検討した。これをわたしは隠れたあいまいさと呼んだ。知的財産やプライバシー、言論の自由をどう保護するかは、憲法起草者たちが行なわなかった根本的な選択に左右される。第4部は、この対立を行政区域に適用した。ここでも教訓は第1部に戻ってくる。政府としてはますます規制しやすいネットを目指したがるし、今後は国境なきインターネットに地理的な領域を復活させようとするだろう。
この4部にわたり、わたしの中心的な目的は、一度述べれば言うまでもないような認識を強いることだった。それは、このネットワークがどう発展するかについては、なんらかの選択をしなくてはならない、ということだ。こうした選択は、ネットワークにどんな価値観が組み込まれるかに根本的に影響してくる。
この第5部における質問とは、われわれにその選択をするだけの能力があるかということだ。わたしの意見では、ない。われわれは実に完璧なほどに、原理原則の問題で司法府を縛ってしまったし、また立法プロセスも、利益誘導の裏返しによって徹底的に腐敗しているので、このきわめてだいじな瞬間に直面している今この時に、われわれはなんら有効な決断ができないでいる。(後略)
翻訳者の山形浩生も巻末に「本書の概要」を書いている。それだけレッシグの主張はまだ新しいということなのだろう。
読んでいて、本文に書いてあるわけではないが、「なるほど」とわかったことがある。
たとえば、悪質な少年犯罪は昔に比べて減っているのに、マスコミの誘導で、その逆のイメージをわれわれは持っている。それによって、少年法改正をあとおしすることが可能になった。同じように、迷惑メールが大量に来ることで、ネット規制を歓迎する世論を作り出すことができる。スパムメールで得するのは、業者だけではないのだ。国民を管理し、支配したい者にとって、スパムは歓迎すべきものだ。と、すると、毎日届く大量のスパムのうしろに、彼らが関わっていないのか、と考えるのがスジだ。
携帯電話の爆発的普及で、通話はすべて簡単に盗聴可能になったいきさつと似ている。
レッシグは第4章「コントロールのアーキテクチャ」でこんな一文を書いている。
「本当に匿名性がほしければ公衆電話を使いなさい!」
町から公衆電話が消えつつあるのは、そういうわけだったのか。
公衆電話が撤去され、かわりに監視カメラが置かれる町。コストとセキュリティーの裏で、それを操って国民を管理しようとする一連の流れがあるのだ。
この手の議論が古臭く思えるのもまた、何らかの力が働いているせいかもしれない。
なお、本書は膨大な正誤表がサイトにあるほど、誤字脱字が多い。さきほどの引用部分でも、途中「この4部にわたり」は「ここまでの4部にわたり」と訂正されているが、それ以外に、僕が訂正した箇所もある。そんな誤字のなかで、本書を読んでいて思わずにんまりと笑ってしまったのは、「著作権」を「著作嫌」と誤って変換している箇所。これって、わざとじゃないんだろうか。
『まごころ−哲学者と随筆家の対話』
2009年9月3日 読書
鶴見俊輔と岡部伊都子の対談『まごころ−哲学者と随筆家の対話』を読んだ。
2003年に京都の岡部宅で収録された対談。
以下、目次
第1章 ”犀のごとく歩め”
「自分は学歴はなくて、病歴がある」(岡部)
「お釈迦さんが言った”犀のごとく歩め”」(鶴見)
「『先生、その問題、自分で考えたんですか』と問う小学生」(鶴見)
「ラジオでは、耳で聞いて、わかる言葉に変えんならん」(岡部)
「朝鮮人は長い間虐げられてるから、動機がずっと続く」(鶴見)
「70万人の在日朝鮮人とどうつきあうか、それが鍵だね」(鶴見)
「桓武天皇のお母さんは百済の王族」(岡部)
「個人の値打ちで勝負する」(鶴見)
「自分の体の感じで平和憲法を支持するのは在日朝鮮人」(鶴見)
第2章 ほんものの人間、ほんとうの歴史
「『鉢の木』を思い出す須田剋太画伯とのつきあい」(鶴見)
「『人間にとって差別は一番いけない』とまず言わはった須田さん」(岡部)
「私に人生や学問のコツを教えてくれた”ランチの女王”」(鶴見)
「日本の学問は落ちた。明治以前の方がよかった」(鶴見)
「学校でなく、自己内対話で自分の見識を養え」(鶴見)
「概念で考える美というものは、私は遠い」(岡部)
「”耳塚”にお連れした時に五体投地された高銀先生」(岡部)
「長い帝国主義の方が、同時に深い把握もしている」(鶴見)
第3章戦争・沖縄・ハンセン病
「私は戦争に加担した女です」(岡部)
「婚約者を殺しにやって、殺されたようなもの」(岡部)
「それからなんべん、婚約者が戦死した沖縄へ行ったか」(岡部)
「敗ける時に敗ける側にいたい」(鶴見)
「命令が下ったら自分は拒絶できたか、という哲学的な問題」(鶴見)
おわりに−死を前にして
「きちんとした反戦運動は、女から起こるしかない」(鶴見)
「『若さからの解放』は機嫌のええもんなんです」(岡部)
第1、2章はおもに鶴見がとばし、3章は岡部が語る。
岡部の京都ことばが心に届く。
戦争を体験した人が語る「戦争は絶対いや」というのは、うわ、ほんとにいやだったんだろうな、と思えるが、戦争体験者の死亡によって、その機会は失われていくんだろうか。
傷痍軍人が年齢と無関係に存在するように、戦争の語り部も年齢にかかわりなく受け継いでいくようにならないだろうか。
体験者の残した手記の朗読とか、イタコの降霊による語り、というような迂回もなく、まさに自分が体験者であるとする語り。
昔は人魚の肉食べて不死になった人とか、何世紀にも渡って歴史に登場した人とかがいたのだが、現代に、そういう人はいるのか。マスコミは何か隠していないか?
2003年に京都の岡部宅で収録された対談。
以下、目次
第1章 ”犀のごとく歩め”
「自分は学歴はなくて、病歴がある」(岡部)
「お釈迦さんが言った”犀のごとく歩め”」(鶴見)
「『先生、その問題、自分で考えたんですか』と問う小学生」(鶴見)
「ラジオでは、耳で聞いて、わかる言葉に変えんならん」(岡部)
「朝鮮人は長い間虐げられてるから、動機がずっと続く」(鶴見)
「70万人の在日朝鮮人とどうつきあうか、それが鍵だね」(鶴見)
「桓武天皇のお母さんは百済の王族」(岡部)
「個人の値打ちで勝負する」(鶴見)
「自分の体の感じで平和憲法を支持するのは在日朝鮮人」(鶴見)
第2章 ほんものの人間、ほんとうの歴史
「『鉢の木』を思い出す須田剋太画伯とのつきあい」(鶴見)
「『人間にとって差別は一番いけない』とまず言わはった須田さん」(岡部)
「私に人生や学問のコツを教えてくれた”ランチの女王”」(鶴見)
「日本の学問は落ちた。明治以前の方がよかった」(鶴見)
「学校でなく、自己内対話で自分の見識を養え」(鶴見)
「概念で考える美というものは、私は遠い」(岡部)
「”耳塚”にお連れした時に五体投地された高銀先生」(岡部)
「長い帝国主義の方が、同時に深い把握もしている」(鶴見)
第3章戦争・沖縄・ハンセン病
「私は戦争に加担した女です」(岡部)
「婚約者を殺しにやって、殺されたようなもの」(岡部)
「それからなんべん、婚約者が戦死した沖縄へ行ったか」(岡部)
「敗ける時に敗ける側にいたい」(鶴見)
「命令が下ったら自分は拒絶できたか、という哲学的な問題」(鶴見)
おわりに−死を前にして
「きちんとした反戦運動は、女から起こるしかない」(鶴見)
「『若さからの解放』は機嫌のええもんなんです」(岡部)
第1、2章はおもに鶴見がとばし、3章は岡部が語る。
岡部の京都ことばが心に届く。
戦争を体験した人が語る「戦争は絶対いや」というのは、うわ、ほんとにいやだったんだろうな、と思えるが、戦争体験者の死亡によって、その機会は失われていくんだろうか。
傷痍軍人が年齢と無関係に存在するように、戦争の語り部も年齢にかかわりなく受け継いでいくようにならないだろうか。
体験者の残した手記の朗読とか、イタコの降霊による語り、というような迂回もなく、まさに自分が体験者であるとする語り。
昔は人魚の肉食べて不死になった人とか、何世紀にも渡って歴史に登場した人とかがいたのだが、現代に、そういう人はいるのか。マスコミは何か隠していないか?
「祝福されない王国」の部屋@workroom*A、『真理先生』
2009年9月2日 読書
workroom*AでshopへなちょこOPEN記念展「祝福されない王国」の部屋。
藤本由紀夫さんの作品に嶽本野ばら君が物語をつけた本『祝福されない王国』の出版記念展になる。
「乙女の自習室」と銘打つだけあって、入ると静謐な空間が待ち受けていた。
でも、おしゃべりしても「しーっ」という感じでもないのが、乙女の自習室たるゆえん。
室内には本で取り上げられた藤本由紀夫さんの作品がかくれんぼのように点在している。
オルゴール作品もあるので、音を出すことが禁じられているはずもなかったのだ。
中央の大テーブルには「祝福されない王国」が連載されていた文芸誌『yom yom』が螺旋状に積んである。
ドリンクは豆から挽いて煎れる珈琲か、瓶のフォルムが素敵なサイダーか。
僕は珈琲を、電動ミルでひいて自分で作った。京都のオオヤコーヒー。
う〜む、美味。
shopへなちょこをのぞくと、僕の原稿が掲載されているフリーペーパー「実験アキレス」とか置いてあった。と、いうか、行ったら実験アキレスの編集長の勝さんが先に来ていたのだった。あと、僕が昔出した「保山ボックス」も販売していて、これがまあ、法外な値段をつけられていて、笑った。野ばら君が絵を描いてくれているので、プレミアがついたのだろう。もうどこにもないセットだと思っていたので、興味ある方は、shopへなちょこをのぞいてみてください。
根本敬さんの『真理先生』を読んだ。
第1章
さぶ・カトちゃん
ボス、シケてますよ
童貞ソー・ヤング
水面のひよこ、水底の弁当
男にとって甲斐性とは
どの面、そして目の前の金
ストーンズのライブ(確かめに行ったもの)
もう一人の俺
第2章
「小説」
第3章
男と男の結婚・男、友情の旅篇
結婚式のスピーチのために記す*挨拶と軽い自己紹介の後に、以下
誰もが一度は考えること−ボノボ、その生態(2005年の暮れに書いた日記より)
人間だもの−伝達回路を開通せよ
そして王道と書いてマイウェイと読む
2007年2月5日から6日の間に「因果境界線」が絶対にある。−もう「サブカル呼ばわり」のコチラの手の内には既に今後必要なものは揃っている。それを以て遡及するのが然るべき筋道である。そこへ固い意志の下突き進むしか、新しいコトや未来の名に値するものなど一切生まれない。
『墓場の鬼太郎』と『ゲゲゲの鬼太郎』の変容から垣間見たもの
赤塚先生から赤塚と呼び捨てになった時
ビッグバーンから始まった宇宙の中で、グレゴリー歴2009年の現在、人類、とりわけ日本人の幸福とは何か!?−そしてサザエさん化を「皇室」に迄も求めてやまない暴走する大衆と、そのサザエさん一家の光と影
時代は変わる由、世襲制もまた良し
この歳(28歳)まで長く生きて来られ、とても感慨深い
死相とは何だ?
ヤキソバパンをパクつきながら考えたこと
あDEいンザLAいふ
全体に根本さんの文章は、もずくの中を歩くような不思議な感覚がともなう。
なんと言えばいいのだろう。
不如意とか、不具合とか、不自由とか、不具、などがまとわりつくのだ。
厄介なものがこびりついている。
2部の「小説」は意外とまっとうに文学してて驚いたのだが、後半、性欲の噴火で根本さんらしい展開になり、根本漫画を読んでいる気分になった。
しかし、根本流の爆発はそこくらいで、随想の部分にいたっては、不具なのだ。
根本さんの生き方そのものなのだ。
文章は、漫画よりも根本さん本人を如実にあらわしているのかもしれない。
まっすぐのつもりなのに、不具ゆえに曲りくねってしまう。
人間バロックとは、根本さんのことではないか、とふと思った。
藤本由紀夫さんの作品に嶽本野ばら君が物語をつけた本『祝福されない王国』の出版記念展になる。
「乙女の自習室」と銘打つだけあって、入ると静謐な空間が待ち受けていた。
でも、おしゃべりしても「しーっ」という感じでもないのが、乙女の自習室たるゆえん。
室内には本で取り上げられた藤本由紀夫さんの作品がかくれんぼのように点在している。
オルゴール作品もあるので、音を出すことが禁じられているはずもなかったのだ。
中央の大テーブルには「祝福されない王国」が連載されていた文芸誌『yom yom』が螺旋状に積んである。
ドリンクは豆から挽いて煎れる珈琲か、瓶のフォルムが素敵なサイダーか。
僕は珈琲を、電動ミルでひいて自分で作った。京都のオオヤコーヒー。
う〜む、美味。
shopへなちょこをのぞくと、僕の原稿が掲載されているフリーペーパー「実験アキレス」とか置いてあった。と、いうか、行ったら実験アキレスの編集長の勝さんが先に来ていたのだった。あと、僕が昔出した「保山ボックス」も販売していて、これがまあ、法外な値段をつけられていて、笑った。野ばら君が絵を描いてくれているので、プレミアがついたのだろう。もうどこにもないセットだと思っていたので、興味ある方は、shopへなちょこをのぞいてみてください。
根本敬さんの『真理先生』を読んだ。
第1章
さぶ・カトちゃん
ボス、シケてますよ
童貞ソー・ヤング
水面のひよこ、水底の弁当
男にとって甲斐性とは
どの面、そして目の前の金
ストーンズのライブ(確かめに行ったもの)
もう一人の俺
第2章
「小説」
第3章
男と男の結婚・男、友情の旅篇
結婚式のスピーチのために記す*挨拶と軽い自己紹介の後に、以下
誰もが一度は考えること−ボノボ、その生態(2005年の暮れに書いた日記より)
人間だもの−伝達回路を開通せよ
そして王道と書いてマイウェイと読む
2007年2月5日から6日の間に「因果境界線」が絶対にある。−もう「サブカル呼ばわり」のコチラの手の内には既に今後必要なものは揃っている。それを以て遡及するのが然るべき筋道である。そこへ固い意志の下突き進むしか、新しいコトや未来の名に値するものなど一切生まれない。
『墓場の鬼太郎』と『ゲゲゲの鬼太郎』の変容から垣間見たもの
赤塚先生から赤塚と呼び捨てになった時
ビッグバーンから始まった宇宙の中で、グレゴリー歴2009年の現在、人類、とりわけ日本人の幸福とは何か!?−そしてサザエさん化を「皇室」に迄も求めてやまない暴走する大衆と、そのサザエさん一家の光と影
時代は変わる由、世襲制もまた良し
この歳(28歳)まで長く生きて来られ、とても感慨深い
死相とは何だ?
ヤキソバパンをパクつきながら考えたこと
あDEいンザLAいふ
全体に根本さんの文章は、もずくの中を歩くような不思議な感覚がともなう。
なんと言えばいいのだろう。
不如意とか、不具合とか、不自由とか、不具、などがまとわりつくのだ。
厄介なものがこびりついている。
2部の「小説」は意外とまっとうに文学してて驚いたのだが、後半、性欲の噴火で根本さんらしい展開になり、根本漫画を読んでいる気分になった。
しかし、根本流の爆発はそこくらいで、随想の部分にいたっては、不具なのだ。
根本さんの生き方そのものなのだ。
文章は、漫画よりも根本さん本人を如実にあらわしているのかもしれない。
まっすぐのつもりなのに、不具ゆえに曲りくねってしまう。
人間バロックとは、根本さんのことではないか、とふと思った。
秋山祐徳太子の『恥の美学』を読んだ。
序章 恥の十七条憲法
第1章 疾風怒濤のポップ・ハプニング
恥ずかしさを突き抜けろ
芸大の受験”芸術”に挑む
見られる恥ずかしさ
行為芸術の原点はチンドン屋
教育ハプニング・二宮金次郎
恥ずかしさを共有する
ビタミン・アートの衝撃
グリコ・ハプニング誕生
強烈な恥を振りまくゼロ次元
全裸で闘う万博破壊共闘派
猥褻か政治犯か
ダダカン、万博を疾走する
第2章 都知事選に恥が結集する
泡沫候補への関心
人生の天王山、到来
選挙ポスターをアートする
選挙活動始まる
ネズミの運動員
”選挙功労者”河野さん
”チンダレ”候補の窪田さん
茨城県から立候補
立会演説会での豹変ぶり
私は
公人と私人
皇宮警察と太子
出馬を許した母の理解
東京を越えて
恥が大逆転する
第3章 ブリキ芸術は人生の軽ろみ
バブル対ブリキの決戦
”世界初”ブリキ製仏像
ブリキの円空
ご当地芸術
徘徊するブリキ板
ブリキ芸術ならではの受難
ブリキか、トタンか
第4章 私だって恥ずかしい[対談前半戦]秋山祐徳太子×南伸坊
第5章 すべての恥は珍百景に通ず
土下座する人
靴の珍光景
葬儀間違い
鹿せんべいの恐怖
珍コレ珍百景
第6章 恥は友を呼ぶ
文豪の恥ずかしながら
恥をかかせない信条
「酒蘭丸」を助ける
無責任きわまりない客
野毛憲法 めげない、こりない、あきらめない
第7章 青春の恥は人生の花
愛国弁当
青春期は大量の恥を浴びよ
面接で恥の逆転劇
フラれて本当の恥を知る
恥のキューピッド
排泄の美学
第8章 ”狂気”乱舞の恥かき人
ふつうの人の情熱
狂気の街頭ハプニング
恥をアートする天才編集長
「恥の石」を大海に投げ込む
第9章 ナンセンスが加速する
モーレツ、サラリーマンアート
中世の恥
パリの恥
秋山”聖徳”太子
恥のインスタレーション
寝たきり芸術
第10章 恥にマニュアルはない[対談後半戦]秋山祐徳太子×南伸坊
シャイであることと、芸術行為者であることは矛盾しないどころか、条件であるように思える。なぜ思えるかと言うと、僕だって肩書きを問われれば「芸術家」だと豪語するくせに、誰よりも恥ずかしがり屋なのだから。と、公言するあたりが、恥知らずなんだろうが、わざと恥知らずなことをして、脇から「ワザ、ワザ」と見抜かれて青ざめるタイプなのだ。この僕は!恥スパイラルである。
序章 恥の十七条憲法
第1章 疾風怒濤のポップ・ハプニング
恥ずかしさを突き抜けろ
芸大の受験”芸術”に挑む
見られる恥ずかしさ
行為芸術の原点はチンドン屋
教育ハプニング・二宮金次郎
恥ずかしさを共有する
ビタミン・アートの衝撃
グリコ・ハプニング誕生
強烈な恥を振りまくゼロ次元
全裸で闘う万博破壊共闘派
猥褻か政治犯か
ダダカン、万博を疾走する
第2章 都知事選に恥が結集する
泡沫候補への関心
人生の天王山、到来
選挙ポスターをアートする
選挙活動始まる
ネズミの運動員
”選挙功労者”河野さん
”チンダレ”候補の窪田さん
茨城県から立候補
立会演説会での豹変ぶり
私は
公人と私人
皇宮警察と太子
出馬を許した母の理解
東京を越えて
恥が大逆転する
第3章 ブリキ芸術は人生の軽ろみ
バブル対ブリキの決戦
”世界初”ブリキ製仏像
ブリキの円空
ご当地芸術
徘徊するブリキ板
ブリキ芸術ならではの受難
ブリキか、トタンか
第4章 私だって恥ずかしい[対談前半戦]秋山祐徳太子×南伸坊
第5章 すべての恥は珍百景に通ず
土下座する人
靴の珍光景
葬儀間違い
鹿せんべいの恐怖
珍コレ珍百景
第6章 恥は友を呼ぶ
文豪の恥ずかしながら
恥をかかせない信条
「酒蘭丸」を助ける
無責任きわまりない客
野毛憲法 めげない、こりない、あきらめない
第7章 青春の恥は人生の花
愛国弁当
青春期は大量の恥を浴びよ
面接で恥の逆転劇
フラれて本当の恥を知る
恥のキューピッド
排泄の美学
第8章 ”狂気”乱舞の恥かき人
ふつうの人の情熱
狂気の街頭ハプニング
恥をアートする天才編集長
「恥の石」を大海に投げ込む
第9章 ナンセンスが加速する
モーレツ、サラリーマンアート
中世の恥
パリの恥
秋山”聖徳”太子
恥のインスタレーション
寝たきり芸術
第10章 恥にマニュアルはない[対談後半戦]秋山祐徳太子×南伸坊
シャイであることと、芸術行為者であることは矛盾しないどころか、条件であるように思える。なぜ思えるかと言うと、僕だって肩書きを問われれば「芸術家」だと豪語するくせに、誰よりも恥ずかしがり屋なのだから。と、公言するあたりが、恥知らずなんだろうが、わざと恥知らずなことをして、脇から「ワザ、ワザ」と見抜かれて青ざめるタイプなのだ。この僕は!恥スパイラルである。
本田透の『世界の電波男』を読んだ。『喪男の哲学史』に続く『喪男の文学史』。
以下、目次。
まえがきマンガ
第1部 人はなぜ物語を求めるのか?
俺が『電波男』だ!/「現実」にしがみつく人々/俺の三次元のトラウマ体験/物語に抱いた「願望充足の予感」/「自我」と「自意識」/ラブコメ漫画に見る「予感」/物語の8つのパターン/物語は人類とともに
第2部 現実飛翔への8つの祈り
1、超人(力・モテ)
力への憧れ/非日常の出入り口としての女/悲劇とカタルシス/『新約聖書』という物語/ゆがんでいく超人たち/『ドラゴンボール』はなぜ世界中でヒットしたか
2、怪物(力・喪)
裏返しの超人/喪男・フランケンシュタインの怪物/イケメンの怪物『吸血鬼ドラキュラ』/人間を滅ぼす怪物『デビルマン』/怪物物語としての『DEATH NOTE』
3、時間(飛翔A)
やり直したいという願望/本格未来小説『タイム・マシン』/オタクの願望がつまった『夏への扉』/未来でダニエルが見たもの/タイム・トラベル作品の現在/どう妄想しても絶望的な未来
4、空間(飛翔B)
どこかにある理想郷/『神曲』誕生秘話/ダンテ、ベアトリーチェにシメられる/加藤保憲が東京を滅ぼしてくれる/その後の『帝都物語』
5、童貞(永劫回帰)
中世の電波男『ドン・キホーテ』/ナポレオンの衝撃/ひきこもり文学の自意識/『罪と罰』誕生の背景
6、人間萌え
『罪と罰』の超人思想/萌えキャラ・ソーニャ登場/『罪と罰』のダークサイド/萌えのミッシング・リンク/人間萌えリアリズム小説『源氏物語』/女漁りが止まらない/モテなくなった光源氏
7、空想萌え
萌え感情の芽生え/喪男の救いの遍歴『ファウスト』/ファウスト先生、恋愛に挑戦/ファウスト先生、古代ギリシャで大活躍/ファウスト先生、現世に帰還/漫画で花開く日本の空想萌え/「童貞ハーレム」としての『ああっ女神さまっ』/萌えの出家僧・森里螢一
8、人工萌え
なぜ「萌え」はモテないのか/リラダン、三次元女への幻滅を語る/エジソンのアジテーション/人工萌えVS自意識のツッコミ/受け継がれる『未来のイヴ』
第3部 『火の鳥』における救いの探求
ニヒリズムに満ちた漫画『火の鳥』/「宇宙編」〜猿田、呪いを受ける/「黎明編」〜猿田一族の先祖/「ヤマト編」〜火の鳥もまた女/「生命編」〜あっさり死ぬ猿田/「復活編」〜心がひとつになる不幸/「未来編」〜猿田博士の満たされぬ生涯/『火の鳥』の物語構造/「鳳凰編」〜二人の手塚の闘い
本書は「世界一身も蓋もない=本当に役立つ文学論」だと著者は言う。
「恋愛資本主義」が跋扈する三次元地獄からのエクソダスとしてオタクをとらえ、救済と文明の進歩と内面の成長を果たす物語を「願望充足の予感を感じさせる装置」として分析してみせたのが本書だ。
今まで読んできた本が「ああっ、そういう話だったのか!」と目を開かされる思いで再登場する。
本文にまき散らされた太字のアジテーションが、これでもか、と著者の怨念にも似た思いを叩き付けていて、痛快だ。
たとえば、ゲーテの『ファウスト』第2部についてあらすじに添いながら解説した「ファウスト先生、古代ギリシャで大活躍」から太字だけを抜き出してみよう。
「空想萌え(女神萌え)」を復活
ぱっぱらっぱっぱっぱー
週刊少年ジャンプで連載されていた『タカヤ』と同じ
まず「国家萌え」へ向かう
(ナポレオンは本当はゲーテの『若きウェルテル』みたいな小説を書いて作家になるつもりだった。こんな人でないと、そもそも世界征服なんて企まない)
ナチスとソ連によって木っ端みじんになる
仮面ライダーから、ゴレンジャーへ。ウルトラマンの単身赴任から、ウルトラ兄弟・ウルトラ一家へ
話がぜんぜん違う方向へ展開するのだ
ネズミ男みたいなヤツ
若い頃モテなかった
女ってイヤですねえ
海原雄山のごとき卓越した評論家ぶり
単に「三次元の女に懲りた」だけだった
本当に爆発します。ドリフのコントみたいに
ヘレナ萌え族(仮)
古代ギリシャへ時間移動
女もセックス抜きに人工的に造り出す妖精みたいなちっちゃな子供
二次元の萌えキャラは永遠のロリータ
ストーカー禁止令
デカルチャー!
突き詰めてみれば「女を力づくで奪おう」とか「金と土地があれば女にモテる」というジャイアニズム「だけ」が戦争の原因だ
我々現代人が三次元主義に冒されているから
もうキャラクターの声優まで勝手に決まっているから、声も聞こえるね
ファウストの頭はとっくにいかれているので何も問題はなかった
その通りだ!独逸の電波男、いざ出陣
「イリアス+オデュッセイア」
スパルタの背後にゲルマン人の軍団が出現して、ゲルマン人の国を築いているというのだ!時代考証滅茶苦茶じゃないか?
古代ギリシャ世界に、満を持してドイツ軍が乱入だッ!
脱童貞した過去も忘れてすっかり魔法使い
劇場版『ドラえもん』におけるのび太のごとく、颯爽と戦場に立つ
架空戦記ですから
これじゃまるで『北斗の拳』のシンがユリアに捧げたサザンクロスの街だ…
妄想のリアリズム化もほどほどに、という教訓
おおお、どうだ、この熱気!適当にページひらいたところで引用しただけなのに、この熱の帯びよう!
たとえば、フェミニズムの立場から批評するような感じで、本田透以外にもこうした批評が次々と出れば、面白いシーンが築けるようにも思うのだが、あいにくと、僕はよく知らない。ネットではいろいろあるのかもしれないけど、ほとんどインターネットしないのでわからない。誰か、教えてください。
以下、目次。
まえがきマンガ
第1部 人はなぜ物語を求めるのか?
俺が『電波男』だ!/「現実」にしがみつく人々/俺の三次元のトラウマ体験/物語に抱いた「願望充足の予感」/「自我」と「自意識」/ラブコメ漫画に見る「予感」/物語の8つのパターン/物語は人類とともに
第2部 現実飛翔への8つの祈り
1、超人(力・モテ)
力への憧れ/非日常の出入り口としての女/悲劇とカタルシス/『新約聖書』という物語/ゆがんでいく超人たち/『ドラゴンボール』はなぜ世界中でヒットしたか
2、怪物(力・喪)
裏返しの超人/喪男・フランケンシュタインの怪物/イケメンの怪物『吸血鬼ドラキュラ』/人間を滅ぼす怪物『デビルマン』/怪物物語としての『DEATH NOTE』
3、時間(飛翔A)
やり直したいという願望/本格未来小説『タイム・マシン』/オタクの願望がつまった『夏への扉』/未来でダニエルが見たもの/タイム・トラベル作品の現在/どう妄想しても絶望的な未来
4、空間(飛翔B)
どこかにある理想郷/『神曲』誕生秘話/ダンテ、ベアトリーチェにシメられる/加藤保憲が東京を滅ぼしてくれる/その後の『帝都物語』
5、童貞(永劫回帰)
中世の電波男『ドン・キホーテ』/ナポレオンの衝撃/ひきこもり文学の自意識/『罪と罰』誕生の背景
6、人間萌え
『罪と罰』の超人思想/萌えキャラ・ソーニャ登場/『罪と罰』のダークサイド/萌えのミッシング・リンク/人間萌えリアリズム小説『源氏物語』/女漁りが止まらない/モテなくなった光源氏
7、空想萌え
萌え感情の芽生え/喪男の救いの遍歴『ファウスト』/ファウスト先生、恋愛に挑戦/ファウスト先生、古代ギリシャで大活躍/ファウスト先生、現世に帰還/漫画で花開く日本の空想萌え/「童貞ハーレム」としての『ああっ女神さまっ』/萌えの出家僧・森里螢一
8、人工萌え
なぜ「萌え」はモテないのか/リラダン、三次元女への幻滅を語る/エジソンのアジテーション/人工萌えVS自意識のツッコミ/受け継がれる『未来のイヴ』
第3部 『火の鳥』における救いの探求
ニヒリズムに満ちた漫画『火の鳥』/「宇宙編」〜猿田、呪いを受ける/「黎明編」〜猿田一族の先祖/「ヤマト編」〜火の鳥もまた女/「生命編」〜あっさり死ぬ猿田/「復活編」〜心がひとつになる不幸/「未来編」〜猿田博士の満たされぬ生涯/『火の鳥』の物語構造/「鳳凰編」〜二人の手塚の闘い
本書は「世界一身も蓋もない=本当に役立つ文学論」だと著者は言う。
「恋愛資本主義」が跋扈する三次元地獄からのエクソダスとしてオタクをとらえ、救済と文明の進歩と内面の成長を果たす物語を「願望充足の予感を感じさせる装置」として分析してみせたのが本書だ。
今まで読んできた本が「ああっ、そういう話だったのか!」と目を開かされる思いで再登場する。
本文にまき散らされた太字のアジテーションが、これでもか、と著者の怨念にも似た思いを叩き付けていて、痛快だ。
たとえば、ゲーテの『ファウスト』第2部についてあらすじに添いながら解説した「ファウスト先生、古代ギリシャで大活躍」から太字だけを抜き出してみよう。
「空想萌え(女神萌え)」を復活
ぱっぱらっぱっぱっぱー
週刊少年ジャンプで連載されていた『タカヤ』と同じ
まず「国家萌え」へ向かう
(ナポレオンは本当はゲーテの『若きウェルテル』みたいな小説を書いて作家になるつもりだった。こんな人でないと、そもそも世界征服なんて企まない)
ナチスとソ連によって木っ端みじんになる
仮面ライダーから、ゴレンジャーへ。ウルトラマンの単身赴任から、ウルトラ兄弟・ウルトラ一家へ
話がぜんぜん違う方向へ展開するのだ
ネズミ男みたいなヤツ
若い頃モテなかった
女ってイヤですねえ
海原雄山のごとき卓越した評論家ぶり
単に「三次元の女に懲りた」だけだった
本当に爆発します。ドリフのコントみたいに
ヘレナ萌え族(仮)
古代ギリシャへ時間移動
女もセックス抜きに人工的に造り出す妖精みたいなちっちゃな子供
二次元の萌えキャラは永遠のロリータ
ストーカー禁止令
デカルチャー!
突き詰めてみれば「女を力づくで奪おう」とか「金と土地があれば女にモテる」というジャイアニズム「だけ」が戦争の原因だ
我々現代人が三次元主義に冒されているから
もうキャラクターの声優まで勝手に決まっているから、声も聞こえるね
ファウストの頭はとっくにいかれているので何も問題はなかった
その通りだ!独逸の電波男、いざ出陣
「イリアス+オデュッセイア」
スパルタの背後にゲルマン人の軍団が出現して、ゲルマン人の国を築いているというのだ!時代考証滅茶苦茶じゃないか?
古代ギリシャ世界に、満を持してドイツ軍が乱入だッ!
脱童貞した過去も忘れてすっかり魔法使い
劇場版『ドラえもん』におけるのび太のごとく、颯爽と戦場に立つ
架空戦記ですから
これじゃまるで『北斗の拳』のシンがユリアに捧げたサザンクロスの街だ…
妄想のリアリズム化もほどほどに、という教訓
おおお、どうだ、この熱気!適当にページひらいたところで引用しただけなのに、この熱の帯びよう!
たとえば、フェミニズムの立場から批評するような感じで、本田透以外にもこうした批評が次々と出れば、面白いシーンが築けるようにも思うのだが、あいにくと、僕はよく知らない。ネットではいろいろあるのかもしれないけど、ほとんどインターネットしないのでわからない。誰か、教えてください。
天王寺動物園入場無料、『ベーシック・インカム−基本所得のある社会へ』
2009年8月25日 読書
夏休み中は天王寺動物園が入場無料だというので、駆け込みで遊びに行った。
ここでのみどころは夜行性動物舎にいるキーウィなのだが、臆病な動物で、ほとんど姿を見せることがない。来場者が多い日などは、ガンガンとガラスを叩く大馬鹿者がいるため、なおさら出て来ない。
虎だのライオンだの、象だのキリンだの、普通に見ていて楽しい動物もいるが、なぜか、僕が見たいと思うのは、夜行性動物舎と爬虫類生態館に集中していて、あと、コアラ。
どこから見ても姿が見えないキーウィとか、たまに舌をピロピロ出すだけの蛇、いつまでもじっとしているコアラを見ていると、まるでウォーホールやストローブ=ユイレ、デレク・ジャーマンあたりの映画を見ているような気分になってくる。日常が溶解していく不思議な時間を過ごしてしまう。
ホッキョクグマがなんだか寂しそうだったな。あれはどういう感情なんだろう。
ゲッツ・W・ヴェルナーの『ベーシック・インカム−基本所得のある社会へ』を読んだ。
以下、目次。
序言−私たちは転換点に立っているのだろうか?
第1章 ゲッツ・W・ヴェルナーの提言、および彼とのインタビュー
未来への基礎:ベーシック・インカム(2005年11月全国紙に掲載されたヴェルナーの広報文)
つねに種を蒔くこと(2004年12月第60号『ア・テンポ』フランク・ベルガー、ジャン=クロード・リンとの対談)
月並みの改革ではなく、根本的な改革を(2005年11月第70号『ア・テンポ』)
私たちの生活はパラダイス状態にある(2005年4月号『ブラント・アインス』ガブリエレ・フィッシャーとの対談)
労働をマニアック視することで、みんな病気になる(2006年4月20日17号『シュテルン』アルノー・ルイクとの対談)
根本的に考えて、一歩一歩行動しなければならない(2006年第1号『バンク・シュピーゲル』シュテファン・ロットハウスがゲッツ・W・ヴェルナーとベネディクトゥス・ハードルプにインタビュー)
第2章 ベーシック・インカムの効果について−論考とインタビュー
不安の報酬/ヴォルフ・ロッター(2005年7月号『ブラント・アインス』)
1、対策
2、労働の嘘
3、骨折り
4、「新しい労働」とは何か?
5、失業は成功
6、刑務所に入る権利
7、市民の権利
8、活動
9、警察の保護下で労働すること
10、真の労働市場
11、理性の値段
労働市場と社会保障政策の分離/トーマス・シュトラウプハールとドリス・クライナウ=メッツラーの対談(2006年3月75号)
賃金は非課税/ヴォルフガング・アイヒホルンとドリス・クライナウ=メッツラーとの対談(2006年7月79号)
租税改革とは新たな分配を学ぶこと/ベネディクトゥス・ハードルプとドリス・クライナウ=メッツラーとの対談(2003年9月45号)
自由を可能にし、共同体を強化する/ザーシャ・リーバーマン(2006年2月23〜24日にカールスルーエ大学で開催されたシンポジウム「無条件のベーシック・インカムを」の講演原稿に手を加えたもの)
何が私たちを押しとどめるのか?
労働は最高の目標
後見ではなく、自由を
家族と教育
企業と従業員
参加、承認、信頼
第3章 反応
異議と回答(2006年第2号『バンク・シュピーゲル』)
読者からの手紙(2005年7月12日シュトゥットガルド新聞)
[解題]ゲッツ・W・ヴェルナー著『ベーシック・インカム−基本所得のある社会へ』に寄せて/小沢修司
ベーシック・インカム構想とは?
経営者的太千葉からのベーシック・インカム論
資本主義の経済発展が「要求」する新たな公共システム
消費税を財源とするベーシック・インカム論
新しい社会を構想する楽しさと喜び
ベーシック・インカムというのは、生活の必要な所得をすべての個人に無条件で支給しようという構想だ。先般の定額給付金の額を増やして、毎月なり毎週なり定期的に支給してくれるものと考えればわかりやすい。今まであった生活保護とか、失業手当てなどはベーシックインカムに吸収されて、なくなる。当然、その仕事に携わっていた公務員のムダはカットされる。失業とか貧困が問題化している昨今では、ベーシック・インカムは面白い提案で、すぐにでも導入してもらいたいと思うのだが。
ヴェルナーの考え方は、いわゆる逆転の発想で、対談でのやりとりでは、今までの固定した考えをほぐすことに主眼がおかれる。
たとえば、アルノー・ルイクとのインタビューでは、ルイクがさんざんヴェルナーをからかう。(詳しい内容は、実際に本を読んでいただくとしよう)
ルイク「あなたは禁忌破りがお好きで『人間がもはや労働する必要がないのは良いことだ』とおっしゃっていますね」
ヴェルナー「ええ。労働への強制から自由であることはなんといってもすごいことですからね」
ルイク「ひとは働くことによってのみ、また何かの価値を生み出すことによってのみ、社会のなかでなにがしかの価値があると認められる。それはまた自己価値をも生み出すのだと」
ヴェルナー「そうなのです。そんな見解を持ってしまうのも、私たちがいまだに古い、もはや時代に合わない道徳的な戒律にしたがって生きているからです。例の『働かざる者、食うべからず』ですよ」
ルイク「経済の課題はなんといっても職場を創出することではありませんか?」
ヴェルナー「いやいや。それはまったくのナンセンスですよ」
ルイク「そう考えると、失業者をたくさんかかえたドイツ経済はすばらしい状態にあることになりますね!」
ヴェルナー「そうです。私たちはパラダイス的な状態にあるのです」
ルイク「失業者があふれているのに、危機ではないと言うのですか?」
ヴェルナー「私たちは思考危機に陥っているのです。これほど多くの失業者が存在するということは、私たちの経済の強みであって、生産性の高さを示すものです」
ルイク「しかし、誰がベーシックインカムを負担するのです?要するに、さらなる増税と、さらなる出費をもたらすだけではありませんか!」
ヴェルナー「いいえ、まったくちがいます。私はあらゆる税を廃止することに賛成します。ただ1つ、付加価値税を除いて」
ルイク「しかし馬鹿を見るのは低所得者層ではありませんか。貧乏人は相対的にもっとも多く税を支払うことになります。しかも、商品は高くなる」
ヴェルナー「いいえ。付加価値税は社会的な観点から設定でき、商品は高くはなりません」
などなど。ベーシック・インカムはマルクス主義なんじゃないかとか、金持ちを肥らせるだけなんじゃないか、とか、いろいろルイクはつっこむが、ヴェルナーはその誤解をひとつひとつ解いて行く。
ザーシャ・リーバーマンが言うように、
「私たちが格闘するのは証拠の不備ではない。説明し、それによって把握されるべきは、誰の目にも明白な諸関連が、なぜ真面目に受け取られず、なぜそこから帰結が引き出され得ないかということである」
2007年に出た以文社の『VOL』02号の特集「ベーシック・インカム−ポスト福祉国家における労働と保障」でも、対談で山森亮がこう言っている。
「ベーシック・インカムの実行可能性レヴェルの話ならともかく、規範レヴェルですでに合意が少ない、ということが分かってきました。これは自分の想像をはるかに超えたもので、ショックと言えばショックなものでした。なぜこれほど抵抗が強いのかいまだによく分からないでいます」
うむ。ベーシック・インカム、今のところ大賛成だな。もうちょっと調べて考えてみよう。
ここでのみどころは夜行性動物舎にいるキーウィなのだが、臆病な動物で、ほとんど姿を見せることがない。来場者が多い日などは、ガンガンとガラスを叩く大馬鹿者がいるため、なおさら出て来ない。
虎だのライオンだの、象だのキリンだの、普通に見ていて楽しい動物もいるが、なぜか、僕が見たいと思うのは、夜行性動物舎と爬虫類生態館に集中していて、あと、コアラ。
どこから見ても姿が見えないキーウィとか、たまに舌をピロピロ出すだけの蛇、いつまでもじっとしているコアラを見ていると、まるでウォーホールやストローブ=ユイレ、デレク・ジャーマンあたりの映画を見ているような気分になってくる。日常が溶解していく不思議な時間を過ごしてしまう。
ホッキョクグマがなんだか寂しそうだったな。あれはどういう感情なんだろう。
ゲッツ・W・ヴェルナーの『ベーシック・インカム−基本所得のある社会へ』を読んだ。
以下、目次。
序言−私たちは転換点に立っているのだろうか?
第1章 ゲッツ・W・ヴェルナーの提言、および彼とのインタビュー
未来への基礎:ベーシック・インカム(2005年11月全国紙に掲載されたヴェルナーの広報文)
つねに種を蒔くこと(2004年12月第60号『ア・テンポ』フランク・ベルガー、ジャン=クロード・リンとの対談)
月並みの改革ではなく、根本的な改革を(2005年11月第70号『ア・テンポ』)
私たちの生活はパラダイス状態にある(2005年4月号『ブラント・アインス』ガブリエレ・フィッシャーとの対談)
労働をマニアック視することで、みんな病気になる(2006年4月20日17号『シュテルン』アルノー・ルイクとの対談)
根本的に考えて、一歩一歩行動しなければならない(2006年第1号『バンク・シュピーゲル』シュテファン・ロットハウスがゲッツ・W・ヴェルナーとベネディクトゥス・ハードルプにインタビュー)
第2章 ベーシック・インカムの効果について−論考とインタビュー
不安の報酬/ヴォルフ・ロッター(2005年7月号『ブラント・アインス』)
1、対策
2、労働の嘘
3、骨折り
4、「新しい労働」とは何か?
5、失業は成功
6、刑務所に入る権利
7、市民の権利
8、活動
9、警察の保護下で労働すること
10、真の労働市場
11、理性の値段
労働市場と社会保障政策の分離/トーマス・シュトラウプハールとドリス・クライナウ=メッツラーの対談(2006年3月75号)
賃金は非課税/ヴォルフガング・アイヒホルンとドリス・クライナウ=メッツラーとの対談(2006年7月79号)
租税改革とは新たな分配を学ぶこと/ベネディクトゥス・ハードルプとドリス・クライナウ=メッツラーとの対談(2003年9月45号)
自由を可能にし、共同体を強化する/ザーシャ・リーバーマン(2006年2月23〜24日にカールスルーエ大学で開催されたシンポジウム「無条件のベーシック・インカムを」の講演原稿に手を加えたもの)
何が私たちを押しとどめるのか?
労働は最高の目標
後見ではなく、自由を
家族と教育
企業と従業員
参加、承認、信頼
第3章 反応
異議と回答(2006年第2号『バンク・シュピーゲル』)
読者からの手紙(2005年7月12日シュトゥットガルド新聞)
[解題]ゲッツ・W・ヴェルナー著『ベーシック・インカム−基本所得のある社会へ』に寄せて/小沢修司
ベーシック・インカム構想とは?
経営者的太千葉からのベーシック・インカム論
資本主義の経済発展が「要求」する新たな公共システム
消費税を財源とするベーシック・インカム論
新しい社会を構想する楽しさと喜び
ベーシック・インカムというのは、生活の必要な所得をすべての個人に無条件で支給しようという構想だ。先般の定額給付金の額を増やして、毎月なり毎週なり定期的に支給してくれるものと考えればわかりやすい。今まであった生活保護とか、失業手当てなどはベーシックインカムに吸収されて、なくなる。当然、その仕事に携わっていた公務員のムダはカットされる。失業とか貧困が問題化している昨今では、ベーシック・インカムは面白い提案で、すぐにでも導入してもらいたいと思うのだが。
ヴェルナーの考え方は、いわゆる逆転の発想で、対談でのやりとりでは、今までの固定した考えをほぐすことに主眼がおかれる。
たとえば、アルノー・ルイクとのインタビューでは、ルイクがさんざんヴェルナーをからかう。(詳しい内容は、実際に本を読んでいただくとしよう)
ルイク「あなたは禁忌破りがお好きで『人間がもはや労働する必要がないのは良いことだ』とおっしゃっていますね」
ヴェルナー「ええ。労働への強制から自由であることはなんといってもすごいことですからね」
ルイク「ひとは働くことによってのみ、また何かの価値を生み出すことによってのみ、社会のなかでなにがしかの価値があると認められる。それはまた自己価値をも生み出すのだと」
ヴェルナー「そうなのです。そんな見解を持ってしまうのも、私たちがいまだに古い、もはや時代に合わない道徳的な戒律にしたがって生きているからです。例の『働かざる者、食うべからず』ですよ」
ルイク「経済の課題はなんといっても職場を創出することではありませんか?」
ヴェルナー「いやいや。それはまったくのナンセンスですよ」
ルイク「そう考えると、失業者をたくさんかかえたドイツ経済はすばらしい状態にあることになりますね!」
ヴェルナー「そうです。私たちはパラダイス的な状態にあるのです」
ルイク「失業者があふれているのに、危機ではないと言うのですか?」
ヴェルナー「私たちは思考危機に陥っているのです。これほど多くの失業者が存在するということは、私たちの経済の強みであって、生産性の高さを示すものです」
ルイク「しかし、誰がベーシックインカムを負担するのです?要するに、さらなる増税と、さらなる出費をもたらすだけではありませんか!」
ヴェルナー「いいえ、まったくちがいます。私はあらゆる税を廃止することに賛成します。ただ1つ、付加価値税を除いて」
ルイク「しかし馬鹿を見るのは低所得者層ではありませんか。貧乏人は相対的にもっとも多く税を支払うことになります。しかも、商品は高くなる」
ヴェルナー「いいえ。付加価値税は社会的な観点から設定でき、商品は高くはなりません」
などなど。ベーシック・インカムはマルクス主義なんじゃないかとか、金持ちを肥らせるだけなんじゃないか、とか、いろいろルイクはつっこむが、ヴェルナーはその誤解をひとつひとつ解いて行く。
ザーシャ・リーバーマンが言うように、
「私たちが格闘するのは証拠の不備ではない。説明し、それによって把握されるべきは、誰の目にも明白な諸関連が、なぜ真面目に受け取られず、なぜそこから帰結が引き出され得ないかということである」
2007年に出た以文社の『VOL』02号の特集「ベーシック・インカム−ポスト福祉国家における労働と保障」でも、対談で山森亮がこう言っている。
「ベーシック・インカムの実行可能性レヴェルの話ならともかく、規範レヴェルですでに合意が少ない、ということが分かってきました。これは自分の想像をはるかに超えたもので、ショックと言えばショックなものでした。なぜこれほど抵抗が強いのかいまだによく分からないでいます」
うむ。ベーシック・インカム、今のところ大賛成だな。もうちょっと調べて考えてみよう。
ジャン・リュック・ナンシーの『水と火』を読んだ。
訳者によって選ばれた2つのテキストをまとめた1冊で、そのチョイスが四大要素の2つを扱っていることに気づいたナンシーがそのことについて文章を寄せている。
「基本要素」は、そのナンシーの文章。
「近接した地点にて」は、場あるいは諸々の場というテーマの共同作品のために依頼されて書かれたテキスト。(接近した地点にて、という表題もついているけど、接近と近接との違いで、何を表わそうとしたのかは、また考えておきます)
このテキストは水を扱っており、読んでいると、ひたひたと水がすぐ近くまで寄せてきている気分が味わえる。
「火」は花火製造の手法を用いた芸術家(蔡國強)の展示会に添えるために書かれたテキスト。
これは実際の文体もそうなのか、ぱちぱちした感じ。
水と火。どうも、この本を明け方に読んだのが悪かったようだ。なんだか熱っぽいような気がして、おりから新型インフルエンザが猛威をふるう昨今、あわてて薬を飲んだのである。しかるのちに体温計で熱をはかってみると(順番が逆!)、平熱で首をひねった。単なる熱帯夜だったのか?ナンシー読んで頭から湯気出てたのか?(難しい本を読むと、よく頭からポッポー!と蒸気が出る)
どちらにしろ、薬の効き目のおかげで、僕の土日はぼ〜っと過ごすことに費やされる。
訳者によって選ばれた2つのテキストをまとめた1冊で、そのチョイスが四大要素の2つを扱っていることに気づいたナンシーがそのことについて文章を寄せている。
「基本要素」は、そのナンシーの文章。
「近接した地点にて」は、場あるいは諸々の場というテーマの共同作品のために依頼されて書かれたテキスト。(接近した地点にて、という表題もついているけど、接近と近接との違いで、何を表わそうとしたのかは、また考えておきます)
このテキストは水を扱っており、読んでいると、ひたひたと水がすぐ近くまで寄せてきている気分が味わえる。
「火」は花火製造の手法を用いた芸術家(蔡國強)の展示会に添えるために書かれたテキスト。
これは実際の文体もそうなのか、ぱちぱちした感じ。
水と火。どうも、この本を明け方に読んだのが悪かったようだ。なんだか熱っぽいような気がして、おりから新型インフルエンザが猛威をふるう昨今、あわてて薬を飲んだのである。しかるのちに体温計で熱をはかってみると(順番が逆!)、平熱で首をひねった。単なる熱帯夜だったのか?ナンシー読んで頭から湯気出てたのか?(難しい本を読むと、よく頭からポッポー!と蒸気が出る)
どちらにしろ、薬の効き目のおかげで、僕の土日はぼ〜っと過ごすことに費やされる。
『高貴なる人々に贈る言葉』
2009年8月21日 読書バルベー・ドールヴィイの『高貴なる人々に贈る言葉』を読んだ。
以下、目次。
1、思想の断片
2、女性に関する断章
3、続・思想の断片
4、その他の箴言
5、散文詩
三杯の紅茶
ラオコーン
1、2は1889年刊行。没年なのだが、死後発刊されたかどうか、まだ調べてません。
3は雑誌「黄色い矮人」に発表されたもの。
5は詩集「忘られたリズム」から。
寸鉄人を刺すアフォリズム、というより、詩集の趣きがある。
巻頭、脈略ある思想を「箙」にたとえ、切り離した思想を「飛んで行く矢」にたとえる。
たまたまボードレールの「火箭」を読んでいたせいもあって、世紀末フランスと詩と矢の三大噺のシンクロに驚いた。
本書を読んで、へえ、と感じた文章を引用しておこう。
哲学は、栓抜きを使って雲にあけた穴のようなものである。
ゲームは城砦である。自分にとって愉快だというより、他人から身を護るためのものである。
旅に出る友人に捧げる、出発する、とは、留まるのに必要なかぎ形の原子の数が足らないということである。
この世紀末大いに話題にされている奴隷廃止より、もっと早くやって来るものがある。それは婦人の廃止である。
平等という卑しい者たちの抱く幻影は、実際は高貴な者の間にしか存在しない。
法の前の平等は、1つのことだけを証明する。すなわち、他人などいないことである。
さすが、ドールヴィイ、わかってらっしゃる。
以下、目次。
1、思想の断片
2、女性に関する断章
3、続・思想の断片
4、その他の箴言
5、散文詩
三杯の紅茶
ラオコーン
1、2は1889年刊行。没年なのだが、死後発刊されたかどうか、まだ調べてません。
3は雑誌「黄色い矮人」に発表されたもの。
5は詩集「忘られたリズム」から。
寸鉄人を刺すアフォリズム、というより、詩集の趣きがある。
巻頭、脈略ある思想を「箙」にたとえ、切り離した思想を「飛んで行く矢」にたとえる。
たまたまボードレールの「火箭」を読んでいたせいもあって、世紀末フランスと詩と矢の三大噺のシンクロに驚いた。
本書を読んで、へえ、と感じた文章を引用しておこう。
哲学は、栓抜きを使って雲にあけた穴のようなものである。
ゲームは城砦である。自分にとって愉快だというより、他人から身を護るためのものである。
旅に出る友人に捧げる、出発する、とは、留まるのに必要なかぎ形の原子の数が足らないということである。
この世紀末大いに話題にされている奴隷廃止より、もっと早くやって来るものがある。それは婦人の廃止である。
平等という卑しい者たちの抱く幻影は、実際は高貴な者の間にしか存在しない。
法の前の平等は、1つのことだけを証明する。すなわち、他人などいないことである。
さすが、ドールヴィイ、わかってらっしゃる。
『思想地図』vol.2「特集・ジェネレーション」
2009年8月20日 読書
『思想地図』vol.2「特集・ジェネレーション」を読んだ。
以下、目次とまとめとか感想とか。
I 家族の現在
毀れた循環−戦後日本型モデルへの弔辞 本田由紀
戦後日本型循環モデルはもう無理なのだ
仕事、家族、教育
長期雇用、年功賃金、性別役割分業、新規学卒一括採用
仕事−(賃金)→家族−(教育費)→教育−(新規労働力)→仕事
「払える余裕のある者が払い、その当人のみならず社会全体が安心と承認を受け取るという、日本ではついぞ存在しなかった社会の体制を、今だからこそ作ることが切実に必要とされるのだ。それは個々人がエゴイズムという遮眼革から解き放たれることでもある」
それでも、家族は続く−カウンセリングの現場から 信田さよ子
はじめに
ニッチとしての開業カウンセリング機関
非医療モデルの援助論=アディクションアプローチ
1、本人より家族を
2、援助の有害性の指摘
3、援助の限界設定
医療モデル→本人の症状中心の医療
ケアの有効性を無謬であるとする援助観
当事者をあくまでも治療対象とする。
困っているひとがクライエントである
まず主訴を確定する
症状→問題、診断名→主訴、治療→援助といった言葉の変換
問題化という契機
異議を唱えて再定義する
主訴は変わる
受容や共感より、積極的質問と意見表明こそカウンセリングのキーポイントである。
家族における権力
親を責める子どもたち
浮かび上がる脆弱な夫婦関係
非権力的親子関係の創造
望ましい家族とは
暴力というリスクを回避するために必要なポイント
○他者性の自覚(配偶者も子どもも他者であるという冷徹な認知)
○親密さは家族の外に求める
○コミュニケーションの断念(新たな関係創出のために)
「あなたのために」「どうしてお前は」等にかわって「私」を主語とした言葉
○子ども中心の関係
○親が子に与えられることは何か(父と母の安定した関係性を日常見せる)
おわりに
II 労働と創造の新しい関係
ゲームプレイ・ワーキング−新しい労働観とパラレル・ワールドの誕生 鈴木健
ヒューマン・コンピューティングの勃興
CAPTCHA(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)
コンピュータとしての社会
「コンピュータ」が人間だったころ
ゲームの労働化と労働のゲーム化
複数化する現実とパラレル・ワールドの誕生 (電脳コイル)
パラレル・ワールドで人々はいかに結びつくか
対抗的創造主義を生きよ!−「労働論の根本問題」に応える 橋本努
1、「労働の理想」の再検討
1a、問題の定式化
2b、アーレント・モデルの拡張
労働→「生の跳躍」エランヴィタル
仕事→「プロテスタンティズムのエートス」
活動→「ジェントルマンの騎士精神」
2、潜在能力論の分岐
2a、「創造」の理念をめぐる対立
3b、3つの応答とその射程
1、最低限の生活水準の保障
2、職能社会
3、市民生活の理念
3、市民主義から創造主義へ
3a、歴史的経緯
3b、全能性に満ちた野生社会
3c、ディオニュソス的生の回復へ向けて
「創造主義者たちによれば、経済的に成功するための『創造性』など、とるに足らない能力にすぎない。真の創造性は、けっして経済的に評価されることのない芸術活動にこそ宿るのである」
「創造主義者は、業績や帰属集団による評価だとか、公共空間における評価といったものを求めない。また、「男のこだわり」だとか「隠れ家」といった、たんなる趣味の豊かさなどを軽蔑する」
民主主義のための福祉−「熟議民主主義とベーシック・インカム」再考 田村哲樹
序論 熟議民主主義とその条件(⇔集計民主主義、多数決)
1、条件としての社会保障
1.1 福祉国家と生産主義
1.2 ギデンズの積極的福祉論
2、民主主義の条件としての社会保障
2.1 対話的民主主義のための積極的福祉か
2.2 労働市場パラダイムからの転換
3、民主主義の条件としてのベーシック・インカム
3.1 財産の平等と民主主義
3.2 民主主義は余暇を必要とする
3.3 なぜ無条件性か?−民主主義の「魅力のなさ」と負担軽減
結論
私小説的労働と組合−柳田國男の脱「貧困」論 大澤信亮
1、柳田國男の綜合性
2、私小説批判
二通りの風景描写
「私」の成立する社会的条件
3、私小説的労働と組合
日本一小さい家
三倉−柳田農政学の学問的背景
(飢餓の救済システム「義倉」「社倉」「常平倉」)
「組合」とは何か
私小説的労働の批判
4、神の言語あるいは所有の放棄について
「新国学」の時代的背景
「自己内部の省察」という方法
山の事件
「組合」の可能性はどこにあるのか
「神の言語」とは何か
III 世代論をどう捉えるか
世代間対立という罠 上野千鶴子インタビュー(聞き手・北田暁大)
『おひとりさまの老後』への批判(東)
団塊世代はゼロからのスタートだった
団塊女性にストックはない
ストック劣化という予想外のシナリオ
非世紀雇用が問題化した背景
エリート女性のネオリベ化がもたらしたもの
家族を当てにできない若者たち
誰が得をするのか?
<ジェネレーション>を思想化する−<世代間の争い>を引き受けて問うこと 天田城介
1、<世代間の争い>の語りは確かに私たちの感情に何がしかを訴えている
2、<ジェネレーション>をその根底において問う
3、この社会において<ジェネレーション>を思想化する
4、自由を生産する−<安全>のもとでの自由が<不安>をも産み出す
5、制御不可能な不可視の全体(性)が個々人の利己的計算を基礎づける
6、<社会>の観念こそが『自由主義的統括実践』を可能にする
7、エコノミーによって生−権力は配備される
8、生きさせることと死の中に廃棄することは<人種主義>によって接合される
9、エコノミーの彼岸における根源的贈与
10、未来における世界の奇跡的な到来
4章以降の見取り図は次のとおり。
フーコーが描出したラディカルな統治理性批判たる<自由主義的統治実践=「統治の過剰性」への不断の自己反省的・自己制御的統治実践>について言及→「4」
政治経済学における<自由主義的統治実践>が、制御不可能な不可視の全体(性)によって基礎づけられていることを剔出→「5」
<自由主義的統治実践>は<社会>という観念を駆逐するものではなく、むしろ<社会>という観念によってこそ可能になっていることを明示→「6」
<自由主義的統治実践>換言すれば経済において権力を行使する統治術たる「バイオエコノミー」こそが「人口」を調節する「生−政治」として立ち現れている→「7」
「生きさせるか、死に廃棄するか(死ぬに任せるか)」という「生−権力」が「人種主義」によって接合可能になっていることを論証→「8」
生−権力をめぐるエコノミーを踏まえた上で、デリダの「死の贈与のエコノミー」を導きの糸に<ジェネレーション>をいかに問うことが可能であるのか論究→「9」
未来(の世界)の到来を前提にこの社会が可能になっているという端的な事実性こそが、未来(の世界)において人々に生存する身体を与え、生存するための全てを享受できる世界を与えてくれる、「奇跡の到来」という「根源的贈与」への信によって支えられていることを論じる→「10」
「総中流の思想」とは何だったのか−「中」意識の原点をさぐる 森直人
1、はじめに
1-1問題提起
「本稿は<敗戦>という集合的体験が直接には語られないことにおいてその後の言説構造のなかに長く持ち越され「戦後日本」について語る言説に意味を備給し続け、その自己言及のあり方を規定してきたことを明らかにする」
いわば<敗戦>の忘却のうえに<高度成長>という歴史的体験の共有化が進行する。
1-2論争の歴史的意義
2、<新中間−大衆社会>論の見取り図
2-1「新中間大衆」の登場
2-2賭金としての「中」意識と論争の構図
2-3共有された誤認
3、生活構造論と「中」意識の再解釈
3-1生活構造論と「第一の戦後」
3-2方法としての生活構造−変動仮説
3-3検証の課題
4、SSM1955の分析
4-1「中」意識(回顧)の分布変動−検証1
Social Stratification and Social Mobility Survey(社会階層と社会移動に関する全国調査)
4-2都市部の「タケノコ生活」仮説−検証2
4-3「中」収斂メカニズムの限界線−検証3
5、おわりに−「総中流」のゼロ記号
生活構造論(3-1)のくだりには笑った。環境の急激な変化にすぐに対応できずに、履歴現象と呼ばれる、今までのパターンを保持しようとする、というところで、こんな文章が。
「急激に所得が上昇しても直ちに洗練された消費活動へと移行できるわけではない(「成金」とはこのことだ)。逆に生活水準が急激に低下しても、短期的には喫緊の必需品への支出より、過去からの惰性で余暇的・娯楽的な支出、生理学的・経済学的には「非合理的」な支出へと傾く慣習から脱けだせない」
まったくもってそのとおり。
特集・胎動するインフラ・コミュニケーション
[座談会]ソシオフィジクスは可能か 東浩紀+北田暁大+西田亮介+濱野智史
SFC-GLOCOK的パラダイム(慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス−国際大学グローバル・コミュニケーション・センター)
トフラー的な未来学との違い(マルクス主義の影響下にあった文明論)
民主制をめぐるパラダイム・シフト
トップダウン・アプローチ
アーキテクチュラル・アプローチとは何か
スケールフリーの法則
ベキ乗分布が生権力を変える
クリエイティブ・エコノミー論の背景
「社会」と「意味」
洗練されたデュルケム主義?
主体・実存の社会学を超えて
アーキテクチャの設計をめぐって
ソシオフィジクスの再発見
「ソシオフィジクス」を知るための10冊 西田亮介+濱野智史
『CODE』『伽藍とバザール』『市場を創る』『紛争の戦略』『クリエイティブ・クラスの世紀』『哲学する民主主義』『フューチャー・オブ・ワーク』『オープンアーキテクチャ戦略』『歴史の方程式』『新ネットワーク思考』
はい、どれも読んでません。ぼちぼち読みます。
ニコ二コ動画の生成力−メタデータが可能にする新たな創造性 濱野智史
「シナのある百科事典」と「ニコニコ動画」
「創造力」と「生成力」−「作者」から「環境」へ
ニコニコ動画上の「N次創作」現象−ユーチューブとの比較考察
「フォークソノミー(folksonomy)」−知の秩序の「第三段階」の到来
トーマス・ヴァンダー・ウォルが「タクソノミー(分類法)」に対比させる形で命名。(民俗の分類法。人々が自由にタグを割りふることでボトムアップ式に分類体系が浮かび上がる)
「フラクソノミー(fluxonomy)」(←流転分類)−ニコニコ動画の「タグ戦争」
「タグ戦争」の量子力学的効果
「作者性」の機能的等価物
<社会>における創造を考える−問題発見・解決の思考と実践 西田亮介
1、はじめに
2、制度設計の<困難>
3、創造の時代
4、個人と組織の創造力を活かす地域活性の理論−創発型地域活性
5、湘南ビーチマネーの意義
6、おわりに
ゴミを貨幣として使う、とは考えたな。
[座談会]再帰的公共性と動物的公共性 東浩紀+大屋雄裕+笠井 潔+北田暁大
アーキテクチャをどう捉えるか
監視社会批判が衰弱した理由
「被害者ばかりに同調してしまう想像力の非対称性」(大屋)
利便性や不安に根拠はあるのか?
主権主義の必要性
世界を変えられるという感覚が麻痺している
千年王国主義運動は終わっていない
公共圏と公共財との違い
ロスジェネが暴発するとき
「あえて」物語を信憑する時代
水面下のパターナリズム
パートタイム的な主体性
1人1票制度の限界?
グーグル的ページリンクの論理
グーグルは道路を作れるか?
設計に抗う力
「再帰性か、動物性か」再び
[特別掲載]「市民性」と批評のゆくえ−<まったく新しい日本文学史>のために 入江哲朗
「市民性」とアンビヴァレンツ
「凡庸さ」と「愚鈍さ」
批評的な力点と「凡庸さ」
「凡庸さ」と「市民性」
「市民性」と「未来」
(北杜夫『楡家の人びと』に対する三島由紀夫の絶賛と、『白きたおやかな峰』に対する批判のアンビヴァレンツを蓮實重彦の「凡庸」論で分析)
1冊とおして不安になったのは、僕が、「なーるほど!」と面白く感じたのは、上野千鶴子が東の批評に対して反論する論調と、対談で笠井潔が加害者あるいはテロリストの立場から監視社会を批判する視点だった。つまり、面白いと思い、しっくりくるのは、自分の年齢に近い人々の発言だったのだ。僕は年齢の若い人の考えていることをちゃんと聞いているんだろうか。
以下、目次とまとめとか感想とか。
I 家族の現在
毀れた循環−戦後日本型モデルへの弔辞 本田由紀
戦後日本型循環モデルはもう無理なのだ
仕事、家族、教育
長期雇用、年功賃金、性別役割分業、新規学卒一括採用
仕事−(賃金)→家族−(教育費)→教育−(新規労働力)→仕事
「払える余裕のある者が払い、その当人のみならず社会全体が安心と承認を受け取るという、日本ではついぞ存在しなかった社会の体制を、今だからこそ作ることが切実に必要とされるのだ。それは個々人がエゴイズムという遮眼革から解き放たれることでもある」
それでも、家族は続く−カウンセリングの現場から 信田さよ子
はじめに
ニッチとしての開業カウンセリング機関
非医療モデルの援助論=アディクションアプローチ
1、本人より家族を
2、援助の有害性の指摘
3、援助の限界設定
医療モデル→本人の症状中心の医療
ケアの有効性を無謬であるとする援助観
当事者をあくまでも治療対象とする。
困っているひとがクライエントである
まず主訴を確定する
症状→問題、診断名→主訴、治療→援助といった言葉の変換
問題化という契機
異議を唱えて再定義する
主訴は変わる
受容や共感より、積極的質問と意見表明こそカウンセリングのキーポイントである。
家族における権力
親を責める子どもたち
浮かび上がる脆弱な夫婦関係
非権力的親子関係の創造
望ましい家族とは
暴力というリスクを回避するために必要なポイント
○他者性の自覚(配偶者も子どもも他者であるという冷徹な認知)
○親密さは家族の外に求める
○コミュニケーションの断念(新たな関係創出のために)
「あなたのために」「どうしてお前は」等にかわって「私」を主語とした言葉
○子ども中心の関係
○親が子に与えられることは何か(父と母の安定した関係性を日常見せる)
おわりに
II 労働と創造の新しい関係
ゲームプレイ・ワーキング−新しい労働観とパラレル・ワールドの誕生 鈴木健
ヒューマン・コンピューティングの勃興
CAPTCHA(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)
コンピュータとしての社会
「コンピュータ」が人間だったころ
ゲームの労働化と労働のゲーム化
複数化する現実とパラレル・ワールドの誕生 (電脳コイル)
パラレル・ワールドで人々はいかに結びつくか
対抗的創造主義を生きよ!−「労働論の根本問題」に応える 橋本努
1、「労働の理想」の再検討
1a、問題の定式化
2b、アーレント・モデルの拡張
労働→「生の跳躍」エランヴィタル
仕事→「プロテスタンティズムのエートス」
活動→「ジェントルマンの騎士精神」
2、潜在能力論の分岐
2a、「創造」の理念をめぐる対立
3b、3つの応答とその射程
1、最低限の生活水準の保障
2、職能社会
3、市民生活の理念
3、市民主義から創造主義へ
3a、歴史的経緯
3b、全能性に満ちた野生社会
3c、ディオニュソス的生の回復へ向けて
「創造主義者たちによれば、経済的に成功するための『創造性』など、とるに足らない能力にすぎない。真の創造性は、けっして経済的に評価されることのない芸術活動にこそ宿るのである」
「創造主義者は、業績や帰属集団による評価だとか、公共空間における評価といったものを求めない。また、「男のこだわり」だとか「隠れ家」といった、たんなる趣味の豊かさなどを軽蔑する」
民主主義のための福祉−「熟議民主主義とベーシック・インカム」再考 田村哲樹
序論 熟議民主主義とその条件(⇔集計民主主義、多数決)
1、条件としての社会保障
1.1 福祉国家と生産主義
1.2 ギデンズの積極的福祉論
2、民主主義の条件としての社会保障
2.1 対話的民主主義のための積極的福祉か
2.2 労働市場パラダイムからの転換
3、民主主義の条件としてのベーシック・インカム
3.1 財産の平等と民主主義
3.2 民主主義は余暇を必要とする
3.3 なぜ無条件性か?−民主主義の「魅力のなさ」と負担軽減
結論
私小説的労働と組合−柳田國男の脱「貧困」論 大澤信亮
1、柳田國男の綜合性
2、私小説批判
二通りの風景描写
「私」の成立する社会的条件
3、私小説的労働と組合
日本一小さい家
三倉−柳田農政学の学問的背景
(飢餓の救済システム「義倉」「社倉」「常平倉」)
「組合」とは何か
私小説的労働の批判
4、神の言語あるいは所有の放棄について
「新国学」の時代的背景
「自己内部の省察」という方法
山の事件
「組合」の可能性はどこにあるのか
「神の言語」とは何か
III 世代論をどう捉えるか
世代間対立という罠 上野千鶴子インタビュー(聞き手・北田暁大)
『おひとりさまの老後』への批判(東)
団塊世代はゼロからのスタートだった
団塊女性にストックはない
ストック劣化という予想外のシナリオ
非世紀雇用が問題化した背景
エリート女性のネオリベ化がもたらしたもの
家族を当てにできない若者たち
誰が得をするのか?
<ジェネレーション>を思想化する−<世代間の争い>を引き受けて問うこと 天田城介
1、<世代間の争い>の語りは確かに私たちの感情に何がしかを訴えている
2、<ジェネレーション>をその根底において問う
3、この社会において<ジェネレーション>を思想化する
4、自由を生産する−<安全>のもとでの自由が<不安>をも産み出す
5、制御不可能な不可視の全体(性)が個々人の利己的計算を基礎づける
6、<社会>の観念こそが『自由主義的統括実践』を可能にする
7、エコノミーによって生−権力は配備される
8、生きさせることと死の中に廃棄することは<人種主義>によって接合される
9、エコノミーの彼岸における根源的贈与
10、未来における世界の奇跡的な到来
4章以降の見取り図は次のとおり。
フーコーが描出したラディカルな統治理性批判たる<自由主義的統治実践=「統治の過剰性」への不断の自己反省的・自己制御的統治実践>について言及→「4」
政治経済学における<自由主義的統治実践>が、制御不可能な不可視の全体(性)によって基礎づけられていることを剔出→「5」
<自由主義的統治実践>は<社会>という観念を駆逐するものではなく、むしろ<社会>という観念によってこそ可能になっていることを明示→「6」
<自由主義的統治実践>換言すれば経済において権力を行使する統治術たる「バイオエコノミー」こそが「人口」を調節する「生−政治」として立ち現れている→「7」
「生きさせるか、死に廃棄するか(死ぬに任せるか)」という「生−権力」が「人種主義」によって接合可能になっていることを論証→「8」
生−権力をめぐるエコノミーを踏まえた上で、デリダの「死の贈与のエコノミー」を導きの糸に<ジェネレーション>をいかに問うことが可能であるのか論究→「9」
未来(の世界)の到来を前提にこの社会が可能になっているという端的な事実性こそが、未来(の世界)において人々に生存する身体を与え、生存するための全てを享受できる世界を与えてくれる、「奇跡の到来」という「根源的贈与」への信によって支えられていることを論じる→「10」
「総中流の思想」とは何だったのか−「中」意識の原点をさぐる 森直人
1、はじめに
1-1問題提起
「本稿は<敗戦>という集合的体験が直接には語られないことにおいてその後の言説構造のなかに長く持ち越され「戦後日本」について語る言説に意味を備給し続け、その自己言及のあり方を規定してきたことを明らかにする」
いわば<敗戦>の忘却のうえに<高度成長>という歴史的体験の共有化が進行する。
1-2論争の歴史的意義
2、<新中間−大衆社会>論の見取り図
2-1「新中間大衆」の登場
2-2賭金としての「中」意識と論争の構図
2-3共有された誤認
3、生活構造論と「中」意識の再解釈
3-1生活構造論と「第一の戦後」
3-2方法としての生活構造−変動仮説
3-3検証の課題
4、SSM1955の分析
4-1「中」意識(回顧)の分布変動−検証1
Social Stratification and Social Mobility Survey(社会階層と社会移動に関する全国調査)
4-2都市部の「タケノコ生活」仮説−検証2
4-3「中」収斂メカニズムの限界線−検証3
5、おわりに−「総中流」のゼロ記号
生活構造論(3-1)のくだりには笑った。環境の急激な変化にすぐに対応できずに、履歴現象と呼ばれる、今までのパターンを保持しようとする、というところで、こんな文章が。
「急激に所得が上昇しても直ちに洗練された消費活動へと移行できるわけではない(「成金」とはこのことだ)。逆に生活水準が急激に低下しても、短期的には喫緊の必需品への支出より、過去からの惰性で余暇的・娯楽的な支出、生理学的・経済学的には「非合理的」な支出へと傾く慣習から脱けだせない」
まったくもってそのとおり。
特集・胎動するインフラ・コミュニケーション
[座談会]ソシオフィジクスは可能か 東浩紀+北田暁大+西田亮介+濱野智史
SFC-GLOCOK的パラダイム(慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス−国際大学グローバル・コミュニケーション・センター)
トフラー的な未来学との違い(マルクス主義の影響下にあった文明論)
民主制をめぐるパラダイム・シフト
トップダウン・アプローチ
アーキテクチュラル・アプローチとは何か
スケールフリーの法則
ベキ乗分布が生権力を変える
クリエイティブ・エコノミー論の背景
「社会」と「意味」
洗練されたデュルケム主義?
主体・実存の社会学を超えて
アーキテクチャの設計をめぐって
ソシオフィジクスの再発見
「ソシオフィジクス」を知るための10冊 西田亮介+濱野智史
『CODE』『伽藍とバザール』『市場を創る』『紛争の戦略』『クリエイティブ・クラスの世紀』『哲学する民主主義』『フューチャー・オブ・ワーク』『オープンアーキテクチャ戦略』『歴史の方程式』『新ネットワーク思考』
はい、どれも読んでません。ぼちぼち読みます。
ニコ二コ動画の生成力−メタデータが可能にする新たな創造性 濱野智史
「シナのある百科事典」と「ニコニコ動画」
「創造力」と「生成力」−「作者」から「環境」へ
ニコニコ動画上の「N次創作」現象−ユーチューブとの比較考察
「フォークソノミー(folksonomy)」−知の秩序の「第三段階」の到来
トーマス・ヴァンダー・ウォルが「タクソノミー(分類法)」に対比させる形で命名。(民俗の分類法。人々が自由にタグを割りふることでボトムアップ式に分類体系が浮かび上がる)
「フラクソノミー(fluxonomy)」(←流転分類)−ニコニコ動画の「タグ戦争」
「タグ戦争」の量子力学的効果
「作者性」の機能的等価物
<社会>における創造を考える−問題発見・解決の思考と実践 西田亮介
1、はじめに
2、制度設計の<困難>
3、創造の時代
4、個人と組織の創造力を活かす地域活性の理論−創発型地域活性
5、湘南ビーチマネーの意義
6、おわりに
ゴミを貨幣として使う、とは考えたな。
[座談会]再帰的公共性と動物的公共性 東浩紀+大屋雄裕+笠井 潔+北田暁大
アーキテクチャをどう捉えるか
監視社会批判が衰弱した理由
「被害者ばかりに同調してしまう想像力の非対称性」(大屋)
利便性や不安に根拠はあるのか?
主権主義の必要性
世界を変えられるという感覚が麻痺している
千年王国主義運動は終わっていない
公共圏と公共財との違い
ロスジェネが暴発するとき
「あえて」物語を信憑する時代
水面下のパターナリズム
パートタイム的な主体性
1人1票制度の限界?
グーグル的ページリンクの論理
グーグルは道路を作れるか?
設計に抗う力
「再帰性か、動物性か」再び
[特別掲載]「市民性」と批評のゆくえ−<まったく新しい日本文学史>のために 入江哲朗
「市民性」とアンビヴァレンツ
「凡庸さ」と「愚鈍さ」
批評的な力点と「凡庸さ」
「凡庸さ」と「市民性」
「市民性」と「未来」
(北杜夫『楡家の人びと』に対する三島由紀夫の絶賛と、『白きたおやかな峰』に対する批判のアンビヴァレンツを蓮實重彦の「凡庸」論で分析)
1冊とおして不安になったのは、僕が、「なーるほど!」と面白く感じたのは、上野千鶴子が東の批評に対して反論する論調と、対談で笠井潔が加害者あるいはテロリストの立場から監視社会を批判する視点だった。つまり、面白いと思い、しっくりくるのは、自分の年齢に近い人々の発言だったのだ。僕は年齢の若い人の考えていることをちゃんと聞いているんだろうか。
『「悪いこと」したら、どうなるの?』
2009年8月19日 読書
藤井誠二の『「悪いこと」したら、どうなるの?』を読んだ。
巻頭に武富健治のマンガがある。多くの取材から描かれている。
以下、目次。
第1章 子どもでも、死刑になるの
少年という理由で死刑にできないのなら…/少年でも死刑になる/きみは「死刑」のことをどれだけ知っているか/死刑確定から執行まで/死刑廃止「後進国」の日本
第2章 「少年法」は子どもを守ってくれるの?
少年が傷害事件を起こしたら/少年の特別扱いが「少年法」/少年審判に「刑罰」はない/「和やかに」そして非公開で/「前科」にならない保護処分/少年でも刑罰への道はある/「原則逆送」と少年刑務所送致/少年刑務所で「どん底体験」を語る/「保護処分」の理由/14才以下で法律に触れたなら/犯罪少年:触法少年:虞犯少年/擬似家族として暮らす/塀のない施設での殺害事件
(註:犯罪少年は14才〜20才未満、触法少年は14才未満、虞犯少年は不良行状の少年)
第3章 少年院ってどんなところ?
移動はかけ声とともに/少年院の種類と収容期間/単独室からのはじまり/少年院の1日/「立ち直り」のための5つのプログラム/「働く」ことの意味をみつける/ひとりひとりにかかわるということ/「基本」と「個別」ふたつの「計画」/くり返しくり返し考える/2級の下から1級の上へ/「サイコドラマ」で自分を知る/役割交換の手紙/母親:被害者との往復書簡/いちばん遅れている教育/保護司の役割/命令された被害者/被害者がそこにはいない/被害者の名前を知らない少年/「立ち直り」の前提になるものは?
(註:立ち直りのための5つのプログラムとは、生活指導、職業指導、教科教育、保健体育、特別活動)
第4章 「少年法」が改正されたのは、なぜ?
逆の立場にいる人たち/12年前に事件/加害者のことも事件の内容も「教えられません」/被害者当事者は蚊屋の外/「被害を受けたほうにも原因があるんじゃないの?」/法務大臣への要望書/少年法改正に関する意見書/なにが改正されたのか/現実と2回目の少年法改正/訴えのみなもとにあるもの/「あすの会」の活動/コピー代や遺体の返還のこと/新しい制度が生かされるために
第5章 犯罪少年の家族は、どうしているの?
どんな生活を送るのだろうか/転居をくり返す母親/出院した少年を殴りつける父親/損害賠償と逃亡/11年前の事件/いのちの金額/謝罪の手紙と「再犯」/聡至君の母とAの母/犯罪はすべてのものを奪いつくす
第6章 被害にあった人は、ゆるしてくれるの?
保護観察の意味/保護司はボランティアだ/仕事をさがす方法/再犯への別れ道/ぼくらの社会はどんな社会か/少年はゆるされるのか/「ゆるす」ということ/「ゆるさなくてはいけない」のか?/更生なんかのぞんでいない
藤井誠二は、被害者側からものを考える人で、厳罰化にも死刑にも肯定的な人だと思う。僕とは正反対の考え方なので、よく言っていることを聞く必要がある。
本書を読んで、今まであまりにも被害者からの立場でものを考えられてこなかった経緯を知り、それが正されつつあることには、納得し、同意するところが多かった。
もう少し彼の著作を読んでみよう。
まだ、僕は死刑に同意する立場からは遠い。何をした人間でも、人間が人間を「こいつは殺してもいい」と決めつけることなどできないんじゃないか、と考えるからだ。もしも親兄弟を殺されて憎しみのあまり、その犯人を「命を奪ってもいい者」と決める場合、僕は2つのことを考える。1つは、死刑にしろ復讐にしろ、そうして人間の命を奪うことに対しても、なんらかの「仕返し」なり「ペナルティー」が発生するのが筋じゃないか。(仇討ち!復讐の連鎖って奴です)。もう1つは、最初に犯人が「親兄弟」を殺したときに、遺族が「犯人を殺せ」と抱く激情と同じものを犯人が抱いていたかもしれない、ということ。つまり、これは単なる順番の問題で、1人の人間を「被害者」「加害者」にわけることなどできないんじゃないか、ということ。
こういうものの考え方は、ミステリー読みとしては、ごく普通のことだと思う。
ミステリーには、殺されてもおかしくないような人物が山ほどあらわれる。
人を殺すには必ずそれなりの理由なり、激情なりがある。その人が「犯人」であれ「遺族」であれ、事情は一緒。だから、「犯人を殺してやりたい!」と思う気持と「あいつ(被害者)を殺してやりたい!」と思う気持に差はなく、逆転すらありうる。
もしも、被害者の心情から「命を奪ったものは命をもって償う」とでも言うのなら、イラク人を虐殺したアメリカにもそれをつきつけて、少なくとも同じ人数だけアメリカ人を殺してインフラを破壊しなければならない。戦争ならいいのだとでもいうなら、犯人は「これは戦争だったのです」と言えばいいのだ。戦争であれ、いかに憎い奴であれ、殺人犯であれ、人の命を奪ってはいけない、という考えが僕からは抜けない。本書では後半に、被害者遺族が加害者を「許さなくてはならない」のか?と問いかけている。もちろん、「しなければいけない」というわけではないだろう。でも、「許せれば一番いい」と僕は思うのだが、間違っているんだろうか。さもなくば、日本はアメリカや中国と永遠に敵対関係にいなければならない。
それと、「被害者」とひとくちに言うけど、本当の被害者はもう死んでいるとしたら、どこまでが被害者なのか。家族か?恋人か?同じ国の人間か?同じ人類か?同じ生とし生けるものか?簡単に「被害者」という言葉をつけてしまうことにも首をかしげざるをえない。
巻頭に武富健治のマンガがある。多くの取材から描かれている。
以下、目次。
第1章 子どもでも、死刑になるの
少年という理由で死刑にできないのなら…/少年でも死刑になる/きみは「死刑」のことをどれだけ知っているか/死刑確定から執行まで/死刑廃止「後進国」の日本
第2章 「少年法」は子どもを守ってくれるの?
少年が傷害事件を起こしたら/少年の特別扱いが「少年法」/少年審判に「刑罰」はない/「和やかに」そして非公開で/「前科」にならない保護処分/少年でも刑罰への道はある/「原則逆送」と少年刑務所送致/少年刑務所で「どん底体験」を語る/「保護処分」の理由/14才以下で法律に触れたなら/犯罪少年:触法少年:虞犯少年/擬似家族として暮らす/塀のない施設での殺害事件
(註:犯罪少年は14才〜20才未満、触法少年は14才未満、虞犯少年は不良行状の少年)
第3章 少年院ってどんなところ?
移動はかけ声とともに/少年院の種類と収容期間/単独室からのはじまり/少年院の1日/「立ち直り」のための5つのプログラム/「働く」ことの意味をみつける/ひとりひとりにかかわるということ/「基本」と「個別」ふたつの「計画」/くり返しくり返し考える/2級の下から1級の上へ/「サイコドラマ」で自分を知る/役割交換の手紙/母親:被害者との往復書簡/いちばん遅れている教育/保護司の役割/命令された被害者/被害者がそこにはいない/被害者の名前を知らない少年/「立ち直り」の前提になるものは?
(註:立ち直りのための5つのプログラムとは、生活指導、職業指導、教科教育、保健体育、特別活動)
第4章 「少年法」が改正されたのは、なぜ?
逆の立場にいる人たち/12年前に事件/加害者のことも事件の内容も「教えられません」/被害者当事者は蚊屋の外/「被害を受けたほうにも原因があるんじゃないの?」/法務大臣への要望書/少年法改正に関する意見書/なにが改正されたのか/現実と2回目の少年法改正/訴えのみなもとにあるもの/「あすの会」の活動/コピー代や遺体の返還のこと/新しい制度が生かされるために
第5章 犯罪少年の家族は、どうしているの?
どんな生活を送るのだろうか/転居をくり返す母親/出院した少年を殴りつける父親/損害賠償と逃亡/11年前の事件/いのちの金額/謝罪の手紙と「再犯」/聡至君の母とAの母/犯罪はすべてのものを奪いつくす
第6章 被害にあった人は、ゆるしてくれるの?
保護観察の意味/保護司はボランティアだ/仕事をさがす方法/再犯への別れ道/ぼくらの社会はどんな社会か/少年はゆるされるのか/「ゆるす」ということ/「ゆるさなくてはいけない」のか?/更生なんかのぞんでいない
藤井誠二は、被害者側からものを考える人で、厳罰化にも死刑にも肯定的な人だと思う。僕とは正反対の考え方なので、よく言っていることを聞く必要がある。
本書を読んで、今まであまりにも被害者からの立場でものを考えられてこなかった経緯を知り、それが正されつつあることには、納得し、同意するところが多かった。
もう少し彼の著作を読んでみよう。
まだ、僕は死刑に同意する立場からは遠い。何をした人間でも、人間が人間を「こいつは殺してもいい」と決めつけることなどできないんじゃないか、と考えるからだ。もしも親兄弟を殺されて憎しみのあまり、その犯人を「命を奪ってもいい者」と決める場合、僕は2つのことを考える。1つは、死刑にしろ復讐にしろ、そうして人間の命を奪うことに対しても、なんらかの「仕返し」なり「ペナルティー」が発生するのが筋じゃないか。(仇討ち!復讐の連鎖って奴です)。もう1つは、最初に犯人が「親兄弟」を殺したときに、遺族が「犯人を殺せ」と抱く激情と同じものを犯人が抱いていたかもしれない、ということ。つまり、これは単なる順番の問題で、1人の人間を「被害者」「加害者」にわけることなどできないんじゃないか、ということ。
こういうものの考え方は、ミステリー読みとしては、ごく普通のことだと思う。
ミステリーには、殺されてもおかしくないような人物が山ほどあらわれる。
人を殺すには必ずそれなりの理由なり、激情なりがある。その人が「犯人」であれ「遺族」であれ、事情は一緒。だから、「犯人を殺してやりたい!」と思う気持と「あいつ(被害者)を殺してやりたい!」と思う気持に差はなく、逆転すらありうる。
もしも、被害者の心情から「命を奪ったものは命をもって償う」とでも言うのなら、イラク人を虐殺したアメリカにもそれをつきつけて、少なくとも同じ人数だけアメリカ人を殺してインフラを破壊しなければならない。戦争ならいいのだとでもいうなら、犯人は「これは戦争だったのです」と言えばいいのだ。戦争であれ、いかに憎い奴であれ、殺人犯であれ、人の命を奪ってはいけない、という考えが僕からは抜けない。本書では後半に、被害者遺族が加害者を「許さなくてはならない」のか?と問いかけている。もちろん、「しなければいけない」というわけではないだろう。でも、「許せれば一番いい」と僕は思うのだが、間違っているんだろうか。さもなくば、日本はアメリカや中国と永遠に敵対関係にいなければならない。
それと、「被害者」とひとくちに言うけど、本当の被害者はもう死んでいるとしたら、どこまでが被害者なのか。家族か?恋人か?同じ国の人間か?同じ人類か?同じ生とし生けるものか?簡単に「被害者」という言葉をつけてしまうことにも首をかしげざるをえない。
『百年の愚行』『100年前のパリ』1、2
2009年8月18日 読書
『百年の愚行』を読んだ。
20世紀に進んだ諸問題を象徴する写真を集めてある。
写真の内容は以下のとおりに分類されている。
「海・川・湖沼」「大気」「森・大地」「動物」「大量生産・大量消費」「核・テクノロジー」「戦争」「差別・迫害」「難民」「貧困」
重油にまみれた鳥とか、クローン羊とか、お馴染みの写真が並ぶ。
コラムの文章のタイトルは以下のとおり。
この100年で変わったこと
青い惑星の危機
動物たちの沈黙
エネルギー消費の時代
テクノロジーのふたつの顔
戦争の世紀
争いの傷跡
難民問題
貧困という名の病
これからの100年に向けて
また、エッセイもいくつか掲載されている。
「人権」の再定義/クロード・レヴィ=ストロース
湖の夢/鄭義
映像として残る人間の愚かさ/アッバス・キアロスタミ
文明の手前で立ち止まる/池澤夏樹
21世紀に我々の子孫が直面するであろう諸問題/フリーマン・ダイソン
この100年の人間が過去の人間に比べてとりたてて愚かなわけはないのだが、愚かさがはっきりとわかるほどに拡大し、大きな影響を与える時代であったということなのだろう。ただ、そういう時代を選びとったのも、そのときに生きていた人間自身なのである。
何が起こっても自業自得とされてしまうのだ。日々、自分が常に何かを選びながら生きていることを意識せねば。
さて、こんな文明批判的、ある種エコロジーっぽい本を読んだのは、100年前にちょっと思いをはせていたからだ。
今、僕は19世紀末の文学を選んで読んでいるが、その頃の風俗を知るために、『100年前のパリ』という本を読んだ。この本は2巻にわかれており、絵葉書的なパリのパノラマが俯瞰できる。写真につけられたキャプションも洒落ている。
そうした粋でのどかな100年前の世界が、この100年でどんなことになっているかというと、世紀末よりも世紀末的だったのである。
しかし、100年前のパリでは、ミニスカートなど無い時代なので、女性はいっさい足を見せていない。この頃のエロスは、今よりも遥かに強烈だったろうな、と感じた。
20世紀に進んだ諸問題を象徴する写真を集めてある。
写真の内容は以下のとおりに分類されている。
「海・川・湖沼」「大気」「森・大地」「動物」「大量生産・大量消費」「核・テクノロジー」「戦争」「差別・迫害」「難民」「貧困」
重油にまみれた鳥とか、クローン羊とか、お馴染みの写真が並ぶ。
コラムの文章のタイトルは以下のとおり。
この100年で変わったこと
青い惑星の危機
動物たちの沈黙
エネルギー消費の時代
テクノロジーのふたつの顔
戦争の世紀
争いの傷跡
難民問題
貧困という名の病
これからの100年に向けて
また、エッセイもいくつか掲載されている。
「人権」の再定義/クロード・レヴィ=ストロース
湖の夢/鄭義
映像として残る人間の愚かさ/アッバス・キアロスタミ
文明の手前で立ち止まる/池澤夏樹
21世紀に我々の子孫が直面するであろう諸問題/フリーマン・ダイソン
この100年の人間が過去の人間に比べてとりたてて愚かなわけはないのだが、愚かさがはっきりとわかるほどに拡大し、大きな影響を与える時代であったということなのだろう。ただ、そういう時代を選びとったのも、そのときに生きていた人間自身なのである。
何が起こっても自業自得とされてしまうのだ。日々、自分が常に何かを選びながら生きていることを意識せねば。
さて、こんな文明批判的、ある種エコロジーっぽい本を読んだのは、100年前にちょっと思いをはせていたからだ。
今、僕は19世紀末の文学を選んで読んでいるが、その頃の風俗を知るために、『100年前のパリ』という本を読んだ。この本は2巻にわかれており、絵葉書的なパリのパノラマが俯瞰できる。写真につけられたキャプションも洒落ている。
そうした粋でのどかな100年前の世界が、この100年でどんなことになっているかというと、世紀末よりも世紀末的だったのである。
しかし、100年前のパリでは、ミニスカートなど無い時代なので、女性はいっさい足を見せていない。この頃のエロスは、今よりも遥かに強烈だったろうな、と感じた。
「アンチ!」@アートスペース亜蛮人、『「政治思想」の現在』
2009年8月17日 読書
アートスペース亜蛮人で「アンチ!」展を見る。
参加アーチストは深木シゲミ、二月太輔、野中ひゆ、谷口晋吾、下山由貴、蛇目、キモグロ派代表穂刈有香、たなかけいこ、pikkoro、r.isotope、吉田嘉名、若松敦
フライヤーには「かわいい作品、こじゃれた作品は要らねぇ!イタイ、キモイ、エグイ、わらケル…激しいもので俺の心を熱く揺すぶってくれ!」とある。
まさしく、僕向けの展示内容のようだ。
さすがに面白い。若い人の作品が多いのだろうか。もっと激しくても、もっと気が狂っていてもいいように思った。
近いうちにもう1回見に行こうかと思っている。
ギャラリーのぞいたら、ちょうど野中ひゆちゃんに会えた。もう会期中だというのに、搬入中だ、と言っていた。こういうズレ方が僕は好きなのかもしれない。以前、僕の作品展で、日を追うにつれて展示物が減っていく、というのをしたことがある。搬出日がたいへんなのがいやで、徐々に持って帰ったのだ。お客さんのことを何も考えていなかった。自分のことだからそう思うのだろうが、そういうのが好きだ。
http://www.aband.jp
マクドナルドにDSを持って行って、ドラゴンクエスト「マクドナルドのたびびとたち」をやってみた。コマンドを選んでからそれが実行されるまでが遅くて、とうてい面白いしろものとは思えなかった。僕のパソコン並みに遅いのだ。どれだけ遅いかわかろうというものだ。また、僕はDSにいっぱいマスコットをぶらさげているので、重くてしかたがない。5回バトルするとお楽しみが待っているらしいが、9月3日までにあと4回行くかな〜?
ダウンロードして遊んだ体験版の立体ピクロスが意外と楽しめた。
マックフルーリのミント&オレオ食べる。チョコミントは僕の味なのだ。
明治学院大学国際学部付属研究所公開セミナーの記録『「政治思想」の現在』を読んだ。
2008年に行なわれたセミナーから。
以下、目次。
はじめに…原武史
「蟹工船」ブームをめぐって…雨宮処凛、高橋源一郎
1995年という転機/プレカリアート問題へ/現代版「蟹工船」/貧困ビジネスへの反撃/信頼ベースの人間関係へ/会場からの質問に答えて
雨宮処凛の「まず左行ったけどちんぷんかんぷんで、右行ったらわかりやすかった」という右翼に走った経緯は、今や古典芸能の範疇だな、と思った。
「民主主義」的管理主義と管理社会…鎌田慧
班競争と効率主義/トヨタ過労死事件/QC活動の実態/トヨタ生産方式とは何か/日本的な「和」の精神/企業と地域社会/派遣労働者問題について/会場からの質問に答えて
僕が今働いている職場でもさかんな5S運動などがおどろおどろしく表現されていて、膝をたたいて笑った。
昭和天皇をめぐって…福田和也、原武史
なぜいま昭和天皇か/昭和天皇の孤独/弟たちや母との関係/天皇をいかに書くか/「御文庫」をめぐるドラマ/現在の皇室について/会場からの質問に答えて
かつて、アングラ演劇を見に行ったら、よく昭和天皇が出て来た(まだ昭和の頃)。そのときは妄想の昭和天皇像だったわけだが、今では実像が明らかにありつつあるらしい。調べて読んでみよう。アングラ演劇の昭和天皇よりも面白いかもしれない。
戦後日本と右翼…鈴木邦男、原武史
三島事件の衝撃/右翼思想は継承されているか/マスコミと右翼/戦後右翼と天皇制/右も左も超えて/会場からの質問に答えて
三島と一緒に死んだ森田必勝が俄然気になって来た。
反貧困の政治思想…湯浅誠
椅子取りゲームをどう見るか/野宿の現実/「格差」「貧困」「ワーキングプア」/日本社会は悪くなりつづけている/ノーと言えない労働者/教訓をいかせるか/五重の排除/自分自身からの排除/<溜め>がない…/見えない<溜め>を見る/貧困問題は社会に返ってくる/二極化が進むなかで何ができるか/会場からの質問に答えて
ホームレス、フリーター、ワーキングプアに対して向けられる声とか、発する声を湯浅誠が再現しているのがまるで人形劇を見ているようで面白い。
たとえば、フリーターに対して「最近の若いやつは何考えてるかわからんね」「会社に縛られたくないらしいよ」「できもしない夢を追っかけとるね」
ホームレスに対して「どうもアパートに住みたくない、仕事をしたくない、社会生活したくないっていう人が増えてきたらしい」「えらい変わった人たちが出てきたもんだ」「野宿なんかしてないで就職活動しろよ」「死ぬ気になってやればなんでも見つかるだろう」「ああいう野宿しているような連中はアパート生活できない」「なんだあいつは。そんな勝手な理由で公園を占拠されちゃたまらん。追い出せ」
非正規労働者に対して「だって、自分たちには養わなきゃいけない家族がいる。だけど、あの人たちは親と同居しているフリーターであり、夫が働いてくれているパート労働者であり、そういう人はまあ大丈夫。仕事がなくなったって生活できなくなるわけじゃないんだから」「自分たちを守るためにはしようがない、あいつらを切ってもしようがない」
正規労働者に対して「正社員だの公務員だのが既得権益の上にあぐらをかいているからじゃないか」「あいつらがもらいすぎているから、いつまでたってもワーキングプア問題が解消できないんじゃないか」
ネットカフェ難民に対して「なんて覇気がないんだ」「向上心を持て」「ガッツを捨てるな」「だから今の若いやつはだめなんだ」
当のネットカフェ難民は「1食500円かけて弁当食いたい」「体を伸ばして布団で寝たい」「まあいいんだよ、自分はこれで。こんなもんなんだよ」
貧困層に対して「この人たちにはきっと何か理由があるにちがいない」「ほらみろ、こいつはお金がないと言いながら、携帯に1万円を使っていた」「ほらみろ、この前生活がたいへんだと言いながら、パチンコ屋にいたのを見た」
つい言いがちな言葉の数々だが、貧困の問題について考えれば、これらの言葉がいかにわかっていない者の言い草であるのかが身にしみる。
現代若者のナショナリズム…北田暁大
ナショナリズムと動機付け問題/ナショナリズムは噴出しているのか/「上」のナショナリズムと信頼/「ぬるいリベラリスト」のポテンシャル?
最近になってナショナリズムが噴出したとか、ネット右翼的言動とか、愛国心の高まりとか、冷静に考えてみれば、ワイドショー的、ネット掲示板的雰囲気と、実態には違いがあるとわかるんだ。
アジア主義、その思想と系譜…中島岳志
なぜ、ボースか/ふたりの革命家の涙/竹内好とアジア主義/アジア主義の二面性/岡倉天心とガンディー−思想としてのアジア主義/大川周明という問題/ふたつのナショナリズム/初発のナショナリズム/藩閥政治の打破/脱亜化するアジア主義/超国家主義の変質/戦後のアジア主義/会場からの質問に答えて
保守主義、アジア主義をわかりやすくたどる。カレーを中村屋に伝授したインド人ボースはテロリストだったのか!これは近いうちに『中村屋のボース』も読んでみなくては。
参加アーチストは深木シゲミ、二月太輔、野中ひゆ、谷口晋吾、下山由貴、蛇目、キモグロ派代表穂刈有香、たなかけいこ、pikkoro、r.isotope、吉田嘉名、若松敦
フライヤーには「かわいい作品、こじゃれた作品は要らねぇ!イタイ、キモイ、エグイ、わらケル…激しいもので俺の心を熱く揺すぶってくれ!」とある。
まさしく、僕向けの展示内容のようだ。
さすがに面白い。若い人の作品が多いのだろうか。もっと激しくても、もっと気が狂っていてもいいように思った。
近いうちにもう1回見に行こうかと思っている。
ギャラリーのぞいたら、ちょうど野中ひゆちゃんに会えた。もう会期中だというのに、搬入中だ、と言っていた。こういうズレ方が僕は好きなのかもしれない。以前、僕の作品展で、日を追うにつれて展示物が減っていく、というのをしたことがある。搬出日がたいへんなのがいやで、徐々に持って帰ったのだ。お客さんのことを何も考えていなかった。自分のことだからそう思うのだろうが、そういうのが好きだ。
http://www.aband.jp
マクドナルドにDSを持って行って、ドラゴンクエスト「マクドナルドのたびびとたち」をやってみた。コマンドを選んでからそれが実行されるまでが遅くて、とうてい面白いしろものとは思えなかった。僕のパソコン並みに遅いのだ。どれだけ遅いかわかろうというものだ。また、僕はDSにいっぱいマスコットをぶらさげているので、重くてしかたがない。5回バトルするとお楽しみが待っているらしいが、9月3日までにあと4回行くかな〜?
ダウンロードして遊んだ体験版の立体ピクロスが意外と楽しめた。
マックフルーリのミント&オレオ食べる。チョコミントは僕の味なのだ。
明治学院大学国際学部付属研究所公開セミナーの記録『「政治思想」の現在』を読んだ。
2008年に行なわれたセミナーから。
以下、目次。
はじめに…原武史
「蟹工船」ブームをめぐって…雨宮処凛、高橋源一郎
1995年という転機/プレカリアート問題へ/現代版「蟹工船」/貧困ビジネスへの反撃/信頼ベースの人間関係へ/会場からの質問に答えて
雨宮処凛の「まず左行ったけどちんぷんかんぷんで、右行ったらわかりやすかった」という右翼に走った経緯は、今や古典芸能の範疇だな、と思った。
「民主主義」的管理主義と管理社会…鎌田慧
班競争と効率主義/トヨタ過労死事件/QC活動の実態/トヨタ生産方式とは何か/日本的な「和」の精神/企業と地域社会/派遣労働者問題について/会場からの質問に答えて
僕が今働いている職場でもさかんな5S運動などがおどろおどろしく表現されていて、膝をたたいて笑った。
昭和天皇をめぐって…福田和也、原武史
なぜいま昭和天皇か/昭和天皇の孤独/弟たちや母との関係/天皇をいかに書くか/「御文庫」をめぐるドラマ/現在の皇室について/会場からの質問に答えて
かつて、アングラ演劇を見に行ったら、よく昭和天皇が出て来た(まだ昭和の頃)。そのときは妄想の昭和天皇像だったわけだが、今では実像が明らかにありつつあるらしい。調べて読んでみよう。アングラ演劇の昭和天皇よりも面白いかもしれない。
戦後日本と右翼…鈴木邦男、原武史
三島事件の衝撃/右翼思想は継承されているか/マスコミと右翼/戦後右翼と天皇制/右も左も超えて/会場からの質問に答えて
三島と一緒に死んだ森田必勝が俄然気になって来た。
反貧困の政治思想…湯浅誠
椅子取りゲームをどう見るか/野宿の現実/「格差」「貧困」「ワーキングプア」/日本社会は悪くなりつづけている/ノーと言えない労働者/教訓をいかせるか/五重の排除/自分自身からの排除/<溜め>がない…/見えない<溜め>を見る/貧困問題は社会に返ってくる/二極化が進むなかで何ができるか/会場からの質問に答えて
ホームレス、フリーター、ワーキングプアに対して向けられる声とか、発する声を湯浅誠が再現しているのがまるで人形劇を見ているようで面白い。
たとえば、フリーターに対して「最近の若いやつは何考えてるかわからんね」「会社に縛られたくないらしいよ」「できもしない夢を追っかけとるね」
ホームレスに対して「どうもアパートに住みたくない、仕事をしたくない、社会生活したくないっていう人が増えてきたらしい」「えらい変わった人たちが出てきたもんだ」「野宿なんかしてないで就職活動しろよ」「死ぬ気になってやればなんでも見つかるだろう」「ああいう野宿しているような連中はアパート生活できない」「なんだあいつは。そんな勝手な理由で公園を占拠されちゃたまらん。追い出せ」
非正規労働者に対して「だって、自分たちには養わなきゃいけない家族がいる。だけど、あの人たちは親と同居しているフリーターであり、夫が働いてくれているパート労働者であり、そういう人はまあ大丈夫。仕事がなくなったって生活できなくなるわけじゃないんだから」「自分たちを守るためにはしようがない、あいつらを切ってもしようがない」
正規労働者に対して「正社員だの公務員だのが既得権益の上にあぐらをかいているからじゃないか」「あいつらがもらいすぎているから、いつまでたってもワーキングプア問題が解消できないんじゃないか」
ネットカフェ難民に対して「なんて覇気がないんだ」「向上心を持て」「ガッツを捨てるな」「だから今の若いやつはだめなんだ」
当のネットカフェ難民は「1食500円かけて弁当食いたい」「体を伸ばして布団で寝たい」「まあいいんだよ、自分はこれで。こんなもんなんだよ」
貧困層に対して「この人たちにはきっと何か理由があるにちがいない」「ほらみろ、こいつはお金がないと言いながら、携帯に1万円を使っていた」「ほらみろ、この前生活がたいへんだと言いながら、パチンコ屋にいたのを見た」
つい言いがちな言葉の数々だが、貧困の問題について考えれば、これらの言葉がいかにわかっていない者の言い草であるのかが身にしみる。
現代若者のナショナリズム…北田暁大
ナショナリズムと動機付け問題/ナショナリズムは噴出しているのか/「上」のナショナリズムと信頼/「ぬるいリベラリスト」のポテンシャル?
最近になってナショナリズムが噴出したとか、ネット右翼的言動とか、愛国心の高まりとか、冷静に考えてみれば、ワイドショー的、ネット掲示板的雰囲気と、実態には違いがあるとわかるんだ。
アジア主義、その思想と系譜…中島岳志
なぜ、ボースか/ふたりの革命家の涙/竹内好とアジア主義/アジア主義の二面性/岡倉天心とガンディー−思想としてのアジア主義/大川周明という問題/ふたつのナショナリズム/初発のナショナリズム/藩閥政治の打破/脱亜化するアジア主義/超国家主義の変質/戦後のアジア主義/会場からの質問に答えて
保守主義、アジア主義をわかりやすくたどる。カレーを中村屋に伝授したインド人ボースはテロリストだったのか!これは近いうちに『中村屋のボース』も読んでみなくては。
『誰も知らない世界と日本のまちがい 自由と国家と資本主義』
2009年8月11日 読書
松岡正剛の『誰も知らない世界と日本のまちがい 自由と国家と資本主義』を読んだ。
『17歳のための世界と日本の見方』のつづきで近代、現代を扱っている。『17歳〜』の方は、その元になった『帝塚山講義』(松岡正剛セカイ読本・低速・)は読んだことがあるが、この『帝塚山講義』を加筆しているらしい。こっちもいずれ読もうっと。
で、『世界と日本のまちがい』の方。以下、目次。
第1講 ネーション・ステートの謎
「異質」に歴史を見る/世界の歴史はタテ・ヨコ・ナナメ/紅茶だって世界を動かす/どこに行っても資本主義/情報ネットワークと自由/資本主義のきびしい掟/自由なサービスはどこまで可能か/「みんな」が受けられるサービスとは/「みんなの国家」が引き受ける/ネーション・ステート−国民国家の意味/近代をまたぐ欲望/欲望と機械がくっついた社会
第2講 エリザベス女王とリヴァイアサン
エリザベスは信長のお姉さん/近代のカギを握る「イギリスの謎」/フランスとの確執/英国国教会の誕生/キーワードは「エミグレ」/移住という思想/一神教と「神の戦争」/カトリックvsプロテスタント/クロムウェルのピューリタン革命/近代国家論の出発、『リヴァイアサン』
第3講 将軍の国と華夷秩序
そのとき日本はどう「世界」と接したか/徳川社会と「負のはたらき」/大帝国「明」の興亡/日本のダブル・スタンダード−和・漢/徳川日本、中国離れのシナリオ/日本乞師と呼ばれた男/開国と通商という宿命/黒船が日本に来るまで−ネーション・ステートのめざめ
第4講 列強の誕生とアジアの危機
「モーラ」の世界から見えるもの/フランスの立て直し−英雄ナポレオン1/欧州各国の自立化を促す−英雄ナポレオン2/ウィーン体制がもたらしたもの−英雄ナポレオン3/ドイツ人が考えたこと/「ロマン」が国をつくる/列強の近代へ/アヘン戦争が世界を変えた/ひどかった南京条約
第5講 開国の背景に何があったのか
強い国家・広い国家ーイギリスとフランス/武力帝国の誕生−ドイツとロシア/自国を強化するフロンティア魂−アメリカの拡張/ペリー来航−とうとう日本もフロンティア/イタリアにも「維新」があった/日朝の深い関係/古代朝鮮の歴史/決定的な敗戦、「白村江の戦い」/充実の李氏朝鮮時代/朝鮮半島への侵略
第6講 明治日本の戦争と文化
日本画と「二つのJ」/東北アジアをめぐる争い/日本が朝鮮に開国を迫った/日清戦争への道のり/アジアか、「脱亜入欧」か/三国干渉による横やり/閔妃殺害のシナリオ/世界を分割する野望−帝国主義国家の成立/アフリカ分割の悲劇/朝鮮を舞台にした日露戦争/列強入りした日本が得たもの−韓国併合
第7講 社会も国家も進化しつづける?
『共産党宣言』の爆発/アタマの中の弁証法・セカイを丸ごと唯物史観/個人から社会へ−経済思想の流れ/理想社会をつくる実験/マルクス経済学のチェック・ポイント/ダーウィン『種の起源』の衝撃/社会は進化しているか?/未来を目指して一直線−スペンサーの社会進化論/変化を受け入れる視点−仏教思想の影響
第8講 カフカとフロイトの部屋
語りえぬ二十世紀を語る/イギリスの3C、ドイツの3B/バルカンの火薬庫に火がついた−第一次世界大戦/フロイトが見つけた「内なる闇」/世界と自分を観察する−現象学の登場/人間って何だろう−実存主義/自と他を結ぶ、ヤスパースの「了解」/説明できない「世界とのかかわり」/カフカの文学/「中心」をもたないという立場/カフカとフロイトの部屋にいた「アウトサイダー」
第9講 二つの世界戦争のあいだ
中東って何だ/イスラム的「エミグレ」のパワー/アラビアのロレンスの真相/中東問題の火種/立ち上がるガンディー−VSイギリス/したたかな革命家ホー・チ・ミン−VSフランス/ワイマール体制とナチスの台頭/世界恐慌の余波−第二次世界大戦突入/民主主義は本当に勝ったのか/アラブとバース主義−第一次・第二次中東戦争
第10講 資本と大衆の時代
数が質になる、大衆のパワー/冷戦時代のポリティクス−代理社会の代理戦争/新植民地主義とは何か/ゲーム理論に溺れるアメリカ/パクス・アメリカーナと新自由主義/1970年代の世界経済の大転換/合理的な自由競争のゆくえ/いくつもの資本主義/資本主義社会の病気と症状/世界の均質化を「編集」でのりこえる
第11講 日本の苗代をとりもどしたい
日本人の「ものの見方」/苗代という方法/「失われた十年」の意味/証券化の嵐が日本にも吹き荒れる/「リスク」が商品になる時代/日本人の「道理」もある/驚くべきレベッカの資本主義/世界のあちこちに「苗」をうえる勇気
第1講で、前作の『17歳〜』について、松岡正剛はこう書いている。
「いろいろの人物や話題をとりあげましたが、そのなかで何を言いたかったかというと、世界と日本を同時に見るには『異質』を排除して歴史を見ようとしてはダメだということを強調したつもりです」
さらに、本書について、こう言っている。
「私が言いたいことは、一言でいえば『世界はもともとけっして同質なんかじゃない』ということです」
そして、本書の巻末「おわりに−苗代の知恵」で、こう書いている。
「本書では『苗代』を例にして、グローバリズムの導入をいったん幼若な苗にして、それから本番で植え替えるという方法があるのではないかということを最終章の提案にしてみました。直撒き、ちょっと待ったという提案です」
さあ、これで結論がわかったから、一件落着か、と思うと、そうではない。本書の面白さは、大きく広げに広げまくった大風呂敷にあるのだ。目次だけを見ていてもそれはじゅうぶんうかがえる。キーワードは「苗代」よりも「風呂敷」なんじゃないかと思えるが、それは松岡正剛のどの著作についても言えることで、ことさら本書だけの特徴というわけではない。
世界と日本、というタイトルからして大風呂敷だが、近現代をテーマにすると、その内容のほとんどは「世界と日本のまちがい」と言うより「イギリスのまちがい」になるが、そこは仕方あるまい。
ただ、僕はこれを初版で読んだのだが、ところどころにひっかかるところがあった。
たとえば、こんな文章。
「ここにおいてヒトラーは、全世界にローマ帝国や神聖ローマ帝国やナポレオン帝国に代わる『第三帝国』を築こうとする決意をかためます。『第三帝国』と名付けたのは、ローマ帝国と神聖ローマ帝国につぐ三番目の帝国という意味です」(第9講より)
なにげなく読みとばしかけたが、ヒトラーの第三帝国は、神聖ローマ帝国とビスマルク帝国に次ぐ来るべき第3の帝国、ということなんじゃなかったか?これはひょっとして、誤字脱字?
ここでは「あれっ」と思って他の文献を調べてみることができたが、他にも読みとばしがあって、うのみにしてはいけない文章があるのかもしれない。と言っても、一読して脳みそにしっかり知識として残るほど出来のいい頭はしていないわけだが。
『17歳のための世界と日本の見方』のつづきで近代、現代を扱っている。『17歳〜』の方は、その元になった『帝塚山講義』(松岡正剛セカイ読本・低速・)は読んだことがあるが、この『帝塚山講義』を加筆しているらしい。こっちもいずれ読もうっと。
で、『世界と日本のまちがい』の方。以下、目次。
第1講 ネーション・ステートの謎
「異質」に歴史を見る/世界の歴史はタテ・ヨコ・ナナメ/紅茶だって世界を動かす/どこに行っても資本主義/情報ネットワークと自由/資本主義のきびしい掟/自由なサービスはどこまで可能か/「みんな」が受けられるサービスとは/「みんなの国家」が引き受ける/ネーション・ステート−国民国家の意味/近代をまたぐ欲望/欲望と機械がくっついた社会
第2講 エリザベス女王とリヴァイアサン
エリザベスは信長のお姉さん/近代のカギを握る「イギリスの謎」/フランスとの確執/英国国教会の誕生/キーワードは「エミグレ」/移住という思想/一神教と「神の戦争」/カトリックvsプロテスタント/クロムウェルのピューリタン革命/近代国家論の出発、『リヴァイアサン』
第3講 将軍の国と華夷秩序
そのとき日本はどう「世界」と接したか/徳川社会と「負のはたらき」/大帝国「明」の興亡/日本のダブル・スタンダード−和・漢/徳川日本、中国離れのシナリオ/日本乞師と呼ばれた男/開国と通商という宿命/黒船が日本に来るまで−ネーション・ステートのめざめ
第4講 列強の誕生とアジアの危機
「モーラ」の世界から見えるもの/フランスの立て直し−英雄ナポレオン1/欧州各国の自立化を促す−英雄ナポレオン2/ウィーン体制がもたらしたもの−英雄ナポレオン3/ドイツ人が考えたこと/「ロマン」が国をつくる/列強の近代へ/アヘン戦争が世界を変えた/ひどかった南京条約
第5講 開国の背景に何があったのか
強い国家・広い国家ーイギリスとフランス/武力帝国の誕生−ドイツとロシア/自国を強化するフロンティア魂−アメリカの拡張/ペリー来航−とうとう日本もフロンティア/イタリアにも「維新」があった/日朝の深い関係/古代朝鮮の歴史/決定的な敗戦、「白村江の戦い」/充実の李氏朝鮮時代/朝鮮半島への侵略
第6講 明治日本の戦争と文化
日本画と「二つのJ」/東北アジアをめぐる争い/日本が朝鮮に開国を迫った/日清戦争への道のり/アジアか、「脱亜入欧」か/三国干渉による横やり/閔妃殺害のシナリオ/世界を分割する野望−帝国主義国家の成立/アフリカ分割の悲劇/朝鮮を舞台にした日露戦争/列強入りした日本が得たもの−韓国併合
第7講 社会も国家も進化しつづける?
『共産党宣言』の爆発/アタマの中の弁証法・セカイを丸ごと唯物史観/個人から社会へ−経済思想の流れ/理想社会をつくる実験/マルクス経済学のチェック・ポイント/ダーウィン『種の起源』の衝撃/社会は進化しているか?/未来を目指して一直線−スペンサーの社会進化論/変化を受け入れる視点−仏教思想の影響
第8講 カフカとフロイトの部屋
語りえぬ二十世紀を語る/イギリスの3C、ドイツの3B/バルカンの火薬庫に火がついた−第一次世界大戦/フロイトが見つけた「内なる闇」/世界と自分を観察する−現象学の登場/人間って何だろう−実存主義/自と他を結ぶ、ヤスパースの「了解」/説明できない「世界とのかかわり」/カフカの文学/「中心」をもたないという立場/カフカとフロイトの部屋にいた「アウトサイダー」
第9講 二つの世界戦争のあいだ
中東って何だ/イスラム的「エミグレ」のパワー/アラビアのロレンスの真相/中東問題の火種/立ち上がるガンディー−VSイギリス/したたかな革命家ホー・チ・ミン−VSフランス/ワイマール体制とナチスの台頭/世界恐慌の余波−第二次世界大戦突入/民主主義は本当に勝ったのか/アラブとバース主義−第一次・第二次中東戦争
第10講 資本と大衆の時代
数が質になる、大衆のパワー/冷戦時代のポリティクス−代理社会の代理戦争/新植民地主義とは何か/ゲーム理論に溺れるアメリカ/パクス・アメリカーナと新自由主義/1970年代の世界経済の大転換/合理的な自由競争のゆくえ/いくつもの資本主義/資本主義社会の病気と症状/世界の均質化を「編集」でのりこえる
第11講 日本の苗代をとりもどしたい
日本人の「ものの見方」/苗代という方法/「失われた十年」の意味/証券化の嵐が日本にも吹き荒れる/「リスク」が商品になる時代/日本人の「道理」もある/驚くべきレベッカの資本主義/世界のあちこちに「苗」をうえる勇気
第1講で、前作の『17歳〜』について、松岡正剛はこう書いている。
「いろいろの人物や話題をとりあげましたが、そのなかで何を言いたかったかというと、世界と日本を同時に見るには『異質』を排除して歴史を見ようとしてはダメだということを強調したつもりです」
さらに、本書について、こう言っている。
「私が言いたいことは、一言でいえば『世界はもともとけっして同質なんかじゃない』ということです」
そして、本書の巻末「おわりに−苗代の知恵」で、こう書いている。
「本書では『苗代』を例にして、グローバリズムの導入をいったん幼若な苗にして、それから本番で植え替えるという方法があるのではないかということを最終章の提案にしてみました。直撒き、ちょっと待ったという提案です」
さあ、これで結論がわかったから、一件落着か、と思うと、そうではない。本書の面白さは、大きく広げに広げまくった大風呂敷にあるのだ。目次だけを見ていてもそれはじゅうぶんうかがえる。キーワードは「苗代」よりも「風呂敷」なんじゃないかと思えるが、それは松岡正剛のどの著作についても言えることで、ことさら本書だけの特徴というわけではない。
世界と日本、というタイトルからして大風呂敷だが、近現代をテーマにすると、その内容のほとんどは「世界と日本のまちがい」と言うより「イギリスのまちがい」になるが、そこは仕方あるまい。
ただ、僕はこれを初版で読んだのだが、ところどころにひっかかるところがあった。
たとえば、こんな文章。
「ここにおいてヒトラーは、全世界にローマ帝国や神聖ローマ帝国やナポレオン帝国に代わる『第三帝国』を築こうとする決意をかためます。『第三帝国』と名付けたのは、ローマ帝国と神聖ローマ帝国につぐ三番目の帝国という意味です」(第9講より)
なにげなく読みとばしかけたが、ヒトラーの第三帝国は、神聖ローマ帝国とビスマルク帝国に次ぐ来るべき第3の帝国、ということなんじゃなかったか?これはひょっとして、誤字脱字?
ここでは「あれっ」と思って他の文献を調べてみることができたが、他にも読みとばしがあって、うのみにしてはいけない文章があるのかもしれない。と言っても、一読して脳みそにしっかり知識として残るほど出来のいい頭はしていないわけだが。
「マドモアゼル・ボードレール」の異名をとるデカダンの女王、ラシルドの『ヴィーナス氏』を読んだ。
男女のちょっと激しいラブストーリー。女性が男になり、ひよわな男(「オカマ」と揶揄される)を飼いならしてスポイルしまくり、男女逆転の愛慾絵巻。変装して男になりすまして愛人に会いにいく女主人公ラウール。あげくのはてには、男としての基本的な作法を身につけていなかったがゆえに、男主人公ジャックは死なないですむ決闘で死んでしまう。ラウールは悲しんで、ジャックに似せた機械人形を作って、愛慾をぶつける。現代だとわりとあるような話だが、19世紀にはきわめて背徳的な書物だったろう。
こうした愛の形を人に説明する際の文章から引用してみよう。
「ラウールの蒼白い顔が赤く燃え上がった。『わたしが男になって恋している相手は、女でなく男です』」
「『彼女は、男になって、お、お、男に恋をしている!』と、彼(レトルブ男爵)は叫んだ。『ああ、神よ、われを憐れみたまえ。頭がばらばらになりそうだ』」
「『そんな男が世の中にいるだろうか?』あべこべが唯一の法であるような未知の世界に」引き入れられ、茫然自失した男爵は呟いた。
『いるのです。それは、両性具有でもなければ不能者でもなく、21歳の美しい雄です。女の本能をもった魂が、入る場所をまちがえたのです』」
ラウールはジャック(呼び名は「ジャジャ」)をとじこめて独占するために、麻薬を与えて、ぼーっと何もできないような心身においやる。
そして、こんな激しい言葉を吐く。
レトルブ「もし、時には麻薬だけで充分でなかったら?」
ラウール「殺すわ」
この男女逆転の仲に、二人の人物が関わってくる。
1人はジャックの姉、マリー。マリーは元娼婦で、ジャックに執心するラウールにダニのようにとりついて、金をせびりとろうとする。(煽りたてた卑劣さの悪魔)
もう1人は信心深いラウールの伯母、エリザベート。二人の仲を自然に反した欲望で、幸福にはなれないと糾弾する。(天使エリザベート)
ラウールはおかたい伯母に対して、こう言い放つ。
「伯母さま、幸福というものは、常軌を逸していればいるほど本物なのよ」
物語は今でいえばまるで昼の(常軌を逸した)メロドラマに似ており、きわめて女性受けするストーリーだな、と感じた。この本の前に読んだ『眠る男』がほとんど何も起こらない小説(作者側から言えば、手をかえ品をかえて何も起こさせない小説)だったのに対して、これは激情にかられていろいろしてしまう小説だったのが対照的で、ジェットコースターノベルかと思うくらいにすらすらと読めた。2世紀前のポルノグラフィーとして劣情を刺激する面もあったのかもしれない。
男女のちょっと激しいラブストーリー。女性が男になり、ひよわな男(「オカマ」と揶揄される)を飼いならしてスポイルしまくり、男女逆転の愛慾絵巻。変装して男になりすまして愛人に会いにいく女主人公ラウール。あげくのはてには、男としての基本的な作法を身につけていなかったがゆえに、男主人公ジャックは死なないですむ決闘で死んでしまう。ラウールは悲しんで、ジャックに似せた機械人形を作って、愛慾をぶつける。現代だとわりとあるような話だが、19世紀にはきわめて背徳的な書物だったろう。
こうした愛の形を人に説明する際の文章から引用してみよう。
「ラウールの蒼白い顔が赤く燃え上がった。『わたしが男になって恋している相手は、女でなく男です』」
「『彼女は、男になって、お、お、男に恋をしている!』と、彼(レトルブ男爵)は叫んだ。『ああ、神よ、われを憐れみたまえ。頭がばらばらになりそうだ』」
「『そんな男が世の中にいるだろうか?』あべこべが唯一の法であるような未知の世界に」引き入れられ、茫然自失した男爵は呟いた。
『いるのです。それは、両性具有でもなければ不能者でもなく、21歳の美しい雄です。女の本能をもった魂が、入る場所をまちがえたのです』」
ラウールはジャック(呼び名は「ジャジャ」)をとじこめて独占するために、麻薬を与えて、ぼーっと何もできないような心身においやる。
そして、こんな激しい言葉を吐く。
レトルブ「もし、時には麻薬だけで充分でなかったら?」
ラウール「殺すわ」
この男女逆転の仲に、二人の人物が関わってくる。
1人はジャックの姉、マリー。マリーは元娼婦で、ジャックに執心するラウールにダニのようにとりついて、金をせびりとろうとする。(煽りたてた卑劣さの悪魔)
もう1人は信心深いラウールの伯母、エリザベート。二人の仲を自然に反した欲望で、幸福にはなれないと糾弾する。(天使エリザベート)
ラウールはおかたい伯母に対して、こう言い放つ。
「伯母さま、幸福というものは、常軌を逸していればいるほど本物なのよ」
物語は今でいえばまるで昼の(常軌を逸した)メロドラマに似ており、きわめて女性受けするストーリーだな、と感じた。この本の前に読んだ『眠る男』がほとんど何も起こらない小説(作者側から言えば、手をかえ品をかえて何も起こさせない小説)だったのに対して、これは激情にかられていろいろしてしまう小説だったのが対照的で、ジェットコースターノベルかと思うくらいにすらすらと読めた。2世紀前のポルノグラフィーとして劣情を刺激する面もあったのかもしれない。
ジョルジュ・ペレックの『眠る男』を読んだ。
物語の主人公は「おまえ」
おおっ『やぶにらみの時計』か!
「おまえ」がしないことを列挙する文章が並ぶ。
「おまえ」は睡眠をとっているのではなく、ひきこもりにも似た、精神が眠った状態なのだ。無気力で無関心。
本書より引用。
「おまえにはやり続ける気がないのだ、自分を護る気も、逆に攻撃をする気も」
「夜と部屋だけがおまえを保護してくれる」
「おまえは、自分の忘れ去られている状態に、幸福らしきものをよく覚えるのだ。口を利く必要もなく、意志を持つ必要もない」
「おまえはまだほとんど生の経験を積んでいない、にもかかわらず、すべてのことがすでに言われ、すでに終ってしまった。おまえはたった25歳にすぎないのに、おまえの道はすっかり引かれている。役割が用意され、レッテルが整えられている」
「どうして一番高い丘の上によじ登ることがあろうか。すぐにまた降りねばならぬというのなら?それにいったん降りたとき、どうやって上に登ったかを語ることで人生を費やしてしまわぬにはどうしたらよいのか?どうして生きているふりをすることがあろうか?」
「午後のあいだじゅう、あるときは朝起きてからずっと、あるときは明け方まで、時間を潰すためでさえなく、もうそのためでさえもなく、ゲームを続けるようになる」
「おまえは忍耐強い、だが待っているわけではないのだ、おまえは自由だ、だが選ぶということもないのだ。おまえは何でも自由にすることができる、だがおまえを動かすものは何ひとつないのだ。おまえは何ひとつ求めない、何ひとつ要求しない、何ひとつ押しつけない。耳で聞きはするけれども、絶対に耳を傾けたりはしない、目で見るけれども、絶対に目を向けたりはしない」
読んでいるときの印象は、学生時代に読んだ『魔の山』に似ていた。
読み進むにつれて、本から呼ばれる「おまえ」が、本当に、僕のことであるかのように思えてきた。
僕がめざめていない男だということについては、ペレックと同意見だ。
物語の主人公は「おまえ」
おおっ『やぶにらみの時計』か!
「おまえ」がしないことを列挙する文章が並ぶ。
「おまえ」は睡眠をとっているのではなく、ひきこもりにも似た、精神が眠った状態なのだ。無気力で無関心。
本書より引用。
「おまえにはやり続ける気がないのだ、自分を護る気も、逆に攻撃をする気も」
「夜と部屋だけがおまえを保護してくれる」
「おまえは、自分の忘れ去られている状態に、幸福らしきものをよく覚えるのだ。口を利く必要もなく、意志を持つ必要もない」
「おまえはまだほとんど生の経験を積んでいない、にもかかわらず、すべてのことがすでに言われ、すでに終ってしまった。おまえはたった25歳にすぎないのに、おまえの道はすっかり引かれている。役割が用意され、レッテルが整えられている」
「どうして一番高い丘の上によじ登ることがあろうか。すぐにまた降りねばならぬというのなら?それにいったん降りたとき、どうやって上に登ったかを語ることで人生を費やしてしまわぬにはどうしたらよいのか?どうして生きているふりをすることがあろうか?」
「午後のあいだじゅう、あるときは朝起きてからずっと、あるときは明け方まで、時間を潰すためでさえなく、もうそのためでさえもなく、ゲームを続けるようになる」
「おまえは忍耐強い、だが待っているわけではないのだ、おまえは自由だ、だが選ぶということもないのだ。おまえは何でも自由にすることができる、だがおまえを動かすものは何ひとつないのだ。おまえは何ひとつ求めない、何ひとつ要求しない、何ひとつ押しつけない。耳で聞きはするけれども、絶対に耳を傾けたりはしない、目で見るけれども、絶対に目を向けたりはしない」
読んでいるときの印象は、学生時代に読んだ『魔の山』に似ていた。
読み進むにつれて、本から呼ばれる「おまえ」が、本当に、僕のことであるかのように思えてきた。
僕がめざめていない男だということについては、ペレックと同意見だ。
JK21デイリーライブ「モー娘。夏歌の巻」@アトリエACT、『ゆらめく炎』
2009年7月31日 読書
JK21のデイリーライブ。
1.ハッピー・グラデュエーション
最近見た夢の話。
須田:日常そのもの
みさき:大きな猿のぬいぐるみ奪われる
真琴:日本人形に囲まれる
みゆき:大学受験失敗
田中:結婚式
月脇:サンタが操縦するタイムマシンに乗って時空をさまよう
椿:宇宙の高さのパフェ食べる
脇坂:テレビから貞子が出てくる
桃菜:テトリス(発熱時に必ずみる、とか)
城島:遅刻
トーク終わりで、モーニング娘。の夏歌特集
2.ひょっこりひょうたん島(月脇、番長)うしろの真琴の振りは完璧!
3.チュ夏パーティー(真琴、桃菜、脇坂)
4.ザ☆ピ〜ス(椿、田中)
伝言ゲーム。背中に書いた文字を伝えていく。
城島が「城島ゆかり」とお題を出すが、須田から月脇への伝言で「ピカチュウ」と変換され、最終的に「ピカチュウ」!月脇以降のメンバーは罰ゲームで空気椅子。
5.エニシングゴーズ
6.フットマン
ライブ終了後は握手会。
あいかわらず、何をしゃべっていいのかわからない。悪意や敵意がないことだけでもわかってもらいたいのだが。
桃菜がペット的なたまらない可愛さを持っている、とは以前から思っていたが、今回、月脇の魅力の種類がなんとなくわかってきた。
月脇は、孫の可愛さなのだ。おじいちゃんが孫を見て、「目の中に入れてもいたくない!」と無条件に可愛く思えてしまうのに似た不思議な魅力を持っている。
本人がこの日記を読むことはまず無いだろうが、こんな意見はうれしいのか?微妙か?絶賛して褒めているつもりなんだけどなあ。
読んだ本は、ピエール・ドリュ・ラ・ロシェルの『ゆらめく炎』
昨日読んだジャック・リゴーをモデルにしたと思しき小説。
今にも自殺しそうな麻薬中毒の男が、友人たちに会って会話したりするが、結局自殺をとめることはできない、という話。
そう難しい小説でもないのに、この本には少々てこずった。
なかなか文意が頭のなかに入っていかないのだ。
そう言えば、と『自殺総代理店』を引っぱりだしてみると、こんな文章があった。
私に起こったあらゆる事柄のなかで、私が全く関与しなかったことを一番よく思い出すのはなぜだろうか。
私は、自分が存在していないと感じる瞬間にだけ生を感じる。
私が生き続けていくためには、自分が存在していないことを信じていくしかない。
(「すべての鏡が私の名を映している」より)
リゴーが他人事の世界でふわふわ生きていたように、なんだか、作中の主人公アランの心情や行動もフワフワした感じだったのだ。
30才で自殺したリゴーへのあてこすりともとれる描写もある。
「その青春は終わろうとしていた。というのも、彼は30才になったばかりだが、30才と言えば、美貌しか持ち合わせていない青年にとっては老けた年だったから」
手厳しいね!
さて、『ゆらめく炎』からいくつか引用してみると。
(金は)際限なく彼の指の間を通り過ぎるが、決してそこにとどまらずに流れ去る束の間の幻だった。
麻薬が再度の転落を正当化するのに吹き込む詭弁とはこうしたものだ−おれはだめな奴だ、だからまた薬に手を出したってかまわないと。
彼はついに、麻薬中毒者たちの生活の真実の性格をはっきりと知った。よく整理された、閉じこもりがちな、気楽さを好む生活。カーテンを引いて、冒険や困難を避ける年金生活者たちの目立たぬ存在。共通の犠牲的精神によって結ばれ、純潔で気むずかしく、お喋り好きで、自分たちの信仰を悪く言われれば眉をひそめて顔をそむけるオールド・ミスたちの変哲もない生活。
個人の意志は過去の時代の神話なのだ。文明に疲れた人種はもはや意志を信ずることはできない。恐らく、彼らは強制の世界の逃げ込むだろう。
「ぼくは女にはほとんど力がない。しかし、女を通してはじめて、物に対して力を持つことができるんだ。ぼくにとって、女とはいつも金のことだった」
「たとえば、ここにいるどの女もぼくは欲しいという気になれない。彼女たちがこわい、ぼくにはこわい。女の前に出ると、戦いの最前線にいるのと同じようにこわいんです。たとえばソランジュですが、彼女と5分間二人っきりになるとしたら、ぼくは鼠になって壁のなかに逃げ込んでしまいますよ」
作品の終わり頃に、主人公アランが自殺する理由をあれこれと考える描写が出てくる。
「男と女の世界に文句を言う筋は何もない。それは畜生の世界だ。そして、おれが自殺するのは、成功した畜生ではないからだ」
「おれが死ぬのは金がないからだ」
「おれが自殺するのは、お前たちがおれを愛さず、おれもお前たちを愛さなかったからだ」
「自殺とは、日常生活の錆によってばねが腐食した人間たちの苦境打開の策である」
「自殺とは一つの行為である。他に何も成し遂げ得なかった人間たちの行為なのである」
いやはや、まったく、甘ったれるな、といい加減な僕でさえ言いたくなるような話だが、やはり、強烈な磁力があることも否定できない。
長く生き過ぎてしまった自分、というものを僕は抱え込んでいるのかもしれない。
なお、この『ゆらめく炎』を原作としてルイ・マルの「鬼火」という映画が作られているが、本書の翻訳当時は、まだ日本公開されていなかったようだ。僕も「鬼火」見たのは20年以上前なんじゃないかな。これを機会に「鬼火」見たら、また自殺の方に針がぶれそうで、恐ろしい。
1.ハッピー・グラデュエーション
最近見た夢の話。
須田:日常そのもの
みさき:大きな猿のぬいぐるみ奪われる
真琴:日本人形に囲まれる
みゆき:大学受験失敗
田中:結婚式
月脇:サンタが操縦するタイムマシンに乗って時空をさまよう
椿:宇宙の高さのパフェ食べる
脇坂:テレビから貞子が出てくる
桃菜:テトリス(発熱時に必ずみる、とか)
城島:遅刻
トーク終わりで、モーニング娘。の夏歌特集
2.ひょっこりひょうたん島(月脇、番長)うしろの真琴の振りは完璧!
3.チュ夏パーティー(真琴、桃菜、脇坂)
4.ザ☆ピ〜ス(椿、田中)
伝言ゲーム。背中に書いた文字を伝えていく。
城島が「城島ゆかり」とお題を出すが、須田から月脇への伝言で「ピカチュウ」と変換され、最終的に「ピカチュウ」!月脇以降のメンバーは罰ゲームで空気椅子。
5.エニシングゴーズ
6.フットマン
ライブ終了後は握手会。
あいかわらず、何をしゃべっていいのかわからない。悪意や敵意がないことだけでもわかってもらいたいのだが。
桃菜がペット的なたまらない可愛さを持っている、とは以前から思っていたが、今回、月脇の魅力の種類がなんとなくわかってきた。
月脇は、孫の可愛さなのだ。おじいちゃんが孫を見て、「目の中に入れてもいたくない!」と無条件に可愛く思えてしまうのに似た不思議な魅力を持っている。
本人がこの日記を読むことはまず無いだろうが、こんな意見はうれしいのか?微妙か?絶賛して褒めているつもりなんだけどなあ。
読んだ本は、ピエール・ドリュ・ラ・ロシェルの『ゆらめく炎』
昨日読んだジャック・リゴーをモデルにしたと思しき小説。
今にも自殺しそうな麻薬中毒の男が、友人たちに会って会話したりするが、結局自殺をとめることはできない、という話。
そう難しい小説でもないのに、この本には少々てこずった。
なかなか文意が頭のなかに入っていかないのだ。
そう言えば、と『自殺総代理店』を引っぱりだしてみると、こんな文章があった。
私に起こったあらゆる事柄のなかで、私が全く関与しなかったことを一番よく思い出すのはなぜだろうか。
私は、自分が存在していないと感じる瞬間にだけ生を感じる。
私が生き続けていくためには、自分が存在していないことを信じていくしかない。
(「すべての鏡が私の名を映している」より)
リゴーが他人事の世界でふわふわ生きていたように、なんだか、作中の主人公アランの心情や行動もフワフワした感じだったのだ。
30才で自殺したリゴーへのあてこすりともとれる描写もある。
「その青春は終わろうとしていた。というのも、彼は30才になったばかりだが、30才と言えば、美貌しか持ち合わせていない青年にとっては老けた年だったから」
手厳しいね!
さて、『ゆらめく炎』からいくつか引用してみると。
(金は)際限なく彼の指の間を通り過ぎるが、決してそこにとどまらずに流れ去る束の間の幻だった。
麻薬が再度の転落を正当化するのに吹き込む詭弁とはこうしたものだ−おれはだめな奴だ、だからまた薬に手を出したってかまわないと。
彼はついに、麻薬中毒者たちの生活の真実の性格をはっきりと知った。よく整理された、閉じこもりがちな、気楽さを好む生活。カーテンを引いて、冒険や困難を避ける年金生活者たちの目立たぬ存在。共通の犠牲的精神によって結ばれ、純潔で気むずかしく、お喋り好きで、自分たちの信仰を悪く言われれば眉をひそめて顔をそむけるオールド・ミスたちの変哲もない生活。
個人の意志は過去の時代の神話なのだ。文明に疲れた人種はもはや意志を信ずることはできない。恐らく、彼らは強制の世界の逃げ込むだろう。
「ぼくは女にはほとんど力がない。しかし、女を通してはじめて、物に対して力を持つことができるんだ。ぼくにとって、女とはいつも金のことだった」
「たとえば、ここにいるどの女もぼくは欲しいという気になれない。彼女たちがこわい、ぼくにはこわい。女の前に出ると、戦いの最前線にいるのと同じようにこわいんです。たとえばソランジュですが、彼女と5分間二人っきりになるとしたら、ぼくは鼠になって壁のなかに逃げ込んでしまいますよ」
作品の終わり頃に、主人公アランが自殺する理由をあれこれと考える描写が出てくる。
「男と女の世界に文句を言う筋は何もない。それは畜生の世界だ。そして、おれが自殺するのは、成功した畜生ではないからだ」
「おれが死ぬのは金がないからだ」
「おれが自殺するのは、お前たちがおれを愛さず、おれもお前たちを愛さなかったからだ」
「自殺とは、日常生活の錆によってばねが腐食した人間たちの苦境打開の策である」
「自殺とは一つの行為である。他に何も成し遂げ得なかった人間たちの行為なのである」
いやはや、まったく、甘ったれるな、といい加減な僕でさえ言いたくなるような話だが、やはり、強烈な磁力があることも否定できない。
長く生き過ぎてしまった自分、というものを僕は抱え込んでいるのかもしれない。
なお、この『ゆらめく炎』を原作としてルイ・マルの「鬼火」という映画が作られているが、本書の翻訳当時は、まだ日本公開されていなかったようだ。僕も「鬼火」見たのは20年以上前なんじゃないかな。これを機会に「鬼火」見たら、また自殺の方に針がぶれそうで、恐ろしい。
ジャック・リゴーの『自殺総代理店』を読んだ。
以下、目次。
ジャック・リゴー/アンドレ・ブルトン
真面目に語ろう…
自殺総代理店
求職
三面記事
ある貧しい青年の物語
お気に召すなら
バレス裁判
すべての鏡が私の名を映している
遺稿断片
ジャック・リゴー年譜
永遠のダンディズム〜訳者後跋に代えて
1920年頃の『リテラチュール』誌に発表されたわずかの作品と、発表する気もなく書きつづられた文章から、リゴーらしさをあらわすものを集めて編まれた1冊。
リゴーはルイ・マルの映画『鬼火』の主人公のモデルとされている人物で、1920年にはパリ・ダダに参加。口にピストル入れて撃ったけど不発、とかの自殺未遂を経て、ついに自殺して果てる。作品がどうこうと言うより、その生き方(死に方?)、行動がダダ。マン・レイの「エマクバキア」で在りし日の姿を見ることができる。
で、そんなリゴーがどんなことを書いているかと言うと。
「生きる理由などありはしない、かといって死ぬ理由もない」
「人生などわざわざ捨てるにも値しない」
昨日読んだヴォネガットが「笑い」に注目してたのとは対照的だ。でも、ダダというかぎりは、シニカルにせよ笑いの要素があったはずなのだ。今リゴーがおれば、セカイ系の作家にでもなっていたのかもしれない。だいたい20才頃に書いた作品が多いので、思春期地獄のまっただなかだ。もったいぶった、傍から見ると笑わずにはおれないスタンスを、自覚的に生きたのかもしれない。リゴーは1899年生れ、1929年自殺で没。30才以降の生を認めなかった姿勢も、一貫している。
ただ、リゴーの本なんかを、仕事のある日などに読んだのは失敗だった。なにもかも虚しく目にうつってしまう。それだけの影響力があったのだ。リゴー、おそるべし。
以下、目次。
ジャック・リゴー/アンドレ・ブルトン
真面目に語ろう…
自殺総代理店
求職
三面記事
ある貧しい青年の物語
お気に召すなら
バレス裁判
すべての鏡が私の名を映している
遺稿断片
ジャック・リゴー年譜
永遠のダンディズム〜訳者後跋に代えて
1920年頃の『リテラチュール』誌に発表されたわずかの作品と、発表する気もなく書きつづられた文章から、リゴーらしさをあらわすものを集めて編まれた1冊。
リゴーはルイ・マルの映画『鬼火』の主人公のモデルとされている人物で、1920年にはパリ・ダダに参加。口にピストル入れて撃ったけど不発、とかの自殺未遂を経て、ついに自殺して果てる。作品がどうこうと言うより、その生き方(死に方?)、行動がダダ。マン・レイの「エマクバキア」で在りし日の姿を見ることができる。
で、そんなリゴーがどんなことを書いているかと言うと。
「生きる理由などありはしない、かといって死ぬ理由もない」
「人生などわざわざ捨てるにも値しない」
昨日読んだヴォネガットが「笑い」に注目してたのとは対照的だ。でも、ダダというかぎりは、シニカルにせよ笑いの要素があったはずなのだ。今リゴーがおれば、セカイ系の作家にでもなっていたのかもしれない。だいたい20才頃に書いた作品が多いので、思春期地獄のまっただなかだ。もったいぶった、傍から見ると笑わずにはおれないスタンスを、自覚的に生きたのかもしれない。リゴーは1899年生れ、1929年自殺で没。30才以降の生を認めなかった姿勢も、一貫している。
ただ、リゴーの本なんかを、仕事のある日などに読んだのは失敗だった。なにもかも虚しく目にうつってしまう。それだけの影響力があったのだ。リゴー、おそるべし。
JK21デイリーライブ「関西出身の巻」@す・適塾、『国のない男』
2009年7月29日 読書
JK21のデイリーライブ。
今日のメンバーは11人。城島、藤井、田中、松田、今崎、碧、須田、椿、月脇、脇坂、新垣。
1.ハッピーグラデュエーション
トークは、疲れの癒し方。
田中:お風呂で寝る
真琴:目に保冷剤
桃菜:扇風機の前に座る
わっきー:寝床でゴロゴロ
すだこ:部屋暗くして好きな音楽聞く
あゆみ:足あげて寝る
月脇:ハンドマッサージ
番長:体バキバキ鳴らす
つばっきー:猫だっこ
みゆき:音楽
ジョージ:プリン食べて寝る
コーナー終わりで、関西出身歌手特集
2.ライフタイムリスペクト(わっきー、ももな)
3.wind(あゆみ、番長)番長歌詞とちる
4.イエーめっちゃホリデイ(まこと、つばき)
真琴は℃-ute、椿はあややファンだとか。歌のタイトルは、みゆきによると「イエス、めっちゃホリデイ」になっていた。まあ、何を言って、何をしても可愛いからいいけど!
古今東西ゲーム
お題は「色」。ジョージが罰ゲームで、日本語禁止トーク。「え〜と」でアウト。
お題は「大阪名物」。わっきーが罰ゲームで。外来語禁止トーク。かなり頑張るが「ボウリング」を言い換えるのに「ボール」使って砕ける。
5.エニシングゴーズ
6.フットマン
7.Kiss(ジョージ、椿)
この日も、仕事の前だったので、サラリーマンカッターと長ズボンで、ライブ終了後は、時間の都合で握手に参加せず飛び出す。
読んだ本はカート・ヴォネガットの『国のない男』
以下、目次。
1、わたしは末っ子だった
2、「トゥワープ」という言葉をご存じだろうか
3、小説を書くときの注意
4、ここで、ちょっとしたお知らせを
5、さあ、そろそろ楽しい話をしよう
6、わたしは「ラッダイト」と呼ばれてきた
7、2004年11月11日で、82歳になった
8、人間主義者とはどういう人を指すかご存じだろうか
9、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ
10、イプシランティの懐古的な女性
11、さて、いい知らせがいくつかと、悪い知らせがいくつかある
12、わたしはかつて、自動車販売会社の社長だった
レクイエム
作者から
訳者あとがき
カート・ヴォネガット作品一覧
カートヴォネガット最晩年の言葉の数々。
本書より、いくつかの引用をしてみよう。それぞれ、わかりやすく、読みやすいが、それこそ年をとったことで自然に備わるマイルドさなのだろうか。
(手紙での質問にこたえる)
「もし自分にとって危険だということがわかっている人間がいるとしたら−たとえば、ポケットにピストルを持っていて、即座に撃ってきそうな人間とか−あなたはどうします?イラクはそんな相手なんです」
返事。
「では、われわれすべてのために、ショットガンを買って−できれば12口径の二連式がいい−隣の家に飛びこんで、その家の人たち(警官を除く)の頭を吹き飛ばしてください。みんな、武装しているかもしれないのですから」
この地球はいまやひどい状態だ。しかしそれはいまに始まったことではなく、ずっと昔からそうだったのだ。「古きよき時代」など、一度たりともあったためしがない。同じような日々を重ねてきただけだ。だから、わたしは自分の孫にはこう言うことにしている。
「年寄りに聞こう、なんて思うなよ。おまえとちっとも変わらないんだから」
唯一わたしがやりたかったのは、人々に笑いという救いを与えることだ。ユーモアには人の心を楽にする力がある。アスピリンのようなものだ。百年後、人類がまだ笑っていたら、わたしはきっとうれしいと思う。
なるほど!笑いが人の心を楽にする薬だというなら、さっそく買いに行きたい吉本グッズがある。僕がほしいのは「ヨクスベール」の方なんだけど。
今日のメンバーは11人。城島、藤井、田中、松田、今崎、碧、須田、椿、月脇、脇坂、新垣。
1.ハッピーグラデュエーション
トークは、疲れの癒し方。
田中:お風呂で寝る
真琴:目に保冷剤
桃菜:扇風機の前に座る
わっきー:寝床でゴロゴロ
すだこ:部屋暗くして好きな音楽聞く
あゆみ:足あげて寝る
月脇:ハンドマッサージ
番長:体バキバキ鳴らす
つばっきー:猫だっこ
みゆき:音楽
ジョージ:プリン食べて寝る
コーナー終わりで、関西出身歌手特集
2.ライフタイムリスペクト(わっきー、ももな)
3.wind(あゆみ、番長)番長歌詞とちる
4.イエーめっちゃホリデイ(まこと、つばき)
真琴は℃-ute、椿はあややファンだとか。歌のタイトルは、みゆきによると「イエス、めっちゃホリデイ」になっていた。まあ、何を言って、何をしても可愛いからいいけど!
古今東西ゲーム
お題は「色」。ジョージが罰ゲームで、日本語禁止トーク。「え〜と」でアウト。
お題は「大阪名物」。わっきーが罰ゲームで。外来語禁止トーク。かなり頑張るが「ボウリング」を言い換えるのに「ボール」使って砕ける。
5.エニシングゴーズ
6.フットマン
7.Kiss(ジョージ、椿)
この日も、仕事の前だったので、サラリーマンカッターと長ズボンで、ライブ終了後は、時間の都合で握手に参加せず飛び出す。
読んだ本はカート・ヴォネガットの『国のない男』
以下、目次。
1、わたしは末っ子だった
2、「トゥワープ」という言葉をご存じだろうか
3、小説を書くときの注意
4、ここで、ちょっとしたお知らせを
5、さあ、そろそろ楽しい話をしよう
6、わたしは「ラッダイト」と呼ばれてきた
7、2004年11月11日で、82歳になった
8、人間主義者とはどういう人を指すかご存じだろうか
9、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ
10、イプシランティの懐古的な女性
11、さて、いい知らせがいくつかと、悪い知らせがいくつかある
12、わたしはかつて、自動車販売会社の社長だった
レクイエム
作者から
訳者あとがき
カート・ヴォネガット作品一覧
カートヴォネガット最晩年の言葉の数々。
本書より、いくつかの引用をしてみよう。それぞれ、わかりやすく、読みやすいが、それこそ年をとったことで自然に備わるマイルドさなのだろうか。
(手紙での質問にこたえる)
「もし自分にとって危険だということがわかっている人間がいるとしたら−たとえば、ポケットにピストルを持っていて、即座に撃ってきそうな人間とか−あなたはどうします?イラクはそんな相手なんです」
返事。
「では、われわれすべてのために、ショットガンを買って−できれば12口径の二連式がいい−隣の家に飛びこんで、その家の人たち(警官を除く)の頭を吹き飛ばしてください。みんな、武装しているかもしれないのですから」
この地球はいまやひどい状態だ。しかしそれはいまに始まったことではなく、ずっと昔からそうだったのだ。「古きよき時代」など、一度たりともあったためしがない。同じような日々を重ねてきただけだ。だから、わたしは自分の孫にはこう言うことにしている。
「年寄りに聞こう、なんて思うなよ。おまえとちっとも変わらないんだから」
唯一わたしがやりたかったのは、人々に笑いという救いを与えることだ。ユーモアには人の心を楽にする力がある。アスピリンのようなものだ。百年後、人類がまだ笑っていたら、わたしはきっとうれしいと思う。
なるほど!笑いが人の心を楽にする薬だというなら、さっそく買いに行きたい吉本グッズがある。僕がほしいのは「ヨクスベール」の方なんだけど。
『ブルバキ−数学者達の秘密結社』
2009年7月28日 読書 コメント (1)
モーリス・マシャルの『ブルバキ−数学者達の秘密結社』を読んだ。
以下、目次。
1、グループがつくられる
ブルバキの育ちの園、エコール・ノルマル・シュペリユール/初めは控え目な計画が、次第にファラオ的になる/田園の集り/実験台モルモットは将来性を示さなければならない/50歳で定年/偉大な才能と優れた頭脳
●ニコラブルバキ協力者の会
●ジャン・デルサルト(1903-1968)
2、名前にまつわる伝説
●本物のブルバキ将軍(1816-1897)
学生の茶番劇かそれとも文学的なほのめかしか?/エリ・カルタンが一風変わった数学者の名づけ親となる/未知の先祖の出現/ニコラ・ブルバキの略歴
●「ブルバキの略歴と業績」
●アンドレ・ヴェイユ(1906-1998)
3、若者と大御所
ルネサンス−西欧数学の復興/19世紀に厳密に、そして抽象的になる/1900年代の導き手ポアンカレとヒルベルト/ほとんど師を持たない見習い数学者/『解析教程』打倒、『現代代数学』万歳!
●1937年の『メダルの戦い』
4、『数学原論』
10部門、60以上の章/発行者フレイマンの加担/ブルバキは『一般から特殊へ』と記述する/新しい用語、新しい記号/ブルバキの対象は誰?
●1、デュドネが語るブルバキの執筆法
●2、集合論
●3、代数学
●4、位相
●5、実一変数関数
●6、位相線型空間
●7、積分
●8、可換代数
●9、リー群とリー環
●10、微分可能多様体と解析的多様体
●11、スペクトル論
●ジャン・デュドネ(1906-1992)
5、公理的方法と構造を目指して
ヒルベルト流の公理的方法/構造の3つの型/ダチョウをまねるとき…/カテゴリー対ブルバキ型の構造
●ブルバキからウリポ、ピアジェそしてレヴィ=ストロースへ…
●1、群の構造
●2、環とイデアルの構造
●3、体の構造
●4、順序構造
6、ブルバキの断片:フィルター
●1、距離の公理
●2、位相空間、開集合と近傍
●3、フィルターの公理
●アンリ・カルタン(1904年生まれ)
7、セミネール・ブルバキ
セミネールの儀式/864の講演、1万ページの講究録/専門化しすぎているという者もいる…
●セミネール・ブルバキの先駆者:「セミネール・アダマール」と「セミネール・ジュリア」
8、繊細にして謹厳な学生達
言葉の重み、酒樽の衝撃/ブルバキは自発的な難読症?/自分自身にも不遜な/ブルバキ嬢の結婚、そしてブルバキの逝去…
9、『人間精神の名誉のために』?
ブルバキの選択−論理もなし、応用数学もなし/ブルバキは基礎論に興味がない/常に一般化を追い求める超公理化師達?/ブルバキは解析学を代数化した
●ブルバキは数学での権力者であったか?
●測度、積分と確率
●クロード・シュヴァレー(1909−1984)
10、学校教育での『現代数学』
ブルバキが高等教育を制覇する/ブルバキが ポリテクニクに入る/至るところに数学を見た/デュドネが「打倒ユークリッド!」と叫ぶとき/革命の後に反革命が/ブルバキは用心深く、中立し、沈黙を守った
11、不死の数学者?
数学の情景は変わった/時間の不足か熱意の不足か?/「彼の仕事は終わっている、しかも見事に終わっている…/数学は上に統一され、下にではない
ブルバキの毀誉褒貶、盛者必衰の理。
面白いのは断然、ブルバキのなりたちあたりで、「カニュラール」と呼ばれる、学生の悪ふざけが横溢している。
ブルバキは八手三郎みたいなもので、複数の数学者達によるペンネームなのだが、実在する個人であると主張しつづける。ブルバキという個人はいない、と暴露する者を相手に、「おまえこそ、架空の合作ペンネームじゃないか」と切り返したりしている。こういう稚気に富んだ遊びは、ミステリに通じるものがあって、親近感が湧く。まるでバーナビー・ロスとエラリイ・クイーンのやりとりみたいなものではないか。
以前に読んだ『アンドレ・ヴェイユ自伝』の記述が正しいならば、アンドレ・ヴェイユがブルバキの経歴を創作し、ポルデヴィア出身だということにした、ということだが、本書ではまた違う記述が見られる。
それは、1960年頃につくられた『ニコラ・ブルバキの略歴と業績』と称する文書で、それによると、
「ブルバキ家はクレタ島出身である〜ソテル・ブルバキの三男はロシアに亡命し、次いで ルーマニアに渡ったが、まもなくギリシャに残った両親との連絡を絶った。ニコラ・ブルバキはこの三男の子孫で、1886年にモルダヴィア地方のククテニに生れた」
ブルバキを「モルダヴィア出身」だと百科事典的に記述することが散見されるのは、この文書をもとにしたものだと思われる。
もともと架空の「ブルバキ」さんの出身がどこであろうと、間違いとか正しいとか言い様がないのだが、ここは架空の土地「ポルデヴィア」だとする方が、よりブルバキらしくて面白いんじゃないかと思う。ポルデヴィア、という土地は、ウリポの作家で、ブルバキの一員でもあったジャック・ルーボーの『麗しのオルタンス』の解説によると、ジャーナリストのアラン・メイユが創作したのだと言う。(ポルデヴィアについて書かれているというミステリマガジンを読んでいないのがとても残念!)メイユがどんなふうにポルデヴィアを書いているのか、ちょちょっと調べてみたが、よくわからない。ここは、フランスに詳しい人にご教示いただきたい。ポルデヴィアに興味を持ったついでに、ライツヴィル物をまた読みたいな、なんて脱線するのが、楽しいのだ。
この本は簡略ながら数学的なことも書いてあり、まったくの数学オンチの僕の頭にはなかなか入ってこなくて、四苦八苦した。最近とんと読書していないような日記が続いていたのは、本書と闘っていたからである。だが、数学的なことはちんぷんかんぷんでも、この本はめちゃくちゃ面白かった!
以下、目次。
1、グループがつくられる
ブルバキの育ちの園、エコール・ノルマル・シュペリユール/初めは控え目な計画が、次第にファラオ的になる/田園の集り/実験台モルモットは将来性を示さなければならない/50歳で定年/偉大な才能と優れた頭脳
●ニコラブルバキ協力者の会
●ジャン・デルサルト(1903-1968)
2、名前にまつわる伝説
●本物のブルバキ将軍(1816-1897)
学生の茶番劇かそれとも文学的なほのめかしか?/エリ・カルタンが一風変わった数学者の名づけ親となる/未知の先祖の出現/ニコラ・ブルバキの略歴
●「ブルバキの略歴と業績」
●アンドレ・ヴェイユ(1906-1998)
3、若者と大御所
ルネサンス−西欧数学の復興/19世紀に厳密に、そして抽象的になる/1900年代の導き手ポアンカレとヒルベルト/ほとんど師を持たない見習い数学者/『解析教程』打倒、『現代代数学』万歳!
●1937年の『メダルの戦い』
4、『数学原論』
10部門、60以上の章/発行者フレイマンの加担/ブルバキは『一般から特殊へ』と記述する/新しい用語、新しい記号/ブルバキの対象は誰?
●1、デュドネが語るブルバキの執筆法
●2、集合論
●3、代数学
●4、位相
●5、実一変数関数
●6、位相線型空間
●7、積分
●8、可換代数
●9、リー群とリー環
●10、微分可能多様体と解析的多様体
●11、スペクトル論
●ジャン・デュドネ(1906-1992)
5、公理的方法と構造を目指して
ヒルベルト流の公理的方法/構造の3つの型/ダチョウをまねるとき…/カテゴリー対ブルバキ型の構造
●ブルバキからウリポ、ピアジェそしてレヴィ=ストロースへ…
●1、群の構造
●2、環とイデアルの構造
●3、体の構造
●4、順序構造
6、ブルバキの断片:フィルター
●1、距離の公理
●2、位相空間、開集合と近傍
●3、フィルターの公理
●アンリ・カルタン(1904年生まれ)
7、セミネール・ブルバキ
セミネールの儀式/864の講演、1万ページの講究録/専門化しすぎているという者もいる…
●セミネール・ブルバキの先駆者:「セミネール・アダマール」と「セミネール・ジュリア」
8、繊細にして謹厳な学生達
言葉の重み、酒樽の衝撃/ブルバキは自発的な難読症?/自分自身にも不遜な/ブルバキ嬢の結婚、そしてブルバキの逝去…
9、『人間精神の名誉のために』?
ブルバキの選択−論理もなし、応用数学もなし/ブルバキは基礎論に興味がない/常に一般化を追い求める超公理化師達?/ブルバキは解析学を代数化した
●ブルバキは数学での権力者であったか?
●測度、積分と確率
●クロード・シュヴァレー(1909−1984)
10、学校教育での『現代数学』
ブルバキが高等教育を制覇する/ブルバキが ポリテクニクに入る/至るところに数学を見た/デュドネが「打倒ユークリッド!」と叫ぶとき/革命の後に反革命が/ブルバキは用心深く、中立し、沈黙を守った
11、不死の数学者?
数学の情景は変わった/時間の不足か熱意の不足か?/「彼の仕事は終わっている、しかも見事に終わっている…/数学は上に統一され、下にではない
ブルバキの毀誉褒貶、盛者必衰の理。
面白いのは断然、ブルバキのなりたちあたりで、「カニュラール」と呼ばれる、学生の悪ふざけが横溢している。
ブルバキは八手三郎みたいなもので、複数の数学者達によるペンネームなのだが、実在する個人であると主張しつづける。ブルバキという個人はいない、と暴露する者を相手に、「おまえこそ、架空の合作ペンネームじゃないか」と切り返したりしている。こういう稚気に富んだ遊びは、ミステリに通じるものがあって、親近感が湧く。まるでバーナビー・ロスとエラリイ・クイーンのやりとりみたいなものではないか。
以前に読んだ『アンドレ・ヴェイユ自伝』の記述が正しいならば、アンドレ・ヴェイユがブルバキの経歴を創作し、ポルデヴィア出身だということにした、ということだが、本書ではまた違う記述が見られる。
それは、1960年頃につくられた『ニコラ・ブルバキの略歴と業績』と称する文書で、それによると、
「ブルバキ家はクレタ島出身である〜ソテル・ブルバキの三男はロシアに亡命し、次いで ルーマニアに渡ったが、まもなくギリシャに残った両親との連絡を絶った。ニコラ・ブルバキはこの三男の子孫で、1886年にモルダヴィア地方のククテニに生れた」
ブルバキを「モルダヴィア出身」だと百科事典的に記述することが散見されるのは、この文書をもとにしたものだと思われる。
もともと架空の「ブルバキ」さんの出身がどこであろうと、間違いとか正しいとか言い様がないのだが、ここは架空の土地「ポルデヴィア」だとする方が、よりブルバキらしくて面白いんじゃないかと思う。ポルデヴィア、という土地は、ウリポの作家で、ブルバキの一員でもあったジャック・ルーボーの『麗しのオルタンス』の解説によると、ジャーナリストのアラン・メイユが創作したのだと言う。(ポルデヴィアについて書かれているというミステリマガジンを読んでいないのがとても残念!)メイユがどんなふうにポルデヴィアを書いているのか、ちょちょっと調べてみたが、よくわからない。ここは、フランスに詳しい人にご教示いただきたい。ポルデヴィアに興味を持ったついでに、ライツヴィル物をまた読みたいな、なんて脱線するのが、楽しいのだ。
この本は簡略ながら数学的なことも書いてあり、まったくの数学オンチの僕の頭にはなかなか入ってこなくて、四苦八苦した。最近とんと読書していないような日記が続いていたのは、本書と闘っていたからである。だが、数学的なことはちんぷんかんぷんでも、この本はめちゃくちゃ面白かった!
『野暮天先生講義録』
2009年7月23日 読書
今和次郎の『野暮天先生講義録』を読んだ。
○春から夏へ
記念の座布団
野暮天の逆転
魚屋のおばあさん
こづかいの分配
年功加俸
家計費の腑分け
生活力学
動線(サーキュレーション)
道端のゴミ
箱の中のくらし
幸福はにげる
ネクタイ談義
アパートとミニスカート
神さま仏さま
お祭り
お客さま
おやじさま
時間と金
労働過多症
レジャー過多症
紳士たちのレジャー
住まいの機械化
雨露をしのげば
平安式の接客
下御殿
妙な分類学
○夏のころ
アクセサリー
ハイヒールの系図
庭づくり
食欲と食物
献立表
フォーク
カラーとスプーン
食料工場
服装の性別
結婚衣裳
緑の卓子
コロニーランド
所管ちがい
シルクロード
うちの文化財「急須」
ある水族館
高山の民俗館
間借りの学生
○立秋
話題の建築物
冷房と上着
とんがった靴
寝部屋拝見
雑用に追われて
不安なアパート
丸ノ内の美観
バテレンの服装
みやげものの美学
少年時代のくらし
くらしの電化
公民館考
盆栽仕立て
デザインというもの
童心にかえる
立候補
お彼岸も過ぎて
Ⅰ967年に日本経済新聞夕刊に連載されたコラムから選ばれたもの。
考現学の今和次郎の文章も42年たつと考古学になっちゃうかな、と思っていたが、まだまだ現在の話として読める。でも、67年って、万博よりも前なんだな、と思うと、かなり昔の時代なような。
住まいが経済的動線だけになることに警鐘をならしたり、ラッシュをみて「妙な所」に団地を作ったかぎりはその居住者たちの運搬に責任を負わねばならない、と言ったり、潜水夫が足につける「かえる式の足」にミニスカートが流行る、と予言したり。
○春から夏へ
記念の座布団
野暮天の逆転
魚屋のおばあさん
こづかいの分配
年功加俸
家計費の腑分け
生活力学
動線(サーキュレーション)
道端のゴミ
箱の中のくらし
幸福はにげる
ネクタイ談義
アパートとミニスカート
神さま仏さま
お祭り
お客さま
おやじさま
時間と金
労働過多症
レジャー過多症
紳士たちのレジャー
住まいの機械化
雨露をしのげば
平安式の接客
下御殿
妙な分類学
○夏のころ
アクセサリー
ハイヒールの系図
庭づくり
食欲と食物
献立表
フォーク
カラーとスプーン
食料工場
服装の性別
結婚衣裳
緑の卓子
コロニーランド
所管ちがい
シルクロード
うちの文化財「急須」
ある水族館
高山の民俗館
間借りの学生
○立秋
話題の建築物
冷房と上着
とんがった靴
寝部屋拝見
雑用に追われて
不安なアパート
丸ノ内の美観
バテレンの服装
みやげものの美学
少年時代のくらし
くらしの電化
公民館考
盆栽仕立て
デザインというもの
童心にかえる
立候補
お彼岸も過ぎて
Ⅰ967年に日本経済新聞夕刊に連載されたコラムから選ばれたもの。
考現学の今和次郎の文章も42年たつと考古学になっちゃうかな、と思っていたが、まだまだ現在の話として読める。でも、67年って、万博よりも前なんだな、と思うと、かなり昔の時代なような。
住まいが経済的動線だけになることに警鐘をならしたり、ラッシュをみて「妙な所」に団地を作ったかぎりはその居住者たちの運搬に責任を負わねばならない、と言ったり、潜水夫が足につける「かえる式の足」にミニスカートが流行る、と予言したり。