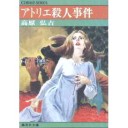岡田鯱彦の『紅い頸巻』を読んだ。1955年
「紅い頸巻」
第1章 恐怖
第2章 父と娘
第3章 秘密
第4章 護衛
第5章 決戦へ
第6章 断崖
第7章 潰滅
第8章 神の摂理
雪深き狼峠の惨劇!
元公爵中御門家に属する3人の男女が互いに殺し殺された事件。
命を狙われているヒロインと、それをなんとか救おうとする主人公。
と、言えば「ハハ〜ン、あのパターンだな」と、2時間ドラマのストーリーを先読みするような予測をしてしまいそうである。
作中にも、こんな思わせぶりな文章がある。
「私は自分に言って聞かせた。誤りを犯してはならぬ。お前の仕事は探偵ではないか。探偵に恋愛は禁物だ。犯罪に関係ある者の性格の闡明こそは必要であるが、探偵自身の恋愛は一向犯罪の究明に役に立たぬ。役に立たぬばかりか、往々にして重大な誤りを犯させる事になる」
狙われているヒロインは、目立つ赤いマフラーを、別の人と交換する。
そして、赤いマフラーをした人物は事故だか殺人だかで命を落とす。
ヒロインの身代わりで、その人は死んでしまったのか!
こういうパターンだと、真犯人が誰なのかは、もう明らかに思えるのだが、その予想は、なんと裏切られてしまうのだ。
これはある意味、意外な真相と言わねばならない。
「三味線殺人事件」
妻の死は「殺人だ」
嫉妬に悩む二十年
色っぽい女師匠
蝦蟇と小鳥
殺すか殺されるか
駈け引きと真実
すると犯人は…
犯罪の真相
渦巻く夜霧
三味線ひくときに、腕をぺろりとなめる癖。
「雪の夜語り」
幼な馴染み
雪江夫人の話
尾形教授の話
創作でしょ?
西村社長の話
降りしきる雪
長い年月を経て明かされる、男女のすれちがいの真相。
誰の話かを匿名にしながら、明らかに自分たちの話をする設定から、真相が明かされるくだりは、まさに「イエス、フォーリンラブ!」の呼吸。
「紅い頸巻」
第1章 恐怖
第2章 父と娘
第3章 秘密
第4章 護衛
第5章 決戦へ
第6章 断崖
第7章 潰滅
第8章 神の摂理
雪深き狼峠の惨劇!
元公爵中御門家に属する3人の男女が互いに殺し殺された事件。
命を狙われているヒロインと、それをなんとか救おうとする主人公。
と、言えば「ハハ〜ン、あのパターンだな」と、2時間ドラマのストーリーを先読みするような予測をしてしまいそうである。
作中にも、こんな思わせぶりな文章がある。
「私は自分に言って聞かせた。誤りを犯してはならぬ。お前の仕事は探偵ではないか。探偵に恋愛は禁物だ。犯罪に関係ある者の性格の闡明こそは必要であるが、探偵自身の恋愛は一向犯罪の究明に役に立たぬ。役に立たぬばかりか、往々にして重大な誤りを犯させる事になる」
狙われているヒロインは、目立つ赤いマフラーを、別の人と交換する。
そして、赤いマフラーをした人物は事故だか殺人だかで命を落とす。
ヒロインの身代わりで、その人は死んでしまったのか!
こういうパターンだと、真犯人が誰なのかは、もう明らかに思えるのだが、その予想は、なんと裏切られてしまうのだ。
これはある意味、意外な真相と言わねばならない。
「三味線殺人事件」
妻の死は「殺人だ」
嫉妬に悩む二十年
色っぽい女師匠
蝦蟇と小鳥
殺すか殺されるか
駈け引きと真実
すると犯人は…
犯罪の真相
渦巻く夜霧
三味線ひくときに、腕をぺろりとなめる癖。
「雪の夜語り」
幼な馴染み
雪江夫人の話
尾形教授の話
創作でしょ?
西村社長の話
降りしきる雪
長い年月を経て明かされる、男女のすれちがいの真相。
誰の話かを匿名にしながら、明らかに自分たちの話をする設定から、真相が明かされるくだりは、まさに「イエス、フォーリンラブ!」の呼吸。
北町一郎の『消えた花嫁』を読んだ。1959年。
あとがきによると、「この小説集は、雑誌『宝石』に発表して江戸川乱歩さんから『公安委員もの』と呼ばれた作品と、その公安委員が介在している作品をおさめたものです」とある。3話までが『宝石』に発表されたもので、それ以外は他の雑誌に発表されたものだが、まとめるにあたっていずれも手を加えてあるそうだ。
なるほど、最初の3つの話にはそれぞれ、ガードナー、クイーン、クロフツへの言及があったのは、『宝石』に発表されたからなのだな、と思った。
ミステリーではあるが、ユーモア小説作家の北町一郎らしく、推理小説的なトリックだの残酷な描写などはまったくない。犯罪すらない話が多くて、今なら日常の謎とか癒し系とか要らぬレッテルをはられそうだ。
以下、各話のネタバレ。
第1話 消えた花嫁
足入れで結婚相手の女性を運ぶ途中、ひと休みしている間に女性が行方不明になる。
結婚が嫌で逃げた、というわけでもなさそうなのに、これはいったい何故?
実は、女性には秘密があった。
無毛症だったのだ。
結婚して、向こうの家で一緒に入浴した際などに、家人にばれるのをおそれて、嫁は植毛手術を受けに行っていたのだ。もちろん、婿もグルだった。
第2話 五月祭前後
日本革新党の「鈴仙」が若原町に潜入しているとの情報に右往左往する。
第3話 狸と狐
本家争いをする東西の佐藤家。全く同じものと思われる良寛の掛け軸を、それぞれの家が所有していた。さて、真贋の真相はいかに。
佐藤家に恨みのあった経師屋が、良寛の書き物を2枚に剥がして東西佐藤家に売り、いずれもめ事になる日をじっと待っていたのだ。
主人公は探偵小説の翻訳もしており、この話ではクロフツのこんな小説を訳している描写がある。
「草深いヨークシア州(イングランド)の沼沢地に近い草原の一軒家に計画された殺人と放火が起り、死体の確認をめぐってフレンチ警部がとまどいする。墓穴の中には死体はなく、容疑者は死体となって発見される」
さあ、この小説は何でしょ〜〜〜か?
第4話 神霊ホルモン
回春薬「神霊ホルモン」の原料は、焼褌散(ショーコンサン)。
女には男のフンドシ、男には女の腰巻(どちらも使用済)の黒焼きを粉末にしたものを用いる。
最近は腰巻をつけている女性が少なくなり、しかたなく、外国人女性のズロース(金髪入り)を原料に使う。
第5話 アクセサリー物語
議員としてのハクをつけるため、メカケを持とうとする男。
回春堂の薬の手助けを借りようとするが、それは議員のセガレならぬ、本物の倅によって中味をすりかえられていた。
議員は回春薬のかわりに飲んだ胃腸薬で健康を回復し、倅は結婚生活がうまくいきだした。
第6話 盗難
泥棒をとらえてみると、女ものの財布が見つかったが、被害者が見つからない。
女がらみの話で、申し出ることができなかったのだ。
第7話 海女と秘仏
男がほしくてたまらない女性を易で占う。
卦は「ここから45度の方角に、あんたのたずねあてるべきものがある」と出た。
捜してみると、なんと、秘仏を発見した。
秘仏は生殖器をかたどっていた。それこそが、たずねあてるべきものだったのだ。
第8話 運命の銀貨
女がスリをはたらくのを目撃した男性。
女は、父親を殺したギャングを見つけ、名刺を盗んで身許を確認していたのだ。
第9話 偶然の審判
密室。
しめ忘れた窓から侵入し、自動施錠のドアから出る。
まあ、これだけ聞いても、何の話なのやら、ってことだけど。
宝クジが真相解決に役立つ。
あとがきによると、「この小説集は、雑誌『宝石』に発表して江戸川乱歩さんから『公安委員もの』と呼ばれた作品と、その公安委員が介在している作品をおさめたものです」とある。3話までが『宝石』に発表されたもので、それ以外は他の雑誌に発表されたものだが、まとめるにあたっていずれも手を加えてあるそうだ。
なるほど、最初の3つの話にはそれぞれ、ガードナー、クイーン、クロフツへの言及があったのは、『宝石』に発表されたからなのだな、と思った。
ミステリーではあるが、ユーモア小説作家の北町一郎らしく、推理小説的なトリックだの残酷な描写などはまったくない。犯罪すらない話が多くて、今なら日常の謎とか癒し系とか要らぬレッテルをはられそうだ。
以下、各話のネタバレ。
第1話 消えた花嫁
足入れで結婚相手の女性を運ぶ途中、ひと休みしている間に女性が行方不明になる。
結婚が嫌で逃げた、というわけでもなさそうなのに、これはいったい何故?
実は、女性には秘密があった。
無毛症だったのだ。
結婚して、向こうの家で一緒に入浴した際などに、家人にばれるのをおそれて、嫁は植毛手術を受けに行っていたのだ。もちろん、婿もグルだった。
第2話 五月祭前後
日本革新党の「鈴仙」が若原町に潜入しているとの情報に右往左往する。
第3話 狸と狐
本家争いをする東西の佐藤家。全く同じものと思われる良寛の掛け軸を、それぞれの家が所有していた。さて、真贋の真相はいかに。
佐藤家に恨みのあった経師屋が、良寛の書き物を2枚に剥がして東西佐藤家に売り、いずれもめ事になる日をじっと待っていたのだ。
主人公は探偵小説の翻訳もしており、この話ではクロフツのこんな小説を訳している描写がある。
「草深いヨークシア州(イングランド)の沼沢地に近い草原の一軒家に計画された殺人と放火が起り、死体の確認をめぐってフレンチ警部がとまどいする。墓穴の中には死体はなく、容疑者は死体となって発見される」
さあ、この小説は何でしょ〜〜〜か?
第4話 神霊ホルモン
回春薬「神霊ホルモン」の原料は、焼褌散(ショーコンサン)。
女には男のフンドシ、男には女の腰巻(どちらも使用済)の黒焼きを粉末にしたものを用いる。
最近は腰巻をつけている女性が少なくなり、しかたなく、外国人女性のズロース(金髪入り)を原料に使う。
第5話 アクセサリー物語
議員としてのハクをつけるため、メカケを持とうとする男。
回春堂の薬の手助けを借りようとするが、それは議員のセガレならぬ、本物の倅によって中味をすりかえられていた。
議員は回春薬のかわりに飲んだ胃腸薬で健康を回復し、倅は結婚生活がうまくいきだした。
第6話 盗難
泥棒をとらえてみると、女ものの財布が見つかったが、被害者が見つからない。
女がらみの話で、申し出ることができなかったのだ。
第7話 海女と秘仏
男がほしくてたまらない女性を易で占う。
卦は「ここから45度の方角に、あんたのたずねあてるべきものがある」と出た。
捜してみると、なんと、秘仏を発見した。
秘仏は生殖器をかたどっていた。それこそが、たずねあてるべきものだったのだ。
第8話 運命の銀貨
女がスリをはたらくのを目撃した男性。
女は、父親を殺したギャングを見つけ、名刺を盗んで身許を確認していたのだ。
第9話 偶然の審判
密室。
しめ忘れた窓から侵入し、自動施錠のドアから出る。
まあ、これだけ聞いても、何の話なのやら、ってことだけど。
宝クジが真相解決に役立つ。
鷲尾三郎の『歪んだ年輪』を読んだ。1964年。
書き下ろしの長編推理。
この事件も南郷探偵事務所の留守をあずかる作家、牟礼順吉が事件の謎を解く。
3つの事件がからみあう。
まず1つめは、シンクロナイズドスイミングの水中ショーで、シンクロ嬢の1人が何者かに射殺される。
2つめは、衣料会社サンライズの警備員、河本亮平が車でひき殺された事件。加害者のバーテン、久下透もそのときに石垣に車を衝突させて即死。
牟礼が亮平の妹、河本千絵子から依頼を受ける。千絵子によると、事件の前に、亮平は何やら大金が手に入りそうだ、とか漏らしていたのだ。
3つめは、そのサンライズで、会社に忍び込んだ泥棒が、警備員の碓井正明に追い掛けられて、屋上から墜落死した事件。
これらの事件はどう関連しているのか。
シンクロ嬢射殺に関して、あやしい「松葉杖の男」が浮かび上がる。
この男はカメラマンを装って、ほかの招待客に紛れてビーチ・クラブの会場へ入ったが、事件のあとで帰って行った形跡がないのだ。松葉杖の男は正真正銘の跛で、膝から下がないのである。
サンライズビルの屋上から落ちて死んだ男は、4人組で進駐軍の倉庫に忍び込んで、薬品を盗み出して、MPに捕らえられ、18年の刑に服していたことが判明する。
そのときの4人組のうち、1人はその場で米兵に射殺され、1人はその米兵を殴って捕まり、15年の刑に服した。うまく逃げのびたのは1人だけ。
結局、1人だけおめおめと逃げのびた男に、1人だけ射殺された遺族がたかった挙げ句の犯罪が、今回の事件の真相だったのである。
本作には、読後、強烈な印象を残す名場面がある。
これだ!
「私はガラス・ドアから往来に出ると、急いで駐車場へ向った。そのとき、樽の底が抜けたようなはげしい夕立が降ってきた。私はあわてて駐車係りの詰所の庇へ逃げこんだ。そしてふと気がつくと、鉄線で囲いのした駐車場の一隅に、さっきのマーキュリーが駐車していて、碓井が車のトランクを開けて、嵩の大きい紙包みを取出していた。運転手は碓井からその荷物を受取ると、土砂降りの雨の中を、デパートのほうへ一目散に駈けて行った。そのとき碓井の眼が偶然に、詰所の庇の下に雨宿りしていた私を見た。私はトランクを締めた彼が、当然運転手のあとを追って駆け出して行くものと思っていた。ところが、彼はそんな不様な恰好を、私に見られるのが癪だったのか、悠然と雨の中を歩いて駐車場から立ち去って行った。折角の洋服を雨に濡らして台なしにするのは彼の勝手だが、彼のあてつけがましい挑戦的な態度が、私には彼がより一層いやな男に思われた。」
おおおおお、何度読み返しても、ぞくぞくっとする名場面。事件の真相を知ったときに、このシーンが、「ああっ、そうだたのか!」と膝を叩くことになるのである。
作中、バー「オルフェ」が出てくる。
「バー”オルフェ”のマダムとは、昨年の春彼女の弟が失踪して、その行方を捜してくれと頼まれて以来、ずっとご無沙汰していて、一年あまりも彼女に会っていなかった」
とある。なぜご無沙汰していたかというと、
「あのときの事件を君(マダム)に無断で小説に書いたので、もし君が読んでいたら、きっと怒るだろうと思ったからさ」らしい。
このマダムの弟失踪事件を扱った、無断で書かれた小説は先日読んだ『その鉄柵の中で』である。
この作品のみどころは、比喩の面白さにもある。
「二人ともお仕着せのイーヴニングを脱がしてアッパッパを着せたら、場末の溝板の上で、アイスキャンデーを噛じりながら井戸端会議している連中と、大した違いはなかった。」
こういう文章ならよくわかるのだが、次に並べた比喩は、なんだかピッタリのような気もするが、よく考えてみると、見たこともないものを比喩に使っているので、本当はよくわからないはずなのである。
「駐車係はクレオパトラに呼ばれた奴隷のように、うやうやしく彼女のそばに駈けつけた。」
「日に灼けて、アスアン・ダムに働いているエジプト人のような顔色をしていた。」
「そこには満月の夜に踊り狂っているカイオア族と間違えられそうな、哀れなテーンエイジャーは一人も見あたらなかった。」
「馨をよく知っているらしいそのボーイは、ニクトクリス女王に仕える奴隷のように、恭しく一礼して立ち去ると、すぐにウイスキーのグラスを盆にのせて運んできた。」
犯罪をおかしてきた「松葉杖の男」は、クライマックスでは、地の文でさんざんな言われようをする。
「不具者としての歪められた人生感が、永年にわたる猜疑と卑屈に痛めつけられて、怒りの発作という力のおもむくままに、残忍な行為をくりかえしつつ、はかない満足にひたっている男、それがこの男の正体なのだ。救われない人間だった」
松葉杖の男になりかわって、作者に「おいおい、それは言い過ぎだろう」とたしなめたくなってくる。
書き下ろしの長編推理。
この事件も南郷探偵事務所の留守をあずかる作家、牟礼順吉が事件の謎を解く。
3つの事件がからみあう。
まず1つめは、シンクロナイズドスイミングの水中ショーで、シンクロ嬢の1人が何者かに射殺される。
2つめは、衣料会社サンライズの警備員、河本亮平が車でひき殺された事件。加害者のバーテン、久下透もそのときに石垣に車を衝突させて即死。
牟礼が亮平の妹、河本千絵子から依頼を受ける。千絵子によると、事件の前に、亮平は何やら大金が手に入りそうだ、とか漏らしていたのだ。
3つめは、そのサンライズで、会社に忍び込んだ泥棒が、警備員の碓井正明に追い掛けられて、屋上から墜落死した事件。
これらの事件はどう関連しているのか。
シンクロ嬢射殺に関して、あやしい「松葉杖の男」が浮かび上がる。
この男はカメラマンを装って、ほかの招待客に紛れてビーチ・クラブの会場へ入ったが、事件のあとで帰って行った形跡がないのだ。松葉杖の男は正真正銘の跛で、膝から下がないのである。
サンライズビルの屋上から落ちて死んだ男は、4人組で進駐軍の倉庫に忍び込んで、薬品を盗み出して、MPに捕らえられ、18年の刑に服していたことが判明する。
そのときの4人組のうち、1人はその場で米兵に射殺され、1人はその米兵を殴って捕まり、15年の刑に服した。うまく逃げのびたのは1人だけ。
結局、1人だけおめおめと逃げのびた男に、1人だけ射殺された遺族がたかった挙げ句の犯罪が、今回の事件の真相だったのである。
本作には、読後、強烈な印象を残す名場面がある。
これだ!
「私はガラス・ドアから往来に出ると、急いで駐車場へ向った。そのとき、樽の底が抜けたようなはげしい夕立が降ってきた。私はあわてて駐車係りの詰所の庇へ逃げこんだ。そしてふと気がつくと、鉄線で囲いのした駐車場の一隅に、さっきのマーキュリーが駐車していて、碓井が車のトランクを開けて、嵩の大きい紙包みを取出していた。運転手は碓井からその荷物を受取ると、土砂降りの雨の中を、デパートのほうへ一目散に駈けて行った。そのとき碓井の眼が偶然に、詰所の庇の下に雨宿りしていた私を見た。私はトランクを締めた彼が、当然運転手のあとを追って駆け出して行くものと思っていた。ところが、彼はそんな不様な恰好を、私に見られるのが癪だったのか、悠然と雨の中を歩いて駐車場から立ち去って行った。折角の洋服を雨に濡らして台なしにするのは彼の勝手だが、彼のあてつけがましい挑戦的な態度が、私には彼がより一層いやな男に思われた。」
おおおおお、何度読み返しても、ぞくぞくっとする名場面。事件の真相を知ったときに、このシーンが、「ああっ、そうだたのか!」と膝を叩くことになるのである。
作中、バー「オルフェ」が出てくる。
「バー”オルフェ”のマダムとは、昨年の春彼女の弟が失踪して、その行方を捜してくれと頼まれて以来、ずっとご無沙汰していて、一年あまりも彼女に会っていなかった」
とある。なぜご無沙汰していたかというと、
「あのときの事件を君(マダム)に無断で小説に書いたので、もし君が読んでいたら、きっと怒るだろうと思ったからさ」らしい。
このマダムの弟失踪事件を扱った、無断で書かれた小説は先日読んだ『その鉄柵の中で』である。
この作品のみどころは、比喩の面白さにもある。
「二人ともお仕着せのイーヴニングを脱がしてアッパッパを着せたら、場末の溝板の上で、アイスキャンデーを噛じりながら井戸端会議している連中と、大した違いはなかった。」
こういう文章ならよくわかるのだが、次に並べた比喩は、なんだかピッタリのような気もするが、よく考えてみると、見たこともないものを比喩に使っているので、本当はよくわからないはずなのである。
「駐車係はクレオパトラに呼ばれた奴隷のように、うやうやしく彼女のそばに駈けつけた。」
「日に灼けて、アスアン・ダムに働いているエジプト人のような顔色をしていた。」
「そこには満月の夜に踊り狂っているカイオア族と間違えられそうな、哀れなテーンエイジャーは一人も見あたらなかった。」
「馨をよく知っているらしいそのボーイは、ニクトクリス女王に仕える奴隷のように、恭しく一礼して立ち去ると、すぐにウイスキーのグラスを盆にのせて運んできた。」
犯罪をおかしてきた「松葉杖の男」は、クライマックスでは、地の文でさんざんな言われようをする。
「不具者としての歪められた人生感が、永年にわたる猜疑と卑屈に痛めつけられて、怒りの発作という力のおもむくままに、残忍な行為をくりかえしつつ、はかない満足にひたっている男、それがこの男の正体なのだ。救われない人間だった」
松葉杖の男になりかわって、作者に「おいおい、それは言い過ぎだろう」とたしなめたくなってくる。
鷲尾三郎の『虹の視角』を読んだ。1963年。
これは本格だ!3つの話が収録されている。
「虹の視角」
プロローグ
舞踏会で
呪われた結婚
事件勃発
不審な男の出現
涙ぐましい友情
犠牲の結婚
食堂の出来事
父と娘の情愛
花嫁の歎き
花嫁の最期
三木氏の出動
意外な事実の発見
現場調査
上杉の供述
酒場・ブルーリボン
菱川総裁の証言
謎の装束
千賀子の供述
その夜の集会
清元四季三葉艸
トリックの看破
事件解決
『黒い恐怖』巻末にこの本の作品紹介文が載っていた。
「元男爵家の令嬢が、新興財閥社長と晴れの結婚式を控えたその直前に、控室で何者かに絞殺されていた。奇怪にも、死体解剖の結果、令嬢の膣内に多量の膣液が分泌されていたのである。だが、膣内にも子宮外にも、精子を発見することは出来なかった」
と、これを読んだだけで、事件の真相があっさりわかってしまうのだから、現代はおそろしい。
主人公は三木氏で、こんな紹介をされている。
「彼が以前に北京に於て立証した、非凡な探偵的手腕や、また且て彼が「疑問の指環」に於て発表した、超人的な想像力と卓越した分析的才能を深く信じていた私は、云々」
デビュー作「疑問の指環」で活躍した三木氏による、オーソドックスな本格が展開される。
結婚式場における、「見えない人」たる神官による殺人、そして、その神官の衣裳を用意しえた人物こそ犯人、という、いや〜、オーソドックス!いいですねえ!
主要人物を集めて、三木氏が解明する事件の真相。オーソドックス!
「まぼろしの女」
親しき友
呪いの放送
生きていた女
力強い言葉
寝台車で
美人がいる筈だ
一葉の写真
京都へ
尋ね人
怪電話
無気味な呼び声
消えた女
三十七号室の怪
黒い影
秘密クラブ
おとし穴
意外の事実
朝の影
戦争の抑留所で死んだはずの妻、節子が生きていた?
新たに妻として千代子を迎えようとしていた津村は、節子に会って、事情を説明しようとする。
何度も節子から呼び出しがあるにもかかわらず、結局、会うことのできない二人。
まるで港のヨーコヨコハマヨコスカ。
このあたり、まさに「まぼろしの女」というタイトルにふさわしいサスペンス。
「影絵の女」
船出
破れた紙片
スリラー・クイズ
情熱の海
裸体の抱擁
報復手段
混濁の渦
犯罪のシルエット
双生児
事件の真相
破れてあちこちに虫食いの穴ができた新聞記事から、何が書かれてあったのかを推理するスリラークイズ。
その記事によると、ハリウッドに進出する女優、沖しのぶが殺人を犯したようだ。
ただ、だれを殺したのかは、破れていてわからない。
それを探偵小説をかじった者や、映画をかじった者たちがよってたかって推理合戦を繰り広げる。
船での旅のため、陸に着く3か月後まで真相はわからないのだ。
たとえば、こんな推理。
(妹尾プロデューサーが被害者だという説に対して)
「妹尾が君の説明するような、有力なプロデューサーだとしたら、無論ジャーナリストもよく知っているだろうし、それならこの新聞の標題にあるような、一方的な報道はしないんじゃないか?つまり沖しのぶという加害者だけを出さずに、きっと『沖しのぶ、プロデューサー妹尾竜二氏を殺害す』と、書くだろう?ところが新聞では、沖しのぶ一人だけしか名前を出していないんだ。だから、僕の推測では、あるいは被害者は、ネームバリューのない人間じゃないだろうかと思うんだよ」
たとえば、文字埋めのこんな推理。
「『しのぶの渡米』『プロデューサー妹尾竜二氏を』それから『としての地位を獲得せんとして』の三つを総合して考えてみると、その笠置ちか子っていうスタンド・インが、たしかに妹尾竜二を誘惑したらしいね。つまり『沖しのぶの渡米中に、プロデューサー妹尾竜二を誘惑し』だ。それから『ニューフェイス』か、それとも『スターとしての地位を獲得せんとして』になるわけだろう」
「ところがその次がわからないんだ。『子』『ていた』という二つは一体どうつづくんだろう?」
もう、ほとんど、『9マイルは遠すぎる』の域の推理作品。
面白かった!
あと興味深かったのは、この女優、沖しのぶは、「セシル・B・デミルにまねかれて、パラマウントで主演映画をとる契約が成立していた」と、いうような、無邪気な実名の使い方だ。以前に読んだ『黒の烙印』では、来日したピエール・カルダンを登場させていたし、同時代の著名人をそのまんま作中に登場させているのが、面白い。
これは本格だ!3つの話が収録されている。
「虹の視角」
プロローグ
舞踏会で
呪われた結婚
事件勃発
不審な男の出現
涙ぐましい友情
犠牲の結婚
食堂の出来事
父と娘の情愛
花嫁の歎き
花嫁の最期
三木氏の出動
意外な事実の発見
現場調査
上杉の供述
酒場・ブルーリボン
菱川総裁の証言
謎の装束
千賀子の供述
その夜の集会
清元四季三葉艸
トリックの看破
事件解決
『黒い恐怖』巻末にこの本の作品紹介文が載っていた。
「元男爵家の令嬢が、新興財閥社長と晴れの結婚式を控えたその直前に、控室で何者かに絞殺されていた。奇怪にも、死体解剖の結果、令嬢の膣内に多量の膣液が分泌されていたのである。だが、膣内にも子宮外にも、精子を発見することは出来なかった」
と、これを読んだだけで、事件の真相があっさりわかってしまうのだから、現代はおそろしい。
主人公は三木氏で、こんな紹介をされている。
「彼が以前に北京に於て立証した、非凡な探偵的手腕や、また且て彼が「疑問の指環」に於て発表した、超人的な想像力と卓越した分析的才能を深く信じていた私は、云々」
デビュー作「疑問の指環」で活躍した三木氏による、オーソドックスな本格が展開される。
結婚式場における、「見えない人」たる神官による殺人、そして、その神官の衣裳を用意しえた人物こそ犯人、という、いや〜、オーソドックス!いいですねえ!
主要人物を集めて、三木氏が解明する事件の真相。オーソドックス!
「まぼろしの女」
親しき友
呪いの放送
生きていた女
力強い言葉
寝台車で
美人がいる筈だ
一葉の写真
京都へ
尋ね人
怪電話
無気味な呼び声
消えた女
三十七号室の怪
黒い影
秘密クラブ
おとし穴
意外の事実
朝の影
戦争の抑留所で死んだはずの妻、節子が生きていた?
新たに妻として千代子を迎えようとしていた津村は、節子に会って、事情を説明しようとする。
何度も節子から呼び出しがあるにもかかわらず、結局、会うことのできない二人。
まるで港のヨーコヨコハマヨコスカ。
このあたり、まさに「まぼろしの女」というタイトルにふさわしいサスペンス。
「影絵の女」
船出
破れた紙片
スリラー・クイズ
情熱の海
裸体の抱擁
報復手段
混濁の渦
犯罪のシルエット
双生児
事件の真相
破れてあちこちに虫食いの穴ができた新聞記事から、何が書かれてあったのかを推理するスリラークイズ。
その記事によると、ハリウッドに進出する女優、沖しのぶが殺人を犯したようだ。
ただ、だれを殺したのかは、破れていてわからない。
それを探偵小説をかじった者や、映画をかじった者たちがよってたかって推理合戦を繰り広げる。
船での旅のため、陸に着く3か月後まで真相はわからないのだ。
たとえば、こんな推理。
(妹尾プロデューサーが被害者だという説に対して)
「妹尾が君の説明するような、有力なプロデューサーだとしたら、無論ジャーナリストもよく知っているだろうし、それならこの新聞の標題にあるような、一方的な報道はしないんじゃないか?つまり沖しのぶという加害者だけを出さずに、きっと『沖しのぶ、プロデューサー妹尾竜二氏を殺害す』と、書くだろう?ところが新聞では、沖しのぶ一人だけしか名前を出していないんだ。だから、僕の推測では、あるいは被害者は、ネームバリューのない人間じゃないだろうかと思うんだよ」
たとえば、文字埋めのこんな推理。
「『しのぶの渡米』『プロデューサー妹尾竜二氏を』それから『としての地位を獲得せんとして』の三つを総合して考えてみると、その笠置ちか子っていうスタンド・インが、たしかに妹尾竜二を誘惑したらしいね。つまり『沖しのぶの渡米中に、プロデューサー妹尾竜二を誘惑し』だ。それから『ニューフェイス』か、それとも『スターとしての地位を獲得せんとして』になるわけだろう」
「ところがその次がわからないんだ。『子』『ていた』という二つは一体どうつづくんだろう?」
もう、ほとんど、『9マイルは遠すぎる』の域の推理作品。
面白かった!
あと興味深かったのは、この女優、沖しのぶは、「セシル・B・デミルにまねかれて、パラマウントで主演映画をとる契約が成立していた」と、いうような、無邪気な実名の使い方だ。以前に読んだ『黒の烙印』では、来日したピエール・カルダンを登場させていたし、同時代の著名人をそのまんま作中に登場させているのが、面白い。
鷲尾三郎の『悪魔が見ていた』を読んだ。1960年。
タイトルはこれであっていると思う。
表紙はこのタイトルだが、奥付は『悪魔は見ていた』だった。
作品2つ収録。
以下、目次。
「悪魔が見ていた」
望楼上から
第二の殺人
カバンの中
米貨八千万円
呼び出し電報
貴婦人の訊問
凄い招待
警部の張込み
事件記者の感
治外法権
謎の自殺
タイプの手紙
秘書の媚態
誘いに乗って
第三の罠
ガーデン・パーティ
秘書と一所に
犯罪の巣
尾行者
生きていた運転手
高飛び寸前
天網恢々
消防士が望楼で火事の見張りしていたら、キキーッと車が止まって、男たちがもみあう現場を目撃してしまう。男は持っていたカバンを屋敷の敷地内に投げ入れ、刺されて車に乗せられて行ってしまう。消防士はカバンをこっそり取りに行く。
あれ?
これ、昨日読んだ「何処かで見ている」とまったく同じシチュエーションではないか。
ただ、長さは倍くらいになっていて、「何処かで」が本格だとすれば、この「悪魔が」はハードボイルドだった。少なくとも、主人公はタフガイで腕っぷし強いし、痛いめにもあいまくる。お決まりの頭殴られて気絶して、目ざめたときは体じゅうがバラバラになったような気分になる。
カバン投げ入れが全部お芝居だったところなど、本筋は「何処かで」と一緒。
「何処かで」が廃墟に住む女性という設定や古井戸に死体を落とすなど、本格テイストたっぷりなのに対して、「悪魔が」は組織的な犯罪であることが頭に残る。
「宿命」
手記の形式で明かされる、恐ろしいお話。
女に逆恨みした産婦人科医が、女に復讐する。
医師は、長い年月の経過と、天然痘のため、すっかり容貌が変っており、女は医師が昔の知り合いだと気づかない。
そして、なかなか子供が出来ない、という悩みを治療すると称して、医師は自分の精子を人工受精し、妊娠させるのである。
女は妊娠して喜ぶが、その夫は煩悶する。
もう、おわかりの通り、夫はかつて睾丸炎をわずらって、種なしになっていたのだ。
夫は自暴自棄になり、事の真相を知るや、医師に襲いかかり、逆に病院の窓から墜落死。女は衰弱して出産後に死んでしまう。
まあ、そういう出自を知らずに、うっかり血のつながった者どうしで結婚したいなどと言い出してしまう、「宿命」のタイトルにふさわしい古典的悲劇だった。
タイトルはこれであっていると思う。
表紙はこのタイトルだが、奥付は『悪魔は見ていた』だった。
作品2つ収録。
以下、目次。
「悪魔が見ていた」
望楼上から
第二の殺人
カバンの中
米貨八千万円
呼び出し電報
貴婦人の訊問
凄い招待
警部の張込み
事件記者の感
治外法権
謎の自殺
タイプの手紙
秘書の媚態
誘いに乗って
第三の罠
ガーデン・パーティ
秘書と一所に
犯罪の巣
尾行者
生きていた運転手
高飛び寸前
天網恢々
消防士が望楼で火事の見張りしていたら、キキーッと車が止まって、男たちがもみあう現場を目撃してしまう。男は持っていたカバンを屋敷の敷地内に投げ入れ、刺されて車に乗せられて行ってしまう。消防士はカバンをこっそり取りに行く。
あれ?
これ、昨日読んだ「何処かで見ている」とまったく同じシチュエーションではないか。
ただ、長さは倍くらいになっていて、「何処かで」が本格だとすれば、この「悪魔が」はハードボイルドだった。少なくとも、主人公はタフガイで腕っぷし強いし、痛いめにもあいまくる。お決まりの頭殴られて気絶して、目ざめたときは体じゅうがバラバラになったような気分になる。
カバン投げ入れが全部お芝居だったところなど、本筋は「何処かで」と一緒。
「何処かで」が廃墟に住む女性という設定や古井戸に死体を落とすなど、本格テイストたっぷりなのに対して、「悪魔が」は組織的な犯罪であることが頭に残る。
「宿命」
手記の形式で明かされる、恐ろしいお話。
女に逆恨みした産婦人科医が、女に復讐する。
医師は、長い年月の経過と、天然痘のため、すっかり容貌が変っており、女は医師が昔の知り合いだと気づかない。
そして、なかなか子供が出来ない、という悩みを治療すると称して、医師は自分の精子を人工受精し、妊娠させるのである。
女は妊娠して喜ぶが、その夫は煩悶する。
もう、おわかりの通り、夫はかつて睾丸炎をわずらって、種なしになっていたのだ。
夫は自暴自棄になり、事の真相を知るや、医師に襲いかかり、逆に病院の窓から墜落死。女は衰弱して出産後に死んでしまう。
まあ、そういう出自を知らずに、うっかり血のつながった者どうしで結婚したいなどと言い出してしまう、「宿命」のタイトルにふさわしい古典的悲劇だった。
鷲尾三郎の『黒い恐怖』を読んだ。
ネタバレしかしていないので要注意。
内容と看板が一致しない青樹ミステリーらしく「長編推理小説」と銘打ってあるが、中味は船曳警部補が登場する本格推理短編集である。
「白い蛇」
服部はくじで百万円を当て、その祝賀会をアパート清雅荘13号室で開いていた。
翌朝、その13号室で服部がガス中毒死していた。
服部は15号室の住人だったが、13号室の井関と部屋を交換して寝ていた。
その後、17号室で本荘が天井からゴム管を首にまきつけた状態で縊死。
服部は日頃から「金竜明神」を信仰しており、ご神体は巳だった。
服部の死は金竜明神の神罰であり、ガス中毒ではなく毒蛇の吐き出す妖気にあたったにちがいない、との憶測も出る。
ゴムホースがまるで蛇になったかのような怪事件。
ガスの供給が1日3回で時間が限られていた、というのは時代か?
窓ガラスの欠けた穴からホースつっこんでガスを注入して中毒死させる。その後、その犯人が別の人物にくびり殺される。
第一の事件の犯人が第二の事件の被害者、というパターン。
「悪魔の仮面」
これはあらすじが本に書いてあった。それをそのまま書くと。
評論家仁科教授が、生まれて初めての二日酔の重苦しい気持で目ざめたのは、見も知らぬ安アパートの一室であった。しかもかたわらには若い女が死んでいた。
昨夜は教授の出版記念会であった。クリスマスイヴの夜でもあった。友人に引づられるようにして珍らしく銀座に出た。けれども、それ以後の行動の記憶が何一つ仁科教授には思い出せないのである。教授は真青になってベッドからころがり出た。
「俺が殺したのではない」教授は己の心に叫び続けた。だがそれを教授以外に誰が証明し信じて呉れると言うのだ。情廉潔白な教授を、一体何者が落し入れようとしてたくらんだ犯罪であろうか。教授は自ら証明する以外にないと思った。
誤字もあるし、四苦八苦してまとめた感のある文章だ。
結局、教授が温厚篤実で、非のうちどころのないよき夫であったことが災いして、この殺人事件は起こったのだ。
犯人は教授の妻で、完璧すぎる夫に物足りなさを感じて、「殺人罪の嫌疑を受けて、恐怖と絶望に懊悩する夫をひそかに楽しんで見てやろうという残忍な異常心理」によって人殺しをしていたのだ。
そんなアホな!当然、犯人解明に関して、推理はいっさい無い。
なお、作中、教授が「クリスマス・イヴの悪魔だ!」と叫ぶシーンがある。鷲尾三郎には「クリスマス・イーヴの悪魔」と題する作品があるが、本作との関連(改題しただけ?)は現在探索中。
「あいびき」
恩人があいびきに使うから、と部屋を貸した男。
戻ってきたら、恩人が殺されていた。
元青線地帯の描写がいい。
「店の広さは、せいぜい畳二枚ぐらいで、そこに調理場と、スタンドと、そして客の床几とが並んでいた。調理場の端に、二階へ昇る階段が、まるで梯子のような急角度でかかっていた。シャツを脱いで、ランニング一枚になった客が、シュミーズの女と声を合わして、”パリ・カナイユ”のシャンソンを合唱していた。ショート・パンツにブラジャーだけの女が、赤い唇で愛嬌よく笑いながら、のれんの間から小路をうろつく客を物色していた。表の床几に腰を下ろして、スカートの裾から団扇で風を送り込んでいた女が、色っぽく微笑んだ。」
「焼酎と豚の臓物を焼く臭いが、狭い小路の内へ重く淀んで、船曳はへどを吐きそうな嫌悪を覚えた。淫らな女の哄笑が風通しのわるい沈んだ空気の中で、まるで彼に挑戦するかのように、毒々しい響きを帯びてきこえてきた。船曳はふとここに働いている女たちは、来年の夏にはどこにいるだろうと考えた。
−女が女の職場をぶっ潰そうとしている。そして、それに反抗し得ない彼女たちなんだ。しかし、踏まれても蹴られても、根強くはびころうとする雑草を、法律だけでもうまく根絶やしすることが出来るだろうか?−」
殺された恩人のあいびきの相手を中心に容疑がかけられるが、犯人は、部屋を貸した男の元女房。よりを戻そう、とやってきた元妻が、部屋の中でいちゃいちゃしている声を聞いて、嫉妬のあまり持ってきたウィスキーに毒を入れて、戸口に置いておいたのだ。
「何処かで見ている」
消防署の望楼から深夜の監視をしていた消防士。
廃墟の横で殺人らしき瞬間を目撃する。
刺された男は、廃墟の敷地内にカバンを放り込んでいた。
襲撃者と刺された男は車で逃げ去り、目撃した消防士はこっそり廃墟に忍び込んで、カバンを持ち帰る。
カバンを取り返そうと暗躍する一団。
廃墟の地下に潜んで住む女。
カバンの中味はいったい?なんと、あけてみたら、古いドタ靴!こんなものをなぜ取り返そうとしているのか?
襲撃とカバン投げ入れは全部、望楼からの見張りに目撃させるためのお芝居だった。
そうやっておびき出して、人殺しの犯人にしたてあげる罠だった。
「野獣の窓」
アパートの3階から2階へロープを使ってしのびこもうとして、墜落して死んだと思しき男。2階の女性を狙ったようだ。
だが、2階の女も殺されていた。
実は、1階の男が3階の男も2階の女も殺して、自分がおりるのに使ったロープは回収していた。
論理的な証明も、物的証拠もないため、被害者の女の妹がからだをはって囮になる。
ネタバレしかしていないので要注意。
内容と看板が一致しない青樹ミステリーらしく「長編推理小説」と銘打ってあるが、中味は船曳警部補が登場する本格推理短編集である。
「白い蛇」
服部はくじで百万円を当て、その祝賀会をアパート清雅荘13号室で開いていた。
翌朝、その13号室で服部がガス中毒死していた。
服部は15号室の住人だったが、13号室の井関と部屋を交換して寝ていた。
その後、17号室で本荘が天井からゴム管を首にまきつけた状態で縊死。
服部は日頃から「金竜明神」を信仰しており、ご神体は巳だった。
服部の死は金竜明神の神罰であり、ガス中毒ではなく毒蛇の吐き出す妖気にあたったにちがいない、との憶測も出る。
ゴムホースがまるで蛇になったかのような怪事件。
ガスの供給が1日3回で時間が限られていた、というのは時代か?
窓ガラスの欠けた穴からホースつっこんでガスを注入して中毒死させる。その後、その犯人が別の人物にくびり殺される。
第一の事件の犯人が第二の事件の被害者、というパターン。
「悪魔の仮面」
これはあらすじが本に書いてあった。それをそのまま書くと。
評論家仁科教授が、生まれて初めての二日酔の重苦しい気持で目ざめたのは、見も知らぬ安アパートの一室であった。しかもかたわらには若い女が死んでいた。
昨夜は教授の出版記念会であった。クリスマスイヴの夜でもあった。友人に引づられるようにして珍らしく銀座に出た。けれども、それ以後の行動の記憶が何一つ仁科教授には思い出せないのである。教授は真青になってベッドからころがり出た。
「俺が殺したのではない」教授は己の心に叫び続けた。だがそれを教授以外に誰が証明し信じて呉れると言うのだ。情廉潔白な教授を、一体何者が落し入れようとしてたくらんだ犯罪であろうか。教授は自ら証明する以外にないと思った。
誤字もあるし、四苦八苦してまとめた感のある文章だ。
結局、教授が温厚篤実で、非のうちどころのないよき夫であったことが災いして、この殺人事件は起こったのだ。
犯人は教授の妻で、完璧すぎる夫に物足りなさを感じて、「殺人罪の嫌疑を受けて、恐怖と絶望に懊悩する夫をひそかに楽しんで見てやろうという残忍な異常心理」によって人殺しをしていたのだ。
そんなアホな!当然、犯人解明に関して、推理はいっさい無い。
なお、作中、教授が「クリスマス・イヴの悪魔だ!」と叫ぶシーンがある。鷲尾三郎には「クリスマス・イーヴの悪魔」と題する作品があるが、本作との関連(改題しただけ?)は現在探索中。
「あいびき」
恩人があいびきに使うから、と部屋を貸した男。
戻ってきたら、恩人が殺されていた。
元青線地帯の描写がいい。
「店の広さは、せいぜい畳二枚ぐらいで、そこに調理場と、スタンドと、そして客の床几とが並んでいた。調理場の端に、二階へ昇る階段が、まるで梯子のような急角度でかかっていた。シャツを脱いで、ランニング一枚になった客が、シュミーズの女と声を合わして、”パリ・カナイユ”のシャンソンを合唱していた。ショート・パンツにブラジャーだけの女が、赤い唇で愛嬌よく笑いながら、のれんの間から小路をうろつく客を物色していた。表の床几に腰を下ろして、スカートの裾から団扇で風を送り込んでいた女が、色っぽく微笑んだ。」
「焼酎と豚の臓物を焼く臭いが、狭い小路の内へ重く淀んで、船曳はへどを吐きそうな嫌悪を覚えた。淫らな女の哄笑が風通しのわるい沈んだ空気の中で、まるで彼に挑戦するかのように、毒々しい響きを帯びてきこえてきた。船曳はふとここに働いている女たちは、来年の夏にはどこにいるだろうと考えた。
−女が女の職場をぶっ潰そうとしている。そして、それに反抗し得ない彼女たちなんだ。しかし、踏まれても蹴られても、根強くはびころうとする雑草を、法律だけでもうまく根絶やしすることが出来るだろうか?−」
殺された恩人のあいびきの相手を中心に容疑がかけられるが、犯人は、部屋を貸した男の元女房。よりを戻そう、とやってきた元妻が、部屋の中でいちゃいちゃしている声を聞いて、嫉妬のあまり持ってきたウィスキーに毒を入れて、戸口に置いておいたのだ。
「何処かで見ている」
消防署の望楼から深夜の監視をしていた消防士。
廃墟の横で殺人らしき瞬間を目撃する。
刺された男は、廃墟の敷地内にカバンを放り込んでいた。
襲撃者と刺された男は車で逃げ去り、目撃した消防士はこっそり廃墟に忍び込んで、カバンを持ち帰る。
カバンを取り返そうと暗躍する一団。
廃墟の地下に潜んで住む女。
カバンの中味はいったい?なんと、あけてみたら、古いドタ靴!こんなものをなぜ取り返そうとしているのか?
襲撃とカバン投げ入れは全部、望楼からの見張りに目撃させるためのお芝居だった。
そうやっておびき出して、人殺しの犯人にしたてあげる罠だった。
「野獣の窓」
アパートの3階から2階へロープを使ってしのびこもうとして、墜落して死んだと思しき男。2階の女性を狙ったようだ。
だが、2階の女も殺されていた。
実は、1階の男が3階の男も2階の女も殺して、自分がおりるのに使ったロープは回収していた。
論理的な証明も、物的証拠もないため、被害者の女の妹がからだをはって囮になる。
鷲尾三郎の『その鉄柵の中で』を読んだ。1962年。
長編ハードボイルド。
南郷探偵社の留守をあずかる小説家、牟礼順吉は、資産家の岩淵家から依頼を受ける。
娘、弥生の行方を探してほしいというのだ。女をさがせ!
岩淵家に隣接する老人ホームが全焼し、身許不明の遺体が発見される。この死体は誰なのか?
そんなとき、牟礼はもう1件依頼を受ける。
酒場オルフェの千春から、弟の亀井剛(ジゴロ業をいとなむ)の行方を探す依頼だ。
いろいろ探るうちに、「手をひけ」と暴力や金や色仕掛けで迫る一団。
渋谷界隈についての描写が興味深い。
「ハチ公が毎日主人を送迎していたころの渋谷駅は、いまから考えると、じつにのんびりとしていたことだろう。改札口から出てくる人を、順に一人々々、顔を見わけて、匂いが嗅ぎわけられた時代だった」
「この渋谷界隈は、猫がしっぽをふる音が聞こえるほどしずかだった。それが、戦後はすっかり様子が変ってしまって、やくざが縄張りを争い、暴力カフェーが通行人の懐を狙い、ポン引が巷に出没するような、下品で荒っぽい街に堕落してしまった。近くに住んでいたサラリーマンの家族たちは、恐れをなして郊外へ移住してしまって、その跡に、ビルや、映画館や、バーが建ちならび、店屋がいく度も代がわりをした。三月も行かないと、街の様子がすっかり変ってしまって、風呂屋の煙突の跡に、キャバレーのネオンが煌いていたりして、方角をたしかめるのに戸惑いさせられた。通行人がやたらと多すぎたし、それにもまして、狭い道路を往きかう車がやけに多すぎた」
一応、ストーリーを追えるだけの部分を登場人物のせりふから引用してみよう。
「亀井はどうやら殺されたらしいのですよ。その証拠を、ぼくは彼のアパートで発見しました。だが、屍体がなくなっていたのです。それで、ぼくの仕事は、屍体の発見と、下手人の捜査ということになりました。ところで、亀井は姿を消すまでは、旭東興業の従業員として”銀世界”で働いていたのです。ですから、ぼくとしては、何か姿を消すか、それとも消された事情が、”銀世界”にあるのではないかと想像したのです。それで、この間”銀世界”へ行きましたが、風間というマネージャーからは、強請とまちがえられて追っ払われました。今日の午後、浅川政吉という男が、西谷辰夫というチンピラと二人づれで、この事件から手を退くようにと言ってきました。しかも二十万円という金を持ってきましたよ」
「”銀世界”じゃ、麻薬の取引をしているってうわさが」
「亀井もその連中の一味なんだろう。それで薬を手に入れては、かもになりそうな女を物色して、薬で意識を不明にしておいてから、いかがわしい写真を撮って、それをタネにして金を強請っていたらしい」
「亀井に写真を撮られた女が、ぼくが行方を捜している、失踪中の女だったとは、全く想像もしなかったね」
「亀井がアパートで射殺された夜、依頼人の隣りにある老人ホームが全焼して、焼跡からは、得体のしれない屍体が一つ余分に発見されたんだ。屍体は完全に焼けていたので、男女の性別も、年令も区別もわからないんだよ。だから、その屍体は亀井剛だとも、また失踪中の娘だとも考えられるのだが、いまのところでは、どちらともきめ手がないんだ。おそらく、それを知っているのは、同じその夜、多摩川で溺死した、松宮音松という浮浪者だけだろう。つまり、老人ホームへ放火した犯人なんだから」
「おそらく誰かが、彼に金を握らして、屍体の証拠湮滅をはかる目的で、彼に放火させたんだろうと思うんだ。つまり、その人物がこの事件の主犯なんだよ」
さて、真相は。
「あれは、亀井とあたしが仕組んだお芝居よ。パパから五百万円を強請ったら、亀井に百万円を渡す約束だったわ。そのプランを思いついたのはあたしなのよ。ところが、パパがそれに気がついて、もう少し問いつめられたら、ばけの皮が剥げそうだったから、あたしはパパを威かすつもりで、ピストルを出したのが、はずみで引き金を引いてしまったの」(弥生)
「あたしが亀井を殺したのよ」(奈々恵)
奈々恵は浮浪者を使って亀井の屍体を処分しようとして、浮浪者の提案により、放火して焼いてしまう。そのあと、奈々恵は浮浪者を酔っぱらわせて川に突き落とす。
いやはや、なんちゅう姉妹だ。
「とにかく、あの家の連中は、精神状態が普通じゃないんだ」
「彼女(姉)は人を殺すことを、屁とも思わない女さ。空気銃で猫を撃ち殺して遊んでいるのからして、健全な精神状態じゃないよ。じつの妹さえも、自分の身代わりにして、罪を免れようとしたばかりか、最後には自分の手で殺そうとさえしたんだからね」
作中、こんな文章が出てくる。
「何か理屈抜きで、おもしろい小説が読みたいもんだね。どれもこれも、汚職や収賄ばかりじゃ、呼吸がつまりそうなんだよ」
社会派推理小説がブームだった時代への注文をこんな発言で示している。
そうした結果として、この作品は娯楽小説をつらぬき、こんな表現まで飛び出したのである。
「勇気があるんだったら、ズボンを脱いで見せて。生きたソーセージが、ドドンパを踊り出すんじゃないこと」
長編ハードボイルド。
南郷探偵社の留守をあずかる小説家、牟礼順吉は、資産家の岩淵家から依頼を受ける。
娘、弥生の行方を探してほしいというのだ。女をさがせ!
岩淵家に隣接する老人ホームが全焼し、身許不明の遺体が発見される。この死体は誰なのか?
そんなとき、牟礼はもう1件依頼を受ける。
酒場オルフェの千春から、弟の亀井剛(ジゴロ業をいとなむ)の行方を探す依頼だ。
いろいろ探るうちに、「手をひけ」と暴力や金や色仕掛けで迫る一団。
渋谷界隈についての描写が興味深い。
「ハチ公が毎日主人を送迎していたころの渋谷駅は、いまから考えると、じつにのんびりとしていたことだろう。改札口から出てくる人を、順に一人々々、顔を見わけて、匂いが嗅ぎわけられた時代だった」
「この渋谷界隈は、猫がしっぽをふる音が聞こえるほどしずかだった。それが、戦後はすっかり様子が変ってしまって、やくざが縄張りを争い、暴力カフェーが通行人の懐を狙い、ポン引が巷に出没するような、下品で荒っぽい街に堕落してしまった。近くに住んでいたサラリーマンの家族たちは、恐れをなして郊外へ移住してしまって、その跡に、ビルや、映画館や、バーが建ちならび、店屋がいく度も代がわりをした。三月も行かないと、街の様子がすっかり変ってしまって、風呂屋の煙突の跡に、キャバレーのネオンが煌いていたりして、方角をたしかめるのに戸惑いさせられた。通行人がやたらと多すぎたし、それにもまして、狭い道路を往きかう車がやけに多すぎた」
一応、ストーリーを追えるだけの部分を登場人物のせりふから引用してみよう。
「亀井はどうやら殺されたらしいのですよ。その証拠を、ぼくは彼のアパートで発見しました。だが、屍体がなくなっていたのです。それで、ぼくの仕事は、屍体の発見と、下手人の捜査ということになりました。ところで、亀井は姿を消すまでは、旭東興業の従業員として”銀世界”で働いていたのです。ですから、ぼくとしては、何か姿を消すか、それとも消された事情が、”銀世界”にあるのではないかと想像したのです。それで、この間”銀世界”へ行きましたが、風間というマネージャーからは、強請とまちがえられて追っ払われました。今日の午後、浅川政吉という男が、西谷辰夫というチンピラと二人づれで、この事件から手を退くようにと言ってきました。しかも二十万円という金を持ってきましたよ」
「”銀世界”じゃ、麻薬の取引をしているってうわさが」
「亀井もその連中の一味なんだろう。それで薬を手に入れては、かもになりそうな女を物色して、薬で意識を不明にしておいてから、いかがわしい写真を撮って、それをタネにして金を強請っていたらしい」
「亀井に写真を撮られた女が、ぼくが行方を捜している、失踪中の女だったとは、全く想像もしなかったね」
「亀井がアパートで射殺された夜、依頼人の隣りにある老人ホームが全焼して、焼跡からは、得体のしれない屍体が一つ余分に発見されたんだ。屍体は完全に焼けていたので、男女の性別も、年令も区別もわからないんだよ。だから、その屍体は亀井剛だとも、また失踪中の娘だとも考えられるのだが、いまのところでは、どちらともきめ手がないんだ。おそらく、それを知っているのは、同じその夜、多摩川で溺死した、松宮音松という浮浪者だけだろう。つまり、老人ホームへ放火した犯人なんだから」
「おそらく誰かが、彼に金を握らして、屍体の証拠湮滅をはかる目的で、彼に放火させたんだろうと思うんだ。つまり、その人物がこの事件の主犯なんだよ」
さて、真相は。
「あれは、亀井とあたしが仕組んだお芝居よ。パパから五百万円を強請ったら、亀井に百万円を渡す約束だったわ。そのプランを思いついたのはあたしなのよ。ところが、パパがそれに気がついて、もう少し問いつめられたら、ばけの皮が剥げそうだったから、あたしはパパを威かすつもりで、ピストルを出したのが、はずみで引き金を引いてしまったの」(弥生)
「あたしが亀井を殺したのよ」(奈々恵)
奈々恵は浮浪者を使って亀井の屍体を処分しようとして、浮浪者の提案により、放火して焼いてしまう。そのあと、奈々恵は浮浪者を酔っぱらわせて川に突き落とす。
いやはや、なんちゅう姉妹だ。
「とにかく、あの家の連中は、精神状態が普通じゃないんだ」
「彼女(姉)は人を殺すことを、屁とも思わない女さ。空気銃で猫を撃ち殺して遊んでいるのからして、健全な精神状態じゃないよ。じつの妹さえも、自分の身代わりにして、罪を免れようとしたばかりか、最後には自分の手で殺そうとさえしたんだからね」
作中、こんな文章が出てくる。
「何か理屈抜きで、おもしろい小説が読みたいもんだね。どれもこれも、汚職や収賄ばかりじゃ、呼吸がつまりそうなんだよ」
社会派推理小説がブームだった時代への注文をこんな発言で示している。
そうした結果として、この作品は娯楽小説をつらぬき、こんな表現まで飛び出したのである。
「勇気があるんだったら、ズボンを脱いで見せて。生きたソーセージが、ドドンパを踊り出すんじゃないこと」
堀井ゆき@電脳戦隊socio5、『黒の烙印』
2010年4月14日 読書出勤前に、あめりか村socio「電脳戦隊socio5」をのぞく。
時間の都合で堀井ゆきのステージだけちゃんと見れた。
他にだれが出ていたのかチェックしていなかったが、じゅうぶん満足。
そのまま、仕事へ。
読んだ本は、鷲尾三郎の『黒の烙印』。1960年。
長編ハードボイルド。
以下、目次。
縁起のわるい女
屍体のある部屋
疑惑の眼
メリー・クリスマス
頭の中のトラクター
訪問者
待合わせ
冠木門の家
彼岸花とガーベラ
屍体もう一つ
一連番号の札束
事件の側面
雪と氷の中の死
0.32口径ラーマ
建物の絵
指輪
女を追って
死霊
セールスマンの死
登攀者
過去への道
シャネルの五番
首魁の影
役者は揃った
残された疑問
縁起のいい女
帝都日報社のカメラマン、槇健策は、「縁起のわるい女」に出会った(板倉とし子)。婚約者が次々と死んでいくのだ。あれ?これ、『黄昏の悪魔』?
槇はその女を自宅まで送り、うっかり鍵を持ってきてしまったので、返しに行ったら、なんと、そこには、縁起のわるい女とはまったく別人の死体(八尾さかえ)。
縁起のわるい板倉とし子は、八尾さかえの兄、八尾保の愛人だった。もちろん、八尾保は縁起のわるいとし子と婚約してまもなく、死んでしまっている。
犯人は、遺産めあてで、犯行を重ねていたのだ。
スルスルッと読める。
犯人が誰だったのかは、読んでのお楽しみ。と、いうか、別にだれが犯人でも一緒みたいな話だった。
時間の都合で堀井ゆきのステージだけちゃんと見れた。
他にだれが出ていたのかチェックしていなかったが、じゅうぶん満足。
そのまま、仕事へ。
読んだ本は、鷲尾三郎の『黒の烙印』。1960年。
長編ハードボイルド。
以下、目次。
縁起のわるい女
屍体のある部屋
疑惑の眼
メリー・クリスマス
頭の中のトラクター
訪問者
待合わせ
冠木門の家
彼岸花とガーベラ
屍体もう一つ
一連番号の札束
事件の側面
雪と氷の中の死
0.32口径ラーマ
建物の絵
指輪
女を追って
死霊
セールスマンの死
登攀者
過去への道
シャネルの五番
首魁の影
役者は揃った
残された疑問
縁起のいい女
帝都日報社のカメラマン、槇健策は、「縁起のわるい女」に出会った(板倉とし子)。婚約者が次々と死んでいくのだ。あれ?これ、『黄昏の悪魔』?
槇はその女を自宅まで送り、うっかり鍵を持ってきてしまったので、返しに行ったら、なんと、そこには、縁起のわるい女とはまったく別人の死体(八尾さかえ)。
縁起のわるい板倉とし子は、八尾さかえの兄、八尾保の愛人だった。もちろん、八尾保は縁起のわるいとし子と婚約してまもなく、死んでしまっている。
犯人は、遺産めあてで、犯行を重ねていたのだ。
スルスルッと読める。
犯人が誰だったのかは、読んでのお楽しみ。と、いうか、別にだれが犯人でも一緒みたいな話だった。
角田喜久男の『黄昏の悪魔』を読んだ。長編と短編2本が収録されている。
「黄昏の悪魔」
黒外套の男
第9号室
血まみれた沓下
酔いどれ楽師
闇に浮く顔
断崖のある屋根
狂女
片桐家の家風
蠢くもの
開かずの部屋
潮騒
滅びゆくもの
江原ユリは、就職しても妙な噂や密告ですぐクビにされ、やっと届いた入社合格通知は不合格のものとすりかえられ、なけなしの金で食堂に入ったら財布ごと荷物を隠されてしまう。
なにものかが彼女を不幸のどん底に落とそうとしているようだ。
あげくのはてに手込めにされそうになったとき、どこからか「黄昏のブルース」が聞こえてくる。そして、彼女を襲っていた男は殺されてしまう。
彼女はなぜ何者かからひどいめにあわされ、また、誰が彼女を影ながら救っているのか?
主人公の女性がひどい目にあっている前半の導入部は、もう昼ドラ真っ青の面白さ。
時代的な言い回しもあるので、現代ミステリーなのに、時代小説と少女小説のハイブリッドを読んでいるような気分になった。
ときたま、登場人物のせりふによって、物語が説明的にまとめられたり、明かされたりする。
たとえば。
「もし俺が警察の手におちるようなことがあったら、この時は、洗いざらい皆ぶちまけてしまう。新宿で焼死したユリの両親が、実はニセ者であったということや、父親に化けたのは先日殺された職員の吉谷であり、母親の衣裳をつけて人目をはばかったのは光川、お前だったということや、当時、防空服一点張りの時代には、平服姿を車の窓からちらっと見せただけで、結構、それと思わせ、化け通せもしたし、新宿へついた晩、うまく空襲があったので年頃な死骸に二人の服を着せ、火の中へ投げこんで顔を焼きつぶそうとしている所を発見され、ついその警防団員を殴り殺してしまったということなどをね」
よくぞペラペラと語ってくださいました!
この事件のキーパーソンとなる片桐という男(家)は、「生まれながらにして、思ったことは必ず通す、いや通る、という生活をおくって」来た。ジャイアンだ。その片桐が田鶴子という女性に惚れて、自分のものにしようとした。ほとんどの男は尻尾をまいて田鶴子のそばから離れたが、ただ1人、江原春策という男だけが片桐と争って、2人で失踪する。片桐は激怒し、江原春策をとらえ、売国奴スパイを処刑するという勝手な名目で私刑にかける。そのときに葬送曲がわりに流されたのが「黄昏のブルース」だったのだ。
その後、片桐は負債をかかえ、江原春策の遺産を狙って、引き揚げてきたその娘ユリにいろんなちょっかいをかけていたのである。片桐はユリを絶望の淵においやって死亡させ、ユリの叔母である和江夫人に遺産を相続させ、その財産を自由にしようとしていたのだ。
さて、その私刑にかけられて死んだはずの春策が実は生き延びていたのではないか、という疑いが出てきた。片桐によるユリ絶望死計画をことごとく妨害する者がいるのだ。
さて、真相は。
ユリを救おうとして殺人にまで手を染めていたのは、やはり、ユリの父親であった。
ただし、それはユリの実の父親であって、春策ではなかった。
おお、最後の最後までメロドラマ!
「私は誰だ」
早苗は正気づいたとき、記憶を失っていた。
すぐ近くの畑の側の路傍にはナイフで刺し殺された男の死体が転がっていた。
自分が殺したのか?
真相は、よくある男女の痴情のもつれによる殺人。犯人によって殴られて昏倒した女性がコートを着せ替えられて、身元がごっちゃになってしまっていた。
「緑眼虫」
こども達に「おばけ屋」とあだなをつけられた無気味な家。
そこに住む男は非人間的で冷酷な印象の人物で、玉虫の背のように緑色の燐光を放ってぎらぎらと光る不思議な眼をしていた。(緑眼虫のタイトルの所以)
その「おばけ屋」をこっそり覗いてみると、中に見えるのは、様々な動物の剥製に、解剖人形。
雰囲気のある怪奇な物語が、実はクスリがらみであったというのが真相。
「黄昏の悪魔」
黒外套の男
第9号室
血まみれた沓下
酔いどれ楽師
闇に浮く顔
断崖のある屋根
狂女
片桐家の家風
蠢くもの
開かずの部屋
潮騒
滅びゆくもの
江原ユリは、就職しても妙な噂や密告ですぐクビにされ、やっと届いた入社合格通知は不合格のものとすりかえられ、なけなしの金で食堂に入ったら財布ごと荷物を隠されてしまう。
なにものかが彼女を不幸のどん底に落とそうとしているようだ。
あげくのはてに手込めにされそうになったとき、どこからか「黄昏のブルース」が聞こえてくる。そして、彼女を襲っていた男は殺されてしまう。
彼女はなぜ何者かからひどいめにあわされ、また、誰が彼女を影ながら救っているのか?
主人公の女性がひどい目にあっている前半の導入部は、もう昼ドラ真っ青の面白さ。
時代的な言い回しもあるので、現代ミステリーなのに、時代小説と少女小説のハイブリッドを読んでいるような気分になった。
ときたま、登場人物のせりふによって、物語が説明的にまとめられたり、明かされたりする。
たとえば。
「もし俺が警察の手におちるようなことがあったら、この時は、洗いざらい皆ぶちまけてしまう。新宿で焼死したユリの両親が、実はニセ者であったということや、父親に化けたのは先日殺された職員の吉谷であり、母親の衣裳をつけて人目をはばかったのは光川、お前だったということや、当時、防空服一点張りの時代には、平服姿を車の窓からちらっと見せただけで、結構、それと思わせ、化け通せもしたし、新宿へついた晩、うまく空襲があったので年頃な死骸に二人の服を着せ、火の中へ投げこんで顔を焼きつぶそうとしている所を発見され、ついその警防団員を殴り殺してしまったということなどをね」
よくぞペラペラと語ってくださいました!
この事件のキーパーソンとなる片桐という男(家)は、「生まれながらにして、思ったことは必ず通す、いや通る、という生活をおくって」来た。ジャイアンだ。その片桐が田鶴子という女性に惚れて、自分のものにしようとした。ほとんどの男は尻尾をまいて田鶴子のそばから離れたが、ただ1人、江原春策という男だけが片桐と争って、2人で失踪する。片桐は激怒し、江原春策をとらえ、売国奴スパイを処刑するという勝手な名目で私刑にかける。そのときに葬送曲がわりに流されたのが「黄昏のブルース」だったのだ。
その後、片桐は負債をかかえ、江原春策の遺産を狙って、引き揚げてきたその娘ユリにいろんなちょっかいをかけていたのである。片桐はユリを絶望の淵においやって死亡させ、ユリの叔母である和江夫人に遺産を相続させ、その財産を自由にしようとしていたのだ。
さて、その私刑にかけられて死んだはずの春策が実は生き延びていたのではないか、という疑いが出てきた。片桐によるユリ絶望死計画をことごとく妨害する者がいるのだ。
さて、真相は。
ユリを救おうとして殺人にまで手を染めていたのは、やはり、ユリの父親であった。
ただし、それはユリの実の父親であって、春策ではなかった。
おお、最後の最後までメロドラマ!
「私は誰だ」
早苗は正気づいたとき、記憶を失っていた。
すぐ近くの畑の側の路傍にはナイフで刺し殺された男の死体が転がっていた。
自分が殺したのか?
真相は、よくある男女の痴情のもつれによる殺人。犯人によって殴られて昏倒した女性がコートを着せ替えられて、身元がごっちゃになってしまっていた。
「緑眼虫」
こども達に「おばけ屋」とあだなをつけられた無気味な家。
そこに住む男は非人間的で冷酷な印象の人物で、玉虫の背のように緑色の燐光を放ってぎらぎらと光る不思議な眼をしていた。(緑眼虫のタイトルの所以)
その「おばけ屋」をこっそり覗いてみると、中に見えるのは、様々な動物の剥製に、解剖人形。
雰囲気のある怪奇な物語が、実はクスリがらみであったというのが真相。
ベラ・ツインズ@タワーレコード難波店、『アトリエ殺人事件』
2010年4月9日 読書
タワーレコード難波店で、WWEのディーバ「ベラ・ツインズ」のインストアイベント。
ブリーとニッキーの双子レスラー。双子ならではの技の連携もある。(イベントではレスラーらしきことはとくに何もしなかったけど)
トークとサインシートプレゼントと握手と3ショットポラ撮影。
トークでは、レッスルマニアを中心に、殿堂入りした猪木のオーラがすごかったとか、アンダーテイカーとショーン・マイケルズの試合が昨年以上によかったとか、マネー・イン・ザ・バンク戦がよかった、とか。両国国技館でのサマースラムツアーの宣伝も。
ディーバが何かスムーズに行なおうとしていたら、ついつい「エクスキューズミー!」とヴィッキー・ゲレロが妨害するんじゃないか、と期待してしまうな。
高原弘吉の『アトリエ殺人事件』を読んだ。
『中1コース』などに掲載された4つの話が入っている。
(でも、あいにくと、僕は『中1時代』派だったんだなあ)
ネタバレしかしていないので、要注意。
以下、目次。
「アトリエ殺人事件」
ねえさんの恋人
死体
捜査本部
容疑者
シャツと万年筆
アトリエで刺し殺された被害者。
最初に主人公の少年が目撃したのは、死んだふり。
死体発見のときに持って行ったシャツを死体が着ていた。
電灯がついていたかどうかもポイント。
「双眼鏡は知っていた」
秘密の楽しみ
幻覚症状!?
あるトリック
江戸川乱歩の「押絵と旅する男」と松本清張の「点と線」がひきあいに出される。
双眼鏡で犯行の瞬間を目撃するが、そんな事件の報道はいっさいなかった。
ひょっとして、テレビ画面を見たんじゃないか、と疑うが、そんな番組はそのとき放送していなかった。
じゃあ、ビデオかも、と思うのは普通の考えだが、こんな展開になる。
「あなたのうちにテレビのビデオ装置はない?」
「録画しておいて、いつでも好きなときに見られるって、あれですか?」
「ええ。そうなの。おたくにあるんじゃない?」
「そんなぜいたくなものありません」
そうなのだ。時代はおよそ40年ほど前の話だ。ビデオは一般家庭に普及していなかったのだ。
目撃されたのは、あいていた窓から見えたドラマの撮影シーンだった。
「かくしマイクのわな」
ウインクした看板
記憶喪失
乗り込む
J・エドワード
短波放送の暗号
産業スパイもの。
かくしマイクを仕掛けたのは、名探偵千里悠介の側。
2つ仕掛けておき、1つは簡単に見つかるようにしておく。
敵はわざと間違った情報を与えようとするが、もう1つ仕掛けた隠しマイクが正しい情報をキャッチしていた。
大きな顔を描いた看板の目の部分が開いて、そこから覗き見して情報を盗もうとしていたのが、最初の章の「ウインク」の真相。
「古屋敷ののろい」
雨の中で木を切る男
調査に乗り出す
古屋敷の秘密
ナゾの嘉永元年八月二日
くず物の宝石
宝のありかを記したと思しき暗号解読もの。
名探偵千里悠介がこの話でも活躍する。
映画「裏窓」(双眼鏡、好きだねえ)と、ダンセイニの「二つのソース壜」が引用される。(穴掘ったり、木を切ったりするけど、死体を埋めるわけでも、また、腹ごなしの運動でもなく、宝を探していた)
暗号は、ある日の日付と、一間の棒、七つ、堅、木。
木を切っていたのは、「堅」と「木」をあわせて「樫」だと推理していたから。
実際は、七つどきに棒を立てて、その影が示したところに隠してあった。
ブリーとニッキーの双子レスラー。双子ならではの技の連携もある。(イベントではレスラーらしきことはとくに何もしなかったけど)
トークとサインシートプレゼントと握手と3ショットポラ撮影。
トークでは、レッスルマニアを中心に、殿堂入りした猪木のオーラがすごかったとか、アンダーテイカーとショーン・マイケルズの試合が昨年以上によかったとか、マネー・イン・ザ・バンク戦がよかった、とか。両国国技館でのサマースラムツアーの宣伝も。
ディーバが何かスムーズに行なおうとしていたら、ついつい「エクスキューズミー!」とヴィッキー・ゲレロが妨害するんじゃないか、と期待してしまうな。
高原弘吉の『アトリエ殺人事件』を読んだ。
『中1コース』などに掲載された4つの話が入っている。
(でも、あいにくと、僕は『中1時代』派だったんだなあ)
ネタバレしかしていないので、要注意。
以下、目次。
「アトリエ殺人事件」
ねえさんの恋人
死体
捜査本部
容疑者
シャツと万年筆
アトリエで刺し殺された被害者。
最初に主人公の少年が目撃したのは、死んだふり。
死体発見のときに持って行ったシャツを死体が着ていた。
電灯がついていたかどうかもポイント。
「双眼鏡は知っていた」
秘密の楽しみ
幻覚症状!?
あるトリック
江戸川乱歩の「押絵と旅する男」と松本清張の「点と線」がひきあいに出される。
双眼鏡で犯行の瞬間を目撃するが、そんな事件の報道はいっさいなかった。
ひょっとして、テレビ画面を見たんじゃないか、と疑うが、そんな番組はそのとき放送していなかった。
じゃあ、ビデオかも、と思うのは普通の考えだが、こんな展開になる。
「あなたのうちにテレビのビデオ装置はない?」
「録画しておいて、いつでも好きなときに見られるって、あれですか?」
「ええ。そうなの。おたくにあるんじゃない?」
「そんなぜいたくなものありません」
そうなのだ。時代はおよそ40年ほど前の話だ。ビデオは一般家庭に普及していなかったのだ。
目撃されたのは、あいていた窓から見えたドラマの撮影シーンだった。
「かくしマイクのわな」
ウインクした看板
記憶喪失
乗り込む
J・エドワード
短波放送の暗号
産業スパイもの。
かくしマイクを仕掛けたのは、名探偵千里悠介の側。
2つ仕掛けておき、1つは簡単に見つかるようにしておく。
敵はわざと間違った情報を与えようとするが、もう1つ仕掛けた隠しマイクが正しい情報をキャッチしていた。
大きな顔を描いた看板の目の部分が開いて、そこから覗き見して情報を盗もうとしていたのが、最初の章の「ウインク」の真相。
「古屋敷ののろい」
雨の中で木を切る男
調査に乗り出す
古屋敷の秘密
ナゾの嘉永元年八月二日
くず物の宝石
宝のありかを記したと思しき暗号解読もの。
名探偵千里悠介がこの話でも活躍する。
映画「裏窓」(双眼鏡、好きだねえ)と、ダンセイニの「二つのソース壜」が引用される。(穴掘ったり、木を切ったりするけど、死体を埋めるわけでも、また、腹ごなしの運動でもなく、宝を探していた)
暗号は、ある日の日付と、一間の棒、七つ、堅、木。
木を切っていたのは、「堅」と「木」をあわせて「樫」だと推理していたから。
実際は、七つどきに棒を立てて、その影が示したところに隠してあった。
城昌幸の『死者の殺人』を読んだ。1960年。
これ、すごい!
21世紀の新しいミステリーと言っても通用する素晴らしさ!
ネタバレするので、未読の人は、なんとかして読んでください。
作品紹介文には、こうある。
「『余の臨終に立会った者に、余の遺産を贈る…』と書かれた不思議な招待状!!その招待状を手に湘南の寒村に集まる者7人…しかし危篤の筈の男は前日忽然と姿を消している…不気味な巫女、鬼気迫る幽霊屋敷!!」
招待状につられて集まった7人だったが、かんじんの主がいない。食事だけは毎日届けられる。嵐の山荘、というわけではないので、帰ろうと思えばいつでも帰れるのだが、主の臨終の時点で屋敷にいないと遺産分配にあずかれないので、みんな居残るのだ。
屋敷に呼ばれた者たちは、この屋敷の主にとっての仇であって、集めて弾劾されるだけの動機はあったのである。
言ってるしりから、1人が首吊り死体になって発見される。
こういうシチュエーションだと、連続殺人が起こるのがパターンだ。
作中の人物もそれを口にする。
「これ、遺産争いじアねえかと、おれ、思うんだ」
「遺産争いねえ?」
「そうだろ?一人でもすくない方が、余計、貰えるわけだろ?だからよオ。片ッぱしから殺していくんだよオ」
(中略)
「そのうち、次ぎつぎと、ここに居る連中、みんな殺されちゃうンだよオ」
(中略)
「推理小説には、連続殺人、多いぞオ。おれ、読んだんだ」
(中略)
「横溝の『悪魔の手毬唄』、凄いぞオ。二人も三人も殺されちゃってよオ…」
これはメフィスト賞作家の作品ではない。50年前の小説なのだ。なんだ、この若いセンスは!(ただし、「だいじょうび」とか「カックン」など、当時の流行語が時代を如実に暴露してしまうけど)
屋敷では死者も出るし、幽霊も出る。これは候補者を減らすための策謀なのか?
そして、その真相たるや、ひっくりかえるほどのビックリであった。
みんなが集まったときに、屋敷の主は、医学的には既に死んでいた。
それにつきそっていた女性が、ヨーガの秘法で、肉体的には死んでいるがまだ生きている精神をテレパシーで感じ取って、その命令にしたがって事件を起こしていたのだ。
つまり、タイトルどおりの「死者の殺人」!
テレパシーで命令を受けていた巫女的体質の実行犯は、したがって真犯人ではない、とされる。
また、幽霊騒ぎは、候補者をこわがらせて追い払うためのいたずらであり、自殺とみられたのは正真正銘の自殺、事故とみられたのは正真正銘の事故。心臓に負担を与えられて苦しんだ人物(死んだみたいな描写)は命をとりとめていたことがラストで明かされる。巫女のしわざもせいぜいが殺人未遂だったのだ。
タイトルに偽りありか!正しくは「死者の殺人未遂」!
これは「うる星やつら」の1エピソードではない。50年前の小説なのだ。
おまけに、あてにしていた遺産も実はあんまりなくて、屋敷に集まった者たちに食事を用意した分で使い果たされていたのだ。
なんと現代ミステリー的な小説なのか!
中島河太郎も解説でこうしめくくる。
「われわれ読者も、ヨガの行者の絶妙な行法に、しばしば異次元に連れ去られる面持になるだろう。城氏の面目を発揮したユニークな一巻である」
これ、すごい!
21世紀の新しいミステリーと言っても通用する素晴らしさ!
ネタバレするので、未読の人は、なんとかして読んでください。
作品紹介文には、こうある。
「『余の臨終に立会った者に、余の遺産を贈る…』と書かれた不思議な招待状!!その招待状を手に湘南の寒村に集まる者7人…しかし危篤の筈の男は前日忽然と姿を消している…不気味な巫女、鬼気迫る幽霊屋敷!!」
招待状につられて集まった7人だったが、かんじんの主がいない。食事だけは毎日届けられる。嵐の山荘、というわけではないので、帰ろうと思えばいつでも帰れるのだが、主の臨終の時点で屋敷にいないと遺産分配にあずかれないので、みんな居残るのだ。
屋敷に呼ばれた者たちは、この屋敷の主にとっての仇であって、集めて弾劾されるだけの動機はあったのである。
言ってるしりから、1人が首吊り死体になって発見される。
こういうシチュエーションだと、連続殺人が起こるのがパターンだ。
作中の人物もそれを口にする。
「これ、遺産争いじアねえかと、おれ、思うんだ」
「遺産争いねえ?」
「そうだろ?一人でもすくない方が、余計、貰えるわけだろ?だからよオ。片ッぱしから殺していくんだよオ」
(中略)
「そのうち、次ぎつぎと、ここに居る連中、みんな殺されちゃうンだよオ」
(中略)
「推理小説には、連続殺人、多いぞオ。おれ、読んだんだ」
(中略)
「横溝の『悪魔の手毬唄』、凄いぞオ。二人も三人も殺されちゃってよオ…」
これはメフィスト賞作家の作品ではない。50年前の小説なのだ。なんだ、この若いセンスは!(ただし、「だいじょうび」とか「カックン」など、当時の流行語が時代を如実に暴露してしまうけど)
屋敷では死者も出るし、幽霊も出る。これは候補者を減らすための策謀なのか?
そして、その真相たるや、ひっくりかえるほどのビックリであった。
みんなが集まったときに、屋敷の主は、医学的には既に死んでいた。
それにつきそっていた女性が、ヨーガの秘法で、肉体的には死んでいるがまだ生きている精神をテレパシーで感じ取って、その命令にしたがって事件を起こしていたのだ。
つまり、タイトルどおりの「死者の殺人」!
テレパシーで命令を受けていた巫女的体質の実行犯は、したがって真犯人ではない、とされる。
また、幽霊騒ぎは、候補者をこわがらせて追い払うためのいたずらであり、自殺とみられたのは正真正銘の自殺、事故とみられたのは正真正銘の事故。心臓に負担を与えられて苦しんだ人物(死んだみたいな描写)は命をとりとめていたことがラストで明かされる。巫女のしわざもせいぜいが殺人未遂だったのだ。
タイトルに偽りありか!正しくは「死者の殺人未遂」!
これは「うる星やつら」の1エピソードではない。50年前の小説なのだ。
おまけに、あてにしていた遺産も実はあんまりなくて、屋敷に集まった者たちに食事を用意した分で使い果たされていたのだ。
なんと現代ミステリー的な小説なのか!
中島河太郎も解説でこうしめくくる。
「われわれ読者も、ヨガの行者の絶妙な行法に、しばしば異次元に連れ去られる面持になるだろう。城氏の面目を発揮したユニークな一巻である」
木々高太郎の『熊笹にかくれて』を読んだ。1960年
巻末の作品紹介文には、こうある。
「殺人の罪で死刑を宣告された男…最高裁でも遂に上告棄却…死刑確定…しかしその男の犯行に不審をいだいた二人の教授が大心池博士の協力で次々と謎の糸をたぐり寄せ意外の結論…久々の快作!!」
以下、目次
箴言
人物展望
1.序曲
2.第一の事件
3.第二の事件
4.再審請求
5.心理法則
6.終曲
ハンセン病差別による「藤本事件」に題材をとった作品で、前半は名前等は変えてあるが、事件のあらましをたどっている。
容疑者としてとらえられた男、賀毛辰治がハンセン氏病だということで、「検事も判事もろくに証拠品を調べていない位、辰治に手を触れることは恐れていたのである。ピンセットやあり合わせの鋏でその証拠品を遠くから引っくりかえす程度であった」
さらに裁判官と法定弁護士だけで、傍聴者もない法廷で裁かれる。
証人になるべき人物は、ハンセン氏病患者と一緒にいたと思われるのが嫌で証言せず、アリバイが証明できない。
また、「辰治はライ病だ。どうせ、この世の中に帰って来られない男だ。そういうわけなら、せめて死刑になっても、いやなこの世を、少し早く去るというだけだ、他の人間ではないにしてもライ病一人位はええ」とする意識もある。
八方ふさがりになってしまい、あと、彼を救うには、真犯人をつきとめるほかない、という結論になり、後半の物語がはじまる。
「箴言」には次のような文章がある。
「若し現実に相似たる物語あり、その前半は描かれたるも、尚後続の見出さるることなくして停頓し居るものあらば、試みにこの物語の構想を参照せば、更に進むるを得るものあらむか。作者これを知らず」
作者は藤本事件のあまりの理不尽な展開に黙っておれなかったのだろう。
1870年頃にノルウェーのハンセン医師がライ菌を発見し、遺伝する病気ではなく、他の伝染病と同様に治療できるものであることが確定した。ライ病に対する忌わしい迷信、嫌悪を一般大衆から除かねばならない契機は1870年代に既にはじまっていたはずだったのである。
前半の部分は、憤りとともに社会的な熱い意識で読めるのだが、後半に入って、「真犯人は別にいる。それをつきとめよう」とする展開になると、その提案自体がなされることをもって本作の目的を達してしまった感がある。したがって、本書ではフィクション上の一応の犯人があばかれるが、それはつけたしのように思えた。
賀毛辰治は、取り調べ中、一度自供し、それをすぐに否定している。
いったん自分の罪を認めるような発言をしたのは何故か、ということが、本書で一番推理小説らしい箇所だった。
辰治はかつて、ある女性をライ病疑惑のデマをとばして、自殺させてしまったことがある。そのときの罪の意識、良心の呵責が、厳しい取り調べの際に自分を罰する意識として浮かびあがってきたのだ。誰も辰治の味方でない、という絶望の心境とあいまって、自暴自棄の発言になったのだ。
う〜む。
たしかに推理小説としては弱いけど、実際にはありうる話だ。
中島河太郎による解説は、次のような文章でしめくくられている。
「探偵作家クラブの例会の土曜会で、木々氏の愛生園視察談を聴いてから、かなりの年月を経た。救癩事業に熱意をこめて語られたので、今も談話の端々を覚えているが、そのヒューマニズムが本篇に結晶して、見事に活かされている。熊笹の匍うている丘から眺める風景のなかに、痛ましい生涯のあることを説いた氏の眼中には、推理小説としての完成はある程度犠牲にしても、惜しくないかもしれない」
巻末の作品紹介文には、こうある。
「殺人の罪で死刑を宣告された男…最高裁でも遂に上告棄却…死刑確定…しかしその男の犯行に不審をいだいた二人の教授が大心池博士の協力で次々と謎の糸をたぐり寄せ意外の結論…久々の快作!!」
以下、目次
箴言
人物展望
1.序曲
2.第一の事件
3.第二の事件
4.再審請求
5.心理法則
6.終曲
ハンセン病差別による「藤本事件」に題材をとった作品で、前半は名前等は変えてあるが、事件のあらましをたどっている。
容疑者としてとらえられた男、賀毛辰治がハンセン氏病だということで、「検事も判事もろくに証拠品を調べていない位、辰治に手を触れることは恐れていたのである。ピンセットやあり合わせの鋏でその証拠品を遠くから引っくりかえす程度であった」
さらに裁判官と法定弁護士だけで、傍聴者もない法廷で裁かれる。
証人になるべき人物は、ハンセン氏病患者と一緒にいたと思われるのが嫌で証言せず、アリバイが証明できない。
また、「辰治はライ病だ。どうせ、この世の中に帰って来られない男だ。そういうわけなら、せめて死刑になっても、いやなこの世を、少し早く去るというだけだ、他の人間ではないにしてもライ病一人位はええ」とする意識もある。
八方ふさがりになってしまい、あと、彼を救うには、真犯人をつきとめるほかない、という結論になり、後半の物語がはじまる。
「箴言」には次のような文章がある。
「若し現実に相似たる物語あり、その前半は描かれたるも、尚後続の見出さるることなくして停頓し居るものあらば、試みにこの物語の構想を参照せば、更に進むるを得るものあらむか。作者これを知らず」
作者は藤本事件のあまりの理不尽な展開に黙っておれなかったのだろう。
1870年頃にノルウェーのハンセン医師がライ菌を発見し、遺伝する病気ではなく、他の伝染病と同様に治療できるものであることが確定した。ライ病に対する忌わしい迷信、嫌悪を一般大衆から除かねばならない契機は1870年代に既にはじまっていたはずだったのである。
前半の部分は、憤りとともに社会的な熱い意識で読めるのだが、後半に入って、「真犯人は別にいる。それをつきとめよう」とする展開になると、その提案自体がなされることをもって本作の目的を達してしまった感がある。したがって、本書ではフィクション上の一応の犯人があばかれるが、それはつけたしのように思えた。
賀毛辰治は、取り調べ中、一度自供し、それをすぐに否定している。
いったん自分の罪を認めるような発言をしたのは何故か、ということが、本書で一番推理小説らしい箇所だった。
辰治はかつて、ある女性をライ病疑惑のデマをとばして、自殺させてしまったことがある。そのときの罪の意識、良心の呵責が、厳しい取り調べの際に自分を罰する意識として浮かびあがってきたのだ。誰も辰治の味方でない、という絶望の心境とあいまって、自暴自棄の発言になったのだ。
う〜む。
たしかに推理小説としては弱いけど、実際にはありうる話だ。
中島河太郎による解説は、次のような文章でしめくくられている。
「探偵作家クラブの例会の土曜会で、木々氏の愛生園視察談を聴いてから、かなりの年月を経た。救癩事業に熱意をこめて語られたので、今も談話の端々を覚えているが、そのヒューマニズムが本篇に結晶して、見事に活かされている。熊笹の匍うている丘から眺める風景のなかに、痛ましい生涯のあることを説いた氏の眼中には、推理小説としての完成はある程度犠牲にしても、惜しくないかもしれない」
渡辺啓助の『海底結婚式』を読んだ。1960年
同じ叢書の『熊笹にかくれて』巻末にあった作品紹介文は次のとおり。
「オンリー殺人事件…被害者は光子の恋文代筆の常客だった女、光子の推理は二転三転。推理の頂点は奇抜な海底結婚式場へ…著者は数度の海底視察に、遂に病に倒れるという悲壮な実感を筆に託した迫力巨編」
どんな時代が舞台かというと、登場人物が「ロマンスシートで、特待生香月光子と二人でベベの映画を鑑賞したいんだ」と、いうような時代だ。
やはり、あっけらかんと明るい作品になっていた。
以下、目次。
1.オンリーさん達
2.七号室の女
3.口留料として
4.室内風景
5.カーテンの蔭
6.隠れていた男
7.逢引(デエト)
8.東ダイ生の意見
9.ブレスト夫人訪問
10.彼女の触診
11.老嬢(オールドミス)の背中
12.外国婦人は簪がお好き
13.知りたがり屋
14.死の筒(ボンベ)
15.東京駅で
16.真犯人は僕です
17.潜水講習会
18.ひそかに花を植える
19.真犯人ではない
20.水と焔と鱶と
21.仇敵
22.黒人兵の花嫁
23.潜水準備
24.真鶴岬
25.海底接吻
26.崖の上のホテル
海底結婚式は、映画「最後の楽園」で「南方の恋人同志が海中で結婚の誓をする儀式」が取り上げられていたことをひきあいに出されている。「最後の楽園」は1957年製作のフォルコ・クィリチ監督のイタリア映画、ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー映画賞を受賞している。
見出しにある「東ダイ」は「東洋ダイヴィングクラブ」の略称。
主人公の推理はたしかに二転三転するが、論理に基づいたものではない。
現場にあった雨傘をヒントに容疑者を考えるが、その傘はある持ち主が別の人物に貸したもので、犯人はさらにそれを拝借して現場においた、とか、そんな感じ。
アクアラングのボンベを使ってガスを吸入させて自殺にみせかけるトリック。
犯人は、いったん自分が犯人だと告白しておいて、それを打ち消されて容疑の圏外に逃れる手を使う。
いずれにしても、推理小説的興味としては、それらしい描写もあるけれど、みどころは別にある小説、という感じだった。
同じ叢書の『熊笹にかくれて』巻末にあった作品紹介文は次のとおり。
「オンリー殺人事件…被害者は光子の恋文代筆の常客だった女、光子の推理は二転三転。推理の頂点は奇抜な海底結婚式場へ…著者は数度の海底視察に、遂に病に倒れるという悲壮な実感を筆に託した迫力巨編」
どんな時代が舞台かというと、登場人物が「ロマンスシートで、特待生香月光子と二人でベベの映画を鑑賞したいんだ」と、いうような時代だ。
やはり、あっけらかんと明るい作品になっていた。
以下、目次。
1.オンリーさん達
2.七号室の女
3.口留料として
4.室内風景
5.カーテンの蔭
6.隠れていた男
7.逢引(デエト)
8.東ダイ生の意見
9.ブレスト夫人訪問
10.彼女の触診
11.老嬢(オールドミス)の背中
12.外国婦人は簪がお好き
13.知りたがり屋
14.死の筒(ボンベ)
15.東京駅で
16.真犯人は僕です
17.潜水講習会
18.ひそかに花を植える
19.真犯人ではない
20.水と焔と鱶と
21.仇敵
22.黒人兵の花嫁
23.潜水準備
24.真鶴岬
25.海底接吻
26.崖の上のホテル
海底結婚式は、映画「最後の楽園」で「南方の恋人同志が海中で結婚の誓をする儀式」が取り上げられていたことをひきあいに出されている。「最後の楽園」は1957年製作のフォルコ・クィリチ監督のイタリア映画、ベルリン国際映画祭でドキュメンタリー映画賞を受賞している。
見出しにある「東ダイ」は「東洋ダイヴィングクラブ」の略称。
主人公の推理はたしかに二転三転するが、論理に基づいたものではない。
現場にあった雨傘をヒントに容疑者を考えるが、その傘はある持ち主が別の人物に貸したもので、犯人はさらにそれを拝借して現場においた、とか、そんな感じ。
アクアラングのボンベを使ってガスを吸入させて自殺にみせかけるトリック。
犯人は、いったん自分が犯人だと告白しておいて、それを打ち消されて容疑の圏外に逃れる手を使う。
いずれにしても、推理小説的興味としては、それらしい描写もあるけれど、みどころは別にある小説、という感じだった。
『なぜ、北海道はミステリー作家の宝庫なのか?』
2010年4月5日 読書
鷲田小彌太と井上美香の共著による『なぜ、北海道はミステリー作家の宝庫なのか?』を読んだ。
北海道がミステリー作家の宝庫だったという認識はなかったので、興味深く読んだ。
以下、目次
序——北海道はミステリー作家の宝庫か?
I ミステリーは文学じゃないのか?
II ミステリーの嚆矢は函館だって?
III 時代小説はミステリーなのか?
IV 戦後における北海道のミステリーは「不毛」か?
V 量からいっても質からいっても、北海道はミステリー作家の宝庫だ
第一部 戦前——函館生まれの探偵小説作家たち
I 函館が生んだ探偵小説三銃士
◆水谷準…日本ミステリーの草創期を切り盛りする
編集者と作家の狭間で/評価されなかった戦後の長編/水谷なしに北海道にミステリーは生まれなかった
◆長谷川海太郎…「谷譲次・林不忘・牧逸馬」の三人で一人
『丹下左膳』も『浴槽の花嫁』もミステリーだ/無国籍小説が持つ意味/倣岸と礼節の間で/「良質な小説」という高みを目指す
◆久生十蘭…探偵小説を芸術にまで高めたファーストランナー
「海豹島」の幻惑、「顎十郎捕物帳」の洒脱/十蘭のメインテーマ/文壇からの冷遇/函館に顔を「背けて」
II ミステリーを切り開く
◆松本恵子…日本初の女性探偵作家
女性探偵作家の夜明け/欧米文化と親しんだ幼少期
◆渡辺啓助…探偵小説の黎明期を生きた長寿作家
作家の道に導いた二つの悲しみ/弟・温の存在
◆渡辺温…横溝正史とコンビを組んだ、夭折のモダンボーイ
「新青年」に生き、「新青年」に散る/愛すべき人柄と惜しまれた才能
◆地味井平造…芸術に遊んだ画家の手遊び
埋もれた存在/乱歩が鮎川が讃えた才能
第二部 戦後——消えた作家、甦った作家
I 「忘却」と「再発見」
◆楠田匡介…脱獄トリックの名手
長編ではなく短編がいい/「復活!」といえば大げさか
◆夏堀正元…影薄い多作な社会派
社会派の落とし穴/本当にミステリー作家なのか?
◆高城高…和製ハードボイルドの先駆者
ハードボイルド前夜を走る/高城は短編作家なのか?
◆中野美代子…ミステリー史に名の出ない偉才
行間に漂うミステリアスで隠微な空気/「一字」で千変万化の世界を織りなす
◆幾瀬勝彬…戦中派の美学
娯楽作と異色作/戦場の記憶を「娯楽」へ転写
◆南部樹未子… 不毛な「愛」のさまざまな結末を描いて
型どおりの愛憎復讐劇
◆佐々木丸美…復活遂げた「伝説」の作家
伝説化で広がったファン層/作家と読者の共通意識
II ミステリーも手がけた作家
◆伊藤整…考え抜かれた方法論で書く
ニヒリズムの極致/独白と幻想
◆井上靖…謎解きの面白さと重厚な人間ドラマ
『氷壁』のハードボイルドなカッコよさ
◆三浦綾子…鈍るミステリーとしての論理性
見逃せない信仰の影響
◆加田伶太郎(福永武彦)…純文学作家の見事なる余技
キャラクター造形の妙
◆寺久保友哉…精神科医が仕掛けるミステリー
心の森を彷徨う
第三部 現役—— 日本ミステリーの一翼を担う
I 第一線で活躍する作家たち
◆佐々木譲…冒険小説から警察小説へ、「エースのジョー」誕生!
冒険小説の白眉『エトロフ発緊急電』/文字通りの代表作『警官の血』/作品の核心にあるもの/
◆今野敏…「自立自尊」の生き方を貫く
二つのシリーズで描く、好対照の警官像/ミステリーと倫理の密なる関係
◆東直己…日本ハードボイルドの巨艦
ハードボイルドの幅を広げた、名無しの探偵/『残光』でハードボイルドを極める/奇妙な小説たちの持つ意味
◆鳴海章…故郷に戻り、新境地を開く
パイロットのプロ意識が見所の『ナイト・ダンサー』/警官の境目を描く『ニューナンブ』/ララバイ東京
◆京極夏彦…世を目晦まし異境に生きる、時代の寵児
ベストセラーの謎/京極作品が読まれる理由/言葉で呪い、言葉で祓う/饒舌と自己演出/辺境としての北海道
◆馳星周…異端こそ、日本文学の正統な潮流
度肝を抜いたデビュー作/恐怖と魅惑の「異国」/底なしの狂気を冷徹に追求
II まだまだいる、ミステリー作家たち
◆井谷昌喜…ジャーナリストならではの視点
説得力あるバイオサスペンス
◆内山安雄…陽性のアジアン・ノワール作家
体当たり人生から生まれた作品/海外で迎えた二度の転機
◆奥田哲也…得体の知れない毒素を仕込む
意図の見えない物語の壊れ方
◆丹羽昌一…中南米の風土に魅せられて
元外交官ならではのリアルな状況描写
◆矢口敦子…ブレイクの秘密
乙女チックなミステリー
◆桜木紫乃…男女の関わりをテーマに
原田康子を超えられるか
◆小路幸也…不思議な浮遊感で描く、救いの物語
新しい発想に満ちた奇抜なストーリー
◆佐藤友哉…に十一世紀に息づく、北海道ミステリー作家の潮流
「恐るべき子ども」が生み出した「おとぎの世界」
III ミステリーも手がけた作家たち
◆原田康子…作家としての原点であるミステリー
原田がミステリーを書いた理由とは
◆渡辺淳一…心の謎への飽くなき探求心
ミステリー好きには一読の価値あり
◆荒巻義雄…伝奇色の濃い荒巻的ミステリー
「架空戦記」前の作品に一興あり
◆嵯峨島昭(宇能鴻一郎)…変態する鬼才の片鱗
官能作家・宇野の異能ぶり
◆久間十義…ぶれない生真面目な視点
実際の事件をモチーフに
IV ジャンルを横断するミステリー
◆川又千秋…荒巻義雄の流れを汲む
『幻詩狩り』の荒唐無稽な面白さ
◆朝松 健…筋金入りのホラー作家
ホラーとミステリーの境界をゆく
◆森真沙子…時代小説に転じたベテラン作家
受け継がれるミステリーの結構
◆宇江佐真理…時代小説界の超新星
宇江佐の時代小説はミステリーだ
V ミステリーを評論する
◆山前 譲…ミステリー評論の正統派
マニアックさを感じさせない叙述
◆千街晶之…本格ミステリー批評を目指して
先入観を裏切るわかりやすさ
跋——なぜ、函館はミステリー作家の水源地なのか?
一、なぜ、函館から生まれたのか?
二、函館が国際都市であったことの影響
三、出身作家を顕彰する小樽、しない函館
四、作家の営為を吸収し、未来へ生かす
五、孤独な闘いを続ける作家たちに光を
読みすすめるうちに、伊藤整や井上靖まで引っ張り出したあたりでは、本当に「宝庫」なのか?と疑問が湧いたが、読み終えてみると、なるほど、いっぱいいるなあ、という気になった。
面白いのは、著者が紹介する作家に対して、けっこう辛口の批評をしているところ。
例えば、夏堀正元。
「夏堀の作品は、国家間の紛争を巻き起こすような『重大』事件を扱いながら、そのディテールは、定食屋でお決まりのメニューを平らげるようにお手軽なのだ」
「死後およそ10年を経て、すでに忘れられた作家の仲間に入ってしまった夏堀。今のところ、その『復活』の兆候はない」
南部樹未子。
「型どおりの愛憎復讐劇が展開し、型どおりそれが原因で殺人が起きる」
「南部は、北海道のワンパターンな情景を配した愛憎ドラマの繰り返しと思われる作品群を残しただけで、終わってしまっている」
佐々木丸美。
「佐々木のミステリーに登場する、感情も思考もそして行動も『稚拙』な主人公たちは、実のところ作家自身の『稚拙』さの表出なのである。そう思うほかない。佐々木の作品や読者にとって、『ナイーブ』は『純真さ』を表すだけの言葉として受けとめられている。ナイーブが持つ否定的な本来の意味−未熟さや、愚かさ、世間知らず、はまったく顧みられていないのだ。これが、佐々木の作品の再刊を熱狂的に求めた最大因である。稚拙なミステリー読者が、それにふさわしいものを佐々木作品のなかに見出したのである」
これらは鷲田が執筆した部分で、鷲田の辛口批評が噴出したのかな、と思っていたら、井上美香(いのうえ・よしか。鷲田研究所所員で鷲田の仕事の補佐などしている)の執筆したところでも、辛口は止まらない。
矢口敦子。
「矢口作品における事件や謎が、登場人物の心情を炙り出すための装置としてしか機能していない」
「人物描写が優れているのかといえば、残念ながら作中に登場する人物たちは、作者の操り人形としか思えないのだ」
「POPの言葉を見返してみると、読者のターゲットは若い女性に絞られている。おそらく、推薦した書店員も女性に違いない。直接的でわかりやすい矢口作品は、そうした層に受け入れられる『乙女チックミステリー』ともいうべきものであり、娯楽作品として2時間枠のサスペンステレビドラマを見るかのような気軽さが魅力なのだろう」
僕の貧弱な読書経験では、上記の4人の作品はまったく読んでいなかった。この本でこきおろされているのを読んで、逆に興味を持ってしまったのは、著者の術中にはまったのかもしれない。
なお、本書によると、水谷準は「1959年以降、水谷はアンソロジーをのぞいて探偵小説の自著書の再刊、復刊を認めていない」のだそうだ!面白そうな著書目録のタイトルだけを見て、うらやましがるしかないのである。
北海道がミステリー作家の宝庫だったという認識はなかったので、興味深く読んだ。
以下、目次
序——北海道はミステリー作家の宝庫か?
I ミステリーは文学じゃないのか?
II ミステリーの嚆矢は函館だって?
III 時代小説はミステリーなのか?
IV 戦後における北海道のミステリーは「不毛」か?
V 量からいっても質からいっても、北海道はミステリー作家の宝庫だ
第一部 戦前——函館生まれの探偵小説作家たち
I 函館が生んだ探偵小説三銃士
◆水谷準…日本ミステリーの草創期を切り盛りする
編集者と作家の狭間で/評価されなかった戦後の長編/水谷なしに北海道にミステリーは生まれなかった
◆長谷川海太郎…「谷譲次・林不忘・牧逸馬」の三人で一人
『丹下左膳』も『浴槽の花嫁』もミステリーだ/無国籍小説が持つ意味/倣岸と礼節の間で/「良質な小説」という高みを目指す
◆久生十蘭…探偵小説を芸術にまで高めたファーストランナー
「海豹島」の幻惑、「顎十郎捕物帳」の洒脱/十蘭のメインテーマ/文壇からの冷遇/函館に顔を「背けて」
II ミステリーを切り開く
◆松本恵子…日本初の女性探偵作家
女性探偵作家の夜明け/欧米文化と親しんだ幼少期
◆渡辺啓助…探偵小説の黎明期を生きた長寿作家
作家の道に導いた二つの悲しみ/弟・温の存在
◆渡辺温…横溝正史とコンビを組んだ、夭折のモダンボーイ
「新青年」に生き、「新青年」に散る/愛すべき人柄と惜しまれた才能
◆地味井平造…芸術に遊んだ画家の手遊び
埋もれた存在/乱歩が鮎川が讃えた才能
第二部 戦後——消えた作家、甦った作家
I 「忘却」と「再発見」
◆楠田匡介…脱獄トリックの名手
長編ではなく短編がいい/「復活!」といえば大げさか
◆夏堀正元…影薄い多作な社会派
社会派の落とし穴/本当にミステリー作家なのか?
◆高城高…和製ハードボイルドの先駆者
ハードボイルド前夜を走る/高城は短編作家なのか?
◆中野美代子…ミステリー史に名の出ない偉才
行間に漂うミステリアスで隠微な空気/「一字」で千変万化の世界を織りなす
◆幾瀬勝彬…戦中派の美学
娯楽作と異色作/戦場の記憶を「娯楽」へ転写
◆南部樹未子… 不毛な「愛」のさまざまな結末を描いて
型どおりの愛憎復讐劇
◆佐々木丸美…復活遂げた「伝説」の作家
伝説化で広がったファン層/作家と読者の共通意識
II ミステリーも手がけた作家
◆伊藤整…考え抜かれた方法論で書く
ニヒリズムの極致/独白と幻想
◆井上靖…謎解きの面白さと重厚な人間ドラマ
『氷壁』のハードボイルドなカッコよさ
◆三浦綾子…鈍るミステリーとしての論理性
見逃せない信仰の影響
◆加田伶太郎(福永武彦)…純文学作家の見事なる余技
キャラクター造形の妙
◆寺久保友哉…精神科医が仕掛けるミステリー
心の森を彷徨う
第三部 現役—— 日本ミステリーの一翼を担う
I 第一線で活躍する作家たち
◆佐々木譲…冒険小説から警察小説へ、「エースのジョー」誕生!
冒険小説の白眉『エトロフ発緊急電』/文字通りの代表作『警官の血』/作品の核心にあるもの/
◆今野敏…「自立自尊」の生き方を貫く
二つのシリーズで描く、好対照の警官像/ミステリーと倫理の密なる関係
◆東直己…日本ハードボイルドの巨艦
ハードボイルドの幅を広げた、名無しの探偵/『残光』でハードボイルドを極める/奇妙な小説たちの持つ意味
◆鳴海章…故郷に戻り、新境地を開く
パイロットのプロ意識が見所の『ナイト・ダンサー』/警官の境目を描く『ニューナンブ』/ララバイ東京
◆京極夏彦…世を目晦まし異境に生きる、時代の寵児
ベストセラーの謎/京極作品が読まれる理由/言葉で呪い、言葉で祓う/饒舌と自己演出/辺境としての北海道
◆馳星周…異端こそ、日本文学の正統な潮流
度肝を抜いたデビュー作/恐怖と魅惑の「異国」/底なしの狂気を冷徹に追求
II まだまだいる、ミステリー作家たち
◆井谷昌喜…ジャーナリストならではの視点
説得力あるバイオサスペンス
◆内山安雄…陽性のアジアン・ノワール作家
体当たり人生から生まれた作品/海外で迎えた二度の転機
◆奥田哲也…得体の知れない毒素を仕込む
意図の見えない物語の壊れ方
◆丹羽昌一…中南米の風土に魅せられて
元外交官ならではのリアルな状況描写
◆矢口敦子…ブレイクの秘密
乙女チックなミステリー
◆桜木紫乃…男女の関わりをテーマに
原田康子を超えられるか
◆小路幸也…不思議な浮遊感で描く、救いの物語
新しい発想に満ちた奇抜なストーリー
◆佐藤友哉…に十一世紀に息づく、北海道ミステリー作家の潮流
「恐るべき子ども」が生み出した「おとぎの世界」
III ミステリーも手がけた作家たち
◆原田康子…作家としての原点であるミステリー
原田がミステリーを書いた理由とは
◆渡辺淳一…心の謎への飽くなき探求心
ミステリー好きには一読の価値あり
◆荒巻義雄…伝奇色の濃い荒巻的ミステリー
「架空戦記」前の作品に一興あり
◆嵯峨島昭(宇能鴻一郎)…変態する鬼才の片鱗
官能作家・宇野の異能ぶり
◆久間十義…ぶれない生真面目な視点
実際の事件をモチーフに
IV ジャンルを横断するミステリー
◆川又千秋…荒巻義雄の流れを汲む
『幻詩狩り』の荒唐無稽な面白さ
◆朝松 健…筋金入りのホラー作家
ホラーとミステリーの境界をゆく
◆森真沙子…時代小説に転じたベテラン作家
受け継がれるミステリーの結構
◆宇江佐真理…時代小説界の超新星
宇江佐の時代小説はミステリーだ
V ミステリーを評論する
◆山前 譲…ミステリー評論の正統派
マニアックさを感じさせない叙述
◆千街晶之…本格ミステリー批評を目指して
先入観を裏切るわかりやすさ
跋——なぜ、函館はミステリー作家の水源地なのか?
一、なぜ、函館から生まれたのか?
二、函館が国際都市であったことの影響
三、出身作家を顕彰する小樽、しない函館
四、作家の営為を吸収し、未来へ生かす
五、孤独な闘いを続ける作家たちに光を
読みすすめるうちに、伊藤整や井上靖まで引っ張り出したあたりでは、本当に「宝庫」なのか?と疑問が湧いたが、読み終えてみると、なるほど、いっぱいいるなあ、という気になった。
面白いのは、著者が紹介する作家に対して、けっこう辛口の批評をしているところ。
例えば、夏堀正元。
「夏堀の作品は、国家間の紛争を巻き起こすような『重大』事件を扱いながら、そのディテールは、定食屋でお決まりのメニューを平らげるようにお手軽なのだ」
「死後およそ10年を経て、すでに忘れられた作家の仲間に入ってしまった夏堀。今のところ、その『復活』の兆候はない」
南部樹未子。
「型どおりの愛憎復讐劇が展開し、型どおりそれが原因で殺人が起きる」
「南部は、北海道のワンパターンな情景を配した愛憎ドラマの繰り返しと思われる作品群を残しただけで、終わってしまっている」
佐々木丸美。
「佐々木のミステリーに登場する、感情も思考もそして行動も『稚拙』な主人公たちは、実のところ作家自身の『稚拙』さの表出なのである。そう思うほかない。佐々木の作品や読者にとって、『ナイーブ』は『純真さ』を表すだけの言葉として受けとめられている。ナイーブが持つ否定的な本来の意味−未熟さや、愚かさ、世間知らず、はまったく顧みられていないのだ。これが、佐々木の作品の再刊を熱狂的に求めた最大因である。稚拙なミステリー読者が、それにふさわしいものを佐々木作品のなかに見出したのである」
これらは鷲田が執筆した部分で、鷲田の辛口批評が噴出したのかな、と思っていたら、井上美香(いのうえ・よしか。鷲田研究所所員で鷲田の仕事の補佐などしている)の執筆したところでも、辛口は止まらない。
矢口敦子。
「矢口作品における事件や謎が、登場人物の心情を炙り出すための装置としてしか機能していない」
「人物描写が優れているのかといえば、残念ながら作中に登場する人物たちは、作者の操り人形としか思えないのだ」
「POPの言葉を見返してみると、読者のターゲットは若い女性に絞られている。おそらく、推薦した書店員も女性に違いない。直接的でわかりやすい矢口作品は、そうした層に受け入れられる『乙女チックミステリー』ともいうべきものであり、娯楽作品として2時間枠のサスペンステレビドラマを見るかのような気軽さが魅力なのだろう」
僕の貧弱な読書経験では、上記の4人の作品はまったく読んでいなかった。この本でこきおろされているのを読んで、逆に興味を持ってしまったのは、著者の術中にはまったのかもしれない。
なお、本書によると、水谷準は「1959年以降、水谷はアンソロジーをのぞいて探偵小説の自著書の再刊、復刊を認めていない」のだそうだ!面白そうな著書目録のタイトルだけを見て、うらやましがるしかないのである。
中村八朗の長編推理小説『汚れた顔の男』を読んだ。1963年。
ネタバレするので、要注意。
深夜の酔いどれ天使
遺書のない情死
残された白い下着
光る短刀
女は待っていた
逃げだしたチンピラ
消えた乗客
誘惑する女肌
あの車を追え!
夜の闇に逃げろ!
第四の失踪者
殺ったのは、俺じゃねえ!
もう一人の男はどこだ!
白い裸の罠
真犯人はAB型の男だ!
課長職にある男性と、水商売のマダムが情死?
肉体関係のあとも遺書もなかったが、状況からみて、情死としか考えられなかった。
死体が発見された宿の女中は、2人が一緒に来て泊まったと証言しているのだ。
さて。
と、いうわけで、中村八朗と言えばジュニア小説のイメージが強いが、これはかなりきっちり書かれた、端正な推理小説だった。ささやかながら、アクションシーンもあるし、濡れ場もある。
情死と見せかけられた2人は、それぞれ別々に宿に来ており、死んでから衣服を取り替えられて、女中を誤認させた。恥ずかしくて顔をふせて入るような宿だったので、女中は着物は覚えていたが、顔の判別がつかなかったのだ。
そして、「俺はたのまれてやっただけだ」の芋ずる式に真犯人があぶり出されるところは、かなり面白かった。こいつが犯人だ、と思ったら、そいつの後ろにまだ黒幕がいて、というのが続いて、まるでわらしべ長者のように、町のちんぴらから、社会的地位のある人物にまで真犯人が昇格していくのだ。
その犯人は意外な犯人ではあるのだが、あいにくと、あっと思わせる論理のからくりがあるわけではない。しかし、この作品が出た時代のことを考えると、じゅうぶんに及第点のとれている推理小説になっているように思えた。
ネタバレするので、要注意。
深夜の酔いどれ天使
遺書のない情死
残された白い下着
光る短刀
女は待っていた
逃げだしたチンピラ
消えた乗客
誘惑する女肌
あの車を追え!
夜の闇に逃げろ!
第四の失踪者
殺ったのは、俺じゃねえ!
もう一人の男はどこだ!
白い裸の罠
真犯人はAB型の男だ!
課長職にある男性と、水商売のマダムが情死?
肉体関係のあとも遺書もなかったが、状況からみて、情死としか考えられなかった。
死体が発見された宿の女中は、2人が一緒に来て泊まったと証言しているのだ。
さて。
と、いうわけで、中村八朗と言えばジュニア小説のイメージが強いが、これはかなりきっちり書かれた、端正な推理小説だった。ささやかながら、アクションシーンもあるし、濡れ場もある。
情死と見せかけられた2人は、それぞれ別々に宿に来ており、死んでから衣服を取り替えられて、女中を誤認させた。恥ずかしくて顔をふせて入るような宿だったので、女中は着物は覚えていたが、顔の判別がつかなかったのだ。
そして、「俺はたのまれてやっただけだ」の芋ずる式に真犯人があぶり出されるところは、かなり面白かった。こいつが犯人だ、と思ったら、そいつの後ろにまだ黒幕がいて、というのが続いて、まるでわらしべ長者のように、町のちんぴらから、社会的地位のある人物にまで真犯人が昇格していくのだ。
その犯人は意外な犯人ではあるのだが、あいにくと、あっと思わせる論理のからくりがあるわけではない。しかし、この作品が出た時代のことを考えると、じゅうぶんに及第点のとれている推理小説になっているように思えた。
『新・現代日本文学全集第46巻 渡辺啓助』
2010年3月30日 読書
東方社の『新・現代日本文学全集第46巻 渡辺啓助』を読んだ。
長編1つと中編2つが収録されている。
巻頭には作者の言葉として、次のような文章が手書きの筆影で載せられている。
「渇しても盗泉の水はのまず」とも云うし、「盗んでのむ水はうまい」とも云う。どちらも同じくらい魅力的なコトバだが、私などは後者を追求することによって、小説を書いてゆきたい、と思う。
以下、小見出しと、簡単なメモ(ネタバレ)。
「美女裁断機」(1956年『傑作クラブ』連載)
お嬢さん失踪
深夜の人形(マネキン)
蠅は知ってる
片足だけが
五百万ドル娘
恐怖のコンクール
生首ショウ
悪魔の二重奏
魔女の休日
(連載時とは小見出しが違っているので、内容に修正などあったのかもしれない。「第1話」から「第9話」まで章立てしてあるが、連作短編ではなくて、1つの流れのある中編)
扇情的なタイトルと、バラバラ死体を扱った作品なので、陰惨で猟奇的な物語なのかと思いきや、読後感は明るい。これは戦後の渡辺啓助作品に共通して言えることだ。江戸川乱歩や大河内常平が書いていたら、えらくセンセーショナルなものになったろうし、横溝正史が書いていたらおどろおどろしくなっていたはずなのに、渡辺啓助が書くと、なんだか爽やかなのだ。
発端は、上野公園のベンチ。佐伯という男が見も知らぬ女性、小栗三津子に電車賃を貸してやったことにはじまり、追いつおわれつの冒険がはじまる。
ペルーで鉱山を経営していた日本人の遺産500万ドルを相続するニッポン娘とは一体誰なのか?
巻き込まれた佐伯は、「まるで悪夢の連続だ。見はじめたらやめられないのが悪夢なんだ」と言う名言を吐く。
なお、現代ミステリーではバラバラ殺人があれば、死体を解体した理由にひと工夫があり、新しい解体動機を提供するところに作者の腕のみせどころがあるのだが、この作品では、これといった動機もなく、バラバラにしている。
ただ、マネキン人形の倉庫で、妙に蠅がたかっている足が1本あって、バラバラ死体の一部だとわかる、とか、猟奇的なお膳立てとして機能している。
「悪魔の唇」(1953年『探偵倶楽部』連載)
空家の中の娘
妖しき鎮魂歌
髪と爪
それは殺人曲でもあった
筑紫琴へ寄せる恋
美容院経営のお嬢さん
再び鎮魂曲が
黒薔薇の君は怒る
あぐり嬢の髪の毛を盗む
聖ジョアンナお銀の洞窟
誰がために石の琴は鳴る
黄色い男
洞窟の黒薔薇
宙吊りの刑
消えたお嬢さん
黄色の屍
昇天した男
律子現わる
それから律子は
遁走
東京のカスバ
決闘
PACKRI座
水上バスで浜離宮へ
声なき影絵
影絵の死
奇怪な発作
不死身の男
女流小説家の丹亜矢子女史が雑誌の「身の上相談」コーナーで書いたアドバイスで、読者の女性が家出してしまい、消息不明になってしまった。
探偵の一本木万助と、聖物蒐集癖のある笹渡多嘉士は、行方不明の読者、鶴ケ谷律子の捜索をはじめるが、殺人事件に巻き込まれて行く。
琴で奏でられる鎮魂歌が事件現場で流れ、隠れキリシタンの洞窟迷路、出没する黄色い男、などなど通俗的な興味にはことかかない。
主人公のひとり、笹渡の「聖物蒐集癖」というのは、殉教者の遺物や、変死者の遺物などを集める癖のことで、この変わり者こそが、事件を解決する主人公に、なる、と思ってしまったが、別にそういう役回りが結局与えられなかったのが、意外。
タイトルの「悪魔の唇」は、神学博士ブラウン教授(ブラウン神父!当然、同名異人)の作った黒い薔薇の名前。
鶴ケ谷律子を探していると、同じ年頃の女性、鶴ケ谷あぐりに出会うが、このあぐりが、アプレ娘で、「美しくって、気品があって、才気ばしっていて、その上、天邪鬼で、アプレ娘の気ままさもあって」「どこが本音だか、ちょっと掴みようがない」と評される。これは「妖精みたいな不思議な香気」をふりまいた『美女裁断機』の小栗三津子と同類の女性像に思われるが、アプレ度はあぐりに軍配があがり、物語のラスト近くでは「妖麗にして狡智、信仰心皆無、物慾主義の女王、祖先に熱烈な殉教者をだした癖に、それと全然相反した家風が生まれ、その代表が、あぐり嬢と云うわけだ」とまで言われる。「薔薇『悪魔の唇』がそのまま、彼女なんだ」とまで!
行方不明の律子はなかなか姿をあらわさないが、婦人伝導師ミス・ブラントが明かす律子の正体には慄然とした。鶴ヶ谷律子とは300年前に殉教したジョアンナお銀の別名だというのだ!
「わたし、三百年前のお銀さまから、身の上相談を持ちかけられたのかと思うと、あんまりユーモラス過ぎて、かえって、とても怖くなるわ。なんだかゾーッとしちゃうわ」
この衝撃の事実がもたらすミスディレクションは、映画「サイコ」で、死んだはずのノーマン・ベイツの母親が家にいたと聞いたときに発せられる「では、あのとき埋葬されたのは、いったい誰だったんでしょう?」を連想させた。
鎮魂曲については、迷路の洞窟で奏でられた際に、人間だけなら簡単に隠れることができるが、大きな琴を隠すのは至難のわざ、という意味の発言がなされる。このあたり、冷静に考えれば、大きなヒントがあったのだが、読んでいるときには、「琴の真相」にまったく思いいたらないあたりが、作者の力量を示している。(あるいは、僕がいかにうかつな読者であるかの証明)。ただ、なぜ鎮魂曲を奏でたのかについては、犯人が「一度、鎮魂曲を使い出すと、自身がそれに憑かれてしまった。その後、ことあるごとに鎮魂曲を聞かせずにいられない偏執的な思いに駆られた。鶴ヶ谷のタブーである鎮魂曲をかなでることによって、彼らに、神秘的な畏怖感を与えながら、じわりじわり追いつめて行こうとする企みであった」とされる。万助が言うように、「なるほど。この事件は、いかにもロマンチックであり過ぎた」のである。
ロマンチックかどうかはわからないが、作中、「パックリ座」というストリップ劇場での演し物は「パクパクパックリ踊り、ヌラリ・トロリ、グッタリタイム」など「およそ意味不明な、それだけ煽情的な」タイトルがついている。「パクパクパックリなどと云う踊りをみても、もう、鼻持ちならないほど下劣だ。ことさらな尻のふり方や腹の肉のびくつかせ方が、どれほど野卑であっても、異様に神聖な美しささえ感じさせるのは、踊子たちが皆若くって逞しいピチピチした肉体を持っていたからだ」
「開幕に先だって、マイクから聞えてくる口上にしても、たとえば、『いよいよお待ちかねの処女幕をあけまアす』と云った風で、万事がその調子だ。下らないとか、馬鹿げているとか、貶してみても、いつしか、そうした卑猥な調子のかもし出す妙にネバネバした雰囲気に、観客自身すっかり包まれているのだ」
うっかりしていたが、この手の演し物も、今や絶滅の危機に瀕しているんじゃないだろうか。
「裸体派」(1957年『宝石』)
山ですっぱだかの女性の死体が発見された。
直前に、ヘリコプターからその女性と、野糞プリンスと呼ばれる男子高校生が2人ともに裸でいるところを目撃されている。だが、その野糞プリンスは現場から忽然と姿を消してしまったのだ。彼はハンサムで、バスの車掌も峠茶屋、うどん屋にいたるまで、顔をすっかり覚えられている存在で、どこへ逃げても人目をひくはずなのに、である。
彼が「野糞プリンス」と呼ばれるのは、キャンプで草むらなどで普通、用をたす場合でも、彼は広々とした草原で人目をはばからずに放尿脱糞するからだ。
それは、彼の純粋さから来るもので、「彼は人間の衣裳があらゆる虚偽と汚辱の始りと考えているのだ」とするヌーディストの発想を受け入れさせるにいたる。彼が山の中で全裸になっていたのはそういうわけなのだ。
寝ているあいだに、女性の死体をかたわらに置き去りにされ、困った彼は女装して逃げおおせたのであった。
長編1つと中編2つが収録されている。
巻頭には作者の言葉として、次のような文章が手書きの筆影で載せられている。
「渇しても盗泉の水はのまず」とも云うし、「盗んでのむ水はうまい」とも云う。どちらも同じくらい魅力的なコトバだが、私などは後者を追求することによって、小説を書いてゆきたい、と思う。
以下、小見出しと、簡単なメモ(ネタバレ)。
「美女裁断機」(1956年『傑作クラブ』連載)
お嬢さん失踪
深夜の人形(マネキン)
蠅は知ってる
片足だけが
五百万ドル娘
恐怖のコンクール
生首ショウ
悪魔の二重奏
魔女の休日
(連載時とは小見出しが違っているので、内容に修正などあったのかもしれない。「第1話」から「第9話」まで章立てしてあるが、連作短編ではなくて、1つの流れのある中編)
扇情的なタイトルと、バラバラ死体を扱った作品なので、陰惨で猟奇的な物語なのかと思いきや、読後感は明るい。これは戦後の渡辺啓助作品に共通して言えることだ。江戸川乱歩や大河内常平が書いていたら、えらくセンセーショナルなものになったろうし、横溝正史が書いていたらおどろおどろしくなっていたはずなのに、渡辺啓助が書くと、なんだか爽やかなのだ。
発端は、上野公園のベンチ。佐伯という男が見も知らぬ女性、小栗三津子に電車賃を貸してやったことにはじまり、追いつおわれつの冒険がはじまる。
ペルーで鉱山を経営していた日本人の遺産500万ドルを相続するニッポン娘とは一体誰なのか?
巻き込まれた佐伯は、「まるで悪夢の連続だ。見はじめたらやめられないのが悪夢なんだ」と言う名言を吐く。
なお、現代ミステリーではバラバラ殺人があれば、死体を解体した理由にひと工夫があり、新しい解体動機を提供するところに作者の腕のみせどころがあるのだが、この作品では、これといった動機もなく、バラバラにしている。
ただ、マネキン人形の倉庫で、妙に蠅がたかっている足が1本あって、バラバラ死体の一部だとわかる、とか、猟奇的なお膳立てとして機能している。
「悪魔の唇」(1953年『探偵倶楽部』連載)
空家の中の娘
妖しき鎮魂歌
髪と爪
それは殺人曲でもあった
筑紫琴へ寄せる恋
美容院経営のお嬢さん
再び鎮魂曲が
黒薔薇の君は怒る
あぐり嬢の髪の毛を盗む
聖ジョアンナお銀の洞窟
誰がために石の琴は鳴る
黄色い男
洞窟の黒薔薇
宙吊りの刑
消えたお嬢さん
黄色の屍
昇天した男
律子現わる
それから律子は
遁走
東京のカスバ
決闘
PACKRI座
水上バスで浜離宮へ
声なき影絵
影絵の死
奇怪な発作
不死身の男
女流小説家の丹亜矢子女史が雑誌の「身の上相談」コーナーで書いたアドバイスで、読者の女性が家出してしまい、消息不明になってしまった。
探偵の一本木万助と、聖物蒐集癖のある笹渡多嘉士は、行方不明の読者、鶴ケ谷律子の捜索をはじめるが、殺人事件に巻き込まれて行く。
琴で奏でられる鎮魂歌が事件現場で流れ、隠れキリシタンの洞窟迷路、出没する黄色い男、などなど通俗的な興味にはことかかない。
主人公のひとり、笹渡の「聖物蒐集癖」というのは、殉教者の遺物や、変死者の遺物などを集める癖のことで、この変わり者こそが、事件を解決する主人公に、なる、と思ってしまったが、別にそういう役回りが結局与えられなかったのが、意外。
タイトルの「悪魔の唇」は、神学博士ブラウン教授(ブラウン神父!当然、同名異人)の作った黒い薔薇の名前。
鶴ケ谷律子を探していると、同じ年頃の女性、鶴ケ谷あぐりに出会うが、このあぐりが、アプレ娘で、「美しくって、気品があって、才気ばしっていて、その上、天邪鬼で、アプレ娘の気ままさもあって」「どこが本音だか、ちょっと掴みようがない」と評される。これは「妖精みたいな不思議な香気」をふりまいた『美女裁断機』の小栗三津子と同類の女性像に思われるが、アプレ度はあぐりに軍配があがり、物語のラスト近くでは「妖麗にして狡智、信仰心皆無、物慾主義の女王、祖先に熱烈な殉教者をだした癖に、それと全然相反した家風が生まれ、その代表が、あぐり嬢と云うわけだ」とまで言われる。「薔薇『悪魔の唇』がそのまま、彼女なんだ」とまで!
行方不明の律子はなかなか姿をあらわさないが、婦人伝導師ミス・ブラントが明かす律子の正体には慄然とした。鶴ヶ谷律子とは300年前に殉教したジョアンナお銀の別名だというのだ!
「わたし、三百年前のお銀さまから、身の上相談を持ちかけられたのかと思うと、あんまりユーモラス過ぎて、かえって、とても怖くなるわ。なんだかゾーッとしちゃうわ」
この衝撃の事実がもたらすミスディレクションは、映画「サイコ」で、死んだはずのノーマン・ベイツの母親が家にいたと聞いたときに発せられる「では、あのとき埋葬されたのは、いったい誰だったんでしょう?」を連想させた。
鎮魂曲については、迷路の洞窟で奏でられた際に、人間だけなら簡単に隠れることができるが、大きな琴を隠すのは至難のわざ、という意味の発言がなされる。このあたり、冷静に考えれば、大きなヒントがあったのだが、読んでいるときには、「琴の真相」にまったく思いいたらないあたりが、作者の力量を示している。(あるいは、僕がいかにうかつな読者であるかの証明)。ただ、なぜ鎮魂曲を奏でたのかについては、犯人が「一度、鎮魂曲を使い出すと、自身がそれに憑かれてしまった。その後、ことあるごとに鎮魂曲を聞かせずにいられない偏執的な思いに駆られた。鶴ヶ谷のタブーである鎮魂曲をかなでることによって、彼らに、神秘的な畏怖感を与えながら、じわりじわり追いつめて行こうとする企みであった」とされる。万助が言うように、「なるほど。この事件は、いかにもロマンチックであり過ぎた」のである。
ロマンチックかどうかはわからないが、作中、「パックリ座」というストリップ劇場での演し物は「パクパクパックリ踊り、ヌラリ・トロリ、グッタリタイム」など「およそ意味不明な、それだけ煽情的な」タイトルがついている。「パクパクパックリなどと云う踊りをみても、もう、鼻持ちならないほど下劣だ。ことさらな尻のふり方や腹の肉のびくつかせ方が、どれほど野卑であっても、異様に神聖な美しささえ感じさせるのは、踊子たちが皆若くって逞しいピチピチした肉体を持っていたからだ」
「開幕に先だって、マイクから聞えてくる口上にしても、たとえば、『いよいよお待ちかねの処女幕をあけまアす』と云った風で、万事がその調子だ。下らないとか、馬鹿げているとか、貶してみても、いつしか、そうした卑猥な調子のかもし出す妙にネバネバした雰囲気に、観客自身すっかり包まれているのだ」
うっかりしていたが、この手の演し物も、今や絶滅の危機に瀕しているんじゃないだろうか。
「裸体派」(1957年『宝石』)
山ですっぱだかの女性の死体が発見された。
直前に、ヘリコプターからその女性と、野糞プリンスと呼ばれる男子高校生が2人ともに裸でいるところを目撃されている。だが、その野糞プリンスは現場から忽然と姿を消してしまったのだ。彼はハンサムで、バスの車掌も峠茶屋、うどん屋にいたるまで、顔をすっかり覚えられている存在で、どこへ逃げても人目をひくはずなのに、である。
彼が「野糞プリンス」と呼ばれるのは、キャンプで草むらなどで普通、用をたす場合でも、彼は広々とした草原で人目をはばからずに放尿脱糞するからだ。
それは、彼の純粋さから来るもので、「彼は人間の衣裳があらゆる虚偽と汚辱の始りと考えているのだ」とするヌーディストの発想を受け入れさせるにいたる。彼が山の中で全裸になっていたのはそういうわけなのだ。
寝ているあいだに、女性の死体をかたわらに置き去りにされ、困った彼は女装して逃げおおせたのであった。