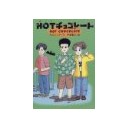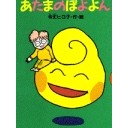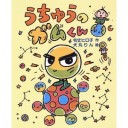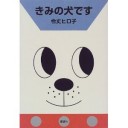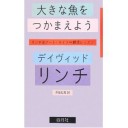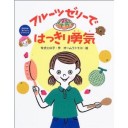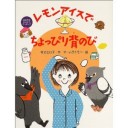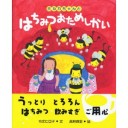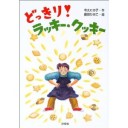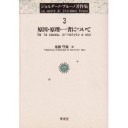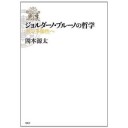『不安の時代-バロック風田園詩』
2012年7月26日 読書
オーデンの『不安の時代~バロック風田園詩~』を読んだ。1947年。
第1部 プロローグ
第2部 七つの時代
第3部 七つの段階
第4部 哀悼歌
第5部 仮面劇
第6部 エピローグ
大橋勇の解説にそって内容を簡単に書いておこう。
第1部 プロローグ/第二次大戦末期、居酒屋に集まった4人が、ラジオの戦争ニュースをきっかけに話し出す。それまでの内的独白は、みんな「多くの者が死んだが、さらに多くが死ぬだろう」で締めくくられる。不安の時代だ。ラジオが伝えるニュースは戦況だけでなく、断片的なコマーシャルなど。
第2部 七つの時代/西欧の深淵に落ち込んだ人間をテーマに語り合う4人。七つの時代とは、シェイクスピアの『お気に召すまま』で皮肉屋ジェークイズが言う、人生の七つの時期で、幼年期、学童時代、恋人時代、兵隊時代、裁判官時代、耄碌時代、第二の幼年期。人間の一生を概観して暗い人生観に到達した4人は、楽園探求の旅に出ることにする。
第3部 七つの段階/「七つの時代」で人間の一生をなぞったように、この「七つの段階」では人類の歴史を総括する。七つの段階は、出エジプト記や聖杯伝説を基にしているという。先史時代から古代文明を経て歴史が進むにつれ、自然破壊、敵対意識、労働の苦しみ、死の恐怖が生まれ、蒸気機関や専制君主が要請される。農家、王侯貴族の優雅な生活、都会、墓地をめぐり、洪水による世界の終末、氷河の出現による終末を想像したとき、嵐が吹き、風景が解体し、世界は崩壊する。はっと目覚めると4人はもとの居酒屋にいるのである。
第4部 哀悼歌/4人は、そのうちの1人のアパートで飲みなおすためにタクシーに乗る。そこで語られるのは、救世主不在の現代西欧世界の荒廃について。
第5部 仮面劇/アパートでパーティ。楽園かと思いきや、夢はさめて、現実が戻ってくる。
第6部 エピローグ/4人はそれぞれの現実に戻っていく。
なるほど。オーデン、奥が深いな。まだまだ全貌はつかめない。
第1部 プロローグ
第2部 七つの時代
第3部 七つの段階
第4部 哀悼歌
第5部 仮面劇
第6部 エピローグ
大橋勇の解説にそって内容を簡単に書いておこう。
第1部 プロローグ/第二次大戦末期、居酒屋に集まった4人が、ラジオの戦争ニュースをきっかけに話し出す。それまでの内的独白は、みんな「多くの者が死んだが、さらに多くが死ぬだろう」で締めくくられる。不安の時代だ。ラジオが伝えるニュースは戦況だけでなく、断片的なコマーシャルなど。
第2部 七つの時代/西欧の深淵に落ち込んだ人間をテーマに語り合う4人。七つの時代とは、シェイクスピアの『お気に召すまま』で皮肉屋ジェークイズが言う、人生の七つの時期で、幼年期、学童時代、恋人時代、兵隊時代、裁判官時代、耄碌時代、第二の幼年期。人間の一生を概観して暗い人生観に到達した4人は、楽園探求の旅に出ることにする。
第3部 七つの段階/「七つの時代」で人間の一生をなぞったように、この「七つの段階」では人類の歴史を総括する。七つの段階は、出エジプト記や聖杯伝説を基にしているという。先史時代から古代文明を経て歴史が進むにつれ、自然破壊、敵対意識、労働の苦しみ、死の恐怖が生まれ、蒸気機関や専制君主が要請される。農家、王侯貴族の優雅な生活、都会、墓地をめぐり、洪水による世界の終末、氷河の出現による終末を想像したとき、嵐が吹き、風景が解体し、世界は崩壊する。はっと目覚めると4人はもとの居酒屋にいるのである。
第4部 哀悼歌/4人は、そのうちの1人のアパートで飲みなおすためにタクシーに乗る。そこで語られるのは、救世主不在の現代西欧世界の荒廃について。
第5部 仮面劇/アパートでパーティ。楽園かと思いきや、夢はさめて、現実が戻ってくる。
第6部 エピローグ/4人はそれぞれの現実に戻っていく。
なるほど。オーデン、奥が深いな。まだまだ全貌はつかめない。
小沢書店版の『オーデン詩集』を読んだ。中桐雅夫訳・福間健二解説。
以下、目次。
1.1927~1932
きょうは顔をあげて
旅
自由な人間
かがり火
よく考えてみよ
見に行き給え
囮
三人の連れ
目撃者
2.1933~1938
獲物
フーズ・フー
この島で
夢
秋の歌
ローマン・ウォール・ブルース
「愛」ってなんなの、本当は?
子守唄
ある晩、ぼくは散歩に出て
戦いのときに
ある専制者の墓碑銘
3.1939~1947
W・B・イェイツをしのんで
1939年9月1日
もうひとつの時間
われわれの性癖
岐路に立って
聖セシーリア祭祝歌
教訓
4.1948~1971
たいせつな五感
支配人
正午の祈祷
聖金曜日の子
あのうえの
城壁なき都市
悪魔の唄
〔詩論・エッセイ〕
作ること、知ること、判断すること
〔詩人論・解説〕
ウィスタンのこと/スティーヴン・スペンダー
オーデンのモダニズムの書きかえ/エドワード・メンデルスン
解説(福間健二)
年譜
本書は詩人の中桐雅夫が翻訳したオーデンの詩を集めたもので、他社から出版されている詩集と重複した詩を割愛した内容になっている。中桐雅夫は推理小説の翻訳もしていて、読みたいと思っていた本もあるので、近いうちに読んでみるつもり。訳者の中桐雅夫に力点をおいた読み方になってしまったのは、オーデンの全貌がなかなかつかめないせいだ。オーデンというと、生まれたときからしわくちゃの顔をしてたんじゃないか、と錯覚してしまうような、年をとったイメージがあるが、本書でスペンダーが、オーデンにも若い頃があったという衝撃の事実を書いてくれている。
詩の数々も面白かったが、「作ること、知ること、判断すること」がオーデンの味を存分に出しているように思えた。これは1956年6月11日にオックスフォード大学で行われた詩学教授就任講演で、僕はもっと戦前のオーデンを、そして戦後のオーデンの長篇詩を読まねばならない。
以下、目次。
1.1927~1932
きょうは顔をあげて
旅
自由な人間
かがり火
よく考えてみよ
見に行き給え
囮
三人の連れ
目撃者
2.1933~1938
獲物
フーズ・フー
この島で
夢
秋の歌
ローマン・ウォール・ブルース
「愛」ってなんなの、本当は?
子守唄
ある晩、ぼくは散歩に出て
戦いのときに
ある専制者の墓碑銘
3.1939~1947
W・B・イェイツをしのんで
1939年9月1日
もうひとつの時間
われわれの性癖
岐路に立って
聖セシーリア祭祝歌
教訓
4.1948~1971
たいせつな五感
支配人
正午の祈祷
聖金曜日の子
あのうえの
城壁なき都市
悪魔の唄
〔詩論・エッセイ〕
作ること、知ること、判断すること
〔詩人論・解説〕
ウィスタンのこと/スティーヴン・スペンダー
オーデンのモダニズムの書きかえ/エドワード・メンデルスン
解説(福間健二)
年譜
本書は詩人の中桐雅夫が翻訳したオーデンの詩を集めたもので、他社から出版されている詩集と重複した詩を割愛した内容になっている。中桐雅夫は推理小説の翻訳もしていて、読みたいと思っていた本もあるので、近いうちに読んでみるつもり。訳者の中桐雅夫に力点をおいた読み方になってしまったのは、オーデンの全貌がなかなかつかめないせいだ。オーデンというと、生まれたときからしわくちゃの顔をしてたんじゃないか、と錯覚してしまうような、年をとったイメージがあるが、本書でスペンダーが、オーデンにも若い頃があったという衝撃の事実を書いてくれている。
詩の数々も面白かったが、「作ること、知ること、判断すること」がオーデンの味を存分に出しているように思えた。これは1956年6月11日にオックスフォード大学で行われた詩学教授就任講演で、僕はもっと戦前のオーデンを、そして戦後のオーデンの長篇詩を読まねばならない。
『老いと勝負と信仰と』
2012年7月23日 読書
加藤一二三九段の『老いと勝負と信仰と』を読んだ。
加藤九段は将棋の棋士であるが、バチカンから「聖シルベストロ教皇騎士団勲章」を授与されたカトリックの騎士でもある。
本書は加藤九段が将棋と信仰について語ったものをまとめたものだが、タイトルにある「老い」については、本人がまったく老いを感じていないことを思い知らされる一方である。
以下、目次
はじめに 棋士として騎士として
「確かなもの」「ゆるぎなきもの」を求め続けたい/将棋は芸術である/将棋で信仰を語る
第1部 勝負と信仰
第1章 勝負も信仰も<真剣に>勝ち取るものである
勝負を捨てたことは一度もない/計7時間の長考で確信した「妙手」/真剣でなければ、求めても与えられない
第2章 祈りは人を強くする勝負強くする
祈りが直接結びついた対局 王将戦/米長八段との順位戦/攻めるべきか自重すべきか、有吉八段との順位戦/キリストの教えが凝縮された「主の祈り」/[初めて」に差し伸べられる、大いなる手/祈りは魂の呼吸
第3章 「直感精読」初めに感じたことが正しい
迷ったら初めの考えが正しい/直感の素晴らしさ/ひらめき、信じることの大切さ
第4章 剛毅と柔和を知ればおそれない、ひるまない
剛毅の欠如は敗北の始まり/名人戦/「柔和」とは、物事に動じないこと/剛毅と柔和を実践したコルベ神父/明日のことを思い悩まない
第5章 人は不完全だからおもしろい、だから生まれる勝負のあや
人は不完全だからポカもある/十段戦 詰まされていた/NHK杯/神の恩寵は自然を完成させる
第6章 負けを引きずらない、それが希望につながる
負け数が多いのは第一線で戦ってきた強さの証/負けることより怠ることのほうが罪/負けから学ぶべきこと/負けは希望を生み出す/スランプとは何か、相性とは何か、1勝19敗を克服
第7章 心地よく生きる、気持ちよく勝負する術
駒音の高さは調子のバロメータ/本当に大切なものは何かを見極める目/いかに心地いい状態をつくるかが大切/いかに憂いをなくすか ギデオンの教え/加藤一二三伝説誕生の理由
第2部 71歳生涯現役加藤一二三の元気の源
1「将棋」
自分のスタイルを変えず、極める姿勢を持ち続ける
勝ち負けに一喜一憂しない 弱いとは思わない
2「駒落ち」
福沢諭吉に学ぶ
将棋の「駒落ち」を人間関係にも応用
3「好敵手」
自ら求める「いい出会い」
好敵手がいるから高められる
4「好敵手(2)次世代」
新しい局面に出合い
若手棋士から刺激を得る
5「猫の絵本」
ベネディクト16世の猫の絵本
~小さなものをつまずかせてはいけない~
6「聖人伝」
ハウツー本だけではなく
偉人伝をゆっくり何度も読む
7「結婚直前準備講座」
30年続ける結婚講座
~若い人との接点を持つ
8「告解 ゆるしの秘跡」
ゆるすことで
初めて自分もゆるされる
9「旅 巡礼」
非日常の世界に身をおくことで
自分をリセットする
10「絵画・彫刻」
時と場所を惜しまず
いいものにたくさん出合う
11「モーツァルト」
ながら聴きでなく
集中して音楽を聴く
12「家族」
おじいちゃんではなく「パイ」
明るい家庭を築く大事さ
13「現代の偉人」
ヨハネ・パウロ2世の
剛毅と柔和にならう
14「聖書」
聖書は喜ばしきものを伝える便り、
読むと必ず元気になります
15「老いと信仰」
「新しきを学ぶ」「経験を語る」ことで、
前向きになれる
あとがきの前に 新加藤一二三伝説
最後の「新伝説」は、「抱いた幼子は泣かない」というものだ。きもちよく赤子が眠ってしまうのではなく、ぱっちり目覚めた状態で、赤子は加藤九段に抱かれているのである。
つい先日も、つづけて2手指して反則負けを喫す、など、将棋界の話題を次々と提供してくれる加藤九段のこれからの活躍を祈る。
加藤九段は将棋の棋士であるが、バチカンから「聖シルベストロ教皇騎士団勲章」を授与されたカトリックの騎士でもある。
本書は加藤九段が将棋と信仰について語ったものをまとめたものだが、タイトルにある「老い」については、本人がまったく老いを感じていないことを思い知らされる一方である。
以下、目次
はじめに 棋士として騎士として
「確かなもの」「ゆるぎなきもの」を求め続けたい/将棋は芸術である/将棋で信仰を語る
第1部 勝負と信仰
第1章 勝負も信仰も<真剣に>勝ち取るものである
勝負を捨てたことは一度もない/計7時間の長考で確信した「妙手」/真剣でなければ、求めても与えられない
第2章 祈りは人を強くする勝負強くする
祈りが直接結びついた対局 王将戦/米長八段との順位戦/攻めるべきか自重すべきか、有吉八段との順位戦/キリストの教えが凝縮された「主の祈り」/[初めて」に差し伸べられる、大いなる手/祈りは魂の呼吸
第3章 「直感精読」初めに感じたことが正しい
迷ったら初めの考えが正しい/直感の素晴らしさ/ひらめき、信じることの大切さ
第4章 剛毅と柔和を知ればおそれない、ひるまない
剛毅の欠如は敗北の始まり/名人戦/「柔和」とは、物事に動じないこと/剛毅と柔和を実践したコルベ神父/明日のことを思い悩まない
第5章 人は不完全だからおもしろい、だから生まれる勝負のあや
人は不完全だからポカもある/十段戦 詰まされていた/NHK杯/神の恩寵は自然を完成させる
第6章 負けを引きずらない、それが希望につながる
負け数が多いのは第一線で戦ってきた強さの証/負けることより怠ることのほうが罪/負けから学ぶべきこと/負けは希望を生み出す/スランプとは何か、相性とは何か、1勝19敗を克服
第7章 心地よく生きる、気持ちよく勝負する術
駒音の高さは調子のバロメータ/本当に大切なものは何かを見極める目/いかに心地いい状態をつくるかが大切/いかに憂いをなくすか ギデオンの教え/加藤一二三伝説誕生の理由
第2部 71歳生涯現役加藤一二三の元気の源
1「将棋」
自分のスタイルを変えず、極める姿勢を持ち続ける
勝ち負けに一喜一憂しない 弱いとは思わない
2「駒落ち」
福沢諭吉に学ぶ
将棋の「駒落ち」を人間関係にも応用
3「好敵手」
自ら求める「いい出会い」
好敵手がいるから高められる
4「好敵手(2)次世代」
新しい局面に出合い
若手棋士から刺激を得る
5「猫の絵本」
ベネディクト16世の猫の絵本
~小さなものをつまずかせてはいけない~
6「聖人伝」
ハウツー本だけではなく
偉人伝をゆっくり何度も読む
7「結婚直前準備講座」
30年続ける結婚講座
~若い人との接点を持つ
8「告解 ゆるしの秘跡」
ゆるすことで
初めて自分もゆるされる
9「旅 巡礼」
非日常の世界に身をおくことで
自分をリセットする
10「絵画・彫刻」
時と場所を惜しまず
いいものにたくさん出合う
11「モーツァルト」
ながら聴きでなく
集中して音楽を聴く
12「家族」
おじいちゃんではなく「パイ」
明るい家庭を築く大事さ
13「現代の偉人」
ヨハネ・パウロ2世の
剛毅と柔和にならう
14「聖書」
聖書は喜ばしきものを伝える便り、
読むと必ず元気になります
15「老いと信仰」
「新しきを学ぶ」「経験を語る」ことで、
前向きになれる
あとがきの前に 新加藤一二三伝説
最後の「新伝説」は、「抱いた幼子は泣かない」というものだ。きもちよく赤子が眠ってしまうのではなく、ぱっちり目覚めた状態で、赤子は加藤九段に抱かれているのである。
つい先日も、つづけて2手指して反則負けを喫す、など、将棋界の話題を次々と提供してくれる加藤九段のこれからの活躍を祈る。
ヌッチョ・オルディネの『ロバのカバラ-ジョルダーノ・ブルーノにおける文学と哲学-』を読んだ。
以下、目次。
1.ブルーノとロバ―先送りされた問い
2.神話、寓話、物語―「ロバ」の素材
「有益な」対「悪霊的な」
「強力な」対「卑しい」
「知恵のある」対「無知な」
3.ロバとメルクリウス―「対立物の一致」の暗号
4.ロバ性の両義的空間
5.人間とロバ―「獣性」と「神性」の狭間で
6.肯定的ロバ性―労苦、謙遜、忍耐
7.否定的ロバ性―閑暇、傲慢、一面性
a)黄金時代の神話
b)懐疑主義者たちとアリストテレス主義者たち
c)キリストと福音主義的改革者たち
8.運命の演説
9.真理の迷宮の中で
10.オリオンからキロンへ―宗教的祭祀の対立するイメージ
11.シレノスとしてのロバ-外観の欺瞞について
12.ブルーノ以前のロバの文学
ピーノの『考察』
マキアヴェッリの『ロバ』と他の例
パラドクスの文学
13.文のエントロピー
14.自然科学と人文科学-「新しい同盟」
ロバによって象徴(代表)される対立物の一致についての考察。両義的存在は、ロバ以外だと、老人とか子供とかしか思い浮かばないが、何かないかな。
以下、目次。
1.ブルーノとロバ―先送りされた問い
2.神話、寓話、物語―「ロバ」の素材
「有益な」対「悪霊的な」
「強力な」対「卑しい」
「知恵のある」対「無知な」
3.ロバとメルクリウス―「対立物の一致」の暗号
4.ロバ性の両義的空間
5.人間とロバ―「獣性」と「神性」の狭間で
6.肯定的ロバ性―労苦、謙遜、忍耐
7.否定的ロバ性―閑暇、傲慢、一面性
a)黄金時代の神話
b)懐疑主義者たちとアリストテレス主義者たち
c)キリストと福音主義的改革者たち
8.運命の演説
9.真理の迷宮の中で
10.オリオンからキロンへ―宗教的祭祀の対立するイメージ
11.シレノスとしてのロバ-外観の欺瞞について
12.ブルーノ以前のロバの文学
ピーノの『考察』
マキアヴェッリの『ロバ』と他の例
パラドクスの文学
13.文のエントロピー
14.自然科学と人文科学-「新しい同盟」
ロバによって象徴(代表)される対立物の一致についての考察。両義的存在は、ロバ以外だと、老人とか子供とかしか思い浮かばないが、何かないかな。
マーティン・ジェイの『アドルノ』を読んだ。
以下、目次。
序文
1 ある傷ついた生活
2 無調の哲学
3 砕かれた全体性―社会と心理
4 操作としての文化、救済としての文化
結び
訳者あとがきによると、それぞれの内容は次のとおり。
1 ある傷ついた生活(ひととなりと経歴)
2 無調の哲学(哲学思想)
3 砕かれた全体性―社会と心理(社会思想)
4 操作としての文化、救済としての文化(文化論・芸術論)
以下、目次。
序文
1 ある傷ついた生活
2 無調の哲学
3 砕かれた全体性―社会と心理
4 操作としての文化、救済としての文化
結び
訳者あとがきによると、それぞれの内容は次のとおり。
1 ある傷ついた生活(ひととなりと経歴)
2 無調の哲学(哲学思想)
3 砕かれた全体性―社会と心理(社会思想)
4 操作としての文化、救済としての文化(文化論・芸術論)
『おなやみジュース』『うらない屋コノミちゃん』
2012年6月26日 読書
令丈ヒロ子さんの『おなやみジュース』と『うらない屋コノミちゃん』を読んだ。
『おなやみジュース』は、15歳の寺子屋シリーズのエッセイ。自分の半生を振り返りながら、悩む思春期のこどもたちに向けて書かれている。
そのなかで、令丈さんが占いに凝っていることが書いてあった。それで、『ホンマに運命』とか、そういう占いを題材にした作品ができたんだな、と納得。
また、お悩み解決が好きだった、というのは、令丈さんのいままでの著作に如実にあらわれている。
こうして本を書くことで、思春期の主に女性の悩みにアドバイスできているわけだから、幼い頃の夢が叶えられているわけである。
また、その後、雑誌小学3年生に連載されたものに加筆訂正をした『うらない屋コノミちゃん』を読んだ。
占いものだ!
この本については、令丈さんの作品にしては珍しく、あきらかに悪の側の存在が描かれている。わかりやすい敵を描いて、それに対抗し、撃破する、という図式は非常に面白いのだが、一面的になりやすい。令丈さんの作品は、たとえ敵であっても、愛すべき存在であったり、一方的な悪の存在は登場しなかったはずなのに、この本はいったい!これは令丈さんにとっては、かなり珍しい部類の本になると思った。
『おなやみジュース』は、15歳の寺子屋シリーズのエッセイ。自分の半生を振り返りながら、悩む思春期のこどもたちに向けて書かれている。
そのなかで、令丈さんが占いに凝っていることが書いてあった。それで、『ホンマに運命』とか、そういう占いを題材にした作品ができたんだな、と納得。
また、お悩み解決が好きだった、というのは、令丈さんのいままでの著作に如実にあらわれている。
こうして本を書くことで、思春期の主に女性の悩みにアドバイスできているわけだから、幼い頃の夢が叶えられているわけである。
また、その後、雑誌小学3年生に連載されたものに加筆訂正をした『うらない屋コノミちゃん』を読んだ。
占いものだ!
この本については、令丈さんの作品にしては珍しく、あきらかに悪の側の存在が描かれている。わかりやすい敵を描いて、それに対抗し、撃破する、という図式は非常に面白いのだが、一面的になりやすい。令丈さんの作品は、たとえ敵であっても、愛すべき存在であったり、一方的な悪の存在は登場しなかったはずなのに、この本はいったい!これは令丈さんにとっては、かなり珍しい部類の本になると思った。
『HOTチョコレート』『あたまのぽよよん』『うちゅうのガムくん』
2012年6月23日 読書
令丈ヒロ子さんの『HOTチョコレート』『あたまのぽよよん』『うちゅうのガムくん』を読んだ。
『HOTチョコレート』は、吸血鬼もの。血よりもホットチョコレートのほうがすき、という吸血鬼の少年。孤独な吸血鬼少年に同情して、自分も吸血鬼になってしまおう、とする少年と、その少年が好きな少女を主人公にしている。
吸血鬼になりかけて、そのパワーに能天気にはしゃぐ少年と、人間でなくなってしまうことについて悲しんでしまう少女。
『あたまのぽよよん』は人の本心が見えてしまう話。エスパーものだが、そのとっかかりの面白さだけを提供してくれるので、きっと、この本読んだこどもは、自分なりのストーリーを紡ぐんだろうなあ。
『うちゅうのガムくん』は、宇宙人もの。でも、ガムなのだ。
『HOTチョコレート』は、吸血鬼もの。血よりもホットチョコレートのほうがすき、という吸血鬼の少年。孤独な吸血鬼少年に同情して、自分も吸血鬼になってしまおう、とする少年と、その少年が好きな少女を主人公にしている。
吸血鬼になりかけて、そのパワーに能天気にはしゃぐ少年と、人間でなくなってしまうことについて悲しんでしまう少女。
『あたまのぽよよん』は人の本心が見えてしまう話。エスパーものだが、そのとっかかりの面白さだけを提供してくれるので、きっと、この本読んだこどもは、自分なりのストーリーを紡ぐんだろうなあ。
『うちゅうのガムくん』は、宇宙人もの。でも、ガムなのだ。
『タビねこくん』『きみの犬です』『××天使』
2012年6月22日 読書
令丈ヒロ子さんの『タビねこくん』『きみの犬です』『××天使』を読んだ。
『タビねこくん』は、人間の言葉を話せて二足歩行しちゃう猫の物語。
猫と人間とでは成長の速度が違うので、主人公のこどもをどんどん追い抜いて大人になっていく、のかな、と思ったら、まだまだ幼い面も残していて、ほっとするやら、ちょっと心配するやら。
つきつめていくと、ジェニーの肖像みたいな結末になるのかもしれないけど、あえてその後どうなったのか、は描かないところが、想像力をかきたてるところでる。
『きみの犬です』もちょっとSFっぽい設定。死んでしまった愛犬の魂がのりうつった少年と、その犬の飼い主でもあった少女との切なく淡い物語。落語の「犬の目」みたいな展開もあり、また、本当に少年は犬の魂を宿していたのかについて、考えさせる。
『××天使』は、天使みならいが下界でコメットさんみたいな活躍。天使から見た人間の世界の描写が、面白い。
今日読んだ3冊は、それぞれ楽しくて、せつなさも感じさせる名作ぞろいだった。
『タビねこくん』は、人間の言葉を話せて二足歩行しちゃう猫の物語。
猫と人間とでは成長の速度が違うので、主人公のこどもをどんどん追い抜いて大人になっていく、のかな、と思ったら、まだまだ幼い面も残していて、ほっとするやら、ちょっと心配するやら。
つきつめていくと、ジェニーの肖像みたいな結末になるのかもしれないけど、あえてその後どうなったのか、は描かないところが、想像力をかきたてるところでる。
『きみの犬です』もちょっとSFっぽい設定。死んでしまった愛犬の魂がのりうつった少年と、その犬の飼い主でもあった少女との切なく淡い物語。落語の「犬の目」みたいな展開もあり、また、本当に少年は犬の魂を宿していたのかについて、考えさせる。
『××天使』は、天使みならいが下界でコメットさんみたいな活躍。天使から見た人間の世界の描写が、面白い。
今日読んだ3冊は、それぞれ楽しくて、せつなさも感じさせる名作ぞろいだった。
『大きな魚をつかまえよう』
2012年6月21日 読書
デイヴィッド・リンチの『大きな魚をつかまえよう』を読んだ。サブタイトルにもあるように、リンチ流アートライフ&瞑想レッスンで、超越瞑想(TM)のことについても語っている。瞑想の方法を説く本ではなく、あくまでも映画などについてのエッセイで占められているが、難解そうな映画の印象とはうってかわって、本書でのリンチの文章は「大丈夫か?」と危惧するほどに純朴な感じだ。
以下、目次。
はじめに
最初のダイヴ
窒息用ゴム製道化服
人生の始まり
アート・ライフ
夜の庭園
幕が上がる
映画
解釈
円環
アイデア
欲望
意識
アイデアを翻訳しよう
ロサンジェルス
イレイザーヘッド
人生の速度
ヨガの修行僧たち
ボブズ・ビッグ・ボーイ
世界でいちばん怒っている犬
音楽
直感
統一場
四番目の意識状態
着実に進もう
近代科学と古代科学
いつでも、どこでも
存在の同一性
ファイナル・カット
セラピー
夢
アンジェロ・バダラメンティ
音響
配役
リハーサル
恐怖
さあ一緒に
ツイン・ピークス
連続ドラマ
赤い部屋
アイデアに訊け
テスト上映
一般化
闇
苦悩
セルフの光
黄金の塔
宗教
ドラッグ
明かりを点けろ
インダストリアル・シンフォニー1番
ロスト・ハイウェイ
制約
マルホランド・ドライブ
箱と鍵
場所の感覚
美
質感
大工の手仕事
セット・アップしよう
炎
映画の光
ストレイト・ストーリー
映画の偉人たち
フェリーニ
キューブリック
インランド・エンパイア
タイトル
新しい仕事の方法
映画監督のコメンタリー
フィルムの死
若い映画監督のデジタル・ビデオ
デジタル・ビデオのクオリティ
映画の未来
常識
アドバイス
睡眠
根気よく続けよう
成功と失敗
また釣りに行こう
思いやり
意識に基づく教育
ほんとうの平和
おわりに
コーダ 真の幸福は内側にある
自選フィルモグラフィ
クリント・イーストウッドのメッセージ
リンチ・瞑想・ビートルズ/草坂虹惠(訳者あとがき)
本書でリンチは、DVDに副音声をつけない理由を説明していたり、撮影媒体でフィルムを使うのはやめたと宣言していたり、といろいろ面白いが、読後今でもひきずっているのは、イレイザーヘッドのくだり。
この「イレイザーヘッド」では、作るうちに作品がある方向に進化していて、監督自身、それぞれのシークエンスが何を物語るのか、意味がわからなかったらしい。悪戦苦闘の末、ある日聖書を開いてみたら、ある一節が目に止まり「そうだったのか!」と全体像をつかむことができたのだと言う。リンチは、文章をこうしめくくっている。
「それがどんな一節なのか、決して言うことはないだろう」
知りたい~!
以下、目次。
はじめに
最初のダイヴ
窒息用ゴム製道化服
人生の始まり
アート・ライフ
夜の庭園
幕が上がる
映画
解釈
円環
アイデア
欲望
意識
アイデアを翻訳しよう
ロサンジェルス
イレイザーヘッド
人生の速度
ヨガの修行僧たち
ボブズ・ビッグ・ボーイ
世界でいちばん怒っている犬
音楽
直感
統一場
四番目の意識状態
着実に進もう
近代科学と古代科学
いつでも、どこでも
存在の同一性
ファイナル・カット
セラピー
夢
アンジェロ・バダラメンティ
音響
配役
リハーサル
恐怖
さあ一緒に
ツイン・ピークス
連続ドラマ
赤い部屋
アイデアに訊け
テスト上映
一般化
闇
苦悩
セルフの光
黄金の塔
宗教
ドラッグ
明かりを点けろ
インダストリアル・シンフォニー1番
ロスト・ハイウェイ
制約
マルホランド・ドライブ
箱と鍵
場所の感覚
美
質感
大工の手仕事
セット・アップしよう
炎
映画の光
ストレイト・ストーリー
映画の偉人たち
フェリーニ
キューブリック
インランド・エンパイア
タイトル
新しい仕事の方法
映画監督のコメンタリー
フィルムの死
若い映画監督のデジタル・ビデオ
デジタル・ビデオのクオリティ
映画の未来
常識
アドバイス
睡眠
根気よく続けよう
成功と失敗
また釣りに行こう
思いやり
意識に基づく教育
ほんとうの平和
おわりに
コーダ 真の幸福は内側にある
自選フィルモグラフィ
クリント・イーストウッドのメッセージ
リンチ・瞑想・ビートルズ/草坂虹惠(訳者あとがき)
本書でリンチは、DVDに副音声をつけない理由を説明していたり、撮影媒体でフィルムを使うのはやめたと宣言していたり、といろいろ面白いが、読後今でもひきずっているのは、イレイザーヘッドのくだり。
この「イレイザーヘッド」では、作るうちに作品がある方向に進化していて、監督自身、それぞれのシークエンスが何を物語るのか、意味がわからなかったらしい。悪戦苦闘の末、ある日聖書を開いてみたら、ある一節が目に止まり「そうだったのか!」と全体像をつかむことができたのだと言う。リンチは、文章をこうしめくくっている。
「それがどんな一節なのか、決して言うことはないだろう」
知りたい~!
『フランソワーズ・アルヌール自伝-映画が神話だった時代』
2012年6月20日 読書 コメント (1)
『フランソワーズ・アルヌール自伝』を読んだ。
以下、目次。
1.「芸名はアルヌールにしましょうよ」母はそう提案した
2.映画への憧れと夢を育んだ、モロッコでの少女時代
3.私はおとぎ話を固く信じていた そして、それは現実になった
4.内気ではにかみ屋だった17歳の私『漂流物』で映画デビュー
5.映画仲間と一緒にいるのは、なんて幸福で自由なのだろう
6.マリナ・ヴラディと過ごした頃のことは、私の人生に刻み込まれた
7.『グルネル河岸通り』と『赤いバラ』での奇妙な体験
8.『欲望と愛』をはじめ、仕事を通じて多くを学んだ
9.『禁断の木の実』のヒットで、もう一人の自分が独り歩きし始めた
10.『トレドの恋人たち』のロケで、スペインへ
11.『過去をもつ愛情』で再びヴェルヌイユ監督と組む
12.『フレンチ・カンカン』は私にとって、終わりのない物語である
13.シモーヌ・シニョレも私も、強烈で手応えのある人生にひかれていた
14.『ヘッドライト』と共に私は世界を駆けめぐった
15.シャルル・トルネの家では子供時代を思い返した
16.失敗もしたけれど悔やんではいない
17.『幸福への招待』、そしてジョルジュとの結婚
18.パリのドーフィーヌ広場、イヴ・モンタンのアパルトマンで
19.モンタンとシニョレの家での充実した日々
20.『大運河』撮影のため、真冬のヴェネツィアへ
21.『幸福への招待』上映のためアメリカへ ジェラール・フィリップと出会う
22.『女猫』への出演で、私はさまざまなことを考えた
23.『学生たちの道』と『アスファルト』新聞王ラザレフの家での日曜日
24.『愛のシーズンオフ』の撮影 結婚の破綻という苦い思いの中で
25.アラン・ドロンのように、私は日本で愛される俳優の一人になった
26.カトリーヌ・ドヌーブは、誰の目にも明らかにスターだ
27.私とシモーヌは、モンタンの稽古を見て幸せをかみしめた
28.たとえ必需品でなくても、私はゴージャスなものが好きだ
29.『爪を磨く野獣』に出ていたあの頃 私にとってのアルジェリア戦争
30.ベルナール・ポールと出会い、『夫婦』に取り組んだ日々
31.『正義の人びと』で初舞台を踏む 怖れで胃が締めつけられる思いで
32.私たちは世の中を変えることを夢み、公平で人間的な世の中にしたいと思った
33.ベルナール、ルイ・ダカンらとの出会いで、新しい世界が開けた
34.ベルナールとの日々 私は自分の仕事を犠牲にしていなかっただろうか?
35.病を、彼の闘いを、私たちは分かち合った
36.水底を蹴って水面に浮かび上がる
本書はジャン=ルイ・マンガロンの協力を得て書かれた自伝で、裏話もたくさん書いてあるし、政治や社会的なこととの関わりについても興味深い発言があった。
裏話で言えば、たとえば、映画『漂流物』で彼女にはヌードのシーンがあるが、当時彼女は17歳で、法律で守られており、体育教師がスタンドインをしていたそうだ。体型がぜんぜん違うのに、スタンドインに気づいた人はいなかったという。
また、同じ『漂流物』で彼女が歌うシーンもあったが、これも吹き替えで、シャンソン界のスター、マリー=ジョゼが歌ったそうだ。そのせいで、彼女は驚くべき音域の持ち主だとずっと誤解され、映画の宣伝のときなどに、歌を披露するような提案がなされると、何かと理由をつけて断っていたそうだ。
政治との関わりについても面白い部分があって、それはいずれ、引用とともに、追記予定。
以下、目次。
1.「芸名はアルヌールにしましょうよ」母はそう提案した
2.映画への憧れと夢を育んだ、モロッコでの少女時代
3.私はおとぎ話を固く信じていた そして、それは現実になった
4.内気ではにかみ屋だった17歳の私『漂流物』で映画デビュー
5.映画仲間と一緒にいるのは、なんて幸福で自由なのだろう
6.マリナ・ヴラディと過ごした頃のことは、私の人生に刻み込まれた
7.『グルネル河岸通り』と『赤いバラ』での奇妙な体験
8.『欲望と愛』をはじめ、仕事を通じて多くを学んだ
9.『禁断の木の実』のヒットで、もう一人の自分が独り歩きし始めた
10.『トレドの恋人たち』のロケで、スペインへ
11.『過去をもつ愛情』で再びヴェルヌイユ監督と組む
12.『フレンチ・カンカン』は私にとって、終わりのない物語である
13.シモーヌ・シニョレも私も、強烈で手応えのある人生にひかれていた
14.『ヘッドライト』と共に私は世界を駆けめぐった
15.シャルル・トルネの家では子供時代を思い返した
16.失敗もしたけれど悔やんではいない
17.『幸福への招待』、そしてジョルジュとの結婚
18.パリのドーフィーヌ広場、イヴ・モンタンのアパルトマンで
19.モンタンとシニョレの家での充実した日々
20.『大運河』撮影のため、真冬のヴェネツィアへ
21.『幸福への招待』上映のためアメリカへ ジェラール・フィリップと出会う
22.『女猫』への出演で、私はさまざまなことを考えた
23.『学生たちの道』と『アスファルト』新聞王ラザレフの家での日曜日
24.『愛のシーズンオフ』の撮影 結婚の破綻という苦い思いの中で
25.アラン・ドロンのように、私は日本で愛される俳優の一人になった
26.カトリーヌ・ドヌーブは、誰の目にも明らかにスターだ
27.私とシモーヌは、モンタンの稽古を見て幸せをかみしめた
28.たとえ必需品でなくても、私はゴージャスなものが好きだ
29.『爪を磨く野獣』に出ていたあの頃 私にとってのアルジェリア戦争
30.ベルナール・ポールと出会い、『夫婦』に取り組んだ日々
31.『正義の人びと』で初舞台を踏む 怖れで胃が締めつけられる思いで
32.私たちは世の中を変えることを夢み、公平で人間的な世の中にしたいと思った
33.ベルナール、ルイ・ダカンらとの出会いで、新しい世界が開けた
34.ベルナールとの日々 私は自分の仕事を犠牲にしていなかっただろうか?
35.病を、彼の闘いを、私たちは分かち合った
36.水底を蹴って水面に浮かび上がる
本書はジャン=ルイ・マンガロンの協力を得て書かれた自伝で、裏話もたくさん書いてあるし、政治や社会的なこととの関わりについても興味深い発言があった。
裏話で言えば、たとえば、映画『漂流物』で彼女にはヌードのシーンがあるが、当時彼女は17歳で、法律で守られており、体育教師がスタンドインをしていたそうだ。体型がぜんぜん違うのに、スタンドインに気づいた人はいなかったという。
また、同じ『漂流物』で彼女が歌うシーンもあったが、これも吹き替えで、シャンソン界のスター、マリー=ジョゼが歌ったそうだ。そのせいで、彼女は驚くべき音域の持ち主だとずっと誤解され、映画の宣伝のときなどに、歌を披露するような提案がなされると、何かと理由をつけて断っていたそうだ。
政治との関わりについても面白い部分があって、それはいずれ、引用とともに、追記予定。
令丈ヒロ子さんの「おなやみかいけつクッキング」シリーズを読んだ。
『フルーツゼリーではっきり勇気』
『チョコブラウニーですなおに笑顔』
『レモンアイスでちょっぴり背のび』
『いちごムースでいつもの元気』
それぞれ、レシピもついている。
宇宙からきたピチが、コメットさんみたいに、お悩みをクッキングで解決していく話だが、悩みをどんよりとさせる側のキャラクターも出して、悪や堕落への誘惑が常に隙をうかがっていることを忘れていない。
『フルーツゼリーではっきり勇気』
『チョコブラウニーですなおに笑顔』
『レモンアイスでちょっぴり背のび』
『いちごムースでいつもの元気』
それぞれ、レシピもついている。
宇宙からきたピチが、コメットさんみたいに、お悩みをクッキングで解決していく話だが、悩みをどんよりとさせる側のキャラクターも出して、悪や堕落への誘惑が常に隙をうかがっていることを忘れていない。
『ミルカちゃんとはちみつおためしかい』『どっきり!ラッキー・クッキー』
2012年6月12日 読書
ジョルダーノ・ブルーノの『カンデライオ』を読んだ。
下ネタも満載の喜劇!
カンデライオ(蝋燭職人)という言葉が、既に女性を相手にせずにいい年まで来た男を指すスラングみたいなもので、おかま、とか男色家とかいうニュアンスがあるようだ。オナニストのことなのかな、と思ってた。主人公は妻をめとっているし。
話の内容は、美貌の妻を持ちながらセクシーな女にのぼせあがってしまう主人公と、その美貌の妻を狙う男などがおりなす艶笑喜劇。
衒学者で、ラテン語を駆使してなんでもかんでも難しくしゃべる男は、さんざんひどい目にあってからかわれる。泥棒にあっても、その泥棒をつかまえてくれ、と叫ぶのに、言葉の正確さにこだわり、挙げ句の果てに、普通の市民にとってちんぷんかんぷんの言葉を使うはめになる、とか。(クイーンの『最後の女』みたいなアイディア!)
下ネタも満載の喜劇!
カンデライオ(蝋燭職人)という言葉が、既に女性を相手にせずにいい年まで来た男を指すスラングみたいなもので、おかま、とか男色家とかいうニュアンスがあるようだ。オナニストのことなのかな、と思ってた。主人公は妻をめとっているし。
話の内容は、美貌の妻を持ちながらセクシーな女にのぼせあがってしまう主人公と、その美貌の妻を狙う男などがおりなす艶笑喜劇。
衒学者で、ラテン語を駆使してなんでもかんでも難しくしゃべる男は、さんざんひどい目にあってからかわれる。泥棒にあっても、その泥棒をつかまえてくれ、と叫ぶのに、言葉の正確さにこだわり、挙げ句の果てに、普通の市民にとってちんぷんかんぷんの言葉を使うはめになる、とか。(クイーンの『最後の女』みたいなアイディア!)
『ジョルダーノ・ブルーノの哲学 生の多様性へ』
2012年6月4日 読書
岡本源太の『ジョルダーノ・ブルーノの哲学 生の多様性へ』を読んだ。
序章 ジョイス 憐れみの感覚
第1章 ディオ・デ・ラ・テッラ 人間と動物
第2章 セラピス 感情と時間
第3章 コヘレト 無知と力
第4章 ペルセウス 善悪と共生
第5章 ヘレネ 芸術と創造
第6章 アクタイオン 生死と流転
終章 ブルーノ 生の多様性
附録 ジェイムズ・ジョイス「ブルーノ哲学」
「ルネサンスの世界文学的影響」
ジョイスは「ベーコンやデカルト以上に、ブルーノこそ、近代哲学と呼ばれているものの父と考えられるべきだ」と評価している。
ブルーノは近代の先駆と解釈されることが多々あるが、そういった先駆性のみで語られるのでは不十分である。
ジョイスが言う「ルネサンスは、そのほかにはなにもしなかったのだとしても、生きて希望をもっては死んで失望するあらゆる存在への憐れみの感覚を、わたしたち自身とわたしたちの芸術のうちに創造したことで、多くのものをなしとげただろう」での「憐れみの感覚」を理解するために、本書は書かれた、と著者は言う。
本書で印象に残るのは、「複合的で、相反するものの一致」をブルーノが手をかえ品をかえ、主張していた、ということ。
あと、各章題の簡単な説明補足を書いておこう。
ディオ・デ・ラ・テッラ(地上の神=人間)
セラピス(古代の神。蛇の絡みついた胴のうえに狼、獅子、犬の3つの頭をもつ獣をしたがえている。狼はうしろ=過去を見て遠吠えし、獅子は横=現在を見てうなり、犬は前=未来を見て喜んでいる)
コヘレト(旧約聖書コヘレトの言葉=伝道の書)「知識が増せば痛みも増す」
ペルセウス(無為をしりぞけ、労苦こそが人間にはふさわしい)
ヘレネ(画家ゼウクシスがクロトンの5人の乙女からもっとも美しい部位を選び集めてヘレネの肖像を描いた逸話から、美が多様であること)
アクタイオン(水浴中のアルテミスを見た狩人アクタイオンが、鹿に変えられて、みずからの猟犬に食い殺されてしまう神話から、猟犬=思考の類比)
序章 ジョイス 憐れみの感覚
第1章 ディオ・デ・ラ・テッラ 人間と動物
第2章 セラピス 感情と時間
第3章 コヘレト 無知と力
第4章 ペルセウス 善悪と共生
第5章 ヘレネ 芸術と創造
第6章 アクタイオン 生死と流転
終章 ブルーノ 生の多様性
附録 ジェイムズ・ジョイス「ブルーノ哲学」
「ルネサンスの世界文学的影響」
ジョイスは「ベーコンやデカルト以上に、ブルーノこそ、近代哲学と呼ばれているものの父と考えられるべきだ」と評価している。
ブルーノは近代の先駆と解釈されることが多々あるが、そういった先駆性のみで語られるのでは不十分である。
ジョイスが言う「ルネサンスは、そのほかにはなにもしなかったのだとしても、生きて希望をもっては死んで失望するあらゆる存在への憐れみの感覚を、わたしたち自身とわたしたちの芸術のうちに創造したことで、多くのものをなしとげただろう」での「憐れみの感覚」を理解するために、本書は書かれた、と著者は言う。
本書で印象に残るのは、「複合的で、相反するものの一致」をブルーノが手をかえ品をかえ、主張していた、ということ。
あと、各章題の簡単な説明補足を書いておこう。
ディオ・デ・ラ・テッラ(地上の神=人間)
セラピス(古代の神。蛇の絡みついた胴のうえに狼、獅子、犬の3つの頭をもつ獣をしたがえている。狼はうしろ=過去を見て遠吠えし、獅子は横=現在を見てうなり、犬は前=未来を見て喜んでいる)
コヘレト(旧約聖書コヘレトの言葉=伝道の書)「知識が増せば痛みも増す」
ペルセウス(無為をしりぞけ、労苦こそが人間にはふさわしい)
ヘレネ(画家ゼウクシスがクロトンの5人の乙女からもっとも美しい部位を選び集めてヘレネの肖像を描いた逸話から、美が多様であること)
アクタイオン(水浴中のアルテミスを見た狩人アクタイオンが、鹿に変えられて、みずからの猟犬に食い殺されてしまう神話から、猟犬=思考の類比)
『ジャック・ルーボーの極私的東京案内』
2012年5月29日 読書
『ジャック・ルーボーの極私的東京案内』を読んだ。
ジャック・ルーボーは、ウリポの作家で、この本も、通常の意味での東京案内にはまったくなっていない。
以下、本書の構成。
山手線各駅俳文
TOTO
てんとう虫
大名時計博物館
公園と庭
作中、いろんな説が出てきて、それが面白かったので、引用しておこう。
あるいは、たまたま何度か車窓から見る機会があったときに、富士山が見えなかったことから、富士山は存在しないとする「富士山問題」をぶちあげる。
「あれは万葉の詩人たちが日本観光局と共謀してでっちあげたものなんです」
また、TOTOのカタログを自動翻訳にかけてトンチンカンな説明にしてしまう。
たとえば、フラッシュバルブが「紅潮弁トイレ」と翻訳される愉快さなどが淡々と並べられ、「ビデ」の項はこんな翻訳
便器のふたの項では、こんな説明が。
ジャック・ルーボーは、ウリポの作家で、この本も、通常の意味での東京案内にはまったくなっていない。
以下、本書の構成。
山手線各駅俳文
TOTO
てんとう虫
大名時計博物館
公園と庭
作中、いろんな説が出てきて、それが面白かったので、引用しておこう。
英語の音には、非英国人にとっては格別に再現しにくいものがある。
それは「th」、たとえば「this」や「that」のような語に出てくる音である。さて、高名な言語学者の解説によると、これとほぼ同じ優秀な結果を得るためには、舌の位置をフォワグラを食べるときと正確に同じにすればよい。あるいは(彼はつけ加えて曰く)ゼリーを食べるときと同じにすればよい、と。
このちょっとした指摘のおかげで、私はイギリスにおけるゼリーの起源を発見することができた。実際、知らぬ者のない事実だが、フォワグラの生産地は14世紀にはイギリス王室に属しており、当然の結果として例の「th」の音が英語の音声に導入された。その後、ジャンヌ・ダルクやそれに続くもろもろが登場した結果、英語はその固有言語の正しい発音のために欠かせないフォワグラをすぐに安値で入手する道を長期間にわたって絶たれてしまった。そこで、ある天才的な料理人がゼリーを発明したのである。
あるいは、たまたま何度か車窓から見る機会があったときに、富士山が見えなかったことから、富士山は存在しないとする「富士山問題」をぶちあげる。
「あれは万葉の詩人たちが日本観光局と共謀してでっちあげたものなんです」
また、TOTOのカタログを自動翻訳にかけてトンチンカンな説明にしてしまう。
たとえば、フラッシュバルブが「紅潮弁トイレ」と翻訳される愉快さなどが淡々と並べられ、「ビデ」の項はこんな翻訳
ちょうどボタンのプッシュで、ノズルは及びますわずかに前にノズル開口の数から、難しい温水洗浄をする直腸洗っている立場の。
便器のふたの項では、こんな説明が。
遅い終わりの席とふたは、大きい爆発音を防ぎます。たとえあなたが彼らを降ろすとしても、ふたと新しいWashlet Gアルファのシートはゆっくり閉まります。