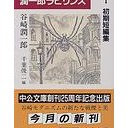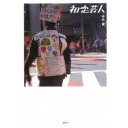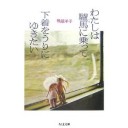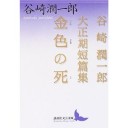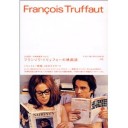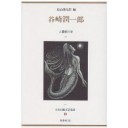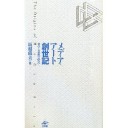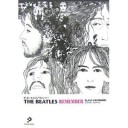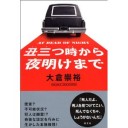『スピノザの世界-神あるいは自然』
2011年7月28日 読書
上野修の『スピノザの世界-神あるいは自然』を読んだ。
スピノザが何を言っているのかをわかりやすくあらわした1冊。
以下、目次。
はじめに
1 企て
スピノザ自身による入門書
純粋享楽を求めて
喜ばしい賭
剰余
目的とは衝動のことである
欲望は衝動を知らない
最高善を定義する
2 真理
道としての方法
方法は真理から自生する
何が何を真とするのか
真理の内的標識とは何か
真理の規範
知性の謎
3 神あるいは自然
『エチカ』
幾何学的証明
実体とは何か
神とは何か
神の存在証明(?)
唯一なる全体
内在的原因としての神
事物は別なふうにはありえなかった
4 人間
デカルトの残した問題
真理空間
精神は身体の観念である
精神はメンタルな能力なしで考える
5 倫理
自由意志の否定
自分をゆるしてやること
神と世界をゆるしてやること
人間をゆるしてやること
社会をゆるしてやること
事物の愛し方
6 永遠
無神論(?)
神への愛
永遠の相のもとに
第三種の認識
神の知的愛
そして至福
あとがき
スピノザは、その数学的な記述が珍しくて若いときに読んで面白がったりしていたが、その内容を理解していたとは思えない。というのは、この本を読んで、「ふむふむ、なるほど!そういうことだったのか」と思わされることが多かったからだ。それらは、本家を読んだときにこそ共鳴せよ、と言う感じだ。
今回、この本を読んで、「実体と様態」についていろいろと考えさせられた。
目次に出てくる「神」だの「真理」だのという言葉は、今やうさんくささしか引き出さないが、スピノザは、まるで違うことについて語っているように思えた。
ちょっと前から、スピノザの本をいくつか並行して読んだりしているが、それでもやっぱり、本家は難物である。頭のいい人に生まれたかった。
スピノザが何を言っているのかをわかりやすくあらわした1冊。
以下、目次。
はじめに
1 企て
スピノザ自身による入門書
純粋享楽を求めて
喜ばしい賭
剰余
目的とは衝動のことである
欲望は衝動を知らない
最高善を定義する
2 真理
道としての方法
方法は真理から自生する
何が何を真とするのか
真理の内的標識とは何か
真理の規範
知性の謎
3 神あるいは自然
『エチカ』
幾何学的証明
実体とは何か
神とは何か
神の存在証明(?)
唯一なる全体
内在的原因としての神
事物は別なふうにはありえなかった
4 人間
デカルトの残した問題
真理空間
精神は身体の観念である
精神はメンタルな能力なしで考える
5 倫理
自由意志の否定
自分をゆるしてやること
神と世界をゆるしてやること
人間をゆるしてやること
社会をゆるしてやること
事物の愛し方
6 永遠
無神論(?)
神への愛
永遠の相のもとに
第三種の認識
神の知的愛
そして至福
あとがき
スピノザは、その数学的な記述が珍しくて若いときに読んで面白がったりしていたが、その内容を理解していたとは思えない。というのは、この本を読んで、「ふむふむ、なるほど!そういうことだったのか」と思わされることが多かったからだ。それらは、本家を読んだときにこそ共鳴せよ、と言う感じだ。
今回、この本を読んで、「実体と様態」についていろいろと考えさせられた。
目次に出てくる「神」だの「真理」だのという言葉は、今やうさんくささしか引き出さないが、スピノザは、まるで違うことについて語っているように思えた。
ちょっと前から、スピノザの本をいくつか並行して読んだりしているが、それでもやっぱり、本家は難物である。頭のいい人に生まれたかった。
『潤一郎ラビリンス1・初期短編集』
2011年7月26日 読書
谷崎潤一郎の『潤一郎ラビリンス1・初期短編集』を読んだ。
明治43年から大正2年にかけての作品が編まれている。
先般、芦屋での「残月祭」に行って来たばかりで、谷崎再評価が自分の中で進んでいる。面白いなあ。
以下、作品ごとに、印象に残った部分を引用しておこう。
刺青
麒麟
少年
幇間
飇風(ひょうふう)
秘密
悪魔
恐怖
明治43年から大正2年にかけての作品が編まれている。
先般、芦屋での「残月祭」に行って来たばかりで、谷崎再評価が自分の中で進んでいる。面白いなあ。
以下、作品ごとに、印象に残った部分を引用しておこう。
刺青
「親方、私はもう今迄のような臆病な心を、さらりと捨ててしまいました。-お前さんは真先に私の肥料になったんだねえ」
麒麟
「あゝ、彼の聖人の徳も、あの夫人の暴虐には及ばぬと見える。今日からまた、あの夫人の言葉が此の衛の国の法律となるであろう」
「私はお前を憎んで居る。お前は恐ろしい女だ。お前は私を亡ぼす悪魔だ。しかし私はどうしても、お前から離れる事が出来ない」
少年
「さあ今度はあべこべに貴様を糞攻めにしてやるぞ」
信一が餅菓子を手当たり次第に口へ啣んでは、ぺっペッと光子の顔へ吐き散らすと、見るみるうちにさしも美しい雪姫の器量も癩病やみか瘡っかきのように、二た目と見られない姿になって行く面白さ。
「ほら仙吉は此処に居るよ」
こう云って、光子は蝋燭の下を指さした。見ると燭台だと思ったのは、仙吉が手足を縛られて両肌を脱ぎ、額へ蝋燭を載せて仰向いて坐って居るのである。顔と云わず頭と云わず、鳥の糞のように溶け出した蝋の流れは、両眼を縫い、唇を塞いで頤の先からぽたぽたと膝の上に落ち、七分通り燃え盡くした蝋燭の火に今や睫毛が焦げそうになって居ても、婆羅門の行者の如く胡坐をかいて拳を後手に括られたまゝ、大人しく端然と控えて居る。
三人は何か新しく珍しい遊戯の方法でも発見したように嬉々として光子の命令に服従し、「腰掛けにおなり」と云えば直ぐ四つ這いになって背を向けるし、「吐月峰(はいふき)におなり」と言えば直ちに畏まって口を開く。次第に光子は増長して三人を奴隷の如く追い使い、湯上りの爪を切らせたり、鼻の穴の掃除を命じたり、Urineを飲ませたり、始終私達を側へ侍らせて、長く此の国の女王となった。
幇間
「旦那、私ゃあ催眠術が大嫌いなんだから、もうお止しなさい。何だか人のかけられるのを見てさえ、頭が変になるんです」
こう云った様子が、恐ろしがって居るようなものゝ、如何にもかけて貰いたそうなのです。
「ちっと罪なようだが、今夜お前から彼奴を此処へ呼んで、精々口先の嬉しがらせを聞かせた上、肝腎の所は催眠術で欺してやるがいゝ。己は蔭で様子を見て居るから、奴を素裸にさせて勝手な藝当やらせて御覧」
こんな相談を始めました。
「なんぼ何でも、それじゃあんまり可哀相だわ」
と、流石の梅吉も一応躊躇したものゝ、後で露見したところで、腹を立てるような男ではなし、面白いからやって見ろ、と云う気になりました。
飇風(ひょうふう)
アルコールの火気に煽られ、良心の麻痺に乗じて、堤を破ったように体中に漲り渡った放埓の血は、肉を爛らせ、皮膚に焼きつき、居てもたっても堪らぬような鞭撻を彼の四肢に加えた。青森を過ぎてから全く独りで車室を占領して了った直彦は、炎の渦に巻き込まれた人間のように、手足を悶え身を藻掻いて、腰掛の上へ大の字に臥そべったり、仰向きのまゝ両足を上げて虚空を蹴ったり、一瞬間も落ち着いて坐っては居られなかった。やがて彼は水蒸気が霜のように結ぼれて居る窓硝子へ、熱した頬をぺったりと押し付け、ふうっと猛獣が嘯くような太い吐息を吐いた。
秘密
みぞおちから肋骨の辺を堅く緊め附けている丸帯と、骨盤の上を括っている扱帯の加減で、私の体の血管には、自然と女のような血が流れ始め、男らしい気分や姿勢はだんだんとなくなって行くようであった。
芝居の弁天小僧のように、こう云う姿をして、さまざまの罪を犯したならば、どんなに面白いであろう。・・・探偵小説や、犯罪小説の読者を始終喜ばせる「秘密」「疑惑」の気分に髣髴とした心持で、私は次第に人通りの多い、公園の六区の方へ歩みを運んだ。そうして、殺人とか、強盗とか、何か非常な残忍な悪事を働いた人間のように、自分を思い込むことが出来た。
悪魔
今度の旅行に限って物の一時間も乗って居ると、忽ち汽車が恐ろしくなる。さながら自分の衰弱した魂を脅喝するような勢で轟々と走って行く車輪の響の凄まじさ。ガラガラガラと消魂しい、気狂いじみた声を立てゝ機関車が鉄橋の上だの隧道の中へ駆け込む時は、頭が悩乱して、胆が潰れて、今にも卒倒するような気分に胸をわくわくさせた。
「さあさあ早く気狂いにおなんなさい。誰でも早く気狂いになった者が勝ちだ。可哀そうに皆さん、気狂いにさえなって了えば、其んな苦労はしないでも済みます」
何処かで、こんな蔭口を利いて居る奴の声も聞える。
そして梯子段の方へ気を配りながら、臆病らしく肩をすぼめて、蒲団の下から手巾を引き摺り出し、拇指と人差指で眼の前へ摘み上げた。
四つに畳まれた手巾は、どす黒い板のように濡れて癒着いて、中を開けると、鼻感冒に特有な臭気が発散した。水洟が滲み透して、くちゃくちゃになった冷たい布を、彼は両手の間に挿んでぬるぬると擦って見たり、ぴしゃりと頬ぺたへ叩き付けたりして居たが、しまいに顰めッ面をして、犬のようにべろべろと舐め始めた。
・・・・此れが洟の味なんだ。
恐怖
汽車へ乗り込むや否や、ピーと汽笛が鳴って車輪ががたん、がたんと動き出すか出さないうちに、私の体中に瀰漫して居る血管の脈搏は、さながら強烈なアルコールの刺戟を受けた時の如く、一挙に脳天へ向って奔騰し始め、冷汗がだくだくと肌に湧いて、手足が悪寒に襲われたように顫えて来る。若し其の時に何等か応急の手あてを施さなければ、血が、体中の総ての血が、悉く頸から上の狭い堅い圓い部分-脳髄へ充満して来て、無理に息を吹き込んだ風船玉のように、いつ何時頭蓋骨が破裂しないとも限らない。
中沢健さんの『初恋芸人』を読んだ。
女性と交際したことのない、芸人の卵が、女性に接近されて、さあ、たいへん。
芸人の世界、あるいはうまく男女交際のできない男のもやもやとした世界、どちらも、いやだけど痛がゆくて、ついつい触ってしまいたくなるような、甘美な苦痛が支配する。
接近してくる女性は、自分のことを醜いと思い込んでいる、こちらも精神的に問題を抱えた女性で、そういう女性がまだ芽の出ない芸人にアプローチしてくる、ってのは、リアリティーがありすぎなのである。
中沢健さんは、先般、BEARSでのイベントに審査員として来ていただいた。僕のことを、怪獣ピッコロみたいだ、と最大級のほめ言葉もいただいた。
この小説は、半分自分が見聞きしてきたドキュメンタリーをまぜながら書かれたものだと思うが、そのせいか、非常に流れがスムーズだ。主人公の心の流れはまったくスムーズじゃないけど、そういうのって、思春期を通ってきた人には全員了解できるような、共通の体験なんじゃないか、と思う。
しかし、最後のページ、女性が主人公にあてたメッセージの最後の一文を読んで、鳥肌がたった。
こわい~!
突如として、ホラー!
女嫌いが加速する!
山口以外のクラスメイトは黙りこみ、教室には彼女の泣く声だけが響く。彼女はひっくひっくしながら、うっすら赤くなった目でボクをにらみ、そして、こう言い放った。
「佐藤君と付き合うくらいなら、死んだほうがマシよ!」
クラスの女子が、「大丈夫?」「元気出しなよ」と慰めに集まっていった。ボクを慰めにくるやつなんて、ひとりもいない。
ボクは席にもどり、なにごともなかったかのように再び文庫本に目をやった。
女性と交際したことのない、芸人の卵が、女性に接近されて、さあ、たいへん。
芸人の世界、あるいはうまく男女交際のできない男のもやもやとした世界、どちらも、いやだけど痛がゆくて、ついつい触ってしまいたくなるような、甘美な苦痛が支配する。
接近してくる女性は、自分のことを醜いと思い込んでいる、こちらも精神的に問題を抱えた女性で、そういう女性がまだ芽の出ない芸人にアプローチしてくる、ってのは、リアリティーがありすぎなのである。
中沢健さんは、先般、BEARSでのイベントに審査員として来ていただいた。僕のことを、怪獣ピッコロみたいだ、と最大級のほめ言葉もいただいた。
この小説は、半分自分が見聞きしてきたドキュメンタリーをまぜながら書かれたものだと思うが、そのせいか、非常に流れがスムーズだ。主人公の心の流れはまったくスムーズじゃないけど、そういうのって、思春期を通ってきた人には全員了解できるような、共通の体験なんじゃないか、と思う。
しかし、最後のページ、女性が主人公にあてたメッセージの最後の一文を読んで、鳥肌がたった。
こわい~!
突如として、ホラー!
女嫌いが加速する!
『乱歩・正史・風太郎』
2011年7月21日 読書
高木彬光の『乱歩・正史・風太郎』を読んだ。山前譲による編集。
推理作家、高木彬光による、江戸川乱歩、横溝正史、山田風太郎らとの交遊録、エッセイ。第4章には、生い立ちからの記述がまとめてあり、興味深い。
「推理小説裏ばなし」の中でも、「重ねて言うが、私が作家として登場できたのは乱歩先生のおかげであり、作家として生き残れたのは横溝先生のおかげである」と書いており、この2人の巨匠への敬愛と、変人と真面目が外面と内面で対照的な山田風太郎への友愛が感じ取れる、心あたたまる本。
推理小説作家としては、乱歩、正史、あるいは松本清張などと肩を並べる巨匠なのに、その研究はまだこれから、という状態で、高木彬光で育った僕などにとっては、渇いたノドにオアシス発見の1冊だった。
1 産みの親・江戸川乱歩
乱歩先生の思い出
乱歩先生について
『孤島の鬼』について
愚作を書け!
乱歩先生のこと
幻影の城主
解説『屋根裏の散歩者』
解説『淫獣』
解説『魔術師』
解説『黄金仮面』
解説『吸血鬼』
解説『緑衣の鬼』
2 育ての親・横溝正史
成城まいり
横溝先生のことども
春たち帰る
思い出
横溝正史の作品について
『獄門島』について
3 水魚の親・山田風太郎
出藍の誉
外遊騒動
風さん奇行帳
解説『甲賀忍法帖』
鬼才に望む
風を視る(1)~(15)
4 推理小説裏ばなし
高木家ご先祖様のこと
刺青との運命的出会い
二重の恩人・柳原緑風氏
天の啓示“義経伝説”
父・高木東園のこと
わが“暗い青春”の記
戦争と敗戦と運命と
初めて書いた小説
乱歩先生との出会い
親友・悪友・珍友
産みの親・育ての親
鮎川哲也氏のこと
恩師との摩擦
女流二作家との因縁
佐賀潜氏のこと
原点に帰れ
いざ往かん 懶惰の城へ
目次中、「風を視る」は山田風太郎全集の月報から。第4章の「推理小説裏ばなし」は高木彬光長編推理小説全集の月報から。僕は、この光文社版の高木彬光長編推理小説全集を中学か高校に買って読んでいたのだが、今本棚から探し出してみてみると、見事に月報は1つも残していなかった。何を貴重と思って大切に取っておくかについて、当時の僕と現在の僕とでは、価値観が違うようだ。
また、推理小説のファンなら誰でも知っているエピソードだが、探偵作家クラブ幹事長をつとめた「O」のくだりでは、激しやすい高木彬光の一面も見れる。
その部分を、引用してみよう。
「鮎川哲也氏のこと」より
高木氏の怒りはとどまらない。その次の「恩師との摩擦」でもO氏に爆発している。
と、はじまり、
そして、悪行が暴露されたときの、O氏の発言が、これ。
あと、文章のはしばしに高木氏の感情がにじみ出ているが、それは実際に本書を読んで感じてもらうしかない。このままでは全文を書き写してしまいそうだ。
ちなみに、この「O」は、大坪砂男であり、彼の晩年を世話した弟子「T」は、都筑道夫と思われる。ここで大坪砂男の名前が出てきたのには、ちょっと因縁めいたものを感じて面白い。大坪砂男と、最近よく読んでいる谷崎潤一郎とは、無縁ではないからだ。
推理作家、高木彬光による、江戸川乱歩、横溝正史、山田風太郎らとの交遊録、エッセイ。第4章には、生い立ちからの記述がまとめてあり、興味深い。
「推理小説裏ばなし」の中でも、「重ねて言うが、私が作家として登場できたのは乱歩先生のおかげであり、作家として生き残れたのは横溝先生のおかげである」と書いており、この2人の巨匠への敬愛と、変人と真面目が外面と内面で対照的な山田風太郎への友愛が感じ取れる、心あたたまる本。
推理小説作家としては、乱歩、正史、あるいは松本清張などと肩を並べる巨匠なのに、その研究はまだこれから、という状態で、高木彬光で育った僕などにとっては、渇いたノドにオアシス発見の1冊だった。
1 産みの親・江戸川乱歩
乱歩先生の思い出
乱歩先生について
『孤島の鬼』について
愚作を書け!
乱歩先生のこと
幻影の城主
解説『屋根裏の散歩者』
解説『淫獣』
解説『魔術師』
解説『黄金仮面』
解説『吸血鬼』
解説『緑衣の鬼』
2 育ての親・横溝正史
成城まいり
横溝先生のことども
春たち帰る
思い出
横溝正史の作品について
『獄門島』について
3 水魚の親・山田風太郎
出藍の誉
外遊騒動
風さん奇行帳
解説『甲賀忍法帖』
鬼才に望む
風を視る(1)~(15)
4 推理小説裏ばなし
高木家ご先祖様のこと
刺青との運命的出会い
二重の恩人・柳原緑風氏
天の啓示“義経伝説”
父・高木東園のこと
わが“暗い青春”の記
戦争と敗戦と運命と
初めて書いた小説
乱歩先生との出会い
親友・悪友・珍友
産みの親・育ての親
鮎川哲也氏のこと
恩師との摩擦
女流二作家との因縁
佐賀潜氏のこと
原点に帰れ
いざ往かん 懶惰の城へ
目次中、「風を視る」は山田風太郎全集の月報から。第4章の「推理小説裏ばなし」は高木彬光長編推理小説全集の月報から。僕は、この光文社版の高木彬光長編推理小説全集を中学か高校に買って読んでいたのだが、今本棚から探し出してみてみると、見事に月報は1つも残していなかった。何を貴重と思って大切に取っておくかについて、当時の僕と現在の僕とでは、価値観が違うようだ。
また、推理小説のファンなら誰でも知っているエピソードだが、探偵作家クラブ幹事長をつとめた「O」のくだりでは、激しやすい高木彬光の一面も見れる。
その部分を、引用してみよう。
「鮎川哲也氏のこと」より
ところが後で選考委員会の模様が伝わって来たときに、私は憤然としてしまった。
この「赤い密室」は最初の段階で、Oという作家の猛烈な横槍にあって、問題にもならずに失格してしまったというのである。
その横槍の内容については、鮎川さんの随筆と私の記憶には若干の違いがある。まあこの点はいわゆる「伝聞」だからしかたがないとして、私の聞いた話では、「この作品は私(O自身)が、原稿が真っ赤になるまで手を入れたのだ。だから授賞には絶対反対である」
というのだし、鮎川さんの聞いた話は、
「この作品は高木君が徹底的に手を入れたのだから、授賞には反対である」
とOが頑張ったからだというのである。ただそのどちらも完全な事実無根だったことはいうまでもない。
その後、昭和三十五年に鮎川さんは『黒い白鳥』と『憎悪の化石』で、探偵作家クラブ賞を受けられたし、数々の傑作によって確固たる地位をかためられたことは、まことにご同慶のいたりだが、Oのそのときの発言に対しては私はいまでも腹が立つ。
作品の評価に個人的な好き嫌いの感情がまじって来るこてゃ、読み手が人間である以上どうにもならないことである。たとえば懸賞などの場合、ある選考委員の激賞する作品のよさがわからなくて困ったというようなことは、私自身にも何度かおぼえがある。
しかし、こういう選考委員会で、これだけ悪質な虚偽の発言が行われたということは、ほかには恐らく例もないのではなかろうか。
この場合には、鮎川さんが一時のショックに屈せずに、たゆまぬ努力を積み重ねられたからこそ救われたのだ。
小説の世界に政治を持ちこむことについてはいろいろの議論もあるが、ここまで来ては「政治的に動く」というような程度の問題ではない。犯罪に近いような行為であると言いきってもよいと私は考えるのだ。
高木氏の怒りはとどまらない。その次の「恩師との摩擦」でもO氏に爆発している。
大いに不愉快な思い出だし、死屍を鞭打つような後味の悪さもあるから、ほんとうはあまり筆も進まないのだが、やはり日本推理小説裏面史の一つの事件として、Oの非行の件だけは私が書き残しておくしか方法がないだろう。
と、はじまり、
もし彼が万一生きかえって私の前に顔を出したと仮定したら、やはり横面をぶんなぐってやりたくなるだろうと思う。少なくとも、私と同じころの年代からの作家で彼を知っている人ならば、多少の程度の差はあっても、似たような気持ちになるのではなかろうか。
彼が公私を混同し、汚職をたえずくりかえし、しかも自分の非をごまかすため、たとえば乱歩先生と私の仲をさくような中傷を続けたために、いまでも腹がたつのである。
それから後は、Oの非行の話になったのだが、その発覚した罪状に私は唖然呆然とした。
探偵作家クラブの預金や現金がすっかりからになっていたことは言うまでもないが、そのほかにも、たとえば捕物作家クラブのような友好団体から、彼は幹事長という肩書きを利用して、公式な借金をしていたのだ。その金額も当時としては相当以上の額だった・・・。
それだけならばまだしもである。ある団体の会計を担当していた女性を手なずけ、相当多額の金を浮き貸しさせていたのだ。その女性は後始末ができなくなって、催眠剤をのみ自殺をはかったというのだが、幸い発見が早く命はとりとめたということだった。
それは不幸中の幸いだが、彼女が病院へかつぎこまれたと聞いたOは、さっそくその事務所へとんで行き、証拠書類を持ち出して焼きすててしまったというのである・・・。
そして、悪行が暴露されたときの、O氏の発言が、これ。
Oは平然とうそぶくように、
「私は自分の仕事もしないで、クラブのために献身的につくしたのですから、このぐらいの金を使うのはとうぜんでしょう」
と言い切ったのである。
あと、文章のはしばしに高木氏の感情がにじみ出ているが、それは実際に本書を読んで感じてもらうしかない。このままでは全文を書き写してしまいそうだ。
ちなみに、この「O」は、大坪砂男であり、彼の晩年を世話した弟子「T」は、都筑道夫と思われる。ここで大坪砂男の名前が出てきたのには、ちょっと因縁めいたものを感じて面白い。大坪砂男と、最近よく読んでいる谷崎潤一郎とは、無縁ではないからだ。
『美ヶ原高原殺人事件』
2011年7月20日 読書松本孝、松本佳子共著による『美ヶ原高原殺人事件』を読んだ。1988年。
「黒い報告書」などの事件小説を書いていた松本孝は、途中から官能小説の書き手となって、多くの作品を世に出している。
その奥さんが松本佳子で、彼女も「石の薔薇」などのレコードの作詞や、短編小説を書いていて、大のミステリーファンなのだそうだ。
あとがきには、こう書いてある。
読んでみた感想を言えば、これは、まさしく堂々たる「邪道」だった。人間であるかぎり、性器もついているし、性欲もあるだろうが、ごく日常的なスケッチに、それがあえて書かれていて、虚を突かれたような気持ちがした。そういう意味では、前衛的な作品とも言える。
登場人物表をみると、「歌謡ポップスの売れっ子作詞家」(男)が、もうセックスアニマルで、複数の女性を相手に、とにかくやりまくるのである。
あと、物語にはほとんど無関係に、「吸血鬼研究家」も出てきて、これはひょっとして、作者が避暑を過ごす美ヶ原高原に、モデルとなる人でもいるんじゃなかろうか、と思った。だって、この話、吸血鬼と何の関係もないのだから。一応、巻末には「登場人物には特定のモデルはない」と断ってはいるけど。
以下、目次。
プロローグ
第1章 嵐の高原
第2章 孤立した別荘地
第3章 貸別荘の美女
第4章 バーベキュー・パーティー
第5章 官能の午後
第6章 睡眠の宴
第7章 山荘の連続殺人
第8章 真昼の惨劇
第9章 生き残った女
第10章 犯人の声
エピローグ
さて、ストーリーはと言うと、前半は嵐で閉ざされた別荘地で、とにかく男女が相手をとっかえひっかえ、と言っても男のほうは1人だけど、セックスに明け暮れる。みんなで睡眠薬を飲むという「スリーピング・パーティー」で目覚めたら、そのやり過ぎ男が殺されていた。女たちも、男(ホモ)も、みんな、被害者の男性を肉体的に慕っていたのである。動機は肉体の独占欲とか嫉妬とか?犯人は?と、いう感じ。
そのあと、毒でばたばたと人が殺されていく。
文章が、固有名詞、商品名を必要以上に書いていたり、「マルビ」など、当時の社会風俗をあらわしていて、面白い。でも、これはよく知らなかったな。
「殺人という恐ろしいアクシデントに、誰の意識も、まだ、さばらばなのだ」
上の文章の「さばらば」って、使ったことない。どういう意味なんだろう。
知らなかったと、いえば、これも。
「<ラコステ>のグリーンのシャツに、白のスラックスをはいている。グリーンは、ホモ・セクシュアルの男どもの好む色である」
え、そうだったの?
事件の真相は、2時間ドラマ的な意外な真相が待っていて、安心して読める娯楽小説に仕上がっていた。
「黒い報告書」などの事件小説を書いていた松本孝は、途中から官能小説の書き手となって、多くの作品を世に出している。
その奥さんが松本佳子で、彼女も「石の薔薇」などのレコードの作詞や、短編小説を書いていて、大のミステリーファンなのだそうだ。
あとがきには、こう書いてある。
殺人は、よくあるミステリーのように、冒頭から死体が転がっている、というふうには起こらない。が、男女のからみ合いのあと、殺人が起きてからは、惨劇が連続する。
・・・なお、ぼくは「推理小説に、官能場面が入るのは邪道だ」という古い通念には、まったく反対だ。性が解放された現代では、男女の愛欲の中にこそミステリーがあると考えているからである。
読んでみた感想を言えば、これは、まさしく堂々たる「邪道」だった。人間であるかぎり、性器もついているし、性欲もあるだろうが、ごく日常的なスケッチに、それがあえて書かれていて、虚を突かれたような気持ちがした。そういう意味では、前衛的な作品とも言える。
登場人物表をみると、「歌謡ポップスの売れっ子作詞家」(男)が、もうセックスアニマルで、複数の女性を相手に、とにかくやりまくるのである。
あと、物語にはほとんど無関係に、「吸血鬼研究家」も出てきて、これはひょっとして、作者が避暑を過ごす美ヶ原高原に、モデルとなる人でもいるんじゃなかろうか、と思った。だって、この話、吸血鬼と何の関係もないのだから。一応、巻末には「登場人物には特定のモデルはない」と断ってはいるけど。
以下、目次。
プロローグ
第1章 嵐の高原
第2章 孤立した別荘地
第3章 貸別荘の美女
第4章 バーベキュー・パーティー
第5章 官能の午後
第6章 睡眠の宴
第7章 山荘の連続殺人
第8章 真昼の惨劇
第9章 生き残った女
第10章 犯人の声
エピローグ
さて、ストーリーはと言うと、前半は嵐で閉ざされた別荘地で、とにかく男女が相手をとっかえひっかえ、と言っても男のほうは1人だけど、セックスに明け暮れる。みんなで睡眠薬を飲むという「スリーピング・パーティー」で目覚めたら、そのやり過ぎ男が殺されていた。女たちも、男(ホモ)も、みんな、被害者の男性を肉体的に慕っていたのである。動機は肉体の独占欲とか嫉妬とか?犯人は?と、いう感じ。
そのあと、毒でばたばたと人が殺されていく。
文章が、固有名詞、商品名を必要以上に書いていたり、「マルビ」など、当時の社会風俗をあらわしていて、面白い。でも、これはよく知らなかったな。
「殺人という恐ろしいアクシデントに、誰の意識も、まだ、さばらばなのだ」
上の文章の「さばらば」って、使ったことない。どういう意味なんだろう。
知らなかったと、いえば、これも。
「<ラコステ>のグリーンのシャツに、白のスラックスをはいている。グリーンは、ホモ・セクシュアルの男どもの好む色である」
え、そうだったの?
事件の真相は、2時間ドラマ的な意外な真相が待っていて、安心して読める娯楽小説に仕上がっていた。
『わたしは驢馬に乗って下着をうりにゆきたい』
2011年7月19日 読書
鴨居羊子の『わたしは驢馬に乗って下着をうりにゆきたい』を読んだ。
大阪はアメリカ村の三角公園を見下ろす橋本ビルを拠点に、ファッションとしての下着を果敢に追って、定着させた鴨居羊子の自伝エッセイ。
強気でバリバリやる一面と涙もろい一面、やり手の面と抜けている面、強さと弱さをあわせもった鴨居羊子は、この本で読むかぎりでは、姉御肌で、立身出世譚の主人公たるにふさわしい人物と受け取れる。
最近読んでいる松本孝の「黒い報告書」シリーズで、奇抜な下着ファッションの社会風俗のことに触れた文章を見つけたので、「あ、これ、鴨居羊子のことかも」と思って、読んでみた。
男社会の中で生きる彼女の姿、母親との愛憎こもごもの確執、壁と冒険、これは読んでいて勇気がわいてくる1冊だった。
以下、目次。
1、
夕刊紙のかけ出し記者
抵抗と希望と情熱
おい、本気か?
のら犬たちが呼んでいる
ピンクのガーター・ベルト
TUNIC LABORATORY;COCO
下着屋三日目
シックスティーン・トーンズ
明治生れの母
スキャンティ生れる
オルフェの鏡
2、
サイコロは投げられた
逆転ゲーム
一坪のオフィス
お茶のカンが金庫
「百に七をかけてごらん」
『下着ぶんか論』を書く
珉珉の夜
集金と預金
男が皮のズボンをはくとき
自信と不安のハプニング“下着ショウ”
各駅停車の東海道
時間借りの縫製室と太陽の船付場
3、
野球と下着
地中海と魔女ルーシーの旅
大人のオモチャ
オフィス、電話、制服、鍵、印鑑
ミス・ペテン展
バラのふるさと
一九〇〇年
海の男
エーゲ海の少年
ギリシァ、スペイン・ショウ
フラメンコの練習
母と鼻吉の死
本書の中で、「大人のオモチャ」と題するページが印象的だったので、いくつか抜粋しておこう。
大阪はアメリカ村の三角公園を見下ろす橋本ビルを拠点に、ファッションとしての下着を果敢に追って、定着させた鴨居羊子の自伝エッセイ。
強気でバリバリやる一面と涙もろい一面、やり手の面と抜けている面、強さと弱さをあわせもった鴨居羊子は、この本で読むかぎりでは、姉御肌で、立身出世譚の主人公たるにふさわしい人物と受け取れる。
最近読んでいる松本孝の「黒い報告書」シリーズで、奇抜な下着ファッションの社会風俗のことに触れた文章を見つけたので、「あ、これ、鴨居羊子のことかも」と思って、読んでみた。
男社会の中で生きる彼女の姿、母親との愛憎こもごもの確執、壁と冒険、これは読んでいて勇気がわいてくる1冊だった。
以下、目次。
1、
夕刊紙のかけ出し記者
抵抗と希望と情熱
おい、本気か?
のら犬たちが呼んでいる
ピンクのガーター・ベルト
TUNIC LABORATORY;COCO
下着屋三日目
シックスティーン・トーンズ
明治生れの母
スキャンティ生れる
オルフェの鏡
2、
サイコロは投げられた
逆転ゲーム
一坪のオフィス
お茶のカンが金庫
「百に七をかけてごらん」
『下着ぶんか論』を書く
珉珉の夜
集金と預金
男が皮のズボンをはくとき
自信と不安のハプニング“下着ショウ”
各駅停車の東海道
時間借りの縫製室と太陽の船付場
3、
野球と下着
地中海と魔女ルーシーの旅
大人のオモチャ
オフィス、電話、制服、鍵、印鑑
ミス・ペテン展
バラのふるさと
一九〇〇年
海の男
エーゲ海の少年
ギリシァ、スペイン・ショウ
フラメンコの練習
母と鼻吉の死
本書の中で、「大人のオモチャ」と題するページが印象的だったので、いくつか抜粋しておこう。
私の下着とは、人間の遊び、オモチャの衣服、と考えてもいいのである。
子供はオモチャによって夢をはぐくみ、日常生活を豊かにし、成長し、思考力をのばしてゆく。だから大人にもオモチャが必要なのだと本気で思った。
大人になった人間も、ピタリとじゃれ遊びをやめて実用くさい顔つきになるのが、人生の暦を見るように思えてならない。私は暦的人生にいつも抵抗していた。
三十歳らしい顔、三十歳らしい好み、六十歳らしいおちつき、十九歳らしいハツラツさ。これではあまりにも当たり前すぎる。何々らしいことなどというのは、どう考えてもいいカッコしいの、優等生面したいい子ちゃん風に思えてならない。
“何々らしい人生”と同じく“何々のための人生”も私は否定した。
感情や友情や、勉強もおけいこごとも、すべて“のための人生”に結びつける人の多いのをみると、人間が合理主義という機械の部品になっている感じがしてならない。
ずっと前、女性文学者の描く「男」と、男性文学者の描く「女」と、一体どちらがほんとの女かを考えたことがあった。ある男性文学者が言った。「男は女がわからないということから出発する。わからないから考える。考えて、そして書く」。これに比べると女は、ある感覚で、わかったものとして男を書いてしまう。
『谷崎潤一郎 犯罪小説集』
2011年7月13日 読書
谷崎潤一郎の『谷崎潤一郎 犯罪小説集』を読んだ。
「柳湯の事件」
銭湯の湯船に沈んでいる死体、というイメージは強烈!何か踏んだな、と思ったら、それが実は、という話で、「モシャクシャ」「ヌラヌラ」という描写がなまなましい。
「途上」
昨日も読んだ、プロバビリティーの犯罪の話。どちらも漢字などの表記が現代人に読みやすいようにしてあるが、こっちのほうがさらに現代風になおされている。
「私」
ポーの某作品に想を得たのか、クリスティーの某作品の先駆にもなっているトリックが使われているが、タイトルで半分真相を明かしているのが、面白い。
「白昼鬼語」
暗号を解いて、犯罪窃視。ポーの「黄金虫」の暗号を使っているが、その内容は、
仏陀の死する夜、
デイアナの死する時、
ネプチューンの北に一片の鱗あり、
彼処においてそれは我れ我れの手によって行われざるべからず
で、これを解読するだけでもたいしたものだ。僕など、高校のときの年賀状で、大関くんが書いてよこした暗号もまだ解けていないというのに!
「柳湯の事件」
銭湯の湯船に沈んでいる死体、というイメージは強烈!何か踏んだな、と思ったら、それが実は、という話で、「モシャクシャ」「ヌラヌラ」という描写がなまなましい。
「途上」
昨日も読んだ、プロバビリティーの犯罪の話。どちらも漢字などの表記が現代人に読みやすいようにしてあるが、こっちのほうがさらに現代風になおされている。
「私」
ポーの某作品に想を得たのか、クリスティーの某作品の先駆にもなっているトリックが使われているが、タイトルで半分真相を明かしているのが、面白い。
「白昼鬼語」
暗号を解いて、犯罪窃視。ポーの「黄金虫」の暗号を使っているが、その内容は、
仏陀の死する夜、
デイアナの死する時、
ネプチューンの北に一片の鱗あり、
彼処においてそれは我れ我れの手によって行われざるべからず
で、これを解読するだけでもたいしたものだ。僕など、高校のときの年賀状で、大関くんが書いてよこした暗号もまだ解けていないというのに!
『谷崎潤一郎 大正期短編集 金色の死』
2011年7月12日 読書
谷崎潤一郎の『大正期短編集 金色の死』を読んだ。
「金色の死」
パノラマ島にインスピレーションをもたらしたという、人工庭園世界。
「人面疽」
映画の話。ここでも、なぜか「黄金仮面」とか想起してしまった。
「小さな王国」
教室国家。ウェーブみたいな世界が展開されるが、展開はきりきりと胸を刺す。
「母を恋うる記」
新内語りの三味線が「天ぷら喰いたい」と聞こえる。ここで「白昼夢」を連想したのは、まさに病膏肓か。
「富美子の足」
犬のようにまとわりつく足フェチの話で、名前が「ふみこ」というのは、わかりやすい冗談で愉快!
「途上」
プロバビリティーの犯罪として、小学生のときから中島河太郎の本で慣れ親しんだ作品。いろんな作品のモトになっていると思う。
「青い花」
洋服を第二の皮膚だとする見解は新鮮で、大いに感銘を受けた。
ぼけて妄想に耽ってしまう年寄りの頭の中身は、既に僕の脳内とたいして変わらない。
「金色の死」
パノラマ島にインスピレーションをもたらしたという、人工庭園世界。
「人面疽」
映画の話。ここでも、なぜか「黄金仮面」とか想起してしまった。
「小さな王国」
教室国家。ウェーブみたいな世界が展開されるが、展開はきりきりと胸を刺す。
「母を恋うる記」
新内語りの三味線が「天ぷら喰いたい」と聞こえる。ここで「白昼夢」を連想したのは、まさに病膏肓か。
「富美子の足」
犬のようにまとわりつく足フェチの話で、名前が「ふみこ」というのは、わかりやすい冗談で愉快!
「途上」
プロバビリティーの犯罪として、小学生のときから中島河太郎の本で慣れ親しんだ作品。いろんな作品のモトになっていると思う。
「青い花」
洋服を第二の皮膚だとする見解は新鮮で、大いに感銘を受けた。
ぼけて妄想に耽ってしまう年寄りの頭の中身は、既に僕の脳内とたいして変わらない。
『フランソワ・トリュフォーの映画誌』
2011年7月11日 読書
山田宏一の『フランソワ・トリュフォーの映画誌』を読んだ。
以下、目次。
序論
第1章 エッフェル塔
第2章 813
第3章 リュミエール
第4章 「カイエ・デュ・シネマ」とヌーヴェル・ヴァーグの仲間たち
第5章 ロベルト・ロッセリーニとネオレアリズモ
第6章 ジャン・コクトー
第7章 ジャン・ヴィゴ
第8章 オーソン・ウェルズ
第9章 極楽コンビ(ローレル/ハーディ)とドタバタ喜劇
第10章 マックス・オフュルス
第11章 ニコラス・レイ
第12章 チャップリン
第13章 ハワード・ホークス
第14章 ヒッチコック
第15章 フリッツ・ラングとルイス・ブニュエル
第16章 ジャック・タチ
第17章 ジャン・ルノワール
第18章 D・W グリフィスあるいは映画への愛
第19章 アンリ・ラングロワとシネマテーク・フランセーズ
第20章 アンドレ・バザン
たとえば、「813」の章では、
「柔らかい肌」「華氏451」「暗くなるまでこの恋を」「私のように美しい娘」「終電車」「日曜日が待ち遠しい!」などから、「813」の出てくるシーンをピックアップする。
これは楽しい!
このタイミングでこの本を読んだのは、来るべき「ニューウェーブ・パラダイス」のための、自分なりの雰囲気作りだったのだが、ハマりにハマりまくった。
以下、目次。
序論
第1章 エッフェル塔
第2章 813
第3章 リュミエール
第4章 「カイエ・デュ・シネマ」とヌーヴェル・ヴァーグの仲間たち
第5章 ロベルト・ロッセリーニとネオレアリズモ
第6章 ジャン・コクトー
第7章 ジャン・ヴィゴ
第8章 オーソン・ウェルズ
第9章 極楽コンビ(ローレル/ハーディ)とドタバタ喜劇
第10章 マックス・オフュルス
第11章 ニコラス・レイ
第12章 チャップリン
第13章 ハワード・ホークス
第14章 ヒッチコック
第15章 フリッツ・ラングとルイス・ブニュエル
第16章 ジャック・タチ
第17章 ジャン・ルノワール
第18章 D・W グリフィスあるいは映画への愛
第19章 アンリ・ラングロワとシネマテーク・フランセーズ
第20章 アンドレ・バザン
たとえば、「813」の章では、
813という数字もトリュフォーのフェティシズムと言っていいでしょう。トリュフォーの映画にしょっちゅう、ほとんどフェティッシュなギャグのように出てくる数字なので、これを口実にトリュフォーの映画のいくつかのシーンを見るのもたのしいかなと思って
「柔らかい肌」「華氏451」「暗くなるまでこの恋を」「私のように美しい娘」「終電車」「日曜日が待ち遠しい!」などから、「813」の出てくるシーンをピックアップする。
これは楽しい!
このタイミングでこの本を読んだのは、来るべき「ニューウェーブ・パラダイス」のための、自分なりの雰囲気作りだったのだが、ハマりにハマりまくった。
『悪の報酬-黒い報告書-』
2011年7月7日 読書松本孝の『悪の報酬-黒い報告書-』を読んだ。1964年
週刊新潮掲載の「黒い報告書」シリーズをまとめた3作目だ。
以下、目次。
堕ちる
女の弱点
殺し屋の女
二つの顔
狼と不良少女
悪の魅力
朝子という女
硫酸と青酸加里
社長と愛人たち
ある男の終幕
敗残者
快楽の報酬
「あとがき」にはこう書いてある。
「あいにくと」と評していいのかどうかわからないが、この後、著者は官能小説の書き手になる。社会的に幅ひろい題材が官能に落ち着いたのは、残念である。
いくつかの作品から、世相をあらわす部分や、犯罪の安い哀しみを描いている部分を引用しておこう。
(街の保護司として、犯罪をおかした少年たちを更生させようと献身してきた中田だったが)
週刊新潮掲載の「黒い報告書」シリーズをまとめた3作目だ。
以下、目次。
堕ちる
女の弱点
殺し屋の女
二つの顔
狼と不良少女
悪の魅力
朝子という女
硫酸と青酸加里
社長と愛人たち
ある男の終幕
敗残者
快楽の報酬
「あとがき」にはこう書いてある。
シリーズの目的は「現実の事件に取材し、犯罪に至るまでの人間関係を追うことに主眼が置かれている。従ってここに扱われた題材は全て現実に発生した事件によっている。そして、こうしめくくる。
今後はしだいに、もっと社会的に幅ひろい題材ともとりくんで行きたいと考えている。
「あいにくと」と評していいのかどうかわからないが、この後、著者は官能小説の書き手になる。社会的に幅ひろい題材が官能に落ち着いたのは、残念である。
いくつかの作品から、世相をあらわす部分や、犯罪の安い哀しみを描いている部分を引用しておこう。
「三本立、八十円」の映画館をでると、街は、もう夜になっていた。伊勢佐木銀座には、色とりどりの人工の光線があふれ、ぞろぞろと、人波がゆきかっている。(「狼と不良少女」)
章一は、「お泊りお二人様四百円、入浴随意」と、ガラス板に灯のはいった旅館へ、マチ子をつれこんだ。(「狼と不良少女」)
-横浜の盛り場へでてきて、すでに四度目の夜である。昼は、安い映画かパチンコ、喫茶店のテレビなどで時間をつぶし、夜は場末のホテルに泊る。こうして、少女をひっぱりまわしてアソびだすと、金のあるうちは、家に帰ることなど、念頭からすっとんでしまうらしい。
(街の保護司として、犯罪をおかした少年たちを更生させようと献身してきた中田だったが)
少年たちが、身につけ、ただよわせている、濃厚な「悪の空気」。(「悪の魅力」)
その魅力が、いつしか中田弘文を、しっかりととらえ、はなさなくなった。彼は、麻薬のように、それをもとめ、そこにどっぷりとひたっていなければ、生きている気がしなくなっていたのだ。
(おれには、金がない。しかし、硫酸がある。青酸カリだってある。やつはおれに、かないはしない。ふふ、ざまあ見ろ!)(「硫酸と青酸加里」)
松本孝の『夜の顔ぶれ』を読んだ。1962年
あとがきには、こう書いてある。
以下、目次。
黒い巨人の踊り
突然、マリコは消えた
殺されるまで
殺してやる
夜の顔ぶれ
「黒い巨人の踊り」は、朝鮮動乱で立川基地に駐留していた黒人兵が、女を拉致してレイプのあげく殺してしまう。犯人は特定できたが、黒人兵はアメリカに帰国してしまい、日本の法の手から逃れてしまう。
と、いうわけで、日本人男性による復讐譚がはじまるのだ。
ジャズ喫茶にはりこんで犯人を捜すのが、当時を思わせる。
「突然、マリコは消えた」は、嫉妬深い男性が女性(マリコ)の行状に不審を抱き、浮気ではないかと疑う話。浮気相手だと思われた医師は、マリコの相談で妊娠中絶手術をしただけの関係なのだが、嫉妬に狂った男は、ついに犯行に及ぶのである。
夫婦にとって、赤ん坊は本来望まれてしかるべきもので、夫のほうは子供大歓迎だっただけに、秘密で中絶をしなければならなかったのである。夫に内緒で手術してまで、マリコが子供をほしがらなかった理由が面白い。
こどもが出来たら、夫の両親と一緒に住むことが約束されていて、マリコはそれがどうにも我慢できなかったのである。
「殺されるまで」はどうしようもない男につかまって、貧乏と売春にさらされる女性の哀しさを描いている。松本孝の作品は、だいたい貧乏、暴力、犯罪、売春、ヤクザといった世界が描かれており、知的遊戯としての殺人事件などは望むべくもない。悲惨な情景は、作中人物のこんな発言でもわかる。
「中絶の失敗で死ぬ子。ヤー公のでいりのとばっちりで、殺されちまう子。ペイ患になって、ポックリ死んじまう子-ここらのペイときたひにゃ、ウドン粉がまぜてあるんで、しまいには血がノリみたいになって、ふいにある日、ポックリといっちまうんですよ。そんな子ばかり・・・
香代ちゃんにかぎらず、ここらの女の子の末路なんて、あわれなもんです。でも、本人たちはその日まで気がつかず、毎晩ああしてキャアキャア、男とさわいでばかりいますがねえ」
(「ペイ」はヘロイン)
「殺してやる」は、売春婦が多く暮らすアパートで、1人の女性がリンチされた。女性は入院後、堂々と、アパートに戻ってきた。リンチの首謀者を殺害するために。
ガス中毒死の工作と、それとは関係なく、犯人に同情(と愛情)を寄せていた人物がリンチ首謀者を殺すタイミングが一致してしまう悲劇。
「夜の顔ぶれ」は、さすがに直木賞候補作らしい、奥行きがある。と、いっても描かれる世界は、あいかわらずである。女性の失踪事件を描いている。主人公は恐妻家の男性。と、言っても、その「女」はヤクザとも関係があり、また若いツバメとも関係があった。
「ユミ子は私を本妻、トリ公を用心棒、竹村をオメカケというふうに使いわけていたのだ」
この3人ともに、女がどこに行ってしまったのかを探しているのである。
3人が力をあわせて調べた結果、第4の男がいることが判明する。
これは金持ちのロマンスグレイ。
3人の男は、女を返せといってもまた出て行ってしまうだろう、と踏んで、第4の男から金を脅し取ろうと画策する。
実に、安っぽい奴らなのである。
現に、「やいやい」と殴りこんだつもりが、第4の男の威厳にすっかり気おされてしまって、「金がほしいのか」と3人に金をあっさりとくれてやるのである。
「よかった、よかった」とうかれて帰る3人は、すぐに警察につかまるのである。
あとがきには、こう書いてある。
この小説集は、37年中に「宝石」等の雑誌に執筆した作品からえらんだ4つの中短編に、昨年第45回の直木賞候補作となった「夜の顔ぶれ」を合わせたものであるが、いずれも新宿を舞台とした小説である。
「黒い巨人の踊り」「突然、マリコは消えた」「殺してやる」は推理小説として、「殺されるまで」は事件小説という註文で、また「夜の顔ぶれ」は、ユーモアのある風俗小説のつもりで書いた。
今後もいろいろなかたちと題材で、大都会の暗黒面を描いてゆきたいと考えている。
以下、目次。
黒い巨人の踊り
突然、マリコは消えた
殺されるまで
殺してやる
夜の顔ぶれ
「黒い巨人の踊り」は、朝鮮動乱で立川基地に駐留していた黒人兵が、女を拉致してレイプのあげく殺してしまう。犯人は特定できたが、黒人兵はアメリカに帰国してしまい、日本の法の手から逃れてしまう。
と、いうわけで、日本人男性による復讐譚がはじまるのだ。
ジャズ喫茶にはりこんで犯人を捜すのが、当時を思わせる。
「突然、マリコは消えた」は、嫉妬深い男性が女性(マリコ)の行状に不審を抱き、浮気ではないかと疑う話。浮気相手だと思われた医師は、マリコの相談で妊娠中絶手術をしただけの関係なのだが、嫉妬に狂った男は、ついに犯行に及ぶのである。
夫婦にとって、赤ん坊は本来望まれてしかるべきもので、夫のほうは子供大歓迎だっただけに、秘密で中絶をしなければならなかったのである。夫に内緒で手術してまで、マリコが子供をほしがらなかった理由が面白い。
こどもが出来たら、夫の両親と一緒に住むことが約束されていて、マリコはそれがどうにも我慢できなかったのである。
「殺されるまで」はどうしようもない男につかまって、貧乏と売春にさらされる女性の哀しさを描いている。松本孝の作品は、だいたい貧乏、暴力、犯罪、売春、ヤクザといった世界が描かれており、知的遊戯としての殺人事件などは望むべくもない。悲惨な情景は、作中人物のこんな発言でもわかる。
「中絶の失敗で死ぬ子。ヤー公のでいりのとばっちりで、殺されちまう子。ペイ患になって、ポックリ死んじまう子-ここらのペイときたひにゃ、ウドン粉がまぜてあるんで、しまいには血がノリみたいになって、ふいにある日、ポックリといっちまうんですよ。そんな子ばかり・・・
香代ちゃんにかぎらず、ここらの女の子の末路なんて、あわれなもんです。でも、本人たちはその日まで気がつかず、毎晩ああしてキャアキャア、男とさわいでばかりいますがねえ」
(「ペイ」はヘロイン)
「殺してやる」は、売春婦が多く暮らすアパートで、1人の女性がリンチされた。女性は入院後、堂々と、アパートに戻ってきた。リンチの首謀者を殺害するために。
ガス中毒死の工作と、それとは関係なく、犯人に同情(と愛情)を寄せていた人物がリンチ首謀者を殺すタイミングが一致してしまう悲劇。
「夜の顔ぶれ」は、さすがに直木賞候補作らしい、奥行きがある。と、いっても描かれる世界は、あいかわらずである。女性の失踪事件を描いている。主人公は恐妻家の男性。と、言っても、その「女」はヤクザとも関係があり、また若いツバメとも関係があった。
「ユミ子は私を本妻、トリ公を用心棒、竹村をオメカケというふうに使いわけていたのだ」
この3人ともに、女がどこに行ってしまったのかを探しているのである。
3人が力をあわせて調べた結果、第4の男がいることが判明する。
これは金持ちのロマンスグレイ。
3人の男は、女を返せといってもまた出て行ってしまうだろう、と踏んで、第4の男から金を脅し取ろうと画策する。
実に、安っぽい奴らなのである。
現に、「やいやい」と殴りこんだつもりが、第4の男の威厳にすっかり気おされてしまって、「金がほしいのか」と3人に金をあっさりとくれてやるのである。
「よかった、よかった」とうかれて帰る3人は、すぐに警察につかまるのである。
『日本幻想文学集成 第5巻 谷崎潤一郎 天鵞絨の夢』
2011年7月5日 読書
松山俊太郎編による『日本幻想文学集成 第5巻 谷崎潤一郎 天鵞絨の夢』を読んだ。『綺想礼讃』を読んで、この谷崎本の解説に接したとき、なんとしても、本体の本書を読まねばなるまい、と思っていたのだ。
谷崎潤一郎は若い頃に読んだことがあったが、今読んでみると、あの頃僕は何を読んでいたのだろうか、といぶかしむくらいに新鮮で、どれもこれも面白い。松山俊太郎の編集の妙なのかもしれない。
収録されているのは、以下の5編。
秘密(1911年)
人魚の嘆き(1917年)
天鵞絨の夢(1919年)
鶴唳(1921年)
夢の浮橋(1959年)
アモラルなモラリスト-エゴティストのエロス-/松山俊太郎
簡単なメモ。
「秘密」での女がつぶやく「Arrested at last」は、女が男を迷宮にいざなう謎の名文句だ。これに匹敵する謎の文句は、『三四郎』での「ストレイシープ」か、「霧に棲む悪魔」の「ゴシュは死んだ」くらいじゃないだろうか。
「天鵞絨の夢」はある情景を場所や立場の違う視点で語りなおす試みだが、中断した、この3つ以外にどんな視点を用意していたのだろうか、それが非常に気になる。
「夢の浮橋」で、まるでアクロイド殺しの面白さを初心者に説くかのような長文がさしはさまれる。その理由は物語が進行するうちに明らかにはなるが、明らかに、この長文は異様だ。
で、それを気持ちが持続するまで引用してみよう。
谷崎潤一郎は若い頃に読んだことがあったが、今読んでみると、あの頃僕は何を読んでいたのだろうか、といぶかしむくらいに新鮮で、どれもこれも面白い。松山俊太郎の編集の妙なのかもしれない。
収録されているのは、以下の5編。
秘密(1911年)
人魚の嘆き(1917年)
天鵞絨の夢(1919年)
鶴唳(1921年)
夢の浮橋(1959年)
アモラルなモラリスト-エゴティストのエロス-/松山俊太郎
簡単なメモ。
「秘密」での女がつぶやく「Arrested at last」は、女が男を迷宮にいざなう謎の名文句だ。これに匹敵する謎の文句は、『三四郎』での「ストレイシープ」か、「霧に棲む悪魔」の「ゴシュは死んだ」くらいじゃないだろうか。
「天鵞絨の夢」はある情景を場所や立場の違う視点で語りなおす試みだが、中断した、この3つ以外にどんな視点を用意していたのだろうか、それが非常に気になる。
「夢の浮橋」で、まるでアクロイド殺しの面白さを初心者に説くかのような長文がさしはさまれる。その理由は物語が進行するうちに明らかにはなるが、明らかに、この長文は異様だ。
で、それを気持ちが持続するまで引用してみよう。
さて、これから先は、私として少々述べにくいことを述べなければならない。
私は仮にこの物語に「夢の浮橋」と云ふ題を与へ、しろうとながら小説を書くやうに書き続けて来たが、上に記してきたところは悉く私の家庭内に起った真実の事柄のみで、虚偽は一つも交へてない。が、何のためにこれを書く気になったかと問はれても、私には答へられない。私は別に、人に読んで貰ひたいと云ふ気があって書くのではない。少くともこの物語は、私が生きてゐる間は誰にも見せないつもりであるが、もし死後に於いて何人かの眼に触れたとしたら、それも悪くはないであらうし、誰にも読まれずに葬り去られたとしても、遺憾はない。私はたゞ書くこと自身に興味を抱き、過去の出来事を一つ一つ振り返って思ひ出してみることが、自分自身に楽しいのに過ぎない。尤も、こゝに記すところのすべてが真実で、虚偽や歪曲は聊かも交へてないが、さう云っても真実にも限度があり、これ以上は書く訳には行かないと云ふ停止線がある。だから私は、決して虚偽は書かないが、真実のすべてを書きはしない。父のため、母のため、私自身のため、等々を慮って、その一部分を書かずにおくこともあるかも知れない。真実のすべてを語らないことは即ち虚偽を語ることである、と云ふ人があるなら、それはその人の解釈のしやうで、敢えてそれに反対はしない。
佐々木中の『九夏前夜』を読んだ。
三十路の男性が、祖父の残した別荘で夏を過ごす。
と、いう物語だというのが、表向き。
まず、この小説の冒頭部分を、ちょこっとだけ引用してみよう。
なんだ、これは!
すわ、「なぞなぞ小説」か、と僕ひとり色めきたって、読みすすめることにした。
その結果、この物語は、実はこういう話なのではないか、という推論が出た。
主人公はすっかりぼけてしまった老人。
一家を惨殺したあげくに、自分のことを三十路の息子だと思い込んでいる。
おそらく、この本を読んだ人も、似たような結論に到達したんじゃないか、と思う。
こう考えることで、なぜ主人公がひとりぼっちなのかもわかるし、周囲を気にしながら庭に墓穴を掘る理由もわかるのである。
こういう「なぞなぞ小説」だと思ったきっかけは単純で、作中、目立つのが、「主体の混乱」と「記憶のあいまい」なのだ。
名前も氏素性も明らかにされない主人公、というか、話者は、とくに他のだれかと会話するわけでもなく、「私」という人称すらほとんど出てこない。しかも、あろうことか、冒頭の文章を見ればわかるように、話者は「お前」なのである。
これは、クーンツの某作品のように、同一の主体をもつ複数の人物が存在しているのか、あるいは、スレイドの某作品のように、複数の主体をもつ1人の人物がいるだけなのか、という仕掛けがあるものと考えられた。
鏡にうつる自分を、まるで他人のように描写するページが続いたり、記憶がないことをえんえんと語るシーンがある。
ほとんどのエピソードは、それが話者である人物についてのものであるという確証もない。
また、こういう文章もあった。
このシーン自体が、ボケ老人の行動だとも言えるが、パラソルのことを「大日傘」などと言う三十男など、どこに存在するのだろう。これは、話者がかなりの老人であることをあらわしている。話者が文学として文章を書いているのなら話しは別だが、普通の思考として、「大日傘」など、すらっと出てくる三十男はいない。
いや、待てよ。この物語の時代が現代でないとしたらどうだ。
ひょっとしたら、これは19世紀の話なのかもしれない。(あるいは鎌倉時代か、とも疑ったが、作中、唯一出てくる家電製品が冷蔵庫なので、少なくとも冷蔵庫が存在している時代にはちがいない。)
いやいや、作中にピアスやら、カレンダーやら、アスファルトという言葉も出てくる。それらは、すべて、現代のものである・・・・のか?古代から耳に孔をあけて装飾品をつけたり、暦を作ったりしていただろうし、アスファルトだって天然のアスファルトなら、現代の産物を意味しない。うむ。わからなくなってきた。
コンピュータもテレビも携帯電話もエアコンも登場しない物語なので、現代のストーリーである証拠はどこにもない。
さらに言えば、この舞台が地球である証拠もないし、だとすれば「夏」は日本で考える四季のうちの夏とは意味合いが違う可能性もある。
うむ。
こういった推理を重ねながら、もっともありそうな落しどころとして行き着いたのが、先に書いた、ボケ老人が家族を殺して、心から息子になりきっている、という状況なのだ。さもなければ、冒頭の「お前」の意味がわからない。
このように複数の主体が入れ替わっている、という仕掛けがある、と結論づけてみてみると、作者のペンネームに大きなヒントがあったことがわかる。
「佐々木中」は、判じ物としては、「佐々木」の「中」だから、答えは「々」。主人公は単独の三十男なのではなくて、ダブルだったのである。
三十路の男性が、祖父の残した別荘で夏を過ごす。
と、いう物語だというのが、表向き。
まず、この小説の冒頭部分を、ちょこっとだけ引用してみよう。
お前の魂の空白のなかで、にがい錫の月がむごく光る。痛がゆく洽く眩ませる。軋めいて痺れさせる。僅かに摘んだ花々も今は踏みにじられた花綵となって赤ぐろい。
なんだ、これは!
すわ、「なぞなぞ小説」か、と僕ひとり色めきたって、読みすすめることにした。
その結果、この物語は、実はこういう話なのではないか、という推論が出た。
主人公はすっかりぼけてしまった老人。
一家を惨殺したあげくに、自分のことを三十路の息子だと思い込んでいる。
おそらく、この本を読んだ人も、似たような結論に到達したんじゃないか、と思う。
こう考えることで、なぜ主人公がひとりぼっちなのかもわかるし、周囲を気にしながら庭に墓穴を掘る理由もわかるのである。
こういう「なぞなぞ小説」だと思ったきっかけは単純で、作中、目立つのが、「主体の混乱」と「記憶のあいまい」なのだ。
名前も氏素性も明らかにされない主人公、というか、話者は、とくに他のだれかと会話するわけでもなく、「私」という人称すらほとんど出てこない。しかも、あろうことか、冒頭の文章を見ればわかるように、話者は「お前」なのである。
これは、クーンツの某作品のように、同一の主体をもつ複数の人物が存在しているのか、あるいは、スレイドの某作品のように、複数の主体をもつ1人の人物がいるだけなのか、という仕掛けがあるものと考えられた。
鏡にうつる自分を、まるで他人のように描写するページが続いたり、記憶がないことをえんえんと語るシーンがある。
ほとんどのエピソードは、それが話者である人物についてのものであるという確証もない。
また、こういう文章もあった。
誰も、誰も居ない、誰一人としてこのおそろしい光から護らぬ無益な大日傘の林立のなかをゆっくりと頼りなく縫うようにして。ぶつかる、またぶつかる、
このシーン自体が、ボケ老人の行動だとも言えるが、パラソルのことを「大日傘」などと言う三十男など、どこに存在するのだろう。これは、話者がかなりの老人であることをあらわしている。話者が文学として文章を書いているのなら話しは別だが、普通の思考として、「大日傘」など、すらっと出てくる三十男はいない。
いや、待てよ。この物語の時代が現代でないとしたらどうだ。
ひょっとしたら、これは19世紀の話なのかもしれない。(あるいは鎌倉時代か、とも疑ったが、作中、唯一出てくる家電製品が冷蔵庫なので、少なくとも冷蔵庫が存在している時代にはちがいない。)
いやいや、作中にピアスやら、カレンダーやら、アスファルトという言葉も出てくる。それらは、すべて、現代のものである・・・・のか?古代から耳に孔をあけて装飾品をつけたり、暦を作ったりしていただろうし、アスファルトだって天然のアスファルトなら、現代の産物を意味しない。うむ。わからなくなってきた。
コンピュータもテレビも携帯電話もエアコンも登場しない物語なので、現代のストーリーである証拠はどこにもない。
さらに言えば、この舞台が地球である証拠もないし、だとすれば「夏」は日本で考える四季のうちの夏とは意味合いが違う可能性もある。
うむ。
こういった推理を重ねながら、もっともありそうな落しどころとして行き着いたのが、先に書いた、ボケ老人が家族を殺して、心から息子になりきっている、という状況なのだ。さもなければ、冒頭の「お前」の意味がわからない。
このように複数の主体が入れ替わっている、という仕掛けがある、と結論づけてみてみると、作者のペンネームに大きなヒントがあったことがわかる。
「佐々木中」は、判じ物としては、「佐々木」の「中」だから、答えは「々」。主人公は単独の三十男なのではなくて、ダブルだったのである。
『夜と死の群像 黒い報告書より』
2011年7月2日 読書松本孝の『夜と死の群像 黒い報告書より』を読んだ。1963年。
「週刊新潮」に掲載された事件小説をおさめてある。と、言っても、50年ほど前の事件で、とくに日本犯罪史に残るような事件ではないため、知っている事件はこれと言って見つからなかった。男と女の犯罪かわらばん、といった趣がある。どれもこれも、安い犯罪なのである。
以下の12編が収録されている。
不倫の女
愛欲の果て
情婦の役割
二千万円の女
転落する花
雪の中の二人の女
好色社長死す
その株に手を出すな
五年目の来訪者
暗い億万長者
父の女の酒場
事件後の事件
引用するのもわびしくて悲しい、当時の世相と、庶民の犯罪の一端をほとんどランダムにちょこっと、書き留めておこう。
「週刊新潮」に掲載された事件小説をおさめてある。と、言っても、50年ほど前の事件で、とくに日本犯罪史に残るような事件ではないため、知っている事件はこれと言って見つからなかった。男と女の犯罪かわらばん、といった趣がある。どれもこれも、安い犯罪なのである。
以下の12編が収録されている。
不倫の女
愛欲の果て
情婦の役割
二千万円の女
転落する花
雪の中の二人の女
好色社長死す
その株に手を出すな
五年目の来訪者
暗い億万長者
父の女の酒場
事件後の事件
引用するのもわびしくて悲しい、当時の世相と、庶民の犯罪の一端をほとんどランダムにちょこっと、書き留めておこう。
彼女は、ふかい関係にこそおちいらなかったが、かなりの人数の男と、つきあっていた。だが、最近では、その男たちも、遠のいてゆくようだった。金ばなれの悪くなった、疲労のかげのこい人妻など、彼らにとって、用のない存在であるのは、あたりまえである。(「不倫の女」)
彼女にとって、自分の家は負担でしかなかった。彼女はわかい、イキのいい女だった。おそくなれば説教され、」外泊すればカンカンになっておこられる家など、チャンスがあれば、いつでもでてしまいたかった。
関西出身のある女デザイナーが、思いきったデザインのブラジャーや、コルセットを発表し、世間をアッといわせたいきおいに乗じて、東京に進出してきた。彼女にあたえられた仕事は、それだったのである。(「愛欲の果て」)
尻のわれ目まで見える「Uパッチ」とか、「ひらめスリップ」「骨盤ガーター」「桜貝キャミター」などという、刺戟的な婦人下着専門の、そのデザイナーについては、中央のジャーナリズムも、いっせいにとりあげていた。
「溝口は、敏腕なデカだった。<原爆刑事>というあだ名がついていたくらいだった」(「情婦の役割」)
老いるにしたがって意地わるさをます姑。そうした姑に一言もたてつくことのできない、まじめだが気弱な夫。そのあいだにはさまって、信子はしだいに不幸になっていった。そしてついに、キャンデーを盗む悲劇をおこしてしまったのであった。(「二千万円の女」)
しかし、和枝の乱脈ぶりは、いっこうにあらたまらなかった。麻薬患者がヤクをもとめるように、彼女はやみくもに男をあさった。(「転落する花」)
「黄色いヘルメットをかぶった、泥だらけの人相のわるい男までひっぱりこんでますね」
ちょうど、地方でマンボが全盛のころであった。(「雪の中の二人の女」)
小諸駅のちかくに、トンネルがある。それをくぐった少し先の一軒家が、ダンスホールになっていた。
木、土の週2回ひらくだけの、安っぽい卓球場みたいな、十畳ばかりのホールだったが、小諸市内や近在のちょっとイカれた連中で、いつも満員だった。
後楽園。この一劃は、野球場を中心としてここ数年のうちに急速に発展し、おびただしい娯楽施設を備えた一大レジャー・センターと化している。(「好色社長死す」)
プール。ローラー・スケート場。競輪場。遊園地・・・。夜、これらの各設備が放つ色とりどりのネオンは目くるめくほど強烈だった。
「何さ。ひとの金で女を抱かせてもらってるくせに、デカいツラするんじゃあないよ。支那人め、顔を見りゃ、すぐわかるんだから」(「五年目の来訪者」)
「ばかやろう。おれは、韓国だ!」
「どっちだって、おんなじだよ」
そのことばをきくと、安斗昌は、逆上した。彼はものも言わず、女をなぐりつけた。女はベッドからおち、ぶざまにはだかの股をひろげて、ころがった。
(日本の白豚め!)安は、酔いがいっぺんにふきとぶのをかんじた。
安斗昌が、少年のころ、彼の父は神楽坂で、靴なおしをやっていた。小学校にあがると、同級生は彼をかこんで、彼のちょっとした言葉づかいなどをとらえては、はやしたてた。それは、グサリと少年の胸を刺すような、冷酷なからかいだった。
血もこおるような、あの屈辱を、安斗昌はけっしてわすれない。中学を出ると彼は一直線に無法者の世界に、とびこんだ。それが、彼にとって、せめてもの反抗の形式だったのだ。
いまのおれには、何もない。希望も、情熱も、何ひとつありはしない。・・・おれは、いろんなものに、熱中した。電気機関車の模型に熱中し、ラジオに熱中し、レコードに熱中し、喫茶店の経営に熱中し、競輪に熱中した。しかし、結局、どれもこれも趣味でしかなかった。だから、ある期間が過ぎると、みんな冷めてしまい、あとには、何ものこらなかった。しかも、もう三十三にもなっちまったというのに・・・(「暗い億万長者」)
バス代を払ってしまうと、百円札が4枚にあとは10円玉が3つしか残らなかった。400円やそこらの持ち金では、女に逢いにゆけるものではない。(「父の女の酒場」)
腕っぷしがつよく、エネルギーに満ちた、明朗な明。皮ジャンバーに、白いマフラーをまき、半長靴をはいて単車をとばす明。それは、近所の娘たちの眼に、さっそうと映った。「イカす青年」だったわけだ。(「事件後の事件」)
『メディア・アート創世記 科学と芸術の出会い』
2011年6月30日 読書
坂根巌夫の『メディア・アート創世記 科学と芸術の出会い』を読んだ。
以下、目次。
はじめに
[I] 私、そして境界領域を訪ね歩いた半世紀
中国・青島(チンタオ)生まれ、京都・丹後育ち
科学者、レオナルド・ダ・ヴィンチを知る
「関係は存在に優位する」の思想に惹かれる
新聞社勤務は、佐賀支局から
世界デザイン会議を取材して
多彩なクリエーターたちとの出会い
企画提案と初めての海外取材
モントリオール万博での発見
日本のアート・アンド・テクノロジーへの取組み
大阪万博EXPO70が始まる
EATグループの世界的デビュー/日本人作家グループの活躍/万国博の大いなる役割
アメリカ留学中の体験
ジョルジ・ケペッシュが説く新しい表現/ソフトウエア展ほか触発されどおしの日々/M・C・エッシャーに会う
「遊び」や「科学と芸術のあいだ」を考察
動きはじめた「メディア・アート」を追って
新聞社を退職して教育の場へ
[II] 科学と芸術の相克を超える思索と試み
J・ブロノフスキー『人類の上昇』の発想
科学の発見と技術がアート表現を呼び覚ます
台頭するアート・アンド・テクノロジー運動
境界領域をつなごうとしたサイエンティストたち
「新しい科学博物館」を提案したF・オッペンハイマー
「サイエンス・アート」と呼ぶべきなのか・・・
日本のキーパーソン、伏見康治
万博、ベニス・ビエンナーレ、ドクメンタが果たしたこと
日本のアート・アンド・テクノロジー運動
ミュージアム、画廊、メディア・センターの拡大
シーグラフとアルス・エレクトロニカの隆盛
境界領域のアートを促す各国のイベント
未来のイメージ展、IMAGINA/DEAF/ISEA/韓国のメディア・アート/ユネスコ
メディア・アートの主な教育機関:海外の例
MIT、メディア・ラボ/ニューヨーク大学ITP/RCA/パリ第八大学/モントリオール大学/UCLA/USC/U.C.サンディエゴ/U.C.バークレー/ZKM/ヘルシンキ芸術デザイン大学
メディア・アートの主な教育機関:国内の例
九州芸術工科大学/筑波大学/神戸芸術工科大学/東京芸術大学、同大学大学院映像研究科/東京大学大学院情報学環/多摩美術大学/武蔵野美術大学
【III】境界領域のアート1 「動」と「光」の饗宴
キネテック・アートとその先駆者たち
フランク・マリーナと機関誌「レオナルド」/シェフェールのサイバネティック・アート/動く彫刻「モビール」の作者、カルダー/タキス、アガム、ティンゲリーの動く作品/ロボット技術との出会い
オプチカル・アート/イリュージョン・アートとの出会い
めくるめくアートが感覚に及ぼす効果/心理学者が見た夢のスケッチと無限音階/日本の錯視芸術の巨匠たち/スコット・キムと名著『ゲーデル・エッシャー・バッハ』
ライト・アートは1920年代の「ルミア」から
先人、トマス・ウィルフレッドの華麗な試み/光と影をテーマにするアーティストたち/松村泰三のライト・アートを象徴する作品/光の演出による「環境アート」の試み
ショー「レーザリアム」に代表されるレーザー・アート
立体視アートの流行は繰り返す
立体視を実現する知覚と方法の探究/プルフリッヒ効果による立体視の原理とは…
ホログラフィ・アート、驚異の美と科学
パルスレーザー開発が身近にしたホログラフィ/ホログラフィ・アートの世界的隆盛と沈静
【IV】境界領域のアート2 数学、幾何学的な造形
エッシャーとペンローズ、発想の連鎖
不可能の構造シリーズが誕生する背景/広がり続けるエッシャー・ファン/エッシャーと日本との密接な関係/不可能の構図の作品の歴史的先駆者について
メビウスの輪の発想から創造へ
万華鏡や立体模型に宿る幾何学
世界を幾何学で捉えるバックミンスター・フラー
数学者ならではの方法と作品
マックス・ビル、ピート・ハイン/ミゲロ・ベロカルのパズル式彫刻/「ルービック・キューブ」をめぐる出来事/ネルソン・マックス「球を裏返す」
【V】境界領域のアート3 電子技術による表現革命
ビデオを活かす表現者、ナム=ジュン・パイク
「ビデオひろば」に始まる日本のビデオ・アート
コンピュータ・アートの登場
CG技術の発表の場、シーグラフの発足
インタラクティブ・アートの大いなる可能性
参加型のゲーム「センソラマ」/サザランド博士のHMD開発/「人工現実」を著したマイロン・クルーガー/エド・タネンバウムと巨大スクリーン/ジェフリー・ショー「ザ・レジブル・シティ(読める街)」
インタラクティブ・アートの表現者と作品
マイケル・ネイマークの数々の試み/クリスタとローランの共作/アグネスとジェフリーの「ハンドサイト」/スコット=ソーナ・スニッブの不可思議な作品/ウォルフガング・ミュンヒと古川聖のコラボレーション/カミーユ作品はいつも詩情豊か/タミコ、民族や文化の境界から生まれる作品/タマシュが作る独特のCG世界/リュック、ハイパーカードで制作/日本のメディア・アートの第一人者
【VI】境界領域のアート4 視聴覚拡張の試み
広がるワールド・サウンドスケープ運動
風や水、街の振動を音楽に/インタラクティブなサウンド・アート/ユニークな音のパフォーマーたち/ポール・マチスが見い出したパイプの音響/日本のサウンド・アート体験
フェノメナ・アートにこめられたシュタイナー思想
「フェノメナート」展を企画
時空を超える宇宙芸術(コズミック・アート)の表現
エイセ・エイシンガとプラネタリウム/オットー・ピーネと「スカイ・アート」/ロスとタレルの宇宙構想/ウォルター・デ・マリアの「雷を呼ぶアート」/ニューポ:(牛波)の「大空絵画」/ウスマン・ハックのSky Ear計画/クルト・ホフステッターのサン・ペンデュラム計画/SOL計画/宇宙線のアート/人工衛星と共に、ときを超える計画
アース・アート、ランド・アートという環境芸術
急速に世界に広まったパノラマ・アート
球面絵画と球面写真によるパノラマ的表現
【VII】境界領域のアート5 生物学の進展と表現
脳波や脳機能が新たなアート表現を呼び込む
遺伝子によるアート(Genetic Art)はやや難解か
「匂い」をはじめ五感に訴えるアートを
【VIII】デジタル・アートとアナログ・アート
八つの相違点を考える
おわりに----メディア・アートの未来へ
最後の方にある、デジタル・アートとアナログ・アートの8つの相違点は、
ハイブリッド性
作品の生命の変化
作品への参加性の拡大
作品の機能性の拡大
アートの定義の変化
アーティストの意味や定義のゆらぎ
アートの新しい役割
教育体制の変貌
である。
本書から、著者の抱いている歯がゆさが伝わってくる。
メディア・アートがアートの世界で取り上げられることの少なさと、新しいアーティストが小粒になっていることについて。
たしかに、読んでいると、最近の作品になるほど、小手先の作品になっているような印象は否めないし、美術館の旧態依然たる態度も、徐々に改善される程度の歩みだ。
突破せよ!
以下、目次。
はじめに
[I] 私、そして境界領域を訪ね歩いた半世紀
中国・青島(チンタオ)生まれ、京都・丹後育ち
科学者、レオナルド・ダ・ヴィンチを知る
「関係は存在に優位する」の思想に惹かれる
新聞社勤務は、佐賀支局から
世界デザイン会議を取材して
多彩なクリエーターたちとの出会い
企画提案と初めての海外取材
モントリオール万博での発見
日本のアート・アンド・テクノロジーへの取組み
大阪万博EXPO70が始まる
EATグループの世界的デビュー/日本人作家グループの活躍/万国博の大いなる役割
アメリカ留学中の体験
ジョルジ・ケペッシュが説く新しい表現/ソフトウエア展ほか触発されどおしの日々/M・C・エッシャーに会う
「遊び」や「科学と芸術のあいだ」を考察
動きはじめた「メディア・アート」を追って
新聞社を退職して教育の場へ
[II] 科学と芸術の相克を超える思索と試み
J・ブロノフスキー『人類の上昇』の発想
科学の発見と技術がアート表現を呼び覚ます
台頭するアート・アンド・テクノロジー運動
境界領域をつなごうとしたサイエンティストたち
「新しい科学博物館」を提案したF・オッペンハイマー
「サイエンス・アート」と呼ぶべきなのか・・・
日本のキーパーソン、伏見康治
万博、ベニス・ビエンナーレ、ドクメンタが果たしたこと
日本のアート・アンド・テクノロジー運動
ミュージアム、画廊、メディア・センターの拡大
シーグラフとアルス・エレクトロニカの隆盛
境界領域のアートを促す各国のイベント
未来のイメージ展、IMAGINA/DEAF/ISEA/韓国のメディア・アート/ユネスコ
メディア・アートの主な教育機関:海外の例
MIT、メディア・ラボ/ニューヨーク大学ITP/RCA/パリ第八大学/モントリオール大学/UCLA/USC/U.C.サンディエゴ/U.C.バークレー/ZKM/ヘルシンキ芸術デザイン大学
メディア・アートの主な教育機関:国内の例
九州芸術工科大学/筑波大学/神戸芸術工科大学/東京芸術大学、同大学大学院映像研究科/東京大学大学院情報学環/多摩美術大学/武蔵野美術大学
【III】境界領域のアート1 「動」と「光」の饗宴
キネテック・アートとその先駆者たち
フランク・マリーナと機関誌「レオナルド」/シェフェールのサイバネティック・アート/動く彫刻「モビール」の作者、カルダー/タキス、アガム、ティンゲリーの動く作品/ロボット技術との出会い
オプチカル・アート/イリュージョン・アートとの出会い
めくるめくアートが感覚に及ぼす効果/心理学者が見た夢のスケッチと無限音階/日本の錯視芸術の巨匠たち/スコット・キムと名著『ゲーデル・エッシャー・バッハ』
ライト・アートは1920年代の「ルミア」から
先人、トマス・ウィルフレッドの華麗な試み/光と影をテーマにするアーティストたち/松村泰三のライト・アートを象徴する作品/光の演出による「環境アート」の試み
ショー「レーザリアム」に代表されるレーザー・アート
立体視アートの流行は繰り返す
立体視を実現する知覚と方法の探究/プルフリッヒ効果による立体視の原理とは…
ホログラフィ・アート、驚異の美と科学
パルスレーザー開発が身近にしたホログラフィ/ホログラフィ・アートの世界的隆盛と沈静
【IV】境界領域のアート2 数学、幾何学的な造形
エッシャーとペンローズ、発想の連鎖
不可能の構造シリーズが誕生する背景/広がり続けるエッシャー・ファン/エッシャーと日本との密接な関係/不可能の構図の作品の歴史的先駆者について
メビウスの輪の発想から創造へ
万華鏡や立体模型に宿る幾何学
世界を幾何学で捉えるバックミンスター・フラー
数学者ならではの方法と作品
マックス・ビル、ピート・ハイン/ミゲロ・ベロカルのパズル式彫刻/「ルービック・キューブ」をめぐる出来事/ネルソン・マックス「球を裏返す」
【V】境界領域のアート3 電子技術による表現革命
ビデオを活かす表現者、ナム=ジュン・パイク
「ビデオひろば」に始まる日本のビデオ・アート
コンピュータ・アートの登場
CG技術の発表の場、シーグラフの発足
インタラクティブ・アートの大いなる可能性
参加型のゲーム「センソラマ」/サザランド博士のHMD開発/「人工現実」を著したマイロン・クルーガー/エド・タネンバウムと巨大スクリーン/ジェフリー・ショー「ザ・レジブル・シティ(読める街)」
インタラクティブ・アートの表現者と作品
マイケル・ネイマークの数々の試み/クリスタとローランの共作/アグネスとジェフリーの「ハンドサイト」/スコット=ソーナ・スニッブの不可思議な作品/ウォルフガング・ミュンヒと古川聖のコラボレーション/カミーユ作品はいつも詩情豊か/タミコ、民族や文化の境界から生まれる作品/タマシュが作る独特のCG世界/リュック、ハイパーカードで制作/日本のメディア・アートの第一人者
【VI】境界領域のアート4 視聴覚拡張の試み
広がるワールド・サウンドスケープ運動
風や水、街の振動を音楽に/インタラクティブなサウンド・アート/ユニークな音のパフォーマーたち/ポール・マチスが見い出したパイプの音響/日本のサウンド・アート体験
フェノメナ・アートにこめられたシュタイナー思想
「フェノメナート」展を企画
時空を超える宇宙芸術(コズミック・アート)の表現
エイセ・エイシンガとプラネタリウム/オットー・ピーネと「スカイ・アート」/ロスとタレルの宇宙構想/ウォルター・デ・マリアの「雷を呼ぶアート」/ニューポ:(牛波)の「大空絵画」/ウスマン・ハックのSky Ear計画/クルト・ホフステッターのサン・ペンデュラム計画/SOL計画/宇宙線のアート/人工衛星と共に、ときを超える計画
アース・アート、ランド・アートという環境芸術
急速に世界に広まったパノラマ・アート
球面絵画と球面写真によるパノラマ的表現
【VII】境界領域のアート5 生物学の進展と表現
脳波や脳機能が新たなアート表現を呼び込む
遺伝子によるアート(Genetic Art)はやや難解か
「匂い」をはじめ五感に訴えるアートを
【VIII】デジタル・アートとアナログ・アート
八つの相違点を考える
おわりに----メディア・アートの未来へ
最後の方にある、デジタル・アートとアナログ・アートの8つの相違点は、
ハイブリッド性
作品の生命の変化
作品への参加性の拡大
作品の機能性の拡大
アートの定義の変化
アーティストの意味や定義のゆらぎ
アートの新しい役割
教育体制の変貌
である。
本書から、著者の抱いている歯がゆさが伝わってくる。
メディア・アートがアートの世界で取り上げられることの少なさと、新しいアーティストが小粒になっていることについて。
たしかに、読んでいると、最近の作品になるほど、小手先の作品になっているような印象は否めないし、美術館の旧態依然たる態度も、徐々に改善される程度の歩みだ。
突破せよ!
鳥飼否宇の『官能的』を読んだ。
カーの作品をもじった連作集。
ストーカーまがい(まがい?)の行動で自ら渦中にとびこんで巻き込まれる不可能事件に、神の啓示ごとき超絶こじつけ推理でケムに巻いたかと思うと、適当な解決に落ち着いたかと思いきや、最後の最後で真相が明かされるという、推理ファンにはたまらない趣向が満載。
で、連作全体を貫く「趣向」が、本格推理ファンなら、きっと早いうちに見抜けるような趣向で、これなどは、作者が読者に対するサービスとして投げ与えてくれたエサなのだ。
僕などは、そのエサがいつ明かされるのかと気になって、一つ一つの作品の瑕など頭がまわらないほどだった。まんまとエサの罠にしてやられたのである。
以下、目次。
「夜歩くと・・・」漸変態に関する考察
「孔雀の羽根に・・・」過変態に関する研究
「囁く影が・・・」完全変態に関する洞察
「四つの狂気」無変態に関する補足
カーの作品をもじった連作集。
ストーカーまがい(まがい?)の行動で自ら渦中にとびこんで巻き込まれる不可能事件に、神の啓示ごとき超絶こじつけ推理でケムに巻いたかと思うと、適当な解決に落ち着いたかと思いきや、最後の最後で真相が明かされるという、推理ファンにはたまらない趣向が満載。
で、連作全体を貫く「趣向」が、本格推理ファンなら、きっと早いうちに見抜けるような趣向で、これなどは、作者が読者に対するサービスとして投げ与えてくれたエサなのだ。
僕などは、そのエサがいつ明かされるのかと気になって、一つ一つの作品の瑕など頭がまわらないほどだった。まんまとエサの罠にしてやられたのである。
以下、目次。
「夜歩くと・・・」漸変態に関する考察
「孔雀の羽根に・・・」過変態に関する研究
「囁く影が・・・」完全変態に関する洞察
「四つの狂気」無変態に関する補足
『ザ・ビートルズ/リメンバー』
2011年6月28日 読書
クラウス・フォアマンの『ザ・ビートルズ/リメンバー』を読んだ。
クラウスは、ビートルズの「リボルバー」のジャケットを描いた人で、ミュージシャンでもある。(マンフレッド・マンのメンバー)。ビートルズのソロ時代のレコーディングなどにミュージシャンとして参加もしており、僕などはてっきり「クラウス・ブーアマン」と読むんだと思い込んでいた。(Klaus Voormann)
初期のビートルズでの、ポールとスチュの喧嘩のエピソードが実際はどうだったのか、とか、そのときにその現場にいた、親しい友人としての証言が聞けて、これは貴重!
以下、目次。
第1章 ビートルズとの出会い
1.生い立ち
2.地下室のロックンロール
3.カイザーケラー鉄の掟
4.ジョージ・ハリスン
5.ジョン・レノン
6.スチュアート・サトクリフ
7.ポール・マッカートニー対スチュアート・サトクリフ
8.国外退去
第2章 デビュー、飛翔するビートルズ
1.2度目のハンブルグ、そしてスチュの死
2.ブライアン・エプスタイン
3.デビューと最後の休日
4.恋におちたら
5.ア・ハード・デイズ・ナイト
第3章 リボルバー
1.LSD体験とエプスタインの映画会
2.マンフレッド・マン、そしてジョンの電話
3.リボルバー制作秘話
第4章 黄金のサージェント・ペパー時代
1.ストロベリー・フィールズ・フォーエバーとペニー・レイン
2.ア・デイ・イン・ザ・ライフ
3.ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ
4.ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー
5.ドント・パス・ミー・バイ
6.ベイビー・ユーアー・ア・リッチマン
第5章 翳りの王国
1.ブライアン・エプスタインの死
2.アラン・クライン
3.スウィート・トロント
第6章 ソロ時代
1.センチメンタル・ジャーニー
2.インスタント・カーマ
3.ジョンの魂
4.ドリス・トロイのソー・ファー
5.オール・シングス・マスト・パス
6.アイ・リメンバー・ジープ
7.ブラインド・マン
8.コンサート・フォー・バングラデシュ
第7章 イマジンの時代
1.イマジン
2.クリップルド・インサイド
3.真実が欲しい&ジェラス・ガイ
4.ニューヨーク・シティ
5.ビー・ヒア・ナウ
6.トライ・サム・バイ・サム
7.想い出のフォトグラフ
8.アルバム「リンゴ」
第8章 失われた週末、ハウス・ハズバンド、そして突然の別れ
1.ジョンと歌った「ロックンロール」
2.ハリー・ニルソン
3.別れ、そしてジョージのやさしさ
4.ハウス・ハズバンド
5.ジョンの死
第9章 NOW
1.ラン・デヴィル・ラン
2.ジョージのためのセレモニー
3.DVD『コンサート・フォー・バングラデシュ』
クラウスは、ビートルズの「リボルバー」のジャケットを描いた人で、ミュージシャンでもある。(マンフレッド・マンのメンバー)。ビートルズのソロ時代のレコーディングなどにミュージシャンとして参加もしており、僕などはてっきり「クラウス・ブーアマン」と読むんだと思い込んでいた。(Klaus Voormann)
初期のビートルズでの、ポールとスチュの喧嘩のエピソードが実際はどうだったのか、とか、そのときにその現場にいた、親しい友人としての証言が聞けて、これは貴重!
以下、目次。
第1章 ビートルズとの出会い
1.生い立ち
2.地下室のロックンロール
3.カイザーケラー鉄の掟
4.ジョージ・ハリスン
5.ジョン・レノン
6.スチュアート・サトクリフ
7.ポール・マッカートニー対スチュアート・サトクリフ
8.国外退去
第2章 デビュー、飛翔するビートルズ
1.2度目のハンブルグ、そしてスチュの死
2.ブライアン・エプスタイン
3.デビューと最後の休日
4.恋におちたら
5.ア・ハード・デイズ・ナイト
第3章 リボルバー
1.LSD体験とエプスタインの映画会
2.マンフレッド・マン、そしてジョンの電話
3.リボルバー制作秘話
第4章 黄金のサージェント・ペパー時代
1.ストロベリー・フィールズ・フォーエバーとペニー・レイン
2.ア・デイ・イン・ザ・ライフ
3.ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ
4.ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー
5.ドント・パス・ミー・バイ
6.ベイビー・ユーアー・ア・リッチマン
第5章 翳りの王国
1.ブライアン・エプスタインの死
2.アラン・クライン
3.スウィート・トロント
第6章 ソロ時代
1.センチメンタル・ジャーニー
2.インスタント・カーマ
3.ジョンの魂
4.ドリス・トロイのソー・ファー
5.オール・シングス・マスト・パス
6.アイ・リメンバー・ジープ
7.ブラインド・マン
8.コンサート・フォー・バングラデシュ
第7章 イマジンの時代
1.イマジン
2.クリップルド・インサイド
3.真実が欲しい&ジェラス・ガイ
4.ニューヨーク・シティ
5.ビー・ヒア・ナウ
6.トライ・サム・バイ・サム
7.想い出のフォトグラフ
8.アルバム「リンゴ」
第8章 失われた週末、ハウス・ハズバンド、そして突然の別れ
1.ジョンと歌った「ロックンロール」
2.ハリー・ニルソン
3.別れ、そしてジョージのやさしさ
4.ハウス・ハズバンド
5.ジョンの死
第9章 NOW
1.ラン・デヴィル・ラン
2.ジョージのためのセレモニー
3.DVD『コンサート・フォー・バングラデシュ』
『ゼロ年代の論点 ウェブ・郊外・カルチャー』
2011年6月27日 読書
円堂都司昭の『ゼロ年代の論点 ウェブ・郊外・カルチャー』を読んだ。
「まえがき」にもあるように、これは2000~2010年の批評に関するガイドブックで、多くの本は既に読んでいたが、それがピシッピシッとあるべき位置にマッピングされていく快感ったらなかった。
以下、目次
まえがき
第1章 ゼロ年代批評のインパクト
●ゼロ年代の批評をリードする――東浩紀『動物化するポストモダン』
●コミュニケーションを鍵として――宇野常寛『ゼロ年代の想像力』
●ニコニコ動画は政治をも動かす――濱野智史『アーキテクチャの生態系』
●この国の批評のかたち─佐々木敦『ニッポンの思想』
「世界視線」とアーキテクチャ
パフォーマティヴとコンスタティヴ/「私」からの逃走と自分探し/投瓶通信の否定/不況下の批評
第2章 ネットの力は社会を揺さぶる
●アイロニーと反省からみた状況のねじれ――北田暁大『嗤う日本の「ナショナリズム」』
●理想と現実、ウェブ2・0と2ちゃんねるのあいだ――梅田望夫『ウェブ進化論』
●宿命とセカイの外へむかって――鈴木謙介『ウェブ社会の思想』
●「祭り」のあとでクールに思考する――荻上チキ『ウェブ炎上』
情報環境と自由、コミュニケーション
セキュリティと環境管理型権力/事件の物語化の変容/秋葉原通り魔事件と「ゲーム的」現実感覚/「呼びかけのメディア」の可能性
第3章 言葉の居場所は紙か、電子か
●「つぶやき」が情報流通インフラになるとき――津田大介『Twitter社会論』
●小説と文芸批評の擁護者として――前田塁『紙の本が亡びるとき?』
●オープン化は「本」をも変えるか――佐々木俊尚『電子書籍の衝撃』
「教養」の終焉と著者2・0
「本」と「青春」の終わり/「文学」の終焉と成熟の不可能性/文学フリマと批評の居場所/レヴュアーの時代/言葉の変化と風景の変化/ニコニコ動画からツイッターへ
第4章 データベースで踊る表現の世界
●「ぼくら語り」にレッドカード――伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』
●オタクの自意識と思春期をめぐって――前島賢『セカイ系とは何か』
●情報処理の方程式は何を読み解くか――福嶋亮大『神話が考える』
キャラ/テクノ/スーパーフラット
セカイ系と萌え/新本格ミステリーと「キャラ」/『アトムの命題』と大量死理論/八〇年代との連続性/「日本ゼロ年」というリセット
第5章 変容するニッポンの風景
●すべては個室になるか─―森川嘉一郎『趣都の誕生』
●「過去」失い流動化する地方─―三浦展『ファスト風土化する日本』
●郊外のデフレカルチャー─―速水健朗『ケータイ小説的。』
建築とアーキテクチャ
二種類の「テーマパーク」/「ホームレス」と「ストリート」/都市デザインとしての2ちゃんねる/物理空間と情報空間
終章 二〇一〇年代にむけて
アーキテクチャ批判という伝統芸/「現実」の時代
主要参考文献
あとがき
「まえがき」にもあるように、これは2000~2010年の批評に関するガイドブックで、多くの本は既に読んでいたが、それがピシッピシッとあるべき位置にマッピングされていく快感ったらなかった。
以下、目次
まえがき
第1章 ゼロ年代批評のインパクト
●ゼロ年代の批評をリードする――東浩紀『動物化するポストモダン』
●コミュニケーションを鍵として――宇野常寛『ゼロ年代の想像力』
●ニコニコ動画は政治をも動かす――濱野智史『アーキテクチャの生態系』
●この国の批評のかたち─佐々木敦『ニッポンの思想』
「世界視線」とアーキテクチャ
パフォーマティヴとコンスタティヴ/「私」からの逃走と自分探し/投瓶通信の否定/不況下の批評
第2章 ネットの力は社会を揺さぶる
●アイロニーと反省からみた状況のねじれ――北田暁大『嗤う日本の「ナショナリズム」』
●理想と現実、ウェブ2・0と2ちゃんねるのあいだ――梅田望夫『ウェブ進化論』
●宿命とセカイの外へむかって――鈴木謙介『ウェブ社会の思想』
●「祭り」のあとでクールに思考する――荻上チキ『ウェブ炎上』
情報環境と自由、コミュニケーション
セキュリティと環境管理型権力/事件の物語化の変容/秋葉原通り魔事件と「ゲーム的」現実感覚/「呼びかけのメディア」の可能性
第3章 言葉の居場所は紙か、電子か
●「つぶやき」が情報流通インフラになるとき――津田大介『Twitter社会論』
●小説と文芸批評の擁護者として――前田塁『紙の本が亡びるとき?』
●オープン化は「本」をも変えるか――佐々木俊尚『電子書籍の衝撃』
「教養」の終焉と著者2・0
「本」と「青春」の終わり/「文学」の終焉と成熟の不可能性/文学フリマと批評の居場所/レヴュアーの時代/言葉の変化と風景の変化/ニコニコ動画からツイッターへ
第4章 データベースで踊る表現の世界
●「ぼくら語り」にレッドカード――伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』
●オタクの自意識と思春期をめぐって――前島賢『セカイ系とは何か』
●情報処理の方程式は何を読み解くか――福嶋亮大『神話が考える』
キャラ/テクノ/スーパーフラット
セカイ系と萌え/新本格ミステリーと「キャラ」/『アトムの命題』と大量死理論/八〇年代との連続性/「日本ゼロ年」というリセット
第5章 変容するニッポンの風景
●すべては個室になるか─―森川嘉一郎『趣都の誕生』
●「過去」失い流動化する地方─―三浦展『ファスト風土化する日本』
●郊外のデフレカルチャー─―速水健朗『ケータイ小説的。』
建築とアーキテクチャ
二種類の「テーマパーク」/「ホームレス」と「ストリート」/都市デザインとしての2ちゃんねる/物理空間と情報空間
終章 二〇一〇年代にむけて
アーキテクチャ批判という伝統芸/「現実」の時代
主要参考文献
あとがき
『行方不明のヘンテコな伯父さんからボクがもらった手紙』
2011年6月26日 読書
マーヴィン・ピークの『行方不明のヘンテコな伯父さんからボクがもらった手紙』を読んだ。
「白鯨」ならぬ白いライオンを追い求める義足のおじさんの冒険物語。
手紙の体裁をとっていて、誤字を訂正したあとや、書き込み、絵など、1ページ1ページが見ていて楽しい作りになっている。コーヒーをこぼした痕なども。
また、断崖めがけて滑落するピンチや、大竜巻のピンチなど、波乱万丈の大冒険が展開し、わけのわからないカメのお化けみたいな動物を家来にして旅をするなど、「ヘンテコ」と呼ばれながらも子供の心をガッチリつかんで離さない面白さだ。
「白鯨」ならぬ白いライオンを追い求める義足のおじさんの冒険物語。
手紙の体裁をとっていて、誤字を訂正したあとや、書き込み、絵など、1ページ1ページが見ていて楽しい作りになっている。コーヒーをこぼした痕なども。
また、断崖めがけて滑落するピンチや、大竜巻のピンチなど、波乱万丈の大冒険が展開し、わけのわからないカメのお化けみたいな動物を家来にして旅をするなど、「ヘンテコ」と呼ばれながらも子供の心をガッチリつかんで離さない面白さだ。
『丑三つ時から夜明けまで』
2011年6月25日 読書
大倉崇裕の『丑三つ時から夜明けまで』を読んだ。
これは、滅法面白い短編集だった。
以下、目次
「丑三つ時から夜明けまで」
「復讐」
「闇夜」
「幻の夏山」
「最後の事件」
まず、最初の作品「丑三つ時から夜明けまで」を見てみよう。
とにかく、20ページめで衝撃が走った!それを今からまんま引用するので、未読で予備知識ない人は、まず、本を読むことをおすすめする。
そうなのだ。この作品集の世界では、幽霊の存在を警察では認めている。
不可能犯罪が起こったとき、それは幽霊の仕業とされ、幽霊を取り締まるゴーストバスターズみたいな「捜査五課」が登場する作品集なのだ。
不可思議な犯罪が起こり、幽霊の仕業だとされ、幽霊嫌いの米田警部補がトリックを推理し、そして、真相はまた別にある、というパターンが、素晴らしい。
幽霊の存在を認めてしまうのは、推理小説としては反則の域なので、それでも面白がれるかどうかは読者のセンスにゆだねられるが、僕みたいに、『火刑法廷』や『大東京四谷怪談』が大好物な読者なら、めちゃくちゃ面白いはずだ。この設定だけで、合格。
捜査五課は掃除機みたいな機械で幽霊を捕獲するところなど、まるっきりゴーストバスターズなのだが、そのチームは、いかにもなメンバーで構成されている。
七種(しちぐさ):警部補
怒木(いするぎ):白装束
車(のり):袴姿
私市(きさいち):坊主頭の巨漢
入戸野(にっとの):人形を抱いた少女
神服(はっとり):眼鏡をかけた少年(コナン風?)
座主坊(ざしゅぼう):2メートル105キロの巨漢
これが、アニメとか、ライトノベルであれば、きっとこれらのキャラクターに淫した展開なり作品が書かれたにちがいないが、これは、あくまでも推理小説。キャラに淫することなく、ストーリーが展開するのは、潔くて、いい。
警察が幽霊の存在を認めるにいたった事件が作品ごとに違う説明になっているのも面白い。
捜査五課の登場のきっかけ、『復讐』では、こんな風。
ウヒャー、面白い!
また、『闇夜』では、頭頂部にナイフを刺された死体が出てくる。
うん?
頭頂部にナイフ?
これは『機械探偵クリク・ロボット』じゃないのか?
そして、案の定、頭頂部ナイフのトリックはクリク・ロボットそのまんまだったが、そのあとの展開が違って、『闇夜』はヒチコックのある映画みたいな怖さをかもし出している。
最終話が、作品の発表順で言うと、最初に掲載されているもので、書き直されて本書に収録されている。
いや~、この設定の勝利に、久々にミステリーの醍醐味を味わったな~。
これは、滅法面白い短編集だった。
以下、目次
「丑三つ時から夜明けまで」
「復讐」
「闇夜」
「幻の夏山」
「最後の事件」
まず、最初の作品「丑三つ時から夜明けまで」を見てみよう。
とにかく、20ページめで衝撃が走った!それを今からまんま引用するので、未読で予備知識ない人は、まず、本を読むことをおすすめする。
「全員にアリバイが成立おまけに動機はない。まいったなぁ」
応接間に戻るなり、米田(捜査一課警部補)が言った。
「こりゃあ、金銭より怨恨だな。金庫の金も手つかずだったしなぁ」
「容疑者のしぼりこみには苦労しますよ。富士衛門の悪評は、知らぬ者がないほどでしたから」
人非人、鬼、悪魔と散々に言われてきた富士衛門。彼のために一家心中をした家族もいる。彼を恨んでいる者など、数えきれないほどだろう。
「だが、現場の状況をどう説明する」
書斎の扉は厳重なロックシステムである。しかも、テレビカメラまでついているのだ。さらに、昨夜11時まではずっと雨が降っていた。そのため、庭は泥沼と化し足跡を残さずに歩ける状態ではなかった。
「不審な足跡は発見されていないんだろう」
書斎へ下りていった富士衛門自身の足跡、インターホンを聞きつけた尾崎の足跡、木道を踏みはずした米田の足跡。その三つ以外には、何の痕跡も発見されなかったのだ。
「つまりですね・・・」
的場が一瞬口ごもった。
「現場は密室だったんです。さらに・・・」
的場の声が一段と小さくなる。
「富士衛門の死は自然死とは思えません」
鈍器での一撃。自然死、自殺でないのは、明らかだ。
「そうしますと、これは・・・」
米田が私の顔を見て口をとがらせた。
「いよいよ、ヤツらのおでましだぜ」
ヤツら・・・。
「これだけの条件をすべて満たしているということは・・・」
的場は額の汗をぬぐう。
「やはり、犯人は幽霊以外にはありえません」
そうなのだ。この作品集の世界では、幽霊の存在を警察では認めている。
不可能犯罪が起こったとき、それは幽霊の仕業とされ、幽霊を取り締まるゴーストバスターズみたいな「捜査五課」が登場する作品集なのだ。
不可思議な犯罪が起こり、幽霊の仕業だとされ、幽霊嫌いの米田警部補がトリックを推理し、そして、真相はまた別にある、というパターンが、素晴らしい。
幽霊の存在を認めてしまうのは、推理小説としては反則の域なので、それでも面白がれるかどうかは読者のセンスにゆだねられるが、僕みたいに、『火刑法廷』や『大東京四谷怪談』が大好物な読者なら、めちゃくちゃ面白いはずだ。この設定だけで、合格。
捜査五課は掃除機みたいな機械で幽霊を捕獲するところなど、まるっきりゴーストバスターズなのだが、そのチームは、いかにもなメンバーで構成されている。
七種(しちぐさ):警部補
怒木(いするぎ):白装束
車(のり):袴姿
私市(きさいち):坊主頭の巨漢
入戸野(にっとの):人形を抱いた少女
神服(はっとり):眼鏡をかけた少年(コナン風?)
座主坊(ざしゅぼう):2メートル105キロの巨漢
これが、アニメとか、ライトノベルであれば、きっとこれらのキャラクターに淫した展開なり作品が書かれたにちがいないが、これは、あくまでも推理小説。キャラに淫することなく、ストーリーが展開するのは、潔くて、いい。
警察が幽霊の存在を認めるにいたった事件が作品ごとに違う説明になっているのも面白い。
捜査五課の登場のきっかけ、『復讐』では、こんな風。
「問題点は一つ。鑑識の見立てでは、鰐田の死は他殺と思われる不審死だ。つまり犯人がいるということになる。では、犯人はどうやって彼を殺したのか?」
米田が怒鳴る。
「撲殺だと言ったのは、おまえらだぞ」
「そうじゃない。本館の周囲に足跡はなかったんだ。雪に跡をつけず、犯人はどうやって本館に入り、鰐田を殺したんだ?さらに、殺害後、どうやって逃亡したんだ?」
嫌な予感は当たったらしい。叶も津上も、米田さえも、蒼い顔をして互いを見合っている。
米田が言った。
「つまり、その何だ・・・この一件は、み、み、密室殺人のケースだと?」
「足跡がない限り、そう言わざるを得ないな」
「署長に報告して参ります」
津上が敬礼をして、すっとんでいった。叶も腕組みをして、大きなため息をついている。米田も苦虫を噛み潰したような顔で、
「密室、密室かぁ」
とくり返す。私は反町と目を合わせた。
「反町さん、つまりこれは・・・」
「幽霊の仕業ということになりますな」
ウヒャー、面白い!
また、『闇夜』では、頭頂部にナイフを刺された死体が出てくる。
うん?
頭頂部にナイフ?
これは『機械探偵クリク・ロボット』じゃないのか?
そして、案の定、頭頂部ナイフのトリックはクリク・ロボットそのまんまだったが、そのあとの展開が違って、『闇夜』はヒチコックのある映画みたいな怖さをかもし出している。
最終話が、作品の発表順で言うと、最初に掲載されているもので、書き直されて本書に収録されている。
いや~、この設定の勝利に、久々にミステリーの醍醐味を味わったな~。