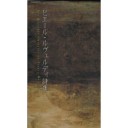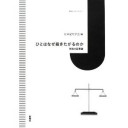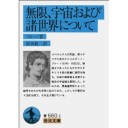『死にゆく都市、回帰する巷 ニューヨークとその彼方』
2012年9月27日 読書
高祖岩三郎の『死にゆく都市、回帰する巷 ニューヨークとその彼方』を読んだ。
本書で取り上げられる「楼閣」と「巷」については、次のような説明がある。
で、ニューヨークで見られる「楼閣」と「巷」の分離は、次のようなものである。
こういった事情は大阪でもキタを見ると歴然としているように思える。ただ、本書でも書かれているように、大阪のミナミ、とくにディープサウスになると、話は別で、そうした分離が進んでいないようだ。これは都市としての後進性をあらわすものではなく、闘争の結果だと思える。
本書ではニューヨークを例にとって、こう書かれている。
ここで言われている「この闘争」というのは、ロバート・モーゼスが
のに対して、住民たちが自動車都市への批判で大同団結して共闘戦線を結成した闘争のことである。
やるもんだな。
以下、目次。
はじめに――ニューヨークとその彼方
2006
1.都市の言葉(ロゴス)について
2.都市空間と芸術(アート)
3.都市の中の詩――あるいは「前夜の詩人たち」
4.歩行都市、自動車都市、自転車都市
5.移民国家(アメリカ)の虚偽
6.アート・情動労働・アクティヴィズム
7.大阪からニューヨークへ――幻のメガロポリス
8.世界の鼓動を聴く――プロスペクト・パークのドラム集団(サークル)
9.ニューヨークの英語――地の果ての言語
10.未来主義の廃墟から
11.再建SDSについて
12.オアハカ市とニューヨーク市を繋ぐもの
2007
13.甦る九・一一直後の光景
14.歴史的宿命に抗して――あるいはピンチョンのAgainst the Day
15.権力もまた夢を視る――あるいはロバート・モーゼス再評価について
16.知性と文化の脱ジェントリフィケーション
17.進歩的な「夢想の政治」は可能か?――スティーブン・ダンコムのDreamについて
18.地球的正義の系譜――アブラハム・リンカーン旅団再訪
19.恐怖による政治
20.セントラルパークという装置
21.ハドソン河のグローバルな詩
22.ニューヨーク以後の都市モデル
23.理論と政治の限界について――直接行動礼賛
24.馬鹿者どもの壁
2008
25.ふたつのアメリカの闘争
26.CNN、FOX――テレビによる単一国民形成
27.不動産アートの出現
28.ポートランドからニューヨークを見る、あるいは都市のエコロジー
29.大統領選挙の悪夢
30.回帰し続ける警察の暴挙――ショーン・ベル事件とその後
31.地球的密集、共棲、そして相互扶助
32.ブルックリンにおける二〇〇八年反G8運動報告会
33.二つの国民選挙
34.垣間みえる新しい時代
35.アメリカ郊外の哀しみ
36.火の河をわたれ!
2009
37.ニュースクール造反有利
38.諸価値の価値転換
39.われわれはただの生を肯定しえるか?
40.回帰するメルヴィル
41.いま政治の穴から垣間見えるもの
42.複数のアメリカ合衆国国歌(アンセム)
おわりに――批判的範疇(カテゴリー)としての都市
NHK-FM「ベスト・オブ・クラシック」
近藤譲
- 現代音楽特集 -(3)
「4つの魔法」 ジャチント・シェルシ作曲
(9分53秒)
(合唱)ケルン放送合唱団
(演奏)南西ドイツ放送実験スタジオ
(演奏)ケルン放送交響楽団のメンバー
(指揮)ルパート・フーバー
「古い墓の浮き彫りに寄せて…」 クラウス・オスパルト作曲
(25分45秒)
(バス・チューバ)クラウス・ブルガー
(合唱)ケルン放送合唱団
(演奏)ケルン打楽器四重奏団
(演奏)南西ドイツ放送実験スタジオ
(指揮)ルパート・フーバー
~ドイツ・ウィッテン テアターザールで収録~
<2012/4/28>
(西部ドイツ放送協会提供)
「ステイシス」 レベッカ・ソーンダース作曲
(47分14秒)
(演奏)ムジーク・ファブリック
~ドイツ・ドナウエッシンゲン
ドナウハレストラヴィンスキーザールで収録~
<2011/10/15>
(南西ドイツ放送協会提供)
本書で取り上げられる「楼閣」と「巷」については、次のような説明がある。
経済活動と労働の非都市化(周縁化)が進行し、その結果、古典的なモデルにおいては合体していた「楼閣」と「巷」の分離がはじまっている。
ここでは「楼閣」とは、大建物および交通機関などの象徴的/基盤的施設である。それに対して「巷」とは、人びとの集合性とその関係性が最大限に活性化した状況/場所である。
で、ニューヨークで見られる「楼閣」と「巷」の分離は、次のようなものである。
投資ゲームの対象としてメトロポリス中心部に建てられた無数の「楼閣」は、使用価値を剥奪された無人空間と化し、「巷」はますますそこから撤退し、周縁部に移動しつつ、浮動を余儀なくされている。民衆的生活圏、ボヘミア、ダウンタウンはマンハッタン島を離れ、ブルックリン、ブロンクスなど、周縁部へと遠心的に拡散している。
こういった事情は大阪でもキタを見ると歴然としているように思える。ただ、本書でも書かれているように、大阪のミナミ、とくにディープサウスになると、話は別で、そうした分離が進んでいないようだ。これは都市としての後進性をあらわすものではなく、闘争の結果だと思える。
本書ではニューヨークを例にとって、こう書かれている。
全米のほとんどの都市が「自動車都市」となったのに対して、ニューヨークがいまだに「歩行都市」なのは偶然ではない。あくまでもこの闘争の賜物だったのである。
ここで言われている「この闘争」というのは、ロバート・モーゼスが
ニューヨーク市と州の開発局を牛耳って、五区とそのまわりにハイウェイや橋を渡し「自動車交通用の巨大空間」を造形した。これはアメリカ全土で進行していた「社会の自動車化」つまり「ダウンタウンを殺し郊外を生産する」運動の一環だった。
のに対して、住民たちが自動車都市への批判で大同団結して共闘戦線を結成した闘争のことである。
やるもんだな。
以下、目次。
はじめに――ニューヨークとその彼方
2006
1.都市の言葉(ロゴス)について
2.都市空間と芸術(アート)
3.都市の中の詩――あるいは「前夜の詩人たち」
4.歩行都市、自動車都市、自転車都市
5.移民国家(アメリカ)の虚偽
6.アート・情動労働・アクティヴィズム
7.大阪からニューヨークへ――幻のメガロポリス
8.世界の鼓動を聴く――プロスペクト・パークのドラム集団(サークル)
9.ニューヨークの英語――地の果ての言語
10.未来主義の廃墟から
11.再建SDSについて
12.オアハカ市とニューヨーク市を繋ぐもの
2007
13.甦る九・一一直後の光景
14.歴史的宿命に抗して――あるいはピンチョンのAgainst the Day
15.権力もまた夢を視る――あるいはロバート・モーゼス再評価について
16.知性と文化の脱ジェントリフィケーション
17.進歩的な「夢想の政治」は可能か?――スティーブン・ダンコムのDreamについて
18.地球的正義の系譜――アブラハム・リンカーン旅団再訪
19.恐怖による政治
20.セントラルパークという装置
21.ハドソン河のグローバルな詩
22.ニューヨーク以後の都市モデル
23.理論と政治の限界について――直接行動礼賛
24.馬鹿者どもの壁
2008
25.ふたつのアメリカの闘争
26.CNN、FOX――テレビによる単一国民形成
27.不動産アートの出現
28.ポートランドからニューヨークを見る、あるいは都市のエコロジー
29.大統領選挙の悪夢
30.回帰し続ける警察の暴挙――ショーン・ベル事件とその後
31.地球的密集、共棲、そして相互扶助
32.ブルックリンにおける二〇〇八年反G8運動報告会
33.二つの国民選挙
34.垣間みえる新しい時代
35.アメリカ郊外の哀しみ
36.火の河をわたれ!
2009
37.ニュースクール造反有利
38.諸価値の価値転換
39.われわれはただの生を肯定しえるか?
40.回帰するメルヴィル
41.いま政治の穴から垣間見えるもの
42.複数のアメリカ合衆国国歌(アンセム)
おわりに――批判的範疇(カテゴリー)としての都市
NHK-FM「ベスト・オブ・クラシック」
近藤譲
- 現代音楽特集 -(3)
「4つの魔法」 ジャチント・シェルシ作曲
(9分53秒)
(合唱)ケルン放送合唱団
(演奏)南西ドイツ放送実験スタジオ
(演奏)ケルン放送交響楽団のメンバー
(指揮)ルパート・フーバー
「古い墓の浮き彫りに寄せて…」 クラウス・オスパルト作曲
(25分45秒)
(バス・チューバ)クラウス・ブルガー
(合唱)ケルン放送合唱団
(演奏)ケルン打楽器四重奏団
(演奏)南西ドイツ放送実験スタジオ
(指揮)ルパート・フーバー
~ドイツ・ウィッテン テアターザールで収録~
<2012/4/28>
(西部ドイツ放送協会提供)
「ステイシス」 レベッカ・ソーンダース作曲
(47分14秒)
(演奏)ムジーク・ファブリック
~ドイツ・ドナウエッシンゲン
ドナウハレストラヴィンスキーザールで収録~
<2011/10/15>
(南西ドイツ放送協会提供)
『切りとれ、あの祈る手を <本>と<革命>をめぐる五つの夜話』
2012年9月26日 読書
佐々木中の『切りとれ、あの祈る手を <本>と<革命>をめぐる五つの夜話』を読んだ。
勇気づけられる書であるが、僕のような怠惰な人間が読むと、言い訳に使いそうで、これは取り扱い注意の本なのである。
以下、目次。
目次についている章題は本文中にはなく、おおまかな流れをつかむための引用句集が巻頭にあるような感じだ。
第一夜「文学の勝利」
「焦慮は罪である」/誰の手下にもならなかったし、誰も手下にしなかった/「拒絶者は悔いぬ」/この時代にあって情報を遮断すること/「すべて」について「すべて」を語れるという幻想/情報を集めるということは、命令を集めるということだ/「すべて」と「ひとつ」をめぐる悪しき知の姿-「批評家」と「専門家」/拒絶することはできないのか/何もしないでいること、彷徨すること/ニーチェは問う、「『哲学者』というものは今日もまだ可能だろうか」/「諸君は、いつも耳を澄まし、いつも一言投げ入れることができる機会をねらっているから、真の生産力をすっかり失くす!」/世界を生み出すこと-概念(conceptus)と受胎(conceptio)/書くこと、「女性になること」-ニーチェ、ラカン、ドゥルーズ/懐妊の賭け/本を読んだ、読んでしまった/グリューンヴェーデル、読むことの狂気/読めない本を読む、他人の夢を見る/少なく、繰り返し読む/何故「藝」か/ベルネ法とフロイトの自由連想-精神分析と文学/ジョイスとフロイト、同じ「歓び」という名を連れて/フロイトはヴァージニア・ウルフに捧げた、水仙の白い花を/ヴァージニアは言い放つ、「最後には孤独な戦いが私たちを待っている」/ロビンソン・クルーソー、孤島の奈落/ヴァージニア・ウルフなんてこわくない/読書の愉悦は神をも羨望させる/そもそも「文学」とは何か/ロック、ヒューム、ニュートン、アダム・スミス-彼ら「文学者」たち/<文学>―聖書を読み書く技藝(アート)-それはいまだ文学と呼ばれなくてはならない、もっと広い意味で
第二夜「ルター、文学者ゆえに革命家」
われわれは革命から来た/六つの革命/「革命」という語について-「大革命」としての宗教改革/暴力革命が「すべて」なのか/大革命とは、聖書を読む運動である/キリスト教世界の腐敗/修道院は貴族の贅沢な社交場になり果てていた/聖アンナへの誓願、修道士ルターの誕生/ルターの苦悩-「私は神を憎んでいた」/ルターは、本を、読んだ/本を読んでいるこの俺が狂っているのか、それともこの世界が狂っているのか/祈りと試練としての読書/ルター、この言葉の人/95箇条の提題に天使が舞い降りる/彼は「彼女」に会いに来た、白い薔薇を一輪持って/「我、ここに立つ。私には、他にどうすることもできない」/『九月聖書』-ドイツ語を鍛え上げる/「明日で世界が終わろうと、私は今日林檎の木を植える」/ドイツ・コラールの創始者、音楽家ルター/法の革命としてのルター革命/法における「良心」の案出/「法治国家」の誕生-世俗国家の宗教化/「聖書博士にして、教皇の妨害者」/「性急さや暴力は神に対する信頼の欠如を暴露している」-言葉による革命/「マルティン・ルター」キング牧師/ドイツ農民戦争の<勝利>/革命の本体はテクストである。決して暴力ではない/革命にとって暴力は二次的なものに過ぎない/文学こそが革命の根源である/ルター、文学者ゆえに革命家
第三夜「読め、母なる文盲の孤児よ ― ムハンマドとハディージャの革命」
「取りて読め、取りて読め、取りて読め」-世界の滅びのなかで/大革命と「カトリック対抗大革命」/血で汚れていない手などない、しかし、それでも/スペインの改革、スペイン神秘主義の闘争/殺されるか、狂気を賭けて読むか/「恐れるな、わたしはあなたに対して、あたかも開かれた本の様になろう」/ムハンマドの<革命>/自分を宗教だと思っている宗教にできることは何もない/ジャーヒリーヤ、女たちの汚辱/「私は、市場をうろついてはものを食うただの男に過ぎない」/ハディージャの求婚/苦悩するムハンマド/大天使ジブリールとの遭遇/ムハンマドの錯乱、ハディージャの庇護/「神は決してあなたを辱めないでしょう」/そして神の啓示は下った-「読め」/「読め。汝の主はこよなきありがたき御方にして、筆を持つ術を教えたもう」/文盲が「読む」/ハディージャなくしてグローバリゼーションなし/女性の擁護者、ムハンマド/母なる文盲、本の母/かくして「本」は受胎した/天使とは何か-読み得ぬことを読むこと/「大天使ジブリールはムハンマドの喉を裂き、」/神は最初に筆を作りこう命じた、「書け」/花咲くイスラーム<文学>/「黄金よりも詩の言葉はすばらしいものである」/文学こそが革命の力であり、革命は文学からしか起こらない/覆せるか、この夜の、この天使との邂逅が/KRSワン、女性と創造性/法の起源をめぐる西欧的思考の例外、父ならぬムハンマド/暴力は先行しない、暴力は国家や法の起源でも根源でもない/「父殺し」の思考の限界/悪しき原理主義、その新たな定義/「最終解脱者を名乗るなかれ」/奇蹟を否定するブッダ/イエスは言う、「その日その時はだれも知らない」/終末の期限を切るものは悪魔である/原理主義者は本が読めない、その勇気もない/「お前は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」/悪しき終末論は自らの生のあいだに世界の終末と滅亡を望む/終末と絶滅の「絶対的享楽」/「読まない」ことは人を殺す/ナチス、世界とともに自殺すること/オウム真理教やナチスと同型の思考を繰り広げる現代思想/前世は此処で、来世も此処だ/私が死んだあとも世界は続く/頼むから辞書くらい引いて貰えないか-アガンベン批判/世界はもっと広く、もっと長く続く/現代文学の抗戦/終わらないフィネガンの通夜/ベケット、永遠に続く終盤戦/『ゴドーを待ちながら』-「そしてまた戦い始めた」/「他の日々と同じようなある日」、「また新たな夜が来る。前へ!」/笑いながら、ベケットは言った-「共生だよ」
第四夜「われわれには見える ― 中世解釈者革命を超えて」
一二世紀に革命が起きた-全ヨーロッパ革命の母なる革命が/一二世紀における資本制の胚胎/彼らは自らを近代と呼んだ-ルターも、オッカムのウィリアムも、一二世紀の法学者も/「新たなる法(jus novum)」を産み出した革命/「聖なる魔王」教皇グレゴリウス七世の闘争/教皇革命は成就した/密やかなる別の革命-『ローマ法大全』の発見/法の革命、『グラーティアヌス教令集』の決定的な勝利/汎ヨーロッパ共通法としての教会法、それは何だったのか/生きるための法、生み育てるための法/法の外に居た子どもたち、その惨禍/革命は子どもの生を「守護する」ことでなくてはならない/国家の本質とは「繁殖を保証する」ことである/どうして国連は「宙に浮いた」ものであるのか、何故世界政府は成立しないのか/近代国家の起源、それは解釈者革命におけるキリスト教共同体である/近代主権の起源としての教皇/近代官僚制の起源としての教皇庁/実証主義、近代科学の起源としての法の革命/会社や協同組合の起源-フィクションとしての法人/中世解釈者革命が近代資本制の原型をつくる/法ナショナリズムの問題/中世解釈者革命は、情報技術革命だった/翻訳、編纂、製本、註釈、修正、索引-そして法は情報化した/神話を舞うこと、律法を舐めること-これも「テクスト」である/人を統治するテクスト、それはもっと広い/何に何を書いてもそれは文学なのだ/われわれの法は、踊られなくてはならない/統治の情報化-法は歌われず、踊られず、飲まれなくなる/情報とデータベースの世界、それは中世解釈者革命の効果に過ぎない/統治の情報化が暴力を生む/暴力革命の誕生/ひとは800年言い続けている-すべては情報である、と/情報と暴力のなかで藻掻く世界、脱出の方途は/われわれには見える。われわれには聞こえる/情報か暴力か、このような二者択一は夢想に過ぎない/「主権」-それは情報と暴力の二分法から析出された/ゆえに、革命とは情報でも暴力でも主権の奪取でもない/世俗化、ヨーロッパの戦略兵器/宗教か世俗化か、それは思考の罠である/「信仰」という概念は放棄されなくてはならない/信仰が消える、読みそして書く時空/一体何を言っているんだこの白人は/ファシズム、スターリニズム-藝術の力を抑圧するからこそ、それは外から回帰する/藝術-その善悪の彼岸/人間の統治としての藝術/情報機器の取り扱いも、儀礼であることを免れない/精が出ますね/藝術と文学は、統治や繁殖と切り離すことができない/なべて藝術とは、受胎の藝術なのです/たかが800年が何だというのだ/辞任要求
第五夜「そして三八〇万年の永遠」
ビニールのかわいらしいプールなのかもしれません/「世界は老いたり(Mundus senescit)」-終末幻想の長い歴史/「文学は終わった」と人は繰り返してきた/ギリシャ文学と哲学、その0.1パーセントの勝利/文字が生まれてから9割は「全文盲」/全文盲の女性の物語/識字の歴史-それは直線的に発達したのではない/印刷術、製紙、眼鏡-読書の物質的基盤/文字が読めない人のための書物、「暦」/カレンダー、手帳、占い、そして挿絵入りの本は昔から売れていた/革命による読書熱、革命の失敗による読書離れ/革命は終わった文学は終わったなんて書いてある本を誰が読むか/一七世紀フランス、コルネイユやラシーヌの時代の識字率/一七世紀イングランド、シェイクスピアやミルトンの時代の識字率/「学問こそ革命の先駆けでありわれらの敵である」/一八五〇年、文学の黄金時代の文盲率はどうだったか/イングランドはディケンズ/フランスはバルザック、フローベール、ボードレール/ロシア帝国、全文盲率九割/ドストエフスキーの闘争/ロシア文学の勝利/文学が生き延びる、藝術が生き延びる、革命が生き延びる/20万年前、ホモ・サピエンス誕生/絵画、服飾、音楽-7万年ないし3万年の歴史/農耕、牧畜、資本の蓄積による経済活動は1万年の歴史しかない/文字の発明から、たった5000年しか経っていない/文学は以上に若い藝術である/文学は終わった?恥ずかしいからやめてください/5000年は20万年の40分の1。八〇歳から見たら二歳児/古生物学によると、世界の終わりはもう来ました。五回もね。で?/有史以来、広島原爆の千倍の威力の隕石が15個は落ちている。誰も死んでいない/世界は滅びないです。残念でした/イナゴの「群生相」/モーリス・ブランショの偉大さ-「終わり」の絶対的拒絶/生物種の平均寿命は400万年/四歳の男の子がやってきて「もう終わりだ」と言ったら/379万年譲ったとしても/「君はなされる!いかなる時でも!」/「どうして作品を発表しなくてはいけないのですか」/夜のなかで足音を響かせること/彼がいてくれてよかった、彼がそこにいた/『ツァラトゥストラ」最終第四部は、自費出版で7部しか配られなかった/フリードリッヒ・ニーチェの勝利/未来の文献学は、大天使の文献学である/足音が聞こえる。それは聞こえる/「言葉は失われることなく残った」/『ツァラトゥストラ』第四部-「勇気を失ってはいけない。多くのことが、まだまだ可能なのだ」/380万年の永遠が、われわれを待っている/この前夜の深まりのなかへ
勇気づけられる書であるが、僕のような怠惰な人間が読むと、言い訳に使いそうで、これは取り扱い注意の本なのである。
以下、目次。
目次についている章題は本文中にはなく、おおまかな流れをつかむための引用句集が巻頭にあるような感じだ。
第一夜「文学の勝利」
「焦慮は罪である」/誰の手下にもならなかったし、誰も手下にしなかった/「拒絶者は悔いぬ」/この時代にあって情報を遮断すること/「すべて」について「すべて」を語れるという幻想/情報を集めるということは、命令を集めるということだ/「すべて」と「ひとつ」をめぐる悪しき知の姿-「批評家」と「専門家」/拒絶することはできないのか/何もしないでいること、彷徨すること/ニーチェは問う、「『哲学者』というものは今日もまだ可能だろうか」/「諸君は、いつも耳を澄まし、いつも一言投げ入れることができる機会をねらっているから、真の生産力をすっかり失くす!」/世界を生み出すこと-概念(conceptus)と受胎(conceptio)/書くこと、「女性になること」-ニーチェ、ラカン、ドゥルーズ/懐妊の賭け/本を読んだ、読んでしまった/グリューンヴェーデル、読むことの狂気/読めない本を読む、他人の夢を見る/少なく、繰り返し読む/何故「藝」か/ベルネ法とフロイトの自由連想-精神分析と文学/ジョイスとフロイト、同じ「歓び」という名を連れて/フロイトはヴァージニア・ウルフに捧げた、水仙の白い花を/ヴァージニアは言い放つ、「最後には孤独な戦いが私たちを待っている」/ロビンソン・クルーソー、孤島の奈落/ヴァージニア・ウルフなんてこわくない/読書の愉悦は神をも羨望させる/そもそも「文学」とは何か/ロック、ヒューム、ニュートン、アダム・スミス-彼ら「文学者」たち/<文学>―聖書を読み書く技藝(アート)-それはいまだ文学と呼ばれなくてはならない、もっと広い意味で
第二夜「ルター、文学者ゆえに革命家」
われわれは革命から来た/六つの革命/「革命」という語について-「大革命」としての宗教改革/暴力革命が「すべて」なのか/大革命とは、聖書を読む運動である/キリスト教世界の腐敗/修道院は貴族の贅沢な社交場になり果てていた/聖アンナへの誓願、修道士ルターの誕生/ルターの苦悩-「私は神を憎んでいた」/ルターは、本を、読んだ/本を読んでいるこの俺が狂っているのか、それともこの世界が狂っているのか/祈りと試練としての読書/ルター、この言葉の人/95箇条の提題に天使が舞い降りる/彼は「彼女」に会いに来た、白い薔薇を一輪持って/「我、ここに立つ。私には、他にどうすることもできない」/『九月聖書』-ドイツ語を鍛え上げる/「明日で世界が終わろうと、私は今日林檎の木を植える」/ドイツ・コラールの創始者、音楽家ルター/法の革命としてのルター革命/法における「良心」の案出/「法治国家」の誕生-世俗国家の宗教化/「聖書博士にして、教皇の妨害者」/「性急さや暴力は神に対する信頼の欠如を暴露している」-言葉による革命/「マルティン・ルター」キング牧師/ドイツ農民戦争の<勝利>/革命の本体はテクストである。決して暴力ではない/革命にとって暴力は二次的なものに過ぎない/文学こそが革命の根源である/ルター、文学者ゆえに革命家
第三夜「読め、母なる文盲の孤児よ ― ムハンマドとハディージャの革命」
「取りて読め、取りて読め、取りて読め」-世界の滅びのなかで/大革命と「カトリック対抗大革命」/血で汚れていない手などない、しかし、それでも/スペインの改革、スペイン神秘主義の闘争/殺されるか、狂気を賭けて読むか/「恐れるな、わたしはあなたに対して、あたかも開かれた本の様になろう」/ムハンマドの<革命>/自分を宗教だと思っている宗教にできることは何もない/ジャーヒリーヤ、女たちの汚辱/「私は、市場をうろついてはものを食うただの男に過ぎない」/ハディージャの求婚/苦悩するムハンマド/大天使ジブリールとの遭遇/ムハンマドの錯乱、ハディージャの庇護/「神は決してあなたを辱めないでしょう」/そして神の啓示は下った-「読め」/「読め。汝の主はこよなきありがたき御方にして、筆を持つ術を教えたもう」/文盲が「読む」/ハディージャなくしてグローバリゼーションなし/女性の擁護者、ムハンマド/母なる文盲、本の母/かくして「本」は受胎した/天使とは何か-読み得ぬことを読むこと/「大天使ジブリールはムハンマドの喉を裂き、」/神は最初に筆を作りこう命じた、「書け」/花咲くイスラーム<文学>/「黄金よりも詩の言葉はすばらしいものである」/文学こそが革命の力であり、革命は文学からしか起こらない/覆せるか、この夜の、この天使との邂逅が/KRSワン、女性と創造性/法の起源をめぐる西欧的思考の例外、父ならぬムハンマド/暴力は先行しない、暴力は国家や法の起源でも根源でもない/「父殺し」の思考の限界/悪しき原理主義、その新たな定義/「最終解脱者を名乗るなかれ」/奇蹟を否定するブッダ/イエスは言う、「その日その時はだれも知らない」/終末の期限を切るものは悪魔である/原理主義者は本が読めない、その勇気もない/「お前は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」/悪しき終末論は自らの生のあいだに世界の終末と滅亡を望む/終末と絶滅の「絶対的享楽」/「読まない」ことは人を殺す/ナチス、世界とともに自殺すること/オウム真理教やナチスと同型の思考を繰り広げる現代思想/前世は此処で、来世も此処だ/私が死んだあとも世界は続く/頼むから辞書くらい引いて貰えないか-アガンベン批判/世界はもっと広く、もっと長く続く/現代文学の抗戦/終わらないフィネガンの通夜/ベケット、永遠に続く終盤戦/『ゴドーを待ちながら』-「そしてまた戦い始めた」/「他の日々と同じようなある日」、「また新たな夜が来る。前へ!」/笑いながら、ベケットは言った-「共生だよ」
第四夜「われわれには見える ― 中世解釈者革命を超えて」
一二世紀に革命が起きた-全ヨーロッパ革命の母なる革命が/一二世紀における資本制の胚胎/彼らは自らを近代と呼んだ-ルターも、オッカムのウィリアムも、一二世紀の法学者も/「新たなる法(jus novum)」を産み出した革命/「聖なる魔王」教皇グレゴリウス七世の闘争/教皇革命は成就した/密やかなる別の革命-『ローマ法大全』の発見/法の革命、『グラーティアヌス教令集』の決定的な勝利/汎ヨーロッパ共通法としての教会法、それは何だったのか/生きるための法、生み育てるための法/法の外に居た子どもたち、その惨禍/革命は子どもの生を「守護する」ことでなくてはならない/国家の本質とは「繁殖を保証する」ことである/どうして国連は「宙に浮いた」ものであるのか、何故世界政府は成立しないのか/近代国家の起源、それは解釈者革命におけるキリスト教共同体である/近代主権の起源としての教皇/近代官僚制の起源としての教皇庁/実証主義、近代科学の起源としての法の革命/会社や協同組合の起源-フィクションとしての法人/中世解釈者革命が近代資本制の原型をつくる/法ナショナリズムの問題/中世解釈者革命は、情報技術革命だった/翻訳、編纂、製本、註釈、修正、索引-そして法は情報化した/神話を舞うこと、律法を舐めること-これも「テクスト」である/人を統治するテクスト、それはもっと広い/何に何を書いてもそれは文学なのだ/われわれの法は、踊られなくてはならない/統治の情報化-法は歌われず、踊られず、飲まれなくなる/情報とデータベースの世界、それは中世解釈者革命の効果に過ぎない/統治の情報化が暴力を生む/暴力革命の誕生/ひとは800年言い続けている-すべては情報である、と/情報と暴力のなかで藻掻く世界、脱出の方途は/われわれには見える。われわれには聞こえる/情報か暴力か、このような二者択一は夢想に過ぎない/「主権」-それは情報と暴力の二分法から析出された/ゆえに、革命とは情報でも暴力でも主権の奪取でもない/世俗化、ヨーロッパの戦略兵器/宗教か世俗化か、それは思考の罠である/「信仰」という概念は放棄されなくてはならない/信仰が消える、読みそして書く時空/一体何を言っているんだこの白人は/ファシズム、スターリニズム-藝術の力を抑圧するからこそ、それは外から回帰する/藝術-その善悪の彼岸/人間の統治としての藝術/情報機器の取り扱いも、儀礼であることを免れない/精が出ますね/藝術と文学は、統治や繁殖と切り離すことができない/なべて藝術とは、受胎の藝術なのです/たかが800年が何だというのだ/辞任要求
第五夜「そして三八〇万年の永遠」
ビニールのかわいらしいプールなのかもしれません/「世界は老いたり(Mundus senescit)」-終末幻想の長い歴史/「文学は終わった」と人は繰り返してきた/ギリシャ文学と哲学、その0.1パーセントの勝利/文字が生まれてから9割は「全文盲」/全文盲の女性の物語/識字の歴史-それは直線的に発達したのではない/印刷術、製紙、眼鏡-読書の物質的基盤/文字が読めない人のための書物、「暦」/カレンダー、手帳、占い、そして挿絵入りの本は昔から売れていた/革命による読書熱、革命の失敗による読書離れ/革命は終わった文学は終わったなんて書いてある本を誰が読むか/一七世紀フランス、コルネイユやラシーヌの時代の識字率/一七世紀イングランド、シェイクスピアやミルトンの時代の識字率/「学問こそ革命の先駆けでありわれらの敵である」/一八五〇年、文学の黄金時代の文盲率はどうだったか/イングランドはディケンズ/フランスはバルザック、フローベール、ボードレール/ロシア帝国、全文盲率九割/ドストエフスキーの闘争/ロシア文学の勝利/文学が生き延びる、藝術が生き延びる、革命が生き延びる/20万年前、ホモ・サピエンス誕生/絵画、服飾、音楽-7万年ないし3万年の歴史/農耕、牧畜、資本の蓄積による経済活動は1万年の歴史しかない/文字の発明から、たった5000年しか経っていない/文学は以上に若い藝術である/文学は終わった?恥ずかしいからやめてください/5000年は20万年の40分の1。八〇歳から見たら二歳児/古生物学によると、世界の終わりはもう来ました。五回もね。で?/有史以来、広島原爆の千倍の威力の隕石が15個は落ちている。誰も死んでいない/世界は滅びないです。残念でした/イナゴの「群生相」/モーリス・ブランショの偉大さ-「終わり」の絶対的拒絶/生物種の平均寿命は400万年/四歳の男の子がやってきて「もう終わりだ」と言ったら/379万年譲ったとしても/「君はなされる!いかなる時でも!」/「どうして作品を発表しなくてはいけないのですか」/夜のなかで足音を響かせること/彼がいてくれてよかった、彼がそこにいた/『ツァラトゥストラ」最終第四部は、自費出版で7部しか配られなかった/フリードリッヒ・ニーチェの勝利/未来の文献学は、大天使の文献学である/足音が聞こえる。それは聞こえる/「言葉は失われることなく残った」/『ツァラトゥストラ』第四部-「勇気を失ってはいけない。多くのことが、まだまだ可能なのだ」/380万年の永遠が、われわれを待っている/この前夜の深まりのなかへ
山田風太郎少年小説コレクション1『夜光珠の怪盗』
2012年9月25日 読書
論創社の山田風太郎少年小説コレクション1『夜光珠の怪盗』を読んだ。
単行本未収録の少年少女向け探偵小説の数々。挿絵も復刻されていて、これは必読。
全体を読んだ印象は、とにかく、鳩が大活躍する作品が多かった、ということだ。鳩は乱歩の『宇宙怪人』などでは悪用もされたが、こっちは正義の側が善用していた。
以下、目次。
「黄金密使」(「少年少女譚海 1950年9月~11月号)
異国の使者
覆面の殺人者
密使の少女
第二の犠牲
鳩を飼う快少年
石鹸売りの小騎士
忠僕をさらう魔猿団
都会の地下牢
空とぶ護衛兵
魔猿団の正体
小騎士の勝ちだ!
黄金山脈
「軟骨人間」(科学の友 1950年1月号)
「古墳怪盗団」(科学の友 1950年2月号)
「空を飛ぶ悪魔」(科学の友 1950年3月号)
「天使の復讐」(六年の学習 1952年3月増刊号)
小さな姉妹
百貫めの大石
一つ目の綱吉
石を投げるもの
「さばくのひみつ」(小学生朝日新聞 1953年7月26日、8月2,9,16,23,30日)
火の神のつたえ
おお石油がでた
ピストルもった男
見つからぬ手紙
あっピストル男
さいごのわな
「窓の紅文字」(少年画報 1953年2月号)
怪人青頭巾
恐しき舞踏会
意外な真犯人
「緑の髑髏紳士」(少年少女漫画と読物 1953年1~3月号)
吹雪の夜のふしぎな事件
少年探偵のり出す
黄金堂にしのびよる魔手
魔煙の空に笑う声
血だけをのこす妖怪紳士
天翔けり去る髑髏紳士
少年探偵はとく妖術の秘密
驚倒すべき真犯人
「夜光珠の怪盗」(太陽少年 1953年1~2月号)
警視総監の鞄
煙突上の怪人
黒手組の地下牢
ねずみはどこからでてきたか
驚天動地の魔法使い
夜光舞踏会の怪奇
竹千代の勝だ!
「ねむり人形座」(よみうり少年少女新聞1961年6月1日~11月2日)
解説で、本作のなかの一作品で用いられたトリックが、「天誅」のトリックを使っていた、と書いてあった。「天誅」といえば、山田風太郎の作品のなかでも突拍子もないトリックとして有名なので、少年もので大丈夫かな、と思われるだろうが、使用されていたのは、密室トリックであって、凶器トリックのほうではなかったので、御安心を。
NHK-FMの「ベスト・オブ・クラシック」現代音楽特集。
近藤譲
- 現代音楽特集 -(2)
「弦楽四重奏曲 第4番」 ハンス・アブラハムセン作曲
(21分00秒)
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
「謝肉祭と四句節の争い」 マウロ・ランツァ作曲
(12分40秒)
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
(演奏)ジャック弦楽四重奏団
「弦楽四重奏曲 第2番」 シモン・ステン・アナーセン作曲
(13分45秒)
(演奏)ジャック弦楽四重奏団
「2012-S」 ジェームズ・クラーク作曲
(14分35秒)
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
~ドイツ・ウィッテン ルドルフ・シュタイナー学校
オーディトリウムで収録~
<2012/4/28>
(西部ドイツ放送協会提供)
「改変旋律歌集」 ワルター・ツィンマーマン作曲
(9分15秒)
(演奏)ジャック弦楽四重奏団
「3つの小ノクターン」 ハンス・アブラハムセン作曲
(8分47秒)
(アコーディオン)フローデ・ハルトゥリ
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
~ドイツ・ウィッテン ルドルフ・シュタイナー学校
オーディトリウムで収録~
<2012/4/29>
(西部ドイツ放送協会提供)
単行本未収録の少年少女向け探偵小説の数々。挿絵も復刻されていて、これは必読。
全体を読んだ印象は、とにかく、鳩が大活躍する作品が多かった、ということだ。鳩は乱歩の『宇宙怪人』などでは悪用もされたが、こっちは正義の側が善用していた。
以下、目次。
「黄金密使」(「少年少女譚海 1950年9月~11月号)
異国の使者
覆面の殺人者
密使の少女
第二の犠牲
鳩を飼う快少年
石鹸売りの小騎士
忠僕をさらう魔猿団
都会の地下牢
空とぶ護衛兵
魔猿団の正体
小騎士の勝ちだ!
黄金山脈
「軟骨人間」(科学の友 1950年1月号)
「古墳怪盗団」(科学の友 1950年2月号)
「空を飛ぶ悪魔」(科学の友 1950年3月号)
「天使の復讐」(六年の学習 1952年3月増刊号)
小さな姉妹
百貫めの大石
一つ目の綱吉
石を投げるもの
「さばくのひみつ」(小学生朝日新聞 1953年7月26日、8月2,9,16,23,30日)
火の神のつたえ
おお石油がでた
ピストルもった男
見つからぬ手紙
あっピストル男
さいごのわな
「窓の紅文字」(少年画報 1953年2月号)
怪人青頭巾
恐しき舞踏会
意外な真犯人
「緑の髑髏紳士」(少年少女漫画と読物 1953年1~3月号)
吹雪の夜のふしぎな事件
少年探偵のり出す
黄金堂にしのびよる魔手
魔煙の空に笑う声
血だけをのこす妖怪紳士
天翔けり去る髑髏紳士
少年探偵はとく妖術の秘密
驚倒すべき真犯人
「夜光珠の怪盗」(太陽少年 1953年1~2月号)
警視総監の鞄
煙突上の怪人
黒手組の地下牢
ねずみはどこからでてきたか
驚天動地の魔法使い
夜光舞踏会の怪奇
竹千代の勝だ!
「ねむり人形座」(よみうり少年少女新聞1961年6月1日~11月2日)
解説で、本作のなかの一作品で用いられたトリックが、「天誅」のトリックを使っていた、と書いてあった。「天誅」といえば、山田風太郎の作品のなかでも突拍子もないトリックとして有名なので、少年もので大丈夫かな、と思われるだろうが、使用されていたのは、密室トリックであって、凶器トリックのほうではなかったので、御安心を。
NHK-FMの「ベスト・オブ・クラシック」現代音楽特集。
近藤譲
- 現代音楽特集 -(2)
「弦楽四重奏曲 第4番」 ハンス・アブラハムセン作曲
(21分00秒)
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
「謝肉祭と四句節の争い」 マウロ・ランツァ作曲
(12分40秒)
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
(演奏)ジャック弦楽四重奏団
「弦楽四重奏曲 第2番」 シモン・ステン・アナーセン作曲
(13分45秒)
(演奏)ジャック弦楽四重奏団
「2012-S」 ジェームズ・クラーク作曲
(14分35秒)
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
~ドイツ・ウィッテン ルドルフ・シュタイナー学校
オーディトリウムで収録~
<2012/4/28>
(西部ドイツ放送協会提供)
「改変旋律歌集」 ワルター・ツィンマーマン作曲
(9分15秒)
(演奏)ジャック弦楽四重奏団
「3つの小ノクターン」 ハンス・アブラハムセン作曲
(8分47秒)
(アコーディオン)フローデ・ハルトゥリ
(演奏)アルディティ弦楽四重奏団
~ドイツ・ウィッテン ルドルフ・シュタイナー学校
オーディトリウムで収録~
<2012/4/29>
(西部ドイツ放送協会提供)
『羊飼いの指輪 ファンタジーの練習帳』
2012年9月24日 読書
ジャンニ・ロダーリの『羊飼いの指輪 ファンタジーの練習帳』を読んだ。
物語の結末を3種類提示する短編集。巻末には作者ロダーリ自身が選ぶベストチョイスが示されている。
ファンタジーの練習帳の副題のとおり、物語は万物に潜んでいて、紡がれるのを待ち受けているような気がしてくる。結末のチョイスは、ロダーリが意外と常識人なことをあらわしていて、これも興味深い。
以下、目次。
魔法の小太鼓
抜け目のないピノッキオ
哀れな幽霊たち
吠え方を知らない犬
砂漠にそびえる屋敷
笛吹きと自動車
町に描いた円
ミラノの町に降った帽子
プレゼーピオに紛れこんだ余所者
ドクター・テリビリス
夜の声
魔法使いジロ
リナルドの異変
羊飼いの指輪
星へ向かうタクシー
ティーノの病気
テレビの騒動
大きなニンジン
ポケットの百リラ
旅する猫
著者の結末
夜からNHK-FMの「ベスト・オブ・クラシック」で、現代音楽特集。
近藤譲
- 現代音楽特集 -(1)
「磯波」 ペル・ネルゴー作曲、アブラハムセン編曲
(4分15秒)
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「虹」 ジェルジ・リゲティ作曲、アブラハムセン編曲
(4分10秒)
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「ピアノ協奏曲」 ハンス・アブラハムセン作曲
(15分00秒)
(ピアノ)パウリーネ・ポスト
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「スウィートハート、グッドバイ!」
ブリギッタ・ムンテンドルフ作曲
(12分40秒)
(声)ニコラ・グリュンデル
(演奏)ケルン音楽舞踊大学・電子音楽スタジオ
(演奏)南西ドイツ放送実験スタジオ
「ジェズアルド・ダブ、消された人物のいる空間」
マルコ・ニコジエヴィチ作曲
(17分35秒)
(ピアノ)パウリーネ・ポスト
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「森」 ハンス・アブラハムセン作曲
(17分25秒)
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
~ドイツ・ウィッテン テアターザールで収録~
<2012/4/27>
(西部ドイツ放送協会提供)
「渡り鳥」 カローラ・バウクホルト作曲
(12分35秒)
(演奏)カレファックス管楽五重奏団
~ドイツ・ウィッテン フェストザールで収録~
<2012/4/27>
(西部ドイツ放送協会提供)
物語の結末を3種類提示する短編集。巻末には作者ロダーリ自身が選ぶベストチョイスが示されている。
ファンタジーの練習帳の副題のとおり、物語は万物に潜んでいて、紡がれるのを待ち受けているような気がしてくる。結末のチョイスは、ロダーリが意外と常識人なことをあらわしていて、これも興味深い。
以下、目次。
魔法の小太鼓
抜け目のないピノッキオ
哀れな幽霊たち
吠え方を知らない犬
砂漠にそびえる屋敷
笛吹きと自動車
町に描いた円
ミラノの町に降った帽子
プレゼーピオに紛れこんだ余所者
ドクター・テリビリス
夜の声
魔法使いジロ
リナルドの異変
羊飼いの指輪
星へ向かうタクシー
ティーノの病気
テレビの騒動
大きなニンジン
ポケットの百リラ
旅する猫
著者の結末
夜からNHK-FMの「ベスト・オブ・クラシック」で、現代音楽特集。
近藤譲
- 現代音楽特集 -(1)
「磯波」 ペル・ネルゴー作曲、アブラハムセン編曲
(4分15秒)
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「虹」 ジェルジ・リゲティ作曲、アブラハムセン編曲
(4分10秒)
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「ピアノ協奏曲」 ハンス・アブラハムセン作曲
(15分00秒)
(ピアノ)パウリーネ・ポスト
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「スウィートハート、グッドバイ!」
ブリギッタ・ムンテンドルフ作曲
(12分40秒)
(声)ニコラ・グリュンデル
(演奏)ケルン音楽舞踊大学・電子音楽スタジオ
(演奏)南西ドイツ放送実験スタジオ
「ジェズアルド・ダブ、消された人物のいる空間」
マルコ・ニコジエヴィチ作曲
(17分35秒)
(ピアノ)パウリーネ・ポスト
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
「森」 ハンス・アブラハムセン作曲
(17分25秒)
(演奏)アスコ・シェーンベルク・アンサンブル
(指揮)ラインベルト・デ・レーウ
~ドイツ・ウィッテン テアターザールで収録~
<2012/4/27>
(西部ドイツ放送協会提供)
「渡り鳥」 カローラ・バウクホルト作曲
(12分35秒)
(演奏)カレファックス管楽五重奏団
~ドイツ・ウィッテン フェストザールで収録~
<2012/4/27>
(西部ドイツ放送協会提供)
マリオ・バルガス=リョサの『チボの狂宴』を読んだ。
これは熱くて興奮する読書体験だった。
ドミニカ共和国に長年君臨した独裁者トゥルヒーリョの暗殺について、トゥルヒーリョ側からと、暗殺者たちからの両視点で描く。また、物語を圧倒的に面白くしているのは、時が過ぎて、独裁時代の部下だった男と、その娘による回想をまじえた会話(男のほうは、既にしゃべれる身体ではないが)が描かれるところだ。
ドミニカの歴史を説明的に語る部分が本来ならうるさく思えるはずなのに、作者の語りがうまいのと、僕自身のドミニカ史の無知があいまって、じゅうぶん面白く読めた。
トゥルヒーリョが、あれだけ威厳に満ちているこわい男なのに、意識せぬ失禁に思い悩んでいる、というのも面白い。
読んでいるあいだ、熱い思いに始終打たれどおしだった。
これは熱くて興奮する読書体験だった。
ドミニカ共和国に長年君臨した独裁者トゥルヒーリョの暗殺について、トゥルヒーリョ側からと、暗殺者たちからの両視点で描く。また、物語を圧倒的に面白くしているのは、時が過ぎて、独裁時代の部下だった男と、その娘による回想をまじえた会話(男のほうは、既にしゃべれる身体ではないが)が描かれるところだ。
ドミニカの歴史を説明的に語る部分が本来ならうるさく思えるはずなのに、作者の語りがうまいのと、僕自身のドミニカ史の無知があいまって、じゅうぶん面白く読めた。
トゥルヒーリョが、あれだけ威厳に満ちているこわい男なのに、意識せぬ失禁に思い悩んでいる、というのも面白い。
読んでいるあいだ、熱い思いに始終打たれどおしだった。
『不完全なレンズで 回想と肖像』
2012年9月19日 読書
ロベール・ドアノー『不完全なレンズで 回想と肖像』を読んだ。
最近読んだサンドラールの『パリ南西東北』、エマニュエル・ボーヴの『あるかなしかの町』でドアノーの写真が使われていたので、ドアノー自身の本も読んでみたのだ。
写真だけを見ているのと、文章読むのとでは、なんだか印象が違っていた。
また、読んでみると、いろんな事実が発覚した。
有名な「パリ市庁舎前のキス」は偶然撮影されたものではなく、演出されたものだったこととか。先にあげた2冊の本両方に収録された写真で、電車の中に根のついた薔薇の木を持ち込んですわっている男の写真がある。郊外の光景の代表格のような作品だが、これも演出作品。名前はポール・バラベ。ドアノーによると「生粋の郊外人である」
以下、目次。
木でできた写真
「デ・ププリエの抜け道」におけるアジェ氏
簡潔な要約と気泡
黒い手帖
映画
工場の煙
ヴィラ・メディチとパヴィヨン・ミミール
ブレーズ・サンドラール
フランソワ・カヴァンナ
DATARの任務を負って
パリのジャック・プレヴェール
孤独な散歩
露天商たち
モード写真
ビストロ
画家たち
ジョルジュ・ブラック
フェルナン・レジェ
パブロ・ピカソ
コンスタンティン・ブランクーシ
ル・ヴェジネのモーリス・ユトリロ
ポール・レオトー
アンドレ・ヴィニョー
素朴派の画家と「ブリュット」な芸術家たち
名前たち
ブラッサイ
アンドレ・ケルテス
アンリ・カルティエ=ブレッソン
ウィリー・ロニス
エドゥアール・ブーバ
集合写真
コローク、暴力、戦争ヌード
ヌード
フォトジェニーと美女
ブリコラージュと科学的写真
分析ラボ
写真-批評
訳注
レンズの半過去形で----ロベール・ドアノー 訳者解説
最近読んだサンドラールの『パリ南西東北』、エマニュエル・ボーヴの『あるかなしかの町』でドアノーの写真が使われていたので、ドアノー自身の本も読んでみたのだ。
写真だけを見ているのと、文章読むのとでは、なんだか印象が違っていた。
また、読んでみると、いろんな事実が発覚した。
有名な「パリ市庁舎前のキス」は偶然撮影されたものではなく、演出されたものだったこととか。先にあげた2冊の本両方に収録された写真で、電車の中に根のついた薔薇の木を持ち込んですわっている男の写真がある。郊外の光景の代表格のような作品だが、これも演出作品。名前はポール・バラベ。ドアノーによると「生粋の郊外人である」
以下、目次。
木でできた写真
「デ・ププリエの抜け道」におけるアジェ氏
簡潔な要約と気泡
黒い手帖
映画
工場の煙
ヴィラ・メディチとパヴィヨン・ミミール
ブレーズ・サンドラール
フランソワ・カヴァンナ
DATARの任務を負って
パリのジャック・プレヴェール
孤独な散歩
露天商たち
モード写真
ビストロ
画家たち
ジョルジュ・ブラック
フェルナン・レジェ
パブロ・ピカソ
コンスタンティン・ブランクーシ
ル・ヴェジネのモーリス・ユトリロ
ポール・レオトー
アンドレ・ヴィニョー
素朴派の画家と「ブリュット」な芸術家たち
名前たち
ブラッサイ
アンドレ・ケルテス
アンリ・カルティエ=ブレッソン
ウィリー・ロニス
エドゥアール・ブーバ
集合写真
コローク、暴力、戦争ヌード
ヌード
フォトジェニーと美女
ブリコラージュと科学的写真
分析ラボ
写真-批評
訳注
レンズの半過去形で----ロベール・ドアノー 訳者解説
『理性と平和 ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ政治理論作品選集』
2012年9月13日 読書
『理性と平和 ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ政治理論作品選集』を読んだ。
ドイツで全35巻のフリートレンダー/ミュノーナ全集を企画した、全集編集者による、フリートレンダー/ミュノーナの紹介、全集の紹介と、政治理論に関する作品を中心にいくつか翻訳したものを載せた1冊。つまりは、全集の宣伝パンフレットの豪華なもの、ととらえてもほぼ間違いはない。と、いうのも、ここで翻訳されている政治理論の作品は、フリートレンダー/ミュノーナのほんの一面でしかなく、今まで読んだ『スフィンクス・ケーキ』『子どものためのカント』の面白みとはまた違う味わいがあったからだ。
しかし、この全集編者が、一筋縄でいかない、いかにもミュノーナ全集出そうとしそうな人物で、面白い。
デートレフ・ティールは、コンピュータ管理関連の仕事をしている哲学者。非常勤講師として哲学を講義したことはあるが、基本は「自由な哲学者」である。
もうひとりのハルトムート・ゲールケンは、フリートレンダー/ミュノーナの写真等も含む全作品の版権を持っている。サン・ラー関連のコレクターでもあり、『オムニヴァース・サン・ラー』というサン・ラー全レコードの目録を収録した著書をものしている。また、「国際サン・ラー・コンベンション」主宰、カイロ・ジャズバンドを結成、カイロ・フリー・ジャズアンサンブル主宰、グループ・ニルを創設、「インド・アフガニスタン・ヨーロッパ音楽週間」を1967年から毎年カブールで企画している。
作家、作曲家、音楽家、映画監督、演技芸術家、俳優、木こり、椎茸栽培者、マルハナバチ飼育者、菌類学者、文書保管人、展示会主催者、表現主義及びダダ文学周辺の多数の作品の編集者、云々。
ミュノーナもすごいが、ゲールケンにも興味がわく。
また、フリートレンダーに大きな影響を与えたカント派の哲学者エルンスト・マルクスについても。
http://www.luebben-web.de/marcus/marc-bio.htm
以下、目次。
はじめに/凡例
訳者序文 (中村博雄)
ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナと日本 (ハルトムート・ゲールケン)
フリートレンダー/ミュノーナの鏡に映る日本 (デートレフ・ティール)
第 1 部 21 世紀に蘇るザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ
1. ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナの生涯と作品
《ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ年譜》
2. 全集編者紹介
(1) ハルトムート・ゲールケン
(2) デートレフ・ティール
3. 全集編集の経過および各巻の内容概説
(1) 全集編集の経緯 ―― きわめて異例な刊行プロジェクト ――
(2) 既刊の巻の概要
(3) 未刊の巻の概要
(4) 今後の展望
4. 翻訳作品について
政治論関係小品選
(1) 自我とその目標 (1933年)
(2) ある5人の共和主義者の会話を立ち聞きして (1933年?)
(3) 道徳と政治 (1934年)
(4) 平和 (とにかく一般論として) (1935年/1947年)
(5) 政治家としてのカント (1937年/1940年)
書簡選
(1) マルチン・ブーバー宛 (1908年8月2日付)
(2) ロマン・ローラン宛 (1934年12月26日付)
(3) フリッツ・ヴォルフ宛 (1935年8月13日付)
(4) ハイレ・セラシエ皇帝宛 (1938年5月15日付)
(5) アンドレ・ジード宛 (1940年8月7日付)
第 2 部 ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ作品翻訳
1. 政治論関係小品選
(1) 自我とその目標
(2) ある5人の共和主義者の会話を立ち聞きして
(3) 道徳と政治
(4) 平和 (とにかく一般論として)
(5) 政治家としてのカント
2. 書簡選
(1) マルチン・ブーバー宛
(2) ロマン・ローラン宛
(3) フリッツ・ヴォルフ宛
(4) ハイレ・セラシエ皇帝宛
(5) アンドレ・ジード宛
3. 断片 36 篇 (1934年~1945年)
フリートレンダー/ミュノーナ自身による簡単な自己紹介 (1)
極性論の根本的特徴――自我-太陽中心 (内面の太陽) の機能について (2)~(14)
カントとの関連 (15)~(17)
宗教に対する姿勢 (18)~(21)
和のある人間生活への道――法治国家、 永遠平和、 世界共和国 (22)~(31)
真の人間の道を歩み続けた人、 フリートレンダー/ミュノーナ (32)~(36)
4. ソネット 1 篇
人名索引/著作索引/雑誌名・新聞名索引/事項索引
日本語文献リスト/おわりに
編者写真・プロフィール
コペルニクスは、惑星系の真ん中に客観的中心を発見しました。一方、カントは、いわば人生系の中心に主観的中心を発見したのです。カントは、自我-太陽中心、本来の人間、人間-自-体を発見しました。
ドイツで全35巻のフリートレンダー/ミュノーナ全集を企画した、全集編集者による、フリートレンダー/ミュノーナの紹介、全集の紹介と、政治理論に関する作品を中心にいくつか翻訳したものを載せた1冊。つまりは、全集の宣伝パンフレットの豪華なもの、ととらえてもほぼ間違いはない。と、いうのも、ここで翻訳されている政治理論の作品は、フリートレンダー/ミュノーナのほんの一面でしかなく、今まで読んだ『スフィンクス・ケーキ』『子どものためのカント』の面白みとはまた違う味わいがあったからだ。
しかし、この全集編者が、一筋縄でいかない、いかにもミュノーナ全集出そうとしそうな人物で、面白い。
デートレフ・ティールは、コンピュータ管理関連の仕事をしている哲学者。非常勤講師として哲学を講義したことはあるが、基本は「自由な哲学者」である。
もうひとりのハルトムート・ゲールケンは、フリートレンダー/ミュノーナの写真等も含む全作品の版権を持っている。サン・ラー関連のコレクターでもあり、『オムニヴァース・サン・ラー』というサン・ラー全レコードの目録を収録した著書をものしている。また、「国際サン・ラー・コンベンション」主宰、カイロ・ジャズバンドを結成、カイロ・フリー・ジャズアンサンブル主宰、グループ・ニルを創設、「インド・アフガニスタン・ヨーロッパ音楽週間」を1967年から毎年カブールで企画している。
作家、作曲家、音楽家、映画監督、演技芸術家、俳優、木こり、椎茸栽培者、マルハナバチ飼育者、菌類学者、文書保管人、展示会主催者、表現主義及びダダ文学周辺の多数の作品の編集者、云々。
ミュノーナもすごいが、ゲールケンにも興味がわく。
また、フリートレンダーに大きな影響を与えたカント派の哲学者エルンスト・マルクスについても。
http://www.luebben-web.de/marcus/marc-bio.htm
以下、目次。
はじめに/凡例
訳者序文 (中村博雄)
ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナと日本 (ハルトムート・ゲールケン)
フリートレンダー/ミュノーナの鏡に映る日本 (デートレフ・ティール)
第 1 部 21 世紀に蘇るザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ
1. ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナの生涯と作品
《ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ年譜》
2. 全集編者紹介
(1) ハルトムート・ゲールケン
(2) デートレフ・ティール
3. 全集編集の経過および各巻の内容概説
(1) 全集編集の経緯 ―― きわめて異例な刊行プロジェクト ――
(2) 既刊の巻の概要
(3) 未刊の巻の概要
(4) 今後の展望
4. 翻訳作品について
政治論関係小品選
(1) 自我とその目標 (1933年)
(2) ある5人の共和主義者の会話を立ち聞きして (1933年?)
(3) 道徳と政治 (1934年)
(4) 平和 (とにかく一般論として) (1935年/1947年)
(5) 政治家としてのカント (1937年/1940年)
書簡選
(1) マルチン・ブーバー宛 (1908年8月2日付)
(2) ロマン・ローラン宛 (1934年12月26日付)
(3) フリッツ・ヴォルフ宛 (1935年8月13日付)
(4) ハイレ・セラシエ皇帝宛 (1938年5月15日付)
(5) アンドレ・ジード宛 (1940年8月7日付)
第 2 部 ザーロモ・フリートレンダー/ミュノーナ作品翻訳
1. 政治論関係小品選
(1) 自我とその目標
(2) ある5人の共和主義者の会話を立ち聞きして
(3) 道徳と政治
(4) 平和 (とにかく一般論として)
(5) 政治家としてのカント
2. 書簡選
(1) マルチン・ブーバー宛
(2) ロマン・ローラン宛
(3) フリッツ・ヴォルフ宛
(4) ハイレ・セラシエ皇帝宛
(5) アンドレ・ジード宛
3. 断片 36 篇 (1934年~1945年)
フリートレンダー/ミュノーナ自身による簡単な自己紹介 (1)
極性論の根本的特徴――自我-太陽中心 (内面の太陽) の機能について (2)~(14)
カントとの関連 (15)~(17)
宗教に対する姿勢 (18)~(21)
和のある人間生活への道――法治国家、 永遠平和、 世界共和国 (22)~(31)
真の人間の道を歩み続けた人、 フリートレンダー/ミュノーナ (32)~(36)
4. ソネット 1 篇
人名索引/著作索引/雑誌名・新聞名索引/事項索引
日本語文献リスト/おわりに
編者写真・プロフィール
『ピエール・ルヴェルディ詩集』
2012年9月11日 読書 コメント (2)
佐々木洋翻訳による『ピエール・ルヴェルディ詩集』を読んだ。
編年順にセレクトされた詩が集められている。
ピエール・ルヴェルディというと、つい先日読んだ『ランプの営み』でトリスタン・ツァラが絶賛していた詩人である。一般には、ココ・シャネルの恋人として有名だろう。
以下、目次
『散文詩集』
詩人たち
旅人とその影
満天の星
前線
行列
『楕円形の天窓』
あの当時…
春の欠落部分
静止した現実
夜の労働者たち
もう眠れない…
やがて
『屋根のスレート』
それぞれのスレートの上で…
宿屋
文字盤
ランプシェード
道
出発
雲の切れ間
鐘の音
奇跡
先端
秘密
獣
翼
遊牧民
正面
十字路
偽の門または肖像画
忍耐
想い出
蒼い棒
『描かれた星たち』
内的な運動
暴動
『縊り縄』
曇り空
乾いた舌
『大自然』
この想い出
私はすべてに執着していた
『はね返るボール』
閉ざされた畑
終わった男
星々の通りの果てで
時は過ぎ去る
苦悩
この世の者でないとき
炎
触れられない現実
海の刻
港
『風の泉』
曲がりくねった道
言葉が降りる
眺め
むこうへ
金の角
何という変わり方
時計の前に
つま先立って
果てのない旅
ゆれ動く風景
またしても愛
旅
『白い石』
単調な岸辺
思い出
黒い舟
真相
いや何も
あがく
『屑鉄』
曲がりくねった心
愛
X
待機
心臓の鼓動
『満杯』
虹
一滴ずつ
『死者たちの歌』
失われた部分
火も炎もなく
二重鍵をかけて
鉄の健康
過度に
垂直に
ほろ酔い加減の頭
鉛の重荷
『緑の森』
生身の体
そして今は
『ドライドッグ』
断腸
外で
こうなってくると、ピエール・ルヴェルディの未訳の作品も読んでみたくなってきた。翻訳を待とう。いつまで?
編年順にセレクトされた詩が集められている。
ピエール・ルヴェルディというと、つい先日読んだ『ランプの営み』でトリスタン・ツァラが絶賛していた詩人である。一般には、ココ・シャネルの恋人として有名だろう。
以下、目次
『散文詩集』
詩人たち
旅人とその影
満天の星
前線
行列
『楕円形の天窓』
あの当時…
春の欠落部分
静止した現実
夜の労働者たち
もう眠れない…
やがて
『屋根のスレート』
それぞれのスレートの上で…
宿屋
文字盤
ランプシェード
道
出発
雲の切れ間
鐘の音
奇跡
先端
秘密
獣
翼
遊牧民
正面
十字路
偽の門または肖像画
忍耐
想い出
蒼い棒
『描かれた星たち』
内的な運動
暴動
『縊り縄』
曇り空
乾いた舌
『大自然』
この想い出
私はすべてに執着していた
『はね返るボール』
閉ざされた畑
終わった男
星々の通りの果てで
時は過ぎ去る
苦悩
この世の者でないとき
炎
触れられない現実
海の刻
港
『風の泉』
曲がりくねった道
言葉が降りる
眺め
むこうへ
金の角
何という変わり方
時計の前に
つま先立って
果てのない旅
ゆれ動く風景
またしても愛
旅
『白い石』
単調な岸辺
思い出
黒い舟
真相
いや何も
あがく
『屑鉄』
曲がりくねった心
愛
X
待機
心臓の鼓動
『満杯』
虹
一滴ずつ
『死者たちの歌』
失われた部分
火も炎もなく
二重鍵をかけて
鉄の健康
過度に
垂直に
ほろ酔い加減の頭
鉛の重荷
『緑の森』
生身の体
そして今は
『ドライドッグ』
断腸
外で
こうなってくると、ピエール・ルヴェルディの未訳の作品も読んでみたくなってきた。翻訳を待とう。いつまで?
ジャン=リュック・ナンシーとフェデリコ・フェラーリの共著による『作者の図像学』を読んだ。
何人かの小説家の肖像を紹介し、解説するように依頼されたことをきっかけにして生まれた本。第二部がその解説部分にあたり、第一部では、「それだけじゃダメだ!」とどうしても言っておきたかった論考を付加した構成。
以下、目次。
第二部の各章のあとに、とりあげられた作家の名前を付け加えておいた。
序文
第一部 作者自身の肖像
第二部 十四の肖像
作者の幽霊(バルザック、ランドルフィ)
写真、シャク蛾 (ジュナ・バーンズ)
幼年期 (トーマス・ベルンハルト)
「“言葉”の深い統一」 (ホルヘ・ルイス・ボルヘス)
いらだつエクリチュール (ギュスタヴ・フローベール)
移行 (カルロ・エミリオ・ガッダとピエル・パオロ・パゾリーニ)
書斎の中の仮面 (アンドレ・ジッド)
不安定な均衡 (ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ)
銘=登録なきエクリチュール (川端康成)
ジャンルのパロディ (アレッサンドロ・マンツォーニ)
人生と小説 (ドラ・マウロ)
文を見る (マルセル・プルースト)
女性の眼差し (ジョルジュ・サンド、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、インゲボルグ・バッハマン)
ひじ掛け椅子の中で (ヴァージニア・ウルフ)
川端康成の写真は、書をしたためているところが写っていて、作者たちは、漢字、書道といったものと、エクリチュールについて考察している。
これってつまり、日本においてエクリチュールを考えるときは、フレンチセオリーの面々とは扱いが違っていて当然なんじゃないのか、と思えた。
また、序文には、こうある。
なるほど。
めんどくさいな、というのが偽らざる心境。
何人かの小説家の肖像を紹介し、解説するように依頼されたことをきっかけにして生まれた本。第二部がその解説部分にあたり、第一部では、「それだけじゃダメだ!」とどうしても言っておきたかった論考を付加した構成。
以下、目次。
第二部の各章のあとに、とりあげられた作家の名前を付け加えておいた。
序文
第一部 作者自身の肖像
第二部 十四の肖像
作者の幽霊(バルザック、ランドルフィ)
写真、シャク蛾 (ジュナ・バーンズ)
幼年期 (トーマス・ベルンハルト)
「“言葉”の深い統一」 (ホルヘ・ルイス・ボルヘス)
いらだつエクリチュール (ギュスタヴ・フローベール)
移行 (カルロ・エミリオ・ガッダとピエル・パオロ・パゾリーニ)
書斎の中の仮面 (アンドレ・ジッド)
不安定な均衡 (ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ)
銘=登録なきエクリチュール (川端康成)
ジャンルのパロディ (アレッサンドロ・マンツォーニ)
人生と小説 (ドラ・マウロ)
文を見る (マルセル・プルースト)
女性の眼差し (ジョルジュ・サンド、シモーヌ・ド・ボーヴォワール、インゲボルグ・バッハマン)
ひじ掛け椅子の中で (ヴァージニア・ウルフ)
川端康成の写真は、書をしたためているところが写っていて、作者たちは、漢字、書道といったものと、エクリチュールについて考察している。
これってつまり、日本においてエクリチュールを考えるときは、フレンチセオリーの面々とは扱いが違っていて当然なんじゃないのか、と思えた。
また、序文には、こうある。
以下に続く二部の内、第二部が最初に作られたものである。作家の肖像を描き出そうとする一種の試みであるが、その試みが、場合に応じて、あるいはまたさまざまなヴァリエーションによって、前提としたり、認めたり、再認したりしているのは、その肖像が私たちに作者を表わしているということ、あるいはもっと正確に、もっと控え目に言うならば、その肖像が、不可視の作者に帰されるような何かを私たちに見させてくれるということである。
次いでこの実践と絡み合うことになった事柄から-この実践の避けがたく、不当だと見なされたところ、危険だったり、無鉄砲だったところ、いずれにせよ完成不可能だったところから-第一部とこの序文が生じた
なるほど。
めんどくさいな、というのが偽らざる心境。
『ひとはなぜ裁きたがるのか』
2012年9月6日 読書
『ひとはなぜ裁きたがるのか』を読んだ。
以下、目次
刊行によせて 吉岡 洋
ひとはなぜ裁きたがるのか―判定過剰の現在と判定の変容 前川 修
Ⅰ 判定の思想をめぐって―?最後の審判?から生命の判定まで
判定の思想―《最後の審判》から生命の判定まで岡田温司
対論 判定の思想をめぐって 岡田温司×檜垣立哉
対論を終えて 檜垣立哉
Ⅱ 揺れる法廷?―メディア・言葉・心理
裁判員制度における判定―集団意思決定の観点から 藤田政博
「言葉」から見た裁判員制度 堀田秀吾
裁判員制度における判定の論理―メディアの観点から 山口 進
討議 裁判員制度における〈判定〉をめぐって 藤田政博×堀田秀吾×山口 進
Ⅲ スポーツにおける判定をめぐって
近代スポーツの終焉?―判定の変容、裁かれる身体の現在 稲垣正浩
対論 スポーツの危機?/判定の危機? 稲垣正浩×吉岡 洋
Ⅳ 記号論の諸相
杜鵑の聞き方─「リヒト」バッシングの分析 木戸敏郎
1.「リヒト=ビルダー」の日本初演
2.「リヒト」の世界初演
3.ヒステリー現象の仕組み
4.ほととぎすの聞き方
5.叫び声の聞き方
6.神話化現象の波紋
7.戦争絵画批判の読み方
8.「リヒト」批判の読み方
9.「リヒト」の再演
自然的記号と対称性─自然科学におけるシンメトリー 坂本秀人
1.序論
2.対称性と群論に関する予備的な考察
3.科学理論における対称性(同一性と保存則)
4.変換群とコードの理論
5.「自然的記号」に関する簡単な注釈
6.自然科学に含まれる対称性の源泉
7.理論が有効であるということの意味
8.人間の生物(生理)学的特性を「慣習」と呼ぶことについて
9.本論と先行研究との関連について
10.結論
研究論文 ミラン・クンデラの『冗談』とファウスト・モチーフの関係性
―数字と名前のシンボル分析 渡辺 青
1.方法-名前と数のシンボル分析
2.『冗談』における登場人物の名前と数字からのシンボル分析
3.『冗談』における悪魔と冗談のシンボル
結論
研究論文 折口信夫の言語伝承考 岡安裕介
1.古神道の原理
3.言語伝承の図式
「天」の図式
「国」の図式
共同体の連結
4.「みこと」の交換
言葉と媒介者
口頭伝承の特性
5.おわりに
(1の次が3になっているのは、本書のママ)
資料 日本記号学会第三〇回大会について
あとがき 前川 修
執筆者紹介
日本記号学会設立趣意書
以下、目次
刊行によせて 吉岡 洋
ひとはなぜ裁きたがるのか―判定過剰の現在と判定の変容 前川 修
Ⅰ 判定の思想をめぐって―?最後の審判?から生命の判定まで
判定の思想―《最後の審判》から生命の判定まで岡田温司
対論 判定の思想をめぐって 岡田温司×檜垣立哉
対論を終えて 檜垣立哉
Ⅱ 揺れる法廷?―メディア・言葉・心理
裁判員制度における判定―集団意思決定の観点から 藤田政博
「言葉」から見た裁判員制度 堀田秀吾
裁判員制度における判定の論理―メディアの観点から 山口 進
討議 裁判員制度における〈判定〉をめぐって 藤田政博×堀田秀吾×山口 進
Ⅲ スポーツにおける判定をめぐって
近代スポーツの終焉?―判定の変容、裁かれる身体の現在 稲垣正浩
対論 スポーツの危機?/判定の危機? 稲垣正浩×吉岡 洋
Ⅳ 記号論の諸相
杜鵑の聞き方─「リヒト」バッシングの分析 木戸敏郎
1.「リヒト=ビルダー」の日本初演
2.「リヒト」の世界初演
3.ヒステリー現象の仕組み
4.ほととぎすの聞き方
5.叫び声の聞き方
6.神話化現象の波紋
7.戦争絵画批判の読み方
8.「リヒト」批判の読み方
9.「リヒト」の再演
自然的記号と対称性─自然科学におけるシンメトリー 坂本秀人
1.序論
2.対称性と群論に関する予備的な考察
3.科学理論における対称性(同一性と保存則)
4.変換群とコードの理論
5.「自然的記号」に関する簡単な注釈
6.自然科学に含まれる対称性の源泉
7.理論が有効であるということの意味
8.人間の生物(生理)学的特性を「慣習」と呼ぶことについて
9.本論と先行研究との関連について
10.結論
研究論文 ミラン・クンデラの『冗談』とファウスト・モチーフの関係性
―数字と名前のシンボル分析 渡辺 青
1.方法-名前と数のシンボル分析
2.『冗談』における登場人物の名前と数字からのシンボル分析
3.『冗談』における悪魔と冗談のシンボル
結論
研究論文 折口信夫の言語伝承考 岡安裕介
1.古神道の原理
3.言語伝承の図式
「天」の図式
「国」の図式
共同体の連結
4.「みこと」の交換
言葉と媒介者
口頭伝承の特性
5.おわりに
(1の次が3になっているのは、本書のママ)
資料 日本記号学会第三〇回大会について
あとがき 前川 修
執筆者紹介
日本記号学会設立趣意書
『蜂起とともに愛がはじまる』
2012年9月5日 読書
廣瀬純の『蜂起とともに愛がはじまる 思想/政治のための32章』を読んだ。
以下、目次
序にかえて 頭痛―知力解放から蜂起へ
『蟹工船』よりも「バートルビー」を―アントニオーニ/メルヴィル/アガンベン
君は「反革命」を覚えているか?―ヒッチコック/赤瀬川/ヴィルノ
聖のび太、聖プレカリアート―ニコラス・レイ/ゲーテ/藤子・F・不二雄
複数の持続を同時に生きよ!―小津/ベルクソン/デ・ホーホ
遊歩者たちは愛し合えるか―タチ/ベンヤミン/フーリエ
思考に外気を送り続けよ―加藤周一/フーコー/デュラス
諦めて、跳べ(賭けを生きる)―パスカル/ロメール/檜垣立哉
顔のファシズム、背中のデモクラシー―山中貞雄/『アンチ・オイディプス』
時間の力を知覚せよ―ドゥボール/アガンベン/ルノワール
現勢性の悲観主義、潜勢力の楽観主義-ドゥボール/タチ/ブルトン
ワン・プラス・ワン(映像関係)-ゴダール/ダネー/ゴラン
革命零年 未来へ帰還せよ!-ネグリ/ゼメキス/マルクス
真冬の亡霊、コミュニズム-ヴィットリーニ/ユイレ/ストローブ
ホタルについて-パゾリーニ/ディディ=ユベルマン/ゴダール
Is this a game or is it real?-コッポラ/デリダ/バダム
すべてが語る、すべてを語る-プラトン/ランシエール/フロベール
身体が何をなし得るか予め知ることはできない-イーストウッド/デリダ
フローは切断なしには流れない-ゴダール/レヴィナス/パチョーリ
倫理とはカメラ位置の問題だ-レヴィナス/ハイデガー/ベルイマン
我々はみな影丸である-サパティスタ運動/大島渚/白土三平
蜂起とともに愛がはじまる-エサ=デ=ケイロス/オリヴェイラ/ペソア
理念をもって生きること-年金改革反対運動/バディウ
印象の自由-ゴダール/ボッティチェッリ
死を恐れず、技芸を生きよ-シュレーター/カミュ/フーコー
消え去っていくパリ-北アフリカ民衆蜂起/バリバール
風評被害も原発事故の内部にある-デリダ/原発事故
増殖するタハリール広場-アラブの春からスペインの春へ
演出は映像を労働から解放する-青山真治/ドゥルーズ
反原発--原発を反転させる-原発事故/シモンドン
地理と疲労--海賊か警察か-フーコー/網野善彦
原発と蜂起
以下、目次
序にかえて 頭痛―知力解放から蜂起へ
『蟹工船』よりも「バートルビー」を―アントニオーニ/メルヴィル/アガンベン
君は「反革命」を覚えているか?―ヒッチコック/赤瀬川/ヴィルノ
聖のび太、聖プレカリアート―ニコラス・レイ/ゲーテ/藤子・F・不二雄
複数の持続を同時に生きよ!―小津/ベルクソン/デ・ホーホ
遊歩者たちは愛し合えるか―タチ/ベンヤミン/フーリエ
思考に外気を送り続けよ―加藤周一/フーコー/デュラス
諦めて、跳べ(賭けを生きる)―パスカル/ロメール/檜垣立哉
顔のファシズム、背中のデモクラシー―山中貞雄/『アンチ・オイディプス』
時間の力を知覚せよ―ドゥボール/アガンベン/ルノワール
現勢性の悲観主義、潜勢力の楽観主義-ドゥボール/タチ/ブルトン
ワン・プラス・ワン(映像関係)-ゴダール/ダネー/ゴラン
革命零年 未来へ帰還せよ!-ネグリ/ゼメキス/マルクス
真冬の亡霊、コミュニズム-ヴィットリーニ/ユイレ/ストローブ
ホタルについて-パゾリーニ/ディディ=ユベルマン/ゴダール
Is this a game or is it real?-コッポラ/デリダ/バダム
すべてが語る、すべてを語る-プラトン/ランシエール/フロベール
身体が何をなし得るか予め知ることはできない-イーストウッド/デリダ
フローは切断なしには流れない-ゴダール/レヴィナス/パチョーリ
倫理とはカメラ位置の問題だ-レヴィナス/ハイデガー/ベルイマン
我々はみな影丸である-サパティスタ運動/大島渚/白土三平
蜂起とともに愛がはじまる-エサ=デ=ケイロス/オリヴェイラ/ペソア
理念をもって生きること-年金改革反対運動/バディウ
印象の自由-ゴダール/ボッティチェッリ
死を恐れず、技芸を生きよ-シュレーター/カミュ/フーコー
消え去っていくパリ-北アフリカ民衆蜂起/バリバール
風評被害も原発事故の内部にある-デリダ/原発事故
増殖するタハリール広場-アラブの春からスペインの春へ
演出は映像を労働から解放する-青山真治/ドゥルーズ
反原発--原発を反転させる-原発事故/シモンドン
地理と疲労--海賊か警察か-フーコー/網野善彦
原発と蜂起
坂出達典の『ビターズ2滴半~村上三郎はかく語りき』を読んだ。
以下、目次
Ⅰ ビターズ2滴半
1 バー・メタモルフォーゼ
1992年、西宮北口/あなたはホモですか?
2 ホモ・セクシャル、通過、A感覚
A感覚とV感覚/稲垣足穂の話/三角形の月/ダンディズムについて/ランボーの写真
3 悪人 背徳
ワルの顔/精神の自由
4 世界の見方
破れた紙と天井の椅子/借景
5 パフォーマンスあるいは奇行
ビール瓶事件/紙ナプキンの作品/溶けたチーズ事件/無目的な行為
6 エエのん決まってる
嫌いという意識の真実性/車椅子の少年
7 自分にかまけなさい
子どもの精神/衝動を解放する
8 DADA、無意味であること
シュールレアリズムとダダ/ダダ以外に良いものはない/無心であること
9 人間・村上三郎
金木義男氏のこと/客のいない演奏/お椀の中身/人間・村上三郎事件/日本酒を注文する
10 時間について
きのふの空のありどころ/存在と時間/拍子木を打つ男/時間は縦に流れている
11 通過-出口
意味と無意味/紙破り/その時を生き抜く
Ⅱ 過ぎるにまかせた10年間に-
Ⅲ 村上三郎とわたし
(村上知彦/堀尾貞治/山崎つる子/松谷武判/浮田要三/堀尾昭子/元永定正/上前智祐/山本淳夫/山下克彦/浅利美織/窪田 順/和田幸三/遊上陽子/大野良平/水垣 尚/永田 収/大西昇子/笹埜能史)
付録:図版 村上三郎略年譜
以下、目次
Ⅰ ビターズ2滴半
1 バー・メタモルフォーゼ
1992年、西宮北口/あなたはホモですか?
2 ホモ・セクシャル、通過、A感覚
A感覚とV感覚/稲垣足穂の話/三角形の月/ダンディズムについて/ランボーの写真
3 悪人 背徳
ワルの顔/精神の自由
4 世界の見方
破れた紙と天井の椅子/借景
5 パフォーマンスあるいは奇行
ビール瓶事件/紙ナプキンの作品/溶けたチーズ事件/無目的な行為
6 エエのん決まってる
嫌いという意識の真実性/車椅子の少年
7 自分にかまけなさい
子どもの精神/衝動を解放する
8 DADA、無意味であること
シュールレアリズムとダダ/ダダ以外に良いものはない/無心であること
9 人間・村上三郎
金木義男氏のこと/客のいない演奏/お椀の中身/人間・村上三郎事件/日本酒を注文する
10 時間について
きのふの空のありどころ/存在と時間/拍子木を打つ男/時間は縦に流れている
11 通過-出口
意味と無意味/紙破り/その時を生き抜く
Ⅱ 過ぎるにまかせた10年間に-
Ⅲ 村上三郎とわたし
(村上知彦/堀尾貞治/山崎つる子/松谷武判/浮田要三/堀尾昭子/元永定正/上前智祐/山本淳夫/山下克彦/浅利美織/窪田 順/和田幸三/遊上陽子/大野良平/水垣 尚/永田 収/大西昇子/笹埜能史)
付録:図版 村上三郎略年譜
トリスタン・ツァラの『ランプの営み』を読んだ。
以下、目次。
芸術ノート
黒人芸術ノート
芸術ノート――H・アルプ
ギョーム・アポリネール『虐殺された詩人』『ティレジアスの乳房』
ピエール・ルヴェルディ『タランの盗人』
ピエール・アルベール=ビロ
黒人詩ノート
ギョーム・アポリネールの死
R・ヒュルゼンベック『幻想的祈り』
詩について
ピエール・ルヴェルディ『屋根のスレート瓦』『迷彩服の騎手』
フランシス・ピカビア『葬儀社の運動選手』『精神的秣の桶』
フランシス・ピカビア『言語なしの思考』
ジャック・リヴィエールへの公開状
芸術と狩猟
ダダの諺
諧謔の破産――あるアンケートへの回答
わたしはオランピアで『しぼんでいく男』を観た
ロートレアモン伯爵あるいは叫びについて
逆さまの写真――マン・レイ
あるアンケートへの回答
ダダについての講演
90年前のダダの時代は、現代と似通っているのか、はたまた、正反対の事態に陥ってしまったのか。現代の日本にとってこそダダは衝撃をもちうるのか、それとも、ダダは権力によって取り込まれ済みなのか。
何とでも解釈のしようがあるところが歯がゆいのだが、そういう時代だからこそ、裏ダダの暗躍する機運にある、と僕は考えている。裏ダダって今とっさに思いついた言葉だけど。
以下、目次。
芸術ノート
黒人芸術ノート
芸術ノート――H・アルプ
ギョーム・アポリネール『虐殺された詩人』『ティレジアスの乳房』
ピエール・ルヴェルディ『タランの盗人』
ピエール・アルベール=ビロ
黒人詩ノート
ギョーム・アポリネールの死
R・ヒュルゼンベック『幻想的祈り』
詩について
ピエール・ルヴェルディ『屋根のスレート瓦』『迷彩服の騎手』
フランシス・ピカビア『葬儀社の運動選手』『精神的秣の桶』
フランシス・ピカビア『言語なしの思考』
ジャック・リヴィエールへの公開状
芸術と狩猟
ダダの諺
諧謔の破産――あるアンケートへの回答
わたしはオランピアで『しぼんでいく男』を観た
ロートレアモン伯爵あるいは叫びについて
逆さまの写真――マン・レイ
あるアンケートへの回答
ダダについての講演
ランボー+ロートレアモン+ジャリ、これがフランス芸術のもっとも純粋かつ複合的な表現だといえば十分ではあるまいか?
ダダはニュアンスを廃棄した。ニュアンスは言葉の中にはない。少数の萎縮症患者の詰めすぎ脳細胞の中にあるのだ。
90年前のダダの時代は、現代と似通っているのか、はたまた、正反対の事態に陥ってしまったのか。現代の日本にとってこそダダは衝撃をもちうるのか、それとも、ダダは権力によって取り込まれ済みなのか。
何とでも解釈のしようがあるところが歯がゆいのだが、そういう時代だからこそ、裏ダダの暗躍する機運にある、と僕は考えている。裏ダダって今とっさに思いついた言葉だけど。
『無限、宇宙および諸世界について』
2012年8月8日 読書
ジョルダーノ・ブルーノの『無限、宇宙および諸世界について』を読んだ。
巻頭、エルピーノとフィロテオによる印象的なやりとりではじまる。本書では、フィロテオがブルーノの説をとなえる主人公である。
例によって序文書簡に目次がわりの全体見取り図が詳細に記されているが、それを書き写すのはたいへん(20ページくらいある!)なので、簡単に言うと、こうなる。
第一対話では宇宙の無限性が説かれる。
第二対話では、エルピーノによって引用されるアリストテレスの所論にフィロテオが反論でこたえる。
序文書簡中に、こんな文章がある。
手厳しいお言葉!
第三対話では天体について語られる。
第四対話は、無限についての再説。
第五対話は、アルベルティーノ登場で、「世界が複数かつ多様であるという主張にたいする反論のすべてが含まれる」12の問題をぶつける。これがクライマックス!
アルベルティーノは、ついに説得されて、ブルーノがこの本で言わんとするところをまとめて言ってくれる。まずは、ブルーノの説に対する反対意見についての露はらい。
と、自らを鼓舞し、自画自讃した後、こうある。
引用中にある「第五元素」というのは、地、水、火、空気のいわゆる四大元素以外のものとして考えられた元素のことで、アリストテレス(エーテル)やキケロ(名づけられぬもの)に記述がある。
以上で、おおよそ、本書で何が書かれているのかはわかるが、面白くてひっかかる箇所がやはり別にいくつかあった。
第三対話のなかに、序文書簡のまとめで言えば、次のようなことが取り上げられた箇所がある。
ここだけでも興味があるってものだが、簡単に言えば、結論は、「逃げ出せ」ということなのである。
また、よく水を吸い取るスポンジを入れた容器に水を入れたら、からっぽの容器に水を入れるよりも大量の水を入れることが可能、というようなパラドックスや、第五対話でアルベルティーノが対決に持ち出す「12の反論」がよく数えると13あり、しかも序文書簡では11番目を説明して終わらせていることも面白い。対話中では、アルベルティーノは「第7に」と反論を述べたあと、その次も「第7に」と違う反論を言っている、まるで「時うどん」のような数字の数え間違いがなされているのだ。実際には13ある反論にひとつひとつ答えていきながら、フィロテオは最終的に最後の反論を「12番目」として終わらせるイリュージョンも見ものだ。
巻頭、エルピーノとフィロテオによる印象的なやりとりではじまる。本書では、フィロテオがブルーノの説をとなえる主人公である。
エルピーノ 宇宙が無限だなどということがどうしてありえましょう?
フィロテオ 宇宙が有限だなどということがどうしてありえましょう?
エルピーノ この無限が証明されると思うのですか?
フィロテオ この有限が証明されると思うのですか?
エルピーノ どのような拡がりなのだろう?
フィロテオ どのような縁に囲まれているのだろう?
例によって序文書簡に目次がわりの全体見取り図が詳細に記されているが、それを書き写すのはたいへん(20ページくらいある!)なので、簡単に言うと、こうなる。
第一対話では宇宙の無限性が説かれる。
第二対話では、エルピーノによって引用されるアリストテレスの所論にフィロテオが反論でこたえる。
序文書簡中に、こんな文章がある。
かくして、世界を無限とする人々に反対して、世界の中心ないし周辺を想定し、有限者や無限者の中心を地球におこうとするアリストテレスの議論が、空しいものであることが明らかになります。結局、『天体論』の第一巻や『自然学』第三巻に、世界の無限性を否定しようとしてこの哲学者が論じている言葉は、舌足らずで、何の意味もないものなのです。
手厳しいお言葉!
第三対話では天体について語られる。
第四対話は、無限についての再説。
第五対話は、アルベルティーノ登場で、「世界が複数かつ多様であるという主張にたいする反論のすべてが含まれる」12の問題をぶつける。これがクライマックス!
アルベルティーノは、ついに説得されて、ブルーノがこの本で言わんとするところをまとめて言ってくれる。まずは、ブルーノの説に対する反対意見についての露はらい。
フィロテオよ。大衆の声も、俗衆の憤慨も、愚か者の蔭口や物識りの嘲りも、気狂いの愚行や低脳の頑固も、嘘つきの情報、悪意の悪口、嫉妬からでた中傷も、君の高貴な姿を私に見誤らせることはできぬし、君の言葉を私から遠ざけることもできないでしょう。忍耐したまえ、わがフィロテオ君、忍耐したまえ。頑迷無知の者たちが厳めしげに集って、さまざまに奸計や作為をめぐらし、君のすぐれた計画と高尚な仕事を脅かして台無しにしようとしても、そのために勇気を粗相させたり尻込みしたりしてはいけませんよ。いつかは皆も私と同じように理解することを確信したまえ。
と、自らを鼓舞し、自画自讃した後、こうある。
君は、天とは真実いかなるものであるかを知らせるために、説きつづけたまえ。天とは実は遊星や星のすべてなのだと。無数に存在する諸世界は一つ一つがどのように区別されているのか。一つの無限空間が存在することは、不可能などころか、いかに必然のことであるか。いかにこれらの無限なる結果は、無限なる原因にふさわしいものであるか。万物の真の実体、質料、活動、動力とはいかなるものであるのか。あらゆる感覚されうる合成物は、どのようにして同じ原理、元素からつくられるのか。無限なる宇宙を認めることに確信をもたせてくれたまえ。元素と天界を内外に限る凸球面、凹球面を打ち砕きたまえ。輸送軌道とか天蓋に固着された星とかを笑いものにしてやりたまえ。活発な議論をわめき立て振り廻して、文盲の俗衆が信じこんでいるあの第一動者と最後の凸球面の堅い壁を、壊して取り払ってしまえ。この地球が真の唯一の中心だという考えを崩してやりたまえ。第五元素という無知な信仰を捨てさせてしまえ。この我々の星、世界も、我々の目に入るあの沢山の星、世界も、同じものからできているいのだということを知らせてくれたまえ。巨大で広大な数限りない諸世界のなかで、どの一つをとっても、他のより小さな無数の世界と、同じ秩序で結ばれていることを、繰り返し教えてくれたまえ。天の外にあるという原動力を天をかこみ閉している壁と一緒に抹消してしまえ。扉を開いて、この星もあの星も相異のないことを見せてやりたまえ。エーテルのなかで、この世界同様、他の諸世界も自立自存していることを示してくれ。万物の運動はその内にすむ霊魂から生ずることを明らかにしてくれ
引用中にある「第五元素」というのは、地、水、火、空気のいわゆる四大元素以外のものとして考えられた元素のことで、アリストテレス(エーテル)やキケロ(名づけられぬもの)に記述がある。
以上で、おおよそ、本書で何が書かれているのかはわかるが、面白くてひっかかる箇所がやはり別にいくつかあった。
第三対話のなかに、序文書簡のまとめで言えば、次のようなことが取り上げられた箇所がある。
強情な狂信者で自分の邪心に気づかぬ者たちが、ふつうどのように議論するものかを見物したのちに、さらにどのようにして議論を打ち切りにするかをはっきりさせている。
ここだけでも興味があるってものだが、簡単に言えば、結論は、「逃げ出せ」ということなのである。
また、よく水を吸い取るスポンジを入れた容器に水を入れたら、からっぽの容器に水を入れるよりも大量の水を入れることが可能、というようなパラドックスや、第五対話でアルベルティーノが対決に持ち出す「12の反論」がよく数えると13あり、しかも序文書簡では11番目を説明して終わらせていることも面白い。対話中では、アルベルティーノは「第7に」と反論を述べたあと、その次も「第7に」と違う反論を言っている、まるで「時うどん」のような数字の数え間違いがなされているのだ。実際には13ある反論にひとつひとつ答えていきながら、フィロテオは最終的に最後の反論を「12番目」として終わらせるイリュージョンも見ものだ。
『パラドクシア・エピデミカ』
2012年8月7日 読書
ロザリー・L・コリーの『パラドクシア・エピデミカ』を読んだ。副題に「ルネサンスにおけるパラドックスの伝統」とある。
序には、次のようにある。
また、本書の構成について、次のように書いている。
以上にように「序」において見取り図が示されている。
「修辞的パラドックス」というのは、無価値なものや、弁護し難いものを弁護してみせるもののことである。
ゴルギアスが、トロイア戦争の因となった美姫ヘレネーを礼讃した文や、
イソクラテスによる、醜男テルシテス讃美や、
シネシウスによる、禿頭礼讃や、
ルキアノスによる、蝿讃美や、
オウィディウスによる、胡桃讃美や、
偽ウェルギリウスによる、羽虫讃美や、
ウルリッヒ・フォン・フッテンの『人で無し(ネモ)』や、
エラスムスの『痴愚神礼讃』や、
オルテンシオ・ランドの『逆説』などがあたる。
以下、目次。
序
序論 パラドックスの諸問題
第1部 修辞と論理のパラドックス
第1章「けちな卑し絵師」―フランソワ・ラブレーとその本
第2章「我が物語を愍れめ」―ロゴスと芸術の永遠性
第3章ジョン・ダンと受肉のパラドックス
第2部 神の存在論のパラドックス
第4章否定神学の中の肯定―無限
第5章否定神学の中の肯定―永遠
第6章『聖堂』の中のロゴス
第3部 存在論的パラドックス―存在と生成
第7章「すべて、存在せぬものばかり」―無問題を解く
第8章賭け―全てか無か
第9章静物画―存在のパラドックス
第10章存在と生成―事物の言語のパラドックス
第11章『神仙女王』に見る存在と生成
第4部 認識のパラドックス
第12章「我れは我れなり」―自己言及の問題
第13章超越知の修辞学
第14章ロバート・バートン『憂鬱の解剖』とパラドックスの構造
1.ルネサンス認識論詩学のパラドックス的伝統
2.ジョン・ダンの周年記念詩と認識論のパラドックス
第15章「狂いし中にもまともな」
第16章「自らの刑執行人」
エピローグ
ロザリー・コリー讃
訳者あとがき
原注
参考文献
索引
各章冒頭には、トマス・ブラウンの『医家の宗教』からの引用が付されている。
それぞれの章で中心的に取り上げられているのは、
第1章 ラブレー
第2章 ペトラルカ
第3章 ジョン・ダン
第4章 トマス・トラハーン
第5章 ジョン・ミルトン
第6章 ジョージ・ハーバート
第7章 シェイクスピア(ソネット)
第8章 ブレーズ・パスカル
第9章 (静物画。ウァニタス)
第10章 (科学)
第11章 エドマンド・スペンサー
第12章 (絵画に描かれる画家の姿から)シェイクスピア、モンテーニュ
第13章 ジョン・デイヴィーズ、ヘレフォードのデイヴィーズ、グレヴィル、ジョン・ダン
第14章 ロバート・バートン
第15章 シェイクスピア(『リア王』)
第16章 シェイクスピア(『ハムレット』)、ジョン・ダン
第14章には、ロバート・バートンの書を「基本中の基本のパラドックス、愚の礼讃である」と評したあとに、いくつかの系譜をあげていて、わかりやすい。
無知の知を讃えたニコラウス・クサーヌス
無知と不確実の遍在を博識の限りを尽くして証明したモンテーニュ
全学問分野の力不足を学識の全力投入で証したハインリッヒ・コルネリウス・アグリッパ
愚行を讃え同時に間接的かつ昏く、人の知を越えた叡智を讃えたエラスムス
その目に世界が愚者で溢れる世界船と映じたゼバスティアン・ブラント
序には、次のようにある。
本書は、パラドックスの伝統を何人かの言語芸術家が一体どういう具合に意識的に利用したかを検討する一方、そうした文学以外のところでのふたつの局面において-ルネサンスの自然科学と、ルネサンス美術の一ジャンルにおいて-パラドクシーがどう機能していたものか、見ようとする。
また、本書の構成について、次のように書いている。
まず一番単純なパラドックス、即ちラブレーが使ったものが典型たる修辞的パラドックスから始め、次に文学の、というか抒情詩が内包する自己言及の根本的パラドックスに転じ、次にペトラルカとシドニーの恋愛詩を繋ぎに、性愛そのもの、そして愛の詩に孕まれる心理学的パラドックスに進もうと工夫してみた。ジョン・ダンの歌う愛のパラドックスはなにも俗なる性愛を歌う作には勿論とどまってはいなかった。その聖愛を言祝ぐ宗教詩を手掛かりに本書は、神をめぐるさまざまな公的パラドックス、無限と永遠といった観念をめぐり、ロゴス観念に含まれる多様なパラドックスを扱う次の段階にと入っていく。そうやって聖なる存在論を論じた後、もっと俗なる存在論に含まれる各種パラドックスに目を転じ、まずは「無」という基本中の基本のパラドックスに付き合ってみる。
この「無」の問題はルネサンス思想中、特に重要なものなので、幾つもの論じ方を示してみた。第7章では道徳的に、第8章では物理と道徳の見地から、そして第9章では美の問題、霊性の問題として、である。
最後のひと塊は人間の知とは何か意識的な検討がなされていたことを扱う章ばかりだ。第12章は自我の文学的表現に孕まれるさまざまな問題を論じるので、第2章を大いに基礎にしている。第13章はダンの周年記念詩篇をテクストに、知ある無知、自己言及、そして否定神学といった主題を論じ、ということはこれら複雑で鳴る詩篇のパラドックスについて新しい見方を提供しもできるはずと願っている。ロバート・バートンの『憂鬱の解剖』を論じる章は『ガルガンチュワとパンタグリュエル』論の章を基礎にしているわけだが、目はそこでの各種自己言及の方に転じ、実際にはこの大作がひとつ丸ごと大きなパラドックスの箱であって、容器としてのこのものをそれぞれが鏡映する小さなパラドックス群を注意深く収めたという構造になっていることを言う。『リア王』のパラドックスについては何を今更屋上屋を架けることもなさそうにも思われようが、まず何故この作かと説明して後、これが修辞的パラドックスの典型作たると同時に道徳的パラドックスとしてもよくでいている点を述べる。最後の章も、鏡映というか、「即合」をみる章になる。即ち自殺、自死についてのパラドックスを、道徳と修辞二面におけるパラドックスとして検討するからである。自殺パラドックスは一方において弁護し難いものの弁護であり、他方、その戦略、その主題においてはそれ自らのパラドキシカルな作用を自らに映しだすからである。
以上にように「序」において見取り図が示されている。
「修辞的パラドックス」というのは、無価値なものや、弁護し難いものを弁護してみせるもののことである。
ゴルギアスが、トロイア戦争の因となった美姫ヘレネーを礼讃した文や、
イソクラテスによる、醜男テルシテス讃美や、
シネシウスによる、禿頭礼讃や、
ルキアノスによる、蝿讃美や、
オウィディウスによる、胡桃讃美や、
偽ウェルギリウスによる、羽虫讃美や、
ウルリッヒ・フォン・フッテンの『人で無し(ネモ)』や、
エラスムスの『痴愚神礼讃』や、
オルテンシオ・ランドの『逆説』などがあたる。
以下、目次。
序
序論 パラドックスの諸問題
第1部 修辞と論理のパラドックス
第1章「けちな卑し絵師」―フランソワ・ラブレーとその本
第2章「我が物語を愍れめ」―ロゴスと芸術の永遠性
第3章ジョン・ダンと受肉のパラドックス
第2部 神の存在論のパラドックス
第4章否定神学の中の肯定―無限
第5章否定神学の中の肯定―永遠
第6章『聖堂』の中のロゴス
第3部 存在論的パラドックス―存在と生成
第7章「すべて、存在せぬものばかり」―無問題を解く
第8章賭け―全てか無か
第9章静物画―存在のパラドックス
第10章存在と生成―事物の言語のパラドックス
第11章『神仙女王』に見る存在と生成
第4部 認識のパラドックス
第12章「我れは我れなり」―自己言及の問題
第13章超越知の修辞学
第14章ロバート・バートン『憂鬱の解剖』とパラドックスの構造
1.ルネサンス認識論詩学のパラドックス的伝統
2.ジョン・ダンの周年記念詩と認識論のパラドックス
第15章「狂いし中にもまともな」
第16章「自らの刑執行人」
エピローグ
ロザリー・コリー讃
訳者あとがき
原注
参考文献
索引
各章冒頭には、トマス・ブラウンの『医家の宗教』からの引用が付されている。
それぞれの章で中心的に取り上げられているのは、
第1章 ラブレー
第2章 ペトラルカ
第3章 ジョン・ダン
第4章 トマス・トラハーン
第5章 ジョン・ミルトン
第6章 ジョージ・ハーバート
第7章 シェイクスピア(ソネット)
第8章 ブレーズ・パスカル
第9章 (静物画。ウァニタス)
第10章 (科学)
第11章 エドマンド・スペンサー
第12章 (絵画に描かれる画家の姿から)シェイクスピア、モンテーニュ
第13章 ジョン・デイヴィーズ、ヘレフォードのデイヴィーズ、グレヴィル、ジョン・ダン
第14章 ロバート・バートン
第15章 シェイクスピア(『リア王』)
第16章 シェイクスピア(『ハムレット』)、ジョン・ダン
第14章には、ロバート・バートンの書を「基本中の基本のパラドックス、愚の礼讃である」と評したあとに、いくつかの系譜をあげていて、わかりやすい。
無知の知を讃えたニコラウス・クサーヌス
無知と不確実の遍在を博識の限りを尽くして証明したモンテーニュ
全学問分野の力不足を学識の全力投入で証したハインリッヒ・コルネリウス・アグリッパ
愚行を讃え同時に間接的かつ昏く、人の知を越えた叡智を讃えたエラスムス
その目に世界が愚者で溢れる世界船と映じたゼバスティアン・ブラント
読んだつもりでいたけど、実際に読んでみると、はじめてだった。
映画で見た部分は上巻の最初の100ページまでに結末以外ほぼおさまっているのにびっくり。
映画で描かれていた、修道僧の堕落と、それにまつわる別のストーリーがあわさっている感じ。
ルイスは十代でこの本を書いたそうだが、解説にもあったように、ルイスは早熟だったが、真に成熟することはなかった、というのがぴったりくる。
今、この『マンク』を読んでも、童貞臭がぷんぷんするライトノベルに思える。
高潔な人間の下卑た面をあらわにする描写は、まるでネットの書き込みみたいで、現代の若い読者にも大いに受け入れられるのではないか、と思った。
映画で見た部分は上巻の最初の100ページまでに結末以外ほぼおさまっているのにびっくり。
映画で描かれていた、修道僧の堕落と、それにまつわる別のストーリーがあわさっている感じ。
ルイスは十代でこの本を書いたそうだが、解説にもあったように、ルイスは早熟だったが、真に成熟することはなかった、というのがぴったりくる。
今、この『マンク』を読んでも、童貞臭がぷんぷんするライトノベルに思える。
高潔な人間の下卑た面をあらわにする描写は、まるでネットの書き込みみたいで、現代の若い読者にも大いに受け入れられるのではないか、と思った。