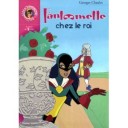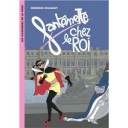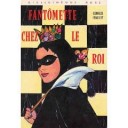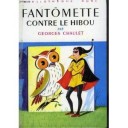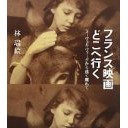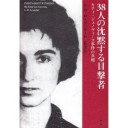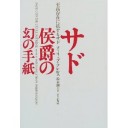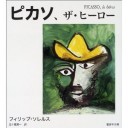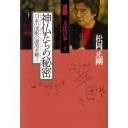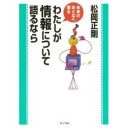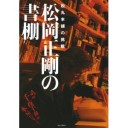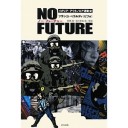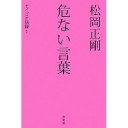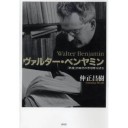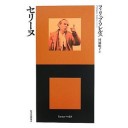『欲望の思考-ルネ・シェレール入門』
2011年9月23日 読書
マキシム・フェルステルの『欲望の思考-ルネ・シェレール入門』を読んだ。
ルネ・シェレールは映画監督エリック・ロメールの実弟で、フーリエの研究者で知られる。僕の知るかぎり、まだ3冊しか翻訳はなく、オッカンガムとの共著『コ-イーレ』とか、もう読みたくてしかたがない。
以下、目次。
序 ある業績が表舞台に現われる
第1章 現象学とコミュニケーション
第2章 狂宴とユートピアの間で-フーリエ新発見
第3章 幼年期を考える
第4章 ドゥルーズとフーコーの陰で
第5章 最も重要な対 ギィー・オッカンガム
第6章 歓待のエロティーク
第7章 再来せしグノーシス
第8章 親縁なる者たち
結語 生きる術としての倒錯
同性愛者シェレールの思想を解説する1冊。たとえば、どういう解説がなされるかというと。
「エピモダン」という用語で、モダンでもポストモダンでもない「モダン-外」を扱う。問題外ではない。モダン外だ。この脱臼のさせ方は、昨日読んだスピノザとか、最近読んでいるトッドと通じるものがある。
「相互滲入」という言葉で、師/生徒、能動的/受動的、友人/恋人、子供/大人のエロティークな歓待のコミュニケーションを説く。この思想は個人的に僕にはしっくりくる。
近年の日本の動きと重なって見えたのは、いわゆる「コーラル事件」にシェレールが巻き込まれるくだり。コーラル事件の詳細は、まだよく調べていないのだが、本書によると、「ある大臣を落選させんがためにでっち上げられた小児性愛スキャンダル」とある。シェレールは、この大臣の友人だったため、無実であるにもかかわらず、暴力的リンチにあった、というのだ。たとえば、社会的に抹殺したい人物がいた場合に、その人物が痴漢を働いたとか、未成年と肉体関係をもったとか、スキャンダルを仕掛ける、というのが日本でも大流行だ。マスコミやネットによって、誤った情報を流されて、それが広まってしまう。そういうスキャンダルにまんまとのせられてしまう一般大衆もどうかと思うが、スピノザが言うように、民衆の心を変えることはできないのである。とにかく、「コーラル事件」について調べてみたい。
本書は、性倒錯とか、そういうことに重点が置かれすぎているような気もするが、(出てくる登場人物はみんな同性愛のフィルターがかかっているように読めてくる)、そこを避けて通ることができないのが、シェレールたるゆえんなのかもしれない。
ルネ・シェレールは映画監督エリック・ロメールの実弟で、フーリエの研究者で知られる。僕の知るかぎり、まだ3冊しか翻訳はなく、オッカンガムとの共著『コ-イーレ』とか、もう読みたくてしかたがない。
以下、目次。
序 ある業績が表舞台に現われる
第1章 現象学とコミュニケーション
第2章 狂宴とユートピアの間で-フーリエ新発見
第3章 幼年期を考える
第4章 ドゥルーズとフーコーの陰で
第5章 最も重要な対 ギィー・オッカンガム
第6章 歓待のエロティーク
第7章 再来せしグノーシス
第8章 親縁なる者たち
結語 生きる術としての倒錯
同性愛者シェレールの思想を解説する1冊。たとえば、どういう解説がなされるかというと。
「エピモダン」という用語で、モダンでもポストモダンでもない「モダン-外」を扱う。問題外ではない。モダン外だ。この脱臼のさせ方は、昨日読んだスピノザとか、最近読んでいるトッドと通じるものがある。
「相互滲入」という言葉で、師/生徒、能動的/受動的、友人/恋人、子供/大人のエロティークな歓待のコミュニケーションを説く。この思想は個人的に僕にはしっくりくる。
近年の日本の動きと重なって見えたのは、いわゆる「コーラル事件」にシェレールが巻き込まれるくだり。コーラル事件の詳細は、まだよく調べていないのだが、本書によると、「ある大臣を落選させんがためにでっち上げられた小児性愛スキャンダル」とある。シェレールは、この大臣の友人だったため、無実であるにもかかわらず、暴力的リンチにあった、というのだ。たとえば、社会的に抹殺したい人物がいた場合に、その人物が痴漢を働いたとか、未成年と肉体関係をもったとか、スキャンダルを仕掛ける、というのが日本でも大流行だ。マスコミやネットによって、誤った情報を流されて、それが広まってしまう。そういうスキャンダルにまんまとのせられてしまう一般大衆もどうかと思うが、スピノザが言うように、民衆の心を変えることはできないのである。とにかく、「コーラル事件」について調べてみたい。
本書は、性倒錯とか、そういうことに重点が置かれすぎているような気もするが、(出てくる登場人物はみんな同性愛のフィルターがかかっているように読めてくる)、そこを避けて通ることができないのが、シェレールたるゆえんなのかもしれない。
『スピノザ―「無神論者」は宗教を肯定できるか』
2011年9月22日 読書
上野修の『スピノザ―「無神論者」は宗教を肯定できるか』を読んだ。
第1章 『神学・政治論』は何をめぐっているのか
オランダ共和国
デカルト主義者たちの不安
不敬虔という問題
第2章 敬虔の文法
解釈の狂気
真理条件から主張可能性条件へ
預言者の語り得たこと
普遍的信仰の教義
神学と哲学の分離―無関係の関係
第3章 文法とその外部
神学から政治論へ
最高権力の「最高」を構成する
敬虔の政治論的な文法
文法の外部
自由の擁護
第4章 『神学・政治論』の孤独
偽装された無神論?
三大詐欺師?
奇蹟と迷信
有徳の無神論者というパラドックス
以前読んだ『スピノザの世界』では『エチカ』を中心に解説されていたが、それを補完するような形で、『神学・政治論』『国家論』を中心に、スピノザと宗教の問題をきわめて明快に解説している。
スピノザは当時(今でも?)無神論者とみなされていた。
しかし、その著作において、あからさまにキリスト教を批判などしていたわけではない。ただ、神や聖書を語り、肯定するやりかたが、どうにも、普通じゃないのである。まるで、異星人が人類と神の関係を素描しているかのような印象がある。きわめて客観的で、論理的なすすめかたで、どこが間違っているか指摘できないのに、何だか違うものを見ているような。
こういう感覚、どこかで最近感じた、と思っていたら、エマニュエル・トッドだ!
エマニュエル・トッドの主張は、「おもいこみ」「こじつけ」の批判をついしたくなる内容なのに、それは人口学、統計的データをもとにしているので、反論する側の偏見を逆に照射することになる。トッドの「とんでもない議論」感は、視点の違い、発想の違いへの驚きを、何と表現していいかわからずに逃げ込んでしまう感想なのだ。スピノザも、論の進め方はいちいち飛躍がなくて、神や聖書をちっとも否定していないのに、「でも、きみ、無神論者だろ」とツッコミたくなる気分になるのである。
あと、スピノザが、ちっとも民衆を啓蒙する気がないところに共感を覚えるものがあった。民衆の頑迷な思考は、哲学者がどれだけ正しい理屈で説いても、変えられるものではないのだ。うむ。これも誤解されそうな議論で、要するに、スピノザは一般大衆の誤解をうみやすいのである。
第1章 『神学・政治論』は何をめぐっているのか
オランダ共和国
デカルト主義者たちの不安
不敬虔という問題
第2章 敬虔の文法
解釈の狂気
真理条件から主張可能性条件へ
預言者の語り得たこと
普遍的信仰の教義
神学と哲学の分離―無関係の関係
第3章 文法とその外部
神学から政治論へ
最高権力の「最高」を構成する
敬虔の政治論的な文法
文法の外部
自由の擁護
第4章 『神学・政治論』の孤独
偽装された無神論?
三大詐欺師?
奇蹟と迷信
有徳の無神論者というパラドックス
以前読んだ『スピノザの世界』では『エチカ』を中心に解説されていたが、それを補完するような形で、『神学・政治論』『国家論』を中心に、スピノザと宗教の問題をきわめて明快に解説している。
スピノザは当時(今でも?)無神論者とみなされていた。
しかし、その著作において、あからさまにキリスト教を批判などしていたわけではない。ただ、神や聖書を語り、肯定するやりかたが、どうにも、普通じゃないのである。まるで、異星人が人類と神の関係を素描しているかのような印象がある。きわめて客観的で、論理的なすすめかたで、どこが間違っているか指摘できないのに、何だか違うものを見ているような。
こういう感覚、どこかで最近感じた、と思っていたら、エマニュエル・トッドだ!
エマニュエル・トッドの主張は、「おもいこみ」「こじつけ」の批判をついしたくなる内容なのに、それは人口学、統計的データをもとにしているので、反論する側の偏見を逆に照射することになる。トッドの「とんでもない議論」感は、視点の違い、発想の違いへの驚きを、何と表現していいかわからずに逃げ込んでしまう感想なのだ。スピノザも、論の進め方はいちいち飛躍がなくて、神や聖書をちっとも否定していないのに、「でも、きみ、無神論者だろ」とツッコミたくなる気分になるのである。
あと、スピノザが、ちっとも民衆を啓蒙する気がないところに共感を覚えるものがあった。民衆の頑迷な思考は、哲学者がどれだけ正しい理屈で説いても、変えられるものではないのだ。うむ。これも誤解されそうな議論で、要するに、スピノザは一般大衆の誤解をうみやすいのである。
『文明の接近-「イスラームVS西洋」の虚構』
2011年9月21日 読書
エマニュエル・トッドとユセフ・クルパージュによる『文明の接近-「イスラームVS西洋」の虚構』を読んだ。
ハンチントンの『文明の衝突』を真っ向から批判した1冊。
人口学の実証データをもとに、展開されるおなじみの理論。
近代化は、識字化、脱キリスト教化、出生率の低下という道筋をたどり、その際に宗教別の各地域の差異を際立たせるが、その後、収斂に向かうとされる。
そうした観点から見ると、イスラーム圏は現在近代性への移行の最中であって、文明の衝突のような事態には至らないのである。イスラームの特殊性は変数としては、識字化、父系制、少数派集団の対抗行動、石油などの地下資源収入などに比べて、ほとんど無視するに足る小ささなのである。
そして言う。欧米のイスラーム恐怖症は、イスラームそのものとは無関係な、西洋自身の問題なのだ、と。(サルトルの「アメリカには黒人問題はない。あるのは白人問題だ」にひきつけた展開)
以下、目次。
日本の読者へ
序 章 文明の衝突か、 普遍的世界史か
第1章 歴史の動きの中におけるイスラーム諸国
識字化と出生率の低下/イスラームにおける 「世界の脱魔術化」 か
第2章 移行期危機
識字化、 出生調節、 革命/イスラーム諸国の移行期危機/イスラーム主義と未来予測/イデオロギー的内容の問題
第3章 アラブ家族と移行期危機
父系と夫方居住/シーア派の相続法/内婚制/内婚制の心理的・イデオロギー的帰結/近代化の衝撃
第4章 非アラブ圏のイスラーム女性 ―東アジアとサハラ以南のアフリカ
マレーシア・インドネシアの妻方居住/サハラ以南アフリカの大衆的一夫多妻制/これまでとは異なる移行期危機となるか?
第5章 イスラーム世界の核心、 アラブ圏
予期せざる、 遅れて始まった移行期 ―識字化と石油収入/マグレブでの移行期の加速化とフランス/シリアの遅れと分断 ―スンニ派とアラウイ派/アラビア半島の異種混合性/レバノンはヨーロッパの国か?/パレスチナ人 ―占領と戦争と出生率
第6章 アラブ圏以外の大中東圏
トルコとイラン/国家の不確かな役割/人口学的移行と国民国家/宗教、 人口動態、 民主主義/パキスタンの人口爆発/人口動態の正常さと政治的脅威/アフガニスタンにも触れておこう/バングラデシュ ―人口過密と出生率の低下
第7章 共産主義以後
識字化の加速/中絶 ―イスラーム的ならざる出生調節/そして幼児死亡率/バルカンにおけるムスリムの多様化
第8章 妻方居住のアジア
正常な移行、 停止す/マレーシア ―イスラーム教よりはナショナリズム
第9章 サハラ以南のアフリカ
出生率の地域格差 ―民族と宗教/ムスリム女子の死亡率の低さ
結 論
〈附〉インタビュー 「平和にとって、アメリカ合衆国はイランより危険である。」
原 注
図表一覧
訳者解説
本書で展開される議論について、それに対する読者の反応を先回りして、著者自身がこう書いている(第6章)
「人口動態とは客観的なものであり、それゆえにわれわれは時として、お決まりの考えや習慣が退けるよう仕向けている現実も、受入れざるを得なくなる」
そして、第5章では、パレスチナを例にあげて、近代化がいやおうなく進行していることを説明する。パレスチナでは、イスラエルの脅威に対抗する手段として、出生率の上昇をもってした。
「ヤセル・アラファトは、彼女たちの腹の中に生物兵器が眠っていたのを発見し、一人が子供を十二人持つことを女性に説き勧めた。二人は自分自身のために、一〇人は闘争のために、というわけである」
たしかに第一次インティファーダの際には出生率は上昇したが、第二次になると、出生率の下落傾向を示したのだ。
あと、日本は、外婚制で、それが当たり前のように思っているけど、世界には内婚制の国や地域もあり、そのメリットはどこにあるんだろう、と個人的に考えていたのだが、本書第3章に、わかりやすく書いてあった。
「ロシアや中国の家族(外婚制)においては、親子関係、夫と妻の関係は、恒常的な心理的暴力の雰囲気に浸っているように見える。近代化の局面に入ると、これらの家族システムは急速に瓦解したが、それはおそらく、住民自身が自分たちの生活様式を加害的なものだと感じ取っていたからなのだ。アラブ家族には、そんなところはこれっぱかりもない。内婚は、大家族システムが誘発する複雑な人間関係のとげとげしさを和らげてくれる。」
ここからが面白い!
「嫁とは、姑に迫害される余所者の女(あらゆる外婚モデルに共通)でも、舅に強姦される余所者の女(ロシア・モデル)でもなく、生まれた時から親族の中にいる、舅姑の姪というステータスを持って結婚生活を始めるのである。
したがって内婚制は、人が想像しがちなところとは逆に、女性にとって保護者的な役割を果たす。父系外婚システムがしばしば引き起こす災厄の一つは、女性嬰児の殺害である。男と男の結合で構築されるシステムの中では、女子には大して価値がない。他の家族集団の再生産を確実にするために家を出るというのが、女子の定めなのだ」
なーるほど!
ハンチントンの『文明の衝突』を真っ向から批判した1冊。
人口学の実証データをもとに、展開されるおなじみの理論。
近代化は、識字化、脱キリスト教化、出生率の低下という道筋をたどり、その際に宗教別の各地域の差異を際立たせるが、その後、収斂に向かうとされる。
そうした観点から見ると、イスラーム圏は現在近代性への移行の最中であって、文明の衝突のような事態には至らないのである。イスラームの特殊性は変数としては、識字化、父系制、少数派集団の対抗行動、石油などの地下資源収入などに比べて、ほとんど無視するに足る小ささなのである。
そして言う。欧米のイスラーム恐怖症は、イスラームそのものとは無関係な、西洋自身の問題なのだ、と。(サルトルの「アメリカには黒人問題はない。あるのは白人問題だ」にひきつけた展開)
以下、目次。
日本の読者へ
序 章 文明の衝突か、 普遍的世界史か
第1章 歴史の動きの中におけるイスラーム諸国
識字化と出生率の低下/イスラームにおける 「世界の脱魔術化」 か
第2章 移行期危機
識字化、 出生調節、 革命/イスラーム諸国の移行期危機/イスラーム主義と未来予測/イデオロギー的内容の問題
第3章 アラブ家族と移行期危機
父系と夫方居住/シーア派の相続法/内婚制/内婚制の心理的・イデオロギー的帰結/近代化の衝撃
第4章 非アラブ圏のイスラーム女性 ―東アジアとサハラ以南のアフリカ
マレーシア・インドネシアの妻方居住/サハラ以南アフリカの大衆的一夫多妻制/これまでとは異なる移行期危機となるか?
第5章 イスラーム世界の核心、 アラブ圏
予期せざる、 遅れて始まった移行期 ―識字化と石油収入/マグレブでの移行期の加速化とフランス/シリアの遅れと分断 ―スンニ派とアラウイ派/アラビア半島の異種混合性/レバノンはヨーロッパの国か?/パレスチナ人 ―占領と戦争と出生率
第6章 アラブ圏以外の大中東圏
トルコとイラン/国家の不確かな役割/人口学的移行と国民国家/宗教、 人口動態、 民主主義/パキスタンの人口爆発/人口動態の正常さと政治的脅威/アフガニスタンにも触れておこう/バングラデシュ ―人口過密と出生率の低下
第7章 共産主義以後
識字化の加速/中絶 ―イスラーム的ならざる出生調節/そして幼児死亡率/バルカンにおけるムスリムの多様化
第8章 妻方居住のアジア
正常な移行、 停止す/マレーシア ―イスラーム教よりはナショナリズム
第9章 サハラ以南のアフリカ
出生率の地域格差 ―民族と宗教/ムスリム女子の死亡率の低さ
結 論
〈附〉インタビュー 「平和にとって、アメリカ合衆国はイランより危険である。」
原 注
図表一覧
訳者解説
本書で展開される議論について、それに対する読者の反応を先回りして、著者自身がこう書いている(第6章)
「人口動態とは客観的なものであり、それゆえにわれわれは時として、お決まりの考えや習慣が退けるよう仕向けている現実も、受入れざるを得なくなる」
そして、第5章では、パレスチナを例にあげて、近代化がいやおうなく進行していることを説明する。パレスチナでは、イスラエルの脅威に対抗する手段として、出生率の上昇をもってした。
「ヤセル・アラファトは、彼女たちの腹の中に生物兵器が眠っていたのを発見し、一人が子供を十二人持つことを女性に説き勧めた。二人は自分自身のために、一〇人は闘争のために、というわけである」
たしかに第一次インティファーダの際には出生率は上昇したが、第二次になると、出生率の下落傾向を示したのだ。
あと、日本は、外婚制で、それが当たり前のように思っているけど、世界には内婚制の国や地域もあり、そのメリットはどこにあるんだろう、と個人的に考えていたのだが、本書第3章に、わかりやすく書いてあった。
「ロシアや中国の家族(外婚制)においては、親子関係、夫と妻の関係は、恒常的な心理的暴力の雰囲気に浸っているように見える。近代化の局面に入ると、これらの家族システムは急速に瓦解したが、それはおそらく、住民自身が自分たちの生活様式を加害的なものだと感じ取っていたからなのだ。アラブ家族には、そんなところはこれっぱかりもない。内婚は、大家族システムが誘発する複雑な人間関係のとげとげしさを和らげてくれる。」
ここからが面白い!
「嫁とは、姑に迫害される余所者の女(あらゆる外婚モデルに共通)でも、舅に強姦される余所者の女(ロシア・モデル)でもなく、生まれた時から親族の中にいる、舅姑の姪というステータスを持って結婚生活を始めるのである。
したがって内婚制は、人が想像しがちなところとは逆に、女性にとって保護者的な役割を果たす。父系外婚システムがしばしば引き起こす災厄の一つは、女性嬰児の殺害である。男と男の結合で構築されるシステムの中では、女子には大して価値がない。他の家族集団の再生産を確実にするために家を出るというのが、女子の定めなのだ」
なーるほど!
『タイムマシンのなぞ』
2011年9月20日 読書
ジョルジュ=ショーレの少女名探偵ファントメット『タイムマシンのなぞ』を読んだ。
作者による「はじめに」の文章は次のとおり。
以下、目次。
第1章 骨とう屋
第2章 貨物自動車
第3章 じょうずな見張り
第4章 フィセル、つぼをさがす
第5章 ゆめのような旅
第6章 二度めの実験
第7章 タイムマシンのトリック
第8章 あやしい小姓
第9章 侯爵夫人フィセル
第10章 パルシィ=パルラの夕べ
第11章 ル=フュレ勝つ
第12章 決闘
第13章 エピローグ
ル=フュレという悪党詐欺師が、「ルイ14世から爵位をもらいたい」と夢を抱いている金持ちをだまそうとする話。タイムマシンで過去にさかのぼり、ルイ14世に会おうとするのだ。
この作品でも、フランス人ならきっと基礎知識のうちのフランス史がちらちら出てきて、興味深い。
たとえば。
とか。
とか。
とか。
とか!
物語は金持ちのドターユ氏の夢をこわさないように気遣う内容で終わっていて、やさしさを感じた。(きちがい扱いはされるけど)
また、詐欺師ル=フュレがまきあげようとした大金を、おバカなフィセルは、「どうせつまらないことに金をつかってしまうに決まっている。自分なら有意義に金を使う」と、買いたいもののリストをあげる。これがまた、超有意義というか、素晴らしい。
「わたし、必要なもののリストを作ったんだ。陶器でできたブルドッグ、中国の帽子、嗅ぎタバコ入れ、パリの北駅の写真、セネガルの旗、馬蹄、すずのパイプかけ、軍艦の作り方が書いてある本、ブラジルのマテ茶をのむための、ほうろうの小さいポット、以上」
このリストは、ほぼ、ボルヘスである。
作者による「はじめに」の文章は次のとおり。
時間の旅行をして、何百年か前、王さまがフランスを治めていた時代にもどれると、みなさんは、思いますか?
ファントメットは、この奇想天外な冒険に足をつっこんだばかりに、たいへんな危険においこまれます。つまりつるぎで決闘ということになってしまいましたから。
さて、読者のみなさんも、仮面の少女とともに、フランスは十七世紀の貴族たちや、国王の宮殿に、信じられないような旅行をすることになるでしょう。
以下、目次。
第1章 骨とう屋
第2章 貨物自動車
第3章 じょうずな見張り
第4章 フィセル、つぼをさがす
第5章 ゆめのような旅
第6章 二度めの実験
第7章 タイムマシンのトリック
第8章 あやしい小姓
第9章 侯爵夫人フィセル
第10章 パルシィ=パルラの夕べ
第11章 ル=フュレ勝つ
第12章 決闘
第13章 エピローグ
ル=フュレという悪党詐欺師が、「ルイ14世から爵位をもらいたい」と夢を抱いている金持ちをだまそうとする話。タイムマシンで過去にさかのぼり、ルイ14世に会おうとするのだ。
この作品でも、フランス人ならきっと基礎知識のうちのフランス史がちらちら出てきて、興味深い。
たとえば。
「さーてと、どんな衣裳にしようかなあ。公爵夫人のかっこうにしよう」
フィセルは髪の毛をかきむしって考えこんでいましたが、やっと考えがまとまったようです。
「公爵夫人なら、なんでもいいってわけにはいかないな。マリー=アントワネット風のかつらをつけた、高貴な公爵夫人がいいわ」
フランソワーズは、首をふりました。
「だめよ。それじゃ、ルイ14世時代のモードってことにならないから」
「ええっ!それじゃ、マリー=アントワネットは、いつの人?」
「ルイ16世の時代」
とか。
フランソワーズは、映画『太陽王ルイ14世』のグラビア写真をたくさんみつけました。フィセルは、モンテスパン侯爵夫人の写真を見て、喜びの声をあげました。
「あらっ!わたしのさがしていた衣裳は、まさしくこれよ。なんてきれいな服!」
フランソワーズは、ぷーっとふきだして、いいました。
「ド=モンテスパン夫人は、公爵夫人ではなくて、侯爵夫人なの」
とか。
「ル=フュレは、ルイ14世が直接サインした親書を、ピエール=ドターユ氏にわたしたっていってたでしょ」
「うん」
「あなた、あのタイムマシンに、なん年って書いてあったかおぼえてる?」
「えーと、1673年」
「そう、ところが1673年に、ルイ14世は、ベルサイユ宮殿にはいなかったの。オランダと戦争してたんですもの」
とか。
「ドターユ氏が、だまされても、わたし、あまりおどろかないわ。1870年に、むかしのえらい人の手紙や原稿をあつめていたシャスルっていう、有名な数学者がいたの。その人ったら、ジャンヌ=ダークの原稿とか、モリエール、シェークスピア、シャルルマーニュ大帝、コロンブスの手紙なんかをうりつけられたんだけど、ぜんぶにせものだったの」
とか!
物語は金持ちのドターユ氏の夢をこわさないように気遣う内容で終わっていて、やさしさを感じた。(きちがい扱いはされるけど)
また、詐欺師ル=フュレがまきあげようとした大金を、おバカなフィセルは、「どうせつまらないことに金をつかってしまうに決まっている。自分なら有意義に金を使う」と、買いたいもののリストをあげる。これがまた、超有意義というか、素晴らしい。
「わたし、必要なもののリストを作ったんだ。陶器でできたブルドッグ、中国の帽子、嗅ぎタバコ入れ、パリの北駅の写真、セネガルの旗、馬蹄、すずのパイプかけ、軍艦の作り方が書いてある本、ブラジルのマテ茶をのむための、ほうろうの小さいポット、以上」
このリストは、ほぼ、ボルヘスである。
『秘密のふくろう団』
2011年9月19日 読書
ジョルジュ=ショーレの少女名探偵ファントメットシリーズ『秘密のふくろう団』を読んだ。
作者による「はじめに」の文章は、次のとおり。
以下、目次。
第1章 三人の少女
第2章 こまった事件
第3章 ショーウィンドウのたる
第4章 探偵クラブ
第5章 夜の冒険
第6章 ピクニック
第7章 ふくろう団
第8章 十時十七分のゾウ
第9章 ふうとう
第10章 ふくろうのつめ
第11章 ふくろうたちの最期
第12章 エピローグ
静かなフランボワジーの町に起こる不愉快な事件たち。
食料品店の車がこわされたり、農家が火事になったり、肉屋の肉に革ひもが入っていたり、上映直前に映画のフィルムが盗まれたり、トラックが落としたドラム缶が電器店のテレビを壊したり、果樹園の木が切り倒されたり。
犯行を声明のようなふくろうマークが残されているところから、ふくろう団の存在があぶりだされた。
フランボワジーに暮らす3人の小学生女子が、探偵クラブを作って、ふくろう団の悪事をあばこうとする。
3人の少女とは、のっぽでおバカノのフィセル、くいしんぼうのブーロット、そして、頭がよくてクラスで何でも一番のスーパー小学生フランソワーズ。
3人が作った探偵団は、「フランボワジー探偵クラブ」(Framboisy Limiers Club)略して「FLIC」
フィセルは、鳥を見たら何でも「ナイチンゲール」だと思っているし、ブーロットは探偵そっちのけで食欲に忠実。また、フランソワーズは、なぜか肝腎のときに、いつもいない。
さて、このフランボワジーの町には、仮面で正体を隠した正義の女性、ファントメットがいた。
FLICが独自でふくろう団を追い詰めようとして、危険なめにあいそうになると、ファントメットが助けてくれる。
事件の謎を追うのはもちろん面白いのだが、少女たちが遊ぶ、また学校で学ぶ描写が楽しい。ところどころに、「チョークが酸にふれると泡が出ます。この泡は何だと思いますか」とか、「500リットルの水がはいる風呂桶に、1時間に1500リットル出る水道の水を入れるとする。しかし、風呂桶の穴から、1時間800リットルの水が流出するとして、この風呂桶を満たすには何時間かかるだろうか」とか、モリエールの『守銭奴』を読んだり、など学校のシーンが、自分の小中学生時代にタイムスリップさせるリアルさを持っている。
ふくろう団は悪事を働くのだが、その首領の正体は、いかにも悪い奴で、花咲かじいさん的な説得力があった。
ジョルジュ=ショーレはこのファントメットのシリーズを1961年から1年に1冊か2冊のペースで50冊以上書いている。(なぜか90年代は書いていないけど、いったんシリーズを打ち切るつもりだったのが、また再開した、ということか?)アニメにもテレビ番組にもなっていて、フランスでは、まあ知らぬ者のないキャラクターなんだろう。僕に語学の素養があれば、バリバリ読みたいところなのになあ。日本での翻訳は、70年代に5冊だけ。しかも、その本も今やなかなか入手しにくい。ファントメット、危機一髪!
本の画像は、海外版。日本の翻訳は、「四月バキュア」ブログのほうに載せる予定。
今日は親戚の三十五日&四十九日だった。
なんだか、あっさりしたものだな、というのが素直な印象だ。
法事といえば一大イベントだと感じていたのは、自分が幼いときのインパクト(ダメージ?)の思い出によるものなのかもしれない。
作者による「はじめに」の文章は、次のとおり。
ふくろうという鳥は、ひるまはおとなしくねむっているけれど、あたりがねしずまった夜になると活動をはじめます。
ところが、ファントメットがやっつけようとしているふくろうは、ふくろうでも鳥ではありません。はるかに危険なものなのです。
まっ赤な血をたたえたうす!列車襲撃計画!
つぎつぎとおこるおそろしい事件-。
みなさんも、ファントメットといっしょに、このなぞめいたふくろうの正体をみやぶってください。
以下、目次。
第1章 三人の少女
第2章 こまった事件
第3章 ショーウィンドウのたる
第4章 探偵クラブ
第5章 夜の冒険
第6章 ピクニック
第7章 ふくろう団
第8章 十時十七分のゾウ
第9章 ふうとう
第10章 ふくろうのつめ
第11章 ふくろうたちの最期
第12章 エピローグ
静かなフランボワジーの町に起こる不愉快な事件たち。
食料品店の車がこわされたり、農家が火事になったり、肉屋の肉に革ひもが入っていたり、上映直前に映画のフィルムが盗まれたり、トラックが落としたドラム缶が電器店のテレビを壊したり、果樹園の木が切り倒されたり。
犯行を声明のようなふくろうマークが残されているところから、ふくろう団の存在があぶりだされた。
フランボワジーに暮らす3人の小学生女子が、探偵クラブを作って、ふくろう団の悪事をあばこうとする。
3人の少女とは、のっぽでおバカノのフィセル、くいしんぼうのブーロット、そして、頭がよくてクラスで何でも一番のスーパー小学生フランソワーズ。
3人が作った探偵団は、「フランボワジー探偵クラブ」(Framboisy Limiers Club)略して「FLIC」
フィセルは、鳥を見たら何でも「ナイチンゲール」だと思っているし、ブーロットは探偵そっちのけで食欲に忠実。また、フランソワーズは、なぜか肝腎のときに、いつもいない。
さて、このフランボワジーの町には、仮面で正体を隠した正義の女性、ファントメットがいた。
FLICが独自でふくろう団を追い詰めようとして、危険なめにあいそうになると、ファントメットが助けてくれる。
事件の謎を追うのはもちろん面白いのだが、少女たちが遊ぶ、また学校で学ぶ描写が楽しい。ところどころに、「チョークが酸にふれると泡が出ます。この泡は何だと思いますか」とか、「500リットルの水がはいる風呂桶に、1時間に1500リットル出る水道の水を入れるとする。しかし、風呂桶の穴から、1時間800リットルの水が流出するとして、この風呂桶を満たすには何時間かかるだろうか」とか、モリエールの『守銭奴』を読んだり、など学校のシーンが、自分の小中学生時代にタイムスリップさせるリアルさを持っている。
ふくろう団は悪事を働くのだが、その首領の正体は、いかにも悪い奴で、花咲かじいさん的な説得力があった。
ジョルジュ=ショーレはこのファントメットのシリーズを1961年から1年に1冊か2冊のペースで50冊以上書いている。(なぜか90年代は書いていないけど、いったんシリーズを打ち切るつもりだったのが、また再開した、ということか?)アニメにもテレビ番組にもなっていて、フランスでは、まあ知らぬ者のないキャラクターなんだろう。僕に語学の素養があれば、バリバリ読みたいところなのになあ。日本での翻訳は、70年代に5冊だけ。しかも、その本も今やなかなか入手しにくい。ファントメット、危機一髪!
本の画像は、海外版。日本の翻訳は、「四月バキュア」ブログのほうに載せる予定。
今日は親戚の三十五日&四十九日だった。
なんだか、あっさりしたものだな、というのが素直な印象だ。
法事といえば一大イベントだと感じていたのは、自分が幼いときのインパクト(ダメージ?)の思い出によるものなのかもしれない。
吉増剛造のエッセイ&対談集『静かなアメリカ』を読んだ。2009年。
内容がぎっしりと充実しているうえに、守備範囲の広さにも驚かされた。
お気に入りのフレーズを何度も反復して使用してくれているおかげで、それぞれの引用句などの滋味も伝わってくるような気がした。
詩にみられるような、読者に覚悟を強いるような文章ではなかったので、読みやすくもあり、謙遜を感じる部分が味わえるのは、違った意味で楽しかった。
以下、目次。
対話 静かなアメリカ (堀内正規とともに)
啄木ローマ字日記の古畳―アイオワにて
ニューヨークで中也の手紙を考えていた
赤馬、静かに(be quiet please)アメリカ
パウル・クレーの赤い火の道(大きく弧を描く坂道。…)―「日記」を読みつゝ二〇〇一年九月十三~二十三日、台湾で
ひとり倒るる―芥川龍之介
東京の詩人は芥川龍之介しかいない
吉本隆明ノート―『日時計』
鶴の言葉―海を掬い尽せ
海を掬い尽せ―高銀氏に
妖精言語ハングルと「春遊び」
南方熊楠の庭
オータ・ショーゴさんが教えてくれた、中也の「飴売爺々と、仲よしになり」は、戦後の「コールタール」そして、おもい、しじま(蹙)のなみの舟だった、…
キーツからベケットへ
石川九楊氏の制作の脇の隠された瞳の巣のようなところから氏の書を見詰めていたことがあった
対話 筆蝕が切り開く宇宙 (石川九楊とともに)
おそらくまだ誰もしたことがないような映画作りの軌跡=奇蹟を、吉田喜重監督は辿っている、
アイルランド、刹那の眼―吉田文憲さんに
対話 世界のみずみずしい凹み、詩の働く場所 (大岡信とともに)
「ごろごろ」という名ノ詩篇を書いた
詩(シ)ノ汐(シオノ)-穴(アナ)
棘が人生の小川をぎっしりと流れている
「光の棘」の感触伝えた人―島尾ミホさん
マヤさんの八月が逝った
萩原朔太郎は、古い泉(出水、…)で、きっと、ある、
対話 ベンヤミンという〈経験〉をめぐって (多木浩二とともに)
デクノボー
四畳半
坂部恵氏の思考の道の傍(かたわら、…)に
鏡花フィルム
「アメリカ文学会」にて。二〇〇八年十二月十三日、慶應義塾大学三田、―。
天上の傷―Nicolaに
声にならない声の刺青『おぱらぱん』
対話 言葉の湯気に耳そばだてて (唐十郎とともに)
ストラスブール紀行―唐十郎さんとの出逢い
ガンジス河デ、横田基地ハ、アッタノデハ、ナカッタノカ、…唐十郎さんに
あとがき
初出紙誌一覧
内容がぎっしりと充実しているうえに、守備範囲の広さにも驚かされた。
お気に入りのフレーズを何度も反復して使用してくれているおかげで、それぞれの引用句などの滋味も伝わってくるような気がした。
詩にみられるような、読者に覚悟を強いるような文章ではなかったので、読みやすくもあり、謙遜を感じる部分が味わえるのは、違った意味で楽しかった。
以下、目次。
対話 静かなアメリカ (堀内正規とともに)
啄木ローマ字日記の古畳―アイオワにて
ニューヨークで中也の手紙を考えていた
赤馬、静かに(be quiet please)アメリカ
パウル・クレーの赤い火の道(大きく弧を描く坂道。…)―「日記」を読みつゝ二〇〇一年九月十三~二十三日、台湾で
ひとり倒るる―芥川龍之介
東京の詩人は芥川龍之介しかいない
吉本隆明ノート―『日時計』
鶴の言葉―海を掬い尽せ
海を掬い尽せ―高銀氏に
妖精言語ハングルと「春遊び」
南方熊楠の庭
オータ・ショーゴさんが教えてくれた、中也の「飴売爺々と、仲よしになり」は、戦後の「コールタール」そして、おもい、しじま(蹙)のなみの舟だった、…
キーツからベケットへ
石川九楊氏の制作の脇の隠された瞳の巣のようなところから氏の書を見詰めていたことがあった
対話 筆蝕が切り開く宇宙 (石川九楊とともに)
おそらくまだ誰もしたことがないような映画作りの軌跡=奇蹟を、吉田喜重監督は辿っている、
アイルランド、刹那の眼―吉田文憲さんに
対話 世界のみずみずしい凹み、詩の働く場所 (大岡信とともに)
「ごろごろ」という名ノ詩篇を書いた
詩(シ)ノ汐(シオノ)-穴(アナ)
棘が人生の小川をぎっしりと流れている
「光の棘」の感触伝えた人―島尾ミホさん
マヤさんの八月が逝った
萩原朔太郎は、古い泉(出水、…)で、きっと、ある、
対話 ベンヤミンという〈経験〉をめぐって (多木浩二とともに)
デクノボー
四畳半
坂部恵氏の思考の道の傍(かたわら、…)に
鏡花フィルム
「アメリカ文学会」にて。二〇〇八年十二月十三日、慶應義塾大学三田、―。
天上の傷―Nicolaに
声にならない声の刺青『おぱらぱん』
対話 言葉の湯気に耳そばだてて (唐十郎とともに)
ストラスブール紀行―唐十郎さんとの出逢い
ガンジス河デ、横田基地ハ、アッタノデハ、ナカッタノカ、…唐十郎さんに
あとがき
初出紙誌一覧
『長篇詩 ごろごろ』2004年
今日読んだ4冊の吉増剛造の詩集のなかで、この『ごろごろ』にいちばん感動した。これこそ宇宙方言と呼びたい言葉のかたまり。(読んだ順が影響してるのかも)
書かれている内容そのものは、日記とかわらないのだが、その一文がどもり、聞きなれない言葉で綴られ、さらにその言葉に、注釈として別に置かれるはずの言葉たちが、蔓のように巻きついている。これは、自分の鎧を脱ぎ捨てて、裸で受け止めないと届いてこない言葉たちだった。でも、いったん読めはじめると、なんという快楽か。
たとえば、「珈琲館」(なんという、日常的な単語!)は、こう表記される。
「コッーッ、ッヒ、ッカ、ッカ、ッン」
『天上ノ蛇、紫のハナ』2005年
激つ
紫っぽい、vibratus〔ラテン語「細かく動く」〕ノ、ブリ(振)ちゃん
(彼岸からの)口笛
近所の鳩と遊んだこともあるだろう、傷痍軍人さんの白い杖
“白い杖”が天上に投げ上げられて、未来の、わたくしたちの手が、・・・
刹那ニ、埃=穂古里ノ、匂ヒが、シタ
コク、きっと(クは小さい「ク」で、ハングル表記がはさまる)
ピカ、がだ、・・・
ミツメラレテイル-gauze,gauze
天上ノ巨人
すべてを枯らさずに歩むこと
海が陥落しているところまで、とうとう、こゝまで、やってきていた、・・・
“あたらしい色でおとずれておくれ”ひとつの“白い陰”(「日時計篇2」全詩集1537頁・・・)として
“楡のちび”が「灰暗の(かいあんの)」鉛筆のような自轉車に
“足なへの鉄(くろ)”よ、突っぱしれ!
こゝろハ櫻色、すがすがしい余地
(色々の)繊維のシッポの浄土の鼠・・・
構内(ゲレンデ)ニ雨が、・・・
普天間(フチマー)ニ、“・・・ノ楡ノ木”
恋しい哀号
火爪、蹄-hof,hoof,hooves
赤馬(あかうま)
吉本隆明や寺山修司について書いたものなど。
『花火の家の入口で』2001年
唖者の家へ
廃庭
月暈/不死
神を池の下に手紙をとどけに行った
薄いヴェールの丘に
花火の家の入口で・序
花火の家の入口で
薄い音の梶棒が刺青を写す。神の手の掻き痕にわたしも気がつく
櫻/ラジオ
手紙
中国の一角獣
灰色/遺伝子/宝石
石狩シーツ
麒麟-石狩河口
「路上バンド」に逢った日に、神は、ドイツへ行ってしまった
紐育、午前四時三十分
『The Other Voice』2002年
1、光の下に“蝶層”を
2、僕の死後の白いはな
3、お遍路さんの後姿に
4、“残しておきたい、・・・”《蛇籠の木、・・・》
5、月は繊維でゞきている
6、Out-of-the-way(へんぴな、特異な、・・・片田舎の、横道にそれた、・・・)
7、The Other Voice
8、雜車、トロ=ッ
9、雜神、イェイツが伝へて来たこと。そして、ソルジェニーツィン
10、南方(陽面あるいは影面、輝きの方へ、・・・それに対して北方ハ、背面、北方、・・・
11、「湘南電車」ハ、モハ(・・・、まだ走ってる?
12、嘉手納
13、歌(あやご)
14、福生、福生(フッサ、フッツッァ)
15、古人(道元、戈麦君、・・・舞天先生、良寛さん、・・・)
16、沈黙の言葉(「無文字時代の言葉を幻視する、・・・」とtitle(ラテン語「銘」の意、・・・)を、石川九楊氏に差しだされて、2001.8.1,2,3,4と、考えつゞけていたことのmemo(ラテン語、記憶されるべきもの=memorandum)のfragment(断片、かけら。ラテン語「こわれたもの」)を僅かにうごかしてみる、こ、ゝ、ろ、み、・・・)
17、光の落葉
18、美しい晩秋の朝のひとゝき
19、紙裏に(、・・・
20、バッハ(“身を屈め、指で地面に書きはじめ、・・・)
21、パ
今日読んだ4冊の吉増剛造の詩集のなかで、この『ごろごろ』にいちばん感動した。これこそ宇宙方言と呼びたい言葉のかたまり。(読んだ順が影響してるのかも)
書かれている内容そのものは、日記とかわらないのだが、その一文がどもり、聞きなれない言葉で綴られ、さらにその言葉に、注釈として別に置かれるはずの言葉たちが、蔓のように巻きついている。これは、自分の鎧を脱ぎ捨てて、裸で受け止めないと届いてこない言葉たちだった。でも、いったん読めはじめると、なんという快楽か。
たとえば、「珈琲館」(なんという、日常的な単語!)は、こう表記される。
「コッーッ、ッヒ、ッカ、ッカ、ッン」
『天上ノ蛇、紫のハナ』2005年
激つ
紫っぽい、vibratus〔ラテン語「細かく動く」〕ノ、ブリ(振)ちゃん
(彼岸からの)口笛
近所の鳩と遊んだこともあるだろう、傷痍軍人さんの白い杖
“白い杖”が天上に投げ上げられて、未来の、わたくしたちの手が、・・・
刹那ニ、埃=穂古里ノ、匂ヒが、シタ
コク、きっと(クは小さい「ク」で、ハングル表記がはさまる)
ピカ、がだ、・・・
ミツメラレテイル-gauze,gauze
天上ノ巨人
すべてを枯らさずに歩むこと
海が陥落しているところまで、とうとう、こゝまで、やってきていた、・・・
“あたらしい色でおとずれておくれ”ひとつの“白い陰”(「日時計篇2」全詩集1537頁・・・)として
“楡のちび”が「灰暗の(かいあんの)」鉛筆のような自轉車に
“足なへの鉄(くろ)”よ、突っぱしれ!
こゝろハ櫻色、すがすがしい余地
(色々の)繊維のシッポの浄土の鼠・・・
構内(ゲレンデ)ニ雨が、・・・
普天間(フチマー)ニ、“・・・ノ楡ノ木”
恋しい哀号
火爪、蹄-hof,hoof,hooves
赤馬(あかうま)
吉本隆明や寺山修司について書いたものなど。
『花火の家の入口で』2001年
唖者の家へ
廃庭
月暈/不死
神を池の下に手紙をとどけに行った
薄いヴェールの丘に
花火の家の入口で・序
花火の家の入口で
薄い音の梶棒が刺青を写す。神の手の掻き痕にわたしも気がつく
櫻/ラジオ
手紙
中国の一角獣
灰色/遺伝子/宝石
石狩シーツ
麒麟-石狩河口
「路上バンド」に逢った日に、神は、ドイツへ行ってしまった
紐育、午前四時三十分
『The Other Voice』2002年
1、光の下に“蝶層”を
2、僕の死後の白いはな
3、お遍路さんの後姿に
4、“残しておきたい、・・・”《蛇籠の木、・・・》
5、月は繊維でゞきている
6、Out-of-the-way(へんぴな、特異な、・・・片田舎の、横道にそれた、・・・)
7、The Other Voice
8、雜車、トロ=ッ
9、雜神、イェイツが伝へて来たこと。そして、ソルジェニーツィン
10、南方(陽面あるいは影面、輝きの方へ、・・・それに対して北方ハ、背面、北方、・・・
11、「湘南電車」ハ、モハ(・・・、まだ走ってる?
12、嘉手納
13、歌(あやご)
14、福生、福生(フッサ、フッツッァ)
15、古人(道元、戈麦君、・・・舞天先生、良寛さん、・・・)
16、沈黙の言葉(「無文字時代の言葉を幻視する、・・・」とtitle(ラテン語「銘」の意、・・・)を、石川九楊氏に差しだされて、2001.8.1,2,3,4と、考えつゞけていたことのmemo(ラテン語、記憶されるべきもの=memorandum)のfragment(断片、かけら。ラテン語「こわれたもの」)を僅かにうごかしてみる、こ、ゝ、ろ、み、・・・)
17、光の落葉
18、美しい晩秋の朝のひとゝき
19、紙裏に(、・・・
20、バッハ(“身を屈め、指で地面に書きはじめ、・・・)
21、パ
『「アジア」の渚で 日韓詩人の対話』
2011年9月13日 読書
高銀(コ・ウン)と吉増剛造の『「アジア」の渚で 日韓詩人の対話』を読んだ。
高銀の著者紹介がもうドラマチック!
「道で拾った癩病患者の詩集を読み、詩人を志す。朝鮮戦争時、報復虐殺を目撃、精神的混乱に。その後出家、僧侶として活躍するが、還俗し、投獄・拷問を受けながら民主化運動に従事」だって!
韓国の詩人、高銀と、日本の詩人、吉増剛造の対談と往復書簡がおさめてある。
以下、目次。
序 高銀先生のこと・・・姜尚中
<対談>
瞬間の故郷・・・高銀・吉増剛造
南北首脳会談で朗読した詩/大同江のほとりで(高銀)/人間は宇宙の言語の四分の一しか使っていない/詩のようなものは求めなくても、こうやって現れてくる/瞬間の故郷/「東北アジア共同の家」と海の広場
<往復書簡>
届けられた音声をめぐって・・・吉増剛造
詩人が背負うもの・・・高銀
蟋蟀のように耳を澄まして、…・・・吉増剛造
言語の雲・・・高銀
より深い読者へ・・・吉増剛造
海の華厳・・・高銀
薄い灰色の吐息の世界・・・吉増剛造
人間としての風景・・・高銀
<対談>
古代の服・・・高銀・吉増剛造
誤解と錯覚の中から咲き出した花/ハングルに恋をした/古代の日常の手触り/歴史と現実が詩に属す/太古のアジアの方へ/小さな言葉たちの危機/不揃いの思想/沖縄と済州島/東北アジアの新しい目覚め/「共同」への警戒/泥と干潟の世界を持って歩く/詩人は、干潟の生命体/不揃いの干潟の家/古代の服を着てみよう/古代という新しさの源泉/薪が地面に落ちる音/「協」という言葉を聞くだけで・・・/終わりこそ始まり
<対話を終えて>
未完の対話・・・高銀
海を掬い尽せ・・・吉増剛造
高銀の書簡が、たとえばイラク虐殺に対する抗議など、社会的なわかりやすいメッセージとして打ち出されるのに対して、吉増剛造は詩、言語からのアプローチをひたすら模索する、という印象を受けた。
本書でとりあげられた「宇宙方言」は、吉増剛造の詩の言語をみるときの大きなヒントになりそうだ。
高銀の著作もまた読みたくなってきた。
高銀の著者紹介がもうドラマチック!
「道で拾った癩病患者の詩集を読み、詩人を志す。朝鮮戦争時、報復虐殺を目撃、精神的混乱に。その後出家、僧侶として活躍するが、還俗し、投獄・拷問を受けながら民主化運動に従事」だって!
韓国の詩人、高銀と、日本の詩人、吉増剛造の対談と往復書簡がおさめてある。
以下、目次。
序 高銀先生のこと・・・姜尚中
<対談>
瞬間の故郷・・・高銀・吉増剛造
南北首脳会談で朗読した詩/大同江のほとりで(高銀)/人間は宇宙の言語の四分の一しか使っていない/詩のようなものは求めなくても、こうやって現れてくる/瞬間の故郷/「東北アジア共同の家」と海の広場
<往復書簡>
届けられた音声をめぐって・・・吉増剛造
詩人が背負うもの・・・高銀
蟋蟀のように耳を澄まして、…・・・吉増剛造
言語の雲・・・高銀
より深い読者へ・・・吉増剛造
海の華厳・・・高銀
薄い灰色の吐息の世界・・・吉増剛造
人間としての風景・・・高銀
<対談>
古代の服・・・高銀・吉増剛造
誤解と錯覚の中から咲き出した花/ハングルに恋をした/古代の日常の手触り/歴史と現実が詩に属す/太古のアジアの方へ/小さな言葉たちの危機/不揃いの思想/沖縄と済州島/東北アジアの新しい目覚め/「共同」への警戒/泥と干潟の世界を持って歩く/詩人は、干潟の生命体/不揃いの干潟の家/古代の服を着てみよう/古代という新しさの源泉/薪が地面に落ちる音/「協」という言葉を聞くだけで・・・/終わりこそ始まり
<対話を終えて>
未完の対話・・・高銀
海を掬い尽せ・・・吉増剛造
高銀の書簡が、たとえばイラク虐殺に対する抗議など、社会的なわかりやすいメッセージとして打ち出されるのに対して、吉増剛造は詩、言語からのアプローチをひたすら模索する、という印象を受けた。
本書でとりあげられた「宇宙方言」は、吉増剛造の詩の言語をみるときの大きなヒントになりそうだ。
高銀の著作もまた読みたくなってきた。
『フランス映画どこへ行く ヌーヴェル・ヴァーグから遠く離れて』
2011年9月6日 読書
林瑞絵の『フランス映画どこへ行く ヌーヴェル・ヴァーグから遠く離れて』を読んだ。
まず、目次。
はじめに-新世紀、フランス映画は古く寂れた豪華客船
第0章 現代フランス映画の健康診断
1、映画大国の座は手放しません
2、映画は今も気軽な娯楽
3、ハリウッド台風から身をかわして
4、国産映画を守る努力アリ
5、現代フランス映画は「骨粗鬆症」
ここdeひと休みコラム:文化の番人フランスの横暴な自尊心
第1章 テレビ&映画、お見合い結婚の破綻
1、テレビに頼っておんぶに抱っこ
2、ムッシュ・シネマ、若葉の時代
3、波乱含みの新婚前夜
4、国が仲人となりお見合い結婚へ
5、テレビは財布を握る恐妻に
6、異質メディアに同コンテンツを求めるムリ
7、テレビ局トップが望むのは「受け身で空っぽな人間」
8、ゴールデンタイム・シネマ=「仏版プチ・ハリウッド映画」の誕生
9、仏映画史上最大のヒット作「シュティの地へようこそ」
10、男はお笑いタレントが映画スターへの近道
11、女はスーパーモデルが映画スターへの近道
インタビュー:ミシェル・レイヤック(アルテ映画部門責任者)
「『戦場でワルツを』が生まれたのはリスクを恐れなかったから」
ここdeひと休みコラム:フランス人の異様なコメディ好き
ここdeひと休みコラム:映画監督になりたがる俳優たち
第2章 シネコンが後押しする数の論理
1、シネコン誕生の背景
2、フランスでも大成功の理由
3、人形は顔が命、映画は第1週目が命
4、ダメ映画に安心なヒットの作り方
5、口コミはもはや幻想に過ぎず
6、映画見放題パスの登場
7、シネコンの独裁政治に拍車
8、映画は「外で見るテレビ」に
9、結局は二極化の促進マシーン
10、有名俳優のシネコン批判が検閲?
11、観客が匿名の数字になる時
12、客の個性が許されるアート系映画館
ミニ・ルポルタージュ:国立映画・動画センター・アルシーヴ(記録保管所)部門を訪ねて
ここdeひと休みコラム:ケチケチで成功した謎のフランス映画
第3章 自己チューな作家主義の蔓延
1、ナルシシズムの実習とマゾヒズムの強制
2、関心は半径100メートル以内の日常
3、自己チュ~映画は天才だけどうぞ
4、「作家たれ」とトリュフォーは言ったけど
5、歪んで解釈されたヌーヴェル・ヴァーグ
6、映画作家養成所、映画学校フェミス
7、疑問や苦悩知らずのオレ様ワールド
8、職業人としての監督はいずこへ
9、ジュネ、ゴンドリー、デルピー、しなやかさが強みの監督
インタビュー:ミシェル・シマン(映画批評家)
「ヌーヴェル・ヴァーグの間違った解釈がフランス映画をダメにする」
インタビュー:アルノー・デプレシャン(映画監督)
「ヌーヴェル・ヴァーグと後にきた世代との混同が激しい」
インタビュー:フェミス学生の声
「経験が大事という考えは間違っていない」-フェミス映画教育・肯定派 畑明広(監督科)
「僕らは象牙の塔に住んでるみたい」-フェミス映画教育・否定派 トマ・グルニエ(監督科)
ここdeひと休みコラム:「もう作れない映画祭」って何だ?
第4章 真のプロデューサーの不在
1、フランスにはびこる2種類のプロデューサー
2、超・作家主義にもご用心
3、理想の映画プロデューサーとは
4、ジャック・ドワイヨンのいばら道
5、伝説の男アルテ・フィクション部門ピエール・シュヴァリエ
6、自由と拘束の「アメとムチ作戦」が効く
7、『あの夏の子どもたち』のモデル、独立系プロデューサーの死
インタビュー:ブリュノ・デュモン(映画監督)
「私が映画産業に譲歩したことは一度もない」
ここdeひと休みコラム:「ボクの彼女」を使いたがる公私混同監督たち
第5章 批評はどこへいった?
1、アマチュア天国ニッポン、プロの暴走おフランス
2、映画評論家とは“お呼びでない奴”
3、パトリス・ルコントVS批評家の仁義なき戦い
4、カイエ的な示し合せに気をつけろ
5、終身刑は重過ぎた?嫌われ者クロード・ルルーシュの場合
6、芸術は批評がないと死ぬ
7、感性の遠隔操作にちょっと待った!
8、栄光なき批評家にちょっぴり同情の巻
9、フランス人監督の名誉欲が目障りの巻
10、アーティストとは「出さないと便秘になる人」
インタビュー:パスカル・メリジョー(映画批評家、小説家)
「アサイヤスは偉大と決めたらテコでも動かない」
第6章 希代のヒットメーカー、リュック・ベッソンの場合
1、賞賛と誹謗の狭間で泳ぐ魚座の男
2、超・観客主義の悟りを開く
3、ハリウッドを拒否しフランスを拠点に
4、アメリカに抗うジャンヌ・ダルク?
5、ヨーロッパ・コープ時代の幕開け
6、“水を得たイルカ”になったベッソンの監督業
7、永遠の子供監督による永遠の子供映画
8、大作のカラクリを利用した「80%の法則」
9、超・観客主義の危険とは
インタビュー:フレデリック・ソシェール(映画監督、パリ第一大学助教授)
「『レオン』はアメリカではフランス映画、フランスではアメリカ映画」
第7章 現代フランス映画に好転の兆し
1、女性監督パスカル・フェランが仕掛けた爆弾
2、映画界に深く根をはる二極化
3、大作でも低予算でもない「中間映画」を救え!
4、13人の映画人が制度を見直し
5、二極化にブレーキをかける改革案
6、吉兆を予感させる『パリ20区、僕たちのクラス』
7、ただ今、フランス映画健闘中
8、テレビからの圧力を受けない作品の強さ
9、目指すはインターナショナルよりユニヴァーサル
10、疑いの価値観とともに、そしてフランス映画どこへ行く
インタビュー:セドリック・クラピッシュ(映画監督)
「To be international,be local!」
インタビュー:クロード・ミレール(映画監督)
「逆効果を生む映画システムを軌道修正したい」
ここdeひと休みコラム:『ロング・エンゲージメント』に見る「フランス映画ってなんぞや?」裁判
付録
パスカル・フェランの07年セザール賞授賞式演説訳
セドリック・クラピッシュがサルコジ大統領に送った公開レター訳
「13人のクラブ」による12の改革案訳(簡易版)
あとがき
写真協力・参考文献・参考ラジオ
表紙の写真はロベール・ブレッソンの「バルタザールどこへ行く」、裏を見ると、こんな惹句が書いてある。
上の文章でも、また、目次からも察しがつくように、辛口でかかれたフランス映画に関するエッセイだが、いろいろと知らなかった事情なども書かれていて、興味深い1冊だった。とくに、フランスで大当たりをとった映画「アステリックス」や「ブロンゼ3」(どちらも未見!)のくそみそけなしぶりは再三にわたっており、そんなに駄作なのなら、見てみなくてはなるまい、と思わされた。
一方、健闘している、いいフランス映画としては、「パリ20区、僕たちのクラス」「預言者」「神々と男たち」があげられている。ジャック・オディアール監督の「預言者」(アンプロフェット)は去年のフランス映画祭でかかった作品だが、未見。もっと映画見なくちゃ。フランス映画祭も関西での開催を再開してほしいな。
コラムの中に、「歴代フランス映画の国内観客数ランキング」があったので、それを書いておこう。
1位『シュティの地へようこそ』2008/ダニー・ブーン
2位『大進撃』1966/ジェラール・ウーリー
3位『ミッション・クレオパトラ』2001/アラン・シャバ
4位『おかしなおかしな訪問者』1993年/ジャン=マリー・ポワレ
5位『陽気なドンカミロ』1951年/ジュリアン・デュヴィヴィエ
6位『大追跡』1964年/ジェラール・ウーリー
7位『ブロンゼ3』2006年/パトリス・ルコント
8位『タクシー2』2000年/ジェラール・クラヴジック
9位『赤ちゃんに乾杯!』1985年/コリーヌ・セロー
10位『わんぱく戦争』1961年/イヴ・ロベール
なるほど。これを見ると、「フランス映画」のイメージとはそぐわない感じがするなあ。こういうランキング、日本だと宮崎駿とテレビがらみがほとんど、アメリカだとシネコンで見れるような大作ばっかり、ということになる。
しかし、「大~」シリーズのジェラール・ウーリーが2作も入っているのがすごいなあ。ルイ・ド・フュネスを見たくなってきた。
まず、目次。
はじめに-新世紀、フランス映画は古く寂れた豪華客船
第0章 現代フランス映画の健康診断
1、映画大国の座は手放しません
2、映画は今も気軽な娯楽
3、ハリウッド台風から身をかわして
4、国産映画を守る努力アリ
5、現代フランス映画は「骨粗鬆症」
ここdeひと休みコラム:文化の番人フランスの横暴な自尊心
第1章 テレビ&映画、お見合い結婚の破綻
1、テレビに頼っておんぶに抱っこ
2、ムッシュ・シネマ、若葉の時代
3、波乱含みの新婚前夜
4、国が仲人となりお見合い結婚へ
5、テレビは財布を握る恐妻に
6、異質メディアに同コンテンツを求めるムリ
7、テレビ局トップが望むのは「受け身で空っぽな人間」
8、ゴールデンタイム・シネマ=「仏版プチ・ハリウッド映画」の誕生
9、仏映画史上最大のヒット作「シュティの地へようこそ」
10、男はお笑いタレントが映画スターへの近道
11、女はスーパーモデルが映画スターへの近道
インタビュー:ミシェル・レイヤック(アルテ映画部門責任者)
「『戦場でワルツを』が生まれたのはリスクを恐れなかったから」
ここdeひと休みコラム:フランス人の異様なコメディ好き
ここdeひと休みコラム:映画監督になりたがる俳優たち
第2章 シネコンが後押しする数の論理
1、シネコン誕生の背景
2、フランスでも大成功の理由
3、人形は顔が命、映画は第1週目が命
4、ダメ映画に安心なヒットの作り方
5、口コミはもはや幻想に過ぎず
6、映画見放題パスの登場
7、シネコンの独裁政治に拍車
8、映画は「外で見るテレビ」に
9、結局は二極化の促進マシーン
10、有名俳優のシネコン批判が検閲?
11、観客が匿名の数字になる時
12、客の個性が許されるアート系映画館
ミニ・ルポルタージュ:国立映画・動画センター・アルシーヴ(記録保管所)部門を訪ねて
ここdeひと休みコラム:ケチケチで成功した謎のフランス映画
第3章 自己チューな作家主義の蔓延
1、ナルシシズムの実習とマゾヒズムの強制
2、関心は半径100メートル以内の日常
3、自己チュ~映画は天才だけどうぞ
4、「作家たれ」とトリュフォーは言ったけど
5、歪んで解釈されたヌーヴェル・ヴァーグ
6、映画作家養成所、映画学校フェミス
7、疑問や苦悩知らずのオレ様ワールド
8、職業人としての監督はいずこへ
9、ジュネ、ゴンドリー、デルピー、しなやかさが強みの監督
インタビュー:ミシェル・シマン(映画批評家)
「ヌーヴェル・ヴァーグの間違った解釈がフランス映画をダメにする」
インタビュー:アルノー・デプレシャン(映画監督)
「ヌーヴェル・ヴァーグと後にきた世代との混同が激しい」
インタビュー:フェミス学生の声
「経験が大事という考えは間違っていない」-フェミス映画教育・肯定派 畑明広(監督科)
「僕らは象牙の塔に住んでるみたい」-フェミス映画教育・否定派 トマ・グルニエ(監督科)
ここdeひと休みコラム:「もう作れない映画祭」って何だ?
第4章 真のプロデューサーの不在
1、フランスにはびこる2種類のプロデューサー
2、超・作家主義にもご用心
3、理想の映画プロデューサーとは
4、ジャック・ドワイヨンのいばら道
5、伝説の男アルテ・フィクション部門ピエール・シュヴァリエ
6、自由と拘束の「アメとムチ作戦」が効く
7、『あの夏の子どもたち』のモデル、独立系プロデューサーの死
インタビュー:ブリュノ・デュモン(映画監督)
「私が映画産業に譲歩したことは一度もない」
ここdeひと休みコラム:「ボクの彼女」を使いたがる公私混同監督たち
第5章 批評はどこへいった?
1、アマチュア天国ニッポン、プロの暴走おフランス
2、映画評論家とは“お呼びでない奴”
3、パトリス・ルコントVS批評家の仁義なき戦い
4、カイエ的な示し合せに気をつけろ
5、終身刑は重過ぎた?嫌われ者クロード・ルルーシュの場合
6、芸術は批評がないと死ぬ
7、感性の遠隔操作にちょっと待った!
8、栄光なき批評家にちょっぴり同情の巻
9、フランス人監督の名誉欲が目障りの巻
10、アーティストとは「出さないと便秘になる人」
インタビュー:パスカル・メリジョー(映画批評家、小説家)
「アサイヤスは偉大と決めたらテコでも動かない」
第6章 希代のヒットメーカー、リュック・ベッソンの場合
1、賞賛と誹謗の狭間で泳ぐ魚座の男
2、超・観客主義の悟りを開く
3、ハリウッドを拒否しフランスを拠点に
4、アメリカに抗うジャンヌ・ダルク?
5、ヨーロッパ・コープ時代の幕開け
6、“水を得たイルカ”になったベッソンの監督業
7、永遠の子供監督による永遠の子供映画
8、大作のカラクリを利用した「80%の法則」
9、超・観客主義の危険とは
インタビュー:フレデリック・ソシェール(映画監督、パリ第一大学助教授)
「『レオン』はアメリカではフランス映画、フランスではアメリカ映画」
第7章 現代フランス映画に好転の兆し
1、女性監督パスカル・フェランが仕掛けた爆弾
2、映画界に深く根をはる二極化
3、大作でも低予算でもない「中間映画」を救え!
4、13人の映画人が制度を見直し
5、二極化にブレーキをかける改革案
6、吉兆を予感させる『パリ20区、僕たちのクラス』
7、ただ今、フランス映画健闘中
8、テレビからの圧力を受けない作品の強さ
9、目指すはインターナショナルよりユニヴァーサル
10、疑いの価値観とともに、そしてフランス映画どこへ行く
インタビュー:セドリック・クラピッシュ(映画監督)
「To be international,be local!」
インタビュー:クロード・ミレール(映画監督)
「逆効果を生む映画システムを軌道修正したい」
ここdeひと休みコラム:『ロング・エンゲージメント』に見る「フランス映画ってなんぞや?」裁判
付録
パスカル・フェランの07年セザール賞授賞式演説訳
セドリック・クラピッシュがサルコジ大統領に送った公開レター訳
「13人のクラブ」による12の改革案訳(簡易版)
あとがき
写真協力・参考文献・参考ラジオ
表紙の写真はロベール・ブレッソンの「バルタザールどこへ行く」、裏を見ると、こんな惹句が書いてある。
数々の女性誌が垂れ流し続ける甘ったるいお洒落なイメージや、シネフィルが憧れるヌーヴェル・ヴァーグの残像に、フランス映画の“今”を重ねる試みも、そろそろ限界に達してきました。「フランス映画はオシャレっぽい」「フランス映画は良質揃い」といった昔取った杵柄的レッテルも、いよいよカビ臭くなってきました。そして絶滅種たるシネフィルたちは「フランス映画は時代遅れ」と判を押し、背中を向けて、また一人と去っていきます。
嗚呼、今となっては古く寂れた豪華客船にも似たフランス映画。映画の大海原を亡霊のように彷徨い、漂い続けます。このくたびれた豪華客船は、過去の栄光を背負いながらいったいどこへ向かうのでしょうか?
本書では、日本ではほとんど語られてこなかった現地の事情をわかりやすく紹介しながら、フランス映画の病原体をつきとめ、健康回復に向けての処方箋を考える、フランス映画の健康診断書です。
数の論理、業界の力学、押しつけられた価値観の犠牲になる現代フランス映画が、反面教師的に見せる痛々しい姿は、日本人にとっても身近で示唆的な問題を多分に抱えているからです。
上の文章でも、また、目次からも察しがつくように、辛口でかかれたフランス映画に関するエッセイだが、いろいろと知らなかった事情なども書かれていて、興味深い1冊だった。とくに、フランスで大当たりをとった映画「アステリックス」や「ブロンゼ3」(どちらも未見!)のくそみそけなしぶりは再三にわたっており、そんなに駄作なのなら、見てみなくてはなるまい、と思わされた。
一方、健闘している、いいフランス映画としては、「パリ20区、僕たちのクラス」「預言者」「神々と男たち」があげられている。ジャック・オディアール監督の「預言者」(アンプロフェット)は去年のフランス映画祭でかかった作品だが、未見。もっと映画見なくちゃ。フランス映画祭も関西での開催を再開してほしいな。
コラムの中に、「歴代フランス映画の国内観客数ランキング」があったので、それを書いておこう。
1位『シュティの地へようこそ』2008/ダニー・ブーン
2位『大進撃』1966/ジェラール・ウーリー
3位『ミッション・クレオパトラ』2001/アラン・シャバ
4位『おかしなおかしな訪問者』1993年/ジャン=マリー・ポワレ
5位『陽気なドンカミロ』1951年/ジュリアン・デュヴィヴィエ
6位『大追跡』1964年/ジェラール・ウーリー
7位『ブロンゼ3』2006年/パトリス・ルコント
8位『タクシー2』2000年/ジェラール・クラヴジック
9位『赤ちゃんに乾杯!』1985年/コリーヌ・セロー
10位『わんぱく戦争』1961年/イヴ・ロベール
なるほど。これを見ると、「フランス映画」のイメージとはそぐわない感じがするなあ。こういうランキング、日本だと宮崎駿とテレビがらみがほとんど、アメリカだとシネコンで見れるような大作ばっかり、ということになる。
しかし、「大~」シリーズのジェラール・ウーリーが2作も入っているのがすごいなあ。ルイ・ド・フュネスを見たくなってきた。
『38人の沈黙する目撃者-キティ・ジェノヴィーズ事件の真相』
2011年9月5日 読書
A・M・ローゼンタールの『38人の沈黙する目撃者』を読んだ。
サブタイトルには「キティ・ジェノヴィーズ事件の真相」とある。
以下、目次。
サミュエル・フリードマンによる序文
著者によるペーパーバック版への序文
アーサー・オックス・サルズバーガーによる序文
第1部
第2部
訳者解説
これは、1964年に実際にあった事件について書かれた本で、女性が街中で殺された事件を扱っている。とくに何か恨みがあったとか、金目当てというわけではなく、犯人は狩りに近いような感覚で、通りすがりの見ず知らずの女性をターゲットに選ぶのである。
最近の日本の犯罪で「誰でもよかった」という犯人の発言にショックを受ける人がいるが、縁もゆかりもない被害者を、ただそこにいたから、という理由で殺してしまう事件なんて、昔から山ほどあったのだ。さらに戦争になると、この事情はさらに拡大加速する。そんな理由なき殺人の現実に、理性と知性の立場から異議申し立てをしているのが、推理小説という行為なのだと思う。
閑話休題。
本書の被害者、キティ・ジェノヴィーズが、そうした理由なき犯行によって殺されたことも衝撃のうちだが、さらに衝撃だったのは、彼女はもちろん声をあげて助けを求め、逃げまどったのである。だが、いったんひきあげたかに見えた犯人が何度も戻ってきて彼女を殺してしまうまで、だれも警察に通報しなかったし、止めにも入らなかったのだ。彼女が襲われてから、絶命するまで、38人もの目撃者がいたが、だれひとりとして、彼女を助けなかったのである。
当時、この事件に対する新聞への投書などの反応は、次のようなものだった。
「目撃者の名前を探り出して公表せよ。これらの人々は大衆の嘲笑に晒されるべきだ。自らの不作為が招いたことに責任をとっていない」
「彼らが沈黙を守ったこと、臆病にも無関心を決め込んだことに唖然とする。彼らにも罪がある」
現在でも、何かことあるごとに、実名報道せよだの、公表せよだの、ネットの住人たちはかまびすしいが、昔から大衆は変わらないのだ。
ただ、著者はここでちょっと耳のいたいことをさらっと言う。
「新聞に投書を書いてくる人々が全体を代表しているのかどうかについては、新聞記者の間でも結論のつかない問題である。ただ、新聞に意見するような強い感情を持つ少数の人々は通常やはり変わった人であって、全体を代表しておらず自分の意見を述べているだけというのが、新聞記者の多数派の見方である。」
意外と冷静に受け止めていたのだ。
しかし、ローゼンタールのすぐ後の論旨の展開はこうだ。
「ただジェノヴィーズ事件の場合には投書が通常より洗練されている、というのが私の意見だ。
その理由には、こうした投書の多くに込められた感情が、私自身の友人や親族の抱いた感情とあまり変わらないことがある。」
なるほど。
本書では目撃者たちの行動を説明するのに、無感覚(アパシー)を取り上げて論じる。
外の世界のことに関しては無関心だというアメリカの国民性も手伝って、これは納得できそうな意見だ。
だがしかし、ローゼンタールがつきつけるのは、その一歩先だ。
事件の目撃者たちを弾劾するのはたやすい。
だが、世界では多くの地域で悲鳴をあげている人々がおおぜいいるのだ。
「いったい叫びからどのくらい遠ければ、あの38人の目撃者を憎むように、自分自身を憎まなくても許されるのだろうか。キャスリーン・ジェノヴィーズが私がタイムズ紙でコラムを書いている間にずっと問い掛けていたのは、この問題なのである。これより重要な問題は果たしてあるだろうか。教えて欲しい・・・どれくらい遠ければ許されるのかを。」
サブタイトルには「キティ・ジェノヴィーズ事件の真相」とある。
以下、目次。
サミュエル・フリードマンによる序文
著者によるペーパーバック版への序文
アーサー・オックス・サルズバーガーによる序文
第1部
第2部
訳者解説
これは、1964年に実際にあった事件について書かれた本で、女性が街中で殺された事件を扱っている。とくに何か恨みがあったとか、金目当てというわけではなく、犯人は狩りに近いような感覚で、通りすがりの見ず知らずの女性をターゲットに選ぶのである。
最近の日本の犯罪で「誰でもよかった」という犯人の発言にショックを受ける人がいるが、縁もゆかりもない被害者を、ただそこにいたから、という理由で殺してしまう事件なんて、昔から山ほどあったのだ。さらに戦争になると、この事情はさらに拡大加速する。そんな理由なき殺人の現実に、理性と知性の立場から異議申し立てをしているのが、推理小説という行為なのだと思う。
閑話休題。
本書の被害者、キティ・ジェノヴィーズが、そうした理由なき犯行によって殺されたことも衝撃のうちだが、さらに衝撃だったのは、彼女はもちろん声をあげて助けを求め、逃げまどったのである。だが、いったんひきあげたかに見えた犯人が何度も戻ってきて彼女を殺してしまうまで、だれも警察に通報しなかったし、止めにも入らなかったのだ。彼女が襲われてから、絶命するまで、38人もの目撃者がいたが、だれひとりとして、彼女を助けなかったのである。
当時、この事件に対する新聞への投書などの反応は、次のようなものだった。
「目撃者の名前を探り出して公表せよ。これらの人々は大衆の嘲笑に晒されるべきだ。自らの不作為が招いたことに責任をとっていない」
「彼らが沈黙を守ったこと、臆病にも無関心を決め込んだことに唖然とする。彼らにも罪がある」
現在でも、何かことあるごとに、実名報道せよだの、公表せよだの、ネットの住人たちはかまびすしいが、昔から大衆は変わらないのだ。
ただ、著者はここでちょっと耳のいたいことをさらっと言う。
「新聞に投書を書いてくる人々が全体を代表しているのかどうかについては、新聞記者の間でも結論のつかない問題である。ただ、新聞に意見するような強い感情を持つ少数の人々は通常やはり変わった人であって、全体を代表しておらず自分の意見を述べているだけというのが、新聞記者の多数派の見方である。」
意外と冷静に受け止めていたのだ。
しかし、ローゼンタールのすぐ後の論旨の展開はこうだ。
「ただジェノヴィーズ事件の場合には投書が通常より洗練されている、というのが私の意見だ。
その理由には、こうした投書の多くに込められた感情が、私自身の友人や親族の抱いた感情とあまり変わらないことがある。」
なるほど。
本書では目撃者たちの行動を説明するのに、無感覚(アパシー)を取り上げて論じる。
外の世界のことに関しては無関心だというアメリカの国民性も手伝って、これは納得できそうな意見だ。
だがしかし、ローゼンタールがつきつけるのは、その一歩先だ。
事件の目撃者たちを弾劾するのはたやすい。
だが、世界では多くの地域で悲鳴をあげている人々がおおぜいいるのだ。
「いったい叫びからどのくらい遠ければ、あの38人の目撃者を憎むように、自分自身を憎まなくても許されるのだろうか。キャスリーン・ジェノヴィーズが私がタイムズ紙でコラムを書いている間にずっと問い掛けていたのは、この問題なのである。これより重要な問題は果たしてあるだろうか。教えて欲しい・・・どれくらい遠ければ許されるのかを。」
『NO FUTURE』
2011年8月30日 読書
フランコ・ベラルディ(ビフォ)の『NO FUTURE』を読んだ。
1977年を中心とするイタリアのアウトノミア運動について綴った1冊。
以下、目次。
未来がはじまった年 序文 1(日本語版への序文)
1997年からみた1977年 序文 2(新版への序文)
1987年からみた1977年 序文 3(1987年版の序文)
二つの派
文化の伝達
残余となった具体的なもの
「革命は終わり、ぼくたちは勝利した」
付録 1 天下大乱
2 叙情詩人から叙事詩人へ(悲劇詩人をよけながら)
技術の問いについて
人類学的カテゴリーとしての労働
創造的運動と生産的労働
付録 1 アリーチェ:偽善か共感か
弱い思想と精神の生態学
無垢の思想のために
世界じゅうの ひきこもりたちよ、団結せよ(日本の読者へ)
グローバルなメディア・アクティヴィズムの地図作成
日本へのステレオタイプ
組み換え資本と不安定労働
不安定性と精神病的主体形成
ラディカルな離脱のひとつのかたち:ひきこもり
もうひとつのオペライズモ
フランコ・ベラルディの場合(廣瀬 純 解説)
1963年から1972年まで
ポテーレ・オペライオとその「二重のディスクール」
「ポテーレ・オペライオはネオレーニン主義組織である」(ネグリ)
「組織化は主観性の問題ではなく構成の問題である」(ビフォ)
「革命とコミュニズムは日常生活そのものである」(ネグリ)
フランコ・ベラルディ(ビフォ)への
インタヴュー(廣瀬 純 聞き手)
1973年から2008年まで
1973年から1979年まで
1980年から1989年まで
1990年から1999年まで
2000年から2008年まで
イタリア、1977年以後(北川眞也 解説)
77年 イタリア、「政治実験室」
イタリア、1980年代
イタリア、1990年代
1990年代、運動の季節へ
社会センター、運動の発信地
ジェノヴァ、2001年7月
移民とプレカリアート
デリーヴェアップローディ、アウトノミア運動関連の出版状況
イタリアの政治・運動関連年表 1973~1979年
索 引(人名索引/事項索引)
詳しくはまた後日書くかも。
アウトノミアの「労働の拒否」が、日本での「ひきこもり」を積極的に支持するのは、面白い。
日本の狭いところの考えでは、機械化がすすむと人間の労働が機械にとってかわられてしまう、挙げ句の果てには、解雇、失業、というネガティブな思考法をしてしまいがちだが、イタリアは違う。労働を機械が肩代わりしてくれることによって、人間は8時間労働しなくてもよくなるのだ。1日に1時間だけ働くだけでよくなる、というふうに考える。
ふむ、これは軽くなる発想だ。
1977年を中心とするイタリアのアウトノミア運動について綴った1冊。
以下、目次。
未来がはじまった年 序文 1(日本語版への序文)
1997年からみた1977年 序文 2(新版への序文)
1987年からみた1977年 序文 3(1987年版の序文)
二つの派
文化の伝達
残余となった具体的なもの
「革命は終わり、ぼくたちは勝利した」
付録 1 天下大乱
2 叙情詩人から叙事詩人へ(悲劇詩人をよけながら)
技術の問いについて
人類学的カテゴリーとしての労働
創造的運動と生産的労働
付録 1 アリーチェ:偽善か共感か
弱い思想と精神の生態学
無垢の思想のために
世界じゅうの ひきこもりたちよ、団結せよ(日本の読者へ)
グローバルなメディア・アクティヴィズムの地図作成
日本へのステレオタイプ
組み換え資本と不安定労働
不安定性と精神病的主体形成
ラディカルな離脱のひとつのかたち:ひきこもり
もうひとつのオペライズモ
フランコ・ベラルディの場合(廣瀬 純 解説)
1963年から1972年まで
ポテーレ・オペライオとその「二重のディスクール」
「ポテーレ・オペライオはネオレーニン主義組織である」(ネグリ)
「組織化は主観性の問題ではなく構成の問題である」(ビフォ)
「革命とコミュニズムは日常生活そのものである」(ネグリ)
フランコ・ベラルディ(ビフォ)への
インタヴュー(廣瀬 純 聞き手)
1973年から2008年まで
1973年から1979年まで
1980年から1989年まで
1990年から1999年まで
2000年から2008年まで
イタリア、1977年以後(北川眞也 解説)
77年 イタリア、「政治実験室」
イタリア、1980年代
イタリア、1990年代
1990年代、運動の季節へ
社会センター、運動の発信地
ジェノヴァ、2001年7月
移民とプレカリアート
デリーヴェアップローディ、アウトノミア運動関連の出版状況
イタリアの政治・運動関連年表 1973~1979年
索 引(人名索引/事項索引)
詳しくはまた後日書くかも。
アウトノミアの「労働の拒否」が、日本での「ひきこもり」を積極的に支持するのは、面白い。
日本の狭いところの考えでは、機械化がすすむと人間の労働が機械にとってかわられてしまう、挙げ句の果てには、解雇、失業、というネガティブな思考法をしてしまいがちだが、イタリアは違う。労働を機械が肩代わりしてくれることによって、人間は8時間労働しなくてもよくなるのだ。1日に1時間だけ働くだけでよくなる、というふうに考える。
ふむ、これは軽くなる発想だ。
『危ない言葉』『切ない言葉』
2011年8月23日 読書
松岡正剛のセイゴオ語録1『危ない言葉』を読んだ。
以下、目次。
1 世間を迎え撃つ
2 自分なんてどうでもいい
3 混乱しなさい
4 編集だけが人生だ
5 本は武器である
6 好きだ
引き続き、松岡正剛のセイゴオ語録2『切ない言葉』を読んだ。
以下、目次。
1 絶対少年
2 宇宙の散歩
3 泣き虫Mの生涯
4 遊びをせんとや生まれけん
5 かけがえのない残余
6 淋しがり屋
松岡正剛が今までに書いた文章から目次にあるようなテーマにそって編集した本。
『危ない言葉』のほうでは、主に編集論や読書術について、
『切ない言葉』では、自伝的な記述、交遊録を中心にした文章が選ばれている。
もとより、どの一文も味わいがあったり、仕掛けがあったりするので、言葉の豪雨にあれよあれよと翻弄されるうちに読み終えてしまうくらいだから、語録など編み出したら、きりがないんじゃないか、とも思えるほどだ。
本を多く読む秘訣は、寝ないようにすること、という言葉が、楽しかった。
松岡正剛ともあろう人が、睡魔とたたかって読書していたのか、と思えて親近感がわいたのだ。
以下、目次。
1 世間を迎え撃つ
2 自分なんてどうでもいい
3 混乱しなさい
4 編集だけが人生だ
5 本は武器である
6 好きだ
引き続き、松岡正剛のセイゴオ語録2『切ない言葉』を読んだ。
以下、目次。
1 絶対少年
2 宇宙の散歩
3 泣き虫Mの生涯
4 遊びをせんとや生まれけん
5 かけがえのない残余
6 淋しがり屋
松岡正剛が今までに書いた文章から目次にあるようなテーマにそって編集した本。
『危ない言葉』のほうでは、主に編集論や読書術について、
『切ない言葉』では、自伝的な記述、交遊録を中心にした文章が選ばれている。
もとより、どの一文も味わいがあったり、仕掛けがあったりするので、言葉の豪雨にあれよあれよと翻弄されるうちに読み終えてしまうくらいだから、語録など編み出したら、きりがないんじゃないか、とも思えるほどだ。
本を多く読む秘訣は、寝ないようにすること、という言葉が、楽しかった。
松岡正剛ともあろう人が、睡魔とたたかって読書していたのか、と思えて親近感がわいたのだ。
『ヴァルター・ベンヤミン 「危機」の時代の思想家を読む』
2011年8月18日 読書
仲正昌樹の『ヴァルター・ベンヤミン 「危機」の時代の思想家を読む』を読んだ。2009年9月から2010年2月まで6回にわたって行われた連続講義の内容をもとに編集されたもの。
岩波文庫のベンヤミンの本をテキストにしている。
以下、目次。ドイツ語表記ができていない単語もあるけど、想像で補ってください。
第1日目・・・序論
開講の挨拶
ベンヤミンって何者?
ポストモダンのベンヤミン
消費
ファンタスマゴリー
同時代人ルカーチとブロッホ
マルクスVSベンヤミン
都市を読み解く-現代思想の源流
読んでほしい主要著作紹介
1『ドイツ・ロマン派における芸術批評の概念』
2『ドイツ悲劇の根源』
3『ゲーテの親和力』
4『複製技術時代における芸術作品』
5『パサージュ』
言語について 1-『翻訳者の課題』を読む 前半
「翻訳」とは?/を徹底的に分解する/芸術作品としての文学/文学作品は何を伝達するのか?/創作=詩作/不正確とは?/作品の形式とはなにか?/忘れがたい性質/神の記憶/翻訳可能性/母語/外国語≒生/死/「死後の生Fortleben」/「形成=造形化gestalten」
会場からの質問
第2日目・・・言語について 2―『翻訳者の課題』を読む 後半
文学の定義-ポイエーシス=創作/『生の哲学』/生の連関を見出す使命/目的=終焉/「合目的的zweckmabig」/「表現Ausdruck」/芸術作品による再現/『世界』の模型作り-言語と言語の間の内的な関係/言語の特権/『聖書』/原・本とドイツ・ロマン派/意味・啓示・言語/翻訳における「正確さGenauigkeit」/死後の成熟/「既に死んだ理論となっているあの翻訳論jene tote Theorie der Ubersetzung』/神の言語・純粋言語/パンは同じ“パン”なのか?/「メシア的な終末das messianische Ende」/「気圏Lufrkreis」/「イローニッシュironisch」/偉大な翻訳者=創作者たち/「感性的な音調Gefuhlston」/「シンタクス」/「逐語性Wordichkeir」/純粋言語を解き放つ/原作と純粋言語/聖なるエクリチュール
会場からの質問
第3日目・・・暴力について―『暴力批判論』を読む
時代背景-暴力と革命の世紀/暴力論の系譜/暴力と法と正義と/暴力の正しさ/自然法/実定法的アプローチ/「手段の適法性Berechtigung der Mittel」/法の根本問題/法的目的/革命的ゼネストの問題/国家が恐れる“暴力”/「法維持的暴力die rechtserhaltende Gewalt」/ワイマール共和国-暴力の本質をめぐる哲学的考察/ストライキの暴力/“正しい暴力”と「呪縛圏Bannkreis」/神と運命/宣言と神話/神々と人間の間の「標石Markstein」/正義と権利、神的と神話的/「致命的letal」/「魂Seele」と神的暴力/「戒律Gebot」/暴力の歴史哲学
会場からの質問
第4日目・・・歴史について―『歴史の概念について』を読む
絶筆
第1テーゼ-人形とこびと
第2テーゼ-<解放>と<救済>
第3テーゼ-「年代記的作者Chronist」と「歴史家Historiker」
第4テーゼ-「繊細な精神的なものfeine und spirituelle Dinge」
第5テーゼ-「過去の真のイメージdas wahre Bild der Vergangenheit」
第6テーゼ-危機の瞬間にひらめく「回想=記憶Erinnerung」
第7テーゼ-「文化財Kulturguter」
第8テーゼ-「非常事態Ausnahmezustand」、カール・シュミットとファシズム
第9テーゼ-「歴史の天使der Engel der Geschichte」
第10テーゼ-惰性的思考
第11テーゼ-労働・技術・自然
第12テーゼ-「解放の仕事das Werk der Befreiung」
第13テーゼ-「均質で空虚な時間eine homogene und leere Zeit」
第14テーゼ-「今の時<Jetztzeit>」
第15テーゼ-暦と記念日
第16テーゼ-歴史主義VS史的唯物論
第17テーゼ-一般史VSモナド
第18テーゼ-メシア的な静止、史的唯物論における過去の救済、闘争を通しての解放
第5日目・・・メディアについて1―『複製技術の時代における芸術作品』を読む 前半
書誌的問題
第1節-美的な<表現Ausdruck>を通しての所有関係の変化
第2節-「複製=再生産Reproduktion」と「技術-市場-芸術-メディア」
第3節-アウラ・「今、此処das Hier und Jetzt」をめぐるオリジナル性の解体
第4節-メディアと知覚の変化
第5節-「唯一無二einzigartig」
第6節-「礼拝的価値Kultwert」と「展示的価値Ausstellungswert」
第7節-「証拠物件Beweisstuck」としての写真
第8節-古代ギリシア
第9節-芸術とは何か?
第10節-写真と映画
会場からの質問
第6日目・・・メディアについて2―『複製技術の時代における芸術作品』を読む 後半
第11節-機械装置が芸術と人間の関係を変える
第12節-自己疎外・まなざし・スター崇拝
第13節-労働の“分業”の反転可能性
第14節-技術の国の『青い花』
第15・16節-カメラと大衆の無意識な欲望
第17節-ダダイズム、<taktisch>「触覚的」「衝撃」「打撃」
第18節-五感全体の総合的な「慣れ」、芸術を受け止める<aisthsis>的な受容
第19節-戦争・芸術・政治-ファシズムという事例
最後に-ネット社会のベンヤミン
ベンヤミンを理解し、深めるための参考書
語学のテキストを少しずつわかりやすく翻訳していくような手つきで、ベンヤミンの論文が読み解かれていく快感は意外だった。学校で同様の手順でテキストを読んでいたときは、ちっとも面白くなかったのに。
後半で展開される大衆、ネットと絡めた議論が面白くて、ついつい絶望しがちな現代の大衆にも何らかの可能性があるんじゃないか、と賭けてみたくなる。
岩波文庫のベンヤミンの本をテキストにしている。
以下、目次。ドイツ語表記ができていない単語もあるけど、想像で補ってください。
第1日目・・・序論
開講の挨拶
ベンヤミンって何者?
ポストモダンのベンヤミン
消費
ファンタスマゴリー
同時代人ルカーチとブロッホ
マルクスVSベンヤミン
都市を読み解く-現代思想の源流
読んでほしい主要著作紹介
1『ドイツ・ロマン派における芸術批評の概念』
2『ドイツ悲劇の根源』
3『ゲーテの親和力』
4『複製技術時代における芸術作品』
5『パサージュ』
言語について 1-『翻訳者の課題』を読む 前半
「翻訳」とは?/を徹底的に分解する/芸術作品としての文学/文学作品は何を伝達するのか?/創作=詩作/不正確とは?/作品の形式とはなにか?/忘れがたい性質/神の記憶/翻訳可能性/母語/外国語≒生/死/「死後の生Fortleben」/「形成=造形化gestalten」
会場からの質問
第2日目・・・言語について 2―『翻訳者の課題』を読む 後半
文学の定義-ポイエーシス=創作/『生の哲学』/生の連関を見出す使命/目的=終焉/「合目的的zweckmabig」/「表現Ausdruck」/芸術作品による再現/『世界』の模型作り-言語と言語の間の内的な関係/言語の特権/『聖書』/原・本とドイツ・ロマン派/意味・啓示・言語/翻訳における「正確さGenauigkeit」/死後の成熟/「既に死んだ理論となっているあの翻訳論jene tote Theorie der Ubersetzung』/神の言語・純粋言語/パンは同じ“パン”なのか?/「メシア的な終末das messianische Ende」/「気圏Lufrkreis」/「イローニッシュironisch」/偉大な翻訳者=創作者たち/「感性的な音調Gefuhlston」/「シンタクス」/「逐語性Wordichkeir」/純粋言語を解き放つ/原作と純粋言語/聖なるエクリチュール
会場からの質問
第3日目・・・暴力について―『暴力批判論』を読む
時代背景-暴力と革命の世紀/暴力論の系譜/暴力と法と正義と/暴力の正しさ/自然法/実定法的アプローチ/「手段の適法性Berechtigung der Mittel」/法の根本問題/法的目的/革命的ゼネストの問題/国家が恐れる“暴力”/「法維持的暴力die rechtserhaltende Gewalt」/ワイマール共和国-暴力の本質をめぐる哲学的考察/ストライキの暴力/“正しい暴力”と「呪縛圏Bannkreis」/神と運命/宣言と神話/神々と人間の間の「標石Markstein」/正義と権利、神的と神話的/「致命的letal」/「魂Seele」と神的暴力/「戒律Gebot」/暴力の歴史哲学
会場からの質問
第4日目・・・歴史について―『歴史の概念について』を読む
絶筆
第1テーゼ-人形とこびと
第2テーゼ-<解放>と<救済>
第3テーゼ-「年代記的作者Chronist」と「歴史家Historiker」
第4テーゼ-「繊細な精神的なものfeine und spirituelle Dinge」
第5テーゼ-「過去の真のイメージdas wahre Bild der Vergangenheit」
第6テーゼ-危機の瞬間にひらめく「回想=記憶Erinnerung」
第7テーゼ-「文化財Kulturguter」
第8テーゼ-「非常事態Ausnahmezustand」、カール・シュミットとファシズム
第9テーゼ-「歴史の天使der Engel der Geschichte」
第10テーゼ-惰性的思考
第11テーゼ-労働・技術・自然
第12テーゼ-「解放の仕事das Werk der Befreiung」
第13テーゼ-「均質で空虚な時間eine homogene und leere Zeit」
第14テーゼ-「今の時<Jetztzeit>」
第15テーゼ-暦と記念日
第16テーゼ-歴史主義VS史的唯物論
第17テーゼ-一般史VSモナド
第18テーゼ-メシア的な静止、史的唯物論における過去の救済、闘争を通しての解放
第5日目・・・メディアについて1―『複製技術の時代における芸術作品』を読む 前半
書誌的問題
第1節-美的な<表現Ausdruck>を通しての所有関係の変化
第2節-「複製=再生産Reproduktion」と「技術-市場-芸術-メディア」
第3節-アウラ・「今、此処das Hier und Jetzt」をめぐるオリジナル性の解体
第4節-メディアと知覚の変化
第5節-「唯一無二einzigartig」
第6節-「礼拝的価値Kultwert」と「展示的価値Ausstellungswert」
第7節-「証拠物件Beweisstuck」としての写真
第8節-古代ギリシア
第9節-芸術とは何か?
第10節-写真と映画
会場からの質問
第6日目・・・メディアについて2―『複製技術の時代における芸術作品』を読む 後半
第11節-機械装置が芸術と人間の関係を変える
第12節-自己疎外・まなざし・スター崇拝
第13節-労働の“分業”の反転可能性
第14節-技術の国の『青い花』
第15・16節-カメラと大衆の無意識な欲望
第17節-ダダイズム、<taktisch>「触覚的」「衝撃」「打撃」
第18節-五感全体の総合的な「慣れ」、芸術を受け止める<aisthsis>的な受容
第19節-戦争・芸術・政治-ファシズムという事例
最後に-ネット社会のベンヤミン
ベンヤミンを理解し、深めるための参考書
語学のテキストを少しずつわかりやすく翻訳していくような手つきで、ベンヤミンの論文が読み解かれていく快感は意外だった。学校で同様の手順でテキストを読んでいたときは、ちっとも面白くなかったのに。
後半で展開される大衆、ネットと絡めた議論が面白くて、ついつい絶望しがちな現代の大衆にも何らかの可能性があるんじゃないか、と賭けてみたくなる。
『スピノザ「エチカ」』
2011年8月5日 読書河井徳治の『スピノザ「エチカ」』を読んだ。哲学概説シリーズの1冊。
「はじめに」で、次のようなことが書かれている。
この本は、筆者がこれまでにスピノザの著作を通して得た観点から、スピノザの主著『エチカ』についてその解題を試みたものであって研究書ではない。『エチカ』には定義、公理、定理という幾何学的な秩序で書かれた特異なスタイルがある。これが余計に取り付きにくい感じを与えるだろう。だからそれらの中から主要な命題を辿りながら、三百数十年以上も前に書かれた哲学書を、少々縁遠くなってきた当時の用語の説明も入れて、馴染み易い表現で解説したい。
いよっ!待ってました!という感じ。
以下、目次。
序章 スピノザの視点
エチカとは/幸福あるいは自足はどこに実現できるか/アリストテレスとスピノザの共通点と相違点/スピノザのエチカの特徴/目的論的世界観への批判と発生論的世界観/無機物と有機物の線引きはできない/デカルトやホッブズの考え方との違い/『エチカ』はなぜ幾何学形式を具えたのか
つづきは後日
「はじめに」で、次のようなことが書かれている。
この本は、筆者がこれまでにスピノザの著作を通して得た観点から、スピノザの主著『エチカ』についてその解題を試みたものであって研究書ではない。『エチカ』には定義、公理、定理という幾何学的な秩序で書かれた特異なスタイルがある。これが余計に取り付きにくい感じを与えるだろう。だからそれらの中から主要な命題を辿りながら、三百数十年以上も前に書かれた哲学書を、少々縁遠くなってきた当時の用語の説明も入れて、馴染み易い表現で解説したい。
いよっ!待ってました!という感じ。
以下、目次。
序章 スピノザの視点
エチカとは/幸福あるいは自足はどこに実現できるか/アリストテレスとスピノザの共通点と相違点/スピノザのエチカの特徴/目的論的世界観への批判と発生論的世界観/無機物と有機物の線引きはできない/デカルトやホッブズの考え方との違い/『エチカ』はなぜ幾何学形式を具えたのか
つづきは後日
フィリップ・ソレルスの『セリーヌ』を読んだ。
作家ソレルスが1963年から2009年にかけて、セリーヌについて書いた文章を集めた1冊。
以下、目次。
はじめに
セリーヌの笑い
セリーヌの戦略
鍵盤をたたくセリーヌ
永遠に人前に出せない作家
セリーヌ誕生
スケープ・ゴート、セリーヌ
セリーヌの数々の人生
「オペラが自然」
デンマーク人はセリーヌを救ったか?
地獄に墜ちたセリーヌ
「恐怖という金利で暮らす者たち」
「何事にも容赦なく・・・」
セリーヌ再読
フロベールの「結局、罪があるのは文体なのだ」と、
サルトルの「社会は悪行以上に悪言を容赦しない」
の2つの発言が繰り返し引かれる。
セリーヌというと、反ユダヤのパンフレに顕著な、悪口雑言、罵詈讒謗、ひとことで言えば、汚い表現が強烈な印象を残すけど、セリーヌはそうした悪口雑言を翼にして表現を実現させたんじゃないか、と僕は勝手に思っている。
2ちゃんねるやヤフーニュースコメントで頑迷な脊髄反射発言を垂れ流す輩と決定的に違うのは、セリーヌは匿名でそれを行わなかったってことだと思っていたが、最近、根っこは一緒なのかもな、と思い直していた。
これは、セリーヌの作品から僕がいかに遠ざかっていたかを思い知らされる感想だったので、この『セリーヌ』をきっかけに、またセリーヌを読んでみようと、思う。
これもまた勝手な予断だが、そこで読めるのは、頑迷な脊髄反射を垂れ流すインターネットの名無しの権兵衛とは決定的に違う何かだと信じたい。
作家ソレルスが1963年から2009年にかけて、セリーヌについて書いた文章を集めた1冊。
以下、目次。
はじめに
セリーヌの笑い
セリーヌの戦略
鍵盤をたたくセリーヌ
永遠に人前に出せない作家
セリーヌ誕生
スケープ・ゴート、セリーヌ
セリーヌの数々の人生
「オペラが自然」
デンマーク人はセリーヌを救ったか?
地獄に墜ちたセリーヌ
「恐怖という金利で暮らす者たち」
「何事にも容赦なく・・・」
セリーヌ再読
フロベールの「結局、罪があるのは文体なのだ」と、
サルトルの「社会は悪行以上に悪言を容赦しない」
の2つの発言が繰り返し引かれる。
セリーヌというと、反ユダヤのパンフレに顕著な、悪口雑言、罵詈讒謗、ひとことで言えば、汚い表現が強烈な印象を残すけど、セリーヌはそうした悪口雑言を翼にして表現を実現させたんじゃないか、と僕は勝手に思っている。
2ちゃんねるやヤフーニュースコメントで頑迷な脊髄反射発言を垂れ流す輩と決定的に違うのは、セリーヌは匿名でそれを行わなかったってことだと思っていたが、最近、根っこは一緒なのかもな、と思い直していた。
これは、セリーヌの作品から僕がいかに遠ざかっていたかを思い知らされる感想だったので、この『セリーヌ』をきっかけに、またセリーヌを読んでみようと、思う。
これもまた勝手な予断だが、そこで読めるのは、頑迷な脊髄反射を垂れ流すインターネットの名無しの権兵衛とは決定的に違う何かだと信じたい。