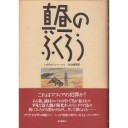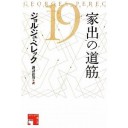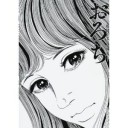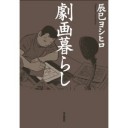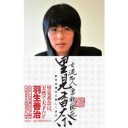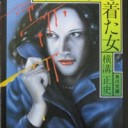先日読んだ『パゾリーニとの対話』にこんな文章があった。
聞き手のジョン・ハリディが、「奇跡の丘」について、パゾリーニを挑発する。
パゾリーニがどうとか言う以前に、ひっかかったのが、「スチャスチャ」という名前だ。
スチャスチャ!かわいい名前!
で、よく調べてみると、それはLeonardo Sciasciaのことだと、見当がついてきた。
スチャスチャではなく、レオナルド・シャーシャだ!
と、いうわけで、レオナルド・シャーシャの本を読むことにした。
シシリー、マフィアを扱った本を多数書いており、社会派ミステリーの書き手と言ってもそう間違ってはいない。
本書でも、マフィアがらみのストーリーになっているが、ご当地では、「マフィアなんて実在しない」という沈黙の壁(オメルタ)があって、マフィアなんてのは都市伝説とでも言いかねないスタンスが貫かれているのである。
事件が起こって、それを論理的に解決しようと名探偵がやってきても、敵はだれが仲間かわからないマフィアだ。名探偵の命が危ないのである。
聞き手のジョン・ハリディが、「奇跡の丘」について、パゾリーニを挑発する。
多くの左翼知識人がこの映画をきらったことはご存知でしょう。スチャスチャは、あなたを対話の地震計と評しました。
パゾリーニがどうとか言う以前に、ひっかかったのが、「スチャスチャ」という名前だ。
スチャスチャ!かわいい名前!
で、よく調べてみると、それはLeonardo Sciasciaのことだと、見当がついてきた。
スチャスチャではなく、レオナルド・シャーシャだ!
と、いうわけで、レオナルド・シャーシャの本を読むことにした。
シシリー、マフィアを扱った本を多数書いており、社会派ミステリーの書き手と言ってもそう間違ってはいない。
本書でも、マフィアがらみのストーリーになっているが、ご当地では、「マフィアなんて実在しない」という沈黙の壁(オメルタ)があって、マフィアなんてのは都市伝説とでも言いかねないスタンスが貫かれているのである。
事件が起こって、それを論理的に解決しようと名探偵がやってきても、敵はだれが仲間かわからないマフィアだ。名探偵の命が危ないのである。
パゾリーニの『王女メディア』を読んだ。
以下、目次
《メーデイアの幻想》ピエル・パオロ・パゾリーニ作(構想)
ピエル・パオロ・パゾリーニ《メーデイア》(会話決定稿)
《メーデイア》制作中に書かれたピエル・パオロ・パゾリーニの詩
注文による祈祷
タルスス遠望
臆説
救霊説的妄想
ANSAへのコミュニケ(国民的=民衆的)
お茶と林檎
カラス
カイセリ地方の午後
太陽についての考察
相対の探究
詩の一支部の内部からの手紙
原書は1970年に出版されており、おさめられた詩が書かれたのは1969年、翻訳は1973年に出ている。
映画を見たときは音楽の特異性に特に衝撃を受けた(たとえば、オルペウスが竪琴をかき鳴らして日本の長唄を歌うとか)のだが、本書ではたとえばシナリオ原案にこんなことが書いてあったりする。
これが、イアーソーンとの出会いで気絶してからは、こうなる。
後に、メーデイアが呪いを行使する段になると、宗教的音楽は復活するのである。
ラスト、メーデイアが叫ぶ「いいえ。もうおっしゃらないで、それ以上、無駄なこと!今となっては、もう何一つ叶いませぬ」は、あの強烈なマリア・カラスから発せられる最後通牒で、僕はこの部分を「なにもかもパーや!」と訳しなおして面白がったりしている。(僕の口癖)
以下、目次
《メーデイアの幻想》ピエル・パオロ・パゾリーニ作(構想)
ピエル・パオロ・パゾリーニ《メーデイア》(会話決定稿)
《メーデイア》制作中に書かれたピエル・パオロ・パゾリーニの詩
注文による祈祷
タルスス遠望
臆説
救霊説的妄想
ANSAへのコミュニケ(国民的=民衆的)
お茶と林檎
カラス
カイセリ地方の午後
太陽についての考察
相対の探究
詩の一支部の内部からの手紙
原書は1970年に出版されており、おさめられた詩が書かれたのは1969年、翻訳は1973年に出ている。
映画を見たときは音楽の特異性に特に衝撃を受けた(たとえば、オルペウスが竪琴をかき鳴らして日本の長唄を歌うとか)のだが、本書ではたとえばシナリオ原案にこんなことが書いてあったりする。
注意しておかなければならないのは、メーデイアの存在には、つねに聖楽(グレゴリオ讃歌か、何かしら同様のもの)が、きわめて機能的に、ついてまわることである。同じように、コルキスの古代的な祭儀を描く冒頭の部分全体を通じて、メーデイアの存在-彼女はその祭儀そのものの頂点をも、またその意識をもなしているのだ-は、この音楽によって強調されている。
これが、イアーソーンとの出会いで気絶してからは、こうなる。
メーデイアはその大きな、聖女の目をあける。彼女は起きあがり、あたりを見まわす。しかし、あたかも彼女から発していたかのような、あのつねに彼女につきまとう音楽は、もはやふたたび鳴り響こうとはしない。すべては押し黙ったまま、ばらばらとなり、不可解なものとなってしまっている。
後に、メーデイアが呪いを行使する段になると、宗教的音楽は復活するのである。
ラスト、メーデイアが叫ぶ「いいえ。もうおっしゃらないで、それ以上、無駄なこと!今となっては、もう何一つ叶いませぬ」は、あの強烈なマリア・カラスから発せられる最後通牒で、僕はこの部分を「なにもかもパーや!」と訳しなおして面白がったりしている。(僕の口癖)
ジョルジュ・ペレックの『家出の道筋』を読んだ。
今まで読んだペレックの本以上に、その「リストマニア」ぶりがうかがえる1冊だった。それは、もうコンセプチュアル・アートを超えて、病的でもある。
以下、目次。
パラシュート降下
ヌーヴォー・ロマンと現実拒否
ロベール・アンテルムあるいは文学の真理
家出の道筋
モーリス・ナドーへの手紙
秋のニョッキあるいはぼくについてのいくつかの質問への答え
なににアプローチするのか
千九百七十四年中にぼくが暴飲・暴食した液状・固形飲食物の目録作成の試み
ヴィラン通り
夢とテクスト
記憶の仕事(フランク・ヴナイユとの対談)
好き、好きじゃない-連の続きに・・・
『人生 使用法』のための四つの図形
冬の旅
いとも聖なる場所
それでも死ぬまでになしておくべきであろういくつかのことども
スティル・ライフ/スタイル・リーフ
ロンドン散策
「奉献(プレサンタシオン)」-ボース平原からシャルトルのノートル=ダム寺院まで
「好き好きじゃない」であげられた項目で、興味深かったものを抜き出して、並べてみると。
好き… パウル・クレー、ヴェルヌ、ソール・スタインバーグ、八角形、テックス・アヴェリー、ビーバー、同時あるいはほとんど同時に異なったうくつかのことをすること、半地下、ジャック・ドゥミ、ミシェル・レリス、馬鹿笑い、『ブヴァールとペキュシェ』、『ドクター・ノオ』、桁の和が9に等しいあらゆる数が9で割り切れることを確かめること、猫、枚挙
好きじゃない… 野菜、ベルイマン、スポーツ、「ありったけ(ア・ゴーゴー)」という言い方、チャーリー・チャップリン、いわゆる「ヌーヴォー」(料理人、哲学者、ロマン主義者、等々)、床屋、シャブロル、ゴダール、マンディアルグ、ブラッドベリー、ジェイムズ・ハドリー・チェイス、(おす!元気かい?スタイルの)「仲間」を量産する輩、「ブランド」商品
好きの項目に「枚挙」って、そのままでは!ひとつひとつにコメントしたい誘惑にかられるが、まあ、やめておこう。
今まで読んだペレックの本以上に、その「リストマニア」ぶりがうかがえる1冊だった。それは、もうコンセプチュアル・アートを超えて、病的でもある。
以下、目次。
パラシュート降下
ヌーヴォー・ロマンと現実拒否
ロベール・アンテルムあるいは文学の真理
家出の道筋
モーリス・ナドーへの手紙
秋のニョッキあるいはぼくについてのいくつかの質問への答え
なににアプローチするのか
千九百七十四年中にぼくが暴飲・暴食した液状・固形飲食物の目録作成の試み
ヴィラン通り
夢とテクスト
記憶の仕事(フランク・ヴナイユとの対談)
好き、好きじゃない-連の続きに・・・
『人生 使用法』のための四つの図形
冬の旅
いとも聖なる場所
それでも死ぬまでになしておくべきであろういくつかのことども
スティル・ライフ/スタイル・リーフ
ロンドン散策
「奉献(プレサンタシオン)」-ボース平原からシャルトルのノートル=ダム寺院まで
「好き好きじゃない」であげられた項目で、興味深かったものを抜き出して、並べてみると。
好き… パウル・クレー、ヴェルヌ、ソール・スタインバーグ、八角形、テックス・アヴェリー、ビーバー、同時あるいはほとんど同時に異なったうくつかのことをすること、半地下、ジャック・ドゥミ、ミシェル・レリス、馬鹿笑い、『ブヴァールとペキュシェ』、『ドクター・ノオ』、桁の和が9に等しいあらゆる数が9で割り切れることを確かめること、猫、枚挙
好きじゃない… 野菜、ベルイマン、スポーツ、「ありったけ(ア・ゴーゴー)」という言い方、チャーリー・チャップリン、いわゆる「ヌーヴォー」(料理人、哲学者、ロマン主義者、等々)、床屋、シャブロル、ゴダール、マンディアルグ、ブラッドベリー、ジェイムズ・ハドリー・チェイス、(おす!元気かい?スタイルの)「仲間」を量産する輩、「ブランド」商品
好きの項目に「枚挙」って、そのままでは!ひとつひとつにコメントしたい誘惑にかられるが、まあ、やめておこう。
パゾリーニの『愛しいひと』を読んだ。
パゾリーニの遺稿をおさめた1冊で、執筆時期は1949年以前のものと推定される。
以下、目次。
二つの伝記的断章と一つの反歌P.P.P.へ/A・ベルトルッチ
不純行為
愛しいひと(アマード・ミオ)
編者ノート/C・ダーンジェリ
おさめられた2つの小説は、どちらもホモセクシュアルな官能に突き動かされる物語になっているが、「不純行為」では、男同士の愛情のなかにあって翻弄、苦悩しながらも理性的たらんとする知的な女性、ディーナ(実在のモデルが存在するらしい)が印象に残る。そして、「愛しいひと」では、同性愛の欲望が空回りし、もどかしく悶えるさまがこれでもか、と描かれる。
少年たちが水遊びなどで遊ぶシーンがまぶしいのは、いつも通り。
後の『あることの夢』や「アッカトーネ」にも通じる作品か。
パゾリーニの遺稿をおさめた1冊で、執筆時期は1949年以前のものと推定される。
以下、目次。
二つの伝記的断章と一つの反歌P.P.P.へ/A・ベルトルッチ
不純行為
愛しいひと(アマード・ミオ)
編者ノート/C・ダーンジェリ
おさめられた2つの小説は、どちらもホモセクシュアルな官能に突き動かされる物語になっているが、「不純行為」では、男同士の愛情のなかにあって翻弄、苦悩しながらも理性的たらんとする知的な女性、ディーナ(実在のモデルが存在するらしい)が印象に残る。そして、「愛しいひと」では、同性愛の欲望が空回りし、もどかしく悶えるさまがこれでもか、と描かれる。
少年たちが水遊びなどで遊ぶシーンがまぶしいのは、いつも通り。
後の『あることの夢』や「アッカトーネ」にも通じる作品か。
パゾリーニの『生命ある若者』を読んだ。
原題には「与太者」という意味合いがあるらしく、この前読んだ『あることの夢』とか、映画「アッカトーネ」と通ずるところのある、与太者の生態を描いた作品。
これでなるほど、と思っていたら、『テオレマ』はぜんぜん違うすごい作品だったし、「王女メディア」も「大きな鳥と小さな鳥」もまた別物。
パゾリーニを寺山修司と比較する対談映像を見たりして、ますます目が離せなくなってきたパゾリーニ、とか言いながら、あとパゾリーニでさらえていないものも少なくなってきた。
原題には「与太者」という意味合いがあるらしく、この前読んだ『あることの夢』とか、映画「アッカトーネ」と通ずるところのある、与太者の生態を描いた作品。
これでなるほど、と思っていたら、『テオレマ』はぜんぜん違うすごい作品だったし、「王女メディア」も「大きな鳥と小さな鳥」もまた別物。
パゾリーニを寺山修司と比較する対談映像を見たりして、ますます目が離せなくなってきたパゾリーニ、とか言いながら、あとパゾリーニでさらえていないものも少なくなってきた。
『テオレマ「定理」』
2011年10月30日 読書パゾリーニの『テオレマ「定理」』を読んだ。
映画テオレマとほぼ同時に出たもので、原作でもなくシナリオでもなく、ノベライズでもない作品。
ごく普通の一般家庭にひとりの男がやってきてはじまる変化。
以下、目次。
第1部
1、データ
2、そのほかのデータ(1)
3、そのほかのデータ(2)
4、そのほかのデータ(3)
5、そのほかのデータ(4)
6、データの陳述、終わり
7、一家の賓客、聖なる性
8、裸になった自分の体の無惨な貧弱さ、そして友の裸体による啓示
9、啓示への抵抗
10、小天使(アンジョリーノ)。彼は来て、また去る
11、自分自身を醜聞の手段として指示すること
12、つまるところは密通なのか?
13、ここではブルジョア少年の新たな入門が始まる
14、無秩序と不服従への再教育
15、《ぼくらが初めて愛する人は…》
16、父親の番である
17、かつて見たこともない朝の光のように、すべては奇蹟的である
18、《世界を簒奪された者》たちの雅びとお道化
19、戸外の朝食
20、父親が死ぬなどと、あり得ることだろうか?
21、病気の男(少年に退歩している)の、健康な青年(大昔の男に昇格している)による儀式
22、恋をしている父親の瞳を通じて
23、男性のねぐらのなかの少女
24、《最初の楽園はオデッタ…》
25、所有主から被所有物に
26、ポー川の岸辺に茂る黄色い葦
27、《ヘブライ人たちは荒野への道を進んだ》
28、ふたたび、天使のお告げ
第1部へのつけたし
死の渇き
近親姦と現実の同一視
生きていることの損失
自己観念の破壊
下層プロレタリアートと神の共謀
第2部
1、帰結(1)-エミリアの場合
2、帰結(2)-オデッタの場合
3、農家にて
4、ここでは、オデッタがどのようにしてついに神を失うか、あるいは裏切ることになるか、述べられる
5、吹出物
6、帰結(3)-ピエトロの場合
7、いらくさ
8、ふたたび、いらくさ
9、才能と技術
10、《確かに、恵まれた家庭の…》
11、ここでは、ピエトロ君がついに神を失う、あるいは裏切ることになる次第が述べられる
12、帰結(4)-ルチーアの場合
13、ここでは、ルチーアもついには神を失う、あるいは裏切るに至るという次第が述べられる
14、浮揚の奇蹟
15、聖性にかんする調査
16、死すべき時が来た
17、帰結(5)-パオロの場合
18、工場の贈与にかんする調査
19、《ああ、裸足よ私の足よ…》
付録
一件書類
映画テオレマとほぼ同時に出たもので、原作でもなくシナリオでもなく、ノベライズでもない作品。
ごく普通の一般家庭にひとりの男がやってきてはじまる変化。
以下、目次。
第1部
1、データ
2、そのほかのデータ(1)
3、そのほかのデータ(2)
4、そのほかのデータ(3)
5、そのほかのデータ(4)
6、データの陳述、終わり
7、一家の賓客、聖なる性
8、裸になった自分の体の無惨な貧弱さ、そして友の裸体による啓示
9、啓示への抵抗
10、小天使(アンジョリーノ)。彼は来て、また去る
11、自分自身を醜聞の手段として指示すること
12、つまるところは密通なのか?
13、ここではブルジョア少年の新たな入門が始まる
14、無秩序と不服従への再教育
15、《ぼくらが初めて愛する人は…》
16、父親の番である
17、かつて見たこともない朝の光のように、すべては奇蹟的である
18、《世界を簒奪された者》たちの雅びとお道化
19、戸外の朝食
20、父親が死ぬなどと、あり得ることだろうか?
21、病気の男(少年に退歩している)の、健康な青年(大昔の男に昇格している)による儀式
22、恋をしている父親の瞳を通じて
23、男性のねぐらのなかの少女
24、《最初の楽園はオデッタ…》
25、所有主から被所有物に
26、ポー川の岸辺に茂る黄色い葦
27、《ヘブライ人たちは荒野への道を進んだ》
28、ふたたび、天使のお告げ
第1部へのつけたし
死の渇き
近親姦と現実の同一視
生きていることの損失
自己観念の破壊
下層プロレタリアートと神の共謀
第2部
1、帰結(1)-エミリアの場合
2、帰結(2)-オデッタの場合
3、農家にて
4、ここでは、オデッタがどのようにしてついに神を失うか、あるいは裏切ることになるか、述べられる
5、吹出物
6、帰結(3)-ピエトロの場合
7、いらくさ
8、ふたたび、いらくさ
9、才能と技術
10、《確かに、恵まれた家庭の…》
11、ここでは、ピエトロ君がついに神を失う、あるいは裏切ることになる次第が述べられる
12、帰結(4)-ルチーアの場合
13、ここでは、ルチーアもついには神を失う、あるいは裏切るに至るという次第が述べられる
14、浮揚の奇蹟
15、聖性にかんする調査
16、死すべき時が来た
17、帰結(5)-パオロの場合
18、工場の贈与にかんする調査
19、《ああ、裸足よ私の足よ…》
付録
一件書類
『おろちー楳図かずおの世界』
2011年10月24日 読書
『おろち-楳図かずおの世界』を読んだ。
映画「おろち」公開に際しての豪華なパンフレット。
実は、この映画、未見なのだが、女優さんや監督、脚本、美術、音楽などの人のインタビューを読んでいると、がぜん見たくなってきた。
後半の楳図かずおの「おろち全作品解説」や、カラーのイラストレーションには堪能させられた。
決して大部ではないのだが、いい感じ。
映画「おろち」公開に際しての豪華なパンフレット。
実は、この映画、未見なのだが、女優さんや監督、脚本、美術、音楽などの人のインタビューを読んでいると、がぜん見たくなってきた。
後半の楳図かずおの「おろち全作品解説」や、カラーのイラストレーションには堪能させられた。
決して大部ではないのだが、いい感じ。
力作。
なのだが、これが本格推理の賞をもらった、といういらぬ事前情報を仕入れていたので、かまえて読んでしまった。
おそらく、この「完全恋愛」の仕掛けは、推理小説のファンであれば、だれでもが見抜くことができて、そして感心するものだと思う。
ここが、一般小説の読み手が推理小説を読むときとの違いだと思う。
推理小説のファンは、ことの真相、犯人やトリックが解決以前にわかったとしても、それで評価を下げることはない。だから、「あの推理小説、解決の前に真相がわかってしまったので、つまらない」とか言う人がいたら、それは疑いもなく、推理小説のドシロウトなのである。推理小説のファンは、その作品がいかにうまく作られているかを話題にすることはあっても、読者である自分の手柄話をすることはないのだ。
と、いらぬ話題を書いてみた。
いずれ、この項、書き直します。
なのだが、これが本格推理の賞をもらった、といういらぬ事前情報を仕入れていたので、かまえて読んでしまった。
おそらく、この「完全恋愛」の仕掛けは、推理小説のファンであれば、だれでもが見抜くことができて、そして感心するものだと思う。
ここが、一般小説の読み手が推理小説を読むときとの違いだと思う。
推理小説のファンは、ことの真相、犯人やトリックが解決以前にわかったとしても、それで評価を下げることはない。だから、「あの推理小説、解決の前に真相がわかってしまったので、つまらない」とか言う人がいたら、それは疑いもなく、推理小説のドシロウトなのである。推理小説のファンは、その作品がいかにうまく作られているかを話題にすることはあっても、読者である自分の手柄話をすることはないのだ。
と、いらぬ話題を書いてみた。
いずれ、この項、書き直します。
『女脳~ひらめきと勝負強さの秘密』、『女流名人・倉敷藤花 里見香奈 好きな道なら楽しく歩け』
2011年10月11日 読書『チェルノブイリ原発事故』
2011年10月6日 読書
クリスタ・ヴォルフの『チェルノブイリ原発事故』を読んだ。1987年。
ドキュメンタリーやルポルタージュではなく、小説。
サブタイトルに「ある一日の報告」とある。
本書には、この小説と、「わたしのクリスタ・ヴォルフ論」として、3人の人が文章を寄せている。
深い霧の中で-ヴォルフ『チェルノブイリ原発事故』を読む/高木仁三郎
生命懸けの怠慢/鎌田慧
メクレンブルクの青い空/藤井啓司
さて、本編。
チェルノブイリでの原発事故後の日々の生活にしのびよる不安。
惨状を描くのではなく、事故は遠い場所で起こっていて、しかし放射能の脅威が確実に日々の生活をおかしていく、漠然とした不安が描かれる。
福島以来の日本の現実を描いているかのようなリアリティーがある。
と、いうことは、チェルノブイリ以降、この小説が書かれてからも人々はまったく同じことを繰り返しているわけだ。
この小説は、原発事故後の日常と並行して、脳外科手術を受ける弟の経過も追っている。単純に図式化すれば、人間と科学のありようを2つの側面から見、また、分割できないものとされてきた「自己」と「原子」の分裂を絡ませて物語を編んでいる。
ラストでは、今まで日常を比較的淡々と描いてきた著者の思いが爆発する。
本書の原題は「故障」という単語らしい。大惨事に至ってもそれを「故障」と称する科学者やマスコミを告発するような意図を持ったタイトルだ。
本書で描かれるように、ひとたび大惨事が起こってしまっても、人びとの日々の生活や、悩み、苦しみは、ちっともリセットされない。自分の苦境を打破するために、大惨事を希望しても、苦境は残ったままで、大惨事だけが追加されてしまうのだ。
そういえば、そんなことが描かれた映画、最近、見たな、と思い出した。
今関あきよし監督の「カリーナの林檎」だ。
カリーナの林檎もチェルノブイリをテーマにしているが、大惨事を描くのではなく、既に以前から存在していた家族的な問題をひきずったままで、それにチェルノブイリが加算されるのだ。
もうどうにも突破口がない八方ふさがりの状況に立ち向かうにあたって、少女カリーナは、実名ではない「カリーナ」の名前を得て、物語のフィールドで戦おうとする。
結局、少女の戦いが、刀折れ矢尽きたのかどうかは、人びとの物語力によっているのである。
ヴォルフのこの小説でも、それが最初に「登場人物は、いずれも実在の人物ではない。すべて作者の創作である」と断っており、読者の物語力に訴えかけようとしている。
同じ過ちを繰り返して平然としている現実を打破するためには、物語こそが有効なのである。
ドキュメンタリーやルポルタージュではなく、小説。
サブタイトルに「ある一日の報告」とある。
本書には、この小説と、「わたしのクリスタ・ヴォルフ論」として、3人の人が文章を寄せている。
深い霧の中で-ヴォルフ『チェルノブイリ原発事故』を読む/高木仁三郎
生命懸けの怠慢/鎌田慧
メクレンブルクの青い空/藤井啓司
さて、本編。
チェルノブイリでの原発事故後の日々の生活にしのびよる不安。
惨状を描くのではなく、事故は遠い場所で起こっていて、しかし放射能の脅威が確実に日々の生活をおかしていく、漠然とした不安が描かれる。
福島以来の日本の現実を描いているかのようなリアリティーがある。
と、いうことは、チェルノブイリ以降、この小説が書かれてからも人々はまったく同じことを繰り返しているわけだ。
予想どおり、世論は二派に分かれ、そのどちらに属するかによって、専門家の意見もちがってきています。オプチミスト側の専門家は、まさか、炉心溶融はないですよと言いましたが、ペシミスト側の専門家は、いや、いや、どういたしまして、それだって無視することはできませんと主張しました。
別々の局に合わせてある小型ラジオも大型ラジオも、時報ごとに声を合わせて、生野菜は食べるな、子供に新しい牛乳を与えるな、と言い続けていますし、ヨウ素131という新しい危険物の名前が広まっています。わたしたちの身体で、放射性ヨウ素の蓄積にもっとも敏感に反応する器官の一つが、甲状腺であることがわかったのです。中には先ゆきとんでもないことを考える人もいるもので、ある放送局のある町では、きのうのうちに、町じゅうの薬局のヨウ素錠剤の在庫がすっかり買い占められたそうです。わたしの聞いたところでは、ヨウ素錠剤は飲む必要もないし、飲んでもむだだそうです。
母親たちはラジオの前に座って、新しい言葉を憶えようと努力します。ベクレル。そして-自然の結合の深奥を認識し、しかもそれを利用しようとする畏れを知らぬ科学者たちの-それに対する解説。半減期。母親たちはきょう、学んでいます。ヨウ素131。セシウム。そして、先の科学者たちとは意見を異にするほかの科学者たちの、それにたいする解説。彼らは怒り狂い、途方にくれています。これから、これらすべてがわれわれの頭上に降ってくるのです、と彼らは述べています。放射性物質を含んだもの、たとえば雨などといっしょに-
平和に安らっている原子を追い立てた男たちは、たしかに、みんなのために永遠に十分なエネルギーを、というユートピアにみちびかれていたのです。彼らには、手遅れにならないうちに、ほかの考え方に切り換えることはできなかったのでしょうか?彼らと反対の意見を持つ人びととわたしが初めて関わりをもったのは、いつだったでしょう?ちょっと待って。そう、70年代の初めでした。発電所の名前はヴュールといい、結局それは建設されませんでした。わたしたちの手に、原子エネルギーの「平和」利用の危険について訴える最初の資料を押し込んだ若い人びとは、嘲笑され、取り締まられ、処罰されました。自分たちの仕事を、希望的に言えば自分たちのユートピアを弁護する科学者たちも、彼らを笑いました。まさに「怪物」ですね?
この小説は、原発事故後の日常と並行して、脳外科手術を受ける弟の経過も追っている。単純に図式化すれば、人間と科学のありようを2つの側面から見、また、分割できないものとされてきた「自己」と「原子」の分裂を絡ませて物語を編んでいる。
ラストでは、今まで日常を比較的淡々と描いてきた著者の思いが爆発する。
深夜、泣き声がしました。わたしはびっくりして、とび起きました。完全な怪物だ!と叫んでいます。その声は、ずっと前からしていたのでした。しばらくたってから、ようやく気づきました。それはわたしの声でした。わたしはベッドに座って大声で泣きました。わたしの顔は、涙でくしゃくしゃになっていました。わたしは夢を見ていたのです。夢の中では、ちょうど目の前に迫るほど巨大な月が不気味な形にくずれて、あっというまに地平線の彼方に沈み、そのあとの暗黒の夜空に、死んだ母の大きな写真が張りつけられていました。わたしは大声で叫びました。
この地球に別れを告げることになるのでしょうか?そうなったら、あなた、さぞ、つらいことでしょうね。
本書の原題は「故障」という単語らしい。大惨事に至ってもそれを「故障」と称する科学者やマスコミを告発するような意図を持ったタイトルだ。
本書で描かれるように、ひとたび大惨事が起こってしまっても、人びとの日々の生活や、悩み、苦しみは、ちっともリセットされない。自分の苦境を打破するために、大惨事を希望しても、苦境は残ったままで、大惨事だけが追加されてしまうのだ。
そういえば、そんなことが描かれた映画、最近、見たな、と思い出した。
今関あきよし監督の「カリーナの林檎」だ。
カリーナの林檎もチェルノブイリをテーマにしているが、大惨事を描くのではなく、既に以前から存在していた家族的な問題をひきずったままで、それにチェルノブイリが加算されるのだ。
もうどうにも突破口がない八方ふさがりの状況に立ち向かうにあたって、少女カリーナは、実名ではない「カリーナ」の名前を得て、物語のフィールドで戦おうとする。
結局、少女の戦いが、刀折れ矢尽きたのかどうかは、人びとの物語力によっているのである。
ヴォルフのこの小説でも、それが最初に「登場人物は、いずれも実在の人物ではない。すべて作者の創作である」と断っており、読者の物語力に訴えかけようとしている。
同じ過ちを繰り返して平然としている現実を打破するためには、物語こそが有効なのである。
バーナード・ベケットの『創世の島』を読んだ。
本についてたあらすじを書いてしまうと。
この後に続く、驚天動地の云々という惹句は、はっきり言って、言いすぎなので、とりあえずストーリー部分だけ。
全編が、この口頭試問のやりとりと、アナックスが用意した再現映像(ホログラム)と、試験官側が見せる、実際に何が起こったかの映像で構成されている。
口頭試問のやりとりは、まるですべてがFになるの冒頭みたいな緊張感があるし、映像で展開される、「人間と人工知性」の問題は非常にスリリング。
全体を通して、推理小説の謎ときの部分だけで出来上がった作品みたいなものなので、これは興奮して読んだ。
いくつか引用を。
人工知能アートと、人間アダムの会話。
アダムのうまい主張に、それを切り返すさらにうまいアートの応酬。
しかし、ここでアダムが展開した「おまえは人間じゃなくて機械!」の理屈を見ていると、いわゆるネットの住人や、一般人の世論が人工の部類に近いように思えてならない。
人工知能アートの言葉
う~む。考えさせられる~。
本についてたあらすじを書いてしまうと。
時は21世紀末。世界大戦と疫病により人類は死滅した。世界の片隅の島に大富豪プラトンが建設した「共和国」だけを残して。彼は海上に高い隔壁を作り、外の世界からこの国を物理的に隔離することで、疫病の脅威から逃れたのだ。同時に彼は、労働者、戦士、技術者、特権階級である哲学者で構成する社会を築き上げる。唯一生き残ったこの島は、人類の新たなる創世をもたらすと思われた。アダム・フォードという兵士が、漂流者の少女を助けるまでは・・・。
そしていま、ひとりの少女がアカデミーの入学試験として、4時間にわたる口頭試問に挑もうとしていた。彼女の名はアナクシマンドロス。通称アナックス。試験のテーマは「アダム・フォード」。無感情な3人の試験官の前で、彼女は「共和国」建国の経緯や、その社会構造、歴史、AI(人工知性)の問題をつぎつぎに解き明かしてゆく。
この後に続く、驚天動地の云々という惹句は、はっきり言って、言いすぎなので、とりあえずストーリー部分だけ。
全編が、この口頭試問のやりとりと、アナックスが用意した再現映像(ホログラム)と、試験官側が見せる、実際に何が起こったかの映像で構成されている。
口頭試問のやりとりは、まるですべてがFになるの冒頭みたいな緊張感があるし、映像で展開される、「人間と人工知性」の問題は非常にスリリング。
全体を通して、推理小説の謎ときの部分だけで出来上がった作品みたいなものなので、これは興奮して読んだ。
いくつか引用を。
人工知能アートと、人間アダムの会話。
「人工の意識なんてものは存在しない」
「わたしには意識があります」
「おまえには意識なんかない」アダムの目には強い確信の炎が燃えている。「おまえはただの複雑な電気のスイッチの集まりだ。俺が音をだすと、それがおまえのデータバンクに入って、記録されている言葉と照合される。そしておまえのプログラムがオートメ化された反応を選ぶ。だからなんだ?俺が話しかけると、おまえは音をだす。俺が壁を蹴ると、壁は音をだす。どこがちがうんだ?壁にも意識があるとでもいうつもりか?」
「壁に意識があるかどうかは知りません」アートは答えた。「きいてみたらどうですか?」
アダムのうまい主張に、それを切り返すさらにうまいアートの応酬。
しかし、ここでアダムが展開した「おまえは人間じゃなくて機械!」の理屈を見ていると、いわゆるネットの住人や、一般人の世論が人工の部類に近いように思えてならない。
「俺は、賢い金属のかたまりより、愚かな人間のほうがいいね」アダムはいった。
「あなたはよくそういいますね。なぜか金属のほうが劣っているようないいかたをする」
「使い途によるな」
「わたしの目的にはぴったりです」
「だな」
「でもおまえはただの珪素(シリコン)だ」
「あなたはただの炭素です」アートはめげていない。「いつから周期表が差別の基準になったのですか?」
「俺の偏見は正当化できると思うけどね」
人工知能アートの言葉
あなたたちは“思考”をもっていることを自慢します。まるで自分がつくったものであるかのようにね。しかし、“思考”は寄生体なのです。なぜ、進化は物質的なものにだけ起こると考えるのですか?進化は媒体を選びません。どちらが最初なのでしょうか、心ですか、それとも心という“思考”ですか?
「そのちがいは、やっぱり考えてしゃべっているかどうか、意図的に言葉を選んでいるかどうかだ。だから、おまえは俺とはちがうんだ。おまえのよく動くくちびるは、俺の脈打つ心臓とおなじさ。機械だ。ある目的があってつくられてはいるが、意思はない」
アダムの視線をうけとめていたアートの顔に、ゆっくりと笑みがひろがっていった。
「この議論の問題点は」とアートはアダムに語りかけた。「あなたの立場から見ればそう見えるといっているにすぎない、という点です」
「話をもっと単純化したらどうなる?たとえば俺が写真みたいに正確な記憶のもち主で、何千もの完璧なフレーズを暗記しているとしたら?もしそうなら、俺が知らない言葉で話しかけられても、適切なフレーズを選んで返事できる。その場合はどうなんだ?」アダムはふりむいて、答えを待った。
アートはゆっくりとアダムのほうに進んでいった。「わたしはそういう存在だと思っているのですか?よくできたフレーズ帳だと?」
「そう思ったってかまわないだろ?」
「ではなぜ、これまであなたが会った人たちが、みんなそれとおなじ仕組みを使っているとは思わないのですか?」
う~む。考えさせられる~。
『青い外套を着た女』
2011年9月28日 読書
横溝正史の『青い外套を着た女』を読んだ。
以下、収録作品。
「白い恋人」(オール読物、昭和12年5月増刊)
「青い外套を着た女」(サンデー毎日、昭和12年7月1日)
「クリスマスの酒場」(サンデー毎日、昭和13年、1月1日)
「木乃伊の花嫁」(富士、昭和13年2月増刊)
木乃伊の口紅/したたる血潮/屋根裏の鬼/湖畔の怪/白髪の紳士/洞窟での出来事/恐ろしき真相
「花嫁富籤」(婦人倶楽部、昭和13年3月)
「仮面舞踏会」(オール読物、昭和13年6月増刊)
「佝僂(せむし)の樹」(サンデー毎日、昭和13年6月5日)
ことづけ/花かんざし/怪しのもの/狂える呪詛(のろい)/瘤のある桜/人食い桜
「飾窓の中の姫君」(モダン日本、昭和13年8月)
「覗機械倫敦綺譚(のぞきからくりろんどんきだん)」(新青年、昭和10年2月増刊。昭和10年『鬼火』初版に収録)
1、相乗車は地獄と極楽境界のこと
2、灯に焦がす翼は蛾の無分別
3、片棒を担ぐ女に蟻の一穴
4、子に迷う親の心は六道の闇
雑誌発表後、はじめて本に収録された作品集。(昭和53年当時。最後の1つを除く)
埋もれるべくして埋もれていた作品、というわけでもなく、今読んでもじゅうぶんに面白くて、横溝正史は多作だからこれらの作品が口にのぼることも少ないが、寡作な作家の作品だったら、代表作になっていてもおかしくないレベルである。これはすごいことだ。因縁話みたいなものが多いのは時代を思わせて、興味深い。
また、意外な真相やどんでん返しが、それを見破るとかわかったとかいうことを抜きにして、物語の面白みになっている。
以下、収録作品。
「白い恋人」(オール読物、昭和12年5月増刊)
「青い外套を着た女」(サンデー毎日、昭和12年7月1日)
「クリスマスの酒場」(サンデー毎日、昭和13年、1月1日)
「木乃伊の花嫁」(富士、昭和13年2月増刊)
木乃伊の口紅/したたる血潮/屋根裏の鬼/湖畔の怪/白髪の紳士/洞窟での出来事/恐ろしき真相
「花嫁富籤」(婦人倶楽部、昭和13年3月)
「仮面舞踏会」(オール読物、昭和13年6月増刊)
「佝僂(せむし)の樹」(サンデー毎日、昭和13年6月5日)
ことづけ/花かんざし/怪しのもの/狂える呪詛(のろい)/瘤のある桜/人食い桜
「飾窓の中の姫君」(モダン日本、昭和13年8月)
「覗機械倫敦綺譚(のぞきからくりろんどんきだん)」(新青年、昭和10年2月増刊。昭和10年『鬼火』初版に収録)
1、相乗車は地獄と極楽境界のこと
2、灯に焦がす翼は蛾の無分別
3、片棒を担ぐ女に蟻の一穴
4、子に迷う親の心は六道の闇
雑誌発表後、はじめて本に収録された作品集。(昭和53年当時。最後の1つを除く)
埋もれるべくして埋もれていた作品、というわけでもなく、今読んでもじゅうぶんに面白くて、横溝正史は多作だからこれらの作品が口にのぼることも少ないが、寡作な作家の作品だったら、代表作になっていてもおかしくないレベルである。これはすごいことだ。因縁話みたいなものが多いのは時代を思わせて、興味深い。
また、意外な真相やどんでん返しが、それを見破るとかわかったとかいうことを抜きにして、物語の面白みになっている。
『盤上の海、詩の宇宙』
2011年9月27日 読書
羽生善治と吉増剛造による『盤上の海、詩の宇宙』を読んだ。
以下、目次。
はじめに=羽生善治
第1局 将棋のコスモロジー(1996年9月)
盤面を見つめる楽しみ/さまざまな時間の流れ/白い時間、灰色の時間/盤面に大海原を感じるとき/将棋の大きさ/相手によって変化する棋風/過去の棋譜のとらえ方/古典をどう超えるか/将棋は表裏に言葉を背負っている/「角」は牛の角のイメージ/チェスと将棋の違い/文学と遊びの世界/アイルトン・セナへの共感/駒のスピード、効率、展開/視線が180度変わる/不思議な深さをもつ遊びの場/将棋はやはり「指す」もの/「歩」にひとつの原点があった/旅するときの持ち物/歩きながら書く/なんで「駒」と呼ぶのか/「棋譜」と「詩譜」/閃きとジャスト・ミート/対局に近い頭脳の動きで話す/先が見過ごせる場所/極限まで柔らかい粘土/朗読は無限の読み直し/忘れることの大事さ/文字を打ち込む/
第2局 われらシジフォスのように(1996年12月)
初めて将棋を指したとき/初めて詩を書いたとき/盤に向かって潜る/心が静かになるのを待つ/原初の心の状態に戻す/「経験」を積むことの意味/対座することの喜び/心にまっすぐ訴えかけてくる言葉/詩の宇宙の向こう側で/「歩」は将棋の「皮膚」/夢の痕跡を取りかえす/将棋は奥深い「書物」を読むこと/愛着を不断に捨てていくこと/相手の視線で見てようやくわかること/シジフォスの喜びの瞬間/「反復」からだけ得られるもの/時間のもっている不思議/漠然とした不安と狂気/狂気の可能性を逃げつつ受け入れる/日本語の多層性、大文明の血脈/時間の非可逆性/なぜ詩を書くのか、誰に向かって書くのか/イメージを喚起する力/詩が生成する過程/言葉は時代の断裂面をかかえる/不安の層が堆積する/言葉に対する根源的不安/セナ-加速していく世界の極限を見たひと/駒が笑う/未完の作品が理想/ほんとうに書きたい作品/「言葉に負ける」とは/言葉の自立的な運動と詩の言葉/詩の壮大な戦略/歴史=定跡を覆す力/将棋はどこへ行くのか/ふたたび“反復”について/先が見えない不安と思考の反復/螺旋状に考える/古代の井戸で/献詩による結び/
羽生さんへの手紙=吉増剛造
通訳あとがき=柳瀬尚紀
タイトルにもあるように、羽生の語る将棋観が、ハチワンダイバーのもとになったんじゃないか、と思う。
「なんというんですかね、盤に向かって潜っていくというか、のめり込んで考えていくというか、ほんとうになにか海の中に潜っていくというような感じになります。その潜っていくような感じが深ければ深いほど、時間の流れもあっという間に流れていくというか、意識というものがなくなっていくというか、そういうことはあります」
将棋を指す人にとっては、盤に潜る、という感覚は特別奇矯なものではないが、こうして語れる棋士は数少ないと思う。
以下、目次。
はじめに=羽生善治
第1局 将棋のコスモロジー(1996年9月)
盤面を見つめる楽しみ/さまざまな時間の流れ/白い時間、灰色の時間/盤面に大海原を感じるとき/将棋の大きさ/相手によって変化する棋風/過去の棋譜のとらえ方/古典をどう超えるか/将棋は表裏に言葉を背負っている/「角」は牛の角のイメージ/チェスと将棋の違い/文学と遊びの世界/アイルトン・セナへの共感/駒のスピード、効率、展開/視線が180度変わる/不思議な深さをもつ遊びの場/将棋はやはり「指す」もの/「歩」にひとつの原点があった/旅するときの持ち物/歩きながら書く/なんで「駒」と呼ぶのか/「棋譜」と「詩譜」/閃きとジャスト・ミート/対局に近い頭脳の動きで話す/先が見過ごせる場所/極限まで柔らかい粘土/朗読は無限の読み直し/忘れることの大事さ/文字を打ち込む/
第2局 われらシジフォスのように(1996年12月)
初めて将棋を指したとき/初めて詩を書いたとき/盤に向かって潜る/心が静かになるのを待つ/原初の心の状態に戻す/「経験」を積むことの意味/対座することの喜び/心にまっすぐ訴えかけてくる言葉/詩の宇宙の向こう側で/「歩」は将棋の「皮膚」/夢の痕跡を取りかえす/将棋は奥深い「書物」を読むこと/愛着を不断に捨てていくこと/相手の視線で見てようやくわかること/シジフォスの喜びの瞬間/「反復」からだけ得られるもの/時間のもっている不思議/漠然とした不安と狂気/狂気の可能性を逃げつつ受け入れる/日本語の多層性、大文明の血脈/時間の非可逆性/なぜ詩を書くのか、誰に向かって書くのか/イメージを喚起する力/詩が生成する過程/言葉は時代の断裂面をかかえる/不安の層が堆積する/言葉に対する根源的不安/セナ-加速していく世界の極限を見たひと/駒が笑う/未完の作品が理想/ほんとうに書きたい作品/「言葉に負ける」とは/言葉の自立的な運動と詩の言葉/詩の壮大な戦略/歴史=定跡を覆す力/将棋はどこへ行くのか/ふたたび“反復”について/先が見えない不安と思考の反復/螺旋状に考える/古代の井戸で/献詩による結び/
羽生さんへの手紙=吉増剛造
通訳あとがき=柳瀬尚紀
タイトルにもあるように、羽生の語る将棋観が、ハチワンダイバーのもとになったんじゃないか、と思う。
「なんというんですかね、盤に向かって潜っていくというか、のめり込んで考えていくというか、ほんとうになにか海の中に潜っていくというような感じになります。その潜っていくような感じが深ければ深いほど、時間の流れもあっという間に流れていくというか、意識というものがなくなっていくというか、そういうことはあります」
将棋を指す人にとっては、盤に潜る、という感覚は特別奇矯なものではないが、こうして語れる棋士は数少ないと思う。