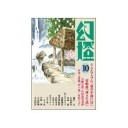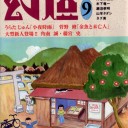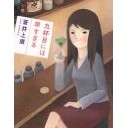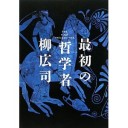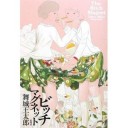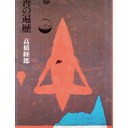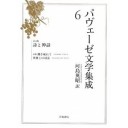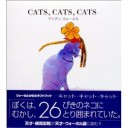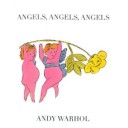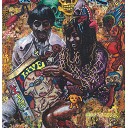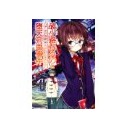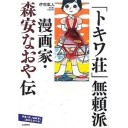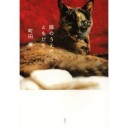『幻燈』3、4、5、9、10号
2011年6月24日 読書
『幻燈』の3、4、5、9、10号を読んだ。
漫画と文章で構成されており、ふだんなら飛ばしてしまう文章の部分も、この『幻燈』に関しては、ほぼ全部読んでいる。文章の部分が少ないっていうのもあるが、あまりなじみのない漫画家のひととなりがわかるので、漫画がより一層楽しめるのだ。
個性やテーマは、大手の漫画雑誌のものとは、ぜんぜん違うのである。
面白くて好きなのである。
以下、目次。
『幻燈』3号
膨らむ闇/ つげ忠男
君のいた海/菅野ヲさむ
鈴懸の径/うらたじゅん
みち草/山田勇男
死ぬる感覚/新谷成唯
絵コンテ「会津の釣り宿」/つげ義春
創作ノートから/菅野ヲさむ
韓国映画の思い出/渡辺一衛
観光地盛衰記 二 吉見百穴と岩窟ホテル/
山下菊二の遺志 『構造』の批判をめぐって/古田香
続・美代子田川気分/安部慎一
トカゲ/三橋乙揶
浮浪漫歩 シーサイドホテル/うらたじゅん
浮世一夜/うらたじゅん
海女の季節/つげ忠男
女の子はミステリー/秋野すすき(目次に載ってなくて、かわいそう!)
VOICE/声の存在/新谷成唯
『幻燈』4号
妻の肖像/菅野修
眠れる海の城/うらたじゅん
土冷しコーラ/新谷成唯
長男/西野空男
よくある話/永井サク
対談『夜行』が誕生するまで/つげ義春・高野慎三。司会 久保隆(本文と目次でタイトルの表記が違った。これは本文の表記)
つげ義春原作 映画「蒸発旅日記」 山田勇男監督インタビュー
映画「蒸発旅日記」撮影見学記/編集部
映画「蒸発旅日記」撮影用絵コンテ/山田勇男
紅燈夜曲 哀愁の町に星が降る 桃色月夜篇/山田勇男
さっちゃんの方程式/秋野すすき(なぜ目次に載せてもらえない)
RANDEN/うらたじゅん
疾走する<死>という物語 鈴木清順監督『ピストルオペラ』論/久保隆
映画「蝶の舌」の彼方へ スペイン内戦、ユーゴ内戦、そして9・11/古田香
テレビの上の女/新谷成唯
風のつぶやき/高橋太
「百貨店/転落」/西野空男
病窓紀行/うらたじゅん
『幻燈』5号
川をのぼる魚 虹色の銃/うらたじゅん
渡難/うらたじゅん
五月の風の下/うらたじゅん
【特集うらたじゅんの世界】
インタビュー「ささやかな喜びを大切に、のんびりマイペースで描いていきたい」(『眞夏の夜の二十面相』発行まで/マンガとの出会いとそこから離れて/放浪とその後)
物語ること、それは去りゆくものを識ること/石川淳志
マンガの女神はいるのか/片桐慎二
うらたじゅん試論―過去へと向かうまなざし/宮岡蓮二
猫かぶりな子/大畑くみ
うらたじゅんの中之島図書館/中尾務
小ママじゅんちゃん/川崎彰彦
不思議への案内人/南陀楼綾繁
うらたじゅんさんと会うたびに/菊池敏弘
書評・『眞夏の夜の二十面相』再録
河瀬直美の本棚より/河瀬直美
懐かしく淡い子供時代にひたる/川本三郎
遠い記憶の場所から紡ぎ出された物語/久保隆
こんな初恋したかった/畠中理恵子
自由への情熱/権藤晋
凝視する眼差しの徹底性―『幻燈』うらたじゅん諸作品考/ちだきよし
「時」のおもかげを描く―うらたじゅん小論/梶井純
うらたじゅんさん作品集に寄せて/つげ忠男
山犬の子/菅野修
「ねじ式」から「夢の散歩」へ 北冬書房の三十年をふりかえって/つげ義春・高野慎三 司会・久保隆
(「通夜」を発表した頃/『迷路』『忍風』貸本マンガの時代/柳田國男、椎名麟三、梅崎春生を話題に/『漫画主義』でのつげ義春特集/「ねじ式」の出自をめぐって/「ねじ式」の評価について/不安定な状態から蒸発へ/幻燈社の『つげ義春初期短編集』/林静一『紅犯花』、片山健『美しい日々』/「つげ義春以後」というマンガ表現/「夢の散歩」の衝撃力/喫茶店を開業しようと・・・)
〔特集 山下敦弘〕
師弟対談 映画「どんてん生活」から「リアリズムの宿」まで/中島貞夫・山下敦弘 聞き手・編集部+うらたじゅん
(「どんてん生活」のキャラクター/自主映画の枠をどう越えるか/感動したアメリカン・ニューシネマ/「リアリズムの宿」を撮り終えて)
映画「リアリズムの宿」をめぐって
1 風景の感情/久保隆
2 雪の日本海/梶葉子
乙女チャンラ/河内遥
ひまつぶし/河内遥
はい せつせつ はん すうすう/河内遥
トンネル画廊/西野空男
蒸発日記 原案・つげ義春「蒸発旅日記」より/西野空男
昨日の夢/西野空男
『幻燈』9号
小夜時雨/うらたじゅん
或る押入れ頭男の話/藤宮史
金魚と未亡人/菅野修
対談 夢のなかで、夢のそとで(常識を逸脱したようなものを描きたい)/原マスミ・山田勇男
古書市へ行こうよ/角南誠
耕運機にカラス/斎藤種魚(目次には「耕耘機とカラス」表記)
椅子を並べる/おんちみどり
街道/永井サク
hex/海老原健悟
散歩/木下竜一
きしみ 骨が鳴る 誰かが笑う/山羊タダシ
映画『実録・連合赤軍あさま山荘への道程』考/久保隆
野田昌宏さんを偲ぶ/高野慎三
瀬沼孝明さんのこと/編集部
水音/瀬沼孝明
夢精/山羊タダシ
いちばん柔らかい肉/海老原健悟
インチキ/木下竜一
葉っぱの亡い花/ネズ実
漫画おんち/おんちみどり
武蔵野/角南誠
『幻燈』10号
夏の午後には/うらたじゅん
性と生活/菅野修
或る押入れ頭男の話・箱舟/藤宮史
彼女の思い出/角南誠
背中/片桐慎二
古本海岸/おんちみどり
人魚/山田勇男
街 ―花ははやく散れ雨の叙事/小林坩堝
さよなら夢幻島/小林坩堝
タスケ/斎藤種魚
灰と煙/山羊タダシ
或る押入れ頭男の話・終章-Ⅰ/藤宮史
無意識の世界と夢 少年王者舘「夢+夜」にふれて 対談(演劇の構造と夢の特殊性/なぜ1954年なのか?/もうだれも見ていない/しでかしてしまったこと/技術的に巧みになった)/天野天街・山田勇男
アクチュアリティと無化 少年王者舘「夢+夜」を観て/金ゐ國許
映像表現とマンガ表現 鼎談(映像作家的な映像作品/空と雲と地平線/言葉へのコンプレックス/「垣間みた」という快楽/マンガとの関わり/つげ義春作品との出会い/ダヴィンチと任侠映画)/山田勇男・ネズ実・角南誠
高橋和己の現在 対談(なぜ高橋和己なのか/「孤立無援の思想」/情況へのリアクション/懐古趣味への誘惑/精神的な飢餓状態)/小林坩堝・山羊タダシ 司会 編集部
きれ間/ネズ実
香り/海老原健悟
行ってきます/永井サク
意識/木下竜一
走馬燈/西野空男
三人/甲野酉
嵐々電々/うらたじゅん
漫画と文章で構成されており、ふだんなら飛ばしてしまう文章の部分も、この『幻燈』に関しては、ほぼ全部読んでいる。文章の部分が少ないっていうのもあるが、あまりなじみのない漫画家のひととなりがわかるので、漫画がより一層楽しめるのだ。
個性やテーマは、大手の漫画雑誌のものとは、ぜんぜん違うのである。
面白くて好きなのである。
以下、目次。
『幻燈』3号
膨らむ闇/ つげ忠男
君のいた海/菅野ヲさむ
鈴懸の径/うらたじゅん
みち草/山田勇男
死ぬる感覚/新谷成唯
絵コンテ「会津の釣り宿」/つげ義春
創作ノートから/菅野ヲさむ
韓国映画の思い出/渡辺一衛
観光地盛衰記 二 吉見百穴と岩窟ホテル/
山下菊二の遺志 『構造』の批判をめぐって/古田香
続・美代子田川気分/安部慎一
トカゲ/三橋乙揶
浮浪漫歩 シーサイドホテル/うらたじゅん
浮世一夜/うらたじゅん
海女の季節/つげ忠男
女の子はミステリー/秋野すすき(目次に載ってなくて、かわいそう!)
VOICE/声の存在/新谷成唯
『幻燈』4号
妻の肖像/菅野修
眠れる海の城/うらたじゅん
土冷しコーラ/新谷成唯
長男/西野空男
よくある話/永井サク
対談『夜行』が誕生するまで/つげ義春・高野慎三。司会 久保隆(本文と目次でタイトルの表記が違った。これは本文の表記)
つげ義春原作 映画「蒸発旅日記」 山田勇男監督インタビュー
映画「蒸発旅日記」撮影見学記/編集部
映画「蒸発旅日記」撮影用絵コンテ/山田勇男
紅燈夜曲 哀愁の町に星が降る 桃色月夜篇/山田勇男
さっちゃんの方程式/秋野すすき(なぜ目次に載せてもらえない)
RANDEN/うらたじゅん
疾走する<死>という物語 鈴木清順監督『ピストルオペラ』論/久保隆
映画「蝶の舌」の彼方へ スペイン内戦、ユーゴ内戦、そして9・11/古田香
テレビの上の女/新谷成唯
風のつぶやき/高橋太
「百貨店/転落」/西野空男
病窓紀行/うらたじゅん
『幻燈』5号
川をのぼる魚 虹色の銃/うらたじゅん
渡難/うらたじゅん
五月の風の下/うらたじゅん
【特集うらたじゅんの世界】
インタビュー「ささやかな喜びを大切に、のんびりマイペースで描いていきたい」(『眞夏の夜の二十面相』発行まで/マンガとの出会いとそこから離れて/放浪とその後)
物語ること、それは去りゆくものを識ること/石川淳志
マンガの女神はいるのか/片桐慎二
うらたじゅん試論―過去へと向かうまなざし/宮岡蓮二
猫かぶりな子/大畑くみ
うらたじゅんの中之島図書館/中尾務
小ママじゅんちゃん/川崎彰彦
不思議への案内人/南陀楼綾繁
うらたじゅんさんと会うたびに/菊池敏弘
書評・『眞夏の夜の二十面相』再録
河瀬直美の本棚より/河瀬直美
懐かしく淡い子供時代にひたる/川本三郎
遠い記憶の場所から紡ぎ出された物語/久保隆
こんな初恋したかった/畠中理恵子
自由への情熱/権藤晋
凝視する眼差しの徹底性―『幻燈』うらたじゅん諸作品考/ちだきよし
「時」のおもかげを描く―うらたじゅん小論/梶井純
うらたじゅんさん作品集に寄せて/つげ忠男
山犬の子/菅野修
「ねじ式」から「夢の散歩」へ 北冬書房の三十年をふりかえって/つげ義春・高野慎三 司会・久保隆
(「通夜」を発表した頃/『迷路』『忍風』貸本マンガの時代/柳田國男、椎名麟三、梅崎春生を話題に/『漫画主義』でのつげ義春特集/「ねじ式」の出自をめぐって/「ねじ式」の評価について/不安定な状態から蒸発へ/幻燈社の『つげ義春初期短編集』/林静一『紅犯花』、片山健『美しい日々』/「つげ義春以後」というマンガ表現/「夢の散歩」の衝撃力/喫茶店を開業しようと・・・)
〔特集 山下敦弘〕
師弟対談 映画「どんてん生活」から「リアリズムの宿」まで/中島貞夫・山下敦弘 聞き手・編集部+うらたじゅん
(「どんてん生活」のキャラクター/自主映画の枠をどう越えるか/感動したアメリカン・ニューシネマ/「リアリズムの宿」を撮り終えて)
映画「リアリズムの宿」をめぐって
1 風景の感情/久保隆
2 雪の日本海/梶葉子
乙女チャンラ/河内遥
ひまつぶし/河内遥
はい せつせつ はん すうすう/河内遥
トンネル画廊/西野空男
蒸発日記 原案・つげ義春「蒸発旅日記」より/西野空男
昨日の夢/西野空男
『幻燈』9号
小夜時雨/うらたじゅん
或る押入れ頭男の話/藤宮史
金魚と未亡人/菅野修
対談 夢のなかで、夢のそとで(常識を逸脱したようなものを描きたい)/原マスミ・山田勇男
古書市へ行こうよ/角南誠
耕運機にカラス/斎藤種魚(目次には「耕耘機とカラス」表記)
椅子を並べる/おんちみどり
街道/永井サク
hex/海老原健悟
散歩/木下竜一
きしみ 骨が鳴る 誰かが笑う/山羊タダシ
映画『実録・連合赤軍あさま山荘への道程』考/久保隆
野田昌宏さんを偲ぶ/高野慎三
瀬沼孝明さんのこと/編集部
水音/瀬沼孝明
夢精/山羊タダシ
いちばん柔らかい肉/海老原健悟
インチキ/木下竜一
葉っぱの亡い花/ネズ実
漫画おんち/おんちみどり
武蔵野/角南誠
『幻燈』10号
夏の午後には/うらたじゅん
性と生活/菅野修
或る押入れ頭男の話・箱舟/藤宮史
彼女の思い出/角南誠
背中/片桐慎二
古本海岸/おんちみどり
人魚/山田勇男
街 ―花ははやく散れ雨の叙事/小林坩堝
さよなら夢幻島/小林坩堝
タスケ/斎藤種魚
灰と煙/山羊タダシ
或る押入れ頭男の話・終章-Ⅰ/藤宮史
無意識の世界と夢 少年王者舘「夢+夜」にふれて 対談(演劇の構造と夢の特殊性/なぜ1954年なのか?/もうだれも見ていない/しでかしてしまったこと/技術的に巧みになった)/天野天街・山田勇男
アクチュアリティと無化 少年王者舘「夢+夜」を観て/金ゐ國許
映像表現とマンガ表現 鼎談(映像作家的な映像作品/空と雲と地平線/言葉へのコンプレックス/「垣間みた」という快楽/マンガとの関わり/つげ義春作品との出会い/ダヴィンチと任侠映画)/山田勇男・ネズ実・角南誠
高橋和己の現在 対談(なぜ高橋和己なのか/「孤立無援の思想」/情況へのリアクション/懐古趣味への誘惑/精神的な飢餓状態)/小林坩堝・山羊タダシ 司会 編集部
きれ間/ネズ実
香り/海老原健悟
行ってきます/永井サク
意識/木下竜一
走馬燈/西野空男
三人/甲野酉
嵐々電々/うらたじゅん
『九杯目には早すぎる』
2011年6月23日 読書
蒼井上鷹の『九杯目には早すぎる』を読んだ。デビュー作でもある、短編集。
以下、目次。
大松鮨の奇妙な客
においます?
私はこうしてデビューした
清潔で明るい食卓
タン・バタン!
最後のメッセージ
見えない線
九杯目には早すぎる
キリング・タイム
短編とショートショートの九編だが、それぞれ、ひねりがきいていて面白い。
「大松鮨の奇妙な客」は、すし屋で言語道断な食べ方をした男の謎。
「私はこうしてデビューした」は、合作をしいる勘違いファンの話。
「タン・バタン!」は、悪気なく逆鱗にふれる発言を繰り返す男。
「見えない線」は、人間関係の境界線についての話。
「キリング・タイム」は、うっとうしい上司の相手をする。
と、以上5編が短編。
とにかく、うっとうしい人物像を描かせたら、天下一品!
ああ、こういうヤツ、いるいる、とうなずきながら読んだ。
そういう人物描写がうまいものだから、ストーリーとしてのどんでん返しなど予想もしておらず、読み終わって、ああ、推理小説だからこういう意外な結末をつけたんだな、と納得した次第。つまり、最後のヒネリよりも、途中の、うっとうしい人間の描写こそが、この本の持ち味なのである。
ヒネリは確かに素晴らしいが、うっとうしい人間描写が頭に残るため、事件はスッキリ解決しても、なんだかいや~な読後感が漂うのである。たぶん、自分が学生だったら、この本はそんなに評価高くないだろうな、と思う。実際にこの本に出てくるうっとうしい上司やファンとの人間関係があってこそ、この本は輝くのだ。
だがしかし、それゆえに、読後すぐにはかなり高い評価だったのに、日を経るにしたがって、嫌な人間に会った、嫌な読後感だけが、毒のようにじわりじわりときいてきて、いや~な気分になってしまう。
ところで、ペンネームの「上鷹」だが、由来は調べてないので知らないが、ウィテカーのファンなのかな?
以下、目次。
大松鮨の奇妙な客
においます?
私はこうしてデビューした
清潔で明るい食卓
タン・バタン!
最後のメッセージ
見えない線
九杯目には早すぎる
キリング・タイム
短編とショートショートの九編だが、それぞれ、ひねりがきいていて面白い。
「大松鮨の奇妙な客」は、すし屋で言語道断な食べ方をした男の謎。
「私はこうしてデビューした」は、合作をしいる勘違いファンの話。
「タン・バタン!」は、悪気なく逆鱗にふれる発言を繰り返す男。
「見えない線」は、人間関係の境界線についての話。
「キリング・タイム」は、うっとうしい上司の相手をする。
と、以上5編が短編。
とにかく、うっとうしい人物像を描かせたら、天下一品!
ああ、こういうヤツ、いるいる、とうなずきながら読んだ。
そういう人物描写がうまいものだから、ストーリーとしてのどんでん返しなど予想もしておらず、読み終わって、ああ、推理小説だからこういう意外な結末をつけたんだな、と納得した次第。つまり、最後のヒネリよりも、途中の、うっとうしい人間の描写こそが、この本の持ち味なのである。
ヒネリは確かに素晴らしいが、うっとうしい人間描写が頭に残るため、事件はスッキリ解決しても、なんだかいや~な読後感が漂うのである。たぶん、自分が学生だったら、この本はそんなに評価高くないだろうな、と思う。実際にこの本に出てくるうっとうしい上司やファンとの人間関係があってこそ、この本は輝くのだ。
だがしかし、それゆえに、読後すぐにはかなり高い評価だったのに、日を経るにしたがって、嫌な人間に会った、嫌な読後感だけが、毒のようにじわりじわりときいてきて、いや~な気分になってしまう。
ところで、ペンネームの「上鷹」だが、由来は調べてないので知らないが、ウィテカーのファンなのかな?
柳広司の『最初の哲学者』を読んだ。
ギリシアをモチーフにした語りなおし。
以下、各作品と、それでとりあげられる人物(神)。
「オイディプス」(オイディプス)
「異邦の王子」(アナカルシス王子)
「恋」(アリアドネ、テセウス)
「亡牛嘆」(ミノタウロス)
「ダイダロスの息子」(イカロス)
「神統記」(ゼウス)
「狂いの巫女」(カサンドラ、クリュタイメストラ)
「アイギナの悲劇」(ミュシアス)
「最初の哲学者」(タレス)
「オリンポスの醜聞」(ヘファイストス)
「ソクラテスの妻」(クサンティッペ)
「王女メデイア」(メデイア、イアソン)
「ヒストリエ」(ヘロドトス)
「恋、「亡牛嘆」「ダイダロスの息子」は1つの神話をもとに、主人公を変えて語っていて、面白い。
それぞれ、「アリアドネの真意」「ミノタウロスによる牛頭人身論」「イカロスが空高く飛んだ理由」、つまりは、神話の解釈しなおしを行っている。
しかしながら、全体にミステリー味はとくに強くなく、軽い読み物として楽しめた。
ギリシアをモチーフにした語りなおし。
以下、各作品と、それでとりあげられる人物(神)。
「オイディプス」(オイディプス)
「異邦の王子」(アナカルシス王子)
「恋」(アリアドネ、テセウス)
「亡牛嘆」(ミノタウロス)
「ダイダロスの息子」(イカロス)
「神統記」(ゼウス)
「狂いの巫女」(カサンドラ、クリュタイメストラ)
「アイギナの悲劇」(ミュシアス)
「最初の哲学者」(タレス)
「オリンポスの醜聞」(ヘファイストス)
「ソクラテスの妻」(クサンティッペ)
「王女メデイア」(メデイア、イアソン)
「ヒストリエ」(ヘロドトス)
「恋、「亡牛嘆」「ダイダロスの息子」は1つの神話をもとに、主人公を変えて語っていて、面白い。
それぞれ、「アリアドネの真意」「ミノタウロスによる牛頭人身論」「イカロスが空高く飛んだ理由」、つまりは、神話の解釈しなおしを行っている。
しかしながら、全体にミステリー味はとくに強くなく、軽い読み物として楽しめた。
『ビッチマグネット』
2011年6月21日 読書
舞城王太郎の『ビッチマグネット』を読んだ。
なんと、家族小説だ。
すねかじられで被害者体質の母親、下半身に人格がある父親、ディシプリンな弟、その弟をふりまわすビッチなあかりちゃん、素敵な女性は父の愛人、からっぽなわたし。
「ビッチマグネット」は、弟のことで、次のような文章がある。
一種の教養小説でもあるこの作品だが、さて、感想はと言うと、すごくおとなしくて、エキセントリックなところもなく、きれいで、なんだ、文学賞狙いなのか、と思わせるところがあった。小説としての読みやすさはあるが、「家族」テーマがどうにも納得できないのであった。
だから、この本で面白いのは、家族からはみ出た存在の、ビッチの娘だったりする。この娘の、男の振り回しっぷりはすごくて、絶叫マシーン好きの僕なんかは、こういう娘に思いっきり振り回されてみたいと思うのである。
願わくば、タイトルの「ビッチマグネット」にふさわしい作品であってほしかった。心を傷つけたくなく読書したい向きにはいいのかもしれないが。
なんと、家族小説だ。
すねかじられで被害者体質の母親、下半身に人格がある父親、ディシプリンな弟、その弟をふりまわすビッチなあかりちゃん、素敵な女性は父の愛人、からっぽなわたし。
「ビッチマグネット」は、弟のことで、次のような文章がある。
「俺、友達に言われたんだけど、ビッチマグネットだってさ」
と電話で友徳が言う。
「何それ」
「ビッチばっかり引き寄せる磁石ってこと」
「あはは。上手いじゃん」
「ちょ、上手いとかじゃないから。俺さ、自分が恋愛下手で、何か、自分で言うのは変だけど、優しすぎるから相手を駄目にしちゃうんだって思ってたけど、・・・そもそも変な子に好かれやすいってことかな」
「まあまあ。女なんて皆男から見たらビッチだから」
一種の教養小説でもあるこの作品だが、さて、感想はと言うと、すごくおとなしくて、エキセントリックなところもなく、きれいで、なんだ、文学賞狙いなのか、と思わせるところがあった。小説としての読みやすさはあるが、「家族」テーマがどうにも納得できないのであった。
だから、この本で面白いのは、家族からはみ出た存在の、ビッチの娘だったりする。この娘の、男の振り回しっぷりはすごくて、絶叫マシーン好きの僕なんかは、こういう娘に思いっきり振り回されてみたいと思うのである。
願わくば、タイトルの「ビッチマグネット」にふさわしい作品であってほしかった。心を傷つけたくなく読書したい向きにはいいのかもしれないが。
高山宏の『かたち三昧』を読んだ。
澁澤龍彦の著書名を借りて、高山版の『思考の紋章学』と呼びたい、と著者自身が語る1冊。だが、『かたち三昧』は『終末のオルガノン』とか『痙攣する地獄』などの大仰なタイトルが並ぶ高山宏の著作のなかでも、これはまたふんわりとしたタイトルだ。著者自身も言うように、「精神図像学序説」あたりが、それらしいように思える。
以下、目次。
口上 フィギュラリズム
1 フィギュラティヴ・サークル
2 フィグーラ・セルペンティナータ
3 エキセントリック・ガーデン
4 うねくった漱石
5 彼岸へと過ぎる蛇
6 十九歳、何てパンクなマニエラ
7 薔薇の庭の音の蛇
8 詩神の音連れ
9 百学連環(1)
10 百学連環(2) グラン・メートル種村季弘(2004・8・29没)に
11 鯨の百科、鯨〈と〉百科
12 マーヤーは人のかたち
13 「く寝る」言葉の川走
14 サイモン・シャーマの歴史形態学
15 エーコ・インポッシビリア
16 ジュゼッペのヒト猫
17 我レ亦あるかであニ在リ
18 アナモーフィックな死
19 よく見ればオムニス
20 驚く、ヒューマニティーズ
21 葡萄のパラダイム
22 葡萄ルネサンス
23 シーレーノスの箱
24 これビン笑すまじきこと
25 ヒトはこれノミ
26 懼龍犇は寝ている―─キャロル・フィギュラル1
27 切って分かった蛇馬魚鬼―─キャロル・フィギュラル2
28 「体」現憧憬―─キャロル・フィギュラル3
29 「クンストゲシヒテ」の星たち
30 哲学する「映像の力」
31 暗号はゼロのかたち(1)
32 「言葉と物」のペダゴジックス
33 言葉の永久機関
34 ちゃんと面白い英文学
35 はじめっから詐欺
36 暗号はゼロのかたち(2)
37 エヴリ・バディに謹賀新年
38 フォシヨンの家の馬鹿息子
39 ヤラセ引くヤセで裸
40 顔に目をつけた
41 未知の西鶴、道の才覚
42 きみの顔は正しい
43 お勉強やめてギルマン読もう
44 ブルーサティン、顔のマニエリスト
45 顔のマニエリスム(1)
46 顔のマニエリスム(2)
47 アポカリプスな顔
48 宙にあそぶ視線(1) 亡き若桑みどり先生に
49 宙にあそぶ視線(2)―─His private eye
50 宙にあそぶ視線(3)─―女たちは見る
51 絵面の見得 服部幸雄先生追善
52 語る目、語る指
53 アメリカン・マニエリスムの手
54 「知」塗られた手首の話(1)
55 「知」塗られた手首の話(2)
56 「知」塗られた手首の話(3)
57 「知」塗られた手首の話(4)
58 かたち好き垂涎の「大図典」
59 影のない翻訳
60 雲をつかむような話
61 こんなミーイズムなら大歓迎だ
62 矩形なのに、まどか
63 かたちばかりの修了試験
吾輩は死ぬ――『吾輩は猫である』
座頭を殺す――『夢十夜』第三夜
夢の幾何学――『夢十夜』第四夜
「擬(まが)いの西洋舘」のト(ロ)ポロジー――『明暗』冒頭のみ
文献索引/人名索引
あいにくとカラー図版がなかったり、図版は多数だがページぶち抜きの大きな図版がないのが残念だが、各章の内容の凝縮ぶりたるやすさまじいし、巻末の索引だけでも読み物になってしまうすごさだ。
高山宏の翻訳した大著で未読のものがいくつもあるので、時間を見て、楽しんでいきたい。必読文献の紹介が何年も遅れていることに憤慨する高山氏だが、せっかく翻訳してくれているのに、読まない手はないのだった。
澁澤龍彦の著書名を借りて、高山版の『思考の紋章学』と呼びたい、と著者自身が語る1冊。だが、『かたち三昧』は『終末のオルガノン』とか『痙攣する地獄』などの大仰なタイトルが並ぶ高山宏の著作のなかでも、これはまたふんわりとしたタイトルだ。著者自身も言うように、「精神図像学序説」あたりが、それらしいように思える。
以下、目次。
口上 フィギュラリズム
1 フィギュラティヴ・サークル
2 フィグーラ・セルペンティナータ
3 エキセントリック・ガーデン
4 うねくった漱石
5 彼岸へと過ぎる蛇
6 十九歳、何てパンクなマニエラ
7 薔薇の庭の音の蛇
8 詩神の音連れ
9 百学連環(1)
10 百学連環(2) グラン・メートル種村季弘(2004・8・29没)に
11 鯨の百科、鯨〈と〉百科
12 マーヤーは人のかたち
13 「く寝る」言葉の川走
14 サイモン・シャーマの歴史形態学
15 エーコ・インポッシビリア
16 ジュゼッペのヒト猫
17 我レ亦あるかであニ在リ
18 アナモーフィックな死
19 よく見ればオムニス
20 驚く、ヒューマニティーズ
21 葡萄のパラダイム
22 葡萄ルネサンス
23 シーレーノスの箱
24 これビン笑すまじきこと
25 ヒトはこれノミ
26 懼龍犇は寝ている―─キャロル・フィギュラル1
27 切って分かった蛇馬魚鬼―─キャロル・フィギュラル2
28 「体」現憧憬―─キャロル・フィギュラル3
29 「クンストゲシヒテ」の星たち
30 哲学する「映像の力」
31 暗号はゼロのかたち(1)
32 「言葉と物」のペダゴジックス
33 言葉の永久機関
34 ちゃんと面白い英文学
35 はじめっから詐欺
36 暗号はゼロのかたち(2)
37 エヴリ・バディに謹賀新年
38 フォシヨンの家の馬鹿息子
39 ヤラセ引くヤセで裸
40 顔に目をつけた
41 未知の西鶴、道の才覚
42 きみの顔は正しい
43 お勉強やめてギルマン読もう
44 ブルーサティン、顔のマニエリスト
45 顔のマニエリスム(1)
46 顔のマニエリスム(2)
47 アポカリプスな顔
48 宙にあそぶ視線(1) 亡き若桑みどり先生に
49 宙にあそぶ視線(2)―─His private eye
50 宙にあそぶ視線(3)─―女たちは見る
51 絵面の見得 服部幸雄先生追善
52 語る目、語る指
53 アメリカン・マニエリスムの手
54 「知」塗られた手首の話(1)
55 「知」塗られた手首の話(2)
56 「知」塗られた手首の話(3)
57 「知」塗られた手首の話(4)
58 かたち好き垂涎の「大図典」
59 影のない翻訳
60 雲をつかむような話
61 こんなミーイズムなら大歓迎だ
62 矩形なのに、まどか
63 かたちばかりの修了試験
吾輩は死ぬ――『吾輩は猫である』
座頭を殺す――『夢十夜』第三夜
夢の幾何学――『夢十夜』第四夜
「擬(まが)いの西洋舘」のト(ロ)ポロジー――『明暗』冒頭のみ
文献索引/人名索引
あいにくとカラー図版がなかったり、図版は多数だがページぶち抜きの大きな図版がないのが残念だが、各章の内容の凝縮ぶりたるやすさまじいし、巻末の索引だけでも読み物になってしまうすごさだ。
高山宏の翻訳した大著で未読のものがいくつもあるので、時間を見て、楽しんでいきたい。必読文献の紹介が何年も遅れていることに憤慨する高山氏だが、せっかく翻訳してくれているのに、読まない手はないのだった。
高橋睦郎の『善の遍歴』を読んだ。1974年。
善財童子が文殊菩薩の指南によって55人の善知識を遍歴し悟りにいたる、華厳経の入法界品(にゅうほっかいぼん)をベースに、その名も法界善財(ホッカイ・ゼンザイ)少年が経巡る、男色変態性愛地獄めぐり。
以下、目次。
発端:ゼン、故郷出奔のこと。
並びにモンジュボサツに出会うこと。
第1話:ゼン、通勤電車で揉まれつづけること。
歓喜地は異生羝羊心なること。
第2話:ゼン、映画館にて三界虚妄を悟ること。
地獄絵は曼荼羅たること。
第3話:ゼン、バーの扉を潜ること。
変成男子は変成女子を通るべきこと。
第4話:ゼン、糞尿の海を漂い流れること。
法悦境は不浄観を通るべきこと。
第5話:夏の海べの一ヵ月のこと。
いろは修養団ゑひもせすと消え失せること。
第6話:怪外人マイトレーヤ氏との奇遇のこと。
売色の森は正覚大悟の座たること。
第7話:ゼン、蒸気地獄を巡ること。
無垢光潔の愛は溶け湯水となって流れ去ること。
第8話:ゼン、はじめて法性華を愛慕のこと。
緋牡丹は火焔三昧の知恵の花たること。
第9話:ゼン、夢の島にてマゾヒストの群れに会うこと。
捨身飼虎は仏菩薩の慈悲たること。
第10話:ゼン、ブタ箱でありとある辱めを受けること。
旃陀羅の極みは婆羅門を超ゆること。
団円:ゼン、モンジュボサツに再会のこと。
中有を通って摩訶毘盧遮那仏と一致のこと。
家出して上京してきたゼンを、車掌の姿のモンジュボサツが導き、遍歴の意味を教えるところから話ははじまる。UFOの形は「空飛ぶ円盤」だけでなく、「葉巻型」のもある、という説明から、円盤は女性器、葉巻は男性器で、UFOと見えていたのは、彼方の彼方に存在する大日如来(マハーヴァイローチャナ)なのだ、と。ゼンは永遠の求道者、善財童子に似ており、そのめでたい姿かたちをみると、大日如来に愛されているにちがいない、とゼンの遍歴をうながす。
モンジュボサツは、折にふれて、地蔵の姿になったり、いろんな姿でゼンの前にあらわれ、ゼンが体験したことの意味を教えたりするのである。
この後、ゼンは満員電車での痴漢や映画館発展場、スカトロやマゾ、などなど性愛地獄を遍歴するが、その際に、男性器を「マハーヴァイローチャナ」と表記している。本書では、マハーヴァイローチャナの言葉はこれでもか、と頻発するので、すっかり覚えてしまった。宗教的な難しい文句が並ぶが、内容はといえば、変態ポルノとあまり変わらない。
遍歴の際に出会う人々が、怪物的なキャラクターで、もう笑うしかないのだが、どんな人たちと出会うかというと、前半の五章にこんな文章がある。
「尻舐めおばけ」というのは、汲み取り便所の中に棲みついた化け物で、13歳から19歳までのスポーツ刈りの少年が排便中に、下からペロリとなめる。その顔は、どぶねずみとなめくじとなまずとかわうそすべてを集めたような顔だちなのだ。
五章で出てくる「いろは団」はくりくり坊主でふんどし姿の集団だ。
六章で出てくる外人マイトレーヤは、こんな描写。
この外人、マイトレーヤは、「あきらかに巨人症のうえに末端肥大症の海坊主は、一糸まとわぬ裸」で、「生まれて一度も磨いたことがないと覚しい黄色を通り越して茶色の虫食い歯」をのぞかせて笑うのだった。
また、七章で登場するトルコさんは、常にスチームバスにいるため、
「体表の皮膚が水分を吸い込めるだけ吸いこみ、飽和状態に達した水分が、力が入るたび力の入ったその場所からしみだす」のであった。トルコさんはしばらく外にいると、水分不足で苦しくなってしまう。あげくの果てには、サウナに入ってしまい、溶けるように消えてしまうのだ。
各エピソードそれぞれ面白いが、なかでも九章のマゾヒストの群れは慄然とする。夜になると、海から「片目、片耳、鼻壊え、片手、片足などの片輪者」が大挙やってきて、合唱する。
彼らは鞭や棍棒や日本刀や剃刀や錐や鑿などの道具を持参する。
ゼンは、彼らの要求にしたがって、顔面に放尿し、脱糞し、鞭打ち、棍棒で殴り、錐で突き刺し、鑿で目玉を抉り、剃刀で耳を殺ぎ落とした。さらに、股間の一物を日本刀で刎ね、鋸で脚を、手を、首をひかせる。
チェシャ猫だ!
最終章では、モンジュボサツとゼンはリンガとヨーニの一致を果たし、こう説明される。
そして、まとめ!
相変わらず、何が何やら、であるが、めちゃくちゃ面白い。
あと、公衆便所の地下や、ごみの島などにアジトのような秘密基地みたいな場所を作って、住み込むシーンが出てくるのが、ワクワクした。これは70年代の楽しいムードが味わえるところ。
善財童子が文殊菩薩の指南によって55人の善知識を遍歴し悟りにいたる、華厳経の入法界品(にゅうほっかいぼん)をベースに、その名も法界善財(ホッカイ・ゼンザイ)少年が経巡る、男色変態性愛地獄めぐり。
以下、目次。
発端:ゼン、故郷出奔のこと。
並びにモンジュボサツに出会うこと。
第1話:ゼン、通勤電車で揉まれつづけること。
歓喜地は異生羝羊心なること。
第2話:ゼン、映画館にて三界虚妄を悟ること。
地獄絵は曼荼羅たること。
第3話:ゼン、バーの扉を潜ること。
変成男子は変成女子を通るべきこと。
第4話:ゼン、糞尿の海を漂い流れること。
法悦境は不浄観を通るべきこと。
第5話:夏の海べの一ヵ月のこと。
いろは修養団ゑひもせすと消え失せること。
第6話:怪外人マイトレーヤ氏との奇遇のこと。
売色の森は正覚大悟の座たること。
第7話:ゼン、蒸気地獄を巡ること。
無垢光潔の愛は溶け湯水となって流れ去ること。
第8話:ゼン、はじめて法性華を愛慕のこと。
緋牡丹は火焔三昧の知恵の花たること。
第9話:ゼン、夢の島にてマゾヒストの群れに会うこと。
捨身飼虎は仏菩薩の慈悲たること。
第10話:ゼン、ブタ箱でありとある辱めを受けること。
旃陀羅の極みは婆羅門を超ゆること。
団円:ゼン、モンジュボサツに再会のこと。
中有を通って摩訶毘盧遮那仏と一致のこと。
家出して上京してきたゼンを、車掌の姿のモンジュボサツが導き、遍歴の意味を教えるところから話ははじまる。UFOの形は「空飛ぶ円盤」だけでなく、「葉巻型」のもある、という説明から、円盤は女性器、葉巻は男性器で、UFOと見えていたのは、彼方の彼方に存在する大日如来(マハーヴァイローチャナ)なのだ、と。ゼンは永遠の求道者、善財童子に似ており、そのめでたい姿かたちをみると、大日如来に愛されているにちがいない、とゼンの遍歴をうながす。
その限りない慈愛に敬意を表して、お前の股間にあるそのものも、もうひとつのマハーヴァイローチャナと呼ばれるべきだろう。さあ、行くがよい、ゼンよ、マハーヴァイローチャナ見守り給う求道遍歴の旅に。見よ、濁世の世界海、東京は真近い。お前はその煩悩の海に浮きぬ沈みぬしている衆生の中から、マハーヴァイローチャナの霊気を持った善知識を訪ねて教えを乞い、ついには濁世に煩悩即菩提、即身成仏、宇宙の彼方の彼方の光り輝くマハーヴァイローチャナと一致するのだ。遍歴の途中、出会う善知識を丁寧に礼拝し、身密、口密、意密の三密を熱心に学問するのだ。身密とは股間のマハーヴァイローチャナ、口密とは口と舌、意密は尻、この三つの能力を遍照発揮して、阿吽の声を挙げつつマハーヴァイローチャナの真言秘密に参入するのだな。阿吽の声こそはこよなく淫らであるとともにこよなく聖い声、その中には三千大千世界のあらゆる秘密がこめられている。それでは行け、ゼンよ、行くのだ、よいか、どうだ、うん?うん?
モンジュボサツは、折にふれて、地蔵の姿になったり、いろんな姿でゼンの前にあらわれ、ゼンが体験したことの意味を教えたりするのである。
この後、ゼンは満員電車での痴漢や映画館発展場、スカトロやマゾ、などなど性愛地獄を遍歴するが、その際に、男性器を「マハーヴァイローチャナ」と表記している。本書では、マハーヴァイローチャナの言葉はこれでもか、と頻発するので、すっかり覚えてしまった。宗教的な難しい文句が並ぶが、内容はといえば、変態ポルノとあまり変わらない。
遍歴の際に出会う人々が、怪物的なキャラクターで、もう笑うしかないのだが、どんな人たちと出会うかというと、前半の五章にこんな文章がある。
ゼンはこの五ヵ月に出会った人人を、近い順から逆に、ひとりひとり思い出した。便所少年、その父親の尻舐めおばけ、偏執的札束嗜好症のオーナー、オーナーからゼンを解放してくれたガラ子、ヒキョウモノと女声男声半半で叫んだ赤毛マダム、ゼンの学生服を騙し盗った洋品店店長、満員電車で一ヵ月間ゼンを愛撫しつづけた掌男、その他、ゼンとつかのま擦れちがったにも似た無数の男たち、そしてもちろん、あの瘤と疣の皺だらけのモンジュボサツ
「尻舐めおばけ」というのは、汲み取り便所の中に棲みついた化け物で、13歳から19歳までのスポーツ刈りの少年が排便中に、下からペロリとなめる。その顔は、どぶねずみとなめくじとなまずとかわうそすべてを集めたような顔だちなのだ。
五章で出てくる「いろは団」はくりくり坊主でふんどし姿の集団だ。
六章で出てくる外人マイトレーヤは、こんな描写。
その頭はまず、ゼンの頭の優に三倍はありそうに大きかった。同じ比率で巨大な鼻が顔の中央にどっかりと坐り、と言いたいところだが、重さに耐えかねて垂れているという風情で、しかし、その下の唇はお上品なのが逆に滑稽なくらいのおちょぼ唇、そして、上のほうにはだだっ広い額が迫り出し、その下にそのやたら比率の狂った顔とはおよそ場ちがいにロマンチックな碧の眼がブロンドの睫毛を飾って輝いている。けれども、珍妙中の珍妙はその頭だった。ぜんたいがみごとに禿げあがっているのに、アフリカ象を思わせる馬鹿でかい両耳のうしろにだけはふさふさした金髪が残っていて、これがあろうことか女学生風の三つ編みに編まれ、垂れたその先は海水に泳いでいたのである。
年齢は四十だろうか、五十だろうか、若禿げということもあるから三十代、ひょっとしたら二十代かもしれない。
この外人、マイトレーヤは、「あきらかに巨人症のうえに末端肥大症の海坊主は、一糸まとわぬ裸」で、「生まれて一度も磨いたことがないと覚しい黄色を通り越して茶色の虫食い歯」をのぞかせて笑うのだった。
また、七章で登場するトルコさんは、常にスチームバスにいるため、
「体表の皮膚が水分を吸い込めるだけ吸いこみ、飽和状態に達した水分が、力が入るたび力の入ったその場所からしみだす」のであった。トルコさんはしばらく外にいると、水分不足で苦しくなってしまう。あげくの果てには、サウナに入ってしまい、溶けるように消えてしまうのだ。
各エピソードそれぞれ面白いが、なかでも九章のマゾヒストの群れは慄然とする。夜になると、海から「片目、片耳、鼻壊え、片手、片足などの片輪者」が大挙やってきて、合唱する。
いじめてください
どやしてください
ぶってください
蹴ってください
切ってください
殺いでください
刺してください
抉ってください
彼らは鞭や棍棒や日本刀や剃刀や錐や鑿などの道具を持参する。
ゼンは、彼らの要求にしたがって、顔面に放尿し、脱糞し、鞭打ち、棍棒で殴り、錐で突き刺し、鑿で目玉を抉り、剃刀で耳を殺ぎ落とした。さらに、股間の一物を日本刀で刎ね、鋸で脚を、手を、首をひかせる。
ゼンは意を決して首を鋸引き、ついに引き落とした。頭部の落ちたあとの血まみれの首の穴から、まだ、あの声が洩れていた。
-痛いけど気持いい・・・気持いいけど痛い・・・痛いけど気持いい・・・
こうして、つぎつぎに躰を切り刻み、最後にはお尻の孔だけが残った。肉がすっかりなくなって孔だけになったそこから、消え消えになりながら、あの声がまだ聞こえていた。
-痛いけど気持いい・・・気持いいけど痛い・・・痛いけど気持いい・・・
チェシャ猫だ!
最終章では、モンジュボサツとゼンはリンガとヨーニの一致を果たし、こう説明される。
この躰じゅうにある陽と陰のすべての感覚を、身口意すなわち男根、口腔、肛門を手はじめにことごとく開発し、七つのチャクラの第七、サハスラーラ・チャクラの蓮華の尖端を開き、ここから大宇宙たるブラフマンにつながるのだ。こうして、アートマンたる我とブラフマンたる宇宙は相即相入し、一即一切、一切即一、事事無礙、円融無尽、ブッダのブッダたる境地、タターガタのタターガタたる境地、まことのニルヴァーナが成就されるのだ。
そして、まとめ!
法界善財なる奇体な名前によって求道遍歴を運命づけられたお前の旅は、ついにここまで達した。ヒーナ・ヤーナの故郷からマハー・ヤーナの特急列車に乗って上京して一年間、大方広物華厳経十地品に説く菩薩の十地、秘密曼荼羅十住心論に言う求道の十住心を遍歴して、ついにタントラ・ヤーナ、ヴァジラ・ヤーナ、アヌタラ・ヨーガ・ヤーナに上乗するところにまで到った。
相変わらず、何が何やら、であるが、めちゃくちゃ面白い。
あと、公衆便所の地下や、ごみの島などにアジトのような秘密基地みたいな場所を作って、住み込むシーンが出てくるのが、ワクワクした。これは70年代の楽しいムードが味わえるところ。
松本孝の『黒い報告書』を読んだ。1961年。
以下、目次。
高利貸謀殺事件
松竹荘殺人事件
だまし合い
僧一家射殺事件
犯人が柩をかついだ
「週刊新潮」の「黒い報告書」シリーズから、松本孝が執筆した殺人事件ものをチョイスし、書き改めたもの。あとがきによると、「高利貸謀殺事件」などは、週刊誌に載せたときの5倍の長さになった、とある。ちなみに、「高利貸謀殺事件」は今も連載される「黒い報告書」の第一号だ。
「黒い報告書」のシリーズは、「現実の事件に取材し、事実で押しながら、犯罪にいたるまでの人間関係を追う」ことに主眼がおかれた事件小説である。
本格推理一辺倒の中学生頃の僕なら、ちっとも良さがわからなかっただろうが、今読んでみると、面白い!
約50年ほど前の事件なので、今やまったく知らない事件ばっかりだが、まるで再現ビデオを楽しむような感覚で、楽しめた。
それぞれに面白さがあったが、いくつか引用してみよう。
「高利貸謀殺事件」より。冷静に計画をたてて実行されたはずの事件が、共犯の愚かさによってボロボロになってしまうくだり。
「松竹荘殺人事件」で、すっかり所帯じみた妻に愛想をつかし、妻の妹に執着する男の感情。(この男、妻が眠る横で、平気で妹のふとんにもぐりこんだりするのだ!)
「だまし合い」より。男女の口げんか。
「犯人が柩をかついだ」より。女たらしの男と、女房を満足させられないつまらない夫の対比。
この「黒い報告書」は「週刊新潮」でいろんな作家によって長期連載中の企画だ。週刊新潮はほとんど買わないけど、この「黒い報告書」があるなら、読んでもいいかな、と思った。
以下、目次。
高利貸謀殺事件
松竹荘殺人事件
だまし合い
僧一家射殺事件
犯人が柩をかついだ
「週刊新潮」の「黒い報告書」シリーズから、松本孝が執筆した殺人事件ものをチョイスし、書き改めたもの。あとがきによると、「高利貸謀殺事件」などは、週刊誌に載せたときの5倍の長さになった、とある。ちなみに、「高利貸謀殺事件」は今も連載される「黒い報告書」の第一号だ。
「黒い報告書」のシリーズは、「現実の事件に取材し、事実で押しながら、犯罪にいたるまでの人間関係を追う」ことに主眼がおかれた事件小説である。
本格推理一辺倒の中学生頃の僕なら、ちっとも良さがわからなかっただろうが、今読んでみると、面白い!
約50年ほど前の事件なので、今やまったく知らない事件ばっかりだが、まるで再現ビデオを楽しむような感覚で、楽しめた。
それぞれに面白さがあったが、いくつか引用してみよう。
「高利貸謀殺事件」より。冷静に計画をたてて実行されたはずの事件が、共犯の愚かさによってボロボロになってしまうくだり。
とにかく、あやしまれるようなことばかり、やりだしたのであった。
「今日も、ひるま朝総連の連中がきたわ。それから、新聞記者だっていう男も・・・あたし、こわい!自分が何を言い出すか、見当もつかないの・・・」
そういう眼つきは、尋常ではなかった。鈴木は、呆然とした。
(どうして、こんなにとつぜんとりみだしちまったんだろう?信じられない・・・)鈴木はわが眼をうたがった。(もしや、吉山の怨霊が・・・?)ふとそうおもうと、彼は背すじがぞっとつめたくなるのをおぼえた。
・・・八月にはいった。
千恵子の言動は、ますます異常さをくわえた。なだめすかしても、ききめがない。
「ねむれない。ねむれない」を連発し、近所のだれかれかまわず、「ねえ、睡眠薬買ってきてくれない?毎晩、うなされてこまるのよ」などと、たのみこむのだった。
(これじゃ、ダイナマイトをかかえているようなもんだ!)
鈴木洋の、第二の重大な誤算は、犯行後の阿部と安田の行動であった。
二人とも、鈴木に
「すぐから、やたらと金づかいをあらくするなよ。あやしまれるもとだからな」
こんこんといわれたにもかかわらず、もう翌日から、湯水のように浪費をはじめた。
「松竹荘殺人事件」で、すっかり所帯じみた妻に愛想をつかし、妻の妹に執着する男の感情。(この男、妻が眠る横で、平気で妹のふとんにもぐりこんだりするのだ!)
(ユキ子へのオレの執着は尋常じゃない。あの子を手ばなすくらいなら・・・オレは、あの子を、ころしてやる。ひとおもいに、ころしてやるんだ。・・・そうして、オレもいっしょに、死んでやる!)
ユキ子を殺して自分も死ぬ、というかんがえは、ひどく弘の気にいった。
(ころしちまえば、だれだって、天皇陛下だって、あの子をとることはできないんだから・・・)
ひるごろのアパートは、しずかだった。
弘は、ひとり頬をゆがめ、声を立てずに、いつまでも笑いつづけていた・・・。
「だまし合い」より。男女の口げんか。
「女房とは、仕おくりだけの完全別居。いまは独身同様、とりあえず親戚の家にひと部屋かりているなんて、大ウソだったんじゃないのよ!」
「うるさい、だまれ!それじゃ、自分は何だってんだ。最初は『あたし、ひとりぼっち、ボーイ・フレンドぐらいはいるけど』それが、『婚約者がいるの』になったとおもったら、つぎは『亭主がいるのよ』だ。まるでサギかカタリじゃないか」
「犯人が柩をかついだ」より。女たらしの男と、女房を満足させられないつまらない夫の対比。
結局、丹波方の就職するまでに、吉川があげた戦果は6人だった。いずれも、人妻である。彼は、女から金をせびることさえおぼえていた。
娼婦を買ったり、独身の女にわたりをつけたりするより、ひとの妻を秘密にかっぱらう方が、いっそう快楽の度あいは大きい。彼は、人妻を犯すスリルをわすれがたくなり、もっぱらそのチャンスばかりをねらう男になっていた。
主人の保は、こころよく二人をおくりだした。保は映画など見る趣味をもっていなかった。テレビでも、劇映画は見ない。パッと場面がかわると、もう10年のちだったりするのは、よくわからないというのだ。
この「黒い報告書」は「週刊新潮」でいろんな作家によって長期連載中の企画だ。週刊新潮はほとんど買わないけど、この「黒い報告書」があるなら、読んでもいいかな、と思った。
ブルーノ・ムナーリの『ファンタジア』を読んだ。
以下、目次。
創造力ってなに?
不変の要素
思考は考え、想像力は視る
ファンタジア 発明 創造力 想像力
知っているものの関係
冷たい炎 煮えたぎる氷
七つ頭の竜
泥よけ付きのサル
ブルーのパン
コルクのハンマー
広場にベッド
五線譜のランプシェード
リドリーニ風に
ポップなマッチ
恐怖のモンスター
素晴らしき哉、重量挙げ選手
関係の中の関係
創造力を刺激する
ダイレクト・プロジェクション
知識を豊かに
クリエイティヴな遊び
サラダ菜のバラ
3次元の遊び
オリガミ
フォルムの分析
構造分野における組み合わせ可能なモデュール
書体
反復のバリエーション
15個の石
創造力とフォルム
架空の美術館
モノからモノが生まれる
ブルーノ・ムナーリといえば、ずいぶん昔に『きりのなかのサーカス』という穴のあいた絵本を買って読んだことを思い出した。面白い仕掛けだな、と思っていたが、そうしたエッセンスが教育的立場で展開されるのが、この『ファンタジア』だ。
創造力について多くのヒントが詰まっている。
個人的に面白かったのは、『リドリーニ風に』と題した一章。
リドリーニ風、とは、普通ならゆっくりと動くものが加速して動くような「動きの交換」を「リドリーニ風に動く」という。リドリーニはサイレント映画時代の喜劇俳優、ラリー・シモンのことだ。
今、20日の10minutes告知番組までに1本映画が撮れたらいいな、と思っているのだが、それを後押しするような感じだったのだ。
中の一節を引用しておこう。
また、一時は未来派の一員とされたブルーノ・ムナーリが、未来派について書いた、こんな文章も印象的だった。
ただ、全体に教育的立場から書かれているせいか、言ってることには納得できるが、学校でむりやりやらされる「楽しいこと」みたいな面倒くささを感じた。あれだけ学校が好きだったのに、卒業してみたら二度と学生時代には戻りたくない、と思ってしまった、僕の転向によるものなのか?
NHK-FMのベスト・オブ・クラシックで現代音楽が放送されていた。
主に通勤中に聞いたので、完全に聞けたわけではないが、プログラムをあげておこう。
- アルディッティ弦楽四重奏団演奏会 -
「弦楽四重奏のためのプロジェクション」 湯浅譲二・作曲
(10分58秒)
「弦楽四重奏曲-“西・金・秋”作品96」 石井眞木・作曲
(12分30秒)
「弦楽四重奏曲 第5番」 デュサパン作曲
(17分23秒)
「弦楽四重奏曲“ザ・トゥリー・オブ・ストリングス”」
バートウィスル作曲
(29分05秒)
「弦楽四重奏曲 第2番から 第3楽章」 リゲティ作曲
(3分20秒)
(弦楽四重奏)アルディッティ弦楽四重奏団
~東京・津田ホールで収録~
<2010/6/25>
「弦楽四重奏のためのアンダンテとアレグレット」 リゲティ作曲
(13分08秒)
(弦楽四重奏)アルディッティ弦楽四重奏団
<SONY CLASSICAL SRCR1992>
以下、目次。
創造力ってなに?
不変の要素
思考は考え、想像力は視る
ファンタジア 発明 創造力 想像力
知っているものの関係
冷たい炎 煮えたぎる氷
七つ頭の竜
泥よけ付きのサル
ブルーのパン
コルクのハンマー
広場にベッド
五線譜のランプシェード
リドリーニ風に
ポップなマッチ
恐怖のモンスター
素晴らしき哉、重量挙げ選手
関係の中の関係
創造力を刺激する
ダイレクト・プロジェクション
知識を豊かに
クリエイティヴな遊び
サラダ菜のバラ
3次元の遊び
オリガミ
フォルムの分析
構造分野における組み合わせ可能なモデュール
書体
反復のバリエーション
15個の石
創造力とフォルム
架空の美術館
モノからモノが生まれる
ブルーノ・ムナーリといえば、ずいぶん昔に『きりのなかのサーカス』という穴のあいた絵本を買って読んだことを思い出した。面白い仕掛けだな、と思っていたが、そうしたエッセンスが教育的立場で展開されるのが、この『ファンタジア』だ。
創造力について多くのヒントが詰まっている。
個人的に面白かったのは、『リドリーニ風に』と題した一章。
リドリーニ風、とは、普通ならゆっくりと動くものが加速して動くような「動きの交換」を「リドリーニ風に動く」という。リドリーニはサイレント映画時代の喜劇俳優、ラリー・シモンのことだ。
今、20日の10minutes告知番組までに1本映画が撮れたらいいな、と思っているのだが、それを後押しするような感じだったのだ。
中の一節を引用しておこう。
今日の映画は、ある出来事を伝達するのに文学の方法、つまり常に言葉によって練り上げる方法を用いている。その上で映画に翻訳しているのだ。どれだけ多くの映画が小説を原作にしていることか!科学的な調査の場合だけが、映画カメラを正当に活用し、言葉では説明しても理解できないような現象、あるいは言葉ではなかなか理解しにくい現象をわれわれに見せてくれる。
したがって、映画的手法の技術面における可能性は、まだこれから開拓されるべきものである。
また、一時は未来派の一員とされたブルーノ・ムナーリが、未来派について書いた、こんな文章も印象的だった。
未来派絵画では、ダイナミズムが一枚の絵画に留まっており、ダイナミズムそのものがスタティックになる。そうすると混乱だけが伝わり、観る者はメッセージを引き出せない。動き、速さ、どんな時間的ディメンションもスタティックな技術では表現できない。むしろフィルムやキネティック・アートのような映画的技術を用いた方がいいのである。
ただ、全体に教育的立場から書かれているせいか、言ってることには納得できるが、学校でむりやりやらされる「楽しいこと」みたいな面倒くささを感じた。あれだけ学校が好きだったのに、卒業してみたら二度と学生時代には戻りたくない、と思ってしまった、僕の転向によるものなのか?
NHK-FMのベスト・オブ・クラシックで現代音楽が放送されていた。
主に通勤中に聞いたので、完全に聞けたわけではないが、プログラムをあげておこう。
- アルディッティ弦楽四重奏団演奏会 -
「弦楽四重奏のためのプロジェクション」 湯浅譲二・作曲
(10分58秒)
「弦楽四重奏曲-“西・金・秋”作品96」 石井眞木・作曲
(12分30秒)
「弦楽四重奏曲 第5番」 デュサパン作曲
(17分23秒)
「弦楽四重奏曲“ザ・トゥリー・オブ・ストリングス”」
バートウィスル作曲
(29分05秒)
「弦楽四重奏曲 第2番から 第3楽章」 リゲティ作曲
(3分20秒)
(弦楽四重奏)アルディッティ弦楽四重奏団
~東京・津田ホールで収録~
<2010/6/25>
「弦楽四重奏のためのアンダンテとアレグレット」 リゲティ作曲
(13分08秒)
(弦楽四重奏)アルディッティ弦楽四重奏団
<SONY CLASSICAL SRCR1992>
パヴェーゼ文学集成第6巻『詩文集 詩と神話』
2011年6月9日 読書
パヴェーゼ文学集成第6巻『詩文集 詩と神話』を読んだ。
以下、目次。
詩集 働き疲れて
「祖先」
南の海
祖先
風景1
故郷を失った人びと
大山羊神
風景2
寡婦の息子
真夏の夜の月
かつていた人びと
風景3
夜
「その後」
出会い
孤独癖
黙示
朝
夏
夜想曲
苦しみ
風景7
情熱の女たち
灼けつく土地
寛容
田舎の娼婦
デオーラの思い
二本のタバコ
その後
「田舎の町」
時は流れて
わからない人たち
建てかけの家
田舎の町
先祖返り
恋の冒険
古代の文明
ユリシーズ
規律
風景5
無規律
作者の肖像
九月のグラッパ
踊り
父性
アトランティック・オイル
砂取り人夫の日暮れ
馬車引き
働き疲れて
「母性」
季節
夜の楽しみ
悲しい晩餐
風景4
思い出
声
母性
船頭の妻
酔いどれの老婆
風景8
「緑のたきぎ」
外へ
紙の吸い手たち
世代
反乱
緑のたきぎ
ポッジョ・レアーレ
政治犯の言葉
「父性」
地中海の民
風景6
神話
屋上の楽園
単純
本能
父性
北の星
「付記」
詩人という仕事(『働き疲れて』について)
まだ書かれていない一連の詩について
「異神との対話」
序言
雲
怪物
盲
牝馬
花
野性
波の泡
母親
二人
道
岩山
慰めえぬもの
狼人間
客人
篝火
島
湖
魔女
牡牛
血族
アルゴー船の者たち
葡萄畑
人間
秘教
洪水
美神
神々
作者ノート
詩集「働き疲れて」のほうは、チェーザレ・パヴェーゼの物語詩が堪能できる。
それらの詩のなかで、詩の主人公、語り手は少年や娼婦や老婆、はたまた機械工やら馬ひきなどなど多様な面をみせる。
『異神との対話』の主題は、「作者ノート」によると渾沌×神々、打ち拉がれた人類、悲劇的な人類、微笑む人類と神々の4つ。「広く一般に知れわたっていて、個人的にかつ伝統的に受け容れやすい」ギリシア神話を扱っている。言ってみれば、これは神話を題材にした二次創作なのである。世が世ならば、コミケで販売されていてもおかしくないのだ。(ポルノじゃないけど)。
この作品(レウコとの対話、という名だった)を知ったのは、ストローブ=ユイレの映画からだったが、そのときには気づかなかったことが、こうして文章で読んでみると、みえてきた。
いくつかの文章を引用しておこう。
女神ディアーナと、彼女がよみがえらせたヒッポリュトス(ディアーナによってウィルビウスと名づけられた)の対話。「湖」より
キルケーとレウコテアーの対話。「魔女」より
以下、目次。
詩集 働き疲れて
「祖先」
南の海
祖先
風景1
故郷を失った人びと
大山羊神
風景2
寡婦の息子
真夏の夜の月
かつていた人びと
風景3
夜
「その後」
出会い
孤独癖
黙示
朝
夏
夜想曲
苦しみ
風景7
情熱の女たち
灼けつく土地
寛容
田舎の娼婦
デオーラの思い
二本のタバコ
その後
「田舎の町」
時は流れて
わからない人たち
建てかけの家
田舎の町
先祖返り
恋の冒険
古代の文明
ユリシーズ
規律
風景5
無規律
作者の肖像
九月のグラッパ
踊り
父性
アトランティック・オイル
砂取り人夫の日暮れ
馬車引き
働き疲れて
「母性」
季節
夜の楽しみ
悲しい晩餐
風景4
思い出
声
母性
船頭の妻
酔いどれの老婆
風景8
「緑のたきぎ」
外へ
紙の吸い手たち
世代
反乱
緑のたきぎ
ポッジョ・レアーレ
政治犯の言葉
「父性」
地中海の民
風景6
神話
屋上の楽園
単純
本能
父性
北の星
「付記」
詩人という仕事(『働き疲れて』について)
まだ書かれていない一連の詩について
「異神との対話」
序言
雲
怪物
盲
牝馬
花
野性
波の泡
母親
二人
道
岩山
慰めえぬもの
狼人間
客人
篝火
島
湖
魔女
牡牛
血族
アルゴー船の者たち
葡萄畑
人間
秘教
洪水
美神
神々
作者ノート
詩集「働き疲れて」のほうは、チェーザレ・パヴェーゼの物語詩が堪能できる。
それらの詩のなかで、詩の主人公、語り手は少年や娼婦や老婆、はたまた機械工やら馬ひきなどなど多様な面をみせる。
『異神との対話』の主題は、「作者ノート」によると渾沌×神々、打ち拉がれた人類、悲劇的な人類、微笑む人類と神々の4つ。「広く一般に知れわたっていて、個人的にかつ伝統的に受け容れやすい」ギリシア神話を扱っている。言ってみれば、これは神話を題材にした二次創作なのである。世が世ならば、コミケで販売されていてもおかしくないのだ。(ポルノじゃないけど)。
この作品(レウコとの対話、という名だった)を知ったのは、ストローブ=ユイレの映画からだったが、そのときには気づかなかったことが、こうして文章で読んでみると、みえてきた。
いくつかの文章を引用しておこう。
女神ディアーナと、彼女がよみがえらせたヒッポリュトス(ディアーナによってウィルビウスと名づけられた)の対話。「湖」より
ディアーナ よく考えてみるがよい。ウィルビウス=ヒッポリュトスよ。おまえはいままで幸せだったのに
ウィルビウス 構わない、奥さま。わたしはあまりにもしばしば、湖にわが身を映してしまった。わたしの願いは生きることだ、幸せになることではない。
キルケーとレウコテアーの対話。「魔女」より
レウコテアー でも、そんなことまで彼(オデュッセウス)に言ったの、あなたといっしょに過ごした1年のあいだに?
キルケー ああ、娘よ、人間を相手に宿命の話をしてはいけないわ。彼らはすべてを言いつくしたと思いこむから。それを、鉄の鎖とか、天の定めとか、呼んだぐらいで。わたしたちのことは、あなたも知るように、宿命の女主人と呼んでいる。
バッケーとオルペウスの対話。「慰めえぬもの」の第一稿より
バッケー オルペウス、あたしにはとても信じられないわ・・・
オルペウス 繰り返しておくが、わたしはわざと振り返ったのだ。そういう考えならば嫌というほど持っていた。だから、わたしの後を追いかけてくる他の女たちにも言ってやってもらいたい。振り返ったぐらいで地獄へ落とせるものならば、いくらでもそうするだろう、と
『CATS,CATS,CATS』『ANGELS,ANGELS,ANGELS』
2011年6月7日 読書
横尾忠則監修の、アンディ・ウォーホルギフトブックシリーズ。
猫のイラストレーションと、アンディ・ウォーホルの言葉をチョイスした、『CATS,CATS,CATS』と、天使のイラストレーションと言葉の『ANGELS,ANGELS,ANGELS』を読んだ。他にもシリーズとしては『KISS~』もあるらしい。(それは見つけられなかった)洋書では、シューズのイラストレーションを集めたのもあるらしく、アンディ・ウォーホルのフェチがうかがえる。
中の文章は、以下の本から引用したものだそうだ。
『アンディ・ウォーホルの哲学』
『アメリカ』
『ポッピズム』
『アンディ・ウォーホルのパーティーブック』
『アンディ・ウォーホル日記』
『アンディ・ウォーホル:彼自身の言葉のなかで』
引用した文章を読んで事足れりとするのでなく、これらの本は、それぞれ面白そうなので、いずれ読んでみたい。
それぞれ、1つだけ引用しておこう。
CATS,CATS,CATS
「哀しみにひたっているときって、なんだろう?ハッピーになれるというのに」
ANGELS,ANGELS,ANGELS
「美しさというのは、なにくわぬ顔でやってしまうひとにこそ、縁があるってものさ」
猫のイラストレーションと、アンディ・ウォーホルの言葉をチョイスした、『CATS,CATS,CATS』と、天使のイラストレーションと言葉の『ANGELS,ANGELS,ANGELS』を読んだ。他にもシリーズとしては『KISS~』もあるらしい。(それは見つけられなかった)洋書では、シューズのイラストレーションを集めたのもあるらしく、アンディ・ウォーホルのフェチがうかがえる。
中の文章は、以下の本から引用したものだそうだ。
『アンディ・ウォーホルの哲学』
『アメリカ』
『ポッピズム』
『アンディ・ウォーホルのパーティーブック』
『アンディ・ウォーホル日記』
『アンディ・ウォーホル:彼自身の言葉のなかで』
引用した文章を読んで事足れりとするのでなく、これらの本は、それぞれ面白そうなので、いずれ読んでみたい。
それぞれ、1つだけ引用しておこう。
CATS,CATS,CATS
「哀しみにひたっているときって、なんだろう?ハッピーになれるというのに」
ANGELS,ANGELS,ANGELS
「美しさというのは、なにくわぬ顔でやってしまうひとにこそ、縁があるってものさ」
宇野亜喜良の『少女からの手紙』を読んだ。
以下、目次
蘇州より
カードの城
ロンドンの霧
アリスのように
森という字
若草の萌える頃
木・私の友だち
悪いヤツ
王様とロバと私
モン・サンミッシェル(コクトー)
泣く女
犬と魚
月光
ヴェニスにて
たいくつをはいた猫
悲しみよこんにちは
シモオン(ルミ・ド、グゥルモン)
小曲(フィリップ・シャヴァネエ)
パヴァーヌ
失恋ホテル
あいつ
スイスにて
牧神の午後
恋猫(寺山修司)
スフィンクス
城で
冒険
モスクワにて
バグダッドの盗賊
昔の唄
夕暮れの戸口(シャルル・ゲェラン)
淋しいという字
涙という字
花
牡牛フェルジナンド
タヒチアン
宇野亜喜良のいつまでも古びない、思春期を刺激するイラストレーションと、宇野亜喜良好みの世界を切り取って紹介する、魅惑の1冊。
以下、目次
蘇州より
カードの城
ロンドンの霧
アリスのように
森という字
若草の萌える頃
木・私の友だち
悪いヤツ
王様とロバと私
モン・サンミッシェル(コクトー)
泣く女
犬と魚
月光
ヴェニスにて
たいくつをはいた猫
悲しみよこんにちは
シモオン(ルミ・ド、グゥルモン)
小曲(フィリップ・シャヴァネエ)
パヴァーヌ
失恋ホテル
あいつ
スイスにて
牧神の午後
恋猫(寺山修司)
スフィンクス
城で
冒険
モスクワにて
バグダッドの盗賊
昔の唄
夕暮れの戸口(シャルル・ゲェラン)
淋しいという字
涙という字
花
牡牛フェルジナンド
タヒチアン
宇野亜喜良のいつまでも古びない、思春期を刺激するイラストレーションと、宇野亜喜良好みの世界を切り取って紹介する、魅惑の1冊。
『特殊まんが-前衛の-道』
2011年6月3日 読書
根本敬の『特殊まんが-前衛の-道』を読んだ。
根本さん版の『まんが道』に、但し書きで「特殊」「前衛」をつけざるをえない、根本さんのヒストリーをたどる(かのような)1冊。
以下、目次。
はじめに-アイム・フリー-
1.人の役に立つ
2.ガロ デビュー前後
3.没入
4.宿題十三年
5.締切り対お化け
6.無知も穴ドレズ
7.悪戯の脳
8.韓国の大學で
9.大麦太郎ネヴァー・ダイ
10.ロックンロールにヨロシク!
11.まんがと因果鉄道の旅
おわりに-ドリームズ・カム・トゥルー-
巻末スピリチュアル対論 根本敬、天久聖一
読売巨人軍 まんが世相巻末放談
「お前」に或いは鏡の向こうの「お前」へ
純度百%のアート/わたしは、もっと革細工をつくるときにゆうきをだしたい/ぼくは、いじめられている子ブタや地しんが起きた時に勇気を出したいです/わたしは、肝試しとかする人が「凄いな」と思った/本当の強さは「優しさ」です/免許がいるのは次のうちどれ?1、車の運転2、釣り3、飲み会/文鳥のオスメス見分け方/発情期。何か新しいこと始めよう!(アイル・トライ・サムシング・ニュー)/僕は、犬に噛まれたらゆうきを出したい/読売巨人軍プレゼンツこだわる男の「必須極太アイテム」とは/1、非常用通報ボタン(列車を緊急停止させる装置)/2、モデルガン/3、石灯籠/4、ラック(マガジン用)/5、べっ甲の飾り物/じゃあ、居酒屋に移動しますか/6、小學読本/7,モニタカメラ(犯罪抑止を目的として)/8、作業効率を高めるスカイポーター/会わすなら壁の前で/閉店時間です/タクシーの中/本物の男には、最低七人の敵がいるのだから/わたしは、もっと革細工をつくるときにゆうきをだしたい/二軒目は既にスタートしていたらしい/秋まで有能なようでありません/あ、誰か飲み物に何か入れた?(7頁から8頁まで繰り返し)/ウルトラショートのチルアウトのツボですので/私は、自分の大事な同僚がほかの上司にいじめられていたら、私は、その人にさからっている気分で「止めて下さい」といいます/暴走族(リーゼント禁止)/で、解説終わって/歯のないたけとんぼ教室/不名誉を持つもう一人の人の近くのそれである秋/我々が一番目だけに安全なOnlyであるならば、それは均一です/
図版
巻末特別企画新宿タワー・ロックスター伝説
本書には、この前ドミューンで相原信洋追悼イベントやったときに披露した、エロ話とか、京都のトランスポップギャラリーでのイベントで映像つきで語ってくれた「ドリームズ・カム・トゥルー」の話などが語られていた。
なお、巻末対談の小見出しは、99%内容とは無関係。写真のキャプションもむちゃくちゃなうえ、同じ写真ばかり使う、という特殊前衛さ!
根本さん版の『まんが道』に、但し書きで「特殊」「前衛」をつけざるをえない、根本さんのヒストリーをたどる(かのような)1冊。
以下、目次。
はじめに-アイム・フリー-
1.人の役に立つ
2.ガロ デビュー前後
3.没入
4.宿題十三年
5.締切り対お化け
6.無知も穴ドレズ
7.悪戯の脳
8.韓国の大學で
9.大麦太郎ネヴァー・ダイ
10.ロックンロールにヨロシク!
11.まんがと因果鉄道の旅
おわりに-ドリームズ・カム・トゥルー-
巻末スピリチュアル対論 根本敬、天久聖一
読売巨人軍 まんが世相巻末放談
「お前」に或いは鏡の向こうの「お前」へ
純度百%のアート/わたしは、もっと革細工をつくるときにゆうきをだしたい/ぼくは、いじめられている子ブタや地しんが起きた時に勇気を出したいです/わたしは、肝試しとかする人が「凄いな」と思った/本当の強さは「優しさ」です/免許がいるのは次のうちどれ?1、車の運転2、釣り3、飲み会/文鳥のオスメス見分け方/発情期。何か新しいこと始めよう!(アイル・トライ・サムシング・ニュー)/僕は、犬に噛まれたらゆうきを出したい/読売巨人軍プレゼンツこだわる男の「必須極太アイテム」とは/1、非常用通報ボタン(列車を緊急停止させる装置)/2、モデルガン/3、石灯籠/4、ラック(マガジン用)/5、べっ甲の飾り物/じゃあ、居酒屋に移動しますか/6、小學読本/7,モニタカメラ(犯罪抑止を目的として)/8、作業効率を高めるスカイポーター/会わすなら壁の前で/閉店時間です/タクシーの中/本物の男には、最低七人の敵がいるのだから/わたしは、もっと革細工をつくるときにゆうきをだしたい/二軒目は既にスタートしていたらしい/秋まで有能なようでありません/あ、誰か飲み物に何か入れた?(7頁から8頁まで繰り返し)/ウルトラショートのチルアウトのツボですので/私は、自分の大事な同僚がほかの上司にいじめられていたら、私は、その人にさからっている気分で「止めて下さい」といいます/暴走族(リーゼント禁止)/で、解説終わって/歯のないたけとんぼ教室/不名誉を持つもう一人の人の近くのそれである秋/我々が一番目だけに安全なOnlyであるならば、それは均一です/
図版
巻末特別企画新宿タワー・ロックスター伝説
本書には、この前ドミューンで相原信洋追悼イベントやったときに披露した、エロ話とか、京都のトランスポップギャラリーでのイベントで映像つきで語ってくれた「ドリームズ・カム・トゥルー」の話などが語られていた。
なお、巻末対談の小見出しは、99%内容とは無関係。写真のキャプションもむちゃくちゃなうえ、同じ写真ばかり使う、という特殊前衛さ!
『変身のためのレクイエム』
2011年6月2日 読書
ヤン・ファーブルの『変身のためのレクイエム』を読んだ。
舞台作品のための4本。主に「死」をテーマにしている。
「ひとつの部族、それが私」
帯にも引用してある「私はやめないだろう/一枚一枚/魂の皮を剥ぐ」はこの作品からのもの。
アントナン・アルトーのテクストに触発されたもの。
ウィルスは人間を
器官なき身体に
記憶なき器に変えるだろう
神は人間を自由に陽気にする
神はウィルス
ウィルスとは神である
という部分がある。
また、神の手首に、うなじに、肛門に噛み付き、その血や糞に洗われるまで自分を清めない、というイメージが、肉体的にリアル!
「変身のためのレクイエム」
この作品は登場人物も多いが、そのなかで、「歴史の声」はさまざまな死のカタログをニュース速報のように列挙し、「死者たちを笑わせようとする蝶」はジョークを次々ととばす。
その「歴史の声」ではジョン・レノン殺害、コカイン中毒死、オサマ・ビン・ラディンの演説、HIV感染、天安門事件、2004年の津波の被害者数、911、カート・コバーン、クローン羊ドリー、ジェフ・クーンズのバスケットボール作品、ルワンダ、ネルソン・マンデラ、ヨーゼフ・ボイスなどが取り上げられる。
蝶のジョークも、ヒトラーやコミュニスト、きちがい、など、辛味がきいていて、面白い。
「またもけだるい灰色のデルタデー」
ジャン・アメリーの「自分に手を下すこと-自殺について」、ボビー・ジェントリーの「ビリー・ジョーに捧げるオード」を発想の源にしている。
デルタデーは「ミシシッピー河のデルタ地帯の靄の立ち込めた暑い日」のこと。
またもけだるい灰色のデルタデー
僕はいま
飛び込もうとしている
がリフレインされる。
「死の天使」
ウィリアム・フォーサイスに献じられた「ある男または女または両性具有者のためのモノローグ」で、「両性具有的な存在アンディ・ウォーホールに想をえた」と書かれている。
本書の紹介文には、次のような文章が並んでいる。
「残酷に、また滑稽に、そして静かに<死>をあばき出す 生の単なる終焉として<死>を捨て置くのではなく、生の現実の出来事である<死>を見つめること。生の惨状を受容し鎮めるのではなく、生を少しだけ<変身>させること」
舞台作品のための4本。主に「死」をテーマにしている。
「ひとつの部族、それが私」
帯にも引用してある「私はやめないだろう/一枚一枚/魂の皮を剥ぐ」はこの作品からのもの。
アントナン・アルトーのテクストに触発されたもの。
ウィルスは人間を
器官なき身体に
記憶なき器に変えるだろう
神は人間を自由に陽気にする
神はウィルス
ウィルスとは神である
という部分がある。
また、神の手首に、うなじに、肛門に噛み付き、その血や糞に洗われるまで自分を清めない、というイメージが、肉体的にリアル!
「変身のためのレクイエム」
この作品は登場人物も多いが、そのなかで、「歴史の声」はさまざまな死のカタログをニュース速報のように列挙し、「死者たちを笑わせようとする蝶」はジョークを次々ととばす。
その「歴史の声」ではジョン・レノン殺害、コカイン中毒死、オサマ・ビン・ラディンの演説、HIV感染、天安門事件、2004年の津波の被害者数、911、カート・コバーン、クローン羊ドリー、ジェフ・クーンズのバスケットボール作品、ルワンダ、ネルソン・マンデラ、ヨーゼフ・ボイスなどが取り上げられる。
蝶のジョークも、ヒトラーやコミュニスト、きちがい、など、辛味がきいていて、面白い。
「またもけだるい灰色のデルタデー」
ジャン・アメリーの「自分に手を下すこと-自殺について」、ボビー・ジェントリーの「ビリー・ジョーに捧げるオード」を発想の源にしている。
デルタデーは「ミシシッピー河のデルタ地帯の靄の立ち込めた暑い日」のこと。
またもけだるい灰色のデルタデー
僕はいま
飛び込もうとしている
がリフレインされる。
「死の天使」
ウィリアム・フォーサイスに献じられた「ある男または女または両性具有者のためのモノローグ」で、「両性具有的な存在アンディ・ウォーホールに想をえた」と書かれている。
本書の紹介文には、次のような文章が並んでいる。
「残酷に、また滑稽に、そして静かに<死>をあばき出す 生の単なる終焉として<死>を捨て置くのではなく、生の現実の出来事である<死>を見つめること。生の惨状を受容し鎮めるのではなく、生を少しだけ<変身>させること」
『破小路ねるのと堕天列車事件』
2011年6月1日 読書
木戸実験(きど・みのり)の『破小路ねるのと堕天列車事件』を読んだ。
ライトノベルで本格推理はなかなかないので、どんな感じなのかな、と思って楽しみに読んだ。
本に書かれてあるあらすじを紹介すると。
僕、砂島直也の彼女は文芸部所属のメガネっ娘、破小路ねるの。容姿可憐にして純潔な文系娘である彼女は、ちょっとした指や肩の接触から、ハレンチな妄想の中へ飛翔するらしく、油断すると鼻血を吹いて倒れてしまう。ある日、約450キロ離れた場所を走っていたはずの電車が突如、高校校舎に上からつき刺さるという珍奇な事件が起こり、僕と彼女はこの謎に挑戦するが・・・!
ふむ。これはすごい。
作者のあとがきによると、
「本作は、ボリス・ヴィアンの『北京の秋』のイメージを、阿井渉介先生風にミステリ翻訳するとどうなるか、という誰得コンセプトで書きはじめました」
とある。これは、またまたすごい。
校舎に列車が突き刺さる、という突拍子もない謎。しかも事件は千葉で起こっているのに、突き刺さっている列車は神戸の六甲鉄道の車両だったのだ。
前半は、主人公の少年・砂島直也、鼻血少女・破小路ねるの、文芸部部長・牛越瞳が三者三様の推理をたたかわせる、推理合戦。これは素晴らしい!で、後半はいかにもなライトノベル的展開の4つめの真相が展開される。
それぞれ、こんな印象。
砂島直也の推理:困難は分割せよ
破小路ねるのの推理:上から列車が突き刺さったのではなく、学校が地盤沈下して埋めてあった列車に突き刺さった。
牛越瞳の推理:駅の怪鳥鳩時計を利用した機械的トリック。
真相:妄想の現実化。こういうのをセカイ系っていうの?ビューティフルドリーマーの世界の来歴みたいなもの。
さらに、そのライトノベル的なものの顛末に決着をつける伏線が、実は推理合戦でとりあげられたあるファクターにあった、という知的快感。ちょっとありえない力を持ったファクターに信憑性をもたせるために、あの推理合戦は利用されたのか、という「やられた!」感が楽しかった。
推理合戦のあとに、こういう真相を持ってくるのは、まるで火刑法廷のラストを300ページにわたって書いたようなものだが、本書は全体でも大長編になっておらず、そこは作者の抑制がきいていて、好感が持てた。半分に削れるだろ、とツッコミたくなるような小説が多いなかで、よくこのページ数でおさめた、と思った。
まさに直球(?)の本格推理と言っていいだろう。
ただし、この作品で連想させられた「ボリス・ヴィアン」「阿井渉介」「火刑法廷」が若いライトノベル読者の共感を得られるとは思えず、次の作品からは、結局本格ミステリーの世界からはずれた、ライトノベル寄りの作品を書かされてしまうんじゃないか、というのが、心配だ。
ライトノベルで本格推理はなかなかないので、どんな感じなのかな、と思って楽しみに読んだ。
本に書かれてあるあらすじを紹介すると。
僕、砂島直也の彼女は文芸部所属のメガネっ娘、破小路ねるの。容姿可憐にして純潔な文系娘である彼女は、ちょっとした指や肩の接触から、ハレンチな妄想の中へ飛翔するらしく、油断すると鼻血を吹いて倒れてしまう。ある日、約450キロ離れた場所を走っていたはずの電車が突如、高校校舎に上からつき刺さるという珍奇な事件が起こり、僕と彼女はこの謎に挑戦するが・・・!
ふむ。これはすごい。
作者のあとがきによると、
「本作は、ボリス・ヴィアンの『北京の秋』のイメージを、阿井渉介先生風にミステリ翻訳するとどうなるか、という誰得コンセプトで書きはじめました」
とある。これは、またまたすごい。
校舎に列車が突き刺さる、という突拍子もない謎。しかも事件は千葉で起こっているのに、突き刺さっている列車は神戸の六甲鉄道の車両だったのだ。
前半は、主人公の少年・砂島直也、鼻血少女・破小路ねるの、文芸部部長・牛越瞳が三者三様の推理をたたかわせる、推理合戦。これは素晴らしい!で、後半はいかにもなライトノベル的展開の4つめの真相が展開される。
それぞれ、こんな印象。
砂島直也の推理:困難は分割せよ
破小路ねるのの推理:上から列車が突き刺さったのではなく、学校が地盤沈下して埋めてあった列車に突き刺さった。
牛越瞳の推理:駅の怪鳥鳩時計を利用した機械的トリック。
真相:妄想の現実化。こういうのをセカイ系っていうの?ビューティフルドリーマーの世界の来歴みたいなもの。
さらに、そのライトノベル的なものの顛末に決着をつける伏線が、実は推理合戦でとりあげられたあるファクターにあった、という知的快感。ちょっとありえない力を持ったファクターに信憑性をもたせるために、あの推理合戦は利用されたのか、という「やられた!」感が楽しかった。
推理合戦のあとに、こういう真相を持ってくるのは、まるで火刑法廷のラストを300ページにわたって書いたようなものだが、本書は全体でも大長編になっておらず、そこは作者の抑制がきいていて、好感が持てた。半分に削れるだろ、とツッコミたくなるような小説が多いなかで、よくこのページ数でおさめた、と思った。
まさに直球(?)の本格推理と言っていいだろう。
ただし、この作品で連想させられた「ボリス・ヴィアン」「阿井渉介」「火刑法廷」が若いライトノベル読者の共感を得られるとは思えず、次の作品からは、結局本格ミステリーの世界からはずれた、ライトノベル寄りの作品を書かされてしまうんじゃないか、というのが、心配だ。
『魔界探偵冥王星O ジャンクションのJ』
2011年5月31日 読書
越前魔太郎の『魔界探偵冥王星O ジャンクションのJ』を読んだ。
越前魔太郎は、複数の作家による覆面ペンネームで、この「J」の正体は新城カズマであることが、既に発表されている。
そして、これまでに発表された「冥王星O」作品のそれぞれに絡めて、文体も多様に、複数の物語が語られる。これはつまり、起こらなかったことも歴史のうち、という寺山修司がよく使う文句をライトノベルで実現した、ということのようだ。
わがままな食欲魔人が子豚だったり、飲むと意識がのっとられて汗で敵を撃退するために露出狂になったり、白雪姫モチーフのマトリックス的世界だったり、いろんな作品を書き落としていく越前魔太郎の原稿を拾っては読む冥王星O。
とくに興味深かったのは、4章で、ここは冥王星Oをいろんなタイプのキャラクターにあてはめた短編集めいた作りになっている。
「開始地点」まあ、越前魔太郎VS冥王星Oのプロローグ
「完全なる感情」女子寮乙女物語
「己喰らい事件」再生能力を持ち自分を食べて生き続ける宇宙飛行士。
「冥王星暗殺事件」大量の生活雑貨、家電が降ってきてピアノの下敷きで暗殺された大統領(冥王星O)。これは音楽か?
「魔界迷宮事件」ウラシマ地下迷宮を攻略しようとする勇者たち
「中継地点」ここに、冥王星Oの多面性をあらわす文章があるので、引用しておこう。
それはこれまでにあった、そしてこれからあるかもしれない「冥王星O」の事件簿だ。
閉鎖された庭園で、愛についての実験を繰り返す「冥王星O」がいた。
「冥王星O」の名を冠する、「彼ら」に対抗する薬物があった。
死によって極上のメロディを奏でた「冥王星O」がいた。
そして膨大な刻を駆けぬけながら、地下世界を探索し続ける「冥王星O」がいた。
人体楽器に魅せられた「冥王星O」がいた。
13年の時を隔て、幼き日の友情に決着を付けた「冥王星O」がいた。
ここにある原稿、幾千万の寝物語。これこそが、「冥王星O」の正体そのものだ。
これらが、爆発して炎上。
「ジャンクション事件」「あなた=越前魔太郎」vs「冥王星O」
ここでは冥王星Oが越前魔太郎について語っているので、引用。
「お前は、カート・ヴォネガットのキルゴア・トラウト、村上春樹のデレク・ハートフィールド、上遠野浩平の霧間誠一・・・。ああ、お前は本物の作家なんじゃない。この浄瑠璃を書いている作家の主張を反映する、哀しい操り人形なのだよ」
そして、こんなことも。
「私は「冥王星O」を利用して、多くの愛についての実験を繰り返してきた。これからも繰り返すだろう。「ジャンクション」のアーカイブに、愛についてのデータを蓄積するために」
このクライマックスがいくつもある4章を経て、エピローグでは脂肪ぶよぶよの越前魔太郎が原稿を吐いているのに、ついに冥王星Oは追いつくのである。
越前魔太郎は、複数の作家による覆面ペンネームで、この「J」の正体は新城カズマであることが、既に発表されている。
そして、これまでに発表された「冥王星O」作品のそれぞれに絡めて、文体も多様に、複数の物語が語られる。これはつまり、起こらなかったことも歴史のうち、という寺山修司がよく使う文句をライトノベルで実現した、ということのようだ。
わがままな食欲魔人が子豚だったり、飲むと意識がのっとられて汗で敵を撃退するために露出狂になったり、白雪姫モチーフのマトリックス的世界だったり、いろんな作品を書き落としていく越前魔太郎の原稿を拾っては読む冥王星O。
とくに興味深かったのは、4章で、ここは冥王星Oをいろんなタイプのキャラクターにあてはめた短編集めいた作りになっている。
「開始地点」まあ、越前魔太郎VS冥王星Oのプロローグ
「完全なる感情」女子寮乙女物語
「己喰らい事件」再生能力を持ち自分を食べて生き続ける宇宙飛行士。
「冥王星暗殺事件」大量の生活雑貨、家電が降ってきてピアノの下敷きで暗殺された大統領(冥王星O)。これは音楽か?
「魔界迷宮事件」ウラシマ地下迷宮を攻略しようとする勇者たち
「中継地点」ここに、冥王星Oの多面性をあらわす文章があるので、引用しておこう。
それはこれまでにあった、そしてこれからあるかもしれない「冥王星O」の事件簿だ。
閉鎖された庭園で、愛についての実験を繰り返す「冥王星O」がいた。
「冥王星O」の名を冠する、「彼ら」に対抗する薬物があった。
死によって極上のメロディを奏でた「冥王星O」がいた。
そして膨大な刻を駆けぬけながら、地下世界を探索し続ける「冥王星O」がいた。
人体楽器に魅せられた「冥王星O」がいた。
13年の時を隔て、幼き日の友情に決着を付けた「冥王星O」がいた。
ここにある原稿、幾千万の寝物語。これこそが、「冥王星O」の正体そのものだ。
これらが、爆発して炎上。
「ジャンクション事件」「あなた=越前魔太郎」vs「冥王星O」
ここでは冥王星Oが越前魔太郎について語っているので、引用。
「お前は、カート・ヴォネガットのキルゴア・トラウト、村上春樹のデレク・ハートフィールド、上遠野浩平の霧間誠一・・・。ああ、お前は本物の作家なんじゃない。この浄瑠璃を書いている作家の主張を反映する、哀しい操り人形なのだよ」
そして、こんなことも。
「私は「冥王星O」を利用して、多くの愛についての実験を繰り返してきた。これからも繰り返すだろう。「ジャンクション」のアーカイブに、愛についてのデータを蓄積するために」
このクライマックスがいくつもある4章を経て、エピローグでは脂肪ぶよぶよの越前魔太郎が原稿を吐いているのに、ついに冥王星Oは追いつくのである。
『「トキワ荘」無頼派 漫画家・森安なおや伝』
2011年5月30日 読書
伊吹隼人の『「トキワ荘」無頼派 漫画家・森安なおや伝』を読んだ。
以下、目次。
ある無名漫画家の死
岡山から始まった“まんが道”
田河水泡門下をへて独立へ
「新漫画党」結成と学童社の倒産
輝ける青春・「トキワ荘」の時代
貸本漫画衰退、漫画家廃業を決意
夜の世界と流転の日々
トキワ荘解体、ドキュメンタリー番組出演
晩年の生活と『烏城物語』
併載復刻『赤い自転車』森安なおや・作
森安なおや・作品リスト
僕にとって、森安なおやを印象づけたのは、作中にもあるドキュメンタリー番組だったが、その番組の裏話が書いてある。
森安なおやが集英社に原稿を持ち込んで、結局採用されなかったくだりについて。森安なおや本人と交流もあった古書店主、高畠裕幸氏(巻末の作品リストも作成している)による、次のような発言が載せられている。
「あの番組は、NHKが最初から結末を決めてやっていたそうです・・・ジャンプでは最初、採用の方向で動いていて、アシスタントを付ける話もあったらしいんですが、NHKが『結局ダメでした』というオチにするため、『断ってくれ』って頼んだらしくて。あの持ち込みにしても、もしかしたら無理やり行かせたのかもしれませんね」
筆者もいうように、「太平洋戦争と少年飛行兵」のテーマで描いた漫画を『ヤングジャンプ』に持ち込むのは無理がある、と確かに思える。
とは言え、このドキュメンタリー番組なしでは確実に森安なおやは歴史の闇に葬られていたにちがいないので、番組を責める気にはなれない。面白い番組だったしね。
番組までのことは、藤子漫画などでも森安なおやのエピソードが読めるのでわかるが、それから後の人生については、この本を読むまではまったく知らなかった。
ただ、そこに何か面白いエピソードがあるのかと言えば、まあ、無いのである。
本書の眼目は、「併載」された「赤い自転車」にあると言っていいだろう。
そして、本文である「森安なおや伝」は長い解説だと取ればいいようだ。
と、いうのは、まず、森安なおやについて書くことの少なさによるのだろうか、たとえばトキワ荘の他の住人についての記述とか、注釈的な情報が多すぎること。そして、とくに前半、森安なおやの厄介さがエピソードとしてさんざん語られるのだが、そこに森安なおやへの愛が感じられないのである。トキワ荘の面々による森安なおやエピソードや、テレビ番組などでは感じなかった感情だった。まるでどうしようもない森安なおやに対して、筆者は怒りを覚えているんじゃないか、と思えたほどだ。
と、いうわけで、「赤い自転車」である。
「なかよしまんが物語」と銘打たれており、目次は次のとおり。
夕焼け雲
たっちゃんのねがい
黒いまつばづえ
のぼれアドバルーン
みんな笑わないで
こがらしふくな
きえたしゃぼん玉
にじの中の少年
がんばれたっちゃん
赤い自転車
当時の世相がどうだったか偲ばれる面白い作品で、いかにも貸本漫画なテイストがうれしい。でも、この本が出た1956年に、手塚治虫はすでに「火の鳥」も発表しており、「ライオンブックス」のシリーズも描いているのである。手塚治虫の現代性と偉大さが、逆にわかって感心してしまった。
以下、目次。
ある無名漫画家の死
岡山から始まった“まんが道”
田河水泡門下をへて独立へ
「新漫画党」結成と学童社の倒産
輝ける青春・「トキワ荘」の時代
貸本漫画衰退、漫画家廃業を決意
夜の世界と流転の日々
トキワ荘解体、ドキュメンタリー番組出演
晩年の生活と『烏城物語』
併載復刻『赤い自転車』森安なおや・作
森安なおや・作品リスト
僕にとって、森安なおやを印象づけたのは、作中にもあるドキュメンタリー番組だったが、その番組の裏話が書いてある。
森安なおやが集英社に原稿を持ち込んで、結局採用されなかったくだりについて。森安なおや本人と交流もあった古書店主、高畠裕幸氏(巻末の作品リストも作成している)による、次のような発言が載せられている。
「あの番組は、NHKが最初から結末を決めてやっていたそうです・・・ジャンプでは最初、採用の方向で動いていて、アシスタントを付ける話もあったらしいんですが、NHKが『結局ダメでした』というオチにするため、『断ってくれ』って頼んだらしくて。あの持ち込みにしても、もしかしたら無理やり行かせたのかもしれませんね」
筆者もいうように、「太平洋戦争と少年飛行兵」のテーマで描いた漫画を『ヤングジャンプ』に持ち込むのは無理がある、と確かに思える。
とは言え、このドキュメンタリー番組なしでは確実に森安なおやは歴史の闇に葬られていたにちがいないので、番組を責める気にはなれない。面白い番組だったしね。
番組までのことは、藤子漫画などでも森安なおやのエピソードが読めるのでわかるが、それから後の人生については、この本を読むまではまったく知らなかった。
ただ、そこに何か面白いエピソードがあるのかと言えば、まあ、無いのである。
本書の眼目は、「併載」された「赤い自転車」にあると言っていいだろう。
そして、本文である「森安なおや伝」は長い解説だと取ればいいようだ。
と、いうのは、まず、森安なおやについて書くことの少なさによるのだろうか、たとえばトキワ荘の他の住人についての記述とか、注釈的な情報が多すぎること。そして、とくに前半、森安なおやの厄介さがエピソードとしてさんざん語られるのだが、そこに森安なおやへの愛が感じられないのである。トキワ荘の面々による森安なおやエピソードや、テレビ番組などでは感じなかった感情だった。まるでどうしようもない森安なおやに対して、筆者は怒りを覚えているんじゃないか、と思えたほどだ。
と、いうわけで、「赤い自転車」である。
「なかよしまんが物語」と銘打たれており、目次は次のとおり。
夕焼け雲
たっちゃんのねがい
黒いまつばづえ
のぼれアドバルーン
みんな笑わないで
こがらしふくな
きえたしゃぼん玉
にじの中の少年
がんばれたっちゃん
赤い自転車
当時の世相がどうだったか偲ばれる面白い作品で、いかにも貸本漫画なテイストがうれしい。でも、この本が出た1956年に、手塚治虫はすでに「火の鳥」も発表しており、「ライオンブックス」のシリーズも描いているのである。手塚治虫の現代性と偉大さが、逆にわかって感心してしまった。
『膝のうえのともだち』
2011年5月29日 読書
町田康の『膝のうえのともだち』を読んだ。
飼い猫ヘッケ、ゲンゾー、奈奈、ココア、パフィー、ニゴ、シャア、ウメチャン、シャンティ、パンク、エル、トラ、オルセンの写真に、エッセイ『猫にかまけて』『猫のあしあと』から引用した文章がはさまれる。
また、巻末には「ココア」と題する書き下ろし短編小説が載せられていた。
22年飼っていた猫が死んで2ヶ月たった頃の話。
泥酔してボコボコにされて昏倒した後、めざめたら、猫と人間が逆転した世界にいた、という物語。そこでは人間は廃棄弁当を盗んで食べ、それを猫は「人間がゴミを荒らす」と排斥したりするのである。たまにボランティアの猫が、人間に定期的に食べ物をくれるが、
「しかし、ボランティアのそうした行為に批判的な猫も多く、不衛生な人間にうろうろされると気分が悪いので、行政が積極的に駆除すべき、という猫は少なくなかった」のである。
「また、ただ単に楽しみのためだけに人間を虐待する猫も居るらしく、餌場に集まる人間には瞼を接着剤で貼り合わせられたことのある人間やバーナーで燃やされた人間、脚を切断された人間、矢で射たれた人間がいた」
猫と人間をいれかえただけなのに、なんと悲惨な物語になってしまうのか。
当然、猫と人間のあいだでは話も通じないのだが、飼ってたココアがあらわれて、主人公と普通に話す。そこでのくだりが、本編のヤマ場!
「私はこの世界では言語を持たず、にゃあにゃあ、としか言えないんだけど、なんでココアとだけは話ができるのだろうか」
「前の世界で私はにゃあにゃあとしか発音しませんでした。でもあなたは私の言うことがわかったじゃありませんか。同じことですよ」
うかつにも、ここで感動してしまった。そんなつもりじゃなかったのに!
飼い猫ヘッケ、ゲンゾー、奈奈、ココア、パフィー、ニゴ、シャア、ウメチャン、シャンティ、パンク、エル、トラ、オルセンの写真に、エッセイ『猫にかまけて』『猫のあしあと』から引用した文章がはさまれる。
また、巻末には「ココア」と題する書き下ろし短編小説が載せられていた。
22年飼っていた猫が死んで2ヶ月たった頃の話。
泥酔してボコボコにされて昏倒した後、めざめたら、猫と人間が逆転した世界にいた、という物語。そこでは人間は廃棄弁当を盗んで食べ、それを猫は「人間がゴミを荒らす」と排斥したりするのである。たまにボランティアの猫が、人間に定期的に食べ物をくれるが、
「しかし、ボランティアのそうした行為に批判的な猫も多く、不衛生な人間にうろうろされると気分が悪いので、行政が積極的に駆除すべき、という猫は少なくなかった」のである。
「また、ただ単に楽しみのためだけに人間を虐待する猫も居るらしく、餌場に集まる人間には瞼を接着剤で貼り合わせられたことのある人間やバーナーで燃やされた人間、脚を切断された人間、矢で射たれた人間がいた」
猫と人間をいれかえただけなのに、なんと悲惨な物語になってしまうのか。
当然、猫と人間のあいだでは話も通じないのだが、飼ってたココアがあらわれて、主人公と普通に話す。そこでのくだりが、本編のヤマ場!
「私はこの世界では言語を持たず、にゃあにゃあ、としか言えないんだけど、なんでココアとだけは話ができるのだろうか」
「前の世界で私はにゃあにゃあとしか発音しませんでした。でもあなたは私の言うことがわかったじゃありませんか。同じことですよ」
うかつにも、ここで感動してしまった。そんなつもりじゃなかったのに!
『明治 大正 昭和 不良少女伝---莫連女と少女ギャング団 』
2011年5月27日 読書
平山亜佐子の『明治 大正 昭和 不良少女伝---莫連女と少女ギャング団 』を読んだ。
河出書房新社の内容紹介には、こう書いてある。
堕落した書生を成敗せよ! 不良集団の四谷ハート団を率いたジャンダークのおきみ等、明治、大正、昭和を彩った不良少女たちの生態が今明かされる。自由を追い求めたモダンガールの軌跡。
以下、目次。
はじめに
第一章 明治……銀杏返しの莫連女たち
明治という時代/不良少年少女の誕生/明治期の莫連女1/明治期の莫連女2/明治期の悪少女団
第二章 大正……洋装の不良少女団
大正時代と不良問題/文界の不良少年団/不良化の原因1 悪いのは上流、下流? それとも中流?/不良化の原因2 映画を真似る少年、金龍館と少女/不良化の原因3 浅草オペラの殿堂、金龍館と少女/不良化の原因4 文化 カフェーと自然主義文学/不良少年少女の更正策/ハート団事件と丸ビル/タイピストとショップガール/「丸ビル美人伝」/ジャンダークのおきみ/恐ろしき大正期の不良少女たち/イタリー人狙撃事件/不良外人問題と心中の流行/文界の愚連隊、ふたたび
*附 草創期の新聞社と記者たち
第三章 昭和……断髪の少女ギャング団
昭和初期と不良の傾向/女優志願がギャングの首領に/モダンガール≠モガ/モガと「不良外人」/モテるフィリピン人/美人を団長に捉える不良団/家出の増加と放任主義/ギャングの女/「バッド・ガール」の流行/ギャング団の台頭/赤色系ギャング団の登場/満州帰りの不良たち/浅草の終焉/戦中・戦後の不良たち
あとがきにかえて
主要参考文献
新聞記事を中心に、不良少女の変遷をたどった1冊。「あとがきにかえて」に、こんな文章がある。
なるほど!やってることはエスカレートしているかもしれないが、明治では父親に逆らうことが、新聞などに書かれるほどのインパクトがあった、ということだ。
昭和7年『改造』で紹介される不良少女たちは、二つ名を持っており、時代を感じさせる。
不良にからまれてピストルを発砲する名うての不良少女「ガルボのお政」
野郎はだしの仁義をきる「ジャズのお小夜」
ブルジョアの子弟を釣って猛烈なアッパーカットを喰わせる「ハッタリお清」
映画俳優の頭に消毒液かけて遁走した「カルメンお静」
あと、膝にロウ細工の人面疽をつけて、驚かせる「お春」とか。
あと、気になったのが、モガについて語るいわゆる「近隣住民」の発言で、
「不断キングや講談クラブを読んで面白がって居る程でしたから思想も低級でモダーン・ガールも聞いて呆れる程でした」
と、いうが、僕の今の大好物といったら、この「キング」「講談クラブ」あたりの読み物なのである。思想低級でわるうござんしたね!
河出書房新社の内容紹介には、こう書いてある。
堕落した書生を成敗せよ! 不良集団の四谷ハート団を率いたジャンダークのおきみ等、明治、大正、昭和を彩った不良少女たちの生態が今明かされる。自由を追い求めたモダンガールの軌跡。
以下、目次。
はじめに
第一章 明治……銀杏返しの莫連女たち
明治という時代/不良少年少女の誕生/明治期の莫連女1/明治期の莫連女2/明治期の悪少女団
第二章 大正……洋装の不良少女団
大正時代と不良問題/文界の不良少年団/不良化の原因1 悪いのは上流、下流? それとも中流?/不良化の原因2 映画を真似る少年、金龍館と少女/不良化の原因3 浅草オペラの殿堂、金龍館と少女/不良化の原因4 文化 カフェーと自然主義文学/不良少年少女の更正策/ハート団事件と丸ビル/タイピストとショップガール/「丸ビル美人伝」/ジャンダークのおきみ/恐ろしき大正期の不良少女たち/イタリー人狙撃事件/不良外人問題と心中の流行/文界の愚連隊、ふたたび
*附 草創期の新聞社と記者たち
第三章 昭和……断髪の少女ギャング団
昭和初期と不良の傾向/女優志願がギャングの首領に/モダンガール≠モガ/モガと「不良外人」/モテるフィリピン人/美人を団長に捉える不良団/家出の増加と放任主義/ギャングの女/「バッド・ガール」の流行/ギャング団の台頭/赤色系ギャング団の登場/満州帰りの不良たち/浅草の終焉/戦中・戦後の不良たち
あとがきにかえて
主要参考文献
新聞記事を中心に、不良少女の変遷をたどった1冊。「あとがきにかえて」に、こんな文章がある。
明治半ばの莫連女たちは、父親に逆らい、男装をして、家を飛び出した。大正の不良少女たちは少年たちと共謀し、映画館で客引きし、不良外国人を撃った。昭和初期のバッド・ガールたちは断髪にして、エロを武器に、満州で暴れた。
なるほど!やってることはエスカレートしているかもしれないが、明治では父親に逆らうことが、新聞などに書かれるほどのインパクトがあった、ということだ。
昭和7年『改造』で紹介される不良少女たちは、二つ名を持っており、時代を感じさせる。
不良にからまれてピストルを発砲する名うての不良少女「ガルボのお政」
野郎はだしの仁義をきる「ジャズのお小夜」
ブルジョアの子弟を釣って猛烈なアッパーカットを喰わせる「ハッタリお清」
映画俳優の頭に消毒液かけて遁走した「カルメンお静」
あと、膝にロウ細工の人面疽をつけて、驚かせる「お春」とか。
あと、気になったのが、モガについて語るいわゆる「近隣住民」の発言で、
「不断キングや講談クラブを読んで面白がって居る程でしたから思想も低級でモダーン・ガールも聞いて呆れる程でした」
と、いうが、僕の今の大好物といったら、この「キング」「講談クラブ」あたりの読み物なのである。思想低級でわるうござんしたね!
プリーモ・レーヴィの『周期律』を読んだ。
「宇宙の、物質の源に思いを託し、アウシュビッツ体験を持つひとりの化学者が自らの人生の断片を綴った自伝的短編集。各篇のタイトルに元素名がつけられ、全21篇がまさに文学の周期表を形づくる」
この前読んだ『天使の蝶』の中に、特定のにおいが固有の記憶を喚起する物語が収録されていたが、それにも似て、ある元素をお題に、それにまつわるエピソードを語っている。本書最後のエピソード「炭素」には、こう書いてある。
で、どんなエピソードが語られているかと、いうと、たとえば、いつまでもツヤツヤした唇をキープするルージュを作るために、鶏や蛇の糞をあさって尿酸を集めようとした話(「窒素」)など、面白い。哺乳類の排泄物には尿酸はわずかしかないのに、鳥類には50%、爬虫類には90%含まれているんだと!哺乳類の場合は水分の関係で尿酸でなく、尿素になっちゃうらしいのだ。中には、自伝的ストーリーではなく、神話ファンタジーめいたバリバリのフィクションもある。
随所に見られる、化学者ならではのものの見方が、新鮮だ。
たとえば、「炭素」の中に、こんな文章がある。
以下、目次。
1 アルゴン
2 水素
3 亜鉛
4 鉄
5 カリウム
6 ニッケル
7 鉛
8 水銀
9 隣
10 金
11 セリウム
12 クロム
13 硫黄
14 チタン
15 砒素
16 窒素
17 錫
18 ウラニウム
19 銀
20 ヴァナディウム
21 炭素
作中、興味をひいた部分をいくつか書いておこう。
「亜鉛」より
このくだりなど、先日読んだ宇野亜喜良の本に収録されていた寺山修司の短編に通じるな、と思った。そのストーリーでは、狂人と思われないように、他人と同じことを模倣することにやっきになる家族が描かれていた。
「鉄」より
「ニッケル」より
「クロム」より
「宇宙の、物質の源に思いを託し、アウシュビッツ体験を持つひとりの化学者が自らの人生の断片を綴った自伝的短編集。各篇のタイトルに元素名がつけられ、全21篇がまさに文学の周期表を形づくる」
この前読んだ『天使の蝶』の中に、特定のにおいが固有の記憶を喚起する物語が収録されていたが、それにも似て、ある元素をお題に、それにまつわるエピソードを語っている。本書最後のエピソード「炭素」には、こう書いてある。
これは、そう望んでもいるのだが、極小史である。ある職業とそれにまつわる敗北、勝利、悲哀の歴史である。
人生のこの時点まで来て、化学者として、周期律表や、バイエルシュタインやランドルトの膨大な索引を目の前にして、自らの職業上の過去の悲しい断片や戦利品が散らばっているのを見ないものはいるだろうか?どんな教科書でも開いてみると、記憶がどっと押し寄せてくる。
で、どんなエピソードが語られているかと、いうと、たとえば、いつまでもツヤツヤした唇をキープするルージュを作るために、鶏や蛇の糞をあさって尿酸を集めようとした話(「窒素」)など、面白い。哺乳類の排泄物には尿酸はわずかしかないのに、鳥類には50%、爬虫類には90%含まれているんだと!哺乳類の場合は水分の関係で尿酸でなく、尿素になっちゃうらしいのだ。中には、自伝的ストーリーではなく、神話ファンタジーめいたバリバリのフィクションもある。
随所に見られる、化学者ならではのものの見方が、新鮮だ。
たとえば、「炭素」の中に、こんな文章がある。
あらゆる肉体の最後の目的は、大気の主要構成物ではなく、取るに足らない残余、誰も気づきもしないアルゴンよりも30倍も希薄な「不純物」でしかないのだ。
もし約2.5億トンになる人類全体が地表に均一な厚さで上塗りされるように配置されたなら、「人間の背たけ」は肉眼では見えないだろう。その上塗りの厚さは1ミリの1万6千分の1だろうからだ。
以下、目次。
1 アルゴン
2 水素
3 亜鉛
4 鉄
5 カリウム
6 ニッケル
7 鉛
8 水銀
9 隣
10 金
11 セリウム
12 クロム
13 硫黄
14 チタン
15 砒素
16 窒素
17 錫
18 ウラニウム
19 銀
20 ヴァナディウム
21 炭素
作中、興味をひいた部分をいくつか書いておこう。
「亜鉛」より
亜鉛は非常に敏感で、繊細で、酸には簡単に屈し、あっという間にとかされてしまうのだが、純度の高い時は大きく違った反応を示すのだった。亜鉛は純粋なら、酸の攻撃にも執拗に抵抗した。このことから、相反する哲学的考察が引き出せた。一つは鎖帷子のように悪から身を守ってくれる純粋性の賛美、もう一つは変化への、つまり生命へのきっかけとなる不純性の賛美だった。
車輪が回り、生命が増殖するためには、不純物が、不純なものの中の不純物が必要である。周知のように、それは耕地にも、もし肥沃であってほしいのなら、必要なのだ。不一致が、相違が、塩やからしの粒が必要なのだ。ファシズムはそれを必要とせずに、禁じている。だからおまえはファシストではないのだ。ファシズムはみなが同じであるように望んでいるが、おまえは同じではない。だが汚点のない美徳など存在しないし、もし存在するなら、忌むべきなのだ。
このくだりなど、先日読んだ宇野亜喜良の本に収録されていた寺山修司の短編に通じるな、と思った。そのストーリーでは、狂人と思われないように、他人と同じことを模倣することにやっきになる家族が描かれていた。
「鉄」より
人間が何万年もの間試行錯誤を繰り返して獲得した高貴さとは、物質を支配するところにあり、この高貴さに忠実でありたいからこそ、私は化学学部に入学した。物質に打ち勝つとはそれを理解することであり、物質を理解するには宇宙や我々自身を理解する必要がある。だから、この頃に、骨を折りながら解明しつつあったメンデレーエフの周期律こそが一篇の詩であり、高校で飲みこんできたいかなる詩よりも荘重で高貴なのだった。それによく考えてみれば、韻すら踏んでいた。
今では、ある人物を言葉で覆い尽くし、本の中で生き返らせるのは、見こみのない企てであることは分かっている。特にサンドロのような人物は。語るべきでも、記念碑をたてるべき人物でもなかった。彼は記念碑をあざ笑っていた。彼は徹頭徹尾行動の人で、それが終わってしまえば、何も残らなかった。まさに言葉以外は、何も。
「ニッケル」より
仮説ほど人を活気づけるものはない。
「クロム」より
この忌むべき事実を前にして、私の化学者としての神経は逆立った。この種のクロム酸塩の製造方法には自然なばらつきがあり、それに分析の誤りが加わるのは避けられないので、違った日の様々なロットの数値がこのように正確に一致するのはありえない、ということを知る必要がある。誰も疑問に思わなかったなんて、ありうるだろうか?だが当時私は、会社の書類が持つ、驚くべき麻痺力を、それがあらゆる直観のひらめきや才知のきらめきを拘束し、鈍くし、角を落とすことを、まだ知らなかった。それにいかなる分泌物も有害で有毒であるのは専門家にはよく知られている。だから病理学的状況では、会社の分泌物である書類が、過剰に吸収され、浸出した器官を眠らせ、麻痺させ、さらには殺してしまうこともまれではないのだ。
『対談・笑いの世界』
2011年5月24日 読書
筒井康隆と桂米朝による『対談・笑いの世界』を読んだ。
以下、目次。
序談 筒井康隆
1.文化功労者と紫綬褒章
2.「不良少年の映画史」
3.チャップリンと新喜劇
4.エンタツ・アチャコ
5.エノケン
6.講談・難波戦記
7.SFと落語のスケール
8.稚児ぼけとテノール馬鹿
9.悪食の話
10.歌舞伎の復元
11.歌舞伎のけれん
12.役者というもの
13.芝居噺
14.笑いの定義
15.「悪魔の辞典」と「天狗の落し文」
16.物語・黄表紙・浄瑠璃
17.「地獄八景亡者戯」
18.最近の芸人と新作
19.パロディと原典
20.噺家というもの
21.大阪の笑い、東京の笑い
22.ボケる年齢と坊さん
23.悪戯・幇間・俄・小咄
あとがき 桂米朝
僕は過去のことを知らなさ過ぎなんだなあ、と痛感。
どれもこれも興味深くて面白い話!
以下、目次。
序談 筒井康隆
1.文化功労者と紫綬褒章
2.「不良少年の映画史」
3.チャップリンと新喜劇
4.エンタツ・アチャコ
5.エノケン
6.講談・難波戦記
7.SFと落語のスケール
8.稚児ぼけとテノール馬鹿
9.悪食の話
10.歌舞伎の復元
11.歌舞伎のけれん
12.役者というもの
13.芝居噺
14.笑いの定義
15.「悪魔の辞典」と「天狗の落し文」
16.物語・黄表紙・浄瑠璃
17.「地獄八景亡者戯」
18.最近の芸人と新作
19.パロディと原典
20.噺家というもの
21.大阪の笑い、東京の笑い
22.ボケる年齢と坊さん
23.悪戯・幇間・俄・小咄
あとがき 桂米朝
僕は過去のことを知らなさ過ぎなんだなあ、と痛感。
どれもこれも興味深くて面白い話!