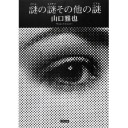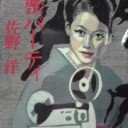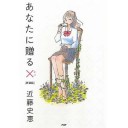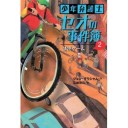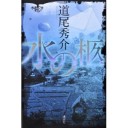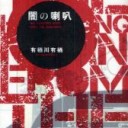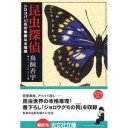『少年弁護士セオの事件簿3 消えた被告人』
2013年6月24日 読書
ジョン・グリシャムの少年弁護士セオのシリーズ。
今回は、育ちのいいセオが、なんと犯人扱いされる。
罠にかけられてしまうのだ。
雑草のような少年ならとにもかく、セオはすっかり困り果ててしまう。
ここでも、やはり悪い奴は悪い奴、という図式は変わらないが、少年の成長物語と考えれば、じゅうぶんな面白さ。
今回は、育ちのいいセオが、なんと犯人扱いされる。
罠にかけられてしまうのだ。
雑草のような少年ならとにもかく、セオはすっかり困り果ててしまう。
ここでも、やはり悪い奴は悪い奴、という図式は変わらないが、少年の成長物語と考えれば、じゅうぶんな面白さ。
石崎幸二の『第四の男』を読んだ。
女子学生誘拐未遂事件は、過去の事件のDNA鑑定に絡まるステップだった!
と、ほとんどネタバレなのだが、DNA鑑定が本書の中心のテーマで、そこから導き出される、謎の「第四の男」の正体を解明する。
作中に出てくる、作者の投影とも思える石崎が、むちゃくちゃな扱いされるのが、毎回楽しい。
まさか、石崎には友達が一人もいない、というのが推理を進めていくひとつのポイントになる、なんて尋常じゃない。
自虐の入った随所のギャグは、まるであだち充。
女子学生誘拐未遂事件は、過去の事件のDNA鑑定に絡まるステップだった!
と、ほとんどネタバレなのだが、DNA鑑定が本書の中心のテーマで、そこから導き出される、謎の「第四の男」の正体を解明する。
作中に出てくる、作者の投影とも思える石崎が、むちゃくちゃな扱いされるのが、毎回楽しい。
まさか、石崎には友達が一人もいない、というのが推理を進めていくひとつのポイントになる、なんて尋常じゃない。
自虐の入った随所のギャグは、まるであだち充。
『謎の謎その他の謎』
2013年6月22日 読書
山口雅也の『謎(リドル)の謎(ミステリ)その他の謎(リドル)』を読んだ。
リドルストーリーをテーマにした作品集。
「異版 女か虎か」アブラハム・ネイサン/山口雅也訳
「群れ」 山口雅也
「見知らぬカード」山口雅也
「謎の殺人鬼リドル」アブラハム・ネイサン・ジュニア/山口雅也訳
bonus track 「私か分身(ドッペルゲンガー)か」山口雅也
「女か虎か」にサロメの話をからめて、究極の選択をあちこちに仕掛けた「異版」は、ここまでくると、もはやリドルストーリーでもなんでもなく、人生そのものだ、と思えてくる。
「見知らぬカード」は読みやすくて面白いけど、書き散らしている感があって、つまり、普通の作家が書きそうな物語で、ちょっと物足りない。
全体にミステリ分が充溢していて、大満足。
リドルストーリーをテーマにした作品集。
「異版 女か虎か」アブラハム・ネイサン/山口雅也訳
「群れ」 山口雅也
「見知らぬカード」山口雅也
「謎の殺人鬼リドル」アブラハム・ネイサン・ジュニア/山口雅也訳
bonus track 「私か分身(ドッペルゲンガー)か」山口雅也
「女か虎か」にサロメの話をからめて、究極の選択をあちこちに仕掛けた「異版」は、ここまでくると、もはやリドルストーリーでもなんでもなく、人生そのものだ、と思えてくる。
「見知らぬカード」は読みやすくて面白いけど、書き散らしている感があって、つまり、普通の作家が書きそうな物語で、ちょっと物足りない。
全体にミステリ分が充溢していて、大満足。
大崎梢の『配達あかずきん』を読んだ。
本屋を舞台にしたミステリー短編集。
「パンダは囁く」
「標野にて。君が袖振る」
「配達あかずきん」
「六冊目のメッセージ」
「ディスプレイ・リプレイ」
大崎梢の本はこれがはじめてで、多くの本を出しているので、他の本に期待してみよう。この『配達あかずきん』では、まだ実力が出ていないのだと思う。
読みやすさは感じられるが、ミステリとしての質は、となると首をかしげざるをえないのだ。
「九マイルは遠すぎる」みたいな展開をみせる作品もあるが、だいたいは書店内ミステリであり、これが書店だからミステリとの親和性もあるけど、たとえば、いろんな職業のそれぞれの専門の知識がなくては解けないミステリがありうるとすれば、そのひとつとして、この『配達あかずきん』は位置づけられるようだ。
入院している人に薦める本のラインナップをテーマにした作品では、その絶妙のチョイスを絶賛するくだりがある。作品としては、こんな天才的な本選びをしたのは誰なのか、がテーマになるが、その絶妙なチョイスは、つまるところ、作者が考えたチョイスであって、それを絶賛されても鼻白むだけである。事件があってそれを名探偵が解決する際に、その天才ぶりを絶賛するのとは違って、入院する人に本を選ぶ、という問題は、万人にとって同じスタートラインにたった問題である。そこでの絶賛、自画自賛は、作者の自意識過剰をしかあらわさない。そして、それを自意識過剰だと読者に思わせた段階で、作者は敗北しているのだ。読者が読みたいのはミステリであって、作者の自慢話ではないのである。
最近読んだ図書館のミステリ、森谷明子の『れんげ野原のまんなかで』がすごくミステリ精神にあふれた傑作だっただけに、落差がよけいに目立った。大崎梢の他の本を読んでみないと、次々と本を書いているモチベーション自体がまだ把握できないので、次に期待!
本屋を舞台にしたミステリー短編集。
「パンダは囁く」
「標野にて。君が袖振る」
「配達あかずきん」
「六冊目のメッセージ」
「ディスプレイ・リプレイ」
大崎梢の本はこれがはじめてで、多くの本を出しているので、他の本に期待してみよう。この『配達あかずきん』では、まだ実力が出ていないのだと思う。
読みやすさは感じられるが、ミステリとしての質は、となると首をかしげざるをえないのだ。
「九マイルは遠すぎる」みたいな展開をみせる作品もあるが、だいたいは書店内ミステリであり、これが書店だからミステリとの親和性もあるけど、たとえば、いろんな職業のそれぞれの専門の知識がなくては解けないミステリがありうるとすれば、そのひとつとして、この『配達あかずきん』は位置づけられるようだ。
入院している人に薦める本のラインナップをテーマにした作品では、その絶妙のチョイスを絶賛するくだりがある。作品としては、こんな天才的な本選びをしたのは誰なのか、がテーマになるが、その絶妙なチョイスは、つまるところ、作者が考えたチョイスであって、それを絶賛されても鼻白むだけである。事件があってそれを名探偵が解決する際に、その天才ぶりを絶賛するのとは違って、入院する人に本を選ぶ、という問題は、万人にとって同じスタートラインにたった問題である。そこでの絶賛、自画自賛は、作者の自意識過剰をしかあらわさない。そして、それを自意識過剰だと読者に思わせた段階で、作者は敗北しているのだ。読者が読みたいのはミステリであって、作者の自慢話ではないのである。
最近読んだ図書館のミステリ、森谷明子の『れんげ野原のまんなかで』がすごくミステリ精神にあふれた傑作だっただけに、落差がよけいに目立った。大崎梢の他の本を読んでみないと、次々と本を書いているモチベーション自体がまだ把握できないので、次に期待!
『ジョーカー・ゲーム』
2013年6月20日 読書
柳広司の『ジョーカー・ゲーム』を読んだ。
陸軍中野学校を思わせる、日本のスパイ「D機関」に関する短編集。
スパイの目的は、敵国の秘密情報を本国にもたらし、国際政治を有利に進めること。D機関では、最初に叩き込まれる第一戒律が「死ぬな。殺すな」であり、殺し殺されることを前提とした軍隊組織とは正反対なのである。
「ジョーカー・ゲーム」
親日家のスパイは、マイクロフィルムを隠していた。憲兵たちが血眼になって探しても見つけられなかったマイクロフィルムは、どこに隠してあったのか。
「幽霊(ゴースト)」
英国総領事は爆弾テロ計画と関係があるのかないのか。状況的にはクロ。心情的にはシロ。さて。
「ロビンソン」
ドジのわりをくって囚われの身となったスパイ。自白剤を打たれ、偽の暗号電文を打たされ、脱出の際も罠に落ちる。彼がつかまった真の理由は?そして、彼を救助する『ロビンソン・クルーソー』の手掛かりとは?
「魔都」
上海租界で抗日テロで自宅を爆破された日本人憲兵。D機関は何を目的に暗躍するのか。
「XX(ダブルクロス)」
遺書を残して死んだドイツ人海外特派員。彼は二重スパイだった。彼は殺されたのか?と、すれば、犯人は?
コン・ゲーム的な、裏には裏があり、念には念をいれる面白さは抜群。
こういう念には念、の面白さを実感したのは、アンドリュー・ヴァクスの小説以来かも。
陸軍中野学校を思わせる、日本のスパイ「D機関」に関する短編集。
スパイの目的は、敵国の秘密情報を本国にもたらし、国際政治を有利に進めること。D機関では、最初に叩き込まれる第一戒律が「死ぬな。殺すな」であり、殺し殺されることを前提とした軍隊組織とは正反対なのである。
「ジョーカー・ゲーム」
親日家のスパイは、マイクロフィルムを隠していた。憲兵たちが血眼になって探しても見つけられなかったマイクロフィルムは、どこに隠してあったのか。
「幽霊(ゴースト)」
英国総領事は爆弾テロ計画と関係があるのかないのか。状況的にはクロ。心情的にはシロ。さて。
「ロビンソン」
ドジのわりをくって囚われの身となったスパイ。自白剤を打たれ、偽の暗号電文を打たされ、脱出の際も罠に落ちる。彼がつかまった真の理由は?そして、彼を救助する『ロビンソン・クルーソー』の手掛かりとは?
「魔都」
上海租界で抗日テロで自宅を爆破された日本人憲兵。D機関は何を目的に暗躍するのか。
「XX(ダブルクロス)」
遺書を残して死んだドイツ人海外特派員。彼は二重スパイだった。彼は殺されたのか?と、すれば、犯人は?
コン・ゲーム的な、裏には裏があり、念には念をいれる面白さは抜群。
こういう念には念、の面白さを実感したのは、アンドリュー・ヴァクスの小説以来かも。
佐野洋の『秘密パーティ』を読んだ。1961年。
政治家を含む男女が開く秘密パーティの最中に、1人の女性が血を吐いて死んだ。
世間体を慮って病死扱いで闇に葬ったはずが、何者かによって脅迫状が届きはじめた。差出人は、パーティに参加したなかにいる!
本書は、中島河太郎の解説によると、「飛行機、ホテル、麻雀をとり入れて、カーの『皇帝のかぎ煙草入れ』のような、本格的トリックをもったデラックスな長編を」という注文で密室ものを書いたが、いやになって、全面的に書き改めたもの、なのだそうだ。書き改める前の作品が残っていたら、佐野洋にとっての異色作になったにちがいない。ただ、本書のサブタイトル「完全殺人の完全なトリック」に、ちょっと名残りをとどめているかもしれない。あらすじでわかるように、本書の大半の興味は、「脅迫者は誰なのか」であって、殺人には重点がおかれていないのである。
真相がわかるのは、ラストの10ページで、あっさりした作風だとは知っていたけど、こんなにもあっさりしているとは、とあらためて佐野洋らしさを満喫できた。
佐野洋は、今年亡くなったばかりで、死んだから、と言って思い出したように追悼で読書したりする失態は避けたい、と思っていたが、実に残念。
以下、目次。
第1章 あるパーティ
第2章 ある計画
第3章 ある手紙
第4章 ある学生
第5章 ある女
第6章 ある写真
第7章 ある会議
第8章 ある秘密
第9章 ある計算
第10章 ある関係
第11章 ある推理
第12章 ある死亡届
第13章 いつの日か
政治家を含む男女が開く秘密パーティの最中に、1人の女性が血を吐いて死んだ。
世間体を慮って病死扱いで闇に葬ったはずが、何者かによって脅迫状が届きはじめた。差出人は、パーティに参加したなかにいる!
本書は、中島河太郎の解説によると、「飛行機、ホテル、麻雀をとり入れて、カーの『皇帝のかぎ煙草入れ』のような、本格的トリックをもったデラックスな長編を」という注文で密室ものを書いたが、いやになって、全面的に書き改めたもの、なのだそうだ。書き改める前の作品が残っていたら、佐野洋にとっての異色作になったにちがいない。ただ、本書のサブタイトル「完全殺人の完全なトリック」に、ちょっと名残りをとどめているかもしれない。あらすじでわかるように、本書の大半の興味は、「脅迫者は誰なのか」であって、殺人には重点がおかれていないのである。
真相がわかるのは、ラストの10ページで、あっさりした作風だとは知っていたけど、こんなにもあっさりしているとは、とあらためて佐野洋らしさを満喫できた。
佐野洋は、今年亡くなったばかりで、死んだから、と言って思い出したように追悼で読書したりする失態は避けたい、と思っていたが、実に残念。
以下、目次。
第1章 あるパーティ
第2章 ある計画
第3章 ある手紙
第4章 ある学生
第5章 ある女
第6章 ある写真
第7章 ある会議
第8章 ある秘密
第9章 ある計算
第10章 ある関係
第11章 ある推理
第12章 ある死亡届
第13章 いつの日か
近藤史恵の『あなたに贈るX』新装版を読んだ。
くちづけによって伝染する死の病が蔓延する世界で起こる、学園推理。
病気に感染すると1ヶ月後には確実に死んでしまうのだが、その病気のキャリアーは死なない。つまりは、吸血鬼もののパターンと言っていいだろう。
全寮制の純潔を重んじる学園内で、1人の女子生徒が死んだ。死因はソムノスフォビアと呼ばれる、口同士のキッスによってのみ伝染する病気だ、と囁かれる。彼女を死に追いやったのは誰なのか、犯人(病気のキャリアー)探しが密かにはじまる。
犯人は無理やり彼女にキッスをしたのか、それとも違うのか。
犯人は男なのか女なのか。
いろんな「こうかも、それとも、逆にこうかも」が錯綜するが、真相は甘酸っぱくて、正統な学園もの、と言える。最後の最後に用意されているサプライズは、物語の決着としてはストンと落ちるものがあるが、ちょっと、いやな結末。
本書は理論社から刊行されていたものだが、理論社がつぶれてしまい、新装版としてPHP研究所から出たもの。
新装版には、後日譚として、「夕映えの向こうに」と題する特別書き下ろし短編もついている。
主人公は本編とは違い、本編で描かれた、ある教師と生徒の禁断の恋についての顛末が描かれている。
思春期ならではの心の動きと、それを乗り越えて成長を遂げる魂。
こりゃ、たしかに、女性が喜びそうな物語だな、と強く感じた。
思春期の人ならきっと、心をつかむはずの文章を引用しておこう。
僕も思春期のはしくれなので、そう感じただけだけど。
くちづけによって伝染する死の病が蔓延する世界で起こる、学園推理。
病気に感染すると1ヶ月後には確実に死んでしまうのだが、その病気のキャリアーは死なない。つまりは、吸血鬼もののパターンと言っていいだろう。
全寮制の純潔を重んじる学園内で、1人の女子生徒が死んだ。死因はソムノスフォビアと呼ばれる、口同士のキッスによってのみ伝染する病気だ、と囁かれる。彼女を死に追いやったのは誰なのか、犯人(病気のキャリアー)探しが密かにはじまる。
犯人は無理やり彼女にキッスをしたのか、それとも違うのか。
犯人は男なのか女なのか。
いろんな「こうかも、それとも、逆にこうかも」が錯綜するが、真相は甘酸っぱくて、正統な学園もの、と言える。最後の最後に用意されているサプライズは、物語の決着としてはストンと落ちるものがあるが、ちょっと、いやな結末。
本書は理論社から刊行されていたものだが、理論社がつぶれてしまい、新装版としてPHP研究所から出たもの。
新装版には、後日譚として、「夕映えの向こうに」と題する特別書き下ろし短編もついている。
主人公は本編とは違い、本編で描かれた、ある教師と生徒の禁断の恋についての顛末が描かれている。
思春期ならではの心の動きと、それを乗り越えて成長を遂げる魂。
こりゃ、たしかに、女性が喜びそうな物語だな、と強く感じた。
思春期の人ならきっと、心をつかむはずの文章を引用しておこう。
僕も思春期のはしくれなので、そう感じただけだけど。
絶望すると、世界はまったく違うように見えるんだ
北嶋さんは、おまえを嫌っているように見えたのか?そんなことも一緒にいてわからなかったのか?おまえは、自分が嫌われているかどうかもわからないバカなのか?
ふいに思う。俺の呪いは、この人にとっても呪いに違いない。
だとすれば、俺の希望も、この人の希望かもしれない、と
『少年弁護士セオの事件簿2 誘拐ゲーム』
2013年6月17日 読書
ジョン・グリシャムの『少年弁護士セオの事件簿2 誘拐ゲーム』を読んだ。
エイプリルという名の少女が、姿を消した。
彼女は遠縁にあたる囚人と文通をしていたのだが、その囚人が脱獄したのだ。
警察によって脱獄囚は捕獲されたが、エイプリルの行方は杳として知れない。
そんなとき、川から身元不明の死体があがった。
今回も法律にくわしい少年セオが活躍する。行方不明のエイプリルを探すために張り紙するのを警察に咎められて、違法なことは何もしていないと逆にやりこめる、とか、オウムが近所の迷惑だと言って巻き起こされた動物裁判所でのやりとりなど、軽いネタもまじえながら、少女失踪の謎をとく。
この少女の家庭環境、というのがちょっと悲惨で、母親は精神的に弱くて薬漬けになっている。父親はバンド活動のため、ふらりと家をあけて数ヶ月帰ってこない。
エイプリルは言う。
「あたしが望んでいるのは、不可能なことです。そして、すべての子どもが望むことです。ふつうの家と、ふつうの家族。それはあたしには手に入りません」
主人公のセオは育ちのいいおぼっちゃんで、ちょっとどうかと思うところもあるが、親戚から鼻つまみのアイクおじさんを登場させているので、そこは少年セオが今後成長していく部分なのかもしれない。
どうかと思うところ、というのは、たとえば、低所得者の住む地域などを「がらが悪い」と思っていたり、「川ネズミ」と呼ばれる護岸壁に掘っ立て小屋を建てて暮らす低所得者を「危険」と感じていたりするところ。
セオの目を開いてくれるのかな、と期待していたおじさんのアイクも「それにしても、40にもなる男たちが、明日のロックスターを夢見て、昼夜逆転の生活をしたり、レンタカーのバンで旅暮らしをしたり、はした金を得るためにバーや友愛会クラブでライブをやってるとはな。みんな、なにかから逃避してるってことだ。まったく、どういうつもりなんだろうな」なんて、がっかりするような発言をしたりする。
このまま、よいことしてセオは育っていき、貧しい人を危険だと思いつづけるんだろうか。シリーズの進展が気になる。
エイプリルという名の少女が、姿を消した。
彼女は遠縁にあたる囚人と文通をしていたのだが、その囚人が脱獄したのだ。
警察によって脱獄囚は捕獲されたが、エイプリルの行方は杳として知れない。
そんなとき、川から身元不明の死体があがった。
今回も法律にくわしい少年セオが活躍する。行方不明のエイプリルを探すために張り紙するのを警察に咎められて、違法なことは何もしていないと逆にやりこめる、とか、オウムが近所の迷惑だと言って巻き起こされた動物裁判所でのやりとりなど、軽いネタもまじえながら、少女失踪の謎をとく。
この少女の家庭環境、というのがちょっと悲惨で、母親は精神的に弱くて薬漬けになっている。父親はバンド活動のため、ふらりと家をあけて数ヶ月帰ってこない。
エイプリルは言う。
「あたしが望んでいるのは、不可能なことです。そして、すべての子どもが望むことです。ふつうの家と、ふつうの家族。それはあたしには手に入りません」
主人公のセオは育ちのいいおぼっちゃんで、ちょっとどうかと思うところもあるが、親戚から鼻つまみのアイクおじさんを登場させているので、そこは少年セオが今後成長していく部分なのかもしれない。
どうかと思うところ、というのは、たとえば、低所得者の住む地域などを「がらが悪い」と思っていたり、「川ネズミ」と呼ばれる護岸壁に掘っ立て小屋を建てて暮らす低所得者を「危険」と感じていたりするところ。
セオの目を開いてくれるのかな、と期待していたおじさんのアイクも「それにしても、40にもなる男たちが、明日のロックスターを夢見て、昼夜逆転の生活をしたり、レンタカーのバンで旅暮らしをしたり、はした金を得るためにバーや友愛会クラブでライブをやってるとはな。みんな、なにかから逃避してるってことだ。まったく、どういうつもりなんだろうな」なんて、がっかりするような発言をしたりする。
このまま、よいことしてセオは育っていき、貧しい人を危険だと思いつづけるんだろうか。シリーズの進展が気になる。
道尾秀介の『水の柩』を読んだ。
いじめられっこの少女がタイムカプセルに入れた手紙は、いじめた相手への告発文だった。
彼女は同級生の少年を誘って、手紙を取り替えるため、校庭を掘り返す計画をたてる。
水の柩、というのは、少年の祖母がかつて住んでいた村がダムの底に沈んだことをさしていて、もちろん、単に住まいを水の底に、というだけでなく、同時に何かを葬っていたのである。
この本を読んで、作者が『ローラ・フェイとの最後の会話』にコメントを寄せていた理由が納得できたような気がする。『ローラ・フェイ~』は今年読んだ本のなかでも1、2を争う感動した本だが、道尾作品にはそれと通じるものがあるのだ。もしも道尾作品で感動している人がいるなら、トマス・H・クックの本を読んだりしたら、心臓が破裂して死んでしまうんじゃないかな。
いじめられっこの少女がタイムカプセルに入れた手紙は、いじめた相手への告発文だった。
彼女は同級生の少年を誘って、手紙を取り替えるため、校庭を掘り返す計画をたてる。
水の柩、というのは、少年の祖母がかつて住んでいた村がダムの底に沈んだことをさしていて、もちろん、単に住まいを水の底に、というだけでなく、同時に何かを葬っていたのである。
この本を読んで、作者が『ローラ・フェイとの最後の会話』にコメントを寄せていた理由が納得できたような気がする。『ローラ・フェイ~』は今年読んだ本のなかでも1、2を争う感動した本だが、道尾作品にはそれと通じるものがあるのだ。もしも道尾作品で感動している人がいるなら、トマス・H・クックの本を読んだりしたら、心臓が破裂して死んでしまうんじゃないかな。
岸田るり子の『過去からの手紙』を読んだ。
ありがちなタイトルだと思ってたら、これが事の真相に関わってて、びっくり。
死んだ子供のために命日になると必ずタンシチューを作る母。
書置きを残してそんな母がいなくなってしまった。
ごみ箱には捨てられたタンシチュー用の肉が!
そうこうするうちに、なんと母が記憶喪失で発見。何があった?
死んだはずの子供が幽霊になって解決の手助けをしたりする、とくに効果的とも思えない展開があったり、母が浮気をしたのかどうなのか、とか、いろんな複雑な関係が入り乱れる。
以下、目次
第1章 シチュー用の肉を捨てて母は消えた
第2章 崖とモク
第3章 幼なじみの呪縛
第4章 記憶は失われていた
第5章 探偵団結成
第6章 捨てられた肉の謎に迫る
第7章 <べろにく>での口論
第8章 記憶のピース
第9章 UFOか人魂か?
第10章 口論の原因
第11章 肉を捨てた理由
第12章 手紙の正体
第13章 見落としていた真相
ありがちなタイトルだと思ってたら、これが事の真相に関わってて、びっくり。
死んだ子供のために命日になると必ずタンシチューを作る母。
書置きを残してそんな母がいなくなってしまった。
ごみ箱には捨てられたタンシチュー用の肉が!
そうこうするうちに、なんと母が記憶喪失で発見。何があった?
死んだはずの子供が幽霊になって解決の手助けをしたりする、とくに効果的とも思えない展開があったり、母が浮気をしたのかどうなのか、とか、いろんな複雑な関係が入り乱れる。
以下、目次
第1章 シチュー用の肉を捨てて母は消えた
第2章 崖とモク
第3章 幼なじみの呪縛
第4章 記憶は失われていた
第5章 探偵団結成
第6章 捨てられた肉の謎に迫る
第7章 <べろにく>での口論
第8章 記憶のピース
第9章 UFOか人魂か?
第10章 口論の原因
第11章 肉を捨てた理由
第12章 手紙の正体
第13章 見落としていた真相
『ぼくが探偵だった夏』
2013年6月14日 読書
内田康夫の『ぼくが探偵だった夏』を読んだ。
浅見光彦が少年だった頃の軽井沢での事件。
穴を掘るのは何のため?
死体を埋めるためなのか。
警察立会いで掘り返してみたら、犬の死骸が出てきたよ。
でも、それはホントかな?
ジョン・グリシャムのセオ・シリーズにも通じる、育ちのいいおぼっちゃまの冒険譚で、少年少女向けの推理小説の正統派だと思った。
ヤングアダルト向けの、いじめやら家庭内暴力の問題が取り上げられる、読んでいてつらい小説に比べて、本書のさわやかさったら、ないのである。その理由としては、悪い奴は、はっきりと、悪者だからなのだ、と思う。仁木悦子の少年少女向け推理小説を読んでいても、そういうところが安心できる面だった。わるいやつは、麻薬の取引をするような、明確な悪人なのだ。
以下、目次。
第1章 妖精の森
第2章 緑の館
第3章 怪しい穴掘り
第4章 夜の冒険
第5章 ルポライターvs.刑事
第6章 大発見
第7章 永遠の思い出
ぼくが少年だった頃
浅見光彦が少年だった頃の軽井沢での事件。
穴を掘るのは何のため?
死体を埋めるためなのか。
警察立会いで掘り返してみたら、犬の死骸が出てきたよ。
でも、それはホントかな?
ジョン・グリシャムのセオ・シリーズにも通じる、育ちのいいおぼっちゃまの冒険譚で、少年少女向けの推理小説の正統派だと思った。
ヤングアダルト向けの、いじめやら家庭内暴力の問題が取り上げられる、読んでいてつらい小説に比べて、本書のさわやかさったら、ないのである。その理由としては、悪い奴は、はっきりと、悪者だからなのだ、と思う。仁木悦子の少年少女向け推理小説を読んでいても、そういうところが安心できる面だった。わるいやつは、麻薬の取引をするような、明確な悪人なのだ。
以下、目次。
第1章 妖精の森
第2章 緑の館
第3章 怪しい穴掘り
第4章 夜の冒険
第5章 ルポライターvs.刑事
第6章 大発見
第7章 永遠の思い出
ぼくが少年だった頃
有栖川有栖の『闇の喇叭』(理論社版)を読んだ。
講談社版は、加筆修正があるらしい。
昭和ならぬ召和の時代、日本に3つめの原爆が落された、もう一つの日本での話。
時は平世(not平成)、北海道はソ連の統治下に入っており、日本では北海道を「北」と呼んで敵視している。
この世界においては、国によって一切の探偵行為が違法とされている。
そんな世界で起きた、1つの日常的な謎(足跡トリック)と、死体の謎(墜落トリックで、そのトリックを使えた人物が1人だけだった、という絞込みで犯人が確定)。
僕は、本格推理小説で、トリックによって犯人を絞り込むのは、アンフェアぎりぎりだと思っている。なぜなら、トリックはたいていの場合、他に方法が絶対にありえない、という状況を論理的に設定できないからだ。作者側としては、トリックが見破られないかぎり、読者が真犯人を推理するのは不可能、ということになる。作者にのみアドバンテージがあるのは、本格派として、どうなんだろう、という思いがしている。
とは言え、最後まで真相が確定できないのは、読書の楽しみでもあるので、読者としては、アリ。
以下、目次。
序 章 分断
第1章 スパイと天使
第2章 怒りの日
第3章 誰も知らない男
第4章 海慧鼻の死
第5章 男と女
第6章 落日の喇叭
終 章 ソラへ
講談社版は、加筆修正があるらしい。
昭和ならぬ召和の時代、日本に3つめの原爆が落された、もう一つの日本での話。
時は平世(not平成)、北海道はソ連の統治下に入っており、日本では北海道を「北」と呼んで敵視している。
この世界においては、国によって一切の探偵行為が違法とされている。
そんな世界で起きた、1つの日常的な謎(足跡トリック)と、死体の謎(墜落トリックで、そのトリックを使えた人物が1人だけだった、という絞込みで犯人が確定)。
僕は、本格推理小説で、トリックによって犯人を絞り込むのは、アンフェアぎりぎりだと思っている。なぜなら、トリックはたいていの場合、他に方法が絶対にありえない、という状況を論理的に設定できないからだ。作者側としては、トリックが見破られないかぎり、読者が真犯人を推理するのは不可能、ということになる。作者にのみアドバンテージがあるのは、本格派として、どうなんだろう、という思いがしている。
とは言え、最後まで真相が確定できないのは、読書の楽しみでもあるので、読者としては、アリ。
以下、目次。
序 章 分断
第1章 スパイと天使
第2章 怒りの日
第3章 誰も知らない男
第4章 海慧鼻の死
第5章 男と女
第6章 落日の喇叭
終 章 ソラへ
『僕はお父さんを訴えます』
2013年6月12日 読書
友井羊の『僕はお父さんを訴えます』を読んだ。
第10回『このミステリーがすごい!』大賞で優秀賞を受賞した作品。
愛犬を何者かに殺された中学生の少年が、犬殺しの犯人として実の父親を訴えた!
裁判を起こすにあたってのいろんなこととか、法律とか、近所の司法試験浪人生に教えてもらいながら、事件の真相に挑んでいく。
少年が父親を裁判にかけた理由というのは、厳しい父親と対峙するにはそうするしかなかったと考えたから、という感じなのだが、真相はあまりにも悲しいものだった。
面白く読めるが、気分は晴れ晴れとしない。とってつけたようなハッピーエンド風のエピローグも、まさに「とってつけた」感じで、ことの真相の悲しさに負けてしまってる感じがした。
以下、目次
1.器物損壊
2.訴訟の準備
3.第一回口頭弁論期日
4.判決
エピローグ
第10回『このミステリーがすごい!』大賞で優秀賞を受賞した作品。
愛犬を何者かに殺された中学生の少年が、犬殺しの犯人として実の父親を訴えた!
裁判を起こすにあたってのいろんなこととか、法律とか、近所の司法試験浪人生に教えてもらいながら、事件の真相に挑んでいく。
少年が父親を裁判にかけた理由というのは、厳しい父親と対峙するにはそうするしかなかったと考えたから、という感じなのだが、真相はあまりにも悲しいものだった。
面白く読めるが、気分は晴れ晴れとしない。とってつけたようなハッピーエンド風のエピローグも、まさに「とってつけた」感じで、ことの真相の悲しさに負けてしまってる感じがした。
以下、目次
1.器物損壊
2.訴訟の準備
3.第一回口頭弁論期日
4.判決
エピローグ
『私と悪魔の100の問答』
2013年6月11日 読書
上遠野浩平の『私と悪魔の100の問答』を読んだ。
少女が人形のハズレ君とかわす問答。
問答しているだけではなく、ストーリーがあり、流れによる問答が展開されるので、あらかじめ100の設問がされていて順番に答えるわけではないのだが、うまい着想だな、と思った。
目次に並んだ100の質問を見ていると、思春期のプラトンに思えてきた。
ブギーポップの世界での物語ではあるが、とくに気にせずに読める。読んでも登場人物とかまったく覚えていない僕が面白く読んだのだから、間違いない。
以下、目次。質問に対する答えを考えてみることで、ストーリーは違え、何かが見えてくるかもしれない。
FIRST SESSION「なんとなく、嫌悪することについて」
Q01青空と聞いて連想することは
Q02自分と他人どちらを軽いと思うか
Q03簡単でないことはなぜ簡単でないのか
Q04他人はどれくらいに分けるべきか
Q05悪い印象ばかり抱きがちなのはなぜか
Q06不潔と清潔の差とは
Q07普通とは好ましいことか
Q08人に用があるときの基準とは
Q09綽名はどこまで譲歩すべきか
Q10進歩と放棄は両立しうるか
Q11疑問はそのまま目的たりうるか
Q12侮辱を感じるときはどれくらい錯覚か
Q13記録されているときは気にすべきか
Q14危険を察したときどうすべきか
Q15日々の生活に安全を感じているか
Q16人生は保証されているか
Q17人並みとは本当に平均的か
Q18嫌いな者と一緒にされて耐えられるか
Q19変態をどう扱うべきか
Q20ボケとツッコミの役割とは
Q21ウケを狙うことと天然は相反するか
Q22気まぐれをどれくらい容認すべきか
Q23汚れると価値は落ちるか
Q24義務から逃げるべきか
Q25何を頑張ればいいのか
SECOND SESSION「おおむね、威張ることについて」
Q26教育と他の業種の差異は考慮すべきか
Q27公平はどこまで徹底されているか
Q28何かに守られている気はするか
Q29理解しがたい他人の気持ちになれるか
Q30やる気とは、結局なんなのか
Q31自覚することに深い意味はあるか
Q32不良ぶることに価値はあるか
Q33格好良さと恥ずかしさの関連性とは
Q34危ないと感じる基準はどこか
Q35目的のための手段は目的たりうるか
Q36人間は何からできているか
Q37他人に対する敵意の源はなにか
Q38嫌えないのは嫌われたくないからか
Q39素直さは美徳か悪徳か
Q40誰にも答えられない問いとは何か
Q41人を不幸にするものとは何か
THIRD SESSION「ぼんやりと、流行りのことについて」
Q42レンタルに精神性はあるか
Q43無駄な努力をするのも個人の自由か
Q44特別なときと普通のときの境目とは
Q45人間と動物の違いとは
Q46恋愛はトラブルの元になるか
Q47離婚式はなぜ一般的でないか
Q48生理的な好き嫌いに実用性はあるか
Q49人の本能は壊れているのか
Q50ニワトリが先かタマゴが先か
Q51流行は他人の物真似か
Q52歴史上でもっとも流行したものは
Q53中世の人間と現代人の差異は何か
Q54国家とはなにか
Q55人権とはなにか
Q56ダサいと思われるのは怖いことか
Q57歴史の重要性はなぜ軽んじられるのか
Q58怖いもの知らずという人は実在するか
Q59女子の怖がりはすべて演技か
Q60安心しているとはどういう状態か
Q61エクソシストとオーメンの違いは
Q62微妙なものをどこまで信じるべきか
Q63ずっと解けない錯覚は真実になるのか
Q64事実と解釈の間にあるものとは
Q65悪いこととは結局なにか
Q66神は悪魔と本当に戦っているのか
FOURTH SESSION「おそらくは、怠けることについて」
Q67馬鹿につける薬はあるか
Q68疲れてるときに眠らず仕事をすべきか
Q69悟りの心境とはなにか
Q70人間の行動はどこまで計算できるか
Q71人が人を褒めるときの主要因はなにか
Q72選ばれたものは他と何が違うのか
Q73歴史に残るものの条件とは
Q74ミロのビーナスは本当に美しいのか
Q75人の想像力は何に刺激されるのか
Q76危険に見合う収入の基準とは
Q77生命の危険はどこに存在しているか
Q78他人の期待に応える必要はあるか
Q79人と人をつないでいるものとはなにか
Q80どうして戦争はなくならないのか
Q81そんな無茶な、と思うときの基準とは
Q82人でなしをどう扱うべきか
Q83社会は個人を疎外するか
Q84『人間失格』は何が失格なのか
Q85矛盾はどこまで矛盾か
Q86教師の採点を信じるべきなのか
FIFTH SESSION「かろうじて、根拠について」
Q87人形はなぜ怖いのか
Q88幽霊や祟りが怖いのはなぜか
Q89占いをつい信じてしまうのはなぜか
Q90不安はどこまで「気のせい」か
Q91冷静な人物は人生を損しているか
Q92暴力には暴力で対抗すべきか
Q93無我夢中とは偶然と同じ意味か
SIXTH SESSION「きっと、自由について」
Q94同情とは弱気の表れなのか
Q95不自然なものには必ず理由があるか
Q96なぜ親の説教は面倒くさいのか
Q97妥協しないために何をすべきか
Q98説得力の有無は何に期待してしまうのか
Q99どうして他人に期待してしまうのか
Q100自由とは、結局なんなのか
少女が人形のハズレ君とかわす問答。
問答しているだけではなく、ストーリーがあり、流れによる問答が展開されるので、あらかじめ100の設問がされていて順番に答えるわけではないのだが、うまい着想だな、と思った。
目次に並んだ100の質問を見ていると、思春期のプラトンに思えてきた。
ブギーポップの世界での物語ではあるが、とくに気にせずに読める。読んでも登場人物とかまったく覚えていない僕が面白く読んだのだから、間違いない。
以下、目次。質問に対する答えを考えてみることで、ストーリーは違え、何かが見えてくるかもしれない。
FIRST SESSION「なんとなく、嫌悪することについて」
Q01青空と聞いて連想することは
Q02自分と他人どちらを軽いと思うか
Q03簡単でないことはなぜ簡単でないのか
Q04他人はどれくらいに分けるべきか
Q05悪い印象ばかり抱きがちなのはなぜか
Q06不潔と清潔の差とは
Q07普通とは好ましいことか
Q08人に用があるときの基準とは
Q09綽名はどこまで譲歩すべきか
Q10進歩と放棄は両立しうるか
Q11疑問はそのまま目的たりうるか
Q12侮辱を感じるときはどれくらい錯覚か
Q13記録されているときは気にすべきか
Q14危険を察したときどうすべきか
Q15日々の生活に安全を感じているか
Q16人生は保証されているか
Q17人並みとは本当に平均的か
Q18嫌いな者と一緒にされて耐えられるか
Q19変態をどう扱うべきか
Q20ボケとツッコミの役割とは
Q21ウケを狙うことと天然は相反するか
Q22気まぐれをどれくらい容認すべきか
Q23汚れると価値は落ちるか
Q24義務から逃げるべきか
Q25何を頑張ればいいのか
SECOND SESSION「おおむね、威張ることについて」
Q26教育と他の業種の差異は考慮すべきか
Q27公平はどこまで徹底されているか
Q28何かに守られている気はするか
Q29理解しがたい他人の気持ちになれるか
Q30やる気とは、結局なんなのか
Q31自覚することに深い意味はあるか
Q32不良ぶることに価値はあるか
Q33格好良さと恥ずかしさの関連性とは
Q34危ないと感じる基準はどこか
Q35目的のための手段は目的たりうるか
Q36人間は何からできているか
Q37他人に対する敵意の源はなにか
Q38嫌えないのは嫌われたくないからか
Q39素直さは美徳か悪徳か
Q40誰にも答えられない問いとは何か
Q41人を不幸にするものとは何か
THIRD SESSION「ぼんやりと、流行りのことについて」
Q42レンタルに精神性はあるか
Q43無駄な努力をするのも個人の自由か
Q44特別なときと普通のときの境目とは
Q45人間と動物の違いとは
Q46恋愛はトラブルの元になるか
Q47離婚式はなぜ一般的でないか
Q48生理的な好き嫌いに実用性はあるか
Q49人の本能は壊れているのか
Q50ニワトリが先かタマゴが先か
Q51流行は他人の物真似か
Q52歴史上でもっとも流行したものは
Q53中世の人間と現代人の差異は何か
Q54国家とはなにか
Q55人権とはなにか
Q56ダサいと思われるのは怖いことか
Q57歴史の重要性はなぜ軽んじられるのか
Q58怖いもの知らずという人は実在するか
Q59女子の怖がりはすべて演技か
Q60安心しているとはどういう状態か
Q61エクソシストとオーメンの違いは
Q62微妙なものをどこまで信じるべきか
Q63ずっと解けない錯覚は真実になるのか
Q64事実と解釈の間にあるものとは
Q65悪いこととは結局なにか
Q66神は悪魔と本当に戦っているのか
FOURTH SESSION「おそらくは、怠けることについて」
Q67馬鹿につける薬はあるか
Q68疲れてるときに眠らず仕事をすべきか
Q69悟りの心境とはなにか
Q70人間の行動はどこまで計算できるか
Q71人が人を褒めるときの主要因はなにか
Q72選ばれたものは他と何が違うのか
Q73歴史に残るものの条件とは
Q74ミロのビーナスは本当に美しいのか
Q75人の想像力は何に刺激されるのか
Q76危険に見合う収入の基準とは
Q77生命の危険はどこに存在しているか
Q78他人の期待に応える必要はあるか
Q79人と人をつないでいるものとはなにか
Q80どうして戦争はなくならないのか
Q81そんな無茶な、と思うときの基準とは
Q82人でなしをどう扱うべきか
Q83社会は個人を疎外するか
Q84『人間失格』は何が失格なのか
Q85矛盾はどこまで矛盾か
Q86教師の採点を信じるべきなのか
FIFTH SESSION「かろうじて、根拠について」
Q87人形はなぜ怖いのか
Q88幽霊や祟りが怖いのはなぜか
Q89占いをつい信じてしまうのはなぜか
Q90不安はどこまで「気のせい」か
Q91冷静な人物は人生を損しているか
Q92暴力には暴力で対抗すべきか
Q93無我夢中とは偶然と同じ意味か
SIXTH SESSION「きっと、自由について」
Q94同情とは弱気の表れなのか
Q95不自然なものには必ず理由があるか
Q96なぜ親の説教は面倒くさいのか
Q97妥協しないために何をすべきか
Q98説得力の有無は何に期待してしまうのか
Q99どうして他人に期待してしまうのか
Q100自由とは、結局なんなのか
鳥飼否宇の『昆虫探偵』を読んだ。文庫版。
「蝶々殺蛾事件」
「哲学虫の密室」
「昼のセミ」
「吸血の池」
「生けるアカハネの死」
「ジョロウグモの拘」
「ハチの悲劇」
ある朝めざめたら虫になっていた主人公が、昆虫の世界での謎の事件に挑む。
挑む、と言っても、解決するのは、別の虫。
それぞれの作品は有名な推理小説のタイトルをもじっている。
「ジョロウグモの拘」は文庫のための書き下ろし。
「蝶々殺蛾事件」
「哲学虫の密室」
「昼のセミ」
「吸血の池」
「生けるアカハネの死」
「ジョロウグモの拘」
「ハチの悲劇」
ある朝めざめたら虫になっていた主人公が、昆虫の世界での謎の事件に挑む。
挑む、と言っても、解決するのは、別の虫。
それぞれの作品は有名な推理小説のタイトルをもじっている。
「ジョロウグモの拘」は文庫のための書き下ろし。