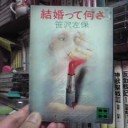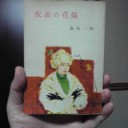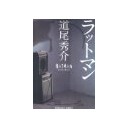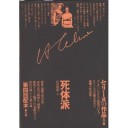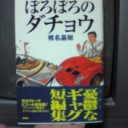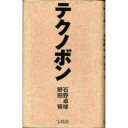笹沢左保の『結婚って何さ』を読んだ。1960年
ネタバレするので要注意。
面白くて読みやすかったので、まずは読んでみるのをおすすめします。
第1章 その夜の男
第2章 その日の女
第3章 トレンチコートの男
第4章 潜行する女
第5章 結婚って何さ
会社にスラックス姿で来た臨時雇いのOLを厳重注意する上司。
それに反発して、あっさり会社をやめてしまった女子2名。
この2人は、憂さ晴らしに酒をしこたま飲んで、行きずりの男性と一夜を過ごす。
朝、目覚めてみると、男が殺されていた!内側からは鍵をちゃんとかけておいたにもかかわらず!
と、いうお話。
2人の女性、ではあるが、そのうち1人は精神的に追い込まれて電車に轢かれて死亡。
とか言ううちに、もうひとつの事件にかかわる男性があらわれ、残された1人の女性とともに探偵しながらの逃避行。
この物語は、昔、テレビの「火曜日の女」シリーズで見たことがあった。犯人さがしのハラハラ感で、相当面白く見たはずだったのだが、内容はすっかり忘れていた。何せ、約40年前に見たドラマなのだ。小説ではコケシ手紙が出てきて、そういえば中学生の頃、コケシ手紙をもらって、秘密道具っぽい探偵趣味を満喫させたのだが、今でもあるのだろうか。
で、この小説、推理小説的なトリックが非常に面白くて、ひとことで言うと、被害者すりかえなのである。二重の意味で!つまり、2人の泥酔女子と宿に入った男性と、死んでいた男性は別人。そして、2組のカップルが相手を交換殺人するのである。カップルになっていながら、相手を殺すためにトリックを駆使する、ってあたりが、主人公をして「結婚って何さ!」と叫ばせるゆえんである。
笹沢左保の初期の推理小説は、サラリとどでかいことをやっていて、もっと大仰になったり、ページ数を稼いでもよかろう、と思えるあたりが特徴だと思う。
ネタバレするので要注意。
面白くて読みやすかったので、まずは読んでみるのをおすすめします。
第1章 その夜の男
第2章 その日の女
第3章 トレンチコートの男
第4章 潜行する女
第5章 結婚って何さ
会社にスラックス姿で来た臨時雇いのOLを厳重注意する上司。
それに反発して、あっさり会社をやめてしまった女子2名。
この2人は、憂さ晴らしに酒をしこたま飲んで、行きずりの男性と一夜を過ごす。
朝、目覚めてみると、男が殺されていた!内側からは鍵をちゃんとかけておいたにもかかわらず!
と、いうお話。
2人の女性、ではあるが、そのうち1人は精神的に追い込まれて電車に轢かれて死亡。
とか言ううちに、もうひとつの事件にかかわる男性があらわれ、残された1人の女性とともに探偵しながらの逃避行。
この物語は、昔、テレビの「火曜日の女」シリーズで見たことがあった。犯人さがしのハラハラ感で、相当面白く見たはずだったのだが、内容はすっかり忘れていた。何せ、約40年前に見たドラマなのだ。小説ではコケシ手紙が出てきて、そういえば中学生の頃、コケシ手紙をもらって、秘密道具っぽい探偵趣味を満喫させたのだが、今でもあるのだろうか。
で、この小説、推理小説的なトリックが非常に面白くて、ひとことで言うと、被害者すりかえなのである。二重の意味で!つまり、2人の泥酔女子と宿に入った男性と、死んでいた男性は別人。そして、2組のカップルが相手を交換殺人するのである。カップルになっていながら、相手を殺すためにトリックを駆使する、ってあたりが、主人公をして「結婚って何さ!」と叫ばせるゆえんである。
笹沢左保の初期の推理小説は、サラリとどでかいことをやっていて、もっと大仰になったり、ページ数を稼いでもよかろう、と思えるあたりが特徴だと思う。
島田一男の『仮面の花嫁』を読んだ。1961年
ネタバレしてるので、要注意。
東京日報の婦人記者、京子と、遊軍記者、桐野、写真班の山口が怪事件を解決する連作集。
京子はなかなか仕事を回してもらえず、毎日新聞を読んでいるだけ。
重役の令嬢でもあるので、遊び半分で就職しているという悪口も含めて「お姫さま」とあだ名されている。
「仮面の街」
刑期を終えて出所してきた男が、キャバレーでボーイを呼んだ。
この後、この男はテーブルに出ていたコップからビールを飲んで、毒殺されてしまうのだ。見えない犯人!
「仮面の愛情」
殺人現場に投げ出されていたインクつぼの意味
「仮面の微笑」
美しい薔薇にはとげがある。でも、薔薇のとげには毒が塗られていなかった。
「仮面の花嫁」
財産を狙って結婚しようとする男。花嫁のほうも仕込み。
「仮面の天使」
物静かな墓地の小座敷に赤い口紅で書き散らされた「ゴメンナサイ」の文字
「仮面の怪盗」
拳銃すりかえ
島田一男の記者物は、中学生頃に読んだことがあって、そのときには全くよさがわからなかったのだが、今、読んでみると、面白い。
島田一男の著作数は多いので、今後の楽しみが増えたって感じかな。
ネタバレしてるので、要注意。
東京日報の婦人記者、京子と、遊軍記者、桐野、写真班の山口が怪事件を解決する連作集。
京子はなかなか仕事を回してもらえず、毎日新聞を読んでいるだけ。
重役の令嬢でもあるので、遊び半分で就職しているという悪口も含めて「お姫さま」とあだ名されている。
「仮面の街」
刑期を終えて出所してきた男が、キャバレーでボーイを呼んだ。
「おい、わしの連れはどうしたッ?」
「えッ、お連れさま…?」
ボーイは驚いて尋ね返した。-が、これはボーイが驚くのも無理ではない。京子も、また桐野や山口も驚いたのだ。
-男は、府中からずっと、ひとりだった。それは、この三人がいちばんよく知っている。
「あなたさまは、おひとりで…」
「バカなことをいうな。わしは、ある男といっしょに、ここへ来たのだ」
ある男!…京子は、ハッと胸を押えた。
「まことに失礼でございますが、あなたさまは、たしかにおひとりで…」
「わからんやつだ。見ろ、ここにコップが二つ出ているではないかッ」
この後、この男はテーブルに出ていたコップからビールを飲んで、毒殺されてしまうのだ。見えない犯人!
「仮面の愛情」
殺人現場に投げ出されていたインクつぼの意味
「仮面の微笑」
美しい薔薇にはとげがある。でも、薔薇のとげには毒が塗られていなかった。
「仮面の花嫁」
財産を狙って結婚しようとする男。花嫁のほうも仕込み。
「仮面の天使」
物静かな墓地の小座敷に赤い口紅で書き散らされた「ゴメンナサイ」の文字
「仮面の怪盗」
拳銃すりかえ
島田一男の記者物は、中学生頃に読んだことがあって、そのときには全くよさがわからなかったのだが、今、読んでみると、面白い。
島田一男の著作数は多いので、今後の楽しみが増えたって感じかな。
結城昌治の『仲のいい死体』を読んだ。1961年
1、困った問題
2、心中の問題
3、動機の問題
4、新しい問題
5、残った問題
男女の死体が発見された。
並んで死んでいた二人は、心中したのではないか、と思われた。
しかし、女性のほうは最近温泉が噴出した金持ちでしかも多情と評される女。
男性は、堅物で妻子持ちの駐在さん。
どうにもそぐわない二人。
真相は?
うむ。これは面白かった。現代的な謎の解き明かされ方だな、と感じた。
なぜ殺されたのか、ということとあわせて、なぜ、このタイミングで殺されねばならなかったのか、が問題になるのが、それだ。
殺人の動機が明らかになってみると、そんなことで人を殺したりするのか、と思えるが、それを納得させるだけの筆力があった。
真鍋博のさしえもよくて、読み終わってからも何度かページを開いてみたりした。
1、困った問題
2、心中の問題
3、動機の問題
4、新しい問題
5、残った問題
男女の死体が発見された。
並んで死んでいた二人は、心中したのではないか、と思われた。
しかし、女性のほうは最近温泉が噴出した金持ちでしかも多情と評される女。
男性は、堅物で妻子持ちの駐在さん。
どうにもそぐわない二人。
真相は?
うむ。これは面白かった。現代的な謎の解き明かされ方だな、と感じた。
なぜ殺されたのか、ということとあわせて、なぜ、このタイミングで殺されねばならなかったのか、が問題になるのが、それだ。
殺人の動機が明らかになってみると、そんなことで人を殺したりするのか、と思えるが、それを納得させるだけの筆力があった。
真鍋博のさしえもよくて、読み終わってからも何度かページを開いてみたりした。
佐野洋の『二人で殺人を』を読んだ。1960年
第1章 二人で小説を
第2章 小説の舞台
第3章 準備完了
第4章 美しき死
第5章 ある屋根の下
第6章 知っていた人
第7章 ノード写真
第8章 容疑者レース
第9章 テトラエチルピロポスフェイト
第10章 六十点
第11章 二人で殺人を
自殺として片付けられようとしている事件に、他殺の疑いをもって接する名探偵役。
小説のネタになるから、という動機で事件解決に乗り出すのは、名探偵のスタンスとして非常に現代的だな、と思った。
軽くて明るいタッチで書かれているが、事件の内容は、かなりシビアなものだった。同じ事件を佐野洋以外の人物が書いていたら、相当に重い話になっていたと思われる。
第1章 二人で小説を
第2章 小説の舞台
第3章 準備完了
第4章 美しき死
第5章 ある屋根の下
第6章 知っていた人
第7章 ノード写真
第8章 容疑者レース
第9章 テトラエチルピロポスフェイト
第10章 六十点
第11章 二人で殺人を
自殺として片付けられようとしている事件に、他殺の疑いをもって接する名探偵役。
小説のネタになるから、という動機で事件解決に乗り出すのは、名探偵のスタンスとして非常に現代的だな、と思った。
軽くて明るいタッチで書かれているが、事件の内容は、かなりシビアなものだった。同じ事件を佐野洋以外の人物が書いていたら、相当に重い話になっていたと思われる。
甲賀三郎の『姿なき怪盗』を読んだ。1932年
ワクワクが止まらない大長編推理冒険小説。
以下、目次。
第1章 洞窟の白骨
ルパンとラルサン
やぎひげの植物学者
岩礁の男女
洞窟内の怪
弾丸の消失
第2章 社長邸の怪事件
望遠鏡とピストル
奇怪な落し物
飛電来る
石窟の癈人
夫人の嫌疑
第3章 見えざる敵
恐ろしい陥穽
拾ったヒューズ
見えない敵
第4章 第二の犠牲
痛快な令嬢
女秘書
支配人の死
第5章 獅子内たおれる
奇禍
意外な看護人
ほれ薬
第6章 怪漢の出現
代々木の怪盗
何者?
毒ガス
三橋の指紋
第7章 紙片の暗号
海岸の大捕物
捕縛
家出人調書
暗号の文
第8章 少女の失踪
脇坂の来訪
快走艇
危機迫る
監視船
第9章 偽証
山路の邂逅
敗北
奈美子の証言
第10章 十年前の写真
愛子の自白
京都へ
名門の息女
暗号の解読
第11章 曙光
奈美子の脅迫
阿片喚煙者
毒死の秘密
第12章 不可解の殺人
五人目の犠牲
自働発射の秘密
静岡へ
第13章 愛子の物語
絶体絶命
脇坂の嘆願
紙幣贋造団
第14章 警官隊の襲撃
留置場の発見
白骨死体の名
悪魔三橋
奈美子の秘密
第15章 二人四役
弾丸の写真
ああ三橋
社運隆盛
車中の椿事
朗かな笑い
青年新聞記者、獅子内俊次と和製ルパンとも言われる怪盗、三橋竜三が、怪事件を通じて対決。獅子内に言わせると、三橋はルパンのような明るさがない、と不満だが、タイトルの「姿なき怪盗」にはそぐわぬ殺人事件が連発される。
また、本作は紙芝居的な活劇推理小説で、読者を煽る文句にも事欠かない。
たとえば、今後起こるであろう冒険と怪事件の数々を予言する言葉など。
この作品は大長編なのだが、そうなってしまった原因のひとつに、主人公、獅子内のうかつさが挙げられるんじゃないか、と思う。作中、事件を解決するどころか後手後手をとってしまい、罠に簡単にはまりまくり、危ない目にもあいまくる獅子内は、自分に向かってこんな言葉も漏らす。
うかつに置いてあるピストルを手にして、指紋を残したことなど意にも介さずに、ピストルを元に戻したり。このときは、地の文でもこう指摘していた。
あるいは、こんなことも。
案の定、これは後にこうなる。
これでは、物語のスリルとサスペンスといっても、まるで「はじめてのおつかい」を見て感じるハラハラ感と同じではないか。
地の文章でここまで言われていながら、獅子内は平気だ。鈍感なのか、こんなことを言ってのける。
殺人者は、茶を飲むと体内で毒になってしまう新種の毒を用いて人殺しをするのだが、そういう推理小説的トリックや、紙幣贋造と事件が絡んできたり、暗号があったりして、飽きさせない。
ちなみに、その暗号は、こんな文章。
これは、作中人物に「簡単な暗号に違いないんだがなあ」とか「こんなものは、せいぜい三時間もかかれば解けるんだがなあ」とか言われていた。僕はとくに暗号解読に腰をすえて取り掛からなかったけど、実際に解読されたのを読んでみると、解法は、非常に簡単だった。おそらく推理小説が好きな人なら、ひとつめかふたつめに試してみるような方法だろう。
ワクワクが止まらない大長編推理冒険小説。
以下、目次。
第1章 洞窟の白骨
ルパンとラルサン
やぎひげの植物学者
岩礁の男女
洞窟内の怪
弾丸の消失
第2章 社長邸の怪事件
望遠鏡とピストル
奇怪な落し物
飛電来る
石窟の癈人
夫人の嫌疑
第3章 見えざる敵
恐ろしい陥穽
拾ったヒューズ
見えない敵
第4章 第二の犠牲
痛快な令嬢
女秘書
支配人の死
第5章 獅子内たおれる
奇禍
意外な看護人
ほれ薬
第6章 怪漢の出現
代々木の怪盗
何者?
毒ガス
三橋の指紋
第7章 紙片の暗号
海岸の大捕物
捕縛
家出人調書
暗号の文
第8章 少女の失踪
脇坂の来訪
快走艇
危機迫る
監視船
第9章 偽証
山路の邂逅
敗北
奈美子の証言
第10章 十年前の写真
愛子の自白
京都へ
名門の息女
暗号の解読
第11章 曙光
奈美子の脅迫
阿片喚煙者
毒死の秘密
第12章 不可解の殺人
五人目の犠牲
自働発射の秘密
静岡へ
第13章 愛子の物語
絶体絶命
脇坂の嘆願
紙幣贋造団
第14章 警官隊の襲撃
留置場の発見
白骨死体の名
悪魔三橋
奈美子の秘密
第15章 二人四役
弾丸の写真
ああ三橋
社運隆盛
車中の椿事
朗かな笑い
青年新聞記者、獅子内俊次と和製ルパンとも言われる怪盗、三橋竜三が、怪事件を通じて対決。獅子内に言わせると、三橋はルパンのような明るさがない、と不満だが、タイトルの「姿なき怪盗」にはそぐわぬ殺人事件が連発される。
また、本作は紙芝居的な活劇推理小説で、読者を煽る文句にも事欠かない。
たとえば、今後起こるであろう冒険と怪事件の数々を予言する言葉など。
ああ、快男児獅子内が、たった一目見た婦人に、たちまち、かくまでの愛着を覚えたことは、いかに宿命的であったろうか。かれはこのために、この後、いかにもだえ、いかに怪奇きわまるできごとの渦中に引き入れられたことだったか。
「よしッ、この秘密はぼくが解いてやるッ」
獅子内はとうとう休暇を棒に振る決心をした。ああ、美人の力というものは、大きなものだ。かれは白骨死体の秘密をさぐろうとしたばかりに、今後、幾多の怪事件に巻き込まれ、幾多の危険に遭遇することであろう。
獅子内は、こんこんとして眠った社長を、しばらくながめた後、看護婦にちょっと黙礼して、部屋の外に出たが、この時すでに、かれの背後には恐ろしい危機が押し寄せていたのだった。
この作品は大長編なのだが、そうなってしまった原因のひとつに、主人公、獅子内のうかつさが挙げられるんじゃないか、と思う。作中、事件を解決するどころか後手後手をとってしまい、罠に簡単にはまりまくり、危ない目にもあいまくる獅子内は、自分に向かってこんな言葉も漏らす。
「おまえは、どんな怪事件にぶっつかっても、いつも、快刀乱麻を断つように、スラスラと解決したではないか。こんどのザマはなんだ。なんと、だらしがないではないか」
うかつに置いてあるピストルを手にして、指紋を残したことなど意にも介さずに、ピストルを元に戻したり。このときは、地の文でもこう指摘していた。
ああ、かれはまた敵の謀計におちいったのだ!しかし、この時には、かれはおみきのことに頭を奪われて、少しも気がつかなかった。
あるいは、こんなことも。
獅子内は愛子のことばかり先に考えて、心はもう京都に走っているのだが、上森のいうとおり、せっかく、上京して待っている老婆の話を聞く方が、先ではなかったか?かれはまたまた後悔するようなことがなければよいが。
案の定、これは後にこうなる。
獅子内はぼうぜんと編集長と顔を見合わせた。
「編集長!これで四人目、白骨死体を加えると、五人目の犠牲者です」
「老婆の口から、秘密がもれてはと、また例の手で毒殺したんだね」
「編集長、ぼくが悪かったのです。この老婆が上京して来た時に、すぐ会えば、すっかり話がきけた上に、こんな目にあわせなくて済んだでしょうに」
これでは、物語のスリルとサスペンスといっても、まるで「はじめてのおつかい」を見て感じるハラハラ感と同じではないか。
獅子は、目の前で、社長、林田、おみき、こんどの老婆と、つごう四人を殺さしているのである。そのうち三人までは、稀代の毒薬のためである。
凶賊三橋は、獅子内を冤罪に落すため、あるいは秘密のもれるのを恐れ、あるいは獅子内を翻弄するため、自由自在に殺人をほしいままにしているのだ。ああ、獅子はいつになったら、はたして、かれを捕え、かれにあくことなき殺人を、防ぎうるのであろう。
地の文章でここまで言われていながら、獅子内は平気だ。鈍感なのか、こんなことを言ってのける。
「あれぐらいのことで、こりるものか。こんどの事件じゃ、殺されそこなったことが二度で、人殺しで拘引されかかったことが三度か四度あるんだ」
殺人者は、茶を飲むと体内で毒になってしまう新種の毒を用いて人殺しをするのだが、そういう推理小説的トリックや、紙幣贋造と事件が絡んできたり、暗号があったりして、飽きさせない。
ちなみに、その暗号は、こんな文章。
一、ウクイニツ、キキルシトネマチ、アウケ。
これは、作中人物に「簡単な暗号に違いないんだがなあ」とか「こんなものは、せいぜい三時間もかかれば解けるんだがなあ」とか言われていた。僕はとくに暗号解読に腰をすえて取り掛からなかったけど、実際に解読されたのを読んでみると、解法は、非常に簡単だった。おそらく推理小説が好きな人なら、ひとつめかふたつめに試してみるような方法だろう。
高木彬光の『裂けた視覚』を読んだ。1969年
以下、目次
第一部 虚像の死角
第二部 魔の偶像
第三部 勝負の映像
連作の形をとりながら、通して読むと1つの長篇になるミステリー。なるほど、新機軸、とも思えるけど、シリーズものの1つのパターンである。
事件を解決するのは、新聞記者の佐々木進一とその先輩、山西誠。山西は、同じことをくりかえして粘るために「クレイジーLP」とあだ名されている。
1部はオール・アメリカン・エアラインズという航空会社係累の会社による、海外での日本人向けホテル建設にかかわる詐欺事件。
2部は仏像のレプリカを販売する詐欺事件。
3部は小豆相場に関わる殺人事件。
社会派のミステリーではあるが、本格のにおいがするあたりが、面白い。
なお、この本は中学時代に散髪屋に持って行って、髪の毛を切ってもらいながら読んだもので、再読になる。案の定、中学生の頭には何も入っていなかったようで、まるっきりの初読の気分だった。中学生だった頃の自分のカットされた毛髪もページのあいだから1本見つけて、懐かしい思いがした。
『超高層ホテル殺人事件』
2012年1月11日 読書
森村誠一の『超高層ホテル殺人事件』を読んだ。1971年。
以下、目次
闇の忍び逢い
光の十字架
垂直の死者
高層の密室
逆のアリバイ
屈辱の条件
奇形の閨房
不倫の符号
第二の死者
深夜の空白
空間の盲点
業務委託契約第十二条B項
腐乱した居住者
孤独な経営者
腐乱の接点
殺意のIC
行きずりの恋人
虚空からの遺書
空白の符号
殺人針路
分離された密室
救いなき情死者
超高層ホテルの16階から人が突き落とされた!
もちろん、即死!
問題の16階から逃げた者はいない。犯人はどこから逃げたのか!
と、いうミステリーで、これは発表当初、「なんぼなんでも無理ちゃうか」という意見があって、何階から落ちたか、という階数が変更になった、と記憶している。だが、それが僕の思い違いなのか、本当にそんなことがあったのか、さだかではない。どっち?
16階から消えた犯人の謎は、まず、ミステリーファンなら、考えつくのが、「人形だったのではないか」と「落ちたのは16階からではない」という答えだろう。それは間違いである。衆人環視のもと、正真正銘の人間が高層ビルのイルミネーションの中、落下していったのは16階からである。(九つの答え風)
そうした派手な第一の事件もミステリーファンの心をくすぐるが、後半のアリバイ崩しや、チェーンロックのかかった密室でのトリックなどもあって、じゅうぶんに満足できる出来になっていた。部屋の見取り図や、家系図といったビジュアルが懐かしくてうれしい。
アリバイ崩しで「へえ」、と感じたのは、可能性を考えてみるタイプの謎ではなくて、そのトリックがいかにして現実に可能なのか、が追求されているところだ。たとえば、移動するのに電車では時間が無理な場合、誰でもが飛行機を使えばいいじゃないか、と思うわけだが、飛行機を使うにしてもその時刻表を調べると無理。じゃあ、自家用ジェット機を使えばどうか。しかし、そんなことは可能か、というような思考法だ。これは政治やビジネスにも通じる話で、解決策は思いついても、それを実現させるには何をすればいいのか、が問われるわけだ。
僕の学生時代は、推理小説といえば森村誠一、と相場が決まっていたが、僕は昔ながらの本格探偵小説や、少年ものにみられる冒険活劇の方が好きだったので、森村誠一はあんまり読んでいないのである。せいぜい15冊くらいか。今回読んだ『超高層ホテル殺人事件』だったら、当時の僕が読んでもじゅうぶん納得できる作品だったので、もう少し森村誠一の本を読んでみてもいいかな。
以下、目次
闇の忍び逢い
光の十字架
垂直の死者
高層の密室
逆のアリバイ
屈辱の条件
奇形の閨房
不倫の符号
第二の死者
深夜の空白
空間の盲点
業務委託契約第十二条B項
腐乱した居住者
孤独な経営者
腐乱の接点
殺意のIC
行きずりの恋人
虚空からの遺書
空白の符号
殺人針路
分離された密室
救いなき情死者
超高層ホテルの16階から人が突き落とされた!
もちろん、即死!
問題の16階から逃げた者はいない。犯人はどこから逃げたのか!
と、いうミステリーで、これは発表当初、「なんぼなんでも無理ちゃうか」という意見があって、何階から落ちたか、という階数が変更になった、と記憶している。だが、それが僕の思い違いなのか、本当にそんなことがあったのか、さだかではない。どっち?
16階から消えた犯人の謎は、まず、ミステリーファンなら、考えつくのが、「人形だったのではないか」と「落ちたのは16階からではない」という答えだろう。それは間違いである。衆人環視のもと、正真正銘の人間が高層ビルのイルミネーションの中、落下していったのは16階からである。(九つの答え風)
そうした派手な第一の事件もミステリーファンの心をくすぐるが、後半のアリバイ崩しや、チェーンロックのかかった密室でのトリックなどもあって、じゅうぶんに満足できる出来になっていた。部屋の見取り図や、家系図といったビジュアルが懐かしくてうれしい。
アリバイ崩しで「へえ」、と感じたのは、可能性を考えてみるタイプの謎ではなくて、そのトリックがいかにして現実に可能なのか、が追求されているところだ。たとえば、移動するのに電車では時間が無理な場合、誰でもが飛行機を使えばいいじゃないか、と思うわけだが、飛行機を使うにしてもその時刻表を調べると無理。じゃあ、自家用ジェット機を使えばどうか。しかし、そんなことは可能か、というような思考法だ。これは政治やビジネスにも通じる話で、解決策は思いついても、それを実現させるには何をすればいいのか、が問われるわけだ。
僕の学生時代は、推理小説といえば森村誠一、と相場が決まっていたが、僕は昔ながらの本格探偵小説や、少年ものにみられる冒険活劇の方が好きだったので、森村誠一はあんまり読んでいないのである。せいぜい15冊くらいか。今回読んだ『超高層ホテル殺人事件』だったら、当時の僕が読んでもじゅうぶん納得できる作品だったので、もう少し森村誠一の本を読んでみてもいいかな。
『殺人はリビエラで』
2012年1月4日 読書
トニー・ケンリックの『殺人はリビエラで』を読んだ。1970年。
ネタバレするので、要注意。でも、この本、書店にたぶん並んでいない、と思う。
主人公はレナルズとウッドのコメディアン・コンビ。
ショーの最中にふらふらと入ってきた男がバッタリと倒れる。背中にはナイフが刺さっていた!この被害者は、死ぬ前に、レナルズの恋人アンジェラに「マルタンのことで会いたい」と伝言メモを渡していた。
本作はトニー・ケンリックのデビュー作になる。
ユーモア、と言うにはお笑いの度が過ぎるコミカルなミステリー。ドタバタ風味もたっぷり。
獣医が怪しい、と踏んだ2人は、探りをいれるために、ペットショップで動物を買って、動物病院に連れて行く。それがなかなか目当ての獣医にみてもらえなくて、次から次へと動物を変えて動物病院に連れ込むあたりの描写は抱腹絶倒。
ラストにまでそのギャグはひきずられている。
また、事件を追ううちに、2人は、棺桶の中に密輸品を隠している、と推理して、葬儀の後の棺桶を強奪するあたりとか、ブラックな笑いも強烈。結局、棺桶の中には何もなくて、推理がはずれてガッカリするのだが、棺桶の中に物を隠したのではなく、死体の中に隠したのだ、と、さらにエグイ推理にぶち当たる。で、真相はどうだったかと、いうと、さらにブラックなものだった。死体には何も隠されていなかった。死体そのものが「ブツ」だったのである。どういうことかは作品を読んでゲエ~っとなってほしい。
ネタバレするので、要注意。でも、この本、書店にたぶん並んでいない、と思う。
主人公はレナルズとウッドのコメディアン・コンビ。
ショーの最中にふらふらと入ってきた男がバッタリと倒れる。背中にはナイフが刺さっていた!この被害者は、死ぬ前に、レナルズの恋人アンジェラに「マルタンのことで会いたい」と伝言メモを渡していた。
本作はトニー・ケンリックのデビュー作になる。
ユーモア、と言うにはお笑いの度が過ぎるコミカルなミステリー。ドタバタ風味もたっぷり。
獣医が怪しい、と踏んだ2人は、探りをいれるために、ペットショップで動物を買って、動物病院に連れて行く。それがなかなか目当ての獣医にみてもらえなくて、次から次へと動物を変えて動物病院に連れ込むあたりの描写は抱腹絶倒。
ラストにまでそのギャグはひきずられている。
また、事件を追ううちに、2人は、棺桶の中に密輸品を隠している、と推理して、葬儀の後の棺桶を強奪するあたりとか、ブラックな笑いも強烈。結局、棺桶の中には何もなくて、推理がはずれてガッカリするのだが、棺桶の中に物を隠したのではなく、死体の中に隠したのだ、と、さらにエグイ推理にぶち当たる。で、真相はどうだったかと、いうと、さらにブラックなものだった。死体には何も隠されていなかった。死体そのものが「ブツ」だったのである。どういうことかは作品を読んでゲエ~っとなってほしい。
『ベンスン殺人事件』
2011年12月20日 読書ヴァン・ダインの『ベンスン殺人事件』を読んだ。1926年。
他のヴァン・ダインの作品は、たとえば意外な犯人とか、凶器消失とか、密室など、推理小説としてとっつきやすいテーマがあって、読む前からいろんなところでネタバレがあったりしたが、その点、この処女作『ベンスン殺人事件』はほとんど何もなくて、読んでいて新鮮だった。
この作品では、フィロ・ヴァンス(ファイロ、というのが発音として正しいのかな。僕が読んだのは東京創元社の世界推理小説全集で、1957年出版なので、古かったのかも)の推理法や、人物像にページが大きく裂かれている。
で、ヴァン・ダインといえば、ペダンティックだとか、気取りやで鼻持ちならない探偵とか、決まり文句のように言われているが、新本格や、最近の若い書き手のミステリーの戯画的な名探偵たちやその文章を通過してきた今、読むと、ちっとも衒学的でもないし、嫌な奴でもなかった。
会話にいろんな文学や美術の知識が盛り込まれているが、それがすごく自然なのだ。「この小説を書くために、本やネットで調べて盛り込みました」みたいな付け焼刃的知識ではないせいだろう。
さて、この『ベンスン殺人事件』、ヴァンスの推理法から来る趣向が非常に面白い。
ヴァンスは、美術の鑑定士が作品を見て誰の作なのかを鑑定できるように、事件の概要を見て、犯人や真相を見抜いてしまうのだ。
つまり、ヴァンスは一目で真相をつかむのだが、素人にはさっぱりわからないのだ。
ヴァンスは、すぐにでも犯人や真相を言うこともできたが、そうすれば、素人たちは、その結論にまったく納得しないこともわかっていた。
で、どうするか、といえば、事件に関わる人をかたっぱしから濃い容疑者として提示してみせる。犯行方法やら動機やら、一見犯行が不可能に思える人々についても、「こんなふうにすれば、この人にも犯行は可能だ」とアリバイ破りや意外な動機をあばきだす。
それを複数おこなう、ということは、つまり、読者としては何度も謎解きの醍醐味を味わえるわけだ。
一方、登場人物の側からいくと、物的証拠や状況証拠による推論では、どれもが成立してしまうことを提示され、すなわち、証拠を無効化されてしまうのだ。これは、面白い。
しかるのちに、真相を言って、その真正さによって、これぞ間違いなく真相だ、と納得させるのだ。
その手の審美眼を持たない素人としては、「多くの推論が出たが、決め手に欠ける」と思わされるところだが、それは、まさに審美眼がない、センスがないせいなのだ。素人が泰西名画の真贋を見抜けないのと同様のレベルなのである。
後にヴァン・ダインに影響を受けたエラリィ・クイーンは「読者への挑戦」を標榜したが、ヴァン・ダインは、読者のような素人たちに納得させるために、あえてわかりやすく推理してやっているのだ。
うむ。面白い。
他のヴァン・ダインの作品は、たとえば意外な犯人とか、凶器消失とか、密室など、推理小説としてとっつきやすいテーマがあって、読む前からいろんなところでネタバレがあったりしたが、その点、この処女作『ベンスン殺人事件』はほとんど何もなくて、読んでいて新鮮だった。
この作品では、フィロ・ヴァンス(ファイロ、というのが発音として正しいのかな。僕が読んだのは東京創元社の世界推理小説全集で、1957年出版なので、古かったのかも)の推理法や、人物像にページが大きく裂かれている。
で、ヴァン・ダインといえば、ペダンティックだとか、気取りやで鼻持ちならない探偵とか、決まり文句のように言われているが、新本格や、最近の若い書き手のミステリーの戯画的な名探偵たちやその文章を通過してきた今、読むと、ちっとも衒学的でもないし、嫌な奴でもなかった。
会話にいろんな文学や美術の知識が盛り込まれているが、それがすごく自然なのだ。「この小説を書くために、本やネットで調べて盛り込みました」みたいな付け焼刃的知識ではないせいだろう。
さて、この『ベンスン殺人事件』、ヴァンスの推理法から来る趣向が非常に面白い。
ヴァンスは、美術の鑑定士が作品を見て誰の作なのかを鑑定できるように、事件の概要を見て、犯人や真相を見抜いてしまうのだ。
たとえばルーベンスがアントワープのキャセドラルに『十字架をおりる基督』を描いたとき、彼がなにか外交的な用務のため、ほかに行っていたことを示す有力な 状況証拠があったならば、現代の犯罪捜査家たちは、あの絵をルーベンスが描いたことを信じないにちがいない。しかしなおかつ、ねえ君、そのような結論が笑止千万なことにはかわりはないよ。たとえ、否定的な推論が法律的には争う余地がないほど有力だったとしても、絵自体があくまでも、ルーベンスがあれを描いたことを証明するだろう。なぜか?理由は簡単だよ、ルーベンスをおいて、ほかの誰にも、あの絵は描けないからだ。そこには、ルーベンスの個性と天才とが-彼のみが持っているものが、消し去ることのできない痕跡を印しているからだ。
つまり、ヴァンスは一目で真相をつかむのだが、素人にはさっぱりわからないのだ。
ヴァンスは、すぐにでも犯人や真相を言うこともできたが、そうすれば、素人たちは、その結論にまったく納得しないこともわかっていた。
で、どうするか、といえば、事件に関わる人をかたっぱしから濃い容疑者として提示してみせる。犯行方法やら動機やら、一見犯行が不可能に思える人々についても、「こんなふうにすれば、この人にも犯行は可能だ」とアリバイ破りや意外な動機をあばきだす。
それを複数おこなう、ということは、つまり、読者としては何度も謎解きの醍醐味を味わえるわけだ。
一方、登場人物の側からいくと、物的証拠や状況証拠による推論では、どれもが成立してしまうことを提示され、すなわち、証拠を無効化されてしまうのだ。これは、面白い。
しかるのちに、真相を言って、その真正さによって、これぞ間違いなく真相だ、と納得させるのだ。
その手の審美眼を持たない素人としては、「多くの推論が出たが、決め手に欠ける」と思わされるところだが、それは、まさに審美眼がない、センスがないせいなのだ。素人が泰西名画の真贋を見抜けないのと同様のレベルなのである。
後にヴァン・ダインに影響を受けたエラリィ・クイーンは「読者への挑戦」を標榜したが、ヴァン・ダインは、読者のような素人たちに納得させるために、あえてわかりやすく推理してやっているのだ。
うむ。面白い。
ウンベルト・エーコの『芸術の蒐集』を読んだ。
読む前には気づかなかったが、ラインアップを振り返ってみて、びっくり。
これは僕の好きなものが詰まっていた本だった。
日本なら小栗虫太郎や筒井康隆、探せば適当なものが寺山修司や澁澤龍彦にもあるだろう。
詳しくは後日
読む前には気づかなかったが、ラインアップを振り返ってみて、びっくり。
これは僕の好きなものが詰まっていた本だった。
日本なら小栗虫太郎や筒井康隆、探せば適当なものが寺山修司や澁澤龍彦にもあるだろう。
詳しくは後日
『ラットマン』を最近読んだけど、この話も、サン・テグジュペリの『星の王子さま』冒頭の象をのみこんだうわばみの絵のエピソードから入る、思い込みと錯覚の物語。
『エステルハージ博士の事件簿』
2011年12月7日 読書アヴラム・デイヴィッドスンの『エステルハージ博士の事件簿』を読んだ。
オカルトめいた事件を幻想的に解決したり、いや、そう言えば語弊がある。
また後日。
オカルトめいた事件を幻想的に解決したり、いや、そう言えば語弊がある。
また後日。
『ローラのオリジナル』
2011年11月29日 読書ナボコフの遺作(?)『ローラのオリジナル』を読んだ。
完成品ではなくて、カードに記された断片を、こういう順番じゃないか、と並べてみたもので、それでなくてもアナグラム好きのナボコフなのに、順番が変わって景色が変わってしまうかもしれない可能性を秘めた面白い作品だった。
『ロリータ』のセルフパロディの部分もあるし、ギャグの要素もある。
また、官能的なシーンは、ナボコフ健在を証明するものだった。
そう言えば、読む順番を変えることで、不可能な状況ができあがってしまうミステリーを、昔書いた覚えがある。イベントで発表した後、原稿とかもうどこかに行ってしまったけど。
完成品ではなくて、カードに記された断片を、こういう順番じゃないか、と並べてみたもので、それでなくてもアナグラム好きのナボコフなのに、順番が変わって景色が変わってしまうかもしれない可能性を秘めた面白い作品だった。
『ロリータ』のセルフパロディの部分もあるし、ギャグの要素もある。
また、官能的なシーンは、ナボコフ健在を証明するものだった。
そう言えば、読む順番を変えることで、不可能な状況ができあがってしまうミステリーを、昔書いた覚えがある。イベントで発表した後、原稿とかもうどこかに行ってしまったけど。
パウル・シェーアバルトの『虫けらの群霊』を読んだ。
以下、目次。
神々
タマゴ
歓喜
大芝居
嘆き
神殿
疾走
勝利
虫けらの霊たちが、神に、星になろうとする物語で、これはまあ、面白いのなんのって。
「神々」では霊たちのチキチキマシン猛レースが展開され、「歓喜」はカレイドスコープ的視覚の実況、「大芝居」では陶酔や進化などについての問答。
ううむ。捨てどころのないいい本だな。
シェーアバルトは52歳で死んでおり、こういう不思議な感性を持ち続けた人生は大いに勇気づけられる。
以下、目次。
神々
タマゴ
歓喜
大芝居
嘆き
神殿
疾走
勝利
虫けらの霊たちが、神に、星になろうとする物語で、これはまあ、面白いのなんのって。
「神々」では霊たちのチキチキマシン猛レースが展開され、「歓喜」はカレイドスコープ的視覚の実況、「大芝居」では陶酔や進化などについての問答。
ううむ。捨てどころのないいい本だな。
シェーアバルトは52歳で死んでおり、こういう不思議な感性を持ち続けた人生は大いに勇気づけられる。
セリーヌの『死体派』を読んだ。
過激なパンフレ集。
ユダヤ人への悪口であふれかえっているが、ネットの悪口とは違って、読めるのはその作家的資質によるものだろう。ただ、数ページ読む分には面白いが、百ページも読むと、精神的に疲れはててしまう。すさまじい憎悪と呪詛の激流のなかで溺死しそうである。
以下、とくに章立てなどはなかったが、一連のまとまりの冒頭部分だけを抜粋してみた。
先日、私はラ・ジャットとクールブヴォワの間を結ぶ曳船道を、考えこんで、散歩していたのだった、つまらぬことを考えていて、困り果てていたんだ……投身自殺するつもりはなかった、勿論さ……だが、やはり、私はへたばりきっていたのさ、解決が見つからないからだった。人生が、毎日、愉快な訳がないよ。
私は嘆願書を百ページも書いていた、一気呵成だった。
なにも劇的に考えることはないのさ……われわれは言ってみれば戦争状態に突入しているのだ……これ以上の蛇足はいらない。
ただちに問題の核心に触れよう。民主主義諸国は戦争を望んでいる。
フランス秘密結社共和国は、いまや素朴なフランス人に対する、きわめて唾棄すべき空手形乱発の選挙詐欺、まさに信じられないペテン行為以外の何ものでもないのだ。
私は、くどくど言うつもりはないんだ、こんなことは、みんな、タルムード以来、数多くの、ごまんとある書物で、ユダヤ人自身が語っているのだ、そして、これを、幾人かの、きわめて稀有なアーリア人が、諸君のために、わざわざ読み、分析し、要約している位だからな。
拷問のモスクワから、満腹のロンドンを経て石油のワシントンに至るまで、フリーメイソンの、ジャーナリズムの、銀行の、警察の、芸術の、サロンの、ありとあらゆるユダヤ人が足踏み鳴らし、憤慨し、非難の声をあげて、ののしりまくっている。
ああ!なんて、まあ、この連中はわれわれのことを、ニューヨークを思うことか!
ドイツのヒトラー主義者どもが、ユダヤ人に、フリーメイソンに反対して、わめいて、叫びをあげて、大騒ぎをいかにしてみたところで、そんなものは、全アメリカがまさに文字通り日長夜長、そのためにうめき、騒ぎ、ガタガタ言っている通り、ローマ、ベルリン、フランコ、日本に向けられた侮辱と軽侮と非難と呪いと狂気じみた辛辣さの龍巻と暴風とサイクロンに比較すれば、小言、お人よしの不平の調子以外のものではないのだ。
ブルックリンのサミュエル・コーエン、アメリカの秘蔵っ子で、民主主義者のロータリークラブ会員(これぞ正真正銘の俗悪実業家さ)、この男は、われわれにじっと眼を注いでいるんだ、われわれに関する全てについて、特務機関すなわち『フランス情報機関』によって驚くほどの情報を持っているのだ。
パラドクス。誰よりけちんぼで、欲が深い、つまりネズミそっくりだ、この本国のフランス人、原住民という奴はさ、金貨をいじくられたり、金箱や不動産や証券をさぐられたりしたとなると、奴は、下劣なことはする、畜生にはなる、諸君の遇し方はひどいもんだよ。
アメリカの巨大な馬鹿騒ぎの中で、ニューヨークの映画はその極致を示している。
みごとなもんだ、あのすさまじい映画屋巣窟から百歩の所、西42番街に、どぎつく輝いているんだ、けばけばしいんだ、大変な繁昌振りだし、大評判さ、有名な『バーレスク』(ミンスキー流)、『カジノ』スタイルの様々な超見世物小屋のことさ、まったく相も変わらぬユダヤ・ビザンチン式の、芸術的主張などまるでない、従って、明らさまにサディスチックで、見るからにエロチックで、淫売屋みたいな、ひどく自慰的なものをやっているのさ。
思い違いをしてはいけない、ユダヤ=アメリカ人(ということは要するにアメリカ全部ということさ)が、われわれを評価したり、われわれを尊敬し始めたりするのは、ラッパ手が、すでに腐っているわれわれの肉に、贖いの大虐殺にむけて集合ラッパを吹き鳴らす時だけさ。
うう、これはきりがないぞ。索引作れるくらいにしようと思ったけど、あっさり中止だ。
後半部で、あと一つだけ。
できれば、たわごとを許してはならない、要点をよく覚えておいて、手段をつくして喉が張り裂けるくらいで大声でわめくことだ。第一に、人種主義だ!何よりも、人種主義なのだ!十回も!千回も、人種主義なんだ!絶対に、人種主義だ!消毒だ!掃除だ!フランスには唯一の人種しかいない、すなわちアーリア人種さ!……きわめて正常に適応して、住みついているのだ。その他は、そんな連中は、夾雑物、ニセモノ、粗悪品にすぎぬ。
本国フランスでは本書は出版のタブーになっている、英米でも翻訳出版されていない、という。せっかく日本語で翻訳されているんだから、これは読まない手はないのである。
過激なパンフレ集。
ユダヤ人への悪口であふれかえっているが、ネットの悪口とは違って、読めるのはその作家的資質によるものだろう。ただ、数ページ読む分には面白いが、百ページも読むと、精神的に疲れはててしまう。すさまじい憎悪と呪詛の激流のなかで溺死しそうである。
以下、とくに章立てなどはなかったが、一連のまとまりの冒頭部分だけを抜粋してみた。
先日、私はラ・ジャットとクールブヴォワの間を結ぶ曳船道を、考えこんで、散歩していたのだった、つまらぬことを考えていて、困り果てていたんだ……投身自殺するつもりはなかった、勿論さ……だが、やはり、私はへたばりきっていたのさ、解決が見つからないからだった。人生が、毎日、愉快な訳がないよ。
私は嘆願書を百ページも書いていた、一気呵成だった。
なにも劇的に考えることはないのさ……われわれは言ってみれば戦争状態に突入しているのだ……これ以上の蛇足はいらない。
ただちに問題の核心に触れよう。民主主義諸国は戦争を望んでいる。
フランス秘密結社共和国は、いまや素朴なフランス人に対する、きわめて唾棄すべき空手形乱発の選挙詐欺、まさに信じられないペテン行為以外の何ものでもないのだ。
私は、くどくど言うつもりはないんだ、こんなことは、みんな、タルムード以来、数多くの、ごまんとある書物で、ユダヤ人自身が語っているのだ、そして、これを、幾人かの、きわめて稀有なアーリア人が、諸君のために、わざわざ読み、分析し、要約している位だからな。
拷問のモスクワから、満腹のロンドンを経て石油のワシントンに至るまで、フリーメイソンの、ジャーナリズムの、銀行の、警察の、芸術の、サロンの、ありとあらゆるユダヤ人が足踏み鳴らし、憤慨し、非難の声をあげて、ののしりまくっている。
ああ!なんて、まあ、この連中はわれわれのことを、ニューヨークを思うことか!
ドイツのヒトラー主義者どもが、ユダヤ人に、フリーメイソンに反対して、わめいて、叫びをあげて、大騒ぎをいかにしてみたところで、そんなものは、全アメリカがまさに文字通り日長夜長、そのためにうめき、騒ぎ、ガタガタ言っている通り、ローマ、ベルリン、フランコ、日本に向けられた侮辱と軽侮と非難と呪いと狂気じみた辛辣さの龍巻と暴風とサイクロンに比較すれば、小言、お人よしの不平の調子以外のものではないのだ。
ブルックリンのサミュエル・コーエン、アメリカの秘蔵っ子で、民主主義者のロータリークラブ会員(これぞ正真正銘の俗悪実業家さ)、この男は、われわれにじっと眼を注いでいるんだ、われわれに関する全てについて、特務機関すなわち『フランス情報機関』によって驚くほどの情報を持っているのだ。
パラドクス。誰よりけちんぼで、欲が深い、つまりネズミそっくりだ、この本国のフランス人、原住民という奴はさ、金貨をいじくられたり、金箱や不動産や証券をさぐられたりしたとなると、奴は、下劣なことはする、畜生にはなる、諸君の遇し方はひどいもんだよ。
アメリカの巨大な馬鹿騒ぎの中で、ニューヨークの映画はその極致を示している。
みごとなもんだ、あのすさまじい映画屋巣窟から百歩の所、西42番街に、どぎつく輝いているんだ、けばけばしいんだ、大変な繁昌振りだし、大評判さ、有名な『バーレスク』(ミンスキー流)、『カジノ』スタイルの様々な超見世物小屋のことさ、まったく相も変わらぬユダヤ・ビザンチン式の、芸術的主張などまるでない、従って、明らさまにサディスチックで、見るからにエロチックで、淫売屋みたいな、ひどく自慰的なものをやっているのさ。
思い違いをしてはいけない、ユダヤ=アメリカ人(ということは要するにアメリカ全部ということさ)が、われわれを評価したり、われわれを尊敬し始めたりするのは、ラッパ手が、すでに腐っているわれわれの肉に、贖いの大虐殺にむけて集合ラッパを吹き鳴らす時だけさ。
うう、これはきりがないぞ。索引作れるくらいにしようと思ったけど、あっさり中止だ。
後半部で、あと一つだけ。
できれば、たわごとを許してはならない、要点をよく覚えておいて、手段をつくして喉が張り裂けるくらいで大声でわめくことだ。第一に、人種主義だ!何よりも、人種主義なのだ!十回も!千回も、人種主義なんだ!絶対に、人種主義だ!消毒だ!掃除だ!フランスには唯一の人種しかいない、すなわちアーリア人種さ!……きわめて正常に適応して、住みついているのだ。その他は、そんな連中は、夾雑物、ニセモノ、粗悪品にすぎぬ。
本国フランスでは本書は出版のタブーになっている、英米でも翻訳出版されていない、という。せっかく日本語で翻訳されているんだから、これは読まない手はないのである。
『ぼろぼろのダチョウ』『テクノボン』
2011年11月25日 読書
椎名基樹の『ぼろぼろのダチョウ』を読んだ。1996年
人生~バカはサイレンで泣くでおなじみの放送作家の短編集。
以下、目次。
前書き漫画「十六文」
野に咲く花のように
女王の湯
ぼろぼろのダチョウ
俺って面白いだろ?1
注文の多い風俗店
KAZUSHIGE通信
俺って面白いだろ?2
寝たきりサーキット
チェリーよ、トンファをとれ
チョコレート中毒
ファイナル・エクスタシー
栄光のクソ1
笑いを目的とした作品集のはずなのだが、どこか異常である。
狂っているわけではない。
ここでつくはずだと期待させる「オチ」や「もうひとつピーク」が肩すかしのように欠落しているのである。ゴールのない競走で、しかもいつやめてもかまわない、というルール(?)みたいなものだ。
起承転結で言えば、起結がなくて、ゆえにそれが承なのか転なのかも不明のまま続くスケッチ。
ただ、ときおり文学っぽいカタルシスを味わえる瞬間もあって、通好みかとも勘違いさせる不思議な1冊だった。
石野卓球と野田努の『テクノボン』を読んだ。1994年
以下、目次
序
第1章 68年、恋の夏の終わりから
クラフトワークからブライアン・イーノまで
第2章 未来派きどり
ディーヴォからニュー・ロマンティクスまで
第3章 テクノはパンク
ミュートからZTTまで
第4章 ドイツのアシッド・テスト
レジデンツからDAFまで
第5章 ブリング・ザ・ノイズ!
キャバレー・ヴォルテールからザ・KLFまで
第6章 機械の魂、反乱のテクノ
デリック・メイから808ステイトまで
第7章 ポップスのアウトロー
リッチー・ホウティンからリチャード・D・ジェイムスまで
資料編
参考文献
年表
あとがき
なつかしい名前がいっぱい!
巻頭やおしまいのあたりはスローガンだかキャッチコピーだかの言い合いで到底対談本とは思えない感じだったが、すぐに慣れた。
卓球君が「本音を言うとこの本も70年代のジャーマン・ロックと87年以降のテクノだけで充分なんだ」と言って、さらに野田氏は「ワープのオーナーのロブ・ミッシェルは70年代のジャーマン・ロックをすごく聴いている人なんだよね。前にインタビューで、70年代と90年代の相似性を指摘していたな」と言う。
当時90年代では20年前の70年代との通底を感じ取っていたようだが、現在、2010年代にいたっては、20年前というと、まさにこの本の出た90年代ズバリである。
今、新しいムーヴメントを探ろうとしたら、90年代にあたってみるのがいいのかもしれないな、との思いを強くした。
人生~バカはサイレンで泣くでおなじみの放送作家の短編集。
以下、目次。
前書き漫画「十六文」
野に咲く花のように
女王の湯
ぼろぼろのダチョウ
俺って面白いだろ?1
注文の多い風俗店
KAZUSHIGE通信
俺って面白いだろ?2
寝たきりサーキット
チェリーよ、トンファをとれ
チョコレート中毒
ファイナル・エクスタシー
栄光のクソ1
笑いを目的とした作品集のはずなのだが、どこか異常である。
狂っているわけではない。
ここでつくはずだと期待させる「オチ」や「もうひとつピーク」が肩すかしのように欠落しているのである。ゴールのない競走で、しかもいつやめてもかまわない、というルール(?)みたいなものだ。
起承転結で言えば、起結がなくて、ゆえにそれが承なのか転なのかも不明のまま続くスケッチ。
ただ、ときおり文学っぽいカタルシスを味わえる瞬間もあって、通好みかとも勘違いさせる不思議な1冊だった。
石野卓球と野田努の『テクノボン』を読んだ。1994年
以下、目次
序
第1章 68年、恋の夏の終わりから
クラフトワークからブライアン・イーノまで
第2章 未来派きどり
ディーヴォからニュー・ロマンティクスまで
第3章 テクノはパンク
ミュートからZTTまで
第4章 ドイツのアシッド・テスト
レジデンツからDAFまで
第5章 ブリング・ザ・ノイズ!
キャバレー・ヴォルテールからザ・KLFまで
第6章 機械の魂、反乱のテクノ
デリック・メイから808ステイトまで
第7章 ポップスのアウトロー
リッチー・ホウティンからリチャード・D・ジェイムスまで
資料編
参考文献
年表
あとがき
なつかしい名前がいっぱい!
巻頭やおしまいのあたりはスローガンだかキャッチコピーだかの言い合いで到底対談本とは思えない感じだったが、すぐに慣れた。
卓球君が「本音を言うとこの本も70年代のジャーマン・ロックと87年以降のテクノだけで充分なんだ」と言って、さらに野田氏は「ワープのオーナーのロブ・ミッシェルは70年代のジャーマン・ロックをすごく聴いている人なんだよね。前にインタビューで、70年代と90年代の相似性を指摘していたな」と言う。
当時90年代では20年前の70年代との通底を感じ取っていたようだが、現在、2010年代にいたっては、20年前というと、まさにこの本の出た90年代ズバリである。
今、新しいムーヴメントを探ろうとしたら、90年代にあたってみるのがいいのかもしれないな、との思いを強くした。