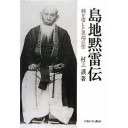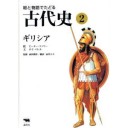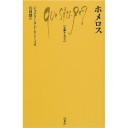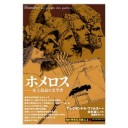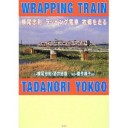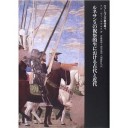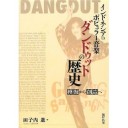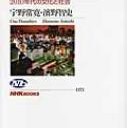『蘭郁二郎探偵小説選1』
2013年4月10日 読書『蘭郁二郎探偵小説選1』を読んだ。
蘭郁二郎というと、日本のSFの古典みたいな印象でいたから、今回のような、探偵小説を読めるのはうれしい。しかも、探偵小説が書くことなど許されなかったはず、と思い込んでいた時代の作品!そんな時代はなかった、ということなのだろうか。
以下、目次。
月澤俊平の事件簿
「闇に溶ける男」
呼止めた少女/落したハンカチ/同じ徽章の男/徽章の罠/遁られぬ難題/庭の天文学/闇に溶ける男
「南風荘の客」
律子とピストル/脂ぎった瀧山/律子への疑惑/月澤俊平/作者の解答
「指環と探偵」
「妙な錠前屋」
「慈雨の殺人」
「発明相談所」
「火星の荒野」
「新兵器出現」
「海底探検余聞」
「南海の毒杯」
第1章
出発/原子工業研究所/海の鍛錬寮/海浜の事件/見知らぬ娘
第2章
智子の証言/眠れる獅子/松野の調査/奇妙な言葉/相川の発見
第3章
研究室の虫/主観的盲点/二つの情報/再び怪事件/液体空気/相川の苦悩
第4章
白い葉の草/木下の発見/井関の発見/狙われた者
第5章
月澤俊平/冷たい男/青森と泡盛/柴山の提案/世間の噂
第6章
不思議な会合/南と北/木下の心境/木下の愕き/めぐり合った船客
第7章
暗い日/露台の口論/良子の拘引/十年の知己/月澤の示唆/旧友署長
第8章
大陰謀/山原船/地下道/偽装謀略
「林檎と名探偵」
1.奇妙な会話 2.正体 3.早い名探偵
少年探偵王
「温室の怪事件」
友人のたのみ/おもとがかれる/見当がつかない/あらわれた宝石/事件の原因
「幽霊自動車の事件」
町のうわさ/消える自動車/追跡
「大宮博士の事件」
照夫君の観察/草の上の足跡/近眼鏡の秘密/犯人はこの家
「不思議な電話の事件」
誕生日の事件/妙な予感/一発の銃声/不思議な電話
「雪の山小屋の事件」
吹雪の山/殺人事件/疑問の杖/手品のタネ
「飾り時計の事件」
深夜の銃声/出口のない部屋/時計は語る
「百貨店の怪盗事件」
意外な死体/また現われた怪盗/空の一騎打
林田葩子作品集
「花形作家」
「第百一回目」
資料篇
「林田葩子女子に就いて」小栗虫太郎
「蘭郁二郎君のこと」海野十三
蘭郁二郎というと、日本のSFの古典みたいな印象でいたから、今回のような、探偵小説を読めるのはうれしい。しかも、探偵小説が書くことなど許されなかったはず、と思い込んでいた時代の作品!そんな時代はなかった、ということなのだろうか。
以下、目次。
月澤俊平の事件簿
「闇に溶ける男」
呼止めた少女/落したハンカチ/同じ徽章の男/徽章の罠/遁られぬ難題/庭の天文学/闇に溶ける男
「南風荘の客」
律子とピストル/脂ぎった瀧山/律子への疑惑/月澤俊平/作者の解答
「指環と探偵」
「妙な錠前屋」
「慈雨の殺人」
「発明相談所」
「火星の荒野」
「新兵器出現」
「海底探検余聞」
「南海の毒杯」
第1章
出発/原子工業研究所/海の鍛錬寮/海浜の事件/見知らぬ娘
第2章
智子の証言/眠れる獅子/松野の調査/奇妙な言葉/相川の発見
第3章
研究室の虫/主観的盲点/二つの情報/再び怪事件/液体空気/相川の苦悩
第4章
白い葉の草/木下の発見/井関の発見/狙われた者
第5章
月澤俊平/冷たい男/青森と泡盛/柴山の提案/世間の噂
第6章
不思議な会合/南と北/木下の心境/木下の愕き/めぐり合った船客
第7章
暗い日/露台の口論/良子の拘引/十年の知己/月澤の示唆/旧友署長
第8章
大陰謀/山原船/地下道/偽装謀略
「林檎と名探偵」
1.奇妙な会話 2.正体 3.早い名探偵
少年探偵王
「温室の怪事件」
友人のたのみ/おもとがかれる/見当がつかない/あらわれた宝石/事件の原因
「幽霊自動車の事件」
町のうわさ/消える自動車/追跡
「大宮博士の事件」
照夫君の観察/草の上の足跡/近眼鏡の秘密/犯人はこの家
「不思議な電話の事件」
誕生日の事件/妙な予感/一発の銃声/不思議な電話
「雪の山小屋の事件」
吹雪の山/殺人事件/疑問の杖/手品のタネ
「飾り時計の事件」
深夜の銃声/出口のない部屋/時計は語る
「百貨店の怪盗事件」
意外な死体/また現われた怪盗/空の一騎打
林田葩子作品集
「花形作家」
「第百一回目」
資料篇
「林田葩子女子に就いて」小栗虫太郎
「蘭郁二郎君のこと」海野十三
『ウジェーヌ・ヴァルモンの勝利』
2013年4月9日 読書
ロバート・バーの『ウジェーヌ・ヴァルモンの勝利』を読んだ。
しょ、しょうり?
世界短編傑作の1つとして有名な「放心家組合」が、「うっかり屋協同組合」というタイトルで収録されている。タイトルのほんわかしたコミカルなムードとは違って、内容は、いまいましい詐欺の話。強烈な事件ではないけど、「銀のスプーンの手がかり」とか、面白く読めた。
ウジェーヌ・ヴァルモンのキャラクターが面白い。
以下、目次。
ダイヤモンドのネックレスの謎
シャム双生児の爆弾魔
銀のスプーンの手がかり
チゼルリッグ卿の失われた遺産
うっかり屋協同組合
幽霊の足音
ワイオミング・エドの釈放
レディ・アリシアのエメラルド
ウジェーヌ・ヴァルモンはフランスを追われてイギリスで活躍する探偵で、作品の随所に英仏の比較が出てきて面白い。もちろん、からかっているのだ。
しょ、しょうり?
世界短編傑作の1つとして有名な「放心家組合」が、「うっかり屋協同組合」というタイトルで収録されている。タイトルのほんわかしたコミカルなムードとは違って、内容は、いまいましい詐欺の話。強烈な事件ではないけど、「銀のスプーンの手がかり」とか、面白く読めた。
ウジェーヌ・ヴァルモンのキャラクターが面白い。
以下、目次。
ダイヤモンドのネックレスの謎
シャム双生児の爆弾魔
銀のスプーンの手がかり
チゼルリッグ卿の失われた遺産
うっかり屋協同組合
幽霊の足音
ワイオミング・エドの釈放
レディ・アリシアのエメラルド
ウジェーヌ・ヴァルモンはフランスを追われてイギリスで活躍する探偵で、作品の随所に英仏の比較が出てきて面白い。もちろん、からかっているのだ。
我輩があれこれ書くよりも、この精神をうまく表している詩があるからそれをご紹介しよう。
立派な法律のおかげで
悪党どもはみんな絞首台のがれ
この詩はそういうイギリス人の考え方をよく表している。
フランスは理想の存亡をかけて今も昔も戦いに挑んだのに対し、ほかの国々は領土や金や商売のために戦争するのだ。我輩はお金の槍では倒せないが、同情の杖をひと振りすれば我輩はあなたの下僕である。
フランス人は自分自身が冗談の的にされるのは我慢できないが、イギリス人はそうではないようだ。
「フランスとはね」とヘイルは鼻を鳴らしてあざけった。「無罪と証明されるまではみんな有罪にされる国がね」
『島地黙雷伝 剣を帯した異端の聖』
2013年4月8日 読書
村上護の『島地黙雷伝 剣を帯した異端の聖』を読んだ。
島地黙雷は、幕末に若き日を送り、明治を通した僧侶。「黙雷」の名は、大乗教典『維摩経』の「維摩の一黙、雷の如し」からとったもの。
サブタイトルの「剣を帯した」とあるのは、幕末の動乱期に青春時代を送ったゆえのものであり、本人は特別に武闘派というわけではないようだ。本書を読むかぎり。
ただし、当時の仏教僧は、廃仏毀釈の荒波をもろに受けており、その対応を問われていた。黙雷はその流れの中で、なんとかして仏教を守ろうと闘った僧であった。
黙雷の事績を書いた本書では、前半は若く貧しい黙雷が刻苦勉励して仏教を学ぶ姿がこれでもか、と描かれている。寺のあとをついでほしい、という養親の願いと、黙雷の向学心(遊学したい)との葛藤が熱い。
また、後半、欧州への外遊が描かれており、もともと、僕がこの本を読もうとした動機はそこを知りたい、という部分ではあったが、さらりと流されていて、この部分をもっと詳しく知りたい、と思った。
以下、目次。
序 幕末・明治の維摩
第1章 出自
1.垰の専照寺
2.十二歳の作『御法度伊呂波具ど木』
3.養子で入寺
第2章 萩の城下
1.苦手な法談
2.非常の出奔
第3章 遊学
1.辛苦の肥後遊学
2.遊学と離縁
3.連城と対論
第4章 僧侶と武
1.武事に関せず
2.剣を帯して
3.風儀改正
第5章 廃仏毀釈
1.復古と維新
2.廃仏毀釈の嵐
第6章 外遊と聖地
1.欧州政教見聞
2.信教の自由
3.布教の諸相
第7章 僧侶の争い
1.宗門クーデター
2.天皇と法主
第8章 家庭と教育
1.女子教育ほか
2.島地家の子女たち
3.邪宗と入信
第9章 奥羽の黙雷
1.同朋とデモクラシー
2.岩手願教寺での荘子講話
終 宗祖に立ち帰れ
参考史料・文献一覧
あとがき
島地黙雷略年譜
人名索引
島地黙雷は、幕末に若き日を送り、明治を通した僧侶。「黙雷」の名は、大乗教典『維摩経』の「維摩の一黙、雷の如し」からとったもの。
サブタイトルの「剣を帯した」とあるのは、幕末の動乱期に青春時代を送ったゆえのものであり、本人は特別に武闘派というわけではないようだ。本書を読むかぎり。
ただし、当時の仏教僧は、廃仏毀釈の荒波をもろに受けており、その対応を問われていた。黙雷はその流れの中で、なんとかして仏教を守ろうと闘った僧であった。
黙雷の事績を書いた本書では、前半は若く貧しい黙雷が刻苦勉励して仏教を学ぶ姿がこれでもか、と描かれている。寺のあとをついでほしい、という養親の願いと、黙雷の向学心(遊学したい)との葛藤が熱い。
また、後半、欧州への外遊が描かれており、もともと、僕がこの本を読もうとした動機はそこを知りたい、という部分ではあったが、さらりと流されていて、この部分をもっと詳しく知りたい、と思った。
以下、目次。
序 幕末・明治の維摩
第1章 出自
1.垰の専照寺
2.十二歳の作『御法度伊呂波具ど木』
3.養子で入寺
第2章 萩の城下
1.苦手な法談
2.非常の出奔
第3章 遊学
1.辛苦の肥後遊学
2.遊学と離縁
3.連城と対論
第4章 僧侶と武
1.武事に関せず
2.剣を帯して
3.風儀改正
第5章 廃仏毀釈
1.復古と維新
2.廃仏毀釈の嵐
第6章 外遊と聖地
1.欧州政教見聞
2.信教の自由
3.布教の諸相
第7章 僧侶の争い
1.宗門クーデター
2.天皇と法主
第8章 家庭と教育
1.女子教育ほか
2.島地家の子女たち
3.邪宗と入信
第9章 奥羽の黙雷
1.同朋とデモクラシー
2.岩手願教寺での荘子講話
終 宗祖に立ち帰れ
参考史料・文献一覧
あとがき
島地黙雷略年譜
人名索引
『ジョルダーノ・ブルーノと大使館のミステリー』
2013年4月4日 読書
ジョン・ボッシーの『ジョルダーノ・ブルーノと大使館のミステリー』を読んだ。
1580年代のヨーロッパ、カトリックとプロテスタントの争いが広がる中でのお話。
フランス王アンリ3世からエリザベス女王に派遣された大使として、ミシェル・ドゥ・カステルノー候が8年間近くロンドンに暮らしていた。カステルノーは、エリザベス女王の虜囚であり、その後継者ともみなされていたスコットランド女王メアリーの自由確保のために尽力していた。メアリーを解放することで、フランスがスコットランドに対する支配力を取り戻すことができるとの思惑からである。カステルノーがメアリーと組んで何をたくらんでいるのかは、エリザベス女王の廷臣たちにとって非常な関心事であった。
さて、そのエリザベス女王の廷臣たるサー・フランシス・ウォルシンガムのもとに、ヘンリー・ファゴットという人物から、何回か手紙が届けられた。その内容は、カステルノー周辺に関わるスパイ文書だった。
ヘンリー・ハワード卿とフランシス・スロックモートンがカステルノーとメアリーの間のパイプ役をしていること。
その二人の訪問は常に夜であること。
裏切りもの、スパイの存在について。
本書の第1部では、こうしたスパイ、ファゴットの手紙からその行動を描き、第2部ではそのファゴットが誰なのか、という謎解きが行われる。
ファゴットが暗躍したのと同じ時期、同じ場所に滞在していた人物がいる。
ジョルダーノ・ブルーノだ。
著者は、ブルーノがファゴット、つまり、スパイなのではないか、と推理して、その論をすすめる。
著者が二人を同一人物だとみなす推理のポイントはいくつかあって、たとえば、「ファゴットはそのスパイ文書の前にも後にも経歴のない人物であること」「カステルノーがロンドンを離れる前夜に、その邸には司祭が1人しかいなかったとの記録があるが、ファゴットもブルーノも司祭だった」「ファゴットの手紙にブルーノにたいする記述はなく、ブルーノもファゴットについて何も書き残していない」などなど。
以下、目次。
第1部 夜の犬
1.ソールズベリー・コート
2.河の上で
3.告白
4.対話篇と騒動
5.アルカディアでの最後の日々
6.火山のもとで
第2部 時の娘、真理
1.反対の一致
Ⅰ大使館の司祭
Ⅱ敵とのコミュニケーション
2.彷徨するブルーノ
Ⅰロンドン
Ⅱ不平家
Ⅲパリ
3.ブルーノ再び捕わる
Ⅰ人
Ⅱ犬
Ⅲ政治活動
Ⅳ司祭
終章.火刑台のファゴット
第3部 テキストと覚え書
テキスト
カステルノー邸について
ジョヴァンニ・カヴァルカンティとそのローマ便りについて
ファゴットの筆跡とブルーノの筆跡について
ブルーノの筆跡の資料
本書で著者は、フランセス・イエイツへの批判を随所にちりばめている。たとえば、イエイツもブルーノがスパイであったとの見解を持っているが、それが、「反エリザベス工作」だとみなされたのに対して、本書では、こうだ。
つまり、カトリックの政治的積極行動主義者の野望を封じ込めるための行動をとっていて、あくまでもエリザベス側の人間だったことを言っているのだ。
また、イエイツは、ブルーノがイングランドに行った任務は、カトリックとプロテスタントの和解の促進だったと説いているが、本書では、それを真っ向から否定している。
本書で語られるブルーノは、自家撞着、一貫しない言動、プラクティカルジョーク好きな、一筋縄ではいかないひねくれものとして描かれる。(僕もそう思う)
その言動から、本当に彼が何を考えているのかを推し量ることは難しいのである。
一方、ファゴットは正体不明のスパイである。
謎のふたりを同定するのは、いきおい、多くを推論に頼らざるをえず、その分、いっそのこと完全に小説にしてしまったほうが、もっと大胆に論旨を推し進めることができたんじゃないかな、と思わされた。
1580年代のヨーロッパ、カトリックとプロテスタントの争いが広がる中でのお話。
フランス王アンリ3世からエリザベス女王に派遣された大使として、ミシェル・ドゥ・カステルノー候が8年間近くロンドンに暮らしていた。カステルノーは、エリザベス女王の虜囚であり、その後継者ともみなされていたスコットランド女王メアリーの自由確保のために尽力していた。メアリーを解放することで、フランスがスコットランドに対する支配力を取り戻すことができるとの思惑からである。カステルノーがメアリーと組んで何をたくらんでいるのかは、エリザベス女王の廷臣たちにとって非常な関心事であった。
さて、そのエリザベス女王の廷臣たるサー・フランシス・ウォルシンガムのもとに、ヘンリー・ファゴットという人物から、何回か手紙が届けられた。その内容は、カステルノー周辺に関わるスパイ文書だった。
ヘンリー・ハワード卿とフランシス・スロックモートンがカステルノーとメアリーの間のパイプ役をしていること。
その二人の訪問は常に夜であること。
裏切りもの、スパイの存在について。
本書の第1部では、こうしたスパイ、ファゴットの手紙からその行動を描き、第2部ではそのファゴットが誰なのか、という謎解きが行われる。
ファゴットが暗躍したのと同じ時期、同じ場所に滞在していた人物がいる。
ジョルダーノ・ブルーノだ。
著者は、ブルーノがファゴット、つまり、スパイなのではないか、と推理して、その論をすすめる。
我々はこれまで、1580年代のほぼ3年間、ロンドンとパリにおける二人の男(ファゴットとブルーノ)の経歴を追ってきた。その二人には、かなり多くの共通点があった。彼らは二人共イタリア人で、カトリック司祭だった。二人共1583年の4月頃に、ロンドンのカステルノー邸を訪れ、それ以降、そこに住んでカステルノーに仕えた。二人共ローマ教皇、スペイン、そしてイングランドのカトリック教徒の陰謀に激しい敵意を持っていた。二人共エリザベス女王自身に拝謁し、途方もない忠誠心をもって女王のことを記した。二人共1585年9月にカステルノーと一緒にイングランドを離れてパリに向かい、到着後すぐにカステルノーに仕えるのをやめた。1586年の間に、1人は永遠にパリを離れ、もう1人は消え失せた。
著者が二人を同一人物だとみなす推理のポイントはいくつかあって、たとえば、「ファゴットはそのスパイ文書の前にも後にも経歴のない人物であること」「カステルノーがロンドンを離れる前夜に、その邸には司祭が1人しかいなかったとの記録があるが、ファゴットもブルーノも司祭だった」「ファゴットの手紙にブルーノにたいする記述はなく、ブルーノもファゴットについて何も書き残していない」などなど。
以下、目次。
第1部 夜の犬
1.ソールズベリー・コート
2.河の上で
3.告白
4.対話篇と騒動
5.アルカディアでの最後の日々
6.火山のもとで
第2部 時の娘、真理
1.反対の一致
Ⅰ大使館の司祭
Ⅱ敵とのコミュニケーション
2.彷徨するブルーノ
Ⅰロンドン
Ⅱ不平家
Ⅲパリ
3.ブルーノ再び捕わる
Ⅰ人
Ⅱ犬
Ⅲ政治活動
Ⅳ司祭
終章.火刑台のファゴット
第3部 テキストと覚え書
テキスト
カステルノー邸について
ジョヴァンニ・カヴァルカンティとそのローマ便りについて
ファゴットの筆跡とブルーノの筆跡について
ブルーノの筆跡の資料
本書で著者は、フランセス・イエイツへの批判を随所にちりばめている。たとえば、イエイツもブルーノがスパイであったとの見解を持っているが、それが、「反エリザベス工作」だとみなされたのに対して、本書では、こうだ。
確かに、彼のイングランドでのスパイ活動はそもそもイングランドのカトリック制度を覆すことに捧げられていたが、それはそうすることがエリザベス女王と彼女の統治下の政府を転覆させようと企てられた政治活動を押え込める限りにおいてであり…
つまり、カトリックの政治的積極行動主義者の野望を封じ込めるための行動をとっていて、あくまでもエリザベス側の人間だったことを言っているのだ。
また、イエイツは、ブルーノがイングランドに行った任務は、カトリックとプロテスタントの和解の促進だったと説いているが、本書では、それを真っ向から否定している。
本書で語られるブルーノは、自家撞着、一貫しない言動、プラクティカルジョーク好きな、一筋縄ではいかないひねくれものとして描かれる。(僕もそう思う)
その言動から、本当に彼が何を考えているのかを推し量ることは難しいのである。
一方、ファゴットは正体不明のスパイである。
謎のふたりを同定するのは、いきおい、多くを推論に頼らざるをえず、その分、いっそのこと完全に小説にしてしまったほうが、もっと大胆に論旨を推し進めることができたんじゃないかな、と思わされた。
パピーニの『逃げてゆく鏡』を読んだ。
パピーニは、先日読んだエリアーデの紀行文で訪ねた模様が書いてあり、俄然興味を持ったのだ。
以下、目次。作品のタイトルの後、簡単な内容まとめ。
「泉水のなかの二つの顔」
水面に映った7年前の自分との再会
「完全に馬鹿げた物語」
あの人物が読み上げた物語はわたしの生活の内面と外面とを余すところなく暴露したものにほかならなかった。
「精神の死」
意志だけで自殺を実行する男
「『病める紳士』の最後の訪問」
わたしを夢見てくれている人は誰なのか?
「もはやいまのままのわたしではいたくない」
わたしはついに自分以外にはなれないことに気づいた
「きみは誰なのか?」
ある日突然、誰もがその存在を認めなくなった男
「魂を乞う者」
平凡な人生を聞いて恐怖する男
「身代わりの自殺」
33歳にしておのれの才能が発揮できなかった者は、あるいは近い未来に向けて何らかの実績を約束できないような者は、恐ろしい義務を持っているはずだ。
と、他人の代わりに命を捧げようとする男。
「逃げてゆく鏡」
すべての現在は自分たちの手によって未来のための犠牲にされ、その未来はやがて現在となるが、またもや別の未来のための犠牲にされ、そのようにして最後の現在まで、すなわち死まで、引き延ばされてゆくであろう。
「返済されなかった一日」
若き日の1年を貸して、年老いてから、ちびちび返済してもらって、若さを楽しむ。
パピーニは、先日読んだエリアーデの紀行文で訪ねた模様が書いてあり、俄然興味を持ったのだ。
以下、目次。作品のタイトルの後、簡単な内容まとめ。
「泉水のなかの二つの顔」
水面に映った7年前の自分との再会
「完全に馬鹿げた物語」
あの人物が読み上げた物語はわたしの生活の内面と外面とを余すところなく暴露したものにほかならなかった。
「精神の死」
意志だけで自殺を実行する男
「『病める紳士』の最後の訪問」
わたしを夢見てくれている人は誰なのか?
「もはやいまのままのわたしではいたくない」
わたしはついに自分以外にはなれないことに気づいた
「きみは誰なのか?」
ある日突然、誰もがその存在を認めなくなった男
「魂を乞う者」
平凡な人生を聞いて恐怖する男
「身代わりの自殺」
33歳にしておのれの才能が発揮できなかった者は、あるいは近い未来に向けて何らかの実績を約束できないような者は、恐ろしい義務を持っているはずだ。
と、他人の代わりに命を捧げようとする男。
「逃げてゆく鏡」
すべての現在は自分たちの手によって未来のための犠牲にされ、その未来はやがて現在となるが、またもや別の未来のための犠牲にされ、そのようにして最後の現在まで、すなわち死まで、引き延ばされてゆくであろう。
「返済されなかった一日」
若き日の1年を貸して、年老いてから、ちびちび返済してもらって、若さを楽しむ。
『フクシマの後で 破局・技術・民主主義』
2013年3月28日 読書
ジャン=リュック・ナンシーの『フクシマの後で 破局・技術・民主主義』を読んだ。
序にかえて
I 破局の等価性――フクシマの後で
II 集積について
III 民主主義の実相
1 六八年―〇八年
2 合致しない民主主義
3 さらけ出された民主主義
4 民主主義の主体について
5 存在することの潜勢力
6 無限なものと共通のもの
7 計算不可能なものの分有
8 有限なものにおける無限
9 区別された政治
10 非等価性
11 無限なもののために形成された空間
12 プラクシス
13 実相
訳者解題
等価性と集積、というキーワード。
なるほど、としっくりくる。
序にかえて
I 破局の等価性――フクシマの後で
II 集積について
III 民主主義の実相
1 六八年―〇八年
2 合致しない民主主義
3 さらけ出された民主主義
4 民主主義の主体について
5 存在することの潜勢力
6 無限なものと共通のもの
7 計算不可能なものの分有
8 有限なものにおける無限
9 区別された政治
10 非等価性
11 無限なもののために形成された空間
12 プラクシス
13 実相
訳者解題
等価性と集積、というキーワード。
なるほど、としっくりくる。
『ヘレネー誘拐・トロイア落城』『絵と物語でたどる古代史』第2巻「ギリシア」
2013年3月26日 読書
講談社学術文庫の『ヘレネー誘拐・トロイア落城』を読んだ。
6世紀のコルートスの「ヘレネー誘拐」は、トロイア戦争の原因となった出来事について書かれたもの。
4世紀前半までに書かれたと思われるトリピオドーロスの「トロイア落城」は、トロイアの木馬の詳しい描写がなされている貴重な作品。
以下、目次
「ヘレネー誘拐」コルートス
1.ペーレウスとテティスの結婚
2.黄金の林檎
3.イーデー山に向かう三女神
4.パリスの判定
5.スパルタを目ざすパリス
6.誘惑されるヘレネー
7.捨てられた娘ヘルミオネー
8.まぼろしの母
「トロイア落城」トリピオドーロス
1.十年戦争の浮き沈み
2.エペイオス、木馬を作る
3.オデュッセウスの作戦解説
4.木馬に乗りこむ戦士たち
5.テネドスに待機する船団
6.シノーンの謀略
7.トロイアの城塞へはこばれたる木馬
8.カサンドレーの空しい叫び
9.木馬にささやくヘレネー
10.合図を送るシノーンとヘレネー
11.殺戮の夜
12.メネラーオスとヘレネーの再会
13.死ぬ者、生きる者
14.終戦
ロイ・バレル著、ピーター・コノリー絵による『絵と物語でたどる古代史』第2巻「ギリシア」を読んだ。
図版が多く、内容は、ホメロスの歌を聞いたり、当時の住人にインタビューした記事をのせたり、と読みやすくする工夫がこらされている。
以下、目次。
第1章 ミノア人
ミノア人の伝説/アーサー・エヴァンズ卿/クノッソス宮殿/日常生活/宗教/牛跳び/マイケル・ヴェントリスと線文字B/アトランティス
第2章 ミケーネ人
ホメロス/トロイア戦争/ハインリヒ・シュリーマン/シュリーマンとミケーネ文明
第3章 初期のギリシア人
アカイア人とドーリス人/都市の出現/初期のアテナイ
第4章 ギリシア文明
ポリスの政治/ソロン、クレイステネス、ペリクレス/日常生活/家族/美術と陶芸/船と貿易/神々
第5章 ペルシア戦争
ペルシア帝国/ペルシアの王たち/マラトンの戦い/テルモピュライの戦い/サラミスの海戦
第6章 ペリクレスと黄金時代
ギリシアの賢人たち/奴隷制/衣服/アクロポリスとその建築群/ギリシアの伝説/音楽/劇場/神託
第7章 運動と競技
ペロプスの伝説/オリュンピア/オリンピック/その他の競技と娯楽
第8章 ペロポネソス戦争
スパルタ/なぜ戦争がはじまったのか/戦士と戦闘/征服されたアテナイ
第9章 アレクサンドロス大王
少年時代/軍隊/戦闘と包囲/ペルセポリス/アレクサンドロスの最後の戦い/征服者の死/帝国の分裂
第10章 征服されたギリシア
ローマ人の襲来/ギリシア・ローマの属州になる/ギリシアの遺産
6世紀のコルートスの「ヘレネー誘拐」は、トロイア戦争の原因となった出来事について書かれたもの。
4世紀前半までに書かれたと思われるトリピオドーロスの「トロイア落城」は、トロイアの木馬の詳しい描写がなされている貴重な作品。
以下、目次
「ヘレネー誘拐」コルートス
1.ペーレウスとテティスの結婚
2.黄金の林檎
3.イーデー山に向かう三女神
4.パリスの判定
5.スパルタを目ざすパリス
6.誘惑されるヘレネー
7.捨てられた娘ヘルミオネー
8.まぼろしの母
「トロイア落城」トリピオドーロス
1.十年戦争の浮き沈み
2.エペイオス、木馬を作る
3.オデュッセウスの作戦解説
4.木馬に乗りこむ戦士たち
5.テネドスに待機する船団
6.シノーンの謀略
7.トロイアの城塞へはこばれたる木馬
8.カサンドレーの空しい叫び
9.木馬にささやくヘレネー
10.合図を送るシノーンとヘレネー
11.殺戮の夜
12.メネラーオスとヘレネーの再会
13.死ぬ者、生きる者
14.終戦
ロイ・バレル著、ピーター・コノリー絵による『絵と物語でたどる古代史』第2巻「ギリシア」を読んだ。
図版が多く、内容は、ホメロスの歌を聞いたり、当時の住人にインタビューした記事をのせたり、と読みやすくする工夫がこらされている。
以下、目次。
第1章 ミノア人
ミノア人の伝説/アーサー・エヴァンズ卿/クノッソス宮殿/日常生活/宗教/牛跳び/マイケル・ヴェントリスと線文字B/アトランティス
第2章 ミケーネ人
ホメロス/トロイア戦争/ハインリヒ・シュリーマン/シュリーマンとミケーネ文明
第3章 初期のギリシア人
アカイア人とドーリス人/都市の出現/初期のアテナイ
第4章 ギリシア文明
ポリスの政治/ソロン、クレイステネス、ペリクレス/日常生活/家族/美術と陶芸/船と貿易/神々
第5章 ペルシア戦争
ペルシア帝国/ペルシアの王たち/マラトンの戦い/テルモピュライの戦い/サラミスの海戦
第6章 ペリクレスと黄金時代
ギリシアの賢人たち/奴隷制/衣服/アクロポリスとその建築群/ギリシアの伝説/音楽/劇場/神託
第7章 運動と競技
ペロプスの伝説/オリュンピア/オリンピック/その他の競技と娯楽
第8章 ペロポネソス戦争
スパルタ/なぜ戦争がはじまったのか/戦士と戦闘/征服されたアテナイ
第9章 アレクサンドロス大王
少年時代/軍隊/戦闘と包囲/ペルセポリス/アレクサンドロスの最後の戦い/征服者の死/帝国の分裂
第10章 征服されたギリシア
ローマ人の襲来/ギリシア・ローマの属州になる/ギリシアの遺産
エウリーピデースの『タウリケーのイーピゲネイア』を読んだ。
1.プロロゴス
イーピゲネイアが生贄にされる経緯から、アルテミスに救われ、タウロイ人の国に連れて来られるまで。
一方、イーピゲネイアの弟、オレステースの狂気は、タウロイ人の国のアルテミス像を盗んでアテーナイに持ち帰れば解放されることが明かされる。
〔パロドス〕(コロス登場の歌と踊り)
2.第一エペイソディオン
牛飼いに捕まった二人の若者、オレステースとピュラデースは、生贄にされることになる。
〔第一スタシモン〕(コロスの歌と踊り)
3.第二エペイソディオン
イーピゲネイアが、囚われの若者が我が弟だとも知らずに、トロイア戦争の顛末について尋ねる。弟の生存を確信したイーピゲネイアは2人の内の1人に弟への手紙を託し、もう1人だけ生贄にすることにする。
しかし、生贄になる方を引き受けたのは、弟のオレステースの方。
〔コンモス〕(区切り)
4.第二エペイソディオン(つづき)
どちらが生贄になるかについてピュラデースは異議申し立て。
手紙の内容が音読されて、姉弟の関係であることが判明する。
〔第二スタシモン〕
5.第三エペイソディオン
イーピゲネイアは策略をこらし、アルテミスの像を盗んで、囚人とともに自分も逃亡しようと企てる。
〔第三スタシモン〕
6.エクソドス
騙して船まで乗り込み、脱走しようとするが、大波と突風で船が岸に押し戻されてしまう。
トアース王の追撃が迫る。
ここで、デウス・エクス・マキーナーのアテナ女神が登場。
オレステースが姉のイーピゲネイアを伴ってアルテミス像をギリシアへ運ぶのは、アポローンの神意であることを明かす。
めでたし、めでたし。
作中で感嘆詞の使い方が面白かったので、パロドスより一部引用しておこう。驚きや悲しみをあらわす感嘆詞が3種類。
破滅です、わたしはもう破滅です。
父の館はなく、
オイモイ、わたしの血族は絶えました。
ペウペウ、アルゴスの国にとってはなんという苦難か。
イオー、神霊よ。
ペウペウ、なんて、ちょっと使ってみたい。
アートスペース亜蛮人で特殊造型&特殊メイク展2。
1階では特殊メイクの写真展示と、実演。
2階では特殊造型物の展示。
行ったときは、ちょうど実演が終わって、怪物が人間に戻りつつある最中だった。
1.プロロゴス
イーピゲネイアが生贄にされる経緯から、アルテミスに救われ、タウロイ人の国に連れて来られるまで。
一方、イーピゲネイアの弟、オレステースの狂気は、タウロイ人の国のアルテミス像を盗んでアテーナイに持ち帰れば解放されることが明かされる。
〔パロドス〕(コロス登場の歌と踊り)
2.第一エペイソディオン
牛飼いに捕まった二人の若者、オレステースとピュラデースは、生贄にされることになる。
〔第一スタシモン〕(コロスの歌と踊り)
3.第二エペイソディオン
イーピゲネイアが、囚われの若者が我が弟だとも知らずに、トロイア戦争の顛末について尋ねる。弟の生存を確信したイーピゲネイアは2人の内の1人に弟への手紙を託し、もう1人だけ生贄にすることにする。
しかし、生贄になる方を引き受けたのは、弟のオレステースの方。
〔コンモス〕(区切り)
4.第二エペイソディオン(つづき)
どちらが生贄になるかについてピュラデースは異議申し立て。
手紙の内容が音読されて、姉弟の関係であることが判明する。
〔第二スタシモン〕
5.第三エペイソディオン
イーピゲネイアは策略をこらし、アルテミスの像を盗んで、囚人とともに自分も逃亡しようと企てる。
〔第三スタシモン〕
6.エクソドス
騙して船まで乗り込み、脱走しようとするが、大波と突風で船が岸に押し戻されてしまう。
トアース王の追撃が迫る。
ここで、デウス・エクス・マキーナーのアテナ女神が登場。
オレステースが姉のイーピゲネイアを伴ってアルテミス像をギリシアへ運ぶのは、アポローンの神意であることを明かす。
めでたし、めでたし。
作中で感嘆詞の使い方が面白かったので、パロドスより一部引用しておこう。驚きや悲しみをあらわす感嘆詞が3種類。
破滅です、わたしはもう破滅です。
父の館はなく、
オイモイ、わたしの血族は絶えました。
ペウペウ、アルゴスの国にとってはなんという苦難か。
イオー、神霊よ。
ペウペウ、なんて、ちょっと使ってみたい。
アートスペース亜蛮人で特殊造型&特殊メイク展2。
1階では特殊メイクの写真展示と、実演。
2階では特殊造型物の展示。
行ったときは、ちょうど実演が終わって、怪物が人間に戻りつつある最中だった。
『ホメロス』(文庫クセジュ)、『ホメロス-史上最高の文学者』
2013年3月21日 読書
ジャクリーヌ・ド・ロミーイの『ホメロス』を読んだ。文庫クセジュ。
以下、目次。
第1章 両詩篇の誕生
1.トロイア戦争からホメロスまで
2.口承詩
3.最後にホメロスが現われた
4.ホメロス問題
第2章 叙事詩の世界と歴史
1.ホメロスの言語
2.慣習と器者
3.ホメロスと発見の実際
4.歴史と詩篇
第3章 両詩篇の構成
1.『イリアス』
2.『オデュッセイア』
第4章 詩作の手順
第5章 神々と驚異
1.神族
2.神々の威厳
3.神意
4.神々の介入
5.魔法と幻想
第6章 「神々に似る」英雄たち
第7章 「死すべき者」としての英雄たち
結び ホメロス以後
著者は本書執筆後に、失明したそうだ。ホメロスという語は、母方の故郷キュメでは「盲人」という意味である。出来すぎてる!
アレクサンドル・ファルヌーの『ホメロス-史上最高の文学者』を読んだ。「知の再発見」双書。
以下、目次。
第1章 神と人間と英雄の物語
第2章 ホメロスの実像
第3章 トロイアによる証明
第4章 ホメロス作品の分析的研究
第5章 ホメロスでたどる人類の歴史
(資料篇)
1.ホメロスの幻影
2.ホメロスの墓の発見
3.18世紀に広まった「ホメロスの生涯」
4.アキレイオン
5.ホメロス作品の翻訳
6.ホメロスと聖書
7.ホメロスとホメロス作品の足跡を題材とした著作
8.20世紀のホメロス
ホメロスを知るためのインターネットサイトと映画作品リスト
ホメロスの作品に登場するギリシアの神々と人物
年表
INDEX
出典(図版)
参考文献
文庫クセジュには、一切図版はなかったが、この「知の再発見」双書は、図版多数。
今回読了したこの2冊は、雰囲気づくりのために読んだものだ。
以下、目次。
第1章 両詩篇の誕生
1.トロイア戦争からホメロスまで
2.口承詩
3.最後にホメロスが現われた
4.ホメロス問題
第2章 叙事詩の世界と歴史
1.ホメロスの言語
2.慣習と器者
3.ホメロスと発見の実際
4.歴史と詩篇
第3章 両詩篇の構成
1.『イリアス』
2.『オデュッセイア』
第4章 詩作の手順
第5章 神々と驚異
1.神族
2.神々の威厳
3.神意
4.神々の介入
5.魔法と幻想
第6章 「神々に似る」英雄たち
第7章 「死すべき者」としての英雄たち
結び ホメロス以後
著者は本書執筆後に、失明したそうだ。ホメロスという語は、母方の故郷キュメでは「盲人」という意味である。出来すぎてる!
アレクサンドル・ファルヌーの『ホメロス-史上最高の文学者』を読んだ。「知の再発見」双書。
以下、目次。
第1章 神と人間と英雄の物語
第2章 ホメロスの実像
第3章 トロイアによる証明
第4章 ホメロス作品の分析的研究
第5章 ホメロスでたどる人類の歴史
(資料篇)
1.ホメロスの幻影
2.ホメロスの墓の発見
3.18世紀に広まった「ホメロスの生涯」
4.アキレイオン
5.ホメロス作品の翻訳
6.ホメロスと聖書
7.ホメロスとホメロス作品の足跡を題材とした著作
8.20世紀のホメロス
ホメロスを知るためのインターネットサイトと映画作品リスト
ホメロスの作品に登場するギリシアの神々と人物
年表
INDEX
出典(図版)
参考文献
文庫クセジュには、一切図版はなかったが、この「知の再発見」双書は、図版多数。
今回読了したこの2冊は、雰囲気づくりのために読んだものだ。
藤子不二雄Aの『夢追い漫画家60年 いつも明日見て…』を読んだ。
以下、目次。
プロローグ
1 電車通勤とお弁当
2 キャラクターでひきつける漫画
3 藤子・F・不二雄(藤本弘)氏との出会い
4 手塚治虫先生の『新寳島』の衝撃
5 デビュー作
6 新聞社の二年間
7 上京の決断
8 トキワ荘の絆
9 いろいろなジャンルに挑戦
10 もうひとつの夢を…
11 漫画家生活六十年をふりかえる…
100年後の皆さんへ 僕からのメッセージ
NHK-BSの番組「100年インタビュー/漫画家 藤子不二雄A」をもとにして作られた1冊。『まんが道』や『愛…しりそめし頃に…』などで、自伝的なストーリーは繰返し語られているが、この本もまた、その路線からはずれないもので、講談や叙事詩のネタみたいな範疇に入ってきたのかもしれない。
各章には、人生の教訓となるようなヒントもちりばめられている。
例をいくつか挙げておこう。
『横尾忠則ラッピング電車故郷を走る』を読んだ。織作峰子ほかのラッピング列車写真と、横尾忠則と、世田谷美術館館長の酒井忠康の文章。
このラッピング電車は2004年12月に登場し、2012年末の全般検査(8年に1回)で解体され、姿を消すことになった。
以下、目次。
序文 横尾忠則氏のラッピング電車に思う(酒井忠康)
1.見る見る速い
2.銀河の旅
3.滝の音、電車の音
4.走れ!Y字路
5.未完のラッピング電車
ラッピング電車について思うこと(横尾忠則)
各章の末尾には、ラッピング電車の原画、イベント写真、新聞記事が載せられてあり、ラッピング電車のページの脇には、地元や観光客などの短いコメントがつけられている。
第5章は、計画だけで実現しなかったラッピング電車「ターザンの雄叫び」「日本の文豪作家」は、実際に作られていたら、こうであったろう、という合成写真がシミュレーションとして掲載されている。一見、まったく違和感なく見れるのだから、おそろしいものだ。
アビ・ヴァールブルクの著作集第4巻『ルネサンスの祝祭的生における古代と近代』を読んだ。
以下、目次。
第1章 いわゆる「ハウスブーフの画家」の素描に見られる、国王マクシミリアンのブリュッヘ捕囚における二つの場面
第2章 中世の表象世界における飛行船と潜水艇
第3章 ヨーハン・アントン・ランブーの水彩模写に見られる、ピエロ・デッラ・フランチェスカの<コンスタンティヌス帝の勝利>
第4章 ウフィツィ美術館所蔵のフランドルのタピスリーに見られる、ヴァロワ朝の宮廷でのメディチ家の祝宴
第5章 一五八九年の幕間劇のための舞台衣裳―ベルナルド・ブオンタレンティの素描とエミリオ・デ・カヴァリエーリの出納簿
第6章 一五世紀のフィレンツェへの文化史的寄与
原註
補註
図版一覧
解題 ヴァールブルクとフランドルのタピスリー/加藤哲弘
解題 フィレンツェの市民生活と祝祭芸術/伊藤博明
あとがき
人名/著作名/美術作品名 索引
第4章でとりあげられるのは、つい先日読んだイエイツの『ヴァロワ・タピスリーの謎』でがぜん興味を覚えた、タピスリーそのものだ。1927年の講演をもとに書かれているもので、ざっとした解説だけだが、この奥にあんなに豊かな謎があると知ったうえでは、非常に面白い。
本の性質上、図版と註が充実していて、楽しく読むことができた。
以下、目次。
プロローグ
1 電車通勤とお弁当
2 キャラクターでひきつける漫画
3 藤子・F・不二雄(藤本弘)氏との出会い
4 手塚治虫先生の『新寳島』の衝撃
5 デビュー作
6 新聞社の二年間
7 上京の決断
8 トキワ荘の絆
9 いろいろなジャンルに挑戦
10 もうひとつの夢を…
11 漫画家生活六十年をふりかえる…
100年後の皆さんへ 僕からのメッセージ
NHK-BSの番組「100年インタビュー/漫画家 藤子不二雄A」をもとにして作られた1冊。『まんが道』や『愛…しりそめし頃に…』などで、自伝的なストーリーは繰返し語られているが、この本もまた、その路線からはずれないもので、講談や叙事詩のネタみたいな範疇に入ってきたのかもしれない。
各章には、人生の教訓となるようなヒントもちりばめられている。
例をいくつか挙げておこう。
合作で漫画を描く時も、互いの批評などは一切しませんでした。それは、まずお互いの漫画を絶対的に認め合っていたからです。
面白い、面白くない…という読者の判断を漫画家は予想することは出来ません。また、漫画家が読者の人気を計算して作品を描いてはダメです。
漫画を描く上でやってはいけないと思っていることは、消去法です。どんどんそこにプラスしていかないと。「これじゃダメだ」ではなくて「こうしたら面白いだろう、ああしたら面白いだろう」ということ。
『横尾忠則ラッピング電車故郷を走る』を読んだ。織作峰子ほかのラッピング列車写真と、横尾忠則と、世田谷美術館館長の酒井忠康の文章。
このラッピング電車は2004年12月に登場し、2012年末の全般検査(8年に1回)で解体され、姿を消すことになった。
以下、目次。
序文 横尾忠則氏のラッピング電車に思う(酒井忠康)
1.見る見る速い
2.銀河の旅
3.滝の音、電車の音
4.走れ!Y字路
5.未完のラッピング電車
ラッピング電車について思うこと(横尾忠則)
各章の末尾には、ラッピング電車の原画、イベント写真、新聞記事が載せられてあり、ラッピング電車のページの脇には、地元や観光客などの短いコメントがつけられている。
第5章は、計画だけで実現しなかったラッピング電車「ターザンの雄叫び」「日本の文豪作家」は、実際に作られていたら、こうであったろう、という合成写真がシミュレーションとして掲載されている。一見、まったく違和感なく見れるのだから、おそろしいものだ。
アビ・ヴァールブルクの著作集第4巻『ルネサンスの祝祭的生における古代と近代』を読んだ。
以下、目次。
第1章 いわゆる「ハウスブーフの画家」の素描に見られる、国王マクシミリアンのブリュッヘ捕囚における二つの場面
第2章 中世の表象世界における飛行船と潜水艇
第3章 ヨーハン・アントン・ランブーの水彩模写に見られる、ピエロ・デッラ・フランチェスカの<コンスタンティヌス帝の勝利>
第4章 ウフィツィ美術館所蔵のフランドルのタピスリーに見られる、ヴァロワ朝の宮廷でのメディチ家の祝宴
第5章 一五八九年の幕間劇のための舞台衣裳―ベルナルド・ブオンタレンティの素描とエミリオ・デ・カヴァリエーリの出納簿
第6章 一五世紀のフィレンツェへの文化史的寄与
原註
補註
図版一覧
解題 ヴァールブルクとフランドルのタピスリー/加藤哲弘
解題 フィレンツェの市民生活と祝祭芸術/伊藤博明
あとがき
人名/著作名/美術作品名 索引
第4章でとりあげられるのは、つい先日読んだイエイツの『ヴァロワ・タピスリーの謎』でがぜん興味を覚えた、タピスリーそのものだ。1927年の講演をもとに書かれているもので、ざっとした解説だけだが、この奥にあんなに豊かな謎があると知ったうえでは、非常に面白い。
本の性質上、図版と註が充実していて、楽しく読むことができた。
『ルネサンス哲学 付:イタリア紀行』
2013年3月12日 読書
ミルチア・エリアーデの『ルネサンス哲学 付:イタリア紀行』を読んだ。
「ルネサンス哲学」はエリアーデの学士論文。
本来の草案をあげておこう。
序:中世の形而上学とルネサンスの自然主義
1:ユマニスム、公会議とギリシア人の到来
2:古代的諸価値の復興
3:スペインにおけるルネサンス
4:北方ルネサンスの哲学
5:中間的諸体系-ジェロラモ・カルダーノ、ニコラス・クザーヌス、ジャンバティスタ・ポルタ
6:自然と経験の優位、哲学と科学-レオナルド、ガリレオ
7:ジョルダノ・ブルーノ
8:カンパネラと近代哲学の基礎
9:マキャベリと個人
結論
補遺:ルネサンス期の宗教的経験と教義の改革
本書では、このなかの1~3が収録されているが、残りの部分が書かれていたかどうかは不明らしい。
1章のギリシア人や、3章のスペイン・ルネサンスの人名など、全然知らない名前がバンバン出てきて、かなり刺激された。
「イタリア紀行」は学士論文に多少なりとも関わりのある、エリアーデ20歳、21歳のときの3回のイタリア紀行文。とはいえ、エリアーデはイタリアのガイドブック的なものを書こうとしたのではない。話はむしろ逆で、ガイドブックで仕入れたにわか知識をひけらかす半可通の観光客を皮肉たっぷりに描いている。エリアーデがまだ若いせいか、ひとの悪さがところどころ出ていて、面白い。
イタリア紀行の読みどころは、パピーニ、パンツィーニ、ボナイウティ、ジェンティーレとの対話だ。エリアーデ、21歳でこんな会話ができたんだ。すごい。
以下、目次。
ルネサンス哲学
1.ユマニスム、公会議とギリシア人の到来
2.古代的諸価値の復興と超克
3.スペインにおける哲学的ルネサンス
イタリア紀行(1927‐1928)
1927年
4月
ヴェネツィア
4月21日
ヴェネツィアでの旅ノート
4月27日
フィレンツェ 4月
フィレンツェ日記
ジョヴァンニ・パピーニとの取りとめのない会話
5月
パンツィーニのローマ
ナポリ、5月
旅のノート:ヴェスヴィオス-ポンペイ
アッバツィア
9月
感傷的な日記の数頁。ヴェネツィアの秋
1928年
ヴェネツィア、4月5日
タルヴィシオ-ヴェネツィア
ローマ、4月25日
ローマの形と色
Natale di Roma(ローマの誕生日)
4月28日
ティヴォリにて、博学者たちとともに
ローマ、5月
エルネスト・ボナイウティのもとにて
ローマ、5月9日
ジョヴァンニ・ジェンティーレを聴講して
1928年の4月28日の題名「博学者たちとともに」の「博学者」とは誰だったのか、というと、本文に、こうある。
「ルネサンス哲学」はエリアーデの学士論文。
本来の草案をあげておこう。
序:中世の形而上学とルネサンスの自然主義
1:ユマニスム、公会議とギリシア人の到来
2:古代的諸価値の復興
3:スペインにおけるルネサンス
4:北方ルネサンスの哲学
5:中間的諸体系-ジェロラモ・カルダーノ、ニコラス・クザーヌス、ジャンバティスタ・ポルタ
6:自然と経験の優位、哲学と科学-レオナルド、ガリレオ
7:ジョルダノ・ブルーノ
8:カンパネラと近代哲学の基礎
9:マキャベリと個人
結論
補遺:ルネサンス期の宗教的経験と教義の改革
本書では、このなかの1~3が収録されているが、残りの部分が書かれていたかどうかは不明らしい。
1章のギリシア人や、3章のスペイン・ルネサンスの人名など、全然知らない名前がバンバン出てきて、かなり刺激された。
「イタリア紀行」は学士論文に多少なりとも関わりのある、エリアーデ20歳、21歳のときの3回のイタリア紀行文。とはいえ、エリアーデはイタリアのガイドブック的なものを書こうとしたのではない。話はむしろ逆で、ガイドブックで仕入れたにわか知識をひけらかす半可通の観光客を皮肉たっぷりに描いている。エリアーデがまだ若いせいか、ひとの悪さがところどころ出ていて、面白い。
イタリア紀行の読みどころは、パピーニ、パンツィーニ、ボナイウティ、ジェンティーレとの対話だ。エリアーデ、21歳でこんな会話ができたんだ。すごい。
以下、目次。
ルネサンス哲学
1.ユマニスム、公会議とギリシア人の到来
2.古代的諸価値の復興と超克
3.スペインにおける哲学的ルネサンス
イタリア紀行(1927‐1928)
1927年
4月
ヴェネツィア
4月21日
ヴェネツィアでの旅ノート
4月27日
フィレンツェ 4月
フィレンツェ日記
ジョヴァンニ・パピーニとの取りとめのない会話
5月
パンツィーニのローマ
ナポリ、5月
旅のノート:ヴェスヴィオス-ポンペイ
アッバツィア
9月
感傷的な日記の数頁。ヴェネツィアの秋
1928年
ヴェネツィア、4月5日
タルヴィシオ-ヴェネツィア
ローマ、4月25日
ローマの形と色
Natale di Roma(ローマの誕生日)
4月28日
ティヴォリにて、博学者たちとともに
ローマ、5月
エルネスト・ボナイウティのもとにて
ローマ、5月9日
ジョヴァンニ・ジェンティーレを聴講して
1928年の4月28日の題名「博学者たちとともに」の「博学者」とは誰だったのか、というと、本文に、こうある。
ところでこの覚書の題名は嘘っぱちである。私はティヴォリにおしゃべりで好奇心の強い学会の博学者と一緒に行ったのではない。私はそこへはひとりで行った。
アレクサンドル・デュマの『王妃マルゴ』読了。鹿島茂の編訳。
全訳ではなく、半分ほどの長さの抄訳なのだが、とばした部分はあらすじで埋めてある。デュマ、面白いな。あらすじをたどるだけの章でも、ワクワクする面白さがあじわえた。また、普通なら「註」として書かれているところが、まるでコラムのような体裁で、歴史的背景などが読めて、これだけでも面白い読物になっていた。雰囲気は、カーの『九つの答』。
長さが半分とは言え、もともとが大長編なので、よみごたえはたっぷり。
そして、圧倒的な物語の面白さに驚いた。
イエイツの『ヴァロワ・タピスリーの謎』を読んで興味がわいてきて、ヴァロワの真珠とうたわれたマルゴの物語を読もう、と思ったのだが、ほんと、読んでよかった。
母后のカトリーヌのこわいことこわいこと!
以下、目次
第1章 ギーズ公のラテン語
美女スパイの使命
第2章 ナヴァール王妃の部屋
聖バルテルミーの虐殺の原因
第3章 王様詩人
第4章 1572年8月24日の晩
ベッドはひとつ
第5章 ルーヴル、および美徳一般について
第6章 返されたギーズ公の借り
第7章 1572年8月24日の夜
第8章 虐殺された人々
第9章 虐殺者
第10章 死か、ミサか、それともバスチーユか
第11章 イノサン墓地のサンザシ
第12章 打ち明け話
ルーヴル宮殿の中は…
第13章 すべての部屋をあける鍵
第14章 第二の初夜
結婚の「成立」
第15章 女が望むことは神も望む
第16章 死んだ敵の死体はいつでもいい匂いがする
第17章 アンブロワーズ・パレの同業者
第18章 死んだはずの男たち
第19章 カトリーヌ母后御用達の調香師のルネの居室
第20章 黒い雌鶏
調香師と占い
第21章 ソーヴ夫人の居室
第22章 陛下、陛下は王になられます
第23章 新たな改宗者
アランソン公の結婚話
第24章 ティゾン街とクロシュ=ペルセ街
第25章 サクランボ色のマント
第26章 マルガリータ
マルゴのスキャンダル
第27章 神の手
第28章 ローマからの書簡
第29章 出発
第30章 モールヴェル
第31章 猟犬狩猟
第32章 友情
第33章 シャルル九世の感謝
第34章 神は命ずる
第35章 王たちの夜
第36章 アナグラム
マリー・トゥシェのその後
第37章 ルーヴルへの帰還
第38章 カトリーヌ母后の飾り紐
第39章 復讐計画
アンジュー公、ポーランド王となる
第40章 呪われた一族
第41章 占い
第42章 失踪の真相
第43章 外交使節団
第44章 オレステスとピュラデス
第45章 オルトン
第46章 『星空亭』
第47章 ド・ムイ・ド・サン=ファール
第48章 ひとつの王冠に二つの頭
第49章 狩猟の本
第50章 鷹狩り
第51章 フランソワ一世の館
第52章 尋問
第53章 アクテオン
第54章 ヴァンセンヌの森
第55章 蝋人形
第56章 目に見えない盾
第57章 判事たち
第58章 足枷責め
第59章 礼拝堂
第60章 サン=ジャン=アン=グレーヴ広場
第61章 晒しの塔
第62章 血の汗
第63章 ヴァンセンヌの主塔の展望台
第64章 摂政
第65章 国王崩御、国王万歳!
第66章 エピローグ
マルゴとアンリ・ド・ナヴァールのその後
全訳ではなく、半分ほどの長さの抄訳なのだが、とばした部分はあらすじで埋めてある。デュマ、面白いな。あらすじをたどるだけの章でも、ワクワクする面白さがあじわえた。また、普通なら「註」として書かれているところが、まるでコラムのような体裁で、歴史的背景などが読めて、これだけでも面白い読物になっていた。雰囲気は、カーの『九つの答』。
長さが半分とは言え、もともとが大長編なので、よみごたえはたっぷり。
そして、圧倒的な物語の面白さに驚いた。
イエイツの『ヴァロワ・タピスリーの謎』を読んで興味がわいてきて、ヴァロワの真珠とうたわれたマルゴの物語を読もう、と思ったのだが、ほんと、読んでよかった。
母后のカトリーヌのこわいことこわいこと!
以下、目次
第1章 ギーズ公のラテン語
美女スパイの使命
第2章 ナヴァール王妃の部屋
聖バルテルミーの虐殺の原因
第3章 王様詩人
第4章 1572年8月24日の晩
ベッドはひとつ
第5章 ルーヴル、および美徳一般について
第6章 返されたギーズ公の借り
第7章 1572年8月24日の夜
第8章 虐殺された人々
第9章 虐殺者
第10章 死か、ミサか、それともバスチーユか
第11章 イノサン墓地のサンザシ
第12章 打ち明け話
ルーヴル宮殿の中は…
第13章 すべての部屋をあける鍵
第14章 第二の初夜
結婚の「成立」
第15章 女が望むことは神も望む
第16章 死んだ敵の死体はいつでもいい匂いがする
第17章 アンブロワーズ・パレの同業者
第18章 死んだはずの男たち
第19章 カトリーヌ母后御用達の調香師のルネの居室
第20章 黒い雌鶏
調香師と占い
第21章 ソーヴ夫人の居室
第22章 陛下、陛下は王になられます
第23章 新たな改宗者
アランソン公の結婚話
第24章 ティゾン街とクロシュ=ペルセ街
第25章 サクランボ色のマント
第26章 マルガリータ
マルゴのスキャンダル
第27章 神の手
第28章 ローマからの書簡
第29章 出発
第30章 モールヴェル
第31章 猟犬狩猟
第32章 友情
第33章 シャルル九世の感謝
第34章 神は命ずる
第35章 王たちの夜
第36章 アナグラム
マリー・トゥシェのその後
第37章 ルーヴルへの帰還
第38章 カトリーヌ母后の飾り紐
第39章 復讐計画
アンジュー公、ポーランド王となる
第40章 呪われた一族
第41章 占い
第42章 失踪の真相
第43章 外交使節団
第44章 オレステスとピュラデス
第45章 オルトン
第46章 『星空亭』
第47章 ド・ムイ・ド・サン=ファール
第48章 ひとつの王冠に二つの頭
第49章 狩猟の本
第50章 鷹狩り
第51章 フランソワ一世の館
第52章 尋問
第53章 アクテオン
第54章 ヴァンセンヌの森
第55章 蝋人形
第56章 目に見えない盾
第57章 判事たち
第58章 足枷責め
第59章 礼拝堂
第60章 サン=ジャン=アン=グレーヴ広場
第61章 晒しの塔
第62章 血の汗
第63章 ヴァンセンヌの主塔の展望台
第64章 摂政
第65章 国王崩御、国王万歳!
第66章 エピローグ
マルゴとアンリ・ド・ナヴァールのその後
山中散生の『ダダ論考』を読んだ。
以下、目次。
ダダの発生
トリスタン・ツァラのダダ宣言
ハンス・アルプの造型言語
チューリッヒ・ダダの展望
フランシス・ピカビアの機械様式
マルセル・デュシャンの“既製品”
マン・レイの超絵画性
ダダの政治参加
マックス・エルンストのコラージュ
クルト・シュヴィッタースのがらくた美学
アルチュール・クラヴァンとジャック・ヴァシュ
パリ・ダダの展望
アンドレ・ブルトンのダダ理念と態度
僕はやっぱり、ダダが好きだな!
ダダのライブでは、観客もヒートアップして、いろんなものが飛び交ったりするらしい。かつて、アーントサリーのライブではスコップが飛びかったそうだが、ダダのライブでも、卵などは当たり前、この『ダダ論考』ではビフテキまで飛び交ったそうだ。そんなライブ、パンクのライブでも見たことない。
ダダがどんな作品を発表してたかというと、
また、その集会がどんなものだったかと言うと、パレ・デ・フェートでの「文学の最初の金曜日」では、こんな調子。
こういうライブが、僕の理想かな。
以下、目次。
ダダの発生
トリスタン・ツァラのダダ宣言
ハンス・アルプの造型言語
チューリッヒ・ダダの展望
フランシス・ピカビアの機械様式
マルセル・デュシャンの“既製品”
マン・レイの超絵画性
ダダの政治参加
マックス・エルンストのコラージュ
クルト・シュヴィッタースのがらくた美学
アルチュール・クラヴァンとジャック・ヴァシュ
パリ・ダダの展望
アンドレ・ブルトンのダダ理念と態度
僕はやっぱり、ダダが好きだな!
ダダのライブでは、観客もヒートアップして、いろんなものが飛び交ったりするらしい。かつて、アーントサリーのライブではスコップが飛びかったそうだが、ダダのライブでも、卵などは当たり前、この『ダダ論考』ではビフテキまで飛び交ったそうだ。そんなライブ、パンクのライブでも見たことない。
ダダがどんな作品を発表してたかというと、
たとえば、インクのしみを白紙に散らしているだけのピカビアの絵画「聖母マリア」(『391』第12号)、アルファベット26文字を並列しただけのアラゴンの詩「自殺」(『カニバール」第1号)、電話帳から抜粋した名前で構成されているブルトンの詩(『カニバール』第2号)
また、その集会がどんなものだったかと言うと、パレ・デ・フェートでの「文学の最初の金曜日」では、こんな調子。
立体派詩人アンドレ・サルモンの開会宣言、ジャン・コクトーがマックス・ジャコブの詩を朗読、エリック・サティをとりまく若い音楽家ダリウス・ミヨー、ジョルジュ・オーリック、フランシス・プーランクらの作曲演奏、フェルナン・レジエ、ホアン・グリ、ジョルジオ・デ・キリコ、フランシス・ピカビアらの絵画の展示、トリスタン・ツァラは詩と称して新聞記事を読み始める。ベルとがらがらがその背音となって鳴りひびく。アンドレ・ブルトンがステージに黒板をはこんでくる。ピカビアが急いでそこに機械の一部分を描く。それを消してまた別のデッサンを描きはじめる。
こういうライブが、僕の理想かな。
『希望論―2010年代の文化と社会』
2013年1月22日 読書
宇野常寛と濱野智史の『希望論―2010年代の文化と社会』を読んだ。
1 「震災」から考える(“フクシマ”を受け止めるための想像力
復興への希望はどこにあるか)
2 「戦後以降」を考える(情報社会の現在地まで
日本的なものの再定義)
3 「希望」を考える(希望と社会・政治・運動
政治と文学の再設定)
1 「震災」から考える(“フクシマ”を受け止めるための想像力
復興への希望はどこにあるか)
2 「戦後以降」を考える(情報社会の現在地まで
日本的なものの再定義)
3 「希望」を考える(希望と社会・政治・運動
政治と文学の再設定)