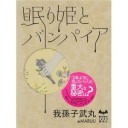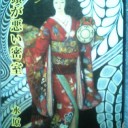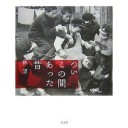『アジアのレコードデザイン集』
2013年9月26日 読書
常盤響と馬場正道の『アジアのレコードデザイン集』を読んだ。
タイポグラフィ
少色刷り
構図
女性
グループ
アジアの街はまるでレコードジャケットのようだった/常盤響
はじめての中国/馬場正道
中国式簡楽譜
タイのレーベル
DOMMUNEで出版記念のイベントやってるのを見て、いつものレコ部と、馬場さんのたたみかけるDJで、すっかり夢中になってしまい、この本読みながら、YOUTUBEなどでアジアの音楽を1日中聴いてた。
DARA PUSPITAとか、最高!
タイポグラフィ
少色刷り
構図
女性
グループ
アジアの街はまるでレコードジャケットのようだった/常盤響
はじめての中国/馬場正道
中国式簡楽譜
タイのレーベル
DOMMUNEで出版記念のイベントやってるのを見て、いつものレコ部と、馬場さんのたたみかけるDJで、すっかり夢中になってしまい、この本読みながら、YOUTUBEなどでアジアの音楽を1日中聴いてた。
DARA PUSPITAとか、最高!
『西田幾太郎 〈絶対無〉とは何か』
2013年9月24日 読書永井均の『西田幾太郎 〈絶対無〉とは何か』を読んだ。
以下、目次
はじめに
第一章 純粋経験-思う、ゆえに、思いあり
1.長いトンネルを抜けると-主客未分の経験
無私の視点/日本語的把握と英語的把握
2.知即行-真理と意志は合致する
意志はどう捉えられるか/知識・倫理・宗教-主客の合一としての
3.デカルトVS西田幾太郎
観念論的要素を取り去れば/「われ思う、ゆえに、われあり」の第一の二義性/「われ思う、ゆえに、われあり」の第二の二義性/西田はデカルトの何を拒否したのか
第二章 場所-〈絶対無〉はどこにあるのか
1.言語哲学者としての西田
確信犯ウィトゲンシュタインとの対決
2.自覚-「私を知る」とはどういうことか
「英国に居て完全なる英国の地図を」/私に於いて私を知る
3.場所としての私
「私」は主格ではありえない!/私は存在しないことによって存在する
4.場所的論理-西田論理学の展開
「がある」と「である」/真の個物とは何か-超越的主語面と超越的述語面/場所の自己限定のプロセス
5.絶対無
無の場所としての意識/自覚において有は無化され、言語において無は有化される
第三章 私と汝-私は頃荒れることによって生まれる
1.思想の体系化
2.田辺元の西田批判
種の論理と場所の論理/「西田先生の教を仰ぐ」/西田と田辺の対立の意味
3.存在する私への死
私と汝は絶対に他なるものである/汝は神のごとく私の底から動く/私は主格となり、一個の自我となる
以下、目次
はじめに
第一章 純粋経験-思う、ゆえに、思いあり
1.長いトンネルを抜けると-主客未分の経験
無私の視点/日本語的把握と英語的把握
2.知即行-真理と意志は合致する
意志はどう捉えられるか/知識・倫理・宗教-主客の合一としての
3.デカルトVS西田幾太郎
観念論的要素を取り去れば/「われ思う、ゆえに、われあり」の第一の二義性/「われ思う、ゆえに、われあり」の第二の二義性/西田はデカルトの何を拒否したのか
第二章 場所-〈絶対無〉はどこにあるのか
1.言語哲学者としての西田
確信犯ウィトゲンシュタインとの対決
2.自覚-「私を知る」とはどういうことか
「英国に居て完全なる英国の地図を」/私に於いて私を知る
3.場所としての私
「私」は主格ではありえない!/私は存在しないことによって存在する
4.場所的論理-西田論理学の展開
「がある」と「である」/真の個物とは何か-超越的主語面と超越的述語面/場所の自己限定のプロセス
5.絶対無
無の場所としての意識/自覚において有は無化され、言語において無は有化される
第三章 私と汝-私は頃荒れることによって生まれる
1.思想の体系化
2.田辺元の西田批判
種の論理と場所の論理/「西田先生の教を仰ぐ」/西田と田辺の対立の意味
3.存在する私への死
私と汝は絶対に他なるものである/汝は神のごとく私の底から動く/私は主格となり、一個の自我となる
『生命学をひらく 自分と向きあう「いのち」の思想』
2013年9月19日 読書
森岡正博の『生命学をひらく 自分と向きあう「いのち」の思想』を読んだ。
1.いのちのとらえ方
死を前にして起こること
こころの問題
誰も教えてはくれない
医療って何?
医療の外側の問い
2.「条件付きの愛」をどう考えるか
生きる意味がわからない
目隠し装置としての宗教と国家
「癒し」の意味
存在肯定への飢餓
「条件付きの愛」
「やさしさの愛」のからくり
システムとの共犯関係
生命を選別するアイデンティティの壁
自分の知らない深層アイデンティティ
3.共感的管理からの脱出
パターナリズムとは
母性による管理
家庭内暴力を起こすもの
調教された子どもの内面
大衆化された「アダルトチルドレン論」
援助と共感の落とし穴
ベトナム帰還兵の聖地
拒絶の記念碑
4.無痛化する社会のゆくえ
「無痛化」とは何か
よろこびの喪失
ICUで眠る人
無痛化を支えるテクノロジー
巨大な問題
5.無痛文明と「ひきこもり」
自分が崩れ落ちた後で
対人恐怖を克服する技
捨て身で腹を割る
処方箋はない
6.生命学はなぜ必要か
「他者」とは
「他者」の力
価値観の変容
知恵の次元
予防医学
パーソン論の考え方
7.「死者」のいのちとの対話
宗教と科学の間で
「脳死の人」
脳死論議の落とし穴
科学では片づけられない
二人称の死
脳死の人との対話
「死者」の持っているいのち
間身体性が支える
二つのリアリティ
日本の議論はなぜ最先端なのか
できなかった脳死判定
中絶をめぐって
胎児は人か
女に殺人をさせるもの
8.「無力化」と戦うために
通説の嘘
経済的理由と胎児条項
視線が人を殺す
「自己否定」の問題
「無力化」というキーワード
優生思想と優生学
1970年代の優生学
21世紀の新優生学
社会全体の無力化
何もしないことを選ぶ知恵
むすび・自分と向きあう「いのち」の思想
1.いのちのとらえ方
死を前にして起こること
こころの問題
誰も教えてはくれない
医療って何?
医療の外側の問い
2.「条件付きの愛」をどう考えるか
生きる意味がわからない
目隠し装置としての宗教と国家
「癒し」の意味
存在肯定への飢餓
「条件付きの愛」
「やさしさの愛」のからくり
システムとの共犯関係
生命を選別するアイデンティティの壁
自分の知らない深層アイデンティティ
3.共感的管理からの脱出
パターナリズムとは
母性による管理
家庭内暴力を起こすもの
調教された子どもの内面
大衆化された「アダルトチルドレン論」
援助と共感の落とし穴
ベトナム帰還兵の聖地
拒絶の記念碑
4.無痛化する社会のゆくえ
「無痛化」とは何か
よろこびの喪失
ICUで眠る人
無痛化を支えるテクノロジー
巨大な問題
5.無痛文明と「ひきこもり」
自分が崩れ落ちた後で
対人恐怖を克服する技
捨て身で腹を割る
処方箋はない
6.生命学はなぜ必要か
「他者」とは
「他者」の力
価値観の変容
知恵の次元
予防医学
パーソン論の考え方
7.「死者」のいのちとの対話
宗教と科学の間で
「脳死の人」
脳死論議の落とし穴
科学では片づけられない
二人称の死
脳死の人との対話
「死者」の持っているいのち
間身体性が支える
二つのリアリティ
日本の議論はなぜ最先端なのか
できなかった脳死判定
中絶をめぐって
胎児は人か
女に殺人をさせるもの
8.「無力化」と戦うために
通説の嘘
経済的理由と胎児条項
視線が人を殺す
「自己否定」の問題
「無力化」というキーワード
優生思想と優生学
1970年代の優生学
21世紀の新優生学
社会全体の無力化
何もしないことを選ぶ知恵
むすび・自分と向きあう「いのち」の思想
木田元の『最終講義』を読んだ。
1999年に中央大学と人文科学研究所で行われた最終講義。実際に話されたものではなく、用意されていた内容を書かれたもの。
以下、目次
最終講義『ハイデガーを読む』
はじめに
大学に入るまで
ドストエフスキーに魅入られて
ドストエフスキー論
ドストエフスキーとキルケゴール
『存在と時間』を読みたくて
大学に入ってから
哲学への深入り
『存在と時間』の読み方
未完の書としての『存在と時間』
『現象学の根本問題』
『存在と時間』と『根本問題』の関係
ナトルプ報告
メルロ=ポンティからの示唆
ハイデガーの性格の悪さ
ハイデガーが分かってきた
ニーチェの遺産
〈存在と時間〉
哲学批判としての哲学
哲学と文学-エルンスト・マッハをめぐって-
はじめに
マッハとフッサール
マッハとゲシュタルト理論
マッハとレーニン
マッハとその思想
力学主義的物理学
現象学的物理学
感性的要素一元論
全体論
現象学的物理学とエネルゲティーク
〈現象学〉の意味
マッハとアインシュタイン
進化論的認識論
マッハとニーチェ
思考経済説
マッハ主義
ウィーン学団
ウィトゲンシュタインの〈現象学〉
ホーフマンスタール
ムージル
マッハとヴァレリー
1999年に中央大学と人文科学研究所で行われた最終講義。実際に話されたものではなく、用意されていた内容を書かれたもの。
以下、目次
最終講義『ハイデガーを読む』
はじめに
大学に入るまで
ドストエフスキーに魅入られて
ドストエフスキー論
ドストエフスキーとキルケゴール
『存在と時間』を読みたくて
大学に入ってから
哲学への深入り
『存在と時間』の読み方
未完の書としての『存在と時間』
『現象学の根本問題』
『存在と時間』と『根本問題』の関係
ナトルプ報告
メルロ=ポンティからの示唆
ハイデガーの性格の悪さ
ハイデガーが分かってきた
ニーチェの遺産
〈存在と時間〉
哲学批判としての哲学
哲学と文学-エルンスト・マッハをめぐって-
はじめに
マッハとフッサール
マッハとゲシュタルト理論
マッハとレーニン
マッハとその思想
力学主義的物理学
現象学的物理学
感性的要素一元論
全体論
現象学的物理学とエネルゲティーク
〈現象学〉の意味
マッハとアインシュタイン
進化論的認識論
マッハとニーチェ
思考経済説
マッハ主義
ウィーン学団
ウィトゲンシュタインの〈現象学〉
ホーフマンスタール
ムージル
マッハとヴァレリー
ディドロ著作集第3巻『政治・経済』
2013年9月17日 読書ディドロ著作集第3巻『政治・経済』を読んだ。
『百科全書』より
政治的権威
自然法
権力
勢力〈国力〉
主権者
アルジャン〈銀・貨幣〉
農業
技芸
一般的定義
諸科学及び諸技芸の起源
技芸の思弁と実践
自由学芸と機械学的技芸への技芸の分割
技芸一般の目的
機械的技芸の一般的取り扱いに関する提案
この方法の利点
この種の取り扱いにおいて辿らねばならない順序
探求の別の動機
諸機械間の独特な差異
技芸の幾何学について
技芸の用語法について
或る製造業の他の製造業に対する優位について
君主の政治原理
出版業についての歴史的・政治的書簡
ガリアニ師讃
エルヴェシウス反駁
1.改良主義か革命か
2.社会問題
3.能力に応じて各人に与えよ
4.ユピテルとルイ15世
5.民主政治
エカテリーナ二世との対談
1.その起源より現下の消滅にまで至るフランスの政治秩序に関する歴史的試論
2.私こと、哲学者ドニの夢想
3.ロシアの国民性について
4.委員会と、それを常設することの利点について
5.奢侈について
6.国家の首都および真の本拠について。色彩を判断する盲人著す。
7.国王の道徳について
8.第三身分について
9.むすび
ディドロ「君主の政治原理」(1774年)より
専制に対する嫌悪と皮肉に満ちているが、ちょっとだけ引用。
「年金を設定しなければならぬ連中をうとんぜよ。これはつねに容易だ」
「隣人にたいしてなされる悪は、自分の臣民の幸福を願ってのことだと市民に納得させよ」
それと、ディドロ「ガリアニ師讃」(1770年)より。
ディドロって、インターネット討論に向いていそうだ。
『百科全書』より
政治的権威
自然法
権力
勢力〈国力〉
主権者
アルジャン〈銀・貨幣〉
農業
技芸
一般的定義
諸科学及び諸技芸の起源
技芸の思弁と実践
自由学芸と機械学的技芸への技芸の分割
技芸一般の目的
機械的技芸の一般的取り扱いに関する提案
この方法の利点
この種の取り扱いにおいて辿らねばならない順序
探求の別の動機
諸機械間の独特な差異
技芸の幾何学について
技芸の用語法について
或る製造業の他の製造業に対する優位について
君主の政治原理
出版業についての歴史的・政治的書簡
ガリアニ師讃
エルヴェシウス反駁
1.改良主義か革命か
2.社会問題
3.能力に応じて各人に与えよ
4.ユピテルとルイ15世
5.民主政治
エカテリーナ二世との対談
1.その起源より現下の消滅にまで至るフランスの政治秩序に関する歴史的試論
2.私こと、哲学者ドニの夢想
3.ロシアの国民性について
4.委員会と、それを常設することの利点について
5.奢侈について
6.国家の首都および真の本拠について。色彩を判断する盲人著す。
7.国王の道徳について
8.第三身分について
9.むすび
ディドロ「君主の政治原理」(1774年)より
専制に対する嫌悪と皮肉に満ちているが、ちょっとだけ引用。
「年金を設定しなければならぬ連中をうとんぜよ。これはつねに容易だ」
「隣人にたいしてなされる悪は、自分の臣民の幸福を願ってのことだと市民に納得させよ」
それと、ディドロ「ガリアニ師讃」(1770年)より。
彼は、自分の論敵が間違っていることを証明する、しかも百ヶ所にもわたってみごとに証明するが、しかし、彼の方が正しいかどうかは、誰にもわからないのだ。問題は今までよりも縺れたままである。
ディドロって、インターネット討論に向いていそうだ。
『運命論者ジャックとその主人』
2013年9月12日 読書
ドニ・ディドロの『運命論者ジャックとその主人』を読んだ。
脱線に告ぐ脱線で綴られた無駄話。
ジャックは運命論者で、すべての事柄は既に天上に書かれており、そのとおりにことは運ぶ、と信じている。そのジャックと、主人とが、旅の道すがら、ジャックの恋物語を聞く、というのが、一応の本筋。
そもそも旅の行き先や目的が、作者によって常にはぐらかされるし、運命論者であることが何か意味を持つのかどうかも、判然としない。
さて、ジャックの恋物語だが、途中で必ず邪魔が入って、スムーズに話が運ばない。
会話のある部分がひっかかって、そっちの話になってしまったり、別の誰かが語りはじめたまったく別の物語がえんえんと続いたり、のどの調子が悪くて続きが言えなくなったり、あげくの果てには作者までもが、まったく違うエピソードを語りはじめる。
そうやって、常に中断されるジャックの恋物語にしたところが、旅の道中の退屈しのぎのおしゃべりなのだから、そもそも続きを絶対に聞かねばならない緊急性を帯びていない。せっかくジャックが恋物語を語っていても、主人が途中で寝てしまい、話がストップしたりもするのだ。
この長編小説は1778年~1780年にヨーロッパ諸国の王侯貴族を中心に回覧された雑誌『文芸通信』で連載された作品。
メタフィクション、という言葉が帯には踊るが、僕が読んで感じた印象は、伝奇小説だった。サイドストーリーが本編と同等の重みをもっているところや、物語の起承転結よりも、物語られることの快感にどっぷり浸かってしまうところなど、伝奇そのものだ。
脱線に告ぐ脱線で綴られた無駄話。
ジャックは運命論者で、すべての事柄は既に天上に書かれており、そのとおりにことは運ぶ、と信じている。そのジャックと、主人とが、旅の道すがら、ジャックの恋物語を聞く、というのが、一応の本筋。
そもそも旅の行き先や目的が、作者によって常にはぐらかされるし、運命論者であることが何か意味を持つのかどうかも、判然としない。
さて、ジャックの恋物語だが、途中で必ず邪魔が入って、スムーズに話が運ばない。
会話のある部分がひっかかって、そっちの話になってしまったり、別の誰かが語りはじめたまったく別の物語がえんえんと続いたり、のどの調子が悪くて続きが言えなくなったり、あげくの果てには作者までもが、まったく違うエピソードを語りはじめる。
そうやって、常に中断されるジャックの恋物語にしたところが、旅の道中の退屈しのぎのおしゃべりなのだから、そもそも続きを絶対に聞かねばならない緊急性を帯びていない。せっかくジャックが恋物語を語っていても、主人が途中で寝てしまい、話がストップしたりもするのだ。
この長編小説は1778年~1780年にヨーロッパ諸国の王侯貴族を中心に回覧された雑誌『文芸通信』で連載された作品。
メタフィクション、という言葉が帯には踊るが、僕が読んで感じた印象は、伝奇小説だった。サイドストーリーが本編と同等の重みをもっているところや、物語の起承転結よりも、物語られることの快感にどっぷり浸かってしまうところなど、伝奇そのものだ。
『啓蒙思想の三態 ヴォルテール、ディドロ、ルソー』
2013年9月11日 読書
市川慎一の『啓蒙思想の三態 ヴォルテール、ディドロ、ルソー』を読んだ。
序文/鷲見洋一
1 ヴォルテールにおけるシナと日本の幻影
はじめに
I歴史家ヴォルテールの評価とヴォルテールの立場
IIヴォルテールに映じた<シナ>
IIIヴォルテールに映じた<日本>
IVヴォルテールの歴史作品に占める<シナ>と<日本>の意義
むすび
2 ディドロにおける政治思想の粗描―『百科全書』から「1772年の三部作」まで
はじめに
I『百科全書』の時代におけるディドロの政治思想
IIルソーが見たディドロの政治思想の問題点
1.ディドロが考えた「自然状態」から「社会状態」への推移
2.ディドロの考えた主権者の人格
3.アンシクロペディストたちが重視した<基本法>
III「1772年の三部作」におけるディドロの政治思想
むすび
3 ディドロとエカテリーナ二世―十八世紀フランスにおける一つのロシア体験
はじめに
Iディドロに映じたロシア
II噛み合わなかった女帝との対話
III専制君主批判の二つの場合
外側からの告発-ディドロの場合
内側からの告発-ラヂーシチェフの場合
むすび
4 ディドロとラヂーシチェフ―エカテリーナ二世をめぐって
5 ルソーと啓蒙思想
はじめに
啓蒙思想家としてのルソーの役割
アンシクロペディストとの対立
ルソーとフランス革命
むすび
6 ルソーにおける人間観と教育観―ディドロと比較して
Iルソーにおける啓蒙理念
IIルソーの教育論における仮説的思考
IIIルソーの方法論-ディドロと比較して
IV『エミール』におけるルソーの人間観と『ラモーの甥』等におけるディドロの人間観
7 ある亡命貴族の目に映じたフランス革命―セナック・ド・メイヤン『レミグレ』の場合
はじめに
Iセナックの目に映じた地方の現実とその改革
IIジャック・ネッケルへの弾劾
III<証言小説>としての『レミグレ』の位置づけ
小説『レミグレ』の梗概
フランス革命の原因分析
亡命貴族の生活と信条
名門貴族の名誉の問題
むすび
8 アレクサンダー・フォン・フンボルトとフランス啓蒙思想家
はじめに
フランス啓蒙思想家から学んだA.V.フンボルト
ヴォルテールとその歴史観
ジャン=ジャック・ルソーと<善良な未開人>神話
探検博物学の先駆者たち(ラ・コンダミーヌ、ビュフォン)と新大陸
ディドロとその自然観
むすび
9 書評・十八世紀を準備した思想家ピエール・ベールの人と思想
ユグノーの受難史の生き証人の観
実証的合理主義を神学の問題に持ち込む
並の翻訳でない野沢氏の個人訳
序文/鷲見洋一
1 ヴォルテールにおけるシナと日本の幻影
はじめに
I歴史家ヴォルテールの評価とヴォルテールの立場
IIヴォルテールに映じた<シナ>
IIIヴォルテールに映じた<日本>
IVヴォルテールの歴史作品に占める<シナ>と<日本>の意義
むすび
2 ディドロにおける政治思想の粗描―『百科全書』から「1772年の三部作」まで
はじめに
I『百科全書』の時代におけるディドロの政治思想
IIルソーが見たディドロの政治思想の問題点
1.ディドロが考えた「自然状態」から「社会状態」への推移
2.ディドロの考えた主権者の人格
3.アンシクロペディストたちが重視した<基本法>
III「1772年の三部作」におけるディドロの政治思想
むすび
3 ディドロとエカテリーナ二世―十八世紀フランスにおける一つのロシア体験
はじめに
Iディドロに映じたロシア
II噛み合わなかった女帝との対話
III専制君主批判の二つの場合
外側からの告発-ディドロの場合
内側からの告発-ラヂーシチェフの場合
むすび
4 ディドロとラヂーシチェフ―エカテリーナ二世をめぐって
5 ルソーと啓蒙思想
はじめに
啓蒙思想家としてのルソーの役割
アンシクロペディストとの対立
ルソーとフランス革命
むすび
6 ルソーにおける人間観と教育観―ディドロと比較して
Iルソーにおける啓蒙理念
IIルソーの教育論における仮説的思考
IIIルソーの方法論-ディドロと比較して
IV『エミール』におけるルソーの人間観と『ラモーの甥』等におけるディドロの人間観
7 ある亡命貴族の目に映じたフランス革命―セナック・ド・メイヤン『レミグレ』の場合
はじめに
Iセナックの目に映じた地方の現実とその改革
IIジャック・ネッケルへの弾劾
III<証言小説>としての『レミグレ』の位置づけ
小説『レミグレ』の梗概
フランス革命の原因分析
亡命貴族の生活と信条
名門貴族の名誉の問題
むすび
8 アレクサンダー・フォン・フンボルトとフランス啓蒙思想家
はじめに
フランス啓蒙思想家から学んだA.V.フンボルト
ヴォルテールとその歴史観
ジャン=ジャック・ルソーと<善良な未開人>神話
探検博物学の先駆者たち(ラ・コンダミーヌ、ビュフォン)と新大陸
ディドロとその自然観
むすび
9 書評・十八世紀を準備した思想家ピエール・ベールの人と思想
ユグノーの受難史の生き証人の観
実証的合理主義を神学の問題に持ち込む
並の翻訳でない野沢氏の個人訳
『ディドロの現代性』
2013年9月10日 読書中川久定の『ディドロの現代性』を読んだ。
I ディドロの18世紀的新しさ―広がりと深さ
1.ディドロ没後200年
祝うことの意味
ディドロの知の広がり
2.『ダランベールの夢』(1)
私の読み違い
クレメール演出の芝居
3.『ダランベールの夢』(2)
日本語とフランス語
翻訳の歪みの原因
4.『ダランベールの夢』(3)
蜜蜂の群れの話・蜘蛛の巣の話
ディドロの知の深み
II 生きているディドロ
1.抑圧されたものの復権(1)
ディドロの精神
秩序を課すること
秩序の転倒
2.抑圧されたものの復権(2)
タヒチ
日本
女性・私生児・子ども・動物
3.抑圧されたものの復権(3)
非理性(狂気)
身体障害者・夢
〈絶対的転倒〉
4.ディドロとはなに者なのか
ディドロの共感
イエス・キリストの影
解説 若き日の思いは一生を貫き、生き方を決定するか/牧野剛
最後の「解説」は、中川久定氏の紹介文。
うちに新しいエアコンが到着。
今年はもう使わないけど。
I ディドロの18世紀的新しさ―広がりと深さ
1.ディドロ没後200年
祝うことの意味
ディドロの知の広がり
2.『ダランベールの夢』(1)
私の読み違い
クレメール演出の芝居
3.『ダランベールの夢』(2)
日本語とフランス語
翻訳の歪みの原因
4.『ダランベールの夢』(3)
蜜蜂の群れの話・蜘蛛の巣の話
ディドロの知の深み
II 生きているディドロ
1.抑圧されたものの復権(1)
ディドロの精神
秩序を課すること
秩序の転倒
2.抑圧されたものの復権(2)
タヒチ
日本
女性・私生児・子ども・動物
3.抑圧されたものの復権(3)
非理性(狂気)
身体障害者・夢
〈絶対的転倒〉
4.ディドロとはなに者なのか
ディドロの共感
イエス・キリストの影
解説 若き日の思いは一生を貫き、生き方を決定するか/牧野剛
最後の「解説」は、中川久定氏の紹介文。
うちに新しいエアコンが到着。
今年はもう使わないけど。
『僕はずっと裸だった』
2013年9月9日 読書
田中泯の『僕はずっと裸だった』を読んだ。
前衛舞踏家ではあるが、役者としても、また言葉の使い手としても、独自のワールドを持っている。
すごくいい年齢の重ね方をしているな、と思った。
001 無意識の踊り
002 私のこども
003 感覚の海の中へ
004 失速・微速・変速
005 何もかもが動いている
006 からだの中のこころ
007 恥にも深さが
008 裸と性の距離
009 裸体という衣裳
010 ヒトが立ったのだ
011 もっとカラダに成る
012 目の中に屍体がある
013 父は警官が嫌いだった
014 判断できない深み
015 隠れん坊は生死の学習
016 目をつむり、立つ
017 私の外国はパリから始まった
018 二十年のギザギザ
019 裸体から雨カッパに着換える
020 青春を完結しない意志
021 感情のエコロジー
022 踊りが感情?
023 からだを動かすと何が見える
024 私とからだ、私のからだ
II………………………………………………………………………………
025 土方巽の弟子になる!
026 ブトーナンセンス
027 一人の時の真実
028 自分が大事だからか
029 「自分」と「私」のあいだで
030 心の片隅・心の隙間に何がある
031 思い出の南方熊楠先生
032 ヒトノフリミテワガフリナオセ
033 心の片隅にしまった一言
034 親しみの奥の方で
035 泥臭い、ダサイ、悪いか!
036 ちょっとの間、自分を留守にする
037 何の値打ちもないのがおどりです
038 「死」も存在の作法だ、と教わった
039 日干しの鯨じゃ様にならん
040 野の花に声をかけたい
041 再び、踊りなんて金になりません
042 地球に境界線は引けるか
043 「野良」、自意識と精神との谷間
044 お百姓さんありがとうです。
045 命と同じ重さの知識や知恵
046 いのちが型を揺り動かす。
III………………………………………………………………………………
047 我々に風景は踊れるか
048 動き続けるから風景なのだ
049 作る・工作することのルーツ
050 根が生えてこそ物になる
051 デレク・ベイリーが聞こえる。
052 時間や場は、自分でつくる?
053 便利はそれほど尊いのか!糞
054 からだの中で育つ大人のために
055 精霊の群れる白州の夏
056 天然・自然が舞台の「春の祭典」
057 古代からの無垢、自然と人間
058 家に棲む自然
059 血は太陽とともにあり
060 雲は空に浮かぶ水の停留所
061 人もまた、移動し留まり、変容する
062 伝統文化は自然の同伴者
063 「自分さがし」とは何のこと!
064 「からだ」よ、脳に服従するなかれ。
065 「生命のダンス」が白州で始まった
066 からだの本当が流行に塗り潰される。
067 白州から敷島へ、桃花村始まる。
068 斜面こそが稽古場・静かな躍動と持続
069 日本中で里山が山里になった。
070 息する者、生きる物、ヒト、人間そして何。
071 恐れや畏れが無くて何の心意気。
072 村に居て異人の来訪を待つ。
IV………………………………………………………………………………
073 「正面」という衣裳について
074 「正面」の面(おめん、つら、おもて、むき)
075 背に腹はかえられぬ。む!
076 私はかろうじて立っている哺乳動物。
077 言葉に因らない純粋な感覚そしてイメージ。
078 オシッコの周辺そして人間社会
079 生理現象も社会現象?
080 師匠・土方巽の放尿と自然
081 自分で見えない背後のある正面、という正義
082 「座る」だけでも大事件。
083 始まりで最大で最終の環境、からだ。
084 足の骨の数の多さよ。
085 進化の原動力になれなかったヒトもいる。
086 篩にかけられた生命や物達
087 かろうじて立っていることの充足感
088 僕は今でも赤い子供だ。
089 カラダとの時間を生きること。
090 脳の拡大と回転舞踊
091 岡田正人のエゾエノキ
092 野良に出かけてオドリのレッスン
093 土方巽の「性根」をのぞいてみると。
094 道具の変遷と輪廻観
095 時は移り、映り、空ろう。
096 すべて記憶にございます。
097 シロウトには文章もカラダの延長
V………………………………………………………………………………
098 写真と岡田と僕のあひだ。
099 リズムの源は地球の回転
100 他人のカラダの中で眼をさます。
101 生きていることへの好奇心こそが
102 シャッター音が聞こえる草叢で
103 緑が空に伸び大地を這う
104 カラダという闇について
105 オドリは道標、古代への生業
106 一瞬の豊かさに誘われて
107 カラダの中でしか生きられない私。
108 顔の奥の方にその人は走り去る。
109 見えるからって何なのさ!
110 誰からも奪われることのないカラダ。
111 見えない物事の話は続く。
112 ちょっと、オドリにさわってみよう。
113 カラダはコトバか?
114 見えているよりもっと見る。
115 時の水平に佇むことの喜び。
116 僕はカラダと生きるカラダモンだ。
117 あられもなくあるとどうだろうか。
118 地図を眺めると喜怒哀楽
119 今回で最終回ではあるのだが、ハテ
対談:杉浦康平+田中 泯
うしろの正面、だれ
「名づけられない踊り」でありつづけたい
「覚醒の彼方の覚醒」を指向する
いま一度、誕生の元気を意識に
森のイマジネーション、夜と闇の力
なぜダンスなのかを探りつつ踊る
前衛舞踏家ではあるが、役者としても、また言葉の使い手としても、独自のワールドを持っている。
すごくいい年齢の重ね方をしているな、と思った。
001 無意識の踊り
002 私のこども
003 感覚の海の中へ
004 失速・微速・変速
005 何もかもが動いている
006 からだの中のこころ
007 恥にも深さが
008 裸と性の距離
009 裸体という衣裳
010 ヒトが立ったのだ
011 もっとカラダに成る
012 目の中に屍体がある
013 父は警官が嫌いだった
014 判断できない深み
015 隠れん坊は生死の学習
016 目をつむり、立つ
017 私の外国はパリから始まった
018 二十年のギザギザ
019 裸体から雨カッパに着換える
020 青春を完結しない意志
021 感情のエコロジー
022 踊りが感情?
023 からだを動かすと何が見える
024 私とからだ、私のからだ
II………………………………………………………………………………
025 土方巽の弟子になる!
026 ブトーナンセンス
027 一人の時の真実
028 自分が大事だからか
029 「自分」と「私」のあいだで
030 心の片隅・心の隙間に何がある
031 思い出の南方熊楠先生
032 ヒトノフリミテワガフリナオセ
033 心の片隅にしまった一言
034 親しみの奥の方で
035 泥臭い、ダサイ、悪いか!
036 ちょっとの間、自分を留守にする
037 何の値打ちもないのがおどりです
038 「死」も存在の作法だ、と教わった
039 日干しの鯨じゃ様にならん
040 野の花に声をかけたい
041 再び、踊りなんて金になりません
042 地球に境界線は引けるか
043 「野良」、自意識と精神との谷間
044 お百姓さんありがとうです。
045 命と同じ重さの知識や知恵
046 いのちが型を揺り動かす。
III………………………………………………………………………………
047 我々に風景は踊れるか
048 動き続けるから風景なのだ
049 作る・工作することのルーツ
050 根が生えてこそ物になる
051 デレク・ベイリーが聞こえる。
052 時間や場は、自分でつくる?
053 便利はそれほど尊いのか!糞
054 からだの中で育つ大人のために
055 精霊の群れる白州の夏
056 天然・自然が舞台の「春の祭典」
057 古代からの無垢、自然と人間
058 家に棲む自然
059 血は太陽とともにあり
060 雲は空に浮かぶ水の停留所
061 人もまた、移動し留まり、変容する
062 伝統文化は自然の同伴者
063 「自分さがし」とは何のこと!
064 「からだ」よ、脳に服従するなかれ。
065 「生命のダンス」が白州で始まった
066 からだの本当が流行に塗り潰される。
067 白州から敷島へ、桃花村始まる。
068 斜面こそが稽古場・静かな躍動と持続
069 日本中で里山が山里になった。
070 息する者、生きる物、ヒト、人間そして何。
071 恐れや畏れが無くて何の心意気。
072 村に居て異人の来訪を待つ。
IV………………………………………………………………………………
073 「正面」という衣裳について
074 「正面」の面(おめん、つら、おもて、むき)
075 背に腹はかえられぬ。む!
076 私はかろうじて立っている哺乳動物。
077 言葉に因らない純粋な感覚そしてイメージ。
078 オシッコの周辺そして人間社会
079 生理現象も社会現象?
080 師匠・土方巽の放尿と自然
081 自分で見えない背後のある正面、という正義
082 「座る」だけでも大事件。
083 始まりで最大で最終の環境、からだ。
084 足の骨の数の多さよ。
085 進化の原動力になれなかったヒトもいる。
086 篩にかけられた生命や物達
087 かろうじて立っていることの充足感
088 僕は今でも赤い子供だ。
089 カラダとの時間を生きること。
090 脳の拡大と回転舞踊
091 岡田正人のエゾエノキ
092 野良に出かけてオドリのレッスン
093 土方巽の「性根」をのぞいてみると。
094 道具の変遷と輪廻観
095 時は移り、映り、空ろう。
096 すべて記憶にございます。
097 シロウトには文章もカラダの延長
V………………………………………………………………………………
098 写真と岡田と僕のあひだ。
099 リズムの源は地球の回転
100 他人のカラダの中で眼をさます。
101 生きていることへの好奇心こそが
102 シャッター音が聞こえる草叢で
103 緑が空に伸び大地を這う
104 カラダという闇について
105 オドリは道標、古代への生業
106 一瞬の豊かさに誘われて
107 カラダの中でしか生きられない私。
108 顔の奥の方にその人は走り去る。
109 見えるからって何なのさ!
110 誰からも奪われることのないカラダ。
111 見えない物事の話は続く。
112 ちょっと、オドリにさわってみよう。
113 カラダはコトバか?
114 見えているよりもっと見る。
115 時の水平に佇むことの喜び。
116 僕はカラダと生きるカラダモンだ。
117 あられもなくあるとどうだろうか。
118 地図を眺めると喜怒哀楽
119 今回で最終回ではあるのだが、ハテ
対談:杉浦康平+田中 泯
うしろの正面、だれ
「名づけられない踊り」でありつづけたい
「覚醒の彼方の覚醒」を指向する
いま一度、誕生の元気を意識に
森のイマジネーション、夜と闇の力
なぜダンスなのかを探りつつ踊る
『大野一雄 百年の舞踏』
2013年9月5日 読書
大野一雄舞踏研究所編による『大野一雄 百年の舞踏』を読んだ。
写真、年譜、書簡、詩文、公演批評から、大野一雄の百年を描き出す。
舞踏批評家コレット・ゴダールが言うように、「踊ることは生きること」(「未生の胎児」)なのである。
以下、目次
序文 大野一雄 百年の舞踏によせて
第1章 胎児の夢―1906‐1948
第2章 鬼哭―1949‐1976
第3章 天と地の結婚―1977‐1995
第4章 日常の糧―1996‐2006
ECCE HOMO-大野一雄氏に/矢川澄子
大野一雄翁狼頌二十句/永田耕衣
大野一雄頌/郡司正勝
未生の胎児 大野一雄、ミュンヘンからアビニョンへ/コレット・ゴダール
死の脈略/コレット・ゴダール
愛のレクイエム/ピエール・ビネ
死と誕生/渡辺保
ウインナ・ワルツ/渡辺保
大野一雄の清澄さ/渡辺保
闇の中から:舞踏 西洋のダンス界に知られ始めた、日本の現代舞踊 大野一雄/リチャード・フィリップ
舞踏家大野一雄の世界/市川雅
写真、年譜、書簡、詩文、公演批評から、大野一雄の百年を描き出す。
舞踏批評家コレット・ゴダールが言うように、「踊ることは生きること」(「未生の胎児」)なのである。
以下、目次
序文 大野一雄 百年の舞踏によせて
第1章 胎児の夢―1906‐1948
第2章 鬼哭―1949‐1976
第3章 天と地の結婚―1977‐1995
第4章 日常の糧―1996‐2006
ECCE HOMO-大野一雄氏に/矢川澄子
大野一雄翁狼頌二十句/永田耕衣
大野一雄頌/郡司正勝
未生の胎児 大野一雄、ミュンヘンからアビニョンへ/コレット・ゴダール
死の脈略/コレット・ゴダール
愛のレクイエム/ピエール・ビネ
死と誕生/渡辺保
ウインナ・ワルツ/渡辺保
大野一雄の清澄さ/渡辺保
闇の中から:舞踏 西洋のダンス界に知られ始めた、日本の現代舞踊 大野一雄/リチャード・フィリップ
舞踏家大野一雄の世界/市川雅
『サン=ジェルマン大通り125番地で』
2013年9月3日 読書
バンジャマン・ペレの『サン=ジェルマン大通り125番地で』を読んだ。
バンジャマン・ペレは、シュルレアリスム運動で、アンドレ・ブルトンと共に歩んだ詩人で、多くの芸術家たちが運動から早々に離脱するなか、ずっとシュルレアリスムから離れなかった。と、いえば律儀で真剣な感じがするけど、本書での解説でも示唆してあったが、この人、すごく、「どうでもいい」感じを大切にして、貫きとおした人なのだ。自分の作品もまったく評価せず、ゴミ扱いし、とくに理由もなく聖職者を罵り、作品からも、いったい何が言いたいのか、何をやりたいのかが読み取れず、うっかり解釈でもしようものなら裏切られてしまう風情なのである。なにをしでかすかわからないので、トラブルメーカーになってしまうこともしばしば。
僕は、このバンジャマン・ペレの作品を、ワルドベルグの『シュルレアリスム』という概説書で学生時代に読んで、感銘を受けた。多くの芸術家の作品も掲載されていたが、このバンジャマン・ペレは、とにかくむちゃくちゃなのだ。コロコロコミックのナンセンス漫画などに通じるところがあるのかもしれない。読んでもちっとも「芸術」に触れたという感触が得られない。これは素晴らしい。
本書では、詩ではなく、厖大な数のコント(短い話)から、いくつかを選んで翻訳してある。そして、なんと、海外では全集が出ているほどの芸術家でありながら、日本では、バンジャマン・ペレの本としては、これが最初になるのだ。
バンジャマン・ペレの作品を全部翻訳してくれたら、大偉業であろうが、そんな言葉が似合わない、ナンセンスな徒労、愚行の塊になるだろう。ぜひとも全作翻訳を!
以下、目次。
興味あふれる人1ドルの不幸
ピュルシェリは車がほしい
死刑囚最後の夜
むかしむかしあるところにひとりのブーランジェールがいました…
旅館「空飛ぶお尻」亭
取っ組み合って
第九番の病
死者か生者か
幽霊たちの楽園にて
訳者解説 私は名づける、動機なしに
-バンジャマン・ペレの文学的ならざる軌跡
1.ペレは何をしたか
初期詩篇?
意味づけしない書き手
左翼反対派の闘士へ
恣意的な言葉たち
ブラジル/パリ/カタールニャ
二度目の戦争、二度目の戦後
「子供っぽい」のではなく「子供」
2.ペレのコントには何ができるか
アンチ=クラテュロスの言語
どうすれば命名行為に失敗できるか
書き手の身振りとしての言葉
バンジャマン・ペレは、シュルレアリスム運動で、アンドレ・ブルトンと共に歩んだ詩人で、多くの芸術家たちが運動から早々に離脱するなか、ずっとシュルレアリスムから離れなかった。と、いえば律儀で真剣な感じがするけど、本書での解説でも示唆してあったが、この人、すごく、「どうでもいい」感じを大切にして、貫きとおした人なのだ。自分の作品もまったく評価せず、ゴミ扱いし、とくに理由もなく聖職者を罵り、作品からも、いったい何が言いたいのか、何をやりたいのかが読み取れず、うっかり解釈でもしようものなら裏切られてしまう風情なのである。なにをしでかすかわからないので、トラブルメーカーになってしまうこともしばしば。
僕は、このバンジャマン・ペレの作品を、ワルドベルグの『シュルレアリスム』という概説書で学生時代に読んで、感銘を受けた。多くの芸術家の作品も掲載されていたが、このバンジャマン・ペレは、とにかくむちゃくちゃなのだ。コロコロコミックのナンセンス漫画などに通じるところがあるのかもしれない。読んでもちっとも「芸術」に触れたという感触が得られない。これは素晴らしい。
本書では、詩ではなく、厖大な数のコント(短い話)から、いくつかを選んで翻訳してある。そして、なんと、海外では全集が出ているほどの芸術家でありながら、日本では、バンジャマン・ペレの本としては、これが最初になるのだ。
バンジャマン・ペレの作品を全部翻訳してくれたら、大偉業であろうが、そんな言葉が似合わない、ナンセンスな徒労、愚行の塊になるだろう。ぜひとも全作翻訳を!
以下、目次。
興味あふれる人1ドルの不幸
ピュルシェリは車がほしい
死刑囚最後の夜
むかしむかしあるところにひとりのブーランジェールがいました…
旅館「空飛ぶお尻」亭
取っ組み合って
第九番の病
死者か生者か
幽霊たちの楽園にて
訳者解説 私は名づける、動機なしに
-バンジャマン・ペレの文学的ならざる軌跡
1.ペレは何をしたか
初期詩篇?
意味づけしない書き手
左翼反対派の闘士へ
恣意的な言葉たち
ブラジル/パリ/カタールニャ
二度目の戦争、二度目の戦後
「子供っぽい」のではなく「子供」
2.ペレのコントには何ができるか
アンチ=クラテュロスの言語
どうすれば命名行為に失敗できるか
書き手の身振りとしての言葉
『南方熊楠英文論考 [ネイチャー]誌篇』
2013年8月29日 読書
『南方熊楠英文論考 [ネイチャー]誌篇』を読んだ。
若き日に大英博物館で学問三昧だった熊楠が、『ネイチャー』誌に初投稿した「東洋の星座」(1893年)から、1900年帰国までに旺盛に執筆、掲載された論文に加え、書簡や下書きが翻訳されており、『ネイチャー』誌掲載分としては最後になった1914年「古代の開頭手術」、活動の場を『ノーツ・アンド・クエリーズ』に移してからの1920年「スコロペンドラ・ケタケア3」までが掲載されている。
以下、目次。
第1章 東洋の星座
星をグループ化して星座とすること(M.A.B)
東洋の星座
(民族によって固有の星座をもつことと、その類似から民族間の近親性をみることは可能か、との問いに、熊楠は中国と古代インドの星座を紹介し、似ている部分を指摘しながらも、それぞれ独自に偶然に星座を作り出したものとしている)
第2章 東洋の科学史に関する小論
動物の保護色に関する中国人の先駆的観察
コムソウダケに関する最古の記述
蛙の知能
宵の明星と暁の明星
網の発明
アミミドロに関する最古の記述
コノハムシに関する中国人の先駆的記述
(西洋での最新の知見が、既に古代中国で記述されていたことを『酉陽雑俎』『論衡』『淵鑑類函』『和漢三才図会』などから指摘)
第3章 虻と蜂に関するフォークロア
古代人のブーゴニア俗信についての質問(C・R・オステン=サッケン)
蜂に関する東洋の俗信
『牛から生まれた蜂の古説(ブーゴニア)とハナアブの関係』(C・R・オステン=サッケン)
琥珀の起源についての中国人の見解
『古代人のブーゴニア伝説の解説への対補』Ⅵ中国と日本の文献に登場するハナアブ(C・R・オステン=サッケン)
ブーゴニア俗信に関する注記-インドにおけるハナアブの存在
(ウェルギリウスなどによって描かれた、牛の死骸からミツバチが発生するという説話がアジアにも存在するか、というオステン=サッケンの問いに対して、熊楠が類似のものならあるが、牛から蜂が発生する例はない、とこたえる。また、この説話を蜂とアブを間違えたことによるものとするオステン=サッケン説について、熊楠は日本、中国、インド、ペルシア、エチオピアの文献、記述をもってこたえている)
第4章 中国古代文明に関する小論
北方に関する中国人の俗信について
洞窟に関する中国人の俗信
幽霊に関する論理的矛盾
(社会学に進化論を適用したハーバート・スペンサーの説を引用した論文。スペンサーが『社会学原理』で「幽霊が服を着ているのはおかしい」と書いていたことに対して、中国の王充が千数百年前に同様のことを書いていると指摘していたりする)
第5章 拇印考
「指紋」法の古さについて①
「指紋」法
「指紋」法の古さについて②
(西洋では指紋が個人鑑別の手段として確立するのは20世紀に入ってからだが、東洋では古くから用いられていたことを述べたもの)
第6章 マンドレイク
マンドレイク①
マンドレイク②
マンドレイク③
(マンドレイク=Mandrakeは、「まんだらけ」ではなく、マンドラゴラのこと。マンドラゴラと同じ性質を持つ植物が、17世紀中国の『五雑組』に「商陸」の名前で記述されていることを指摘、さらに、中東にも同様の伝説があることを書いている)
第7章 さまよえるユダヤ人
さまよえるユダヤ人①
さまよえるユダヤ人②
さまよえるユダヤ人③
さまよえるユダヤ人④
(ユダヤ人靴屋のアハスエルスが、ゴルゴダに向かうイエス・キリストを冷たく追い払ったため、永遠に地上をさまようことになった、という物語について、インドの賓頭盧=びんずる説話との関連を指摘。びんずるは、神力を使って山を持ち上げて通ったことを咎められ、罰として永久にこの世にとどまることになった)
第8章 驚くべき音響・死者の婚礼
驚くべき音響①
驚くべき音響②
驚くべき音響③
驚くべき音響④
死者の婚礼
(マルコ・ポーロの『東方見聞録』を引用した論文)
第9章 ロスマ論争
シュレーゲルから南方熊楠宛書簡(4通)
セイウチ
(17世紀中国の『正字通』中にある「落斯馬」という海の生物の正体について、オランダの東洋学者グスタフ・シュレーゲルが「イッカク」だと解釈したのに対して、熊楠は「セイウチだ!」と反論)
第10章 ムカデクジラ
ムカデクジラ①
ムカデクジラ(W・F・シンクレア)
ムカデクジラ②
スコロペンドラ・ケタケア①
スコロペンドラ・ケタケア(ジェイムズ・リッチー)
スコロペンドラ・ケタケア(C・C・B)
スコロペンドラ・ケタケア(ジェイムズ・リッチー)
スコロペンドラ・ケタケア②
スコロペンドラ・ケタケア(コンスタンス・ラッセル)
スコロペンドラ・ケタケア③
(古代ギリシアのアイリアノスと貝原益軒が書いた、海を泳ぐ巨大ムカデの正体について。ゴカイ類の一種と特定。なお、「ムカデクジラ」のタイトルは『ネイチャー』誌掲載分、「スコロペンドラ・ケタケア」は『ノーツ・アンド・クエリーズ』誌掲載)
第11章 日本の発見
日本におけるタブー体系 概要
日本におけるタブー体系
日本の発見
(日本と西洋の交流について書かれたもので、マルコ・ポーロ以前に日本がアジア、アラブとの交流があったことを指摘し、西洋による日本の発見、という視点に対峙した)
第12章 日本の記録にみえる食人の形跡
日本の記録にみえる食人の形跡
(E・S・モースが「緊急の状況に追い込まれて人肉で命をつないだという記録は日本にあるか」と問い掛け、熊楠は『エンサイクロペディア・ブリタニカ』の「カニバリズム」の項から、習慣、飢饉、怒り、屍愛、呪術及び医薬、宗教の面からそれぞれこたえる)
第13章 隠花植物研究
ピトフォラ・オエドゴニア
ピトフォラの分布(G・S・ウェスト)
ピトフォラの分布
ホオベニタケの分布
ホオベニタケの分布(ジョージ・マッシー)
魚類に生える藻類
魚類に生える藻類(ジョージ・マッシー)
粘菌の変形体の色①
粘菌の変形体の色②
(日本帰国後、熊楠が採集、標本にした菌類などを送付、報告。また、帰国したために「顕微鏡の性能不足と参考図書の不足のために、それが実際なんの種なのかを確かめられないでいる」とか書いている)
第14章 雑纂1―俗信・伝統医術
貝合戦による占いについて①
貝合戦による占いについて②
虫に刺されることによる後天的免疫
頭蓋の人為的な変形、および一夫多妻制に関する習俗のいくつか
魔よけの籠
石、真珠、骨が増えるとされること
古代の開頭手術
(貝合戦は、タニシの動きで戦の命運を占う風習について。石、真珠、骨が増える話は、仏舎利がひとりでに数を増していた記述についての解釈を述べている)
第15章 雑纂2―自然科学など
エン麦の黒穂菌を画家の顔料として使うこと
水平器の発明
中国のペスト
ライオンの天敵
トウモロコシ
インディアン・コーン①
インディアン・コーン②
中国の蟹災害
タコの酢とクラゲのアラック
「オロコマ」という奇妙な哺乳類
花粉を運ぶコウモリと鳥
(ライオンの天敵が何なのかというと、なんと、ヤマアラシ!蟹災害は、田んぼを荒らす大量のカニのこと。現代の中国でもこういう災害はあるのか、と熊楠は問うている。水につけると、その水が酢になってしまう、というタコ、その水が酒になるというクラゲについて、事実なのか空想なのか、問う熊楠。また、「オロコマ」あるいは「オコロム」という獣は、大型犬ほどの大きさで、きつね色の毛、とがった鼻、大きく鋭い歯を持ち、獲物をしとめると、木の葉や枝を覆いかぶせて、いったんその場を離れる。しばらくしてから虎をともなって戻ってくるらしい。襲われたインディオは、木の葉を覆われた後、戻ってくる前に逃げ出すのだが、獲物がなくなった、と知ったオロコマは、恐ろしいうなり声をあげてから、悲しげに困ったような顔を虎に向けるそうだ。こんな獣が本当にいるのかどうか、熊楠は問うている)
若き日に大英博物館で学問三昧だった熊楠が、『ネイチャー』誌に初投稿した「東洋の星座」(1893年)から、1900年帰国までに旺盛に執筆、掲載された論文に加え、書簡や下書きが翻訳されており、『ネイチャー』誌掲載分としては最後になった1914年「古代の開頭手術」、活動の場を『ノーツ・アンド・クエリーズ』に移してからの1920年「スコロペンドラ・ケタケア3」までが掲載されている。
以下、目次。
第1章 東洋の星座
星をグループ化して星座とすること(M.A.B)
東洋の星座
(民族によって固有の星座をもつことと、その類似から民族間の近親性をみることは可能か、との問いに、熊楠は中国と古代インドの星座を紹介し、似ている部分を指摘しながらも、それぞれ独自に偶然に星座を作り出したものとしている)
第2章 東洋の科学史に関する小論
動物の保護色に関する中国人の先駆的観察
コムソウダケに関する最古の記述
蛙の知能
宵の明星と暁の明星
網の発明
アミミドロに関する最古の記述
コノハムシに関する中国人の先駆的記述
(西洋での最新の知見が、既に古代中国で記述されていたことを『酉陽雑俎』『論衡』『淵鑑類函』『和漢三才図会』などから指摘)
第3章 虻と蜂に関するフォークロア
古代人のブーゴニア俗信についての質問(C・R・オステン=サッケン)
蜂に関する東洋の俗信
『牛から生まれた蜂の古説(ブーゴニア)とハナアブの関係』(C・R・オステン=サッケン)
琥珀の起源についての中国人の見解
『古代人のブーゴニア伝説の解説への対補』Ⅵ中国と日本の文献に登場するハナアブ(C・R・オステン=サッケン)
ブーゴニア俗信に関する注記-インドにおけるハナアブの存在
(ウェルギリウスなどによって描かれた、牛の死骸からミツバチが発生するという説話がアジアにも存在するか、というオステン=サッケンの問いに対して、熊楠が類似のものならあるが、牛から蜂が発生する例はない、とこたえる。また、この説話を蜂とアブを間違えたことによるものとするオステン=サッケン説について、熊楠は日本、中国、インド、ペルシア、エチオピアの文献、記述をもってこたえている)
第4章 中国古代文明に関する小論
北方に関する中国人の俗信について
洞窟に関する中国人の俗信
幽霊に関する論理的矛盾
(社会学に進化論を適用したハーバート・スペンサーの説を引用した論文。スペンサーが『社会学原理』で「幽霊が服を着ているのはおかしい」と書いていたことに対して、中国の王充が千数百年前に同様のことを書いていると指摘していたりする)
第5章 拇印考
「指紋」法の古さについて①
「指紋」法
「指紋」法の古さについて②
(西洋では指紋が個人鑑別の手段として確立するのは20世紀に入ってからだが、東洋では古くから用いられていたことを述べたもの)
第6章 マンドレイク
マンドレイク①
マンドレイク②
マンドレイク③
(マンドレイク=Mandrakeは、「まんだらけ」ではなく、マンドラゴラのこと。マンドラゴラと同じ性質を持つ植物が、17世紀中国の『五雑組』に「商陸」の名前で記述されていることを指摘、さらに、中東にも同様の伝説があることを書いている)
第7章 さまよえるユダヤ人
さまよえるユダヤ人①
さまよえるユダヤ人②
さまよえるユダヤ人③
さまよえるユダヤ人④
(ユダヤ人靴屋のアハスエルスが、ゴルゴダに向かうイエス・キリストを冷たく追い払ったため、永遠に地上をさまようことになった、という物語について、インドの賓頭盧=びんずる説話との関連を指摘。びんずるは、神力を使って山を持ち上げて通ったことを咎められ、罰として永久にこの世にとどまることになった)
第8章 驚くべき音響・死者の婚礼
驚くべき音響①
驚くべき音響②
驚くべき音響③
驚くべき音響④
死者の婚礼
(マルコ・ポーロの『東方見聞録』を引用した論文)
第9章 ロスマ論争
シュレーゲルから南方熊楠宛書簡(4通)
セイウチ
(17世紀中国の『正字通』中にある「落斯馬」という海の生物の正体について、オランダの東洋学者グスタフ・シュレーゲルが「イッカク」だと解釈したのに対して、熊楠は「セイウチだ!」と反論)
第10章 ムカデクジラ
ムカデクジラ①
ムカデクジラ(W・F・シンクレア)
ムカデクジラ②
スコロペンドラ・ケタケア①
スコロペンドラ・ケタケア(ジェイムズ・リッチー)
スコロペンドラ・ケタケア(C・C・B)
スコロペンドラ・ケタケア(ジェイムズ・リッチー)
スコロペンドラ・ケタケア②
スコロペンドラ・ケタケア(コンスタンス・ラッセル)
スコロペンドラ・ケタケア③
(古代ギリシアのアイリアノスと貝原益軒が書いた、海を泳ぐ巨大ムカデの正体について。ゴカイ類の一種と特定。なお、「ムカデクジラ」のタイトルは『ネイチャー』誌掲載分、「スコロペンドラ・ケタケア」は『ノーツ・アンド・クエリーズ』誌掲載)
第11章 日本の発見
日本におけるタブー体系 概要
日本におけるタブー体系
日本の発見
(日本と西洋の交流について書かれたもので、マルコ・ポーロ以前に日本がアジア、アラブとの交流があったことを指摘し、西洋による日本の発見、という視点に対峙した)
第12章 日本の記録にみえる食人の形跡
日本の記録にみえる食人の形跡
(E・S・モースが「緊急の状況に追い込まれて人肉で命をつないだという記録は日本にあるか」と問い掛け、熊楠は『エンサイクロペディア・ブリタニカ』の「カニバリズム」の項から、習慣、飢饉、怒り、屍愛、呪術及び医薬、宗教の面からそれぞれこたえる)
第13章 隠花植物研究
ピトフォラ・オエドゴニア
ピトフォラの分布(G・S・ウェスト)
ピトフォラの分布
ホオベニタケの分布
ホオベニタケの分布(ジョージ・マッシー)
魚類に生える藻類
魚類に生える藻類(ジョージ・マッシー)
粘菌の変形体の色①
粘菌の変形体の色②
(日本帰国後、熊楠が採集、標本にした菌類などを送付、報告。また、帰国したために「顕微鏡の性能不足と参考図書の不足のために、それが実際なんの種なのかを確かめられないでいる」とか書いている)
第14章 雑纂1―俗信・伝統医術
貝合戦による占いについて①
貝合戦による占いについて②
虫に刺されることによる後天的免疫
頭蓋の人為的な変形、および一夫多妻制に関する習俗のいくつか
魔よけの籠
石、真珠、骨が増えるとされること
古代の開頭手術
(貝合戦は、タニシの動きで戦の命運を占う風習について。石、真珠、骨が増える話は、仏舎利がひとりでに数を増していた記述についての解釈を述べている)
第15章 雑纂2―自然科学など
エン麦の黒穂菌を画家の顔料として使うこと
水平器の発明
中国のペスト
ライオンの天敵
トウモロコシ
インディアン・コーン①
インディアン・コーン②
中国の蟹災害
タコの酢とクラゲのアラック
「オロコマ」という奇妙な哺乳類
花粉を運ぶコウモリと鳥
(ライオンの天敵が何なのかというと、なんと、ヤマアラシ!蟹災害は、田んぼを荒らす大量のカニのこと。現代の中国でもこういう災害はあるのか、と熊楠は問うている。水につけると、その水が酢になってしまう、というタコ、その水が酒になるというクラゲについて、事実なのか空想なのか、問う熊楠。また、「オロコマ」あるいは「オコロム」という獣は、大型犬ほどの大きさで、きつね色の毛、とがった鼻、大きく鋭い歯を持ち、獲物をしとめると、木の葉や枝を覆いかぶせて、いったんその場を離れる。しばらくしてから虎をともなって戻ってくるらしい。襲われたインディオは、木の葉を覆われた後、戻ってくる前に逃げ出すのだが、獲物がなくなった、と知ったオロコマは、恐ろしいうなり声をあげてから、悲しげに困ったような顔を虎に向けるそうだ。こんな獣が本当にいるのかどうか、熊楠は問うている)
『薔薇十字社とその軌跡』
2013年8月28日 読書
論創社の「出版人に聞く」シリーズ第10弾、『薔薇十字社とその軌跡』を読んだ。
薔薇十字社を設立した内藤三津子に小田光雄がインタビューしている。
内藤三津子は、新書館の「フォア・レディース」担当から、天声出版の『血と薔薇』を企画、編集に携わり、薔薇十字社設立、倒産後は出帆社を経て、現在は編集プロダクションNアトリエ主宰。
自分の読書遍歴に欠かせない出版社の名前が飛び出してきて、興味はつきない。
以下、目次。
第1部
1 前口上
2 戦後文芸誌『世代』のこと
3 玄光社と堀内誠一
4 姉と中山書店
5 七曜社でのアルバイト
6 新書館入社
7 「フォア・レディース」のこと
8 新書館をやめる
9 「フォア・レディース」の波紋
第2部
10 『話の特集』に入る
11 『若い生活』の編集
12 『話の特集』のスポンサーと矢崎泰久
13 天声出版へ
14 矢牧一宏の軌跡
15 神彰のこと
16 『血と薔薇』の企画
17 三島由紀夫の参加
18 『血と薔薇』創刊
19 『血と薔薇』四号問題
第3部
20 薔薇十字社設立とその周辺
21 『血と薔薇』が雑誌に与えた影響
22 取次の条件
23 薔薇十字社のスタート
24 松山俊太郎の存在
25 島崎博と『定本三島由紀夫書誌』
26 未刊に終わった写真集『男の死』
27 『幻影城』、三崎書房、絃映社
28 澁澤龍彦『黄金時代』
29 塚本邦雄『悦楽園園丁辞典』
第4部
30 都市出版社との関係
31 詩を中心とする文学・芸術季刊誌『都市』
32 『家畜人ヤプー』事件とベストセラー化
33 『家畜人ヤプー』の作者
34 三島由紀夫と『家畜人ヤプー』
35 沼正三と天野哲夫
36 森下小太郎と倉田卓次
37 『諸君!』の森下文
38 倉田の著作のこと
39 薔薇十字社の倒産
40 トリプル倒産と高利貸し
41 小出版社の相次ぐ倒産
第5部
42 最後の本のことなど
43 森茉莉とのトラブル
44 出帆社と路書房
45 出帆社のスタッフ
46 出帆社の始まりと刊行書目
47 出なかった『泉鏡花全戯曲集』
48 路書房の摘発
49 出帆社の終わりと白夜書房
50 出帆新社について
51 編集プロダクション「Nアトリエ」
52 いいだ・ももと「思想の海へ」
53 いいだ・ももと出版
54 近畿大学の仕事
55 松山俊太郎のこと
56 松山と蔵書
57 『インドを語る』と『綺想礼讃』
58 それでもすてきな出版人生
薔薇十字社全刊行書一覧(2008年4月)/古書りぶる・りべろ
本書には、山ほど面白いエピソードが語られているのだが、そのなかから、とくに興味をひいたところをあげておこう。
フォア・レディースの成功について、内藤三津子の感性の起源について聞かれたときの答え。
「私は昔の少女小説を最後に読んだ世代だと思うんですよ。子どもの頃に貸本屋で吉屋信子などの小説を読んだという。『ひまわり』『少女の友』の世代ですしね。ところが1960年代にはそういった少女小説も貸本屋もなくなりつつあった。それでも女の子たちの気持ちの中にはやっぱり少女小説が読みたいという願望が確固として根づいていたのでしょうね。もちろんそれは旧来の少女小説とはちがうもので、それが寺山修司や立原えりかの物語としてうまく女の子たちに浸透していったんじゃないでしょうか」
松山俊太郎が渡辺温『アンドロギュノスの裔』、『大坪砂男全集』の企画を出したこと。
その松山俊太郎の家は足の踏み場もない状態になっていて、飲み付き合いが半端じゃないことなど。
森茉莉が『ドッキリチャンネル』で『マドモワゼル・ルウルウ』の印税を踏み倒されたと書いているが、それは何者かに吹き込まれた誤解だということ。
『家畜人ヤプー』の作家、沼正三の正体について。「続・家畜人ヤプー」や太田出版刊以降のリライト版はともかく、もともとの都市出版社版の『家畜人ヤプー』は倉田卓次判事が書いたものだということ。
出帆社と出帆新社とは人脈的にもまったくの別ものであること。
などなど。詳しくは本書にあたっていただくにかぎる。
薔薇十字社を設立した内藤三津子に小田光雄がインタビューしている。
内藤三津子は、新書館の「フォア・レディース」担当から、天声出版の『血と薔薇』を企画、編集に携わり、薔薇十字社設立、倒産後は出帆社を経て、現在は編集プロダクションNアトリエ主宰。
自分の読書遍歴に欠かせない出版社の名前が飛び出してきて、興味はつきない。
以下、目次。
第1部
1 前口上
2 戦後文芸誌『世代』のこと
3 玄光社と堀内誠一
4 姉と中山書店
5 七曜社でのアルバイト
6 新書館入社
7 「フォア・レディース」のこと
8 新書館をやめる
9 「フォア・レディース」の波紋
第2部
10 『話の特集』に入る
11 『若い生活』の編集
12 『話の特集』のスポンサーと矢崎泰久
13 天声出版へ
14 矢牧一宏の軌跡
15 神彰のこと
16 『血と薔薇』の企画
17 三島由紀夫の参加
18 『血と薔薇』創刊
19 『血と薔薇』四号問題
第3部
20 薔薇十字社設立とその周辺
21 『血と薔薇』が雑誌に与えた影響
22 取次の条件
23 薔薇十字社のスタート
24 松山俊太郎の存在
25 島崎博と『定本三島由紀夫書誌』
26 未刊に終わった写真集『男の死』
27 『幻影城』、三崎書房、絃映社
28 澁澤龍彦『黄金時代』
29 塚本邦雄『悦楽園園丁辞典』
第4部
30 都市出版社との関係
31 詩を中心とする文学・芸術季刊誌『都市』
32 『家畜人ヤプー』事件とベストセラー化
33 『家畜人ヤプー』の作者
34 三島由紀夫と『家畜人ヤプー』
35 沼正三と天野哲夫
36 森下小太郎と倉田卓次
37 『諸君!』の森下文
38 倉田の著作のこと
39 薔薇十字社の倒産
40 トリプル倒産と高利貸し
41 小出版社の相次ぐ倒産
第5部
42 最後の本のことなど
43 森茉莉とのトラブル
44 出帆社と路書房
45 出帆社のスタッフ
46 出帆社の始まりと刊行書目
47 出なかった『泉鏡花全戯曲集』
48 路書房の摘発
49 出帆社の終わりと白夜書房
50 出帆新社について
51 編集プロダクション「Nアトリエ」
52 いいだ・ももと「思想の海へ」
53 いいだ・ももと出版
54 近畿大学の仕事
55 松山俊太郎のこと
56 松山と蔵書
57 『インドを語る』と『綺想礼讃』
58 それでもすてきな出版人生
薔薇十字社全刊行書一覧(2008年4月)/古書りぶる・りべろ
本書には、山ほど面白いエピソードが語られているのだが、そのなかから、とくに興味をひいたところをあげておこう。
フォア・レディースの成功について、内藤三津子の感性の起源について聞かれたときの答え。
「私は昔の少女小説を最後に読んだ世代だと思うんですよ。子どもの頃に貸本屋で吉屋信子などの小説を読んだという。『ひまわり』『少女の友』の世代ですしね。ところが1960年代にはそういった少女小説も貸本屋もなくなりつつあった。それでも女の子たちの気持ちの中にはやっぱり少女小説が読みたいという願望が確固として根づいていたのでしょうね。もちろんそれは旧来の少女小説とはちがうもので、それが寺山修司や立原えりかの物語としてうまく女の子たちに浸透していったんじゃないでしょうか」
松山俊太郎が渡辺温『アンドロギュノスの裔』、『大坪砂男全集』の企画を出したこと。
その松山俊太郎の家は足の踏み場もない状態になっていて、飲み付き合いが半端じゃないことなど。
森茉莉が『ドッキリチャンネル』で『マドモワゼル・ルウルウ』の印税を踏み倒されたと書いているが、それは何者かに吹き込まれた誤解だということ。
『家畜人ヤプー』の作家、沼正三の正体について。「続・家畜人ヤプー」や太田出版刊以降のリライト版はともかく、もともとの都市出版社版の『家畜人ヤプー』は倉田卓次判事が書いたものだということ。
出帆社と出帆新社とは人脈的にもまったくの別ものであること。
などなど。詳しくは本書にあたっていただくにかぎる。
マリオ・ヂ・アンドラーヂの『マクナイーマ』を読んだ。
以下、目次
マクナイーマ
大きくなってから
森の母神さま・シー
お月さまになった蛇女
巨人のピアイマン
おフランス娘と巨人
マクンバ
太陽の女神・ヴェイ
アマゾンの女たちへの手紙
ピアウイー・ポードリ
セイウシーばあさん
行商人・大きな香雨鳥・人間たちの不正
ジゲーの妻、シラミだらけの女
お守りのムイラキタン
オイベーの臓物
ウラリコエーラ川
大熊座
終章
この本については、「サロン・ジ・アートルーム」というユーストリーム番組で、本の紹介をもたもたとやらせてもらった。そっちで雰囲気つかんでください。
映画「マクナイーマ」の感想のときに書いた、エイモス・チュツオーラとエレンディラ的な世界であるのは、原作においてもかわらず。本を読んで感じたのは、さらに、ラブレーの味も加わったかな、というくらいかな。
ひとつだけ、印象的なシーンを。
女装して逃げるマクナイーマが、蟻塚に追い込まれてしまい、巨人に「さあ、出て来い!」と迫られる。マクナイーマは「まず、コルセット」と穴の外にコルセット置いて、巨人が「コルセットなんかいらん!」とつかんで遠くに投げ捨てる。その後も少しずつ衣服を外に出しては巨人に投げ捨てさせるのを続けたあと、自分のしりの穴を外に出して、「次は、くさいくさいヒョウタンを出します」と言い、巨人に「くさいヒョウタンなんかいらん!」と投げ捨てさせ、しりの穴もろとも自分自身が遠くに投げ出されてまんまと脱出に成功するシーン。これぞ名シーン。
マクナイーマの口癖は「あぁ、めんどくさ!」と「健康(サウーヂ)はわずか、サウーヴァ蟻はたくさん、それがブラジルの害悪だ」
マクナイーマはブラジル人の象徴だとされるが、ブラジル人って、こんなにいいかげんで、本能のままに生きるんだろうか?
以下、目次
マクナイーマ
大きくなってから
森の母神さま・シー
お月さまになった蛇女
巨人のピアイマン
おフランス娘と巨人
マクンバ
太陽の女神・ヴェイ
アマゾンの女たちへの手紙
ピアウイー・ポードリ
セイウシーばあさん
行商人・大きな香雨鳥・人間たちの不正
ジゲーの妻、シラミだらけの女
お守りのムイラキタン
オイベーの臓物
ウラリコエーラ川
大熊座
終章
この本については、「サロン・ジ・アートルーム」というユーストリーム番組で、本の紹介をもたもたとやらせてもらった。そっちで雰囲気つかんでください。
映画「マクナイーマ」の感想のときに書いた、エイモス・チュツオーラとエレンディラ的な世界であるのは、原作においてもかわらず。本を読んで感じたのは、さらに、ラブレーの味も加わったかな、というくらいかな。
ひとつだけ、印象的なシーンを。
女装して逃げるマクナイーマが、蟻塚に追い込まれてしまい、巨人に「さあ、出て来い!」と迫られる。マクナイーマは「まず、コルセット」と穴の外にコルセット置いて、巨人が「コルセットなんかいらん!」とつかんで遠くに投げ捨てる。その後も少しずつ衣服を外に出しては巨人に投げ捨てさせるのを続けたあと、自分のしりの穴を外に出して、「次は、くさいくさいヒョウタンを出します」と言い、巨人に「くさいヒョウタンなんかいらん!」と投げ捨てさせ、しりの穴もろとも自分自身が遠くに投げ出されてまんまと脱出に成功するシーン。これぞ名シーン。
マクナイーマの口癖は「あぁ、めんどくさ!」と「健康(サウーヂ)はわずか、サウーヴァ蟻はたくさん、それがブラジルの害悪だ」
マクナイーマはブラジル人の象徴だとされるが、ブラジル人って、こんなにいいかげんで、本能のままに生きるんだろうか?
『ニグロとして生きる』
2013年8月22日 読書
エメ・セゼールとの対話『ニグロとして生きる』を読んだ。
聞き手はポスト・コロニアル研究者のフランソワーズ・ヴェルジェス。
2004年から行われたインタビューのまとめと、対談後のヴェルジュスによる小論、そして1956年第1回黒人作家・芸術家国際会議でのエメ・セゼールの講演が収録されている。
以下、目次。
はじめに
エメ・セゼールは語る
対談を終えて―エメ・セゼール小論
セゼールのポストコロニアル的読解のために
セゼールと奴隷制
セゼールと植民地主義
セゼールの現在性
文化と植民地支配
文化と文明の関係
黒人文化の諸条件
植民地支配の功罪
文化借用の問題
自生的文明と現代世界
解説 しかし神話は殺せるだろうか―ネグリチュードをめぐる蜂起と寛容(真島一郎)
ヴェルジェスの小論の前半は、なにかと批判の多いポストコロニアル理論の有効性を検討しているが、彼女が言う「ポストコロニアル的アプローチは、善の誘惑から逃れることを可能にしてくれる」という視点には、可能性を感じた。
聞き手はポスト・コロニアル研究者のフランソワーズ・ヴェルジェス。
2004年から行われたインタビューのまとめと、対談後のヴェルジュスによる小論、そして1956年第1回黒人作家・芸術家国際会議でのエメ・セゼールの講演が収録されている。
以下、目次。
はじめに
エメ・セゼールは語る
対談を終えて―エメ・セゼール小論
セゼールのポストコロニアル的読解のために
セゼールと奴隷制
セゼールと植民地主義
セゼールの現在性
文化と植民地支配
文化と文明の関係
黒人文化の諸条件
植民地支配の功罪
文化借用の問題
自生的文明と現代世界
解説 しかし神話は殺せるだろうか―ネグリチュードをめぐる蜂起と寛容(真島一郎)
ヴェルジェスの小論の前半は、なにかと批判の多いポストコロニアル理論の有効性を検討しているが、彼女が言う「ポストコロニアル的アプローチは、善の誘惑から逃れることを可能にしてくれる」という視点には、可能性を感じた。
『帰郷ノート/植民地主義論』
2013年8月21日 読書
エメ・セゼールの『帰郷ノート/植民地主義論』を読んだ。
エメ・セゼールはマルティニーク生まれ、パリで学び、1930年代、フランス植民地主義の同化政策を批判し、ネグリチュードの思想を生み出した詩人、戯曲作家、政治家。
以下、目次。
序 偉大なる黒人詩人(アンドレ・ブルトン)
帰郷ノート
植民地主義論
エメ・セゼール小論(砂野幸稔)
甦るセゼール
マルティニック
奴隷制植民地社会
ハイチ革命とトゥサン・ルヴェルチュール
奴隷解放令と同化政策
「開化民」の旅
生い立ち
黒人学生
黒人意識
植民地帝国フランス
「ニグロ問題は当世の流行」
黒人意識-アメリカ黒人文学のインパクト
黒人意識-『正当防衛』
黒人意識-「源泉への回帰」
ネグリチュード-『黒人学生』
『帰郷ノート』
「帰郷」-『熱帯』
政治家セゼール
「同化」法案
『植民地主義論』
共産党離党-『モーリス・トレーズへの手紙』
「ウイ」-フランス共同体国民投票
「自治」から「モラトリアム」へ
「パパ・セゼール」
クレオール性とセゼール
『植民地主義論』の冒頭で、エメ・セゼールはこう書いている。
「自らの活動が生み出した諸問題を解決しえないことが明らかになった文明は衰退しつつある文明である」
このとき、エメ・セゼールはプロレタリアートと植民地問題について言っているのだが、今読むと別の文脈で読めてしまう。
エメ・セゼールはマルティニーク生まれ、パリで学び、1930年代、フランス植民地主義の同化政策を批判し、ネグリチュードの思想を生み出した詩人、戯曲作家、政治家。
以下、目次。
序 偉大なる黒人詩人(アンドレ・ブルトン)
帰郷ノート
植民地主義論
エメ・セゼール小論(砂野幸稔)
甦るセゼール
マルティニック
奴隷制植民地社会
ハイチ革命とトゥサン・ルヴェルチュール
奴隷解放令と同化政策
「開化民」の旅
生い立ち
黒人学生
黒人意識
植民地帝国フランス
「ニグロ問題は当世の流行」
黒人意識-アメリカ黒人文学のインパクト
黒人意識-『正当防衛』
黒人意識-「源泉への回帰」
ネグリチュード-『黒人学生』
『帰郷ノート』
「帰郷」-『熱帯』
政治家セゼール
「同化」法案
『植民地主義論』
共産党離党-『モーリス・トレーズへの手紙』
「ウイ」-フランス共同体国民投票
「自治」から「モラトリアム」へ
「パパ・セゼール」
クレオール性とセゼール
『植民地主義論』の冒頭で、エメ・セゼールはこう書いている。
「自らの活動が生み出した諸問題を解決しえないことが明らかになった文明は衰退しつつある文明である」
このとき、エメ・セゼールはプロレタリアートと植民地問題について言っているのだが、今読むと別の文脈で読めてしまう。
『眠り姫とバンパイア』
2013年8月15日 読書
我孫子武丸の『眠り姫とバンパイア』を読んだ。
少女の優希の章と、家庭教師の男性・歩実の章が交互に語られる。
母親に隠れてこっそりと父親に会っている優希。
優希は、父親がバンパイアになったと思い込んでいる。
歩実は、母親が離婚した夫を娘にあわせていないのだ、と思い、友人でもある前任の家庭教師に聞いてみると、意外な事実がわかった。
優希の父親は3年前に事故で死んでいる、というのだ。
ふむ。
これは面白かった。
娘は、父親がバンパイアにちがいない、と信じる理由がちゃんとあるし、また、それを望んでいたりもする。
この本は講談社のミステリーランドの1冊で、小中学生のういういしい読者が、この本によって、新本格のお得意のわざをはじめて喰らうのか、と思うと、ゾクゾクする。
少女の優希の章と、家庭教師の男性・歩実の章が交互に語られる。
母親に隠れてこっそりと父親に会っている優希。
優希は、父親がバンパイアになったと思い込んでいる。
歩実は、母親が離婚した夫を娘にあわせていないのだ、と思い、友人でもある前任の家庭教師に聞いてみると、意外な事実がわかった。
優希の父親は3年前に事故で死んでいる、というのだ。
ふむ。
これは面白かった。
娘は、父親がバンパイアにちがいない、と信じる理由がちゃんとあるし、また、それを望んでいたりもする。
この本は講談社のミステリーランドの1冊で、小中学生のういういしい読者が、この本によって、新本格のお得意のわざをはじめて喰らうのか、と思うと、ゾクゾクする。
水原章の『頭が悪い密室』を読んだ。
水原章は関西学院大学卒の日本推理作家協会会員。
本書には、1953年の『別冊宝石』に収録された「日の果て」から、1970年の『雪』に掲載された「血の掟」までの作品が集められている。
以下、目次。
第一部
白い檻
世界をおれのポケットに
人間消失
血の掟
死者からのラブレター
蛸人
第二部
けものが眠るとき
あたしは夜が怖い
死を賭けろ
頭が悪い密室
仮面をかぶって殺せ
謎を解いてちょうだい
断崖
キッスで火を点けろ
第三部
色彩学教程
解剖学教程
生物学教程
確率論教程
物理学教程
第四部
日の果て
殺意
第四部はそれぞれ『別冊宝石』、『密室』(1960年)に掲載されたもので、ページ数も多く、小説として厚みがあるが、それ以外の作品は、「デイリースポーツ」や「新大阪新聞」に掲載されたもので、短いページ数で話が進む、推理クイズみたいな味わいを感じさせるものが多い。
それが、いい!
この本は思わぬ収穫だった。
本書を読んでいて、連想したのは、推理もの(ハードボイルド)貸本マンガだった。中学のときなど、『影』や『トップ屋ジョー』シリーズ、『台風五郎』や『ゴリラ』シリーズなど、読み漁ったものだが、そのときの興奮がよみがえった。時代もほぼ同じ頃なのではなかろうか。
母校の先輩だと知っていたら、大学で推理小説同好会をしきっていたときに、お招きして、いろいろお話など聞けたのに、と思った。
タイトルになった「頭が悪い密室」は今風の題名だが、本書の真骨頂は、「キッスで火を点けろ」みたいな、貸本漫画テイストのものだと思う。
面白かった!
水原章は関西学院大学卒の日本推理作家協会会員。
本書には、1953年の『別冊宝石』に収録された「日の果て」から、1970年の『雪』に掲載された「血の掟」までの作品が集められている。
以下、目次。
第一部
白い檻
世界をおれのポケットに
人間消失
血の掟
死者からのラブレター
蛸人
第二部
けものが眠るとき
あたしは夜が怖い
死を賭けろ
頭が悪い密室
仮面をかぶって殺せ
謎を解いてちょうだい
断崖
キッスで火を点けろ
第三部
色彩学教程
解剖学教程
生物学教程
確率論教程
物理学教程
第四部
日の果て
殺意
第四部はそれぞれ『別冊宝石』、『密室』(1960年)に掲載されたもので、ページ数も多く、小説として厚みがあるが、それ以外の作品は、「デイリースポーツ」や「新大阪新聞」に掲載されたもので、短いページ数で話が進む、推理クイズみたいな味わいを感じさせるものが多い。
それが、いい!
この本は思わぬ収穫だった。
本書を読んでいて、連想したのは、推理もの(ハードボイルド)貸本マンガだった。中学のときなど、『影』や『トップ屋ジョー』シリーズ、『台風五郎』や『ゴリラ』シリーズなど、読み漁ったものだが、そのときの興奮がよみがえった。時代もほぼ同じ頃なのではなかろうか。
母校の先輩だと知っていたら、大学で推理小説同好会をしきっていたときに、お招きして、いろいろお話など聞けたのに、と思った。
タイトルになった「頭が悪い密室」は今風の題名だが、本書の真骨頂は、「キッスで火を点けろ」みたいな、貸本漫画テイストのものだと思う。
面白かった!
『ヴァン・ショーをあなたに』
2013年8月13日 読書
近藤史恵の『ヴァン・ショーをあなたに』を読んだ。
タルト・タタンの夢のシリーズ。
以下、目次
錆びないスキレット
憂さばらしのピストゥ
ブーランジェリーのメロンパン
マドモワゼル・ブイヤベースにご用心
氷姫
天空の泉
ヴァン・ショーをあなたに
読みやすくて面白い。
ささやかな謎なので、かぎりなく普通小説に近いかな。
以下、ネタばれ
猫を逃がした子どもと、錆びなくなったスキレット
にわかベジタリアンに腹いせ
新規開店のパン屋がメロンパンを置きたくない理由
レシピの秘密と嫉妬心
氷の味で、元カレの出所を知る
星の王子様のメッセージ
アルコールを受け付けない体質を知らないフランス人
タルト・タタンの夢のシリーズ。
以下、目次
錆びないスキレット
憂さばらしのピストゥ
ブーランジェリーのメロンパン
マドモワゼル・ブイヤベースにご用心
氷姫
天空の泉
ヴァン・ショーをあなたに
読みやすくて面白い。
ささやかな謎なので、かぎりなく普通小説に近いかな。
以下、ネタばれ
猫を逃がした子どもと、錆びなくなったスキレット
にわかベジタリアンに腹いせ
新規開店のパン屋がメロンパンを置きたくない理由
レシピの秘密と嫉妬心
氷の味で、元カレの出所を知る
星の王子様のメッセージ
アルコールを受け付けない体質を知らないフランス人
『ついこの間あった昔』
2013年8月12日 読書
林望の『ついこの間あった昔』を読んだ。
『写真でみる日本生活図引』のなかから写真をピックアップして、林望が解説、随想を加えた1冊。
自分の子どもの頃の写真見ても、大昔の時代のことのように思えてしまう。
ちょっと前のことでもすぐに「古い!」と言ってしまうのは、ほんと、つまらないなあ。
本書は、大昔のことのように見える光景でも、実はほんの少し前まではこうだった、という、錯覚を正してくれる恰好の材料になろう。
以下、目次。
ついこの間あった昔-序にかえて-
ばあさんたちの文化
ピクニックの約束事
リトル・マザーズ
悪ガキの心底
チャンバラの剣士たち
荒っぽく、しかし仲良く
罠を仕掛ける
行水、束の間涼し
牡丹餅、おはぎ、女の手
子供部屋という発想
衝撃的写真
首都高速と真っ赤なN360
渋谷が田舎だったころ
馬糞の時代
黒煙上がれば国威も揚がる
テレビ様降臨の日
夏休みと洗濯機
乙女たちの晴れ姿
肥溜めの香り
聖なる汚穢
羞恥のありどころ
混浴という美風
滅びゆく技術
手仕事の風景
郵便屋さん
オバサンの籠の中には
葬式の原則
おそるべき風景
鉾をおさめて 伊根浦の捕鯨
隠居の夢
『写真でみる日本生活図引』のなかから写真をピックアップして、林望が解説、随想を加えた1冊。
自分の子どもの頃の写真見ても、大昔の時代のことのように思えてしまう。
ちょっと前のことでもすぐに「古い!」と言ってしまうのは、ほんと、つまらないなあ。
本書は、大昔のことのように見える光景でも、実はほんの少し前まではこうだった、という、錯覚を正してくれる恰好の材料になろう。
以下、目次。
ついこの間あった昔-序にかえて-
ばあさんたちの文化
ピクニックの約束事
リトル・マザーズ
悪ガキの心底
チャンバラの剣士たち
荒っぽく、しかし仲良く
罠を仕掛ける
行水、束の間涼し
牡丹餅、おはぎ、女の手
子供部屋という発想
衝撃的写真
首都高速と真っ赤なN360
渋谷が田舎だったころ
馬糞の時代
黒煙上がれば国威も揚がる
テレビ様降臨の日
夏休みと洗濯機
乙女たちの晴れ姿
肥溜めの香り
聖なる汚穢
羞恥のありどころ
混浴という美風
滅びゆく技術
手仕事の風景
郵便屋さん
オバサンの籠の中には
葬式の原則
おそるべき風景
鉾をおさめて 伊根浦の捕鯨
隠居の夢
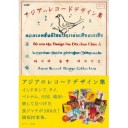
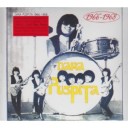

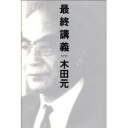
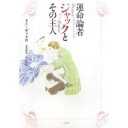

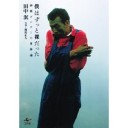

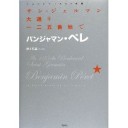
![『南方熊楠英文論考 [ネイチャー]誌篇』](http://diarynote.jp/data/blogs/m/20130903/49497_201309030250045136_1.jpg)