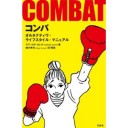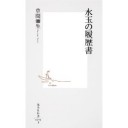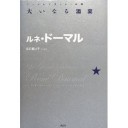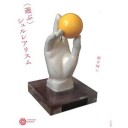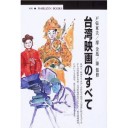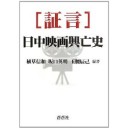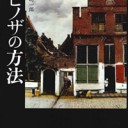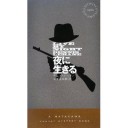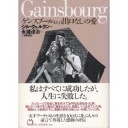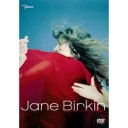『アサイラム・ピース』
2013年11月26日 読書
アンナ・カヴァンの『アサイラム・ピース』を読んだ。
どこかで何者かが、自分を裁判にかけて、何の罪でかは判然としないが、判決がくだされる。
カフカ的と呼ばれたのもよくわかる世界。
また、アサイラム・ピースは、おそらくは薬物依存で作者が収容された施設でのひとコマを描いている。
以下、目次。
母斑
上の世界へ
敵
変容する家
鳥
不満の表明
いまひとつの失敗
召喚
夜に
不愉快な警告
頭の中の機械
アサイラム・ピース
終わりはもうそこに
終わりはない
どこかで何者かが、自分を裁判にかけて、何の罪でかは判然としないが、判決がくだされる。
カフカ的と呼ばれたのもよくわかる世界。
また、アサイラム・ピースは、おそらくは薬物依存で作者が収容された施設でのひとコマを描いている。
以下、目次。
母斑
上の世界へ
敵
変容する家
鳥
不満の表明
いまひとつの失敗
召喚
夜に
不愉快な警告
頭の中の機械
アサイラム・ピース
終わりはもうそこに
終わりはない
『ジュリアとバズーカ』
2013年11月25日 読書
アンナ・カヴァンの『ジュリアとバズーカ』を読んだ。
これは妄想と被害妄想と潔癖症のひりひりする手記が小説化されたもので、と、いうか、手記だな!
各短編はバラバラのようでいて、手記だけに連続性もある。
各作品から、一部引用しておこう。
「以前の住所」
歩道には文字通り群集がひしめいており、誰かにぶつからずに歩くなどということは不可能だ。人間の顔をさがすが見つからない。ただ、仮面、ダミー、ゾンビの大群が、頭を下げて、すごい勢いでやみくもにすれ違っていくだけだ。
「ある訪問」
防ごうと思えば防げた、そしてその非はすべて自分自身にある喪失の漠然とした苦さにわたしは打ちひしがれてしまうように思われるのです。
「霧」
彼は何かのふりをしている。彼の大量生産された作り物の顔をわたしは無関心のまま、黙って眺めていた。彼の目には光のきらめきが、生気がなかった。知性とか表情などまったく見られぬ、平たい緑色の石だ。
彼は、詰め物をした服と傘とで作られた人形だ。本物ではない。
「実験」
鏡の中の少女はかなり魅力的に見えたが、彼女はわたしとは何の関係もないのだから、どうと言うこともなかった。彼女は鏡に映った影にすぎない。何ものでもないのだ。わたしではないのだ。
「英雄たちの世界」
子供の時間の進み方の恐ろしいほどののろさ。劣等感と、決して言われることのない優しい言葉をかけてもらおうとする苦闘との果てしない年月。誰かが責めを負わなければならぬと考え、自分を責める苦悩。無関係な他人に与えられた愛を自分にもと切望する苦しさ。どのような未来でもこれ以上ひどいわけがなかった。
「メルセデス」
突然、恐ろしいことに車が動き出した。ドアを開けて乗りこむか、それとも彼を引きずり出すかだと決意して、わたしはまた狂ったようにドアに飛びかかった。遅すぎた。メルセデスはもう手の届かない所にまで行ってしまい、わたしの手は空をつかんだだけだった。「とまって!」わたしは死にもの狂いで叫んだ。「わたしをおいてはいけないはずよ!」
「クラリータ」
わたしは頭から爪先まで赤い発疹とみみずばれでおおわれていた。おまけに、ひっかいていたところからは血がたくさん出ている。むずがゆさは恐るべきもので、ただただかきむしるか、そうでもなければ気が狂うかだった。
「はるか離れて」
わたしはできるだけみんなから離れ、まるでまわりの人間が存在していないかのようにふるまった。このことがどんなにみんなを怒らせたか、彼女たちの態度から分かった。同じ寮の女の子たちは、わたしを仲間はずれにすることで仕返しができると考えたらしいが、これこそわたしが望んでいたこと、わたしにぴったりのことだった。
「今と昔」
わたしはびっくりすると同時に信じなかった。二人の関係が、わたしが気づかぬうちにこんなにもひどくなるなどということはあり得ないことに思われた。しかし、明らかにそうだった。過去何週間も何ヶ月間も、わたしは目が見えなかったか、あるいは頭がおかしくなっていたのにちがいない。そして今は、心が乱れ、動揺して、きちんと考えることができず、どうしたら良いのかまったく分からなかった。
「山の上高く」
自分が死の願望に取りつかれていることは承知している。わたしはこれまで人生を楽しんだこともなければ、他人を好きだったこともない。わたしが山を愛するのは、それが生を否定するものであり、不滅で、冷酷で、何ものにも触れられることがなく、何事にも無関心な存在、つまりわたしがそうなりたいと望んでいる存在だからだ。人間は憎むべきものだ。彼らの醜い顔や汚らしい感情がわたしは大嫌いだ。人間なんかみんな滅ぼしてしまいたい。
「失われたものの間で」
わたしはしょっちゅう何かをなくす。暗闇の中で。落したり、置き場所が分からなくなったりするのではない。置き忘れるわけでもない。気がつくともうそこにないのだ。突然なくなってしまうのだ。
「縞馬」
彼女が出した結論は、彼はその創造力故に、自分ではそれと気づかぬまま、何らかの基本的な必要に迫られて冷酷なのだ、というものだった。しだいに、彼女は理解しようとするのをあきらめた。彼は彼女には複雑すぎた。彼女には彼の持つ多くの矛盾を解明することはできず、ただそれを受け入れるしかなかった。
「タウン・ガーデン」
わたしが歩道を歩いていくのを彼らは黙ったまま見つめ、それから集まって、わたしのあとを執念深い顔で見やりながらこそこそささやき合う。「ほら、彼女よ、庭を持ってる女よ」わたしのうしろでこうささやくのだ。「絶対、何か不正なことがあるに決まってるわよ」「どうもうさんくさい女だもんね」「頭がおかしいみたいよ」「いつでもひとりなのよ。誰かと一緒にいるのを見たことないわ-これはあやしいわよ」「正常じゃないわよね」「どこか狂ってるのね」「あたしが前からずっとそう言ってたじゃない」
「取り憑かれて」
彼がいなくなってから、世界は、狼狽するほど奇妙なものになってしまった。彼女にできることは何ひとつないし、行ける所はどこにもない。途方にくれ、さびしく、目がくらみ、何もかも、自分自身でさえも-これは、彼が絶え間なく励まし、安心させてくれなくても生きていけるほど強くないのだ-奪われてしまったような気持ちだった。孤独が彼女を責めつけた。何日間も彼女は誰とも会わず、誰とも話さなかった。電話はめったにかかってこない。
「ジュリアとバズーカ」
みんなはどこに行ってしまったんだろう?花婿は死んでしまったか、あるいはどこかの女の子と一緒にベッドに入っている。
これは妄想と被害妄想と潔癖症のひりひりする手記が小説化されたもので、と、いうか、手記だな!
各短編はバラバラのようでいて、手記だけに連続性もある。
各作品から、一部引用しておこう。
「以前の住所」
歩道には文字通り群集がひしめいており、誰かにぶつからずに歩くなどということは不可能だ。人間の顔をさがすが見つからない。ただ、仮面、ダミー、ゾンビの大群が、頭を下げて、すごい勢いでやみくもにすれ違っていくだけだ。
「ある訪問」
防ごうと思えば防げた、そしてその非はすべて自分自身にある喪失の漠然とした苦さにわたしは打ちひしがれてしまうように思われるのです。
「霧」
彼は何かのふりをしている。彼の大量生産された作り物の顔をわたしは無関心のまま、黙って眺めていた。彼の目には光のきらめきが、生気がなかった。知性とか表情などまったく見られぬ、平たい緑色の石だ。
彼は、詰め物をした服と傘とで作られた人形だ。本物ではない。
「実験」
鏡の中の少女はかなり魅力的に見えたが、彼女はわたしとは何の関係もないのだから、どうと言うこともなかった。彼女は鏡に映った影にすぎない。何ものでもないのだ。わたしではないのだ。
「英雄たちの世界」
子供の時間の進み方の恐ろしいほどののろさ。劣等感と、決して言われることのない優しい言葉をかけてもらおうとする苦闘との果てしない年月。誰かが責めを負わなければならぬと考え、自分を責める苦悩。無関係な他人に与えられた愛を自分にもと切望する苦しさ。どのような未来でもこれ以上ひどいわけがなかった。
「メルセデス」
突然、恐ろしいことに車が動き出した。ドアを開けて乗りこむか、それとも彼を引きずり出すかだと決意して、わたしはまた狂ったようにドアに飛びかかった。遅すぎた。メルセデスはもう手の届かない所にまで行ってしまい、わたしの手は空をつかんだだけだった。「とまって!」わたしは死にもの狂いで叫んだ。「わたしをおいてはいけないはずよ!」
「クラリータ」
わたしは頭から爪先まで赤い発疹とみみずばれでおおわれていた。おまけに、ひっかいていたところからは血がたくさん出ている。むずがゆさは恐るべきもので、ただただかきむしるか、そうでもなければ気が狂うかだった。
「はるか離れて」
わたしはできるだけみんなから離れ、まるでまわりの人間が存在していないかのようにふるまった。このことがどんなにみんなを怒らせたか、彼女たちの態度から分かった。同じ寮の女の子たちは、わたしを仲間はずれにすることで仕返しができると考えたらしいが、これこそわたしが望んでいたこと、わたしにぴったりのことだった。
「今と昔」
わたしはびっくりすると同時に信じなかった。二人の関係が、わたしが気づかぬうちにこんなにもひどくなるなどということはあり得ないことに思われた。しかし、明らかにそうだった。過去何週間も何ヶ月間も、わたしは目が見えなかったか、あるいは頭がおかしくなっていたのにちがいない。そして今は、心が乱れ、動揺して、きちんと考えることができず、どうしたら良いのかまったく分からなかった。
「山の上高く」
自分が死の願望に取りつかれていることは承知している。わたしはこれまで人生を楽しんだこともなければ、他人を好きだったこともない。わたしが山を愛するのは、それが生を否定するものであり、不滅で、冷酷で、何ものにも触れられることがなく、何事にも無関心な存在、つまりわたしがそうなりたいと望んでいる存在だからだ。人間は憎むべきものだ。彼らの醜い顔や汚らしい感情がわたしは大嫌いだ。人間なんかみんな滅ぼしてしまいたい。
「失われたものの間で」
わたしはしょっちゅう何かをなくす。暗闇の中で。落したり、置き場所が分からなくなったりするのではない。置き忘れるわけでもない。気がつくともうそこにないのだ。突然なくなってしまうのだ。
「縞馬」
彼女が出した結論は、彼はその創造力故に、自分ではそれと気づかぬまま、何らかの基本的な必要に迫られて冷酷なのだ、というものだった。しだいに、彼女は理解しようとするのをあきらめた。彼は彼女には複雑すぎた。彼女には彼の持つ多くの矛盾を解明することはできず、ただそれを受け入れるしかなかった。
「タウン・ガーデン」
わたしが歩道を歩いていくのを彼らは黙ったまま見つめ、それから集まって、わたしのあとを執念深い顔で見やりながらこそこそささやき合う。「ほら、彼女よ、庭を持ってる女よ」わたしのうしろでこうささやくのだ。「絶対、何か不正なことがあるに決まってるわよ」「どうもうさんくさい女だもんね」「頭がおかしいみたいよ」「いつでもひとりなのよ。誰かと一緒にいるのを見たことないわ-これはあやしいわよ」「正常じゃないわよね」「どこか狂ってるのね」「あたしが前からずっとそう言ってたじゃない」
「取り憑かれて」
彼がいなくなってから、世界は、狼狽するほど奇妙なものになってしまった。彼女にできることは何ひとつないし、行ける所はどこにもない。途方にくれ、さびしく、目がくらみ、何もかも、自分自身でさえも-これは、彼が絶え間なく励まし、安心させてくれなくても生きていけるほど強くないのだ-奪われてしまったような気持ちだった。孤独が彼女を責めつけた。何日間も彼女は誰とも会わず、誰とも話さなかった。電話はめったにかかってこない。
「ジュリアとバズーカ」
みんなはどこに行ってしまったんだろう?花婿は死んでしまったか、あるいはどこかの女の子と一緒にベッドに入っている。
将棋竜王戦第4局、東浩紀対談集『震災ニッポンはどこへいく』
2013年11月22日 読書
今日は1日、ニコニコ生放送で将棋竜王戦を観戦していた。
羽生さんの解説で、目が離せなかった。
東浩紀対談集『震災ニッポンはどこへいく』を読んだ。
はじめに/東浩紀
第1章 震災から語る
01 福島から考える言葉の力/和合亮一
福島を言葉で語ること
「ばらばら」になる人々
震災を溺れながら経験する
沈鬱な時間を過ごすこと
絶望の果ての「連帯」
日本語を復興する
02 震災・原発・インターネット/津田大介
3.11とツイッターの役割
ソーシャルメディアの可能性
ばらばらになっていく「わたしたち」
文学者として考える
目的はなにか
問われる「国のかたち」
政治とはなにか
3.11の前は能天気な時代だった
自然発生的な公共性
03 「終わりなき日常」のあとの日常/竹熊健太郎
「終わりなき日常」の終わり
新しい出版、オルタナティブな流通
平等幻想からの脱出
原発事故でわかったこと
空気の支配する国で
文化はどう生き残るべきか
第2章 メディアを語る
04 「おもしろい」をセカイに広めるには/川上量生
『コクリコ坂から』について
文化の計量化は可能か
文化を次代へ手渡すために
辺境としての日本の可能性とは
開国か鎖国か-これからの政治について
05 「ばらばら」から始まるエクストリーム/宇川直宏
DOMMUNEと3.11
エクストリームの条件
日本を意識すること
因果鉄道の乗車駅/DOMMUNE FUKUSHIMA!
「動物意志2.0」ソーシャルメディアとしての猫会議
「物語」としての福島
欲望としての日本
マイノリティの連帯
猫ダンジョンを超えて
06 『アーキテクチャの生態系』とその後/濱野智史
『アーキテクチャの生態系』再読
「2ちゃんねる化する世界」をモデレートする
尖閣デモと朝日新聞
ネット民主主義の限界と可能性
ニコ生の理念とは
AKB48の政治学
橋下徹とAKB48
聖地巡礼を巡って
希望の場所
第3章 3.11後の哲学、科学、文学
07 3.11後、哲学とはなにか/國分功一郎
3.11の経験
哲学で「やってみせる」
消費社会批判を超えて
言説のスケール
『存在論的、郵便的』から『一般意志2.0』へ
一元論の哲学と二元論の哲学
ハイデガーを「農夫」から解き放つこと
「楽しい」の哲学を求めて
08 私たちはどのような科学と生きるのか/菊池誠、八代嘉美
震災後の科学コミュニケーション
放射能問題に関するコンセンサス
補償問題をどうするか
被災地の瓦礫拡散問題
被曝者差別と分断する社会
脱原発の哲学
見えないものをめぐって
科学技術とアイデンティティ
09 3.11から文学へ/市川真人、高橋源一郎
バカバカしくてやってられない
言葉の機能と教育の失敗
文学者の本当の仕事
第4章 『日本2.0』から考える
10 新憲法と政治メディア/境真良、津田大介
「フロー」と「ストック」の新憲法
二院制の再検討
グランドデザインを書き換える
開かれた国のために
「動員の革命」の先へ
新しい政治メディアとは!?
11 熟議はどこまで可能か/鈴木寛
いまの日本が抱えるガバナンスの問題点
革命後の世界を構想する仕事
「卒近代」の憲法
ゲンロン草案のテーマとはなにか
最善を尽くして勝負する権利
ゲンロン草案をアップデートするために
12 国をつくる言葉の力/猪瀬直樹
官僚システムとの戦い
「僕はマクロは信じないことにしている」
多様性の擁護
なぜ寄付金なのか?
今必要な政治家とは
シングルマザーを応援する
歴史の軸を立てる
「言葉の力」とはなにか
羽生さんの解説で、目が離せなかった。
東浩紀対談集『震災ニッポンはどこへいく』を読んだ。
はじめに/東浩紀
第1章 震災から語る
01 福島から考える言葉の力/和合亮一
福島を言葉で語ること
「ばらばら」になる人々
震災を溺れながら経験する
沈鬱な時間を過ごすこと
絶望の果ての「連帯」
日本語を復興する
02 震災・原発・インターネット/津田大介
3.11とツイッターの役割
ソーシャルメディアの可能性
ばらばらになっていく「わたしたち」
文学者として考える
目的はなにか
問われる「国のかたち」
政治とはなにか
3.11の前は能天気な時代だった
自然発生的な公共性
03 「終わりなき日常」のあとの日常/竹熊健太郎
「終わりなき日常」の終わり
新しい出版、オルタナティブな流通
平等幻想からの脱出
原発事故でわかったこと
空気の支配する国で
文化はどう生き残るべきか
第2章 メディアを語る
04 「おもしろい」をセカイに広めるには/川上量生
『コクリコ坂から』について
文化の計量化は可能か
文化を次代へ手渡すために
辺境としての日本の可能性とは
開国か鎖国か-これからの政治について
05 「ばらばら」から始まるエクストリーム/宇川直宏
DOMMUNEと3.11
エクストリームの条件
日本を意識すること
因果鉄道の乗車駅/DOMMUNE FUKUSHIMA!
「動物意志2.0」ソーシャルメディアとしての猫会議
「物語」としての福島
欲望としての日本
マイノリティの連帯
猫ダンジョンを超えて
06 『アーキテクチャの生態系』とその後/濱野智史
『アーキテクチャの生態系』再読
「2ちゃんねる化する世界」をモデレートする
尖閣デモと朝日新聞
ネット民主主義の限界と可能性
ニコ生の理念とは
AKB48の政治学
橋下徹とAKB48
聖地巡礼を巡って
希望の場所
第3章 3.11後の哲学、科学、文学
07 3.11後、哲学とはなにか/國分功一郎
3.11の経験
哲学で「やってみせる」
消費社会批判を超えて
言説のスケール
『存在論的、郵便的』から『一般意志2.0』へ
一元論の哲学と二元論の哲学
ハイデガーを「農夫」から解き放つこと
「楽しい」の哲学を求めて
08 私たちはどのような科学と生きるのか/菊池誠、八代嘉美
震災後の科学コミュニケーション
放射能問題に関するコンセンサス
補償問題をどうするか
被災地の瓦礫拡散問題
被曝者差別と分断する社会
脱原発の哲学
見えないものをめぐって
科学技術とアイデンティティ
09 3.11から文学へ/市川真人、高橋源一郎
バカバカしくてやってられない
言葉の機能と教育の失敗
文学者の本当の仕事
第4章 『日本2.0』から考える
10 新憲法と政治メディア/境真良、津田大介
「フロー」と「ストック」の新憲法
二院制の再検討
グランドデザインを書き換える
開かれた国のために
「動員の革命」の先へ
新しい政治メディアとは!?
11 熟議はどこまで可能か/鈴木寛
いまの日本が抱えるガバナンスの問題点
革命後の世界を構想する仕事
「卒近代」の憲法
ゲンロン草案のテーマとはなにか
最善を尽くして勝負する権利
ゲンロン草案をアップデートするために
12 国をつくる言葉の力/猪瀬直樹
官僚システムとの戦い
「僕はマクロは信じないことにしている」
多様性の擁護
なぜ寄付金なのか?
今必要な政治家とは
シングルマザーを応援する
歴史の軸を立てる
「言葉の力」とはなにか
『少女と魔法―ガールヒーローはいかに受容されたのか』
2013年11月19日 読書須川亜紀子の『少女と魔法―ガールヒーローはいかに受容されたのか』を読んだ。
女の子向けの魔女っ子、あるいは魔法少女アニメの受容史。
傾向が読み取りやすい過去の事例に比べて、現代の作品群については、なかなか手ごわそう。
以下、目次。
まえがき
第一章 ガールヒーローとしての「魔法少女」研究――本書の目的と構成
「魔女」の意味
「魔女」と「少女」の出会い
大衆文化における表象とオーディエンスたち
カルチュラルスタディーズにおけるポストフェミニズムテレビ学
「ポスト」フェミニズムという用語について
オーディエンス研究の採用
オーディエンス研究の方法論
本書の目的
本書の構成
第二章 「少女」と魔法と〈フェミニズム〉――「少女」文化における魔女
1.日本の「少女」文化――「少女」文化、カワイイ、そしてガール・パワー
「少女」とは何か?
明治期の少女雑誌と「少女」読者
「少女」が意味するもの
少女と女の子
「少女」文化における「西洋」表象
1910年代~30年代の少女雑誌における「西洋」表象
1950年代以降の少女向け大衆メディアにおける「西洋」表象
「西洋」表象と上流階級の結びつき
身近な「西洋」、遠い「西洋」
2.「少女」がまとう「カワイイ」の鎧
「カワイイ」のポリティクス
1970年代の「カワイイ」の顕在化
「カワイイ」玩具とキャラクターグッズ
3.1960年代から2000年代までの日本の「フェミニズム」の流れ
子どもを守る母としての立場
母性愛と利他主義
普通の年少未婚女性たちの「〈フェミニズム〉のようなもの」
1980年代後半~2000年代初頭の「ポストフェミニズム」とジェンダー平等
4.魔女と魔法――少女の魔力の表象の歴史とポリティクス
キリスト教文化圏の大衆メディアにおける魔女
魔女の変容-主婦〈家政婦〉魔女
魔女の変容-「魔法少女」カートゥーンと若者向けドラマ
フェミニズムの中の魔女
5.日本における西洋の魔女と魔法の表象
日本土着の「魔女」(魔力を持つ女性)たち-妖怪
日本土着の「魔女」(魔力を持つ女性)たち-巫女
若者向けアニメの中の女妖怪
第三章 女の子向け「魔法少女」テレビアニメの表象分析――サリーからどれみまで(1966年から2003年まで)
1.ガール・ヒーローの不在から誕生へ
「魔法少女」アニメに関する先行研究
テキスト分析
テレビ放送の開始と初期の子ども番組
ガールヒーロー誕生への期待
女の子向け「魔法少女」テレビアニメの登場-定義と特徴
1、表相性(身体的特徴)
2、表相性(属性・出自)
3、機能する家族、長子
4、経済的安定性
5、魔法アイテムと呪文
6、家庭性(ドメスティシティ)
2.黎明期:正統魔女と世俗魔女サリーとアッコ
『魔法使いサリー』(1966~68年)
フェミニニティ、パワー、交渉、折衷
ジェンダー化された赤色とパワー
フェミニニティを手放さない、社会的規範への抵抗
「適切な」フェミニニティと家庭性(ドメスティシティ)
異化作用としてのサリー
勤勉性と自己犠牲
ポニーとサリー
異化作用から、日本文化との折衷へ
『ひみつのアッコちゃん』(1969~70年)
「西洋」表象と文化の融合
「西洋」イメージの土着化
1970年代前後の社会状況
「少女」にとっての変身
自己肯定のための変身
3.「女の時代」期:コケティッシュ魔女とアイドル魔女――メグとマミ
『魔女っ子メグちゃん』(1974~75年)
昭和50年代の女性たちの変化
山口百恵と秋川リサ-コケティッシュなアイドルの登場
コケティッシュなガールヒーロー、メグ
女性ライバルの競争とファッション、フェミニニティ
コケティッシュでカワイイことの有効性
『魔法の天使クリィミーマミ』(1983~84年)
昭和50年代(1975~84年)の社会文化的コンテキスト
『魔法の天使クリィミーマミ』の6つのコード
ニューファミリーと原宿クレープ
有償労働の顕在化とジェンダー平等
異性による承認と「適切」なフェミニニティ
異性愛的希求性-男性による女性の承認-とその有効性の限界
歪曲した「三角」関係-〈三位一体〉の自己の表象
「適切」なフェミニニティの肯定と、過剰なセクシュアリティの否定
フランケンシュタインとドラキュラ-分身テーマの系譜
異性の他者による、むき出しの自己の肯定へ
「私は私」-脱-理想化と自己肯定
4.「ポスト・フェミニズム」期:チームヒロインと母性・ケア――セーラームーンとどれみ
『美少女戦士セーラームーン』シリーズ(1992~97年)
『美少女戦士セーラームーン』シリーズの6つのコード
複数主人公の多様性と統一性
まこと(セーラージュピター)の魅力-カワイくカッコイイフェミニニティ
多様性から統一へ-セーラー服コスチュームの機能
「地球を守る」テーマとパワフルな女性の団結
ガールパワー-バブル崩壊後のジェンダー戦略
ファッションと変身を通じた女性の結束
女性のパワーとしてのフェミニニティの「利用」
フェミニニティと女性のホモソーシャルコミュニティの拡大
マザーリング、ケア
セクシュアリティと生殖のテーマ
マザーリングと強さを通じての女性同士の団結
ポストフェミニズム期における母性の復活と女性のパワー
『おジャ魔女どれみ』シリーズ(1999~2003年)
2000年代の社会文化的コンテキスト
『おジャ魔女どれみ』の6つのコード
どれみの魔女見習い仲間たち
ファッション、ドレス、身体
ファッションが媒介する女性の団結
育児とケア
「母性」の表象
パワーとしての母役割とケア
5.おわりに
第四章 女の子向け「魔法少女」テレビアニメに関する女性オーディエンスの理解
1.オーディエンス調査方法
2.1960年代生まれの女性オーディエンス――サリー・アッコ世代
自己犠牲的行為への称讃と現実
適切な行為と「恥ずかしさ」
変身を通じた少女アイデンティティ形成と自己肯定
魔法のコンパクトと変身ごっこ
商品としての魔法のコンパクトのインパクト
変身の妄想と現実認識
私的空間における秘密のアイデンティティとフェミニンな自己形成
「西洋」表象と家族との思い出
類似と相違の間の相互作用
家庭、家族、家族内の位置の認識
個人より、関係性への興味
西洋式一軒家と西洋ライフスタイル
サリー・アッコ世代の「魔法少女」テレビアニメ理解
3.1970~80年代前半生まれの女性オーディエンス――メグ・マミ世代
共鳴とテキスト密猟
身体とセクシュアリティ
可変的身体の快楽
ファッション、スタイル、カワイイ文化
「西洋」表象とカワイイ
社会的に期待されるカワイイと関連玩具、グッズの機能
自己表現としてのカワイイのパフォーマンス
学校生活(集団調和)の抑圧と「魔法少女」アニメ
私的閉鎖空間における自己表現・肯定としての変身
キャラクターの占有化を通しての個の再確認
メグ・マミ世代の「魔法少女」テレビアニメ理解
4.1997、98年代生まれオーディエンス――セーラームーン・どれみ世代
ファッション、自己表現、自己肯定
セーラームーン・どれみ世代にとっての変身
多様性の尊重と集団結束の快楽
「カワイイ」と「カッコイイ」フェミニニティ
カワイイ家事なら受容範囲内
ヘゲモニックな「西洋」の美への無関心
家族の記憶と父親表象
セーラームーン・どれみ世代の「魔法少女」テレビアニメ理解
第五章 2003年以降の女の子向け「魔法少女」テレビアニメ
1.多様化する「魔法少女」たち
2.伝統的ヒーローに近づくガールヒーローたち
物語、オーディエンス、視聴形式、物語構造の多様化
3.『ふたりはプリキュア』(2004~05年)――バディなふたり
バディの憂鬱
変身-メイクアップ、ドレスアップ、パワーアップ
戦闘と浄化
ケアとマザーリング
『ふたりはプリキュア』の提示した葛藤と可能性
4.『フレッシュプリキュア!』(2009~10年)――育児の困難と贖罪
無垢なロールモデルとしてのプリキュア-「性の闇」か?
変身-オーディエンスに背中を向けるプリキュア
子育て、マザーリングの困難
子どもの非制御性とケアのパワー
玩具を通じたマザーリングの実践
トラウマを持つ少女の意義-東せつな=キュアパッション
セカンド・チャンス-やり直すという選択
機械と人間-制御される機械化人間の末路
少女のトラウマ、癒やし、再生
『フレッシュプリキュア!』の提示した可能性と限界
5.『スマイルプリキュア!』(2012~13年)――少女の決断、責任、自信
変身-メイクアップによる変身の強調
選び取り、決断する力
決断、責任感、勝利、自信
「プリンセス」の意味
『スマイルプリキュア!』が問いかけるもの
女の子向け「魔法少女」テレビアニメの展望
第六章 まとめと展望
本書の目的と研究の展望
各章のまとめ
オーディエンス調査における3つのキーファクターのまとめ
1、「西洋」に関連する表象の機能
2、魔法、セクシュアリティ、ファッション
3、女性同士の団結と母性、マザーリング、ケア
方法論的、理論的結果と今後の課題
おわりに
あとがき
巻末付録:おもな女の子向け「魔法少女」テレビアニメ
参考文献一覧
索引
女の子向けの魔女っ子、あるいは魔法少女アニメの受容史。
傾向が読み取りやすい過去の事例に比べて、現代の作品群については、なかなか手ごわそう。
以下、目次。
まえがき
第一章 ガールヒーローとしての「魔法少女」研究――本書の目的と構成
「魔女」の意味
「魔女」と「少女」の出会い
大衆文化における表象とオーディエンスたち
カルチュラルスタディーズにおけるポストフェミニズムテレビ学
「ポスト」フェミニズムという用語について
オーディエンス研究の採用
オーディエンス研究の方法論
本書の目的
本書の構成
第二章 「少女」と魔法と〈フェミニズム〉――「少女」文化における魔女
1.日本の「少女」文化――「少女」文化、カワイイ、そしてガール・パワー
「少女」とは何か?
明治期の少女雑誌と「少女」読者
「少女」が意味するもの
少女と女の子
「少女」文化における「西洋」表象
1910年代~30年代の少女雑誌における「西洋」表象
1950年代以降の少女向け大衆メディアにおける「西洋」表象
「西洋」表象と上流階級の結びつき
身近な「西洋」、遠い「西洋」
2.「少女」がまとう「カワイイ」の鎧
「カワイイ」のポリティクス
1970年代の「カワイイ」の顕在化
「カワイイ」玩具とキャラクターグッズ
3.1960年代から2000年代までの日本の「フェミニズム」の流れ
子どもを守る母としての立場
母性愛と利他主義
普通の年少未婚女性たちの「〈フェミニズム〉のようなもの」
1980年代後半~2000年代初頭の「ポストフェミニズム」とジェンダー平等
4.魔女と魔法――少女の魔力の表象の歴史とポリティクス
キリスト教文化圏の大衆メディアにおける魔女
魔女の変容-主婦〈家政婦〉魔女
魔女の変容-「魔法少女」カートゥーンと若者向けドラマ
フェミニズムの中の魔女
5.日本における西洋の魔女と魔法の表象
日本土着の「魔女」(魔力を持つ女性)たち-妖怪
日本土着の「魔女」(魔力を持つ女性)たち-巫女
若者向けアニメの中の女妖怪
第三章 女の子向け「魔法少女」テレビアニメの表象分析――サリーからどれみまで(1966年から2003年まで)
1.ガール・ヒーローの不在から誕生へ
「魔法少女」アニメに関する先行研究
テキスト分析
テレビ放送の開始と初期の子ども番組
ガールヒーロー誕生への期待
女の子向け「魔法少女」テレビアニメの登場-定義と特徴
1、表相性(身体的特徴)
2、表相性(属性・出自)
3、機能する家族、長子
4、経済的安定性
5、魔法アイテムと呪文
6、家庭性(ドメスティシティ)
2.黎明期:正統魔女と世俗魔女サリーとアッコ
『魔法使いサリー』(1966~68年)
フェミニニティ、パワー、交渉、折衷
ジェンダー化された赤色とパワー
フェミニニティを手放さない、社会的規範への抵抗
「適切な」フェミニニティと家庭性(ドメスティシティ)
異化作用としてのサリー
勤勉性と自己犠牲
ポニーとサリー
異化作用から、日本文化との折衷へ
『ひみつのアッコちゃん』(1969~70年)
「西洋」表象と文化の融合
「西洋」イメージの土着化
1970年代前後の社会状況
「少女」にとっての変身
自己肯定のための変身
3.「女の時代」期:コケティッシュ魔女とアイドル魔女――メグとマミ
『魔女っ子メグちゃん』(1974~75年)
昭和50年代の女性たちの変化
山口百恵と秋川リサ-コケティッシュなアイドルの登場
コケティッシュなガールヒーロー、メグ
女性ライバルの競争とファッション、フェミニニティ
コケティッシュでカワイイことの有効性
『魔法の天使クリィミーマミ』(1983~84年)
昭和50年代(1975~84年)の社会文化的コンテキスト
『魔法の天使クリィミーマミ』の6つのコード
ニューファミリーと原宿クレープ
有償労働の顕在化とジェンダー平等
異性による承認と「適切」なフェミニニティ
異性愛的希求性-男性による女性の承認-とその有効性の限界
歪曲した「三角」関係-〈三位一体〉の自己の表象
「適切」なフェミニニティの肯定と、過剰なセクシュアリティの否定
フランケンシュタインとドラキュラ-分身テーマの系譜
異性の他者による、むき出しの自己の肯定へ
「私は私」-脱-理想化と自己肯定
4.「ポスト・フェミニズム」期:チームヒロインと母性・ケア――セーラームーンとどれみ
『美少女戦士セーラームーン』シリーズ(1992~97年)
『美少女戦士セーラームーン』シリーズの6つのコード
複数主人公の多様性と統一性
まこと(セーラージュピター)の魅力-カワイくカッコイイフェミニニティ
多様性から統一へ-セーラー服コスチュームの機能
「地球を守る」テーマとパワフルな女性の団結
ガールパワー-バブル崩壊後のジェンダー戦略
ファッションと変身を通じた女性の結束
女性のパワーとしてのフェミニニティの「利用」
フェミニニティと女性のホモソーシャルコミュニティの拡大
マザーリング、ケア
セクシュアリティと生殖のテーマ
マザーリングと強さを通じての女性同士の団結
ポストフェミニズム期における母性の復活と女性のパワー
『おジャ魔女どれみ』シリーズ(1999~2003年)
2000年代の社会文化的コンテキスト
『おジャ魔女どれみ』の6つのコード
どれみの魔女見習い仲間たち
ファッション、ドレス、身体
ファッションが媒介する女性の団結
育児とケア
「母性」の表象
パワーとしての母役割とケア
5.おわりに
第四章 女の子向け「魔法少女」テレビアニメに関する女性オーディエンスの理解
1.オーディエンス調査方法
2.1960年代生まれの女性オーディエンス――サリー・アッコ世代
自己犠牲的行為への称讃と現実
適切な行為と「恥ずかしさ」
変身を通じた少女アイデンティティ形成と自己肯定
魔法のコンパクトと変身ごっこ
商品としての魔法のコンパクトのインパクト
変身の妄想と現実認識
私的空間における秘密のアイデンティティとフェミニンな自己形成
「西洋」表象と家族との思い出
類似と相違の間の相互作用
家庭、家族、家族内の位置の認識
個人より、関係性への興味
西洋式一軒家と西洋ライフスタイル
サリー・アッコ世代の「魔法少女」テレビアニメ理解
3.1970~80年代前半生まれの女性オーディエンス――メグ・マミ世代
共鳴とテキスト密猟
身体とセクシュアリティ
可変的身体の快楽
ファッション、スタイル、カワイイ文化
「西洋」表象とカワイイ
社会的に期待されるカワイイと関連玩具、グッズの機能
自己表現としてのカワイイのパフォーマンス
学校生活(集団調和)の抑圧と「魔法少女」アニメ
私的閉鎖空間における自己表現・肯定としての変身
キャラクターの占有化を通しての個の再確認
メグ・マミ世代の「魔法少女」テレビアニメ理解
4.1997、98年代生まれオーディエンス――セーラームーン・どれみ世代
ファッション、自己表現、自己肯定
セーラームーン・どれみ世代にとっての変身
多様性の尊重と集団結束の快楽
「カワイイ」と「カッコイイ」フェミニニティ
カワイイ家事なら受容範囲内
ヘゲモニックな「西洋」の美への無関心
家族の記憶と父親表象
セーラームーン・どれみ世代の「魔法少女」テレビアニメ理解
第五章 2003年以降の女の子向け「魔法少女」テレビアニメ
1.多様化する「魔法少女」たち
2.伝統的ヒーローに近づくガールヒーローたち
物語、オーディエンス、視聴形式、物語構造の多様化
3.『ふたりはプリキュア』(2004~05年)――バディなふたり
バディの憂鬱
変身-メイクアップ、ドレスアップ、パワーアップ
戦闘と浄化
ケアとマザーリング
『ふたりはプリキュア』の提示した葛藤と可能性
4.『フレッシュプリキュア!』(2009~10年)――育児の困難と贖罪
無垢なロールモデルとしてのプリキュア-「性の闇」か?
変身-オーディエンスに背中を向けるプリキュア
子育て、マザーリングの困難
子どもの非制御性とケアのパワー
玩具を通じたマザーリングの実践
トラウマを持つ少女の意義-東せつな=キュアパッション
セカンド・チャンス-やり直すという選択
機械と人間-制御される機械化人間の末路
少女のトラウマ、癒やし、再生
『フレッシュプリキュア!』の提示した可能性と限界
5.『スマイルプリキュア!』(2012~13年)――少女の決断、責任、自信
変身-メイクアップによる変身の強調
選び取り、決断する力
決断、責任感、勝利、自信
「プリンセス」の意味
『スマイルプリキュア!』が問いかけるもの
女の子向け「魔法少女」テレビアニメの展望
第六章 まとめと展望
本書の目的と研究の展望
各章のまとめ
オーディエンス調査における3つのキーファクターのまとめ
1、「西洋」に関連する表象の機能
2、魔法、セクシュアリティ、ファッション
3、女性同士の団結と母性、マザーリング、ケア
方法論的、理論的結果と今後の課題
おわりに
あとがき
巻末付録:おもな女の子向け「魔法少女」テレビアニメ
参考文献一覧
索引
『コンバ オルタナティヴ・ライフスタイル・マニュアル』
2013年11月14日 読書
マティルド・セレルの『コンバ オルタナティヴ・ライフスタイル・マニュアル』を読んだ。
パリのFM「ラディオ・ノヴァ」の番組のコーナーをもとにテクスト化された本で、マティルド・セレルは番組のパーソナリティー。
社会問題や政治問題に異議申し立てするアクションの方法が書かれている。そういう問題にコミットしたいけど、特定の団体に入ったりするのは躊躇している人向けに、あなたにも出来るアクション集。
本書の言い方だと、「それぞれの人に、それぞれのミニバスティーユ襲撃」
以下、目次。アクションの数々の詳しい内容は、実際に読んでみるにかぎる!
ミツバチを養子にしよう
大麻の物資援助システムに協力しよう
パレオ式にたらふく食べよう
ヴォキャブラリーを“破格語法”化しよう
フランスにひげを生やそう
核兵器廃絶アクションをしよう
エスカレイターを嫌おう
バイコットしよう
を批判したおそう
バッテリーを交換しよう
声明や要求事項を振り付けにしよう
大義のためにクリックしよう
あなたのVOLの埋め合わせをしよう
巡礼・○○詣でに反対しよう
連帯キセルをしよう
銀行をビシビシ締め上げよう
カミカゼ・ダンサーになろう
人道的な海賊行為を擁護しよう
“分別あるスシ”で昼食をとろう
あなたのプレゼントを非物質化しよう
オフィスの汚染を除去しよう
広告の公共空間への侵略に抗おう
トランスジェンダー的実存主義者になろう
この世からきれいに消えよう
お乳をあげよう
グリーンなナンパをしよう
ニセ新聞を発行しよう
強制国外退去を阻止しよう
目の不自由な人たちのためにXを録音しよう
食虫性になろう
キス=インの練習をしよう
有毛の抵抗に突入しよう
エコ(年)賀状を送ろう
連帯貯蓄をしよう
あなたの消費主義を悪魔払いしよう
あなた自身でやろう
クリスマスに、無防備な子供を守ろう
グラスフェミーしよう
雇用センターを人間的な機関にしよう
心理地理学の基礎を学ぼう
直属の上司をののしろう
グローバルにイこう!
何人かで洗おう
結婚をグリーンに染めよう
ビオナニストなマスターベイションをしよう
フリーなセディーユのために闘おう
あなたの乳房を見せよう
新種のグラフィティを“描こう”
イケア(IKEA)をヤッちゃおう
罪を悔いるために、あなたの体を差し出そう
エコな酔っぱらい方を選ぼう
セクシャル療法を最適化しよう
PARK(ing)DAYをオーガナイズしよう
“性の助手(セクシュアル・アシスタント)”になろう
コンサートのチケット代をヴォランティア活動でまかなおう
電動で漕ごう
ゴミ箱の重さを量ろう
スーパーマーケットの店内でピック=ニックしよう
地球のことを思っておしっこしよう
ゴミ箱に潜ろう
週一菜食主義を実践しよう
国際連帯休暇を取ろう
球根テロを企てよう
CO2の節制に、宗教上の節制を活用しよう
星たちを再び輝かせよう
通りの名前を変えよう
サイクロヌーディスタ(自転車裸族)に加わろう
あなたのショッピング・カートを“GMOフリー”な商品で満たそう
共和国を修繕しよう
山頂を塗り直そう
あなたのキーボードで反乱を起こそう
フライド・ポテトで走ろう
あなたの犬を“犠牲”にしよう
社長を監禁しよう
職場で昼寝しよう
スロウ・カルチャーにしよう
茶色の“砂金採取”を支援しよう
親切になろう!
静寂をストックしよう
エコロ=ジック・ムーヴメントをフォロウしよう
別のサッカーをサポートしよう
山羊で刈ろう
自分をロカヴォアに変えよう
アンプラグしよう
携帯電話の価値を上げよう
あなたのネット・サーフィンを緑色にしよう
グリーンバードの群れで飛ぼう
素っ裸で旅しよう
「バイコット」は、ボイコットのような不買運動ではなく、エコ努力をしている企業の商品を買う、という運動。
「キス=イン」はダイ=インのキスバージョン
「グラスフェミー」は、使用済みガラスびんの分別の細かさ、うっとうしさを解消するため、ガラスをゴミ箱に投げつけて粉砕するやりかた。
「PARK DAY」は、パーキング・メーター式の駐車スペースで、車をとめずに人工芝マットをひいて、ベンチをセットして読書したりする。
「イケアをやっつける」のは、イケアの家具を本来の用途と違う使い方を提案する「マケア」の活動など。
「別のサッカー」は、シチュアシオニストのアスガー・ヨルン(本書では、実際の発音に近いエスカ・ヨーン表記)が考案した「スリーサイデッドフットボール」のこと。3チーム同時に戦い、得点した点数で勝つのではなく、失った点の少ないチームが勝つルール。
「あなたの乳房を見せよう」は、イスラムの導師が女性の肌の露出度と地震を結びつけた発言をしたことへの抗議から出た運動。みんなで集まって乳房を露出し、地震を引き起こそうとするもので、「ブーブクエイク」と呼ばれている。
などなど。
再三にわたって提案されるのが、ユロ・エコロジーで、シャワー中におしっこすることで、水洗トイレの水の量を節約するやりかた。日本人が全員、1日1回これを実行すると、1年で50メートルプール5万杯分の水の節約になるという。
これなら実行可能だ!
パリのFM「ラディオ・ノヴァ」の番組のコーナーをもとにテクスト化された本で、マティルド・セレルは番組のパーソナリティー。
社会問題や政治問題に異議申し立てするアクションの方法が書かれている。そういう問題にコミットしたいけど、特定の団体に入ったりするのは躊躇している人向けに、あなたにも出来るアクション集。
本書の言い方だと、「それぞれの人に、それぞれのミニバスティーユ襲撃」
以下、目次。アクションの数々の詳しい内容は、実際に読んでみるにかぎる!
ミツバチを養子にしよう
大麻の物資援助システムに協力しよう
パレオ式にたらふく食べよう
ヴォキャブラリーを“破格語法”化しよう
フランスにひげを生やそう
核兵器廃絶アクションをしよう
エスカレイターを嫌おう
バイコットしよう
を批判したおそう
バッテリーを交換しよう
声明や要求事項を振り付けにしよう
大義のためにクリックしよう
あなたのVOLの埋め合わせをしよう
巡礼・○○詣でに反対しよう
連帯キセルをしよう
銀行をビシビシ締め上げよう
カミカゼ・ダンサーになろう
人道的な海賊行為を擁護しよう
“分別あるスシ”で昼食をとろう
あなたのプレゼントを非物質化しよう
オフィスの汚染を除去しよう
広告の公共空間への侵略に抗おう
トランスジェンダー的実存主義者になろう
この世からきれいに消えよう
お乳をあげよう
グリーンなナンパをしよう
ニセ新聞を発行しよう
強制国外退去を阻止しよう
目の不自由な人たちのためにXを録音しよう
食虫性になろう
キス=インの練習をしよう
有毛の抵抗に突入しよう
エコ(年)賀状を送ろう
連帯貯蓄をしよう
あなたの消費主義を悪魔払いしよう
あなた自身でやろう
クリスマスに、無防備な子供を守ろう
グラスフェミーしよう
雇用センターを人間的な機関にしよう
心理地理学の基礎を学ぼう
直属の上司をののしろう
グローバルにイこう!
何人かで洗おう
結婚をグリーンに染めよう
ビオナニストなマスターベイションをしよう
フリーなセディーユのために闘おう
あなたの乳房を見せよう
新種のグラフィティを“描こう”
イケア(IKEA)をヤッちゃおう
罪を悔いるために、あなたの体を差し出そう
エコな酔っぱらい方を選ぼう
セクシャル療法を最適化しよう
PARK(ing)DAYをオーガナイズしよう
“性の助手(セクシュアル・アシスタント)”になろう
コンサートのチケット代をヴォランティア活動でまかなおう
電動で漕ごう
ゴミ箱の重さを量ろう
スーパーマーケットの店内でピック=ニックしよう
地球のことを思っておしっこしよう
ゴミ箱に潜ろう
週一菜食主義を実践しよう
国際連帯休暇を取ろう
球根テロを企てよう
CO2の節制に、宗教上の節制を活用しよう
星たちを再び輝かせよう
通りの名前を変えよう
サイクロヌーディスタ(自転車裸族)に加わろう
あなたのショッピング・カートを“GMOフリー”な商品で満たそう
共和国を修繕しよう
山頂を塗り直そう
あなたのキーボードで反乱を起こそう
フライド・ポテトで走ろう
あなたの犬を“犠牲”にしよう
社長を監禁しよう
職場で昼寝しよう
スロウ・カルチャーにしよう
茶色の“砂金採取”を支援しよう
親切になろう!
静寂をストックしよう
エコロ=ジック・ムーヴメントをフォロウしよう
別のサッカーをサポートしよう
山羊で刈ろう
自分をロカヴォアに変えよう
アンプラグしよう
携帯電話の価値を上げよう
あなたのネット・サーフィンを緑色にしよう
グリーンバードの群れで飛ぼう
素っ裸で旅しよう
「バイコット」は、ボイコットのような不買運動ではなく、エコ努力をしている企業の商品を買う、という運動。
「キス=イン」はダイ=インのキスバージョン
「グラスフェミー」は、使用済みガラスびんの分別の細かさ、うっとうしさを解消するため、ガラスをゴミ箱に投げつけて粉砕するやりかた。
「PARK DAY」は、パーキング・メーター式の駐車スペースで、車をとめずに人工芝マットをひいて、ベンチをセットして読書したりする。
「イケアをやっつける」のは、イケアの家具を本来の用途と違う使い方を提案する「マケア」の活動など。
「別のサッカー」は、シチュアシオニストのアスガー・ヨルン(本書では、実際の発音に近いエスカ・ヨーン表記)が考案した「スリーサイデッドフットボール」のこと。3チーム同時に戦い、得点した点数で勝つのではなく、失った点の少ないチームが勝つルール。
「あなたの乳房を見せよう」は、イスラムの導師が女性の肌の露出度と地震を結びつけた発言をしたことへの抗議から出た運動。みんなで集まって乳房を露出し、地震を引き起こそうとするもので、「ブーブクエイク」と呼ばれている。
などなど。
再三にわたって提案されるのが、ユロ・エコロジーで、シャワー中におしっこすることで、水洗トイレの水の量を節約するやりかた。日本人が全員、1日1回これを実行すると、1年で50メートルプール5万杯分の水の節約になるという。
これなら実行可能だ!
草間彌生の『水玉の履歴書』を読んだ。
2012年の草間彌生へのインタビューと、文献からの引用などからまとめられた1冊。
以下、目次
はじめに
第1章 芸術
コラム 21世紀の草間芸術
見る人を作品世界に没入させるアーティスト
果てしなく変化し続けるアーティスト
第2章 闘い
コラム アート・マーケットにおける草間
世界中に広がり続けるマーケット
コレクターから見た草間アートの魅力
第3章 人生
コラム 文筆家としての草間彌生
第4章 社会
コラム パブリックアートとしての草間作品
第5章 生・死・愛
草間彌生 闘いの記録/鈴木布美子
「世界のクサマ」へ
画家を志す
国内から海外へ
アメリカでの草間
センセーショナルだった「ハプニング」
日本に戻ってきてからの活動
再評価の動き
草間アートの真骨頂
主要引用・参考文献一覧
本書のインタビューで、草間彌生は「私は日本で生まれ、育ちましたが、日本の文化、伝統からは影響を受けていません。むしろ、自分の心の中から湧いてくる創造力を武器に古い習慣や芸術と闘ってきたのです」と言っている。
また、「みんなが同じような服を着るのは封建的です。私はうんと変わった服を着たいと思ってきました」とも言っている。
草間彌生はすっかり世間に認知され、一般のお客さんが多数支持する存在になったが、彼女の闘いを彼女だけのものにせず、自分自身闘わないと意味がないと思う。
草間彌生展を見に行ったときに、お客さんが誰からも後ろ指さされない普通のファッションの人ばっかりだったのに、がっかりしたことがある。
草間彌生の闘いは、まだまだはじまったばかりなのだ。
2012年の草間彌生へのインタビューと、文献からの引用などからまとめられた1冊。
以下、目次
はじめに
第1章 芸術
コラム 21世紀の草間芸術
見る人を作品世界に没入させるアーティスト
果てしなく変化し続けるアーティスト
第2章 闘い
コラム アート・マーケットにおける草間
世界中に広がり続けるマーケット
コレクターから見た草間アートの魅力
第3章 人生
コラム 文筆家としての草間彌生
第4章 社会
コラム パブリックアートとしての草間作品
第5章 生・死・愛
草間彌生 闘いの記録/鈴木布美子
「世界のクサマ」へ
画家を志す
国内から海外へ
アメリカでの草間
センセーショナルだった「ハプニング」
日本に戻ってきてからの活動
再評価の動き
草間アートの真骨頂
主要引用・参考文献一覧
本書のインタビューで、草間彌生は「私は日本で生まれ、育ちましたが、日本の文化、伝統からは影響を受けていません。むしろ、自分の心の中から湧いてくる創造力を武器に古い習慣や芸術と闘ってきたのです」と言っている。
また、「みんなが同じような服を着るのは封建的です。私はうんと変わった服を着たいと思ってきました」とも言っている。
草間彌生はすっかり世間に認知され、一般のお客さんが多数支持する存在になったが、彼女の闘いを彼女だけのものにせず、自分自身闘わないと意味がないと思う。
草間彌生展を見に行ったときに、お客さんが誰からも後ろ指さされない普通のファッションの人ばっかりだったのに、がっかりしたことがある。
草間彌生の闘いは、まだまだはじまったばかりなのだ。
ルネ・ドーマルの『大いなる酒宴』を読んだ。
風濤社の「シュルレアリスムの本棚」記念すべき最初の本。
ルネ・ドーマルはアンドレ・ブルトンのシュルレアリスム運動とは最後まで合流しなかった「大いなる賭け」の主要メンバーの詩人だが、ブルトンのシュルレアリスム運動に参加した者だけがシュルレアリストだというわけではないのである。
本書『大いなる酒宴』は36歳で夭折したルネ・ドーマルが残した『類推の山』と並ぶ小説の代表作で、本邦初訳。
以下、目次
序文あるいは取扱説明書
第1章 言葉の力と思考の弱さについての、煩雑な対話
第2章 人工天国
第3章 あたりまえの日の光
索引
訳者解説
カメレオンの法則-あとがきにかえて
ざっと言うと、第1章は、酒場での混沌とした乱痴気騒ぎ。
演説をぶつものあり、即興で歌うものあり、相談をもちかけるものあり、10巻にわたる哲学講義をはじめるものあり、いつまでも終わらないどうどうめぐりの話をするものあり。それぞれみんな酒が入っているので、熱を帯びているが、支離滅裂。
みんな渇きにまかせて酒を飲み続けているが、うまい酒ではない。
第2章は、酒場の上の屋根裏部屋の物置のなかにひろがる「町」の散策。
酒場のカオスから逃れてきたものたちの町で、ここでは禁酒が貫かれている。
これは現実の社会を風刺した架空の町めぐりになっている。
この町に住んでいるのは、「無用のオブジェこしらえ家」(絶対住めない家とかつくってる)、「無用な身ぶりこしらえ家」(コンテンポラリーダンスみたいな動きを1日中してる)、「無用の言説こしらえ家」(シジン=韻律にのった嘘つき、ショーセツカ=幻影商人、ヒヒョーカ=パン屑ひろいなど)「せつめい者」(カークシャ=科学者にあらず、テツガッシャ=哲学者にあらず)などなど。
ここでは、酒を飲まないかわりに、いつわりの飲み物で代用している。
第3章は、めざめたんだか、めざめていないんだか。
第2章に「アハム・エゴメ」という作家が登場する。「アハム」はサンスクリット語で「我」、「エゴメ」はラテン語で「私自身」。この作家が書こうとしている本が、本書のタイトルまんまの『大いなる酒宴』で、構成を語ってくれる。これがこの本の最適なあらすじなのかもしれない。
風濤社の「シュルレアリスムの本棚」記念すべき最初の本。
ルネ・ドーマルはアンドレ・ブルトンのシュルレアリスム運動とは最後まで合流しなかった「大いなる賭け」の主要メンバーの詩人だが、ブルトンのシュルレアリスム運動に参加した者だけがシュルレアリストだというわけではないのである。
本書『大いなる酒宴』は36歳で夭折したルネ・ドーマルが残した『類推の山』と並ぶ小説の代表作で、本邦初訳。
以下、目次
序文あるいは取扱説明書
第1章 言葉の力と思考の弱さについての、煩雑な対話
第2章 人工天国
第3章 あたりまえの日の光
索引
訳者解説
カメレオンの法則-あとがきにかえて
ざっと言うと、第1章は、酒場での混沌とした乱痴気騒ぎ。
演説をぶつものあり、即興で歌うものあり、相談をもちかけるものあり、10巻にわたる哲学講義をはじめるものあり、いつまでも終わらないどうどうめぐりの話をするものあり。それぞれみんな酒が入っているので、熱を帯びているが、支離滅裂。
みんな渇きにまかせて酒を飲み続けているが、うまい酒ではない。
第2章は、酒場の上の屋根裏部屋の物置のなかにひろがる「町」の散策。
酒場のカオスから逃れてきたものたちの町で、ここでは禁酒が貫かれている。
これは現実の社会を風刺した架空の町めぐりになっている。
この町に住んでいるのは、「無用のオブジェこしらえ家」(絶対住めない家とかつくってる)、「無用な身ぶりこしらえ家」(コンテンポラリーダンスみたいな動きを1日中してる)、「無用の言説こしらえ家」(シジン=韻律にのった嘘つき、ショーセツカ=幻影商人、ヒヒョーカ=パン屑ひろいなど)「せつめい者」(カークシャ=科学者にあらず、テツガッシャ=哲学者にあらず)などなど。
ここでは、酒を飲まないかわりに、いつわりの飲み物で代用している。
第3章は、めざめたんだか、めざめていないんだか。
第2章に「アハム・エゴメ」という作家が登場する。「アハム」はサンスクリット語で「我」、「エゴメ」はラテン語で「私自身」。この作家が書こうとしている本が、本書のタイトルまんまの『大いなる酒宴』で、構成を語ってくれる。これがこの本の最適なあらすじなのかもしれない。
第1部では、生きているという実感を少しでも強くもちたいけれど、なんの方針もないために、ぐでんぐでんに酔っぱらい、もううまくもない酒のために頭も鈍りきり、途方にくれているものたちの悪夢を描く。第2部では、ここで起こっていること全部と、亡霊同然の〈逃亡者たち〉の実態を描写する。禁酒がいかにたやすいか、人工天国のまやかしの飲料のせいで、もはや渇きのカの字も忘れてしまう事態にいたるありさまを書く。最後の第3部では、下階の酒よりももっと上等で、もっと現実的な酒が存在するかもしれないということを示すつもりなんだ。でも、その酒は、自分自身の知性のひらめき、自分自身の心のうずき、自分自身の腕が流す汗によってでなければ手に入らないんだ。
『〈遊ぶ〉シュルレアリスム』
2013年11月5日 読書
巌谷國士の『〈遊ぶ〉シュルレアリスム』を読んだ。
今年、徳島と東京で開催された同名の展覧会の図録として刊行された1冊だが、著者はシュルレアリスムを自由闊達に語っており、楽しく読めた。
序 〈遊ぶ〉シュルレアリスム
『シュルレアリスム宣言』まで
ある種のブリコラージュ
だれにでもできる手作業
野生の思考、野生の目
〈遊ぶ〉シュルレアリスム
どこからでも入れる部屋
第1室 友人たちの集い
解説
シュルレアリストたち
トランプ・チェス・ビリヤード
機関誌と美しい書物
友人たちの展覧会
第2室 オブジェと言葉の遊び
解説
デュシャンのレディメイド
マン・レイと語呂あわせ
箱から家具・モードまで
「オブジェの店」ローズ・セラヴィ
第3室 コラージュと偶然の出会い
解説
エルンストにはじまる
イメージの錬金術
岡上淑子の場合
ヤン・シュヴァンクマイエル
第4室 写真の超現実
解説
オブジェ・肖像・レイヨグラフ
都市とモードの超現実
プラハの町角で
遠い国のふたり
第5室 人体とメタモルフォーズ
解説
女性像あれこれ
奇妙なフィギュアたち
ドミンゲスとデカルコマニー
メタモルフォーズ
第6室 不思議な風景
解説
ダリと現実の変容
「囚われの美女」としての風景
タンギーの不思議
トワイヤンとマッタ
第7室 驚異・自然・コレクション
解説
マグリットの領域
神話・メルヘン・手作業
ブルトンの書斎から
瀧口修造の「贈り物」
今年、徳島と東京で開催された同名の展覧会の図録として刊行された1冊だが、著者はシュルレアリスムを自由闊達に語っており、楽しく読めた。
序 〈遊ぶ〉シュルレアリスム
『シュルレアリスム宣言』まで
ある種のブリコラージュ
だれにでもできる手作業
野生の思考、野生の目
〈遊ぶ〉シュルレアリスム
どこからでも入れる部屋
第1室 友人たちの集い
解説
シュルレアリストたち
トランプ・チェス・ビリヤード
機関誌と美しい書物
友人たちの展覧会
第2室 オブジェと言葉の遊び
解説
デュシャンのレディメイド
マン・レイと語呂あわせ
箱から家具・モードまで
「オブジェの店」ローズ・セラヴィ
第3室 コラージュと偶然の出会い
解説
エルンストにはじまる
イメージの錬金術
岡上淑子の場合
ヤン・シュヴァンクマイエル
第4室 写真の超現実
解説
オブジェ・肖像・レイヨグラフ
都市とモードの超現実
プラハの町角で
遠い国のふたり
第5室 人体とメタモルフォーズ
解説
女性像あれこれ
奇妙なフィギュアたち
ドミンゲスとデカルコマニー
メタモルフォーズ
第6室 不思議な風景
解説
ダリと現実の変容
「囚われの美女」としての風景
タンギーの不思議
トワイヤンとマッタ
第7室 驚異・自然・コレクション
解説
マグリットの領域
神話・メルヘン・手作業
ブルトンの書斎から
瀧口修造の「贈り物」
『台湾映画のすべて』
2013年11月4日 読書
『台湾映画のすべて』を読んだ。
台湾映画と台湾の政治や社会との関わりを研究するプロジェクトの成果をまとめた1冊。2004年11月の台湾映画に関する国際シンポジウムで一部が報告発表されている。
以下、目次。
序章 健康写実映画からニューシネマへ/戸張東夫
台湾映画の基礎を築いた台湾語映画(1950年代)
「健康写実映画」で中影の指導的地位確立(1960年代)
抗日愛国映画で台湾社会の挫折感癒す(1970年代)
ニューシネマは改革指向?(1980年代~戒厳令解除まで)
第1章 中央電影と台湾映画の盛衰/廖 金鳳
戦後中国映画としてスタートした台湾映画(1949~1962年)
黄金時代に地位を固めた中影(1963~1972年)
「国族主義(中華民国のナショナリズム)」再構築(1972~1983年)
遅きに失したニューシネマ(1982~1989年)
ポスト・ニューシネマ期の台湾映画の変容(1990~1996年)
歴史に見捨てられ、地球から姿を消す台湾映画(1996~2005年)
第2章 ニューシネマと台湾の政治改革/戸張東夫
改革の潮流から生まれたニューシネマ
低予算、新人監督、素人を起用
改革に関心示さぬニューシネマ
反対勢力の圧力で自己規制
第3章 台湾映画の中のエスニックグループ像/陳 儒修
ブームの発端となった「坊やの人形」
外省人第二世代の成長過程を記録した「少年」
「童年往事」は三世代の台湾経験
「牯嶺街少年殺人事件」と眷村意識
「悲情城市」に見るエスニックグループ衝突の歴史
漢族による原住民差別突いた「超級公民」
エスニックグループ融合の未来を暗示する「きらめきの季節」
おわりに
参考文献
〈台湾映画の主要な潮流と代表作〉
台湾語映画、国語映画、そして台湾映画へ
日本統治時代
台湾語映画
健康写実映画
瓊瑶映画
武侠映画・功夫映画
政治宣伝映画(国民革命、反共、抗日戦争、軍事教育、尋根)
社会派リアリズム
ニューシネマ
ポスト・ニューシネマ
これも、番組の事前に読んでおけばよかった本の1冊。
台湾映画と台湾の政治や社会との関わりを研究するプロジェクトの成果をまとめた1冊。2004年11月の台湾映画に関する国際シンポジウムで一部が報告発表されている。
以下、目次。
序章 健康写実映画からニューシネマへ/戸張東夫
台湾映画の基礎を築いた台湾語映画(1950年代)
「健康写実映画」で中影の指導的地位確立(1960年代)
抗日愛国映画で台湾社会の挫折感癒す(1970年代)
ニューシネマは改革指向?(1980年代~戒厳令解除まで)
第1章 中央電影と台湾映画の盛衰/廖 金鳳
戦後中国映画としてスタートした台湾映画(1949~1962年)
黄金時代に地位を固めた中影(1963~1972年)
「国族主義(中華民国のナショナリズム)」再構築(1972~1983年)
遅きに失したニューシネマ(1982~1989年)
ポスト・ニューシネマ期の台湾映画の変容(1990~1996年)
歴史に見捨てられ、地球から姿を消す台湾映画(1996~2005年)
第2章 ニューシネマと台湾の政治改革/戸張東夫
改革の潮流から生まれたニューシネマ
低予算、新人監督、素人を起用
改革に関心示さぬニューシネマ
反対勢力の圧力で自己規制
第3章 台湾映画の中のエスニックグループ像/陳 儒修
ブームの発端となった「坊やの人形」
外省人第二世代の成長過程を記録した「少年」
「童年往事」は三世代の台湾経験
「牯嶺街少年殺人事件」と眷村意識
「悲情城市」に見るエスニックグループ衝突の歴史
漢族による原住民差別突いた「超級公民」
エスニックグループ融合の未来を暗示する「きらめきの季節」
おわりに
参考文献
〈台湾映画の主要な潮流と代表作〉
台湾語映画、国語映画、そして台湾映画へ
日本統治時代
台湾語映画
健康写実映画
瓊瑶映画
武侠映画・功夫映画
政治宣伝映画(国民革命、反共、抗日戦争、軍事教育、尋根)
社会派リアリズム
ニューシネマ
ポスト・ニューシネマ
これも、番組の事前に読んでおけばよかった本の1冊。
『インド映画への招待状』
2013年10月30日 読書
杉本良男の『インド映画への招待状』を読んだ。
これも、あらかじめ読んでおけばよかった本。
以下、目次。
はじめに
序章 インド映画ってなに?
①熱狂するファン
インド人は映画好き
娯楽映画に熱狂する
政治を巻き込む大騒動
スターの誘拐、スターの死
②インド映画とは
多言語国家インド
娯楽映画と芸術映画
インド映画のグローバル化、ハイブリッド化
③むかしサタジット・レイ、いまラジニ・ガーント
大インド映画祭
1950年代のインドへの敬愛
すすけたインド-「一瞬メガ・ヒット」の時代のインド映画ブーム
第1章 神話の時代
浅草公演見世物記「佛國活動幻晝」
①ファンタジーとテクノロジー
インドへの映画の渡来-リュミエールのミッション
映画とマジック
プレ・ムーヴィー-宗教的な視覚芸能
②インド映画の出現
短編記録映画の製作
スワデーシとしてのインド国産映画
インド映画の父ファルケー
【神話と教訓】「ハリシュチャンドラ王」
神話・叙事詩・歴史
サイレントの黄金期
愛国映画
娼婦から良家の子女へ
映画の製作と興行
③歌う映画、踊る映画
言葉が分断し、音楽がつなぐ
『ナーティヤシャーストラ』と「ナヴァ・ラサ」
民俗芸能-大衆演劇-映画
ハイブリッド演劇-パールシー劇場
マンゲーシュカル父の悲劇-『サンギート・ナタック』
サタジット・レイの嘆き-ベンガルのジャトラ
花街から生まれたフィルム・ソング
④トーキー映画の黄金時代
映画スタジオ
【黄金の三角関係】「デーヴダース」
歌って踊れるスター
サイガル
ヌールジャハーンとラター・マンゲーシュカル
戦時下のインド映画
【戦時下のアンチ・ヒーロー】「運命」
インド・ナショナリズムと映画-タゴールとガンディー
第2章 インド映画三都物語 娯楽映画の都ボンベイ
インド独立
①ボリウッド
家族としての国家-ネルー型社会主義リアリズム
インド民衆演劇協会(IPTA)
映画の王様ラージ・カプール
1950年代の四天王
【国民的叙事詩】「母なるインド」
②世界一の映画生産国
一人のスター、六曲の歌、三つの踊り
インドのキスの危機
世界一の映画生産国
③ハイブリッド・ミュージック
プレイバック
ラターとアーシャー-女声プレイバック・シンガー
ムケーシュ、ラファー、キショール-男声プレイバック・シンガー
ラジオとフィルム・ソング
ハイブリッド・ミュージックの作曲家
④アンチ・ヒーローとヴァイオレンス
スーパースターの時代
アミターブ・バッチャン
【マルチスター映画】「炎」
アクション、ヴァイオレンス、レイプ
第3章 インド映画三都物語 芸術映画の拠点カルカッタ
①サタジツト・レイ
芸術映画への道
【芸術映画の成立】「大地のうた」
ヒューマニズム
②ベンガルの芸術映画と娯楽映画
ガタク
セーン
IPTA系の監督・俳優
二足のわらじ
③ニュー・シネマ
FFC後援映画
シャーム・ベネガル
ベネガル以後
【黄金の娼妓】「踊り子」
④地方語映画の繚乱
オリヤー映画
アッサム映画・マニプーリー映画
マラーティー映画
カンナダ映画
マラヤーラム映画
ゴーパーラクリシュナンとアラヴィンダン
アラブへの出稼ぎ
第4章 インド映画三都物語 映画を政治化するマドラス
①娯楽映画とナショナリズム
南インドの地方意識と映画
ドラーヴィダ・ナショナリズム
長篇劇映画の製作
大衆演劇とナショナリズム
南インドのトーキー映画
トーキーの名作
【女性の自立】「犠牲の大地」
②少年よ大志を抱け
ボーイズ・カンパニー
映画と政治のシナリオ・ライター
【うるわしき兄妹愛】「女神」
③家族・親族関係のメタファー
よき息子、頼もしい兄
よき息子、頼もしい兄(たぶん誤植と思われる。内容は政治家にもなったMGRのイメージ戦略について)
④共産党と芸道もの-テルグ映画
第5章 越境するインド映画
①越境する愛 ジャンルを超えて
欲しいのはお金、望むのは愛
「アイ・ラブ・ユー」
ラヴ・ロマンス時代の女神たち
【越境する愛】「私はあなたの何?」
独立五十周年とインド・ナショナリズム
政治と映画の共犯関係
②南インドの卓越 言葉の壁を超えて
南インドと北インド
南インド出身女優の華麗な系譜
ライバル
映画(reel)から現実(real)へ
南インドからの旋風-マニ・ラトナムとA・R・ラフマーン
③情報化時代のインド映画 国境を超えて
コピーの氾濫
カセットの衝撃
サテライト・テレビの衝撃
テレビ・ドラマからクイズ番組へ
ディジタルの衝撃
海外市場の卓越
④還流する「インド」
インド人資本の還流
NRI好み
ビューティフル・インディア
ルビコンを渡る
あとがき
これも、あらかじめ読んでおけばよかった本。
以下、目次。
はじめに
序章 インド映画ってなに?
①熱狂するファン
インド人は映画好き
娯楽映画に熱狂する
政治を巻き込む大騒動
スターの誘拐、スターの死
②インド映画とは
多言語国家インド
娯楽映画と芸術映画
インド映画のグローバル化、ハイブリッド化
③むかしサタジット・レイ、いまラジニ・ガーント
大インド映画祭
1950年代のインドへの敬愛
すすけたインド-「一瞬メガ・ヒット」の時代のインド映画ブーム
第1章 神話の時代
浅草公演見世物記「佛國活動幻晝」
①ファンタジーとテクノロジー
インドへの映画の渡来-リュミエールのミッション
映画とマジック
プレ・ムーヴィー-宗教的な視覚芸能
②インド映画の出現
短編記録映画の製作
スワデーシとしてのインド国産映画
インド映画の父ファルケー
【神話と教訓】「ハリシュチャンドラ王」
神話・叙事詩・歴史
サイレントの黄金期
愛国映画
娼婦から良家の子女へ
映画の製作と興行
③歌う映画、踊る映画
言葉が分断し、音楽がつなぐ
『ナーティヤシャーストラ』と「ナヴァ・ラサ」
民俗芸能-大衆演劇-映画
ハイブリッド演劇-パールシー劇場
マンゲーシュカル父の悲劇-『サンギート・ナタック』
サタジット・レイの嘆き-ベンガルのジャトラ
花街から生まれたフィルム・ソング
④トーキー映画の黄金時代
映画スタジオ
【黄金の三角関係】「デーヴダース」
歌って踊れるスター
サイガル
ヌールジャハーンとラター・マンゲーシュカル
戦時下のインド映画
【戦時下のアンチ・ヒーロー】「運命」
インド・ナショナリズムと映画-タゴールとガンディー
第2章 インド映画三都物語 娯楽映画の都ボンベイ
インド独立
①ボリウッド
家族としての国家-ネルー型社会主義リアリズム
インド民衆演劇協会(IPTA)
映画の王様ラージ・カプール
1950年代の四天王
【国民的叙事詩】「母なるインド」
②世界一の映画生産国
一人のスター、六曲の歌、三つの踊り
インドのキスの危機
世界一の映画生産国
③ハイブリッド・ミュージック
プレイバック
ラターとアーシャー-女声プレイバック・シンガー
ムケーシュ、ラファー、キショール-男声プレイバック・シンガー
ラジオとフィルム・ソング
ハイブリッド・ミュージックの作曲家
④アンチ・ヒーローとヴァイオレンス
スーパースターの時代
アミターブ・バッチャン
【マルチスター映画】「炎」
アクション、ヴァイオレンス、レイプ
第3章 インド映画三都物語 芸術映画の拠点カルカッタ
①サタジツト・レイ
芸術映画への道
【芸術映画の成立】「大地のうた」
ヒューマニズム
②ベンガルの芸術映画と娯楽映画
ガタク
セーン
IPTA系の監督・俳優
二足のわらじ
③ニュー・シネマ
FFC後援映画
シャーム・ベネガル
ベネガル以後
【黄金の娼妓】「踊り子」
④地方語映画の繚乱
オリヤー映画
アッサム映画・マニプーリー映画
マラーティー映画
カンナダ映画
マラヤーラム映画
ゴーパーラクリシュナンとアラヴィンダン
アラブへの出稼ぎ
第4章 インド映画三都物語 映画を政治化するマドラス
①娯楽映画とナショナリズム
南インドの地方意識と映画
ドラーヴィダ・ナショナリズム
長篇劇映画の製作
大衆演劇とナショナリズム
南インドのトーキー映画
トーキーの名作
【女性の自立】「犠牲の大地」
②少年よ大志を抱け
ボーイズ・カンパニー
映画と政治のシナリオ・ライター
【うるわしき兄妹愛】「女神」
③家族・親族関係のメタファー
よき息子、頼もしい兄
よき息子、頼もしい兄(たぶん誤植と思われる。内容は政治家にもなったMGRのイメージ戦略について)
④共産党と芸道もの-テルグ映画
第5章 越境するインド映画
①越境する愛 ジャンルを超えて
欲しいのはお金、望むのは愛
「アイ・ラブ・ユー」
ラヴ・ロマンス時代の女神たち
【越境する愛】「私はあなたの何?」
独立五十周年とインド・ナショナリズム
政治と映画の共犯関係
②南インドの卓越 言葉の壁を超えて
南インドと北インド
南インド出身女優の華麗な系譜
ライバル
映画(reel)から現実(real)へ
南インドからの旋風-マニ・ラトナムとA・R・ラフマーン
③情報化時代のインド映画 国境を超えて
コピーの氾濫
カセットの衝撃
サテライト・テレビの衝撃
テレビ・ドラマからクイズ番組へ
ディジタルの衝撃
海外市場の卓越
④還流する「インド」
インド人資本の還流
NRI好み
ビューティフル・インディア
ルビコンを渡る
あとがき
『〔証言〕日中映画興亡史』
2013年10月29日 読書
植草信和、坂口英明、玉腰辰己編著による『〔証言〕日中映画興亡史』を読んだ。
活況を呈する中国映画だが、現在、日本に中国映画がほとんど入ってこなくなっている。それを尖閣問題に全て帰することができるのか、という疑問から本書は日中の映画の交流の歴史をたどって検証している。
本書で再三提案されるのは、シナリオライターの不足に嘆く中国映画と、ソフトに強い日本、ここに突破口があるのではないか、ということだ。
以下、目次。
はじめに 日中のへだたりと映画交流 玉腰辰己
中国映画の歴史と日本人
証言1 中国映画の歩み 佐藤忠男
1.海外での中国映画の発見・評価
2.中国映画の歴史(1)1896~1945年
3.中国映画の歴史(2)1945~1949年
4.中国映画の歴史(3)1949~1965年
5.中国映画の歴史(4)1960~1984年
6.中国映画の歴史(5)1985年~
証言2 二十一世紀の中国映画界 坂口英明
映画大国となった中国
1.1997年~2002年 WTO加盟と映画政策の改革時代
変革前夜 エンタテインメント映画時代の幕開け
変革の引き金となったWTO加盟
国営撮影所の再編
民営映画会社の台頭
映画興行改革とシネコンの拡大
輸出入の整備
2.2002年~2009年 国内娯楽大作の成功と香港映画界とのコラボによる拡大期
エンタメ新時代の象徴、「HERO 英雄」の登場
中国三人の巨匠監督の活躍
CEPA締結後の香港映画人とのコラボレーション
2000年代の国際合作映画および日本との関係
第六世代、または地下電影の監督たち
3.2010年~現在 メガヒットの時代
ハリウッド製3D映画の大ブーム
現代の中国を描く新世代の映画監督の登場
台湾映画の盛況と新たな貿易協定
日中間ビジネスはどうなるのか
証言3 中国映画の中の日本人 門間貴志
1.抗日時代の日中映画
2.新中国の映画における日本像
3.中国における日本映画の受容
4.日中の蜜月時代
5.香港映画と日本
6.抗日映画の多様性
7.抗日テレビドラマの隆盛
徳間康快の功績
証言4 初期の日中合作と中国政治の影 佐藤純彌
1.「君よ憤怒の河を渉れ」の中国での大ヒット
2.「未完の対局」と「敦煌」
3.徳間康快さんのこと
4.これからの日中映画交流をどうすべきか
証言5 東光徳間と中国映画祭 鈴木 一
1.文芸坐支配人から東光徳間へ
2.中国映画の高揚と配給事情
3.今後の文化交流のあり方
「第五世代」の衝撃
証言6 素顔の中国映画監督たち 水野衛子
1.始まりは陳凱歌から
2.張芸謀作品の字幕も担当
3.「ヘブン・アンド・アース天地英雄」撮影に参加
4.中国映画大変貌の10年
5. 現代の中国映画
証言7 活字とフィルムをとおして知った中国映画 植草信和
1.ひとりのアジア映画ファンとして
2.誠実だった中国の同業者との友誼
3.活字から遠く離れて
4. その後の「データブック」と中華圏映画
証言8 中国圏映画からアジア映画へ 暉峻創三
1.中国映画第五世代の台頭
2.本格的なアジア映画との取り組み
3.世界に進出し始めたアジア映画
4.香港映画とウォン・カーウァイ
5. 映画祭ディレクターの仕事
日中合作秘話
証言9 始皇帝暗殺から東アジア合作まで 井関 惺
1.香港映画人とのつきあいから中国との関わりが始まった
2.「始皇帝暗殺」で陳凱歌と共同製作
3.変貌する中国映画界
4.新しいアジアでの国際合作の道を開いた「墨攻」
5.中国でスクリーン数が激増している
証言10 現代の中国映画を創る 牛山拓二
1.上海撮影所との合作「最後の恋、初めての恋」
2.上海、東京、台北、三地域でロケした「アバウト・ラブ」
3.第六世代の映画作家との人間関係で産まれた「夜の上海」
4.いま注目しているのは東南アジア映画人
5.再び中国との連携はあるのか
佐藤忠男の証言1で、時代区分の年数がかぶっているのは、中華人民共和国を毛沢東が宣言した1949年から、1965年に文化大革命がはじまるまでの時期を区切ったのと、次節で紹介される革命を讃える映画「紅色娘子軍」が1960年の作品だったことによる。
今まで見てきた映画が、歴史のなかに位置付けされていくのには、興奮した。
こういう本をあらかじめ読んでおけば、もっとユーストリーム番組でも話が深められたのに、と残念。
活況を呈する中国映画だが、現在、日本に中国映画がほとんど入ってこなくなっている。それを尖閣問題に全て帰することができるのか、という疑問から本書は日中の映画の交流の歴史をたどって検証している。
本書で再三提案されるのは、シナリオライターの不足に嘆く中国映画と、ソフトに強い日本、ここに突破口があるのではないか、ということだ。
以下、目次。
はじめに 日中のへだたりと映画交流 玉腰辰己
中国映画の歴史と日本人
証言1 中国映画の歩み 佐藤忠男
1.海外での中国映画の発見・評価
2.中国映画の歴史(1)1896~1945年
3.中国映画の歴史(2)1945~1949年
4.中国映画の歴史(3)1949~1965年
5.中国映画の歴史(4)1960~1984年
6.中国映画の歴史(5)1985年~
証言2 二十一世紀の中国映画界 坂口英明
映画大国となった中国
1.1997年~2002年 WTO加盟と映画政策の改革時代
変革前夜 エンタテインメント映画時代の幕開け
変革の引き金となったWTO加盟
国営撮影所の再編
民営映画会社の台頭
映画興行改革とシネコンの拡大
輸出入の整備
2.2002年~2009年 国内娯楽大作の成功と香港映画界とのコラボによる拡大期
エンタメ新時代の象徴、「HERO 英雄」の登場
中国三人の巨匠監督の活躍
CEPA締結後の香港映画人とのコラボレーション
2000年代の国際合作映画および日本との関係
第六世代、または地下電影の監督たち
3.2010年~現在 メガヒットの時代
ハリウッド製3D映画の大ブーム
現代の中国を描く新世代の映画監督の登場
台湾映画の盛況と新たな貿易協定
日中間ビジネスはどうなるのか
証言3 中国映画の中の日本人 門間貴志
1.抗日時代の日中映画
2.新中国の映画における日本像
3.中国における日本映画の受容
4.日中の蜜月時代
5.香港映画と日本
6.抗日映画の多様性
7.抗日テレビドラマの隆盛
徳間康快の功績
証言4 初期の日中合作と中国政治の影 佐藤純彌
1.「君よ憤怒の河を渉れ」の中国での大ヒット
2.「未完の対局」と「敦煌」
3.徳間康快さんのこと
4.これからの日中映画交流をどうすべきか
証言5 東光徳間と中国映画祭 鈴木 一
1.文芸坐支配人から東光徳間へ
2.中国映画の高揚と配給事情
3.今後の文化交流のあり方
「第五世代」の衝撃
証言6 素顔の中国映画監督たち 水野衛子
1.始まりは陳凱歌から
2.張芸謀作品の字幕も担当
3.「ヘブン・アンド・アース天地英雄」撮影に参加
4.中国映画大変貌の10年
5. 現代の中国映画
証言7 活字とフィルムをとおして知った中国映画 植草信和
1.ひとりのアジア映画ファンとして
2.誠実だった中国の同業者との友誼
3.活字から遠く離れて
4. その後の「データブック」と中華圏映画
証言8 中国圏映画からアジア映画へ 暉峻創三
1.中国映画第五世代の台頭
2.本格的なアジア映画との取り組み
3.世界に進出し始めたアジア映画
4.香港映画とウォン・カーウァイ
5. 映画祭ディレクターの仕事
日中合作秘話
証言9 始皇帝暗殺から東アジア合作まで 井関 惺
1.香港映画人とのつきあいから中国との関わりが始まった
2.「始皇帝暗殺」で陳凱歌と共同製作
3.変貌する中国映画界
4.新しいアジアでの国際合作の道を開いた「墨攻」
5.中国でスクリーン数が激増している
証言10 現代の中国映画を創る 牛山拓二
1.上海撮影所との合作「最後の恋、初めての恋」
2.上海、東京、台北、三地域でロケした「アバウト・ラブ」
3.第六世代の映画作家との人間関係で産まれた「夜の上海」
4.いま注目しているのは東南アジア映画人
5.再び中国との連携はあるのか
佐藤忠男の証言1で、時代区分の年数がかぶっているのは、中華人民共和国を毛沢東が宣言した1949年から、1965年に文化大革命がはじまるまでの時期を区切ったのと、次節で紹介される革命を讃える映画「紅色娘子軍」が1960年の作品だったことによる。
今まで見てきた映画が、歴史のなかに位置付けされていくのには、興奮した。
こういう本をあらかじめ読んでおけば、もっとユーストリーム番組でも話が深められたのに、と残念。
『寺山修司劇場「ノック」 閉ざされたドア、閉ざされた心をノックしてみる』
2013年10月24日 読書
『寺山修司劇場「ノック」 閉ざされたドア、閉ざされた心をノックしてみる』を読んだ。
ワタリウムでの展覧会の図録(行けなかった!)なのだが、本単独でじゅうぶん面白かった。
以下、目次。
天井桟敷はどこへ行こうとしているのか/寺山修司
寺山修司劇場「ノック」戯曲のことばと写真
青森県のせむし男
大山デブ子の犯罪
毛皮のマリー
時代はサーカスの象にのって
人力飛行機ソロモン
邪宗門
阿片戦争
盲人書簡上海篇
市街劇ノック
疫病流行記
阿呆船
奴婢訓
観客席
レミング 世界の涯てへ連れてって
百年の孤独
(作品ノート)/寺山修司
海外の時評
演劇実験室天井桟敷その他の公演作品
花札傳綺/新宿版千一夜物語/怪談青ひげ/美女劇伯爵令嬢小鷹狩掬子の七つの大罪/さらば映画よファン篇・スター篇/「瞼の母」における愛の研究/昭和白虎隊外伝 安保心中新宿お七/書を捨てよ、町へ出よう/星の王子さま/オデッセイ’69/犬神/ガリガリ博士の犯罪/イエス/ブラブラ男爵/東京零年/地獄より愛をこめて/青少年のための無人島入門/走れメロス/地球空洞説/血の起源/釘/引力の法則/中国の不思議な役人/身毒丸/こども狩り/青ひげ公の城
天井桟敷について
天井桟敷ポスター
寺山修司略年譜
幻想写真館『犬神家の人々』
おわりに
ワタリウムでの展覧会の図録(行けなかった!)なのだが、本単独でじゅうぶん面白かった。
以下、目次。
天井桟敷はどこへ行こうとしているのか/寺山修司
寺山修司劇場「ノック」戯曲のことばと写真
青森県のせむし男
大山デブ子の犯罪
毛皮のマリー
時代はサーカスの象にのって
人力飛行機ソロモン
邪宗門
阿片戦争
盲人書簡上海篇
市街劇ノック
疫病流行記
阿呆船
奴婢訓
観客席
レミング 世界の涯てへ連れてって
百年の孤独
(作品ノート)/寺山修司
海外の時評
演劇実験室天井桟敷その他の公演作品
花札傳綺/新宿版千一夜物語/怪談青ひげ/美女劇伯爵令嬢小鷹狩掬子の七つの大罪/さらば映画よファン篇・スター篇/「瞼の母」における愛の研究/昭和白虎隊外伝 安保心中新宿お七/書を捨てよ、町へ出よう/星の王子さま/オデッセイ’69/犬神/ガリガリ博士の犯罪/イエス/ブラブラ男爵/東京零年/地獄より愛をこめて/青少年のための無人島入門/走れメロス/地球空洞説/血の起源/釘/引力の法則/中国の不思議な役人/身毒丸/こども狩り/青ひげ公の城
天井桟敷について
天井桟敷ポスター
寺山修司略年譜
幻想写真館『犬神家の人々』
おわりに
『啓蒙の世紀の神秘思想 サン=マルタンとその時代』
2013年10月22日 読書
今野喜和人の『啓蒙の世紀の神秘思想 サン=マルタンとその時代』を読んだ。
サン=マルタンは、18世紀、フランス革命期の神秘思想家で、「マルチニスム」(彼の師、マルチネス・ド・パスカリの名からつけられている)がサン=マルタンの名からつけられたもの、つまりサン=マルタンの思想とイコールである、とされる誤解、マルチニスム自体に対する誤解、また、サン=マルタンの思想に名づけられた「イリュミニスム」が、イリュミナティはじめ、別の思想と取り違えられる誤解、さらには、サン=マルタンの思想そのもののわかりにくさなどがあいまって、実態がつかみにくいのだが、本書ではサン=マルタンとは何であったのかを、わかりやすく解き明かそうとしている。
以下、目次。
序
1.イリュミニスムとエゾテリスムについて
定義
エゾテリスムの概略史
いくつかの関連語彙について
エゾテリスム研究の現在
本書の構成
2.人と作品
第1部 啓蒙と反啓蒙のはざまで
第1章 哲学者の敵、神学者の敵―サン=マルタンとルソー
1.神の敵の敵
2.ルソーへのまなざし
むすび
第2章 言語論におけると反―恣意性をめぐって
1.ピュセイ説対テセイ説
2.「起源」のアポリア
3.原初言語の「機械的」形成
4.サン=マルタンの場合
むすびにかえて-クール・ド・ジェブランと18世紀
第3章 イリュミニストとイデオローグ―サン=マルタン―ガラ論争
1.論争の経緯と争点
2.親ルソー対反ルソー?
むすび
第2部 神秘思想家のフランス革命
第1章 革命とイリュミニスム
1.フリーメーソン
2.カトリーヌ・テオ事件
3.神の加護
第2章 『革命についての手紙』
1.市民サン=マルタン
2.「人類の革命」
3.宗教戦争
むすび
第3章 普遍学に向けて―小説『クロコディル』を読む
1.啓蒙主義
2.既成教会
3.オカルティズム
4.大団円、もしくは普遍学の誕生
第4章 ニコラ・ド・ボヌヴィル-「マルチニストの革命家」
1.生涯
2.マルチニスムとの関わり
3.陰謀テーゼ
むすび
第5章 ジャック・カゾット-「反革命マルチニスト」
1.カゾットの革命観
2.マルチニスムとの関わり
第6章 革命後のサン=マルタン
第3部 ロマン主義と神秘思想
第1章 サン=マルタンとシャトーブリアン
1.『キリスト教精髄』と『霊的人間の使命』
2.自然と心情
3.「誠実な文人」と「幻視の人」
むすび
第2章 バルザックとサン=マルタン
1.トゥーレーヌの人
2.マルチニスムとカトリシスム
3.バルザック的世界へ
第3章 サン=マルタンにおける人間と自然
1.自然の沈黙、自然の言(ことば)
2.〈渇望する人〉の使命
終章 マルチニスムの光芒
1.フランス
2.ドイツおよびスラヴ圏
3.その後の展開
あとがき
参考文献
サン=マルタン関係略年表
人名索引
目次中、言語論における「ピュセイ説」「テセイ説」は、それぞれ、「自然説」「契約説」のこと。
「序」の「本書の構成」から、全体の見取り図を描くと、こうなる。
サン=マルタンは、18世紀、フランス革命期の神秘思想家で、「マルチニスム」(彼の師、マルチネス・ド・パスカリの名からつけられている)がサン=マルタンの名からつけられたもの、つまりサン=マルタンの思想とイコールである、とされる誤解、マルチニスム自体に対する誤解、また、サン=マルタンの思想に名づけられた「イリュミニスム」が、イリュミナティはじめ、別の思想と取り違えられる誤解、さらには、サン=マルタンの思想そのもののわかりにくさなどがあいまって、実態がつかみにくいのだが、本書ではサン=マルタンとは何であったのかを、わかりやすく解き明かそうとしている。
以下、目次。
序
1.イリュミニスムとエゾテリスムについて
定義
エゾテリスムの概略史
いくつかの関連語彙について
エゾテリスム研究の現在
本書の構成
2.人と作品
第1部 啓蒙と反啓蒙のはざまで
第1章 哲学者の敵、神学者の敵―サン=マルタンとルソー
1.神の敵の敵
2.ルソーへのまなざし
むすび
第2章 言語論におけると反―恣意性をめぐって
1.ピュセイ説対テセイ説
2.「起源」のアポリア
3.原初言語の「機械的」形成
4.サン=マルタンの場合
むすびにかえて-クール・ド・ジェブランと18世紀
第3章 イリュミニストとイデオローグ―サン=マルタン―ガラ論争
1.論争の経緯と争点
2.親ルソー対反ルソー?
むすび
第2部 神秘思想家のフランス革命
第1章 革命とイリュミニスム
1.フリーメーソン
2.カトリーヌ・テオ事件
3.神の加護
第2章 『革命についての手紙』
1.市民サン=マルタン
2.「人類の革命」
3.宗教戦争
むすび
第3章 普遍学に向けて―小説『クロコディル』を読む
1.啓蒙主義
2.既成教会
3.オカルティズム
4.大団円、もしくは普遍学の誕生
第4章 ニコラ・ド・ボヌヴィル-「マルチニストの革命家」
1.生涯
2.マルチニスムとの関わり
3.陰謀テーゼ
むすび
第5章 ジャック・カゾット-「反革命マルチニスト」
1.カゾットの革命観
2.マルチニスムとの関わり
第6章 革命後のサン=マルタン
第3部 ロマン主義と神秘思想
第1章 サン=マルタンとシャトーブリアン
1.『キリスト教精髄』と『霊的人間の使命』
2.自然と心情
3.「誠実な文人」と「幻視の人」
むすび
第2章 バルザックとサン=マルタン
1.トゥーレーヌの人
2.マルチニスムとカトリシスム
3.バルザック的世界へ
第3章 サン=マルタンにおける人間と自然
1.自然の沈黙、自然の言(ことば)
2.〈渇望する人〉の使命
終章 マルチニスムの光芒
1.フランス
2.ドイツおよびスラヴ圏
3.その後の展開
あとがき
参考文献
サン=マルタン関係略年表
人名索引
目次中、言語論における「ピュセイ説」「テセイ説」は、それぞれ、「自然説」「契約説」のこと。
「序」の「本書の構成」から、全体の見取り図を描くと、こうなる。
まず第1部で啓蒙の世紀に啓蒙の本国たるフランスでサン=マルタンがどのような自己認識をもって思想家としての活動を行ったか、主にルソーとの比較を通して明らかにした後、特に言語論における神秘思想の位置付けについて、代表的著作やイデオローグ・ガラとの論争を通じて解明する。
次いで第2部ではフランス革命という、政治上のみならず、思想的に見ても史上類を見ない大変革に向けた、神秘思想家サン=マルタンの特異なまなざしについて、イリュミニスムとの関係を指摘される他の思想家・著作家の立場とも比較して考察し、ともすれば神話的に語られがちな大革命と神秘思想の関係を新たな視点から見直すことも目指す。
第3部では19世紀ロマン主義に与えた彼の影響の本質を、シャトーブリアンとの比較、およびバルザックにおける思想の受容の分析を通じて明らかにする。また、現在の環境問題との関連でサン=マルタンの自然観を見直した時、どのような意義を持ちうるかも論じる。
さらに、フランス・ドイツその他の国々におけるロマン主義、およびそれ以降の思想・文学における「マルチニスム」の影響研究をできる限り網羅的に紹介する補遺的な終章を付け、今後の研究の深化・拡大への基礎とする。
國分功一郎の『スピノザの方法』を読んだ。
以前、7割方読んでいながら、読了できていなかったものを、今回最初から読み直した。
無限遡行の逆説や、デカルトにとって重要だった「説得」のモードがスピノザにはなかったこととか、わかりやすく書かれていた。
本書は、『知性改善論』『デカルトの哲学原理』『エチカ』から、スピノザの方法を描き出す。
以下、目次
凡例
序章 方法という問題
第一部 ふたつの逆説
第一章 方法の三つの形象 I
1 道具 ――哲学におけるソフィズムの問題
2 標識 ――哲学における説得の問題
第二章 方法の三つの形象 II
1 道 ――方法の逆説
2 道 ――方法論の逆説
第一部の総括
第二部 逆説の起源
第三章 スピノザのデカルト読解 I
1 「スピノザの思想」、「デカルトの思想」
2 コギト
3 循環
第四章 スピノザのデカルト読解 II
1 四つの操作
2 規則と順序
3 並べ替えの意味
4 観念と実在
第五章 スピノザのデカルト読解 III
1 分析と総合
2 第二のア・ポステリオリな証明
3 第一のア・ポステリオリな証明
4 ア・プリオリな証明
第二部の総括
第三部 逆説の解決
第六章 スピノザの観念思想
1 道について、ふたたび ――方法の逆説の解決
2 方法書簡 ――方法論の逆説の解決
3 「与えられた真の観念」
4 定義、十全な観念、虚構
第七章 スピノザの方法
1 『エチカ』という書物
2 定義と公理
3 冒頭諸定理の証明手続き
4 冒頭諸定理の証明対象
5 神の存在証明
6 系譜学、観念の構築、状態の描写 ――『エチカ』と『デカルトの哲学原理』
第三部の総括
結論 スピノザの方法からスピノザの教育へ
あとがき
以前、7割方読んでいながら、読了できていなかったものを、今回最初から読み直した。
無限遡行の逆説や、デカルトにとって重要だった「説得」のモードがスピノザにはなかったこととか、わかりやすく書かれていた。
本書は、『知性改善論』『デカルトの哲学原理』『エチカ』から、スピノザの方法を描き出す。
以下、目次
凡例
序章 方法という問題
第一部 ふたつの逆説
第一章 方法の三つの形象 I
1 道具 ――哲学におけるソフィズムの問題
2 標識 ――哲学における説得の問題
第二章 方法の三つの形象 II
1 道 ――方法の逆説
2 道 ――方法論の逆説
第一部の総括
第二部 逆説の起源
第三章 スピノザのデカルト読解 I
1 「スピノザの思想」、「デカルトの思想」
2 コギト
3 循環
第四章 スピノザのデカルト読解 II
1 四つの操作
2 規則と順序
3 並べ替えの意味
4 観念と実在
第五章 スピノザのデカルト読解 III
1 分析と総合
2 第二のア・ポステリオリな証明
3 第一のア・ポステリオリな証明
4 ア・プリオリな証明
第二部の総括
第三部 逆説の解決
第六章 スピノザの観念思想
1 道について、ふたたび ――方法の逆説の解決
2 方法書簡 ――方法論の逆説の解決
3 「与えられた真の観念」
4 定義、十全な観念、虚構
第七章 スピノザの方法
1 『エチカ』という書物
2 定義と公理
3 冒頭諸定理の証明手続き
4 冒頭諸定理の証明対象
5 神の存在証明
6 系譜学、観念の構築、状態の描写 ――『エチカ』と『デカルトの哲学原理』
第三部の総括
結論 スピノザの方法からスピノザの教育へ
あとがき
「幻想浪漫展 異形のみる夢」@アートスペース亜蛮人、『夜に生きる』
2013年10月15日 読書
アートスペース亜蛮人に行って、「幻想浪漫展 異形のみる夢」を見てきた。
タイトルの横に「人間の形体に潜む 美と醜、聖と淫」と書いてある。
出展作家は、東學、eerie、伽椰子、三宮玄太、タムラグリア、dr°see、仲谷進、西村美希、向井正一
一歩入るなり、キメラと錬金術、夢想と妄想の行き着く世界が展開されている。いや、「展開」というより、奥へ奥へと吸い寄せられる感じ。
ちょっと怖いアングラな世界ではあるが、こういう世界にも「トレンド」みたいなものがあって、かつて隆盛を誇った「髑髏」と「眼球」は、今、「鳥」と「足」にとってかわられているようだ。頭の周辺で代表されていたアングラが、脳みそから最も遠い場所で今は表現されているのである。
デニス・ルヘインの『夜に生きる』を読んだ。
どこを切ってもクライム・ノワール。
3部構成で1926年から1935年まで、禁酒法時代の無法者~ギャングを描いている。
各部に登場人物表がついている。人が死にすぎるので、それくらいがちょうどいい。
第一部 ボストン 1926年~1929年
1.9時の街の12時の男
2.欠けた彼女
3.ヒッキーのシロアリ
4.まんなかにある穴
5.荒仕事
6.すべての罪深き聖人たち
7.そいつの口
8.薄闇に
9.ボスと道連れ
10、面会
第二部 イーボーシティ 1929年~1933年
11.この街でいちばん
12.音楽と銃
13.心の穴
14.爆発
15.彼の娘の眼
16.ギャング
17.今日のこと
18.誰の息子でも
19.いい日もない
20.ミ・グラン・アモール
21.導きの光
22.心の火を消すなかれ
第三部 すべての乱暴な子供 1933年~1935年
23.散髪
24.終わりの迎え方
25.上には上
26.ふたたび闇へ
27.ピナル・デル・リオの農場経営者
28.手遅れ
29.ああいう稼業の男
タイトルの横に「人間の形体に潜む 美と醜、聖と淫」と書いてある。
出展作家は、東學、eerie、伽椰子、三宮玄太、タムラグリア、dr°see、仲谷進、西村美希、向井正一
一歩入るなり、キメラと錬金術、夢想と妄想の行き着く世界が展開されている。いや、「展開」というより、奥へ奥へと吸い寄せられる感じ。
ちょっと怖いアングラな世界ではあるが、こういう世界にも「トレンド」みたいなものがあって、かつて隆盛を誇った「髑髏」と「眼球」は、今、「鳥」と「足」にとってかわられているようだ。頭の周辺で代表されていたアングラが、脳みそから最も遠い場所で今は表現されているのである。
デニス・ルヘインの『夜に生きる』を読んだ。
どこを切ってもクライム・ノワール。
3部構成で1926年から1935年まで、禁酒法時代の無法者~ギャングを描いている。
各部に登場人物表がついている。人が死にすぎるので、それくらいがちょうどいい。
第一部 ボストン 1926年~1929年
1.9時の街の12時の男
2.欠けた彼女
3.ヒッキーのシロアリ
4.まんなかにある穴
5.荒仕事
6.すべての罪深き聖人たち
7.そいつの口
8.薄闇に
9.ボスと道連れ
10、面会
第二部 イーボーシティ 1929年~1933年
11.この街でいちばん
12.音楽と銃
13.心の穴
14.爆発
15.彼の娘の眼
16.ギャング
17.今日のこと
18.誰の息子でも
19.いい日もない
20.ミ・グラン・アモール
21.導きの光
22.心の火を消すなかれ
第三部 すべての乱暴な子供 1933年~1935年
23.散髪
24.終わりの迎え方
25.上には上
26.ふたたび闇へ
27.ピナル・デル・リオの農場経営者
28.手遅れ
29.ああいう稼業の男
『ゲンスブール×2ノワール』
2013年10月11日 読書セルジュ・ゲンスブールの『ゲンスブール×2ノワール』を読んだ。
ゲンスブールが書いた小説と、死後インタビューに答える、という設定で語った未来の手記。
小説のほうは、『スカトロジーダンディ』から大幅な改訳となっている。
「エフゲニー・ソコロフ」
訳者あとがき「エフゲニー・ハンバート・ゲンスブール」田村源二
「ゲンスブール自らの死を語る」
訳者あとがき「デカダンスの帝王の涙」永瀧達治
ゲンスブールが書いた小説と、死後インタビューに答える、という設定で語った未来の手記。
小説のほうは、『スカトロジーダンディ』から大幅な改訳となっている。
「エフゲニー・ソコロフ」
訳者あとがき「エフゲニー・ハンバート・ゲンスブール」田村源二
「ゲンスブール自らの死を語る」
訳者あとがき「デカダンスの帝王の涙」永瀧達治
『ゲンスブールとの1週間』
2013年10月10日 読書
立川直樹の『ゲンスブールとの1週間』を読んだ。
ゲンスブールに会いに行って、過ごした1週間のことを書いている。
ゲンスブールが、そのとき、最も印象に残っている女性3人として、「フランス・ギャル、ジェーン・バーキン、ブリジット・バルドー」をあげているのが興味深い。(このときのゲンスブールのパートナーは、バンブー)
バーキン、バルドーはともかく、フランス・ギャルか!という思い。
たしかに、ゲンスブールの人生にとって大きな意味を持つ女性ではあるのだが。
ゲンスブールに会いに行って、過ごした1週間のことを書いている。
ゲンスブールが、そのとき、最も印象に残っている女性3人として、「フランス・ギャル、ジェーン・バーキン、ブリジット・バルドー」をあげているのが興味深い。(このときのゲンスブールのパートナーは、バンブー)
バーキン、バルドーはともかく、フランス・ギャルか!という思い。
たしかに、ゲンスブールの人生にとって大きな意味を持つ女性ではあるのだが。
『ゲンスブールまたは出口なしの愛』
2013年10月8日 読書
ジル・ヴェルランの『ゲンスブールまたは出口なしの愛』を読んだ。
今週末にゲンスブールのトークイベントに出演する関係で、音楽聞いたり、いろいろ読んで、おさらい中なのだ。
奇しくも、著者のジル・ヴェルランが、最近お亡くなりになったばかりで、びっくりしていたところ。
階段落ちて死んだそうだ。
階段には要注意。
以下、目次。
プロローグ 推定的ノンフィクション
1 そうさ、俺がゲンスバール…
2 君が素敵なものを持っているかぎり
3 白状すると、嫌な思いもしたよ・あなたは、違うかい、モナムール
4 ツイスト族へのレクイエム
5 イェイェの時代に
6 アニーはキャンディが好き
7 ジップ!シュバーン!パウ!ブロップ!ヴィーズ!
8 肉体の愛は出口なし…
9 君は僕の理性の絶対条件
10 ディ・ドゥ・ディ・ドゥ・ダー!
11 自分自身をメチャクチャにしたくなる衝動に駆られる日があるものさ
12 起て祖国の子らよ・栄光の日が訪れた
13 至上なるエキス・美味なる子供・私の肉、私の血・ああ、私のベビー、私の魂
14 私はあまりにも苦しい、ある日曜日に死んでしまうだろう
今週末にゲンスブールのトークイベントに出演する関係で、音楽聞いたり、いろいろ読んで、おさらい中なのだ。
奇しくも、著者のジル・ヴェルランが、最近お亡くなりになったばかりで、びっくりしていたところ。
階段落ちて死んだそうだ。
階段には要注意。
以下、目次。
プロローグ 推定的ノンフィクション
1 そうさ、俺がゲンスバール…
2 君が素敵なものを持っているかぎり
3 白状すると、嫌な思いもしたよ・あなたは、違うかい、モナムール
4 ツイスト族へのレクイエム
5 イェイェの時代に
6 アニーはキャンディが好き
7 ジップ!シュバーン!パウ!ブロップ!ヴィーズ!
8 肉体の愛は出口なし…
9 君は僕の理性の絶対条件
10 ディ・ドゥ・ディ・ドゥ・ダー!
11 自分自身をメチャクチャにしたくなる衝動に駆られる日があるものさ
12 起て祖国の子らよ・栄光の日が訪れた
13 至上なるエキス・美味なる子供・私の肉、私の血・ああ、私のベビー、私の魂
14 私はあまりにも苦しい、ある日曜日に死んでしまうだろう
アラン・クレイソンの『セルジュ・ゲンスブール性愛の仮面』を読んだ。
明日をも知れず
ヒップスター
レコーディング・アーティスト
ベビー・ポップ
海の向こう
欲望
イニシャルBB
’69はエロな年
人気の極み
性愛芸術家
レゲエに乗って
パンク老人
レクイエム’91
ガブリエル・クロフォード監督の「ジェーン・バーキン/マザー・オブ・オール・ベイブス」を見た。
ジェーン・バーキンに関するドキュメンタリー。
以下、チャプター。
イントロダクション
ゲンスブールとの出会い
ドワイヨンと映画
愛しい人
マイクを置いた日
子供たちと共に
平和の歌
憧れ
明日をも知れず
ヒップスター
レコーディング・アーティスト
ベビー・ポップ
海の向こう
欲望
イニシャルBB
’69はエロな年
人気の極み
性愛芸術家
レゲエに乗って
パンク老人
レクイエム’91
ガブリエル・クロフォード監督の「ジェーン・バーキン/マザー・オブ・オール・ベイブス」を見た。
ジェーン・バーキンに関するドキュメンタリー。
以下、チャプター。
イントロダクション
ゲンスブールとの出会い
ドワイヨンと映画
愛しい人
マイクを置いた日
子供たちと共に
平和の歌
憧れ
山折哲雄と森岡正博の対談『救いとは何か』を読んだ。
第1章 「殺すな」の思想を問う
ある少年の問い
「殺すな」の思想と近代
「三種還元の方法」の限界(三種は、社会学的方法、心理学的方法、精神医学的方法)
誰もが加害者でもある。
少年の問いにどう答えるか
「比較地獄」の時代
「無常」の三原則(「地上に永遠なるものは一つとしてない」「形あるものは壊れる」「人は生きて死ぬ」)
ロゴスの力
第2章 魂、そして死について
「一人」という問題
親鸞の「一人」
デカルトのコギト論
ヨーロッパ的人間観との違い
集団主義による「いじめ」
鎮魂について
「信ずる宗教」と「感ずる宗教」
「心」をめぐる探究の系譜
浄土と無常
宮澤賢治の信仰心
「写真葬」と化した現代の葬儀
死のイメージ・トレーニング
無神論について
死んだらどうなるのか?
理想の死に方
第3章 限りある命をどう生きるか
命のイメージ
手を合わせる理由
限りある命をどう生きるか
「誕生肯定」と「消滅肯定」
絶望と欲望からの解放
命をめぐるアメリカでの論争
ハンス・ヨナスの思想
悪の問題
菊池寛の小説と赦し(「恩讐の彼方に」と「ある抗議書」)
第4章 「個人の幸福」と「全体の幸福」
宮澤賢治の幸福論
「なめとこ山の熊」の二つの死
救いとしての死
「やまなし」に描かれた二つの世界
『銀河鉄道の夜』の思想
若い世代の生きるキツさ
二つの手立て
すべての魂に誕生肯定はあり得るか
第5章 救いとは何か
「人は死んでも消えてしまわない」
天地万物に命が宿る
「命を大切に」という標語
「ハーバード白熱教室」の欺瞞
功利主義的哲学への批判
「サバイバル戦略」と「無常戦略」
命の生まれ変わり
原発事故をどう受け止めるか
救いの最終的な根拠とは?
第1章 「殺すな」の思想を問う
ある少年の問い
「殺すな」の思想と近代
「三種還元の方法」の限界(三種は、社会学的方法、心理学的方法、精神医学的方法)
誰もが加害者でもある。
少年の問いにどう答えるか
「比較地獄」の時代
「無常」の三原則(「地上に永遠なるものは一つとしてない」「形あるものは壊れる」「人は生きて死ぬ」)
ロゴスの力
第2章 魂、そして死について
「一人」という問題
親鸞の「一人」
デカルトのコギト論
ヨーロッパ的人間観との違い
集団主義による「いじめ」
鎮魂について
「信ずる宗教」と「感ずる宗教」
「心」をめぐる探究の系譜
浄土と無常
宮澤賢治の信仰心
「写真葬」と化した現代の葬儀
死のイメージ・トレーニング
無神論について
死んだらどうなるのか?
理想の死に方
第3章 限りある命をどう生きるか
命のイメージ
手を合わせる理由
限りある命をどう生きるか
「誕生肯定」と「消滅肯定」
絶望と欲望からの解放
命をめぐるアメリカでの論争
ハンス・ヨナスの思想
悪の問題
菊池寛の小説と赦し(「恩讐の彼方に」と「ある抗議書」)
第4章 「個人の幸福」と「全体の幸福」
宮澤賢治の幸福論
「なめとこ山の熊」の二つの死
救いとしての死
「やまなし」に描かれた二つの世界
『銀河鉄道の夜』の思想
若い世代の生きるキツさ
二つの手立て
すべての魂に誕生肯定はあり得るか
第5章 救いとは何か
「人は死んでも消えてしまわない」
天地万物に命が宿る
「命を大切に」という標語
「ハーバード白熱教室」の欺瞞
功利主義的哲学への批判
「サバイバル戦略」と「無常戦略」
命の生まれ変わり
原発事故をどう受け止めるか
救いの最終的な根拠とは?