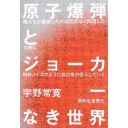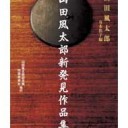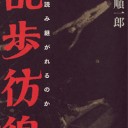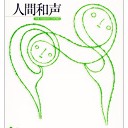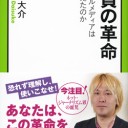『傲れる野獣の追放』
2014年1月10日 読書ジョルダーノ・ブルーノの『傲れる野獣の追放』(1584年)を読んだ。
ジョヴァンニ・ジェンティーレによると、ブルーノのイタリア語著作の「道徳的対話」と呼ばれる3つの作品の最初のもの。
内容は、ユピテル(ゼウス)による、星座の仕分け、総入れ替え。
天の星座が、神の悪行をあらわすものとなってしまった現状を憂えて、それらを追放し、新しい徳をその座につけていく。今ある星座がみんな悪い、と断罪されるわけではなく、星座によっては、配置変えという方が正しいものもある。
星座になりたくて、「富」や、その逆パターンとして「貧乏」や、「運」、「閑暇」などがアピールするくだりもあって、面白い。
後半には、古代エジプト賛美があったりして、ブルーノらしい。
以下、目次。ただし、これらの小見出しなどは、訳者によって読みやすくするためにつけられたもののようだ。
訳者解説
説明の書簡 フィリップ・シドニーへの献辞と本書の概略
第一対話 天の浄化の始まり
第一部 老ユピテルの改悛とモムスの召喚
有為転変と対立物の一致
老ユピテルの改悛
運命について
モムスの召喚
ユピテルとヴェヌスの会話
半人たちの横行と神々の黄昏
ヴルカヌスとヴェヌスの老衰
第二部 悪徳のホロスコープ
神々の集会
ユピテルの演説
悪徳のホロスコープ(1)
美徳の追放と悪徳の栄光
悪徳のホロスコープ(2)
ユピテルによる罪の告白
内なる情念の浄化
天の浄化の提案
第三部 〈熊〉の追放
新たな会議の開催と天の浄化の開始
〈熊〉の追放と〈真理〉の導入
〈竜〉の追放と〈賢慮〉の導入
〈ケフェウス〉の追放と〈知恵〉の導入
〈牛飼〉の追放と〈法〉の導入
〈北冠〉は天に残る
衒学者批判
〈審判〉の導入
〈ヘラクレス〉の新たな任務
メルクリウスの来訪
摂理についての滑稽な話
摂理についての深淵な話
第二対話 天の浄化の中心思想
第一部 真理・賢慮・知恵・法・審判
真理
賢慮
知恵
法
審判
古代ローマ人の賛美
文法学者たちへの批判
第二部 ヘラクレスの座を巡る論争
〈富〉の登場
〈貧乏〉の登場
〈富〉と〈貧乏〉の関係
〈貪欲〉
〈運〉の登場
〈運〉の正義
ユピテルの裁断
第三部 剛毅と勤勉
〈運〉の退出
〈剛毅〉
〈竪琴〉の追放とムネモシュネーと九人のムーサたちの導入
〈白鳥〉の追放と〈改悛〉の導入
〈カシオペア〉の追放と〈純一〉の導入
〈ペルセウス〉の新たな任務
〈勤勉〉(〈熱意〉〈労苦〉)の登場
ユピテルの指令
〈勤勉〉(〈熱意〉〈労苦〉)の提案
ナポリの暴動
第三対話 天の浄化の完成
第一部 閑暇を巡る論争
〈閑暇〉と〈眠り〉の登場
〈閑暇〉の演説
〈閑暇〉の三段論法
ユピテルの返答
〈眠り〉の失態
閑暇の家の住民たち
閑暇の使命
第二部 古代エジプト人の英知
〈トリプトレモス〉の追放と〈人間性〉の導入
〈蛇遣〉の追放と〈聡明さ〉の導入
〈矢〉の追放と〈注意〉の導入
〈ワシ〉の追放と〈雅量〉の導入
〈イルカ〉の追放と〈慈愛〉の導入
〈天馬〉の追放と〈神的狂気〉の導入
〈アンドロメダ〉の追放と〈希望〉の導入
円積問題に関する考察
〈信義〉が〈三角形〉の座を占める
〈牡羊〉の追放と〈競争心〉の導入
〈雄牛〉の追放と〈忍耐〉の導入
〈昴〉の追放と〈会話〉の導入
〈双子〉の追放と〈平和〉の導入
〈カニ〉の追放と〈改宗〉の導入
〈獅子〉の追放と〈寛大〉の導入
〈乙女〉の追放と〈純潔〉の導入
〈天秤〉の追放と〈公正〉の導入
〈サソリ〉の追放と〈誠意〉の導入
〈射手〉の追放と〈瞑想〉の導入
〈雄ヤギ〉の功績
エジプト人の卓越した信仰
神名の起源
魔術
カバラ
アスクレピウスの嘆き
エジプトの偶像崇拝の擁護
角を付けることの本来の意味
聖人崇拝の批判
〈雄ヤギ〉は〈自由〉とともに天に留まる
〈水瓶〉の追放。人類の起源について。〈節制〉の導入
〈魚〉の追放と〈沈黙〉の導入
第三部 アンリ三世への期待
〈クジラ〉の追放と〈平安〉の導入
オリオン
オリオンの処遇と〈精励〉の導入
エリダヌス川の処遇
〈ウサギ〉の追放と〈希望〉の導入
〈大犬〉の追放と〈伝道〉の導入。狩猟を巡る議論
〈子犬〉の追放と〈社交性〉の導入
〈船〉の追放と〈気前の良さ〉の導入
〈ヒドラ〉の処遇
〈カラス〉の追放と〈魔術〉の導入
カラスの隠喩の考察
〈カップ〉の追放と〈禁欲〉の導入
ケンタウルスのキロン
〈ケンタウルス〉は〈純一〉とともに天に留まる
〈三重冠〉はアンリ三世に与えられ、天の座を〈勝利〉が継承する
南の〈魚〉が追放され、〈健康〉が導入される
訳注
僕は、3月3日生れの魚座なので、ついつい、天の「魚」の処遇が気になってしまった。
魚は、天を追放されて、もとのエウフラテス川に戻され、それとともに〈無駄話〉〈饒舌〉〈おしゃべり〉が去っていく。そして、天の空位を〈沈黙〉〈寡黙〉が占めにむかう。魚座って、そんなにおしゃべりなのか。
また、作中、〈貪欲〉は三つの頭を持つ存在として登場する。この三つの頭は何かというと、吝嗇、醜い収入、頑迷さ、であり、それぞれが、こう言っている。
吝嗇「もっと寛大な好人物と思われるよりも、もっと富んでいたほうがいい」
醜い収入「紳士であるために餓死してはならない」
頑迷さ「それはわたしの名誉にならなくとも、わたしの役に立つのだ」
この〈貪欲〉について、率直にものを言うモムスは、ぼろくそな描写をする。ごくごく一部を書いておくと。
「顔は普通より大きいけれども、頭はたいそう小さいです。彼女は、年老いていて、卑しく、薄汚く、うつむき加減の表情をして、色が黒く、しわだらけです」
「ちっぽけな動物であるにもかかわらず、彼女はとても容量の大きな何でも呑み込む腹を持っています。彼女は愚かで、金銭目当てで、奴隷根性の持ち主で、まっすぐ前を見ようとすると仰向けになってしまいます」
「彼女は恩知らずで、彼女の邪悪な希望にとっては、何をもらおうとそれはけっして多くも、かなりの量でも、じゅうぶんでもないのです。彼女は取れば取るほど陰鬱になるのです」
セリーヌのパンフレ顔負けだ。
また、古代エジプト人の偶像崇拝を擁護するくだりでは、こう言っている。
「彼ら(すべての栄光ある卓越した民族)が彼らの盾に獣を描いたり、彼らの肖像や彫刻に獣を付け加えるとき、彼らは何を求めているというのでしょうか。彼らはきっとこう言いたがっているのです。『(見物人よ)この肖像に描かれている人物は、その隣に一緒に描かれている獣なのだ』と。あるいは『もしもあなたがこの獣が何かを知りたいならば、その正体は、この肖像に描かれた人物であり、その人の名はここに書いてある』と。もっと獣らしく見えるために、キツネや雄羊や雄ヤギの毛皮を着る人は大勢いるではないですか」
さらに、こう言う。
「自分がどれほど鳥類に近いかを示し、どれほど軽やかに雲へと舞い上がることができるかを知らせるために、ベレー帽や帽子に羽根をつける人は大勢いるのです」
なるへそ!
それと、オリオンは、「恐怖のために天で放尿している」、と書いてあった。オリオンを美化して歌う歌を今後聞いたときは、「でも、あれ、天でおしっこしてるんだな」と思い出してしまうだろうな。
ジョヴァンニ・ジェンティーレによると、ブルーノのイタリア語著作の「道徳的対話」と呼ばれる3つの作品の最初のもの。
内容は、ユピテル(ゼウス)による、星座の仕分け、総入れ替え。
天の星座が、神の悪行をあらわすものとなってしまった現状を憂えて、それらを追放し、新しい徳をその座につけていく。今ある星座がみんな悪い、と断罪されるわけではなく、星座によっては、配置変えという方が正しいものもある。
星座になりたくて、「富」や、その逆パターンとして「貧乏」や、「運」、「閑暇」などがアピールするくだりもあって、面白い。
後半には、古代エジプト賛美があったりして、ブルーノらしい。
以下、目次。ただし、これらの小見出しなどは、訳者によって読みやすくするためにつけられたもののようだ。
訳者解説
説明の書簡 フィリップ・シドニーへの献辞と本書の概略
第一対話 天の浄化の始まり
第一部 老ユピテルの改悛とモムスの召喚
有為転変と対立物の一致
老ユピテルの改悛
運命について
モムスの召喚
ユピテルとヴェヌスの会話
半人たちの横行と神々の黄昏
ヴルカヌスとヴェヌスの老衰
第二部 悪徳のホロスコープ
神々の集会
ユピテルの演説
悪徳のホロスコープ(1)
美徳の追放と悪徳の栄光
悪徳のホロスコープ(2)
ユピテルによる罪の告白
内なる情念の浄化
天の浄化の提案
第三部 〈熊〉の追放
新たな会議の開催と天の浄化の開始
〈熊〉の追放と〈真理〉の導入
〈竜〉の追放と〈賢慮〉の導入
〈ケフェウス〉の追放と〈知恵〉の導入
〈牛飼〉の追放と〈法〉の導入
〈北冠〉は天に残る
衒学者批判
〈審判〉の導入
〈ヘラクレス〉の新たな任務
メルクリウスの来訪
摂理についての滑稽な話
摂理についての深淵な話
第二対話 天の浄化の中心思想
第一部 真理・賢慮・知恵・法・審判
真理
賢慮
知恵
法
審判
古代ローマ人の賛美
文法学者たちへの批判
第二部 ヘラクレスの座を巡る論争
〈富〉の登場
〈貧乏〉の登場
〈富〉と〈貧乏〉の関係
〈貪欲〉
〈運〉の登場
〈運〉の正義
ユピテルの裁断
第三部 剛毅と勤勉
〈運〉の退出
〈剛毅〉
〈竪琴〉の追放とムネモシュネーと九人のムーサたちの導入
〈白鳥〉の追放と〈改悛〉の導入
〈カシオペア〉の追放と〈純一〉の導入
〈ペルセウス〉の新たな任務
〈勤勉〉(〈熱意〉〈労苦〉)の登場
ユピテルの指令
〈勤勉〉(〈熱意〉〈労苦〉)の提案
ナポリの暴動
第三対話 天の浄化の完成
第一部 閑暇を巡る論争
〈閑暇〉と〈眠り〉の登場
〈閑暇〉の演説
〈閑暇〉の三段論法
ユピテルの返答
〈眠り〉の失態
閑暇の家の住民たち
閑暇の使命
第二部 古代エジプト人の英知
〈トリプトレモス〉の追放と〈人間性〉の導入
〈蛇遣〉の追放と〈聡明さ〉の導入
〈矢〉の追放と〈注意〉の導入
〈ワシ〉の追放と〈雅量〉の導入
〈イルカ〉の追放と〈慈愛〉の導入
〈天馬〉の追放と〈神的狂気〉の導入
〈アンドロメダ〉の追放と〈希望〉の導入
円積問題に関する考察
〈信義〉が〈三角形〉の座を占める
〈牡羊〉の追放と〈競争心〉の導入
〈雄牛〉の追放と〈忍耐〉の導入
〈昴〉の追放と〈会話〉の導入
〈双子〉の追放と〈平和〉の導入
〈カニ〉の追放と〈改宗〉の導入
〈獅子〉の追放と〈寛大〉の導入
〈乙女〉の追放と〈純潔〉の導入
〈天秤〉の追放と〈公正〉の導入
〈サソリ〉の追放と〈誠意〉の導入
〈射手〉の追放と〈瞑想〉の導入
〈雄ヤギ〉の功績
エジプト人の卓越した信仰
神名の起源
魔術
カバラ
アスクレピウスの嘆き
エジプトの偶像崇拝の擁護
角を付けることの本来の意味
聖人崇拝の批判
〈雄ヤギ〉は〈自由〉とともに天に留まる
〈水瓶〉の追放。人類の起源について。〈節制〉の導入
〈魚〉の追放と〈沈黙〉の導入
第三部 アンリ三世への期待
〈クジラ〉の追放と〈平安〉の導入
オリオン
オリオンの処遇と〈精励〉の導入
エリダヌス川の処遇
〈ウサギ〉の追放と〈希望〉の導入
〈大犬〉の追放と〈伝道〉の導入。狩猟を巡る議論
〈子犬〉の追放と〈社交性〉の導入
〈船〉の追放と〈気前の良さ〉の導入
〈ヒドラ〉の処遇
〈カラス〉の追放と〈魔術〉の導入
カラスの隠喩の考察
〈カップ〉の追放と〈禁欲〉の導入
ケンタウルスのキロン
〈ケンタウルス〉は〈純一〉とともに天に留まる
〈三重冠〉はアンリ三世に与えられ、天の座を〈勝利〉が継承する
南の〈魚〉が追放され、〈健康〉が導入される
訳注
僕は、3月3日生れの魚座なので、ついつい、天の「魚」の処遇が気になってしまった。
魚は、天を追放されて、もとのエウフラテス川に戻され、それとともに〈無駄話〉〈饒舌〉〈おしゃべり〉が去っていく。そして、天の空位を〈沈黙〉〈寡黙〉が占めにむかう。魚座って、そんなにおしゃべりなのか。
また、作中、〈貪欲〉は三つの頭を持つ存在として登場する。この三つの頭は何かというと、吝嗇、醜い収入、頑迷さ、であり、それぞれが、こう言っている。
吝嗇「もっと寛大な好人物と思われるよりも、もっと富んでいたほうがいい」
醜い収入「紳士であるために餓死してはならない」
頑迷さ「それはわたしの名誉にならなくとも、わたしの役に立つのだ」
この〈貪欲〉について、率直にものを言うモムスは、ぼろくそな描写をする。ごくごく一部を書いておくと。
「顔は普通より大きいけれども、頭はたいそう小さいです。彼女は、年老いていて、卑しく、薄汚く、うつむき加減の表情をして、色が黒く、しわだらけです」
「ちっぽけな動物であるにもかかわらず、彼女はとても容量の大きな何でも呑み込む腹を持っています。彼女は愚かで、金銭目当てで、奴隷根性の持ち主で、まっすぐ前を見ようとすると仰向けになってしまいます」
「彼女は恩知らずで、彼女の邪悪な希望にとっては、何をもらおうとそれはけっして多くも、かなりの量でも、じゅうぶんでもないのです。彼女は取れば取るほど陰鬱になるのです」
セリーヌのパンフレ顔負けだ。
また、古代エジプト人の偶像崇拝を擁護するくだりでは、こう言っている。
「彼ら(すべての栄光ある卓越した民族)が彼らの盾に獣を描いたり、彼らの肖像や彫刻に獣を付け加えるとき、彼らは何を求めているというのでしょうか。彼らはきっとこう言いたがっているのです。『(見物人よ)この肖像に描かれている人物は、その隣に一緒に描かれている獣なのだ』と。あるいは『もしもあなたがこの獣が何かを知りたいならば、その正体は、この肖像に描かれた人物であり、その人の名はここに書いてある』と。もっと獣らしく見えるために、キツネや雄羊や雄ヤギの毛皮を着る人は大勢いるではないですか」
さらに、こう言う。
「自分がどれほど鳥類に近いかを示し、どれほど軽やかに雲へと舞い上がることができるかを知らせるために、ベレー帽や帽子に羽根をつける人は大勢いるのです」
なるへそ!
それと、オリオンは、「恐怖のために天で放尿している」、と書いてあった。オリオンを美化して歌う歌を今後聞いたときは、「でも、あれ、天でおしっこしてるんだな」と思い出してしまうだろうな。
『原子爆弾とジョーカーなき世界』、「高谷史郎 明るい部屋」展トークイベント
2014年1月3日 読書
宇野常寛の『原子爆弾とジョーカーなき世界』を読んだ。
ファンタジーの作動する場所―『DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る』
糸子のために―『カーネーション』
堀江さんとのこと―『刑務所なう。』
僕たちは「夜の世界」を生きている―『七夜物語』
東京タワーとビッグサイトのあいだで―『巨神兵東京に現わる』/「館長庵野秀明特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技」
原子爆弾とジョーカーなき世界―『ダークナイトライジング』
解放の呪文はいかにして唱えられてきたか―『すうねるところ』
遊びをせんとや生まれけむ―大河ドラマ『平清盛』
“補完”後の未来―『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』
鎌倉にて―『最後から二番目の恋』
番外編 これは想像力の要らない/必要な仕事だ―2012年12月衆議員総選挙から日本を考える
いま爆弾を、花火に変える方法は―『So long!』
「高谷史郎 明るい部屋」展の関連トークイベント(主催:東京都写真美術館)配信を見た。
<出演>
坂本龍一(音楽家)
浅田彰(批評家)
高谷史郎(アーティスト)
浅田彰さん、絶好調。東京の写真美術館でトークしてるのに、「東京みたいな田舎」と断言し、美術館の使い勝手の悪さをけなす。あわててキュレーターがフォローに入る一幕も。東浩紀や宮台のこともスバッと斬ってた。
ファンタジーの作動する場所―『DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る』
糸子のために―『カーネーション』
堀江さんとのこと―『刑務所なう。』
僕たちは「夜の世界」を生きている―『七夜物語』
東京タワーとビッグサイトのあいだで―『巨神兵東京に現わる』/「館長庵野秀明特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技」
原子爆弾とジョーカーなき世界―『ダークナイトライジング』
解放の呪文はいかにして唱えられてきたか―『すうねるところ』
遊びをせんとや生まれけむ―大河ドラマ『平清盛』
“補完”後の未来―『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』
鎌倉にて―『最後から二番目の恋』
番外編 これは想像力の要らない/必要な仕事だ―2012年12月衆議員総選挙から日本を考える
いま爆弾を、花火に変える方法は―『So long!』
「高谷史郎 明るい部屋」展の関連トークイベント(主催:東京都写真美術館)配信を見た。
<出演>
坂本龍一(音楽家)
浅田彰(批評家)
高谷史郎(アーティスト)
浅田彰さん、絶好調。東京の写真美術館でトークしてるのに、「東京みたいな田舎」と断言し、美術館の使い勝手の悪さをけなす。あわててキュレーターがフォローに入る一幕も。東浩紀や宮台のこともスバッと斬ってた。
2014年最初の読了本は、
紀田順一郎の『乱歩彷徨』。
江戸川乱歩が自作の仕分けをしたことについて、
主に語られていた。
なかで、平林初之輔が乱歩の作品に対して評した
「常識的といってもよいほどな、生温るい説明的な文章」
の一文が、興味深かった。
乱歩自身もそれを認めていたようだ。
年末に読んだ『死美人』(黒岩涙香の翻案を乱歩が現代語訳した)の
あとがきでも、乱歩は自分の文章について謝ってたっけ。
第Ⅰ部 乱歩低迷
1 深夜の瞑想
2 「探偵小説」の曲がり角
3 「眼高手低」の自覚
4 新時代の探偵小説を開拓
5 エログロ・ナンセンス時代の旗手へ
6 二重世界願望と郷愁と
7 休筆宣言と放浪
8 低迷の上に弾圧
9 本格探偵小説の復活を信じて
10 評論集の隠された意図
11 第一人者の再生演出
12 再コード化への道
第Ⅱ部 乱歩彷徨
1 少年雑誌という舞台
2 『怪人二十面相』における心理洞察
3 『怪人二十面相』の読者像
4 休載の謎をめぐって
5 『怪人二十面相』の基調変化
6 「誘拐」という記号
7 乱歩作品の異質性
8 なぜ「少年倶楽部」に起用されたか
9 二十面相はいかにして教育的となったか
10 「国民精神総動員」下の探偵もの
第Ⅲ部 乱歩変容
1 「じつにおどろくべき変化」
2 戦中体制への「協力」
3 追い詰められた戦争末期
4 劇的な性格変化とその意味
5 少年ものと旧作再録
6 再起への苦闘
7 推理小説界の振興に向けて
8 戦後も持続した「社会活動」
9 第二の創作『幻影城』
10 全集という名の評価
11 松本清張という名のライバル
12 乱歩は清張をどう評価したか
13 清張は乱歩をどう評価したか
14 乱歩復活と幻想怪奇ブームの実態
15 激動の時代をこえて殿堂入り
第Ⅳ部 乱歩復活
1 《創造者》の自覚
2 「私を怖わがらせた批評家」
3 「文芸球場」の「ピンチ・バッタア」
4 「一本の藁」と「新しき神」
5 居心地のよくない「大衆文学」
6 《もう一つの可能性》を夢見て
7 「エログロ」からの距離
8 精神分析と同性愛への関心
9 《第二の創作》への情熱
10 『幻影城』、自己回復と再生の企て
11 『探偵小説四十年』の隠された意味
12 ライバル松本清張と《一人の芭蕉》
あとがき
参考文献
乱歩主要作品一覧
乱歩略年譜
『がんじす河のまさごよりあまたおはする仏たち』
2013年12月31日 読書
稲垣足穂の『がんじす河のまさごよりあまたおはする仏たち』を読んだ。
巻末の「弥勒」が1940年の作品で最も昔のもので、前のほうの作品ほど最近のものになっている。
主に、Ⅰは仏教、Ⅱはキリスト教に関する内容になっていた。
「弥勒」は学生時代に難解さを感じながら読んだ作品だったが、今読み直してみると、なんとまあ、スラスラと読める。これは、僕に読解力がついた、とかいうわけではなく、主に「弥勒」第二部の極貧の描写が、体験的にわかるようになった、という、出来ることなら難解なままでいてほしかった理由からだ。
以下、目次。
Ⅰ
東洋の幻想
兜率上生
僕の弥勒浄土
廻るものの滑稽
別の秩序
生の連続
Ⅱ
悪魔の魅力
姦淫への同情
新生の記
幼きイエズスの春に
Ⅲ
有楽町の思想
俗人論
子供たちと道徳
フェヒナーの地球擁護
Ⅳ
弥勒
解説 弥勒から弥勒まで/松山俊太郎
巻末の「弥勒」が1940年の作品で最も昔のもので、前のほうの作品ほど最近のものになっている。
主に、Ⅰは仏教、Ⅱはキリスト教に関する内容になっていた。
「弥勒」は学生時代に難解さを感じながら読んだ作品だったが、今読み直してみると、なんとまあ、スラスラと読める。これは、僕に読解力がついた、とかいうわけではなく、主に「弥勒」第二部の極貧の描写が、体験的にわかるようになった、という、出来ることなら難解なままでいてほしかった理由からだ。
以下、目次。
Ⅰ
東洋の幻想
兜率上生
僕の弥勒浄土
廻るものの滑稽
別の秩序
生の連続
Ⅱ
悪魔の魅力
姦淫への同情
新生の記
幼きイエズスの春に
Ⅲ
有楽町の思想
俗人論
子供たちと道徳
フェヒナーの地球擁護
Ⅳ
弥勒
解説 弥勒から弥勒まで/松山俊太郎
澁澤龍彦の『推理小説月旦』を読んだ。
ミステリー関連の文章を集めた1冊。
I 私と推理小説――情熱あるいは中毒
推理小説とオカルティズム――小栗虫太郎を中心に
ミステリーにふける――AL’ESSENCE(本質を求めよ)
推理小説月旦―― 一九六〇年十月-六一年三月
Ⅱ ポオ(「古典案内」)
黄金虫
江戸川乱歩『パノラマ島奇談』解説
玩具愛好とユートピア――乱歩文学の本質
夢野久作の不思議
『夢野久作全集』第一巻
絢爛たる知的遊戯への招待――小栗虫太郎『黒死館殺人事件』
小栗虫太郎『黒死館殺人事件』解説
「小栗虫太郎・木々高太郎集」解説
『久生十蘭全集』第二巻の解説
スタイリスト十蘭
久生十蘭のこと
橘外男『青白き裸女群像・他』解説
『大坪砂男全集』第一巻 解説
中井英夫『幻想博物館』解説
中井英夫『悪夢の骨牌』書評
中井英夫について
中井さんのこと
埴谷雄高のデモノロギー――銅版画の雰囲気
ダンディズムとフランス料理
佐野洋『透明受胎』
澁澤龍彥編『暗黒のメルへン』編集後記
Ⅲ 仮面について――現代ミステリー映画論
『怪奇小説傑作集』第四巻 解説
私の好きなミステリー・ベスト10――ミステリー映画ベスト1
推理小説に関する381人の意見
犯罪文学者考
ミステリー関連の文章を集めた1冊。
I 私と推理小説――情熱あるいは中毒
推理小説とオカルティズム――小栗虫太郎を中心に
ミステリーにふける――AL’ESSENCE(本質を求めよ)
推理小説月旦―― 一九六〇年十月-六一年三月
Ⅱ ポオ(「古典案内」)
黄金虫
江戸川乱歩『パノラマ島奇談』解説
玩具愛好とユートピア――乱歩文学の本質
夢野久作の不思議
『夢野久作全集』第一巻
絢爛たる知的遊戯への招待――小栗虫太郎『黒死館殺人事件』
小栗虫太郎『黒死館殺人事件』解説
「小栗虫太郎・木々高太郎集」解説
『久生十蘭全集』第二巻の解説
スタイリスト十蘭
久生十蘭のこと
橘外男『青白き裸女群像・他』解説
『大坪砂男全集』第一巻 解説
中井英夫『幻想博物館』解説
中井英夫『悪夢の骨牌』書評
中井英夫について
中井さんのこと
埴谷雄高のデモノロギー――銅版画の雰囲気
ダンディズムとフランス料理
佐野洋『透明受胎』
澁澤龍彥編『暗黒のメルへン』編集後記
Ⅲ 仮面について――現代ミステリー映画論
『怪奇小説傑作集』第四巻 解説
私の好きなミステリー・ベスト10――ミステリー映画ベスト1
推理小説に関する381人の意見
犯罪文学者考
寺山修司の『恋愛辞典』を読んだ。
恋愛に関するエッセイや詩をコンパクトに集めた本。
以下、目次
プロローグ
恋愛論-きみが人生の時
愛の時刻表
人生万歳
たし算
ひき算
恋愛論
さよならのジャック
恋愛詩集-山羊にひかれて
家なき子
山羊にひかれて
ある日
愛する
十五歳
二人のことば
二人のための英語のお稽古
サ行二段活用恋愛形
ダイヤモンド Diamond
さよならという名の猫
私が死んでも
思い出すために
バラード-キスキス
樅の木の歌
二万四千回のキッス
ジョーカー・ジョー
少年歌集-麦藁帽子
美しき日々
頬燃ゆる
猟銃をもてる夫人
惑いの年
魔に憑かれて
失いし日の
恋愛エッセイ-恋人たちの城
自然のなかの兄と妹-ポールとヴィルジニー
娼婦とパリジャン-マルグリットとアルマン
水夫と港の女-セギャアルとテレーズ
船出した男とその妻-イノックとアンニ
ギャングとウェイトレス-ボニーとクライド
恋愛処方詩集-さよならだけが人生ならば
初恋の人が忘れられなかったら
妻のいる人を好きになったら
わかれた人がにくかったら
故郷の母のことを思い出したら
お月さましか話相手がいなかったら
海が好きだったら
四月生まれだったら
永遠にあこがれたら
孤独を忘れてしまいたかったら
幸福が遠すぎたら
恋物語-ポケットに恋唄を
砂に書いたラブレター
ポケットに恋唄を
いるかいないか
長距離歌手
(解説 裸足で恋を /白石征)
恋愛に関するエッセイや詩をコンパクトに集めた本。
以下、目次
プロローグ
恋愛論-きみが人生の時
愛の時刻表
人生万歳
たし算
ひき算
恋愛論
さよならのジャック
恋愛詩集-山羊にひかれて
家なき子
山羊にひかれて
ある日
愛する
十五歳
二人のことば
二人のための英語のお稽古
サ行二段活用恋愛形
ダイヤモンド Diamond
さよならという名の猫
私が死んでも
思い出すために
バラード-キスキス
樅の木の歌
二万四千回のキッス
ジョーカー・ジョー
少年歌集-麦藁帽子
美しき日々
頬燃ゆる
猟銃をもてる夫人
惑いの年
魔に憑かれて
失いし日の
恋愛エッセイ-恋人たちの城
自然のなかの兄と妹-ポールとヴィルジニー
娼婦とパリジャン-マルグリットとアルマン
水夫と港の女-セギャアルとテレーズ
船出した男とその妻-イノックとアンニ
ギャングとウェイトレス-ボニーとクライド
恋愛処方詩集-さよならだけが人生ならば
初恋の人が忘れられなかったら
妻のいる人を好きになったら
わかれた人がにくかったら
故郷の母のことを思い出したら
お月さましか話相手がいなかったら
海が好きだったら
四月生まれだったら
永遠にあこがれたら
孤独を忘れてしまいたかったら
幸福が遠すぎたら
恋物語-ポケットに恋唄を
砂に書いたラブレター
ポケットに恋唄を
いるかいないか
長距離歌手
(解説 裸足で恋を /白石征)
『十蘭ジュラネスク』
2013年12月25日 読書
久生十蘭の短編集『十蘭ジュラネスク』を読んだ。
全集が出ているので、全集を読むのが筋なのだが、重いので、最近出た文庫で、久生十蘭をちょびちょび読んだり再読だったりしていきたい。
本書に収録されていたのは、以下の作品。
「美国横断鉄路」はエディット・トレインの前に読んで、メルヘソの忘年会で内容とか話したら、おもいっきり、ひかれた。中国人を残虐に扱う話だったのである。(美国は、米国のこと)
「生霊」
「南部の鼻曲り」
「葡萄蔓の束」
「無惨やな」
「遣米日記」
「藤九郎の島」
「美国横断鉄路」
「影の人」
「その後」
「死亡通知」
全集が出ているので、全集を読むのが筋なのだが、重いので、最近出た文庫で、久生十蘭をちょびちょび読んだり再読だったりしていきたい。
本書に収録されていたのは、以下の作品。
「美国横断鉄路」はエディット・トレインの前に読んで、メルヘソの忘年会で内容とか話したら、おもいっきり、ひかれた。中国人を残虐に扱う話だったのである。(美国は、米国のこと)
「生霊」
「南部の鼻曲り」
「葡萄蔓の束」
「無惨やな」
「遣米日記」
「藤九郎の島」
「美国横断鉄路」
「影の人」
「その後」
「死亡通知」
『死美人』を読んだ。
これは、ガボリオのルコック探偵シリーズのパスティーシュとしてボアゴベが書いた小説を黒岩涙香が翻案した小説を江戸川乱歩が現代語に書き直した長編。
ガボリオ~ボアゴベ~黒岩涙香~江戸川乱歩というマトリョーシカみたいな作品。
波瀾万丈の紙芝居的ミステリーで、面白かった。ルコック探偵は、「零骨」という名前になっている。
以下、目次
深夜の紳士
スペードの女王
おしの訊問
零骨先生
老探偵の助言
おしの知恵
尾行
第二の死体
箱時計
奇襲
にせ使者
探偵の誓い
大いなる遺産
鳥羽の推理
青年紳士
血統さがし
生死の転轍
モルグの事件
死美人の写真
写真の持ち主
許婚者
怪しき行商人
類二郎の狼狽
買収
拘引
すばらしい報告
訊問(1)
訊問(2)
家宅捜索
密室のカード
意外な知らせ
老探偵の悲歎
零骨先生の決意
獄房の面会
告白
身分証明書
鳥羽の計画
準備完了
転轍手の話
怪しき馬車
痛烈な非難
チウレリー公園
老先生の失踪
公判開始
起訴状
事実審理
証拠調べ
恐ろしき手紙
証人尋問
痛ましき証人
論告を弁論
判決
印度の大守
耳よりの話
伴大佐事件
すばらしい鴨
黒眼鏡の男
神出鬼没
停車場にて
長蛇を逸す
重大な手掛り
発車
儲け口
俄か探偵
新方針
愛蘭の血統
珠子を狙うもの
迎えの男
訪問客
恐ろしい計画
誘拐
大守殿下の変装
峰井法律出張所
倉場の話
古い書類
系図の内容
事件の黒幕
劇場の密談
また出しぬかれました
鉄道の沿線が怪しい
大変な事実
曲者の名は?
謎の水車小屋
長老と青年
事態急迫
赤い旗白い旗
毒酒の計
地底の少女
水地獄
死刑執行迫る
九死に一生
署長の好意
類二郎の告白
事件の真相
その夜の出来事
もぬけのから
おしのゆくえ
燃ゆる悪魔
断頭台
危機一髪
大団円
あとがき/江戸川乱歩
「破天荒」について
「幽霊塔」の思出
「暗黒星」について
これは、ガボリオのルコック探偵シリーズのパスティーシュとしてボアゴベが書いた小説を黒岩涙香が翻案した小説を江戸川乱歩が現代語に書き直した長編。
ガボリオ~ボアゴベ~黒岩涙香~江戸川乱歩というマトリョーシカみたいな作品。
波瀾万丈の紙芝居的ミステリーで、面白かった。ルコック探偵は、「零骨」という名前になっている。
以下、目次
深夜の紳士
スペードの女王
おしの訊問
零骨先生
老探偵の助言
おしの知恵
尾行
第二の死体
箱時計
奇襲
にせ使者
探偵の誓い
大いなる遺産
鳥羽の推理
青年紳士
血統さがし
生死の転轍
モルグの事件
死美人の写真
写真の持ち主
許婚者
怪しき行商人
類二郎の狼狽
買収
拘引
すばらしい報告
訊問(1)
訊問(2)
家宅捜索
密室のカード
意外な知らせ
老探偵の悲歎
零骨先生の決意
獄房の面会
告白
身分証明書
鳥羽の計画
準備完了
転轍手の話
怪しき馬車
痛烈な非難
チウレリー公園
老先生の失踪
公判開始
起訴状
事実審理
証拠調べ
恐ろしき手紙
証人尋問
痛ましき証人
論告を弁論
判決
印度の大守
耳よりの話
伴大佐事件
すばらしい鴨
黒眼鏡の男
神出鬼没
停車場にて
長蛇を逸す
重大な手掛り
発車
儲け口
俄か探偵
新方針
愛蘭の血統
珠子を狙うもの
迎えの男
訪問客
恐ろしい計画
誘拐
大守殿下の変装
峰井法律出張所
倉場の話
古い書類
系図の内容
事件の黒幕
劇場の密談
また出しぬかれました
鉄道の沿線が怪しい
大変な事実
曲者の名は?
謎の水車小屋
長老と青年
事態急迫
赤い旗白い旗
毒酒の計
地底の少女
水地獄
死刑執行迫る
九死に一生
署長の好意
類二郎の告白
事件の真相
その夜の出来事
もぬけのから
おしのゆくえ
燃ゆる悪魔
断頭台
危機一髪
大団円
あとがき/江戸川乱歩
「破天荒」について
「幽霊塔」の思出
「暗黒星」について
ブラックウッドの『人間和声』を読んだ。1910年、ブラックウッド40歳のときの長篇。
「勇気と想像力ある秘書求む。当方は隠退した聖職者。テノールの声とヘブライ語の多少の知識を必須とす。独身者。浮世離れした人間であること」
という募集広告に応募した主人公の青年は、もとから「彼にとって名づけることは創造り出すことだった」というような人物であった。素養があった、ということか。彼はこの「秘書」に採用され、長い試用期間を経て徐々に明かされる、この募集の本来の意味のスケールのでかさに驚く。
おおざっぱに言えば、世界征服の呪文を完成させるために、彼との和声が必要とされていた、ということなのだが、昨日読了した『普遍音楽』とも通じるものがあって、面白かった。
以下、本書で語られる「名は体をあらわす」(雑なまとめかただけど、まあ、そんなもの)思想などについての引用を残しておこう。
名前の持つ現実感-真の名前の意味、誤った名前の滑稽さ、不正確な発音の残酷さをまったく感じなくなることはなかった。彼は知っていた。いつか遠い未来のある日、素晴らしい娘が自分の人生にあらわれ、自分の真の名前を音楽のように歌って、唇が子音と母音を生み出すにつれて、彼女の全人格がそれを表わし-そして自分は彼女を愛するだろう。自分の名前は滑稽で憎むべきものではあるけれども、彼女の声に応えて歌うだろう。二人は同じ和音の二つの楽音のように、お互いに必要なものとして、文字通り共に諧調を奏でるだろう
「真の名前を正しく発音することは、その生命そのものに参与し、その本質と共に振動し、その内奥の存在の窮極の秘密を知ることを意味する。」
「言葉は“存在”の帷である。それを真に語ることは、帷の片隅を持ち上げることである」
「我々はみな、宇宙が神に向かって歌う大いなる音楽の“音”なのだ」
「物の特質は『それをつくった“音”の圧し消された発声』にすぎない。物自体がその名前なんだ」
「偉大な“名前たち”を正確に発声すれば、それらの特殊な性質を自分の魂に呼び込み、かれらのように偉大な不滅の存在となり得ること」
「私が求めているのは、ある種の名前を正確に発音することだ-いや、ある名前をと言っておこう。この名前の性質はまことに複雑なので、単一の声では発声することができない。私には和音が必要なのだ。四つの声から成る人間の和音が」
「勇気と想像力ある秘書求む。当方は隠退した聖職者。テノールの声とヘブライ語の多少の知識を必須とす。独身者。浮世離れした人間であること」
という募集広告に応募した主人公の青年は、もとから「彼にとって名づけることは創造り出すことだった」というような人物であった。素養があった、ということか。彼はこの「秘書」に採用され、長い試用期間を経て徐々に明かされる、この募集の本来の意味のスケールのでかさに驚く。
おおざっぱに言えば、世界征服の呪文を完成させるために、彼との和声が必要とされていた、ということなのだが、昨日読了した『普遍音楽』とも通じるものがあって、面白かった。
以下、本書で語られる「名は体をあらわす」(雑なまとめかただけど、まあ、そんなもの)思想などについての引用を残しておこう。
名前の持つ現実感-真の名前の意味、誤った名前の滑稽さ、不正確な発音の残酷さをまったく感じなくなることはなかった。彼は知っていた。いつか遠い未来のある日、素晴らしい娘が自分の人生にあらわれ、自分の真の名前を音楽のように歌って、唇が子音と母音を生み出すにつれて、彼女の全人格がそれを表わし-そして自分は彼女を愛するだろう。自分の名前は滑稽で憎むべきものではあるけれども、彼女の声に応えて歌うだろう。二人は同じ和音の二つの楽音のように、お互いに必要なものとして、文字通り共に諧調を奏でるだろう
「真の名前を正しく発音することは、その生命そのものに参与し、その本質と共に振動し、その内奥の存在の窮極の秘密を知ることを意味する。」
「言葉は“存在”の帷である。それを真に語ることは、帷の片隅を持ち上げることである」
「我々はみな、宇宙が神に向かって歌う大いなる音楽の“音”なのだ」
「物の特質は『それをつくった“音”の圧し消された発声』にすぎない。物自体がその名前なんだ」
「偉大な“名前たち”を正確に発声すれば、それらの特殊な性質を自分の魂に呼び込み、かれらのように偉大な不滅の存在となり得ること」
「私が求めているのは、ある種の名前を正確に発音することだ-いや、ある名前をと言っておこう。この名前の性質はまことに複雑なので、単一の声では発声することができない。私には和音が必要なのだ。四つの声から成る人間の和音が」
アタナシウス・キルヒャーの『普遍音楽』(1650)を読んだ。
アンドレアス・ヒルシュ篇のドイツ語版を基にした翻訳で、ヒルシュ篇で割愛された部分は巻末に「補説」として掲載されており、本文でもラテン語版原著を参照、また図版を補ってまとめられている。
以下、目次
献辞
恵み深き読者へのまえがき
第一巻 解剖学
聴覚の卓越に関する前書き
第1章 音の定義
第2章 音の発生
第3章 音の主体
第4章 音を出す物体の性質
第5章 音のあらゆる種類
第6章 直接的な音の主原因
結果1 スコットランドの不思議な石
結果2 水中の音はどうか
結果3 自然界の真空
第7章 耳の解剖
第8章 内耳
第9章 内耳・外耳の用途と使用
第10章 体内の空気の性質
第11章 音の伸暢
第12章 声の性質と種類
結論
第13章 発声器官
第14章 様々に異なる声
結論1 声の大小の原因
結論2 声の声低の原因
結論3 粗い声や柔らかな声の原因
結論4 人間の声と楽器の比較
第15章 全ての動物の自然の声
1.ナマケモノの不思議な声
2.鳥の声
3.ナイチンゲールとその声
4.他の鳥の声
5.カエルの鳴き声
6.コオロギ、バッタ
第16章 音と声に関する諸問題
音響論補遺 身体の気質を音や声からどのようにして推測するのか
動物の声と人間の声に関する、音響判断の実験
第二巻 文献学
第1章 音楽の発明
第2章 音楽の分類
第3章 古代ヘブライ人とその音楽
1.ヘブライ人とそのネギノート
2.ヘブライ人の打楽器
3.ヘブライ人の気鳴楽器
4.ヘブライ人の笛
5.ヘブライ人の楽器の使用法
第4章 特にダビデの音楽
1.ダビデの歌と詩篇の詩句
2.詩篇の題名
3.詩篇の詩句のアクロスティック
4.詩篇のメロディーと形式
5.詩篇の様々な韻律
6.ヘブライ人の今日の音楽
第5章 ギリシア人の音楽とその楽器
1.ギリシア人に用いられた歌唱法
2.抒情詩のあらゆる歌い手
3.ギリシア人の楽器
4.ギリシア音楽の完成
第6章 今日のギリシア音楽
第三巻 楽器
第一部 絃楽器
第1章 絃の加工及び区別、性質、価値
結論
第2章 多絃楽器
1.クラヴィチェンバロ
2.単一の鍵盤
3.十七のパルムラを持つ楽器をどのように調絃すべきか
4.クラヴィチェンバロの絃の比率
5.クラヴィチェンバロに適したシンフォニア
第3章 リュート、マンドーラ、キターラ
1.リュートに張るべき絃 配列、位置、調絃
2.キターラ
3.ケリュスまたはヴィオラ
4.プサルテリウム
第二部 気鳴楽器、あるいは空気、風、息を吹き込んで鳴らす楽器
第1章 これらに分類されるもの
第2章 気鳴楽器の分類
1.三穴のフィストーラ〔笛〕
2.リトゥルス、コルナムーサ及び類似の楽器
第3章 オルガン その準備と特性
1.オルガンの各部分
2.オルガンの秘部
3.レジスター、通気孔、ふいご
4.動物の舌〔Zooglossa〕と人間の舌〔Anthropoglossa〕
第三部 クルーサあるいは打楽器
第1章 木材の音
どのようにクシュロルガヌムを作るかという実験
結論
猫オルガン
第2章 鐘とその使用法
エルフルトの大鐘
第3章 ティンパニー、シンバル及び同類の楽器
第四巻 比較 新旧の音楽、二種
第一部 問題提起
第1の問い ギリシア人の音楽はどのようなものであったか、そしてどの点が優れていたのか
1.謎に満ちた古代人の音楽
2.古代の神聖な音楽
第2の問い 古代人の楽器
第3の問い 古代人は多声で歌ったのかどうか、どのように作曲されたのか
第4の問い 古代人はどのような音符を用いたのか
第5の問い 古代の音楽は今日のものより完全で優れていたのか
1.新旧の声楽曲
2.新旧の多声音楽
3.新旧の器楽
第6の問い 音楽が力を持つのは何故、どのようにか 人間の感情を動かす、古代音楽の「驚きの仕掛け」について書かれていることは真実か否か
第7の問い ハルモニアの数がどのように情動を喚起するのか
第8の問い 種々の音が種々の心の状態を引き起こすかどうか、その原因は何か
第二部 実践論
第1章 多声音楽の考察と発展
第2章 教会歌唱の卓越
第3章 詩篇、聖歌、讃歌の違いはどのようなものか
第4章 グレゴリオ聖歌の卓越性とその誤った歌い方
第5章 多声音楽の誤った歌い方と歌手の不足
第6章 今日の作曲家の欠点と誤り
第三部 情動的音楽
第1章 どのように作るべきか
結論
第2章 旋法 その性質と情動への作用
第3章 情動的音楽 いつ、どこで行うのか
1.情動的音楽に適した場所
2・情動的音楽に適した時
第4章 情動的音楽それ自体 どのように作品化されるべきか
第5章 ハルモニアの様々な様式
第6章 あらゆる情動を動かす作曲をどのように行うのか
王による音楽についてのエピローグ
第五巻 魔術
第一部 自然哲学
第1章 音楽の持つ驚異的な作用
第2章 協和音と不協和音の性質と成立
音楽の実験
第3章 音楽が引き起こす感情の動き
音楽の実験 一方の絃が隔たっている他方の絃を動かす
第4章 音の共感と反感
音楽の実験
第二部 協和音と不協和音の魔術
治療術、すなわちどのようにして重病が音楽により治癒するのか
第1章 驚異の音楽による治療の原因
第2章 ダビデはどのようにして自らのハープを演奏してザウル王を悪魔から解放したのか
結論
第3章 音楽によって狂乱に陥ったデンマーク王をめぐる不思議な話
第4章 タランチュラと音楽の不可思議な治療
アプリアの蜘蛛、タランチュラに噛まれ、毒に中った人間
疑問1 タランチュラに取り憑かれた人間は、音楽以外の手段で治癒できないのは何故か
第5章 様々なタランチュラの様々な性質
疑問2 タランチュラに襲われた人間はなぜ幾つかの色を特に好み、喜びを見出すのか
疑問3 なぜタランチュラに襲われた者が驚くべき行動を見せるのか
第6章 音楽はどのようにして預言を起こすのか
第7章 音楽の幾つかの不思議な作用、また、音に有用となり得る物体あるいは害し得る物体
結論 ある年のある時期にマメルティン海で捕獲されたプシュピアという魚 もしくはメジキについて また、音楽は動物に対して力を持つのか
第8章 草木、植物、樹木、動物は音楽と結びついて、病気から恢復する自然の力を持つのかどうか
第三部 劇場の音楽
第1章 不思議な音の描写と分類
第2章 野原での叫び声やラッパの響きによってエリコの壁が崩壊したのは如何にしてか
第3章 ハーメルンの子どもたち 冒険のような連れ去りは笛によって起きたのか
第4章 幾つかの鐘の不思議な音
第5章 幾つかの音の隠れた原因、特に、フィンランドのスメレ洞穴の響き
第6章 スウェーデンの海岸の不思議な音
結論
第四部 音響の魔術
木霊の性質と不思議な作用
序1 音と光の類似性
結論
序2 反響体
序3 反響の媒体
結論
音響が屈折する比率
木霊の音響論 問題点
結論 変容した木霊が起こるのかどうか 別の言葉になった際、一回で聞き取れるのか
建築に仕組まれた聴覚の道具
実験1 音を増大させる管あるいはサイフォン
興味深い疑問 音が管の中に閉じ込められると、しばらくの間そこに留まることができるのかどうか
実験2 全く不思議なことに、細長い木材によって声は広がっていく
実験3 声は、直接発するよりも、丸く巻いた管や郵便ラッパを通した方がよく通り、しかも増大する
実験4 音は曲面に沿って進むと非常に強くなる
実験5 蝸牛状の管の中の声は螺旋状に曲がっているので、さらに大きな力強さを得る
反響の魔術
序1 ウィトゥルウィウスの劇場及びその不思議なエカエ
序2 ミラーノの邸宅の不思議な木霊 シモネッタと呼ばれる
序3 幾つかの不思議なエカエと反響する場所
課題1 どのようにして、難聴に役立つあらゆる有用な聴覚装置を造ったらよいのか
課題2 人はどのようにして自然の魔術を像に向けたらよいのか
これはあらゆる音を明瞭に、不明瞭に聞かせる
課題3 全ての言葉を繰り返す像をどのようにして作ったらよいのか
自然の魔術・要約
空中に浮かぶ像・あらゆる明瞭な音、不明瞭な音を完全に聞かせる像を作ることができるかどうか
第五部 奇蹟論の学智
あらゆる自動楽器-自動で音が鳴るもの-をどのように作るべきか
課題1 風室をどのように作るべきか
課題2 水力で動くふいごを用いて水オルガンにどのように強い風を送ればよいのか
課題3 どのように音調シリンダーを作ればよいのか
道具1 古代人、特にウィトゥルウィスの水力オルガン
道具2 音を出す水力オルガンをどのように作ればよいのか
道具3 ひとりでに音を発する自動打鐘装置をどのように作ればよいのか
道具4 フルダの塔に掛かっているツィンベル・シュテルンの描写
かつては黄金の車輪と呼ばれていた
道具5 クラヴチェンバロをどのように作ったらよいのか
それ本来の音とケリュスや絃のハルモニアを聞かせることができる
道具6 あらゆる楽器-ケリュス・ハープ・リュート・ティオルバ・クラヴィチェンバロ・オルガン・レーガルなど-の音と調和を聴かせる楽器を作るにはどのようにしたらよいか
道具7 特定の鳥の声を作るにはどのようにしたらよいか
道具8 ピュータゴラースの鍛冶屋の自動音楽を比率に従って表現するにはどうしたらよいか
三人の鍛冶職人が鉄床を打つ
道具9 ふいごも車輪もシリンダーも持たず、自然の風と空気だけでひとりでに鳴るハルモニアの装置をどのように作ったらよいか
道具10 共鳴の音楽をどのように作ればよいのか
あるいは、共鳴するだけでハルモニア的な音を自ら発する楽器をどのように作ったらよいか
実験1 ガラスを使って、触れていない絃をどのように鳴らすか
実験2 大鐘が鳴っているように錯覚させるにはどうするか
実験3 音の聞こえない人がどのようにして音楽を聴くことができるのか
第六部 音楽の隠匿術、秘密の記譜法
遠く離れた良き友人たちに、秘めた心や考えを音によって伝えるにはどのようにするか
1.音楽の隠匿術
2.秘密の記譜法
第六巻 類比 自然のデカコルドンすなわち十管の楽器
まえがき
第一部 十管の楽器
神はオルガン奏者であるから、世界はオルガンと比較される
全能の創造者としての神は、賢明なオルガン奏者が驚嘆すべき演奏をするがごとく
六日間でどのように被造物を作り上げたのか
世界オルガンの六つの大レジスター-六日間の日々の仕事に従って
レジスター1 あるいは四元素の調和
四元素の調和
レジスター2 天上のシンフォニー
1.天体同士の素晴らしい類似
2.そもそも天体のどこに音楽のハルモニアがあるのか
3.土星の運動
4.木星の運動
5.火星の運動
6.コロスの歌-天上界の恒星のハルモニア
レジスター3 石、草木、動物の天とのシンフォニー
1.特に石、植物、動物
2.あらゆる事物のハルモニア的調和
交感による世界音楽-十のエンネアコルドにおいて全自然界のシンフォニーが表象される
3.自然魔術
自然魔術に適合する実地の規範-様々な自然物をハルモニア的に組み合わせる際に留意すべきだ
規範1
規範2
規範3 キミア
規範4 植物学、ハルモニアの治療術
規範5 医学
1.治療術 ハルモニアの原則
2.あらゆる病気治療の本質、ヒュポクラテースの意見による
3.ハルモニア的な繋がりについて、医者はよく注意すべきである
4.あらゆる物のハルモニア的比率
5.ハルモニア的比率の、様々な実例への適用
レジスター4 人間の音楽、あるいは大・小世界の照応
1.人間の病気の特徴
2.人体の各部分のハルモニア的比率
3.小世界内部のハルモニア
4.天上界や根源世界に対して、小世界の敏感に聞き取れるハルモニア及び音楽
5.動物における繊細なハルモニア
レジスター5 脈のハルモニアと人体の脈の動き
1.特別な脈
2.脈搏のリズムすなわちハルモニア
3.様々な年代の均等なリズムとハルモニア
4.気候、空気、土地、季節の違いによる脈搏のハルモニア
5.人間の五感のハルモニア的一致
レジスター6 感情の調和、あるいは様々な感情が織り成すハルモニア
脈から知り得る幾つかの情動
1.愛の音楽
2.ハルモニア的な愛の魅惑
結論1
結論2 愛の不思議な力と、その自然な傾向
結論3 相反するコンプレクシオ同士の者の愛
結論4 愛する者同士の間で、蒼白な顔色や憂鬱が生じるのはどこからか
結論5 愛の病を音楽でどのように癒すか
3.理性的慾求のハルモニア
4.いかにして魂の完全とそのハルモニア的比率に到達すればよいのか
レジスター7 統治界の調和性、統治の世界音楽
1.三つの数学的比率 いかにしてそれが世俗の支配の三つの状態につながるのか
結論
2.あらゆる不協和音を相殺して、幸福な統治をどのように行うべきか
3.称讃に価する統治のモデル
レジスター8 ハルモニア的形而上学
1.魂の構成
2.数字と魂が合成されることの論証
3.ハルモニア的、及び幾何学的比較
4.数字の1が同時に全であるのは如何にしてか
5.対象に影響力を持つハルモニア
レジスター9 天使の音楽とハルモニア
1.天使と人間の理性をハルモニアから比較する-自身に対して、世界に対して
2.全ての事物の創造の順序あるいは大世界の鏡
3.知覚できない天使の音楽
4.魂のハルモニア四種、あるいは四つの一体化
5.4という数字に隠されたハルモニア
6.天使界と天使の位階
レジスター10にして最終 神の音楽、あるいは神と地上世界との調和
1.神と人間の間のハルモニア
2.創造によらない単一は、多の中にどのようにして流出するのか
創造された事物の中から三位一体は如何にして現れ出るのか
3.神の三位一体の、天使の合唱を伴う調和した音楽-そして一すなわち神は全の中の全である
4.聖なる三位一体のハルモニア
5.三位一体と天使自身とのハルモニア
6.我々人間は天使の位階に従い、如何にして上昇していくのか、そして如何にして神と一体となるのか
7.畜生が人間を恐れ、家臣が君主を恐れるのはなぜか
8.天使の合唱の幾つかの特別な作用
9.天使はどのようにして天上の音楽を指揮するのか
10.天上のエンネアスまたは「九」のハルモニア
あるいは階層または天使の天上界の九の序列
11.下方のエンネアスのハルモニアと天使のハルモニア
最後の結論 先に述べた、隠された音楽の秘密の繰り返し
人間は如何にして天上の音楽について全智たるのか
補説1 比率と音楽
補説2 古代ギリシアの音階
補説3 音程を幾何学的に求める
補説4 音算箱
補説5 様々な回転面を用いて反響板を作成する
補足図版
参考文献
書名索引
主要人名索引
事項索引
訳者あとがき
アンドレアス・ヒルシュ篇のドイツ語版を基にした翻訳で、ヒルシュ篇で割愛された部分は巻末に「補説」として掲載されており、本文でもラテン語版原著を参照、また図版を補ってまとめられている。
以下、目次
献辞
恵み深き読者へのまえがき
第一巻 解剖学
聴覚の卓越に関する前書き
第1章 音の定義
第2章 音の発生
第3章 音の主体
第4章 音を出す物体の性質
第5章 音のあらゆる種類
第6章 直接的な音の主原因
結果1 スコットランドの不思議な石
結果2 水中の音はどうか
結果3 自然界の真空
第7章 耳の解剖
第8章 内耳
第9章 内耳・外耳の用途と使用
第10章 体内の空気の性質
第11章 音の伸暢
第12章 声の性質と種類
結論
第13章 発声器官
第14章 様々に異なる声
結論1 声の大小の原因
結論2 声の声低の原因
結論3 粗い声や柔らかな声の原因
結論4 人間の声と楽器の比較
第15章 全ての動物の自然の声
1.ナマケモノの不思議な声
2.鳥の声
3.ナイチンゲールとその声
4.他の鳥の声
5.カエルの鳴き声
6.コオロギ、バッタ
第16章 音と声に関する諸問題
音響論補遺 身体の気質を音や声からどのようにして推測するのか
動物の声と人間の声に関する、音響判断の実験
第二巻 文献学
第1章 音楽の発明
第2章 音楽の分類
第3章 古代ヘブライ人とその音楽
1.ヘブライ人とそのネギノート
2.ヘブライ人の打楽器
3.ヘブライ人の気鳴楽器
4.ヘブライ人の笛
5.ヘブライ人の楽器の使用法
第4章 特にダビデの音楽
1.ダビデの歌と詩篇の詩句
2.詩篇の題名
3.詩篇の詩句のアクロスティック
4.詩篇のメロディーと形式
5.詩篇の様々な韻律
6.ヘブライ人の今日の音楽
第5章 ギリシア人の音楽とその楽器
1.ギリシア人に用いられた歌唱法
2.抒情詩のあらゆる歌い手
3.ギリシア人の楽器
4.ギリシア音楽の完成
第6章 今日のギリシア音楽
第三巻 楽器
第一部 絃楽器
第1章 絃の加工及び区別、性質、価値
結論
第2章 多絃楽器
1.クラヴィチェンバロ
2.単一の鍵盤
3.十七のパルムラを持つ楽器をどのように調絃すべきか
4.クラヴィチェンバロの絃の比率
5.クラヴィチェンバロに適したシンフォニア
第3章 リュート、マンドーラ、キターラ
1.リュートに張るべき絃 配列、位置、調絃
2.キターラ
3.ケリュスまたはヴィオラ
4.プサルテリウム
第二部 気鳴楽器、あるいは空気、風、息を吹き込んで鳴らす楽器
第1章 これらに分類されるもの
第2章 気鳴楽器の分類
1.三穴のフィストーラ〔笛〕
2.リトゥルス、コルナムーサ及び類似の楽器
第3章 オルガン その準備と特性
1.オルガンの各部分
2.オルガンの秘部
3.レジスター、通気孔、ふいご
4.動物の舌〔Zooglossa〕と人間の舌〔Anthropoglossa〕
第三部 クルーサあるいは打楽器
第1章 木材の音
どのようにクシュロルガヌムを作るかという実験
結論
猫オルガン
第2章 鐘とその使用法
エルフルトの大鐘
第3章 ティンパニー、シンバル及び同類の楽器
第四巻 比較 新旧の音楽、二種
第一部 問題提起
第1の問い ギリシア人の音楽はどのようなものであったか、そしてどの点が優れていたのか
1.謎に満ちた古代人の音楽
2.古代の神聖な音楽
第2の問い 古代人の楽器
第3の問い 古代人は多声で歌ったのかどうか、どのように作曲されたのか
第4の問い 古代人はどのような音符を用いたのか
第5の問い 古代の音楽は今日のものより完全で優れていたのか
1.新旧の声楽曲
2.新旧の多声音楽
3.新旧の器楽
第6の問い 音楽が力を持つのは何故、どのようにか 人間の感情を動かす、古代音楽の「驚きの仕掛け」について書かれていることは真実か否か
第7の問い ハルモニアの数がどのように情動を喚起するのか
第8の問い 種々の音が種々の心の状態を引き起こすかどうか、その原因は何か
第二部 実践論
第1章 多声音楽の考察と発展
第2章 教会歌唱の卓越
第3章 詩篇、聖歌、讃歌の違いはどのようなものか
第4章 グレゴリオ聖歌の卓越性とその誤った歌い方
第5章 多声音楽の誤った歌い方と歌手の不足
第6章 今日の作曲家の欠点と誤り
第三部 情動的音楽
第1章 どのように作るべきか
結論
第2章 旋法 その性質と情動への作用
第3章 情動的音楽 いつ、どこで行うのか
1.情動的音楽に適した場所
2・情動的音楽に適した時
第4章 情動的音楽それ自体 どのように作品化されるべきか
第5章 ハルモニアの様々な様式
第6章 あらゆる情動を動かす作曲をどのように行うのか
王による音楽についてのエピローグ
第五巻 魔術
第一部 自然哲学
第1章 音楽の持つ驚異的な作用
第2章 協和音と不協和音の性質と成立
音楽の実験
第3章 音楽が引き起こす感情の動き
音楽の実験 一方の絃が隔たっている他方の絃を動かす
第4章 音の共感と反感
音楽の実験
第二部 協和音と不協和音の魔術
治療術、すなわちどのようにして重病が音楽により治癒するのか
第1章 驚異の音楽による治療の原因
第2章 ダビデはどのようにして自らのハープを演奏してザウル王を悪魔から解放したのか
結論
第3章 音楽によって狂乱に陥ったデンマーク王をめぐる不思議な話
第4章 タランチュラと音楽の不可思議な治療
アプリアの蜘蛛、タランチュラに噛まれ、毒に中った人間
疑問1 タランチュラに取り憑かれた人間は、音楽以外の手段で治癒できないのは何故か
第5章 様々なタランチュラの様々な性質
疑問2 タランチュラに襲われた人間はなぜ幾つかの色を特に好み、喜びを見出すのか
疑問3 なぜタランチュラに襲われた者が驚くべき行動を見せるのか
第6章 音楽はどのようにして預言を起こすのか
第7章 音楽の幾つかの不思議な作用、また、音に有用となり得る物体あるいは害し得る物体
結論 ある年のある時期にマメルティン海で捕獲されたプシュピアという魚 もしくはメジキについて また、音楽は動物に対して力を持つのか
第8章 草木、植物、樹木、動物は音楽と結びついて、病気から恢復する自然の力を持つのかどうか
第三部 劇場の音楽
第1章 不思議な音の描写と分類
第2章 野原での叫び声やラッパの響きによってエリコの壁が崩壊したのは如何にしてか
第3章 ハーメルンの子どもたち 冒険のような連れ去りは笛によって起きたのか
第4章 幾つかの鐘の不思議な音
第5章 幾つかの音の隠れた原因、特に、フィンランドのスメレ洞穴の響き
第6章 スウェーデンの海岸の不思議な音
結論
第四部 音響の魔術
木霊の性質と不思議な作用
序1 音と光の類似性
結論
序2 反響体
序3 反響の媒体
結論
音響が屈折する比率
木霊の音響論 問題点
結論 変容した木霊が起こるのかどうか 別の言葉になった際、一回で聞き取れるのか
建築に仕組まれた聴覚の道具
実験1 音を増大させる管あるいはサイフォン
興味深い疑問 音が管の中に閉じ込められると、しばらくの間そこに留まることができるのかどうか
実験2 全く不思議なことに、細長い木材によって声は広がっていく
実験3 声は、直接発するよりも、丸く巻いた管や郵便ラッパを通した方がよく通り、しかも増大する
実験4 音は曲面に沿って進むと非常に強くなる
実験5 蝸牛状の管の中の声は螺旋状に曲がっているので、さらに大きな力強さを得る
反響の魔術
序1 ウィトゥルウィウスの劇場及びその不思議なエカエ
序2 ミラーノの邸宅の不思議な木霊 シモネッタと呼ばれる
序3 幾つかの不思議なエカエと反響する場所
課題1 どのようにして、難聴に役立つあらゆる有用な聴覚装置を造ったらよいのか
課題2 人はどのようにして自然の魔術を像に向けたらよいのか
これはあらゆる音を明瞭に、不明瞭に聞かせる
課題3 全ての言葉を繰り返す像をどのようにして作ったらよいのか
自然の魔術・要約
空中に浮かぶ像・あらゆる明瞭な音、不明瞭な音を完全に聞かせる像を作ることができるかどうか
第五部 奇蹟論の学智
あらゆる自動楽器-自動で音が鳴るもの-をどのように作るべきか
課題1 風室をどのように作るべきか
課題2 水力で動くふいごを用いて水オルガンにどのように強い風を送ればよいのか
課題3 どのように音調シリンダーを作ればよいのか
道具1 古代人、特にウィトゥルウィスの水力オルガン
道具2 音を出す水力オルガンをどのように作ればよいのか
道具3 ひとりでに音を発する自動打鐘装置をどのように作ればよいのか
道具4 フルダの塔に掛かっているツィンベル・シュテルンの描写
かつては黄金の車輪と呼ばれていた
道具5 クラヴチェンバロをどのように作ったらよいのか
それ本来の音とケリュスや絃のハルモニアを聞かせることができる
道具6 あらゆる楽器-ケリュス・ハープ・リュート・ティオルバ・クラヴィチェンバロ・オルガン・レーガルなど-の音と調和を聴かせる楽器を作るにはどのようにしたらよいか
道具7 特定の鳥の声を作るにはどのようにしたらよいか
道具8 ピュータゴラースの鍛冶屋の自動音楽を比率に従って表現するにはどうしたらよいか
三人の鍛冶職人が鉄床を打つ
道具9 ふいごも車輪もシリンダーも持たず、自然の風と空気だけでひとりでに鳴るハルモニアの装置をどのように作ったらよいか
道具10 共鳴の音楽をどのように作ればよいのか
あるいは、共鳴するだけでハルモニア的な音を自ら発する楽器をどのように作ったらよいか
実験1 ガラスを使って、触れていない絃をどのように鳴らすか
実験2 大鐘が鳴っているように錯覚させるにはどうするか
実験3 音の聞こえない人がどのようにして音楽を聴くことができるのか
第六部 音楽の隠匿術、秘密の記譜法
遠く離れた良き友人たちに、秘めた心や考えを音によって伝えるにはどのようにするか
1.音楽の隠匿術
2.秘密の記譜法
第六巻 類比 自然のデカコルドンすなわち十管の楽器
まえがき
第一部 十管の楽器
神はオルガン奏者であるから、世界はオルガンと比較される
全能の創造者としての神は、賢明なオルガン奏者が驚嘆すべき演奏をするがごとく
六日間でどのように被造物を作り上げたのか
世界オルガンの六つの大レジスター-六日間の日々の仕事に従って
レジスター1 あるいは四元素の調和
四元素の調和
レジスター2 天上のシンフォニー
1.天体同士の素晴らしい類似
2.そもそも天体のどこに音楽のハルモニアがあるのか
3.土星の運動
4.木星の運動
5.火星の運動
6.コロスの歌-天上界の恒星のハルモニア
レジスター3 石、草木、動物の天とのシンフォニー
1.特に石、植物、動物
2.あらゆる事物のハルモニア的調和
交感による世界音楽-十のエンネアコルドにおいて全自然界のシンフォニーが表象される
3.自然魔術
自然魔術に適合する実地の規範-様々な自然物をハルモニア的に組み合わせる際に留意すべきだ
規範1
規範2
規範3 キミア
規範4 植物学、ハルモニアの治療術
規範5 医学
1.治療術 ハルモニアの原則
2.あらゆる病気治療の本質、ヒュポクラテースの意見による
3.ハルモニア的な繋がりについて、医者はよく注意すべきである
4.あらゆる物のハルモニア的比率
5.ハルモニア的比率の、様々な実例への適用
レジスター4 人間の音楽、あるいは大・小世界の照応
1.人間の病気の特徴
2.人体の各部分のハルモニア的比率
3.小世界内部のハルモニア
4.天上界や根源世界に対して、小世界の敏感に聞き取れるハルモニア及び音楽
5.動物における繊細なハルモニア
レジスター5 脈のハルモニアと人体の脈の動き
1.特別な脈
2.脈搏のリズムすなわちハルモニア
3.様々な年代の均等なリズムとハルモニア
4.気候、空気、土地、季節の違いによる脈搏のハルモニア
5.人間の五感のハルモニア的一致
レジスター6 感情の調和、あるいは様々な感情が織り成すハルモニア
脈から知り得る幾つかの情動
1.愛の音楽
2.ハルモニア的な愛の魅惑
結論1
結論2 愛の不思議な力と、その自然な傾向
結論3 相反するコンプレクシオ同士の者の愛
結論4 愛する者同士の間で、蒼白な顔色や憂鬱が生じるのはどこからか
結論5 愛の病を音楽でどのように癒すか
3.理性的慾求のハルモニア
4.いかにして魂の完全とそのハルモニア的比率に到達すればよいのか
レジスター7 統治界の調和性、統治の世界音楽
1.三つの数学的比率 いかにしてそれが世俗の支配の三つの状態につながるのか
結論
2.あらゆる不協和音を相殺して、幸福な統治をどのように行うべきか
3.称讃に価する統治のモデル
レジスター8 ハルモニア的形而上学
1.魂の構成
2.数字と魂が合成されることの論証
3.ハルモニア的、及び幾何学的比較
4.数字の1が同時に全であるのは如何にしてか
5.対象に影響力を持つハルモニア
レジスター9 天使の音楽とハルモニア
1.天使と人間の理性をハルモニアから比較する-自身に対して、世界に対して
2.全ての事物の創造の順序あるいは大世界の鏡
3.知覚できない天使の音楽
4.魂のハルモニア四種、あるいは四つの一体化
5.4という数字に隠されたハルモニア
6.天使界と天使の位階
レジスター10にして最終 神の音楽、あるいは神と地上世界との調和
1.神と人間の間のハルモニア
2.創造によらない単一は、多の中にどのようにして流出するのか
創造された事物の中から三位一体は如何にして現れ出るのか
3.神の三位一体の、天使の合唱を伴う調和した音楽-そして一すなわち神は全の中の全である
4.聖なる三位一体のハルモニア
5.三位一体と天使自身とのハルモニア
6.我々人間は天使の位階に従い、如何にして上昇していくのか、そして如何にして神と一体となるのか
7.畜生が人間を恐れ、家臣が君主を恐れるのはなぜか
8.天使の合唱の幾つかの特別な作用
9.天使はどのようにして天上の音楽を指揮するのか
10.天上のエンネアスまたは「九」のハルモニア
あるいは階層または天使の天上界の九の序列
11.下方のエンネアスのハルモニアと天使のハルモニア
最後の結論 先に述べた、隠された音楽の秘密の繰り返し
人間は如何にして天上の音楽について全智たるのか
補説1 比率と音楽
補説2 古代ギリシアの音階
補説3 音程を幾何学的に求める
補説4 音算箱
補説5 様々な回転面を用いて反響板を作成する
補足図版
参考文献
書名索引
主要人名索引
事項索引
訳者あとがき
『テリブル・ダークネス~カルトアートの恐怖の回廊 (禁断異系の美術館EX) 』
2013年12月12日 読書
相馬俊樹の『テリブル・ダークネス~カルトアートの恐怖の回廊 (禁断異系の美術館EX) 』を読んだ。
1部は 現代作家、2部は、古典的な名作。
カタログとして便利だけど、これで見るかぎり、現代の作家さん、負けてるな。
こういうカルト的なアートを見てよく思うのは、興味あるのは、作家のほうだな、ということだ。作家の面白さあっての、作品の面白さだ、と感じる。もちろん、箸にも棒にもかからない作品など論外だけど、なんてことない作品でも、作家が面白ければ、また興味もわこうというものだ。本書に関して言えば、写真があるにもかかわらず、作品の内容を描写してくれている紙幅が、すごくもったいない気がした。
1.暗冥の回廊
サンティアゴ・カルーゾ――凍結された悪夢
オリビエ・ド・サガザン――腐乱の肉衣を纏って暗黒のダンス
マット・ヒューズ――デカダンスの亡霊たち
ブディ・ネスター――奇怪極まる驚異の肖像画
フレッド・エィナウディ――戦慄美のノスタルジー
カール・パーソン――未来のダーク・エロティシズム
レイ・ドンリィ――聖人たちの不気味なる沈黙
エリザベス・マグラス――グロテスクと奇想の聖骨箱
タニア・コヴァーツ――呪物の漂う容器
チャールズ・プファール――テリブル・マザーのヴァギナ・デンタータ
ダニー・マルブーフ――融合異体の悦楽郷
2.恐怖と逸楽の回廊
妖婦とゾンビが手を結ぶ……ハンス・バルドゥング《イブ、蛇、そして死》
未成熟の官能美……ルーカス・クラナッハの裸婦
冷たいエロス……フォンテーヌブロー派の裸婦
狂乱の宴……ゴヤ《魔宴》
絶望の深淵……ミケランジェロ《最後の審判》
生き埋めという究極の拷問……ハリー・クラーク《早すぎた埋葬》
少女の恐怖と蠱惑……イリナ・イオネスコによるエヴァのヌード
腐肉と鮮血でメメント・モリ……マーク・プレント
聖痛美の沈黙……カニグリア
明晰夢の誘惑……ポール・デルヴォー
広大なる魔術的風景……レオノーラ・キャリントンとレメディオス・バロ
1部は 現代作家、2部は、古典的な名作。
カタログとして便利だけど、これで見るかぎり、現代の作家さん、負けてるな。
こういうカルト的なアートを見てよく思うのは、興味あるのは、作家のほうだな、ということだ。作家の面白さあっての、作品の面白さだ、と感じる。もちろん、箸にも棒にもかからない作品など論外だけど、なんてことない作品でも、作家が面白ければ、また興味もわこうというものだ。本書に関して言えば、写真があるにもかかわらず、作品の内容を描写してくれている紙幅が、すごくもったいない気がした。
1.暗冥の回廊
サンティアゴ・カルーゾ――凍結された悪夢
オリビエ・ド・サガザン――腐乱の肉衣を纏って暗黒のダンス
マット・ヒューズ――デカダンスの亡霊たち
ブディ・ネスター――奇怪極まる驚異の肖像画
フレッド・エィナウディ――戦慄美のノスタルジー
カール・パーソン――未来のダーク・エロティシズム
レイ・ドンリィ――聖人たちの不気味なる沈黙
エリザベス・マグラス――グロテスクと奇想の聖骨箱
タニア・コヴァーツ――呪物の漂う容器
チャールズ・プファール――テリブル・マザーのヴァギナ・デンタータ
ダニー・マルブーフ――融合異体の悦楽郷
2.恐怖と逸楽の回廊
妖婦とゾンビが手を結ぶ……ハンス・バルドゥング《イブ、蛇、そして死》
未成熟の官能美……ルーカス・クラナッハの裸婦
冷たいエロス……フォンテーヌブロー派の裸婦
狂乱の宴……ゴヤ《魔宴》
絶望の深淵……ミケランジェロ《最後の審判》
生き埋めという究極の拷問……ハリー・クラーク《早すぎた埋葬》
少女の恐怖と蠱惑……イリナ・イオネスコによるエヴァのヌード
腐肉と鮮血でメメント・モリ……マーク・プレント
聖痛美の沈黙……カニグリア
明晰夢の誘惑……ポール・デルヴォー
広大なる魔術的風景……レオノーラ・キャリントンとレメディオス・バロ
R・A・ラファティの第四長編『第四の館』(1969年)を読んだ。なに、これ、すごすぎる!
新聞記者フレッド・フォーリーは、とんでもないことに気づいた。
政界の大物、オーヴァーラークは、実は中世イスラム(500年ほど前)、マムルーク朝のカー・イブン・モッドなのではないだろうか!『中世の歴史』に載っているカー・イブン・モッドの木彫りの像が、オーヴァーラークそっくりなだけでなく、カー・イブン・モッドが死んだとはどこにも書いていないのだ!
その後、人類を超えた存在になろうとする集団たちの暗躍に巻き込まれたフレディは、あちこちから陰謀論を集められる、「陰謀論のセンター」的存在になっていく。
いわく、
「低周波の影響で歯茎がゆるくなると思いこんだグループがあったよ。連中は超低音を使った音楽に強く抗議し、猛烈に反対運動をくりひろげて『グープ・ボックス』とかいったコイン式の機械を襲撃して壊したりした。しまいに軍隊の『葬送ラッパ』から低い音をいくつか抜こうとした」
あるいは、次のようなことを信じる3人の蒸気機関車の機関士
「寂しい夜には汽笛に答える巨大飛行生物がいる」「その生き物は列車をまるごと持ち上げられるほど大きくはないが、機関車1台で走っていたら持ち上げられる」「蒸気機関車の行方不明事件はそいつが原因なのだ」「巨大飛行生物は汽笛を求愛行動だと信じている」
あるいは、
「すべての赤毛女は、人類と交雑して面倒と破壊を撒き散らすために外宇宙からやってきた宇宙生物だ」
あるいは、
「おみくじクッキーの格言や教訓は、実はチベット奥地に住む悪の親玉が送ってくる邪悪な暗号だ」
あるいは、
「白いオークの木は人食いで、理由なく姿を消した人は、みな白いオークの木のそばで行方不明になっているはずだ」「オーク材はきわめて危険な成分を含んでいるので、オーク材を大量に使用する家具工場の従業員には規制を加えるべきだ」
あるいは、こんな新しい伝染病
「死の波動が訪れて、最初は鼻がムズムズし、それから倦怠感といらつき、やがて眠気に襲われ、最終的に死にいたる」「そのすべてが5時間で進行する」「それを伝染させる細菌は遊糸か、ハコヤナギの木から飛んだ綿で、もっともありそうな説としてはそうしたものに似た、外世界からやってきた何かに乗って運ばれる」
これらの、与太話を、フレディは、疑うことなく、まずは信じ込んでしまうのだ。
本書の表紙に描かれた四種類の動物は、「城の外」で戦う4つの超自然的集団のそれぞれの象徴である。その4つは、ヒキガエル、大蛇、鷹、アナグマ。この4つは、四福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)の象徴「テトラモルフ」(四形態)に対応している、という。
クライマックスでは、街に疫病が蔓延して、暴動が起る。『クロコディル』ではフランス革命の騒動が作中に反映していたが、この『第四の館』では1968年の五月革命が影響しているようだ。
以下、目次。
第1章 おれはこの手で世界を引き裂くぞ
第2章 すっごく死んでるか、すっごく年取ってるか
第3章 あいつらにも殺せるかもしれないが、おれはもっと惨たらしく殺せるぞ
第4章 山上の嘘吐き
第5章 螺旋状の情熱と聖人のごときセクシーダイナマイト
第6章 使われざる力の復讐
第7章 優美な犬どもと再帰者たち
第8章 あなたの喉のライン、なめらかな動き
第9章 だが、おれは奴らをたいらげるぞ、フェデリコ、おれは奴らをたいらげる
第10章 そんなに怖がるなんて、か弱い体の持ち主でもあるまいし
第11章 「おまえを呼んではおらん」と主は言われた
第12章 第四の館
第13章 そしてすべての怪物たちが立ちあがる
新聞記者フレッド・フォーリーは、とんでもないことに気づいた。
政界の大物、オーヴァーラークは、実は中世イスラム(500年ほど前)、マムルーク朝のカー・イブン・モッドなのではないだろうか!『中世の歴史』に載っているカー・イブン・モッドの木彫りの像が、オーヴァーラークそっくりなだけでなく、カー・イブン・モッドが死んだとはどこにも書いていないのだ!
その後、人類を超えた存在になろうとする集団たちの暗躍に巻き込まれたフレディは、あちこちから陰謀論を集められる、「陰謀論のセンター」的存在になっていく。
いわく、
「低周波の影響で歯茎がゆるくなると思いこんだグループがあったよ。連中は超低音を使った音楽に強く抗議し、猛烈に反対運動をくりひろげて『グープ・ボックス』とかいったコイン式の機械を襲撃して壊したりした。しまいに軍隊の『葬送ラッパ』から低い音をいくつか抜こうとした」
あるいは、次のようなことを信じる3人の蒸気機関車の機関士
「寂しい夜には汽笛に答える巨大飛行生物がいる」「その生き物は列車をまるごと持ち上げられるほど大きくはないが、機関車1台で走っていたら持ち上げられる」「蒸気機関車の行方不明事件はそいつが原因なのだ」「巨大飛行生物は汽笛を求愛行動だと信じている」
あるいは、
「すべての赤毛女は、人類と交雑して面倒と破壊を撒き散らすために外宇宙からやってきた宇宙生物だ」
あるいは、
「おみくじクッキーの格言や教訓は、実はチベット奥地に住む悪の親玉が送ってくる邪悪な暗号だ」
あるいは、
「白いオークの木は人食いで、理由なく姿を消した人は、みな白いオークの木のそばで行方不明になっているはずだ」「オーク材はきわめて危険な成分を含んでいるので、オーク材を大量に使用する家具工場の従業員には規制を加えるべきだ」
あるいは、こんな新しい伝染病
「死の波動が訪れて、最初は鼻がムズムズし、それから倦怠感といらつき、やがて眠気に襲われ、最終的に死にいたる」「そのすべてが5時間で進行する」「それを伝染させる細菌は遊糸か、ハコヤナギの木から飛んだ綿で、もっともありそうな説としてはそうしたものに似た、外世界からやってきた何かに乗って運ばれる」
これらの、与太話を、フレディは、疑うことなく、まずは信じ込んでしまうのだ。
本書の表紙に描かれた四種類の動物は、「城の外」で戦う4つの超自然的集団のそれぞれの象徴である。その4つは、ヒキガエル、大蛇、鷹、アナグマ。この4つは、四福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)の象徴「テトラモルフ」(四形態)に対応している、という。
クライマックスでは、街に疫病が蔓延して、暴動が起る。『クロコディル』ではフランス革命の騒動が作中に反映していたが、この『第四の館』では1968年の五月革命が影響しているようだ。
以下、目次。
第1章 おれはこの手で世界を引き裂くぞ
第2章 すっごく死んでるか、すっごく年取ってるか
第3章 あいつらにも殺せるかもしれないが、おれはもっと惨たらしく殺せるぞ
第4章 山上の嘘吐き
第5章 螺旋状の情熱と聖人のごときセクシーダイナマイト
第6章 使われざる力の復讐
第7章 優美な犬どもと再帰者たち
第8章 あなたの喉のライン、なめらかな動き
第9章 だが、おれは奴らをたいらげるぞ、フェデリコ、おれは奴らをたいらげる
第10章 そんなに怖がるなんて、か弱い体の持ち主でもあるまいし
第11章 「おまえを呼んではおらん」と主は言われた
第12章 第四の館
第13章 そしてすべての怪物たちが立ちあがる
津田大介の『動員の革命』を読んだ。
ソーシャルメディアを動員の手段として考える本。
この本で、読後一番心に残ったのは、動員とはぜんぜん関係ないけど、納豆は200回かきまわすとおいしくなる、ということだった。
以下、目次。
はじめに――1200人を呼び込む力
第1章 ソーシャルメディア×革命 「アラブの春」を起こした真の力とは
1 ソーシャルメディア・インパクト
•ツイッターの利用者は1700万人
•鳩山元首相に始まり、「流出」に終わった2010年
•アラブの春から東日本大震災、ステマまで
•インターネットはストック型からフロー型へ
2 そもそも、ソーシャルメディアってなんだ?
•ユーザーが双方向に情報を交換するメディア
•ソーシャルメディアの登場と発展
3 中東の革命、先進国の動乱
•情報統制に対抗する手段としてツイッターを利用
•ついに抑えきれなくなったジャスミン革命
•若者たちの怒りが爆発する
4 「動員」という革命
•外へ出ていき、「変われ!」と叫んだから変わった
•「出る杭」から「納豆」へ
•多種多様な世界の人と知り合うきっかけに
第1章・対話編 モーリー・ロバートソン×津田大介 ソーシャルメディアで世界は変わったか
1 世界のソーシャルメディア最前線
•ミンクの毛皮で反プーチン・デモ
•「携帯のおまけ」が運動を広げる目的で使われた
•中国の「金の盾」はハッタリ
•ネットの検閲をアウトソーシングしている
2 ソーシャルメディアとともに有機的に進化していく革命
•世界中を駆けめぐった少女の死の瞬間
•政府の脇の甘さを突いたジャスミン革命
•アマチュアのジャスミン革命からプロのエジプトへ
•「悪の美学」の発露としてのロンドン暴動
•大人の戦いのオキュパイ・ウォールストリート
3 日本のデモは何が未成熟なのか
•主体なきデモ、フジテレビ騒動
•呉越同舟するための方法論が日本にはない
•ソーシャルメディアが明らかにしたこと
第2章 ソーシャルメディア×情報発信 ムーブメントを起こすために必要なこと
1 発信者が押さえておくべき5つのキーワード
•「情報発信をしなければリターンはない」
•5要素を上手く使って「動員」を起こせ!
2 僕ならソーシャルメディアをこう使う Part1 ビジネス
•ソーシャルメディア利用の3つの目的
•苦情への対応を全てオープンにする
•少額の支援活動を取り入れてブランド力を上げる
•ソーシャルメディアで企業はどうふるまうべきか
3 僕ならソーシャルメディアをこう使う Part2 街おこし編
•セーシェル共和国の国家モデル
•人は何にお金を払うのか
•地方のコミュニティを固定化するには
•「得手に帆を上げる」ことで盛り上げていく
4 僕ならソーシャルメディアをこう使う Part3 ジャーナリズム編
•お風呂で知った尖閣事件
•ソーシャルメディアは拡声器であり、情報源
5 手段が変わると、世の中も変わる
•コンシューマライゼーションの時代
•モバイル、クラウドの発展が動員の革命を変えた
•アイディアが即座に実現できる環境は整っている
第2章・対話編 宇川直宏×津田大介 ソーシャルメディア時代のスーパースターとは
•フリースタイルが求められる時代
•ライフキャスティング、その動員の秘密
•有吉弘行から考える〈人の気〉のメカニズム
•「わら人形」的メンタリティとは
第3章 ソーシャルメディア×震災 東北復興のためにできること
1 震災直後から活躍したソーシャルメディア
•震災当日の連絡は全てツイッターで
•原発情報より炊き出しの情報がほしい
2 テレビとネットが手を組んだ
•被災地でも効果的だったサイマル放送
•ユーチューブで家族の無事を知る
•テレビでは切られてしまう情報が重要
3 ソーシャルメディアのマイナス面は?
•デマとどう付き合いか
•救命情報が消えない
•情報格差は“生死”に関わる
•もっと簡単に、もっと楽に
4 ソーシャルメディアで復興の速度を速めるには
•情報/雇用/お金
•マスメディアは飽きるが、ソーシャルメディアは飽きない
•一枚岩でまとまれない現実を伝える
•ほとんど報道されなかった潮来市の災害情報
•9億もの義捐金を集めた栄村
•善意を金銭化するには
第4章 ソーシャルメディア×未来 新しいマネタイズの方法とは?
1 これから「寄付」がブームになる!
•税制の改革で「寄付文化」が浸透
•NPOの機能をソーシャルメディアで
2 マイクロペイメントは世界を変える
•少額のお金を簡単に送れる仕組み
•親切を数値化できる
•海外のソーシャルメディアが狙うのは個人間送金サービス
•社会を動かすエンジン
3 クラウドファンディング
•クラウドファンディングとは?
•1年で82億円も集めたキックスターター
•日本では社会貢献活動から
•共感がお金を呼ぶ
第4章・対話編 家入一真×津田大介 ソーシャルメディアの力でマネタイズする
•クリエイターが資金調達をするために
•真面目な企画からバカっぽい企画まで
•リターンの設定が何よりも重要
•「これいいね!」が拡散していく
•クラウドファンディングからファンクラブモデルへ
•個人をマネタイズする仕組み
おわりに
特別鼎談 中沢新一×いとうせいこう×津田大介 「動員」で世の中を変えていこう
•新しいデモのかたち
•デモと音楽
•民意と政治をつなぐ
•ロビイングもすごく重要
•地域と密着したデモ
ソーシャルメディアを動員の手段として考える本。
この本で、読後一番心に残ったのは、動員とはぜんぜん関係ないけど、納豆は200回かきまわすとおいしくなる、ということだった。
以下、目次。
はじめに――1200人を呼び込む力
第1章 ソーシャルメディア×革命 「アラブの春」を起こした真の力とは
1 ソーシャルメディア・インパクト
•ツイッターの利用者は1700万人
•鳩山元首相に始まり、「流出」に終わった2010年
•アラブの春から東日本大震災、ステマまで
•インターネットはストック型からフロー型へ
2 そもそも、ソーシャルメディアってなんだ?
•ユーザーが双方向に情報を交換するメディア
•ソーシャルメディアの登場と発展
3 中東の革命、先進国の動乱
•情報統制に対抗する手段としてツイッターを利用
•ついに抑えきれなくなったジャスミン革命
•若者たちの怒りが爆発する
4 「動員」という革命
•外へ出ていき、「変われ!」と叫んだから変わった
•「出る杭」から「納豆」へ
•多種多様な世界の人と知り合うきっかけに
第1章・対話編 モーリー・ロバートソン×津田大介 ソーシャルメディアで世界は変わったか
1 世界のソーシャルメディア最前線
•ミンクの毛皮で反プーチン・デモ
•「携帯のおまけ」が運動を広げる目的で使われた
•中国の「金の盾」はハッタリ
•ネットの検閲をアウトソーシングしている
2 ソーシャルメディアとともに有機的に進化していく革命
•世界中を駆けめぐった少女の死の瞬間
•政府の脇の甘さを突いたジャスミン革命
•アマチュアのジャスミン革命からプロのエジプトへ
•「悪の美学」の発露としてのロンドン暴動
•大人の戦いのオキュパイ・ウォールストリート
3 日本のデモは何が未成熟なのか
•主体なきデモ、フジテレビ騒動
•呉越同舟するための方法論が日本にはない
•ソーシャルメディアが明らかにしたこと
第2章 ソーシャルメディア×情報発信 ムーブメントを起こすために必要なこと
1 発信者が押さえておくべき5つのキーワード
•「情報発信をしなければリターンはない」
•5要素を上手く使って「動員」を起こせ!
2 僕ならソーシャルメディアをこう使う Part1 ビジネス
•ソーシャルメディア利用の3つの目的
•苦情への対応を全てオープンにする
•少額の支援活動を取り入れてブランド力を上げる
•ソーシャルメディアで企業はどうふるまうべきか
3 僕ならソーシャルメディアをこう使う Part2 街おこし編
•セーシェル共和国の国家モデル
•人は何にお金を払うのか
•地方のコミュニティを固定化するには
•「得手に帆を上げる」ことで盛り上げていく
4 僕ならソーシャルメディアをこう使う Part3 ジャーナリズム編
•お風呂で知った尖閣事件
•ソーシャルメディアは拡声器であり、情報源
5 手段が変わると、世の中も変わる
•コンシューマライゼーションの時代
•モバイル、クラウドの発展が動員の革命を変えた
•アイディアが即座に実現できる環境は整っている
第2章・対話編 宇川直宏×津田大介 ソーシャルメディア時代のスーパースターとは
•フリースタイルが求められる時代
•ライフキャスティング、その動員の秘密
•有吉弘行から考える〈人の気〉のメカニズム
•「わら人形」的メンタリティとは
第3章 ソーシャルメディア×震災 東北復興のためにできること
1 震災直後から活躍したソーシャルメディア
•震災当日の連絡は全てツイッターで
•原発情報より炊き出しの情報がほしい
2 テレビとネットが手を組んだ
•被災地でも効果的だったサイマル放送
•ユーチューブで家族の無事を知る
•テレビでは切られてしまう情報が重要
3 ソーシャルメディアのマイナス面は?
•デマとどう付き合いか
•救命情報が消えない
•情報格差は“生死”に関わる
•もっと簡単に、もっと楽に
4 ソーシャルメディアで復興の速度を速めるには
•情報/雇用/お金
•マスメディアは飽きるが、ソーシャルメディアは飽きない
•一枚岩でまとまれない現実を伝える
•ほとんど報道されなかった潮来市の災害情報
•9億もの義捐金を集めた栄村
•善意を金銭化するには
第4章 ソーシャルメディア×未来 新しいマネタイズの方法とは?
1 これから「寄付」がブームになる!
•税制の改革で「寄付文化」が浸透
•NPOの機能をソーシャルメディアで
2 マイクロペイメントは世界を変える
•少額のお金を簡単に送れる仕組み
•親切を数値化できる
•海外のソーシャルメディアが狙うのは個人間送金サービス
•社会を動かすエンジン
3 クラウドファンディング
•クラウドファンディングとは?
•1年で82億円も集めたキックスターター
•日本では社会貢献活動から
•共感がお金を呼ぶ
第4章・対話編 家入一真×津田大介 ソーシャルメディアの力でマネタイズする
•クリエイターが資金調達をするために
•真面目な企画からバカっぽい企画まで
•リターンの設定が何よりも重要
•「これいいね!」が拡散していく
•クラウドファンディングからファンクラブモデルへ
•個人をマネタイズする仕組み
おわりに
特別鼎談 中沢新一×いとうせいこう×津田大介 「動員」で世の中を変えていこう
•新しいデモのかたち
•デモと音楽
•民意と政治をつなぐ
•ロビイングもすごく重要
•地域と密着したデモ
津田大介の『情報の呼吸法』を読んだ。
ハウトゥー本ではなく、短い自伝というか、長い自己紹介のような本だった。
わかりやすい!
以下、目次。
はじめに
第1章 情報は行動を引き起こすためにある
情報の爆発的増大は必然的な変化
ソーシャルメディアが社会的うねりに火をつける
東日本大震災で浮かび上がったソーシャルメディアの役割
震災時に「情報のハブ」になる
「伝えないと」という強いモチベーション
情報をシェアすることは楽しい
情報は行動するためのガソリンである
もともとが雑誌的人間だった
「ナタリー」を立ち上げる
今度は自分ひとりでメディアを作る
メディア作りの原点は新聞部
ナップスターの衝撃で人生が変わった
デジタルコンテンツ配信について修行する
「ツイッターの伝道師」と呼ばれて
「人選び」で情報の格差が広がる
誤配を通じて自分を知る
情報の必然性をデザインする
情報の受発信は「連想ゲーム」
一期一会のアウラにうまく乗っていく
新旧メディアのハイブリッド
第2章 情報は「人」をチャンネルにして取り込む
情報のほとんどはツイッターが起点
ソーシャルネットワークからニュースを手に入れる
情報は「セグメント化」して取り入れる
7~8割を追えるくらいのタイムラインをキープする
グーグルとツイッターを組み合わせた調査法
「人」に注目して情報の信憑性をはかる
知らないことは、訊いてみる
情報を「振り返る」というリテラシー
ソーシャルメディアと自分との相性をさぐる
古典を読んで情報の偏りを是正する
いかにして情報をスルーするか
宣伝の文句に惑わされないために
オフラインの情報価値が上がっている1:人に会う
「ツイッター飲み」という新しいオフ会
オフラインの情報価値が上がっている2:本を読む
1割のネガティブよりも9割のポジティブ
大切なことはすべてエゴサーチが教えてくれた
第3章 情報は発信しなければ、得るものはない
情報の「発信力」を高めるには
フォロワーを増やすには、フォローを増やす
継続してできることを自分の「タグ」にする
自分にしかできない発信をした「SHARE FUKUSHIMA」
「情報の棚卸し」にソーシャルメディアが役に立った
リアルタイム紀行型ジャーナリズム
マスメディアの報道が伝えない現実はたくさんある
新しい政治メディアを作りたい
政治の「情報の血流」をよくしたい
いま「メルマガ」である理由
面白いと思うものを発信すれば人はついてくる
有料の情報には価値が眠っている
エンゲージメントをして、まずは「ギブ」する
パブリックとプライベートのバランス
自分のリプライを「線引き」する
新旧メディアを組み合わせて発信する
生煮え状態のアイデアをたくさん置いておく
自分にボールを投げてアイデアの文脈を作る
「キュレーター」ではなく「バーテンダー」
考えるための材料を継続して提供する
発信の「軸」を決めて、直感を信じる
第4章 ソーシャルキャピタルの時代がやってくる
ソーシャルメディアはローカルな「しばり」から開放する
人間関係という資本を棚に蓄えておく
ソーシャルキャピタルとは何か
飛び出していく人間が孤独ではなくなった
ローカルコミュニティの再定義が求められている
情報発信の仕方しだいでコミュニティの未来も変わる
人間関係資本が経済資本をうまく牽引するために
送金のプラットフォームで社会は変わる
人はすべて他人にとってのソーシャルキャピタルである
おわりに
ハウトゥー本ではなく、短い自伝というか、長い自己紹介のような本だった。
わかりやすい!
以下、目次。
はじめに
第1章 情報は行動を引き起こすためにある
情報の爆発的増大は必然的な変化
ソーシャルメディアが社会的うねりに火をつける
東日本大震災で浮かび上がったソーシャルメディアの役割
震災時に「情報のハブ」になる
「伝えないと」という強いモチベーション
情報をシェアすることは楽しい
情報は行動するためのガソリンである
もともとが雑誌的人間だった
「ナタリー」を立ち上げる
今度は自分ひとりでメディアを作る
メディア作りの原点は新聞部
ナップスターの衝撃で人生が変わった
デジタルコンテンツ配信について修行する
「ツイッターの伝道師」と呼ばれて
「人選び」で情報の格差が広がる
誤配を通じて自分を知る
情報の必然性をデザインする
情報の受発信は「連想ゲーム」
一期一会のアウラにうまく乗っていく
新旧メディアのハイブリッド
第2章 情報は「人」をチャンネルにして取り込む
情報のほとんどはツイッターが起点
ソーシャルネットワークからニュースを手に入れる
情報は「セグメント化」して取り入れる
7~8割を追えるくらいのタイムラインをキープする
グーグルとツイッターを組み合わせた調査法
「人」に注目して情報の信憑性をはかる
知らないことは、訊いてみる
情報を「振り返る」というリテラシー
ソーシャルメディアと自分との相性をさぐる
古典を読んで情報の偏りを是正する
いかにして情報をスルーするか
宣伝の文句に惑わされないために
オフラインの情報価値が上がっている1:人に会う
「ツイッター飲み」という新しいオフ会
オフラインの情報価値が上がっている2:本を読む
1割のネガティブよりも9割のポジティブ
大切なことはすべてエゴサーチが教えてくれた
第3章 情報は発信しなければ、得るものはない
情報の「発信力」を高めるには
フォロワーを増やすには、フォローを増やす
継続してできることを自分の「タグ」にする
自分にしかできない発信をした「SHARE FUKUSHIMA」
「情報の棚卸し」にソーシャルメディアが役に立った
リアルタイム紀行型ジャーナリズム
マスメディアの報道が伝えない現実はたくさんある
新しい政治メディアを作りたい
政治の「情報の血流」をよくしたい
いま「メルマガ」である理由
面白いと思うものを発信すれば人はついてくる
有料の情報には価値が眠っている
エンゲージメントをして、まずは「ギブ」する
パブリックとプライベートのバランス
自分のリプライを「線引き」する
新旧メディアを組み合わせて発信する
生煮え状態のアイデアをたくさん置いておく
自分にボールを投げてアイデアの文脈を作る
「キュレーター」ではなく「バーテンダー」
考えるための材料を継続して提供する
発信の「軸」を決めて、直感を信じる
第4章 ソーシャルキャピタルの時代がやってくる
ソーシャルメディアはローカルな「しばり」から開放する
人間関係という資本を棚に蓄えておく
ソーシャルキャピタルとは何か
飛び出していく人間が孤独ではなくなった
ローカルコミュニティの再定義が求められている
情報発信の仕方しだいでコミュニティの未来も変わる
人間関係資本が経済資本をうまく牽引するために
送金のプラットフォームで社会は変わる
人はすべて他人にとってのソーシャルキャピタルである
おわりに
『時間ループ物語論 成長しない時代を生きる』
2013年12月1日 読書
浅羽通明さんの『時間ループ物語論 成長しない時代を生きる』を読んだ。
一定の時を繰り返す物語について、アニメや小説、漫画、ゲーム、落語、神話などなど、サブカルチャーの範囲におさまらず古今東西の事例をあげて語った1冊。
前半は主にサブカルチャーの話題。中盤で分析とルーツ、後半は主に高等遊民の話で、読んでいてまったく飽きさせない。なんだか、自分のことを言われているような気が始終しながらの読書だった。
僕はかなり前になるけど、大阪で浅羽さんとの対談のイベントに参加したことがある。山本精一くんも一緒に。『フールズメイト』誌での連載を読んでいたので、南方熊楠でも読んでおかないと話についていけないかな、とおっかなびっくりだったが、実際にお会いしてみると、腰の低い実に真摯な方で、楽しくトークできた思い出がある。
以下、目次。
第一講:オリエンテーション
恒川光太郎「秋の牢獄」精読――ユートピアに囚われて
「秋の牢獄」-ループする雨上がりの腫れた1日
北風伯爵がやってくる
渡り続ける11月7日という名前の夢
リアルをとりあえず置いてきたリピーターたち
何でもあるけど「希望」だけがないユートピア
私たちは「秋の牢獄」を生きている
第二講:時間ループ物語とは何か①
未来喪失という拷問――「エンドレスエイト」ほか
世界でただ一人「昨日」に取り残される恐怖-北村薫『ターン』
同じ10分間が30年繰り返す倦怠-R・R・スミス『倦怠の檻』
ほんの700万年、人類の時間止めちゃいます-S・スチャリクトル『しばし天の祝福から遠ざかり』
自殺者は人生を無限にやり直さなければならない-田中小実昌『タイムマシンの罰』
同じ演技を毎晩毎晩、何年も…という閉塞-S・エリン『パーティの夜』
1053498回終わらない夏休み-『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ『エンドレスエイト』
意識と記憶の連続、時間ループのジレンマ
アニメ版『エンドレスエイト』が11回連続で描いた渋い「進歩」
第三講:時間ループ物語とは何か②
猶予された時間の生き方――「恋はデジャ・ブ」ほか
ある朝目覚めると、昨日が繰り返していた-『恋はデジャ・ブ』
ループする時間の過ごし方-ニヒリズムを超えて
もしも冴えないアラサー女性が人生やり直しをできたなら-『未来の想い出』
専業主婦、ビジネス・ウーマン、元不良少女、もう一つの女の人生やり直し-垣谷美雨『リセット』
「他人の芝生は青くない」とわかった女たちのニーチェ的「選択」
とっても前向きな時間ループものの古典的名作-K・グリムウッド『リプレイ』
第四講:時間ループ物語とは何か③
ゲーム的試行錯誤の世界――「ひぐらしのなく頃に」ほか
時間ループ現象は問題先送りのメタファー!?
1999年7月、ノストラダムスの幽霊たち-佐伯かよの『永遠の夜に向かって』
あのときわたしが遅れなければ…、青春の「喪の作業」-伊藤伸平『はるかリフレイン』
メタフィクション時間ループ・ミステリー-竜騎士07『ひぐらしのなく頃に』
「ゲーム的リアリズム」考-桜坂洋『All You Need Is Kill』
凡人の名探偵を可能にする時間ループ-西澤保彦『七回死んだ男』
愛する者たちを助けるとは、何回も死ぬことだ-香納諒一『ステップ』
ターゲットが絞られているシングル・イシュー型時間ループ
時間ループの罠、意外な連鎖反応を阻止せよ-『バタフライ・エフェクト』
人類破滅まで40年、来たる核戦争を回避できますか-筒井康隆『秒読み』
もしモンゴル帝国が全世界を支配していたら-豊田有恒『モンゴルの残光』
実ははた迷惑だった時間ループ-佐藤正午『Y』
第五講:時間ループ物語とは何か④
悦楽の時間よ、永遠に――「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」ほか
ずうっとずうっと楽しく暮らしていたいっちゃッ
現実もそれはそれで終わらない「暴力が必要とは限らない」夢
「日々、学園祭の前夜祭気分」の「おたく」たちのユートピア
『エンドレスエイト』、もう一つの『ビューティフル・ドリーマー』
デイタイムズビリーバーを永遠に-愛妻家が世界の未来を奪う
終わらない初恋-『恋する死者の夜』と『長門有希の日記』
恋愛という起動装置-時間ループはかく引き起こされ、かく終わらせられる
「将来」「未来」を見据えるリアルな充実がモラトリアムを終わらせる
戦争に匹敵する凝縮した充実が明日のないループ時空を成立させる
恋愛が「夢の時空」からリアルへと変わったゼロ世代
『魔法少女まどか☆マギカ』考-宇野常寛説への疑問
第六講:世代対立の不毛を超えて
コンテンツ批評諸家の時間ループ物語論へ物申す――『不可能性の時代』ほか
世界が終わる前日、僕たちは…
「セカイ系」は時間ループの夢を見るのか
道具としての「物語」論-社会反映論を超えて
「いまの俺たちこそ特別な時代を生きている」という中二病
「普遍化」という知の用法-「特権化」しがちな自分へ冷や水をぶっかけるために
受け手系と送り手系?ネットで見つけた二つの分類
時間ループ物語はいかなる願望を充足し、いかなる恐怖を洗い流すのか?
物語の広大な宇宙の中で、時間ループ物語を捉え直すために
第七講:ループものの起源をさかのぼる①
人生時間の伸縮――『ファウスト』、輪廻転生、さまよえるユダヤ人ほか
ファウスト博士のワイドスクリーン・バロック
成長前向き型の時間ループのルーツ、近代的英雄の典型『ファウスト』
東洋前近代の成長前向き型の時間ループ!!輪廻転生
ネガティブな時間ループのご先祖さま-シジフォスの神話、浄土思想
不死という刑罰、さまよえるユダヤ、オランダ人伝説
ソクラテスにプラトン、偉人たちが暮らす地獄「リンボー」と「賽の河原」
さまよえるユダヤ人、ひらき直る-シャミッソー『影をなくした男』
ガリヴァーの悪夢-不老を忘れた不死
北欧神話「ヴァルハラ宮」、イスラムの天女「フーリー」、ニーチェ「永劫回帰」思想
第八講:ループものの起源をさかのぼる②
予知と夢落ち――『フラッシュ・フォワード』「鼠穴」「芝浜」「夢金」ほか
「時間」の不可逆性のジレンマ
未来を知って生きたいという願望-「予知予言譚」
予知譚からループへ-『フラッシュフォワード』と『7時03分』
古典落語に見る夢ループ『鼠穴』『芝浜』『夢金』
夢オチは東洋の神秘?-『邯鄲枕の夢』『南柯太守伝』
夢という名の「脳内未来」-星新一『殺意』『改善』
「物語」-操作可能なもう一つの「夢」
第九講:ループものの起源をさかのぼる③
物語の迷宮と時間の近代化――『デス博士の島その他の物語』『毒入りチョコレート事件』『時間の比較社会学』ほか
きみだって、同じなんだよ-再読、三読という時間ループ
すべて名作小説は時間ループ物語である!?-塚崎幹夫『名作の読解法』
事件の真相とは一創作に過ぎない-アントニー・バークリー『毒入りチョコレート事件』
物語創作とは時間ループ作業である
O・ヘンリーのマルチ・エンディング小説
「時間ループ物語」はなぜ誕生したか
動物化しなくても物語消費論は分岐の数だけある
タイムトラベルの誕生-ループ物語の比較社会学
『時間の比較社会学』再び、テレビという名の時間秩序
第十講:ループものの起源をさかのぼる④
浦島太郎伝説とユートピアの陥穽――『母性社会日本の病理』『銀河鉄道999』『夢十夜』ほか
そうよ、怖いカニが待っているのよ
河合隼雄『母性社会日本の病理』の予見
竜宮城はアキバである
浦島太郎を時間ループ問題から考える
時間の隠れ里-M・エリアーデの聖なる時間
浦島太郎が誤った三つの分岐点
玉手箱とは何か-文化英雄としての浦島太郎
竜宮の体験を醸成してクリエイターへ
『銀河鉄道999』-昭和後期が生んだ浦島譚の名作
豚に舐められますが好う御座んすか-『夢十夜』の戦慄
第十一講:大先達に学ぶサバイバル法
高等遊民の愉悦と不安――『三四郎』『それから』『一握の砂』ほか
黄金の午睡(ゴールデン・スランバー)-二度と還らない学生時代の夢
明治の浦島太郎、長井代助の愉悦
『それから』は恋愛小説ではない
ループしている長井代助の時間
恋しちゃいけない高等遊民
代助が誤った三つの分岐点
『それから』のそれから考-名探偵長井代助のまぼろし
みんな学校が恋しかった-内海文三から啄木、宮本顕治まで
代助の劣化した後輩たち-武者小路実篤『友情』、久米正雄『学生時代』
リアル高等遊民-学校が生んだ雇用ミスマッチ
そして誰もが代助になった
杉作J太郎のループする高校時代から『けいおん!』へ
第十二講:ループの時代を超えてゆくために
平成ユートピアの囚われ人――『けいおん!』『門』『上海バンスキング』ほか
近代文学者たち-彼らは分岐点をどう曲がったか
竜宮城に残る-研究者になるというモラトリアム
崖の下の宗助-夏目漱石『門』のループする時間
「螺旋的時間」-「直線的時間」=「円環的時間」
森鴎外の直線的時間-そこでは学校は通過点にすぎない
「日常系」-「非日常系」との境界がぼけた平成の現実
平成~復活する「生活系」-仕事と子育てで甦る「直線的時間」
もう成長しない日本-生きる指針としての「時間ループ物語」
自分を国家を人類を彫りだすアート
物語の力を試す-あとがきに代えて
後半で登場し、浅羽さんが再三にわたって応用してみせる、浦島太郎の三つの分岐点は、次のとおり。
1、うまい話を何も疑わず竜宮城へついていってしまった。
2、竜宮城の快楽原則へ溺れながら里心を起こしてしまった。
3、開けてはならない玉手箱をあっさり開けてしまった。
僕ならば、1つめの分岐点は浦島の失敗を繰り返すにちがいないが、2つめ、3つめは大丈夫かな。
なお、この本は、ユーストリーム番組「Salon the Art Room」のブック・レビューのコーナーで紹介させていただいたのだが、なんと、読み終わったのが、番組当日の朝、というギリギリの状態で、うまくご紹介できなかったかと思う。じゃあ、数日あればちゃんと用意できたのか、と言えば、それはまた別の話、ということで。
一定の時を繰り返す物語について、アニメや小説、漫画、ゲーム、落語、神話などなど、サブカルチャーの範囲におさまらず古今東西の事例をあげて語った1冊。
前半は主にサブカルチャーの話題。中盤で分析とルーツ、後半は主に高等遊民の話で、読んでいてまったく飽きさせない。なんだか、自分のことを言われているような気が始終しながらの読書だった。
僕はかなり前になるけど、大阪で浅羽さんとの対談のイベントに参加したことがある。山本精一くんも一緒に。『フールズメイト』誌での連載を読んでいたので、南方熊楠でも読んでおかないと話についていけないかな、とおっかなびっくりだったが、実際にお会いしてみると、腰の低い実に真摯な方で、楽しくトークできた思い出がある。
以下、目次。
第一講:オリエンテーション
恒川光太郎「秋の牢獄」精読――ユートピアに囚われて
「秋の牢獄」-ループする雨上がりの腫れた1日
北風伯爵がやってくる
渡り続ける11月7日という名前の夢
リアルをとりあえず置いてきたリピーターたち
何でもあるけど「希望」だけがないユートピア
私たちは「秋の牢獄」を生きている
第二講:時間ループ物語とは何か①
未来喪失という拷問――「エンドレスエイト」ほか
世界でただ一人「昨日」に取り残される恐怖-北村薫『ターン』
同じ10分間が30年繰り返す倦怠-R・R・スミス『倦怠の檻』
ほんの700万年、人類の時間止めちゃいます-S・スチャリクトル『しばし天の祝福から遠ざかり』
自殺者は人生を無限にやり直さなければならない-田中小実昌『タイムマシンの罰』
同じ演技を毎晩毎晩、何年も…という閉塞-S・エリン『パーティの夜』
1053498回終わらない夏休み-『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ『エンドレスエイト』
意識と記憶の連続、時間ループのジレンマ
アニメ版『エンドレスエイト』が11回連続で描いた渋い「進歩」
第三講:時間ループ物語とは何か②
猶予された時間の生き方――「恋はデジャ・ブ」ほか
ある朝目覚めると、昨日が繰り返していた-『恋はデジャ・ブ』
ループする時間の過ごし方-ニヒリズムを超えて
もしも冴えないアラサー女性が人生やり直しをできたなら-『未来の想い出』
専業主婦、ビジネス・ウーマン、元不良少女、もう一つの女の人生やり直し-垣谷美雨『リセット』
「他人の芝生は青くない」とわかった女たちのニーチェ的「選択」
とっても前向きな時間ループものの古典的名作-K・グリムウッド『リプレイ』
第四講:時間ループ物語とは何か③
ゲーム的試行錯誤の世界――「ひぐらしのなく頃に」ほか
時間ループ現象は問題先送りのメタファー!?
1999年7月、ノストラダムスの幽霊たち-佐伯かよの『永遠の夜に向かって』
あのときわたしが遅れなければ…、青春の「喪の作業」-伊藤伸平『はるかリフレイン』
メタフィクション時間ループ・ミステリー-竜騎士07『ひぐらしのなく頃に』
「ゲーム的リアリズム」考-桜坂洋『All You Need Is Kill』
凡人の名探偵を可能にする時間ループ-西澤保彦『七回死んだ男』
愛する者たちを助けるとは、何回も死ぬことだ-香納諒一『ステップ』
ターゲットが絞られているシングル・イシュー型時間ループ
時間ループの罠、意外な連鎖反応を阻止せよ-『バタフライ・エフェクト』
人類破滅まで40年、来たる核戦争を回避できますか-筒井康隆『秒読み』
もしモンゴル帝国が全世界を支配していたら-豊田有恒『モンゴルの残光』
実ははた迷惑だった時間ループ-佐藤正午『Y』
第五講:時間ループ物語とは何か④
悦楽の時間よ、永遠に――「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」ほか
ずうっとずうっと楽しく暮らしていたいっちゃッ
現実もそれはそれで終わらない「暴力が必要とは限らない」夢
「日々、学園祭の前夜祭気分」の「おたく」たちのユートピア
『エンドレスエイト』、もう一つの『ビューティフル・ドリーマー』
デイタイムズビリーバーを永遠に-愛妻家が世界の未来を奪う
終わらない初恋-『恋する死者の夜』と『長門有希の日記』
恋愛という起動装置-時間ループはかく引き起こされ、かく終わらせられる
「将来」「未来」を見据えるリアルな充実がモラトリアムを終わらせる
戦争に匹敵する凝縮した充実が明日のないループ時空を成立させる
恋愛が「夢の時空」からリアルへと変わったゼロ世代
『魔法少女まどか☆マギカ』考-宇野常寛説への疑問
第六講:世代対立の不毛を超えて
コンテンツ批評諸家の時間ループ物語論へ物申す――『不可能性の時代』ほか
世界が終わる前日、僕たちは…
「セカイ系」は時間ループの夢を見るのか
道具としての「物語」論-社会反映論を超えて
「いまの俺たちこそ特別な時代を生きている」という中二病
「普遍化」という知の用法-「特権化」しがちな自分へ冷や水をぶっかけるために
受け手系と送り手系?ネットで見つけた二つの分類
時間ループ物語はいかなる願望を充足し、いかなる恐怖を洗い流すのか?
物語の広大な宇宙の中で、時間ループ物語を捉え直すために
第七講:ループものの起源をさかのぼる①
人生時間の伸縮――『ファウスト』、輪廻転生、さまよえるユダヤ人ほか
ファウスト博士のワイドスクリーン・バロック
成長前向き型の時間ループのルーツ、近代的英雄の典型『ファウスト』
東洋前近代の成長前向き型の時間ループ!!輪廻転生
ネガティブな時間ループのご先祖さま-シジフォスの神話、浄土思想
不死という刑罰、さまよえるユダヤ、オランダ人伝説
ソクラテスにプラトン、偉人たちが暮らす地獄「リンボー」と「賽の河原」
さまよえるユダヤ人、ひらき直る-シャミッソー『影をなくした男』
ガリヴァーの悪夢-不老を忘れた不死
北欧神話「ヴァルハラ宮」、イスラムの天女「フーリー」、ニーチェ「永劫回帰」思想
第八講:ループものの起源をさかのぼる②
予知と夢落ち――『フラッシュ・フォワード』「鼠穴」「芝浜」「夢金」ほか
「時間」の不可逆性のジレンマ
未来を知って生きたいという願望-「予知予言譚」
予知譚からループへ-『フラッシュフォワード』と『7時03分』
古典落語に見る夢ループ『鼠穴』『芝浜』『夢金』
夢オチは東洋の神秘?-『邯鄲枕の夢』『南柯太守伝』
夢という名の「脳内未来」-星新一『殺意』『改善』
「物語」-操作可能なもう一つの「夢」
第九講:ループものの起源をさかのぼる③
物語の迷宮と時間の近代化――『デス博士の島その他の物語』『毒入りチョコレート事件』『時間の比較社会学』ほか
きみだって、同じなんだよ-再読、三読という時間ループ
すべて名作小説は時間ループ物語である!?-塚崎幹夫『名作の読解法』
事件の真相とは一創作に過ぎない-アントニー・バークリー『毒入りチョコレート事件』
物語創作とは時間ループ作業である
O・ヘンリーのマルチ・エンディング小説
「時間ループ物語」はなぜ誕生したか
動物化しなくても物語消費論は分岐の数だけある
タイムトラベルの誕生-ループ物語の比較社会学
『時間の比較社会学』再び、テレビという名の時間秩序
第十講:ループものの起源をさかのぼる④
浦島太郎伝説とユートピアの陥穽――『母性社会日本の病理』『銀河鉄道999』『夢十夜』ほか
そうよ、怖いカニが待っているのよ
河合隼雄『母性社会日本の病理』の予見
竜宮城はアキバである
浦島太郎を時間ループ問題から考える
時間の隠れ里-M・エリアーデの聖なる時間
浦島太郎が誤った三つの分岐点
玉手箱とは何か-文化英雄としての浦島太郎
竜宮の体験を醸成してクリエイターへ
『銀河鉄道999』-昭和後期が生んだ浦島譚の名作
豚に舐められますが好う御座んすか-『夢十夜』の戦慄
第十一講:大先達に学ぶサバイバル法
高等遊民の愉悦と不安――『三四郎』『それから』『一握の砂』ほか
黄金の午睡(ゴールデン・スランバー)-二度と還らない学生時代の夢
明治の浦島太郎、長井代助の愉悦
『それから』は恋愛小説ではない
ループしている長井代助の時間
恋しちゃいけない高等遊民
代助が誤った三つの分岐点
『それから』のそれから考-名探偵長井代助のまぼろし
みんな学校が恋しかった-内海文三から啄木、宮本顕治まで
代助の劣化した後輩たち-武者小路実篤『友情』、久米正雄『学生時代』
リアル高等遊民-学校が生んだ雇用ミスマッチ
そして誰もが代助になった
杉作J太郎のループする高校時代から『けいおん!』へ
第十二講:ループの時代を超えてゆくために
平成ユートピアの囚われ人――『けいおん!』『門』『上海バンスキング』ほか
近代文学者たち-彼らは分岐点をどう曲がったか
竜宮城に残る-研究者になるというモラトリアム
崖の下の宗助-夏目漱石『門』のループする時間
「螺旋的時間」-「直線的時間」=「円環的時間」
森鴎外の直線的時間-そこでは学校は通過点にすぎない
「日常系」-「非日常系」との境界がぼけた平成の現実
平成~復活する「生活系」-仕事と子育てで甦る「直線的時間」
もう成長しない日本-生きる指針としての「時間ループ物語」
自分を国家を人類を彫りだすアート
物語の力を試す-あとがきに代えて
後半で登場し、浅羽さんが再三にわたって応用してみせる、浦島太郎の三つの分岐点は、次のとおり。
1、うまい話を何も疑わず竜宮城へついていってしまった。
2、竜宮城の快楽原則へ溺れながら里心を起こしてしまった。
3、開けてはならない玉手箱をあっさり開けてしまった。
僕ならば、1つめの分岐点は浦島の失敗を繰り返すにちがいないが、2つめ、3つめは大丈夫かな。
なお、この本は、ユーストリーム番組「Salon the Art Room」のブック・レビューのコーナーで紹介させていただいたのだが、なんと、読み終わったのが、番組当日の朝、というギリギリの状態で、うまくご紹介できなかったかと思う。じゃあ、数日あればちゃんと用意できたのか、と言えば、それはまた別の話、ということで。
『北洋探偵小説選』を読んだ。
トリックを紹介した本で、名前だけは知っていたが、これだけの数の作品をまとめて読む日が来るとは、思ってもみなかった。
リラダンに影響を受けた作品が目立つ。
4本腕のある女性の嘆きとか、一種独特のムードだ。
北洋の作品には宇宙線や放射性物質がよく登場する。実際に京都帝国大学で講師をつとめる理学部理系の作家で、湯川秀樹に「カストリ雑誌に小説を書いてるそうだな」とか言われて小説を書くのをやめたらしい。享年31歳。かなり若くして死んでいる。
本書では、科学読物の「アトム君の物語」が意外と面白かった。
新しい科学の分野であった原子力の研究所に、市民たちが集まって、反対し、打ち壊そうとする描写など、1949年の作品とは思えない。
集まった群衆に、セーヤ中学校のペリオ校長が、語りかける。
「私たち大人はいろいろな偏見にわざわいされています。そしてまた悲しいことに人間の悪を見なれてきているために、すべてのことを悪意に解釈しやすくなっています。
(中略)
悪質の宣伝にまどわされることなく、自分の眼でよく見なければならない。
市民諸君。
私たちはなぜこの研究所の前に集まってきたのか?某新聞の記事を見て、サリコの森の爆発を見てでしょうか?しかし私たちはその記事が果たして正しいかどうかということは知らない。そして爆発事件の真相も知らない。脅迫状の事件も果たして本当かどうかも知らない。その真相も知らずに私たちはただ群集心理によって集まってきたのではないでしょうか?」
以下続く冷静な言葉で、群集はいったん反省して家に帰っていくが、それを見ていたコスミおじさんは、こう言う。
「こういうことはきっと何度もくりかえされるだろうよ」
「むかし蒸気機関が発明されたときもそうだった。今度の原子力の発明は蒸気機関どころの騒ぎではないからね、頭の古い人々はいままでの生活が変わるのをおそれている。新しいことがおこるととまどいして、どうしてよいかわからないために、むしろそんなものがない方がいいと思ってしまう」
作者は、戦後まもない時期に、科学と人間とのつきあいかたを考えようとした、冷静な良識派なのかな、と思いきや、こんな展開が待っていた。われらが頼れるコスミおじさんは、原子力を悪用しようとするミスダー・キリングの工場に行って、原子爆弾で秘密工場を爆破し、キリングの野望を打ち砕く。最後にこう言いながら。
「ニルス君の別荘も崩れたかもしれないね。もうあの辺は放射線が危なくてしばらく住めないよ」
なんという決着のつけかた!
以下、目次。
写真解読者
1、発端
2、天空の峯々
3、過失
4、終結
ルシタニア号事件
失楽園(パラダイス・ロースト)
無意識殺人(アンコンシャス・マーダー)
天使との争ひ
死の協和音(ハーモニックス)
異形の妖精
こがね虫の証人
清滝川の惨劇
展覧会の怪画
砂漠に咲く花-新世界物語
盗まれた手
1、サン・トノレにおける事件
2、多すぎる手
3、エルブランの下宿にて
4、墓が暴かれた
5、最後の椿事
アトム君の冒険
はしがき
1、ラジューム事件
2、不思議な扉
3、ミスター・キリング
4、放射線
5、冒険の計画
6、惨事
7、群集の誤解
8、来るべき世界
9、目印
10、新世界ばんざい!
アトム君のノートより
電子/電子の応用/原子のなか/原子核のなか/放射線/放射性元素/核分裂
あとがき 父兄の方々へ
首をふる鳥
自然は力学を行う
トリックを紹介した本で、名前だけは知っていたが、これだけの数の作品をまとめて読む日が来るとは、思ってもみなかった。
リラダンに影響を受けた作品が目立つ。
4本腕のある女性の嘆きとか、一種独特のムードだ。
北洋の作品には宇宙線や放射性物質がよく登場する。実際に京都帝国大学で講師をつとめる理学部理系の作家で、湯川秀樹に「カストリ雑誌に小説を書いてるそうだな」とか言われて小説を書くのをやめたらしい。享年31歳。かなり若くして死んでいる。
本書では、科学読物の「アトム君の物語」が意外と面白かった。
新しい科学の分野であった原子力の研究所に、市民たちが集まって、反対し、打ち壊そうとする描写など、1949年の作品とは思えない。
集まった群衆に、セーヤ中学校のペリオ校長が、語りかける。
「私たち大人はいろいろな偏見にわざわいされています。そしてまた悲しいことに人間の悪を見なれてきているために、すべてのことを悪意に解釈しやすくなっています。
(中略)
悪質の宣伝にまどわされることなく、自分の眼でよく見なければならない。
市民諸君。
私たちはなぜこの研究所の前に集まってきたのか?某新聞の記事を見て、サリコの森の爆発を見てでしょうか?しかし私たちはその記事が果たして正しいかどうかということは知らない。そして爆発事件の真相も知らない。脅迫状の事件も果たして本当かどうかも知らない。その真相も知らずに私たちはただ群集心理によって集まってきたのではないでしょうか?」
以下続く冷静な言葉で、群集はいったん反省して家に帰っていくが、それを見ていたコスミおじさんは、こう言う。
「こういうことはきっと何度もくりかえされるだろうよ」
「むかし蒸気機関が発明されたときもそうだった。今度の原子力の発明は蒸気機関どころの騒ぎではないからね、頭の古い人々はいままでの生活が変わるのをおそれている。新しいことがおこるととまどいして、どうしてよいかわからないために、むしろそんなものがない方がいいと思ってしまう」
作者は、戦後まもない時期に、科学と人間とのつきあいかたを考えようとした、冷静な良識派なのかな、と思いきや、こんな展開が待っていた。われらが頼れるコスミおじさんは、原子力を悪用しようとするミスダー・キリングの工場に行って、原子爆弾で秘密工場を爆破し、キリングの野望を打ち砕く。最後にこう言いながら。
「ニルス君の別荘も崩れたかもしれないね。もうあの辺は放射線が危なくてしばらく住めないよ」
なんという決着のつけかた!
以下、目次。
写真解読者
1、発端
2、天空の峯々
3、過失
4、終結
ルシタニア号事件
失楽園(パラダイス・ロースト)
無意識殺人(アンコンシャス・マーダー)
天使との争ひ
死の協和音(ハーモニックス)
異形の妖精
こがね虫の証人
清滝川の惨劇
展覧会の怪画
砂漠に咲く花-新世界物語
盗まれた手
1、サン・トノレにおける事件
2、多すぎる手
3、エルブランの下宿にて
4、墓が暴かれた
5、最後の椿事
アトム君の冒険
はしがき
1、ラジューム事件
2、不思議な扉
3、ミスター・キリング
4、放射線
5、冒険の計画
6、惨事
7、群集の誤解
8、来るべき世界
9、目印
10、新世界ばんざい!
アトム君のノートより
電子/電子の応用/原子のなか/原子核のなか/放射線/放射性元素/核分裂
あとがき 父兄の方々へ
首をふる鳥
自然は力学を行う