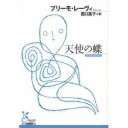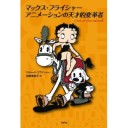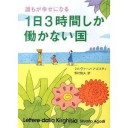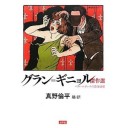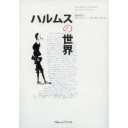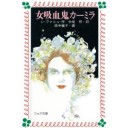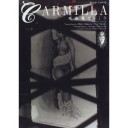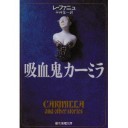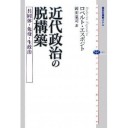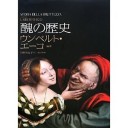ドミューンで、相原信洋追悼番組。
「追悼・相原信洋1944-2011/DREAMS」
19:00-21:30 「相原信洋ANIMATION史1965-2011」
出演:松本俊夫、かわなかのぶひろ、中島崇、辻直之
21:30-22:00 「相原信洋とあがた森魚」
出演/演奏:あがた森魚
22:00-23:30 「相原信洋と田名網敬一、そして広島アニメーションフェスティバル」
出演:田名網敬一、木下小夜子、伊藤桂司
23:30-24:00 「相原信洋と根本敬」
出演:根本敬、五所純子
というタイムスケジュールだった。じゃっかん押し気味。
このときに流れたアニメ作品とか全部メモしていたのだが、今、さがすとどこにも発見できないので、また見つかったらアップ予定。
「STONE」「カルマ」「やまかゞし」「妄動」「相原さんの遺品より」「ひまわりふくろう映画学校ドキュメント」あがたさんのライブをはさんで、「WIND」「MEMORY OF RED」「スクラップダイアリー」「Fetish Doll」「キリコ」「般若心経」「DREAMS」だったかな?途中、相原氏の親族もぞくぞくと登場。家族には「ゴミ屋敷」としか思われていない相原氏の部屋をなんとか保存したいという、姪っこの訴えもあり。
あがたさんのライブは1曲めはオフマイクで。その後「俺の知らない内田裕也は俺の知ってる宇宙の夕焼け」「赤色エレジー」。
田名網さんはぽろっとアニメーション審査の内幕を暴露。
根本さんは映る前からハイテンションでおしまくる。エロ話の師匠をそれらしく追悼する。最後には森昌子の「せんせい」の狂ったDJ。
読んだ本は、近代ナリコ編集による『宇野亜喜良---少女画 六つのエレメント』
第1章 意匠
第2章 装飾
第3章 細部
第4章 変容
第5章 連環
第6章 物語
「スクスク」寺山修司・作 宇野亜喜良・絵
第7章 資料編
エッセイ:細部の詩/穂村弘
エッセイ:宇野さんの左手/江國香織
再録:僕の個人史
三つのアニメーション(「白い祭」「お前とわたし」「午砲(ドン)」
再録:宇野亜喜良の巻 雑誌『新婦人』より
宇野亜喜良アルバム
再録:左ききの魔術師 雑誌『キネマ旬報増刊 サイケの世界』より
再録:インタビュー 『モダンジュース別冊・宇野亜喜良の世界』より
再録:「あなたのための贈り物」
再録:「メモ」
宇野亜喜良インタビュー
宇野亜喜良年譜
あとがき/宇野亜喜良
宇野亜喜良といえば、少女趣味の世界から、ゲイ雑誌の表紙までてがける人なのだが、決して本人はゲイじゃない、ということが何度か触れられていて、ああ、みんなはすぐにそういうふうに解釈してしまうんだな、ということが照射された。
本書では、フォア・レディーズのときのワクワク感が再現されていて、楽しかった。ひまわりやジュニアそれいゆ以降、少女趣味を体現したものは新書館フォア・レディーズまで途切れていた、との発言に、へえ~と思った。脈々と発信者は存在していたのだろうが、寺山修司のような強力な存在が参戦することでそれがまとまった、ということなのか。
「追悼・相原信洋1944-2011/DREAMS」
19:00-21:30 「相原信洋ANIMATION史1965-2011」
出演:松本俊夫、かわなかのぶひろ、中島崇、辻直之
21:30-22:00 「相原信洋とあがた森魚」
出演/演奏:あがた森魚
22:00-23:30 「相原信洋と田名網敬一、そして広島アニメーションフェスティバル」
出演:田名網敬一、木下小夜子、伊藤桂司
23:30-24:00 「相原信洋と根本敬」
出演:根本敬、五所純子
というタイムスケジュールだった。じゃっかん押し気味。
このときに流れたアニメ作品とか全部メモしていたのだが、今、さがすとどこにも発見できないので、また見つかったらアップ予定。
「STONE」「カルマ」「やまかゞし」「妄動」「相原さんの遺品より」「ひまわりふくろう映画学校ドキュメント」あがたさんのライブをはさんで、「WIND」「MEMORY OF RED」「スクラップダイアリー」「Fetish Doll」「キリコ」「般若心経」「DREAMS」だったかな?途中、相原氏の親族もぞくぞくと登場。家族には「ゴミ屋敷」としか思われていない相原氏の部屋をなんとか保存したいという、姪っこの訴えもあり。
あがたさんのライブは1曲めはオフマイクで。その後「俺の知らない内田裕也は俺の知ってる宇宙の夕焼け」「赤色エレジー」。
田名網さんはぽろっとアニメーション審査の内幕を暴露。
根本さんは映る前からハイテンションでおしまくる。エロ話の師匠をそれらしく追悼する。最後には森昌子の「せんせい」の狂ったDJ。
読んだ本は、近代ナリコ編集による『宇野亜喜良---少女画 六つのエレメント』
第1章 意匠
第2章 装飾
第3章 細部
第4章 変容
第5章 連環
第6章 物語
「スクスク」寺山修司・作 宇野亜喜良・絵
第7章 資料編
エッセイ:細部の詩/穂村弘
エッセイ:宇野さんの左手/江國香織
再録:僕の個人史
三つのアニメーション(「白い祭」「お前とわたし」「午砲(ドン)」
再録:宇野亜喜良の巻 雑誌『新婦人』より
宇野亜喜良アルバム
再録:左ききの魔術師 雑誌『キネマ旬報増刊 サイケの世界』より
再録:インタビュー 『モダンジュース別冊・宇野亜喜良の世界』より
再録:「あなたのための贈り物」
再録:「メモ」
宇野亜喜良インタビュー
宇野亜喜良年譜
あとがき/宇野亜喜良
宇野亜喜良といえば、少女趣味の世界から、ゲイ雑誌の表紙までてがける人なのだが、決して本人はゲイじゃない、ということが何度か触れられていて、ああ、みんなはすぐにそういうふうに解釈してしまうんだな、ということが照射された。
本書では、フォア・レディーズのときのワクワク感が再現されていて、楽しかった。ひまわりやジュニアそれいゆ以降、少女趣味を体現したものは新書館フォア・レディーズまで途切れていた、との発言に、へえ~と思った。脈々と発信者は存在していたのだろうが、寺山修司のような強力な存在が参戦することでそれがまとまった、ということなのか。
プリーモ・レーヴィの『天使の蝶』を読んだ。
これは楽しい「すこしふしぎ」な奇想小説集。
次々と珍奇な機械を発明してセールスにくるシンプソン氏のシリーズも含む。
以下、作品ごとに、簡単なメモ。
「ビテュニアの検閲制度」
検閲を人間に任せると、脳が冒される危険があり、機械に任せると杓子定規になる。で、どうするかと言うと、ニワトリにすべてをまかすのだ。
「記憶喚起剤」
特定のにおいが特定の記憶を呼び覚ます。
「詩歌作成機」
設定によって、詩を作ってくれる機械。途中で熱暴走をおこし、韻を踏んで不調を告げる。
「天使の蝶」
おたまじゃくしがカエルに変態するように、人間ももうちょっと長生きすれば、違うものに変態するのでは。
「猛成苔」
自動車にはえる地衣植物。車には性別があって、そのコケの生態も変わってくる。
「低コストの秩序」
オリジナルと同じ部位に同じ分子をあてはめることで、まるっきりのコピーを作り出す三次元複製機「ミメーシン」。炭素を使ってダイヤモンドを量産だってできる。
「人間の友」
サナダムシの細胞の配列を解読すると、そこにはメッセージが書かれていた。
「《ミメーシン》の使用例」
ミメーシンで妻を複製した男。これはどっちも本物だけど重婚?同一人物の妻どうしで嫉妬や不公平が生じてくる。
「転換剤」
苦痛と快楽を逆にする転換剤。生命を守ろうとするより自殺願望ばかり起こる。失意のどん底にある人には、ばら色の日々が。
「眠れる冷蔵庫の美女」
わがままなコールドスリープ美女にだまされるな!
「美の尺度」
基準値を設定して、美を測定する機械。
「ケンタウロス論」
そうか。ケンタウロスは人間の口で馬が必要とする栄養をとらねばならなかったのか。
さて、この「ケンタウロス論」では面白い第二創世論が展開される。ノアの方舟に乗れなかった膨大な種が、洪水がひいたあと、大地で発酵し、空前絶後の婚姻と受胎がはじまる。あらゆるものがあらゆるものと交わり、あらゆるものを生み出す。ケンタウロスの場合は人と馬のあいのこ、ということになる。この空前絶後の愛の交わりによって生まれたものの例が楽しい。
「完全雇用」
格安の労働力、昆虫と取引。ミツバチと会話するため、シンプソン氏は8の字ダンスしてコミュニケートしようとする。
「創世記第六日」
人間をどういう生物にするかについての会議。
「退職扱い」
バーチャルリアリティー機械「トレック」の顛末。
これは楽しい「すこしふしぎ」な奇想小説集。
次々と珍奇な機械を発明してセールスにくるシンプソン氏のシリーズも含む。
以下、作品ごとに、簡単なメモ。
「ビテュニアの検閲制度」
検閲を人間に任せると、脳が冒される危険があり、機械に任せると杓子定規になる。で、どうするかと言うと、ニワトリにすべてをまかすのだ。
「記憶喚起剤」
特定のにおいが特定の記憶を呼び覚ます。
「詩歌作成機」
設定によって、詩を作ってくれる機械。途中で熱暴走をおこし、韻を踏んで不調を告げる。
「天使の蝶」
おたまじゃくしがカエルに変態するように、人間ももうちょっと長生きすれば、違うものに変態するのでは。
「猛成苔」
自動車にはえる地衣植物。車には性別があって、そのコケの生態も変わってくる。
「低コストの秩序」
オリジナルと同じ部位に同じ分子をあてはめることで、まるっきりのコピーを作り出す三次元複製機「ミメーシン」。炭素を使ってダイヤモンドを量産だってできる。
「人間の友」
サナダムシの細胞の配列を解読すると、そこにはメッセージが書かれていた。
「《ミメーシン》の使用例」
ミメーシンで妻を複製した男。これはどっちも本物だけど重婚?同一人物の妻どうしで嫉妬や不公平が生じてくる。
「転換剤」
苦痛と快楽を逆にする転換剤。生命を守ろうとするより自殺願望ばかり起こる。失意のどん底にある人には、ばら色の日々が。
「眠れる冷蔵庫の美女」
わがままなコールドスリープ美女にだまされるな!
「美の尺度」
基準値を設定して、美を測定する機械。
「ケンタウロス論」
そうか。ケンタウロスは人間の口で馬が必要とする栄養をとらねばならなかったのか。
さて、この「ケンタウロス論」では面白い第二創世論が展開される。ノアの方舟に乗れなかった膨大な種が、洪水がひいたあと、大地で発酵し、空前絶後の婚姻と受胎がはじまる。あらゆるものがあらゆるものと交わり、あらゆるものを生み出す。ケンタウロスの場合は人と馬のあいのこ、ということになる。この空前絶後の愛の交わりによって生まれたものの例が楽しい。
なぜイルカは魚に似ているにもかかわらず、子を産み、乳で育てるのか?それは、イルカがマグロと雌牛の子どもだからだ。なぜ蝶はあれほど優雅な色をし、器用に飛ぶのか?蝿と花の子どもだからだ。亀はひき蛙と岩の子どもだし、コウモリはフクロウとネズミの子どもだし、貝はナメクジとすべすべした小石の子どもなのだ。馬と小川からはカバが生まれ、イモムシとストリクス(ローマ神話で吸血フクロウ)からはハゲワシが生まれた。
「完全雇用」
格安の労働力、昆虫と取引。ミツバチと会話するため、シンプソン氏は8の字ダンスしてコミュニケートしようとする。
「創世記第六日」
人間をどういう生物にするかについての会議。
「退職扱い」
バーチャルリアリティー機械「トレック」の顛末。
『粟津潔 デザインする言葉』
2011年5月18日 読書
粟津潔の『デザインする言葉』を読んだ。粟津デザイン室編。
デザイナー粟津潔のデザインについての発言の引用と、原画やスケッチ、美術セット写真を集めて編んだ1冊。
粟津潔はあまりアフォリズム風の言葉を書かなかったので、面白みは文章よりも図版のほうに大きく偏っているようにも思えた。
以下、目次。
第1章 すべては荒野だった
すべては荒野だった/デザインや絵画については、授業を受けた経験もなければ/私たちの未来に執念がほしい/映画は私にとって教師だった/友人の詩人、寺山修司が/チェ・ゲバラの死に顔/地図は私のデザインの故郷/言葉にたよらず、人々を目で見える地獄に案内/都市や街が、人間という生物の模倣を/私はデザイナーになる以前/人物のスケッチは、電車の中/犬さえも都市に関与できる/革命、革命といいながら/近所には、ヒゲの退役軍人や、歯科医/人生わずか二万日/創造する行為に組織や団体はいらない/ひとはやっとの思いで生きている/たとえば、自分のネクタイを1本選ぶ/私は生まれて間もなく、父を交通事故で/映画を作り出す過程とは、日々の美術作戦だ
第2章 デザインはどこにあるのか
私は毎日、デザインについて/日常のなんの変哲もない新聞や雑誌の一頁を眺めて/デザインって無意識のうちに/世界が分子、粒子のような点であっても/人間はみな思いもよらぬ出来事になかで/人は誰でも死ななくてはならない/デザインすることは、ある条件がつきものだ/今日のデザインなり建築は/線をどこまでも引くという単純な行為/都市をささえる建造物も/とにかくよいと惚れこんだら/デザインがわれわれを見張っている/デザインの解体ということは/ものを創りだすことは、見ること/<かた>をくりかえす/言葉以前の言葉/海を見る時のように線描を/方法とは、一回性の完結ではない/<かたち>はイメージがなければ/点・直線は非在であるが/完成された姿だけで、評価しても/ものを創りだしてゆく行為は/かつてポスターは街頭の美術/これは私の指紋/フェリーニのデッサン、スケッチ、イラスト/創造行為の原点が/エイゼンシュテインの当時/シャボン玉をふく人/夜明けを見ることを、ためらう
第3章 イメージの海を泳ぐ
文字の起源が絵である/きまって恐怖に近い感情/活字は何者かが描いたもの/イメージの海がひらかれる/自分自身の口唇も/デザインは新しい未知の視覚体験/私の指紋を押してみる/ほんものの自然は/象形文字を書き始めたのは/<かたち>は不思議なもの/海にはENDマークがよく似合う/イラストレーションとは/水や雨というと/複製化した現代のメディア/レタリング文字あるいは活字体にしても/漢字を覚えはじめた子どもの頃/世の中のさまざまなことに疑問をもつ/目標はないけれど/人の一生には、色々なことが
第4章 砂漠の上のデザイナー
砂漠の上にさらされている/私は哲学者や学者ではない/『心中天網島』は、金がないところで/「あなたはビートルズですか」/六十歳の半ばを超えたガウディは/自分の国をすてて/私は好奇心の塊のような人間/出会いということを、大切に/その人自身の人格を示している/気取った雰囲気をとりのぞいて/人間は皮膚という仮面をかぶっている/立ち止まることのできない永遠/絵を描くこと、働くこと、社会を変えること/十字架のように張りつけになって/自分が自分でわかっているようで/どこにも所属せず、定まった仕事もなく/真の笑いでないもの/象形文字を書き始めた/砂漠を超えることができるだろうか
イメージ図版 デザインが生まれる時
ささやき、人、暗闇/うごめき、質感、文字/モーション、地図、線/眺め、生と死、曼陀羅/繰り返し、コラージュ、海/予感、シネマ、時代/生まれくる、ダンス、エンジェル
デザイナー粟津潔のデザインについての発言の引用と、原画やスケッチ、美術セット写真を集めて編んだ1冊。
粟津潔はあまりアフォリズム風の言葉を書かなかったので、面白みは文章よりも図版のほうに大きく偏っているようにも思えた。
以下、目次。
第1章 すべては荒野だった
すべては荒野だった/デザインや絵画については、授業を受けた経験もなければ/私たちの未来に執念がほしい/映画は私にとって教師だった/友人の詩人、寺山修司が/チェ・ゲバラの死に顔/地図は私のデザインの故郷/言葉にたよらず、人々を目で見える地獄に案内/都市や街が、人間という生物の模倣を/私はデザイナーになる以前/人物のスケッチは、電車の中/犬さえも都市に関与できる/革命、革命といいながら/近所には、ヒゲの退役軍人や、歯科医/人生わずか二万日/創造する行為に組織や団体はいらない/ひとはやっとの思いで生きている/たとえば、自分のネクタイを1本選ぶ/私は生まれて間もなく、父を交通事故で/映画を作り出す過程とは、日々の美術作戦だ
第2章 デザインはどこにあるのか
私は毎日、デザインについて/日常のなんの変哲もない新聞や雑誌の一頁を眺めて/デザインって無意識のうちに/世界が分子、粒子のような点であっても/人間はみな思いもよらぬ出来事になかで/人は誰でも死ななくてはならない/デザインすることは、ある条件がつきものだ/今日のデザインなり建築は/線をどこまでも引くという単純な行為/都市をささえる建造物も/とにかくよいと惚れこんだら/デザインがわれわれを見張っている/デザインの解体ということは/ものを創りだすことは、見ること/<かた>をくりかえす/言葉以前の言葉/海を見る時のように線描を/方法とは、一回性の完結ではない/<かたち>はイメージがなければ/点・直線は非在であるが/完成された姿だけで、評価しても/ものを創りだしてゆく行為は/かつてポスターは街頭の美術/これは私の指紋/フェリーニのデッサン、スケッチ、イラスト/創造行為の原点が/エイゼンシュテインの当時/シャボン玉をふく人/夜明けを見ることを、ためらう
第3章 イメージの海を泳ぐ
文字の起源が絵である/きまって恐怖に近い感情/活字は何者かが描いたもの/イメージの海がひらかれる/自分自身の口唇も/デザインは新しい未知の視覚体験/私の指紋を押してみる/ほんものの自然は/象形文字を書き始めたのは/<かたち>は不思議なもの/海にはENDマークがよく似合う/イラストレーションとは/水や雨というと/複製化した現代のメディア/レタリング文字あるいは活字体にしても/漢字を覚えはじめた子どもの頃/世の中のさまざまなことに疑問をもつ/目標はないけれど/人の一生には、色々なことが
第4章 砂漠の上のデザイナー
砂漠の上にさらされている/私は哲学者や学者ではない/『心中天網島』は、金がないところで/「あなたはビートルズですか」/六十歳の半ばを超えたガウディは/自分の国をすてて/私は好奇心の塊のような人間/出会いということを、大切に/その人自身の人格を示している/気取った雰囲気をとりのぞいて/人間は皮膚という仮面をかぶっている/立ち止まることのできない永遠/絵を描くこと、働くこと、社会を変えること/十字架のように張りつけになって/自分が自分でわかっているようで/どこにも所属せず、定まった仕事もなく/真の笑いでないもの/象形文字を書き始めた/砂漠を超えることができるだろうか
イメージ図版 デザインが生まれる時
ささやき、人、暗闇/うごめき、質感、文字/モーション、地図、線/眺め、生と死、曼陀羅/繰り返し、コラージュ、海/予感、シネマ、時代/生まれくる、ダンス、エンジェル
『マックス・フライシャー アニメーションの天才的変革者』(追記あり)
2011年5月17日 読書
リチャード・フライシャーの『マックス・フライシャー アニメーションの天才的変革者』を読んだ。
ベティ・ブープやポパイでおなじみマックス・フライシャーの長男、自身も映画監督のリチャード・フライシャーが描く父親像。
以下、目次。
まえがき(レナード・マルティン)
序文ならびに謝辞
1 少年時代
2 漫画家デビュー
3 映画の世界へ─ロトスコープの発明
4 ココとの共演─『インク壺から』
5 バウンシング・ボールとご一緒に
6 マンハッタンでの出会い
7 フライシャー・スタジオ開設
8 ベティ・ブープ登場
9 ポパイとベティをめぐって
10 川の見える部屋
11 父“パップス”と私
12 母・エシーのこと
13 カラーへの挑戦
14 労働組合騒動
15 ニューヨーク脱出
16 新天地マイアミ
17 ガリヴァー&スーパーマン
18 兄弟の断絶
19 不意打ち
20 追い打ち
21 救いの手
22 私とディズニー、そして父
23 反撃
24 裁判の日々
25 インクウェル再び
26 破産
27 失意の晩年
28 ベティ・ブープの復活と父の最期
訳者あとがき
索引
(追記)
ブログ「四月バキュア」に、ヘレン・ケインが「ベティ・ブープのモデルは私だ」と訴えて、敗訴したこともちょこっと書きました。
http://ameblo.jp/hozanhyan/entry-10905274361.html
ベティ・ブープやポパイでおなじみマックス・フライシャーの長男、自身も映画監督のリチャード・フライシャーが描く父親像。
以下、目次。
まえがき(レナード・マルティン)
序文ならびに謝辞
1 少年時代
2 漫画家デビュー
3 映画の世界へ─ロトスコープの発明
4 ココとの共演─『インク壺から』
5 バウンシング・ボールとご一緒に
6 マンハッタンでの出会い
7 フライシャー・スタジオ開設
8 ベティ・ブープ登場
9 ポパイとベティをめぐって
10 川の見える部屋
11 父“パップス”と私
12 母・エシーのこと
13 カラーへの挑戦
14 労働組合騒動
15 ニューヨーク脱出
16 新天地マイアミ
17 ガリヴァー&スーパーマン
18 兄弟の断絶
19 不意打ち
20 追い打ち
21 救いの手
22 私とディズニー、そして父
23 反撃
24 裁判の日々
25 インクウェル再び
26 破産
27 失意の晩年
28 ベティ・ブープの復活と父の最期
訳者あとがき
索引
(追記)
ブログ「四月バキュア」に、ヘレン・ケインが「ベティ・ブープのモデルは私だ」と訴えて、敗訴したこともちょこっと書きました。
http://ameblo.jp/hozanhyan/entry-10905274361.html
裁判官、被害者、殺人犯の3つの罪のスガタを描いた小説集。
判事でありながら、毎夜老人を殺す妄想にくるしむ男。
いきなり探偵にあなたは殺人事件の被害者だと言われる男。
超能力で自由に人を殺すことが出来る少年が、国家権力を握るに至る。
これもまた、シルヴァーノ・アゴスティ(監督)の考えさせられる小説の傑作。
判事でありながら、毎夜老人を殺す妄想にくるしむ男。
いきなり探偵にあなたは殺人事件の被害者だと言われる男。
超能力で自由に人を殺すことが出来る少年が、国家権力を握るに至る。
これもまた、シルヴァーノ・アゴスティ(監督)の考えさせられる小説の傑作。
『誰もが幸せになる 1日3時間しか働かない国』
2011年5月11日 読書
シルヴァーノ・アゴスティの『誰もが幸せになる 1日3時間しか働かない国』を読んだ。
いかにもな癒しハウトゥ本らしいタイトルだが、中身は面白い。
アゴスティの監督した映画を見て面白かったので読んでみたのだが、なかなかの収穫。
1日に3時間しか働かない国キルギシアからの手紙。
もちろん、読者は「そんな楽観的な」「ユートピア」「ありえない」「無理」などという先入観をもってこの本に接するわけだが、それらの意見は手紙を書いている本人も同様に抱いていたことで、それらがほぐれていく過程が面白い。
いかにもな癒しハウトゥ本らしいタイトルだが、中身は面白い。
アゴスティの監督した映画を見て面白かったので読んでみたのだが、なかなかの収穫。
1日に3時間しか働かない国キルギシアからの手紙。
もちろん、読者は「そんな楽観的な」「ユートピア」「ありえない」「無理」などという先入観をもってこの本に接するわけだが、それらの意見は手紙を書いている本人も同様に抱いていたことで、それらがほぐれていく過程が面白い。
『アウシュビッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』
2011年4月28日 読書
プリーモ・レーヴィの『アウシュビッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察』を読んだ。
以下、目次
序
若者たちに
旅
地獄の底で
通過儀礼
カー・ベー
私たちの夜
労働
良い一日
善悪の此岸
溺れるものと助かるもの
化学の実験
オデュッセウスの歌
1944年10月
クラウシュ
研究所の三人
最後の一人
十日間の物語
若い読者に答える
本書は、アウシュビッツ収容所に流刑された作家プリーモ・レーヴィの体験を綴った作品だ。
本書の原題「SE QUESTO E’UN UOMO」(これが人間か)は、巻頭に書かれた詩から取られている。一部、紹介すると。
アウシュビッツの悲惨な状況は目を覆いたくなるものがあるが、プリーモ・レーヴィは、大声で被害者の叫びをあげるのでなく、冷静に、むしろユーモアをまじえて淡々と描写している。ユーモアというか、それは皮肉とも言えるのかもしれない。たとえば、こんな描写。
巻末には、講演にいった際に質疑応答でよく聞かれることをまとめて書いてある。これが、なんとも、感動的に読み応えがあるのだ。
1.あなたの本にはドイツ人への憎しみ、恨み、復讐心の表現がありません。彼らを許したのですか?
2.ドイツ人は知らなかったのでしょうか?連合国側は?どのようにして、ヨーロッパの真ん中で、だれにも知られずに、大虐殺が、何百万人もの人を殺戮することが、できたのでしょうか?
3.ラーゲルから脱走した囚人はいましたか?なぜ大衆的な反乱が起きなかったのでようか?
4.解放後アウシュビッツを訪れたことがありますか?
5.なぜあなたはドイツのラーゲルだけ問題にして、ソビエトのラーゲルについて沈黙しているのですか?
6.『アウシュビッツは終わらない』の登場人物で、解放後、会った人はいますか?
7.ナチのユダヤ人に対する狂信的憎悪をどう説明しますか?
8.もしラーゲルで囚人生活を送っていないとしたら、あなたはいま何になっていましたか?あの時代を思い出して何を感じますか?生き残れたのはどんな理由からだと思いますか?
これらの質問への答えは、本書にあたってみるに如くはないが、虚をつかれてしまったなあ。
以下、目次
序
若者たちに
旅
地獄の底で
通過儀礼
カー・ベー
私たちの夜
労働
良い一日
善悪の此岸
溺れるものと助かるもの
化学の実験
オデュッセウスの歌
1944年10月
クラウシュ
研究所の三人
最後の一人
十日間の物語
若い読者に答える
本書は、アウシュビッツ収容所に流刑された作家プリーモ・レーヴィの体験を綴った作品だ。
本書の原題「SE QUESTO E’UN UOMO」(これが人間か)は、巻頭に書かれた詩から取られている。一部、紹介すると。
暖かな家で
何ごともなく生きているきみたちよ
家に帰れば
熱い食事と友人の顔が見られるきみたちよ
これが人間か、考えてほしい
泥にまみれて働き
平和を知らず
パンのかけらを争い
他人がうなずくだけで死に追いやられるものが。
アウシュビッツの悲惨な状況は目を覆いたくなるものがあるが、プリーモ・レーヴィは、大声で被害者の叫びをあげるのでなく、冷静に、むしろユーモアをまじえて淡々と描写している。ユーモアというか、それは皮肉とも言えるのかもしれない。たとえば、こんな描写。
幸運なことに、私は1944年になってから、アウシュビッツに流刑にされた。
こうして3歳のエミーリアは死んだ。ドイツ人にとって、ユダヤ人の子供を殺す歴史的必然性は自明のことだったからだ。ミラーノの技師アルド・レーヴィの娘、エミーリアは、好奇心にあふれ、見えっぱりで、ほがらかで、頭のよい女の子だった。旅行中、人のひしめく貨車で、父と母はブリキの桶に温かな湯を入れて、エミーリアに湯浴みさせた。そのお湯は、堕落したドイツ人の機関士が、私たち全員を死にひきずってゆく当の機関車から、取り出すのを、許したものだった。
巻末には、講演にいった際に質疑応答でよく聞かれることをまとめて書いてある。これが、なんとも、感動的に読み応えがあるのだ。
1.あなたの本にはドイツ人への憎しみ、恨み、復讐心の表現がありません。彼らを許したのですか?
2.ドイツ人は知らなかったのでしょうか?連合国側は?どのようにして、ヨーロッパの真ん中で、だれにも知られずに、大虐殺が、何百万人もの人を殺戮することが、できたのでしょうか?
3.ラーゲルから脱走した囚人はいましたか?なぜ大衆的な反乱が起きなかったのでようか?
4.解放後アウシュビッツを訪れたことがありますか?
5.なぜあなたはドイツのラーゲルだけ問題にして、ソビエトのラーゲルについて沈黙しているのですか?
6.『アウシュビッツは終わらない』の登場人物で、解放後、会った人はいますか?
7.ナチのユダヤ人に対する狂信的憎悪をどう説明しますか?
8.もしラーゲルで囚人生活を送っていないとしたら、あなたはいま何になっていましたか?あの時代を思い出して何を感じますか?生き残れたのはどんな理由からだと思いますか?
これらの質問への答えは、本書にあたってみるに如くはないが、虚をつかれてしまったなあ。
『グラン=ギニョル傑作選——ベル・エポックの恐怖演劇』
2011年4月27日 読書
真野倫平編・訳による『グラン=ギニョル傑作選——ベル・エポックの恐怖演劇』を読んだ。
以下、目次。
序文(アニェス・ピエロン)
『闇の中の接吻』(モーリス・ルヴェル)
『幻覚の実験室』(アンドレ・ド・ロルド/アンリ・ボーシェ)
『悪魔に会った男』(ガストン・ルルー)
『未亡人』(ウジェーヌ・エロ/レオン・アブリク)
『安宿の一夜』(シャルル・メレ)
『責苦の園』(ピエール・シェーヌ)
『怪物を作る男』(マクス・モレー/シャルル・エラン/ポル・デストク)
グラン=ギニョル主要作品紹介
(『あいつだ!』『時計宝石商カリエ』『あいつの仲間』『性的スキャンダル』『グドロン博士とプリュム教授の療法』『午前二時、マルブフ街』『究極の拷問』『灯台守』『仮面舞踏会は中断される』『強迫観念、あるいは二つの力』『白い狂気』『担当外科医』『ル・アーヴルの三人の紳士』『ヴェルディエ教授の手術』『ハンプトン・クラブの夜』『サルペトリエール病院の講義』『精神病院の音楽会』『大いなる死』『恐怖の実験』『閉ざされた扉』『サボタージュ』『二分法』『赤い照明の下で』『盲人作業場』『硫酸をかけられた男』『血まみれのヒバリ、あるいはヒバリ愛好家たち』『美しき連隊』『灼熱の大地』『黒い館の謎』『緩慢な死の館』『大いなる恐怖』『ペール=ラシェーズ墓地のクリスマス・イヴ』『死んだ子供』『アッシャー家の崩壊』『激烈な欲望』『死を前にして』『サド侯爵』『狂気の女たち』『ブロンズ夫人とクリスタル氏』『電話口で』『彼方へ』『安楽死、あるいは殺す義務』『肉体の棺』『通り過ぎる死、あるいは闇の中で』『死女の愛人』『精神病院の犯罪、あるいは悪魔のような女たち』『チェカの赤い夜』『死を殺した男』『裸の男』『墓の中の光(神ハワレラトトモニ)』『血の接吻』『悪徳の人形』『鉤爪』『麻薬』『三つの仮面』『切り裂きジャック』『黒魔術』『夜の叫び声』『悪夢』『死の宝くじ、あるいは肱掛椅子の七つの犯罪』)
解説
書誌
グラン=ギニョル座、あるいはグラン=ギニョル劇について、解説ではこんなふうに書いている。
うわ~、見たい!
上記「グラン=ギニョル主要作品紹介」から、例をあげてあらすじを紹介してみよう。
『赤い照明の下で』三幕のドラマ(モーリス・ルヴェル/エチエンヌ・レー)1911年
『血まみれのヒバリ、あるいはヒバリ愛好家たち』二幕のドラマ(シャルル・ガラン)1911年
うわー!
筋立てはとことんわかりやすい。これら多くの作品も次々と翻訳が出ればいいな、と思う。
翻訳された作品のそれぞれのテーマ、モチーフなどを書いておくと。
『闇の中の接吻』
硫酸を顔にかける事件の復讐劇。
かつてはスターに硫酸をかける屈折した女性ファンが日本にもいたけど、さすがに現代ではあまり聞かないなあ。でも、ギャルバンで、人気のある子にメンバーが嫉妬のあまり熱湯かけたり、というようなことは、いまだにあるらしい。こわい!
『幻覚の実験室』
催眠を使った医学演劇。
『悪魔に会った男』
悪魔との契約。ガストン・ルルーがグラン=ギニョルのために書いた唯一の作品。
『未亡人』
「未亡人」とは、ギロチンの異名。うっかりギロチンに首をはめてしまって、はずし方がわからずに右往左往するドタバタ。
『安宿の一夜』
場末の安宿。ブルジョアが下層階級に対して抱く恐怖心を描いているとか。
『責苦の園』
オクターヴ・ミルボーの同名小説に舞台装置を借りている。拷問劇。
『怪物を作る男』
サーカスで見世物用に奇怪な動物を作り、美女を怪物に改造。
これらグラン=ギニョルを読んでて、幼い頃からのワクワク感がよみがえってきた。僕は中高生の頃にディクスン・カーが大好きでよく読んでたのだが、そのときのトキメキが再燃した。
そういえば、カーにも『夜歩く』のもとになった作品で、『グラン=ギニョール』(1929年)と題する小説がある。カーが1927年8月から5ヶ月間パリを中心にヨーロッパに滞在した時期に、グラン=ギニョルを見て、大きな影響を受けたらしい。カーは『夜歩く』の成功後、1930年4月から再びヨーロッパ旅行をしており、ほとんどをパリで過ごしている。その1930年にもカーはグラン=ギニョル劇場で観劇しているそうだ。上演の記録などから、カーが何を見てその創作のヒントにしたのかを想像するのは、きっと面白い作業だろうな、と思った。
なお、本書の編・訳者、真野倫平氏がグラン=ギニョルの紹介と関連資料の展示を行っているサイトがある。
極東グラン=ギニョル研究所
http://www.fides.dti.ne.jp/grandguignol/
以下、目次。
序文(アニェス・ピエロン)
『闇の中の接吻』(モーリス・ルヴェル)
『幻覚の実験室』(アンドレ・ド・ロルド/アンリ・ボーシェ)
『悪魔に会った男』(ガストン・ルルー)
『未亡人』(ウジェーヌ・エロ/レオン・アブリク)
『安宿の一夜』(シャルル・メレ)
『責苦の園』(ピエール・シェーヌ)
『怪物を作る男』(マクス・モレー/シャルル・エラン/ポル・デストク)
グラン=ギニョル主要作品紹介
(『あいつだ!』『時計宝石商カリエ』『あいつの仲間』『性的スキャンダル』『グドロン博士とプリュム教授の療法』『午前二時、マルブフ街』『究極の拷問』『灯台守』『仮面舞踏会は中断される』『強迫観念、あるいは二つの力』『白い狂気』『担当外科医』『ル・アーヴルの三人の紳士』『ヴェルディエ教授の手術』『ハンプトン・クラブの夜』『サルペトリエール病院の講義』『精神病院の音楽会』『大いなる死』『恐怖の実験』『閉ざされた扉』『サボタージュ』『二分法』『赤い照明の下で』『盲人作業場』『硫酸をかけられた男』『血まみれのヒバリ、あるいはヒバリ愛好家たち』『美しき連隊』『灼熱の大地』『黒い館の謎』『緩慢な死の館』『大いなる恐怖』『ペール=ラシェーズ墓地のクリスマス・イヴ』『死んだ子供』『アッシャー家の崩壊』『激烈な欲望』『死を前にして』『サド侯爵』『狂気の女たち』『ブロンズ夫人とクリスタル氏』『電話口で』『彼方へ』『安楽死、あるいは殺す義務』『肉体の棺』『通り過ぎる死、あるいは闇の中で』『死女の愛人』『精神病院の犯罪、あるいは悪魔のような女たち』『チェカの赤い夜』『死を殺した男』『裸の男』『墓の中の光(神ハワレラトトモニ)』『血の接吻』『悪徳の人形』『鉤爪』『麻薬』『三つの仮面』『切り裂きジャック』『黒魔術』『夜の叫び声』『悪夢』『死の宝くじ、あるいは肱掛椅子の七つの犯罪』)
解説
書誌
グラン=ギニョル座、あるいはグラン=ギニョル劇について、解説ではこんなふうに書いている。
モンマルトルの丘のふもと、シャプタル通りの路地の奥に一つの劇場があった。礼拝堂を改装して作られた、席数280の小さな劇場である。この劇場の売り物は、残酷で猟奇的な恐怖演劇であった。日が傾くと、人々は身の毛もよだつようなスリルを求めて劇場につめかけた。あまりの恐怖に観客が気絶することもしばしばで、介抱のために専属の医者が雇われたと噂された。
この劇場では、凶悪犯罪や猟奇殺人、サディズム・マゾヒズム、さまざまな性的倒錯といった、一般の劇場とは異なる特殊な題材が好んで取り上げられた。殺人や拷問の場面では、身体切断や血のりなどの特殊効果がふんだんに用いられた。「医学演劇」と呼ばれる一連の作品があり、マッド・ドクターや精神異常者が血の海を繰り広げた。また、中国、インド、アフリカなど異境を舞台にした作品も多く、そこにはしばしば荒唐無稽なエキゾチシズムが認められた。
うわ~、見たい!
上記「グラン=ギニョル主要作品紹介」から、例をあげてあらすじを紹介してみよう。
『赤い照明の下で』三幕のドラマ(モーリス・ルヴェル/エチエンヌ・レー)1911年
(1)フィリップは最愛の恋人を急病で失った。彼は彼女の思い出を保存するため、遺体の写真を撮影する。(2)葬儀から戻ったフィリップが写真を現像すると、彼女が目を開いている画像が浮かび上がる。(3)墓地の事務室。棺が掘り返されるあいだ、法医学者が早すぎた埋葬の例を挙げる。棺が開けられ、もがき苦しみ血まみれになった死体が現れる。
『血まみれのヒバリ、あるいはヒバリ愛好家たち』二幕のドラマ(シャルル・ガラン)1911年
(1)中国。愛鳥家のリーは大切なヒバリを妻に託して商用に旅立つ。留守中に隣人が妻をだましてかごを開けさせ、鳥を逃がす。(2)リーは隣人を家に呼び、鳥が何者かに盗まれたので犯人に復讐すると告げる。彼は妻の両親を立会人に呼ぶと、その目の前で隣人を殺害する。彼はさらに驚く両親に娘の生首を見せ、これは鳥を逃がした罰だと言い放つ。
うわー!
筋立てはとことんわかりやすい。これら多くの作品も次々と翻訳が出ればいいな、と思う。
翻訳された作品のそれぞれのテーマ、モチーフなどを書いておくと。
『闇の中の接吻』
硫酸を顔にかける事件の復讐劇。
かつてはスターに硫酸をかける屈折した女性ファンが日本にもいたけど、さすがに現代ではあまり聞かないなあ。でも、ギャルバンで、人気のある子にメンバーが嫉妬のあまり熱湯かけたり、というようなことは、いまだにあるらしい。こわい!
『幻覚の実験室』
催眠を使った医学演劇。
『悪魔に会った男』
悪魔との契約。ガストン・ルルーがグラン=ギニョルのために書いた唯一の作品。
『未亡人』
「未亡人」とは、ギロチンの異名。うっかりギロチンに首をはめてしまって、はずし方がわからずに右往左往するドタバタ。
『安宿の一夜』
場末の安宿。ブルジョアが下層階級に対して抱く恐怖心を描いているとか。
『責苦の園』
オクターヴ・ミルボーの同名小説に舞台装置を借りている。拷問劇。
『怪物を作る男』
サーカスで見世物用に奇怪な動物を作り、美女を怪物に改造。
これらグラン=ギニョルを読んでて、幼い頃からのワクワク感がよみがえってきた。僕は中高生の頃にディクスン・カーが大好きでよく読んでたのだが、そのときのトキメキが再燃した。
そういえば、カーにも『夜歩く』のもとになった作品で、『グラン=ギニョール』(1929年)と題する小説がある。カーが1927年8月から5ヶ月間パリを中心にヨーロッパに滞在した時期に、グラン=ギニョルを見て、大きな影響を受けたらしい。カーは『夜歩く』の成功後、1930年4月から再びヨーロッパ旅行をしており、ほとんどをパリで過ごしている。その1930年にもカーはグラン=ギニョル劇場で観劇しているそうだ。上演の記録などから、カーが何を見てその創作のヒントにしたのかを想像するのは、きっと面白い作業だろうな、と思った。
なお、本書の編・訳者、真野倫平氏がグラン=ギニョルの紹介と関連資料の展示を行っているサイトがある。
極東グラン=ギニョル研究所
http://www.fides.dti.ne.jp/grandguignol/
『繻子の靴』(上・下)
2011年4月26日 読書
ポール・クローデルの『繻子の靴』(上・下)を読んだ。この戯曲はポール・クローデルの集大成的作品と言われており、ちゃんと上演すれば10時間ほどかかるらしい。
中心となるストーリーは、若く美しい人妻ドニャ・プルエーズを巡る四角関係。お相手となる3人の男性とは。
年老いた夫ドン・ペラージュ。セックスレス。
恋の相手、主人公(?)騎士ドン・ロドリッグ。繻子の靴の呪いと結婚の秘蹟によりすれ違ったり妨害されたりで結ばれない。
彼女に邪恋を抱くドン・カミーユ。表面上は結ばれてるが。
タイトルは「繻子の靴 あるいは最悪必ずしも定かならず 四日間のスペイン芝居」。口上が述べる段になると、「スペイン芝居」は「スペイン歌舞伎」となっている。なるほど!歌舞伎と言われると、わかりやすい。
前書きに前半(「一日目」「二日目」)のあらすじが書いてあったので、それを引用しておこう。
「三日目」のあらすじをまとめた文章がパッと見当たらなかったので、簡単に書くと、ペラージュはロドリッグとの恋を現世では達成できず、城とともに自爆する。
って、ここで自爆してしまって、後、どんな話が続くのか、ということなのだが、四日目はドタバタだった!個人的には、次の四日目がいちばん見たい。
たとえば、四日目の第9場「スペイン国王の宮廷」は「浮かぶ宮殿の中にある」こんな感じ。
ただ、それまでにも、笑いの要素はもちろんあって、僕は「二日目」に登場する「抑えがたき男」のくだりが面白かった。
抑えがたき男は、名のとおりに抑制のきかない男で、出てきて好き勝手しほうだい。
「俺はいやだよ、楽屋でじーっと辛抱してるなんて、作者のほうでいくらそうしろって言ったってね」
と、楽屋落ち的発言してみせたり、
「ドン・ロドリッグのママをご紹介いたしましょう」
と言っておきながら、そのせりふを受けてママ、ドニャ・オノリアが登場すると、
「(怒鳴って)出てくるなってば!呼びに行くまで待ってろよ、全く!誰が出て来いと言った。引っこんでいろってば!」
とカンシャクを爆発させるのだ。
四日目は、最初に海の水をなめて「甘めえ」と言ったりしちゃうし、なんだかよくわからない綱引きが始まったりして、興味津々だ。
さて、これらあらすじを踏まえて、各場の登場人物を順に。
「一日目」
第1場 口上役、イエズス会神父
第2場 ドン・ペラージュ、ドン・バルタザール
第3場 ドン・カミーユ、ドニャ・プルエーズ
第4場 ドニャ・イザベル、ドン・ルイス
第5場 ドニャ・プルエーズ、ドン・バルタザール
第6場 スペイン国王、宰相
第7場 ドン・ロドリッグ、中国人の召使
第8場 黒人娘ジョバルバラ、ナポリのお巡り
第9場 ドン・フェルナン、ドン・ロドリッグ、ドニャ・イザベル、中国人の召使
第10場 ドニャ・プルエーズ、ドニャ・ミュジーク(音楽姫)
第11場 黒人女、ついで中国人の召使
第12場 守護天使、ドニャ・プルエーズ
第13場 ドン・バルタザール、旗手
第14場 ドン・バルタザール、旗手、中国人、軍曹、兵士たち(ドニャ・ミュジークの歌声)
「二日目」
第1場 ドン・ジル、織物職人の親方、騎士たち
第2場 抑えがたき男、ドニャ・オノリア、ドニャ・プルエーズ
第3場 ドニャ・オノリア、ドン・ペラージュ
第4場 ドン・ペラージュ、ドニャ・プルエーズ
第5場 副王、貴族たち、考古学者、礼拝堂付き司祭
第6場 聖ヤコブ
第7場 国王、ドン・ペラージュ
第8場 ドン・ロドリッグ、船長
第9場 ドン・カミーユ、ドニャ・プルエーズ
第10場 ナポリの副王、ドニャ・ミュジーク
第11場 ドン・カミーユ、ドン・ロドリッグ
第12場 ドン・ギュスマン、ルイス・ペラルド、オゾリオ、レメディオス、原住民の人夫たち
第13場 二重の影
第14場 月
「三日目」
第1場 聖ニコラ、ドニャ・ミュジーク(音楽姫)、聖ボニファス、アテネの聖ドニ、聖アドリビトゥム、侍祭たち
第2場 ドン・フェルナン、ドン・レオポルド・オーギュスト
第3場 副王、アルマグロ
第4場 歩哨3人
第5場 旅籠屋の女将、ドン・レオポルド・オーギュスト
第6場 ドン・ラミール、ドニャ・イザベル
第7場 ドン・カミーユ、侍女
第8場 ドニャ・プルエーズ(眠っている)、守護天使
第9場 副王、秘書官、ドニャ・イザベル
第10場 ドン・カミーユ、ドニャ・プルエーズ
第11場 副王、ドン・ラミール、ドニャ・イザベル、ドン・ロディラール
第12場 副王、艦長
第13場 副王、ドニャ・プルエーズ、士官たち、少女
「四日目」
第1場 漁師たち、アルコシェート、ボゴチヨス、マルトロピーヨ、マンジャカバイヨ(彼は黒い体毛が濃く、なかでも際立って馬鹿面をしている)船尾には少年のシャルル・フェリックスが手に紐をつけて坐っている。
第2場 ドン・ロドリッグ、日本人絵師大仏、ドン・マンデス・レアル
第3場 ドニャ・セテペ(七剣姫)、肉屋の娘
第4場 スペイン国王、侍従長、宰相、女優
第5場 第一のチーム=ビダンス組、第二のチーム=ヒンニュリュス組
第6場 女優、ドン・ロドリッグ、小間使い
第7場 ディエゴ・ロドリゲス、副官、(ドン・アルヒンダス)
第8場 ドン・ロドリッグ、ドニャ・セテペ
第9場 スペイン国王ならびにその宮廷、ドン・ロドリッグ
第10場 ドニャ・セテペ、肉屋の娘
第11場 大詰め、ドン・ロドリッグ、レオン神父、兵士2人
「解題」
一、クローデル、この多重的なる存在
1、多重的ということ-クローデルの紋章のために
2、<始原>と<外部>-問題形成の地平
二、結節点となる作品あるいは詩作の変容
1、初期劇作群と散文詩『東方の認識』-主題と言語
2、真昼時の深淵から-『真昼に分かつ』の危機とその変容
3、午後の地平-劇場の誘惑
三、『繻子の靴』あるいはバロック的世界大演劇
1、成立過程
2、主題と構成
3、多様な言語態-バロックの精髄
4、もうひとつの<黄昏>-「途方もない道化芝居」による
5、『繻子の靴』の余白に
四、上演とテクスト-『繻子の靴』以後の地平
1、音楽の徴の下に-技法の実験
2、劇場という現場へ-ジャン=ルイ・バローとコメディ・フランセーズ
3、ヴィテーズ革命-イデオロギーの時代の終焉あるいは演劇作業の勝利
本書は、本文と同じほどの分量の注釈がつけられている。それは本1冊分十分にあるもので、読み応えがあった。訳者の渡辺守章氏は、まず本文を通して読んだ後に、注釈を読むように、と「あとがき」になってから書いていたが、もう遅い。
本文と注釈をその都度往復して楽しませてもらったが、本文の流れが訳注の弾幕でときおり見えなくなってしまうあたり、まるでニコニコ動画みたいだった。
中心となるストーリーは、若く美しい人妻ドニャ・プルエーズを巡る四角関係。お相手となる3人の男性とは。
年老いた夫ドン・ペラージュ。セックスレス。
恋の相手、主人公(?)騎士ドン・ロドリッグ。繻子の靴の呪いと結婚の秘蹟によりすれ違ったり妨害されたりで結ばれない。
彼女に邪恋を抱くドン・カミーユ。表面上は結ばれてるが。
タイトルは「繻子の靴 あるいは最悪必ずしも定かならず 四日間のスペイン芝居」。口上が述べる段になると、「スペイン芝居」は「スペイン歌舞伎」となっている。なるほど!歌舞伎と言われると、わかりやすい。
前書きに前半(「一日目」「二日目」)のあらすじが書いてあったので、それを引用しておこう。
「一日目」
時代はスペインが世界に覇を唱えた16世紀後半、舞台は全世界。アフリカ北海岸の総指揮官ドン・ペラージュの若く美しい妻ドニャ・プルエーズと、新大陸の征服者たらんとする騎士ドン・ロドリッグの、地上では叶えられない恋が主筋。アフリカを拠点に、プルエーズに邪な恋を仕掛ける背教者ドン・カミーユが絡む。アフリカへ出発するプルエーズはロドリッグに手紙を書き、駆け落ちをしようとするが、出奔に際して、館の入口を守る聖母に「繻子の靴」の片方を捧げ、「悪へと走る時は、必ず片方の足が萎えているように」と祈る。その手紙に応えて出発したロドリッグは、暗闇の戦いに巻きこまれ重傷を負う。副筋は、ペラージュの従姉妹の娘ドニャ・ミュジーク(音楽姫)と、ナポリの副王との幻想的な恋。プルエーズ守護役の騎士ドン・バルタザールはプルエーズ脱走を容認し、船出した音楽姫の歌声を聞きながら、銃弾に倒れる。
「二日目」
母の城に引き取られたロドリッグの容態は重い。そこに現れたペラージュはプルエーズに、カミーユの守るモガドール要塞の司令官となれと命ずる。運命と深層の欲望との共犯。天上からは、オリオン星座の姿を取った聖ヤコブが、地上で引き離された恋人同士を天上で結びつける予兆を語る。国王からの帰国の命令を携えたロドリッグは、モガドールへ向かうプルエーズを追う。プルエーズの悲恋とは反対に、ミュジークはシチリアでナポリの副王と会い、音楽の徴の下に二人は結ばれる。モガドールに着いたロドリッグに、プルエーズは会うことを拒否する。その拒否を聞くロドリッグの黒い影は、そのまま執念の影となって残る。月光の中、白い壁に、恋する男女二人の姿が一体の黒い「二重の影」として出現し、神を糾弾する。「月」が現れて、禁じられた恋に責めさいなまれる二人の恋人の、深層の言葉を解放する。
「三日目」のあらすじをまとめた文章がパッと見当たらなかったので、簡単に書くと、ペラージュはロドリッグとの恋を現世では達成できず、城とともに自爆する。
って、ここで自爆してしまって、後、どんな話が続くのか、ということなのだが、四日目はドタバタだった!個人的には、次の四日目がいちばん見たい。
たとえば、四日目の第9場「スペイン国王の宮廷」は「浮かぶ宮殿の中にある」こんな感じ。
この宮殿は、幾つもの浮台からなっているが、それらはいずれもつぎはぎ細工のようで、しかも繋ぎ方が悪く、絶えずひび割れの音を発して、上下に浮きつ沈みつしているから、役者は誰一人として自分の足でしっかり立っている者はいず、この壮麗な御座所の構築は、世にも奇怪な仕方で変化する。廷臣たちのパントマイムは、一見して明らかなように、必死になってそこに踏みとどまろうとする様子を表しており、激しく頭を振り、両手を握り締め、腕を組み、眼は天を仰ぎ地を見つめ、真にそうだという大袈裟な仕草によって(陽気でかつ不吉な小楽曲に乗ってだが)、深い絶望落胆を見せている。動いてやまぬ床は、廷臣たちに、脚の屈伸や身体の傾斜によって、居場所に留まることを強いており、時として、世にも奇想天外な仕方で、彼らを驚くべきジグザグ行動へと追いやる。
ただ、それまでにも、笑いの要素はもちろんあって、僕は「二日目」に登場する「抑えがたき男」のくだりが面白かった。
抑えがたき男は、名のとおりに抑制のきかない男で、出てきて好き勝手しほうだい。
「俺はいやだよ、楽屋でじーっと辛抱してるなんて、作者のほうでいくらそうしろって言ったってね」
と、楽屋落ち的発言してみせたり、
「ドン・ロドリッグのママをご紹介いたしましょう」
と言っておきながら、そのせりふを受けてママ、ドニャ・オノリアが登場すると、
「(怒鳴って)出てくるなってば!呼びに行くまで待ってろよ、全く!誰が出て来いと言った。引っこんでいろってば!」
とカンシャクを爆発させるのだ。
「四日目」
かつての征服者である老残のロドリッグが-彼は「三日目」の別離のあとで、王の寵を失い、日本に来て、合戦で片足を失っている-、プルエーズを失ったあとで、いかにして最終的な救いに達するかを主題としている。ロドリッグの支えとなるはずの存在が、モガドールでプルエーズがロドリッグに託した七剣姫であり、少年の姿で現れるこの少女は、マジョルカ島の「進歩屋食肉店のあんちゃんを振ってお供について来ている肉屋の娘」を子分にしている。娘は父に、アルジェ解放を説くのだが、「地球の統一」を使命とする父は乗らない。娘は、前夜に出遭って恋に落ちたオーストリアの騎士ドン・ファンの招きに応えて、レパントへ出撃する船団へと、海を泳いで追いつこうとする。その間、ロドリッグ自身は、イギリス女王メアリーだと名乗る女優の誘惑に乗って、国王の仕掛けた「鼠捕り」の罠に嵌ってしまう。かつての「英雄=征服者」は、いみじくも国王が宣告するように、「全世界の見世物」となって、つまり「道化」として追放されるのである。
四日目は、最初に海の水をなめて「甘めえ」と言ったりしちゃうし、なんだかよくわからない綱引きが始まったりして、興味津々だ。
さて、これらあらすじを踏まえて、各場の登場人物を順に。
「一日目」
第1場 口上役、イエズス会神父
第2場 ドン・ペラージュ、ドン・バルタザール
第3場 ドン・カミーユ、ドニャ・プルエーズ
第4場 ドニャ・イザベル、ドン・ルイス
第5場 ドニャ・プルエーズ、ドン・バルタザール
第6場 スペイン国王、宰相
第7場 ドン・ロドリッグ、中国人の召使
第8場 黒人娘ジョバルバラ、ナポリのお巡り
第9場 ドン・フェルナン、ドン・ロドリッグ、ドニャ・イザベル、中国人の召使
第10場 ドニャ・プルエーズ、ドニャ・ミュジーク(音楽姫)
第11場 黒人女、ついで中国人の召使
第12場 守護天使、ドニャ・プルエーズ
第13場 ドン・バルタザール、旗手
第14場 ドン・バルタザール、旗手、中国人、軍曹、兵士たち(ドニャ・ミュジークの歌声)
「二日目」
第1場 ドン・ジル、織物職人の親方、騎士たち
第2場 抑えがたき男、ドニャ・オノリア、ドニャ・プルエーズ
第3場 ドニャ・オノリア、ドン・ペラージュ
第4場 ドン・ペラージュ、ドニャ・プルエーズ
第5場 副王、貴族たち、考古学者、礼拝堂付き司祭
第6場 聖ヤコブ
第7場 国王、ドン・ペラージュ
第8場 ドン・ロドリッグ、船長
第9場 ドン・カミーユ、ドニャ・プルエーズ
第10場 ナポリの副王、ドニャ・ミュジーク
第11場 ドン・カミーユ、ドン・ロドリッグ
第12場 ドン・ギュスマン、ルイス・ペラルド、オゾリオ、レメディオス、原住民の人夫たち
第13場 二重の影
第14場 月
「三日目」
第1場 聖ニコラ、ドニャ・ミュジーク(音楽姫)、聖ボニファス、アテネの聖ドニ、聖アドリビトゥム、侍祭たち
第2場 ドン・フェルナン、ドン・レオポルド・オーギュスト
第3場 副王、アルマグロ
第4場 歩哨3人
第5場 旅籠屋の女将、ドン・レオポルド・オーギュスト
第6場 ドン・ラミール、ドニャ・イザベル
第7場 ドン・カミーユ、侍女
第8場 ドニャ・プルエーズ(眠っている)、守護天使
第9場 副王、秘書官、ドニャ・イザベル
第10場 ドン・カミーユ、ドニャ・プルエーズ
第11場 副王、ドン・ラミール、ドニャ・イザベル、ドン・ロディラール
第12場 副王、艦長
第13場 副王、ドニャ・プルエーズ、士官たち、少女
「四日目」
第1場 漁師たち、アルコシェート、ボゴチヨス、マルトロピーヨ、マンジャカバイヨ(彼は黒い体毛が濃く、なかでも際立って馬鹿面をしている)船尾には少年のシャルル・フェリックスが手に紐をつけて坐っている。
第2場 ドン・ロドリッグ、日本人絵師大仏、ドン・マンデス・レアル
第3場 ドニャ・セテペ(七剣姫)、肉屋の娘
第4場 スペイン国王、侍従長、宰相、女優
第5場 第一のチーム=ビダンス組、第二のチーム=ヒンニュリュス組
第6場 女優、ドン・ロドリッグ、小間使い
第7場 ディエゴ・ロドリゲス、副官、(ドン・アルヒンダス)
第8場 ドン・ロドリッグ、ドニャ・セテペ
第9場 スペイン国王ならびにその宮廷、ドン・ロドリッグ
第10場 ドニャ・セテペ、肉屋の娘
第11場 大詰め、ドン・ロドリッグ、レオン神父、兵士2人
「解題」
一、クローデル、この多重的なる存在
1、多重的ということ-クローデルの紋章のために
2、<始原>と<外部>-問題形成の地平
二、結節点となる作品あるいは詩作の変容
1、初期劇作群と散文詩『東方の認識』-主題と言語
2、真昼時の深淵から-『真昼に分かつ』の危機とその変容
3、午後の地平-劇場の誘惑
三、『繻子の靴』あるいはバロック的世界大演劇
1、成立過程
2、主題と構成
3、多様な言語態-バロックの精髄
4、もうひとつの<黄昏>-「途方もない道化芝居」による
5、『繻子の靴』の余白に
四、上演とテクスト-『繻子の靴』以後の地平
1、音楽の徴の下に-技法の実験
2、劇場という現場へ-ジャン=ルイ・バローとコメディ・フランセーズ
3、ヴィテーズ革命-イデオロギーの時代の終焉あるいは演劇作業の勝利
本書は、本文と同じほどの分量の注釈がつけられている。それは本1冊分十分にあるもので、読み応えがあった。訳者の渡辺守章氏は、まず本文を通して読んだ後に、注釈を読むように、と「あとがき」になってから書いていたが、もう遅い。
本文と注釈をその都度往復して楽しませてもらったが、本文の流れが訳注の弾幕でときおり見えなくなってしまうあたり、まるでニコニコ動画みたいだった。
ダニイル・ハルムスの『ハルムスの世界』を読んだ。
以下、目次。
『出来事』
青いノートNo.10
出来事
落ちて行く老婆たち
ソネット
ペトロフとカマロフ
眼の錯覚
プーシキンとゴーゴリ
指物師クシャコフ
長持
ぺトラコフの身の上に起きた出来事
殴り合いの話
夢
数学者とアンドレイ・セミョーノヴィチ
門番を驚かせた若い男
心の準備のできていない人が突然新しい考えに出会ったときにどうなるかを示す四つの例
失くし物
マカーロフとペーテルセンNo.3
リンチ
出会い
失敗に終わった上演
ポン!
最近、店で売られているもの
マシュキンはコシュキンを殺した
夢が人間をからかう
狩人
歴史上のエピソード
フェージャ・ダヴィドーヴィチ
プーシキンについてのエピソード
とても気持ちのいい夏の日の始まり(交響曲)
パーキンとラクーキン
不条理文学の先駆者ダニイルハルムス
スターリン時代の不条理な現実
ハルムス再発見
『ハルムス傑作コレクション』
「ひとりの男がいた」
交響曲第二番
「親愛なるニカンドル・アンドレエヴィチ」
「ひとりのフランス人にソファがプレゼントされた」
プーシキンについて
<コラム>国民のアイドル、プーシキン
四本足のカラス
「眼に小石の刺さった、背の低い紳士が」
現象と存在についてNo.1
現象と存在についてNo.2
「あるエンジニア」
<コラム>壁の建設
スケッチ
講義
「本物の自然愛好家」
通りで起きたこと
レジ係
<コラム>ビッグ・ブラザー
物語
「ひとりの男が干しエンドウばかり食べているのに飽きて」
「みんなお金が好き」
朝
<コラム>実生活でのハルムス
「午後2時にネフスキー大通りで」
騎士
「イヴァン・ヤーコヴレヴィチ・ボーボフ」
<コラム>デフィツィット
おじいさんの死
寓話
邪魔
<コラム>黒いコートを着た男
「公案」
画家と時計
卑しい人物
「私はカプチン会の坊主と呼ばれている」
<コラム>子ども嫌い
「私は塵を舞い上げた」
名誉回復
権力
転落
私の妻に起きたこと
<コラム>椰子の木の下で
多面的な診察
「なぜみんなが私のことを天才だと思うのか」
「私たちは部屋が二つあるアパートに住んでいた」
関係
ハルムスの作品世界ー無意味さの意味
『出来事』全編と、あと、翻訳者のチョイスで訳されたもの、それに加えて、随所にコラムが書かれていて、ハルムスのことを総合的に知るにはうってつけの本。
この本読んで知ったけど、ハルムスはふだんからちょっと変なファッションで町を歩いており、子どもたちにからかわれたりしてたそうだ。
その変な格好とは。
帽子をかぶっていて、派手なジャケットにハイソックス。
親近感わくね~。
以下、目次。
『出来事』
青いノートNo.10
出来事
落ちて行く老婆たち
ソネット
ペトロフとカマロフ
眼の錯覚
プーシキンとゴーゴリ
指物師クシャコフ
長持
ぺトラコフの身の上に起きた出来事
殴り合いの話
夢
数学者とアンドレイ・セミョーノヴィチ
門番を驚かせた若い男
心の準備のできていない人が突然新しい考えに出会ったときにどうなるかを示す四つの例
失くし物
マカーロフとペーテルセンNo.3
リンチ
出会い
失敗に終わった上演
ポン!
最近、店で売られているもの
マシュキンはコシュキンを殺した
夢が人間をからかう
狩人
歴史上のエピソード
フェージャ・ダヴィドーヴィチ
プーシキンについてのエピソード
とても気持ちのいい夏の日の始まり(交響曲)
パーキンとラクーキン
不条理文学の先駆者ダニイルハルムス
スターリン時代の不条理な現実
ハルムス再発見
『ハルムス傑作コレクション』
「ひとりの男がいた」
交響曲第二番
「親愛なるニカンドル・アンドレエヴィチ」
「ひとりのフランス人にソファがプレゼントされた」
プーシキンについて
<コラム>国民のアイドル、プーシキン
四本足のカラス
「眼に小石の刺さった、背の低い紳士が」
現象と存在についてNo.1
現象と存在についてNo.2
「あるエンジニア」
<コラム>壁の建設
スケッチ
講義
「本物の自然愛好家」
通りで起きたこと
レジ係
<コラム>ビッグ・ブラザー
物語
「ひとりの男が干しエンドウばかり食べているのに飽きて」
「みんなお金が好き」
朝
<コラム>実生活でのハルムス
「午後2時にネフスキー大通りで」
騎士
「イヴァン・ヤーコヴレヴィチ・ボーボフ」
<コラム>デフィツィット
おじいさんの死
寓話
邪魔
<コラム>黒いコートを着た男
「公案」
画家と時計
卑しい人物
「私はカプチン会の坊主と呼ばれている」
<コラム>子ども嫌い
「私は塵を舞い上げた」
名誉回復
権力
転落
私の妻に起きたこと
<コラム>椰子の木の下で
多面的な診察
「なぜみんなが私のことを天才だと思うのか」
「私たちは部屋が二つあるアパートに住んでいた」
関係
ハルムスの作品世界ー無意味さの意味
『出来事』全編と、あと、翻訳者のチョイスで訳されたもの、それに加えて、随所にコラムが書かれていて、ハルムスのことを総合的に知るにはうってつけの本。
この本読んで知ったけど、ハルムスはふだんからちょっと変なファッションで町を歩いており、子どもたちにからかわれたりしてたそうだ。
その変な格好とは。
帽子をかぶっていて、派手なジャケットにハイソックス。
親近感わくね~。
スタニスワフ・レムの『枯草熱』を読んだ。1976年。
毎年この季節のなると、この小説を読もう、と思って何年たつやら。
と、いうのは、このタイトル「枯草熱(こそうねつ)」は原題が「カタル」で、その内容は、ズバリ、花粉症なのだ。
主人公の宇宙飛行士は、花粉症ゆえに、補欠にまわされてしまったのだ。火星に花粉なんかないというのに!
他にも、花粉症で苦しんでる時期に読もうと思ってる本があるので、もし読めたらまたアップします。
さて、この作品はミステリーになっている。ネタバレするのでご容赦。
読んでいて、いったい今、何が進行しているのかが明らかになるのが、ほぼ半分読み終わったあたり。
そして、やっとわかるのが、連続怪死事件のミッシングリンクさがし。
狂って死んでしまった被害者たちの共通点を探して、事件の真相をあばこうとする。
主人公は、ある被害者の行動をトレースすることで、死へのトリガーが那辺にあるのかを探ろうとしていたのだ。
共通点はいくつかあって、それは、
硫黄泉で湯治していた。
年齢は50歳前後。
がっしりした体格。
独身。
日光浴。
花粉症(アレルギー)
など。
こういう共通点が人を死なせるのはなぜなのか。
あと、死者はみんなハゲだった、という特徴もある!
なにか陰謀にまきこまれたのではないか、とも思える序盤だったが、ミッシング・リンク探しの話と判明すると、あとは一気呵成。
上にあげた死者の共通点は、次のように解釈される。
要するに、毒薬というか化学兵器というか、その毒性が致死のレベルに達するには、いくつかの要因が重なって起きる必要があって、それらを満たした者だけが死んでいたのだ。
これは、偶然の悪魔だ。
ラスト近くで、主人公もこの毒にやられて幻覚を見る。
その描写は圧巻。
主人公がいかにして罠の積み重ねを獲得していくかが、面白い。
チェスタトンか泡坂妻夫を見るような。
偶然の積み重ねがとんでもない事態を引き起こすミステリーは、それこそ掃いて捨てるほど存在している。
ひとつひとつの偶然が何だったのかが謎になるミステリー(泡坂とか)、
百万分の一の偶然でとんでもないことが起こるミステリー(小栗とか)
レムのこの作品がそうしたミステリーと違うのは、偶然の積み重ねをあばく快楽に主眼を置かず、今回主人公は毒が発現して幻覚を見るに至ったが、もしも主人公がその罠を逃れたとしても、別の人物が毒を発現させていたはずだ、という確率の問題としてわれわれの前に投げ出したところだ。
毎年この季節のなると、この小説を読もう、と思って何年たつやら。
と、いうのは、このタイトル「枯草熱(こそうねつ)」は原題が「カタル」で、その内容は、ズバリ、花粉症なのだ。
主人公の宇宙飛行士は、花粉症ゆえに、補欠にまわされてしまったのだ。火星に花粉なんかないというのに!
他にも、花粉症で苦しんでる時期に読もうと思ってる本があるので、もし読めたらまたアップします。
さて、この作品はミステリーになっている。ネタバレするのでご容赦。
読んでいて、いったい今、何が進行しているのかが明らかになるのが、ほぼ半分読み終わったあたり。
そして、やっとわかるのが、連続怪死事件のミッシングリンクさがし。
狂って死んでしまった被害者たちの共通点を探して、事件の真相をあばこうとする。
主人公は、ある被害者の行動をトレースすることで、死へのトリガーが那辺にあるのかを探ろうとしていたのだ。
共通点はいくつかあって、それは、
硫黄泉で湯治していた。
年齢は50歳前後。
がっしりした体格。
独身。
日光浴。
花粉症(アレルギー)
など。
こういう共通点が人を死なせるのはなぜなのか。
あと、死者はみんなハゲだった、という特徴もある!
なにか陰謀にまきこまれたのではないか、とも思える序盤だったが、ミッシング・リンク探しの話と判明すると、あとは一気呵成。
上にあげた死者の共通点は、次のように解釈される。
死んでいったのは、ホルモン軟膏を使い、リタリンを服用し、硫黄泉にはいり、砂糖をまぶしたナポリ風の炒りアーモンドを好んで食った男だったのである。
要するに、毒薬というか化学兵器というか、その毒性が致死のレベルに達するには、いくつかの要因が重なって起きる必要があって、それらを満たした者だけが死んでいたのだ。
これは、偶然の悪魔だ。
ラスト近くで、主人公もこの毒にやられて幻覚を見る。
その描写は圧巻。
主人公がいかにして罠の積み重ねを獲得していくかが、面白い。
チェスタトンか泡坂妻夫を見るような。
偶然の積み重ねがとんでもない事態を引き起こすミステリーは、それこそ掃いて捨てるほど存在している。
ひとつひとつの偶然が何だったのかが謎になるミステリー(泡坂とか)、
百万分の一の偶然でとんでもないことが起こるミステリー(小栗とか)
レムのこの作品がそうしたミステリーと違うのは、偶然の積み重ねをあばく快楽に主眼を置かず、今回主人公は毒が発現して幻覚を見るに至ったが、もしも主人公がその罠を逃れたとしても、別の人物が毒を発現させていたはずだ、という確率の問題としてわれわれの前に投げ出したところだ。
『女吸血鬼カルミラ』
2011年4月1日 読書レ・ファニュの『女吸血鬼カルミラ』を読んだ。榎林哲訳。
以下、目次。
こわい夢
月夜のできごと
美しいお客さま
かわったくせ
とがった歯
なぞの肖像画
真夜中の怪物
地獄への道
夢遊病
青いあざ
将軍のいかり
仮面舞踏会
ふしぎなたのみ
あれはてた屋敷のあと
カルミラの正体
吸血鬼のさいご
むすび
本書ではカーミラでなくカルミラと名前を訳したために、名前を変えたキャラクターが「マーカラ」「ミラーカ」とかじゃなくて「ミルカラ」「ミラルカ」になっている。
こうして、何冊か「カーミラ」を読んでいると、1回目にはさらっと流していたことが妙に気になってくる。
馬車に乗ってたターバン巻いた悪相の黒人とか。
せむしの旅芸人が魔除けのお守りを売りにきたとき、真っ先にカーミラが購入するが、お守りはまったく吸血鬼に効果はなかったのか、とか。(カーミラにすすめられてローラは枕にお守りをつけて寝る。その晩は快眠できるのだ)
以下、目次。
こわい夢
月夜のできごと
美しいお客さま
かわったくせ
とがった歯
なぞの肖像画
真夜中の怪物
地獄への道
夢遊病
青いあざ
将軍のいかり
仮面舞踏会
ふしぎなたのみ
あれはてた屋敷のあと
カルミラの正体
吸血鬼のさいご
むすび
本書ではカーミラでなくカルミラと名前を訳したために、名前を変えたキャラクターが「マーカラ」「ミラーカ」とかじゃなくて「ミルカラ」「ミラルカ」になっている。
こうして、何冊か「カーミラ」を読んでいると、1回目にはさらっと流していたことが妙に気になってくる。
馬車に乗ってたターバン巻いた悪相の黒人とか。
せむしの旅芸人が魔除けのお守りを売りにきたとき、真っ先にカーミラが購入するが、お守りはまったく吸血鬼に効果はなかったのか、とか。(カーミラにすすめられてローラは枕にお守りをつけて寝る。その晩は快眠できるのだ)
レ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』を読んだ。百々佑利子訳。
以下、目次
おそろしいできごとのはじまり
お客さま
二人のゆうれい
カーミラ
月夜
おそろしいゆめ
のどのきず
シュピルスドルフ将軍
吸血鬼
吸血鬼の最期
本書は児童向けの本で、ページを開けば挿絵があって、読んでいて楽しかった。
巻末には小学生の感想文もついていたが、本文と感想を読んで思ったのは、女性が寄せるカーミラへの共感のようなものだ。
吸血鬼になったカーミラ、退治されるカーミラに同情を寄せ、女性同士の性愛への甘美な憧れ、と言った感情が強く感じられる。これは平井訳にはあまりなかったもので、女性の翻訳者をまって如実に表に出てきたものだ。つまり、百合小説としての読みが前面に出てきているのだ。
以下、目次
おそろしいできごとのはじまり
お客さま
二人のゆうれい
カーミラ
月夜
おそろしいゆめ
のどのきず
シュピルスドルフ将軍
吸血鬼
吸血鬼の最期
本書は児童向けの本で、ページを開けば挿絵があって、読んでいて楽しかった。
巻末には小学生の感想文もついていたが、本文と感想を読んで思ったのは、女性が寄せるカーミラへの共感のようなものだ。
吸血鬼になったカーミラ、退治されるカーミラに同情を寄せ、女性同士の性愛への甘美な憧れ、と言った感情が強く感じられる。これは平井訳にはあまりなかったもので、女性の翻訳者をまって如実に表に出てきたものだ。つまり、百合小説としての読みが前面に出てきているのだ。
『女吸血鬼カーミラ』
2011年3月30日 読書
レ・ファニュの『女吸血鬼カーミラ』を読んだ。中尾明訳。
以下、目次。
第1章 馬車できた少女
こどもべやの幽霊
いやな思い出
将軍の手紙
旅行馬車
黒い服の貴婦人
神経質な客
人相の悪い従者
十二年まえの顔
美しい少女
第2章 熱病の流行
運命の糸
少女のくせ
讃美歌のひびき
背なかのまがった旅芸人
魔物のうわさ
第3章 ま夜中の怪物
伯爵夫人の肖像画
青ざめた顔
わたしの警告
愛と犠牲
ゆめの悪霊
おまもり札
第4章 青いあざ
あたたかいくちびる
血まみれのねまき
カーミラのゆくえ
睡眠歩行
針のきずあと
馬車で遠足
第5章 さびれた城あと
古城へむかって・・・
仮面の女
まいご
美しい客
しげみの中の礼拝堂
木こりの老人
第6章 吸血鬼のさいご
町の医者
ミラーカとカーミラ
伯爵夫人の墓
生きている死体
吸血鬼のひみつ
マーカラの恋人
この翻訳では、今までになかった部分が付加されていた。
まず、カーミラが葬送の讃美歌を聞いて、「耳が痛い!」と嫌がるシーンがあるが、そのときの讃美歌の歌詞が書いてある。
「世を さる ともをば かなしむ まじ
死こそ かみに ゆく かどで なり けれ
まことの やすみは あめに あれば
死の とく きたるを われ いとわじ
なきがら おくるを なげき なせそ
さきだち ゆきにし 主を おもいて
主は よみがえりて さかえを 受く
われらも すえの日 はかをぞ いでん
わかるる ともをば み手に ゆだね
死の ねむり さます みこえを またん」
また、ラストあたりで、今までの翻訳になかった部分として、吸血鬼に関する情報が載せてある。鏡にうつらないとか、サンザシやニンニクに弱いとか、銀の弾丸で退治されるケースもある、とか。こういう内容のことを、解説では書かず、本文のほうに書いているのである。
なるほど、いろんな翻訳があるものだ。
以下、目次。
第1章 馬車できた少女
こどもべやの幽霊
いやな思い出
将軍の手紙
旅行馬車
黒い服の貴婦人
神経質な客
人相の悪い従者
十二年まえの顔
美しい少女
第2章 熱病の流行
運命の糸
少女のくせ
讃美歌のひびき
背なかのまがった旅芸人
魔物のうわさ
第3章 ま夜中の怪物
伯爵夫人の肖像画
青ざめた顔
わたしの警告
愛と犠牲
ゆめの悪霊
おまもり札
第4章 青いあざ
あたたかいくちびる
血まみれのねまき
カーミラのゆくえ
睡眠歩行
針のきずあと
馬車で遠足
第5章 さびれた城あと
古城へむかって・・・
仮面の女
まいご
美しい客
しげみの中の礼拝堂
木こりの老人
第6章 吸血鬼のさいご
町の医者
ミラーカとカーミラ
伯爵夫人の墓
生きている死体
吸血鬼のひみつ
マーカラの恋人
この翻訳では、今までになかった部分が付加されていた。
まず、カーミラが葬送の讃美歌を聞いて、「耳が痛い!」と嫌がるシーンがあるが、そのときの讃美歌の歌詞が書いてある。
「世を さる ともをば かなしむ まじ
死こそ かみに ゆく かどで なり けれ
まことの やすみは あめに あれば
死の とく きたるを われ いとわじ
なきがら おくるを なげき なせそ
さきだち ゆきにし 主を おもいて
主は よみがえりて さかえを 受く
われらも すえの日 はかをぞ いでん
わかるる ともをば み手に ゆだね
死の ねむり さます みこえを またん」
また、ラストあたりで、今までの翻訳になかった部分として、吸血鬼に関する情報が載せてある。鏡にうつらないとか、サンザシやニンニクに弱いとか、銀の弾丸で退治されるケースもある、とか。こういう内容のことを、解説では書かず、本文のほうに書いているのである。
なるほど、いろんな翻訳があるものだ。
レ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』を読んだ。清水みち、鈴木万里の翻訳に、徳吉久の写真がふんだんに使われている。写真はストーリーに沿った挿絵ではなく、雰囲気を作るためのもの。本文は横書き。
以下、目次
プロローグ
1.記憶
2.訪問者
3.驚愕
4.奇癖
5.肖像画
6.闇
7.悪夢
8.失踪
9.疫病
10.復讐
11.回顧
12.令嬢
13.礼拝堂
14.変貌
15.棺
16.伝説
平井呈一の古めかしい翻訳でなく、どの言葉もわかりやすい、読みやすいカーミラ。その分、雰囲気が損なわれてもいるが、そこはまあ、一長一短といったところか。
翻訳が違えば、なんとなく印象に残るシーンも違ってくるのが不思議だ。
平井版では、カーミラの同性愛的描写に息詰まる迫力を感じたものだが、この現代版では、わりとあっさりしているように思えた。
翻訳によって、なるほど、と思わされる部分もあった。
たとえば、第6章のある文章を、平井版と並べてみよう。
平井呈一訳
清水みち、鈴木万里訳
このあたりなどは、平井版の註釈として、清水、鈴木版を読むことだって出来そうだ。
さて、平井版と雰囲気が違う、というところを、ひとつ例に挙げておこう。
第4章に出てくる、せむしの旅芸人の口上。
まず、現代的な清水、鈴木訳から。
つづいて、平井訳。
同じ原文から訳したとは思えない違いだ!
以下、目次
プロローグ
1.記憶
2.訪問者
3.驚愕
4.奇癖
5.肖像画
6.闇
7.悪夢
8.失踪
9.疫病
10.復讐
11.回顧
12.令嬢
13.礼拝堂
14.変貌
15.棺
16.伝説
平井呈一の古めかしい翻訳でなく、どの言葉もわかりやすい、読みやすいカーミラ。その分、雰囲気が損なわれてもいるが、そこはまあ、一長一短といったところか。
翻訳が違えば、なんとなく印象に残るシーンも違ってくるのが不思議だ。
平井版では、カーミラの同性愛的描写に息詰まる迫力を感じたものだが、この現代版では、わりとあっさりしているように思えた。
翻訳によって、なるほど、と思わされる部分もあった。
たとえば、第6章のある文章を、平井版と並べてみよう。
平井呈一訳
ちょうどそれは、そこから地獄(アヴェルナス)へ下りてまいる曲がり目に近いような感じでございました。
清水みち、鈴木万里訳
今にして思えば、冥府の入り口、アヴェルノ湖へ向かって下る最初の曲がり角のようなものだったのでしょうか。
このあたりなどは、平井版の註釈として、清水、鈴木版を読むことだって出来そうだ。
さて、平井版と雰囲気が違う、というところを、ひとつ例に挙げておこう。
第4章に出てくる、せむしの旅芸人の口上。
まず、現代的な清水、鈴木訳から。
「聞けば、この森には狼のような化物がいるとか、お嬢様方、魔除けのお守りはいかがかな」旅芸人は敷石の上に帽子を投げるとこう言いました。「あっちもこっちも死人だらけだ。だが、この霊験あらたかなお守りさえ枕につけておけば、化物が出ようと何のその」
つづいて、平井訳。
「さあてご婦人がたよ、魔除けのお守りはお求めないかな。世の噂に聞くならば、ご当所の森のうちには、人の生き血を吸う魔物めが、狼のようにウロチョロ、ウロチョロしておるそうじゃ。あちらでもこちらでも、魔性のものにかかってコロリコロリと死ぬものが多いによって、それここに、この魔除けのお札がある。これをもっておれば大丈夫、金の脇差じゃ。これなる守り札を、ちょいとこうして枕に針でとめておく。ただのこれだけで、魔性のやつが来ても大の安心、カンラカンラと笑ってやれるのじゃ」
同じ原文から訳したとは思えない違いだ!
レ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』を読んだ。平井呈一訳。
7編の中短編が収録されている。
レ・ファニュは19世紀のアイルランドの怪奇小説家で、この短編集読んでるかぎりは、非常に薄気味悪い。
で、各編の、薄気味悪かった部分をとりあげていこうかと思う。
「白い手の怪」
「墓掘りクルックの死」
「シャルケン画伯」
「大地主トビーの遺言」
「仇魔」
1.足音
2.監視者
3.公告
4.バートン氏、牧師と語る
5.バートン氏おのれの病歴を語る
6.再会
7.逃亡
8.小康
9.冥福
「判事ハーボットル氏」
1.判事の家
2.ピーターズ氏
3.ルイズ・パインウェック
4.妨害
5.捜索者
6.逮捕
7.裁判長トゥーフォールド
8.だれか屋敷へはいったものがある
9.判事、屋敷を去る
「吸血鬼カーミラ」
1.子供のころの恐怖
2.客
3.意見の交換
4.彼女の性癖
5.ふしぎな相似
6.ふしぎな苦悶
7.地獄への道
8.捜索
9.医師
10.子に先立たれて
11.ものがたり
12.懇願
13.木こり
14.めぐりあい
15.試練と処刑
16.むすび
カーミラだけは、その後の女吸血鬼もののお手本みたいなもので、薄気味悪さよりも、ストーリーのうまさが光っていた。
何より驚いたのは、現代に通じるところが多々あるところだ。
まず、カーミラがどんな女性であったかという描写を見ると、
わ。こんな女の子、山ほど知ってる!
また、結局吸血鬼は棺で血に浸されて寝ているところを突き止められると、杭を打たれて首をはねられて、あっさりと死んでしまうのだが、これは現代のインターネットの世界で、その実名や職業、住所をつきとめられると大ダメージを負ってしまうのと同工異曲ではないか。
そして、吸血鬼は、自殺したものがなる、と書いてあり、日本での自殺者の増加を考えあわせると、なるほど、カーミラみたいな人物をざらに見かけるのは、むべなるかな、とも思えてくるのである。
7編の中短編が収録されている。
レ・ファニュは19世紀のアイルランドの怪奇小説家で、この短編集読んでるかぎりは、非常に薄気味悪い。
で、各編の、薄気味悪かった部分をとりあげていこうかと思う。
「白い手の怪」
ものの5分もたたないうちに、病児はキャーッと声をたてて、火のつくように泣きだしました。と、その瞬間です。乳母はその時はじめて、子供の病気の真因をさぐりあてたのでした。夫人も、乳母の目の行くほうをともに追って、その時はっきりそれを目に見たのです。
二人は、枕元にある戸棚の戸のすきまからスルリとすべり出て、垂れ幕のかげにひそみこんだ、例の白いブヨブヨした手を、はっきりとその時見たのでした。
「墓掘りクルックの死」
客は馬のそばへ引きかえした。すると、死んだ墓掘り男の死骸の置いてある馬車小屋のとびらが、ひとりでにギーとあいたようであった。客は、そのまま戸口から中へはいった。
「シャルケン画伯」
三人とも、今夜の客に妙なくせが二つあったことを見のがすほど、おちつきを失っていたわけではなかった。それは、座にいる間、客のまぶたが一ども閉じなかったこと-つまり、まばたきを一ぺんもしなかったことと、それから呼吸をするたびに胸が波を打たないために、からだ全体が死人のようにじっと静止していることと、この二つであった。
「大地主トビーの遺言」
犬は、ややしばらく、倒れた木の幹のあいだへしきりと頭をつっこんでいたが、そのうちにだんだん首が長く伸びてきて、胴体が白い大きなトカゲみたいによじれ、なおも懸命にもぐりこもうとして、目をすえ、ウーウーうなりながら、柵にのみこまれるように身をもんでいた。
「仇魔」
1.足音
2.監視者
3.公告
4.バートン氏、牧師と語る
5.バートン氏おのれの病歴を語る
6.再会
7.逃亡
8.小康
9.冥福
あとを尾けられているのかな。・・・こういう疑念は、どんな時だって、あんまりいい気持のものではありません。ことに、そんな寂しい道では、なおさらのことです。あんまり気になるから、バートン氏は、ひとつあとから来るやつと顔を見合わせてやろうと思って、いきなりクルリとうしろをふり向きました。ところが、見わたす往来には、月かげがしらじらとさしているばかりで、人の影、犬の子いっぴき見えません。
「判事ハーボットル氏」
1.判事の家
2.ピーターズ氏
3.ルイズ・パインウェック
4.妨害
5.捜索者
6.逮捕
7.裁判長トゥーフォールド
8.だれか屋敷へはいったものがある
9.判事、屋敷を去る
老判事がギョッと驚いたことには、ルイズ・パインウェックの姿をそこに見つけたのです。パインウェックは例のごとく薄い唇にニヤリと笑みをうかべながら、青白い顎をグイとあげ、人目に立つのも知らぬげに、細い首巻を曲がった指で気にしてひろげては、あっちこっち見まわしています。首をまわすたびに、麻縄の食いこんだ跡らしい、紫色に腫れ上がった傷あとが、首のまわりにはっきりとみえました。
「吸血鬼カーミラ」
1.子供のころの恐怖
2.客
3.意見の交換
4.彼女の性癖
5.ふしぎな相似
6.ふしぎな苦悶
7.地獄への道
8.捜索
9.医師
10.子に先立たれて
11.ものがたり
12.懇願
13.木こり
14.めぐりあい
15.試練と処刑
16.むすび
カーミラだけは、その後の女吸血鬼もののお手本みたいなもので、薄気味悪さよりも、ストーリーのうまさが光っていた。
何より驚いたのは、現代に通じるところが多々あるところだ。
まず、カーミラがどんな女性であったかという描写を見ると、
朝起きてくるのが遅いのなんの、だいたい午後の1時ごろにならなければ寝室から降りてまいりません。そしてチョコレートを一杯飲むだけで、なにも食べません。それからわたくしと散歩に出ます。と申しても、ほんのそこらをぶらつくだけでございますが、見ているとどうやら疲れてしまうようすで、いくらも歩かないうちにお城へもどるか、木立のあいだにところどころ置いてあるベンチに休むかいたします。これはからだが疲れるのであって、心はそれに同調しているのではないのでございます。その証拠には、いつでもおしゃべりは元気にいたして、またたいそう話上手でございました。
わ。こんな女の子、山ほど知ってる!
また、結局吸血鬼は棺で血に浸されて寝ているところを突き止められると、杭を打たれて首をはねられて、あっさりと死んでしまうのだが、これは現代のインターネットの世界で、その実名や職業、住所をつきとめられると大ダメージを負ってしまうのと同工異曲ではないか。
そして、吸血鬼は、自殺したものがなる、と書いてあり、日本での自殺者の増加を考えあわせると、なるほど、カーミラみたいな人物をざらに見かけるのは、むべなるかな、とも思えてくるのである。
『近代政治の脱構築-共同体・免疫・生政治』
2011年3月22日 読書
ロベルト・エスポジトの『近代政治の脱構築-共同体・免疫・生政治』を読んだ。
エスポジトの過去10年にわたる論考を集めて、彼の主著3部作『コムニタス』『イムニタス』『ビオス』に相当する部分にそって、第1部(共同体)第2部(免疫)第3部(生政治)の3部構成でまとめてある。
以下、目次。
訳者によるイントロダクション ナポリ発、全人類へ―ロベルト・エスポジトの思想圏/岡田温司
「ナポリを見てから死ね」/「ロベルト・エスポジト」-「ポスト・ロジエ・ベルト」/エスポジトを読む三つの鍵/エスポジトの生政治-アガンベンとネグリのあいだ/フーコーの限界/免疫(イムニタス)・共同体(コムニタス)/免疫化の功罪/ナチズムの遺産とその転倒/法と免疫/「人格」の脱構築
第1部
第1章 共同体の法
第2章 メランコリーと共同体
第3章 共同体とニヒリズム
第2部
第4章 免疫型民主主義
第5章 自由と免疫
第6章 免疫化と暴力
第3部
第7章 生政治と哲学
第8章 ナチズムとわたしたち
第9章 政治と人間の自然
第10章 全体主義あるいは生政治―二十世紀の哲学的解釈のために
第11章 非人称の哲学へ向けて
うひょ~。
エスポジトの過去10年にわたる論考を集めて、彼の主著3部作『コムニタス』『イムニタス』『ビオス』に相当する部分にそって、第1部(共同体)第2部(免疫)第3部(生政治)の3部構成でまとめてある。
以下、目次。
訳者によるイントロダクション ナポリ発、全人類へ―ロベルト・エスポジトの思想圏/岡田温司
「ナポリを見てから死ね」/「ロベルト・エスポジト」-「ポスト・ロジエ・ベルト」/エスポジトを読む三つの鍵/エスポジトの生政治-アガンベンとネグリのあいだ/フーコーの限界/免疫(イムニタス)・共同体(コムニタス)/免疫化の功罪/ナチズムの遺産とその転倒/法と免疫/「人格」の脱構築
第1部
第1章 共同体の法
第2章 メランコリーと共同体
第3章 共同体とニヒリズム
第2部
第4章 免疫型民主主義
第5章 自由と免疫
第6章 免疫化と暴力
第3部
第7章 生政治と哲学
第8章 ナチズムとわたしたち
第9章 政治と人間の自然
第10章 全体主義あるいは生政治―二十世紀の哲学的解釈のために
第11章 非人称の哲学へ向けて
ナチズムが戦争から抜け出たのは、軍事的、政治的レベルにおいて決定的に敗北したからであって、文化的、言語的レベルにおいては、必ずしも全面的に敗北したわけではない(第10章より)
うひょ~。
ウンベルト・エーコの『醜の歴史』を読んだ。
豊富な図版と引用で、西洋における「醜」の歴史をたどる浩瀚な1冊。
以下、目次。
序論
第1章 古典世界の醜
1.ギリシア世界は美によって支配されていたか?
2.ギリシア世界と恐怖
第2章 受難、死、殉教
1.宇宙の汎美主義ヴィジョン
2.キリストの受難
3.殉教者、隠者、贖罪者
4.死の凱旋
第3章 黙示録、地獄、悪魔
1.恐怖の世界
2.地獄
3.悪魔のメタモルフォセス
第4章 モンスター(怪物)とポルテント(予兆)
1.プロディジオ(驚異)とモンスター(怪物)
2.測りがたいものの美学
3.モンスターの教訓化
4.ミラビリア(驚異)
5.モンスターの運命
第5章 醜悪なもの、滑稽なもの、猥褻なもの
1.プリアポス
2.農夫を主題にした風刺文学と謝肉祭
3.ルネサンスの解放
4.カリカチュア(諷刺漫画)
第6章 古代からバロック時代までの女性の醜さ
1.反女性の伝統
2.マニエリスムとバロック
第7章 近代世界の悪魔
1.叛逆天使サタンから哀れなメフィストフェレスへ
2.「敵」の悪魔化
第8章 魔女信仰、悪魔崇拝、サディズム
1.魔女
2.悪魔崇拝、サディズム、残酷趣味
第9章 フィジカ・クリオーサ(肉体への好奇心)
1.月の出産と死体の開腹
2.人相学
第10章 ロマン主義による醜の解放
1.醜の美学
2.醜い者と呪われた者
3.醜い者と不幸な者
4.不幸な者と病んだ者
第11章 不気味なもの
1.不気味なもの
第12章 鉄の塔と象牙の塔
1.産業社会の醜さ
2.デカダン主義と醜の放縦
第13章 アヴァンギャルドと醜の勝利
1.アヴァンギャルドと醜の勝利
第14章 他者の醜、キッチュ、キャンプ
1.他者の醜
2.キッチュ
3.キャンプ
第15章 現代の醜
1.現代の醜
エーコは本書15章で「醜」への省察を4つにまとめている。
醜は時代や文化によって相対的であること。
昨日受け入れがたかったものが明日には受け入れられるかもしれないこと。
醜いと感じられたものが、適切なコンテキストでは全体としての美に役立つこともあること。
省察のこれら3つの相対主義は、あげられている図版を見るかぎり、確かに納得させられるもので、今の眼で見たら、なぜこれが醜であるのかがよくわからないものがあった。
そして4つめは、生理学に基づいた反応は時代や文化が異なろうと多かれ少なかれ不変であること!ちゃぶ台をひっくり返した~。
また、美術が執拗に繰り返し醜を表現した理由は、こう解釈される。「形而上学者の楽観主義にもかかわらず、この世界には、どうしようもないことだし、哀しいことだが、何らかの悪がある」ということを思い出させようとしたのだ、と。
エーコの「醜の歴史」を受けて、振り返って、現代日本での「醜礼讃」の傾向はどう解釈すればいいものか、課題は大きい。
豊富な図版と引用で、西洋における「醜」の歴史をたどる浩瀚な1冊。
以下、目次。
序論
第1章 古典世界の醜
1.ギリシア世界は美によって支配されていたか?
2.ギリシア世界と恐怖
第2章 受難、死、殉教
1.宇宙の汎美主義ヴィジョン
2.キリストの受難
3.殉教者、隠者、贖罪者
4.死の凱旋
第3章 黙示録、地獄、悪魔
1.恐怖の世界
2.地獄
3.悪魔のメタモルフォセス
第4章 モンスター(怪物)とポルテント(予兆)
1.プロディジオ(驚異)とモンスター(怪物)
2.測りがたいものの美学
3.モンスターの教訓化
4.ミラビリア(驚異)
5.モンスターの運命
第5章 醜悪なもの、滑稽なもの、猥褻なもの
1.プリアポス
2.農夫を主題にした風刺文学と謝肉祭
3.ルネサンスの解放
4.カリカチュア(諷刺漫画)
第6章 古代からバロック時代までの女性の醜さ
1.反女性の伝統
2.マニエリスムとバロック
第7章 近代世界の悪魔
1.叛逆天使サタンから哀れなメフィストフェレスへ
2.「敵」の悪魔化
第8章 魔女信仰、悪魔崇拝、サディズム
1.魔女
2.悪魔崇拝、サディズム、残酷趣味
第9章 フィジカ・クリオーサ(肉体への好奇心)
1.月の出産と死体の開腹
2.人相学
第10章 ロマン主義による醜の解放
1.醜の美学
2.醜い者と呪われた者
3.醜い者と不幸な者
4.不幸な者と病んだ者
第11章 不気味なもの
1.不気味なもの
第12章 鉄の塔と象牙の塔
1.産業社会の醜さ
2.デカダン主義と醜の放縦
第13章 アヴァンギャルドと醜の勝利
1.アヴァンギャルドと醜の勝利
第14章 他者の醜、キッチュ、キャンプ
1.他者の醜
2.キッチュ
3.キャンプ
第15章 現代の醜
1.現代の醜
エーコは本書15章で「醜」への省察を4つにまとめている。
醜は時代や文化によって相対的であること。
昨日受け入れがたかったものが明日には受け入れられるかもしれないこと。
醜いと感じられたものが、適切なコンテキストでは全体としての美に役立つこともあること。
省察のこれら3つの相対主義は、あげられている図版を見るかぎり、確かに納得させられるもので、今の眼で見たら、なぜこれが醜であるのかがよくわからないものがあった。
そして4つめは、生理学に基づいた反応は時代や文化が異なろうと多かれ少なかれ不変であること!ちゃぶ台をひっくり返した~。
また、美術が執拗に繰り返し醜を表現した理由は、こう解釈される。「形而上学者の楽観主義にもかかわらず、この世界には、どうしようもないことだし、哀しいことだが、何らかの悪がある」ということを思い出させようとしたのだ、と。
エーコの「醜の歴史」を受けて、振り返って、現代日本での「醜礼讃」の傾向はどう解釈すればいいものか、課題は大きい。
陳舜臣の『凍った波紋』を読んだ。1970年。
真珠業界を舞台に展開される現代ミステリー。
ではあるが、陳舜臣ミステリーの特色である2つの要素、
1、戦争のときに起こったことが事件の根にある。
2、犯人っぽくない女性が事件の鍵を握っている。
は、ここでも健在で、ああ、陳舜臣の推理小説を読んでるなあ、と堪能。
以下、目次。
ミニに真珠
桃食いザル
しらたま
ポイント
痴惑
かげろう
その名
デートの夜
曲線
焦点
暗い影
ひめごと
転換
赤い輪
積木
波がしら
ざわめき
夜光虫
幕
さて、今回事件の根っこになった戦争中の出来事とは何か。
昭和12年にはじまった日中戦争。
伸びた戦線の周辺地域を安定させるため、日本軍は中国の地方軍閥を懐柔する手段に出た。
そんな軍閥のなかで、金銭欲や名誉欲もあまりないけど、色きちがいの将軍がいた。
この将軍、女性コレクターでハーレムを作り、狂乱の限りを尽くしていたのだ。
その将軍のもとに派遣された日本人女性。これが事件のもとになる。
戦後、その将軍のもとにいたことを知る人物(もちろん、脅迫するわけだ)が、次々と死んでいく。
犯人はその女性なのか、脅迫する男たちを許せない正義感の強い人物か、それとも、女性を慕う男なのか、それとも、女性が中国で生んだ息子が日本にやってきて母親のために復讐したのか、それとも、そんな復讐心に燃える青年を手助けしようとしたホモなのか。
真相は闇の中。いや、読めばわかるかな。
真珠業界を舞台に展開される現代ミステリー。
ではあるが、陳舜臣ミステリーの特色である2つの要素、
1、戦争のときに起こったことが事件の根にある。
2、犯人っぽくない女性が事件の鍵を握っている。
は、ここでも健在で、ああ、陳舜臣の推理小説を読んでるなあ、と堪能。
以下、目次。
ミニに真珠
桃食いザル
しらたま
ポイント
痴惑
かげろう
その名
デートの夜
曲線
焦点
暗い影
ひめごと
転換
赤い輪
積木
波がしら
ざわめき
夜光虫
幕
さて、今回事件の根っこになった戦争中の出来事とは何か。
昭和12年にはじまった日中戦争。
伸びた戦線の周辺地域を安定させるため、日本軍は中国の地方軍閥を懐柔する手段に出た。
そんな軍閥のなかで、金銭欲や名誉欲もあまりないけど、色きちがいの将軍がいた。
この将軍、女性コレクターでハーレムを作り、狂乱の限りを尽くしていたのだ。
その将軍のもとに派遣された日本人女性。これが事件のもとになる。
戦後、その将軍のもとにいたことを知る人物(もちろん、脅迫するわけだ)が、次々と死んでいく。
犯人はその女性なのか、脅迫する男たちを許せない正義感の強い人物か、それとも、女性を慕う男なのか、それとも、女性が中国で生んだ息子が日本にやってきて母親のために復讐したのか、それとも、そんな復讐心に燃える青年を手助けしようとしたホモなのか。
真相は闇の中。いや、読めばわかるかな。