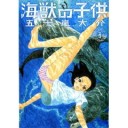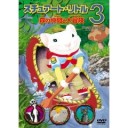常盤寄席〜『ばらの合唱・死の町』『疾風影太郎』『海獣の子供』
2008年9月19日 落語
夜勤明けに、谷6に行って来週行くイベントの場所とか調べながら散策。
もうひとつの目的は、「ひかりの輪」の大阪道場の場所の確認。いろんなところに「出て行け」のビラは貼ってあったが、かんじんの支部の場所はわからず。まあ、わかったところで行くことはないけど。21日の上祐説法会のときには、もっと騒がしくなってるんだろうな。それより、上町あたりは面白い店がちらほらあって、楽しかった。
夕方から天満橋で「常盤寄席」
1.みかん屋/桂ひろば
マクラは桂こごろうと行った北海道と地震。
2.ヘイ!タクシー/笑福亭仁智
マクラは3日で四国三十ケ所巡ったことと、小さな飛行機。
智之介復活とあって飛び入りで出演。
3.軽業/林家染太
マクラは、握手の際に御祝儀かと思ったらピップエレキバン。
「とったりみたり」(角力)では「大麻を」とタイムリーにボケる。
4.死神/笑福亭智之介
マクラは入院中の点滴と排便。
読んだ漫画はまず、小沢さとるの復刻2冊。
『ばらの合唱(コーラス)・死の町』
「ばらの合唱」は「週刊マーガレット」に昭和39年に連載された少女漫画。
野球選手と事故でめくらになった娘の恋物語。
自分だけ軽傷で済んだ野球選手は責任を感じてか、さっぱり打てなくなる。
野球選手は「めくらがなんだ。おしになったっていい。たとえびっこになったっていい。ぼくはきみがすきなんだ」と思っているが、娘のほうは「あの人にもうめくらのわたしをみせたくない」と言って会おうとしない。
結局、娘の妹があいだに入ってやきもきするうちに雨にうたれて肺炎になり、結果、娘と選手は結ばれる。
「死の町」は富士見出版から昭和34年7月に発行された単行本。「盗まれた街」タイプのSF。
遊星人が「命の実」を使って、住人に変身していく。
「へんね、おかあさんはいつもとちがうみたい」みたいな。
手に星形のあさがあるのが別人のしるし。
最後は命の実の畑にガソリン撒いてもやしちゃう。
『疾風影太郎』は武内つなよし原作の忍者漫画。「週刊少年サンデー」昭和35年33号〜42号連載。
「なぞの黒鳥の巻」
山形玄斎ひきいる竜の部落の忍者(正義)と湯煙虎太夫ひきいる虎の部落の忍者(悪)がとにかく戦いまくる。主人公はタイトルどおり、影太郎。
少年ジェットよろしく馬を模したスクーター状の乗り物「流れ飛車」が出て来たりする。
敵だと思ってた風丸が実は味方であった。風丸は影太郎の成長と、竜の部落の復興を確認して、江戸に帰って行く。
「やみの竜王の巻」
人がり新左によって濡れ衣きせられ、さらに脱獄させられた影太郎たち。
新左は若葉城を狙う「やみの竜王」で、城のものたちが脱獄した影太郎を追って竜の部落に兵を出しているすきに、手薄になった城を攻め落す計略。
さあ、これから戦いが勃発、というときに、「だけど影太郎たちが計略に気づいて駆け付けて、若葉城は無事でした」みたいな顛末を1ページですませている。急に連載がうちきられたと思われる。
『ひみつのアッコちゃん(赤塚不二夫)』(「たのしい幼稚園」平成元年5月増刊号ふろく)
「天使はうそつき」「万引きつかまえ作戦」「アッコちゃんの大まじゅつ」「小さな世界のぼうけん」「銀行強盗大ついせき」「カンきちのちょきんとプレゼント」
収録作品は昭和37年4月から昭和40年9月まで『りぼん』に掲載されたもの。
背景が明らかに昭和30年代なのだが、こういうのはエバーグリーンなんだ。
『ウルトラマン(一峰大二)』(「ヒーローマガジン」平成元年10月号ふろく)
「3大怪獣の巻」「怪獣ケムラーの巻」
怪獣の怖さといったらない。
同じヒーローマガジンのふろく『大挑戦!なぞなぞ111』を解いてみたが、間違った問題を復習しておく。
「とってもよごれているトンボは?」(こたえ:アカトンボ)
「すみっこに『五』ってかいてあるものは、なんだ?」(こたえ:はしご)
「いつも月がでている国ってどこかな?」(こたえ:ヨルダン)
『海獣の子供』1〜3、五十嵐大介
渾身の大作。
第2巻読んでるとき、テレビではちょうど台風のニュースで持ちきりだった。
第3巻は過去のことが明かされる。
絵のもつパワーが凄い。
僕にとっての夏休み感は、どれだけマスメディアと無縁な時間を過ごせるか、にかかっている。第1巻〜第2巻あたりはその点、最高。3巻に入ってただ茫洋としていたスケールがはっきりと「大きいですよ!」「深いですよ!」と主張しはじめた。
この先、どうおさめていくのか、楽しみだ。
読書は『ナショナリズムの由来』を少しずつ。電車の中で読むことには慣れたが、鞄の中身が本だけになってしまうのがたいへん。
もうひとつの目的は、「ひかりの輪」の大阪道場の場所の確認。いろんなところに「出て行け」のビラは貼ってあったが、かんじんの支部の場所はわからず。まあ、わかったところで行くことはないけど。21日の上祐説法会のときには、もっと騒がしくなってるんだろうな。それより、上町あたりは面白い店がちらほらあって、楽しかった。
夕方から天満橋で「常盤寄席」
1.みかん屋/桂ひろば
マクラは桂こごろうと行った北海道と地震。
2.ヘイ!タクシー/笑福亭仁智
マクラは3日で四国三十ケ所巡ったことと、小さな飛行機。
智之介復活とあって飛び入りで出演。
3.軽業/林家染太
マクラは、握手の際に御祝儀かと思ったらピップエレキバン。
「とったりみたり」(角力)では「大麻を」とタイムリーにボケる。
4.死神/笑福亭智之介
マクラは入院中の点滴と排便。
読んだ漫画はまず、小沢さとるの復刻2冊。
『ばらの合唱(コーラス)・死の町』
「ばらの合唱」は「週刊マーガレット」に昭和39年に連載された少女漫画。
野球選手と事故でめくらになった娘の恋物語。
自分だけ軽傷で済んだ野球選手は責任を感じてか、さっぱり打てなくなる。
野球選手は「めくらがなんだ。おしになったっていい。たとえびっこになったっていい。ぼくはきみがすきなんだ」と思っているが、娘のほうは「あの人にもうめくらのわたしをみせたくない」と言って会おうとしない。
結局、娘の妹があいだに入ってやきもきするうちに雨にうたれて肺炎になり、結果、娘と選手は結ばれる。
「死の町」は富士見出版から昭和34年7月に発行された単行本。「盗まれた街」タイプのSF。
遊星人が「命の実」を使って、住人に変身していく。
「へんね、おかあさんはいつもとちがうみたい」みたいな。
手に星形のあさがあるのが別人のしるし。
最後は命の実の畑にガソリン撒いてもやしちゃう。
『疾風影太郎』は武内つなよし原作の忍者漫画。「週刊少年サンデー」昭和35年33号〜42号連載。
「なぞの黒鳥の巻」
山形玄斎ひきいる竜の部落の忍者(正義)と湯煙虎太夫ひきいる虎の部落の忍者(悪)がとにかく戦いまくる。主人公はタイトルどおり、影太郎。
少年ジェットよろしく馬を模したスクーター状の乗り物「流れ飛車」が出て来たりする。
敵だと思ってた風丸が実は味方であった。風丸は影太郎の成長と、竜の部落の復興を確認して、江戸に帰って行く。
「やみの竜王の巻」
人がり新左によって濡れ衣きせられ、さらに脱獄させられた影太郎たち。
新左は若葉城を狙う「やみの竜王」で、城のものたちが脱獄した影太郎を追って竜の部落に兵を出しているすきに、手薄になった城を攻め落す計略。
さあ、これから戦いが勃発、というときに、「だけど影太郎たちが計略に気づいて駆け付けて、若葉城は無事でした」みたいな顛末を1ページですませている。急に連載がうちきられたと思われる。
『ひみつのアッコちゃん(赤塚不二夫)』(「たのしい幼稚園」平成元年5月増刊号ふろく)
「天使はうそつき」「万引きつかまえ作戦」「アッコちゃんの大まじゅつ」「小さな世界のぼうけん」「銀行強盗大ついせき」「カンきちのちょきんとプレゼント」
収録作品は昭和37年4月から昭和40年9月まで『りぼん』に掲載されたもの。
背景が明らかに昭和30年代なのだが、こういうのはエバーグリーンなんだ。
『ウルトラマン(一峰大二)』(「ヒーローマガジン」平成元年10月号ふろく)
「3大怪獣の巻」「怪獣ケムラーの巻」
怪獣の怖さといったらない。
同じヒーローマガジンのふろく『大挑戦!なぞなぞ111』を解いてみたが、間違った問題を復習しておく。
「とってもよごれているトンボは?」(こたえ:アカトンボ)
「すみっこに『五』ってかいてあるものは、なんだ?」(こたえ:はしご)
「いつも月がでている国ってどこかな?」(こたえ:ヨルダン)
『海獣の子供』1〜3、五十嵐大介
渾身の大作。
第2巻読んでるとき、テレビではちょうど台風のニュースで持ちきりだった。
第3巻は過去のことが明かされる。
絵のもつパワーが凄い。
僕にとっての夏休み感は、どれだけマスメディアと無縁な時間を過ごせるか、にかかっている。第1巻〜第2巻あたりはその点、最高。3巻に入ってただ茫洋としていたスケールがはっきりと「大きいですよ!」「深いですよ!」と主張しはじめた。
この先、どうおさめていくのか、楽しみだ。
読書は『ナショナリズムの由来』を少しずつ。電車の中で読むことには慣れたが、鞄の中身が本だけになってしまうのがたいへん。
小朝正蔵いっ平三人の会@松竹座〜『ロベスピエール/毛沢東 革命とテロル』
2008年9月9日 落語
午後2時から松竹座で「小朝正蔵いっ平三人の会」
子ほめ/林家はな平
親子酒/林家たこ平
悋気の独楽/林家いっ平
西行鼓ケ滝/林家正蔵
仲入り
太神楽曲芸/翁家勝丸
お札はがし/春風亭小朝
(お囃子/内海英華)
開場時間に到着したら、あまりにも観客の年齢層が高くて驚いた。全員の髪の毛を抜いて並べたら、全体として白く見えたに違いない。火曜日の午後2時に見に来れるのは老人だけだ、と言われればそうなのかもしれないが。
二等席で見たせいか、マイクを通して響く声はなんだか聞き取りにくくて、しかも天井から高座を見下ろしているような気分。いっ平あたりからやっと慣れて見ることができた。
それぞれ面白くて、見に来た価値はあったと思うが、仲入りまでは、ちょっとどうかな、と首をひねっていた。たこ平の酔っぱらい演技に客席から拍手が起こっていたが、まるで拍手を求めているかのような演技で、すごく違和感があった。上方であれば、拍手が起こりそうなときにはそれを回避して笑いにつなげるだろうと思った。それが上方と江戸の違いなのか、と僕は思ったのだが、さて。
いっ平は期待していなかった分だけ、面白く見れた。マクラでは東京の落語家さんの話などですっかり気分がほぐれた。演目も今まで上方で聞いていた噺とは微妙に設定が違っていて、「ほほう」と思った。体当たりの演出は、それはそれでありなんじゃないか、と満足。
それとは対照的だったのは正蔵で、テレビではたよりないけど高座ではさぞ本格的なんだろう、と期待していた。まあ、期待はずれとはいかないまでも、まあ、う〜んと、まあ、普通と言っておこうか。笑わせてもらったんだけど。
名人芸を見せてもらったのは仲入り後で、これは堪能した。
ちなみに、僕の席の周辺は当然ながらお年寄りばかりが坐っていたが、小朝の熱演(何分したんだろう。30分以上はやってたかな)のときは、既に疲れ果てて寝ている人がちらほら。
スラヴォイ・ジジェクの『ロベスピエール/毛沢東 革命とテロル』を読んだ。
以下、目次
1、毛沢東−無秩序のマルクス主義的君主
2、バディウ−世界の論理
3、ロベスピエール−恐怖(テロル)という「神的暴力」
幕間1−「たら…れば」歴史論の反転
4、バートルビー
壱、グローバル金融の竹篦返しー「スターウォーズ」3の陥穽
弐、…しないことが好き−バートルビーの政治
幕間2−頽廃と偽善
壱、『24』
弐、偽善への訴答−二つの死
5、非常事態
ジジェク節が冴え渡る。内容についてはだれかが書いている要約を読むか、本書にあたってください。訳者の悪ノリぶりが、ジジェクが感染したようにみえて、逆算してジジェクの毒を感じさせる。
本書では、他の思想家などの概念や言葉を借用して、持論を展開していくやり方が多用されている。まあ、これは珍しいことではなく、新約聖書読んでいたって、たとえ話で何事かを了解させる手続きが多くとられている。いわば編集作業のようなものなのだが、こういうことをされると、わかったような気になるのが面白い。真正な理解を求めるよりも、僕はわかったような気になりたい、あるいは、そっちの方が面白い、と思っちゃうんだから、しかたない。
いくつか、本文より引用しておこう。
「これをスターリニストの業界用語(ジャーゴン)で言い換えれば、不動の『全体』は、じつは『全体』ではなく、諸要素の集塊にすぎない、ということである」(p33)
「マルクスが看過したことは、要するに、月並みに解釈されたデリダ的表現を用いて言えば、生産力の充全な配備の『不可能性の条件』であるこの内在的な障碍/矛盾が、同時に、『可能性の条件』でもあるという点である」(p42)
「出来事のこうした自己抹消は、ベンヤミンの口吻を藉りて、憂鬱の左翼主義的政治とでも呼んでみたくなるような領域の可能性を開いている」(p102)
「ラカンの表現を藉りてレーニンの立場を表現すれば、『革命ハ自ラノ権威ニノミ依拠スル(革命ハ自ラヲノミ恃みトスル)』と言うことができるが、これが認められねばならない。言い換えれば、『他者』による庇護を求めることなく革命的行為を引き受けねばならない」(p148)
「国家は、その制度的側面から言えば、巨大な存在(プレゼンス)であり、それは諸利害の代理(リプレゼンテーション)といった表現では説明できない。そしてそれが可能だと主張することが、民主主義の錯認なのだ。この過剰を、バディウは、民主主義が表象−代理(リプレゼント)するものを超える国家の再−現前(表象)(リ−プレゼンテーション)とう過剰として、概念化する。ベンヤミンの表現を用いてこう言ってもよい。民主主義は、制定された暴力を大なり小なり取り除くことができるが、依然として制定する暴力に依存し続けねばならない、と」(p151)
「アウシュビッツで起こったことについての説得的な虚構的描写を制作するよりも、アウシュビッツで起こったことについてのドキュメンタリー作品を観るほうが楽なのは、なぜだろう?なぜショアーについての傑作のすべてが喜劇なのだろうか?ここではアドルノを匡さねばならない。アウシュビッツ以後に不可能になったのは詩ではない。むしろ散文が不可能になったのだ」(p210)
「いわゆる『原理主義者』の場合、信が『他者』へ置き換えられるというイデオロギーの『正常』な機能は、直接的な信−彼らは『それをマジで信じている』−の暴力的な回帰によって、攪乱される。この回帰の第一の帰結は、ラカンがマルキ・ド・サドに事寄せて論じたように、原理主義者がファンタジーと自分自身を即座に同一化してしまうことで、自分のファンタジーに服って(まつらって)しまうことである」(p211)
「ここで同時にわれわれは、ベンヤミンを敷衍して言えば、あらゆる文明の衝突はその底流にある野蛮同士の衝突であることの証左もまた、手にしているのである」(p260)
昔、よく名言集というのを読んでいた。その名言を自分の状況にあてはめて、なにごとかわかった気になったり、打開されたような気になっていたものだが、こうした名言を飛び渡っていって編まれた1つの流れは、名言の威光もあって、それらしく見えるものである。言うまでもなく、僕は、それらしく見えていれば、それもよし、と思っているのだ。
子ほめ/林家はな平
親子酒/林家たこ平
悋気の独楽/林家いっ平
西行鼓ケ滝/林家正蔵
仲入り
太神楽曲芸/翁家勝丸
お札はがし/春風亭小朝
(お囃子/内海英華)
開場時間に到着したら、あまりにも観客の年齢層が高くて驚いた。全員の髪の毛を抜いて並べたら、全体として白く見えたに違いない。火曜日の午後2時に見に来れるのは老人だけだ、と言われればそうなのかもしれないが。
二等席で見たせいか、マイクを通して響く声はなんだか聞き取りにくくて、しかも天井から高座を見下ろしているような気分。いっ平あたりからやっと慣れて見ることができた。
それぞれ面白くて、見に来た価値はあったと思うが、仲入りまでは、ちょっとどうかな、と首をひねっていた。たこ平の酔っぱらい演技に客席から拍手が起こっていたが、まるで拍手を求めているかのような演技で、すごく違和感があった。上方であれば、拍手が起こりそうなときにはそれを回避して笑いにつなげるだろうと思った。それが上方と江戸の違いなのか、と僕は思ったのだが、さて。
いっ平は期待していなかった分だけ、面白く見れた。マクラでは東京の落語家さんの話などですっかり気分がほぐれた。演目も今まで上方で聞いていた噺とは微妙に設定が違っていて、「ほほう」と思った。体当たりの演出は、それはそれでありなんじゃないか、と満足。
それとは対照的だったのは正蔵で、テレビではたよりないけど高座ではさぞ本格的なんだろう、と期待していた。まあ、期待はずれとはいかないまでも、まあ、う〜んと、まあ、普通と言っておこうか。笑わせてもらったんだけど。
名人芸を見せてもらったのは仲入り後で、これは堪能した。
ちなみに、僕の席の周辺は当然ながらお年寄りばかりが坐っていたが、小朝の熱演(何分したんだろう。30分以上はやってたかな)のときは、既に疲れ果てて寝ている人がちらほら。
スラヴォイ・ジジェクの『ロベスピエール/毛沢東 革命とテロル』を読んだ。
以下、目次
1、毛沢東−無秩序のマルクス主義的君主
2、バディウ−世界の論理
3、ロベスピエール−恐怖(テロル)という「神的暴力」
幕間1−「たら…れば」歴史論の反転
4、バートルビー
壱、グローバル金融の竹篦返しー「スターウォーズ」3の陥穽
弐、…しないことが好き−バートルビーの政治
幕間2−頽廃と偽善
壱、『24』
弐、偽善への訴答−二つの死
5、非常事態
ジジェク節が冴え渡る。内容についてはだれかが書いている要約を読むか、本書にあたってください。訳者の悪ノリぶりが、ジジェクが感染したようにみえて、逆算してジジェクの毒を感じさせる。
本書では、他の思想家などの概念や言葉を借用して、持論を展開していくやり方が多用されている。まあ、これは珍しいことではなく、新約聖書読んでいたって、たとえ話で何事かを了解させる手続きが多くとられている。いわば編集作業のようなものなのだが、こういうことをされると、わかったような気になるのが面白い。真正な理解を求めるよりも、僕はわかったような気になりたい、あるいは、そっちの方が面白い、と思っちゃうんだから、しかたない。
いくつか、本文より引用しておこう。
「これをスターリニストの業界用語(ジャーゴン)で言い換えれば、不動の『全体』は、じつは『全体』ではなく、諸要素の集塊にすぎない、ということである」(p33)
「マルクスが看過したことは、要するに、月並みに解釈されたデリダ的表現を用いて言えば、生産力の充全な配備の『不可能性の条件』であるこの内在的な障碍/矛盾が、同時に、『可能性の条件』でもあるという点である」(p42)
「出来事のこうした自己抹消は、ベンヤミンの口吻を藉りて、憂鬱の左翼主義的政治とでも呼んでみたくなるような領域の可能性を開いている」(p102)
「ラカンの表現を藉りてレーニンの立場を表現すれば、『革命ハ自ラノ権威ニノミ依拠スル(革命ハ自ラヲノミ恃みトスル)』と言うことができるが、これが認められねばならない。言い換えれば、『他者』による庇護を求めることなく革命的行為を引き受けねばならない」(p148)
「国家は、その制度的側面から言えば、巨大な存在(プレゼンス)であり、それは諸利害の代理(リプレゼンテーション)といった表現では説明できない。そしてそれが可能だと主張することが、民主主義の錯認なのだ。この過剰を、バディウは、民主主義が表象−代理(リプレゼント)するものを超える国家の再−現前(表象)(リ−プレゼンテーション)とう過剰として、概念化する。ベンヤミンの表現を用いてこう言ってもよい。民主主義は、制定された暴力を大なり小なり取り除くことができるが、依然として制定する暴力に依存し続けねばならない、と」(p151)
「アウシュビッツで起こったことについての説得的な虚構的描写を制作するよりも、アウシュビッツで起こったことについてのドキュメンタリー作品を観るほうが楽なのは、なぜだろう?なぜショアーについての傑作のすべてが喜劇なのだろうか?ここではアドルノを匡さねばならない。アウシュビッツ以後に不可能になったのは詩ではない。むしろ散文が不可能になったのだ」(p210)
「いわゆる『原理主義者』の場合、信が『他者』へ置き換えられるというイデオロギーの『正常』な機能は、直接的な信−彼らは『それをマジで信じている』−の暴力的な回帰によって、攪乱される。この回帰の第一の帰結は、ラカンがマルキ・ド・サドに事寄せて論じたように、原理主義者がファンタジーと自分自身を即座に同一化してしまうことで、自分のファンタジーに服って(まつらって)しまうことである」(p211)
「ここで同時にわれわれは、ベンヤミンを敷衍して言えば、あらゆる文明の衝突はその底流にある野蛮同士の衝突であることの証左もまた、手にしているのである」(p260)
昔、よく名言集というのを読んでいた。その名言を自分の状況にあてはめて、なにごとかわかった気になったり、打開されたような気になっていたものだが、こうした名言を飛び渡っていって編まれた1つの流れは、名言の威光もあって、それらしく見えるものである。言うまでもなく、僕は、それらしく見えていれば、それもよし、と思っているのだ。
最終回四葉の会@天満天神繁昌亭〜スチュアート・リトル3
2008年9月5日 落語
天満天神繁昌亭で林家染丸プロデュース「四葉の会 最終回」
兵庫船/林家染吉
十七歳/桂三四郎
借家借り/林家染佐
京の茶漬/林家染丸
中入り
悋気の独楽/林家染弥
茶の湯/桂あさ吉
勢揃ご挨拶/全員
(三味線・山澤由江、吉川絹代)
半年間続いた四葉の会の最終回。
すごく面白かった。
この会にかける意気込み、てなものもあるのだろうか。この落語家さん、こんなに面白かったっけ、と見直すことが多々。
染丸師匠は挨拶でこんなことを。
「まだまだ未熟で芸ももの足らぬ、そうしたご批判ご感想もいろいろ頂戴いたしました。しかし私は彼らにあえてそのことは伝えておりません。今初めて明かしました。なぜなら自分の芸のレベルは彼ら自身が一番よく知っていると思うからなのです」
なるほど。落語だと、うるさい批評家も多いのだろう。お客さんの年齢層も高いし。
帰宅して録画しておいた「スチュアート・リトル3/森の仲間と大冒険」を見た。
「3」は実物は出てこず、みんなアニメ。3Dではないけど、CGを駆使している。
オーデュ・バーデン監督。
人間と同じ行動をとろうと無理するネズミが、知らず識らずのうちに疎外されていく。
レイクスカウトの集団行動でも、人間の子供なら簡単に渡れるせせらぎが、スチュアートには大冒険になる。おまけに、スチュアートがさんざんな冒険の末にみんなと合流しても、みんなはスチュアートがはぐれていたことに気づいてもいない。
森の中に猛獣がおり、猫がつかまった、とスチュアートが報告しても、だれも信じない。
スチュアートは結局、自分の行動によって、打開をはからざるをえなくなる。
もう、スチュアートが不憫で不憫で。
深く考えると、アメリカや家族といったものの矛盾や悲劇にまで話は進んでしまいそうだ。
ファミリー映画としては肩のこらない面白い出来になっていた。
「2」を見ていないので、何ともいえないが、ネコの性格づけも凄くシンプルになっていた。
兵庫船/林家染吉
十七歳/桂三四郎
借家借り/林家染佐
京の茶漬/林家染丸
中入り
悋気の独楽/林家染弥
茶の湯/桂あさ吉
勢揃ご挨拶/全員
(三味線・山澤由江、吉川絹代)
半年間続いた四葉の会の最終回。
すごく面白かった。
この会にかける意気込み、てなものもあるのだろうか。この落語家さん、こんなに面白かったっけ、と見直すことが多々。
染丸師匠は挨拶でこんなことを。
「まだまだ未熟で芸ももの足らぬ、そうしたご批判ご感想もいろいろ頂戴いたしました。しかし私は彼らにあえてそのことは伝えておりません。今初めて明かしました。なぜなら自分の芸のレベルは彼ら自身が一番よく知っていると思うからなのです」
なるほど。落語だと、うるさい批評家も多いのだろう。お客さんの年齢層も高いし。
帰宅して録画しておいた「スチュアート・リトル3/森の仲間と大冒険」を見た。
「3」は実物は出てこず、みんなアニメ。3Dではないけど、CGを駆使している。
オーデュ・バーデン監督。
人間と同じ行動をとろうと無理するネズミが、知らず識らずのうちに疎外されていく。
レイクスカウトの集団行動でも、人間の子供なら簡単に渡れるせせらぎが、スチュアートには大冒険になる。おまけに、スチュアートがさんざんな冒険の末にみんなと合流しても、みんなはスチュアートがはぐれていたことに気づいてもいない。
森の中に猛獣がおり、猫がつかまった、とスチュアートが報告しても、だれも信じない。
スチュアートは結局、自分の行動によって、打開をはからざるをえなくなる。
もう、スチュアートが不憫で不憫で。
深く考えると、アメリカや家族といったものの矛盾や悲劇にまで話は進んでしまいそうだ。
ファミリー映画としては肩のこらない面白い出来になっていた。
「2」を見ていないので、何ともいえないが、ネコの性格づけも凄くシンプルになっていた。
アリオダンスプロジェクト第2回予選@アリオ八尾〜はるなんせい@ワッハ上方小演芸場
2008年8月25日 落語アリオ八尾でダンスプロジェクト第2回予選。
アニメーションダンスのTOZAWAがゲストで踊る。
ブレイブ、ドープ、エビザイル、ダンシングベイベー、お弁当箱、ビートポップ、アラジンの7組。
途中、ゲストダンサーのステージもはさまれた。
1回目の予選は有力候補が2つか3つにしぼれたが、今回は接戦なんじゃないか、と思った。
http://www.ario-yao-f.jp/compe02.html
夜からはワッハ上方で「はるなんせい」
救世主伝説・北東の剣/旭堂南青
フライヤーにはこう表記があったが、内容からいくと、「木刀の剣」か。だって「木刀を真剣のごとく使う木刀真剣」だったから。
愛ラブ和子/桂春菜
母親の実話エピソードを集めて作ったそうな。
中入り
忠臣蔵外伝・忠僕元助/旭堂南青
いよいよ赤穂浪士の季節がはじまったか。まだ、早い?
仁侠伝/桂春菜
高倉健と竹内力!ということは、もはや「昭和」じゃない。
アニメーションダンスのTOZAWAがゲストで踊る。
ブレイブ、ドープ、エビザイル、ダンシングベイベー、お弁当箱、ビートポップ、アラジンの7組。
途中、ゲストダンサーのステージもはさまれた。
1回目の予選は有力候補が2つか3つにしぼれたが、今回は接戦なんじゃないか、と思った。
http://www.ario-yao-f.jp/compe02.html
夜からはワッハ上方で「はるなんせい」
救世主伝説・北東の剣/旭堂南青
フライヤーにはこう表記があったが、内容からいくと、「木刀の剣」か。だって「木刀を真剣のごとく使う木刀真剣」だったから。
愛ラブ和子/桂春菜
母親の実話エピソードを集めて作ったそうな。
中入り
忠臣蔵外伝・忠僕元助/旭堂南青
いよいよ赤穂浪士の季節がはじまったか。まだ、早い?
仁侠伝/桂春菜
高倉健と竹内力!ということは、もはや「昭和」じゃない。
花花寄席@うめだ花月〜常盤寄席@常盤漢方薬局ビル
2008年8月15日 落語夜勤明けにうめだ花月に行き、花花寄席を見る。
普請ほめ/桂三幸
千早ふる/林家花丸
虚礼困惑騒動/月亭遊方
中入り
狸賽/月亭八光
壷算/笑福亭仁昇
朝の10時開演だったせいか、お客さんの入りは少なめ。
それと、各持ち時間が微妙に短くて、噺をいくぶん端折っているのが、残念だった。独演会でもないのだから、普通はこんな感じなのだろうとは思ったが。
今回も遊方さんには笑わせてもらった。
入場者プレゼントで、うちわや、杜仲茶など。
帰宅して1時間ほど睡眠。
夜からは常盤寄席。
阿弥陀池/笑福亭喬介
遊山船/桂ひろば
コギャルばあちゃん/林家染太
おみやげに線香花火。
帰りに大川を渡るので、橋の上から「さっても綺麗な、イカリの、イカリの、…何もいてへんがな」と声をかけた。
どちらの寄席でも、月亭可朝のストーカー事件をマクラにもってきていた。旬の話題だし。
普請ほめ/桂三幸
千早ふる/林家花丸
虚礼困惑騒動/月亭遊方
中入り
狸賽/月亭八光
壷算/笑福亭仁昇
朝の10時開演だったせいか、お客さんの入りは少なめ。
それと、各持ち時間が微妙に短くて、噺をいくぶん端折っているのが、残念だった。独演会でもないのだから、普通はこんな感じなのだろうとは思ったが。
今回も遊方さんには笑わせてもらった。
入場者プレゼントで、うちわや、杜仲茶など。
帰宅して1時間ほど睡眠。
夜からは常盤寄席。
阿弥陀池/笑福亭喬介
遊山船/桂ひろば
コギャルばあちゃん/林家染太
おみやげに線香花火。
帰りに大川を渡るので、橋の上から「さっても綺麗な、イカリの、イカリの、…何もいてへんがな」と声をかけた。
どちらの寄席でも、月亭可朝のストーカー事件をマクラにもってきていた。旬の話題だし。
上方亭ライブ@ワッハ上方〜近鉄将棋まつり〜現代の音楽
2008年8月10日 落語午後2時30分からワッハ上方で上方亭ライブ。
動物園/森乃石松
代脈/桂福車
石松は、時間がもらえたので「らくだ」か「たちぎれ線香」か迷ったあげく、あいだをとって「動物園」にした、と言ってた。
福車は終演後、8月21日の「桂福団治門弟の会」の宣伝。珍しい「作の市」をするというので、行きたいのは山々だが、あいにくと仕事だ。
ライブラリーで枝雀の「青菜」と「胴斬り」。対談は坂田明と。
天王寺に足を伸ばして、将棋まつり。
行くとサイン会の真っ最中。
お楽しみ抽選会は、なぜか東大阪市や吹田市、守口市など、大阪市外の人ばかり当たる。将棋ファンは市内には少ないのか?
最後のイベント、記念対局を見る。
渡辺明竜王VS阿部隆八段。
解説は内藤國雄九段、聞き手は矢内理絵子女王・女流名人。
先手の渡辺竜王は、公開対局全勝をめざす(現在1戦1勝!)と勝利宣言。
後手、阿部八段も、自分は地元関西の棋士だと強調して、これは面白くなってきた。
面白いのは、最後まで続く。
内藤九段は、オリンピックの話題から、将棋には審判がいないので気楽だ、と言う。そして、もしも将棋の審判になれたら、どういう行為にイエローカードを出すかと矢内女王にきく。内藤九段は「穴熊にはイエローカードを出したい」とズバリ。穴熊戦法の流行が将棋を確実につまらなくしている、と言う。昼休みに将棋を指す、というようなことがしにくくなった(決着がつくのに時間がかかる)とか、いろいろ思うところがあるらしい。その話を対局しながら聞いていた渡辺竜王は、急遽、穴熊に王を囲いはじめる。1筋の香をあげたとき、場内ワッと歓声が湧いた。内藤九段「いらんことを言ってしまったかな」
内藤九段はこの後も短手数の将棋が好きだ、と宣言したりしていた。
矢内女王のトークもなかなか達者なもので、勝負が長引けばこの2人のトークがそれだけ長く聞ける特典があるなあ、と感じていた。
勝負は矢倉穴熊の渡辺竜王が勝利。全勝街道まっしぐらだ。2勝めだけど。
また、内藤九段のトークで「常に今の自分が一番強いと言い切っている棋士がいる」とエピソードを紹介してくれた。それは加藤一二三九段で、名人を獲得したときより、今の方が強いのだ、と言う。加藤九段の名前が出たとたん、場内は湧いた。さすがの人気だ。ひょっとして、今日のトークコーナーとか解説のときにも加藤九段の話が出ていたのかもしれない。あいにくと、今回の将棋まつりに加藤九段は登場しないが、どんなタイトルホルダーよりも、加藤九段が出てきたら一番うれしいのかもしれない。
なお、詰将棋パラダイスの協力により、毎日懸賞詰将棋が出題されていたようだ。知らなかった。捨ててあった出題用紙を見ると柴田昭彦作の13手詰めと、こども、女性、級位者向け問題の5手詰めが載っていた。どちらもどうにかこうにか解いたが、5手詰めの方に、倍以上時間を費やしてしまった。変化のしかたによって、駒が余ってしまう答えになるので、それがひっかかってしまったのだ。
帰宅時に、NHK-FMで「現代の音楽」の後半部を聞いた。
2週にわたって、白石美雪をゲストに招き、ミュージックトゥモローの模様が紹介されていた。「現代の音楽」は再放送もないし、CD化される見込みも薄い。東京を中心に行われるコンサートに行けない僕にとっては、この放送を聞き逃すと、おそらく一生聞くことのできない音が、流れるのだ。
先週、ちょうどイベント中で聞き逃したので、今日こそは、と思っていたのだが、とりあえず、聞き逃したのは、
「幻影とマントラ」 西村 朗・作曲
(25分00秒)
(管弦楽)NHK交響楽団
(指揮)ジャン・ドロワイエ
〜東京オペラシティ・コンサートホールで収録〜
後半なんとか聞けた、と思ってたら、時間が余ったから、と「ミュージックトゥモロー」からではなく、CDの音楽。
「ギターと11楽器のための“響きあう隔たり2”」
原田敬子・作曲
(10分02秒)
(演奏)イクトゥス・アンサンブル
(指揮)ジョルジュ・エリー・オクトール
<Cypzes CYP−5605>
たしかに、このCDを入手する予定もなくて、一期一会だったには違いないのだが、無理してでも遠くに足を伸ばして、聞きに行くしかないのか、とちょっと困った結論が出そうになる。先立つものがないのだ。
動物園/森乃石松
代脈/桂福車
石松は、時間がもらえたので「らくだ」か「たちぎれ線香」か迷ったあげく、あいだをとって「動物園」にした、と言ってた。
福車は終演後、8月21日の「桂福団治門弟の会」の宣伝。珍しい「作の市」をするというので、行きたいのは山々だが、あいにくと仕事だ。
ライブラリーで枝雀の「青菜」と「胴斬り」。対談は坂田明と。
天王寺に足を伸ばして、将棋まつり。
行くとサイン会の真っ最中。
お楽しみ抽選会は、なぜか東大阪市や吹田市、守口市など、大阪市外の人ばかり当たる。将棋ファンは市内には少ないのか?
最後のイベント、記念対局を見る。
渡辺明竜王VS阿部隆八段。
解説は内藤國雄九段、聞き手は矢内理絵子女王・女流名人。
先手の渡辺竜王は、公開対局全勝をめざす(現在1戦1勝!)と勝利宣言。
後手、阿部八段も、自分は地元関西の棋士だと強調して、これは面白くなってきた。
面白いのは、最後まで続く。
内藤九段は、オリンピックの話題から、将棋には審判がいないので気楽だ、と言う。そして、もしも将棋の審判になれたら、どういう行為にイエローカードを出すかと矢内女王にきく。内藤九段は「穴熊にはイエローカードを出したい」とズバリ。穴熊戦法の流行が将棋を確実につまらなくしている、と言う。昼休みに将棋を指す、というようなことがしにくくなった(決着がつくのに時間がかかる)とか、いろいろ思うところがあるらしい。その話を対局しながら聞いていた渡辺竜王は、急遽、穴熊に王を囲いはじめる。1筋の香をあげたとき、場内ワッと歓声が湧いた。内藤九段「いらんことを言ってしまったかな」
内藤九段はこの後も短手数の将棋が好きだ、と宣言したりしていた。
矢内女王のトークもなかなか達者なもので、勝負が長引けばこの2人のトークがそれだけ長く聞ける特典があるなあ、と感じていた。
勝負は矢倉穴熊の渡辺竜王が勝利。全勝街道まっしぐらだ。2勝めだけど。
また、内藤九段のトークで「常に今の自分が一番強いと言い切っている棋士がいる」とエピソードを紹介してくれた。それは加藤一二三九段で、名人を獲得したときより、今の方が強いのだ、と言う。加藤九段の名前が出たとたん、場内は湧いた。さすがの人気だ。ひょっとして、今日のトークコーナーとか解説のときにも加藤九段の話が出ていたのかもしれない。あいにくと、今回の将棋まつりに加藤九段は登場しないが、どんなタイトルホルダーよりも、加藤九段が出てきたら一番うれしいのかもしれない。
なお、詰将棋パラダイスの協力により、毎日懸賞詰将棋が出題されていたようだ。知らなかった。捨ててあった出題用紙を見ると柴田昭彦作の13手詰めと、こども、女性、級位者向け問題の5手詰めが載っていた。どちらもどうにかこうにか解いたが、5手詰めの方に、倍以上時間を費やしてしまった。変化のしかたによって、駒が余ってしまう答えになるので、それがひっかかってしまったのだ。
帰宅時に、NHK-FMで「現代の音楽」の後半部を聞いた。
2週にわたって、白石美雪をゲストに招き、ミュージックトゥモローの模様が紹介されていた。「現代の音楽」は再放送もないし、CD化される見込みも薄い。東京を中心に行われるコンサートに行けない僕にとっては、この放送を聞き逃すと、おそらく一生聞くことのできない音が、流れるのだ。
先週、ちょうどイベント中で聞き逃したので、今日こそは、と思っていたのだが、とりあえず、聞き逃したのは、
「幻影とマントラ」 西村 朗・作曲
(25分00秒)
(管弦楽)NHK交響楽団
(指揮)ジャン・ドロワイエ
〜東京オペラシティ・コンサートホールで収録〜
後半なんとか聞けた、と思ってたら、時間が余ったから、と「ミュージックトゥモロー」からではなく、CDの音楽。
「ギターと11楽器のための“響きあう隔たり2”」
原田敬子・作曲
(10分02秒)
(演奏)イクトゥス・アンサンブル
(指揮)ジョルジュ・エリー・オクトール
<Cypzes CYP−5605>
たしかに、このCDを入手する予定もなくて、一期一会だったには違いないのだが、無理してでも遠くに足を伸ばして、聞きに行くしかないのか、とちょっと困った結論が出そうになる。先立つものがないのだ。
午後2時30分からワッハ上方で上方亭ライブ。
鷺とり/桂吉坊
青菜/桂歌之助
超満員。
ライブラリーで「とっておき米朝噺」あほだら経と数え唄。
あほだら経は「ないないづくし」「ぼうぼうづくし」の2本立て。
数え唄の吉田茂は、まぎれもない本名なのだそうだ。今と昔のネタで、昭和の今ならこうだったろう、という歌に仕上がっている。
当時既に70才をはるかに越えた年齢の演者たち。後継者はいたのか?
午後6時30分からは天満天神繁昌亭で「たっぷりじっくり仁福です」
僕たちヒロー・キッズ/桂三弥
ちりとてちん/露の吉次
悋気の独楽/桂きん枝
中入り
皿屋敷/桂文也
転失気/笑福亭仁福
演目が告げられなかったので、三弥のネタはタイトルを間違っているかもしれない。
今日は淀川の花火大会もあり、オリンピックもあり、さらに桂三若とざこばの娘まいちゃんが大阪天満宮で結婚式を挙げている。本来なら、客も噺家も落語会どころではない、というところだ。もちろん、噺家はそれをネタにしていた。(複数!)
この落語会では、RO水という純水のペットボトルと、保温用ケースのおみやげがあった。
見た映画はジョニー・トー監督の「柔道龍虎房」2004年香港。
柔道を捨てて荒んだ生活を送っていた男が、再び柔道にめざめるまで。
最後には決闘まである。
彼のまわりには夢をあきらめない人物や柔道を愛する人たちが集まっていた。
日本でデビューしてスターになろうとする女性。
片腕を脱臼させる必殺技の持ち主。
大会に出場して救急車で運ばれ、そのまま死んでしまう親父。
強そうな者がいれば勝負を挑み、片腕で戦う術を編み出したりする柔道バカ。
自称姿三四郎の知恵おくれの男。
この「自称三四郎」の役割は、先日見た「こころの湯」で、再開発に納得せずに最後まで抵抗する知恵おくれの弟に似て、作品のメッセージを伝える象徴にもなっている。
自称三四郎がたどたどしく歌う「姿三四郎」の歌が、僕にはこう聞こえた。
「やればできるさ できかけや〜
男は恋して 泣きなおす
焼き魚だけ、泣け 愛のイカメシ まみむめも
三四郎 あのUFOの ユー・アー・サン」
素晴らしい歌詞だ!
最初のうちは、ゲームセンターで不器用に暴れる登場人物とか、オフビートなギャグが満載でとりとめがなく不思議な雰囲気だったが、最後の方では柔道にストーリーが収斂してきて、おおげさなタイトルがそれらしくはまってきた。なお、視力が徐々に失われて、ついに失明してしまう、という流行のシチュエーションも取り入れられていた。
本作は黒澤明へのオマージュが明らかになっているが、知恵遅れ的映画のため、とくにツッコむ気も起こらず、微笑ましいムードをかもし出していた。
鷺とり/桂吉坊
青菜/桂歌之助
超満員。
ライブラリーで「とっておき米朝噺」あほだら経と数え唄。
あほだら経は「ないないづくし」「ぼうぼうづくし」の2本立て。
数え唄の吉田茂は、まぎれもない本名なのだそうだ。今と昔のネタで、昭和の今ならこうだったろう、という歌に仕上がっている。
当時既に70才をはるかに越えた年齢の演者たち。後継者はいたのか?
午後6時30分からは天満天神繁昌亭で「たっぷりじっくり仁福です」
僕たちヒロー・キッズ/桂三弥
ちりとてちん/露の吉次
悋気の独楽/桂きん枝
中入り
皿屋敷/桂文也
転失気/笑福亭仁福
演目が告げられなかったので、三弥のネタはタイトルを間違っているかもしれない。
今日は淀川の花火大会もあり、オリンピックもあり、さらに桂三若とざこばの娘まいちゃんが大阪天満宮で結婚式を挙げている。本来なら、客も噺家も落語会どころではない、というところだ。もちろん、噺家はそれをネタにしていた。(複数!)
この落語会では、RO水という純水のペットボトルと、保温用ケースのおみやげがあった。
見た映画はジョニー・トー監督の「柔道龍虎房」2004年香港。
柔道を捨てて荒んだ生活を送っていた男が、再び柔道にめざめるまで。
最後には決闘まである。
彼のまわりには夢をあきらめない人物や柔道を愛する人たちが集まっていた。
日本でデビューしてスターになろうとする女性。
片腕を脱臼させる必殺技の持ち主。
大会に出場して救急車で運ばれ、そのまま死んでしまう親父。
強そうな者がいれば勝負を挑み、片腕で戦う術を編み出したりする柔道バカ。
自称姿三四郎の知恵おくれの男。
この「自称三四郎」の役割は、先日見た「こころの湯」で、再開発に納得せずに最後まで抵抗する知恵おくれの弟に似て、作品のメッセージを伝える象徴にもなっている。
自称三四郎がたどたどしく歌う「姿三四郎」の歌が、僕にはこう聞こえた。
「やればできるさ できかけや〜
男は恋して 泣きなおす
焼き魚だけ、泣け 愛のイカメシ まみむめも
三四郎 あのUFOの ユー・アー・サン」
素晴らしい歌詞だ!
最初のうちは、ゲームセンターで不器用に暴れる登場人物とか、オフビートなギャグが満載でとりとめがなく不思議な雰囲気だったが、最後の方では柔道にストーリーが収斂してきて、おおげさなタイトルがそれらしくはまってきた。なお、視力が徐々に失われて、ついに失明してしまう、という流行のシチュエーションも取り入れられていた。
本作は黒澤明へのオマージュが明らかになっているが、知恵遅れ的映画のため、とくにツッコむ気も起こらず、微笑ましいムードをかもし出していた。
上方亭ライブ〜歌之助独演会
2008年8月2日 落語まんだらけで「まんが祭り」
前回とあまりラインナップが変わっていないような気がした。
それでも数冊買う。
ワッハ上方で上方亭ライブ。
癪の合薬/林家染弥
マジックで瀧川一紀。
天満天神繁昌亭で桂歌之助独演会
ある事情で無駄足を踏み、開口一番の桂吉の丞には間に合わず。
看板の一/桂歌之助
曲芸/豊来家一輝
七度狐/桂歌之助
日本舞踊「紀伊の国」/桂歌之助
中入
次の御用日/桂歌之助
前回とあまりラインナップが変わっていないような気がした。
それでも数冊買う。
ワッハ上方で上方亭ライブ。
癪の合薬/林家染弥
マジックで瀧川一紀。
天満天神繁昌亭で桂歌之助独演会
ある事情で無駄足を踏み、開口一番の桂吉の丞には間に合わず。
看板の一/桂歌之助
曲芸/豊来家一輝
七度狐/桂歌之助
日本舞踊「紀伊の国」/桂歌之助
中入
次の御用日/桂歌之助
ONLY染二「らくだ」
2008年8月1日 落語千林商店街に行くと、商店街のテーマソングや「キャンディマシーンに乗って」が流れていた。
天満天神繁昌亭のレイトショーで、「ONLY染二」
らくだ/林家染二
1時間弱の落語で、最初はちょっと走ったか、と思われる。
最初のほうに出てくる「どぶさる」「ごねる」なんていう言葉もさらっと使っていたように思えた。
いや、しかし、日本酒が飲みたくて飲みたくてしかたなくなった。
天満天神繁昌亭のレイトショーで、「ONLY染二」
らくだ/林家染二
1時間弱の落語で、最初はちょっと走ったか、と思われる。
最初のほうに出てくる「どぶさる」「ごねる」なんていう言葉もさらっと使っていたように思えた。
いや、しかし、日本酒が飲みたくて飲みたくてしかたなくなった。
Chupiライブ〜LPSA将棋ツアー〜桂梅団治のこれ独演会?
2008年7月27日 落語この日記もまたくわしくは後日。
朝8時半からはラジオで落語〜米朝よもやま話。
高校野球放送で、とうぶんは夏休みのようだ。
永和信用金庫前で、Chupi(りさちゃんとリンダ)のライブ。
1日に3回あったようだが、1回目の午後1時半の分だけ見た。
4曲。
3回とも見たかった。
バルーンの犬をりさちゃんにもらい、それを次の移動場所までずっと連れ歩く。
7月28日(なにわの日)のタオルもいただく。
神戸市産業振興センターで日本女子プロ将棋協会主催のLPSA TOUR 2008 in KOBE
到着したときは、藤森奈津子女流三段と松尾香織女流初段の「次の一手名人戦」の対局中。
椅子に坐ってすぐに「さあ、次の一手はなんですか」とマイクを向けられたが、盤面もろくによく見ていなかったので、パスさせてもらった。
それでも、何回かあった「次の一手」の問題を当てることができて、記念品をもらった。
懸賞詰め将棋の答えあわせのあと、お好み対局、山崎隆之七段VS中井広恵女流六段の対局途中で、泣く泣く会場をあとにする。
次のイベントがあったのだ。
このイベントには、小学生の天才棋士、中七海ちゃんも来ていた。対局しているところを見たかった!
この七海ちゃんは兵庫県の小学生だが、関西を代表する棋士である。今後も将棋を続けていってほしい。
午後5時半から天満天神繁昌亭で「桂梅団治のこれ独演会?」
餅屋問答/桂梅団治
悋気の独楽/立川生志
鬼の面/桂梅団治
中入
お玉牛/桂梅団治
井戸の茶碗/立川生志
朝8時半からはラジオで落語〜米朝よもやま話。
高校野球放送で、とうぶんは夏休みのようだ。
永和信用金庫前で、Chupi(りさちゃんとリンダ)のライブ。
1日に3回あったようだが、1回目の午後1時半の分だけ見た。
4曲。
3回とも見たかった。
バルーンの犬をりさちゃんにもらい、それを次の移動場所までずっと連れ歩く。
7月28日(なにわの日)のタオルもいただく。
神戸市産業振興センターで日本女子プロ将棋協会主催のLPSA TOUR 2008 in KOBE
到着したときは、藤森奈津子女流三段と松尾香織女流初段の「次の一手名人戦」の対局中。
椅子に坐ってすぐに「さあ、次の一手はなんですか」とマイクを向けられたが、盤面もろくによく見ていなかったので、パスさせてもらった。
それでも、何回かあった「次の一手」の問題を当てることができて、記念品をもらった。
懸賞詰め将棋の答えあわせのあと、お好み対局、山崎隆之七段VS中井広恵女流六段の対局途中で、泣く泣く会場をあとにする。
次のイベントがあったのだ。
このイベントには、小学生の天才棋士、中七海ちゃんも来ていた。対局しているところを見たかった!
この七海ちゃんは兵庫県の小学生だが、関西を代表する棋士である。今後も将棋を続けていってほしい。
午後5時半から天満天神繁昌亭で「桂梅団治のこれ独演会?」
餅屋問答/桂梅団治
悋気の独楽/立川生志
鬼の面/桂梅団治
中入
お玉牛/桂梅団治
井戸の茶碗/立川生志
トクトコ、桂三風@上方亭〜染二百席錬磨「激突!上方落語面長派!2」@天満天神繁昌亭
2008年7月19日 落語ワッハ上方の上方亭でトクトコ(漫才)と桂三風(落語)。
トクトコは探偵小説ネタ。
桂三風は米揚げ笊。
終演後、米揚げ笊の実物を見せてくれて、しかも、希望者にプレゼントしていた。小学生が「はいっ」と手をあげてもらっていたが、米揚げ笊をどう使うのかは、今後の課題だろう。
ライブラリーも盛況。
映像を見るほどの時間の余裕はなく、サバンナ八木の『ぼくの怪獣大百科(レッド)』を読了。
カラー!
午後6時からは天満天神繁昌亭で「染二百席錬磨〜激突!上方落語面長派!2」これ、チケットぴあで券買ったとき、「染、二百席錬磨」と切りどころを間違えているのが可笑しくて、笑いをこらえるのがたいへんだった。そのときの僕は、さぞかしにこやかで温和な人間に見えていたことだろう。
たぬさい/笑福亭呂竹
壷算/林家染二
猫の忠信/桂九雀
中入り
遊山船/林家染左
土橋万歳/林家染二
会場で、演芸ジャーナリストのやまだりよこさんに久々の再会。
ぷがじゃの頃の話などをした。
なんと、僕が13年間勤務していた大学で非常勤講師をされている。
落語会に頻繁に行くようになったので、またどこかで御会いしそうだ。
ハチワンダイバー最終回。真面目な終わり方だった。とってつけたようなまとめ方だったが、もっともっと御都合主義でアンビリーバブルなハッピーエンドの方が楽しかったのにな、と思った。
トクトコは探偵小説ネタ。
桂三風は米揚げ笊。
終演後、米揚げ笊の実物を見せてくれて、しかも、希望者にプレゼントしていた。小学生が「はいっ」と手をあげてもらっていたが、米揚げ笊をどう使うのかは、今後の課題だろう。
ライブラリーも盛況。
映像を見るほどの時間の余裕はなく、サバンナ八木の『ぼくの怪獣大百科(レッド)』を読了。
カラー!
午後6時からは天満天神繁昌亭で「染二百席錬磨〜激突!上方落語面長派!2」これ、チケットぴあで券買ったとき、「染、二百席錬磨」と切りどころを間違えているのが可笑しくて、笑いをこらえるのがたいへんだった。そのときの僕は、さぞかしにこやかで温和な人間に見えていたことだろう。
たぬさい/笑福亭呂竹
壷算/林家染二
猫の忠信/桂九雀
中入り
遊山船/林家染左
土橋万歳/林家染二
会場で、演芸ジャーナリストのやまだりよこさんに久々の再会。
ぷがじゃの頃の話などをした。
なんと、僕が13年間勤務していた大学で非常勤講師をされている。
落語会に頻繁に行くようになったので、またどこかで御会いしそうだ。
ハチワンダイバー最終回。真面目な終わり方だった。とってつけたようなまとめ方だったが、もっともっと御都合主義でアンビリーバブルなハッピーエンドの方が楽しかったのにな、と思った。
男前寄席@ワッハ上方〜ヅラ刑事
2008年7月14日 落語夜勤明けの朝食はシリアルにヨーグルト。(玄米フレーク)
昼食は掌(たなごころ)心斎橋店でランチ。(パスタランチでサラダバイキング)
3時のおやつは、Delices du palaisでアップルマンゴーのタルト、ブレンドコーヒーと。
いろんなブログ読んでたら、食事について書いてあるのが多いので、試しに書いてみた。メタボ健診に対応しなくては、と考えているわりに、食べたい放題の食生活だ。
夜からはワッハ上方の小演芸場で「第2回 男前寄席」
第1回はバレンタインチョコ持参で割り引きがあったそうだが、今回は、受付で「三四郎と南青って男前ですね」と告げれば割引。言おうとしたら、いやいや、言っていただかなくて結構です、と割引料金で入れた。男に言われてもね、ということか?
子ほめ/桂三四郎
将棋大名/旭堂南青
奇跡のラッキーカムカム/月亭遊方
中入り
那須余一/旭堂南青
がまの油/桂三四郎
遊方さんの落語を聞くのは久しぶりだったのだが、大爆笑させてもらった。最近落語を集中的に聞くようにしているが、その中でも一番の爆笑だったと思う。次の機会にでも、御挨拶にうかがうとするか。
帰宅して、河崎実監督の映画「ヅラ刑事」を見た。2006年。
モト冬樹主演。鬘をアイスラッガーのように飛ばす。
デブ刑事、ウガンダの生前の勇姿が見れた。
デカチン刑事が出てきたり、チビ刑事が出てきたり、必殺のレーザー光線をハゲで反射したり、と、センスはまるっきり少年ギャグ漫画の世界。それも、コロコロくらいかな。面白い!
昼食は掌(たなごころ)心斎橋店でランチ。(パスタランチでサラダバイキング)
3時のおやつは、Delices du palaisでアップルマンゴーのタルト、ブレンドコーヒーと。
いろんなブログ読んでたら、食事について書いてあるのが多いので、試しに書いてみた。メタボ健診に対応しなくては、と考えているわりに、食べたい放題の食生活だ。
夜からはワッハ上方の小演芸場で「第2回 男前寄席」
第1回はバレンタインチョコ持参で割り引きがあったそうだが、今回は、受付で「三四郎と南青って男前ですね」と告げれば割引。言おうとしたら、いやいや、言っていただかなくて結構です、と割引料金で入れた。男に言われてもね、ということか?
子ほめ/桂三四郎
将棋大名/旭堂南青
奇跡のラッキーカムカム/月亭遊方
中入り
那須余一/旭堂南青
がまの油/桂三四郎
遊方さんの落語を聞くのは久しぶりだったのだが、大爆笑させてもらった。最近落語を集中的に聞くようにしているが、その中でも一番の爆笑だったと思う。次の機会にでも、御挨拶にうかがうとするか。
帰宅して、河崎実監督の映画「ヅラ刑事」を見た。2006年。
モト冬樹主演。鬘をアイスラッガーのように飛ばす。
デブ刑事、ウガンダの生前の勇姿が見れた。
デカチン刑事が出てきたり、チビ刑事が出てきたり、必殺のレーザー光線をハゲで反射したり、と、センスはまるっきり少年ギャグ漫画の世界。それも、コロコロくらいかな。面白い!
兵庫県立美術館で「冒険王・横尾忠則」を見た。
60年代未公開作品から最新絵画まで、膨大な数の作品が展示してあった。(絵画等約170点、グラフィック原画が数百点!)
90年代から現在に至る絵画作品がすごくいい。
どの時代の作品もよくて目を離せないのはもちろんなのだが、かつては天井桟敷の頃のイラストレーションがいい、と思っていたり、コラージュ作品がいい、と思っていた時期がある。今は、なんといっても、ここ20年ほどの絵画がググッとくる。
横尾忠則が少年時代に熱中した物事が、作品にドーンと表現されている。それは、今回のタイトル「冒険王」に示されているように、南洋一郎と江戸川乱歩による「少年向け冒険」の世界なのだ。これが、僕にとってもドンピシャリのストライクなのだ。
これらに匹敵するのは、手塚治虫と月光仮面くらいしか思い浮かばない。あっ、プロレスもあったかな。ジャイアント馬場がジン・キニスキーやボボ・ブラジルと戦っていた頃。
とにかく、作品展示数が多くて、流れ込むイメージの総量といったらない。
じっくり見ていてはいくら時間があっても足りないので、ひととおり見た後、図録を買って、おりにふれて眺めることにした。図録がまた安い!(でも、美術館で見るのとは感動が全然違うので、図録で飽き足らなくなったら、また行くかも。そう考えてくると、画集でしか知らない絵画も、美術館に足を運んでみると、感動が違ってくるんだろうな、と推測される。困った)
さらに、アニメーションも上映されており、トークショーや公開制作まである。
やはり、もう1回くらい行くことになるか?
締めきりに間に合わなかったが、横尾忠則とプリンセス天効の講演会が気になる。トークショーの模様がどこかで上映されればいいのに。
夜は天満天神繁昌亭で「上方VS江戸」
時うどん/桂三四郎
お見立て/桂平治
遊山舟/桂福楽
妾馬/桂平治
中入り
仔猫/桂福楽
「上方の笑い、江戸の粋」とサブタイトルがついていた。
「時うどん」はみんなが知っているネタながら、いろんなバージョンや工夫があって、飽きない。
平治は江戸落語をきっちり聞かせてくれて、すごく面白かった。普段は上方落語の方が笑わせてくれるので好きだ、と断言できるのだが、うまい江戸落語を聞くと、こっちの方が格は上か、と心がゆらいだりする。別物、と考えた方がいいんだろうけど。
福楽は上方落語の特徴、はめものの落語を選んで、はなしてくれた。
「仔猫」はテレビでしか聞いたことがなかったので、実際に聞いてみて、鳥肌がたった。
ビデオやラジオで落語をよく聞いているが、落語会に出かけていって聞いてみないと面白さは半分も味わえないんだな、とか思うと、これまた、困った。時間とお金は有限なのだ。とくに、貧乏な僕にとっては、大文字の「有限」だ。困ったものだ。
帰宅したら、ちょうどアニメ「RD潜脳調査室」に間に合った。
「仮面のメイドガイ」も「図書館戦争」も「スポンジボブ」も終わってしまった今、見ているアニメで毎週楽しみなのは、この「RD」と「ポルフィの長い旅」「銀魂」「ソウルイーター」「ぷるるんしずくちゃんあはっ」「コードギアスR2」くらいか。夏の新作アニメ、何か面白いのあるかな?
その後、芸術劇場でチェルフィッチュ見る。
せりふがリアルだというだけでなく、同じ話題がループしたり、話者が変転するところも、リアル。あまりにもリアルすぎて、はたしてこれが「演劇」たりうるのか、とも考えてしまう。演劇的世界に浸った観客の殻を破ることはできるが、そうでない一般の人(僕も含む)にとっては、再現されたリアルでしかない。大阪の人間のリアルなら、「そんなアホな」という非日常が常にセットされているが、岡田氏は関西人ではない。放送された「フリータイム」に関して言えば、せいぜいがアフロに関するくだりで笑いが起こる程度で、演劇という特殊空間でなければ笑いにもつながらないだろう。ほとんどの台詞が、どこかで聞いたことのあるような日常の会話で、その場かぎりで忘れてしまうような内容である。関西人なら、時間を埋めるためであっても口に出さないような内容だ。(つまり、これは実現しないリアル。チェルフィッチュでは実現しないリアルが再現されている、ということ)ドキュメンタリーであっても視点の選択などで、作家の誘導はなされるが、チェルフィッチュはそうした誘導を排しようとしているように思えた。要するに、これはわれわれがいかにリアルに耐えうるか、という問題なのだろう。ところが、われわれは普段、リアルに耐え得ている。どうやって耐えているかと言えば、リアルを演出によって外すことによって、だ。そうでないと、リアルそのものはあまりにも退屈すぎるから。チェルフィッチュを面白いな、と思った瞬間に、われわれは既にその罠にはまっているのかもしれない。二重否定は肯定ですよ、マイナスかけるマイナスはプラスですよ、裏の裏をかくのは鵜のみと見た目は一緒ですよ、というような堂々回りの陥穽が待ち受けているように思える。恐怖の演劇を見に来るお客さんがいる、ということは、その演劇から逃げなかった事実をもって、既に恐怖は失敗している、というようなジレンマ。チェルフィッチュがリアルならば、なぜそれを金出して見に行くのか、というジレンマ。まとまらないままに、ずらずら書いてみた。チェルフィッチュが新しいことは間違いない。こんなにいろいろ考えたんだから。
「フリータイム」の後の大江健三郎との対談では、大江健三郎の面白さがきわだっていた。このおっさん、まだまだおもろいことをやってくれそうだ、という雰囲気がビンビンと伝わってきた。
60年代未公開作品から最新絵画まで、膨大な数の作品が展示してあった。(絵画等約170点、グラフィック原画が数百点!)
90年代から現在に至る絵画作品がすごくいい。
どの時代の作品もよくて目を離せないのはもちろんなのだが、かつては天井桟敷の頃のイラストレーションがいい、と思っていたり、コラージュ作品がいい、と思っていた時期がある。今は、なんといっても、ここ20年ほどの絵画がググッとくる。
横尾忠則が少年時代に熱中した物事が、作品にドーンと表現されている。それは、今回のタイトル「冒険王」に示されているように、南洋一郎と江戸川乱歩による「少年向け冒険」の世界なのだ。これが、僕にとってもドンピシャリのストライクなのだ。
これらに匹敵するのは、手塚治虫と月光仮面くらいしか思い浮かばない。あっ、プロレスもあったかな。ジャイアント馬場がジン・キニスキーやボボ・ブラジルと戦っていた頃。
とにかく、作品展示数が多くて、流れ込むイメージの総量といったらない。
じっくり見ていてはいくら時間があっても足りないので、ひととおり見た後、図録を買って、おりにふれて眺めることにした。図録がまた安い!(でも、美術館で見るのとは感動が全然違うので、図録で飽き足らなくなったら、また行くかも。そう考えてくると、画集でしか知らない絵画も、美術館に足を運んでみると、感動が違ってくるんだろうな、と推測される。困った)
さらに、アニメーションも上映されており、トークショーや公開制作まである。
やはり、もう1回くらい行くことになるか?
締めきりに間に合わなかったが、横尾忠則とプリンセス天効の講演会が気になる。トークショーの模様がどこかで上映されればいいのに。
夜は天満天神繁昌亭で「上方VS江戸」
時うどん/桂三四郎
お見立て/桂平治
遊山舟/桂福楽
妾馬/桂平治
中入り
仔猫/桂福楽
「上方の笑い、江戸の粋」とサブタイトルがついていた。
「時うどん」はみんなが知っているネタながら、いろんなバージョンや工夫があって、飽きない。
平治は江戸落語をきっちり聞かせてくれて、すごく面白かった。普段は上方落語の方が笑わせてくれるので好きだ、と断言できるのだが、うまい江戸落語を聞くと、こっちの方が格は上か、と心がゆらいだりする。別物、と考えた方がいいんだろうけど。
福楽は上方落語の特徴、はめものの落語を選んで、はなしてくれた。
「仔猫」はテレビでしか聞いたことがなかったので、実際に聞いてみて、鳥肌がたった。
ビデオやラジオで落語をよく聞いているが、落語会に出かけていって聞いてみないと面白さは半分も味わえないんだな、とか思うと、これまた、困った。時間とお金は有限なのだ。とくに、貧乏な僕にとっては、大文字の「有限」だ。困ったものだ。
帰宅したら、ちょうどアニメ「RD潜脳調査室」に間に合った。
「仮面のメイドガイ」も「図書館戦争」も「スポンジボブ」も終わってしまった今、見ているアニメで毎週楽しみなのは、この「RD」と「ポルフィの長い旅」「銀魂」「ソウルイーター」「ぷるるんしずくちゃんあはっ」「コードギアスR2」くらいか。夏の新作アニメ、何か面白いのあるかな?
その後、芸術劇場でチェルフィッチュ見る。
せりふがリアルだというだけでなく、同じ話題がループしたり、話者が変転するところも、リアル。あまりにもリアルすぎて、はたしてこれが「演劇」たりうるのか、とも考えてしまう。演劇的世界に浸った観客の殻を破ることはできるが、そうでない一般の人(僕も含む)にとっては、再現されたリアルでしかない。大阪の人間のリアルなら、「そんなアホな」という非日常が常にセットされているが、岡田氏は関西人ではない。放送された「フリータイム」に関して言えば、せいぜいがアフロに関するくだりで笑いが起こる程度で、演劇という特殊空間でなければ笑いにもつながらないだろう。ほとんどの台詞が、どこかで聞いたことのあるような日常の会話で、その場かぎりで忘れてしまうような内容である。関西人なら、時間を埋めるためであっても口に出さないような内容だ。(つまり、これは実現しないリアル。チェルフィッチュでは実現しないリアルが再現されている、ということ)ドキュメンタリーであっても視点の選択などで、作家の誘導はなされるが、チェルフィッチュはそうした誘導を排しようとしているように思えた。要するに、これはわれわれがいかにリアルに耐えうるか、という問題なのだろう。ところが、われわれは普段、リアルに耐え得ている。どうやって耐えているかと言えば、リアルを演出によって外すことによって、だ。そうでないと、リアルそのものはあまりにも退屈すぎるから。チェルフィッチュを面白いな、と思った瞬間に、われわれは既にその罠にはまっているのかもしれない。二重否定は肯定ですよ、マイナスかけるマイナスはプラスですよ、裏の裏をかくのは鵜のみと見た目は一緒ですよ、というような堂々回りの陥穽が待ち受けているように思える。恐怖の演劇を見に来るお客さんがいる、ということは、その演劇から逃げなかった事実をもって、既に恐怖は失敗している、というようなジレンマ。チェルフィッチュがリアルならば、なぜそれを金出して見に行くのか、というジレンマ。まとまらないままに、ずらずら書いてみた。チェルフィッチュが新しいことは間違いない。こんなにいろいろ考えたんだから。
「フリータイム」の後の大江健三郎との対談では、大江健三郎の面白さがきわだっていた。このおっさん、まだまだおもろいことをやってくれそうだ、という雰囲気がビンビンと伝わってきた。
ゲゲゲの鬼太郎〜仁福・都二人会
2008年7月6日 落語今朝のABCラジオ「なみはや亭」で、桂吉の丞の「時うどん」を放送していた。昨日見たばっかりだったので、汗をふきながら「う〜寒い」と身をすくめてお客さんに想像力を要求する笑いが、目に見えるようだった。なみはや亭のもう1本は笑福亭智之介の「桃太郎」だった。
まんだらけグランドカオスの漫画祭り、今日までなので、もう1回行って、また漫画買う。
ベルセルクの32巻が70円で買えるなんて!
通天閣に出来た松竹の「TENGEKI」行こうかな、と思ってたけど、漫画を抱えていてはやはり間に合わず。もうちょっと日にちをおいて行った方が、ゆっくり見れるかもしれない。
録画しておいた映画「ゲゲゲの鬼太郎」を見る。
鬼太郎と人間の少女との淡い恋が、とってつけた感じで浮いていた。あと、死んだ父親と息子とのキャッチボール、という中途半端なお涙ちょうだいが、これまた浮いている。でも、無理矢理にでも恋と涙を入れてしまうあたりが、ファミリー向け映画らしくてほほえましい。
午後5時30分から、天満天神繁昌亭で「仁福・都二人会」
寄合酒/笑福亭呂竹
青菜/露の都
住吉駕篭/笑福亭仁福
中入り
対談/仁福+都
眼鏡屋盗人/露の都
猿後家/笑福亭仁福
落語のネタより、プライベートな話で盛り上がる。
仁福さんは、今までは繁昌亭の人気で人を呼べていたけど、ばれてしもた、と情けなくぼやいて笑いを誘う。会場はあいにくと満席にならなかったのだ。
都さんは吉永小百合で大サービス。
まんだらけグランドカオスの漫画祭り、今日までなので、もう1回行って、また漫画買う。
ベルセルクの32巻が70円で買えるなんて!
通天閣に出来た松竹の「TENGEKI」行こうかな、と思ってたけど、漫画を抱えていてはやはり間に合わず。もうちょっと日にちをおいて行った方が、ゆっくり見れるかもしれない。
録画しておいた映画「ゲゲゲの鬼太郎」を見る。
鬼太郎と人間の少女との淡い恋が、とってつけた感じで浮いていた。あと、死んだ父親と息子とのキャッチボール、という中途半端なお涙ちょうだいが、これまた浮いている。でも、無理矢理にでも恋と涙を入れてしまうあたりが、ファミリー向け映画らしくてほほえましい。
午後5時30分から、天満天神繁昌亭で「仁福・都二人会」
寄合酒/笑福亭呂竹
青菜/露の都
住吉駕篭/笑福亭仁福
中入り
対談/仁福+都
眼鏡屋盗人/露の都
猿後家/笑福亭仁福
落語のネタより、プライベートな話で盛り上がる。
仁福さんは、今までは繁昌亭の人気で人を呼べていたけど、ばれてしもた、と情けなくぼやいて笑いを誘う。会場はあいにくと満席にならなかったのだ。
都さんは吉永小百合で大サービス。
竹丸よ、ワッハを救え!@ワッハ上方レッスンルーム
2008年7月5日 落語まんだらけグランドカオスで漫画祭り。難ありコミックスが3冊210円。「読めればいいや」の僕は、それでじゅうぶん。
読みたかったマンガを適当にみつくろって購入。
午後7時からワッハ上方レッスンルームで「竹丸よ、ワッハを救え!」
結構な客入り。今日の上方亭ライブは、あの小さなところにお客さんが百人も入って新記録だったらしい。上方亭ライブは最初、行く予定にしていたのだが、漫画が重くていったん家に置きに帰っていると間に合わなくなってしまったのだ。見に行ってたらたいへんだったろうな。
さて、番組は竹丸と、本日の出演者とのトークがまずあってから、本番。
時うどん/桂吉の丞
米朝の弟子の吉朝の弟子の吉の丞。吉朝の弟子なので「吉」の字をもらうのだが、芸名の候補として他に「吉外」もあったという。ホントかね?
今朝の「ケロロ軍曹」は、タイムリーにも「時うどん」ネタの応用だった。発射する弾丸の数を数えるのに、途中、時間をたずねて、1発誤解させるのだ。それ以外にも「寿限無」ネタのバリエーションもやってたな。「ジュテーム、ジュテーム、五劫のシルブプレ」とか言ってた。
代り目/林家竹丸
おでんを買いに行ったはずの女房が、旦那のひとりごとを聞くくだりまで。
高峰秀子主演の「銀座カンカン娘」で、志ん生が最後にいきなり落語をはじめて、そのまま映画も終わってしまうが、そのときのネタが、これ。
寝床/桂三弥
このネタは昨日読んだ『名人』で志ん生が得意にしていたと書かれていた。もちろん、骨子は同じでもかなり違うもので、義太夫嫌さに番頭が土蔵に逃げ込んだら、旦那は土蔵の戸の隙間から義太夫を語り込む「義太夫が土蔵の中で、グワーッと渦を巻いちゃった」という展開にはならないし、サゲの「いま、あの人はドイツにいる」もない。誰の「寝床」だったか忘れたけど、「今、あの人は〜にいる」というサゲを上方落語でも聞いたことがあるので、東西の相違、というわけでもないのかもしれない。(〜の部分の国名は、ドイツではなく、中東のどこかの国だったと記憶している)
中入りをはさんで、トリは竹丸。
瓦版事始(狐狸窟彦兵衛・作)/林家竹丸
瓦版のニュースとして、先に演じた「代り目」のネタを出してくる、など、きわめて斬新。
この落語聞きにいくときに、道でばったりとamUの2人に会い、短く立ち話した。アイドルイベント帰りかと尋ねられた。最近のアイドルイベント乱立は、ありがたいことなのだが、有料イベントの高額ぶりにちょっとついていけないところもあるので、あえて控えめにしているのだ。(たとえば、僕が企画するライブは1500円なのだが、アイドルイベントはその倍以上するのが相場なのだ。納得いかん)
読みたかったマンガを適当にみつくろって購入。
午後7時からワッハ上方レッスンルームで「竹丸よ、ワッハを救え!」
結構な客入り。今日の上方亭ライブは、あの小さなところにお客さんが百人も入って新記録だったらしい。上方亭ライブは最初、行く予定にしていたのだが、漫画が重くていったん家に置きに帰っていると間に合わなくなってしまったのだ。見に行ってたらたいへんだったろうな。
さて、番組は竹丸と、本日の出演者とのトークがまずあってから、本番。
時うどん/桂吉の丞
米朝の弟子の吉朝の弟子の吉の丞。吉朝の弟子なので「吉」の字をもらうのだが、芸名の候補として他に「吉外」もあったという。ホントかね?
今朝の「ケロロ軍曹」は、タイムリーにも「時うどん」ネタの応用だった。発射する弾丸の数を数えるのに、途中、時間をたずねて、1発誤解させるのだ。それ以外にも「寿限無」ネタのバリエーションもやってたな。「ジュテーム、ジュテーム、五劫のシルブプレ」とか言ってた。
代り目/林家竹丸
おでんを買いに行ったはずの女房が、旦那のひとりごとを聞くくだりまで。
高峰秀子主演の「銀座カンカン娘」で、志ん生が最後にいきなり落語をはじめて、そのまま映画も終わってしまうが、そのときのネタが、これ。
寝床/桂三弥
このネタは昨日読んだ『名人』で志ん生が得意にしていたと書かれていた。もちろん、骨子は同じでもかなり違うもので、義太夫嫌さに番頭が土蔵に逃げ込んだら、旦那は土蔵の戸の隙間から義太夫を語り込む「義太夫が土蔵の中で、グワーッと渦を巻いちゃった」という展開にはならないし、サゲの「いま、あの人はドイツにいる」もない。誰の「寝床」だったか忘れたけど、「今、あの人は〜にいる」というサゲを上方落語でも聞いたことがあるので、東西の相違、というわけでもないのかもしれない。(〜の部分の国名は、ドイツではなく、中東のどこかの国だったと記憶している)
中入りをはさんで、トリは竹丸。
瓦版事始(狐狸窟彦兵衛・作)/林家竹丸
瓦版のニュースとして、先に演じた「代り目」のネタを出してくる、など、きわめて斬新。
この落語聞きにいくときに、道でばったりとamUの2人に会い、短く立ち話した。アイドルイベント帰りかと尋ねられた。最近のアイドルイベント乱立は、ありがたいことなのだが、有料イベントの高額ぶりにちょっとついていけないところもあるので、あえて控えめにしているのだ。(たとえば、僕が企画するライブは1500円なのだが、アイドルイベントはその倍以上するのが相場なのだ。納得いかん)
1 2