『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統』2
2012年11月30日 読書 コメント (1)
『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統』
つづき。
ジョルダーノ・ブルーノの哲学がどんなものだったのかを本人がまとめた発言がある。火あぶりになる前に、本人がとうとうと、自らの哲学をまくしたてるのが記録として残っているのだ。
以下、そのくだり。本書に載っている。
さて、前回のつづき。ジョルダーノ・ブルーノ満を持して登場。
第11章 ジョルダーノ・ブルーノ――最初のパリ滞在
前提としての古典的記憶術
「ローマの弁論家たちはある種の記憶法を用いていた。この記憶法については『ヘレンニウスへ』に纏まった記述があり、キケロとクインティリアヌスもそれに言及している。まず一つの建物を選び、その一連の場所を記憶する。次に論題を想起するための影像を作り、それをこの記憶した場所に割り振る。弁論家たちは演説を行う際に、想像の空間の中でこのあらかじめ記憶してある場所を通り過ぎながら、そこに割り振ってある影像を拾い集める」
『イデアの影について』
「魔法使いマーリンのものだとされている叡智の詩の一つは、色々な動物たちにはそれぞれ苦手なことがあるということを謎々の形で述べている。例えば豚はその本性からして空を飛ぶには適していない。それゆえ読者はもしこの眼前の書物にふさわしい力を自分が備えているという自信が持てないなら、読むのはやめるべきだと警告しておこう。この著作の道しるべとして置かれた冒頭のこの詩の雰囲気、つまり神秘めかしながらも大言壮語するこの調子は本論に入ってからも一貫して持続している」
『キルケーの呪文』
「この作品の呪文の典拠は、『イデアの影について』の天上的図像の出所と同じように、コルネリウス・アグリッパの『オカルト哲学について』である」
ブルーノのイギリス訪問と隠された使命
「ブルーノは、イギリスで出版されたこれらの著作のあちこちで、厳しい検閲と監視が当たり前のこの時代、土地の人間ならばまず発言を許されるはずのないことを述べている」
第12章 ジョルダーノ・ブルーノのイギリス滞在――ヘルメス教的改革
オックスフォード大学にて
「(ジョージ・アボットの『誤って正統信仰という名を得た、教皇制度を支持するヒル博士の根拠-根拠薄弱であることを暴露され、目的遂行にはあまりに不十分であることが検討の結果明らかとなった、その姿』からの引用)
彼はやたらに多くの説を並べて見せたが、その中にコペルニクスの意見もあってそれを説き始めた。あの地球は回っており、天界はじっと止まっておるという愚説だ。本当のところ回っておったのはこの男の頭の中身の方だった」
『勝ち誇る野獣の追放』
「ブルーノの『勝ち誇る野獣の追放』(1584年)の基本的なテーマは、エジプト人の魔術的宗教の讃美である。彼らの崇拝の内実は「事物に宿る<神>」の崇拝であったとされる」
ブルーノのエジプト主義
「ジョルダーノ・ブルーノはここで一体何をしているのだろうか。答えは簡単である。彼は、少しばかり無害な魔術に手を染め、その主たる拠り処である『アスクレピウス』の魔術については黙っておくといったフィチーノ流の弱々しい試みを完全に捨て去り、ルネサンス魔術をその異教の源泉へと連れ戻しているのである」
「エジプト人たちの驚嘆すべき魔術的宗教は戻ってくるだろう。彼らの道徳律が今の時代の渾沌に取って代わり、<悲嘆>の予言は成就するだろう。そしてこの現在の暗黒を追放すべきエジプトの光の回帰を告げる天上の徴こそが、コペルニクスの観た太陽なのである」
『宇宙の乙女』
「(ストパイオスの詞華集採録の断簡『宇宙の乙女』より)<悪口する蛇遣い座>、<傲慢な鷲座>、<肉欲のイルカ座>、<短気な馬座>、<情欲の海蛇座>を追い出そう。<大食の鯨座>、<残忍なオリオン座>、<贅沢なエリダヌス座>、<無知蒙昧なゴルゴン座>、<臆病な兎座>をすべて遠のけよう。<貪欲なアルゴー座>、<不節制な酒杯座>、<不正な天秤座>、<鈍重な蟹座>、<欺瞞の山羊座>、これらすべてを胸の奥底に秘めておくことをもうやめよう。」
星座に結びつけられた美徳と悪徳
「天上界を見回してみてもそこに見える48の星座は、醜い動物の姿をした星座、例えばぶざまな奇形の熊つまり大熊座や、牡羊座や牡牛座といった動物の形をした黄道十二宮の星座や、神々の恥ずべき行為を想い起こさせる図像、例えばメルクリウスの盗みを憶えている琴座や、ユピテル自身の私生児であるヘラクレスやペルセウスの姿といったものばかりである」
パリンゲニウスからの影響
「ブルーノが「エジプト的」改革の内実とする道徳的教説は、禁欲的なものではなく、その一部はエピクロス主義的なものである。この道徳観は、おそらくパリンゲニウスのヘルメティズムとエピクロス主義の融合という独創的な試みによって準備されたのであろう。パリンゲニウスもまた、自然主義的-エピクロス的な倫理観を基盤として、修道士や司祭の自然に悖る生活や道徳的頽廃に対する諷刺を展開しているのである」
星座のヘルメス教的改革
「<カシオペア座>が検討の対象になると、他の神々が彼女をどうするか決める前に、いきなり火星が飛び出してきて、カシオペアの性格はスペイン人に非常に似ているから断固天界にその図像を残すべきである、と激しい口調で要求する」
宗教的ヘルメティスト、ブルーノ
「しかし今日ではカトリックになりたくないと望む者は、誰でも懲罰と責め苦を耐え忍ばなければならない。というのも愛ではなく暴力が用いられているからである」
ブルーノ、〈太陽の都市〉、〈ユートピア〉
「いずれにせよブルーノの魔術的ヘルメティズムは、エリザベス朝の半ばカトリックの信条を懐く者たち、不満を感じるインテリゲンツィアたち、また他の密かな不平不満を懐く社会分子に対して、彼らの秘められた願望に対するある種のはけ口を与えたのだった。それは彼らも憎悪していたスペインのカトリシズムが与える騒擾への使嗾とは全く別の解放感だった」
第13章 ジョルダーノ・ブルーノのイギリス滞在――ヘルメス教的哲学
コペルニクス的宇宙と魔術的上昇
「このような男、ブルーノのような男を、オックスフォードの学者たちはどう理解のしようがあっただろうか。いやそもそも誰がこのような人物を理解できるだろうか。魔術師の誇大妄想が、唖然とするほどの激しさで詩的熱狂と融合している。狂人、恋する男、そして詩人が、ジョルダーノ・ブルーノにおけるほど緊密に一体化した例は、いかに空想を逞しくしたとしても思い描くことすらできない」
ヒエログリフとしてのコペルニクス的宇宙
「真相を言ってしまえば、ブルーノにとってコペルニクスの図は一種のヒエログリフ、つまり力強い神的な神秘を背景に秘めたヘルメス教的な封印の一種なのだった」
「ブルーノは、コペルニクスが地球の運動を仮説として呈示した、その「単に数学的」な論証を遥かに越えて、それがヘルメス・トリスメギストスとコルネリウス・アグリッパの主張を実証していると考えた。つまり他の言葉で言うならば、宇宙の生動という魔術的哲学の証左をそこに見たのだった」
無限の宇宙、無数の世界
「ブルーノの言うところに従えば、最初の<叡智の神殿>はエジプト人とカルデア人によって建立された。第二のそれはペルシアの祭司(マギ)とゾロアスターによって、第三のそれはインドの裸形苦行僧たちによって、第四のそれはトラキアにおいてオルフェウスによって、第五のそれはギリシア人、つまりタレース及び他の賢者たちによって、第六のそれはイタリア人、とりわけルクレティウスによって、第七のそれはドイツ人たち、つまりアルベルトゥス・マグヌス、クサーヌス、コペルニクス、そしてパリンゲニウスによってそれぞれ建設された。わたしには、この系譜は、彼のコペルニクス主義の解釈と等質のものに思える。彼がコペルニクス主義を「エジプト主義」の回帰を告げる先駆けとして捉えたように、ルクレティウスの宇宙像もまた彼にとっては、拡張された形でのエジプト的叡智の一種に見えていたのではないだろうか。ブルーノはこの見地からルクレティウスの無限の宇宙と無数の世界の観念を採用し、そしてそれを自身のコペルニクス主義に融合させたのではないだろうか。コペルニクス主義自体、彼の場合にはすでに拡張された形でのヘルメス教的幻視と一体化しているのである」
習合の信奉と衒学の嫌悪
「とはいえしかしブルーノの最大の敵、彼の強迫観念であり悪夢は「文法屋の衒学者ども」であった。このタイプの衒学は、アリストテレス主義的な衒学とも結びつき得る。しかし文法家本来の衒学は、偏狭な哲学体系という姿をとるだけではない。そもそもの哲学的研究そのものを衒学者は軽蔑するのである。彼はラテン文体、単語や言い回しの辞書といった細かなことに注意を集中し、それと引き替えに哲学は捨ててしまう」
宗教的和解の心象画
「(『原因、原理と一者について』)目の見えないモグラのように振る舞う者たちもいるでしょう。彼らは自分の頭上に広々とした天界への眺めが啓けたと感じるやいなや、慌てて土を掘り、地下に潜り込み、そのまま馴染みの暗闇の中にいつまでも居続けようとするのです。また夜鳥に似た者たちもいます。彼らは視力が利かず、東の空に日輪の先駆けである茜色の帯が明け染めるのを見ただけで、慌てて薄暗いねぐらに潜り込むのです」
第14章 ジョルダーノ・ブルーノとカバラ
『天馬ペガソスのカバラ』
「ブルーノの魔術の典拠は元々かなり貧弱なものだったのかもしれない。というのも彼は不思議なほど、アグリッパの独創性のない受け売りの寄せ集めに熱中し、それに頼りきっているからである」
ブルーノの魔術研究
「もし人がヘルメス教的な体験を経ることで、かくも大いなる諸力を獲得できるのならば、どうしてキリストもまた、このような方法によってこそ彼の大いなる力を獲得したのだと考えてはならないのだろうか」
「天然自然」な活用
「ブルーノの見地からして最も本質的なことは、衒学的な知ったかぶりによって神的な自然との交流の手段が損なわれてしまった、その亀裂を癒す手段を発見することである。その手段が、生きた<声>、徴、図像、封印であった。この交流の生きた手段がいつ発見されるか(あるいはある種の神懸り的忘我の境地で、それが内的意識の上に刻印されるか)ということを彼は問題にし続ける。もしそれが可能となるならば、それによって統合された宇宙は心性の内面に反照され、<魔術師>(マグス)は力を獲得してエジプトの神官の如き生活を送り、自然と魔術的な交流に入るのである」
『三○の封印』
「ブルーノの構想の全体の中で、ルネサンス的<魔術師>のそのキリスト教的側面はどうなってしまったのだろうか。それは消えてしまった、というのが答えだろう」
エジプト主義とフリーメイソンの前史
「フリーメイソン前史というテーマが、非常に曖昧模糊とした領域に属するものであることは認めなければならない。ここでは暗闇の中で手探りで進むしかない。そしてその暗闇の中にはさまざまな神秘が待ち受けている。しかしこうした手探り状態において、当時のイギリスで霊的な充足を味わえずにいた人々を心に思い描く時、そうした彼らにとってこそ、このブルーノの「エジプト風の」伝道は、ある種<魔笛>が初めて重苦しい大気の上を軽やかに馳せたかの如き慰めに満ちた暗示を与えたのかもしれない」
第15章 ジョルダーノ・ブルーノ――英雄的狂信家またはエリザベス朝の宮廷人
『英雄的熱狂』
「シドニーへの献辞の中でブルーノは、自分のペトラルカ模倣は、婦人に向けられた愛を詠う通例のそれではなく、魂の知的領域に連関したより高次の詩的営為である、と説明している」
神性に捧げる恋愛詩
「手短に言うなら、『英雄的熱狂』が現実に目指している宗教経験は、ヘルメティズム的な世界認識(グノーシス)だとわたしは思う。それは<魔術師>(マグス)としての人間を描く神秘的な恋愛詩であり、彼が元々神的なものとして創造され、神的な力を備え、この神的な力を備え、この神的な力によって再び神性と合体する途上にあるその過程を描くのである」
〈聖なる愛〉の啓示体験
「16世紀のキリスト教徒はカトリックであれプロテスタントであれ、宗教的ヘルメティズムを熱烈に支持したし、その傾向はブルーノの時代まで続いていた。彼らは宗教の名においてなされる犯罪と戦争の惨禍に疲労困憊し、寛容と統合の道を捜し求めていた」
エリザベス女王崇拝への参加
「『英雄的熱狂』はまた、騎士道精神との関わりにおける女王崇拝を反映したものである。騎士道は、エリザベス女王統治下で大いなる復興を遂げた」
第16章 ジョルダーノ・ブルーノ――二度目のパリ滞在
〈カトリック同盟〉支配下のパリへ
「ブルーノの第二のパリ滞在中に起きた驚くべき事件は、ファブリツィオ・モルデンテの発明した新型のコンパスを廻っている」
「ブルーノは当時パリにいたモルデンテと知り合いになり、この新案コンパスの非常な感銘を受けた。彼は自分の話を熱心に聴いてくれるあのサン=ヴィクトル修道院の司書にそのことを語り、モルデンテは「幾何学の神様」のような存在だと述べている。そしてモルデンテはラテン語ができないようだから、自分がその発明の解説書をラテン語訳してあげてもよいと思っている、と付け加えた。彼はこの言葉以上のことを実行してみせた。つまりモルデンテのコンパスについての対話篇を4篇も仕上げ、その中で発明者自身はその神の如き発明の素晴らしさをまだ十分に理解したとは言えない、と庇護者よろしく一席ぶってみせたのである。もちろん彼、ブルーノはその意味をしっかりと理解したというわけだった。あまり不自然とは言えない話だが、コルピネッリの書簡の証言により、モルデンテは「われを忘れて怒り狂った」ことが分かっている。この結果、彼は出版されたこの対話篇初版を全部買い占めて破棄してしまった」
コレージュ・ド・カンブレでの公開討論会
「司書コタンの記録によれば、この演説が終わった時、ブルーノは席から立ち上がって、誰でもアリストテレスを擁護するなり、彼を批判するなり随意にされるがよい、と述べたそうである。誰も何も言わなかった。そこでブルーノは同じ言葉をもっと大声で、あたかも勝利を収めた者の如くに叫んだ。その時、「ロドルフス・カレリウス」と名乗る一人の若い論客が立ち上がって、ブルーノの中傷的な非難からアリストテレスを擁護すべく長々と演説を始めた。彼はまず開口一番、今まで<王立教授団>が沈黙を保っていたのは、ブルーノの発言が答える価値がないほどにひどいものに思えたからだ、と切り口上で始めた。彼は自分の弁論を終えるとブルーノに答弁するよう要求したが、ブルーノは黙ったままその場を立ち去ろうとした。討論会場に来ていた学生たちはこれを許さずブルーノを捕えて、彼がアリストテレスに対する非難中傷を取り消さない限りは立ち去ることはならない、と言った。ブルーノは翌日この批判演説に答弁することを条件にして、ようやく彼らの手を逃れることができた。演説をした男は掲示板にブルーノが翌日また討論会場に姿を見せるだろうことを告示した。翌日になるとこの「ロドルフス・カレリウス」は議長の席に着き、ブルーノの自惚れと詐欺的な論弁に対し、非常なる優雅さをもって、アリストテレスの弁護を行い、再度彼に答弁を要求した。「しかしブルーノは会場に姿を見せなかった。それどころかそれ以来この町そのものから逐電してしまったのである」
カトリック再改宗の試み
「このアリストテレスの<想像力論>(『アリストテレスの自然学講義における想像力論』1586年パリで上梓)はブルーノの全著作でも最も難解なものの一つである-これはいささか語るに落ちた月並みなコメントだが、ともかくその難解さは徹底している」
「これらは<普遍学>やありとあらゆる天才的な思いつきと組み合わされて、ほとんど狂気の沙汰としか言いようのない複雑さを呈している」
「しかしわたしには、ブルーノはけっして打算によって行動する人物ではなかったように思えてならない。打算は彼の本性の裡にはない行動形態なのである。彼の人生のすべての行動は唐突であり、自発的である」
「だからわたしは、この時期彼がパリでカトリック教会に帰還しようとしたことは、全く彼らしい、また真剣なものであったと考える」
第17章 ジョルダーノ・ブルーノのドイツ滞在
ヴィッテンベルク大学にて
「ブルーノはヴィッテンベルクに滞在中相当量の仕事をしているが、その大半は大学での講義が基になっている」
「これら(『ルルスの結合法による光明』『論理学によって狩り立てられたる進歩と光明』『熟達の熱弁』)はすべてブルーノの研究者にとっては重要な著作であり、特に彼とルルス主義の関係を考える際には欠かせない資料である。しかしその反面、イギリスで書かれたものに比べるとはっきりと退屈なものである」
「ブルーノは形態を造型することが不可能な三つの「形を持ち得ないものたち」を列挙している。それは<混沌>、<冥府>そして<夜>である」
フランクフルトでの出版
「エジプトの宗教は彼が信奉するものであり、それは万民法と普遍的な愛の掟を破壊するようなことはしない。ところが狂信的な党派、例えば「アリストテレス主義者たち」はまさにそうした非道の行いに走り、自身の偏見を他人に押しつけようとする」
「しかしまた、『巨大さ、無数なるもの、形なきものについて』『三重に最小なるものと尺度について』そして『モナド、数、及び図形について』といった作品を、最初から最後まで通して読むには、英雄的と言わねばならない熱意を必要とすることも確かである」
ブルーノの〈普遍学〉
「わたしはブルーノの著作を飾るこれらの気狂いじみた図案こそが、彼の言う<普遍学>なのだと考える。『30の封印』でブルーノは宗教の四つの指針として<愛>、<魔術>、<技芸>、<普遍学>を挙げていたことを想い起こさなければならない」
第18章 ジョルダーノ・ブルーノ――最後の刊行本
『図像、記号、イデアの構成について』
「想起しておくべき点は、この記憶体系が150の魔術的ないし護符的な図像を基盤として構築されるものだということである。これらの図像は、エジプトのデカン神霊たち、惑星の図像、また他のこうした架空の図像から成っていた」
魔術的図像による宇宙の内面化
「『図像の構成について』には狂乱ないし<狂気>を論じた言葉や章句も散見する。<狂気>と共に真理に没頭する者は、神的なものの面影を追い求める。この主張は『英雄的熱狂』での<狂気>を論じた章句に似通っている。ここではしかしブルーノは、詩と絵画と哲学は同一の営みだというあの命題に別の形式を与える。つまり彼はこの三つ組にもう一つ音楽を加えるのである。「真の哲学は音楽、詩、ないしは絵画である。真の絵画は詩、音楽、そして哲学である。真の詩ないし音楽は、神的な叡智であり絵画である」」
第19章 ジョルダーノ・ブルーノ――イタリア帰国
ヴェネツィアでの投獄
「まだブルーノがノラの幼い子供だった頃、非常に古めかしい感じのする一匹の巨大な蛇が家の壁の裂け目から姿を現した。幼少時、揺り籠の傍に姿を見せる蛇は、ヘラクレスの物語から分かるように、英雄的運命を告げる予兆である。ブルーノが自身を一人の<救世主>だと考えていたことにはほとんど疑いの余地がない」
ナヴァール王アンリへの期待
「フィルポはまた同時に、ブルーノの性格と気質がこうした困難で繊細な感覚を必須とする危険な課題に立ち向かうには全く向いていなかったことを鋭く指摘している。実際ブルーノは苛立ちやすく、喧嘩早く-というよりは病的な憤怒の発作に見舞われ易く、そうなるとあたりかまわず怖ろしい言葉で罵り続け、まわりの人々をぞっとさせるのだった。彼は結局あれほど探し求めていた魔術的な魅力に富む人格というものを持ち合わせてはいなかった。そして自分の大切な提言をこの異常な発作で台なしにすることになったのである」
異端審問始まる
「反自由主義的なヴェネツィア名門の出であるモチェニゴとしては、ナヴァール王の登場により彼の町にも自由の風が吹き始めることを望むはずはなかった。したがって彼は反ナヴァール王の立場だったはずである。それに加えてブルーノは、モチェニゴの家に寄寓中にひどい怒りの発作に襲われてそれを押さえることができなかったらしい」
異端判決の根拠
「もし地動説がブルーノの有罪判決の一つの事由であったとしても、それはガリレオの事例とは全く異なっている。ガリレオは地球が動いているという彼の主張を撤回するように強制されたわけだし、またその主張自体、真正の数学と力学に基づいたものであった。彼はジョルダーノ・ブルーノとは異なった精神風土に生きた人間であり、その世界においてはもはや「ピュタゴラス教徒的な企図」も「ヘルメス教的封印」もなんの意味も持ってはいなかった。科学者としての彼は真正に科学的な根拠に基づいて彼の結論に到達したのである。対してブルーノの哲学は、彼の宗教から分離することはできない。彼が無限の宇宙と無数の世界という拡張された形式の<世界認識>(グノーシス)の裡に見たものは、まさに彼の宗教、つまり<此岸的世界を廻る宗教>そのものだったからである。そしてそれは<神>の「面影」が顕す新しい神性の啓示でもあった。彼にあっては、コペルニクス主義はこの新しい啓示の一つの象徴であり、その啓示はエジプト人の信奉した自然宗教とその魔術への回帰と同義であるべきものでもあった。そして非常に奇妙なことではあるのだが、この回帰を彼は、カトリックの基本枠の中で行い得ると考えていたのである。
このようなわけで、ブルーノが哲学的思想家として迫害され、無数の世界の存在や地球の運動の主張といった大胆の理論のために火刑に処されたのだとする伝説に追随することはもはや不可能である 」
シェイクスピア、ガリレオへの影響
「ブルーノがコペルニクス説を活用してみせたそのやり方が、異端審問官たちにある種の印象を残したことは間違いない。したがってガリレオがまたしても地動説を支持した時に、その背景にそれ以上のものがあるのではないかという疑惑を、異端審問官たちの心に掻き立ててしまったのではないか、と考えてみることはできそうである」
次回は、最終回
つづき。
ジョルダーノ・ブルーノの哲学がどんなものだったのかを本人がまとめた発言がある。火あぶりになる前に、本人がとうとうと、自らの哲学をまくしたてるのが記録として残っているのだ。
以下、そのくだり。本書に載っている。
宇宙は無限である。なぜなら神的な力が無限である以上、有限の世界を生み出すはずはないからである。地球も月や他の惑星同様に、一つの星である。ピュタゴラスもそう述べている。さらに星々はそれが一つの世界であって、その数は無数である。この宇宙の中には普遍的な摂理が存在し、その摂理の恩恵によって、宇宙の中のすべての存在物は生命を吹き込まれ運動している。この宇宙の万物の本性は、神性の、つまり<神>の影ないし<面影>であって、この<神>の本質は言葉で言い表すことも説明することもできない。自分はしかしこの神性の本質的属性が全き<一者>性であることを-神学者たちや偉大なる哲学者たちと同じく-了解している。神性の三つの属性、<力>、<叡智>、<知性>、<愛>と同一のものである。
こうしたことを哲学の見地からではなく信仰の見地から見るならば、叡智つまり<精神>の子は、哲学者たちには<知性>と呼ばれ、神学者たちには<言葉>と呼ばれている。それは人間の肉体の形を取ったのだと信じなけらばならないとされてきた。しかし自分は、いつもこの点には疑いを感じてきた。それは疑問の余地があると思ったので、確信的な信仰を持つには至らなかったのである。神的な聖霊に関しては、自分はピュタゴラス教徒たちと同一の見解を持っている。つまりソロモンが言うように、「<主>の聖霊が大地に充ち満ちている。そしてこれが万物を支え保っているのだ」という見方、あるいはウェルギリウスが、
霊気が裡なるすべてを、その各部に浸透しつつ養い育て、
精神は渾沌たる巨魁を衝き動かす
と述べるその見方を自分も正しいと思っている、と彼は述べた。
さて、前回のつづき。ジョルダーノ・ブルーノ満を持して登場。
第11章 ジョルダーノ・ブルーノ――最初のパリ滞在
前提としての古典的記憶術
「ローマの弁論家たちはある種の記憶法を用いていた。この記憶法については『ヘレンニウスへ』に纏まった記述があり、キケロとクインティリアヌスもそれに言及している。まず一つの建物を選び、その一連の場所を記憶する。次に論題を想起するための影像を作り、それをこの記憶した場所に割り振る。弁論家たちは演説を行う際に、想像の空間の中でこのあらかじめ記憶してある場所を通り過ぎながら、そこに割り振ってある影像を拾い集める」
『イデアの影について』
「魔法使いマーリンのものだとされている叡智の詩の一つは、色々な動物たちにはそれぞれ苦手なことがあるということを謎々の形で述べている。例えば豚はその本性からして空を飛ぶには適していない。それゆえ読者はもしこの眼前の書物にふさわしい力を自分が備えているという自信が持てないなら、読むのはやめるべきだと警告しておこう。この著作の道しるべとして置かれた冒頭のこの詩の雰囲気、つまり神秘めかしながらも大言壮語するこの調子は本論に入ってからも一貫して持続している」
『キルケーの呪文』
「この作品の呪文の典拠は、『イデアの影について』の天上的図像の出所と同じように、コルネリウス・アグリッパの『オカルト哲学について』である」
ブルーノのイギリス訪問と隠された使命
「ブルーノは、イギリスで出版されたこれらの著作のあちこちで、厳しい検閲と監視が当たり前のこの時代、土地の人間ならばまず発言を許されるはずのないことを述べている」
第12章 ジョルダーノ・ブルーノのイギリス滞在――ヘルメス教的改革
オックスフォード大学にて
「(ジョージ・アボットの『誤って正統信仰という名を得た、教皇制度を支持するヒル博士の根拠-根拠薄弱であることを暴露され、目的遂行にはあまりに不十分であることが検討の結果明らかとなった、その姿』からの引用)
彼はやたらに多くの説を並べて見せたが、その中にコペルニクスの意見もあってそれを説き始めた。あの地球は回っており、天界はじっと止まっておるという愚説だ。本当のところ回っておったのはこの男の頭の中身の方だった」
『勝ち誇る野獣の追放』
「ブルーノの『勝ち誇る野獣の追放』(1584年)の基本的なテーマは、エジプト人の魔術的宗教の讃美である。彼らの崇拝の内実は「事物に宿る<神>」の崇拝であったとされる」
ブルーノのエジプト主義
「ジョルダーノ・ブルーノはここで一体何をしているのだろうか。答えは簡単である。彼は、少しばかり無害な魔術に手を染め、その主たる拠り処である『アスクレピウス』の魔術については黙っておくといったフィチーノ流の弱々しい試みを完全に捨て去り、ルネサンス魔術をその異教の源泉へと連れ戻しているのである」
「エジプト人たちの驚嘆すべき魔術的宗教は戻ってくるだろう。彼らの道徳律が今の時代の渾沌に取って代わり、<悲嘆>の予言は成就するだろう。そしてこの現在の暗黒を追放すべきエジプトの光の回帰を告げる天上の徴こそが、コペルニクスの観た太陽なのである」
『宇宙の乙女』
「(ストパイオスの詞華集採録の断簡『宇宙の乙女』より)<悪口する蛇遣い座>、<傲慢な鷲座>、<肉欲のイルカ座>、<短気な馬座>、<情欲の海蛇座>を追い出そう。<大食の鯨座>、<残忍なオリオン座>、<贅沢なエリダヌス座>、<無知蒙昧なゴルゴン座>、<臆病な兎座>をすべて遠のけよう。<貪欲なアルゴー座>、<不節制な酒杯座>、<不正な天秤座>、<鈍重な蟹座>、<欺瞞の山羊座>、これらすべてを胸の奥底に秘めておくことをもうやめよう。」
星座に結びつけられた美徳と悪徳
「天上界を見回してみてもそこに見える48の星座は、醜い動物の姿をした星座、例えばぶざまな奇形の熊つまり大熊座や、牡羊座や牡牛座といった動物の形をした黄道十二宮の星座や、神々の恥ずべき行為を想い起こさせる図像、例えばメルクリウスの盗みを憶えている琴座や、ユピテル自身の私生児であるヘラクレスやペルセウスの姿といったものばかりである」
パリンゲニウスからの影響
「ブルーノが「エジプト的」改革の内実とする道徳的教説は、禁欲的なものではなく、その一部はエピクロス主義的なものである。この道徳観は、おそらくパリンゲニウスのヘルメティズムとエピクロス主義の融合という独創的な試みによって準備されたのであろう。パリンゲニウスもまた、自然主義的-エピクロス的な倫理観を基盤として、修道士や司祭の自然に悖る生活や道徳的頽廃に対する諷刺を展開しているのである」
星座のヘルメス教的改革
「<カシオペア座>が検討の対象になると、他の神々が彼女をどうするか決める前に、いきなり火星が飛び出してきて、カシオペアの性格はスペイン人に非常に似ているから断固天界にその図像を残すべきである、と激しい口調で要求する」
宗教的ヘルメティスト、ブルーノ
「しかし今日ではカトリックになりたくないと望む者は、誰でも懲罰と責め苦を耐え忍ばなければならない。というのも愛ではなく暴力が用いられているからである」
ブルーノ、〈太陽の都市〉、〈ユートピア〉
「いずれにせよブルーノの魔術的ヘルメティズムは、エリザベス朝の半ばカトリックの信条を懐く者たち、不満を感じるインテリゲンツィアたち、また他の密かな不平不満を懐く社会分子に対して、彼らの秘められた願望に対するある種のはけ口を与えたのだった。それは彼らも憎悪していたスペインのカトリシズムが与える騒擾への使嗾とは全く別の解放感だった」
第13章 ジョルダーノ・ブルーノのイギリス滞在――ヘルメス教的哲学
コペルニクス的宇宙と魔術的上昇
「このような男、ブルーノのような男を、オックスフォードの学者たちはどう理解のしようがあっただろうか。いやそもそも誰がこのような人物を理解できるだろうか。魔術師の誇大妄想が、唖然とするほどの激しさで詩的熱狂と融合している。狂人、恋する男、そして詩人が、ジョルダーノ・ブルーノにおけるほど緊密に一体化した例は、いかに空想を逞しくしたとしても思い描くことすらできない」
ヒエログリフとしてのコペルニクス的宇宙
「真相を言ってしまえば、ブルーノにとってコペルニクスの図は一種のヒエログリフ、つまり力強い神的な神秘を背景に秘めたヘルメス教的な封印の一種なのだった」
「ブルーノは、コペルニクスが地球の運動を仮説として呈示した、その「単に数学的」な論証を遥かに越えて、それがヘルメス・トリスメギストスとコルネリウス・アグリッパの主張を実証していると考えた。つまり他の言葉で言うならば、宇宙の生動という魔術的哲学の証左をそこに見たのだった」
無限の宇宙、無数の世界
「ブルーノの言うところに従えば、最初の<叡智の神殿>はエジプト人とカルデア人によって建立された。第二のそれはペルシアの祭司(マギ)とゾロアスターによって、第三のそれはインドの裸形苦行僧たちによって、第四のそれはトラキアにおいてオルフェウスによって、第五のそれはギリシア人、つまりタレース及び他の賢者たちによって、第六のそれはイタリア人、とりわけルクレティウスによって、第七のそれはドイツ人たち、つまりアルベルトゥス・マグヌス、クサーヌス、コペルニクス、そしてパリンゲニウスによってそれぞれ建設された。わたしには、この系譜は、彼のコペルニクス主義の解釈と等質のものに思える。彼がコペルニクス主義を「エジプト主義」の回帰を告げる先駆けとして捉えたように、ルクレティウスの宇宙像もまた彼にとっては、拡張された形でのエジプト的叡智の一種に見えていたのではないだろうか。ブルーノはこの見地からルクレティウスの無限の宇宙と無数の世界の観念を採用し、そしてそれを自身のコペルニクス主義に融合させたのではないだろうか。コペルニクス主義自体、彼の場合にはすでに拡張された形でのヘルメス教的幻視と一体化しているのである」
習合の信奉と衒学の嫌悪
「とはいえしかしブルーノの最大の敵、彼の強迫観念であり悪夢は「文法屋の衒学者ども」であった。このタイプの衒学は、アリストテレス主義的な衒学とも結びつき得る。しかし文法家本来の衒学は、偏狭な哲学体系という姿をとるだけではない。そもそもの哲学的研究そのものを衒学者は軽蔑するのである。彼はラテン文体、単語や言い回しの辞書といった細かなことに注意を集中し、それと引き替えに哲学は捨ててしまう」
宗教的和解の心象画
「(『原因、原理と一者について』)目の見えないモグラのように振る舞う者たちもいるでしょう。彼らは自分の頭上に広々とした天界への眺めが啓けたと感じるやいなや、慌てて土を掘り、地下に潜り込み、そのまま馴染みの暗闇の中にいつまでも居続けようとするのです。また夜鳥に似た者たちもいます。彼らは視力が利かず、東の空に日輪の先駆けである茜色の帯が明け染めるのを見ただけで、慌てて薄暗いねぐらに潜り込むのです」
第14章 ジョルダーノ・ブルーノとカバラ
『天馬ペガソスのカバラ』
「ブルーノの魔術の典拠は元々かなり貧弱なものだったのかもしれない。というのも彼は不思議なほど、アグリッパの独創性のない受け売りの寄せ集めに熱中し、それに頼りきっているからである」
ブルーノの魔術研究
「もし人がヘルメス教的な体験を経ることで、かくも大いなる諸力を獲得できるのならば、どうしてキリストもまた、このような方法によってこそ彼の大いなる力を獲得したのだと考えてはならないのだろうか」
「天然自然」な活用
「ブルーノの見地からして最も本質的なことは、衒学的な知ったかぶりによって神的な自然との交流の手段が損なわれてしまった、その亀裂を癒す手段を発見することである。その手段が、生きた<声>、徴、図像、封印であった。この交流の生きた手段がいつ発見されるか(あるいはある種の神懸り的忘我の境地で、それが内的意識の上に刻印されるか)ということを彼は問題にし続ける。もしそれが可能となるならば、それによって統合された宇宙は心性の内面に反照され、<魔術師>(マグス)は力を獲得してエジプトの神官の如き生活を送り、自然と魔術的な交流に入るのである」
『三○の封印』
「ブルーノの構想の全体の中で、ルネサンス的<魔術師>のそのキリスト教的側面はどうなってしまったのだろうか。それは消えてしまった、というのが答えだろう」
エジプト主義とフリーメイソンの前史
「フリーメイソン前史というテーマが、非常に曖昧模糊とした領域に属するものであることは認めなければならない。ここでは暗闇の中で手探りで進むしかない。そしてその暗闇の中にはさまざまな神秘が待ち受けている。しかしこうした手探り状態において、当時のイギリスで霊的な充足を味わえずにいた人々を心に思い描く時、そうした彼らにとってこそ、このブルーノの「エジプト風の」伝道は、ある種<魔笛>が初めて重苦しい大気の上を軽やかに馳せたかの如き慰めに満ちた暗示を与えたのかもしれない」
第15章 ジョルダーノ・ブルーノ――英雄的狂信家またはエリザベス朝の宮廷人
『英雄的熱狂』
「シドニーへの献辞の中でブルーノは、自分のペトラルカ模倣は、婦人に向けられた愛を詠う通例のそれではなく、魂の知的領域に連関したより高次の詩的営為である、と説明している」
神性に捧げる恋愛詩
「手短に言うなら、『英雄的熱狂』が現実に目指している宗教経験は、ヘルメティズム的な世界認識(グノーシス)だとわたしは思う。それは<魔術師>(マグス)としての人間を描く神秘的な恋愛詩であり、彼が元々神的なものとして創造され、神的な力を備え、この神的な力を備え、この神的な力によって再び神性と合体する途上にあるその過程を描くのである」
〈聖なる愛〉の啓示体験
「16世紀のキリスト教徒はカトリックであれプロテスタントであれ、宗教的ヘルメティズムを熱烈に支持したし、その傾向はブルーノの時代まで続いていた。彼らは宗教の名においてなされる犯罪と戦争の惨禍に疲労困憊し、寛容と統合の道を捜し求めていた」
エリザベス女王崇拝への参加
「『英雄的熱狂』はまた、騎士道精神との関わりにおける女王崇拝を反映したものである。騎士道は、エリザベス女王統治下で大いなる復興を遂げた」
第16章 ジョルダーノ・ブルーノ――二度目のパリ滞在
〈カトリック同盟〉支配下のパリへ
「ブルーノの第二のパリ滞在中に起きた驚くべき事件は、ファブリツィオ・モルデンテの発明した新型のコンパスを廻っている」
「ブルーノは当時パリにいたモルデンテと知り合いになり、この新案コンパスの非常な感銘を受けた。彼は自分の話を熱心に聴いてくれるあのサン=ヴィクトル修道院の司書にそのことを語り、モルデンテは「幾何学の神様」のような存在だと述べている。そしてモルデンテはラテン語ができないようだから、自分がその発明の解説書をラテン語訳してあげてもよいと思っている、と付け加えた。彼はこの言葉以上のことを実行してみせた。つまりモルデンテのコンパスについての対話篇を4篇も仕上げ、その中で発明者自身はその神の如き発明の素晴らしさをまだ十分に理解したとは言えない、と庇護者よろしく一席ぶってみせたのである。もちろん彼、ブルーノはその意味をしっかりと理解したというわけだった。あまり不自然とは言えない話だが、コルピネッリの書簡の証言により、モルデンテは「われを忘れて怒り狂った」ことが分かっている。この結果、彼は出版されたこの対話篇初版を全部買い占めて破棄してしまった」
コレージュ・ド・カンブレでの公開討論会
「司書コタンの記録によれば、この演説が終わった時、ブルーノは席から立ち上がって、誰でもアリストテレスを擁護するなり、彼を批判するなり随意にされるがよい、と述べたそうである。誰も何も言わなかった。そこでブルーノは同じ言葉をもっと大声で、あたかも勝利を収めた者の如くに叫んだ。その時、「ロドルフス・カレリウス」と名乗る一人の若い論客が立ち上がって、ブルーノの中傷的な非難からアリストテレスを擁護すべく長々と演説を始めた。彼はまず開口一番、今まで<王立教授団>が沈黙を保っていたのは、ブルーノの発言が答える価値がないほどにひどいものに思えたからだ、と切り口上で始めた。彼は自分の弁論を終えるとブルーノに答弁するよう要求したが、ブルーノは黙ったままその場を立ち去ろうとした。討論会場に来ていた学生たちはこれを許さずブルーノを捕えて、彼がアリストテレスに対する非難中傷を取り消さない限りは立ち去ることはならない、と言った。ブルーノは翌日この批判演説に答弁することを条件にして、ようやく彼らの手を逃れることができた。演説をした男は掲示板にブルーノが翌日また討論会場に姿を見せるだろうことを告示した。翌日になるとこの「ロドルフス・カレリウス」は議長の席に着き、ブルーノの自惚れと詐欺的な論弁に対し、非常なる優雅さをもって、アリストテレスの弁護を行い、再度彼に答弁を要求した。「しかしブルーノは会場に姿を見せなかった。それどころかそれ以来この町そのものから逐電してしまったのである」
カトリック再改宗の試み
「このアリストテレスの<想像力論>(『アリストテレスの自然学講義における想像力論』1586年パリで上梓)はブルーノの全著作でも最も難解なものの一つである-これはいささか語るに落ちた月並みなコメントだが、ともかくその難解さは徹底している」
「これらは<普遍学>やありとあらゆる天才的な思いつきと組み合わされて、ほとんど狂気の沙汰としか言いようのない複雑さを呈している」
「しかしわたしには、ブルーノはけっして打算によって行動する人物ではなかったように思えてならない。打算は彼の本性の裡にはない行動形態なのである。彼の人生のすべての行動は唐突であり、自発的である」
「だからわたしは、この時期彼がパリでカトリック教会に帰還しようとしたことは、全く彼らしい、また真剣なものであったと考える」
第17章 ジョルダーノ・ブルーノのドイツ滞在
ヴィッテンベルク大学にて
「ブルーノはヴィッテンベルクに滞在中相当量の仕事をしているが、その大半は大学での講義が基になっている」
「これら(『ルルスの結合法による光明』『論理学によって狩り立てられたる進歩と光明』『熟達の熱弁』)はすべてブルーノの研究者にとっては重要な著作であり、特に彼とルルス主義の関係を考える際には欠かせない資料である。しかしその反面、イギリスで書かれたものに比べるとはっきりと退屈なものである」
「ブルーノは形態を造型することが不可能な三つの「形を持ち得ないものたち」を列挙している。それは<混沌>、<冥府>そして<夜>である」
フランクフルトでの出版
「エジプトの宗教は彼が信奉するものであり、それは万民法と普遍的な愛の掟を破壊するようなことはしない。ところが狂信的な党派、例えば「アリストテレス主義者たち」はまさにそうした非道の行いに走り、自身の偏見を他人に押しつけようとする」
「しかしまた、『巨大さ、無数なるもの、形なきものについて』『三重に最小なるものと尺度について』そして『モナド、数、及び図形について』といった作品を、最初から最後まで通して読むには、英雄的と言わねばならない熱意を必要とすることも確かである」
ブルーノの〈普遍学〉
「わたしはブルーノの著作を飾るこれらの気狂いじみた図案こそが、彼の言う<普遍学>なのだと考える。『30の封印』でブルーノは宗教の四つの指針として<愛>、<魔術>、<技芸>、<普遍学>を挙げていたことを想い起こさなければならない」
第18章 ジョルダーノ・ブルーノ――最後の刊行本
『図像、記号、イデアの構成について』
「想起しておくべき点は、この記憶体系が150の魔術的ないし護符的な図像を基盤として構築されるものだということである。これらの図像は、エジプトのデカン神霊たち、惑星の図像、また他のこうした架空の図像から成っていた」
魔術的図像による宇宙の内面化
「『図像の構成について』には狂乱ないし<狂気>を論じた言葉や章句も散見する。<狂気>と共に真理に没頭する者は、神的なものの面影を追い求める。この主張は『英雄的熱狂』での<狂気>を論じた章句に似通っている。ここではしかしブルーノは、詩と絵画と哲学は同一の営みだというあの命題に別の形式を与える。つまり彼はこの三つ組にもう一つ音楽を加えるのである。「真の哲学は音楽、詩、ないしは絵画である。真の絵画は詩、音楽、そして哲学である。真の詩ないし音楽は、神的な叡智であり絵画である」」
第19章 ジョルダーノ・ブルーノ――イタリア帰国
ヴェネツィアでの投獄
「まだブルーノがノラの幼い子供だった頃、非常に古めかしい感じのする一匹の巨大な蛇が家の壁の裂け目から姿を現した。幼少時、揺り籠の傍に姿を見せる蛇は、ヘラクレスの物語から分かるように、英雄的運命を告げる予兆である。ブルーノが自身を一人の<救世主>だと考えていたことにはほとんど疑いの余地がない」
ナヴァール王アンリへの期待
「フィルポはまた同時に、ブルーノの性格と気質がこうした困難で繊細な感覚を必須とする危険な課題に立ち向かうには全く向いていなかったことを鋭く指摘している。実際ブルーノは苛立ちやすく、喧嘩早く-というよりは病的な憤怒の発作に見舞われ易く、そうなるとあたりかまわず怖ろしい言葉で罵り続け、まわりの人々をぞっとさせるのだった。彼は結局あれほど探し求めていた魔術的な魅力に富む人格というものを持ち合わせてはいなかった。そして自分の大切な提言をこの異常な発作で台なしにすることになったのである」
異端審問始まる
「反自由主義的なヴェネツィア名門の出であるモチェニゴとしては、ナヴァール王の登場により彼の町にも自由の風が吹き始めることを望むはずはなかった。したがって彼は反ナヴァール王の立場だったはずである。それに加えてブルーノは、モチェニゴの家に寄寓中にひどい怒りの発作に襲われてそれを押さえることができなかったらしい」
異端判決の根拠
「もし地動説がブルーノの有罪判決の一つの事由であったとしても、それはガリレオの事例とは全く異なっている。ガリレオは地球が動いているという彼の主張を撤回するように強制されたわけだし、またその主張自体、真正の数学と力学に基づいたものであった。彼はジョルダーノ・ブルーノとは異なった精神風土に生きた人間であり、その世界においてはもはや「ピュタゴラス教徒的な企図」も「ヘルメス教的封印」もなんの意味も持ってはいなかった。科学者としての彼は真正に科学的な根拠に基づいて彼の結論に到達したのである。対してブルーノの哲学は、彼の宗教から分離することはできない。彼が無限の宇宙と無数の世界という拡張された形式の<世界認識>(グノーシス)の裡に見たものは、まさに彼の宗教、つまり<此岸的世界を廻る宗教>そのものだったからである。そしてそれは<神>の「面影」が顕す新しい神性の啓示でもあった。彼にあっては、コペルニクス主義はこの新しい啓示の一つの象徴であり、その啓示はエジプト人の信奉した自然宗教とその魔術への回帰と同義であるべきものでもあった。そして非常に奇妙なことではあるのだが、この回帰を彼は、カトリックの基本枠の中で行い得ると考えていたのである。
このようなわけで、ブルーノが哲学的思想家として迫害され、無数の世界の存在や地球の運動の主張といった大胆の理論のために火刑に処されたのだとする伝説に追随することはもはや不可能である 」
シェイクスピア、ガリレオへの影響
「ブルーノがコペルニクス説を活用してみせたそのやり方が、異端審問官たちにある種の印象を残したことは間違いない。したがってガリレオがまたしても地動説を支持した時に、その背景にそれ以上のものがあるのではないかという疑惑を、異端審問官たちの心に掻き立ててしまったのではないか、と考えてみることはできそうである」
次回は、最終回
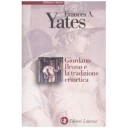

コメント