『ブルバキ−数学者達の秘密結社』
2009年7月28日 読書 コメント (1)
モーリス・マシャルの『ブルバキ−数学者達の秘密結社』を読んだ。
以下、目次。
1、グループがつくられる
ブルバキの育ちの園、エコール・ノルマル・シュペリユール/初めは控え目な計画が、次第にファラオ的になる/田園の集り/実験台モルモットは将来性を示さなければならない/50歳で定年/偉大な才能と優れた頭脳
●ニコラブルバキ協力者の会
●ジャン・デルサルト(1903-1968)
2、名前にまつわる伝説
●本物のブルバキ将軍(1816-1897)
学生の茶番劇かそれとも文学的なほのめかしか?/エリ・カルタンが一風変わった数学者の名づけ親となる/未知の先祖の出現/ニコラ・ブルバキの略歴
●「ブルバキの略歴と業績」
●アンドレ・ヴェイユ(1906-1998)
3、若者と大御所
ルネサンス−西欧数学の復興/19世紀に厳密に、そして抽象的になる/1900年代の導き手ポアンカレとヒルベルト/ほとんど師を持たない見習い数学者/『解析教程』打倒、『現代代数学』万歳!
●1937年の『メダルの戦い』
4、『数学原論』
10部門、60以上の章/発行者フレイマンの加担/ブルバキは『一般から特殊へ』と記述する/新しい用語、新しい記号/ブルバキの対象は誰?
●1、デュドネが語るブルバキの執筆法
●2、集合論
●3、代数学
●4、位相
●5、実一変数関数
●6、位相線型空間
●7、積分
●8、可換代数
●9、リー群とリー環
●10、微分可能多様体と解析的多様体
●11、スペクトル論
●ジャン・デュドネ(1906-1992)
5、公理的方法と構造を目指して
ヒルベルト流の公理的方法/構造の3つの型/ダチョウをまねるとき…/カテゴリー対ブルバキ型の構造
●ブルバキからウリポ、ピアジェそしてレヴィ=ストロースへ…
●1、群の構造
●2、環とイデアルの構造
●3、体の構造
●4、順序構造
6、ブルバキの断片:フィルター
●1、距離の公理
●2、位相空間、開集合と近傍
●3、フィルターの公理
●アンリ・カルタン(1904年生まれ)
7、セミネール・ブルバキ
セミネールの儀式/864の講演、1万ページの講究録/専門化しすぎているという者もいる…
●セミネール・ブルバキの先駆者:「セミネール・アダマール」と「セミネール・ジュリア」
8、繊細にして謹厳な学生達
言葉の重み、酒樽の衝撃/ブルバキは自発的な難読症?/自分自身にも不遜な/ブルバキ嬢の結婚、そしてブルバキの逝去…
9、『人間精神の名誉のために』?
ブルバキの選択−論理もなし、応用数学もなし/ブルバキは基礎論に興味がない/常に一般化を追い求める超公理化師達?/ブルバキは解析学を代数化した
●ブルバキは数学での権力者であったか?
●測度、積分と確率
●クロード・シュヴァレー(1909−1984)
10、学校教育での『現代数学』
ブルバキが高等教育を制覇する/ブルバキが ポリテクニクに入る/至るところに数学を見た/デュドネが「打倒ユークリッド!」と叫ぶとき/革命の後に反革命が/ブルバキは用心深く、中立し、沈黙を守った
11、不死の数学者?
数学の情景は変わった/時間の不足か熱意の不足か?/「彼の仕事は終わっている、しかも見事に終わっている…/数学は上に統一され、下にではない
ブルバキの毀誉褒貶、盛者必衰の理。
面白いのは断然、ブルバキのなりたちあたりで、「カニュラール」と呼ばれる、学生の悪ふざけが横溢している。
ブルバキは八手三郎みたいなもので、複数の数学者達によるペンネームなのだが、実在する個人であると主張しつづける。ブルバキという個人はいない、と暴露する者を相手に、「おまえこそ、架空の合作ペンネームじゃないか」と切り返したりしている。こういう稚気に富んだ遊びは、ミステリに通じるものがあって、親近感が湧く。まるでバーナビー・ロスとエラリイ・クイーンのやりとりみたいなものではないか。
以前に読んだ『アンドレ・ヴェイユ自伝』の記述が正しいならば、アンドレ・ヴェイユがブルバキの経歴を創作し、ポルデヴィア出身だということにした、ということだが、本書ではまた違う記述が見られる。
それは、1960年頃につくられた『ニコラ・ブルバキの略歴と業績』と称する文書で、それによると、
「ブルバキ家はクレタ島出身である〜ソテル・ブルバキの三男はロシアに亡命し、次いで ルーマニアに渡ったが、まもなくギリシャに残った両親との連絡を絶った。ニコラ・ブルバキはこの三男の子孫で、1886年にモルダヴィア地方のククテニに生れた」
ブルバキを「モルダヴィア出身」だと百科事典的に記述することが散見されるのは、この文書をもとにしたものだと思われる。
もともと架空の「ブルバキ」さんの出身がどこであろうと、間違いとか正しいとか言い様がないのだが、ここは架空の土地「ポルデヴィア」だとする方が、よりブルバキらしくて面白いんじゃないかと思う。ポルデヴィア、という土地は、ウリポの作家で、ブルバキの一員でもあったジャック・ルーボーの『麗しのオルタンス』の解説によると、ジャーナリストのアラン・メイユが創作したのだと言う。(ポルデヴィアについて書かれているというミステリマガジンを読んでいないのがとても残念!)メイユがどんなふうにポルデヴィアを書いているのか、ちょちょっと調べてみたが、よくわからない。ここは、フランスに詳しい人にご教示いただきたい。ポルデヴィアに興味を持ったついでに、ライツヴィル物をまた読みたいな、なんて脱線するのが、楽しいのだ。
この本は簡略ながら数学的なことも書いてあり、まったくの数学オンチの僕の頭にはなかなか入ってこなくて、四苦八苦した。最近とんと読書していないような日記が続いていたのは、本書と闘っていたからである。だが、数学的なことはちんぷんかんぷんでも、この本はめちゃくちゃ面白かった!
以下、目次。
1、グループがつくられる
ブルバキの育ちの園、エコール・ノルマル・シュペリユール/初めは控え目な計画が、次第にファラオ的になる/田園の集り/実験台モルモットは将来性を示さなければならない/50歳で定年/偉大な才能と優れた頭脳
●ニコラブルバキ協力者の会
●ジャン・デルサルト(1903-1968)
2、名前にまつわる伝説
●本物のブルバキ将軍(1816-1897)
学生の茶番劇かそれとも文学的なほのめかしか?/エリ・カルタンが一風変わった数学者の名づけ親となる/未知の先祖の出現/ニコラ・ブルバキの略歴
●「ブルバキの略歴と業績」
●アンドレ・ヴェイユ(1906-1998)
3、若者と大御所
ルネサンス−西欧数学の復興/19世紀に厳密に、そして抽象的になる/1900年代の導き手ポアンカレとヒルベルト/ほとんど師を持たない見習い数学者/『解析教程』打倒、『現代代数学』万歳!
●1937年の『メダルの戦い』
4、『数学原論』
10部門、60以上の章/発行者フレイマンの加担/ブルバキは『一般から特殊へ』と記述する/新しい用語、新しい記号/ブルバキの対象は誰?
●1、デュドネが語るブルバキの執筆法
●2、集合論
●3、代数学
●4、位相
●5、実一変数関数
●6、位相線型空間
●7、積分
●8、可換代数
●9、リー群とリー環
●10、微分可能多様体と解析的多様体
●11、スペクトル論
●ジャン・デュドネ(1906-1992)
5、公理的方法と構造を目指して
ヒルベルト流の公理的方法/構造の3つの型/ダチョウをまねるとき…/カテゴリー対ブルバキ型の構造
●ブルバキからウリポ、ピアジェそしてレヴィ=ストロースへ…
●1、群の構造
●2、環とイデアルの構造
●3、体の構造
●4、順序構造
6、ブルバキの断片:フィルター
●1、距離の公理
●2、位相空間、開集合と近傍
●3、フィルターの公理
●アンリ・カルタン(1904年生まれ)
7、セミネール・ブルバキ
セミネールの儀式/864の講演、1万ページの講究録/専門化しすぎているという者もいる…
●セミネール・ブルバキの先駆者:「セミネール・アダマール」と「セミネール・ジュリア」
8、繊細にして謹厳な学生達
言葉の重み、酒樽の衝撃/ブルバキは自発的な難読症?/自分自身にも不遜な/ブルバキ嬢の結婚、そしてブルバキの逝去…
9、『人間精神の名誉のために』?
ブルバキの選択−論理もなし、応用数学もなし/ブルバキは基礎論に興味がない/常に一般化を追い求める超公理化師達?/ブルバキは解析学を代数化した
●ブルバキは数学での権力者であったか?
●測度、積分と確率
●クロード・シュヴァレー(1909−1984)
10、学校教育での『現代数学』
ブルバキが高等教育を制覇する/ブルバキが ポリテクニクに入る/至るところに数学を見た/デュドネが「打倒ユークリッド!」と叫ぶとき/革命の後に反革命が/ブルバキは用心深く、中立し、沈黙を守った
11、不死の数学者?
数学の情景は変わった/時間の不足か熱意の不足か?/「彼の仕事は終わっている、しかも見事に終わっている…/数学は上に統一され、下にではない
ブルバキの毀誉褒貶、盛者必衰の理。
面白いのは断然、ブルバキのなりたちあたりで、「カニュラール」と呼ばれる、学生の悪ふざけが横溢している。
ブルバキは八手三郎みたいなもので、複数の数学者達によるペンネームなのだが、実在する個人であると主張しつづける。ブルバキという個人はいない、と暴露する者を相手に、「おまえこそ、架空の合作ペンネームじゃないか」と切り返したりしている。こういう稚気に富んだ遊びは、ミステリに通じるものがあって、親近感が湧く。まるでバーナビー・ロスとエラリイ・クイーンのやりとりみたいなものではないか。
以前に読んだ『アンドレ・ヴェイユ自伝』の記述が正しいならば、アンドレ・ヴェイユがブルバキの経歴を創作し、ポルデヴィア出身だということにした、ということだが、本書ではまた違う記述が見られる。
それは、1960年頃につくられた『ニコラ・ブルバキの略歴と業績』と称する文書で、それによると、
「ブルバキ家はクレタ島出身である〜ソテル・ブルバキの三男はロシアに亡命し、次いで ルーマニアに渡ったが、まもなくギリシャに残った両親との連絡を絶った。ニコラ・ブルバキはこの三男の子孫で、1886年にモルダヴィア地方のククテニに生れた」
ブルバキを「モルダヴィア出身」だと百科事典的に記述することが散見されるのは、この文書をもとにしたものだと思われる。
もともと架空の「ブルバキ」さんの出身がどこであろうと、間違いとか正しいとか言い様がないのだが、ここは架空の土地「ポルデヴィア」だとする方が、よりブルバキらしくて面白いんじゃないかと思う。ポルデヴィア、という土地は、ウリポの作家で、ブルバキの一員でもあったジャック・ルーボーの『麗しのオルタンス』の解説によると、ジャーナリストのアラン・メイユが創作したのだと言う。(ポルデヴィアについて書かれているというミステリマガジンを読んでいないのがとても残念!)メイユがどんなふうにポルデヴィアを書いているのか、ちょちょっと調べてみたが、よくわからない。ここは、フランスに詳しい人にご教示いただきたい。ポルデヴィアに興味を持ったついでに、ライツヴィル物をまた読みたいな、なんて脱線するのが、楽しいのだ。
この本は簡略ながら数学的なことも書いてあり、まったくの数学オンチの僕の頭にはなかなか入ってこなくて、四苦八苦した。最近とんと読書していないような日記が続いていたのは、本書と闘っていたからである。だが、数学的なことはちんぷんかんぷんでも、この本はめちゃくちゃ面白かった!
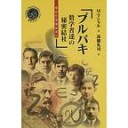

コメント
『計量構造を【π】と【1】』とし
『正則構造』(四則演算)
『意味構造』(形態空間(ニッチ)での【π】と【1】のカタチ)
で捉えたい。
『計量構造の【π】と【1】』は、平面(座標)を生む。
『正則構造』は、計算の普遍性を生む。
『意味構造』は、国語と算数(数学)の[カオス]と[コスモス]の融合の立場を呈示する。
『計量構造』の順序性は、[幻のマスキングテープ』
『正則構造』は、『自然比矩形』
『意味構造』は、『創発直方体』 『創発円筒体』 などなど
この数の言葉を眺望する絵本は、「もろはのつるぎ」(有田川町ウエブライブラリー)